『時間をやくパン屋さん』という本があるのご存知でしょうか?
小学3、4年生向けの本で、夏休み感想画対象の本に選定されていました。
感想文用の本を購入しに行って、間違えて感想画対象の本を買うという痛恨のミスでしたが、感想文用として読むことにしたうちの娘。
元々は韓国の本らしく、著者は『キム・ジュヒョン』となっています。それが和訳されて出版されたようです。
なぜブログに残すことにしたかと言うと、
- 悔しさをバネにするなら注意が必要でしょう?
- これって、引き寄せの法則のことですよね?
この2点が気になったからです。
そして本の中で、言及が無かったから。
身近に子どもさんがいらしたら、『そういうことだよ』と付け足してくれるといいなぁと思って残しておきます。
↓引き寄せの法則についてはこちら
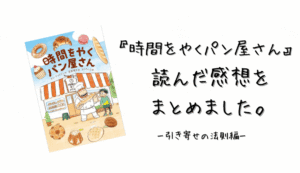

まずは『①悔しさをバネにするなら注意が必要でしょう?』こちらから。
時間をやくパン屋さん※血の色の復讐マカロン
『血じゃなくてジャムだよ。人は赤い色を見るとこうふんするんだ。どうしても復讐の赤い色を入れてくれって、特別注文だったから。』
『復讐?』
『そうだ、復讐。なかには復讐の時間を覚えておきたい人もいるんだね。その苦くて残酷なつらい時間をやしてくれってね。くちゃくちゃとかみしめながら、ずっとわすれないんだ、ぜったいに仕返ししてやるんだ、って』
『時間をやくパン屋さん』 P87
時間をやくパン屋さんでは、覚えておきたい時間(思い出)の味をパンに込めて、そのまま焼いて食べることができます。
楽しい時間を焼く人が多い中、エマという12歳の女の子が『血の色の復讐マカロン』を注文します。
エマはお母さんから洋服をもらうのですが、その洋服はお友達がゴミに捨てた洋服。
学校に着ていくと、その洋服を見たお友達から馬鹿にされてしまうのです。
その悔しさを忘れないように、絶対に忘れないように、うんと苦くて、鋭くて、吐きそうな味にして欲しいという注文をしました。



きっと、悔しさをバネにするということが言いたいんだと思うんですよ。それが原動力になるのはいいのだけれど、それだけのエネルギーで動くと人は疲弊することがある。それをここで補足します。
悔しさをバネにする本当の意味とは?
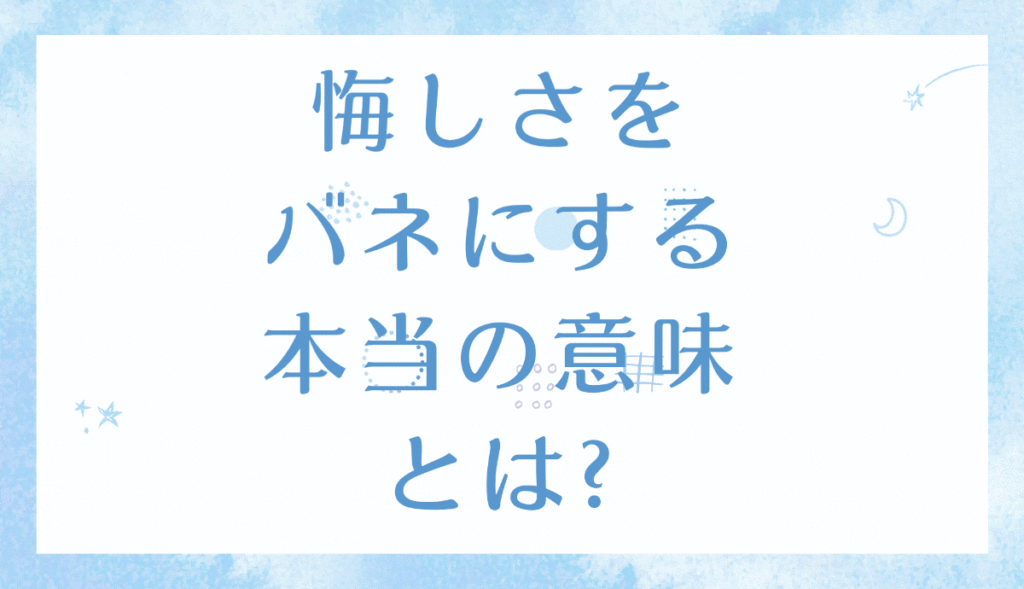
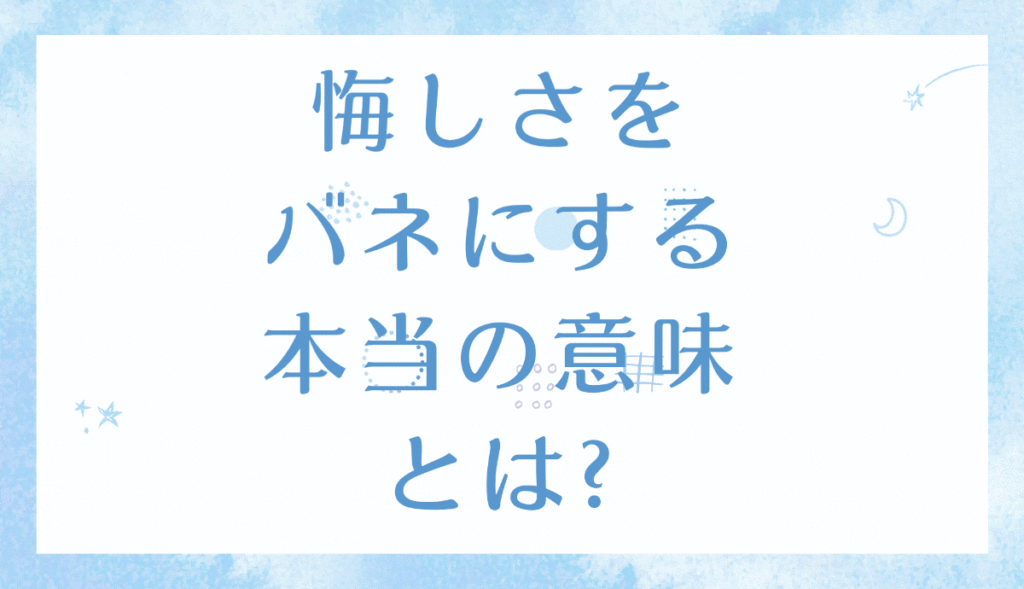
『悔しさをバネにする』って、よく聞きますけど、奥が深いですよね。
感情をどう受け止め、どう自己成長につなげて行くかが大切だと感じてます。
- 悔しさの感情を認識する
- 悔しさをに原動力に変える
- 自己反省と改善の機会
- 他者との比較を超えて
- 感情のバランスを取る
①悔しさの感情を認識する
まず、悔しさを感じること自体は、人として普通のこと。
目標に向かって努力しているとき、思っていた結果が得られなかったり、他者に認められなかったりすることで、悔しい思いをすることがある。
この『悔しさ』は、自身の重要なシグナル。
自身の限界を知り、それを克服するためのモチベーションにもなる。悔しさを無視するのではなくて、しっかりと受け入れることが第一歩です。



まずは『悔しい』という感情を自覚するのが先。
②悔しさを原動力に変える
悔しさを感じたとき、その感情をただ抱え込むのではなくて、自分の成長のためのエネルギー源とすることができる。
例えば、テストで思うような点数が取れなかったとき、その点数に対して悔しさを覚えるなら、おのずと『次こそは頑張ろう』といった前向きな気持ちが芽生えますよね。
悔しさを前進するための手段として受け止めることで、次の自己成長へと促すことができます。
③自己反省と改善の機会
悔しさはまた、自己反省にもなります。
『どうしてあのとき、上手くいかなかったのか?』と自問自答することで、自分が抱える課題や改善点に気づくことができる。
この過程を経ることで、同じ失敗を繰り返すことを防ぎ、次の挑戦に向けた戦略を練ることができるようになる。
④他者との比較を超えて
『悔しさをバネに』とは、他者との比較を止めて、自分自身の成長に重きを置く方がいい。
周囲の人々と自分を比べ、『あの人は成功しているのに、自分は…』と落ち込む、その思考パターンが悔しさを悪化させることになるからです。



むしろ、『自分はこういう経験をしたからこそ、次はもっと頑張れる』と自分の経験を見つめることが、本当の意味での『バネ』になる。
⑤感情のバランスを取る
最後に重要なのは、悔しさを感じる一方で、その感情に振り回されないバランスを保つこと。
悔しさを感じることは成長にとって大切ですが、その感情が過度になると自己評価を下げたり、無気力に繋がったりする可能性もある。
感情を上手に受容することで、冷静に自分を見つめ、建設的な行動を選択することができるようになる。
このように、悔しさをバネにすることの本当の意味は、自分自身と向き合い、自己成長の糧とすることにあります。これを実践することで、ただの悔しさが、人生において大きな力となる。
悔しさをバネにした時の落とし穴
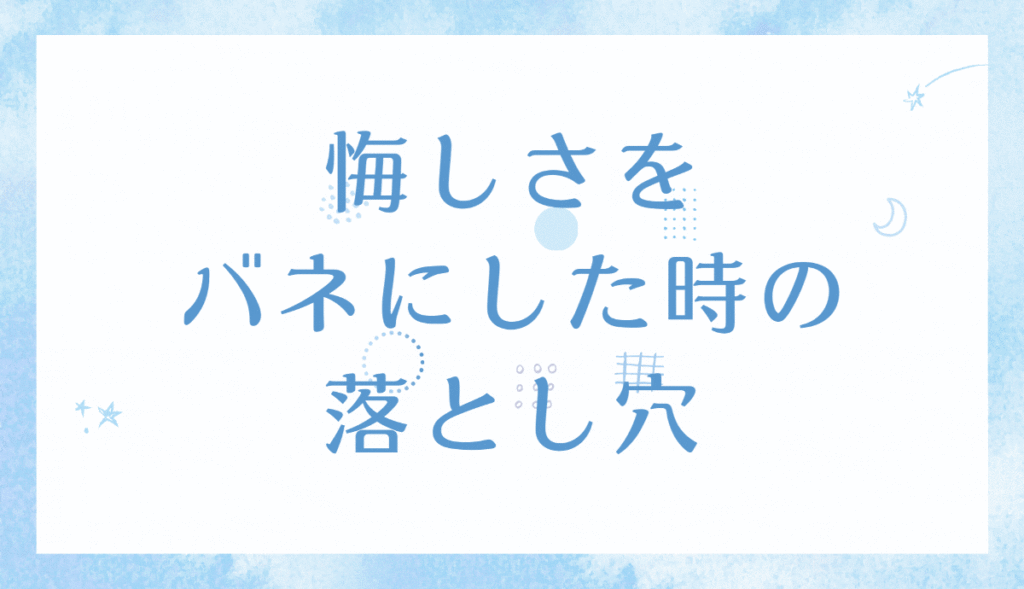
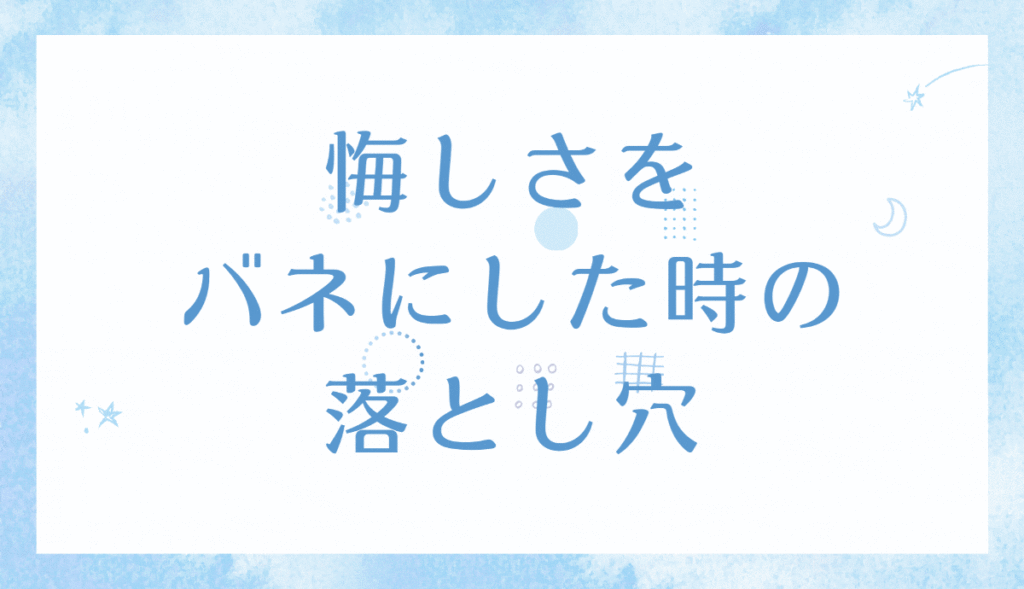
『悔しさを前向きなエネルギーに変える』というアプローチは、非常に積極的で力強いものに思えますよね。



けれど、その背後には注意すべき落とし穴が存在していることも忘れてはいけないんです。ここでは、そのリスクについて詳しく考察して行こうと思います。
- 一時的なエネルギーの危うさ
- モチベーションの減退
- 比較による悪影響
- 幸福感の欠如
①一時的なエネルギーの危うさ
悔しさから生まれるエネルギーは、一時的なものであることを理解しておくこと。



この瞬間的な活力にばかり頼ると、徐々に心や体が疲れ果ててしまう。
他者の成功に対する悔しさを機に努力を始めることもあるかもしれませんが、その背後には疲労感が潜む可能性があることを理解しておくといいです。
②モチベーションの減退
成果を上げたとき、多くの人は一瞬の満足を得るものの、その後に『次に何をすべきか?』という不安や、さらなる挑戦に対する意欲の低下が伴うことがよくあります。



この状態が続くと、悔しさを原動力にした次の挑戦への意欲が薄れ、無意識に再び悔しさを求め続けるというネガティブな循環にはまってしまう危険性があります。
③比較による悪影響
悔しさを原動力にすることで、新たな『悔しさの種』を無意識に探し求めることがある。
いつの間にか自分よりも成功した他人と自分を比較して、その結果再び悔しさを感じることで努力を続けようとすると、心の中には常に『悔しい』という感情が漂うことになる。
このサイクルが、精神的な疲労を引き起こす要因になることがあります。
④幸福感の欠如
悔しさをバネにすることが習慣化すると、自分の生活が『悔しさ』に支配されやすくなる。
この状態では、成果を得ても心の満足感や幸福感を感じられず、無力感や劣等感が増してしまうことが多いです。
負のループ。



以上のことから、悔しさをエネルギーに変えること自体は効果的な戦略ではあるものの、その特性や関連するリスクをきちんと理解して、持続可能で前向きな姿勢を育むことが必要不可欠になる。
悔しさとエネルギーの関係
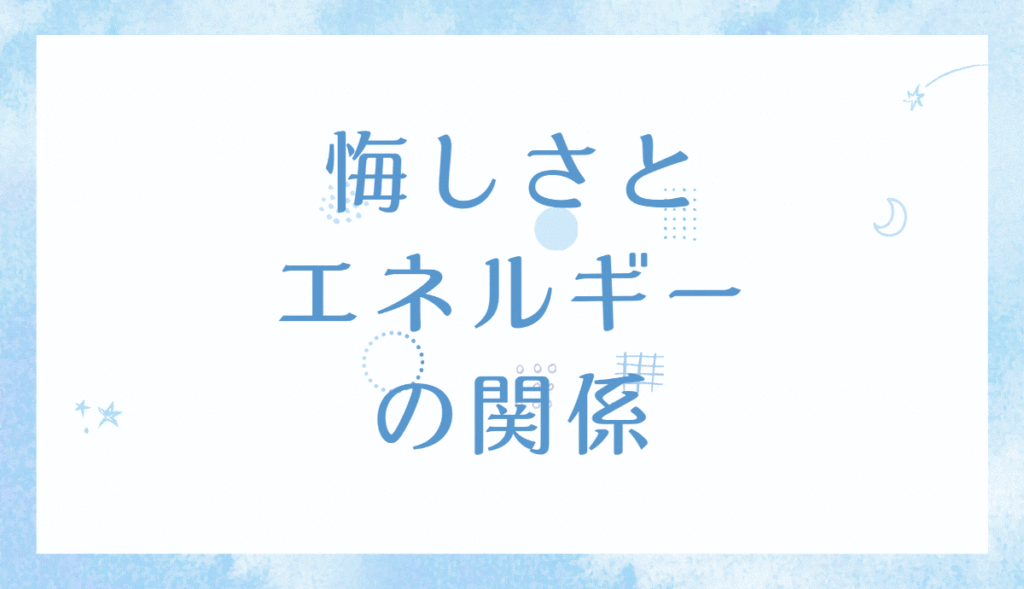
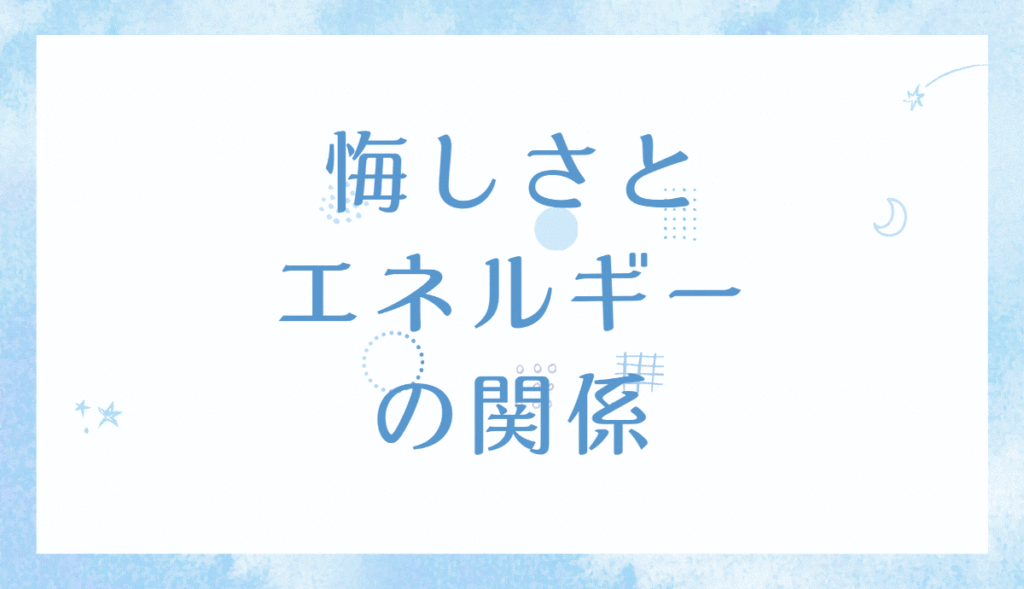
- 悔しさが生むエネルギーの性質
- エネルギーの枯渇とその影響
- 逆境からの真のエネルギー獲得
- 自己理解の重要性
- 新たな目標設定によるエネルギーの再生
①悔しさが生むエネルギーの性質
人々が抱く『悔しさ』は、目標達成に向けての強力な推進力になることがあります。
周囲の成功を目の当たりにしたり、自分の期待に応えられなかったときの感情は、成長の原動力へと変換される可能性も秘めていますが、こうした悔しさから生まれるエネルギーは、持続性に欠ける場合が多く、その背後には疲労感が隠れていることが少なくありません。
悔しさから生まれるエネルギーは『負』をまとうことがあるからです。
②エネルギーの枯渇とその影響
悔しさをポジティブな活動へと転換する行動は一目魅力的に見えますが、この感情に過度に依存することは、精神的な疲弊をもたらします。



頻繁に『悔しい』と感じることで、新しい『悔しさの元』を探す思考パターンが身についてしまい、結果としてネガティブな感情の循環に陥るリスクがあるということです。
この状態では、自己を消耗させ、持続的な成長が阻害されることになります。
③逆境からの真のエネルギー獲得
逆境や失敗は悔しさを引き起こす要因になりますが、それを乗り越えたときにはより強固なエネルギーを得ることができます。
悔しさを感じている間は一時的な活力にとどまりますが、逆境を克服し、そこから得られる達成感や喜びは、持続可能で深いエネルギー源となる。



ここで一旦、悔しさのエネルギーを終了させることができるといいんです。
④自己理解の重要性
悔しさは誰もが経験する感情ですが、その感情に振り回されるのではなく、どのように能動的に活用するかが重要。
自分がなぜそんな感情を持つのか、そしてその感情を次のステップへどう結びつけていくのかを考えることで、エネルギーを前向きに効果的に活用する道が開けます。
自己理解を深めることで、悔しさは成長への強力な駆動力に変わる。
例えば、自分がサッカーをしているとしますよね?
選抜メンバーに選ばれると思っていたのに、なぜか外れた。悔しいじゃないですか。
その悔しさはどこから来るのでしょうか?
他者(親など)から罵倒される、残念がられる、人と比べて責められるから?それとも、自身の技術が求められなかったから?それともライバルがいて、その人の方が選ばれたから?
理由は、色々ありますよね。
⑤新たな目標設定によるエネルギーの再生
悔しさをエネルギーに転換する過程では、つい『悔しさの種』を探し求めがちですが、これはしばしば疲労を引き起こす原因にもなります。
そこで重要なのは、安易な選択を避け、自己成長に寄与する新しい目標を設定することです。
新たな目標設定は、ポジティブなエネルギーの源となり、持続的な成長を後押しする要素となります。
どういうことかと言うと、例に挙げたサッカーで説明してみます。



悔しさを伴った理由が『いつもライバルだった人が選抜に選ばれたから』だとしましょう。すると、悔しさの種は『スキルもそんなに変わらない、あいつさえいなければ、俺が選抜になったのに。』
これが安易な選択になります。
この安易な選択を軸に目標を設定するならば、ライバルに勝つために早く走る練習をしたり、シュートの練習をするでしょうね。
例えば監督が、スキル以外にチームの士気を気にしていたらどうでしょう。そこから掘ると、スキル以外に、的確に状況判断ができる人材が必要で、仲間と協力しながらプレーできる人材を選抜するはずです。
もし、目立ちたいがために自身がシュートをすることだけを意識し、スキルだけに特性がある場合、選抜されるでしょうか?



ゴールの前に皆が集中している、どこに誰がいて、それぞれのスキルを認識し、相手チームのスキルと配置を見抜き、その中から自分がシュートを決めた方がいいのか、それとも自分以外の仲間にパスを回して、そこからゴールを目指した方がいいのか?その状況判断を一瞬にできるスキルを持った他の人材がいた場合、わたしが監督ならその人を選ぶ。
仲間を信頼するそのエネルギーが、さらに良いエネルギーを出すから、チーム全体の士気が自然と上がるんですよ。スキルも大事ですけど、大差がないなら、そこまで考えるでしょう?
自己成長に寄与する新しい目標を設定するならば、仲間を信頼しパスを出す勇気を持つこと。
こうなるはずです。



足が速くなる練習をしたり、シュートの練習をすることに専念はしないはず。それは安易で愚かな選択になるから。
悔しさをレジリエンス(逆境力)の源泉に
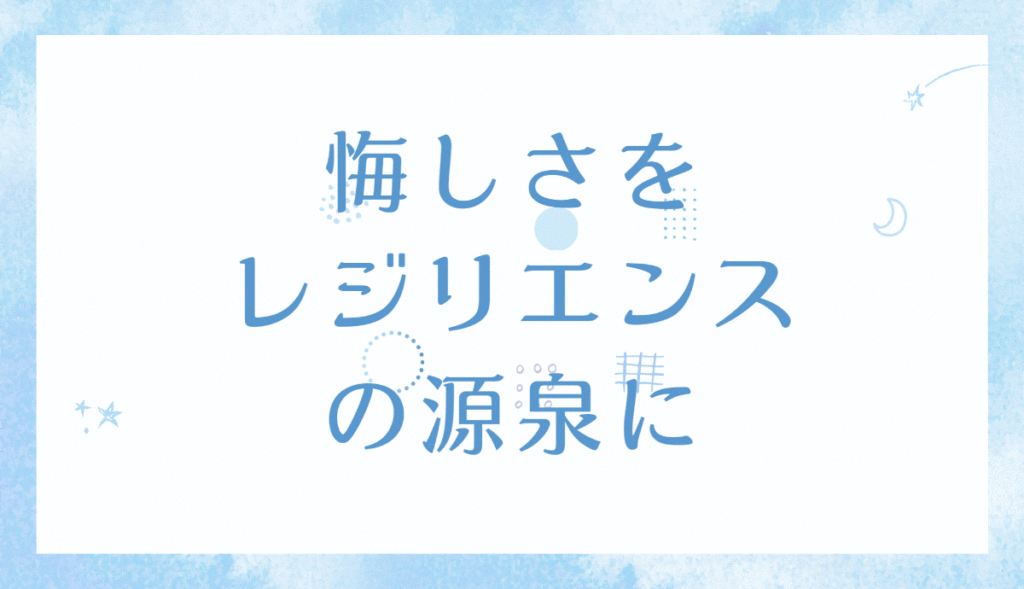
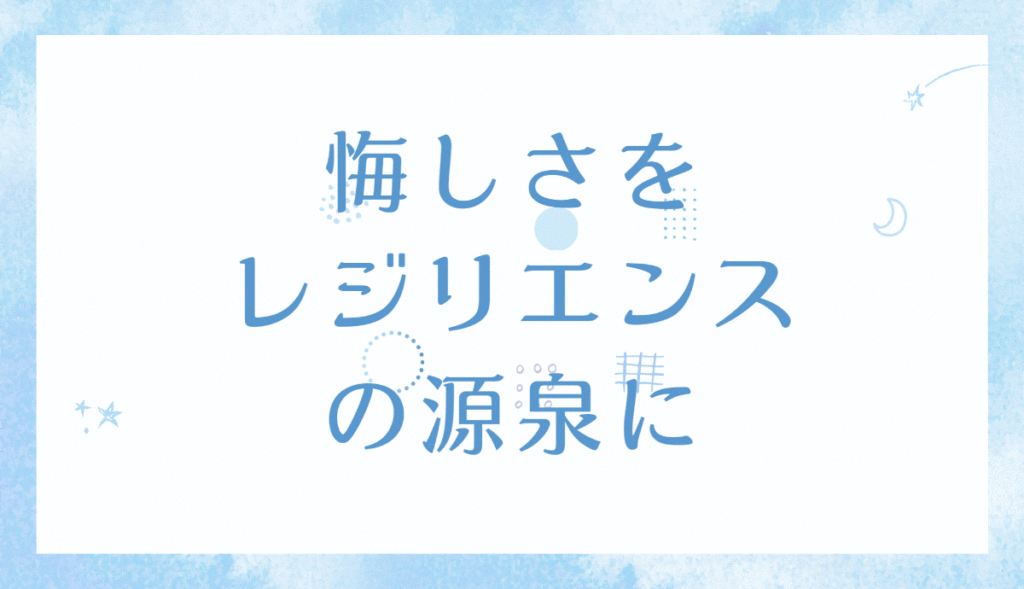
- 悔しさのポジティブな側面
- 知覚の変化
- 悔しさをエネルギーに変える方法
- 忍耐力と適応力の強化
- レジリエンス(新たな挑戦に直面したときに必要不可欠な力のこと)の重要性
①悔しさのポジティブな側面
悔しさは、一見するとネガティブな感情ですが、実はこれをうまく活用することで、逆境力を高める素晴らしい源泉になる。
悔しさを感じる経験は、自己成長のきっかけとして活かすことができます。
この感情をしっかり受容し、次へのエネルギーに変換することで、より強く、より レジリエントな自分を作り上げて行くことができます。
②知覚の変化
人生での数々の試練や悔しさを、私たちが『成長の機会』として捉えることができれば、その瞬間がレジリエンス(新たな挑戦に直面したときに必要不可欠な力のこと)の強化につながります。
たとえば、悔しさを抱えたとき、自分に起こった出来事を冷静に考え、何が原因なのかを考えることが大切です。
このプロセスを通じて、私たちは『似たような状況に直面したとき、どう対処するべきか』というスキルを磨くことができる。
混乱しがちなのが、他者(親など)の期待が入っているとき。
自分でもそれを自覚していればいいですが、サッカーで例えるならば、親から『なんでパスなんか回したの?あれ、シュート自分で決められたでしょう!?』と言われる環境があったとき。
親は自分の子どもが目立つことを喜ぶ思考回路にいる。
自分も親の喜ぶ様子が見たい、だから頑張る。
これを自分で理解していればいいんですけど、大抵は、他者(親など)の期待に応えようとしている自分に気が付かず、問題のすり替えが起こり、シュートを決めて自分も目立ちたいと思っていると錯覚が起こる。



違う、その人はシュートを決めて自分が目立ったことで、親が喜ぶことが嬉しいんです。サッカーとは関係ない、親を喜ばせることがその人の人生なんです。
その思考回路が本当に自分のものかどうか?の判断は必要ってことです。
要するに『知覚』。分かっていればいいんです。
他者(親など)が喜ぶ姿が見たい自分がいるのか、シュートを決めて目立ちたいという自分がいるのか。
そして、話題は逸れますが、他者(親など)が喜ぶ姿が見たい自分がいた場合は、なぜそうなってしまっているかのパラダイムに気づいた方がいいかもしれません。
③悔しさをエネルギーに変える方法
例えば、自分が望んでいた成果が得られなかったとき、その悔しさを単なるストレスとして受け取るのではなく、次の挑戦への原動力にしてみる。
目標を再設定し、それに向かって行動を起こすことが重要。
『この悔しさをどう活かすか』が、私たちの再起動の鍵になる。
具体的な行動例
- 目標の再設定: 悔しさを感じた後は、まず自分の目指すべき目標を再評価し、現実的かつ挑戦的な内容にしてみる。
- 自己反省: どのような状況が悔しさを生んだのか、何が足りなかったのかを振り返り、次に活かせる貴重なフィードバックに変える。
- 小さなステップを踏む: いきなり大きな目標を目指すのではなく、小さなステップを積み重ねることで、悔しさを感じたことによるエネルギーを持続的に活用して行く。
④忍耐力と適応力の強化
続けて努力し、少しずつ結果を出していくことで、自信もついて行く。
この自信が、次の困難を乗り越えるための基盤になり、私たちのレジリエンス(新たな挑戦に直面したときに必要不可欠な力のこと)を強化することになる。
サッカーの例で例えるならば、小さな『パスを出す』という勇気から、仲間意識が芽生え、良いプレーができるようになり、選抜に選ばれるようにもなり、チームに貢献することができるようになる。
そのエネルギーがチーム全体に行き渡れば優勝できる可能性も高まる。
その流れが全て自分の自信に繋がって行きます。
⑤レジリエンスの重要性
悔しさをエネルギーに変え、その経験を糧にしていけるかどうかが、未来の成功を左右することになります。
この力を身につけることで、より困難な状況にも立ち向かう勇気と知恵を持つことができる。
過去の自分と比べることが大切な理由
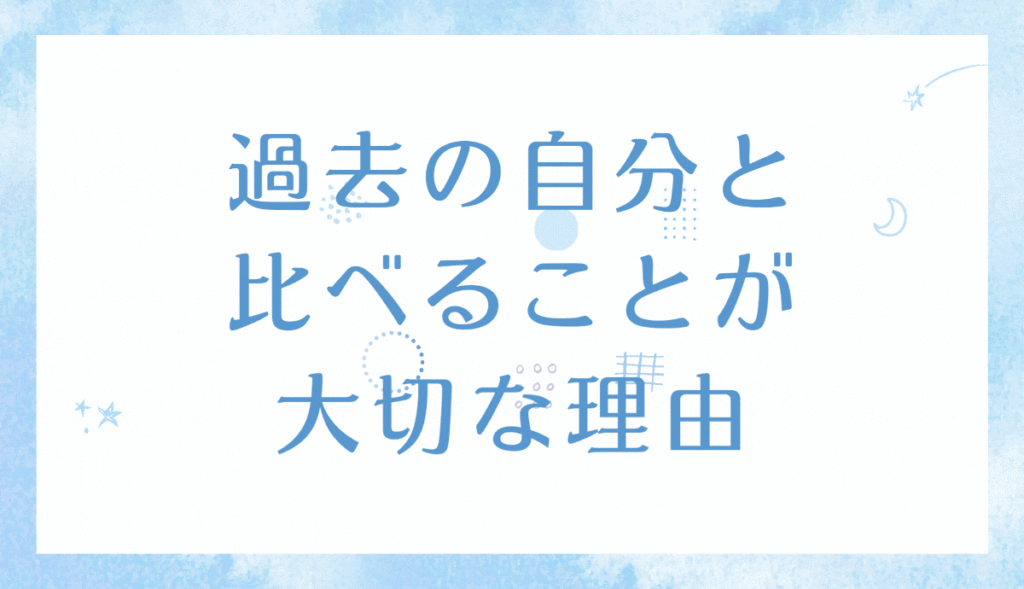
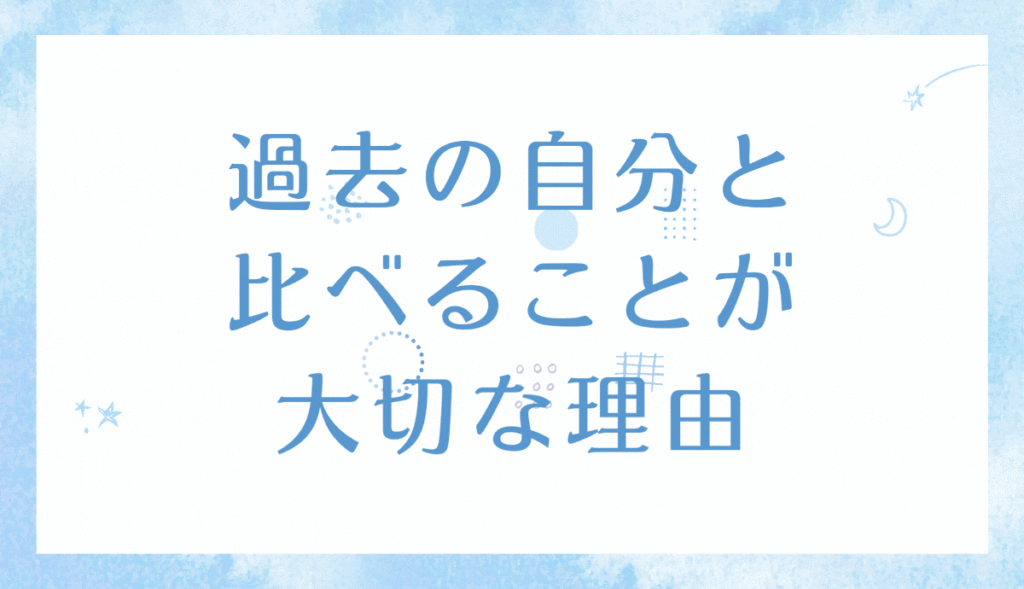
- 成長を実感するための手段
- 自信を深める
- 視点を広げる
- 達成感の促進
- 競争心を和らげる
- 自己成長の道筋を描く
①成長を実感するための手段
過去の自分と比較することは、自分の成長を実感するための有効な手段。
このプロセスを通じて、自分がどれだけ進化したのか、どのようなスキルを身につけたのかを明確に理解できます。
例えば、数ヶ月前にできなかったことが今では簡単にできるようになっていると気付くことで、自己肯定感を持てる。
②自信を深める
過去の自分と比較することで、自信を持つことができます。
身近な成功体験を挙げ、自分が乗り越えてきた困難や課題を振り返ることで、『あの時よりも今は成長している』という実感が生まれる。この自信は新たな挑戦に対する動機にもつながります。
サッカーの経験で言うならば、ライバルに悔しさを抱いていた自分と比べると、そこを通った後はきっと、適切なパスを出すことができなかった自分への悔しさに変わっている、こんな感じです。
次はきっと、もっと周りを見るようになる。
③視点を広げる
過去との比較は、単に自分の成長を確認するだけでなく、自分が何に対してどのように反応してきたのかを振り返る機会でもある。
これにより、困難な状況に対する自分の思考パターンや行動パターンを把握でき、次回同じようなシチュエーションに直面したときに適切なアプローチを考える手助けになります。
サッカーでの経験が、人生に生きてきます。あのときこうだった、その経験が社会に出たときに生きてくる。
もし、ライバルに勝つことを繰り返す人生だったらどうでしょう?差は歴然。
④達成感の促進
過去の自分と比べることで、目標達成へのモチベーションを高めることができる。
『今の自分は、過去の自分が設定した目標を達成するためにどれだけ努力してきたのか』を考えることで、次なるステージに向けての意欲が湧いてきます。
サッカーの例で例えるならば、チームへの貢献という目標を設定して歩んできてるはずです。
小さな行動『仲間を信頼してパスを出す』これで、チームの一員として活躍できているはず。そしてその中で、なくてはならない人材になっているということです。
選抜には絶対に選ばれるようになっている、そこから次のステージ『チームで優勝をすること』になる。
今の自分は、チームで協力して優勝を目指すこと。



過去の自分は、チーム内で自身がシュートを決めて目立つこと。こちらだと、次のステージが無いの分かりますか?ずっと同じステージ。極端な例ですけどね。
⑤競争心を和らげる
他者との比較がもたらす嫉妬や劣等感が気になる方も、過去の自分と比べることでその競争心を和らげることができる。
他人と競うことばかりに焦点を当てるのではなくて、自分自身との格闘に集中することで、よりポジティブなエネルギーを生むことができます。
⑥自己成長の道筋を描く
過去の自分との比較は、自己成長の道筋を描く手助けにもなります。
何がうまくいったのか、どのようなことを改善しなくてはならないのかを考えることで、次のステップを具体的に考えることができるんです。
目標を設定し、それを達成するための計画を立てることは何よりも重要です。
まとめ
過去の自分と自分を比較することは、自身の成長を客観的に把握し、自信を深めるための重要な手段です。
悔しさを感じるからこそ、次への原動力を得られるのです。
そしてこの悔しさを乗り越えていく過程で、私たちはレジリエンス(新たな挑戦に直面したときに必要不可欠な力のこと)を養うことができます。
つまり、過去の自分と自分を比較し、悔しさを認識し、それをポジティブなエネルギーに変えていく。
このサイクルを繰り返すことで、私たちは確実に自己成長を遂げていくことができる。
本を読んで、この知識を足したいと思ったので、記事にまとめました。
子どもさんが、この本を手に取ることがあったなら、補足として付け足してもらえると、未来に繋がるんじゃないかと思います。
子どもはとても素直。けど、考え方が分からないから。知識の補足をした方がいい。
二ーバーの祈りってご存知ですか?和訳されたものはいくつかるのですが、その中から今回は2つ。



わたしは、変えることのできないものについてはそれを変える力を身に付けたいと思って生きてます。変えられないものはあると思う、けど、変えられないことも無いと思うんですよ。子どもには、両者を見極めるための知恵をさずけて行きたいです。
その知恵が明りになり、正しい道を照らしてくれるから。
サッカーの例で言うならば、変えることのできないものは、『サッカーで選抜から外れたこと』『監督』でしょうね。それを受け入れる強さを身に付けるためにどうするか。
監督に見る目がない。
これで終わるのも一手。監督を変えられないから受け入れるのか、それとも他のクラブチームへ移動するのか。考え方は色々。
選抜から外れたことであっても、受け入れないといけない。どういう風に受け入れるのか?が重要になってくると思います。
わたしなら、子どもが自身がゴールすることに拘っているのが見えた時点で、、



もっと周りを見ろ、お前じゃなくてもゴールできる人材が周りに何人いたと思う?そのスキルくらい分かるだろう?チームメイトも信じれないようじゃぁ、サッカーなんて辞めてしまえ。
監督の采配に応じたプレーにした方がいいのか、それとも、自身の見る世界にもっとすごい大きなスケールがあれば、それに相応するくらいの反論があれば、言ってこい。
くらい言ってるかもです。
変えねばならないものを何に充てるか。まず、変えられるものと、変えられないものを見分ける力が必要なんです。
『あの監督見る目ないわー』と愚痴を言う愚かさたるや。そういうことを子どもに教えて行きたいんです。
わたしなら、自身の思考(仲間を信じる力)に充てますが、その判断は子どもと話し合いながら決めます。あくまでも、例、ですからね。色々な考え方があると思います。

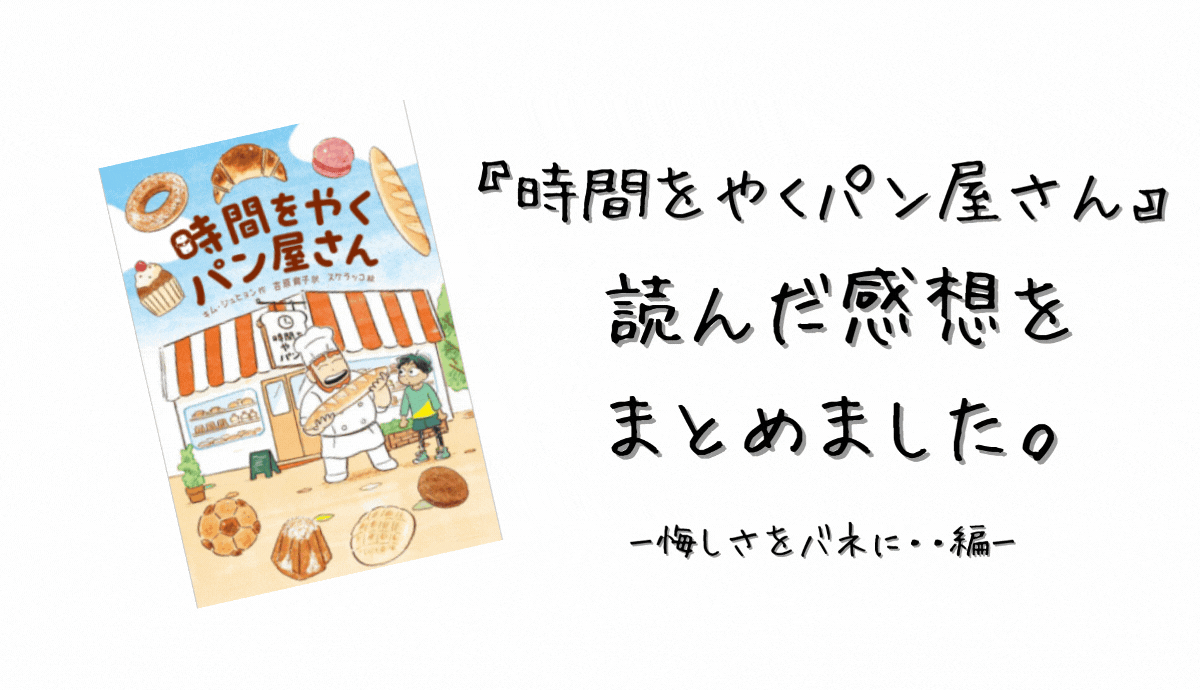

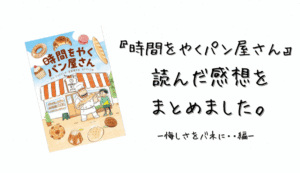
コメント