『生きてる次元が違う』日常生活していると、たまに耳にしたり、自分で発言したりすることがありますよね?
理解しようとしても理解できないほど自分とはかけ離れている。
この意味合いで間違いはないですが、良い意味と悪い意味どちらも含まれています。
- レベルが高すぎて次元が違う、次元が高い
- 相容れない、同じ土俵にも上がりたくない、次元が低すぎる
という2つの意味合い。
以前、3次元と5次元について記事をまとめたのですが、この記事では1次元~5次元までの思考をさらに細かくまとめてみました。
自分がどの次元にいるのか?目安になるかもしれません。ご参考程度にどうぞ。
『次元が違う』と感じるときは?
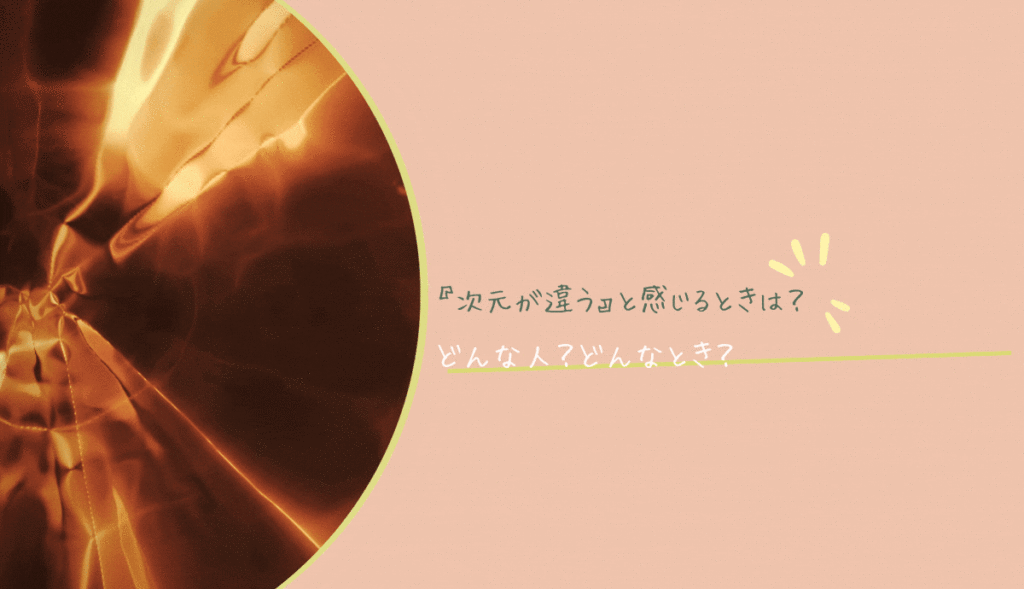
私たちが日常生活の中で『次元が違う』と感じる瞬間は色々ですよね。
それを理解することで、自分自身の考え方や行動がどのように次元を超えているのか、または逆に固定されているのかを知ることができます。
- 『次元が違う』とは何か?
- 『次元が違う』と感じる瞬間
①『次元が違う』とは何か?
『次元が違う』とは、単に能力やレベルを指すだけではなく、視点や思考の広がりを示す言葉でもあります。例えば、ある人が特定の分野で非常に高いパフォーマンスを発揮している場合、私たちはその人を『次元が違う』と表現しますが、これはその人が持っている観点やアプローチが我々のそれとは異なるために生じる印象です。
高いパフォ―マンスを発揮する場として、主に3つに分けられると思います。
物理次元:私たちが普段感じることのできる、物質的な世界
感情的次元:人間関係や感情の動き、感情をどのように処理し、どのようなレベルで表現・制御できるか
精神的次元:自己認識や内面的な探求のレベル
②『次元が違う』と感じる瞬間
日常生活の中で、人に対して『次元が違う』と感じる瞬間はいくつかあります↓
本質を見抜く視点
迷わずすぐに行動する力
人を動かす影響力
圧倒的な努力と継続力
価値観が独特でブレない
時間の効率的な使い方(驚異的なスピード)
これらで圧倒的な差を見せつけられたとき、相手の思考力、行動力、価値観、スキルのレベルが自分とは違う次元にあると感じやすいと思います。

『次元が違う』と感じる人は、普通の人が無意識にしていることを疑い、圧倒的な行動と考え方で差をつけている人だと思います。
このように、『次元が違う』と感じる瞬間は、自分自身の成長や周囲との関係性における理解の広がりを示すものであり、そこには深い意味と価値が存在することを知っておいた方がいいと思っています。
次元ごとの考え方や行動について、それぞれの特徴をベースにまとめてみました。
一般的な物理的な次元(空間と時間)だけでなく、考え方的な側面も含めて説明してみます。
1次元から5次元までの思考の違いを理解してみよう
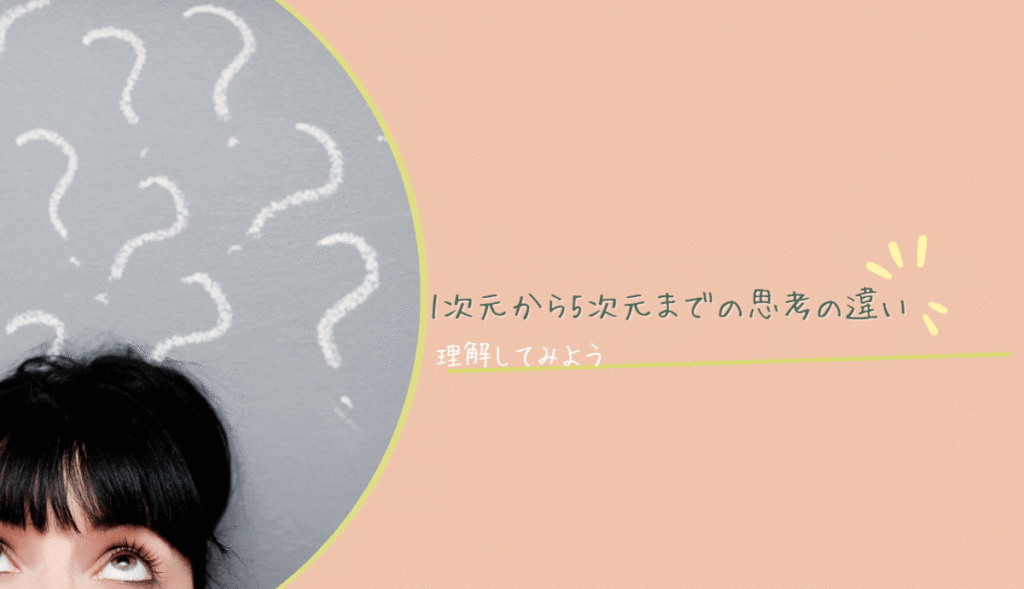
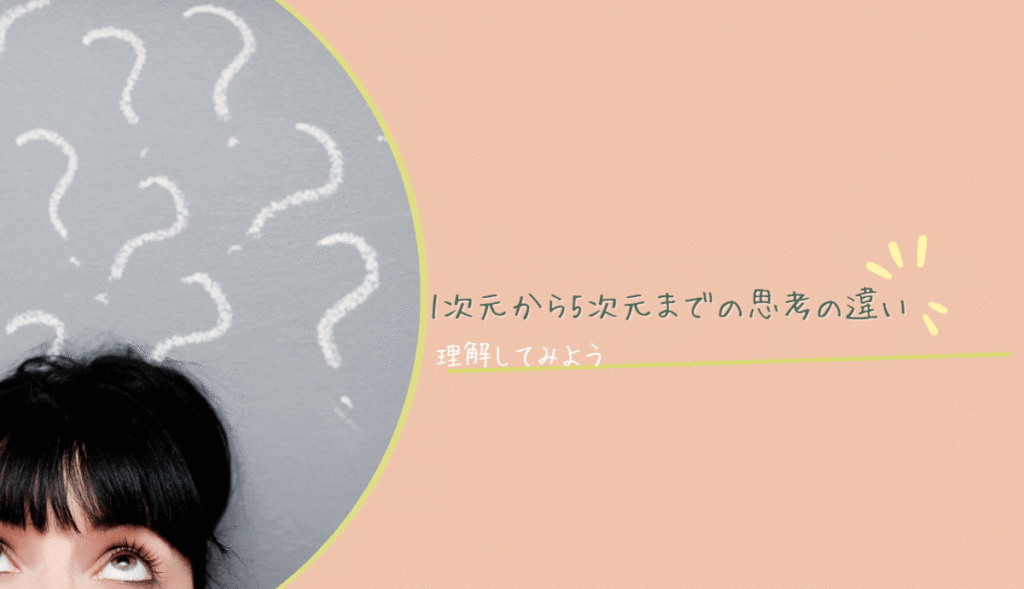
まず、単純に表にまとめると、こんな感じになります↓
| 次元 | 思想の特徴 | 実行する特徴 |
|---|---|---|
| 1次元 | 単純で直線的な思考 | 指示待ち、白黒思考 |
| 2次元 | 選択肢が増える | 見た目や効率を重視 |
| 3次元 | 多角的な現実的 | 計画的・バランスを考える |
| 4次元 | 時間を超えた視点 | 未来志向・本質を探る |
| 5次元 | 結果を超越した意識 | 直感・宇宙的なつながり |
| 次元 | お金の受け取り方 | 実行する |
|---|---|---|
| 1次元(白黒思考) | お金がある=成功、お金がない=失敗 | 思いついただけ、あるいは無計画に使う |
| 2次元(表面的) | お金=ステータス、贅沢できることが重要 | ブランド品や見た目だけお金を使う |
| 3次元(現実的) | お金は労働や努力の結果 | 計画的に稼ぐ、貯金・投資を考える |
| 4次元(エネルギーの流れ) | お金はエネルギー、考えるほどの流れが生まれる | 価値を生み出すことを重視、循環を意識 |
| 5次元(制限のない意識) | お金は持つ人の意識やエネルギー、波動が反映される、内面的な成長や価値観の変革と連動してその扱い方や使い方が変わる | 執着せず、自然に豊かさが流れ込む |
1次元や2次元の状態は、非常に固定的で単純なエネルギーや意識のパターンを示します。これらの次元は、基本的な生存本能や原始的な感情、分離感といった要素が強く働くため、一度その状態に落ち込むと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
低次元(一次元・二次元の思考に固定されている人)では、恐るべき低次元の状況にいても、高次元の視点が生まれにくいです。



恐怖、怒り、悲しみなど、深く根ざした感情は、自己防衛のために発生しやすく、それらにとらわれると論理的で柔軟な思考が難しくなるからです。
1次元(一次元的な思想・行動)
1次元とは、直線的な世界です。思考が単純で、視野が狭い状態を指すことが多いです。
- どうしてもを一方向からしか見ない(白黒思考、単純な偶然関係)。
- 深く考えず、単純なルールに従って行動する。
- 変化を嫌い、同じパターンを繰り返す。
- 目の前に集中し、大局は見ない。
- 自分の意見がないか、あるいは桁外れに偏った価値観を持っている。
- ルールが変わっても『上司が言ったからそれが正しい』と思う。
- この人は敵だから100%悪い、あの人は味方だから100%正しい。



例えば、『〇〇さんが言っていたからそうする。』など、指示待ちの行動が主。起きた事象を善か悪か、成功か失敗かでしか判断できません。
2次元(二次元的な思想・行動)
2次元は、縦と横の広がる世界がある。 思想的には、選択肢や考え方が増え、より柔軟な判断が可能にはなりますが、思考(立体的な視点)はまだなく、1次元と同じく、基本的に指示待ちで、言われたことしかできません。
- 理解の幅が広く、複数の視点を持つが、深さはあまりない。
- 経験則に基づいて行動するが、応用力に欠ける。
- 表面的な部分を重視しがちで、本質を見落とすことがある。
- この人は金持ちだから成功者。
- この人は貧乏だから負け組。
- 見た目がいい人=性格もいい。
- ダサイ人=性格も悪い。



例えば、『効率がいいからこの方法を選ぶ』といった一見合理的とも思えるような単純思考からくる行動が見られ、ファッションやステータスを重視、見た目や社会的評価を気にしています。2次元のアニメや漫画のように、自分にとって都合の良い理想的な価値観を持っています。
3次元(三次元的な思想・行動)
三次元は、現実世界の空間を持つ世界。思考が立体的になり、より深い洞察や複雑な判断ができるようになります。
- 多角的な視点で課題を考え、長期的な計画を立てる。
- 現実主義的で、感情だけでなく論理的に判断する。
- 『どうすれば成功するか』『最適なバランスは何か』を考えながら行動する。



例えば、仕事や人間関係において、全体のバランスを考慮した行動が取れます。目標達成のためにリスク管理をしながら戦略的に動くことができます。自分の意見を持ちつつも、他人の意見も尊重することができます。
三次元的な思考・行動の特徴
- 現実主義的な視点
→物理的な世界に強く注目しているため、目に見えるものや実証可能なものを基準にする判断。 - 経験と論理を重視する
→目の前の事象を合理的・論理的に捉え、過去の経験や実績をもとに意思決定をする。 - 起こる関係に基礎を置いた考え方
→ 『AをするとBになる。経験的にそうだったから。』といった直線的な発生関係の理解を基礎にして行動する。
勉強する→試験で良い点を取る、運動する→健康になる、仕事を頑張る→昇進するetc… - 計画と実行を重視する
→長期的な視点を持つ場合もあるが、それは未来の予測可能な範囲内での話であり、『時間の超越』や『パラレルな視点』は、ほぼない。時間や現実の概念は単純な因果関係の中で捉え、『偶然の流れ』『複数の可能性が共存する』ような視点は持ちにくい。。
三次元的な視点の限界
三次元の思考は『現実世界』の範囲内に収まりやすく、より広い次元(4次元・5次元)のような『抽象的』『超越的』な思考には発展しにくい。
例えば、科学的・数学的な論理思考は3次元の中では高度思考ですが(直感的には重いものが早く落ちると思いがちだが、科学的には、すべての物体は真空中は同じ速度で落ちる(ガリレオの実験)と論理的に説明できる)、スピリチュアルな直感的理解(4次元の視点)とは異なります。
物事を『多角的』に見ることはあっても、その多角性は物理的・論理的な範囲内に留まりがちです。



わたしの解釈は、本当の意味での多角的な視点(視座を変えたり、時間軸を超えて思考すること)は3次元ではなく、4次元以上と判断しています。多角的な視点を本当に持っていれば、4次元以上の思考が必要になってくるからです。
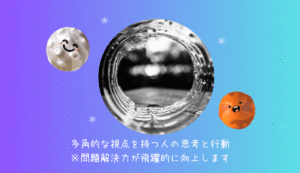
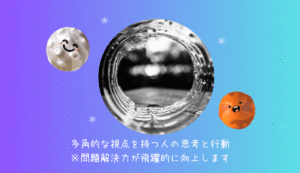
3次元的な考え方
→ 目の前の課題を解決するために最適な方法を考える。(論理的・実証的なアプローチ)
4次元的な考え方
→ この課題が生まれた本質的な原因は何か?未来にはどう変化するのか?(軸や抽象的な視点を時間を置く)
4次元(四次元的な思想・行動)
四次元は『時間』という要素が曖昧な世界。未来や過去の影響を考慮し、時空を超えた視点で思考する。
- 過去の出来事の意味を考え、未来にどのような影響があるかを想定する。
- 目の先の利益よりも、長期的な幸福や成長を優先する。
- 本質の本質や真理を探求し、哲学的・スピリチュアルな視点を持つことがある。



『この選択が10年後にどう影響するか?』といった未来志向の思考があり、歴史や文化の流れを踏まえて行動することができる。目に見える現象だけでなく、潜在的にある本質や法則を探ることができる。
5次元(五次元的な思想・行動)
五次元的な意識は、私たちが通常感じる『時間』や『因果関係』という枠組みを超え、個人がより広い視野で宇宙の理性やエネルギーの流れを直感的に捉えられる状態。このような意識は、表面的な偶然の裏に隠された深い意味や連関を認識するための新たな思考のあり方です。
- 『自分』という存在を超えて、宇宙や他の意識とつながるような視点を持つ。
- 起きた事象を超越、直感的・瞬間的に本質的に理解する。
- 『すべては続いている』『現実は意識が進んでいる』といった考えを持つ。



共感力が最大限に高く、他人の感情やエネルギーを直感的に理解。固定概念を持たず、柔軟に状況に適応することができます。『今この瞬間がすべて』というような生き方をしています。
五次元でのエネルギー(スピリチュアルな説明)
表面的な偶然の背後にある法則性
通常、出来事は偶然や単なる因果関係として捉えられがちですが、拡張された意識状態では、一見無関係に見える現象同士が実は深いレベルで連関していると認識されます。これにより、偶然と思われる事象にも潜在的な意味やパターンがあると理解できるようになります。
直感による統合的な理解
この状態では、論理的な分析だけではなく、直感や内面的な洞察を通じて、物事の全体像や相互関係を把握する能力が高まります。結果として、私たちは日常の中で『偶然』と捉えていた出来事に対しても、より深い意味づけを行い、全体としての流れやメッセージを感じ取れるようになります。
五次元におけるエネルギーの特徴
- 波動(振動数)として存在、人のエネルギーを見る
- 感情・意識・思考がエネルギーとして、自分に与える影響を考える
- 物質を超えたエネルギーフィールド(オーラ、気)として作用、宇宙全体とのつながりを形成
- 高次の意識(魂、宇宙意識)とつながることで変化する
『エネルギーとは、すべての存在が発する波動であり、意識によって変化する』と考えています。
つまり、肯定的な感情は高い波動を持ち、否定的な感情は低い波動を持つという意味です。
ヘーゲルの言う、絶対精神とはこのことだと思っています↓
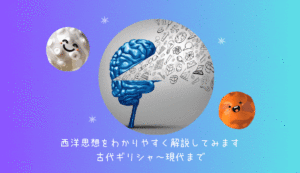
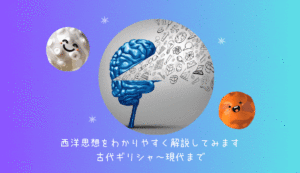
まとめ
低次元と高次元は対立するものではなく、むしろ統合すべき両極の側面だと思っています。
日常の低次元の経験があっても、それを意識的に受け入れ、学びに変えることで、全体的な意識の成長や統合が促進されるという見方ができるからです。
つまり、低次元の思考状態では、体験に対して反応的に怒りや恐れといった感情が生じやすい一方で、高次元の意識を持つ人は、同じ体験を内省の材料や学びの機会と捉え、そこから成長するための洞察を引き出す傾向がある。
考え方、捉え方、感情処理の仕方に違いがあります。



そして、そこから派生する波長が宇宙に繋がります。だから、5次元思考でいた方が生きやすいんです。
人の思考や意識の次元は、状況によって変動します。
特に3次元以下は引きがとても強い。磁石と一緒。そして、人は次元が落ちても気が付きにくい。
次元が落ちても気づかない理由と低次元の影響


5次元の意識を体現していれば、低次元の影響を受ける時期もあるものの、意識の根底が高次元にあるため、再び高次元の状態に意識を戻すのは比較的容易。
日常の中で低次元的な状況に引き戻されることがあっても、根本的な意識は既に高次元にあるため、すぐに元の状態に戻れる可能性が高いです。
では、5次元以外が、なぜ低次元に落ちても気づかないのかを考えてみます。
- 物理的な宇宙が3次元
- 低次元の影響を受けるとどうなるか?
①物理的な宇宙が3次元である
普段の生活の中で、私たちは家庭、学校、社会、メディアなどからさまざまな価値観や行動パターンを学び、自然と取り入れています。私たちは常に低次元の影響(生存本能、固定観念、恐れなど)を受けやすい環境にあります。
- 自己中心的な価値観
社会や文化の中で、個人の生存や成功、競争が強調されるため、無意識のうちに自分自身の利益を最優先に考える傾向が育まれます。 - 防衛本能や恐れに基づく反応
危険や不確実性に対する防衛反応(怒り、恐れ、不安など)は、幼少期からの経験や環境によって強化され、日常の中で自動的に働くパターンになっています。 - 分離感や孤立感
他者との違いや競争に焦点が当たり、互いに切り離された存在として認識されるため、全体的な一体感よりも分離された自己意識が強くなります。
比較することで自己の現状や成長の方向性を見出すことができます。ただし、重要なのは、自己評価を外部からの数値や順位だけに依存させず、内面的な成長や創造性、個々の可能性にも目を向ける必要がある。
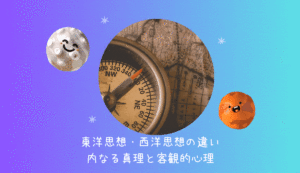
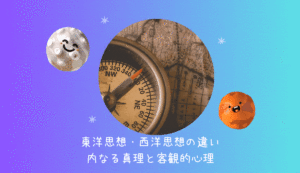
これらのパターンは、意識的に注意を向けなければ無意識のうちに日常生活で繰り返され、私たちの思考や感情、行動の基盤となっています。そのため、何も意識せずにいると、これらの低次元的な反応が『デフォルト』として働いてしまい、高次元の意識や広い視野を気づきにくくしていきます。
その中で、4次元や5次元とされる高次元の意識状態を保ち続けるのは至難の業とも言えます。しかし、内面的な意識の浄化や成長、瞑想や内省といった実践を通じて、高次元意識を体験し、統合することは可能であり、目指すと生きやすくなります。
②低次元の影響を受けるとどうなるか?
| 影響 | 結果 |
|---|---|
| ネガティブな人と一緒にいる | 『あの人の考え方、やっぱり正しいのかも、、?』と無意識に影響を受ける |
| 批判や悪口を聞き続ける | 『なんか自分もイライラしてきた』と感情が乱れる |
| 低レベルな戦いに巻き込まれる | 本来の目的を忘れ、余計なエネルギーを使う |
| SNSで低次元の論争を見続けている | 思考が荒れ、感情が不安定になる |



低次元の人や環境に巻き込まれると、自分の思考が『いつの間にか低次元化』しやすいのは確か。
まとめ
次元の変動は誰にでも起こることなので、それ自体が悪いわけではありません。
大切なのは、『今の自分の思考の次元はどこにあるのか?』を意識すること。1次元~5次元までありますが、大体人は、1次元~3次元をウロウロしています。
1次元思考になることもあれば、3次元的思考をすることもある。それが自身のエネルギーです。
それを2次元~3次元、3次元、3次元~4次元と上げて行くことに意味がある。普段から意識しておくことが大切。
これは重要なポイントです。


高次元思考を身につけるためのマインドセット
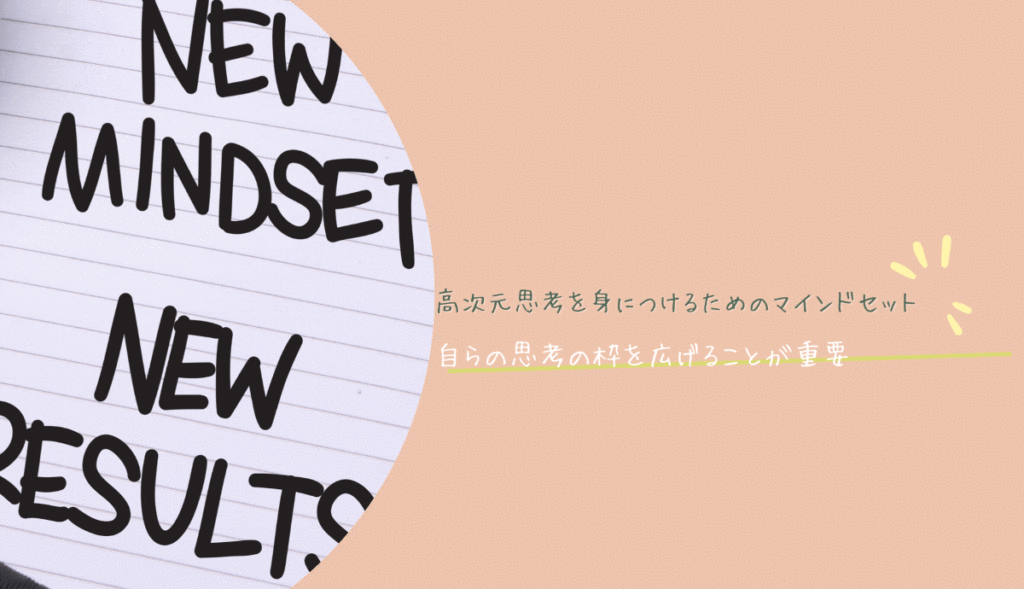
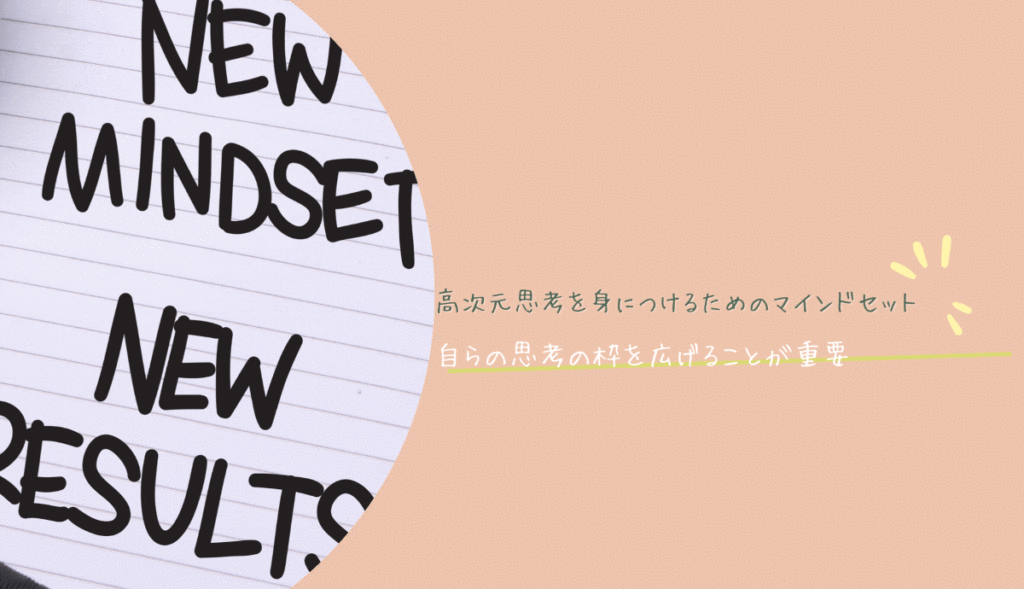
高次元思考を身につけるためには、まずは自らの思考の枠を広げることが重要です。
以下に、高次元思考を養うための具体的なマインドセットや習慣を紹介します。
- 自己理解を深める
- 他者との対話を重視する
- 常に学び続ける
- 結果ではなくプロセスに注目する
- 自分のビジョンを持つ
①自己理解を深める
高次元思考を実践するためには、自分自身を理解し、自分の考えや感情に気づくことが欠かせません。以下の方法で自己認識を高めることができます。
- 日記(ブログ)をつける:毎日の出来事や感情について記録することで、自分の思考パターンや反応を確認できます。
- 瞑想や自己反省:静かな時間を持ち、自分の内面に向き合うことで、思考をクリアにし、目的を見つけやすくなります。


②他者との対話を重視する
他者とのコミュニケーションは、高次元思考を育てるために非常に重要です。
- オープンマインド:相手の意見や視点に対して偏見を持たず、受け入れる姿勢を持つこと。
- フィードバックを求める:自分の考えを他者に話し、彼らの意見を聞くことで新たな視点を得ることができます。
③常に学び続ける
高次元思考を身につけるためには、継続的な学びが欠かせません。
- 本を活用する:自己啓発書やビジネス書を読んで、新しい考え方に触れる。
- 多様な経験を重ねる:異なるバックグラウンドを持つ人々との交流や、未知の分野に挑戦して、視野を広げることも大切です。
④結果ではなくプロセスに注目する
高次元思考を実践する際には、結果だけに焦点を当てず、プロセスを重視する姿勢が必要です。
- 学びと成長を楽しむ:結果がどうであれ、その過程で得た学びや成長に目を向ける。
- 失敗を恐れない:失敗を成長の一部として受け入れ、次に生かすための経験として活用します。
無理に思考を訂正する必要はなく、その過程で得た学びに焦点を当てることには意味があると思います。その焦点(視点)が気づきになることがあるからです。
⑤自分のビジョンを持つ
高次元思考を身につけるには、自分が目指すビジョンを明確にし、そこに向かって進むことが重要。
- 短期的・長期的な目標設定:目指す方向性を定め、短期的な目標と長期的なビジョンを設定する。
- ビジョンボードの作成:目に見える形で夢や目標を表現し、視覚的な刺激を通じてモチベーションを高めることが有効です。
これらのマインドセットを意識し、日々の生活に取り入れることで、あなたの思考は自然と高次元へとシフトしていきます。考え方の次元を上げていくことで、人生の質も向上していきます。
物事を俯瞰的に捉える具体的なトレーニング方法
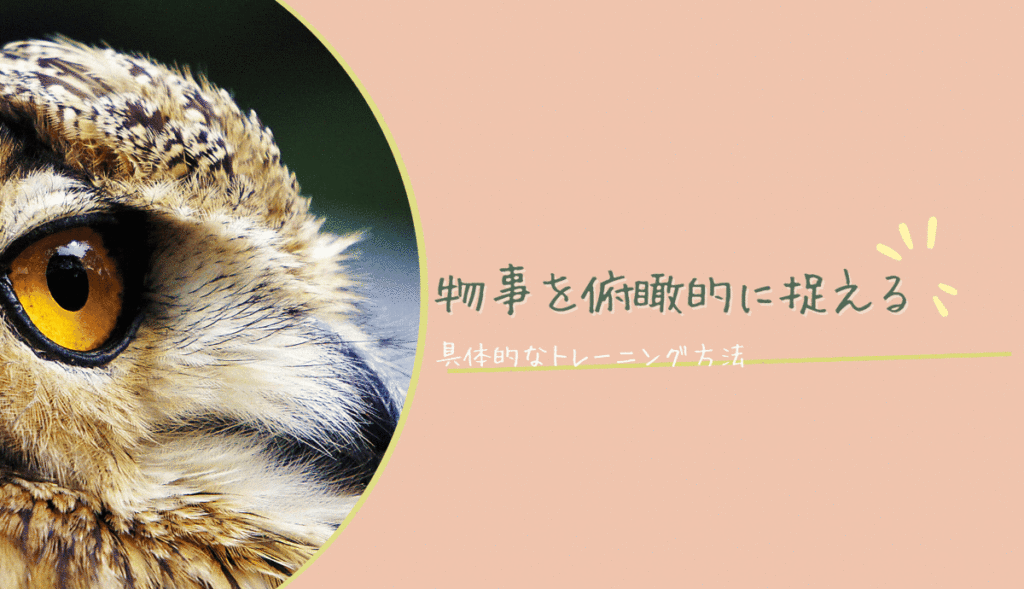
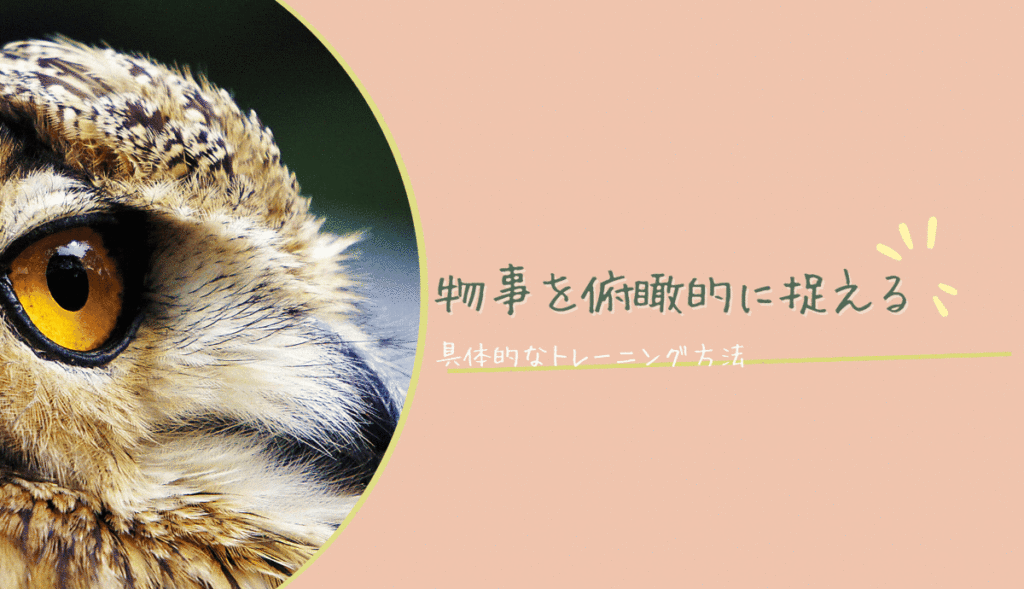
物事を俯瞰的に捉える力を身につけるためには、日々のトレーニングが欠かせません。以下に、実践しやすい具体的な方法をいくつか紹介します。
①自己観察を行う
自己観察は、まず自身の思考や行動を客観的に分析することから始まります。以下のステップを試してみてください。
- 日記(ブログ)を書く: 日々の出来事や感じたことを記録し、自分の感情や反応を分析します。後から読み返すことで、自分の思考のパターンを見つけやすくなります。
- ルーチンをチェック: 日常の中で、何気なく行っている行動を見直し、どのように思考が働いているのかを理解します。『なぜこの選択をしたのか?』と自問自答することで、思考の根底にある価値観や意図に気づくことができます。
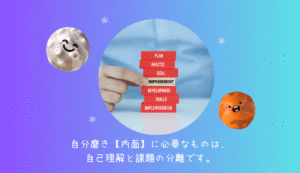
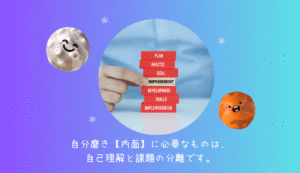
②俯瞰視点を養う
物事に対して高い視点を持つことは、俯瞰思考において重要な要素です。
- 視点を変える: 環境を変えて物事を観察してみることから始める。例えば、普段の視線を少し上げて周囲を見渡すと、新たな発見があります。また、屋上や高台から景色を眺めることで、物事の全体像を把握する感覚が養われます。
- グラフィック化する: 複雑な問題や情報をフローチャートやマインドマップにして視覚化すると、構造が明確になり、全体像を見る助けとなります。視覚的な要素は理解を深め、思考を整理する助けになります。
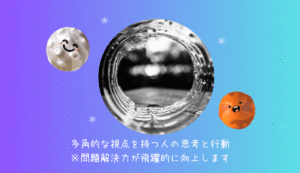
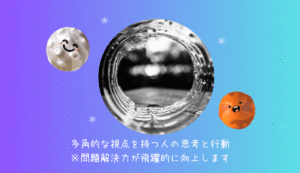
③時間軸を意識する
物事を考える際、『過去・現在・未来』の時間軸を意識すると、情報の流れや変化をよりリアルに把握することができます。
- 歴史的背景を調べる: 自分が直面している問題の背景や歴史を調査し、その因果関係を把握します。特にビジネスにおいては、市場の流れや競合分析に役立ちます。
- 未来予測を行う: 今の選択が未来にどのような影響を与えるかを考え、必ずシミュレーションを行う癖をつけてください。行動の結果が未来にどのように反映されるかを意識することで、現在の行動が重要であることを自覚できます。
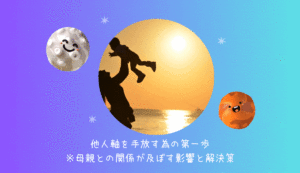
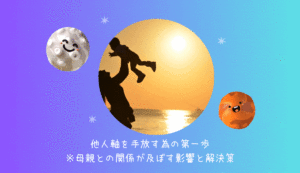
以上のトレーニング方法を日常に取り入れることで、物事を俯瞰的に捉える力を鍛え、思考の次元を高めることができます。
まとめ
物事を俯瞰的に捉え、高次元思考を身につけることは、私たちの仕事や生活を大きく変えていきます。
自己理解を深め、常に学び続けることが、自分のビジョンを明確にし、失敗を恐れずに行動できる一助になる。
日々のトレーニングを通じて、時間軸を意識し、より深い理解と洞察力を手に入れることができます。
このように、高次元思考を養うことは、自己成長と豊かな人生につながる重要なスキルです。




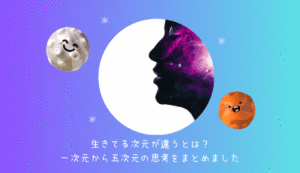
コメント