最初はただのモヤモヤだったんです。なんか納得いかない。なんか苦しい。なんか全部めんどくさい。……そう、ただの『なんか』まみれ。
でも気づいたら、

これ、なんで私ばっかり?なんであの人は平気そうなのに?
という問いが、ずーっと頭の中でループ再生されていたんです。
で、行きついた先が哲学でした。いや、そんな予定はなかったんですけど、そうなってしまっていた。
モヤモヤ → 書く → 悩む → 考える → 調べる → 哲学?みたいな感じで、気づいたらソクラテスと肩を並べて問い立ててました(気のせい)。
でも本当に、自分の頭で考えて、体験通して頭で整理してきてから、偉人たちの哲学がよく分かってきた。これって、こういうことだよね?あれって、これでしょ?全部理解できるようになってた。



うそつけ。



だよね。それもあるかもしれない。だから、まとめてみたの。
結局、問いを持つこと自体が生きる意味を作るから。
というわけで、今回は──『なぜ人は悩み、問いを持つのか?』その旅を、自分の経験と一緒に振り返ってみると同時に、あなたが感じているそのモヤモヤって、実は『東洋の曖昧さ』とも『西洋のロジカル思考』ともズレちゃってるから起きてる。学校でも道徳でも親からも、なんだか『正解』ばかり求められるのに、実際は正解への考え方すら曖昧に教えられる。だから悩む。考え方が分からないから。
だからこそ本当に必要なのは、『東洋のゆるい多様性』を認めつつ、『西洋のガチなロジカル思考』を身につけて、自分で納得のいく答えを見つける能力だって気づいたわけです。
これがわたしの出した正解。
この記事を読むと、『なんで私だけが苦しいの?』という違和感が、実は古代からの哲学者も持っていた超定番の悩みでもあり、自分にも通じるということが分かります。さらに、東洋と西洋の哲学や心理学の『問いの立て方』や『答えの探し方』を知ることで、自分のモヤモヤがどんな風に整理されていくか、その道筋も見えてくるかもしれません。
ついでに、



哲学?ムリムリ、そんなの小難しくて苦手、ダリーよ!
というあなたでも、



あれ、意外と哲学って自分と関係ありまくりじゃね?
と思えるように、分かりやすく、ユルく、楽しく書きましたのでご安心を。実際、関係ありまくりますから。



そしたら、気軽にソクラテスと一緒に肩を並べて歩けるから(気のせい)。
私が“問い”を持つようになったきっかけ


人と自分を比べては落ち込み、周りの言動にモヤモヤを抱えていたあの頃。
私は、物心ついた小学生のころから、他人の考えや態度に対して『なんでそうなるの?』という違和感ばかりを感じていました。間違ってる、変わってほしい。そう思って何度も衝突しました。
違和感を感じるものの、やっぱり周りの人の言動に支配されてしまい、そこに馴染んだ。
だけど、違和感はずっと消えなかった。その教えに従いながらも、



おかしくない?….どうして、こんなことが言えるんだろう…..
という感覚が残っていて、今思えば、あの違和感は、自分としてのひとつの正解だったのかもしれない。
そういう態度を取り始めると、『まだまだ未熟』『まだまだ成長が足りない』『理解が足りない』と言われ、『あなたは、変わらなければならない』と何度も言われました。それが、とても辛かった。



今だから言えることは、そもそも、成長は足りなかったかもしれない。合ってる。けど、そもそも『理解』とは何だ?『足りない』とは何だ?理解しなければならないのは私だけなのか?それはなぜ?『理解』があるなら、私はこんな風に悩んでいないはず。色々矛盾が生じる。よって、その言葉もおかしいと判断します。
と返すでしょうね。(by ロジカルマン)
だから、何度もぶつかりました。『わたしが悪い』と言われるたびに、本をたくさん読んで“正解探し”を始めました。でも、あるときふと気づいたんです。
そもそも、『変わらなければならない』と言われて傷ついていた自分こそが、他人に変化を求めていたのではないかと。
むしろ、変わらなければならないと思っていたのは、自分の中の“正しさの押しつけ”だったと気づいたとき、初めて私は問いを自分に向けました。



私は、自分の人生を歩いているの?私ずっと他責で生きてる。
それが、私の“内面を掘る旅”のはじまりでした。
ただ、そこからは長かった。次は、『全部自分のせいだ』と自分を責め始める時期がきます。自責で押しつぶされそうになりながら、それでも前を向こうとした。けれど、ふと思ったんです。



なんで、私はこんなにも“自分が悪い”と思い込んで生きてんだろう?なんで、こんなに感情に支配されてしまうんだろう?
ここから、もう一度『世界を見る』フェーズに入ります。読む本の分野を増やしてみました。哲学や心理学、成功哲学。あらゆる知に触れながら、私は自分の“生きづらさの正体”を探しに行きました。
書くことは、そんな旅の中で唯一、手元に残った『自分との対話』。最初はただ感情をぶつけるように文字を吐き出していたけれど、だんだんと、誰かに伝えるように言葉を選ぶようになり、『自分の思考』が『誰かのヒント』に変わればいいなとブログを開始。
今では、私の発信が誰かの方位磁針のようなものにでもなればいいなと思っています。 悩みで動けなくなっている人に、『どこに向かえばいいか』を考えるきっかけを渡す。 たとえ最短ルートじゃなくても、自分の地図を持てば、迷い方すら変わるから。
進んでいる方向が東か西か?を迷うんじゃなくて、せめて、東への行き方を迷えるようになる。これが大事。
そして、ふと気づいたんです。
自分の歩んできたこの流れが、



これってさ…もしかして──これ、気のせい?……西洋があって東洋があって…色々繋がってない????
いや、気のせいでも調べてみたくなった。
というわけで、過去の偉人たちがどんな悩みと向き合い、どんな問いを立て、どんな理論を生み出してきたのか。
はい、比較表です。まとめてみました。
【過去の自分に向き合った偉人たち(西暦順)】
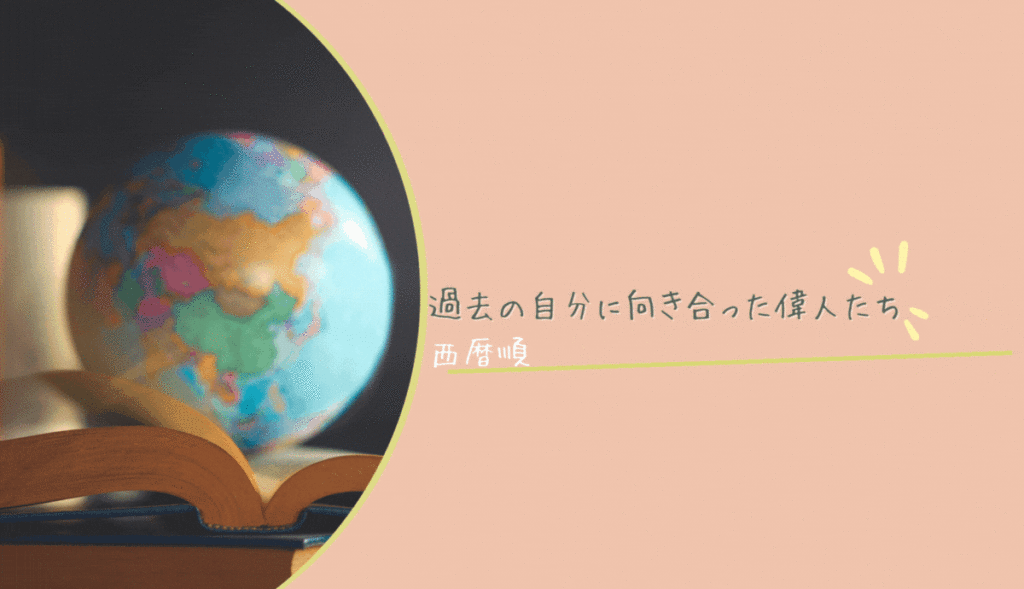
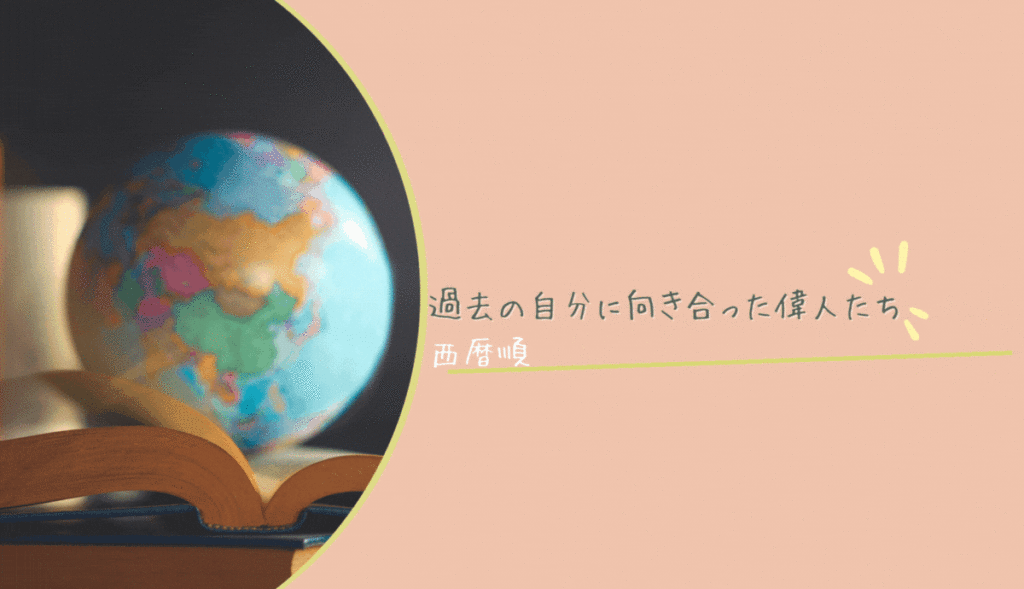
思いつくだけ並べてみた。あえて、東洋と西洋まぜてみる。
東洋と西洋と比較することで、色々な見方ができるようになるから。
| 人物 | 活動時期 | 主な悩み・向き合ったこと | 生まれた理論・思想 |
|---|---|---|---|
| 老子 | 紀元前6世紀頃 | 俗世に対する虚無感・人生の無常 | 道(タオ)・無為自然 |
| 釈迦(ブッダ) | 紀元前5世紀頃 | 老・病・死による生きる苦しみ | 四諦・八正道・中道 |
| ソクラテス | 紀元前5世紀頃 | 無知・無理解に対する恐れ | 無知の知・対話法 |
| イエス・キリスト | 紀元前1世紀頃 | 使命と死の受容、人間の罪と愛 | 愛と赦し・神の国 |
| カント | 1724-1804年 | 道徳・理性・自由の関係 | 純粋理性批判・実践理性批判 |
| ヘーゲル | 1770-1831年 | 精神と歴史の矛盾 | 弁証法・精神現象学 |
| ニーチェ | 1844-1900年 | 病弱・孤独・絶望・愛の喪失 | 力への意志・超人思想 |
| フロイト | 1856-1939年 | 抑圧・家族との葛藤 | 精神分析・無意識理論 |
| アドラー | 1870-1937年 | 劣等感・身体的コンプレックス | アドラー心理学・再定義 |
| ユング | 1875-1961年 | 夢・無意識との葛藤 | 分析心理学・個性化 |
| パールズ | 1893-1970年 | 抑圧・戦争神経症 | ゲシュタルト療法 |
| ナポレオン・ヒル | 1883-1970年 | 貧困・恐怖・劣等感 | 成功哲学・思考は現実化する |
| エリクソン | 1902-1994年 | アイデンティティの混乱 | 発達段階理論 |
| フランクル | 1905-1997年 | ナチス収容所・死の恐怖 | ロゴセラピー |
| マズロー | 1908-1970年 | なぜ人は満たされないのか/成長できないのか | 欲求5段階説・自己実現・自己超越 |
共通点になる『軸』は次の3つ。
『他者』や『社会』への応用に発展している
→ ユングは神話とつなぎ、アドラーは人間関係に応用し、東洋でも釈迦は八正道で社会実践に落としてる。
悩み(苦悩)を起点にしている
→ 老子も釈迦も、ソクラテスも、フロイトも、みんな『どう生きれば?』という問いから始まってる。
『自分の内面』と向き合っている
→ 手法は違えど、思考・感情・欲望との対話を経て、個人の軸を見つけようとしてる。
| 視点 | 東洋 | 西洋 |
|---|---|---|
| 出発点 | 『いかに在るか(存在・体験)』 | 『いかに知るか(認識・理論)』 |
| 対象 | 個人の“在り方”や体験から出発 | 普遍的な“理論”や真理から出発 |
| スタイル | 実践・体験→教え 『謎?別に解かなくていいよ』 『それより、今、自然の流れに沿ってる?』 『言葉にした瞬間、ズレるよね』 | 思考・抽象→体系化 『この裏に何かあるでしょ?』 『構造はどうなってるの?』 『体系化して伝えたい』 |
東洋のズレは、『本当はすごく深くて複雑な体験があったのに、それを言葉にしようとすると、どうしても単純化されてしまう』というところにあります。
本来は、もっと多面的に、いろいろな“在り方”として見られるものなのに、言葉で枠をつけた瞬間に固定されてしまう。
だからこそ、東洋思想では言葉を慎み、感覚や沈黙を重んじる。



でも、それを支える“教え”がなかったら?そのズレは、単なる誤作動になるでしょう?
教えがない × ズレがある → 『お前がおかしい(性悪説)』
教えがある × ズレがある → 『本来から逸れてるだけ(性善説)』
ズレを優しく受け止めるには、『全体性を信じる教え』が必要だと思う。
わたしがブログに書き残していることは、西洋的な行為です。
『問いを言葉にし、構造を見つけて、体系化して伝える』──それは、読者にとっての“方位磁針”にはなるけれど、それが唯一の正解とは思っていません。



むしろ、その方位磁針を持って、自分の地図をちゃんと歩けるようになってほしいと思っています。東洋を否定してるわけじゃないですよ。言葉にせず、感覚だけで渡っていけるほど、今の世の中は甘くない。だから私は、東洋の感覚と、西洋のフレーム──どちらも統合した『歩き方の設計図』を書いているんです。
東洋も西洋も、目的地は似てる、そして後半で交差している。
東洋も西洋も、目的地は似ている
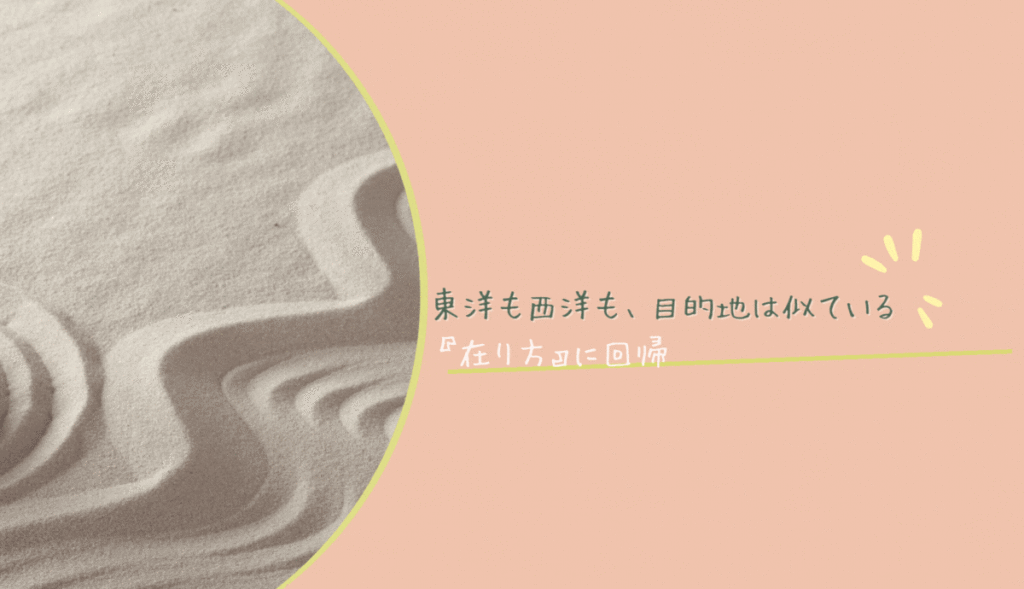
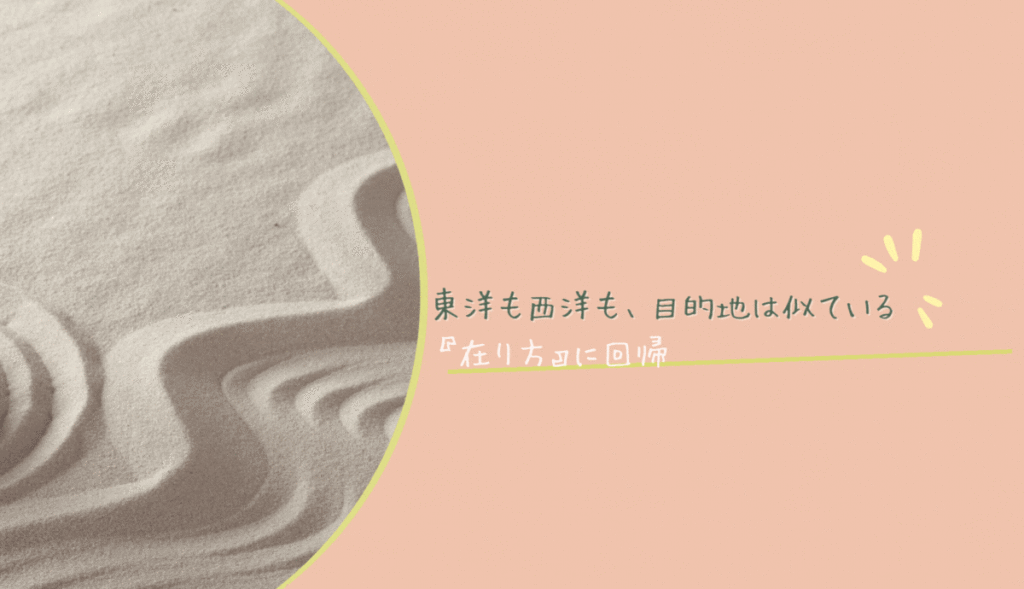
| 要素 | 東洋 | 西洋 |
|---|---|---|
| 目的地 | 『真理』ではなく、『調和した在り方』 | 『在り方』ではなく、『真理・合理性』 |
| 結果として得るもの | 生きやすさ・悟り | 説明力・理解・技術発展 |
| 終着点 | 無(空・タオ)とつながる | 統一的な原理とつながる |



表を見る限り、後期の西洋哲学者・心理学者(ニーチェ・ユング・フロイト・アドラー・マズローあたり)は明らかに『在り方』に回帰してきていると思える。
『今ここに立ち返る』
→ アドラー『とりあえず“今”に集中しようぜ』
→ パールズ(ゲシュタルト)『何を感じてる?その感覚は今どこにある?それを言葉にしてみて』
『未完成を受け入れる』
→ ユング『あなたの中には、まだ出番待ちの人格が何人もいます。控室パンパンです。そろそろシャドウ出しときます?あっちのが楽でしょ、正直。』
→ ニーチェ『同じ人生を何度でも繰り返せって?いいよ、今度はもっと笑ってやる。』
『他人を責めず、自分を整える』
→ アドラー『その悩み、実は他人の課題です』
→ マズロー『まず寝て、食って、そこから自己実現しましょう』
『心の深層と向き合う』
→ フロイト『で、結局それってお母さんの影響じゃない?』
→ ユング『夢?無意識?それ、全部“あなた”のことですよ?』
そして──後期の西洋思想が示している“もうひとつの回帰”
特に、19世紀後半から20世紀にかけて登場した西洋の思想家たちは、それまでの『知とは何か』『真理とは何か』という理論中心の哲学から、『どう生きるか』『どう在るか』へと問いを移していったようにも思えます。
例えば
- ニーチェは、あらゆる価値が崩壊する時代において『自らの価値を創造すること(超人思想)』を説く
- フロイトは、『人間は理性の存在ではない』として、抑圧された感情や無意識の動きを可視化
- ユングは、『個性化』というキーワードで、魂の統合・自己実現の過程を重視
- アドラーは、『目的論』によって過去を手放し、『今ここ』の在り方を肯定
彼らの理論・思想は、どれも最終的に『どう生きるか、どう自分を受け止めるか』という問いに帰着します。



こまでで息切れしてませんか?もう少し付き合ってください。次は、ヒルとニーチェの意外な共通点、行ってみます。
例えば、ニーチェとナポレオン・ヒルで見ると
| 観点 | ニーチェ | ナポレオン・ヒル |
|---|---|---|
| 出発点 | 無価値感・絶望・喪失 | 貧困・劣等感・不安 |
| 世界観 | 価値の崩壊・神は死んだ | チャンスは無限にある |
| 問い | 『この人生に意味はあるのか?』 | 『成功は誰にでも可能か?』 |
| 転換点 | 永劫回帰・運命愛 | 思考は現実化する・信念の力 |
| メッセージ | 自ら価値を創造しろ | 自ら信念を選び取り、実現せよ |
| 本質 | 意味を外に求めず、自分が与える | 成功を外に期待せず、内から引き寄せる |
成功哲学の文脈でも、たとえばナポレオン・ヒルの『思考は現実化する』は、『現実に意味を与える力は自分にある』という強烈なメッセージ。
それは、ニーチェの『永劫回帰』とも通じる思想。
『絶望的な現実であっても、どうせなら自分で“選び取れ”』
『何度でも繰り返すこの瞬間を、自らの意思で肯定せよ』
つまり、ヒルもニーチェも──立場や文脈は違えど、“人生の意味は、他者や運命から与えられるものではなく、自分の視点と解釈によって創られる”というメッセージを残しているとも取れますよね。
そこに仏教の『空』が入る。
結局のところ、私たちが見ている世界──誰かの態度とか、起きた出来事とか、それはすべて“認知”というフィルターを通して見えてる。
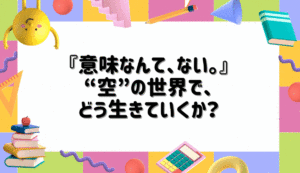
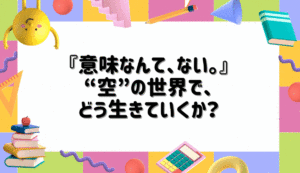
だから、『事実』より『どう捉えたか』のほうが、その人の現実になっていく。
“空”の視点で『どの認知にも絶対的な正しさはない』ってことが見えてくると、意味は無数にあって、選ぶのは自分。
重要なのは、『それでも私はこう意味づけて生きたい』と選べる力。
つまり、『意味がない』と知ったうえで、『それでもなお、自分の意志で意味を与える』。
加えて、マズローもまた重要な存在です。彼は『人はなぜ満たされないのか?』という問いから出発し、欲求5段階説を通じて、最終的に自己実現や自己超越という“本当の自分”として社会とつながる“在り方”の次元に到達しました。晩年には、『人はもっと大きなものとつながることで、人生に深い意味を見出す』と考えるようになっていた。
彼が晩年に語った“自己超越”という概念は、仏教や道教が説く“自己の解体と宇宙との一体感”にどこか似ているようにも思える。
ただの欲求5段階説ではなく、彼もまた“在り方”を中心とする流れに合流していたとも考えられるので、西洋思想は“知る”ことから始まるけれど、結局は、“生きる”ことへと降りてきたのかもしれない。
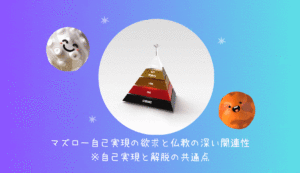
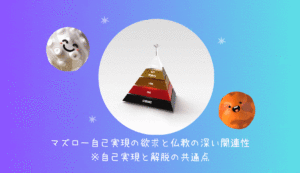
東洋の在り方と、西洋のフレーム枠
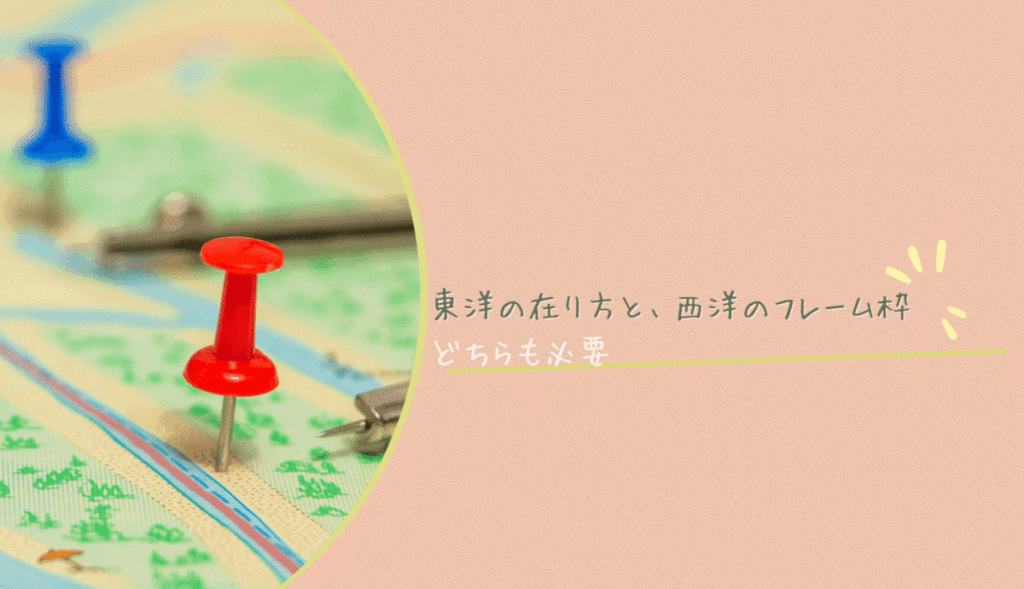
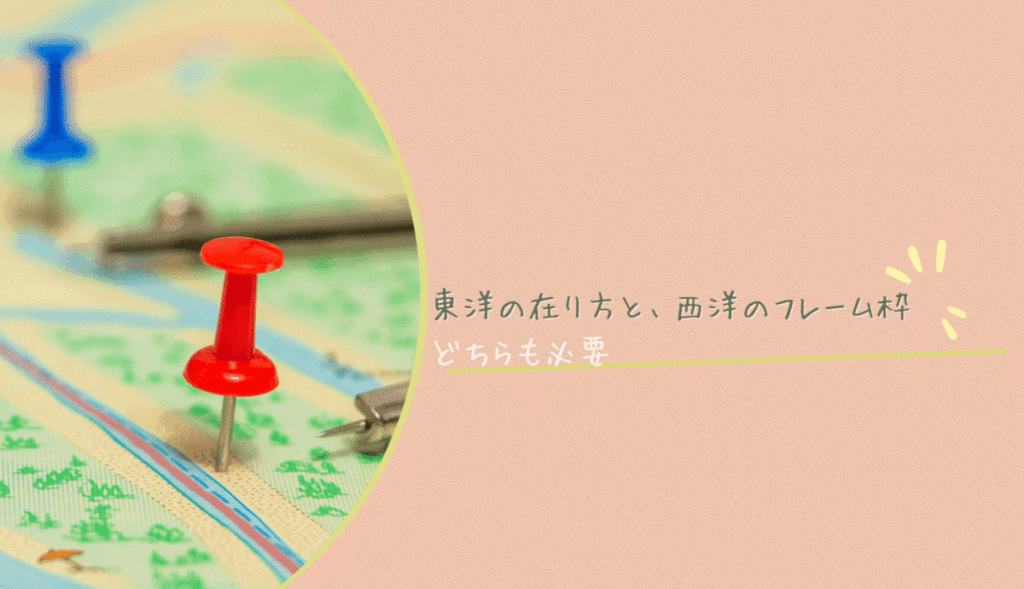
東洋では、こうした『在り方』が昔からまとまった形で教えられてきてたんですよね(現在は途切れてるけど)。



たとえば、儒教を説いた孔子のように、『人はどう生きるべきか?』という問いが、早い段階から社会規範として組み込まれていたイメージです。
ただし、東洋思想は『どう生きるべきか』と言っても、その答えはあくまで『在り方』ベースであり、個人によっても多様で曖昧なところがあります。それが逆に、『私はどう在るべきか?』という問いで迷いやすくなることもある。
だからこそ、抽象的な『在り方』だけでなく、『どう考えるか』『どう捉えるか』という西洋的な『フレーム』視点が加わると、自分なりの在り方に構造や言語が与えられ、輪郭がはっきりしてくるじゃないですか。
そういう意味で、東洋・西洋の融合はとても大事だと感じてます。



西洋は、ひとつの“真理”に向かおうとする中で、それぞれの偉人が人生で悩み、葛藤しながら、まるでバトンリレーのように手探りで気づきを積み重ねていった──そんなふうに見える。ある人は哲学という形で、またある人は心理学という形で。形は違っても、悩みや問いの本質は受け継がれている。時代を超えて、名前を変えて、でも確実に『問い』はつながっているように思えるんです。だから、全部繋がって行く。
『悩み』はどこから来て、どこへ向かうのか?──東洋と西洋の見立ての違い
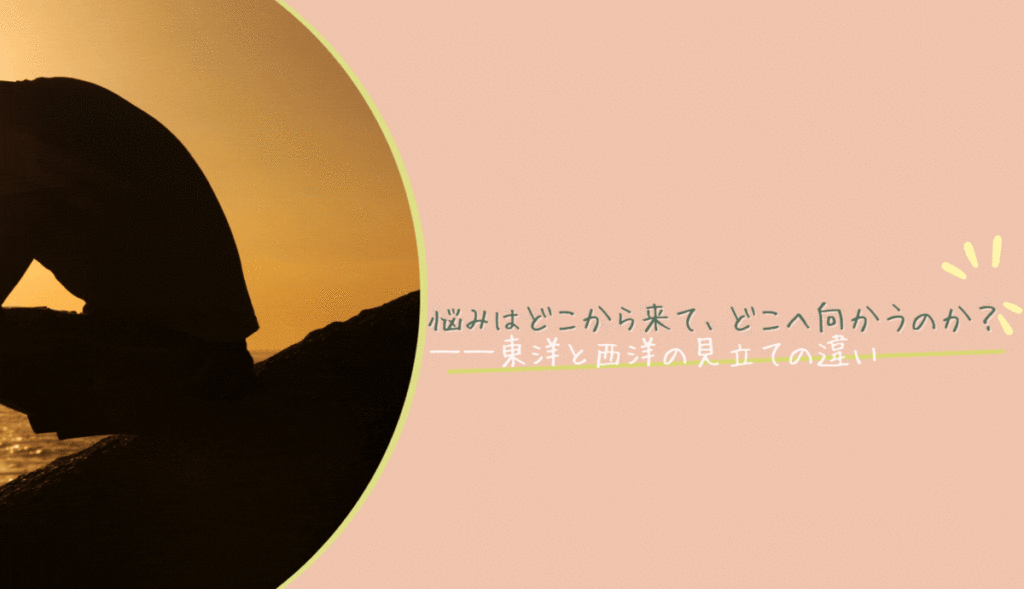
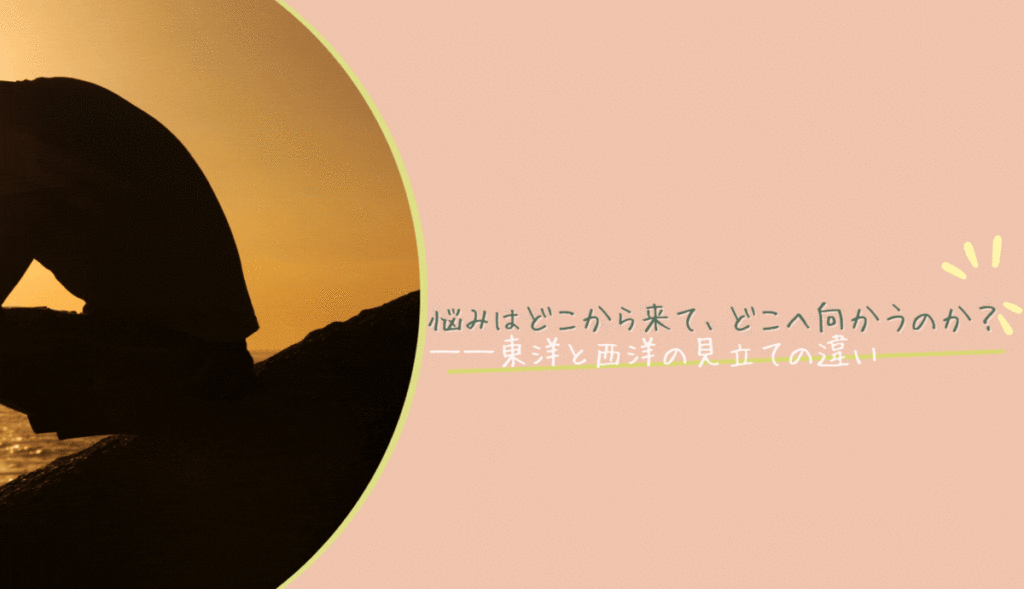
まるで、東洋は地図の中に実際に立って歩いている人で、西洋はその地図を俯瞰して見ながら、『どう全体を捉えるか』を考えているような違いがある。
もちろん、東洋のその“地図”は詳細な道路や交差点が書き込まれたナビのようなものではなく、あくまで『方向性』や『空気感』を示すようなもの。だからこそ、見る人によって解釈も変わるし、迷いも生まれやすい地図でもあるんです。



↓この水色の部分は何だろう????川?道路?波長?通れる?通れるんなら、通ろうかなー。
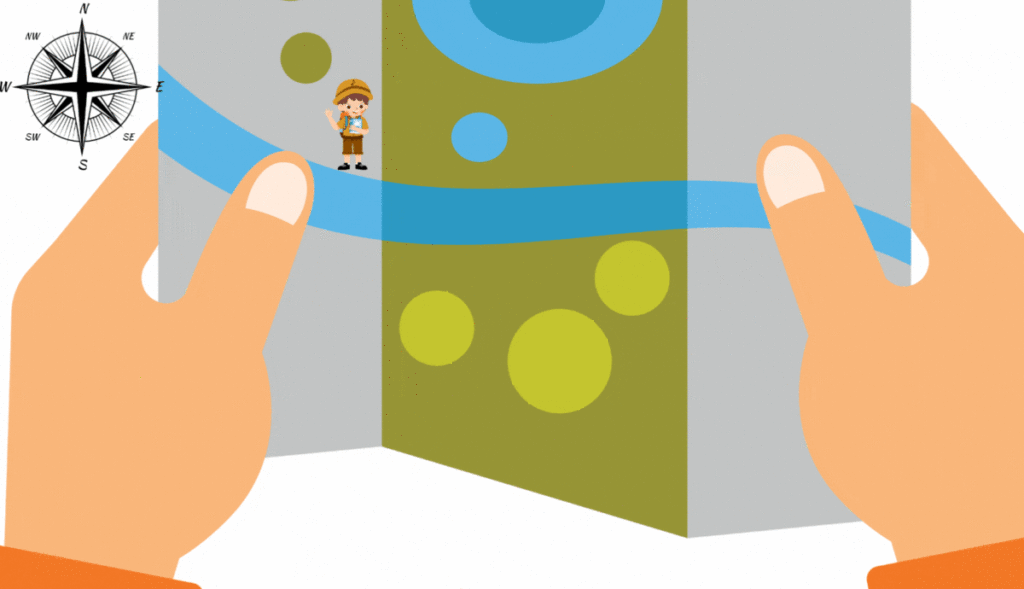
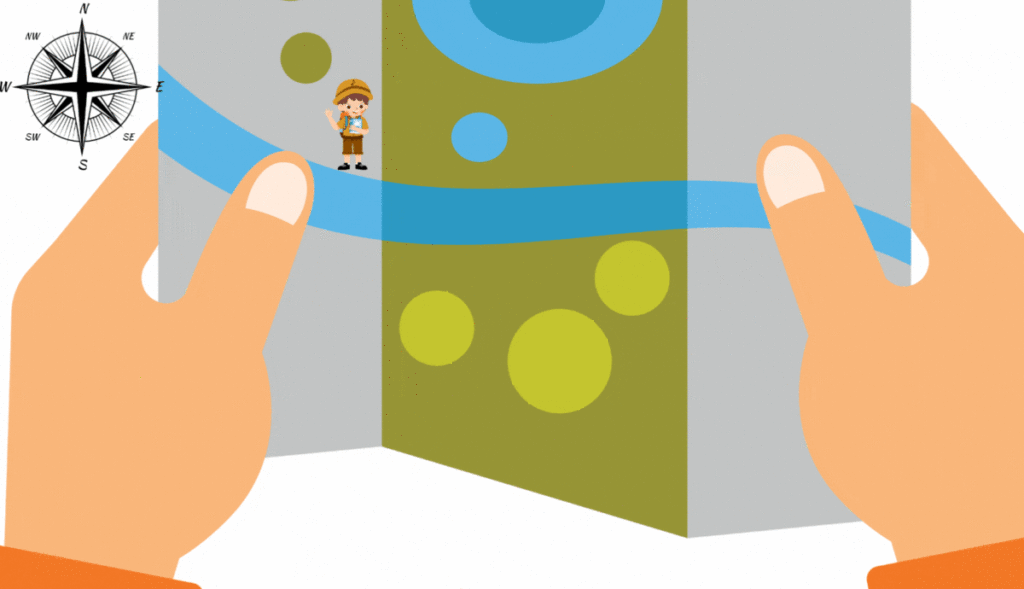
まず、どこに向かいたいの?



例えば、頭にビルが浮かんだからビルを描き、木も描く。最後には、突然キッチン。世界観はバラバラだけど、本人には“描いたつもり”になっている。でも傍から見たら、『で、何の絵?』ってなる──そんな状態です。
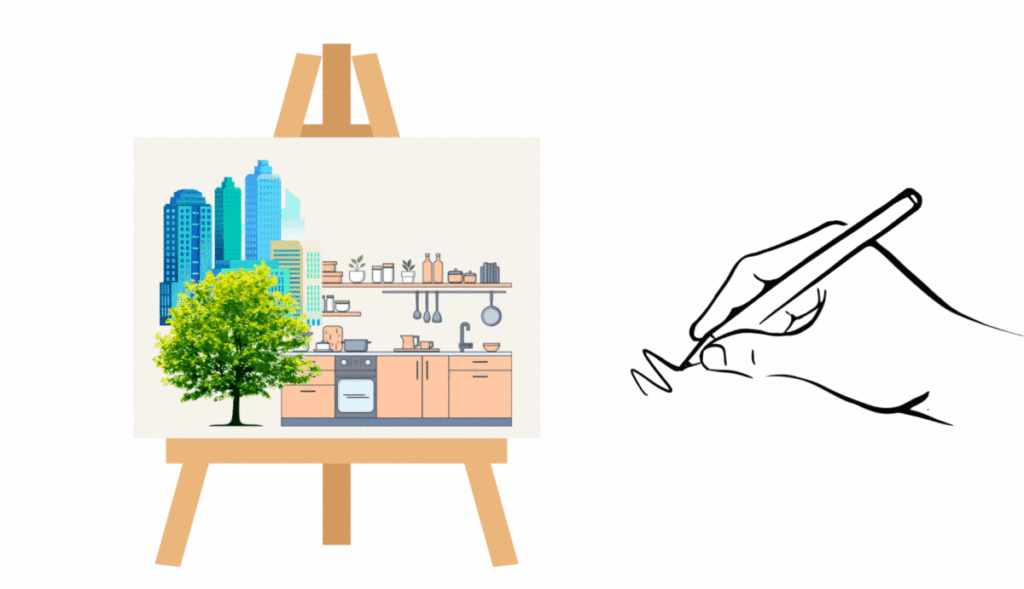
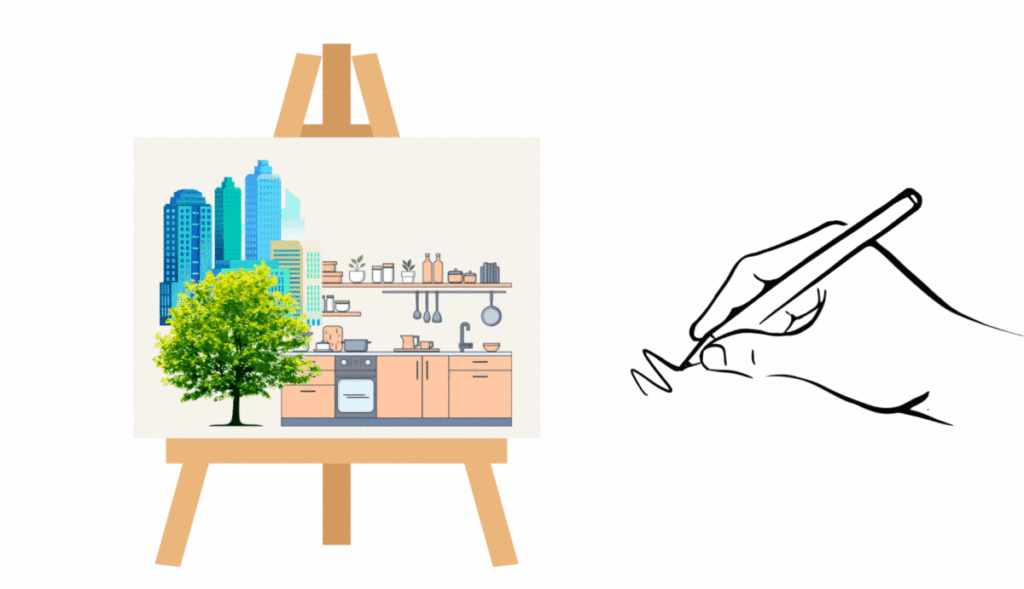
『何を描きたいか』だけを追っていくと、思いついたまま気分で手を動かすだけになるから、まとまりがなくなる。これが人生だとすると、ただ生きた。悩みはたくさんある。そうなりません?だって、描いてるものが、何の絵なのか、自分でも今イチよく分かってないんだから。
だけど、ビルを描くこともキッチンを描くことも、間違いではないじゃないですか。だけど、人生に意味を持たせるなら、ある程度の指針、フレームは必要。
つまり、『描きたいこと(東洋思想(直感・感覚・在り方))』と『どう描くか(西洋思想(構造・論理・技術))』って、どっちもいるんですよね。
つまり、
- 描きたいものがないと無味乾燥。
- でも描き方が分からないと混沌カオス。
- 両方そろって、ようやく“伝わる自己表現”や“納得できる人生”になる。
自分はビルの絵を描き、そこのビルの下には木がいくつもある。そんな風景。という指針。
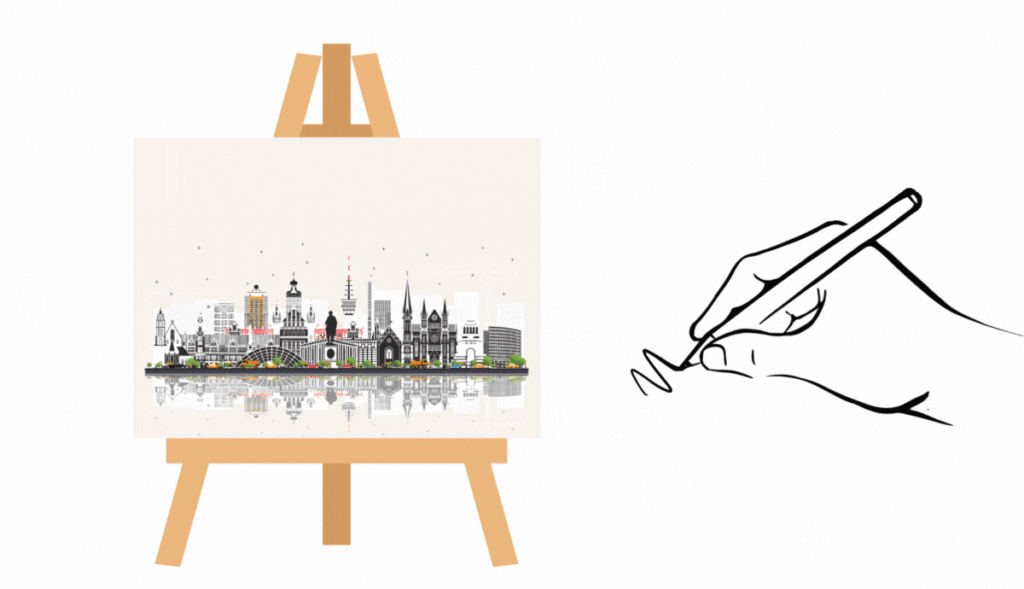
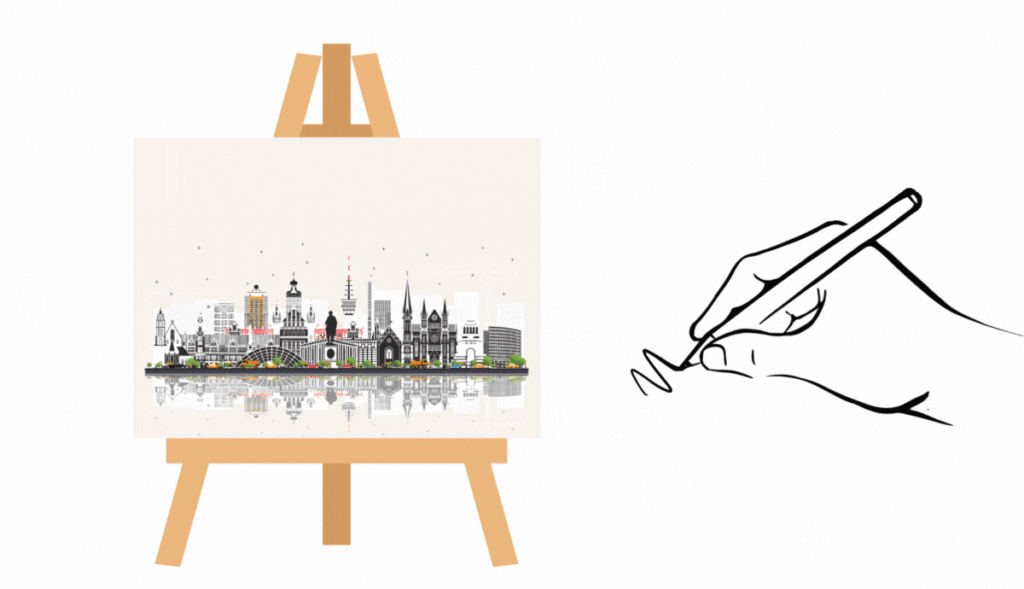
という持論で、わたし自身が書くことを通じて辿ってきたプロセスそのもので、ようやくたどり着いた道でもある。
東洋思想と西洋思想の教え方の違い
東洋思想は、個人の悩みというよりも、『時代』や『自然』との関係の中で生まれた“在り方の洞察”。ただし、そこには『個人の悩み』がまったく含まれていないわけではなく、むしろ“個人の悩みを、宇宙や秩序のズレとして捉える”という独特の見方がある。
例えば、仏教(釈迦)の場合
- 『苦しみ(苦)』は、無常な世界に執着することで起きる
- 解決は、『執着を手放し、世界の“空”という構造を理解すること』
→ つまり、『あなたが苦しんでるのは、“世界の成り立ち”を誤解してるからだよ』と言っている
例えば、道教(老子)の場合
- 『無為自然』= 宇宙の“道(タオ)”に沿って生きることが調和
- 苦しみは、『人間のつくった規範や欲望』によって“道”から外れてしまった状態
→ 『あなたが苦しいのは、自然の流れに逆らってるからだよ』
逆に、西洋の代表的な例を挙げてみると──
例えば、フロイトの場合
- 『苦しみ』は、抑圧された無意識の欲望や記憶によって生じる。
- 解決は、『無意識の内容を言語化し、自我がそれを認識・統合すること』
→ つまり、『あなたが苦しんでるのは、自分の中の“欲望や記憶”を見て見ぬふりしてるからだよ』と言っている。
例えば、アドラーの場合
- 『苦しみ』は、過去の出来事ではなく、現在の目的(生き方)とのズレから生じる。
- 解決は、『自分の目的に気づき、“今ここ”の在り方を選びなおすこと』
→ 『あなたが苦しいのは、“ほんとはどう生きたいか”に気づいてないからだよ』と言っている。
東洋思想では、『私は苦しい』という感情も、単なる心の問題ではなく、“世界の秩序や宇宙とのズレ”として読み解く視点がある。
例えば、



もっと頑張らなきゃ…
って思って苦しくなるときって、大体、誰も見てないのに100m走を全力で走らされてる感じなんです。スタートの合図もゴールもないのに、なぜか勝手に笛が鳴ってる。それ、“自然の流れ”じゃなくて、“自己プレッシャー劇場”。
誰も求めていないのに、本人が『走らねば』と思い込み、どこに向かってるのかも分からないまま苦しんでる図。
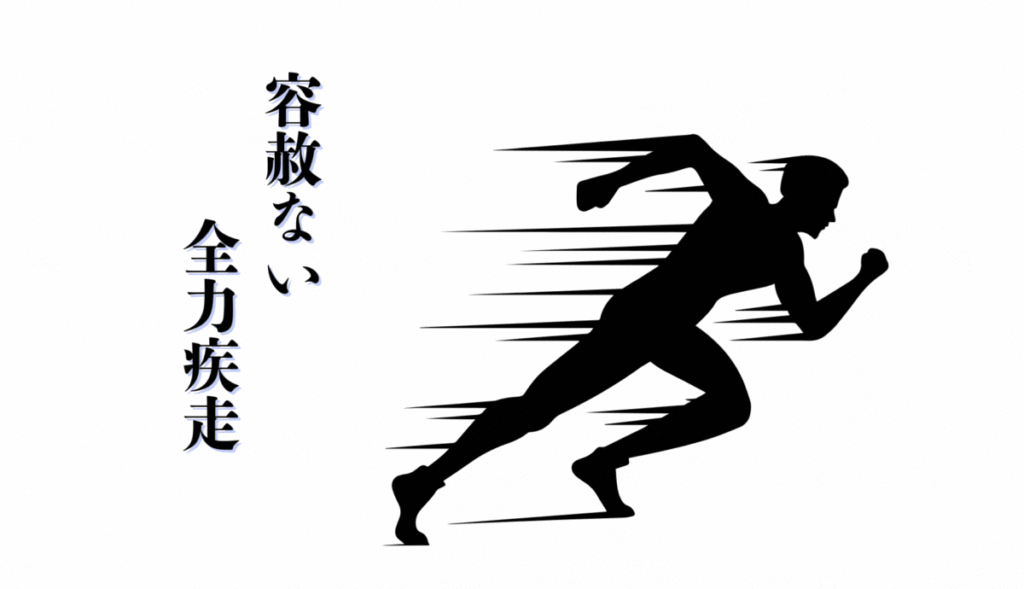
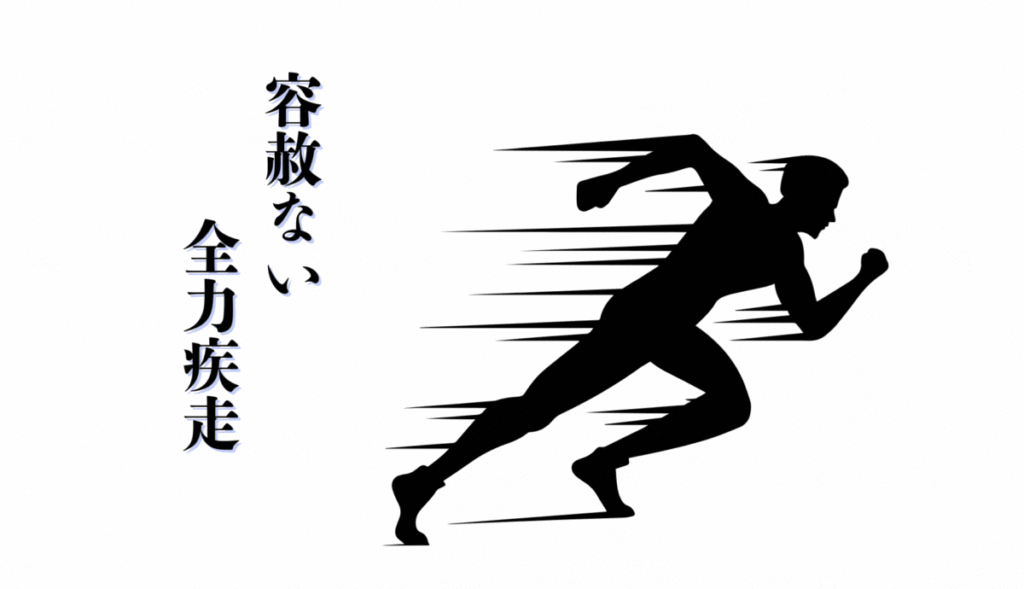



ちゃんとしなきゃ。
って焦ってるとき、“何をちゃんとしたいのか、どうちゃんとしたいのか?”は謎のままのことがある。目的も分からず、ただ『ちゃんとしろ』って言われて育った脳が、勝手に非常ベル鳴らしてるだけ。



『走らないといけない』という前提を手放し、『自分を見つめる』。
分かります?わたしは分からない。言葉が曖昧すぎるでしょ。
これが東洋。解釈は様々。
そして西洋思想は、その“自己プレッシャー劇場”を見逃さずに、その空回りっぷりすら、『じゃあどうしたらいい?』とマジメに構造化してくれるタイプ。
例えば、西洋って、



ちゃんとしなきゃ。
って軽く言っただけの話を、



要するにこういう状態?
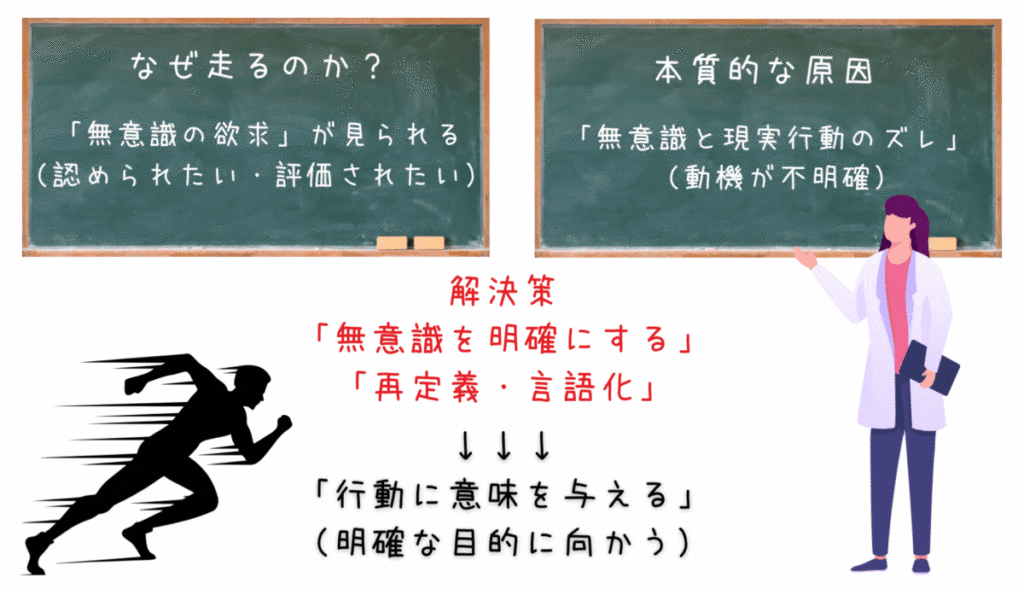
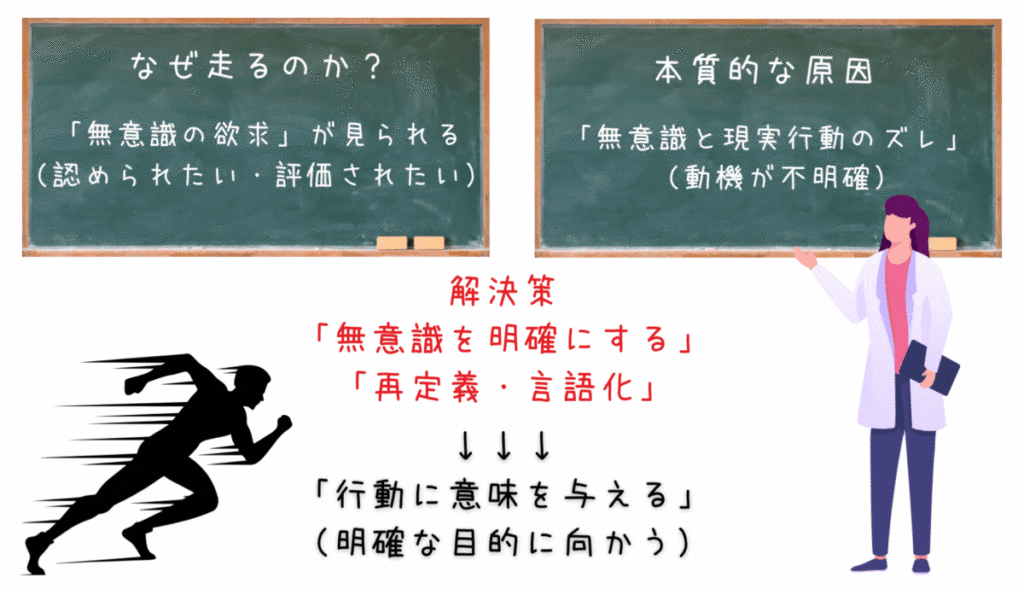
と翌日ガチの図解にして持ってくる友だち、みたいなところがある。空回ってる気持ちすら、『それ構造的にどうなってる?』って真面目に解析しようとする。
もしくは、ちゃんと照明を当てて、カメラを回して、



はい、ここが原因ね。
と分析しはじめる。無意識のドタバタも、全部セリフ付きの脚本にしてくれるんです。
東洋と西洋は、出発点も、アプローチも、言語化のスタイルも違う。けれど、深いところでは“人間の悩み”という同じ泉から水を汲んでる。


まとめ
東洋は『世界って、だいたいこんな感じだよ』ってふわっと教えてくれて、西洋は『じゃあ、私はこう生きてみる!』ってガッツリ選ばせてくれる。
どっちか片方だけだと、実はちょっと物足りない。
例えるなら、空にいっぱい浮かんでる風船がいろんな生き方や価値観だとして、その中からひとつだけを選んで自分の手でつかむような感じ。



まぁ、どの風船でも別にいいよね~
ってぼんやりしてると、いつまでたっても自分の居場所が見つからない。それがブレない軸になるのに。
だからこそ、



私はこの風船に決めた!
って、自分の手で選び取ることが大事。それは、ただ風に流されてフワフワしてるんじゃなくて、



私はここにいる!
って自分自身で目印を立てるようなもの。
哲学や心理学は、遠い世界の知識じゃなくて、違和感から始まって、問いを持ち、書いて、探して、気づいて、また問い直す。



多分、問いを持つって、私たちが『ちゃんと生きようとしてる証』なんだと思います。悩んで、立ち止まって、自分に聞き返す。そういう姿勢そのものが、人生に意味をつくっていくんだと思う。
では、あなたは今日、どんな問いを持っていますか?その問いこそが、あなたの人生の軸をつくっていくかも。横を向いたら、ソクラテスがいる──
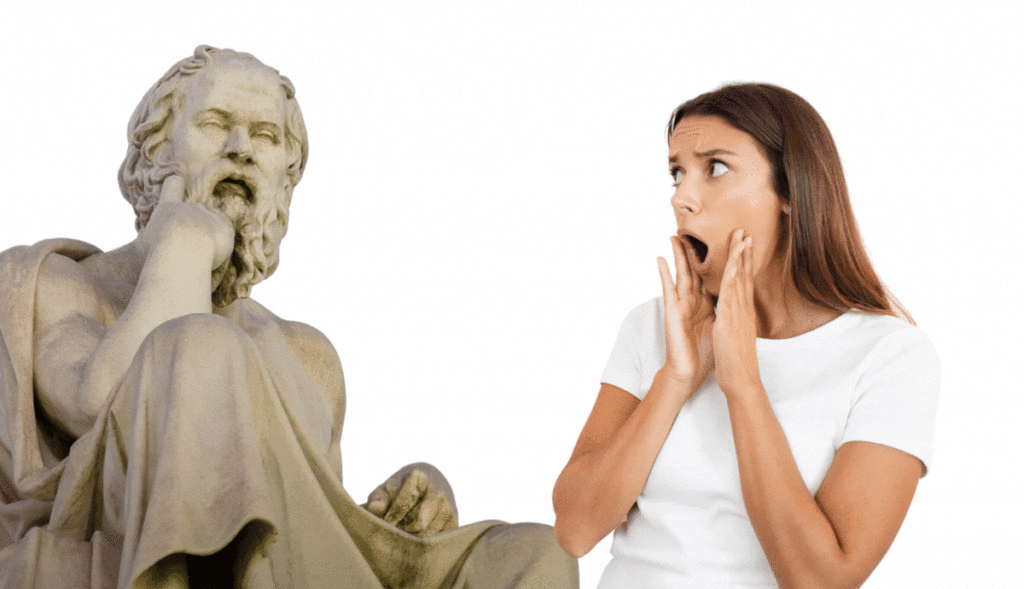
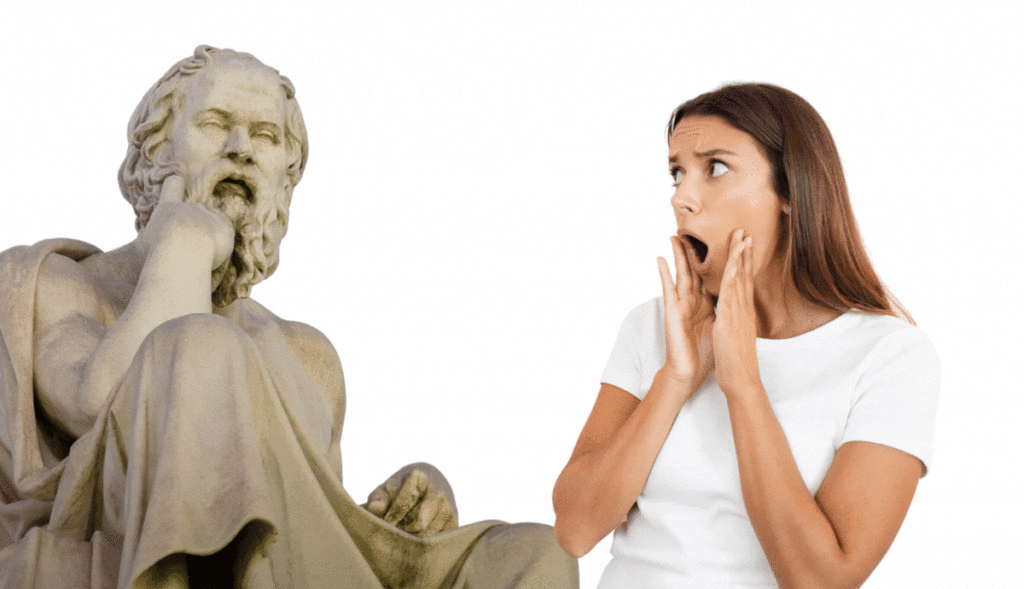
かもしれません。
グダグダと論じてしまったのですが、東洋思想は『自然と調和せよ』と言うけれど、その“自然”って、山や川のことじゃなくて──『自分との調和』のことでもありますよね。
でも、それが何とズレているのか、なぜ苦しいのかを理解するには、東洋だけでは感覚的すぎて見えない部分がありすぎるでしょ。
だからこそ、西洋哲学が『構造』や『言語』で補ってくれる。
- 『自分って何?』(デカルト)
- 『自由って何?』(カント)
- 『意味って何?』(ニーチェ)
- 『無意識って何者?』(フロイト・ユング)
- 『他人との違いって、なんでこんなにしんどいの?』(アドラー)
- 『この人生、意味あるの?』(フランクル)
- 『あなたの“今ここ”って誰が演じてるの?実は親の価値観や過去の傷つきパターンを“自動再生”してるだけかもよ?』(パールズ)
こうして問いを重ねることで、東洋の『なんとなく……分かる』を、西洋が『分かってきた気がする』に変えてくれる。
つまりこうです。
で、結局たどり着くのが…
だからこそ現代は、どっちかじゃなく“どっちも”が必要な時代。問いながら整えて、整えながら問い続ける。



それが多分、現代を『生きるってこと』なんじゃないかとも思う。
こう考えると、生きづらさもなくなりません?
ぼんやりして、悩んでたのが、ちょっと霧が晴れた感じたするといいなと、願います。
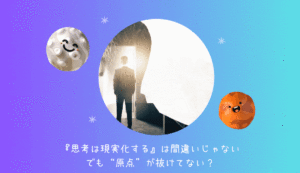
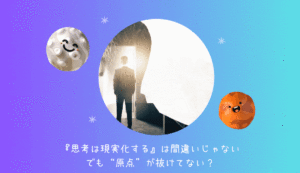
この記事に含まれる要素
1. 感情の直視・受容と統合
- 記事中で『なぜ悩むのか』『思考のくせ』を掘る、感情の扱い方(見つめる → 理解する)を考える。
→ ロジャース的自己一致・ユング的統合プロセス
2. 認知の癖に気づく(認知的不協和・スキーマ)
- “悩みの意味とは?”という問いかけから、自分が抱えている物語(スキーマ)を俯瞰する。
→ フェスティンガー(認知的不協和)・ヤング(スキーマ療法)
3. 再構築・ナラティブ
- 『何のために悩んでいるのか』を問い直し、意味づけし直す。
→ ナラティブ・セラピー
4. 境界・課題の分離
- “他者の悩みに巻き込まれず、自分の役割・境界を意識する。
→ アドラー心理学(課題の分離)
5. マインドフルネス・仏教的観察
- 感情を評価せずに“在るままに見つめる
→ 仏教 / ACT
6. 自己選択・価値に沿った行動
- “悩みを理由に行動しない”ではなく、『意味づけし直す → 次どうしたい?』という価値に基づく問いに繋がっている。
→ ACT(Committed Action) / SDT



コメント