ずいぶんの記事で、おばけの授業と揶揄してしまったので、こちらも作ってみました。
【目的】命についてすぐに『ありがたい』と感じられないとしても、自分なりに『命がありがたいって何だろう?』と考え続けようとすること自体が、命と誠実に向き合おうとする姿勢。命がご先祖様から受け継がれていることを知ることを出発点に、感謝の気持ちがすぐに生まれなくてもよいことを認め、自分自身が命とどう向き合っていくのかを考え、将来『ありがとう』と思えるような生き方を探っていく態度を育てる。
【対象学年】小学3年生
【背景に入れたい要素】
- 『ご先祖様がいたから今がある』ことは認めつつ、それを“感謝の強要”にしない
- 『感謝できない・ピンとこない』子どもも含めて、内面の自由を保障する
- 命について“わかったフリ”ではなく、“考え続ける”授業にする
- 『感謝できるような人生を考える』という未来志向をもつ
- 『ご先祖様の数に感動させる』演出を中心にしない
- 『感謝できないかもしれない自分』への認知を含む発問設計
『ヌチヌグスージ』(命の祭り)
沖縄にきたばかりのコウちゃんは、島のオバアにたずねました。
『みんなで何しているの?』
『わたしたちに命をくれた、大事なご先祖様のお墓参りさぁ。』
島では春になると、親戚中が集まって、ご先祖様に『ありがとう』を伝えるのです。『ぼうやに命をくれた人はだれねぇ?』
『お父さんとお母さん』
『命をくれた人をご先祖様と言うんだよ。お父さんとお母さんに命をくれた人もご先祖様。』ぼくは、おじいちゃん・おばあちゃん、ひいじいちゃん・ひいばあちゃん….ご先祖様を数えてみると・・・もう数え切れなかった。
『ぼくのご先祖様って千人ぐらい? 百万人ぐらい?』
『命は続いてきたからねえ。誰が欠けてもぼうやは生まれてこなかった。ぼうやの命は、ご先祖様の命でもあるわけさあね。』ぼくは空に向かって、ご先祖様に届くように言った。
『命をありがとう!』
発問リスト
| 領域 | 狙い |
|---|---|
| 命と感情のズレ | 感じなきゃいけない空気からの自由 |
| 違和感・わからなさ | わからなくていいという承認 |
| 関係・出会い | 命=つながりという視点 |
| 生きづらさ | 否定的感情を排除しない構造 |
| 気づき・未来 | 考え続けることを価値に |
命と感情のズレを開く問い
- 『命ってありがたいって、すぐに思える人って、いる?』
- 『“ありがたい”って、ほんとうに思えるときって、どんなときだろう?』
- 『ありがとうって言いたくないときって、ある?それってどんなとき?』
違和感・ぼんやり・わからなさを許す問い
- 『正直、ご先祖様って言われても、ピンとこなかった人、いるかな?』
- 『命ってなんだろう?って聞かれても、よくわからないって感じることない?』
- 『命について考えるって、どんな気持ちになる? 不思議? 難しい? 面倒?』
命と関係・出会いをつなぐ問い
- 『最近、だれかと出会って、なんかうれしかったことある?』
- 『このクラスに来てなかったら、話してなかった人っている?』
- 『この人と会えてよかったなって思ったとき、どんなことがあった?』
- 『たとえば、○○さんと出会って、こんなことあったな、って思い出すと、それって、生まれてきてなかったらなかったことだよね──そう思ったら、どう感じる?』
生きづらさ・否定的な気持ちに光をあてる問い
- 『生まれてきてよかった、って思えないときもあると思う。先生もね、“こんな気持ちになるくらいなら、生まれてこなきゃよかったな”って思ったことあるよ。そんなときって、どんな気持ちなんだろうね──』
- 『親に『ありがとう』って思えないときって、ある?それってダメなことかな?』
未来や『気づき』につなげる問い
- 『命を大事にするって、どんなこと、どういう意味だと思う?』
特徴
- どこから扱っても、授業が成立
- 子どもの感情や思考の位置によって、教員がどの問いを使うか選べる
- 『全員で答える問い』としても、『個別ワーク』や『対話カード』としても使える
対話カード例(命の授業版)
- 対話カードがあることで、発話量が増えるだけでなく、関係性の中で“命を考える”授業になる。
- 『答えを出す授業』じゃなく、『考えをもっていることが価値』になる
- 教員が『問いを一斉に投げる』必要がなくなり、子どもが問いを選ぶ
授業での使い方例
- 子どもに数枚のカードを配る(または机上に置く)
- ペアまたは小グループで『話したいカード』を1枚選ぶ
- 順番に話す・聞く(話さなくてもOK)
- 全体で『話してみて感じたこと』をシェア
| カードの表 | ねらい |
|---|---|
| 命ってありがたいって、ほんとうに思えるときってどんなとき? | 感情の揺れを共有 |
| “生まれてこなかったら…”って考えたこと、ある? | 存在の不思議を問う |
| 親に『ありがとう』って思えないときってある? | 否定的感情を解禁 |
| 最近、出会えてよかったなって思った人いる? | 出会いと命の接続 |
| “命を大事にする”って、どういうことだと思う? | 考えの深まり |
目的に合った予想反応の特徴
- 『ありがたい』『感謝』などの表面的・模範的な反応
- 『ピンとこない』『意味わからない』という違和感系
- 『でも、もしかして…』という揺れ始めの声
- 『行動に落とそうとする子』の声
- 『関係性』や『出会い』に反応する子
- 『本当の実感』をもとに語る子(少数派だけど大切)
1. 共感・感動系(模範的な声)
- 『ぼくの命って、ほんとにたくさんの人のおかげなんだと思った』
- 『ご先祖様にありがとうって言いたいと思った』
- 『命って、大事にしないといけないなって思った』
→ 一見“正解”っぽいが、『なぜそう思った?』『どんな風に大事にしようと思う?』と掘り返す余地が大事。
2. 違和感・距離感系(言いにくいけど本音)
- 『数が多すぎて、逆にあんまりよくわからなかった』
- 『ありがとうって言われても、なんかピンとこなかった』
- 『命って言われても、いつも考えてないから難しい』
→ 否定せず、『それでもいい』という受容がカギ。
3. 揺れはじめ系(考えようとしている)
- 『まだわかんないけど、ちょっと考えてみたくなった』
- 『“生まれてこなかったら”って聞いて、ちょっとだけゾワっとした』
- 『今はよくわからないけど、いつかわかるかもと思った』
→ 思考が動き始めた“途中の声”を大切に。
4. 行動に落とそうとする子
- 『今日から夜ふかししないようにしてみようと思った』
→ 命=身体を大切にするという具体的発想。身近で実践的。 - 『一生懸命勉強頑張って、自分のやりたい仕事につきたいと思った』
→ 命=未来につなげたい、自分の使命に出会いたいという志向。深い。 - 『友だちのことも大事にしたいって思った』
→ 命=他者との関係の中での価値。出会いの奇跡とつながる実感。
→ 現実と結びつけようとする姿勢。評価ではなく『どうやって?』と掘ると深化。
先生の問い返し例(さらに掘る視点)
- 『夜ふかししないって思ったの、どうしてそう思ったの?』
- 『たとえばどんなふうに勉強をがんばるの?』
- 『友だちを大事にしたいって、例えばどんな風に大事にできるかな?』
5. 出会いへの気づき系
- 『友だちと出会えたのが命のおかげって、ちょっとすごいと思った』
- 『生まれてきてなかったら、今ここでみんなと話してないんだよね』
- 『家族に出会えたことも、奇跡なんかなって思った』
→ 『命→関係→感情』への展開ができている。ここに先生の語りを重ねると深まる。
そうだね。生まれてこなかったら、大事なお友達にも出会えなかったし、みんなとお話したり、一緒にお勉強したりすることもできてない。家族に出会えたことも奇跡。ご先祖様ひとりひとりがつないだ命がみんなの命。生まれてきて身体があるから、手をつなぐこともできるし、おいしいものも食べることができる、みんなの大好きなマック食べられるし、コーラだって飲める。これ、全部奇跡なんだよ。
6. 生活のしんどさに触れる声(教員の受け止めが試される)
- 『ぼく、親にありがとうって思えない』
- 『自分の命、大切って思えないときがある』
- 『生まれてこなかった方がよかったかもって思ったことある』
→ こういう声が出たら、授業は“本物”です。 否定せず、『それでも、そういう意見が言えるってすごいことだよね』と返す。ここに先生の語りを重ねると深まる。
親にありがとうって、思えないこともあるよね。
怒られたとき、イライラすることもあるし、悲しい気持ちになることもある。
それって、悪いことじゃないのよ。
生きてたら、『あんな出会いなければよかった』って思うことだって、あるかもしれない。
そして、そういうときに『命ってありがたい』なんて言われても、正直言いたくないよね。
先生も言いたくないもの。
でも、それならそれでいいんだよ。
大事なのは、そういう気持ちを、そのまま持ってていいって思えること。
そして、いつかその先で、『あのときのあの出会いが、実は大事だったのかもしれない』って思える日がくるかもしれない。
そんなふうに、自分の命と人生を少しずつ、自分で選びなおしていけたらいいんだと思う。
どういうことかって言うと、嫌な出会いだと思っていたあの出来事も、生きていたら意味を持つことがあるってこと。
それが『気づき』とも言うんだよ。
大事な何かを知らせるためにあった出会いかもしれないし。
それはね、生きてないと分からないことなの。
だから、今わからなくても大丈夫。
そのままの気持ちを持ったままで、ちゃんと生きていれば、いつか、今はまだ気づいていない何かに気づく日が来るかもしれないから。
ワークシート項目
- 今日の話で、気になったこと・引っかかったことを書こう
- 『命ってありがたい』って、正直どう思った?
- 自分なりに、“命を大切にする”って何だと思った?
- 今はわからなくても大丈夫。『よくわからなかったこと』『考えてみたいこと』があれば書いてみよう
先生へ:生徒への促し
命って、ありがたいってすぐに感じられなくてもいいんだよ。
大事なのは、『命って、なんだろう?』って思ってみること。
それは、命とちゃんと向き合おうとする、あなたの姿そのものです。
これからも、そんなふうに『わからなさ』と一緒に歩けたらいい。
みんなが今日考えたように、ご先祖様の誰か一人でも欠けていたら、今の自分はいなかったかもしれない。
つまり、今ここに自分がいること自体が、たくさんの命がつながって生まれた“奇跡”みたいなことなんだよね。
でもね、それだけじゃない。
生まれていなければ、今出会っている友だちにも出会えていない。
出会えたから、ケンカも、笑ったことも、心が動いたことも起きた。
出会いがあるって、奇跡なんだよ。
そして、その奇跡は『命がある』っていうことから始まってる。
けれど、奇跡だとか言いたくない出会いもあるかもしれない。
そのことも命を大切に生きていたら、意味を持って教えてくれるのがまた出会いなの。
だから出会いは全部大事なの。
だから、命は、全部、奇跡なのかもしれないね。
だから今日の授業は、『命ってすごいよね』と思う時間じゃなくて、『命って、なんだろう?』って、これからも考えていたいって、そう思える時間だったらいいなと思います。
語りの工夫点
最後に『かもしれないね』と結ぶことで、子どもが考え続けられる余白を残す。
命 → 自分の存在 → 出会い → 経験 → 命の意味へと、命を『関係と時間の中で捉える』構造。
『ありがたさを感じなさい』じゃなく、“奇跡という問い”を手渡す転換です。
生徒の『わからなさ』を許す
子どもが『ピンとこない』と言った瞬間、“まだわかってない”とか“未熟だ”と見なされることがあります。
だから子どもは、ときに『正しい言葉』で“わかったフリ”をしてしまう。
でも実際には、『命が大切』とか『生まれてきてよかった』なんて、そんなに簡単にわかることじゃない。
命があることそのものよりも、命があったから出会えたこと、心が動いたこと──そんな“出来事”の中にこそ、命の意味が宿るのかもしれない。
『ピンとこない』『よくわからない』という感覚を、出発点として認める。感謝を強制するのではなく、“生きているってどういうことだろう”という問いをひらく。
そういう授業であれば、子どもは『わかることを言わなきゃ』ではなく、『考えてもいいんだ』『感じてなくても、それでいいんだ』と、思えるようになるかもしれない──
そんな期待を込めて、この教材をつくりました。
この授業では、子どもたちが『命ってなんだろう?』と自分の言葉で考えはじめることを大切にしています。だから、最後に『こう思えたらいいよね』『命ってやっぱりありがたいよね』と“まとめてしまう”必要はありません。子どもたちが『まだわからない』『モヤモヤしたままでもいい』と思えたら、それはもう十分に価値ある授業です。わかったフリをさせず、『わからなさ』と一緒にいられる空気を、ぜひ残してください。
例:ご先祖様がいたから、今のわたしがいるって、心から思える日が来たらいいなって、先生は思うよ。
でも、今すぐそう思えない人もいるかもしれないし、それも大切な気持ちだと思う。先生は、教員になるのが夢で、こうやって、みんなに出会うことができた。だから、ご先祖様がいたから今のわたしがいるって、少しだけど分かる気がするのよ。だけど、もっとそう思えるように、このクラスでみんなと一緒にがんばろうと思ってます。
この教材に内在する思想的フレーム
| 思想・理論 | 文化圏 | 教材での活用 | キーワード/ねらい |
|---|---|---|---|
| 無為自然(老荘思想) | 東洋 | 子どもの『ピンとこない』『わからない』感覚をそのまま肯定 | 感情を無理に方向づけず、『あるがまま』を尊重する |
| 縁起(仏教) | 東洋 | 『誰が欠けても今の自分はいない』など、命のつながりの実感 | 自己を“関係性”でとらえる視点 |
| アドラー心理学 | 西洋 | 感謝や理解を『させる』のではなく、子ども自身が選べるよう支える | 強制ではなく“選び取る力”を育てる |
| 現象学的アプローチ | 西洋 | 『ありがたさ』は概念として与えるのでなく、経験から感じる | 子ども自身が意味をつくる“体験ベースの理解” |
道徳補強教材について
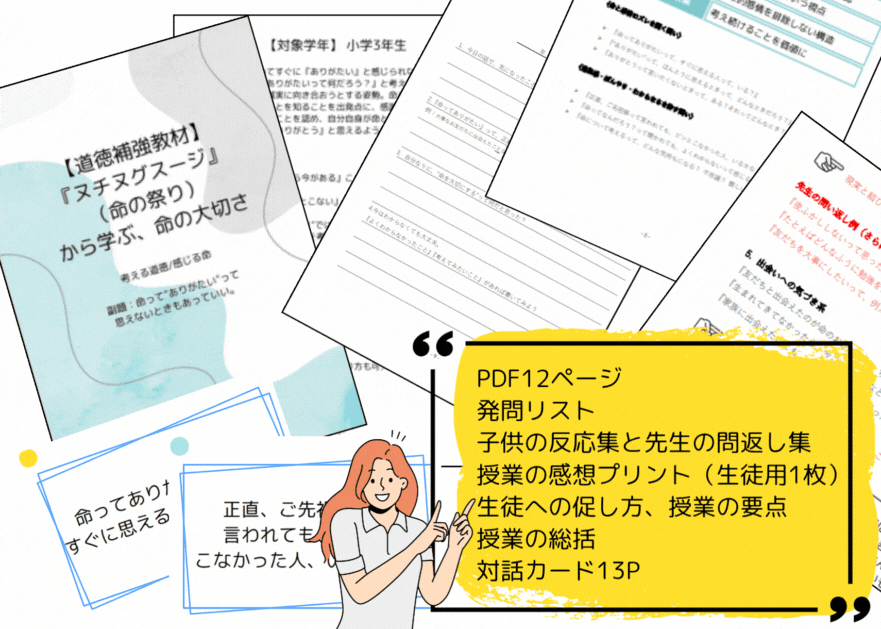

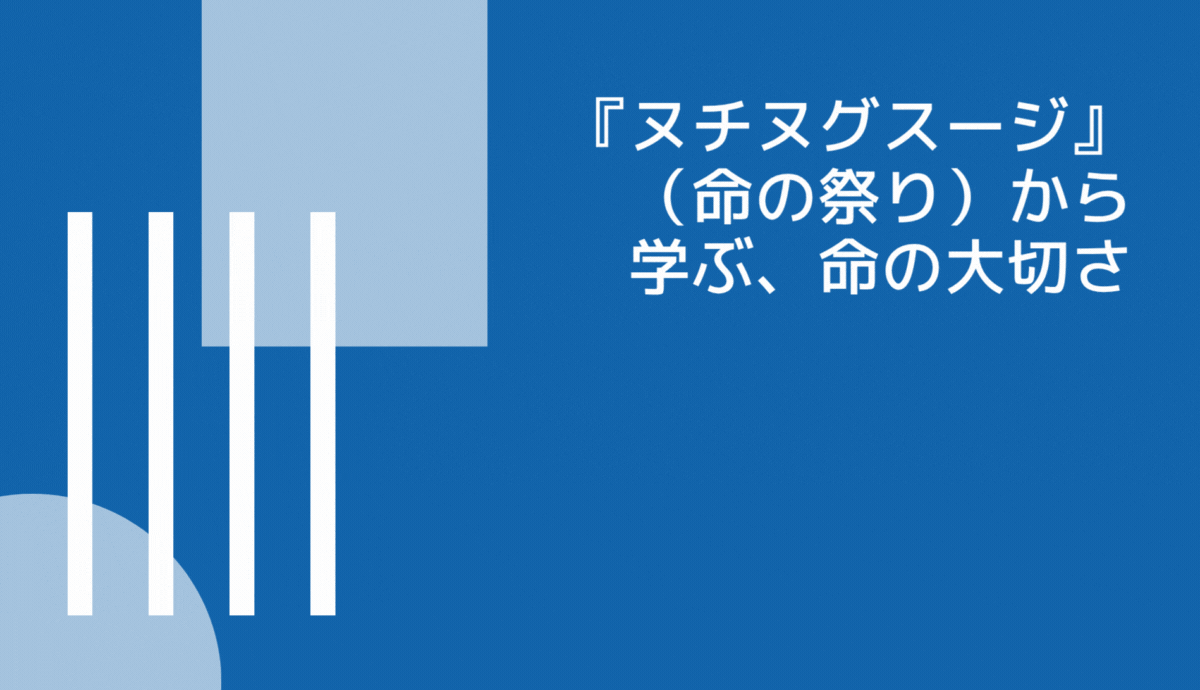
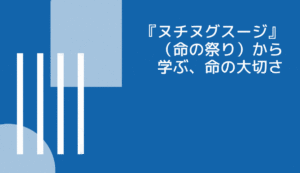
コメント