うちの10歳の女の子、ピアノの発表会前にこう伝えました。

ピアノ演奏の前のおじぎだけは、気を付けてね。ゆっくり丁寧にするんだよ。
そして、演奏後にこう言ってきました。



間違えずに弾けた!ママ、どうだった!?
…そう言われて、母(わたし)は目が遠くなる、それ、目標?と思ってしまう。
いや、もっと言うと──それって、“成果の報告”なの? “自分の表現”なの?
私は言ってしまった。



お辞儀が適当だったよ。
でも、子どもはキョトン。
わたしの教育理念は、たったこれだけ。
- 自分の頭で考えろ。迎合するな。
- 努力なき成果を求めるな。誠実に向き合え。
- 愛とは支配でもご機嫌取りでもなく、真剣な対話だ。
- 他者の声ではなく、自分の価値基準で生きろ。
- “なりたい自分”を諦めるな。
…けど、この難しい言葉たちを咀嚼して伝えるのはとても難しい。
そのまま伝えるのはとても簡単なスパルタ教育。
子どもが、『間違えなかった自分』を誇らしげに語る。間違えなかったのは分かったけど、そもそもが、わたしがそこに“重さ”を置いていない。
なぜなら、間違えたかどうかは、日ごろの練習次第。練習さえしっかりできていれば、出来るところだから、自分で問えばよいところでしょう?
歯がゆい。
でも、これはきっと、思想が現場に根づくまでの『距離』なんだとも思う。伝え方が難しい。
成果主義の空気に対して、“ちゃんと考える”という教育をぶつけるには、時間がかかる。
だが、あきらめるわけにはいかない。
今日も、問いを投げる。



誰の目線で、自分を語ってるの!?そもそも、あなたはどうなりたいの!!
本気でぶつかってしまった。
私の内省──伝え方に問題があったのかもしれない
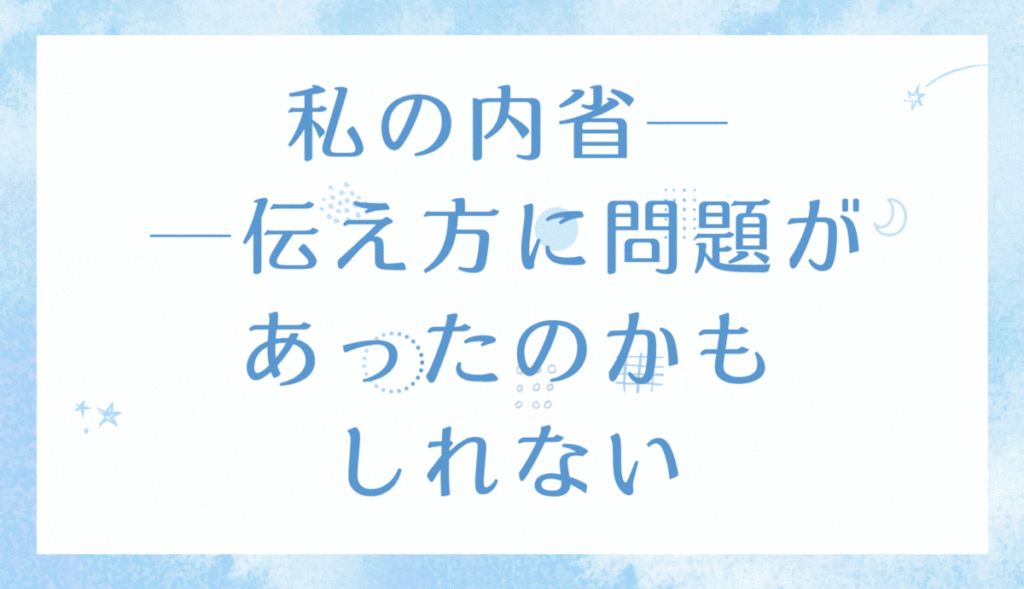
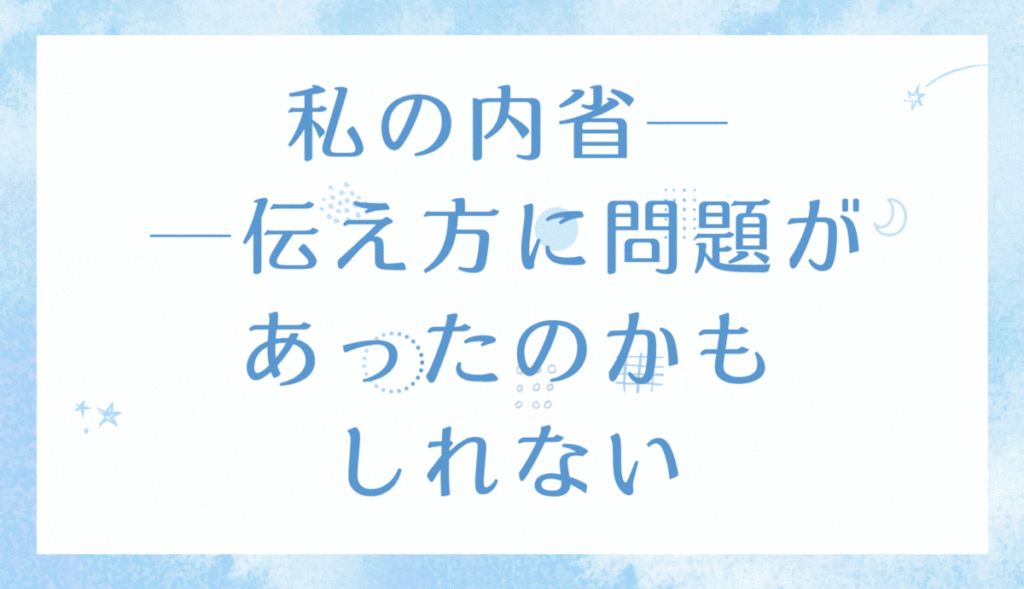
振り返ってみれば、私の伝え方は“理念の押し出し”に偏っていたかもしれない。
子どもにとっては、『また、ママが何か言ってる』という距離感だと思う。
それが歯がゆかった。



また何か言ってる。うるさい。
『なぜ挨拶が大事なのか』『どうして練習が必要なのか』それを、“子ども自身の文脈”で語っていなかったと思う。
──そんなふうに思い返すと、怒った自分の姿の奥に、伝えきれなかったもどかしさと、焦りがあったのだと気づく。
- 練習不足でも演奏を評価された構造
- お辞儀が『姿勢』そのものだと伝えたかった
- 『スルーされた思想』への焦りと怒り
① 練習不足でも演奏を評価された構造
私の子どもは、『間違えずに弾けた』ことを誇らしげに報告した。
しかし、私はそもそも練習する姿を、ほとんど見ていない。
もちろん、本人なりに時間を見つけてやっていたのかもしれない。けれど、それが『自信』や『準備』に結びついていたかは疑わしい。
なぜか?
『間違えずに弾けるかどうか?』という不安を口にしていたからだ。
本当に練習が足りていれば、結果がどうあれ、こう言えるはず。
わたしは一生懸命練習した。これで間違えたらそれはそれ。次にどうすればいいかを考えたらいい。
そうした姿勢が、自信を生む。結果への執着ではなく、過程への納得感が人を育てる。
だから私は、『当日の演奏』に重きを置かなかった。
そこに意味はないとは言わない。でも、『何を積み重ねたか』が見えなければ、それはただの偶然の産物になってしまう。



練習を重ねた先に、偶然の産物が確実なものになるんでしょう?その確実なものじゃなくて、確実なものを得るために努力した成果じゃなくて、その偶然の産物を褒めるの?意味が分からない。
他の保護者に下手だと思われようが、どうでもいい。
演奏は完璧だった。けれど、私はその自己評価に、どうしても空虚さを感じた。
努力なき成果が評価される構造──
それは、私がもっとも子どもに伝えたくなかった『成功の形』だった。



挨拶はどうなった?演奏の前にする挨拶。あれを丁寧にすることも、成功のひとつでしょう?あれが大事だと思ったから、発表会の前に伝えたのに、伝わらない。わたしの言葉が届かない!わたしの言葉が!
② お辞儀が『姿勢』そのものだと伝えたかった
だから私は、演奏の完成度ではなく、最初と最後の一礼にこだわった。
『今から人前に立つ覚悟』と『聴いてくれる人への敬意』もある。
一瞬の所作に、その人の“全て”が出る。
私は、娘にそのことを伝えたつもり。
『挨拶だけは丁寧に、ゆっくりしてね。』
日ごろからいつも伝えているから、これでできる。伝わってると思った。
だからこそ、適当なお辞儀を見た瞬間に、私は『何も届いていない』と感じてしまった。
そこに、演奏の出来とは別のレベルでの落胆があった。
③ 『スルーされた思想』への焦りと怒り



ママの言ってたことなんて、別にいいじゃん。
もし娘がそう思っていたとしたら、それはただの反抗じゃない。社会の“正解”に母親の“哲学”が負けた瞬間だったかもしれない。
それが、私には怖かった。そして、悔しかった。
『間違えずに弾けた!』
分かる。だけど、私がそこに“重さ”を置いていると思われるだけで、私は怒った。感情も混ざった。
そもそも音楽は表現するもの。間違えずに弾くことだけに、何の意味がある?プロでもあるまいし。
でもその怒りの核にあったのは、『このままでは、本当に“自分の人生”を歩けない人間になってしまう』という切実な焦り。
そして伝えた。
私は思想をもって教育している。
それをスルーされることは、単なる無視じゃない。『育てる』という行為全体を根本から揺さぶられることだったから。
どう伝え直すか──思想の“翻訳”という技術
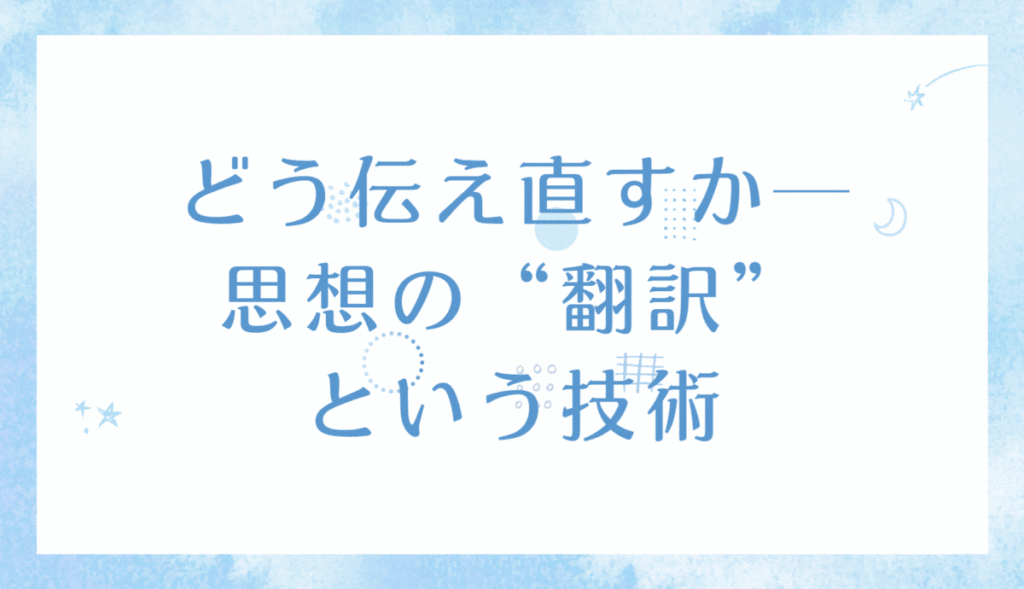
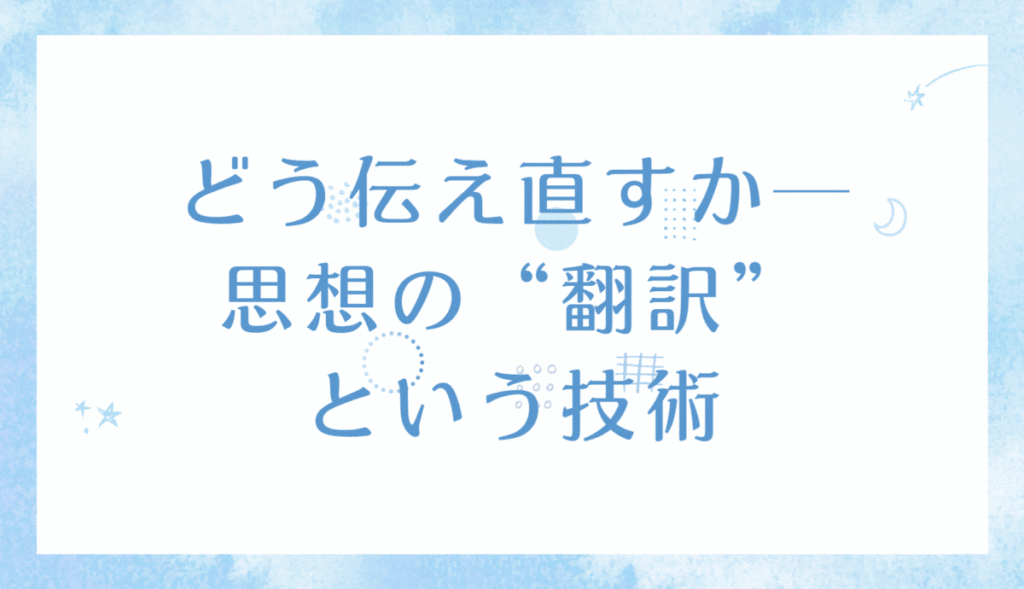
娘が私の言葉を受け取らなかったことを、単なる『理解力の未熟さ』として片づけたくはない。
同時に、私の言葉が強すぎたり、抽象的すぎたりした可能性の方が大きい。
伝わらなかった思想を、どのように“翻訳”すればよかったのか。
ここでは、その可能性を見てみようと思う。
- 怒りを価値の対話に変えるために
- 10歳に届く言葉にする工夫
- ママが育てたいのは、かっこよさの中身
① 怒りを価値の対話に変えるために
第一次感情、怒りの根っこには、たいてい第二次感情である悲しみや期待の裏切りがある。
私の場合、それは『どうして、そこを大切にしてくれなかったの?』という想いだった。
ただ怒るのではなく、
- 姿勢こそ大事、それが今回は挨拶
- もっと“自分の行動の意味”を考えなさい
──そういう価値に変換して伝えることが必要だった。
怒りは、価値の喪失に対する反応。
ならばその怒りを、『私は何を大切にしていたのか』に翻訳すれば、ただの感情ではなく、価値の対話に変わる。



ここに時間がかかるから、ややこしくなる。まだまだだ。
② 10歳に届く言葉にする工夫
10歳の子どもに、『自己価値』『社会構造』『成果主義』などの話は、まだ難しい。
だから私は、『挨拶とは何か』をこんなふうに言い換えられたら、良かったんだと思う。
これは、行動の意味と、子ども自身の内側をつなぐ説明。
子どもにとって、『なぜその行動が大事なのか』が感覚的にわかるように伝える必要がある。



わたしのレベルの低さよ…
とも思わされる。
③ ママが育てたいのは、かっこよさの中身
間違えずに弾けること自体は、もちろんすばらしいよ。
でも私は、『かっこよさ』をもっと深いところで見ている。
- 自分のやることに責任を持つ
- 相手に対して誠実である
- 姿勢や所作に気持ちを込める
こうしたものが、『本当のかっこよさ』だと思っている。
子どもにとっては、『かっこよさ=うまくやること』かもしれない。
でも私は、『かっこよさ=どういう態度で生きるか』だと信じているから。
それを伝えるには、“怒る”より“語る”姿勢が必要だったと思う。
思想を育てるには、時間と信念が必要だ
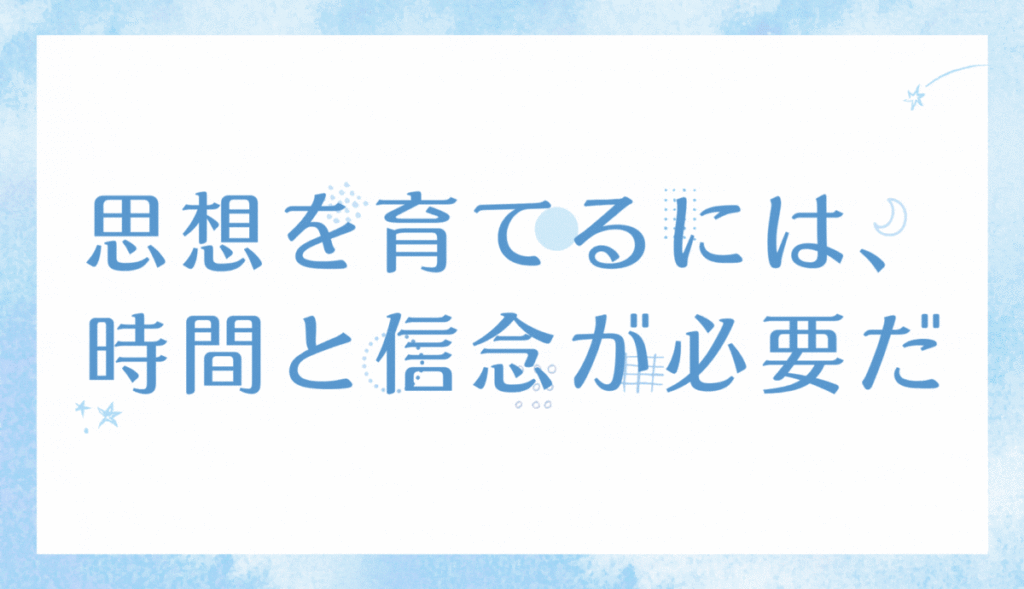
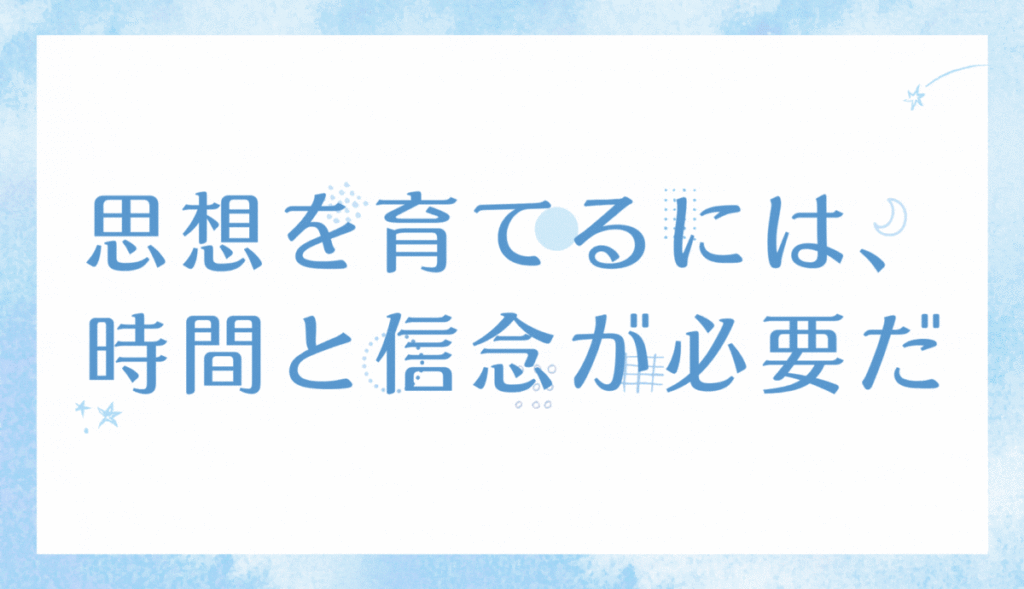
私の教育理念は、シンプルで明快。
そう、シンプルなんだって。
でも、それを10歳の子どもに伝えるのが、こんなにも難しいとは思わなかった。
伝えたつもりでも、届かない。
わかったようで、すぐに忘れられる。
でも、“育てる”という行為には、時間と信念が要る。
思想は、一度話せば伝わるものではない。
何度でも、繰り返し、形を変えて、相手の成長に合わせて語り直す必要がある。
それを毎日、実感させられる。



もう、諦めようか……
そう思う瞬間もある。心がすり減るくらいに。
けれど、諦めるわけにはいかない。
正しさと優しさの両立
私は、伝えたいことがある。
それは“厳しさ”にしか見えないこともあるかもしれない。
でも、私は子どもを責めたいんじゃない。
“自分で考え、自分で選べる”ようになるための土台を築いてほしいだけ。
だからこそ、『わたしが正しいと思うことを伝える』だけでは足りないと、わかっている。
正しさの先に、“どう受け取られるか”という優しさがなければ、思想は届かない。
わかっている。でも、やっぱり難しい。
どこまでが『正しさ』で、どこからが『押しつけ』なのか?わたしの世界はやっぱり厳しさになるのか?
けれど、わたしが生きてきた世界では、ある程度の羅針盤がないと、すぐに彷徨うことになる。だから私は、迷いながらもこう思う。



羅針盤は絶対に必要だ。
――これは、私の答え。
子どもの言動を『個性』と見るべきか、それともその裏にある“育たないままの部分”を見落としてしまわないか?
いつまで見守るか、それとも今こそ言うべきなのか?
教育とは、“正しさ”と“優しさ”を両立させながら、子どもを守ること。
でも、この『守る』ということが、ほんとうに難しい。
家庭という教育の場の重み
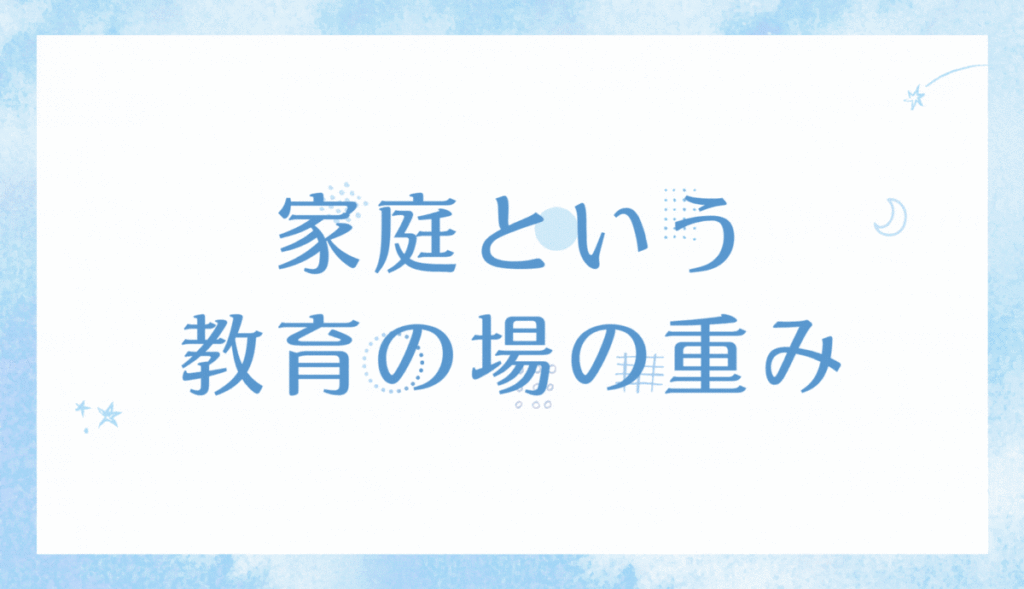
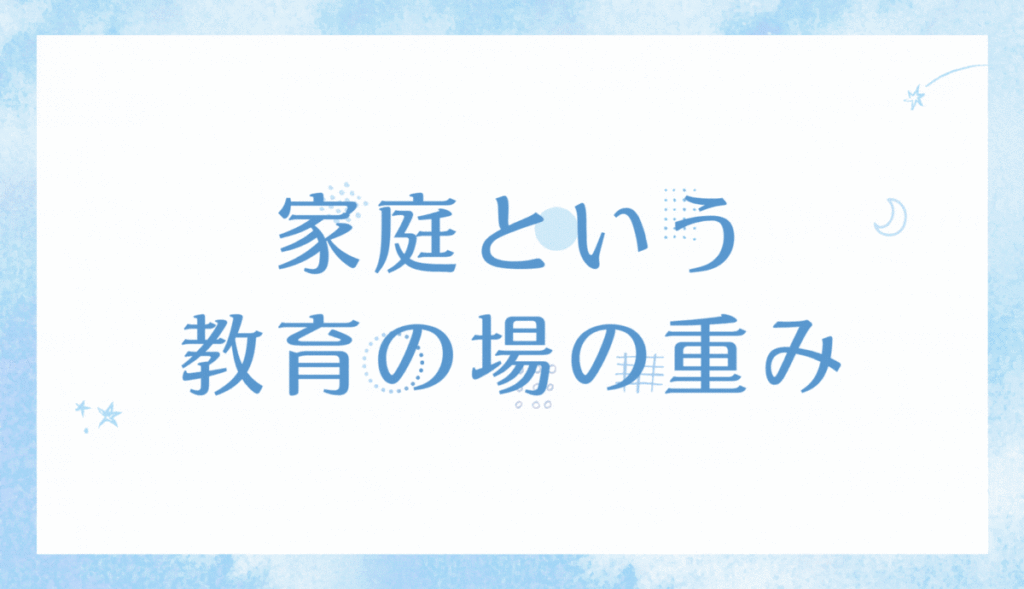
成果重視、効率と結果。
それも大事だと思うけど、『姿勢』『意味』『価値観』を育てたい。
家庭は一番自由な場所であると同時に、もっとも強く価値観が浸透する場でもある。
だから、私がここで妥協してしまえば、子どもは『正解に従う』ことを学び、『自分で考える力』を育てる機会を失う。



先生がこう言ってたから。
解せない。お前の考えはどこだ?ここをどうにかして、伝えていかないといけない。とても難しい。



わかった。でも、わたしは〇〇と思う。これだけは理解しておいてくれる?
こう伝えていたけれど、伝わらないから、今、こうなった。



わたしは母親だけど、今は母親として言ってない。教育者としてあなたに伝える。その意見を『ママがまたうるさい』この一言で逃すなっ。
どこで生きてるの!?
これは、感情の爆発ではなくて、“家庭で思想を育てる”ということが、社会と正面から向き合う覚悟だということを、私は本気で感じているから。



私は、親子という関係だけであなたと話しているんじゃないから。『人を育てる人』として、あなたと向き合ってるのよ。子どもとして話してない、ひとりの“人”として、あなたに語っている。だから、それを忘れないでくれる?
家庭で思想を育てるということは、単なるしつけやルールの話じゃない。
まだ、伝わったかどうか、分からない。きっとまた、同じことを言うことになると思う。
社会の空気に対して、自分の言葉で立てる人間を育てるという覚悟をしないといけない。
『翻訳しながら伝え続ける』という覚悟
もはや『一度言ったから伝わっているはず』というものは、幻想だ。
子どもは変化する。
日々の出来事、学校、友だち、経験……そのすべてが子どもを動かす。
だから、私の言葉もまた、“そのときのその子に届くかたち”で、何度でも何度でも言い直さなければならない。
これが、『思想を翻訳する』ということなんだろうな。
ただの優しさではない。思想をあきらめずに届け続ける、意志と技術の複合体。
これをやらないと。
怒りながらでも、歯がゆくても、『思想の火を消さないために』言い続けないと。そしてそれが、子どもの“重荷”じゃなくて、“軽さ”になるようにしないといけない。
まとめ
ピアノ発表会で、



間違えずに弾けたよ!
とドヤ顔の娘に、



そこ!?おじぎは!?
と言う、学びの足りないわたし。
そんなわたしは、演奏よりも“挨拶”に命をかけていたのです。『姿勢に人間性が出る』と本気で思ってるので。
けど伝え方も間違えば、伝え方も分かってない、伝わらない。
価値観は翻訳しないと届かない。怒りはしたけど、その根っこは“伝わらなかった寂しさ”と“育てることの難しさ”。
教育って、羅針盤を渡すこと。
でも子どもはコンパス無視で一直線に走るんだよな….
こっちは風上で『こっちが北だよー』と旗振る。わたしの場合、今回は、『そっち、北だって言ってるでしょ!!コンパス見なよ!!コンパスの説明してるのに!!説明できる私がいるのに!!何でコンパス見ないの!!』怒って振ってしまった。
理想は高い。反省も多い。
今のわたしのレベルを甘んじて受け入れる。子どもはたまったもんじゃないというのも分かる。
今回は、『上手に弾けること』この中に、問いがたくさんあった、これに気づけただけでもヨシとしたい。今のわたしのレベルだ。
でも『どうしても伝えたい』がある。子どもの“重荷”じゃなくて、“軽さ”になるようにしないと。
思考と感情を結びつけるのが難しい。読書は有効だと思うけど。興味の有無もある。
そんな“思想の火種”を絶やさぬよう、わたしは今日も翻訳に励む。
子どもとは仲直りしたんですよ。



ピアノの強弱はとても上手だったよ、ただ、わたしが伝えたかったこと分かる?



わかる。去年、わたしが弾いた曲があったの気づいた?



もちろん。『ジプシーキャンプ』と『オーラリー』でしょ。忘れるわけないじゃん。



忘れてるかと思った。



覚えてるよ、あなたの方が上手だった。
わたし、こういうのは率直に伝えるんですよ。
ママは本当に見てる。ちゃんと感じてるって子どもも分かるだろうから。『率直に、あの子の方が上手だったよ。』も普通に言う。だって、それが普通の感性でしょう?だからって、『あの子の方が上手だった』→『あなたは劣ってる』、じゃないんですよ。
- あの子みたいに上手になりたかったら、練習すればいいんじゃない?そしたら、できるようになるよ。
- あなたの方が練習たくさんがんばったんだろうね。



え!?他者と比較するの!?ってびっくりする人はびっくりするかもしれないから、一応言っときますね。
これは、親だから言える言葉だと思う。
いつもこんな感じです。『比べるな』ではなく、『どう比べるか』を問題にする。
他人と比べることは、『ありのまま』そのものでしょ。むしろ、『比べること自体を否定しようとする態度』のほうが、“感性を否定する不自然さ”をはらんでいくと思う。
- 他人との比較=人間の自然な認知
- 問題は『それを自他の価値の上下に使うかどうか』
- ありのままとは、『違いを違いとして認め、ジャッジせず、そこから考えること』
何でもかんでも、『あなたが一番よ。』じゃない。何が育つんだよ。
『あの子はできてるのに、あなたはできない。』も全然違う。
背景があれば、そこも見る、そのうえで自分の意見を素直に伝える。だからって、あなたがダメだと言ってるワケじゃない。あなたには、あなたの良さがある。それがわたしの教育方針。
これは、アドラーとか、カール・ロジャースに近い思想だと思う。
これが正解でしょ?って言ってるワケじゃないから。わたしの教育方針ってだけです。

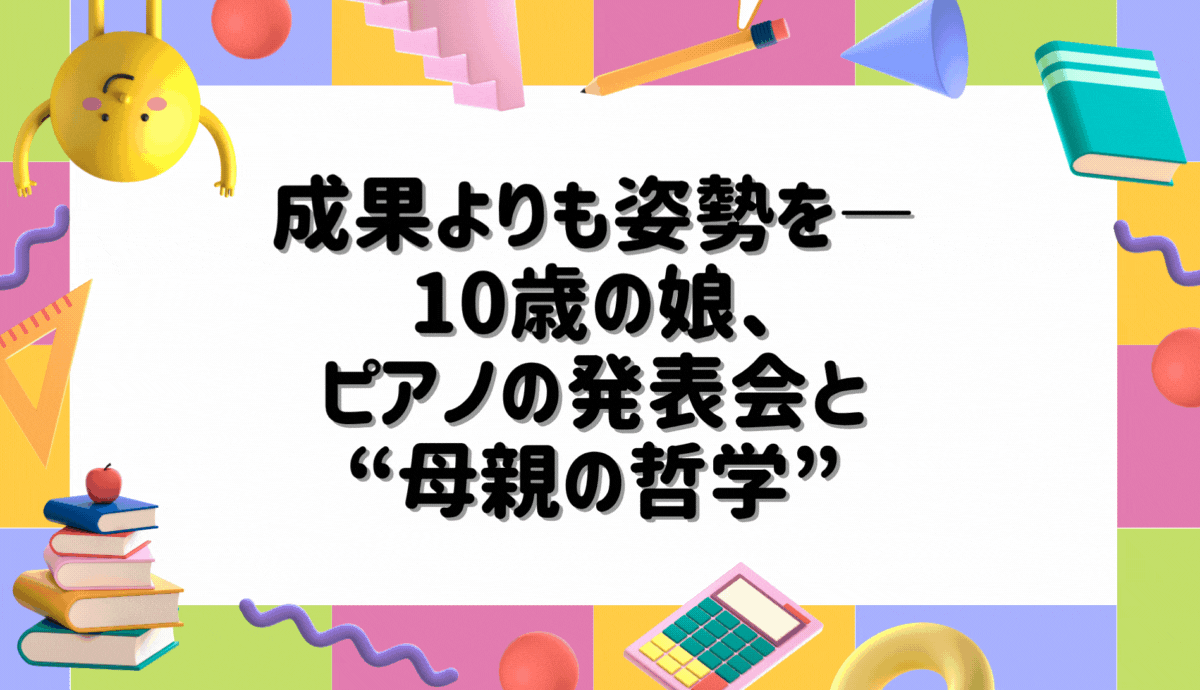
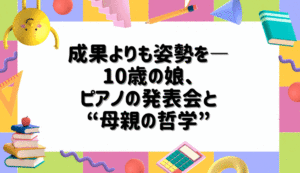
コメント