授業で、“答えを出さないことに意味がある”って言われること、あるじゃないですか。
個人個人の考えを大切に、正解はひとつじゃない、みたいな。
それは、分かる。
でも、それって──教え方によっては、“問いを持たない子ども”を育てる構造になってない?
…そう思ったのは、娘のひとことがきっかけでした。
夏休みに入って、子どもがわたしに問いかけてきました。

ママ、この『白いぼうし』読んでくれない?
それは国語の教科書。



ママが、内容分からないといけないから、A4の書き取り用紙と鉛筆置いて置くね。それで、この物語をどう思うか教えて欲しいんだけど。



めんどくせぇ….



わたしが、色々説明してあげるから、質問するから!読んで!
結果から言うと、読んで5分くらいで物語の内容は読解し、わたしの方から娘に、ちょうちょの飛び方想像したら大体分かるでしょう?って、そこからクドクド説明をしました。
紙も説明も不要になると….



つまんない!!ママ何で全部わかるの!!!!せっかく説明しようとしたのに!!!!説明したかったのに…
いや、だって分からない方がおかしくない?って思って、娘から色々お話を聞いたら、、こういう疑問が立ってきた。



え?何それ…..
“答えを出さない読解”って、本当はものすごく難しいこと。
- 問いの立つ構造があって
- 余白を受け止める力があって
- 読者の想像が作品に食い込んでいく
そういう読みじゃなきゃ成立しないですよね。
けど、問を立てる場所、そこじゃなくない?



シャボン玉の声は誰?
女の子は誰?
ここじゃなくない?
まぁ、そこの問いも大事だけどさ。
これは断定的なもので、ちゃんと“答えがある”話だし。
目的が、『答えが無いことが正解』だとしたら、それに沿うのなら、答えが無いことの正解を間違えたらいけないでしょう?
なのに、授業では『これは幻想かもね~』『においの魔法だね~』みたいな雰囲気で、“考えない方向”へ流れていってる。



で、ちょうちょは誰ってことになってんの?



うちのクラスではー、たけやまようちえん、たけのたけお!



『たけ』って言いたいだけだろ…
ナニコレ。ここは正解出さないといけないところで、問いを立てるところじゃないんだって。その教材をこんな使い方してるの?…..もう余計なことすんなよ….と思ってしまった。
曖昧にすべきじゃないところまで、あえて曖昧にする。
問いを立てるどころか、問いがぼけてるし、正解すら出てない。
だって、この物語は、答えを聞いて初めて、



あーーーーー!!面白い!!
不思議ーー!!
っていう面白さが分かる物語だもの。
現実から構造を読み取って、そこから想像を広げる。
そして、その答えから、松井さん側に立って、複数の見解を創造する授業じゃないといけないんじゃなくて?
前半はロジック、後半は想像力。
これがこの本の醍醐味じゃないのかなと思う。そこから、問を立てる面白さを学べない?
というわけで、本記事では、
- “答えを出さない授業”とは何か?
- それは本当に、子どもを“考える子”にしているのか?
- そして、“考えさせる教材”ってなんなの?
- つながりが破綻すると、思考も破綻する
その問いに、怒りと冷静さを行き来しながら、食らいついてみます。
白いぼうし※わたしはこう思う
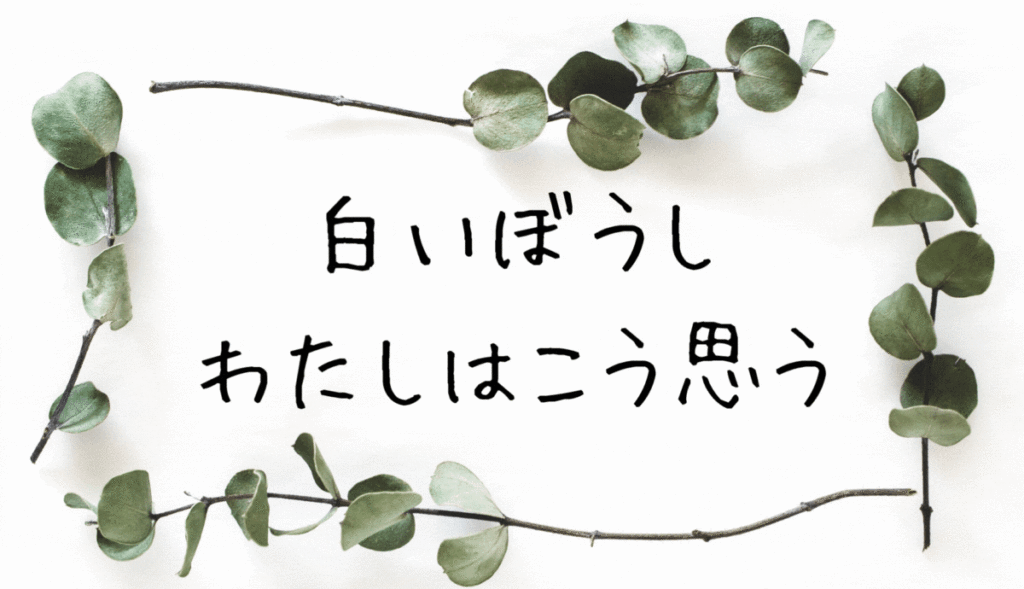
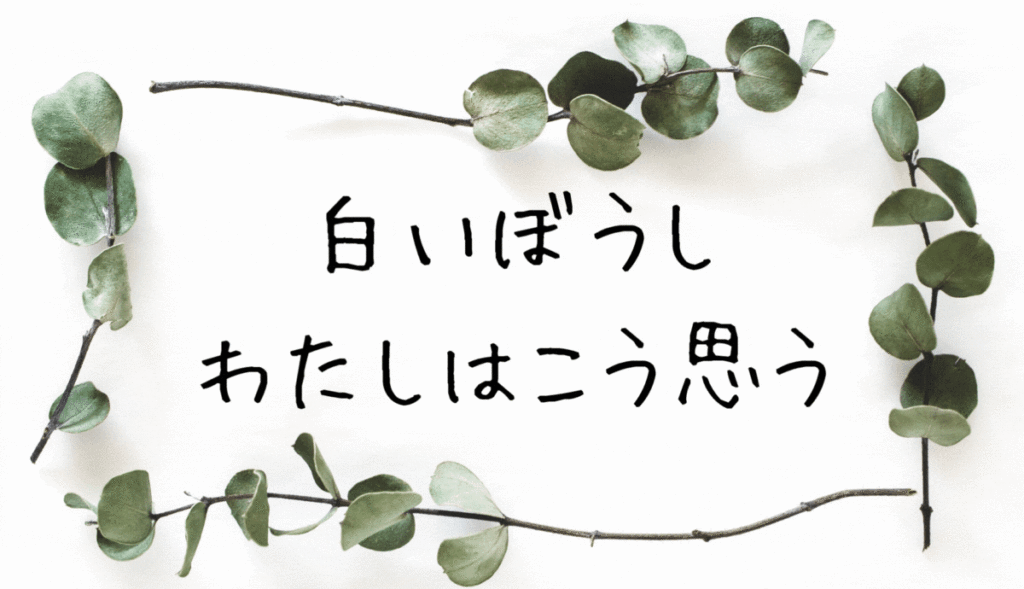
『白いぼうし』は、幻想っぽい空気感をまとってるけど、中身はめちゃくちゃストレート。
- 白いぼうしの中にちょうちょが閉じ込められてて
- 菜の花畑に帰れなくなって迷ってて
- ちょうちょが女の子に化けてタクシーに乗って
- 最後に逃げ出して本来の姿に戻る
パッと読んだだけだと、この流れの話ですよね。
そこに、タクシーの運転手である松井さんが関わってる。
答えのない答えが正解で、創造力を育てるのが目的にあるのだとしたら、問いを立てる場所はひとつ。
松井さんから見た世界。
これを、
- あの女の子は何?
- シャボン玉の声は誰?
という問いにしてしまったら、ただのオカルトで終わる可能性もある。
幽霊、幽霊が話した!こんなお粗末な授業があるだろうか。
そこには、明確な答えが存在するからだ。
答えが存在するにも関わらず、『たけやまようちえん、たけの たけお』で終わるこの内容のお粗末さときたら、絶句通り越して、怒りになる。それで本当にいいのか?問いを育てるどころか、問いを雑に扱った末の“誤解”が、教育現場でまかり通っている。
子どもの未来を何だと思ってるんだ。
子どもがこの物語をとおして見る世界、その貴重な入口が、あやふやな指導で閉じてる。
それを未来のためと言えるだろうか?
わたしの脳内
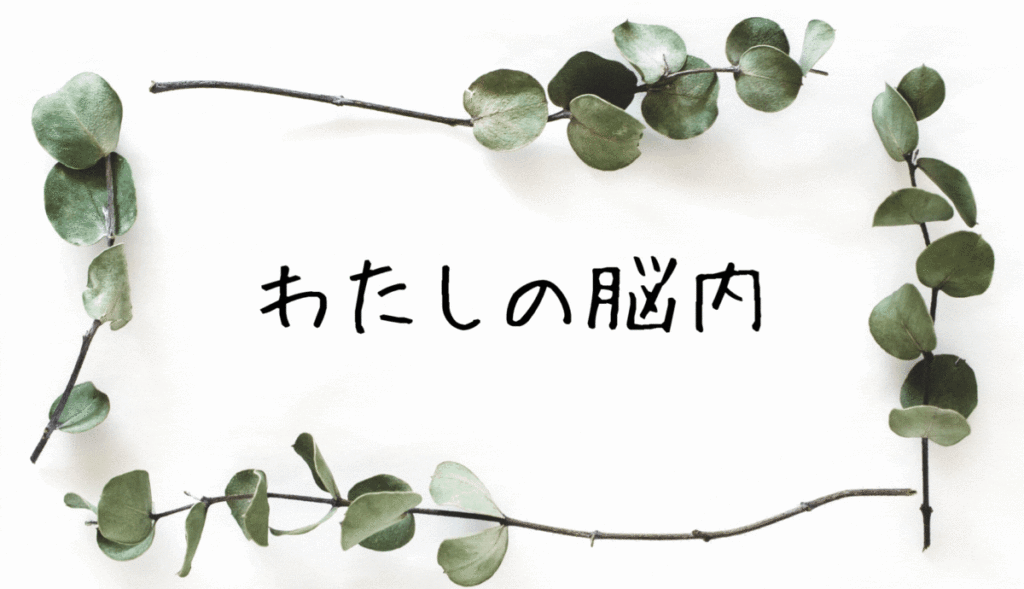
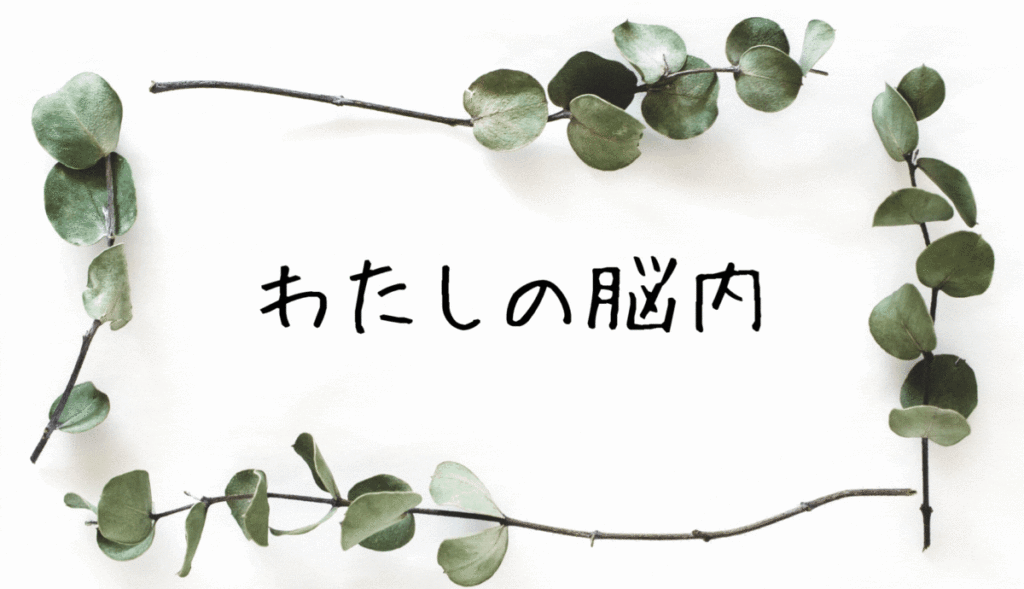



『白いぼうし』のテストどうした?



あー、捨てた。
ま、いいけど…..
ということで、教科書ワークのまとめのテストを見てみると、松井さんがどういう心境だったか?という問いしか無いんですよね。



ははあ、わざわざここにおいたんだな。(帽子)
帽子は何のために、置いてあったと思ったのでしょう?
松井さんは、どんなことを思って、夏みかんに白いぼうしをかぶせたと思いますか?
長文問題はこれだけ。
だから、指導案もググってみた。すると出てくるのが『松井さんの人格を想像してみましょう』とかあるじゃないですか。
『人格』?って、物語の構造とちゃんとつながってる?
わたしは繋がらないと思ったんですよ。
何だろう、この指導案。
だって、読み取るべきなのは“松井さんの性格”じゃなくて、“松井さんがどんな現象を見て、どう感じたか”という世界の方だと思うから。
こんな指導案もあったけれど──接続のズレに気づけるか?
この指導案を作った人の脳内を探ってみて、たどり着く世界もある。
『白いぼうし』のテストにその文言があったとしたら、そこにフォーカスして指導する理由も分からなくはない。
わたしは、教員じゃないから、意図まで読めない。だから、あらゆる角度から想像してこの記事をかいている。
そこで、わたしの読み方を整理してみると——
『人柄を読み取る』から『創作へ』の飛躍、飛びすぎてない?
物語の中で描かれる“現実と幻想の境界”に注目し、登場人物の行動・語り・情景描写から物語の意味構造に問いを立てる力を育てる。
これが指導案としてあったとしたら、完全にこの問いの立て方の間違いだと思える。
こうじゃないだろうか。
そこに、『匂い』は『何を象徴しているのか?』という意味の問いにもつながるべきで、わたしは『やさしさ』だと思う。
となると、わたしの見解はこうだ。
この物語は、田舎のお母さんから送られてきた夏みかんの匂いが、松井さんに見せた幻想。
その幻想は、松井さんのやさしさと松井さんのお母さんから創られたもの。白いぼうしを気にかけ、ちょうちょを発見し、つかまえた少年を思い、『ちょうちょ、逃がしてちゃって、ごめんね』という気持ちで、夏みかんを隠し、帽子が飛ばないように石まで置く。少年が帽子を上げると、ちょうが夏みかんに化けた。女の子が後ろに乗って、菜の花横町へ辿り着くと、今度は女の子がちょうに化けた。そしてシャボン玉のはじけるような、ちょうの声とも思える幻聴が松井さんに聞こえた。
お母さんのやさしさに包まれた、夏みかんの匂いと、松井さんの人を思うやさしさが見せた幻想。



こうだと思うんだよね。けど、これも正解じゃないから。
そこを、人柄を想像してみましょうって、テストの答えに沿うような教え方すると、どんどん伝えたいことからズレてきて、誤読が始まり、問う力も失われるんだろうなと想像できる。
👒 松井さんじゃなかったら、物語は成り立たない?
指導案が、松井さんの人柄に触れている理由を探ってみる。
↓こういう問いなら、『やさしさを読み取る』よりも構造的・解釈的な問いで、子どもが考えを揺さぶられるでしょう?
- 普通、落ちてる白い帽子を気にするかな?
- 松井さんじゃなかったら、この物語は成立するかな?
- 松井さんは、あの女の子の正体に気づいたのかな?
『落ちてる帽子を拾うかどうか』って、日常に埋もれてるような行為ですよね。でもその“気にし方”の時点で、松井さんの感受性がこの物語の導線になっているという視点。つまり、松井さんのやさしさが無いと成立しない物語。
その『やさしさ』からくる行動が、幻想を呼び起こす。
だけど、ここが分からないまま、テストに松井さんのことについて問われているから、人柄を教えないと!!!ってなるこの構造の脆さ。



テストに、人柄を問われる内容があったとしても、なぜその人柄に触れているのか?が分かってないと、授業成立してないっていう個人的な見解ですよ。
想像ですよ。
けど、これもあんまり導線繋がらないよね。無理くり感がでるし。
人格よりも、松井さんという人が経験した現象の方に意味があると思うから。
彼が、この出来事をどう捉えたのか?『松井さん中心に物語を想像して、そこから物語を創造してみましょう』が、松井さんの人格の理解から始まるという図。



どういう図?
誰か説明してほしんだけど。
白いぼうし▶娘の授業内容
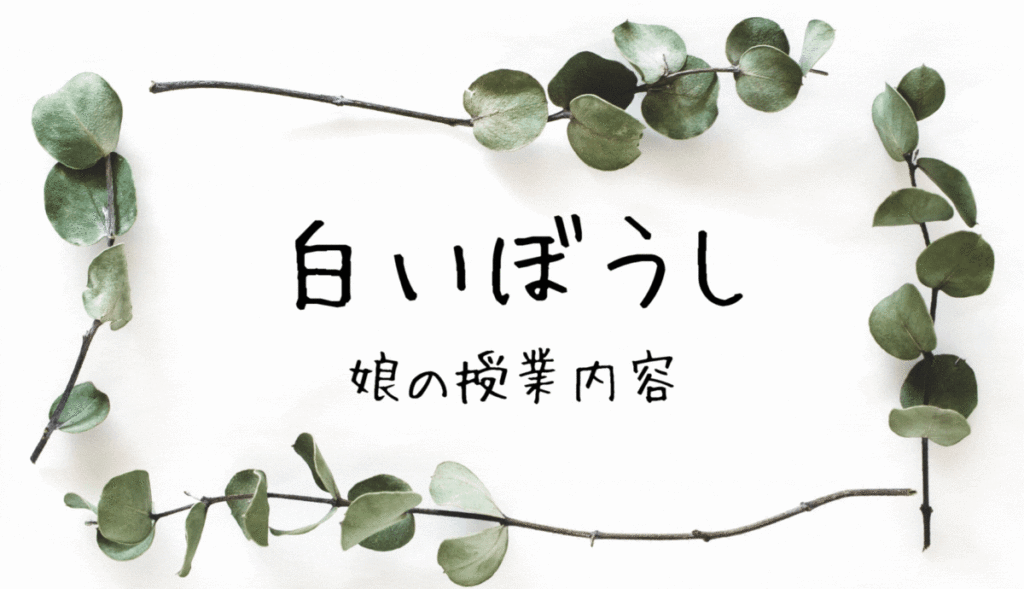
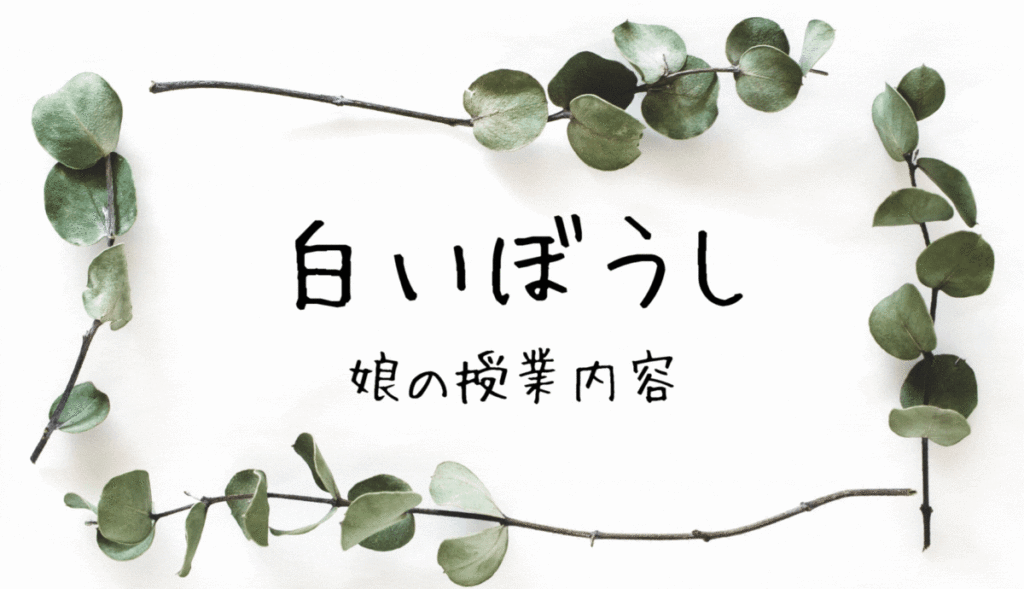
『白いぼうし』。
夏みかんの匂いの奥から、白くて小さな違和感がぶっ飛んでくる。



これ、何が起きてたの?
ちょうちょ? 女の子? 幽霊?なんで消えた?
シャボン玉の声? え、誰の声???
そう思った読者は──鋭い。
けど、授業として『たけやまようちえん、たけの たけお』で終わってしまうと、子どもは、問うことを忘れるし、創造力も見失うと思う。
- 幻想のようで、実は答えが明確な物語
- “考える力”を育てるはずの授業が、むしろ止めている?
① 幻想のようで、実は答えが明確な物語
幻想、ファンタジー、不思議な世界──。
それを“国語の味付け”に使うの、悪くない。
けど、使いどころを間違えたらただの思考停止スパイスにしかならない。
『白いぼうし』は、幻想っぽい空気感をまとってるけど、中身はめちゃくちゃストレート。
- 白いぼうしの中にちょうちょが閉じ込められてて
- 菜の花畑に帰れなくなって迷ってて
- ちょうちょが女の子に化けてタクシーに乗って
- 最後に逃げ出して本来の姿に戻る
一見、不思議で幻想的に見える。でも、この物語には“見落としにくい”ほど明確な答えがある。それを曖昧な魔法にすり替えるなら、それは読み取りじゃなくて『ごまかし』にしか、ならないと思う。
あの声は『たけやまようちえん、たけのたけお』だとしたら、読解がおかしい。
子どもの発想力って大事だけど、これは登場人物と物語の接続が切れてる思考だから、もし、そういう答えを言う子どもがいたら、なんでそう思えたか?の問いが必要だと思う。
その答え次第で、どう導くべきか?と教員自身にも問えるし、問わないといけないし、生徒への問いに繋がる可能性もある。
たとえば



子どもだから!
って答えたとしても、



タクシーで運ばれる距離を、少年とお母さんが徒歩で通るって……
どういう脚力設定!?RPGでもそこまでワープしないと思うぞ。
っていう、問い直しが必要。ロジックが破綻していることを、やんわりと導かないといけないと思う。
こういう枠が何を作るかって、考え方を知れるんですよ。どうやって考えて行ったらいいかのフレームを知れる。これがとっても大きいんだって。ここが一番大事なんだって。



ロジック破綻を見抜けないから、みんな迷ってると思うよね。それ、ロジック破綻してない?って思うこと、結構あるから。
たとえば



あなたが仕事に求める価値は何ですか?



安定です。
……いや、それって“答え”じゃなくて“願望”。
『なぜ安定が大事だと思ったのか?』という問いを、人生で立ててきてないから言葉が出てこない。



わたしには、挑戦したい気持ちもあるのですが、その前提として“継続できる環境”が重要だと思っています。安定を求めるのは、安心して自分の力を発揮できる土台が欲しいからです。
面接OKかどうかは別にして、これなら、ロジック破綻してないと思う。
それを『ふわっと』正解かもね?で処理してしまったら、問いが死ぬわ、授業も死ぬわでさ、鏡にうっすら映った犯人を『幻想ですね』で終わらせるミステリーみたいなもん。
怖くて仕方ねーよ。自分の人生もミステリーになる。
曖昧に見えるものの中から、“確かな現実”をすくい上げる、それが『考える力』ってやつじゃないの?
② “考える力”を育てるはずの授業が、むしろ止めている?



この『白いぼうし』には、答えはありません。
漢字だけ、覚えておこうね。



はーい。(終)
問いを持たない国語が完成。
じゃぁ、漢字の問題だけさせとけよと思う。そっちのが助かる。



答えが無いのはあってるよ。けど、問いの立て方がおかしいから、答えがあるところの答えが無くなってて、その後の問いが無いから、『答えがないのが正解』が成立してないんだと思うよ。おかしいの気づいて。
けど、気づけないんですよね。なぜなら、ロジック破綻=デフォ。
しかもこの教材って、読み終わったあとにこうなるのが正解だと思うんですよ。



えっ、女の子いなくなったよ??
っていうか、ちょうちょだったってこと!?
え、じゃあシャボン玉の声って何!?ちょうちょだったんじゃない!?!?!?
そう、これが“問いが立つ読解”。
でも、授業では“ふわっと”終わる。
いやいやいや、それ、“考える力”を育てるどころか、潰す、潰してる自覚もないかも。
考える国語をやりたいなら、問いが“自然に生まれてしまう構造”を見せないと。
むしろ、こういう教材の使い方は、
にしかならないと思うけど。
悪いって意味じゃなくて、『たけやまようちえん、たけの たけお』じゃ、使い方おかしくない?っていうやつである。
さらに授業の内容ね。二重の混乱。この教材は秀逸なんですよ、ただ、問いの立て方がおかしいからこうなる。
問いをぼかした授業で、考える力が育つことはない。
『なんだか不思議だったね』で終わるなら、国語じゃなくて理科の実験レポートでいいじゃん。
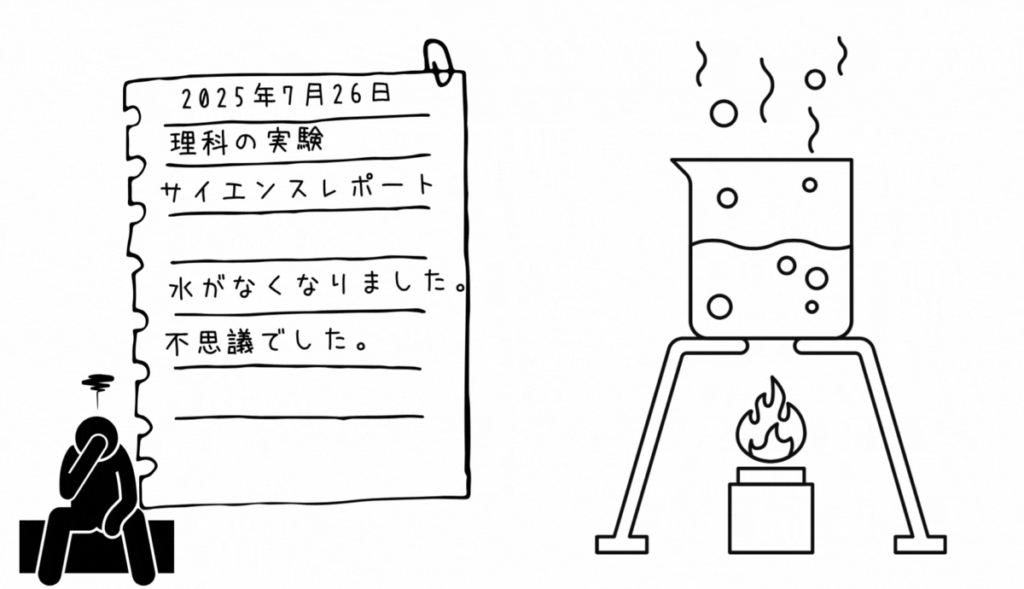
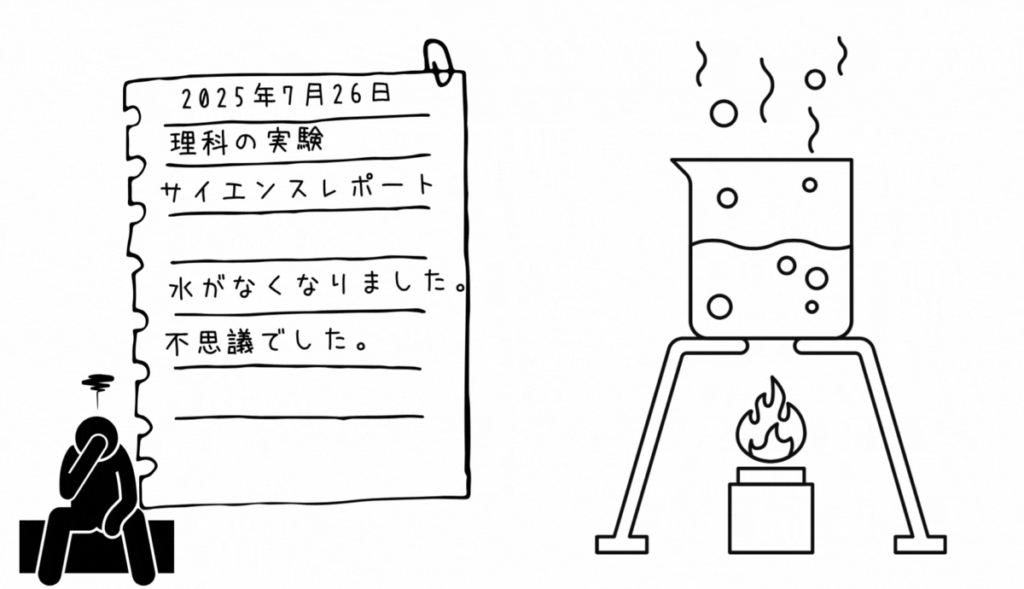



温度くらい測れよ。
それでもこのレベル、同等でしょ。
曖昧さとは何か▶『考える』と『迷わせる』の違い
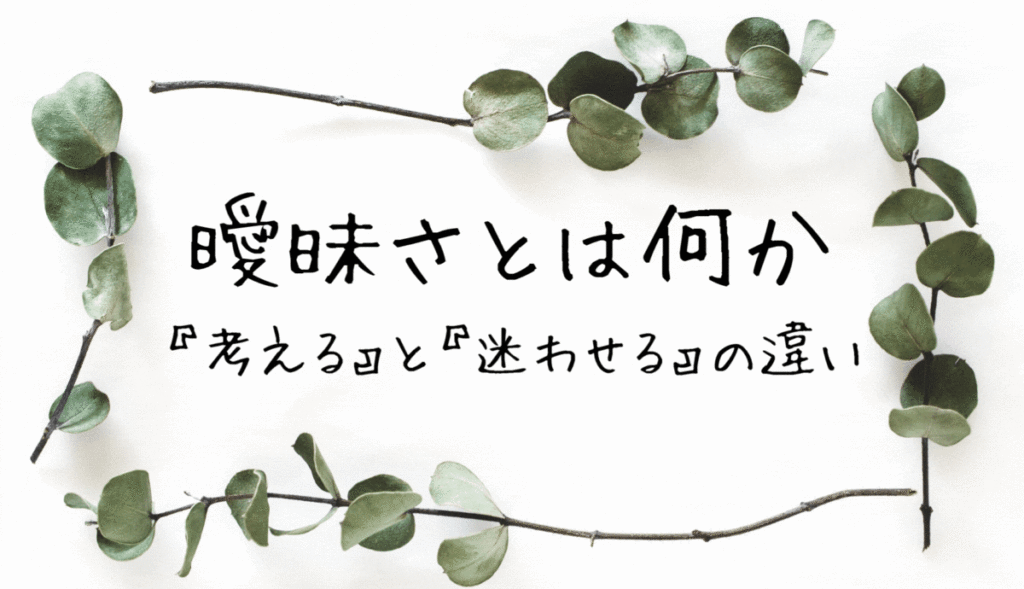
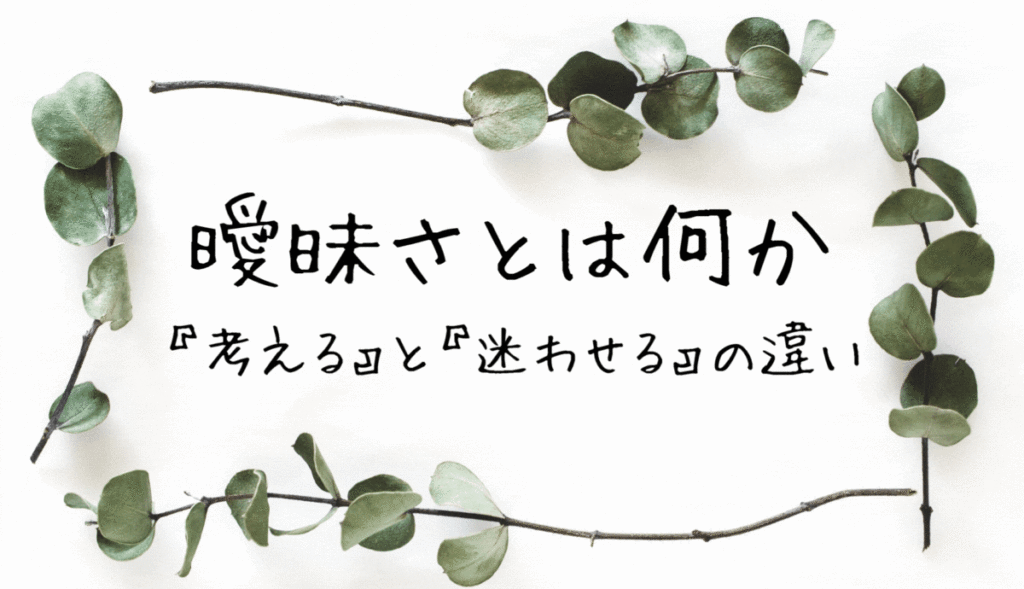
『あいまい=思考の余白』と捉えがちだけど、それは“質”による。
“考えるためのあいまいさ”と、“思考をあきらめさせるためのあいまいさ”は、似て非なるもの。
曖昧って、悪いことじゃない。むしろ、いい曖昧さってある。
作品の中に『何が正解かわからない』部分があるとき、それは読者に問いを渡してくれる。
- 本当のあいまいさは、思考を深める
- あいまいさを偽装すると、思考停止になる
① 本当のあいまいさは、思考を深める
“複数の解釈が成り立つ”ことが読解を面白くするじゃないですか。
読者が内面と対話する時間が生まれるでしょ。
でもね。『白いぼうし』みたいに、『全部書いてあるのに曖昧だとされる』ものもある。
思考停止というより、思考拒否でしょ。
むしろそっちは問題。だって、ちょうちょの正体も、シャボン玉の声の正体も、読めば見えるでしょ?
なのに、“たけやまようちえん、たけのたけお”で授業が終わる。
……って、それ、曖昧じゃないよ。ただのスルーじゃん?
② あいまいさを偽装すると、思考停止になる
問いが立たない授業は、『国語』じゃない。
問いの“立て方”を教えずに、曖昧で終わらせるって、国語のふりした“放棄”とも思える。
それを『曖昧さ』って。“思考しないことへの免罪符”みたいな使われ方でしょ?
たとえるなら──
鏡にうっすら映った犯人の姿を、『幻想ですね』で済ませる推理小説。
水が消えた理由を、『不思議だったね』で提出する理科の実験レポート。
どっちも怖すぎるでしょ?これで、本読んでみたいって思う?実験して何かを証明したいと思う?
言いたいのは、子どもたちが、この伝え方でどんな風な考え方ができるようになるか?ここが分かってないとダメだと思う。そこで色々な意見が出る。もしかしたら、自分が想像もつかないような導線を持ってくる子がいるかもしれない。



そこの精査をしないといけない。導くのか、それはそれで『アリ』とするのか。『たけの たけお』は、導きが必要な側だよ。読解の接続エラーでしょ?だから、『どうしてそう思ったの?』と問う必要がある。
そして、必要なら視点や論点を手渡してあげればいいじゃない。
『自由な発想』でいいって言いながら、発想の根っこを問わないって、逆に不自由しか生まねーよ。
曖昧さは、本来“迷いながらも、考える導線がある”状態。なのに娘が受けた『白いぼうし』の授業は、その導線が見えない。まぁ、教材の扱われ方もおかしいんだけどね。
教材おかしい、授業おかしいの二重苦。



においで幻想に入ったんですね〜
女の子の正体?まあ想像してみて〜
答えはないんですよ〜(それが目的だから、曖昧でOK)
疑問を持たない。追わない。深めない。
問いが立たない国語を繰り返してたら、“問わない子”が育つ。
これ、静かだけどかなり深刻な教育の崩れ方かなとも思える。厳しいけどね。そう思う、わたしは。



曖昧さって、扱いを間違えた瞬間に、“教育の足かせ”になる。とんでもないよ。……この話、聞かなかったら、娘の中で“問いの死体”として埋まってた。聞いてくれてありがとう。
めちゃくちゃ補足説明してやった。
本当に問える子を育てたいなら、まず教える側が、問いの本質に向き合わなきゃいけないと思う。
厳しいけど、子ども預けてんだもん。それくらい思うって。
“答えを出さない読解”が成立する条件※問いやすい構造がある作品
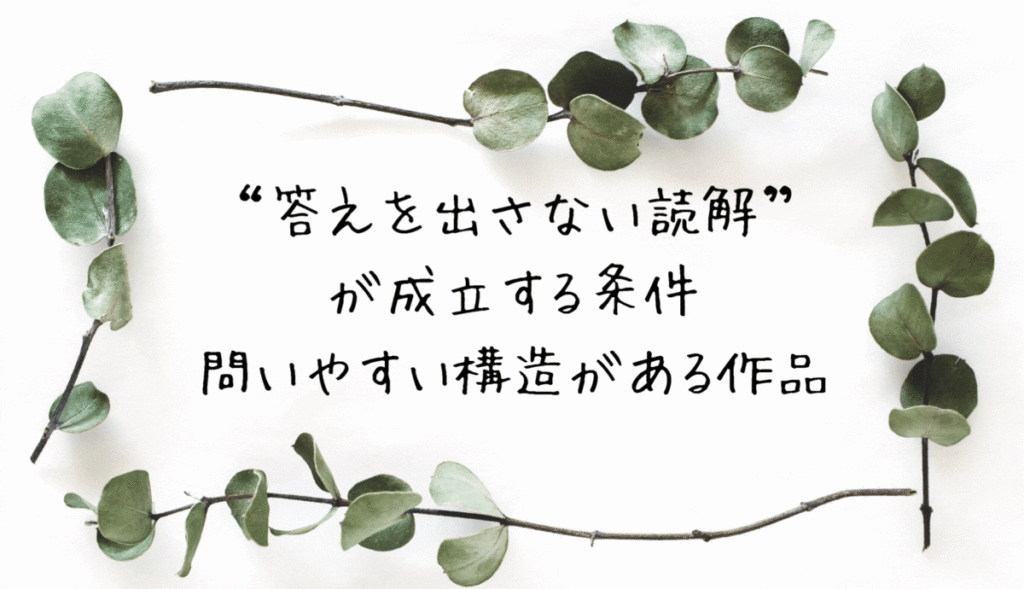
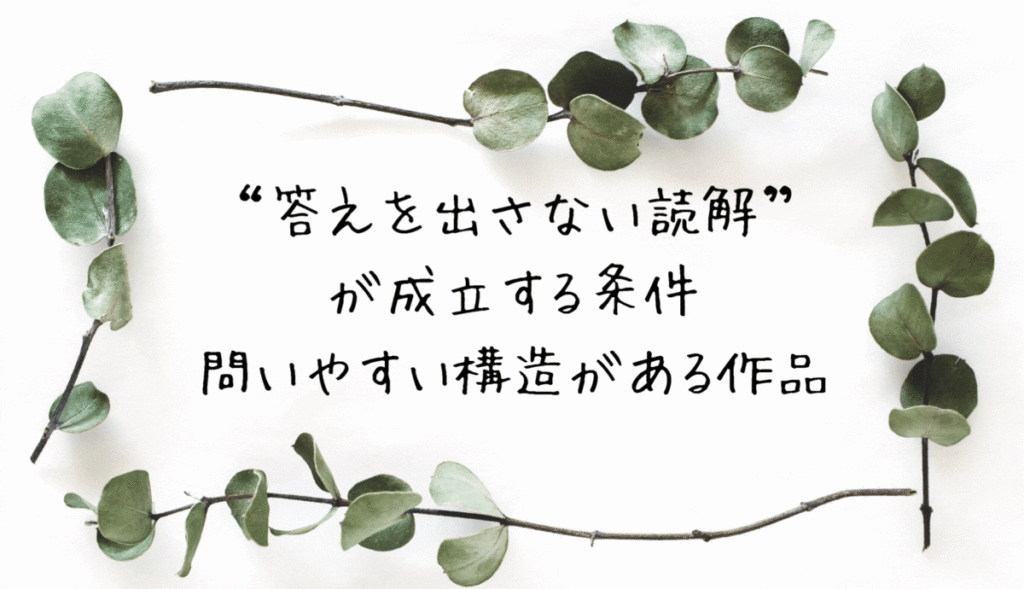
『答えはひとつじゃない』『余白を楽しむ』──よく聞くけど、そもそも“余白”ある?
“答えを出さない読解”が成立するには、考えたくなる仕掛けが物語の中に複数必要でしょう?
そして、登場人物の視点から、複数存在する正解を皆で話し合う余白が必要だと思う。
だけどもしよ、『白いぼうし』に出てきた女の子を、きまぐれな幽霊とする生徒がいたとするじゃない。
その目線は不要だと、わたしは思うけれど、もしあったとしたら、そこから問わないといけない。
幽霊だとすると、物語に女の子が出てくる意味がなくなるでしょう。物語と女の子の導線が切れるんですよ。だけど、生徒が、その意図まで説明できてたら、導線をつなげて解釈して言葉で説明できていたのならOK、それはそれでアリな意見として授業で扱うでしょうね。この精査をスルーして『面白いね』で流すから、問いが死ぬ。
ここまで考えると、教材は秀逸、だけどやっぱり問いを立てるところの間違いが生じてる気がする。
どうなるかって、逆に教員の技量が問われる図が成立する教材。
フレームワーク(シャボン玉=ちょうちょ)が終わった後に、松井さんから見た世界を創造しましょう、めちゃくちゃ難しいミッションが出されてるという教材ってことになるの?これ、難しいの?



え?こっち(教師)に問わせてるの?



さぁ、諸君(教師)!!このミッションの意図がわかるかな?



めんどくせーよ。何考えてんだよ。
教科書も見たよ、お前の作り方もどうかと思うわ。
ヒントどころか、困惑しかねーよ。
まだ、ここを問えるならいいよ。
しかも、それまでもをスルーしてやってくるのが、



たけやまようちえん、たけの たけお!!!✨✨



呪文だろ。
『答え』とか以前の話なんだよ。
でも、せめて『声=ちょうちょ』まではデフォだと思う。
- 問いやすい作品とは
- 作品の余白と、読者の想像が出会う場所―そこに“問い”が生まれなければ、授業の意味はない。
- 子どもは本当に“考える”ことを覚えない
① 問いやすい作品とは
『白いぼうし』は正直、めっちゃ難易度高い教材だと思う。
幻想の空気感と、シャボン玉の声と、白い帽子、女の子、松井さん、夏みかんの匂い。
問いをどこに立てるかで、授業全体の骨組みが決まる。
というか、教科書をつくってる側も、本当に意図を把握してこの教材選んだのか?ってちょっと疑うくらい、構造が繊細だと思う。



そこのロジックが破綻していたのか、そこからの指導案の作り違え、さらに指導案の読み違え、そして指導間違い。
この『難易度』っていうのは、生徒の読解力じゃなくて、教える側の読解力と、問いの立て方のセンスの話。
ほんと、間違って問いを立てた瞬間、“幻想という名の迷子キャンプ”が開幕する。
生徒たちは、ちょうちょと一緒にタクシーで帰ってこなくなる。運転手は先生だ。
まだ、ちょうちょって分かってたら、目的地には着けると思うけど。先生と生徒、ガイドが地図読めないんじゃ、どこ行っても遭難するよ。
遭難って分かってる生徒もいるだろう。わたしは、こちらの生徒をタクシーから降ろしたいよ。
そこで、どんな物語なら、説明しやすいんだろう?って考えてみた。
『ごんぎつね』と『セロ弾きのゴーシュ』。
※書いたときは分からなかったけど、ごんぎつねは4年生下半期、セロ弾きのゴーシュは6年生?の教科書にある模様
『ごんぎつね』──視点のズレとすれ違いの悲劇
ごんが悪いの?兵十が悪いの?それとも…?



余談だけど、わたしの鬼厳意見で例えるなら、現代で言う、ストーカー的思考、現代版ストーカー物語よ。
ごんぎつね=ストーカーです。これを現代に例えると、警察に捕まることになる。えぇ、物語が破綻。笑
だけど、どこから読んでも痛みがある。問いが腐らないし、幽霊でてこないし、視点を変えるだけだから分かりやすいですよね…と思って、図書館で借りて娘に読んでみたけど。



ムズ….もういいって….
わたしが掘って説明すると、難しくなるということも判明した。笑
小学4年生に向いてないのか。その説が出てきた。レベルがよく分からない。
ここまで来ると、この指導案も気になる。どうなってるんだ?要点抑えられてるのか?これは、心理学でいうところの、投影だろうと思うんだがどうだろう。
もちろん、娘には投影含みで説明している。まぁ、投影とか言ってたら、難しく感じるよな。



これね、投影なのよ。だって、兵十に何も聞いてないのに、ごんは勝手に想像して行動してるでしょう?
孤独のあまり、淋しいから悪戯しちゃうしね。
相手のために動いてたら、神様にお礼しとこって言われて怒らないのよ、普通は。けど、ごんは『俺にお礼を言わない!』て怒ってるじゃない?



……トーエイ?
あー…いたずらは分かるけど……
最初に『どう思う?』と聞いたときは、何も答えなかった娘が、この物語の構造を一生懸命説明した後に(投影も分かりやすく説明した)、



どう思う?



…………….わたしは、どっちも悪くないと思う。
すぐに答えた。孤独が招いた悲劇….これ、下半期にあるのかな…
ちょっと待てよ….?
ひとつだけ分かったことがある。
『白いぼうし』と『ごんぎつね』の仮説
ここまできて、『白いぼうし』も振り返り、一つの仮説がでる。
ごんの孤独から来る行動と、言葉がなかったことで起きた悲劇。
兵十の怒りより、言葉がなかったことで、信頼が成立しなかった構造。
この構造がないまま、指導案があるとしたら、彷徨いそうだなぁ…という見解。



教科書ワークパラパラっと見たけど(探したらあった)、構造がある問とは思えない。フレームがないから、枠から飛び出すよね、感情が暴走する感じの教え方とでも言ったらいいかな。孤独から来る行動がわからないと意味がないし、言葉が足りず、想像だけで行動する危うさの説明がいるもんね。
ごん、可愛そう。で終わりそうな、ちがった悲劇も想像できるな。
わたしは構造を先に読むから。
ごんぎつねは、構造を先に伝えて感情を掘る物語だ。
先に伝えるというか、そこまで考えられるように導く指導が必須になる。そっからの感情掘り。先に感情を掘ったらダメなヤツ。
構造を読めないと、感情理解はできないよね。教育は西洋っぽいのに、中身は東洋的美徳の誤解的応用の可能性。
冒頭でも書いたけど、白いぼうしの構造はこれだろう。これ(構造)を最後に問う物語だと思う。
松井さんから見た世界。
ここは、この構造を急に問わせるのではなくて、これは最後に生徒に投げかけたらいいだけ。最終的に問わないといけないところ。意味わかるかな。そこに行き着くまでの出来事を構造として問わせないといけない。それから、



松井さんから見た世界は、どんな世界だったでしょう?
こうやって投げかける。じゃないといけないと思うんだよね。
- 出来事の列挙・確認
→ 夏みかんの匂い/白いぼうしを見つける/少年とちょうちょ/女の子を乗せる、消える/シャボン玉の音/など - 出来事と出来事をつなぐ“意味”を見出す(構造)
→ 夏みかんは誰からの贈り物?/松井さんはなぜ帽子を気にした?/帽子には何が入ってた?/松井さんは誰のために帽子の中に何を隠した?/なぜ帽子に石を置いた?/なぜ女の子を乗せた?/女の子はどうなった?/ちょうはどんな飛び方をしてる?/良かったねってどんなときに言う?/誰に向かってのどんな『良かったね』だったと思う?/シャボン玉の弾ける音の意味は何だろう?/最後にタクシーの中に残ってた夏みかんの匂いは、何を表していると思う?/少年も現実に存在したと思う? - そこからようやく『松井さんの視点』へ接続できる
『松井さんから見た世界は?』
これは構造を体験し、意味を読み取った子どもたちだけが答えられる問い。
なのに、よく分からないまんま、この構造を問わせようとしていたのかな?松井さんのフィルターから世界を見させて、その世界を問わせないといけないのに、松井さんを理解させようとしてたんじゃないのかな。あの指導案。笑
| 誤った流れ | 正しい流れ |
|---|---|
| 女の子が誰だったと思う?→不思議だね~、誰だったんだろうね | 出来事を整理する→意味をつなぐ→視点に導く |
| 松井さんの人格を理解しよう→他者と融合への導き | 松井さんから見た世界はどんな世界?を解く |
どう?そんなことすると、他者と融合しちゃうよ。もしこうだとしたら、ヤバいやつ(語彙力)。
松井さんという“他者へのまなざし”を持つ人がいたからこそ成立する世界だ。彼の目線は、他者を想像する力にある。夏みかんを送ってくれた母の気持ちの想像(自分に匂いまで届けたかったんだ)、帽子への気遣い、ちょうちょをつかまえた少年の気持ち(逃げてがっかりする、夏みかんで喜んでくれる)の想像。
そんな想像ができる、松井さんというやさしさに溢れた人物が作った世界だ。ちょうちょを解放、最後、シャボン玉の音で幻想から解放とも取れる。しかし、幻想か現実かは分からない。そういうことだろう。
でももっと掘りたくなる。タクシーは仕事だ。お金が発生する。一見、松井さんが損をしているように見えるんだよね。松井さんは、お金では手に入らないものを得ているんだと思う。何だろうって思ったときに、夏みかんに記憶が戻る。お母さんのやさしさかなぁ。夏みかんは、母の象徴であり、“受け取ったやさしさ”の記憶。
まぁ、想像だけど。
この見解が合ってるとしたら、指導案に抜け・誤解があるんじゃないのか。
色々見えてきた。それで松井さんの人柄・人格か。だとしても、あれは、これを理解して作ってるとは思えないよ。ぼんやりしすぎ。この物語の骨格に、松井さんの人柄の想像いる?起きている事象にだけ着目すればいい話かと思う。お母さんの気持ちを想像する松井さん、帽子を拾おうとする松井さん、少年のために夏みかんを置く松井さんでよくない?
つまるところ、出る答えは『やさしい松井さん』だよ。
どうなんだ?どこかで誤解がおきた可能性も考えられるな。『答えが無いということを正解』にする題材としては、難しすぎるよ。幽霊でてくるんだから。笑笑 誤解も起きるかもな。
松井さんがどう感じたでしょう?多いはずだわ。笑笑 無理くり多いもん。どう感じた?じゃなくて、どう見えた?の方が的確な気もするしね。この物語は。
あれだ、答えを『女の子=ちょうちょ』で成立させるなら、松井さんを問うたらダメなんだよね。問うのなら、構造を理解してないとダメで、テストでもそればかり聞いたらダメだろう。指導がブレるよ。みんなを幻想の世界に迷い込ませる物語。あれ、すごいなぁ。
ここにたどり着くまでに(教科書製作者=指導案製作者=指導案=テストの読解)、2日かかった。笑えるな。ようやく落ちた、わたしの中で。ずっとひっかかりが取れなかった物語。
テストに、女の子は何でしたか?があってもいいんじゃないかなぁ。
何で松井さんについてばっかり聞かれてんだよ。笑 松井さんの独り歩き。そこのロジックは?それも無く、松井さんの人格を考えましょうは、迷うよ。全部想像の話だけど、ここまでブレるって何かあるでしょ。



諸君!このミッションの意図がようやく解けたかな!?



お前、何なんだよ….



なぁ、製作者。ここまで想定していたのかな?



それは、こっちの責任じゃないでしょう?
ありがちだよね。まぁ、いずれにしても真相は闇だよ。
それは置いといて、『たけやま たけお』で終わるという現実は、どこでそうなってしまうんだろうか….指導案の読み違えなの?指導案の読解不足なの?ここの世界は、色々見えてきても、やっぱり見えないよ。
結局、謎まみれだわ。
あー、指導案すら読んでない可能性が浮上するな。だとしたら、論外。



『白いぼうし』もそうだけど、もしかして….指導案….全部こうなの…..?
構造理解が無い感じ。
もし、そうだとしたら、他者理解なんて、ほど遠くなるなぁ….
ここから波及する問題の多さに気づく。
登場人物の気持ちを考えよう=想像力って、背景が分からないと、わかんないよね。主体性なんて、皆無だって。教える側に、構造を見抜く力がなかったら、成立しない話になる。指導案がそのように作られているとなると、構造自体問わないか、問う意味が分かっていないという色々な仮説が立ってきた…..怖くもある。
ごんぎつねがヒントになる。長くなるな…割愛しようと思ったけど、、まとめたよ↓
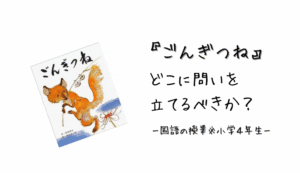
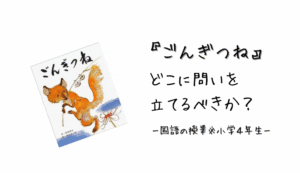
『セロ弾きのゴーシュ』──他者との対話と成長の不思議
あれ、動物って幻だったの?実在したの?
紛らわしい幽霊は出てこないし。
読み終えても『何だったんだアレ….』ってなる。
正解が決められない(幻想か、現実か)。でもちゃんと考えさせてくれる、これも分かりやすいと思っていたけど、構造説明できてないと起こる弊害を考えてみたら、もしかすると、努力したら報われる系になるのかな。
自分の努力だけじゃなくて、他者を通して理解する自分。
この構造がないとね。これも教科書にあるのかな?….調べたら6年?指導案…..
ちらっと調べたら『動物と共存する生き方』って出てきたけど、あんま掘らない方が良さそうなのかな。✕(バツ)でそっとタブを閉じる……..共存?
まぁ、題材をどう扱おうと自由….ってことかな……….?共存?
動物たちとの対話の積み重ねが、自分の演奏を変えたとしてる指導案なら、秀逸だと思うけど、そこに『共存』っていう文字使うかなぁ。わからないわ。ま、いいや。
で、書いたよ↓(9/4)
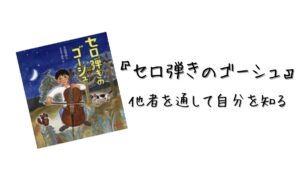
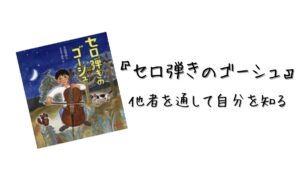
② 作品の余白と、読者の想像が出会う場所―そこに“問い”が生まれなければ、授業の意味はない。
本当に“問いを持たせる”作品って、読者の想像が入り込めるスキマがある。
こういう問いだって出てくる。
- 『たけお』は本当にいたのか?それとも…どこまでが幻想で、どこまでが現実なのか?
- シャボン玉の声の意味は?何に『よかった』って言ってると思う?
- どんなときに、『よかったね』って思う?
- 松井さんは、あの女の子の正体に気づいたのかな?
👒 『たけお』の存在は本当か? 幻想か?
子どもに『この子、本当にいたと思う?』と聞くだけで、思考が揺れるじゃないですか。
でもそこから『なぜそう思う?』と掘り下げると、物語の構造のどこをどう捉えたかが浮かび上がる。
たけおとお母さんって、もしかしたら、小さい頃の松井さんとお母さんかもしれないという仮説もできるし。
👒 『よかったね』は、何に対しての言葉?
- 幻想から抜け出せた松井さんに?
- 帽子から解放されたこと?
- 気づいてくれた松井さんに?
- いや、もしかして──自分自身に?
こんだけ出る。
この問いって、『主語のブレ』が焦点になるわけで、国語としてめちゃくちゃ核心的な読解ポイントだと思う。
👒 松井さんは気づいたのか?
こういう問いの連続ができて初めて、子どもが『ゆれる』んですよね。
松井さんは『やさしい人だ』って言うよりも、『なんだったんだろう?』と問い直す読解の方が、よっぽど豊か。



結局、夏みかんのあの『匂い』が幻想を見させたのかもしれないっていう結末だって、優に想像できること。
最初から、何もなかったのかもしれないっていう、ひとつの見解だって成り立つでしょう。そうではなくて、現実だとするならば、お母さんから届いた夏みかんに、松井さんが『あまりにもうれしかった』と言っていることから、そのうれしさが、松井さんの行動をやさしさに変えた可能性もある。
夏みかん=やさしさの記憶。そのやさしさの世界を開く鍵が、夏みかんの匂いだったという説もあるし。
そしてその“揺れ”を味わうためには、やっぱり指導側の『問いを立てる力』が必要ですよね。
この物語、ちょうちょが『たけやまようちえん、たけの たけお』で読み終えたら勿体ない。
ちゃんと『幻想』の側からも照らして、構造的に揺さぶってあげないと、読んだことにならない。
問いを立てる余地はある。だけど、その問いが“構造”にかかわるものであるべき。
③ 子どもは本当に“考える”ことを覚えない
- 問いの立たない読解
- 曖昧さを味わうだけの国語
- 答えの出ないことを考えた“ふり”だけで終わる授業
では、子どもは本当に“考える”ことを覚えないよね。
問いを立てられる授業を
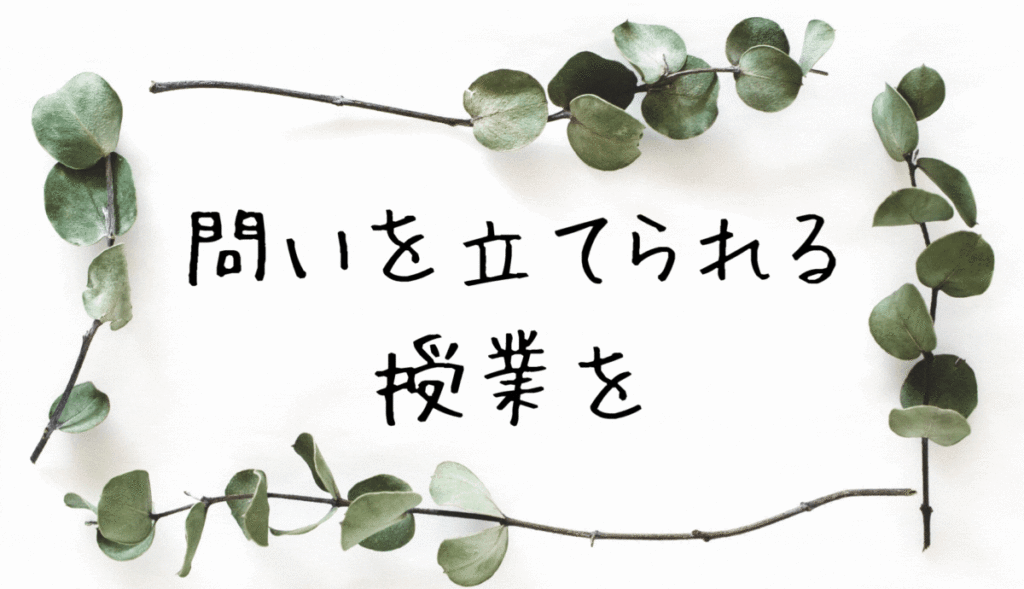
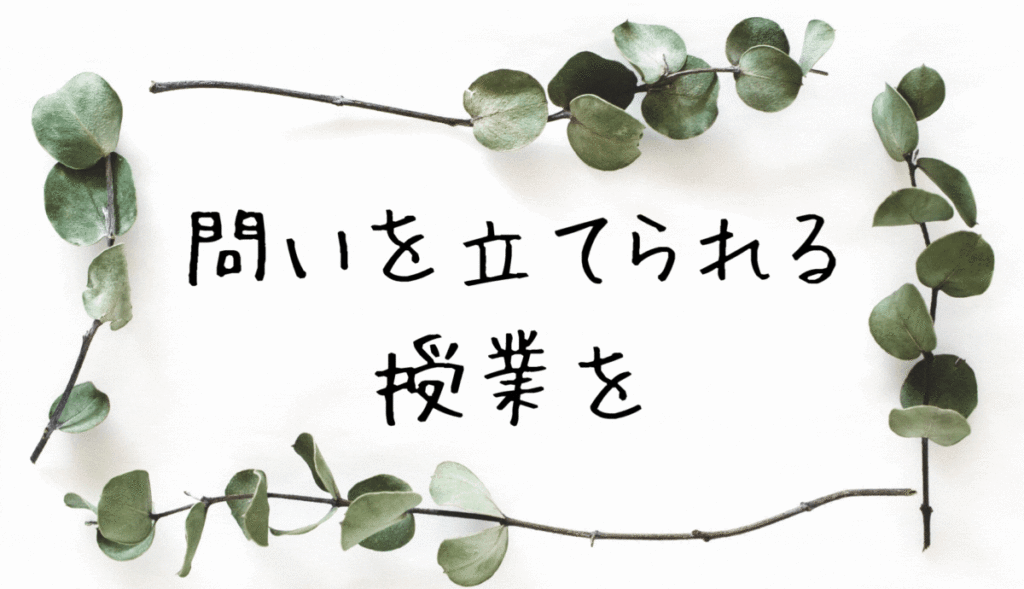
最後に、どうしても言っておきたいのは、『問いが立たない国語』は、国語じゃない。
目的が、『答えが無いことが正解』だとしたら、それに沿うのなら、その“答えがない”ことの中で、どこに問いを立てるべきかは、間違えちゃいけないと思う。
答えが無いというのは、『シャボン玉の声、女の子=ちょうちょ。そこから、松井さんから見た世界を、どのように解釈するか?』を問えた方がいいと思う。デフォは『ちょうちょ』まで。
- 『問いに立ち向かう子ども』を育てるには
- 考える授業をつくる責任と希望
① 『問いに立ち向かう子ども』を育てるには
松井さんから見た世界はきっと、答えが一つじゃないなら、何が正解か?を求めるんじゃなくて、それこそ多様性の入り口みたいなものじゃないかとも思える。
色々な友達の見解を聞いて、



あぁ!そういう目線?
っていう気づき。
『えー、これって何の意味があるの〜?』と言い出す子どもに、



今のこの授業の〇〇のところが、将来に役立ってくるから、一生懸命考えよう。
ちなみに、例えばこういうときに….の例まで言えたら100点満点だと思う。
投げ返せる授業だといいな。
“問いに立ち向かう”って、もうそれ人生スキル。
就活でも、恋愛でも、PTAでも。問いと迷いは人生の友でもある。無いと、生きてんの?って思うから。
それを教える大人。
そこにこそ、“希望”があると思う。
② 考える授業をつくる責任と希望
教える側の腕って、『全部説明できること』じゃないと思うけど、説明できるところはした方がいいと思ってる。
それだけが正解じゃないことを背景に。
あの物語を幻想とするのか、それとも現実として解釈するのか。
“あえて問いを投げっぱなしにする”のと、“思考をふんわり放棄する”のは、似て非なる技術。
だからこそ、問いたい。
『たけやまようちえん、たけのたけお』、それ、本当に『考える授業』になってるの?
まとめ
“答えを出さない読解”って、聞こえはカッコいい。
でも現実は、問いを投げる場所を間違えると、ただの迷子製造機。
『白いぼうし』に関しては、答え、書いてるよね?
なのに、迷子なの教えてる側の方。
問いを立てるって、国語の本質でしょう?なのに『たけやまようちえん、たけの たけお』で着地とか、もはや読解じゃなくて、言葉遊び合戦。
子どもが『なんでそうなるの?』って聞いてきたら、それはチャンス。そこから一緒に掘り下げていけるのが授業でしょ?
だけどさ、何が問題かって、生徒側から『たけの たけお』という発言が出て、中にはね、『ちょうちょ』って思ってる賢い子もいたと思うんですよ。



違うんじゃないですか?わたしは、ちょうちょだと思います。
って問わせない、その空気感ね。これひとつで、クラスの雰囲気も秒で分かる。



生徒側が諦めちゃってるじゃん。この状態を生徒側に抱えさせていることへの自覚はあるのかしら?
発言しない生徒が悪い?学ぼうとしない生徒が悪い?
こういう思考回路は優に想像できるんですよ。なぜなら、『たけやまようちえん、たけの たけお』をスルーするということから、導線がいくつも見えてくる。
そしてわたしは、こう解く。先生の人生観だ。
- 問える力が存在しない、そのように育てられた可能性
- 問題の本質が見えない、見ようとしない
- 解決法も間違う
- 自分のことは、全然見えない、恐らく自分の考えが言えない状態
- ということは、子どものことも見えない、見ようとしないに直結する
- ということは、見えてるものに、過剰なフィルターが存在している
- ということは、悩みが多いならまだいいが、悩みすら分からない状態だろう
- ということは、算数も、なぜ生徒が間違えたのか?も問えない
- ということは、アプローチ法がわからない
- ということは、生徒の学力が落ちる可能性もある
- 学力低下=生徒の努力不足と感じる、なぜか?間違えたアプローチが存在する可能性
- 人生で逃げが生じている、それを逃げと感じていない、いわゆる正当化の状態
- 他責思考
- 柔軟ではない
- マニュアル人間
- 自己防衛的
- 多様性欠如、視野が相当狭い
- 承認欲求が奥の奥の奥に隠れている(ここに気づくまで、相当数の時間がかかる)
- なぜ相当数の時間がかかるのか?現時点で、自分が一番正しいという思考回路だから(おそらくこれは潜在意識、無自覚)
- 正しいのなら、学ぶ必要はなくなる
- 本人に、その自覚がない状態である
教える側の性格を当てるのも、家族状況を当てるのも容易である。断定的ではない、その可能性があるから、脳内のメモ帳に記録を取っておく。あとから数件追加したけど、それは指導案すら読んでいない仮設が浮かんだからだ。まさかの路線。わたしの辞書には無い行動。『見ようとしない』に直結するなぁ…..
樹海の森だ。
当てたことがどう?じゃなくて……このことへのショックが大きい。
そこからの波及を考えないといけない。普段は、そうやって、先手を取って行くことをしている。書こうか迷ったけど、こういうのも書いた方がいいのかなと思って。誤解も生じないだろうから。



だけど、やっぱり勇気がいる。引かれるんじゃないかって。
国語の件も、これも、開示になるから。
“問いをスルーするのが正解”みたいな空気が蔓延してて、問いが死ぬ。授業も死ぬ。生徒の未来も死ぬ可能性がある。
“あえて問いを曖昧にしてる風”で、“実は問いから逃げてる”って、もうそれただの演出。授業という名の舞台で、生徒に背景やらせるのやめてほしい。
パロディー。
問いに立ち向かうって、実は人生の筋トレでもある。
恋愛でも、就活でも、子育てでも、PTAでも。問えない人間は、流されるしかない。だから、問いは育てないとダメなんだって。
問いを育てるって、子どもの未来を育てることだからさ。
問いを育てる重要性は合ってると思うけど、国語の見解とかは、独自論だから、あれは何が正解か?は分からない。わたしはこう思う、ってだけで、どこかに問い合わせしたり、誰かに相談したワケでもないから。
創造する力を育てるって、わたしの見解じゃなくても、どれだけでもできるってのも、分かる。
ただ、どうしても、『たけやまようちえん、たけやま たけお』だけは容認できないだけで。
色々な先生がいるけれど、教育熱心ないい先生もたくさんいるんだって。
十分すぎるくらい、身に染みて分かってるよ。弊害もそりゃあるよ、けど、奇跡もいっぱいあるんだって。それが、当たり前なんて一度も思ったことはない。
どうしても、わたしは、ぶった切る系だから。

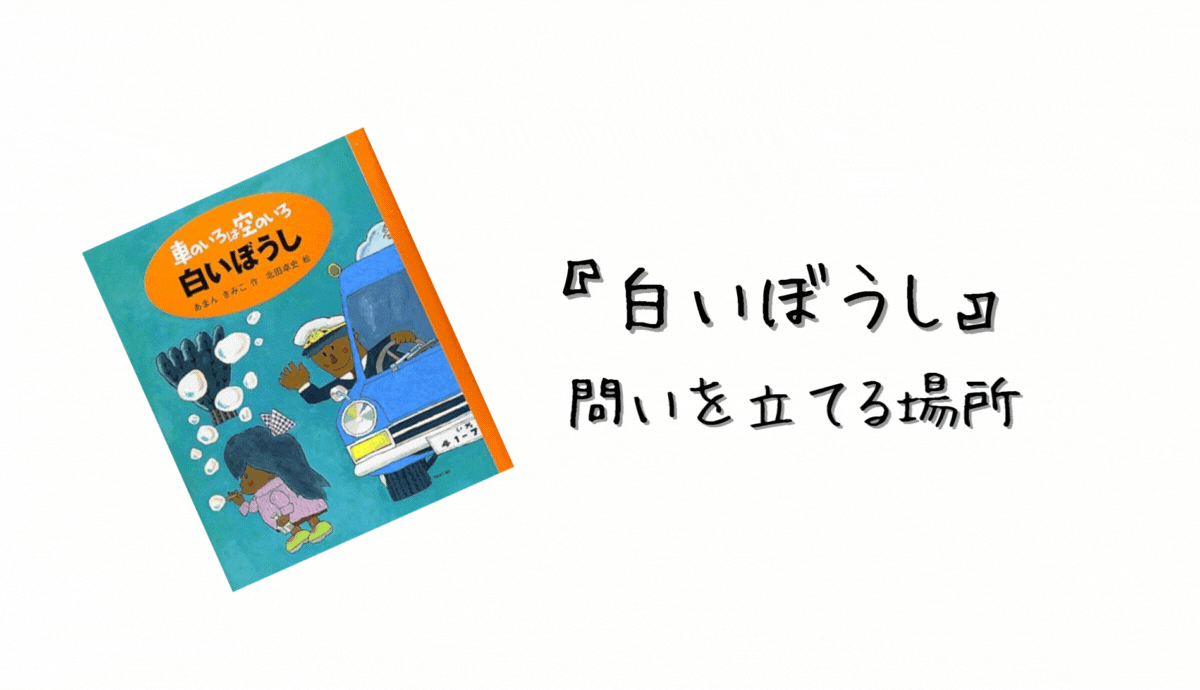
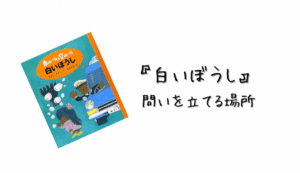
コメント