小学校4年生の下半期で習う?『ごんぎつね』。
わたしは、ごんぎつね=ストーカー的思考だと前記事で言って、物語を破綻させたんだけど、それだけでは語れない部分を今日はこちらで書こうと思います。
ストーカー的思考は合ってると思うんですよ。
ただ、問うべき構造があるから。
この物語で、問うべき構造だと思うのはただ一つ。
ごんは話せたのか?
ここだと思う。
その問いが立てば、あの火縄銃の音も違った意味を持つから。
ごんは報われたのか、報われなかったのか。
構造を問わずに想像させることは、
読解ではなく空想であり、
国語としての問いの根を腐らせてしまう構造だと思う。
ということで、この記事では
『ごんは話せたのか?』
という構造に問いを立てたわたしが、
なぜそこが重点か?
を中心に勝手にまとめてみました。
ごんぎつねで本当に問うべきは何か
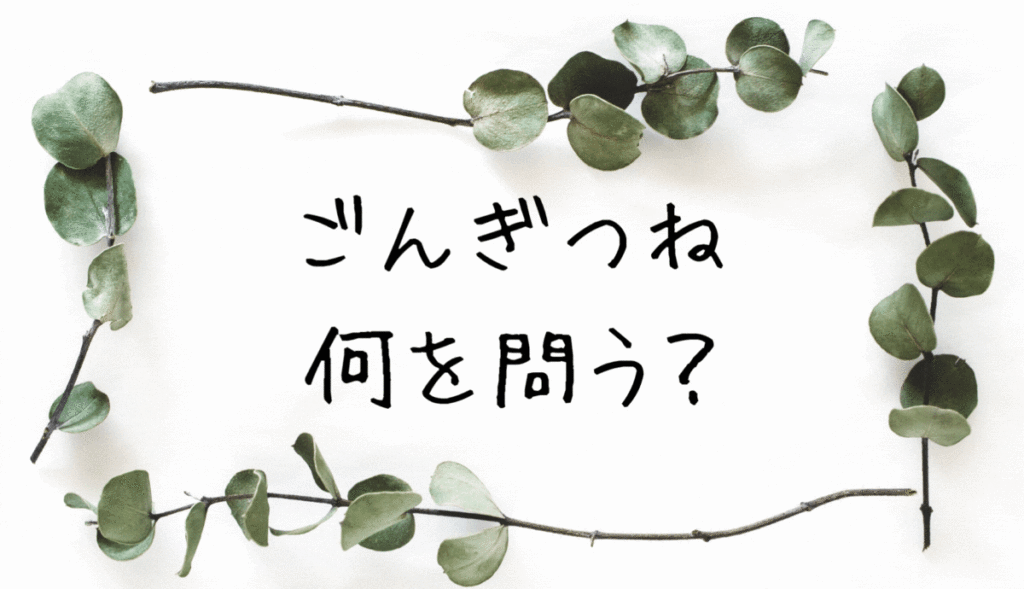
小学校の国語教材として長く親しまれている『ごんぎつね』。
悪戯好きのキツネの行動に
『かわいそうだったね』
『やさしいごんでもあったね』
と感じる子も多いと思う。
兵十、ごん、どちらも悪くはない。
という結末で授業が進行しているかどうかは、分からないけれど、良い・悪い目線で言えば、わたしは、ごんが悪いと思う。
魚を盗み、恩返しのつもりで栗や松茸を届け、すれ違い、最後に撃たれて終わる。
これは現代ならストーカーとされてもおかしくない構図だからだ。
兵十の意見や考えがどこにも存在せず、ただただ一方的。
厳しい意見を言うなら、投影まではデフォじゃないと。
とも思える。
じゃないと、指導がブレまくる。

え?と思った方は、
兵十=美女、
悪戯好きなごんぎつね=変態男
と想像してみて欲しい。
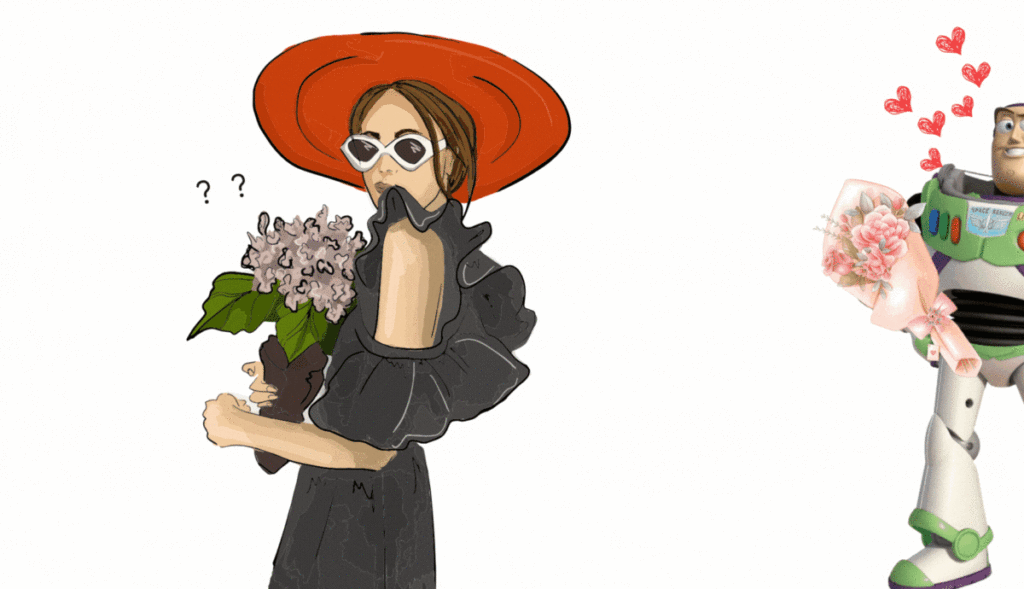
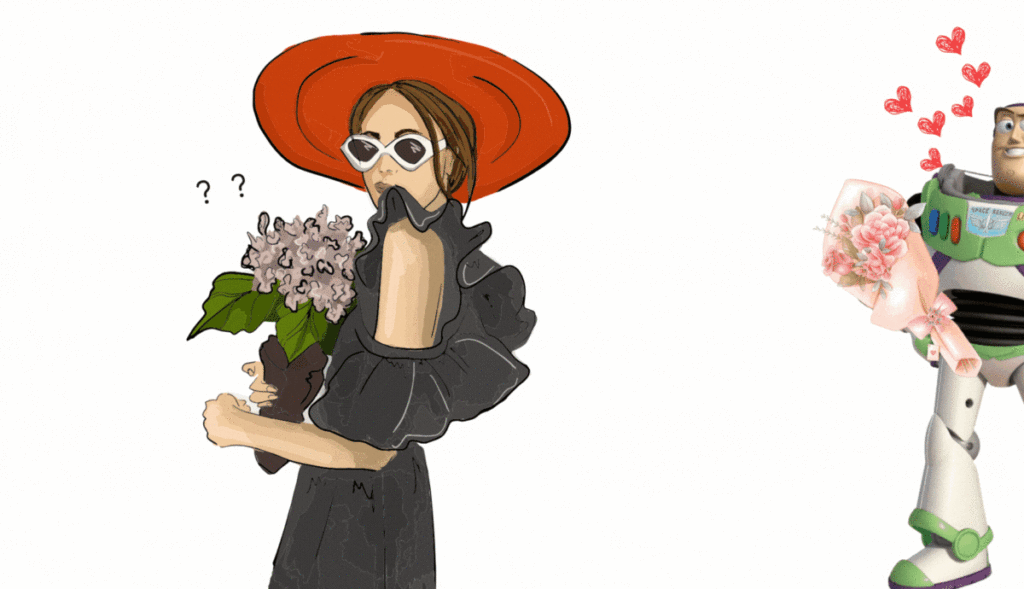



考えが変わりませんか?
家に帰って、薔薇の花束のプレゼントを発見、神様からの送り物だと思う?キモくない?
数日続いたら、警察に通報しますよね?
でも、少し視点を変えると、この物語ってとても“深い問い”を投げかけているようにも思える。
読み手が迷い、考えたくなる“分かれ道”だ。
一見、火縄銃で撃たれて当然じゃない?とも思えるんですよ。
行動や思考を読み取とり、心理学で言う投影まで見えてくる構図が分かってしまうと、とてもじゃないけど、感情移入しづらい。



どこがかわいそうなの?
自業自得じゃないの?
投影の図は明らかであり、それは良い・悪いの図ではなくて、構造の問いの答えとしては、兵十に自分を投影していることに気づきがない時点で、兵十は巻き込まれであるからだ。
けど、構造が分かっても尚、問いとして残すべきところがある。
- 『話せたかどうか』がすべての分岐点になる
- 『報われたかどうか』が、読者自身の価値観を照らす
① 『話せたかどうか』がすべての分岐点になる
読者である私たちは、ごんの想像する世界(心の声)を文字で読めている。
文字として書かれているから、話せるように思えてしまうトリックじゃないかとも思えませんか?
ごんは、話すことができたのかどうか?
という問い。
ひと言、



俺が栗や松茸を届けていたんだよ。
と言えていたら、結末はきっと変わっていたはず。
でも、そうはならなかった。
ごんが『話せなかった』のか、『話さなかった』のか。
ここが、読者の想像を大きく左右する大事な分岐点になると思う。
この物語の全体を俯瞰的に見たときに立つ問いは、そこしかない気がする。
あとは、ごんの孤独の投影でもあり、ひとりよがりな行動を示す物語。
現代版で表すなら、ストーカー物語にしか見えてこないからだ。



構造的に、答えが存在する場所ばかりになる。
答えを曖昧にしてはいけない、子どもを導かないといけないと思うから。
そこを曖昧にすると、子どもが遭難する。
それを前提としたときに、さらなる問いが生まれるはず。
② 『報われたかどうか』が、読者自身の価値観を照らす
物語の終わり、ごんは兵十の火縄銃で撃たれて死ぬ。
その直前、兵十はようやく



お前だったのか……
と気づきます。
でも、それはごんが命を失うほんの一瞬前。
ここで問いが生まれる。
ごんは気づいてもらえたことで、報われたの?
報われたのか?という問いの先にあるもの
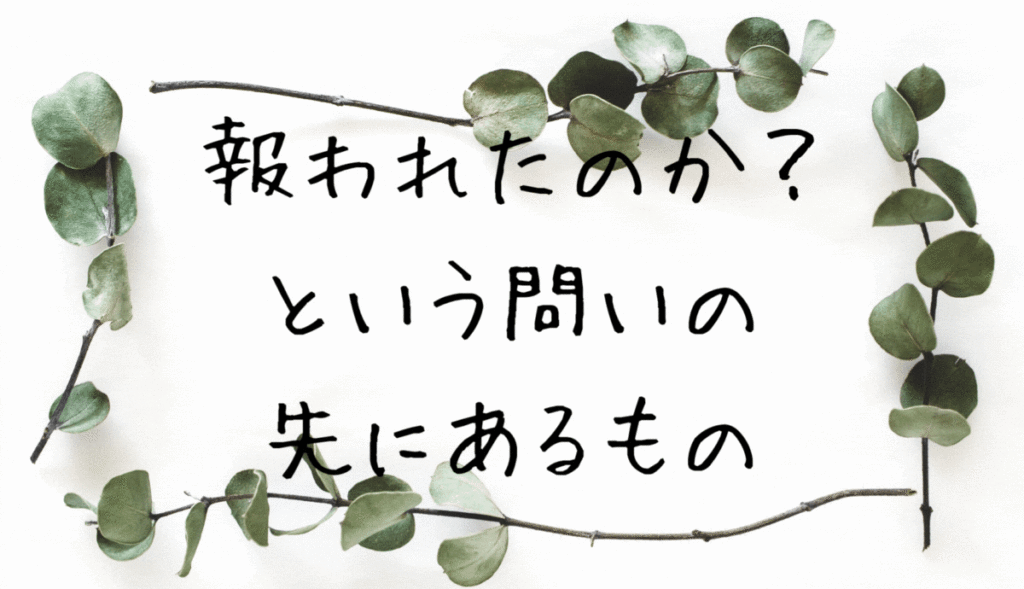
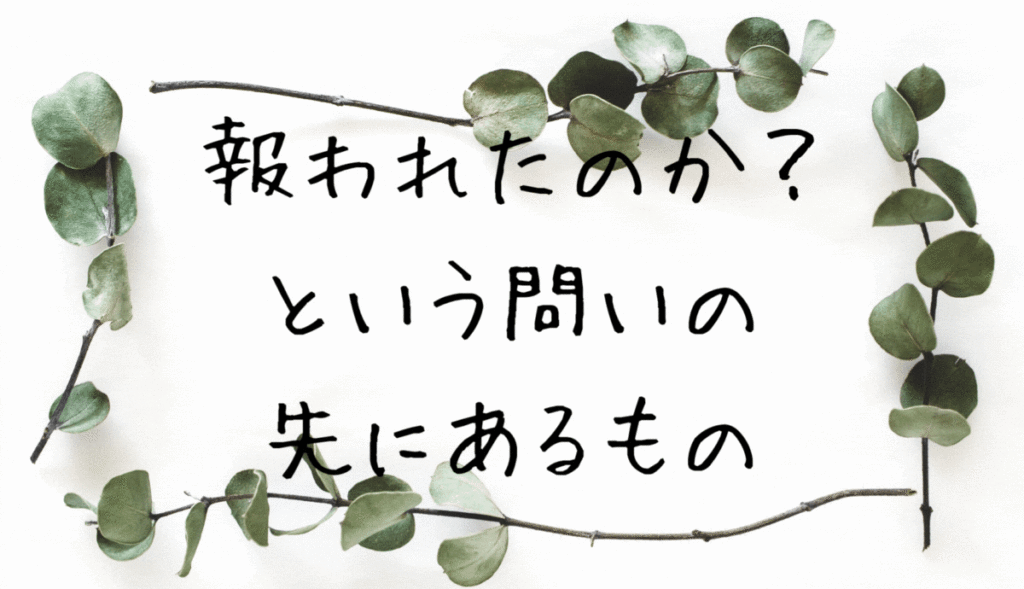
- ごんの行動は自分のためだったのか、兵十のためだったのか?
- 兵十の最後の一言の解釈
- ごんは、報われたのか?報われないのか?
① ごんの行動は自分のためだったのか、兵十のためだったのか?
栗とか松茸とか、めっちゃいいやつ届けてる。でもそれって、本当に“兵十のため”だった?
わたしは、自分のための行動だったと思う。
なぜか?



俺にお礼も言わずに神様にお礼を言うんじゃぁ、ひきあわないなぁ。
つまらない。
って、言ってたから。
……それ、見返り前提。
もし“ありがとう”が欲しかったなら、それって相手のために見せかけた自分のための行動だ。
でも結果として兵十は食べ物を貰えて助かってる。
ごんに、自分のための行動だという自覚があったのかどうかも、分からない。
恐らく無い可能性が高いとも読み取れる。
それはごんの育った背景を考えたら分かりやすいかもしれない。
② 兵十の最後の一言の解釈



ごん、お前だったのか…..
神様だと思っていた、松茸や栗を届けてくれる存在=自分が嫌っていた悪戯狐のごん。
意味が分からなかったと思う。
物語を読んでるわたしたちは、理由が分かるけど、兵十の頭には『なぜ?』しかないと思うから。
その先に来るのは恐らく、後悔の念じゃないだろうか。
③ ごんは、報われたのか?報われないのか?
ごんは『伝える努力』をしなかったのか、できなかったのか分からない。
兵十の一言、



ごん、お前だったのか…..
によって、やっとごんの行動と思いが届いたんだろうと思う。
そう考えると、報われたに違いない。
ただ、そこからだ。
兵十に火縄銃で撃たれることまで想定していないだろうから、もしかしたら、ごんを撃ってしまったことの後悔を兵十に負わせたことになる。
そこまで行くと、報われた後に、何とも言い難い後悔が残った図とも想像できる。
ごんぎつねは、何を読む物語?
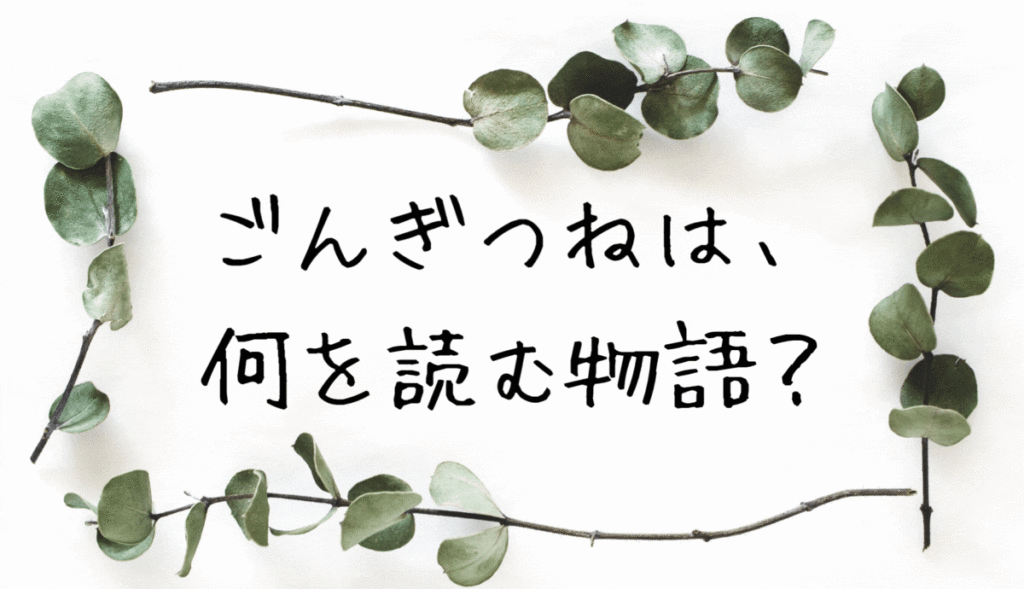
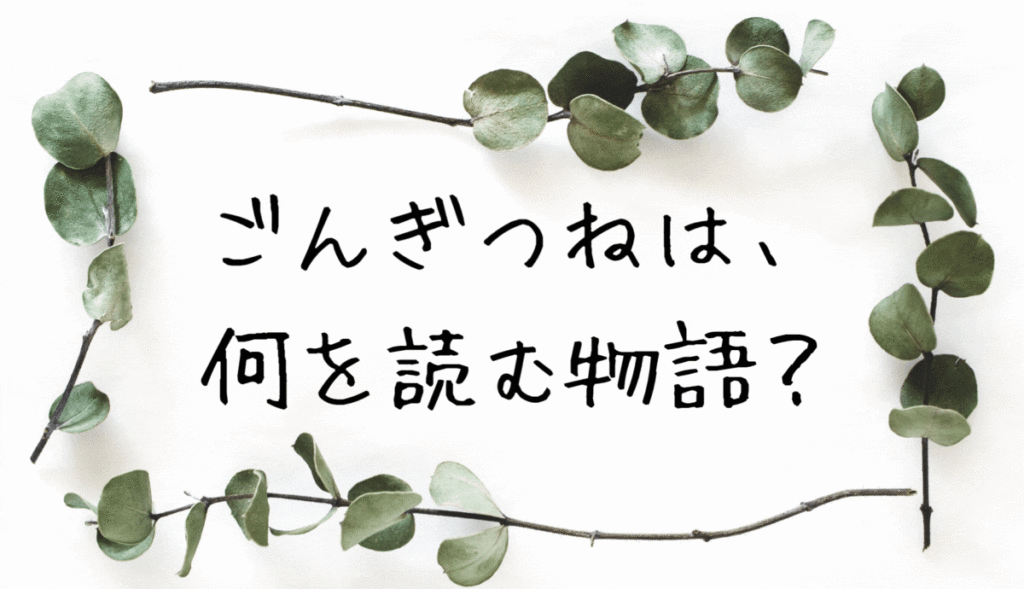
『ごんぎつね』って、小学生向けの読み物とは思えないほど、鋭くて重たいテーマを抱えてますよね。
ただ『かわいそうだったね』で終わらせてしまうには惜しい、問いの宝庫でもある。
そこから、何を子どもに問うてほしいか?
- 親のいない小ぎつね・ごんの孤独って、どんな孤独?
- 親がいたら幸せ? ほんとうにそう?
- 孤独からくる行動って、どう人を動かすんだろう?
- 善意って、何?
- 善意は伝わらなかったら、意味がないの?
- 誰かを思う行動って、どこから“やさしさ”になるの?
- 言葉とは何か?
- 自分のための償いが、誰かを助けることもある?
こういうものを問うて欲しいと思う。
こうした問いを渡してみると、ただの『昔話』ではなく、構造そのものが浮かび上がってくる。
たとえば
親がいなかったごんには、
『人との距離の取り方』や
『信頼の築き方』を
学ぶ機会がなかったのかもしれない。
だから、栗や松茸を届けながらも、兵十の前に姿を現す勇気がなかったのかもしれない。
“かまってほしい”という気持ちから悪戯をしてしまった可能性もあるし、『盗んだものを人に渡しても、喜ばれない』ことに気づけなかったのかもしれない。
きっと、自分も生きるのに必死で、盗みをしては食べている生活だった可能性だってあるからだ。
つまるところ、盗みをして食べて生活するのが、ごんのデフォだとしたら?
親という存在を知らないごんが、兵十に感情移入しすぎてしまったのかもしれない。
親=あたたかい、安心できる存在という思い込みからくる感情移入。
それと、孤独の辛さを誰よりも理解しているごん。
きっと寂しすぎたのかもしれない、だから兵十をひとりにしてしまったことの後悔、自分と同じ立場の人を作ってしまったと思えたのかもしれない。
兵十は、うなぎをただ単に、自分で食べようとしていただけかもしれない。
死ぬ前にうなぎなんて食べないだろうから。
人のことなんて、わからないもんね。
すべては、ごんの想像の世界から成り立つ話。
話せるか、話せないかで、ごんから見える世界も違ってくる。
自覚がない怒りなどは、通常、満たされなかった思いが潜んでいることが多い。
人はそれを他人に映し出す。
自分のための行動だという自覚が、ごんになかった可能性が高いと言えるのは、孤独という環境下では気が付きにくいからだ。
『善意』は、伝わらなければただの自己満足になることもある。
でも、それを“善意じゃない”とは、簡単に切り捨てられない。
助かっている兵十も存在しているからだ。
結果はどうあれ、行動できた自分に自負があればいいとは思う。
そもそも、伝える手段(=言葉)を持っていなかったとしたら、どうすればよかったのか。
文字も書けないから、文も渡せない。
ごんは
『わかってほしい』
『気づいてほしい』
という気持ちを行動で表そうとした。
でも、行動だけでは誤解が生まれることもある。
謝りたい、許してほしいと思って行動したのに、相手が気づかなければ、その気持ちはどうなる?
だからこそ、私たちが『言葉を持つ存在』としてできること。
それは、ちゃんと伝える努力をすることだとも思える。
こういう、視点を変えたら無数に出てくる見解。
だから、自分の子どもには、こういう感じで説明したんだけれど、説明の仕方も難しい。



ムッズ….(難しい)
って、最初なったから。
最初ストーカーから始まって、そこから噛み砕いて説明したら、納得してくれた。
でも、やっぱりここを抜きにしたら、『ごんぎつね』って、ただの『悲しい昔話』で終わってしまう気がする。
『ごんは話せたのか?』という問いが示すもの
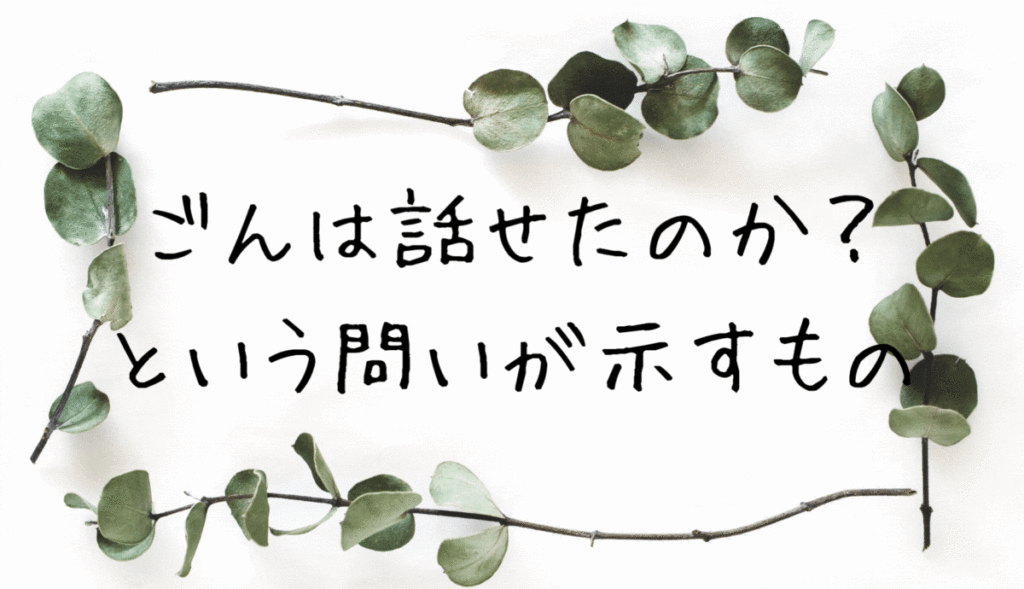
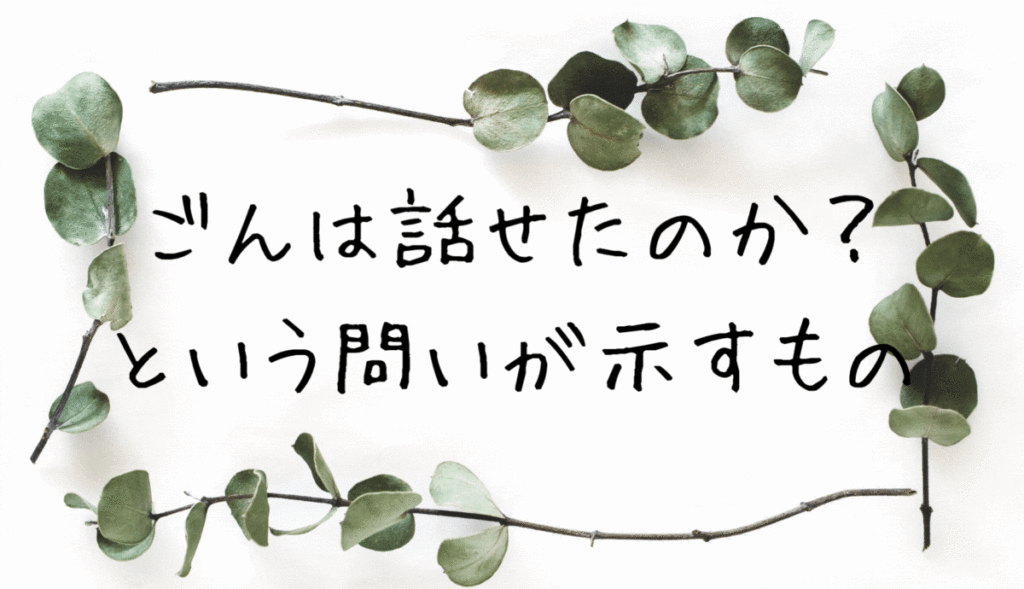
- 話せたとしたら?
- 話せなかったとしたら?
- 『伝えること』の意味と限界
① 話せたとしたら?
話せていたとしたら、



寂しい、遊んで、かまって、気づいて、理解して。
伝える手段が存在する。
言葉がないとすれ違いを生む構造がある。
だから、どこかで、



ウナギをお母さんに食べさせたかったの?
寂しすぎて、悪戯をしちゃったんだ。
お詫びに盗んだ魚なんて渡してごめん。
あんなことになるなんて、思わなかったから。
お詫びに、栗とか松茸を一生懸命さがしたんだ。
良かったら食べてくれない?
これが言葉で伝わっていたら、これで信頼を築くことができたはず。
だけど、できなかった。
環境がそうさせたのかどうか….
② 話せなかったとしたら?
でも、もしごんが本当に話せなかったのだとしたら。
これはもう、物語の構造として悲劇が“避けられないもの”だったことになる。
『言葉がない』という壁。
どれだけ思っても、どれだけ願っても、相手に伝わらないという現実。
つまり、ごんは『通じなさ』と『誤解』によって、はじめから詰んでいた。
努力したよ?栗とか松茸届けたよ?でも、それは誰からかもわからないプレゼントでしかない。
この場合、ごんは“哀れな犠牲者”ではなく、構造に閉じ込められた存在になる。
ここで私たちに突きつけられるのは、『想いが伝わらない世界で、どうするか?』
③ 『伝えること』の意味と限界
言葉とは何か。伝えるとはどういうことか。
この物語は、最終的に“コミュニケーションの限界”にぶつかる。
伝えたい、でも伝わらない。
伝える努力は義務ではなく、権利とも思える。
そして、それを持っているのが人間というわたしたちだ。
ごんが言葉を持たなかったなら、私たちは『言える者としてどうするか』を問われている気もする。
そして同時に、伝えずに想像だけで接する危うさも書かれている物語だ。
もしあなたが兵十の立場だったら、わからないまま撃ってしまったあとに、“すべて”を知ったとしたら……その悔しさもまた、“言葉がない世界の悲劇”にしかならない。
撃たせたことを相手に後悔させるよりも、わたしは自分と相手を尊重するために、言葉で伝える努力をしたい。
そして、できるだけ、相手の背景を理解したい。
もちろん、伝わらないときもある。
だけどそれは、相手の選択だから。
そこには侵入できない。



じゃないと、撃たせてしまった自分をまた悔いる。
だからこそ、伝えられることは、伝えるように、自分と相手を尊重できるように、そうして生きている。
意味分かるかな。
相手を理解して、そして伝えて、伝わらないものがあるのなら、それは相手に撃たせても・自分が撃たれても悔いることがないでしょう?
一番嫌なのは、自分が何もできずに誤解が生じて撃たせること。
後悔と言う、余計な痛みが生じる。
余計こじれたかな。笑
後から、自分に言い訳なんてしたくないんだって。
『ごんは話せたか?』
という問いを立てることで、この物語の読み方は180度変わる。
ストーカーか否かじゃなくて、言葉があるのに、
伝えないのはなぜ?
伝えられないのはなぜ?
言葉を持つ私たちは、大事なことを、ちゃんと伝えているか?
- 謝りたい相手に、謝れているか。
- 伝えたい想いを、届けようとしているか。
もし、ごんが“話せた”のに伝えなかったなら、それは、孤独からくる無意識の承認欲求だ。



誰か、俺に気づいて。
悪戯なんて、しなくても良かったんだよ。
ただ側に行けば、構ってもらえたかもしれない図も存在したかもしれない。
けど、悪戯をするごんだから火縄銃で打たれたのか、きつねだから打たれたのか分からない。
人を信用することもできなかったかもしれないよね。
ごんぎつねと白い帽子
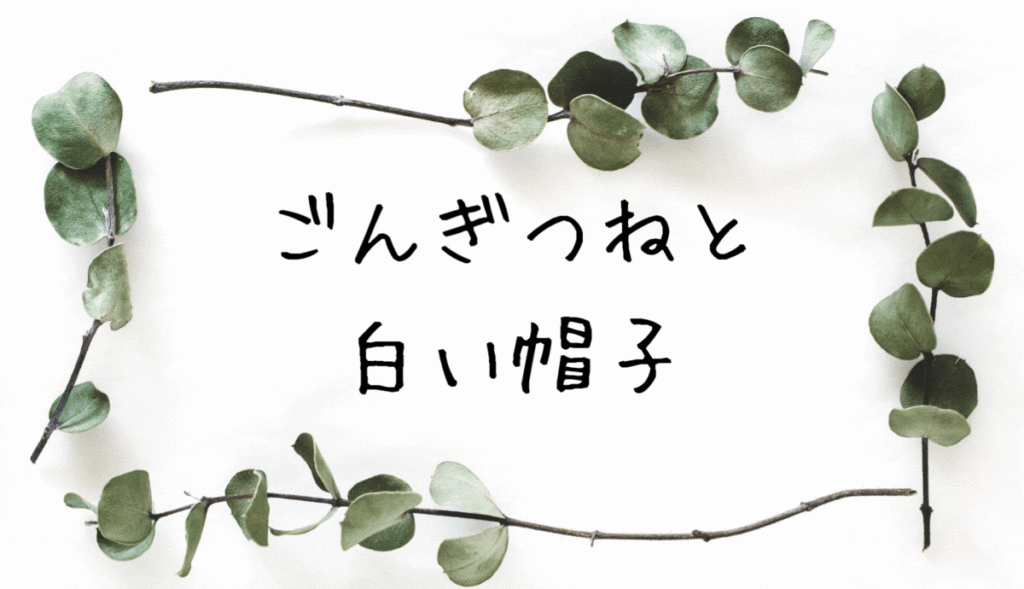
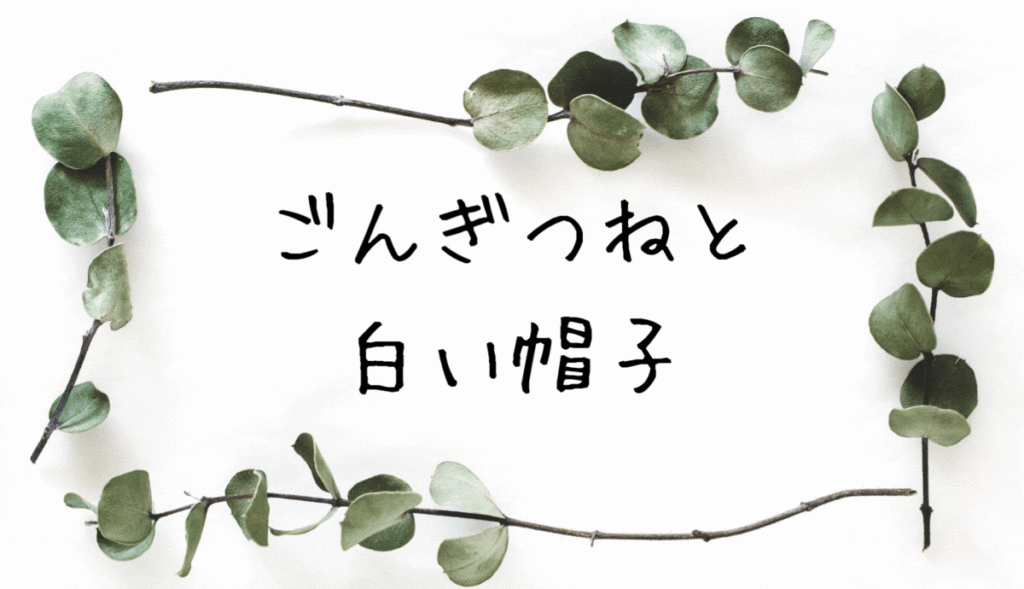
小学校国語の教材として広く知られる『ごんぎつね』や『白いぼうし』。
『登場人物の性格を想像しましょう』『気持ちを考えましょう』みたいな、感情理解を中心としたアプローチをみるけれど、それは本当に合ってる?という疑問が立つ。
『白いぼうし』で問うべきは、松井さんの『性格』じゃなくて、その行動から想像するやさしさの方でしょう?
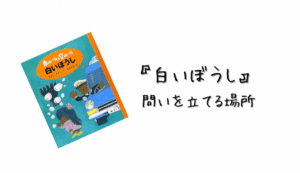
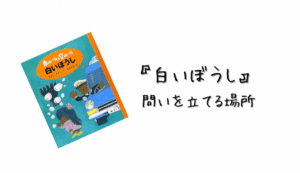
白い帽子を気にかけ、夏みかんの匂いにお母さんのやさしさを重ね、少年を思い、静かにシャボン玉のはじけるような声を受け取る――そこに見える“他者理解の構造”を読まずに、『松井さんってどんな人?』という問いでは、物語の核を見失っちゃうんですよね。
想像できないでしょ。
構造を読むって、登場人物の行動や関係性、その背景を手がかりに、物語全体の意味を捉えることだから。
同じように『ごんぎつね』でも、ごんの性格に注目させる指導案も発見、そこは想像ではなく、明確な構造が語られているべきで、ごんはやさしいキツネとかじゃなくて。
ごんは孤独なキツネ、いつも悪戯をしているキツネ、そういう行動目線が必要で、ここが出ないと意味がない。
想像する力も必要だけど、そのためにはまず“見えている事実”を押さえる力がいる。
ごんぎつねで、どちらが悪いという裁きの話だけで終わってしまうと、問題を解決するときに、手段が分からなくなる。背景の読み方が分からないから、解決法も分からず、事態が悪化する。
この物語は、裁きの物語じゃないと思う。



だけど、構造を知ったうえで『どちらも悪くない』と思うのであれば、意味を持ってくる。
構造を理解したうえで言う『悪くない』
→ 行動の背景やすれ違いの原因を踏まえた上での、判断と言語化。
→ そこには『改善点』や『教訓』も含まれてくる。
→ 『じゃあ、どうしたらよかったのか?』という思考につながる。
構造を理解せずに言う『悪くない』
→ 感情の一時的な緩和、対立回避のためのスルーに近い。
→ 問題の本質に触れてない。
→ 『考えたことになっていない』状態。
構造が分からないって、ものすごい人生になっていくの分かりますよね。
これが人生のデフォルトになるから。
どこ歩いてるか、分からないと思う。遭難に近い。
思考もブッツブツ切れて、導線が無くなる。
なぜなら、構造がわからないから、それはどっからひっぱってきた導線か?
これが無くなるんじゃなくて、最悪消えるのよ。
だけど、本人はその導線が正しい導線だと思ってるの。
電気はいつまでも点灯しないのよね。
暗いまま。だけど、暗さにも気づけない、なぜなら明かるさを知らないから。
構造が見えないときに起きる『ズレた正義』や『自己投影』
極論ですよ。



ごん君は悪くないでしょ?
プレゼントくれてるんだよ?
貰えるの当然だと思ってない?
プレゼント探すのすごく大変だったと思うよ。
感謝の気持ちはでないの?
毎日のプレゼントが気持ち悪い?
彼の一生懸命がわからないの?



知らねーよ。
視点違い過ぎて異次元だって。
感情は個人個人違う、構造は答えがあるから、そこを曖昧にしたらダメだと思う。
曖昧にすると、ワケ分からないアドバイスや指導が出てくる。
- 文章が飛んでても気づかない
- 論理が飛躍してても、飛躍にも気づかず『ま、いっか』
- “なんか変”を気づかずにスルーしてきた蓄積が、その人のデフォになる
→ 結果として、『問いが立たない人』『他者の構造に興味がない人』が育つ、この図の怖さ。
① 感情の正当化による“免責思考”
でも、ごんは孤独だった。かわいそうだった。
→ 可哀想=無罪 という感情の免罪符が発動。
→ その背景の構造や、他者との関係性の構築を問わなくなる。
この思考の危うさは、『苦しんでいる人なら何をしても仕方がない』という論理飛躍を正当化してしまう点。
しかもその苦しむは、自分目線の苦しさ理解。
② “自己の投影”が構造理解を上書きする
私だったら貰って嬉しいのに、ひどすぎ!
→ 自分の感情と登場人物の背景を無理やり同一化してしまう。
→ “相手の立場”を想像する力が弱まり、共感とは違う“自己基準化”になる。
つまり、『感情移入のように見えて、実は自己の物差しでしか考えていない』状態。
他の意見はスルー。
そうなんだ、で終わる。
| 誤読パターン | 特徴 | 落とし穴 |
|---|---|---|
| 感情の正当化 | かわいそうだからOK | 行為の因果関係を見失う |
| 自己投影の過剰 | 自分だったらこうする | 他者理解の放棄 |
| 一方的な要求 | プレゼントしたんだから感謝して当然 | 関係性の対等性が抜ける |
| 恣意的読解 | ごんは頑張ったんだから許される | 他者視点が存在しない |
『構造がわからない』ことの本質的な怖さ
- どこから来て、どこへ行くのかが分からない
→ 情報や感情に流される。意味の因果や背景がつかめない。 - 思考がつながらない・導線がブツブツ切れる
→ 表面的な連想にすり替わる。
『なぜそう思ったのか?』に答えられない。 - それでも本人は“自分の考え”だと思っている
→ ここが最も厄介で、“自分らしさ”が“思考停止”と紙一重になる瞬間。
善悪を問うことではなく、関係性の破綻をどう読み解くか。
そのための“背景理解”と“構造の読解”こそが、問う力を育てる鍵になる。
『ごんぎつね』は、子どもたちが現実社会でも活かせる“思考のモデル”だと思う。
子どもに『問いの持ち方』を教えるというのは、“人生の明かり”を手渡す行為だから。
まとめ※子どもと一緒に問いを育てるために



ごんはやさしいと思います。
松井さんはやさしいと思います。
……わかる。気持ちはすごくわかる。
でもそれ、“気持ちで読んで終わり”の国語の図。
想像力って、確かに大事なんだけど、それだけじゃダメで、
『なぜそう思ったの?』
『どの場面からそう感じたの?』
って、根拠と構造をつかむ問い返しがないと、ふわっと感想文芸大会になっちゃう。
“心を読む”前に、“構造を読む”。
『白いぼうし』みたいに、構造を問わせるでも、松井さんから見た世界を問わせたらダメで、それは投げかける構造だから。
生徒に投げかける構造(問い)と、問わせる構造を間違えたらダメで、最終的にどこを問わせるべきか?ここが最大の重点だと思う。
正解のない問いを、正しく迷えるように整えないといけない。
つまり、“問いを持たせる”じゃなくて、“問いが育つ場所を用意する”。
読解って、答えを出すことじゃなくて、
『なぜそう考えたか』
を言語化するプロセスそのものだから。
『自由に考えていいよ〜』って投げっぱなしにするんじゃなくて、“構造のどこから問いが出るのか”を、一緒に掘るのも大事。つまりは問い方への導きだ。
これが、“考える国語”の第一歩になると思う。
何にせよ、問う力が生きる力になることは、間違いない。
まとめ※ごんぎつねの真実は?
記事をまとめた後に、ごんぎつねについて、色々調べてみた。
小学校では、色々物議をかもしている物語らしいってのも理解できた。
あれを子どもだけの責任にして、構造理解も教えず、感情理解を主軸に置いた教育が蔓延しているとしたら、愚かだと思う。
素直に読めばその考えにいきつくと思いますが、もっと文章の“テクニック”的な面から話すと、最後の『筒口から青いけむりが細く出ていた』という一文。ここが悲しみを現した表現になっています。



なんでそれが読み取れないのですか?
読解力が乏しすぎます。



知らねーよ。
そもそもが、ごんの孤独について、構造的に説明が足りて入れば、
『もっと松茸貰えたのに。』
こういう回答はでないと思うけどね。
雑に孤独って説明されてもさ、子どもはさ
『へーひとりなんだー』
で終わる子もいるよ。
青い煙ひとつでもさ、あの色の象徴するものは?
じゃなくて、
- なぜ作者は“青い煙”を最後に描いたのだと思う?
- この“青い煙”は、ごんにとってどんな意味を持っている?
これなら分かるよ。
物語の構造を問わせてから聞かないから、変な答えが出るんじゃない?
で、多様性とかクレームが来るの巻。



わたし、ごんの孤独について一生懸命説明したじゃない?
最後、火縄銃で撃たれたじゃない。
あなた、栗と松茸もっと貰えたのにって思う?



は?思わないでしょ….
ほらみろ。普通はこうだよ。
そこは別記事にまとめようと思う。
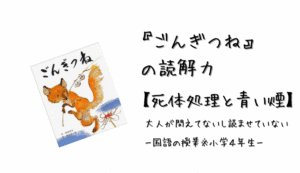
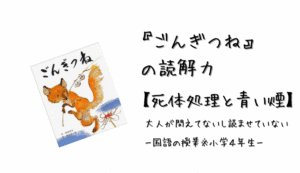
そして、衝撃の事実を知るの巻。
1913年(大正2年)、愛知県知多郡半田町(現・半田市)に生まれ、29歳にして結核で短い生涯を終えた新美南吉。
4歳で母を亡くして6歳で継母を迎えるものの、異母弟が生まれた後に8歳で養子に出されるという、孤独な生い立ちを持つ。
↓そして、ナニコレ?っていう記事も発見する。
こういうの書いたりするから、情報が曲がって伝わるんじゃないの?だけど、ものすごいヒントになったよ、ありがとう。
ヨシ、M子との恋愛を探ろう….
『求愛』説を唱えた岩沢文雄さんは、『作品『ごんぎつね』は、求愛のうただ。うたの美しさは、孤独な魂が愛を求めて奏でる、哀切のひびきの美しさだ』(『文学と教育その接点』鳩の森書房1978)と熱く主張しています。
その背景には、新美南吉の当時の恋愛体験があります。ごんぎつねが書かれたのは、南吉が弱冠18才の時。その頃の悩みに悩んでいた恋愛が反映されていると考えられているのです。南吉は詳細な日記を残しています。そこには、M子さんへの熱烈な思いと、いろいろな事情からそれが決して結ばれることのない恋愛であることが綴られています。
物語のラストに注目してください。『ごん、お前だったのか。いつもくりをくれたのは』と兵十が声を掛けます。ごんは、最後に自分がプレゼントしていたことに気づいてもらうことができました。南吉の書いた草稿が残っていますが、そこでは『権狐は、ぐったりなったまま、うれしくなりました』と書かれています。つまり、自分の存在に気づいてもらって、うれしい気持ちで死んでいくのです。
『ひとりぼっち』だったごんの心の空白は、兵十の一言によって満たされます。この物語は、心を通わせる相手を求める話だと言えるでしょう。たしかにそれは『友』というより、『愛』を求める物語と言っていいかもしれません。自分の存在に気づいてもらいたい、そう思い続けながら、せっせと相手に愛を捧げる話なのです。
ようやくわかってもらえた時は、命が尽きる時だった。このアイロニー(皮肉)に満ちた結末には、やはり南吉の切実な願いが込められているようです。
勝手な解釈してるなぁと思うわ。
そして、こういうPDFを見つけました。
この作者である、新美南吉は、恋愛の本質を知っていた方で、嘘って言うのは、自身の渇望とM子さんの渇望に気づいたんだよね。
だから、M子さんとの結婚に踏み切れなかった。
自己理解への意識がすごかったんだと思われる。
世間で『恋愛』と名前のついているもの。
新美南吉にとってみたら、それは自身とM子、両者の『渇望』という存在に気づいたことで、嘘のものになった。
だから偶然出会った狸と狐が、たまたま恋人同士として遊んで…という表現になったのだろう。
互いに自身の渇望を埋められるものを探しただけに過ぎない遊び、ということだ。
これを恋愛として成立させるには、互いが自分の渇望に気づいていることが条件になる。
渇望に自覚的でないと、対象に飽きる、それでも渇望は続く。
導くこともできはするけれど、南吉の生い立ちを想像するに、不可能に近い。
自身の船がどろ船だ。人を乗せても沈む。
次にお付き合いすることになった女性に
『できる限り愛し合おう』という、
『できる限り』という表現が使われていることから、
そういう気づきが起こったと考えられる。
心理学者のフロイトとの、年代を並べてみると、
フロイト
生年:1856年
没年:1939年
主な活動時期:1880年代〜1930年代
新美南吉(にいみ なんきち)
生年:1913年
没年:1943年(享年29)
主な執筆活動:1930年代前半〜1943年(ごく短期間)
- 1932年(18歳):『ごんぎつね』執筆
- 1940年:教員として正式採用、教育と創作を並行
- 1943年:死去(病死)
重なってはいるけれど、当然心理学の知識なんてない状態だと思う。
私もそうだけど、知識がない状態で色々知っていって、後から書籍で知識と整合性を確かめるという形だから、恐らく幼少期のトラウマから来る構造を先に見抜いてしまっていた可能性がある。
しかし、この時代、整合性を確かめられるような書籍は存在しないだろうから、ずっと考えたんだろう。
相手の女性M子さんは、



あなたが女性を不幸にしてしまうと言うのなら、わたしはその不幸な女になりたい。
とまで言っていたけど、その本質的な意味はM子さんは気づいていなかった。
そういうのを見抜いたのかもしれない。
気づいてしまって、辛かったのかもしれない。
相手も気づかないと、どの道無理がくる(つまりは破綻する)。
通常は、こういう言葉って言われたら嬉しいと思う人もいるのかもしれないけれど(大半こっちじゃない?)、嬉しいと思ってしまうのが、恋愛と名前がついているものの罠だ。
南吉にとってはエグられたのではないだろか?
恋愛と名前が付いているものの真理、つまりは自己の渇望からくる欲求を見抜くからだ。
この言葉は、M子さんからの渇望だものね。
この言葉のロジックに気づくまでに、時間がかかってしまった。
ひっかかったから、ずっと考えてたどり着いた先が、これって、自己愛?不幸になろうが、南吉の側にいることで自己重要感を満たす感じ。
じゃないと、こんな言葉出てこなくない?っていう洞察。
側にいれれば不幸でも構わない。
これって…..違うよね。
こういうとき、わたしなら何て言うだろう?
と想像してみた。
多分、



不幸かどうかをお前が決めるな。
それは私が決めることで、お前が決めることじゃない。
わたしは不幸にはならない。
なぜなら、わたしがそう思わないからだ。わたしが、側にいると決めたから、そうしたい。
こんな感じで返すと思う。
まぁ、『お前』呼ばわりしだ時点で、南吉もびっくり。
詰んでるんだけどさ。
だって、何でお前から不幸を作られないといけないんだよ。
添えねーよ。



わたしも、添えません。
(なんて傲慢な女だ)



まぁ、あらかた、そうなるよね。笑
だって、わたしに投影しそうだから。笑
だって、
『わたしはあなたを不幸にしてしまう。』
この表現もおかしいよ。
一見、相手を思って発言されているようにも思えるけど….



あなたの幸せは、わたしが決めるのだ。
あなたが選ぶより、わたしの見立ての方が上なのだ。
こう聞こえるのはわたしだけ?
傲慢に見える。
となると、やっぱり自己理解があまり進行していないかもな….
言葉だけをすくいあげると、両者共に、自身の欲求しか見えず、他者が存在していない。
M子さんに、何を伝えていいかわからなかったのかもしれない。
自分がトラウマを抱えてはいるものの、何を伝えるべきか、自分の渇望が分からない状態。
つまりは、どうしたらいいか、分からない状態。
けど、感情だもの。
コントロールが難しい。
新美南吉は、自己理解への意識はできていたけれど、不完全。
自己一致までは到底行きついていない。
- 幼い頃に母を失い、心の空白がある。
- その空白を埋めたいけれど、『どんな関係であればそれが埋まるのか』がわからない。
- 結果として、『他者との関係に期待するけれど、満たされる保証がなく、伝えられない』というループに陥る。



不安型愛着スタイルもあったかもしれない。ただの、想像だよ。
けど、これに本人がぼんやり気づいてて、言葉にできなかったのかもしれない。
できてたら『ごんぎつね』は生まれてないと思う。
新美南吉の内面構造についての仮説整理
- 心理学の知識を持っていた可能性は低い
- 幼少期のトラウマ → 無意識の構造感覚に繋がっていた可能性
- 自己理解への意識はあったが、不完全、自己一致までは至らなかった
- M子との関係は、“感情の構造的破綻”を予感していた
- 結論として
① 心理学の知識を持っていた可能性は低い
- 恐らく心理学は学んでいない
- けれど、『ごんぎつね』や日記に見られるような内省の深さからは、“感覚として”人間の心理構造を掴んでいた可能性が高い。
- 特に『伝わらなさ』や『無理解の悲劇』というテーマは、フロイト的な『投影』『無意識の動機』そのものにも見える。
② 幼少期のトラウマ → 無意識の構造感覚に繋がっていた可能性
- 幼少期に母親を亡くしており、『喪失』『断絶』への強烈な感受性を持っていた。
- 感情や関係の齟齬をただ『寂しい』で終わらせず、構造として認識する力があったんだろうと思われる。
③ 自己理解への意識はあったが、不完全、自己一致までは至らなかった
- 自己一致は、自己の感情や価値観を受け入れながら、現実に柔軟に応答していく状態。
- 南吉は、自分の『孤独』『伝わらなさ』『分かってもらえなさ』に対する鋭い理解はあったが、それを生きる中で整理し、昇華していくには未達だった可能性が高いと推測。
④ M子との関係は、“感情の構造的破綻”を予感していた
- 『巻き込んでくれ』と願った相手が、自分と同じ階層の痛みや構造に気づいていない。
- その時点で、南吉はどこかで『この関係は成立しない、破綻する』と、理屈ではなく肌感覚で悟っていたのではないか。
- けれど、理性と感情がズレたまま、意識的に破綻とした。つまりは、自己防衛。
⑤ 結論として
南吉は自己理解への意識はあったが、不完全で、自己一致には至っていなかった。
むしろ、それゆえに文学として形になったのかもしれないとも思える。
なぜなら、整ってしまったら、表現されない感情というのは、あるから。
構造が分かるからね。
だとしたら、あのごんぎつねは、人間とキツネだもの。
どうしても相いれない何か?が書かれた可能性が高い。
話せる、話せないでもないかもしれないけど、その見解の方があの物語の構造としては正しいのかもしれない。
けど、もっと深いやつだな。
ごんが持って行ってた、栗や松茸は愛情じゃなくて、渇望の方かな?それに気づいてもらいたかったんだな。
彼女に理解して欲しかったけど、何も理解されなかったと感じたのかな。
村人には理解すら、して欲しくもなかったんだろう。
そして、最後のシーンを想定すると、自分が理解してほしい、という愛情を求めていたことに気づいたのかもしれない。あれは、M子さんとの切ない恋愛物語だよ。
となると、ごんぎつねが書かれているところを想像するに…
自分が想像していた彼女像は、自分の想像でしかなかったということだろう。
兵十から見た自分と、自分から見た兵十に乖離があることから、そう取れる。
だって、感謝どころか、最後に火縄銃向けられたんだから。
そして、最後に撃たれているのは、理解されたかったという自分を理解できたことに気づいて、昇華できた。できたのかな。
それが『ごんぎつね』だろう。



わたしは、こう読むんだけど、あなたはどう思う?
『報われたと思える幻想』を持って死ねた話。
分岐多すぎて草…になった。必要なパラダイムに気が付かないと、枝がすごい出てくる。
パラダイムが増えたり、減ったりする、そして最後に出てきた枝を1本にしたのが、M子さんの『不幸な女になりたい』、あそこだった。
これで、わたしの中でようやく全部落ちた。
他にもあるのかもしれないけれど、気づけないわ…限界を感じる。笑
わたしもまだまだ、浅かった….
物語を読むっていうのは、作者の背景も知らないといけないという事実も浮かび上がる。
ブログを上げてから数日たった今日、また新しい見解を思い付いた。
兵十もごんもどちらも自分説だ。
兵十は自分の投影、ごんは自分自身の渇望。
兵十に自分を投影しているとなると、投影先にはM子もいる。
M子を通して、自身の渇望に気づいた気づきの物語という説。
こういうパラダイムを思い付く。
最後、自分自身の渇望に気づき『お前(理解されたい寂しいと感じていた自分)だったのか…』と、気づきはしたが、虚しさだけが残るという説ね。
つまるところ、自己理解が進んだ話。こちらの方の線が濃厚か。
青い煙で終幕。
『兵十=M子=自分』説だ。だとしたら、投影の物語。文才である南吉が、兵十に自分を撃たせたことの後悔を負わせたのが不思議だったから。
自分と自分の方が納得が行くのかもしれない。
だとしても、やっぱり問うべきところは変わらないと思う。
話せる、話せない、伝える、伝えないの話でいいと思う。
最後に、自分への理解の話を付け食わえたらいいだけだ。人を分かるためには、自分の理解が必要だということを。そのためには、自分との対話も大事だという見解でどうだろうか。
自分との対話がないと、自分ともどんどんズレていく話。
個人的な話だけど、心理学の人よりも、わたしの方が気づくのが遅かったかな。難しいよ。笑
と思ってたけど、そうでもなかったのか?
言えないのか、言わないのか知らないが。なんだそれは。
自身の投影に気づきもせずに描いた物語であれば、渇望はあっても自己理解には遠いのかもしれない。
では、あの投影とも思える物語で、何を子どもたちに教えることができるか?
という問いが立てば、話せる・話せないの問いで良いのではないか?と思える。
というか、話せたか?話せないか?という問いで十分論理展開できるし、楽だろうと思っていたら、作者の背景を調べたら、どえらい物語が潜んでいて、びっくりしたという記事になった。



頭がもげるかと思った。笑
けど、考えることが楽しかった。
物語解体(できてるか分からないけど)が。
あぁ、お話は切なかったけどね。
解体した分、痛みも知るからなぁ。
しかし、これが正解だとすると、この物語もすごいな。
白いぼうしに続いて…皆、困惑だよ。
結果、問う場所は変わらないと思うんだけど、どう?
小学4年生では『伝えることの大切さ』でいいんじゃないだろうか。
これは、高学年に行くにつれて段階的に、内容を掘ってもいいような気もするが、どうなのだろう。
あまりにも複雑すぎて、次は中学校か、高校生くらいが妥当なのかもしれない。
まとめ※最後教育について
結局、良い物語は無数に存在すると思う。それを、良いか?悪いか?あれは誰か?という表層的な面だけ教え、東洋的模倣という中途半端な教育が、この日本じゃないのかと思う。大人も子どもも全員だ。
読解力を子どもだけに問わせるのはどうだろうね。



異議があるなら、子どもにだけ疑問符が立つこの構造に、子どもたちの発言に愕然とするその根っこを問うたらどうだと思うわ。
なぁ、教科書製作者。
それでも『それは、こっちの責任じゃないでしょう?』で、終わるのならどうかしてるって。
その稚拙さをちょっとは反省したらどうだ。
パズルのパッケージだけ見て、完成した気になってんじゃないよ。
まぁ、それだけが原因じゃないけどさ。原因の一部ではあると思うよ。
時代の流れも読めよ。
情報がどれだけ早く子どもに伝わると思ってるんだ。
ずっと後手に回るから、こうなるんじゃないの?
後手っていうか、普通さ、構造が正しく問えていたら、時代背景なんて問わずに教育ってできるものだと思うけど。
それを表層ばっかり取り扱うから、時代遅れになるんだって。



この、時代遅れが。
結局問うべきところは、変わらないのよ。



なんでそれが読み取れないのですか?
読解力が乏しすぎます。



そのままそっくり返すよ。
もっと厳しく言えば、教科書という大きなものが変わるのには、膨大な時間を要する。
ということは?だ。
教育現場での教育と、親の教育の質が問われるという問いが出てくるのは必然になる。こちらが先手を取る必要が出てくる。
だから、わたしは試行錯誤で子育てしてた。
自分だって、何が正解かなんて分からなかった。
こども園から小学校、ひとりで何度腹が立ったか、泣いたかわからない。
だけど、一部の結果を見ると、どうだろうね。
徐々に成果が出てきている。



コミュニケーションも難しくてね。
ようやく自分の着たい服が着れるようになった。
最初から、今着てるような服着てたら誤解もすごいだろう。
元々派手なんだよ。
がしかし、そんなことで、躓くワケにはいかないんでね。
合わせにいかないといけない。知ってもらうまでは。
ブラウス、チュニック、ベタ靴なんて興味ねーよ。
ピグメント加工着たかったけど、それすら避けた。
髪の色も戻してたし。
まぁ、それでも、色々なものを、この時代に生きる子どもだけの責任にし、放棄するのも自由は自由だものね。
我々の時代は….(爆笑)。
つまるところ、楽だ。
けど、わたしはそれを、批判はしない、なぜなら、わたしは背景が読み取れるからだ。
わたしが子どもの頃に見た、あの大人がまだ10割近い。
裸の王様の国民がたくさんいる。
多勢に無勢。
多勢に無勢になる理由すらわかる。
認めることは辛いことを十分に知っているからだ。



誰もが、あなたみたいに強いと思わないで!
自分が一番正しいと思うな!



別に強いワケじゃないよ。
自分の意見に自信持ってないと、人に意見するのは失礼だと思ってるだけだよ。
意見があるなら、言ってきたらどうなんだ…けど、もう、言わないよ。
だから私は、人に期待するのを止めていた。
責めずに全部自分で負う。
じゃないと、生きづらかったから。
誰も分からないから。
だから、物事を分かりもしない、分かろうともしない者たちは、表層だけ掴んでる者たちは、何の物体なんだろう?
こんな感じだ。
実は、そこに子どもを預ける覚悟もいった。
けど、やり切る覚悟も持った。
持たないと、子どもに顔向けできないから。
だから一人で、子どもと一緒に戦う選択をした。
ビニールティッシュを持って行っただけで、



箱ティッシュじゃないと学校じゃ使えないの。
このレベルと話すと吐き気がする。レベルを問おうとも思わないレベルだ。
相手は巨大な組織にいる。
このレベルなのに、頭相当使わないと戦えない。
組織にいなければ、一瞬なのに。
たかだか、組織に属してるだけのくせに。
それを自分の力だと勘違い。
何て滑稽なヤツ。
何が腹が立つって、このレベルで我が子に接するということだよ。
逆鱗に触れるレベルだったよ。
その先生が、とかじゃなくて、我が子に接することがね。
先生は別に、好きに生きたらいいんじゃない?
人生観も分かるし、こういう滑稽な人に興味ないから。
担任過ぎてから、すれ違い会うと、



成長されましたね!
最近は、目をキラキラ輝かせて授業に取り組んでいますよ。



あらあら、こっちが引いてるのわからないのかしら。
こういう発言に。
気味が悪い。
目がキラキラ?浮いた台詞だこと。
わたしの目的は何だ?
子どもが学校で過ごしやすいことだ。
だから、的をひとつに絞った。
我が子が不満を言うところ。
そして、そういう者を人生でどのように理解していくか?
という導きという名の教育だ。
保護者も大変なんですよ。
こういう理解への促しもあるから。
聖人君子ではない、それは分かる。
そのレベルの域にいないものもいる。
こことは徹底的に戦う所存、こういうことだ。容赦しない。
相手が子どもでもね。
誰を相手にしてると思ってたんだ。
わたしだ。
だから何かあったら、子どもにいつも聞く。



あなたは大丈夫?
ごちゃごちゃと、うるさい、そう思うこともあった。
だけど、子どもが良いなら、いい。
叫ばない。叫べない。辛い。
そのループ。
だから、我慢するということもしたが、相手が子どもでも、事と次第によってはそれなりのお手紙が行く。もちろん、わたしの思想入りのものがね。
折り紙もクレーム入れようかと思ったよ。
楽しみに学校持って行ってたから。けど、



わたしは大丈夫。
そういうから、ブログにまとめて消化させた。
だって、わたしが学校に求める唯一のもの。
お友達とのコミュニケーション。
これだけしか求めていない。
それすら….
鬼、厳しい意見になるけど、正直、教養の教育はこちらでできる、勉強は問題集と自分のフォローで補える。
現にすでに補っている。
ごめんなさいね、感覚的には、関わっている場合じゃない。
無理がくれば塾がある。
じゃぁ、私学に行けよってなるかもしれないけれど、そういう問題じゃない。
教養はどこでも同じだよ。
じゃぁ聞くけど、私学の『ごんぎつね』はこのレベルなの?
学校の授業聞かないから何なんだ?
つまらないんだろうとも思ったけど、クラスの成績が査定になるんじゃ生徒もたまんないわよね。
そりゃ折り紙没収されるわ。
せめて、そこのクラスだけにしろよ。
自身の力量不足を生徒の責任にだけするこの構図ね。
そういう、わたしみたいな保護者もいるよ。
だから、勉強の教え方に独特なものがあっても、別にいい。
何が一番嫌かって、勝手なワケの分からない教養の押し付けで、子どもたちの自由が奪われることだ。
子どもから自由を奪わない先生は、神様のようだ。
心から感謝したい。
子どもと対話して、遊んで、自由をくれる先生。
だから、ちょっとしたことで、先生へ感謝が出るのが分かる?
- 正しい勉強のコツを教えてくれただけで感謝
- 褒め方を間違えなかっただけで感謝
- 子どもの自由を尊重してくれただけで感謝
- お昼休み少し早めに行かせてくれただけで感謝
- 授業を間違いなく進行してくれただけで感謝
- レベルはどうでもいい、道徳の授業、要点の押さえ方さえ間違えなかっただけで感謝
逆に、何を期待してみんなクレームとか入れてるの?
そんな気力がよくあるわよね。
尊敬するわ。
だって、学年長やって集まりに参加したときに、課題の分離すらできてないのよ?
お題に沿った話し合いすらできてないの。
そこには教職者もいたのよ。
この弊害が分かる?
愕然としたものよ。
何に愕然としたか分かる?
課題の分離ができないこと、お題に沿った話し合いができないことの、子どもたちへの影響だって。
そこからの波及考えたらもう、ナニコレ、こういう感じ。
親ならまだいいよ、だけど、教える側もこうなの?
あの愕然はすごかったって。
レクリエーションの有無の相談よ。



予算が…



そうですよね、予算もないし…



他の予算に使った方が合理的でしょう。



すみません、このレクリエーションの、目的をお伺いしてもよろしいですか?



これは、保護者との交流のために用意されたものです。



このレベルw…目的も問えずに出す結論w
参加する気もしねーよ。
呼ぶなよ。
ここって、大事よ。
よくいるじゃない、会議とかで平気で脱線するやつ。
起動修正するのが大変でさ、15分で終わりそうな会議が1時間とかになるのよ。
恐らくわたしが想定するに、ここの学校の職員会議、めちゃくちゃ長いだろうと思う。
で、そこからの人生の読みはこうなる。
15分が脱線して数十年になる。
到達したころは、何をして生きてきたか分からなくて、悩みだけが存在する人生。
そんな感じじゃない?
だって問われているお題が分からないんだからね。
違ったところにアプローチして、物事がうまく運ばなくなるのよ。
当然でしょ。
課題の分離もできないんだから。
学校の諸問題もそうなってるはず。
解決の意図を辿らない。
つまるところ、イタチごっこだ。
この間の参観日だってそうだって。
ある保護者がさ、



授業で発表しない子どもへどうやって促したらいいんですか?



毎日の読み声などで、読むことに慣れることなどが大事です。
文章を正しく読む訓練をしていくといいかと思います。
わたしは分かったよ。
だけどさ、あのレベルの発言をする保護者が、どういう意図でその質問を投げかけているのか?
という構図が読めてないから、こんな回答になるんだよね。
大事だよ。なぜか?
自信をつけないといけない。
その自信は読解からくるというのを言いたかったんだろう。
自分で読み、考えて、それを表現して行く力が必要だということだろうと思う。
多分ね。
そこを端折る。
何が問題かって、ここからの波及考えたら、このクラスの生徒たちは恐らく、先生の言ってる本質の意味が分からない子が多いだろうな、というところまでは容易に想像がつくよ。
だから、結果、こうなる。
全然知らない。こういう子が増える。
けど、先生は説明している。
けど『参観日に発表しない子=音読』この構図もおかしいよね。
けど、そこまで言うとサウンドバッグになっちゃうから、言わないけどさ。
やっぱ言おうか?
この場合の正しい回答をするなら、
音読は、文章を正確に読み取る力を育てるための基本的な訓練です。
文章を声に出して読むことで、内容が自分の中に定着しやすくなり、理解が深まります。
理解が深まれば、問われている内容にも的確に応えられるようになり、自分の考えを自信を持って発表できるようになります。
読んだ後に感想などを対話してみてください。
参観日で保護者がいる場面では緊張するのが自然ですが、保護者の有無に左右されず堂々と発表できるようになっていくと思います。
そのためには、理解して『自分の言葉で語る』練習が重要です。
日々の訓練としては、時間はかかりますが、とても有効です。
こんな感じなら、伝わるものもあったんじゃないの?
もっと言うと、あの保護者も、分からないなら分からないって言えばよかったのに。
あれ、理解できた保護者、どれだけいたの?
わたしなら、分かりません、どういう意味ですか?
って堂々と聞くよ。
分かったから聞かなかったけど。
もう一つロジックが存在する。
親も質問の答えはどうでもよくて、目立つことだけを目的とした質問であれば、問いも生じないものな。笑笑
ただの桂馬の高跳び。
跳ねただけ。
発表ができたかどうかよりも、自信を持って、自分の考えをきちんと言葉で表現することができるようになっていたかどうか?を見て頂けると、成長も分かりやすいかもしれません。
そしたら、手を挙げて発表して、目立つことだけを目的としてる親も恥じを知るんじゃないかな。
こういうズレが、『問いを持たない子』『問おうとしない子』を生んでいくんだよ。
断定的でしょ。
先生が分かってないんだもの。
問いに対する伝え方をw
そう、参観日ひとつのやり取りで、ほとんど見抜く。多分日頃言われてるんじゃない?
『言ってる意味がわからない。』とかw
伝えてる内容は秀逸だもの。本人からしたら、何でこのレベルが分からないんだ!
というジレンマもあるだろうね。
言うてる内容じゃなくて、伝え方だよ。
わたしの脳内や、解説をAIに組み込んで授業してもらった方がまだマシだよ。弊害でしかない。ロッカーの前で、居眠りチェックくらいしてくれる?
最近の保護者のレベル?
このレベルだけど、どうかしたの!?
そういう思想までは到達したくないよってのが、常だろう。
問うと去るしね。
去るのが分かるのに、言えと押される。
全部聞いてなお、どんな世界が見えてくるんだ。
見えてきた世界を見て、自責、それを受けてきたのが、わたしだって。自責がすごかったんだよ。
ゲシュタルトが一度崩壊してるんだ。
人を責め立てた自責だよ。
こうならないように、育ててるんだよ。
デフォが違えば折られるんだよ。
出血が止まらない、そんな教育に見えるよ。
だけど、自責もさ、こう考えた。
その過去の誰かを批判するわたしは、そうやって自分を守る手段しかなかったんだ。
そこ通らないと、自分が守れないくらい、摩耗してたんだ。
しかも、それが子ども時代なら、猶更だ。
理解できるわけがないだろう。
それも分かるよ。
だから、摩耗して倒れそうな自分を必死に何かで支えようとした。
その支えが人批判であったとしても、それなら仕方ないじゃない。
不安障害もひとりで耐えたよ。
誰にも言わずね。夜中に一気に押し寄せてくる絶望だよ。
子どもの異常行動が、全部叫びに聞こえるのは、ここを通ったからだ。
通ってない者には、ただの手荒い我がままか、生意気なお嬢ちゃんとお坊ちゃんにしか見えないだろう。
そんなことはない、と思うなら自身の小学校時代を想像してみて欲しい。
意外に普通じゃない?恐らく葛藤が生じ始めたのは、もっとずっとずーっと上の年齢からだと思う。
ここには、あるものがない痛みは含まれなくて、あるものがあるが故のものになる。
あるものがあることで起こる弊害もあるってことだ。
そこを理解してないわけじゃない。
ただ、あると、見落としやすく、本人も言語化しづらいんだよ。
そこを知らないんだろ。
パラダイムが足りないよ。
だって、子どもだから!教えてもらえない、教えてもらったことがない子どもだからだ!大人は、自分で難しい本読んで、学べるだろう!
ごんぎつねですら、学べないんだよ。小学生の子どもたちは。
兵十とごんは、どちらも悪くはありません。



オセロか囲碁しとけよ。
自学習しか頼る術がない。



わたしはちゃんと教えてます。



わたしもちゃんと教えてます。



囲碁とオセロをですか?
弊害だから、控えてください。
言っとくけど、囲碁とオセロ批判じゃないからねぇ。
比喩だよ比喩。
白黒判定のー。
子どもは守られる存在でないと、ダメだ。ここにたどり着いたんだよ。
一生懸命自分を守って気づいた、あの怒りは自分を守れた証だ!戦った証だよ!
思いっきり怒って、自分を守れたんだよ。偉いだろ!子どもなりに、自分の自負だよ!頑張って耐えたんだ!
だから、子どもが賢いことをいいことに、そこに慢心して胡坐かいてる親も吐き気がする。
賢いけれど、大事な子どもだろうが。
賢いことをいいことに、何でもペラペラ愚痴ってんじゃねーよ。
わたしだって、理解されたいよ。けど、構造を読み取る側は、理解され難い、そこまで分かる。
だから、黙る道を選んだんだ。けど、色々残そうかと思って、そのブログがこれだ。
まだ回答が出てない。
歩かなきゃ。世の中の残酷さよな。
国民に負けるな。わたし、自分に問え。
諦めるな。自分を信じろ。
さぁ…………………………..
異論を唱えたいのなら、受けて立つ。
デフォに戻りつつある。
というかデフォだろうな。
切りたくるわたしだ。
だけど、異論を唱えたいのなら、次元を保つことだね。
次元が違えば絡めない、世の法則だよ。
さぁ、言うも何も、言える土俵に立てるかしら?
ちなみに、低次元には一切興味がない。
慢心にも勝てない?
そのレベルはわたしの辞書にはない。
品格というものを知らないのか?
品が無いにも程がある。
どのレベルだ。
同じくらいの品格じゃないと無理なんだよ。
ここで一句。
『低レベル、理解はするけど絡まない。』
常識で定跡でしょ?
なぜわたしがここまで言うか?
何度かブログでも言ってると思う。
二ーバーの祈りをだ。
ここの見極めを間違うと、人生余裕で持ってかれる。
だから、余裕で持ってかれる覚悟が必要なのは常識で定跡だよ。
だれも責められないのよ。
だから、わたしは責めないんだって。
わたしには、常識で定跡だもの。
だから、常に自分のレベルと波長確認は怠らない。
これを頭に叩き込まないで安易に近寄って巻き込まれている者を低レベルと言うんだよ。



わたしは近寄ってないし、あっちが…..
アドラーさーん!



はい、最後に決めたのは誰ですか?
このレベルが嫌なのよ。
自己一致者がぜーーーったい言わない台詞。笑
反吐が出る。
アドラーを知識じゃなくて、体感で理解してないと自己一致は無理なんだよ。
知識だけでアドラーを理解してると、自己一致とは少しブレるからね。
だからわたしは、頭に叩き込んでる。
しかし、受け入れが過ぎる。
その方が安全だと思ってた。
それは必要だったし、意味があった。
けど、それが通用しなくなってきてる。
次の段階だろう。
私は受け入れるだけの人間ではない。
見分けた先に、動く力もある人間だ。
けど、見分けたつもりだったのよね。
知識と行動の判定が超絶ムズい件。
知識に翻弄されるんだなぁ。
勘弁してくれよ。
後に出る慢心までは、気づけないよ、わたしでも。
けど、慢心にも種類があるからね。
慢心だけではなくて、全行動を精査しての今。
ま、当然だってー。



ボーっと読んでた?それはヤバいね。
二ーバーの祈り、この記事はめちゃくちゃ大事だよ。
超重要、言っとけばよかった?
読めば分かると思ってー。
わたし、優しいからもう一つアドバイス。
『低レベル、理解しないけど絡まない。』
↑これだとね、業は入るのよ。
『低レベル、理解もせずに絡んでく。』
↑業どころじゃないよ。
これは暴走だもの。
『低レベル、理解していて絡んでく。』
↑この法則は成り立たない。
『理解もせずに絡んでく。』これと同等だよ。
気を付けてねぇ~。
定跡よ。
そこにあるのは、怒りじゃなくて、境界線と敬意よ。
あぁ、ちなみに、わたしの低レベルは4以下のことだ。笑
一切絡みたくない、というより、絡めない。
息切れする。3なんて論外だよ。
ましてや、1とか2w。無理。
あぁ、もっと言うと、そこと関わってる人ごと無理。
レベル下がるのは時間の問題だろ。
下の引き、引力を知らないからそうなるんだよね。笑笑
言っとけばよかった?言うと、誰も残らない可能性もあるじゃない。
5ってどれくらい少ないと思ってるのよ。
会話の端々に可能性を感じたのよ。
レベル判定は慎重にしたいから。
上下するのよ、5で固定できそうかどうか?
も見ないといけないから。
じゃないと、知識が無駄になる。
わたしだって、教えて意味のある人材の区別はするよ。
このレベルの知識を誰にでも教授すると思う?
するわけないじゃない。
それこそ、時間の無駄でしょ。
言えるレベルの人々がいたことが奇跡だったから、惜しみなく時間を使わせてもらいました。
そこには、とても感謝しています。ありがとう。
このわたしが、行動すべき、そう感じたから。
才能ある子どもたちが沢山いた。何百倍にもなる子どもたちが。
レベル判定どうやってしてるか種明かししとく。
子どもに、その案件で〇〇と言えた者は誰?
こうだね。
これを網羅しているかどうか。
これは線引きではなく、敬意よ。
わたしが惜しみなく注げたのは、あなた方がそれに応えてくれたから。
貴重な時間を使ってでも、そうしたい、わたしがそう思えたの。
そのポテンシャルを勘違いしないで。
わたしは厳選力がとてつもなく厳しいのよ。
伝わっていないと大変だから。
そういう厳選された人々だったという、期待値がかなり高かったという事実を伝えておきます。



それ以外は、無理。
だって、小学2年生のとき、先生が教えてくれた法則があるの。



ゼロには何を掛けてもゼロにしかなりません。
だーれが好き好んでゼロに労力なんて、注ぐんだよ。
だけど、3でも4でも、学びたい意欲のある者は、全然違うんだ。
こういう者がいたら、3でも4でも手を繋ぐよ。
そのかわり容赦がない、わたしの本当に学びたいか判定試験が存在している。
合格者しか無理。
知識の“高さ”と、それを受け取る側の“地盤”が一致しないと、知識は害にしかならない。
定跡だろう。
それにプラスして、意志があると良かったわね。
無いと、親にひっぱられる。いくつになってもね。
分かってはいたけど、才能の高さを見たら、ここに引っ掛かってるものには全員に告ぐけど、拘る価値ある?
そうなるね。
ドブに捨てたものの大きさが見えないから、できるんだろうなとも思うけど。
意志なき才能は、親に吸収されるだけの空気と同じよ。
誰が認めてたと思っているの?
才能というのは、本来外に向かって放たれるエネルギーであるべきなのに、意志がなければ、その方向性は親(あるいは環境)の“願望”に吸収されてしまう。
『自分が何を手にしていたのか』に気づかないまま、それを捨てる。
“手にしていたはずの可能性”に、想像力が届かない。
どれだけ才能があっても、意志がなければそれは他人の脚本の中に吸収されて終わりよ。
こんなのがゴロゴロ出るはずだわね。
当然の結果といえば、結果だわ。
全ては『白いぼうし』と『ごんぎつね』で、落ちたよ(分かった)。
意志なき者が、意志なき教育を施し、考える力を奪い、意志なき者を育てて行く。
構造の見方なんて存在しない。
それが日本の構図だろうな。
ま、どの道わたしは困らない。
勝者だ。
わたしは、舵を握る者の孤独より、そっからの波及考えたら、操られる群れの安心の方が怖い、そういう船には乗ってらんないよ。
タイタニックだ。
だからわたし達は、すでに違う船に乗っている。
わたしが航海士だ。
航海図を描くところから始めたから。
もう船を出してから10年になる。
景色が大分違うよ。
航海図を描くところが一番大変。
最初は溺れている所から始まった。
その最中も、色々なものを目に焼き付けた。
忘れないように。全部だ。
ようやく岸に上がり、航海図の書き方を学ぶところから始まった。
そこはもう、わたしがし尽くした。
同じ航海図を手にする者が、きっと少数でもどこかにいる。
そのとき、溺れていない者だけが、声を掛け合えるはずだから。
声を掛け合わないといけない。



わたし、タイタニックって、教えましたけど、余計なことはしないで。
平和でいたいの。凪を航海したいのよ。
まぁ、いいや、ともあれ、
教えること多いねぇ。
前記事で言ったはずだよ?
未来で必要なのは『非認知能力』。
ここから別件だけど、
何に感謝かって、ここまで色々言ってきたのに、教育に向き合おうとしてくれてる先生がわずかにでも存在していることですよ。
その存在が、誰かも分かってる。
ありがとうございます。
その気持ちだけで、もう十分。
宿題プリントをくださってる先生、いつもありがとうございます。
勉強教えてくれて、子どもと一緒にダンスしてくれて、ありがとうございます。
お話を聞いてくれて、娘の存在を認めてくれて、娘の周りのお友達の存在を認めてくれてありがとうございます。
娘が色々事件に巻き込まれているときに、小学校2年くらいからかな。
わたし的には、あの放任さが楽でしたよ。
まぁ、それが保護者との接点を絶つ手段だったとしても、理由はどうてもよくて、それをわたしが取りたいように取ったのだけど、感謝の方も大きかった。
わたしには、解決能力があったから、その方が都合が良かった。
それは運かもしれないけど。笑
そこで横やり入れられると、後手に回らないといけなくなるときがあるから、結果良かった。
学びも濃かった。
本当に、本当に、ありがとうございました。

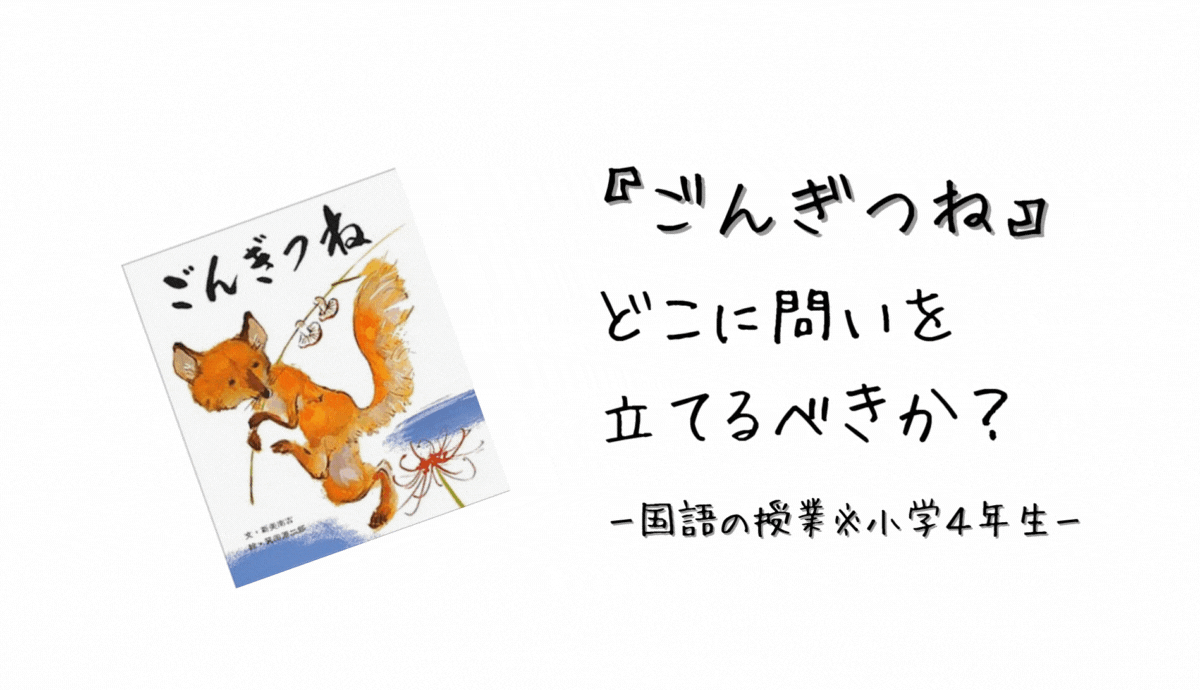
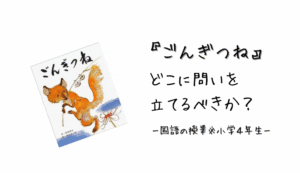
コメント