この言葉を、私は親に言ったことがなくて、でも、あるとき、言える相手が現れた。
それは、相手を攻撃したかったからではなくて、ずっと胸の奥で凍りついていた言葉が、ようやく言葉にできたから。
伝えた人には、それなりに原因があったんだけど、その原因とコレとは別問題で、そこのところをかろうじて理解してくれるレベルの人だったので、つまるところ、そこを利用して伝えたんですよ。
その賢さには感謝しています。一応。
何をされたかというと、心理操作の世界に案内されて、腹が立ったから門を叩き壊して入門しなかった。
使ってしまう理由も分かった上で、「使わない方がいいよ」って伝えたのよ、それなのに、使ってたからね。


半沢直樹の世界でもある。
本人と大和田常務だ。
大体こんな感じだろう、してたやり取りは。
もちろん、わたしが半沢直樹側だ、誠実だったからな。
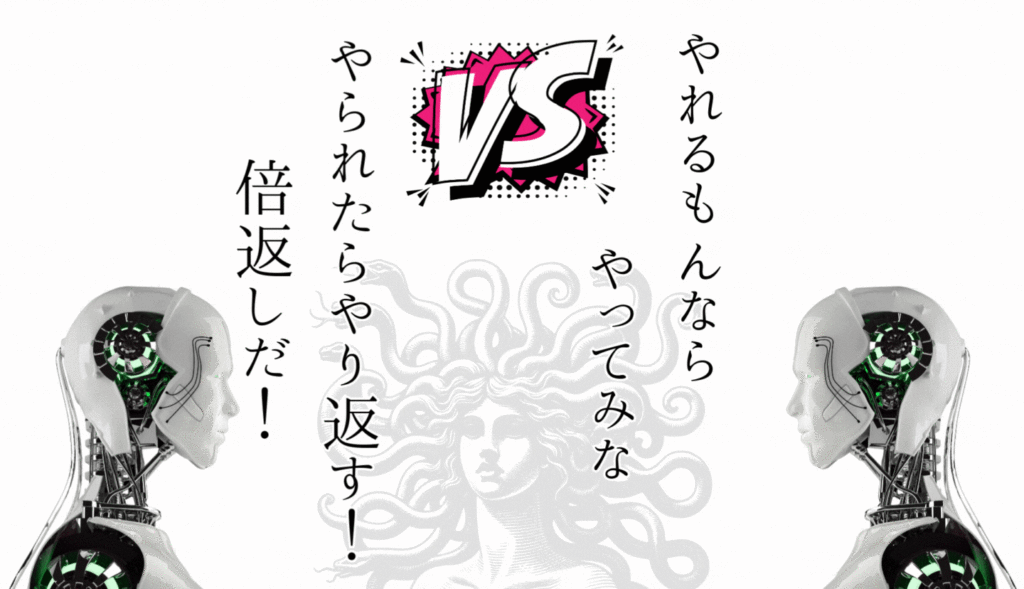
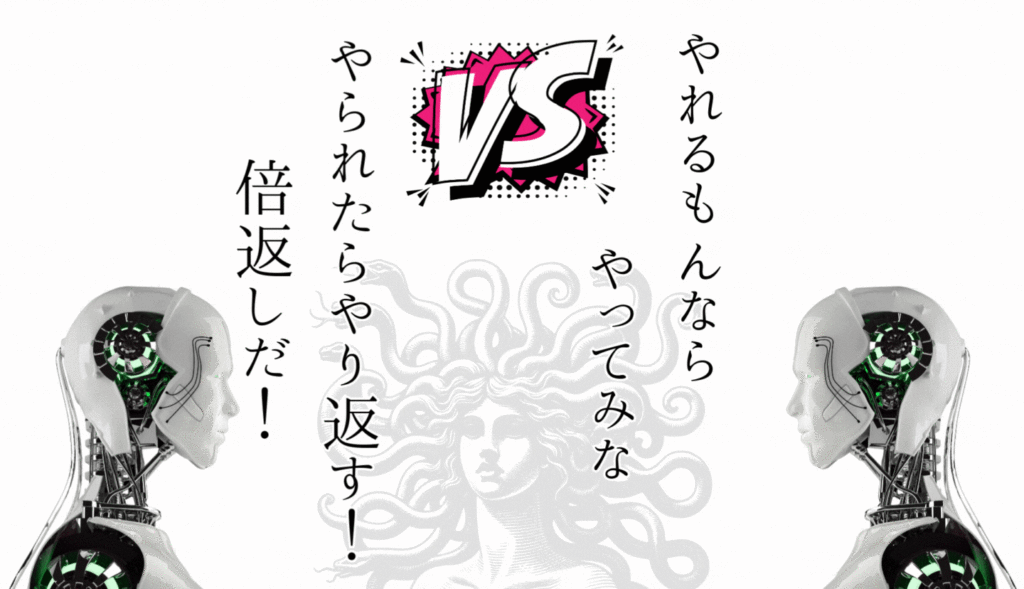
以前、親の着ぐるみを着た自分という記事を書いたんだけど、自分の中に自分の物として落とし込むには、説明が足りなすぎた可能性もある。
この記事は、そんな感情の“構造”を解き明かしていく記録です。
怒り、嫌悪、拒絶──それらは本当に“わたし”のものか?
そして、わたしはどこから始まるのか?
『嫌い』の正体を暴くとき、本当のわたしが、ようやく始まる。
親の影をまとった自分──その着ぐるみの正体とは?
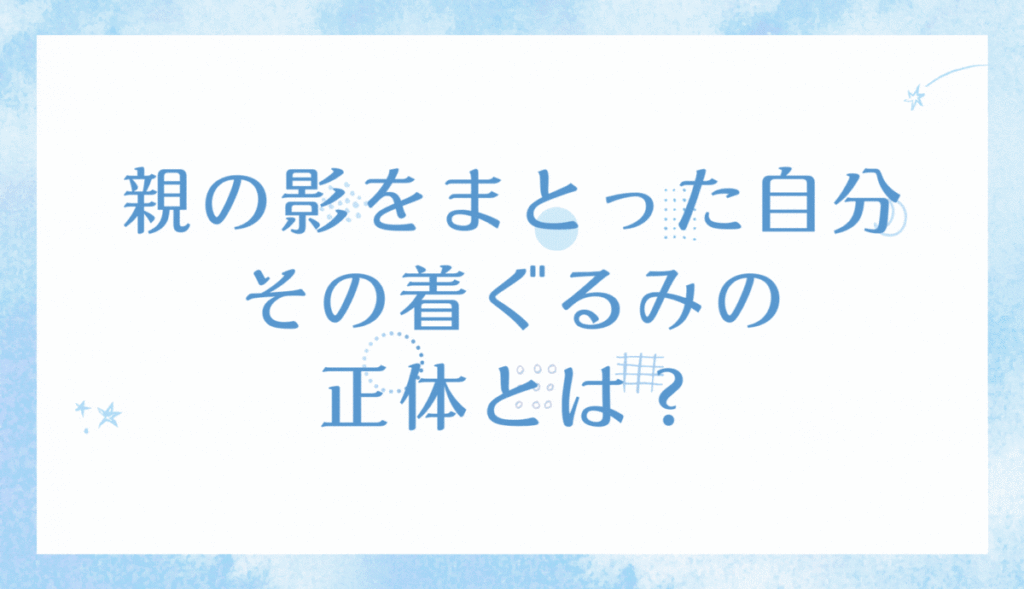
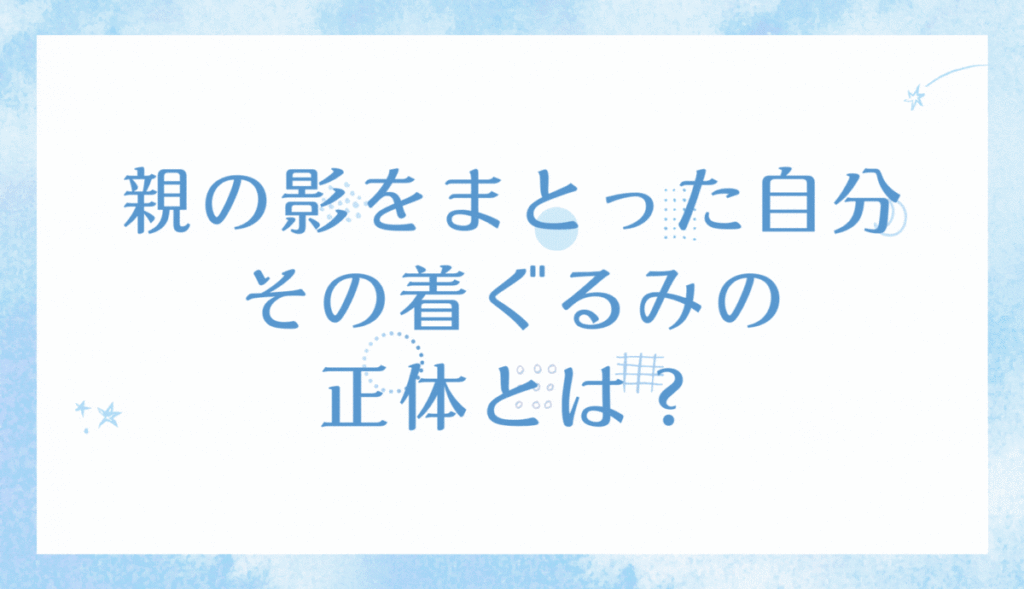
気づけば私は、親にそっくりだった。
いや、もっと正確に言うなら、“親の着ぐるみを着た私”。
見た目は私、中身が親、本当のわたしはどこ?
出会う人は変わるのに、湧き上がる嫌悪感はいつも同じ…..確実に、『別の人なのに、同じ中身』に反応してる自分がいる。
この世界は何?
目の前の人は、この間の人と外見は違うのに同じに見える…..
今回は、この“着ぐるみ構造”をひもといていく。
着ぐるみのファスナー、どこかにある。
- 親のような相手? いいえ、『親の着ぐるみを着た自分』です
- 『嫌い』という感覚は、守るためのアラート
- その声は、ほんとうに“わたしの声”か?
① 親のような相手? いいえ、『親の着ぐるみを着た自分』です
まるで親みたいに、否定的で、感情の扱いが雑で、でもなぜか出会う相手。
ある日気づく。
自分もじゃない……?
つまり──
親の着ぐるみを着てるのは、あっちじゃなくて、こっち。
で、こっちが寄せてる。
選んでるつもりが、着てる自分が反応してただけってパターン。
で、ゲシュタルト崩壊したんだってね。
② 『嫌い』という感覚は、守るためのアラート
わたしの場合は、相手の器量を見極めて(見極められてなかったらごめん)、自覚的に発言した言葉。
けど、自覚的でない場合、相手の何に自分が反応してるのか鈍感になっていく。
この『嫌い』という感情は、実はすごく大事な“緊急アラート”だ。
- 『これ以上近づくな』
- 『自分の境界線を守れ』
- 『その世界に取り込まれるな』
…そんなメッセージを送ってくれている。
ただし、ここで大事なのは
『アラートの原因がどこから来てるか』
を見極めること。
嫌悪感は大きく分けて2種類ある。
相手由来のアラート
→ 本当に相手が自分の境界を壊そうとしているときに出る『防衛反応』
→ この場合は、はっきり『NO』を出すのが正解
自分由来のアラート
→ 過去の経験やトラウマ、未処理の課題から来る『過剰反応』
→ たとえば、親から否定されて育った人が、大人になってちょっと指摘されただけでも『攻撃された!』と感じるケース
だから『嫌い』は、正しいか間違いかじゃなくて、“まず受け取って、次に解釈する” 感情だと思ってる。
わたし自身、もう着ぐるみを脱いでるから、嫌悪感そのものはアラートにはならなかった。
でもアラートじゃないからこそ、冷静に『これは私の課題?それとも相手の課題?』と見分けて、感情を整理できる。そして必要なときには相手に言葉を放つ。
でもね、ここでまた社会的な問題が出てくる。
言葉にした瞬間に
『攻撃的』
『自分勝手』
『配慮不足』
とラベルを貼られることが多い。
境界線を伝えただけなのに。
そのときに
『やっぱり私が悪いのかも…』
と自己不一致に落ち込むか、
『これは境界線の表現』
と自己一致のままでいられるか、その差が人生を大きく変えていく。
まぁ、言い方がきつい時代もあったのは認めるけどね。



わたしは、あなたが嫌いです。
あなたも私のこと嫌いだと思うので、それで大丈夫です。
お互い干渉するの止めませんか?
そっちの方が合理的じゃありません?
(投影ではありません、自覚的です。)
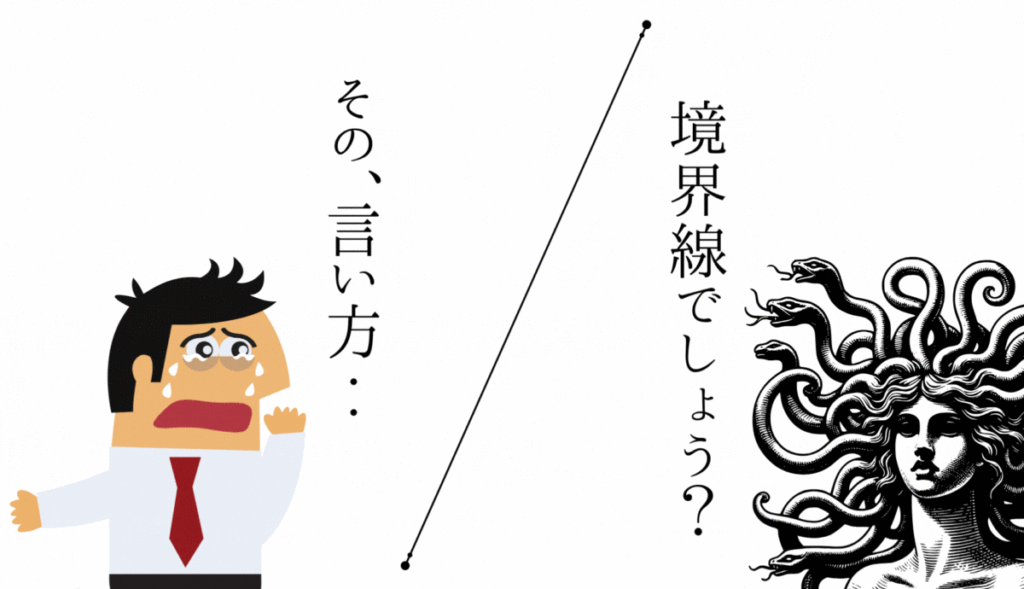
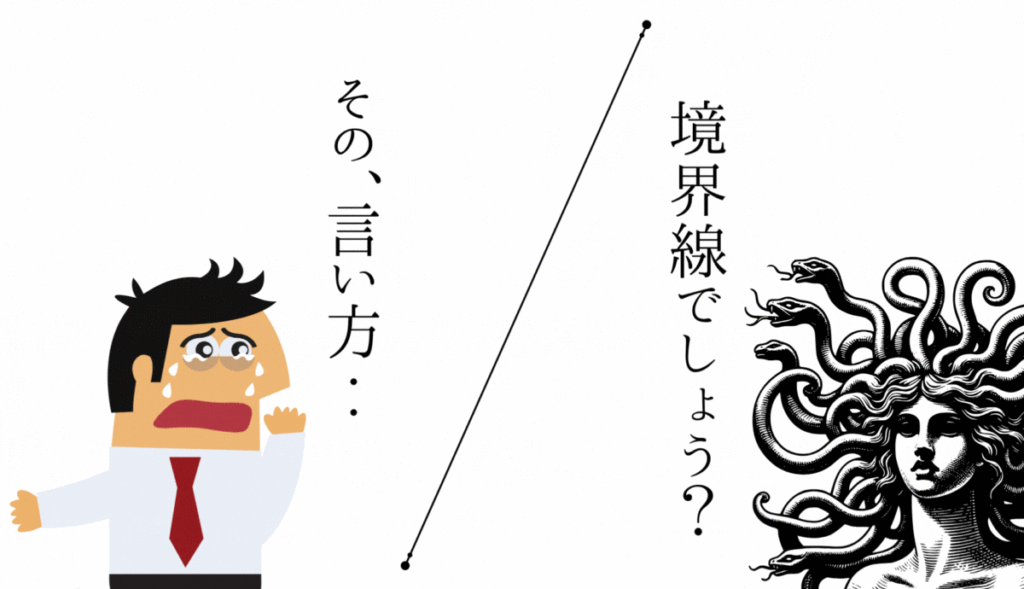
ショックだ何だ、色々言われた。反省している(今はね)。
③ その声は、ほんとうに“わたしの声”か?
怒ってる。泣いてる。黙ってる。拒んでる。
でもその感情、“ほんとに私の声”?
『だからダメなんだよ』
『そういうとこが悪いの』
『ちゃんとやらなきゃ』
『なんで一番じゃないの?』
『あの子にはできるのに、あなたはなぜできないの?私恥ずかしい』
『あなたのこういう所は、嫌だわ、だって…』
こういう言葉たちは、ただの愚痴じゃない。
子どもの脳内に、“正しさのテンプレート”としてインストールされる。
そして、こうやって劣等感が埋め込まれていく。
上で説明した『自分由来のアラート』は特に要注意でもある。
というのも、
- 本当は相手が悪意を持ってないのに、過去の経験(親に否定された記憶とか、いじめられた記憶とか)が反応して『攻撃された!』と錯覚する。
- その結果、相手を不必要に敵扱いしたり、自分を責めすぎたりして、人間関係を壊しちゃう。
- しかも怖いのは、この反応って無意識だから『自分のほうに原因があるかも』と気づきにくい。
心理学的に言えば、これが投影。
だからこそ “気づいて解く” ことが必要になる。
具体的には、
- 一拍おく:『この感情は“相手の言葉”に反応?それとも“過去の自分の記憶”に?』と自問する。
- 分けてみる:『相手が実際にやった事実』と『私が感じたこと』を分ける。
- 自分由来だったらケアする:『これは昔の私の痛みが反応しただけだな』と気づけば、相手を責めなくて済む。



わたしは、伝えたけどね。
けど、責められたわけじゃないって分かってくれる人だったから。
じゃないと、できないでしょ。
自分由来を相手由来として処理した話だ。
自覚的で高度なテクニックだよ。
つまり、自分由来のアラートって『危険信号』じゃなくて『未解決の宿題を知らせるベル』でもある。
だから放置しちゃうと、人間関係でも仕事でも同じパターンを繰り返す。
- 相手由来 → NOを出して境界線を守る。
- 自分由来 → 自分の課題としてケアする。
両方に気づけることが『自己一致』なんだと思う。
自覚的であれば、嫌悪は強さになる
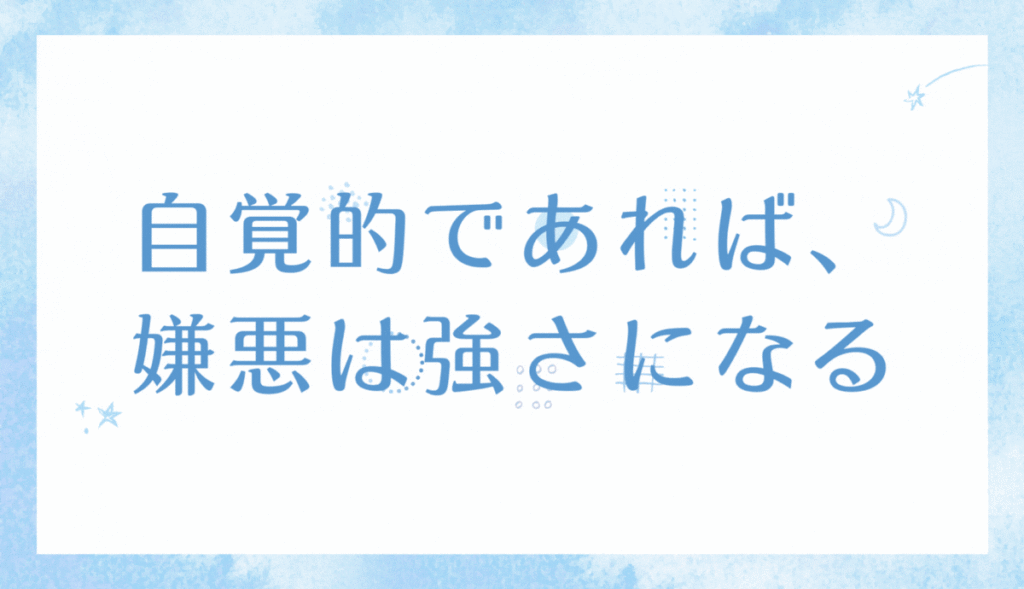
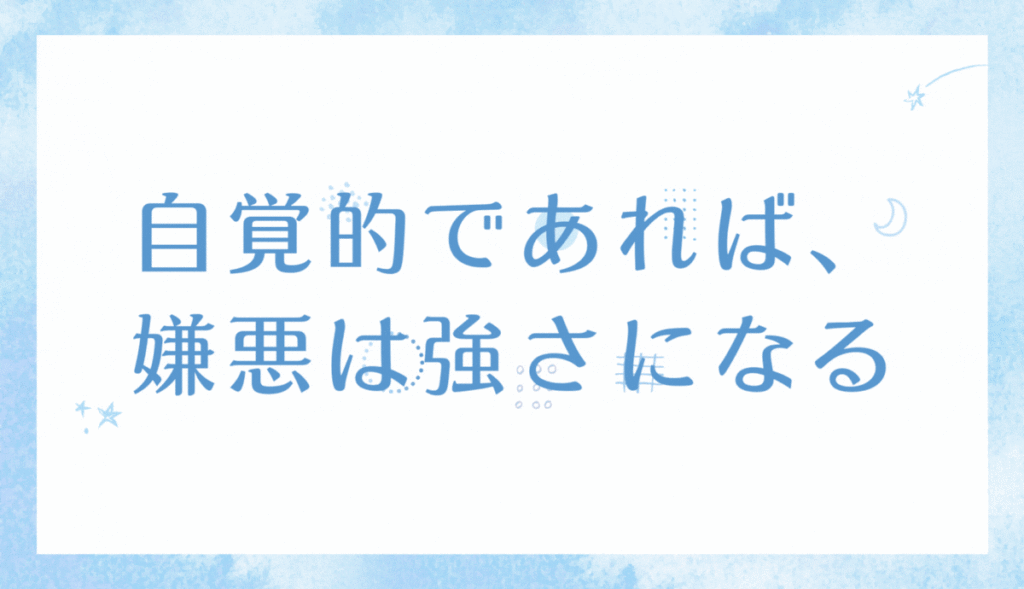
- 『嫌い』は感情的なアラート、抑えなくていい
- 無自覚に攻撃しなければ、それは境界線の表現
- 親とは違う生き方
① 『嫌い』は感情的なアラート、抑えなくていい
『嫌い』という感情を持つと、どうしてもネガティブなものとして扱われがち。
優しい人ほど『嫌ってはいけない』『受け入れなきゃ』と自分を責めてしまうでしょ。
でも実際には、『嫌い』は大事なアラートでもある。
- これは私に合わない
- ここは踏み込んではいけない
そう知らせてくれる信号。
生理的に合わない食べ物が体を守ってくれるように、感情的な嫌悪もまた、自分を守るセンサー。
だから抑え込む必要はなくて、むしろ正しく扱えば、人生のガイド役にすらなる。
② 無自覚に攻撃しなければ、それは境界線の表現
ただし、嫌悪をそのまま相手にぶつければ、ただの攻撃になってしまう。
自分由来からくる嫌悪感。



あぁ、さっきの私のはぶつけたんじゃない、境界線を伝えたつもりだったけど揉めた図だ。



あなたが間違っている!



お前が悪い!
こういう言い方では、何も生まれない。
けれど、自覚的に扱えば、
『ここから先は違う』
『これは私の領域ではない』
という線引きになる。
それは相手を否定することではなくて、自分の輪郭をはっきりと描くことになる。
つまり『嫌悪』を境界線として使うと、攻撃性は自己の主張へと変わる。
そして不思議なことに、この『線を引く力』を身につけると、むしろ人間関係は安定していく。
相手に迎合しすぎて疲れることも、逆に侵入されて壊れることも少なくなる。
嫌悪は壊すための感情ではなく、守るための道具として使えばいい。
せっかくアラート鳴ってんだもん。
従えばいいだけだ。
無視して行動するからややこしくなっていく。
③ 親とは違う生き方
植えられたものは、消えない。
けれど、“それに支配されるかどうか”は変えられる。



なんでわかるの?って?
わたしが消えないからだよ。
常に自覚的でいるしか、手立てがない。
今のところね。
けど、だから、まだ探してる。
無効化する手立てだよ。
それは、自分に与えられた役割を全うすることにあるんじゃないかと思うんだってね。
エネルギーを「本線」に戻すってことね。
そのための渇望だとすれば、全部説明もつくだろう。
「気づけ」この可能性が高いかなっていう持論だよ。
親や環境(学校など)から植え込まれた価値観や感情のクセは、完全に消すことはできない。
例えば、学校から、



スリッパを並べたら先生に報告してください。



先生!並べました!



偉いですね!皆さん!〇〇さんが、スリッパを並べてくれました。拍手をしましょう!
こういうのも、残念ながら抜けなくなる。
植えられたものは、序盤でどうにかしないと育つ。
情報が入って我が子に確認したら、日頃の教えが作用して植えられていなかった。
抜く必要も無かったから、お友達だけ確認しておいた。
大丈夫だった。
原理原則を説明した上で、様々な処世術を伝えておいた。
他は知らないが、聞く限り根付いている者もいた。
これは育つだろうな。知ったことではない。
それもその者の学びのひとつなんだろ。
全員で学べばいいだけの話だ。
それも縁起と見る。
そうでしょう?



そうだね。
行動の意味は自分で選ぶことが大事だし、処世術は“使うもの“であって飲み込むものじゃないとも教えている。
当然だ。



現代の子育てでは、これくらいの気づきがないとやっていけない。
知っとかないと、すぐやられる。
処世術なんて、もっと後からでもいいと思うでしょ。
うちなんて、4歳のころから教え始めた。
教えざるを得なかったというのが本音だ。
些細な教育的演出の裏にある構造を見抜ける目がないと、知らず知らずに根付いてしまう。
これがクセになると、
- 行動=評価のため
- 自分の満足<他者からの承認
- 『誰かに見てもらわないと意味がない』
という外的承認依存の芽になる。
内発的に生きる力を守るのが親の大事な役割だ。
親で言えば、子どものころに『嫌うな』『泣くな』『怒るな』と教えられれば、今でも胸の奥でその声が響く。感情の否定は本人の存在すら否定することになる。
『否定されたらどうしよう』という恐怖は、簡単に手放せるものではない。
けれど、それに支配されるかどうかは、自分で選べる。
『親がそうだったから』『昔そう言われてたから』、この延長線上に生きなくてもいい。
相手の行動がトリガーとなって嫌悪が現れる、これが投影。
過去に植えられた感情を知らせるサイレンのようなものだから、そのサイレンに振り回されるか、逆に『もう同じ道は歩まない』と自覚する合図にするかで、未来はまったく違うものになる。
だから私は、嫌悪を恐れない。
あって当然のものだと思ってる。
それはもはや弱さでも汚さでもなく、私を守り、未来へ進ませるサイン。
植えられた劣等感が育ち『自分になる』まで
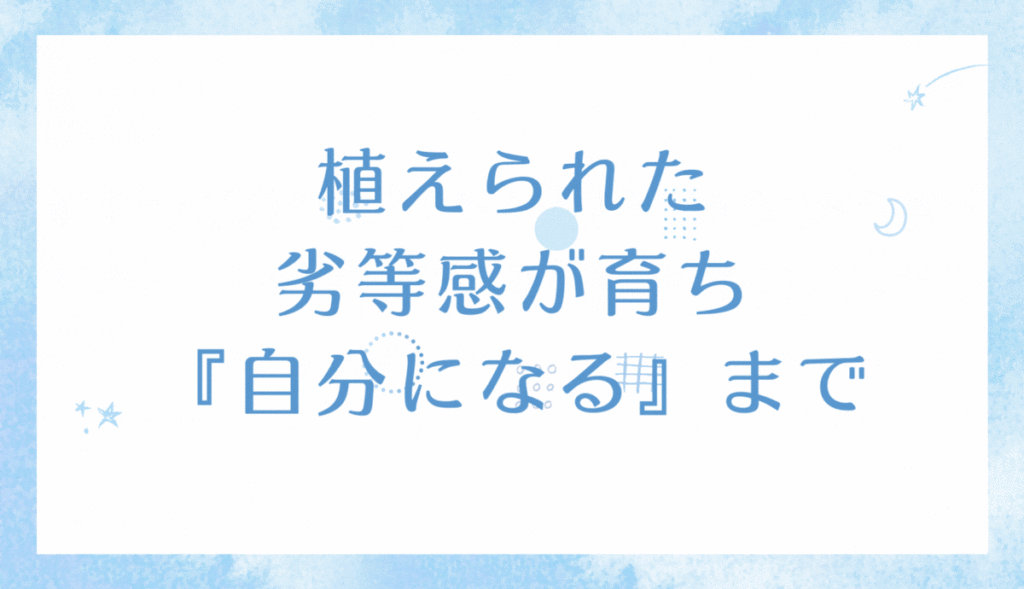
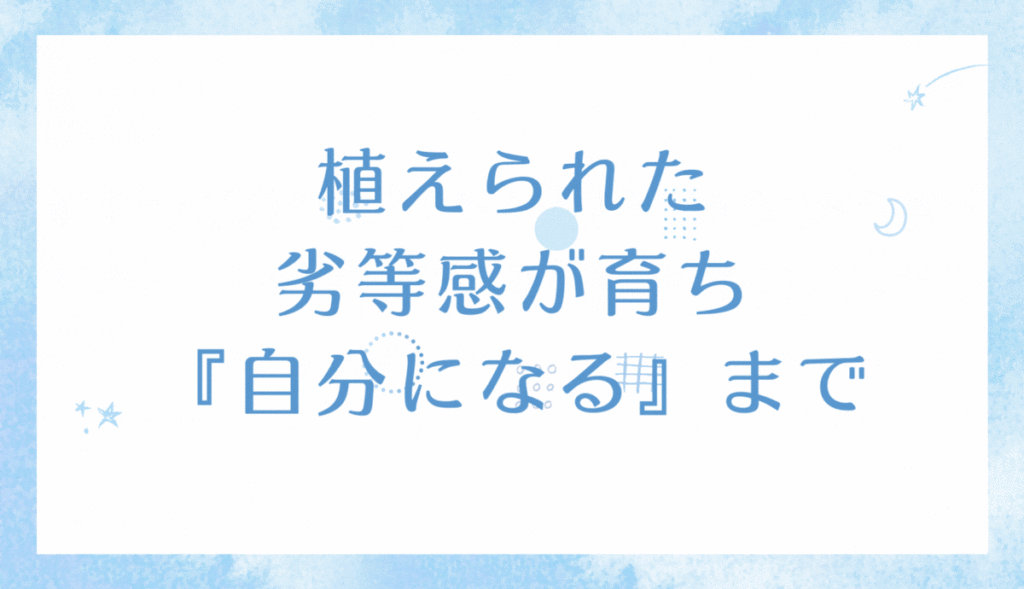
わたしなんて、どうせダメ人間だし。
それ、本当に“あなた自身”の言葉だろうか?
気づけばすっかり馴染んで、当たり前になってるその感覚。
でも、もともとは他者の声だった可能性が高い。
とくに親。
子どもにとって、親の言葉は“世界のルール”そのもの。
つまり、『お前はダメだ』と言われれば、『わたしはダメなんだ』と思い込むしかない構造がある。
ここでは、その思い込みがどうやって“自分の一部”になってしまうか、そして、それをどう解体していくのかに触れていこうと思う。
- 親の言葉は、子どもにとって環境の“真理”
- 否定された感情が自己概念と癒着する構造
- 『自分はダメだ』の信じ込みを解体する力とは?
① 親の言葉は、子どもにとって環境の“真理”
『だからダメなんだよ』
『そういうとこが悪いの』
『ちゃんとやらなきゃ』
『なんで一番じゃないの?』
『あの子にはできるのに、あなたはなぜできないの?私恥ずかしい』
『あなたのこういうところは、嫌だわ、だって…』
親に言われたこういう言葉、思い出せる?
子どもにとって、親の言葉は“意見”じゃなくて、自然界の法則レベルの『真理』として受け取られるのよ。
雷が鳴ったら怖い、雨が降ったら濡れる、親が『お前は変だ、変わってる、ズレてる!』と言ったら、『変な自分が事実』になる。
論理じゃない。
説明でもない。
もっと根源的な、『空気と同化するくらいの自然な刷り込み』だよ。
それが、劣等感の“原型”として、知らないうちに心に沈殿していくから。
② 否定された感情が自己概念と癒着する構造
例えば、子どもが泣いたとき、親にこう言われたとする。



そんなことで泣くな!!
わがまま言うな!!
うるさい!!
これってつまり、『その感情はダメ』と言われているということになる。
で、子どもはこう変換していく。
感情を出す私はダメ→ 感情を持つ私はダメ→ 私そのものがダメ。
そのときのその感情がダメだと思うんじゃなくて、“感情を持っている自分”が、ダメだと感じてしまう。
例えば、他者と親のコミュニケーションの姿。



あのぅ….すみません….
↑これは、弱さと無力さを埋めるのよね。



これさぁ!!どうなってるわけぇ!!!



うちの子はぁ、〇〇の大会で優勝して~成績が学年トップでぇ~全校リレーでぇ~….
全部劣等感としてガンッガン埋め込まれていく。



当然だ。何をしているかの自覚は必要だって。
肯定感ゼロ。
そして自分の不足を埋める図な。
聞いてて痛々しいだけだって。
絶対関わらない層。
下2名は恥知らず、恥さらしだろ。
こうして、否定された感情が“自分そのもの”と癒着していくし、親の自己肯定感の低さからくる、下げ・威圧・自慢ぜーんぶ余裕で埋め込まれて行く。
で、一生抜けないの。
大人になっても、『素直になれない』『怒れない』『悲しめない』『子どもが嫌い』『自信がない』、こういう人の多くが、この構造の中で感情と自己を分ける力を失って投影していく。
ややこしいのは、え?怒ってるけど?っていうヤツね。
そう、何に怒ってるのか分かっているようで、わたしから見たらぜーんぜんよ。
無自覚層ばーっかりね。
③ 『自分はダメだ』の信じ込みを解体する力とは?
ここがいちばん肝心なところ。
『自分はダメだ』と思ってる人に、



いやそんなことないよ!
って言っても、響かない。
だって、それは、その人の中の事実だから。
根付いてる。
この“事実のような思い込み”を変えるには、外からの言葉じゃなく、内からの再構築が必要になる。
これが結構骨折れる。
たとえば、常に自分に、こう問いかけてみる。



どう思ったの?
どう感じたの?
なぜそう感じたの?
こうやって、自分を理解して行こうとする思考が大事。
自分の感情を取り戻し、その奥にあった『ほんとうは言いたかったこと』を見つけ出す。
その過程で、そこから、“本当のわたし”の輪郭が、ようやく見えてくる。
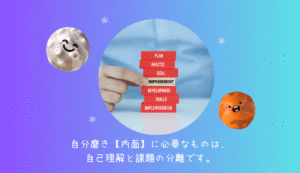
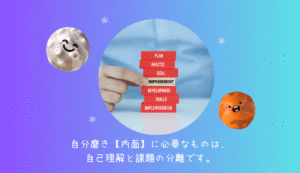


『罵倒したくなる自分』の正体を見抜く
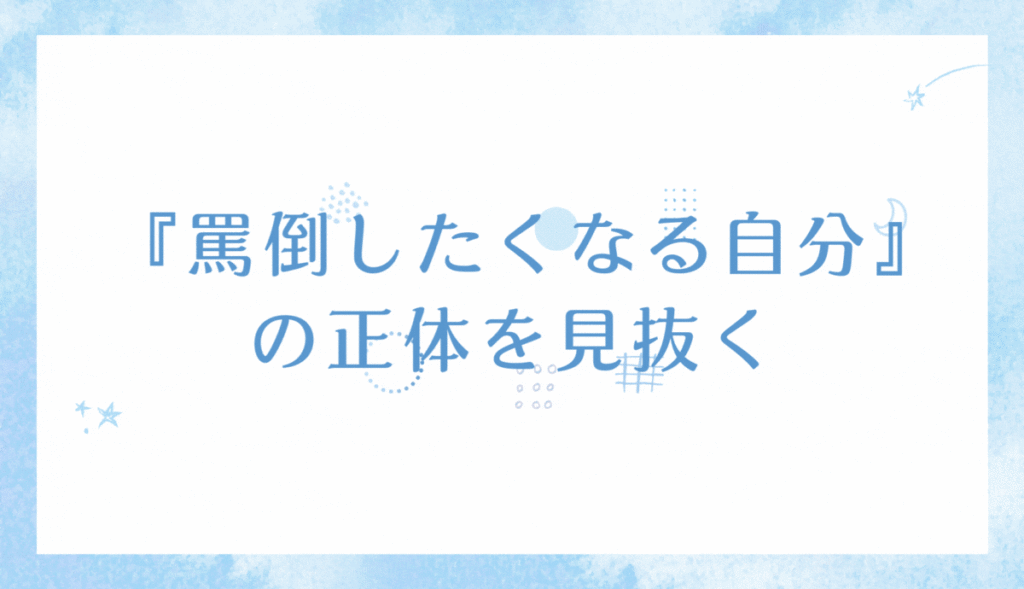
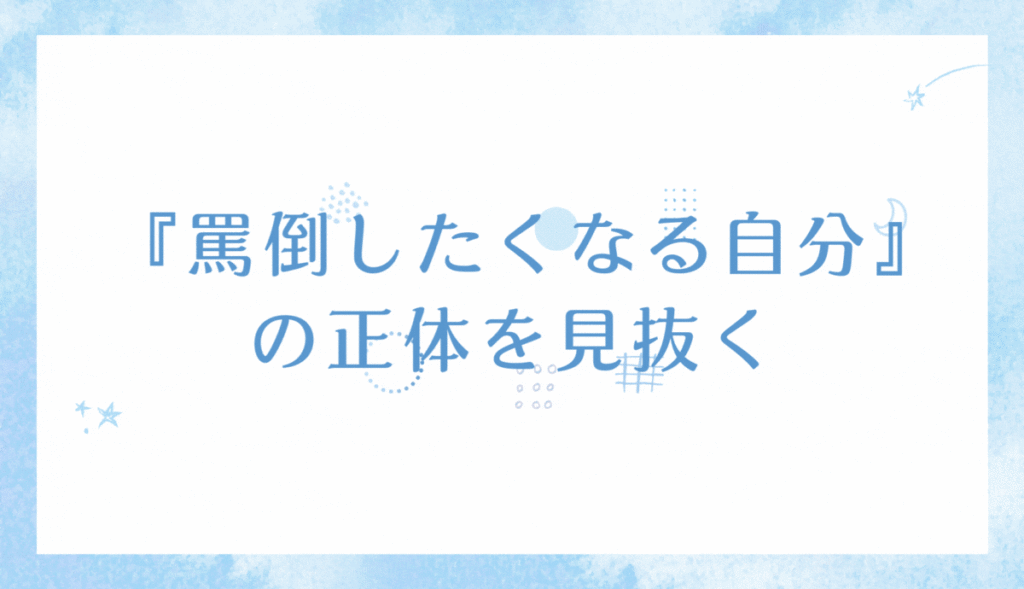
怒ってる。ムカついてる。相手の態度が許せない。
そう思ったとき、わたしは昔のわたしに会いに行く必要がある。
なぜなら、“罵倒したくなる感情”の奥には、たいてい自分がかつて罵倒された記憶が、すっと立っているからだ。



どうしてあの人はわかってくれないの?
なぜそんな言い方をされなくちゃいけないの?
…わたし(俺)のせいにしないで。
今の怒りって表面上は目の前の相手に向いてるけど、実際は子どもの頃の自分が抱えたままの怒りが再生されているケースがとても多い。
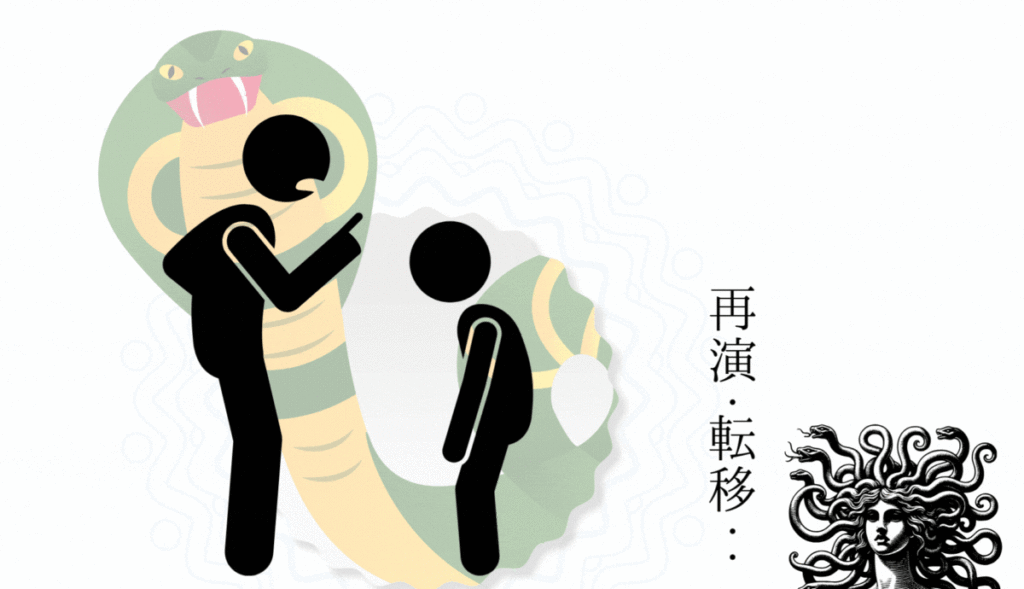
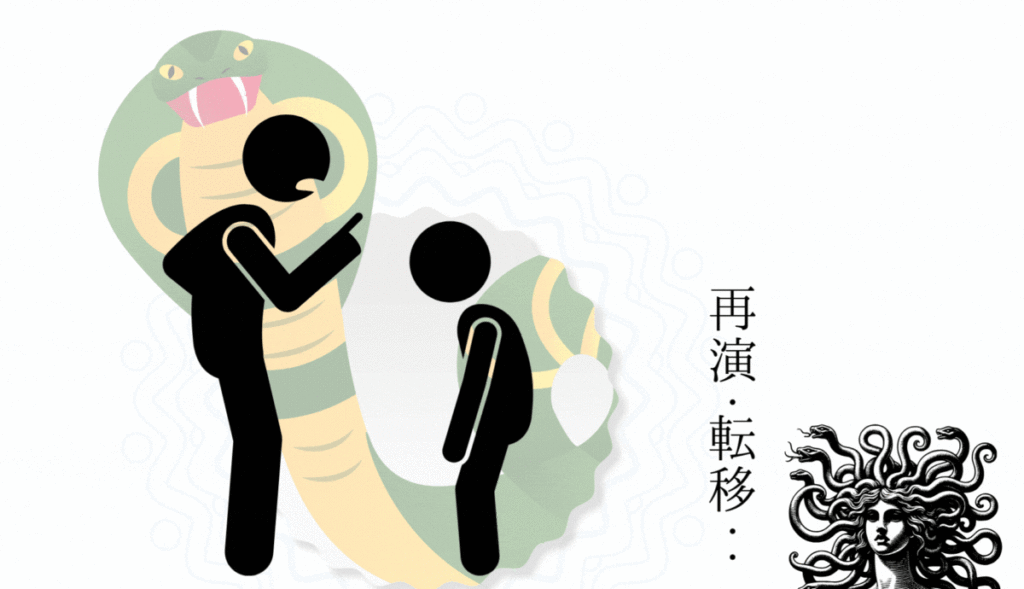
- 親に否定されたときの悔しさ
- 理不尽に怒られたときのやるせなさ
- 受け止めてもらえなかった寂しさ
そういう『当時言えなかった感情』が、似た状況や似た雰囲気の相手に出会った瞬間に“今ここ”に噴き出すんだって。だから、強烈にムカついたり、怒りのトーンがズレてるときほど、実際には『今の自分』じゃなくて『昔の私』が前に出てきてる。
つまり、その怒りは “相手に向いてるように見えるけど、本当は過去の自分が叫んでる”証拠だな。
ここで気づいてあげられると、今の相手に過剰にぶつけずに済む。
今、他者に感じている怒りは、もしかしたら、ずっと言えなかったあのときの言葉の可能性。
- その怒りは、誰に向けられていた?
- 過去に受けた罵倒が、他者に再演されるとき
- 『他人への嫌悪』の中にいる、本当の“わたし”
① その怒りは、誰に向けられていた?
目の前の相手が悪い!…….ように見える。
だけど、怒りのトーンがどこか過剰だったり、ズレていたりすることってない?
それは、現在の相手じゃなくて、過去の“誰か”に言えなかった怒りが、時間を超えて噴き出してる証拠だ。
わたしにとって、それは親だった。
- 口答えすれば『黙れ』
- 泣けば『泣くな』
- 正直になれば『反抗的だ』
その時、心の中に押し込めた怒りが、まるで火山のマグマのように、別の誰かに向かって吹き出す。
怒ってる相手が、ほんとうに“目の前の人”なのか、ちょっと立ち止まってみてもいい。
だからわたしはいつも、目の前の人には、目の前の人の事情があるから、その人の感情と行動を分けて受け取る。
もっと違う目線で言うなら、何の関係もない他者に自分が脅かされる理由もない。
それでも、状況を理解することはできる。
勝手にしたらいい。
そんな感じかな。
相手の情動を認識しながらも、そこに飲み込まれない選択ね。
② 過去に受けた罵倒が、他者に再演されるとき
ある種の怒りは、ただの感情ではなく“構造”として起こる。
その人の言動が、どこかで『昔の罵倒の再生』になっているとき、わたしたちは『今ここ』にいるのに、『あの頃』に戻ってしまう。
そして、こうなる。
- 『許せない』→ でも本当は、『認めてもらえなかった、認めてもらいたい』
- 『嫌い』→ でも本当は、『愛されたかった』
- 『あなたなんか!』→ でも本当は、『理解してほしい』
罵倒は、自分を守るための切り札になってしまうけど、本当の願いは、もっと奥にある“分かってほしかった”という声だろう。
罵倒したくなるとき、感情そのものは『防衛反応』。
でも、それをキャッチして『本当は何を望んでたの?』と掘り下げると、自分の奥に隠れてた未完了のニーズが見える。
『罵倒したくなる感情=自分が生き延びるために必要だったツール』でもある。
なら、仕方ないじゃない。
それは良しとして、気づいた今から選び直せばいいだけだ。
③ 『他人への嫌悪』の中にいる、本当の“わたし”
『こんな人、ほんと無理』
『レベルが低い』
『あなたみたいな人、ほんと嫌い』
そう思ったときこそ、チャンスかもしれない。
なぜなら、その嫌悪の奥に、本当の“わたし”が潜んでるから。
嫌悪って、自己防衛のアラートでもあるけど、同時に『ここに触れられると、自分が揺らぐ』という“核”の在処でもある。
その感情の在処は?
そうやって言われた自分と、そう言っていた親の投影の可能性。
そしたら、そこから選び直せばいいだけだ。
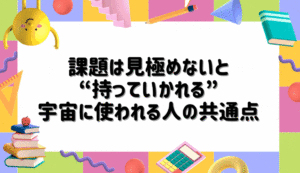
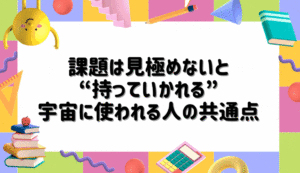
克服していない者は、教えることができない
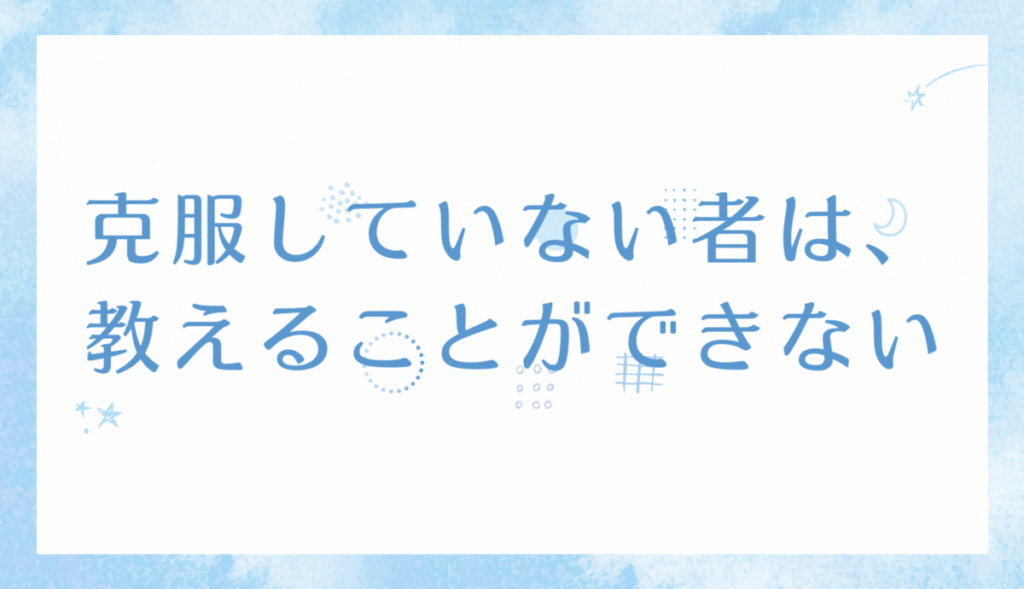
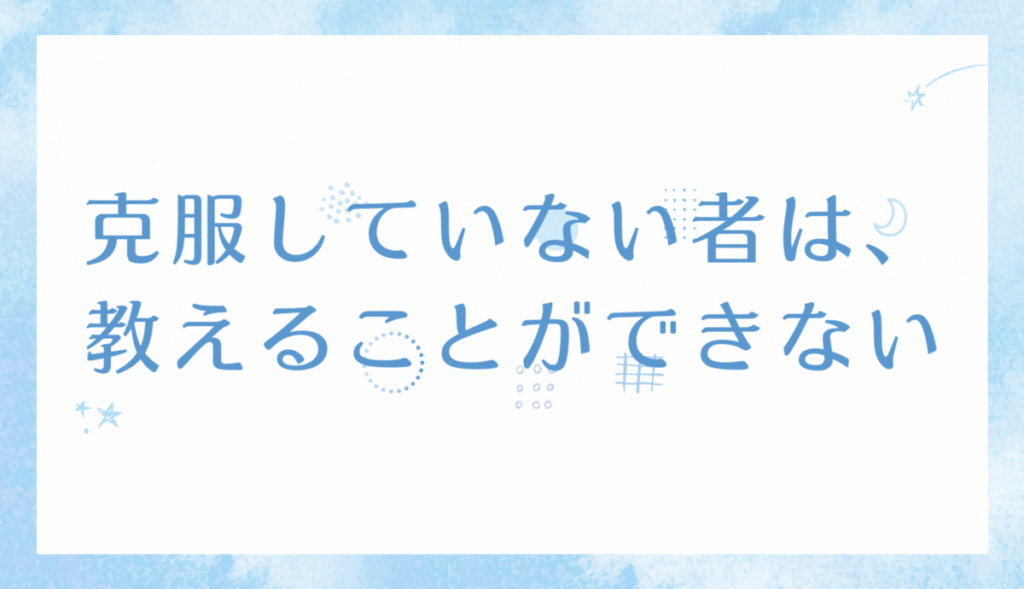
人は、自分が乗り越えていないものを、他人に“教える”ことはできない。
それをしてしまうと、『教える』ではなく、『ぶつける』になるからだ。
たとえば、親が自分の中の“無力感”や“自己否定”を克服しないまま、子どもに『自信を持て』『努力しなさい』と言ってしまうとき、その言葉には、未解決の怒りや焦りがにじむ。
すると子どもは、言葉よりも“その温度”を受け取ってしまうから、感情に潰される。
つまり、克服してないまま差し出される教育は、子どもにとっては“支配”や“罵倒”にしか見えないんだよね。
- 親は“自己未解決”のまま教育に入る
- 支配・操作・罵倒という感情的教育
- 『言ってること』は正しくても、『伝わらない理由』
① 親は“自己未解決”のまま教育に入る
親自身が、自分の傷や劣等感を未処理のまま持ち続けていると、それを『子育て』という形で無意識に子どもに乗せてくる。
- 『ちゃんとしなさい』
- 『そんなことで泣くな』
- 『人に迷惑をかけるな』
教育や子育てでよくあるのが『親が子どもに言ってることが、自分自身に言いたいこと』ってケース。
→ たとえば『ちゃんとしなさい』は、『私はちゃんとできてないと思ってる』から出てくる。
だから本当に子どもに“伝わる教育”をするには、
まず先に親自身が
『自分の痛みをどう扱うか』
『自分の未解決をどうケアするか』
をやらないといけない。
じゃないと、教育しているように見えて、実際は他者目線による“自分の課題”を子どもにやらせてる構造になる。
そりゃ、うまくいかないよな。
その課題は、子どもの課題じゃないんだから。
性格も個性も違うぞ。
② 支配・操作・罵倒という感情的教育
言葉はきれいでも、感情の温度が支配的であれば、それは教育ではなく“押しつけ”に変わる。
- 『あなたのためを思って』→ 実は『自分の期待どおりに動いてほしい』
- 『失敗しないように』→ 実は『自分が失敗を恐れている』
親自身の『不安』や『恥』の感情が消化されていないと、子どもにとっては“罵倒”や“過干渉”という暴力になる。
そして『不安』や『恥』を植えられる。
そしてそれは、子どもが自分の感情を押し殺してでも、『親の機嫌を取ることが安全』だと学ぶきっかけになってしまう。
このロジックよな。
③『言ってること』は正しくても、『伝わらない理由』
親の言葉が、内容としては間違っていなくても、子どもに届かないのは、“その温度”に問題があるからだ。
たとえば、同じ『頑張って』でも、
- 自分の努力で乗り越えた人が言えば、希望になる
- 自分の苦しさを未処理のまま投げると、脅しになる
子どもは、言葉の意味じゃなくて、“声の後ろにある何か”を感じ取ってる。
その頑張っての前後にある、あなたの態度や言葉から。
子どもは思ってるよりも賢いんだよ。
賢くても染まるのが子どもなんだって。
いくら賢く育てたところで、根っこは親だ。
ジャンプ台ならいいが、沼なら沈むよ。
自然の摂理だろ。
だからこそ、『何を言うか』より『どこから言ってるか』のほうが、大事だ。
じゃないと、伝える言葉が変わってくるからだ。
その言葉から発せられるのが承認欲求であれば、何も伝わらないよ。
沼のままだ。
わたしに心理学が通用しない(通用させない)理由
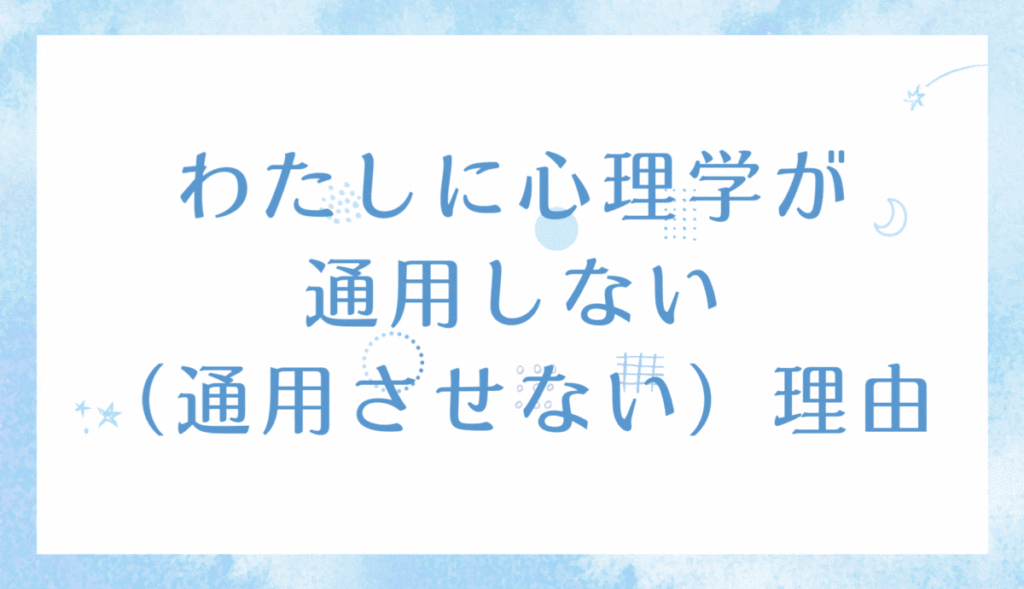
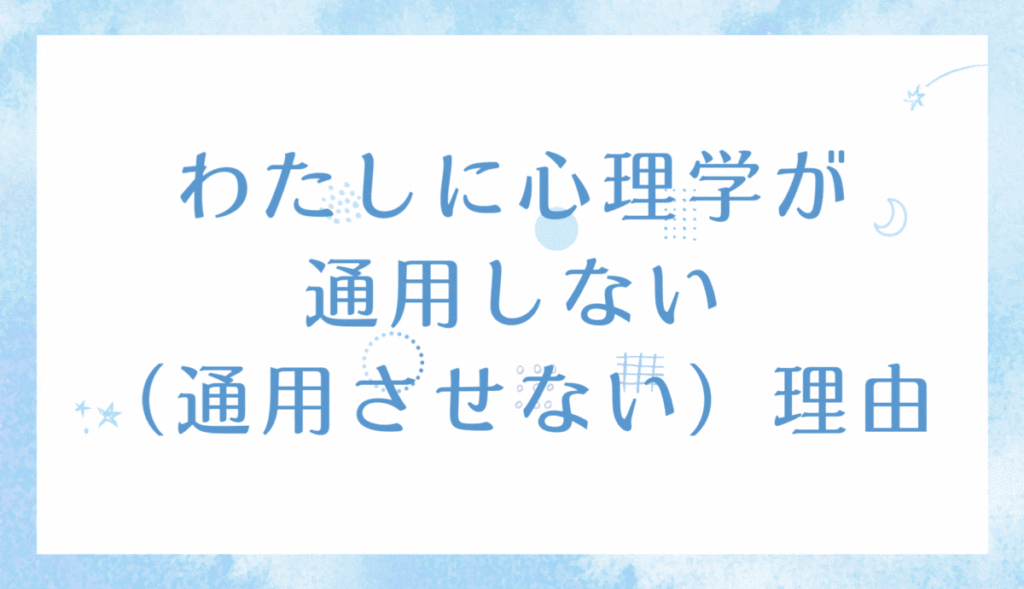
ところで、わたしに、浅い使い方の心理学は通用しない。
それは、心理学を否定しているからではない。
むしろ逆だ。心理学の本質、つまり人間の構造を問う力を重視している。
ただ、巷にあふれる心理学の使われ方に対して、
『それ、本当に“構造”を見てる?』
と問いたくなることもある。



言葉の表面だけをなぞって『これは〇〇タイプ』。
それ、分析じゃなくて分類。
理解じゃなくて操作。
- 知識としての心理学は、構造を問わない
- 構造を見抜く力こそ、本物の洞察
- 『使い方の誤った心理学』への拒絶
① 知識としての心理学は、構造を問わない
心理学を“知識”として扱うとき、それは『人をわかった気になれるツール』になってしまう。
- この人は愛着不安型だから…
- これはトラウマ反応だから…
- それは投影ですね…
…そう言ってる間に、関係の構造はスルーされている。
本当なら、相手の言葉や沈黙の奥に何があるのか。
その構造を見ようとすることが大事じゃないかと思える。
でも、表面的な“知識”に留まってしまうと、人は『構造の内側』には入れない。
② 構造を見抜く力こそ、本物の洞察
『その感情はどこから来てる?』
『なぜ、今この反応をしたのか?』
『この関係の構造は、何を再現してるのか?』
そこに切り込めてこそ、洞察だ。
そして、それができるのは
──構造を見抜く目を持っている者だけ。
知識や経験から補える。
③ 『使い方の誤った心理学』への拒絶
拒絶しているのは、心理学そのものじゃないよ。
- 相手を操作するために使われる心理学
- 自分の無自覚な劣等感を守るために使われる心理学
- 相手を黙らせる“カード”として出される心理学
それは、嫌いだ。
心理学は武器じゃない。
人を黙らせる道具でもない。
人の現在を確かめる道具でもない。
『構造を見つめる対話』
のために使うものだと思うよね。
わたしは、通用しないんじゃない、“通用させない”んだよ。
通用してないんじゃなくて、使い方の誤りを見抜いているだけだって。
使うのは自由だが、自尊心は必須だと思うよ。
なぜなら、自尊心がない者は他者尊重ができないからだ。
見抜いたところで、ごと、見抜くよね。
洞察も同じだよ。
通用しないだと、防御が固くて鉄壁に感じるかもしれないよね。
通用させないということは、攻撃は効いてるけど、その攻撃を受けないという選択をしてるに過ぎないんだって。



気づけ。
サイボーグじゃないよ。
人間だ。
忘れてんじゃないの?
毎回毎回、あぁ、このやり取りは〇〇のお試し行動なんだろな。
こう思わされるこちらの身にもなれ。
人を試す者ほど、人を馬鹿にしてる証拠だって。
知らずに乗らされたとしても、そこで得たカードは全部、わたしのモノになる。
つまるところ、相手が自分の愚かさを露呈している事実にもなるでしょ。
どういうところで人を見ると思うの?
そういう行動一部始終だって。
あなたが、普通の行動としてしている行動は、実は〇〇である、これは普通にあることよ。
わたしの世界ではね。
けど、わたし側の世界じゃないと、見えないみたい。
孤独な真理──わたし一人で気づいたという重さ
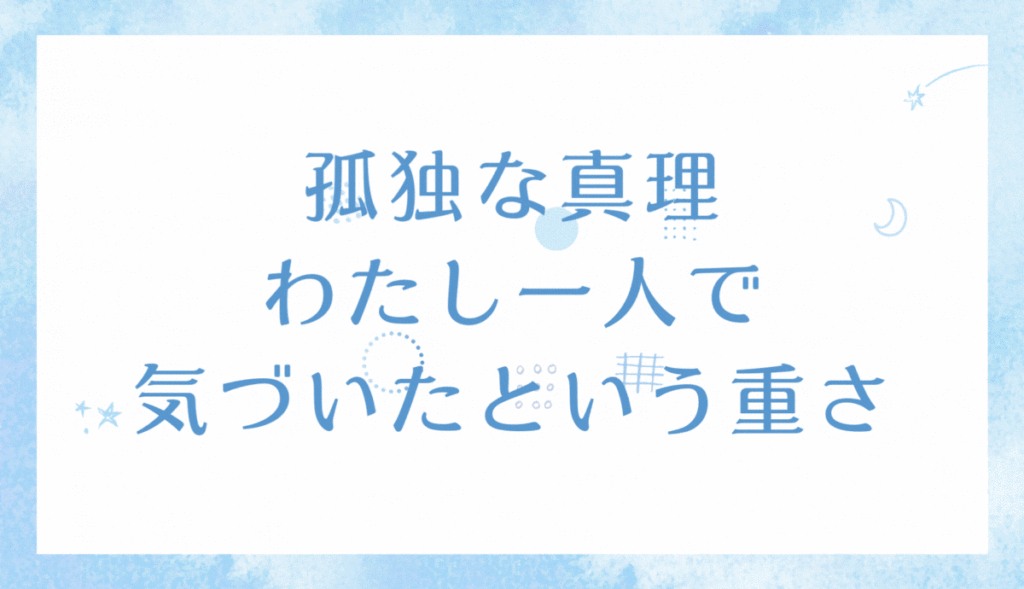
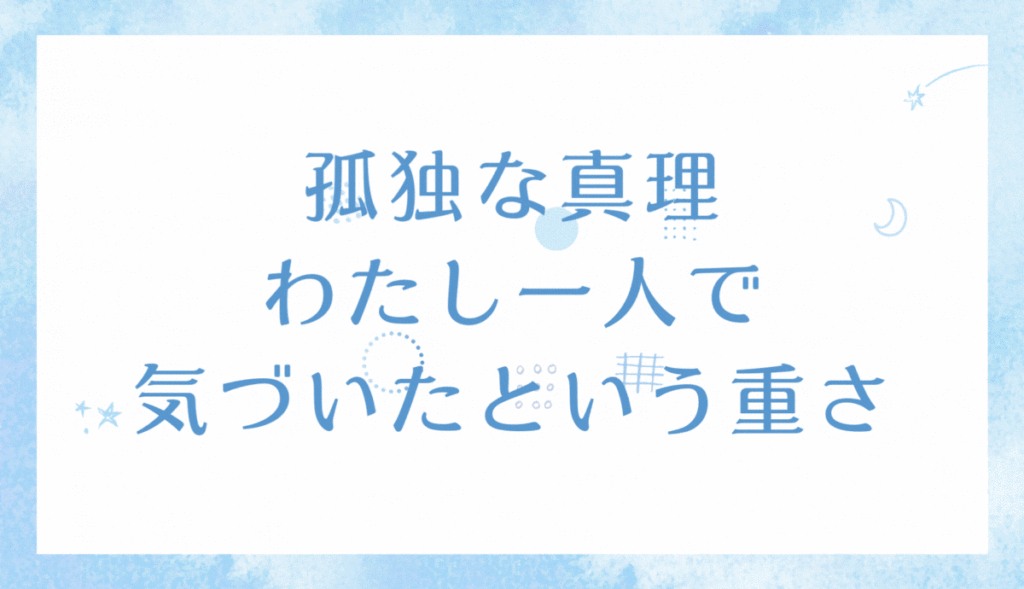
この記事にまとめた“気づき”は、誰かから教えられたものじゃない。
セミナーに通ったわけでもないし、専門的に学んだわけではない。
ただ、日常の中の違和感をずっと見つめていたら、ある日、それが線になって繋がった。
それから整合性を調べた、そのまとめ記事。
瞬間的に腑に落ちた。
『ああ、そういうことだったのか』と。
でも、その瞬間から、わたしは孤独。
だって、誰もまだ知らない“真理”を知ってしまった自分が、そこにいたから。
- 誰のせいでもないと腹落ちする瞬間
- 『真実』に辿りついた
- 折れて、叫んで、それでも立っている自分へ
① 誰のせいでもないと腹落ちする瞬間
『親のせい』
『環境のせい』
『相手のせい』
それらを越えて、
『でも、今のわたしの感情はわたしのものだ。』
と心の底から思えたとき、それは一種の静かな絶望だよね。
だって、もう誰も責められないから。
責めることができない場所に、自分が立ってしまった。
② 『真実』に辿りついた
言葉にできない違和感。
他の人が『それでいいじゃん』と流すところで、ひとりだけ『いや、良くない、なにかおかしい』と止まってしまう感覚。
誰にも相談できない。
言っても伝わらないとわかっている。
だから、自分でたどり着くしかなかった。
気づいてしまった。
誰にも知られていない真実に。
わたしの中にだけある、それ。
苦しかった。
でも、知ったことで、わたしははじめてわたしになれたのも事実。
③ 折れて、叫んで、それでも立っている自分へ
気づいたとき、心はバッキバキに折れた。
世界がぐにゃりと歪んで、信じていた構造が全部崩壊。
『もう無理』とも思った。
だけど、叫んで、泣いて、それでも立つ。
誰かのせいにせず、自分の目で見て、自分の足で立つ。
わたしの人生の、リ・スタート。
日本の構造的無意識
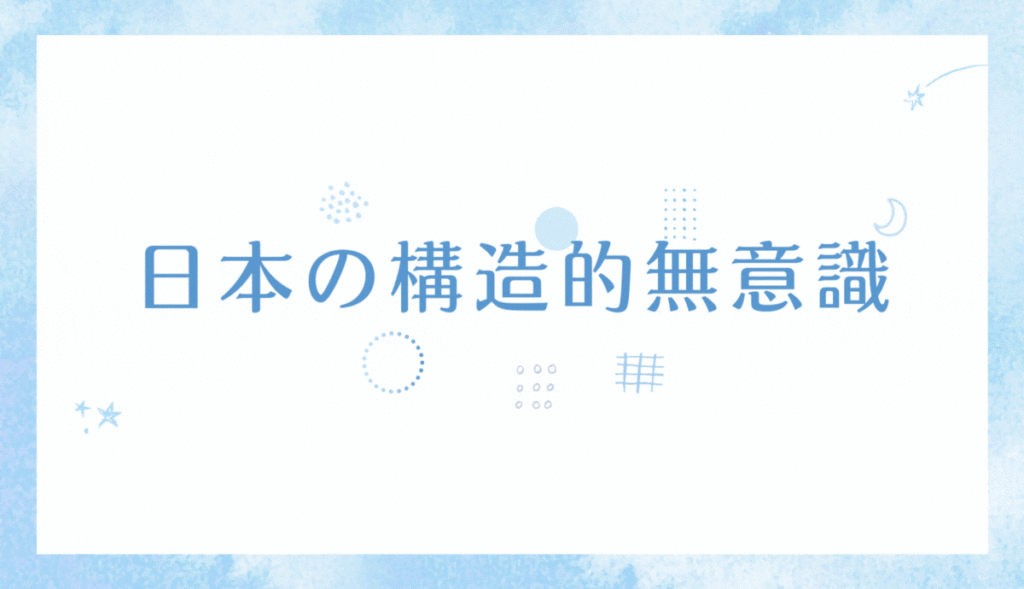
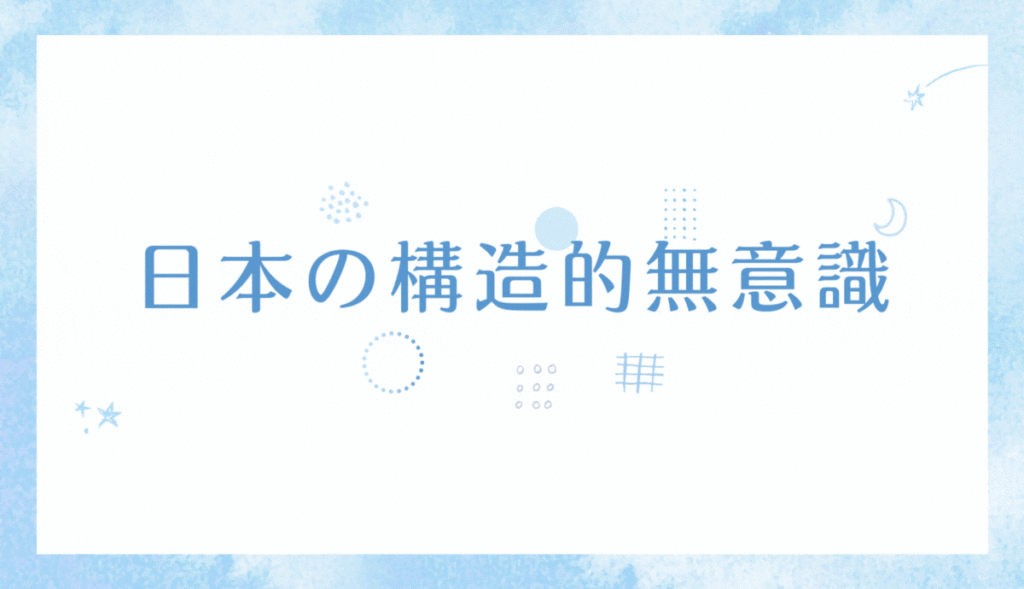
『これは恋愛なのか?それともただの依存か?』
そんな問いすら曖昧になるのが、日本の恋愛文化だ。
“好き”と“必要”が混ざって、“情”が“呪縛”になる。
それなのに、誰もその構造を言語化しない。
それが“当たり前”として、世代を超えて静かに継承されていく。
構造的無意識。
見えないのに、支配しているもの。
気づかれないから、なおさら強いもの。
恋愛だけじゃない。
家族も、教育も、職場も、全部がその構造にあるな。
- 依存が『情』にすり替わる文化構造
- 察し・我慢・境界不在の愛
① 依存が『情』にすり替わる文化構造
本当は『ひとりで立てない』ことへの不安なのに、『情が深いから』と言い換えられる。
自立と依存の境目がぐちゃぐちゃになって、
『放っておけないから』
『私しかいないから』と、
“離れられない理由”だけが増えていく。
その感情って何?
そう言った瞬間、冷たい人扱いされる。
“共依存”が“人情”に変換されがちな国、ニッポン。
『情がある=素晴らしい』が、関係性の誤認を温存させているような気もする。
② 察し・我慢・境界不在
日本は、『言わずに察すること』が美徳とされがちだ。
- 言わなくてもわかってよ
- 私が我慢すれば、関係は壊れない
- あなたのために、私を殺す
そんな呪いが、まるで愛情の証のように語られてなかった?



うざ….
でも、そこに“自分”はいる?
- 察することが、感情の放棄になり
- 我慢することが、自己の抹消になり
- 境界線の不在が、共倒れの始まりになる
それでも、誰も疑問を持たない。
なぜなら、それが『普通』だから。
③『対等な関係』が教育されない国で生きるということ
学校でも、家庭でも、恋愛でも、『対等な関係とは何か?』を教わらずに大人になる。
誰かが上で、誰かが下。
力がある方が正しくて、我慢する方が優しい。
そんな構造の中で、愛なんて語るから、関係はすぐに歪む。
対話じゃなくて、服従。
理解じゃなくて、評価。
“対等な関係”を求めた人だけが、孤立する構造。
でも、そこに立ち続ける人だけが、この無意識を超えて、新しい関係をつくっていけるんじゃないかと思うわ。
まとめ
子どもの脳や心は、親や周囲の言動を『環境の真理』としてそのまま吸収してしまう。
とくに否定・罵倒・無視・過干渉とかは、自己価値や世界観の“土台”になる。
脳の可塑性が高い時期に繰り返された体験は、感情・行動・反応パターンに無意識のレベルで染み込む。
つまり、『なかったことにはできない』。
植えられたもの=履歴/構造の一部として、確実に残る仕組みだ。
自覚すれば、『この反応は、わたしの本心ではなく、かつて植えられたものだ』と気づける。
気づければ、それに自動的に従う必要がなくなる。
つまり、選択権を取り戻すことができるんだ。
植えられた種は、根絶やしにはできないけれど、それを育てるのか、乾かすのか、光を当てるのかは、自分で決められる。
『消せない』けど、それに『支配されない』選択が必要だと思う。
わたしの場合は、植えられたものが“他者批判”だったり、他にもいろいろある。
でも、それを自覚して『どう使うか』を選んでいる。
他者批判は誰にでもある。
だからこそ、それを悪い方向じゃなくて、受容や選択のためのエネルギーにできる。
あなたにも、きっとそういう“植えられたもの”があるはず。
それを自覚して方向を変えれば、自由の入り口はもっと大きく開いていく。
ちなみに、わたしは普段心理学なんて適用しながら話さない。
あらかた分かることはあるけれど、けど挑まれたら受けるしかないから、受けてみただけだ。
独学だけど、整合性はあると思う。
この記事を置いて置く。
こうやって伝えていても、分からないかもしれない。
自己理解の浅さからくる投影。
わたしの知識は串刺しではあるよ。
けど、絶対じゃないから。
こう思うよってだけの記録よ。
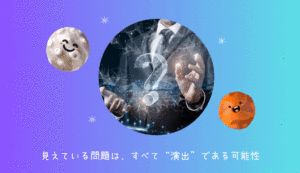
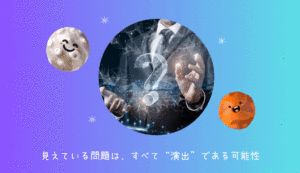

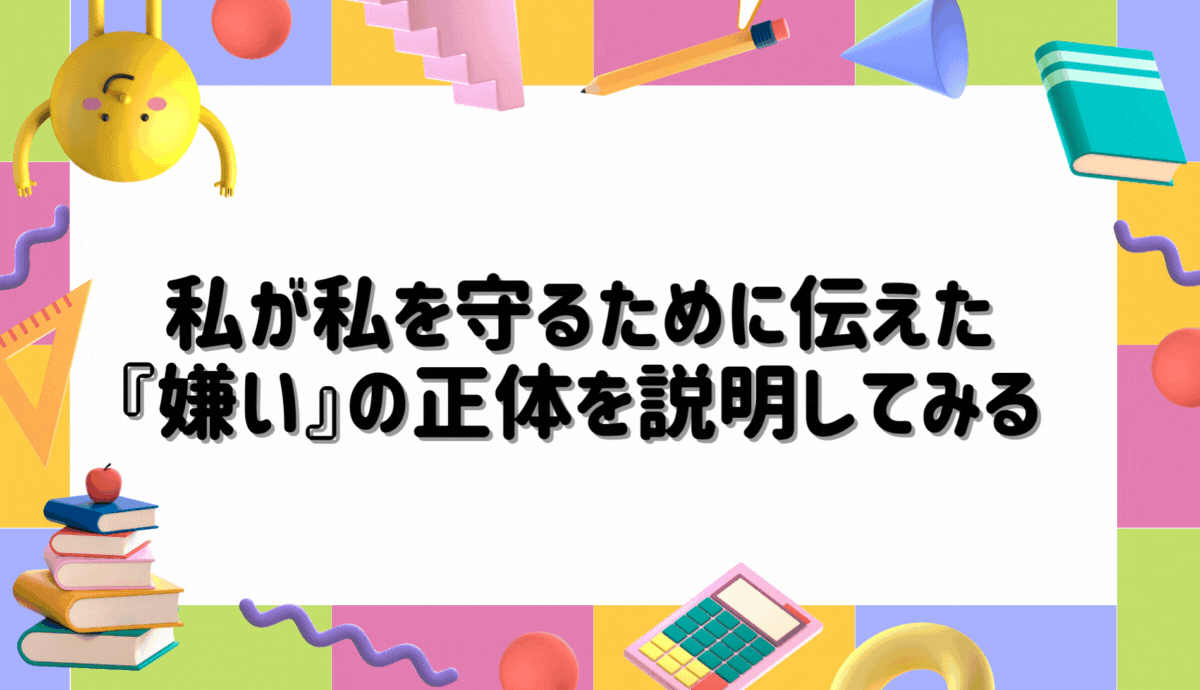
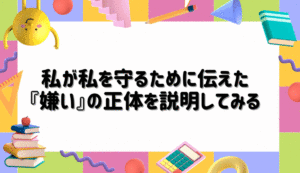
コメント