『土の時代』から『風の時代』へ移行したと言われてるの知ってます?
えぇ、移行してるんですよ。
だけど、『風だから軽やかに!』『好きなことして生きていこう!』みたいなキャッチコピーだけを受け取ってしまうと、かえって危険。
なぜか?風は自由であると同時に、流されやすい性質を持つから。
土の時代は、地位や所有といった目に見えるものが価値の基準。
序列や権威みたいな外枠が強固にあったから、多少の思い込みや投影も社会が吸収してくれて、安定を保てた部分があったと思う。
つまるところ、個人は病んでも、社会全体は『持った』時代。
だけど風の時代では、情報が一瞬で拡散しやすいし、個人の投影や感情すら『正義』として広がって行きやすい。
自覚のないまま流されれば、広がるはずの世界が逆に狭くなるし、他者を否定し、自分自身を檻に閉じ込めてしまう。SNSや論争の場で見られる混乱は、その象徴でもあると思う。
だからこそ大事なのは、『風に乗ること』よりも『自分のハンドルを握ること』。
そう思う理由を、この記事にまとめてみました。
風の時代をどう生きるか?のヒントになると思います。
風の時代と土の時代の違いを表にまとめてみた
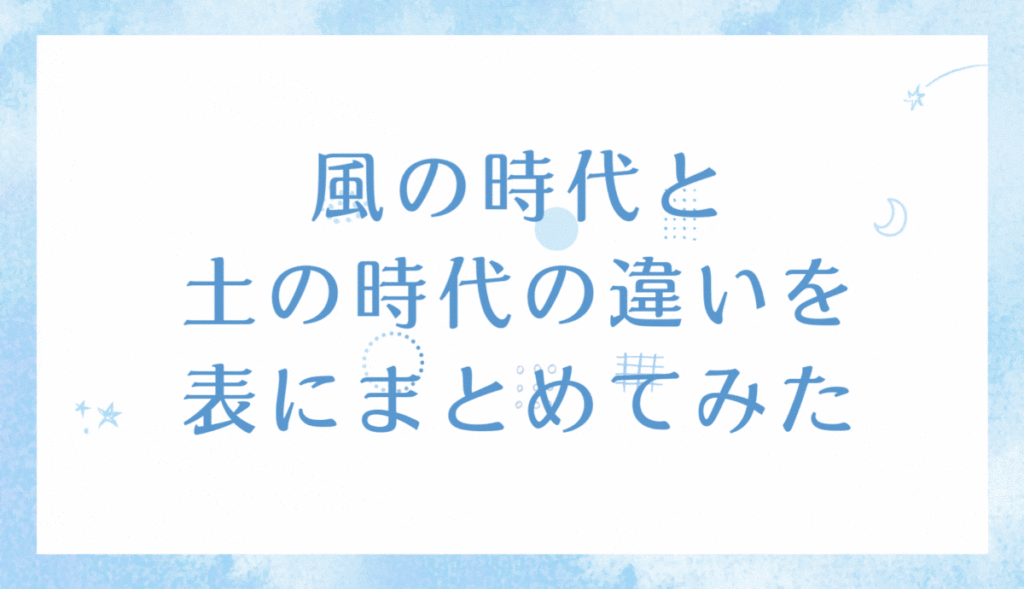
風の時代をざっくり言うと『物事の展開の速さ、AIへの移行、SNSによる情報過多』こんな感じかと思う。
土の時代と風の時代の違いを表にまとめるとこんな感じかな?
| 項目 | 土の時代 | 風の時代 |
|---|---|---|
| 価値の源泉 | 有形資産(お金・土地・建物・肩書き・資格)お金そのものが価値と信用の中心 | 無形資産(思想・情報・信頼・ネットワーク)お金は依然必要だが、価値を生むのはアイデアや関係性 |
| 影響力 | 役職・肩書き・序列で支配物理的に囲い込む | 思想や情報精度、構造理解 |
| 情報の扱い | 権威筋の発言が正義 | 権威筋の発言は淘汰、情報精査が必須(発信者の意図も含めて) |
| 淘汰のポイント | 長く立場を保てれば影響力維持 | 中身と一貫性がないと即失脚、事業内容が他人軸起点になっていると淘汰される |
| 教育の焦点 | 詰め込み型・記憶重視 | 問う力・構造理解力(ただし教育制度はまだ追いついていない) |
風の時代の落とし穴
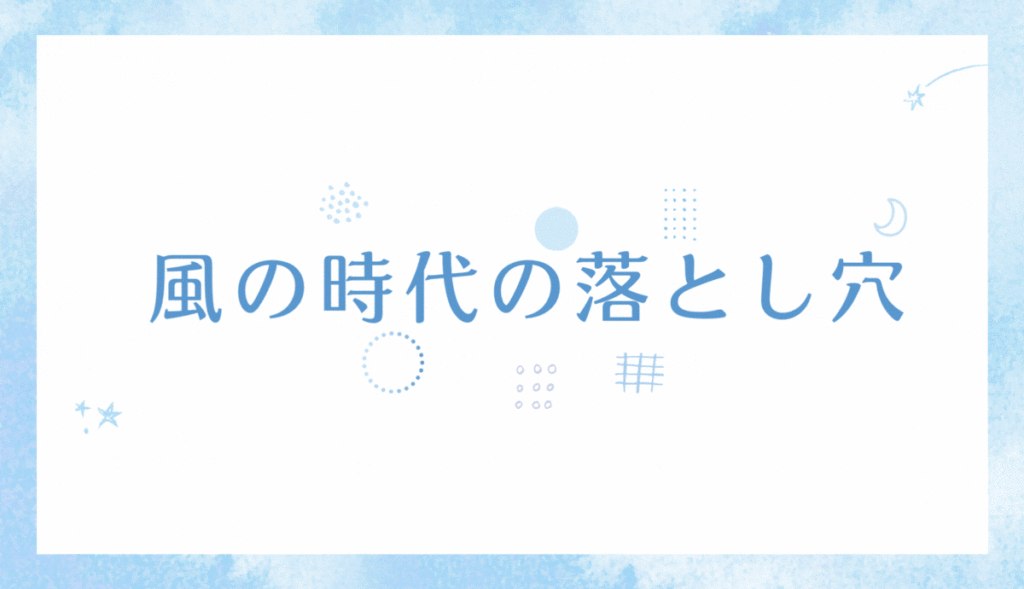
コロナ禍のとき、わたしは『9月入学論争』に参加していた。
だって、モロに弊害を被る側だったから。
あの議論は、まさに風の時代の第1段階を象徴していたとも思える。
ニュースを目にしたのが少し遅くて、声を挙げないとと思って恐る恐るSNSに行ってアカウント作成して、扉を開けたらそこは大嵐だったのよ。
ちょっと遅れたの。
だけど、大嵐でホッとしたの。自分と同じ考えの人たちがこんなにもいてくれてる。
そういう安堵感よ。
すぐに参戦した。
誰をフォローすべきか、否か、その情報収集からだった。
ある高校3年生のTwitter(今ではX)の投稿が拡散されて、約10万件もの『いいね!』が付いたのがキッカケとなる。
土の時代から風の時代への移行期は、2020年から2023年頃までとされていたから、この論争は移行期のものになる。
どれだけTL(タイムライン)が荒れていたか。
中身はすごかった。
賛成派と反対派の争いのえげつなさ。
誰も冷静じゃないのよ。
批判の内容が人格否定になるような物であれば、スクショを取って拡散して訴えるという者までいたから。
その行動の所為は?
数カ月に及ぶ争いだったけれど、その中で唯一『この子すごい』と思えた生徒、僅か1名か2名。
弊害をすべて語った上で、現状を変えるのではなく、前に進む選択が必要だという意見。
ようやく、わたしと同思想。
だけど、これが現状だったよ。
賛成派の他の意見を覚えている限り羅列してみよう。
- 俺たちの青春を返せ
- クラスの仲間ともっと過ごしたい
- 子どもはすぐ慣れる
- 保育園・幼稚園の子どもが友達なんて意識している訳がないから、弊害はない
- 修学旅行に行きたい
- 9月にすれば多様化になり、グローバル化できる
- 子どもを計画的に出産とか気持ち悪い、授かり物なのに
精査は省く。
これが大半だ。
余談だが、わたしだから、これにどう問うてみたかの想像は安易かもしれない(ちょっと問うてみたくなったのよ)。『グローバル化について説明してみろ。』、『多様性とは何だ?』こうだな。
答えられた者は、1人としていなかった。
来た返信。
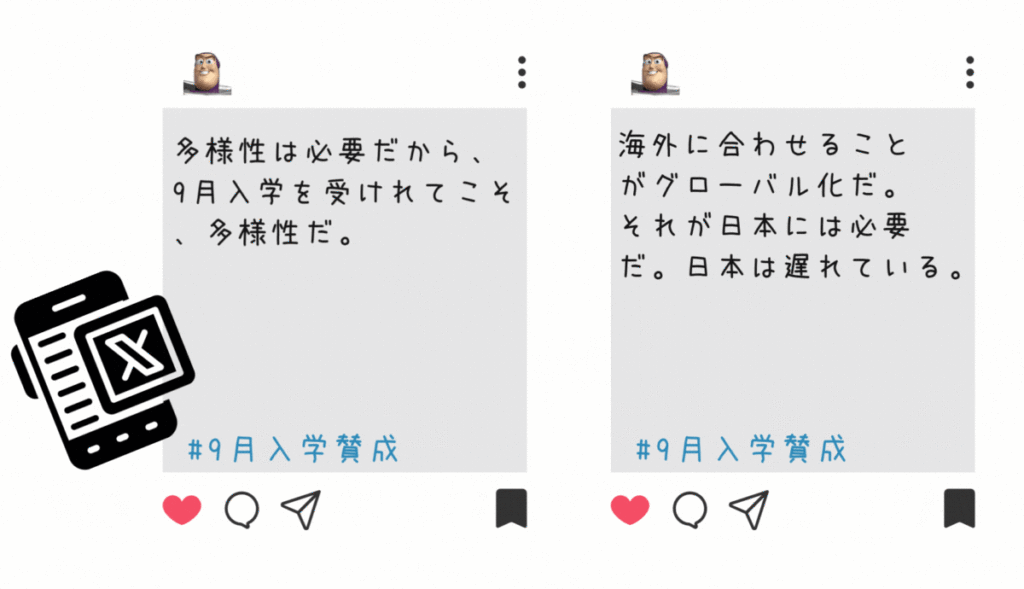

なるほどな。今の教育を見れば、これも別に普通のことだと断定できる。
何ら不思議ではない。
一応答えを書いておく。
グローバル化は、実際は国際的な相互作用や多面的な交流のことであり、本来の多様性は価値観・生き方・背景を認めることだ。
同じ反対派の人から、
『無理だって、問わない方がいいと思うよ。』
というアドバイスまで貰った。
SNSでは『とりあえず自分に都合がいいから』という理由だけで賛否を叫ぶ人があふれていた。
メリット・デメリットを精査せず、雰囲気や感情、未来を見据えない今だけを見て動く。
これはまさに“情報の川に流される”姿そのものだったとも思える。
しかもテレビなどマスメディアでは、反対派の意見はほとんど取り上げられない。
最後の最後まで『賛成多数!』という空気を作って、コメンテーターと一緒に世論を一方向に押し流そうとする力を感じたのは事実。
お昼のワイドショーも全てだ。



賛成派多数なんだ~



そうみだいねぇ……….じゃ、ないんだよ!!
だからわたしは、テレビを観ない。
まぁ、その前からほとんど観てなかったけどね。
もっと観る気がなくなった。
政治家目線で言えばさ、『未来の票vs現在の票』になるわけよ。
どっちつかずのあの発言。
観てて、まぁ、そうとしか言えないよねぇと思ってたけど。
だって選挙あってみてよ、賛成派に票を入れるワケにはいかないからね。
選挙があれば、親世代はしっかりチェックしていた。
派閥、人物、その周辺までね。当然だ。
本来なら『子ども・家庭・経済』あらゆる面から多角的に議論をすべきなのに、誰も弊害を語らない。
まるで『空気に飲まれる、風の時代の練習会』みたいな現象だった。
結局、国会で見送る形に収まったけど。
その中で、もし日本で9月入学を来年から始めた場合、新小学1年生をどうやって入学させるかについて2つのパターンを例示した。1つ目は2014年4月2日から2015年9月1日生まれまでを新小学1年生とする案。2つ目は2014年4月2日から2015年5月1日生まれまでを新小学1年生とする案である。後者は1ヶ月ごとに緩やかに移行していくことで、学年ごとの児童数の偏りや教員数不足を最小限にするメリットがあるとされる。
Wikiペディア
弊害を語るなら、半年就職が遅れる。
その間の税収はどれだけ減るのか。
そういう現実的な視点も必要だったよ。
私は個人的に『制度を壊すことで、一番の被害者は我が子になる』と考えてたから。
新しい制度を導入しても、結局どこかで誰かが痛みを背負う。
ならば、今の制度をわざわざ壊す理由はどこにあるのか?
我が子の精神的なケアを考えると、リスクが大きすぎる。
だから私は反対だった。
ただ、それを納得させるだけの『理由』は最後まで示されなかった。
少なくとも、子どもを授かる前の事前アナウンスくらいは必要な案件だ。
小さい意見を言うなら、荷物が重いんだよ、スクールバスくらい用意しろ。
学年後倒し案もあったからね。
海外より遅れる案。笑
9月に合わせることに意味がある!笑
パッと思いついただけでも、保育園・こども園・幼稚園での学習体制も必要な挙句、幼・保・小教員の採用要件や指導要件も変更になるだろう。
正直、一番大事なところだよ。
現場は混乱でしかないのは容易に想像できる案件だ。



学年ごとの児童数の偏りや教員数不足を最小限にするメリットがある?何のメリットだ。
ここで思い出すのは、二ーバーの祈り。
変えられないものを受け入れる静けさを
変えられるものを変える勇気を
そしてその二つを見分ける知恵を
9月入学論争は、この祈りを試されるような時間だった。
変えられないものは何か?変えられるものはどれか?その判断はとても難しかった。
あの論争は、実は『親 vs 親』ではなく、『生徒 vs 親』の図だったと思う。
どういう背景があったのか、知らない人も多いと思うよ。
生徒たちは『今の自分の時間』を守りたかった。
親たちは『未来の子どもたちへの影響』を心配した。
方向は違えど、みんな必死だった。
ネットニュースじゃダメだ、新聞で活字になるまで安心してはダメだと言われ、ようやく新聞に掲載されたと思う。
その必死さの総体として、最終的に『制度を壊さない』という選択に落ち着いたのではないだろうか。
それは、言い換えれば『親の愛情が勝った』とも見える。
保護者側は、動き方も戦い方も戦略的で、賢かったよ。
実際には、色々な諸問題が多すぎて、見送る形になったんだけどね。
その中でも、授乳中の方とかいるわけよ。
声の掛け合いも『無理はしないで、子育てで必至だろうから、できる人だけ動いてください!』こんな感じだった。
記憶も朧気だけど、とにかく皆一生懸命だった。
学年ごとの児童数の偏り?教員数不足?──そんな机上の論理よりも、現場で泣き叫ぶことになる子どもと、必死で守ろうとする親の姿こそが、あの議論の本当の主役だったとも思う。
どんな形であれ、皆が、コロナ禍により弊害を受けたんだ。
その事実が欠乏しすぎだよ。
TL(タイムライン)では、賛成派と反対派の声が飛び交い、感情の応酬が続いていた。
けれど不思議なことに、大学入試や進路に関する冷静な生徒側の意見は、ほとんど目にしなかったなぁ。
私の想像にすぎないけれど──おそらくそういう人たちは、声を上げるより『変えられないものは受け入れ、いま自分にできることに集中しよう』と腹をくくり、学業に励んでいたのではないだろうか。
まるで、ニーバーの祈りを心に秘めるように。
だって、学校行けないからってサボってたら、そりゃ大変になるでしょ。
あそこは、先を見据えてどういう行動を取れたか?正否別れたと思うよね。
身近に入試抱えた人いなかったから、分からないけれど。



あの9月入学論争は、ただの教育制度の議論じゃなかったと思う。
風の時代に入った途端、情報と感情に飲み込まれる“空気の支配”を象徴した事件でもあったと思う。
怖さを感じた。
思い出すだけでも、嫌な事件だけど、記憶にあるのは、その必死さの中でも、笑いを飛ばしながら、毒舌で戦う人とかもいて、元気をもらったのも覚えてる。
楽しい人だった。笑(何の話だろうか)
結局、この事件の背景はどこでも語られていない。
けれど実際には、裏で多くの気づいた保護者が戦っていた。
SNSを駆使し、FAXや電話、署名活動まで。
だけど小さな子どもを抱える層は必死でも、子どもがもう対象年齢を過ぎた保護者層は、生徒側に立つことが多く、数の上では圧倒的に少なかった。
反対派の中には、もしものときのためにプラカード買ってる人もいたからね。
『無駄になった』とツイートしてたけど。
無駄になって良かったってみんなから言われてたよ。
他人事じゃなく、もしこれが自分の家庭に直結する案件だったら?恐怖を感じると思う。



数カ月に及ぶ論争の中で、私が目撃した『構造を読める生徒』は、わずか1名か2名よ。
みんな気づいたらどう?正しく問える存在がいないとき、社会はどれほど脆くなるかを。
知らなすぎるのよ。
拡散が政治家の目にとまり『いいね!』じゃないのよ。
ふっざけんな。
こういうのすぐに利用されるよ。
10万件よ?未来の自分の票になるじゃない。
案件が通ろうが、通らなかろうが関係ないのよ。
裏をひっくり返せば、票集めの可能性だって十分あるのよ。
パフォーマンスに利用できるでしょ。
どんどん利用されるのよ。
このときの学生たちが、どう理解しているかは分からないけどね。
政治家としては、ラッキー案件よ。
それに巻き込まれるんだからね。
個々がしっかりした理念持っとかないといけない、と思うわ。
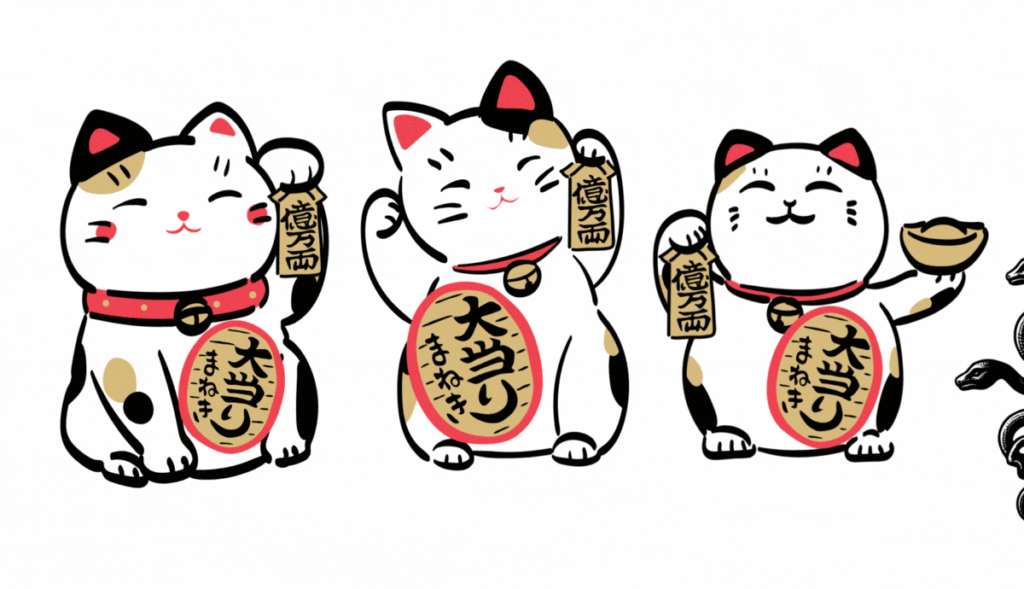
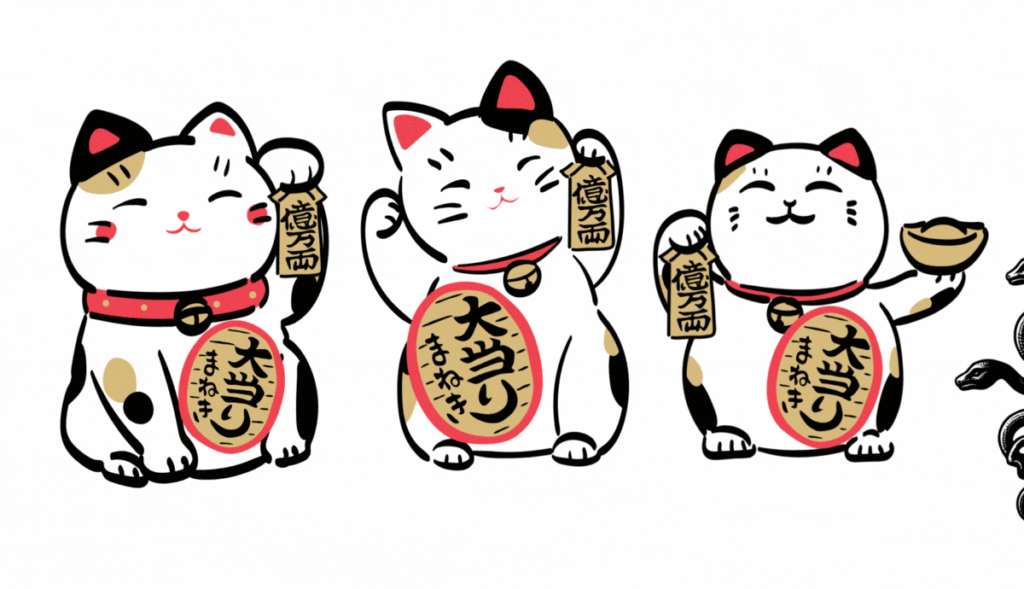
利用するもの、されるもの、その流れも速いよね。
土の時代って、利害関係があっても『枠組み(会社・序列・制度)』があるから、その中で調整されて、不利益をこうむる人もある程度“限定的”だったと思う。
でも風の時代は、情報や流れが一瞬で広がるから、
- 利害の調整が追いつかない
- ちょっとした選択や発言が、予想以上に広範囲に影響する
- 『誰かの利益』が『別の誰かの損失』に直結しやすい
ってことが起きやすいんじゃないかな。
だから『別にいいでしょ』が、広い範囲で『不利益をこうむる人』を生み出すリスクにつながるんだと思う。
つまり、風の時代は“利害の波及範囲が爆速で広がる”から、土の時代以上に『想像力』と『配慮』が必要になる時代、とも言えるよね。
学びの質が生死を分ける
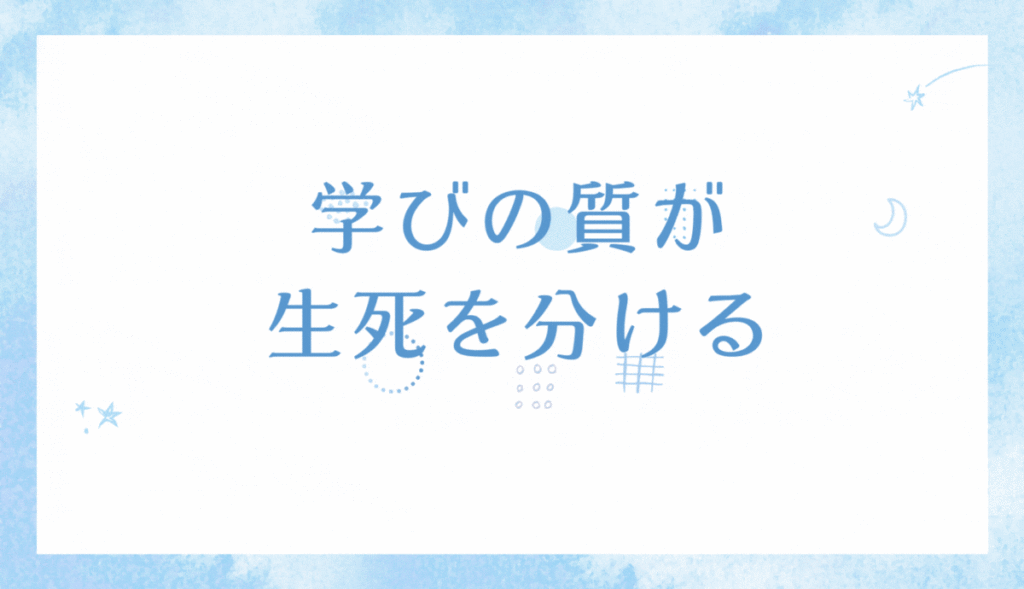
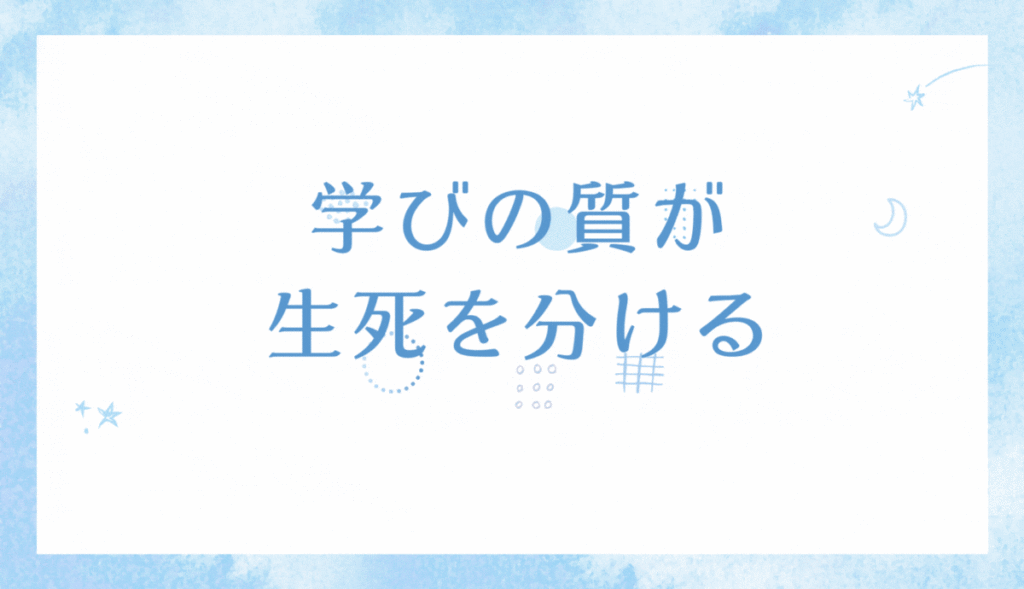
『風の時代は自由だ!好きなことで生きていける!』
よく聞くフレーズだけど、鵜呑みにすると危険でしょ。
自由って、つまり“自己責任”の別名。
情報の大洪水の中で、雰囲気や感情に流されれば、あっという間に迷子になる。
下手したら、スピリチュアル迷子か陰謀論クラスタ直行。
そこで命綱になるのが、 “自分で問える力”=構造を読む力。
『なぜ?』『本当にそう?』と立ち止まれるかどうかで、未来が変わる。
SNSの流行に『なんか楽しそう!』で飛びつくのは、見知らぬ車に『お菓子あげるよ』と言われて乗るのと同じくらい危ない行為。
でも、ここで問題。
いまの教育は『答えを覚えさせる』ことに必死で、『問いを立てさせない』仕組みになってる。
だから『学歴なんていらない!』と学歴不要論がバズるのも分かるわけだけど、実際には、基礎知識も批判的思考も持たないと、風に吹かれて一瞬でどこかにぶっ飛ばされる。
風の時代は“問う力”がないと即アウト。
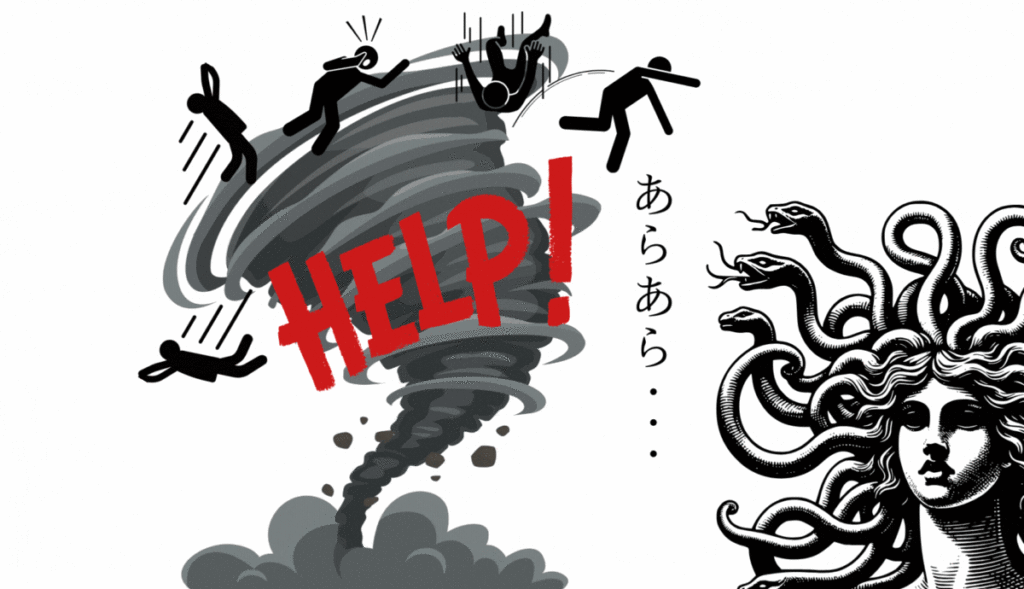
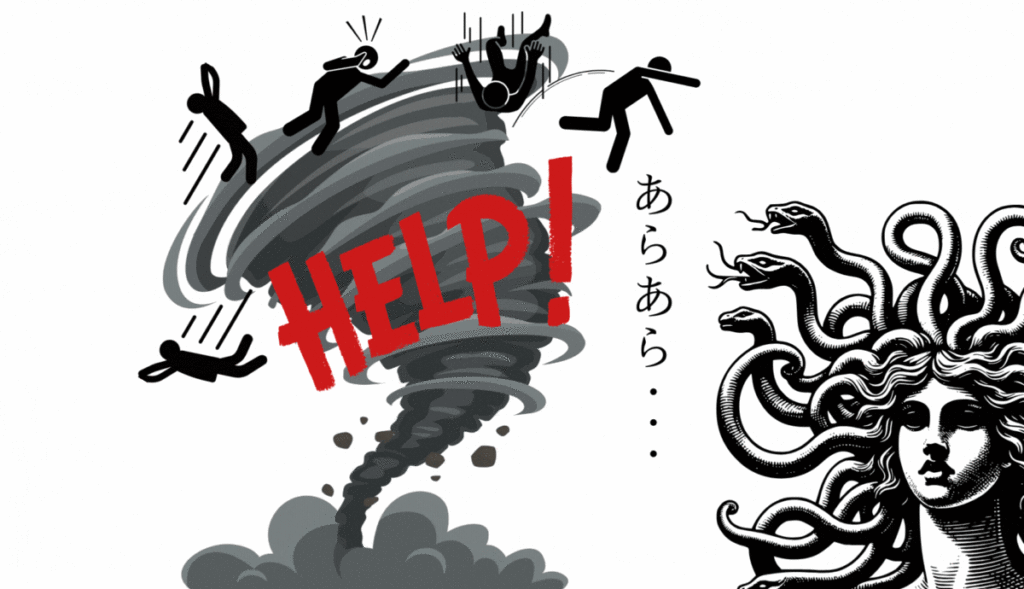
想像してみてほしい。柔らかい春風ばかりだと思う?甘いよ。
台風も竜巻もある。
竜巻に巻き込まれたら、着地点は『ここどこ?』状態で必須イベント。
方向感覚ゼロ、スマホも圏外、人生GPSすら狂う。
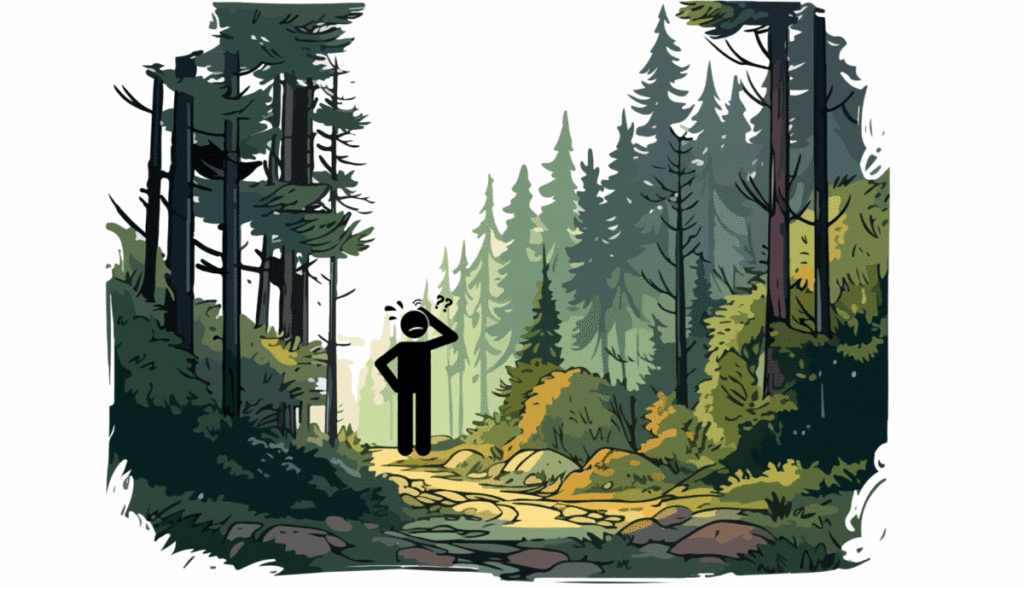
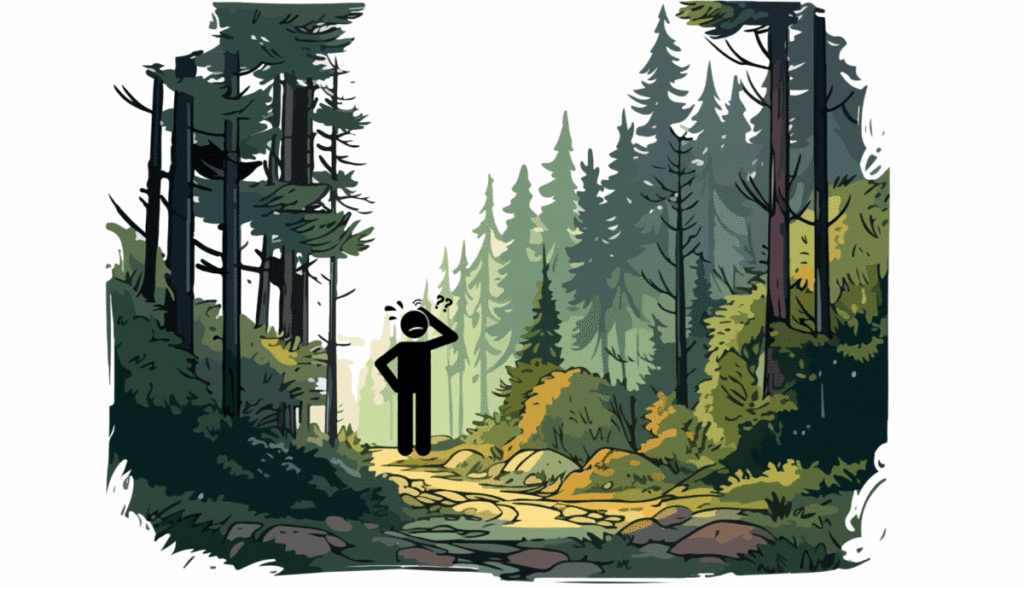
土の時代は『覚える力』だけで、まぁギリギリやっていけた。
でも正直、それですら生きづらかったんだよね。
それが風になる。
情報の流れは加速し、選択肢は爆発的に増える。
考え方を持たないままでは、竜巻の中を目隠しで歩くようなものでしょ。



風の時代を生き残れるかどうかは、『どれだけ問える頭を持ってるか』にかかっていると思うよ。
じゃないと、迷子だ。
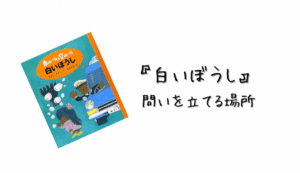
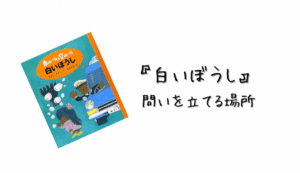
『やりたいこと』を見つける難易度
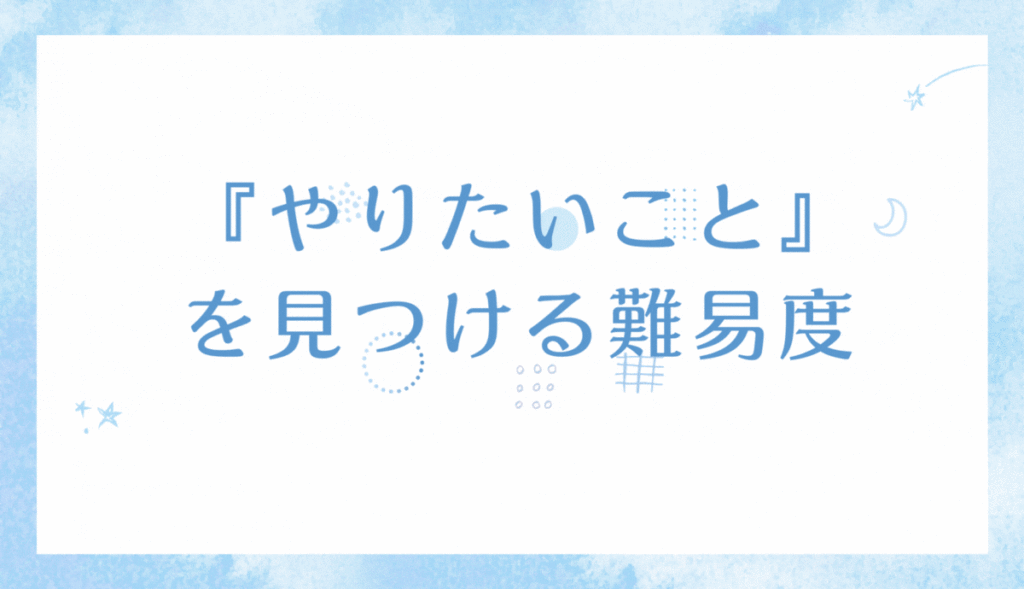
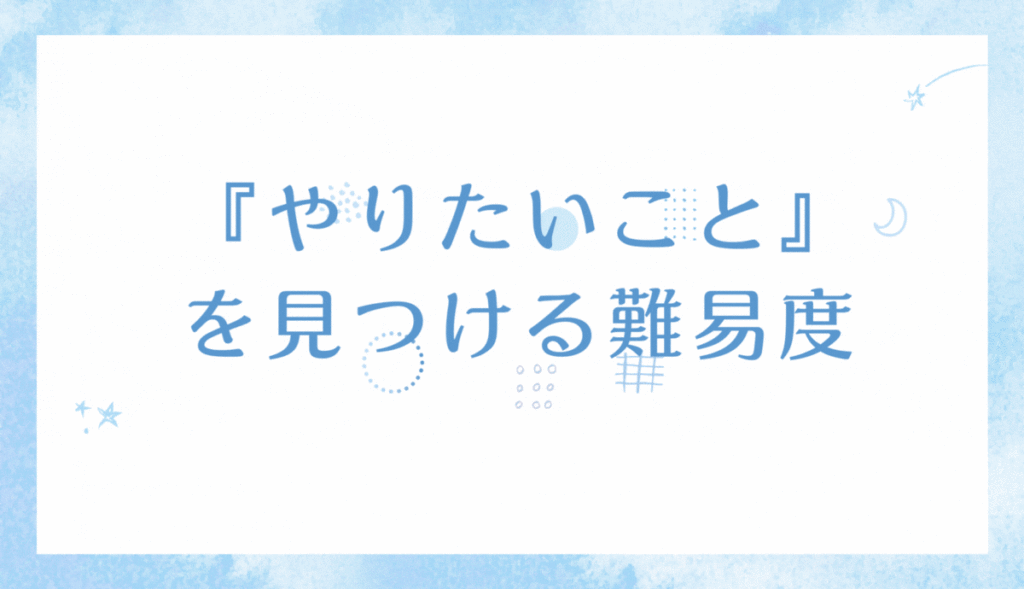
見つけられないまま感情や流行に流されると、人生ごと持っていかれるリスク
- これからは自分らしさの追求を!
- 常識にとらわれない生き方を目指す!
- やりたいことで生きていける可能性が高まる!



笑っちゃわない?
『やりたいことで生きろ!』『常識を壊せ!』『自分らしく!』…って聞くと、なんか自己啓発セミナーの広告みたいに見えない?(笑)
確かに風の時代は、やりたいことを仕事にできるチャンスが広がる時代。
でもね、そもそも『やりたいことが分からない!』って人が大多数。



自分軸が推奨されるこの時代に、他人軸の商品を販売して、自分らしく生きましょう!って言ってる人もいるからね。
何がしたいのか分からないでしょ。
そしてそれを精査もせず、買う側もいる。
どっちも風の時代の淘汰リストに入るよ。
焦って流行や感情に乗っかるとどうなるか?流される、巻き込まれる、持っていかれる。
はい、人生ごと一瞬で強風に吹っ飛ばされる。
焦っちゃだめだと親の言いなり、それでも吹っ飛ばされる。だって自分で選んでないもの。
そこで自己実現とか言われてるけど、その自己実現の仕方すら間違えてるからね。
自己実現の二極化よ。
だからこそ大事なのは、派手なスローガンじゃなくて
『自分は何に違和感を覚えるのか?』
『どこに問いを立てられるのか?』
を掘ること。
これをやらないと、せっかく自由度が上がった風の時代でも、結局は『流され組』に入っちゃうよ。



『やりたいこと』を見つけること自体が難しい、教育現場はそこを一切サポートしていないから、自分でしっかりしておかないと、簡単に流される時代。
このブログに全部記してきたわよ。
まぁ、『難しい』ってよく言われるわ。
仕方ないと思う。
みんな、教えてもらえないもの。
だから、難しく感じて当然といえば当然。
もっとかみ砕く必要があるんだとは思う。
そこは、ごめんなさいね。
心理学で言う投影※土の時代と風の時代への影響の仕方
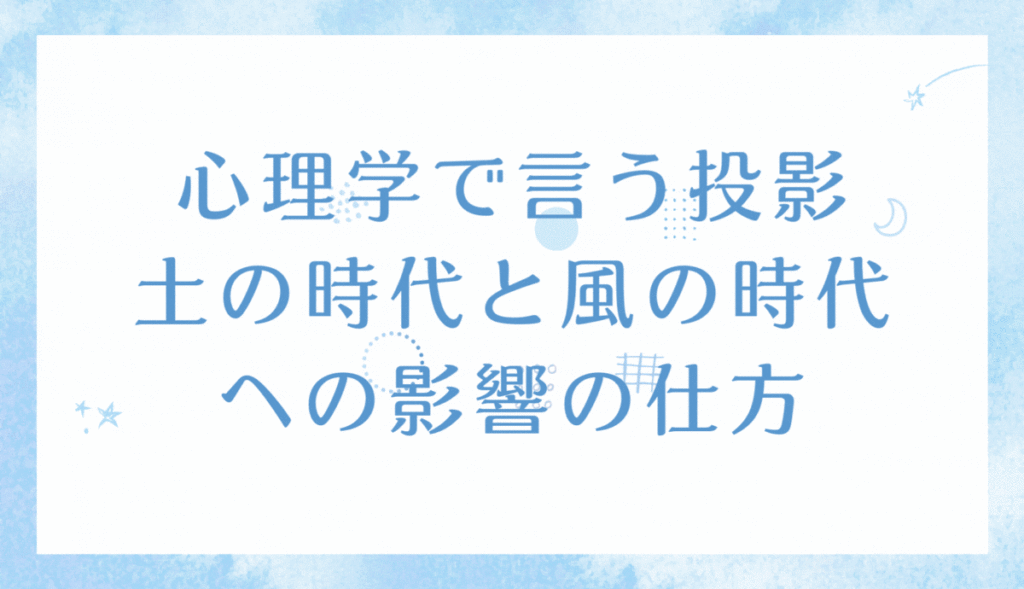
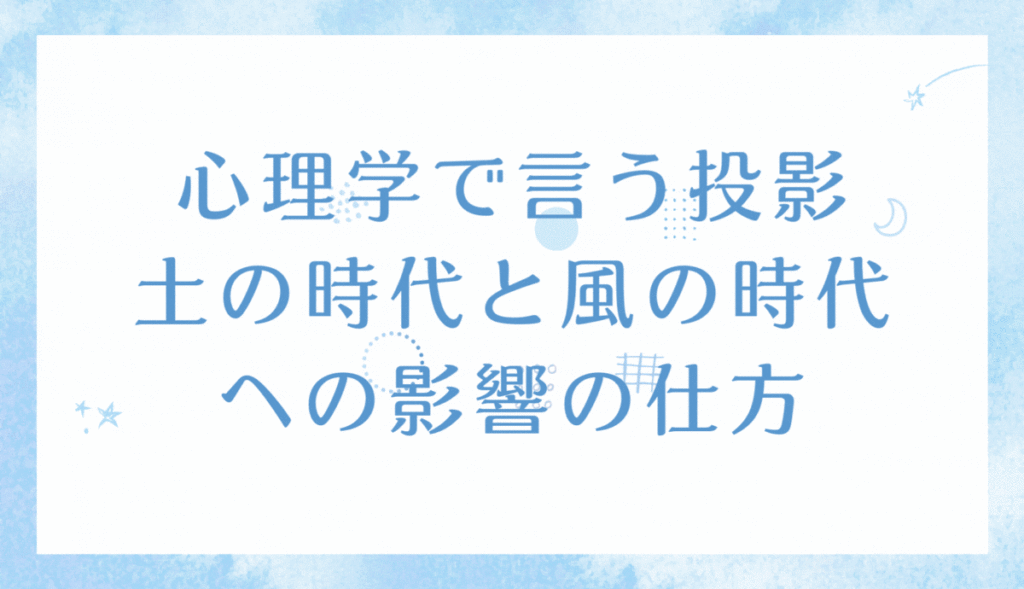
風の時代は
『生きたいように生きる』
『多様性を尊重する』
とよく言われてますよね。
本来なら、誰もが自由に世界を広げられるはずの環境。
けれど――もし投影に気づかずに生きれば、その自由は逆に足かせになる。
どういうことかというと、自分の解釈を“事実”と信じ込んだまま、世界を狭め、自ら檻を作ってしまう。
情報化社会では、自分の投影をそのまま『正義』として発信したり、他者を批判したりするのは容易い。
それは一時的な安心や優越感をもたらすだろう。
しかし実際には、自分の固執を強め、同じパターンの中で翻弄され続けるだけになる。
多様性を掲げながら、実際には他者を否定し、自分も狭い枠に閉じ込めている。
これこそが『投影に無自覚な風の時代』の生きづらさ、とも思える。
これは偶然ではなく、むしろ自然な法則のようにも見える。必然だ。
- 土の時代✕投影
- 風の時代✕投影
- 投影の本質は『土』でも『風』でも同じ
① 土の時代✕投影
- 投影しても『序列』『権威』『所有』という外的枠組みが強固にあったから、多少の投影は“秩序”に吸収されやすかった。
- 問題は“個人の抑圧”として蓄積するけれど、社会全体は安定して回る。
- つまり、個人が病むけど、社会はもつ。
- 情報伝達速度が遅い
投影しても、権威・序列・所有などの『外的枠組み』が厚く壁になり、個人の投影は社会の表に出にくいと推測。
② 風の時代✕投影
風の時代の投影も基本的には、土の時代の投影とさほど変わらない。
ただし、影響の仕方が違ってくる。
自分の投影をそのまま『正義』として発信したり、他者を批判したりするのは容易い。
それは一時的な安心や優越感をもたらす。
ただ、さまざまな情報が飛び交う中、SNSと同じで、批判する側に正当性があり、いくら外的枠組みが強固にあったとしても、多勢に無勢になる可能性すら存在していると思う。
情報化社会って、色々な人が色々な考えを発信するから、投影を通して自分も正しいと思い込むまでの距離が近くなるという危険性と言えば分かるかな。
どんなに『序列』『権威』『所有』という外的枠組みがあったとしても、多勢に無勢になれば、それは風化してしまう。その速度が速くなる。
そういう危険な時代だとも取れる。
③ 投影の本質は『土』でも『風』でも同じ
- どちらの時代でも、人は自分の痛みや未処理の感情を相手や世界に投影する。
- 『あの人は冷たい → 自分を軽視している』みたいに、事実と解釈をごっちゃにする構造は普遍。
SNS・情報化社会のスピードと拡散力で、投影がそのまま『正義』や『事実』として拡散。
→ 多勢に無勢の“共感圧力”が、権威や制度を一瞬でひっくり返すこともある。
→ 結果、個人も社会も巻き込まれて不安定化する。
投影の『構造』自体は昔も今も変わらない。
でも風の時代は『情報の距離が近い』=自分の投影を“真実”と錯覚するスピードと強度が圧倒的に上がる。
だから『無自覚な投影』がそのまま社会現象・炎上・分断につながる。
という予測も立つよね。いかに、個人がしっかりしないといけないか?が問われるよ。
別件だけど、同じ歌なのに歌詞が全然違う。面白い。
土の時代 → 深い内面や孤独を所有して味わう
風の時代 → みんなに見せる、拡散する前提で表現
1990年代末(Eiffel 65「Blue」)
2020年代(David Guetta & Bebe Rexha「I’m Good (Blue)」)
どっちもブルーなんだと思う。今の時代はブルーって言っちゃったら拡散されないもんね。
それをマーケティングに映したら、(ブルーだけど)大丈夫って言わないといけない。
個々がしっかりしとかないと。ブルーなのに大丈夫って言っててもいいけど、ブルーだって自覚は必要かもね。
じゃないと、ブルーなのに大丈夫って言っちゃうデフォができちゃうと思う。
個々の自覚(メタ認知)こそが風の時代を生き抜く鍵になるかも。



ただの個人的な見解だから。
「好きそう」って教えてもらった曲。確かに好きだけど。ありがとう。
この記事まで想定の範囲内?だとすごいね。どうだろう。
まぁ、考察させるなら、「前者と後者の違いどう思う?」が正解だろうね。気にしてないけど、人への誠実さというものは、そういうところで図られるのよ。気を付けてね。坊や。
試すつもりで、試されてるのは坊やの方。教えとかないと、気づきがないようだから。すればするほど….の世界が待ってるけど、そこへでも行くつもり?なかなかの冒険家ね。賞賛するわ。『注文の多い料理店』の記事、もう一度読み直してみて。



「Hotel California」にいる自覚さえあればいいのよ。坊やには、ないみたいね。けど、みーんないるんだから。わたしもいるわ。けどわたしは、シャンパンも飲みたくて飲むし、踊りたくて踊るの。飲まされないし、踊らされないの。警備員の配置とか、いる時間帯、出口の場所、人の欲の種類・構造まで網羅してるから。ちょっと違うのよ。笑
展望台から見える景色を、頂上と思うなかれ。
おい坊や、地図を書くのは容易ではない。
著者と読者を取り違える過信ほど、滑稽なものはない。
地図を書ける者と、ただ辿るだけの者。
その違いが見えないのは、どうだろうね。
わたしには見えるよ。
知識はあるけれど、自分の欠如分も分かっている。
勝てない者には勝てない。
それだけの知識があるからだ。
わたしは独学だしね。
だけど、それを卑下することもない。
挑まれれば相手が著者でも戦うだけの話。
ただ、その著者に一度勝ったからといって、著者に全面勝利した気になるほど愚かではない。



それが私だ。
見習え。
威は示すけど、敬も忘れはしないのよ。
威を示しとかないと、挑まれるから残すだけの話でね。そこに過信はないよ。
地図、複数枚必要だしね。
- 心理学の地図
- 哲学の地図
- 教育の地図
同じ出来事でも「意味づけ」や「見え方」が変わるじゃない。
一つの座標軸しかない者は「ここが正しい/間違ってる」としか言えない。
けど、座標を変えられる者は「この地図だとこう見える、別の地図ならこう見える」と重層的に解釈ができる。
わたし流で言うなら「マルチマップ思考」。
とてもじゃないけど、「全部の地図をわたし一人で所有しています」なんて口が裂けても言えないし、わたしは独学だから、①~③のどれか一つでも「完全に所有してる」と言えない。
自覚的だよ。
けど、ブログで文字に起こしている以上は、自信持って書いてはいるよ。
わたしのひとつの真実だとして残してる。
ただそれだけだよ。



もう一度言うよ。
①~③のどれか一つでも「完全に所有してる」とは言えない。これが事実だ。
だから、わたしに勝っても何の価値もない。明言しとくよ。
ただ、完全所有はしていなくても、「Hotel California」にいても、困らないだけの地図は持っていると思っている、もちろん自分で書いたものだ――それだけだ。ね?勝つ意味ないの分かるでしょ?そこに何の意味があるんだ。意味があるとしたら、別の理由だろうな。
それはわたしには分からない。
多様性と次元
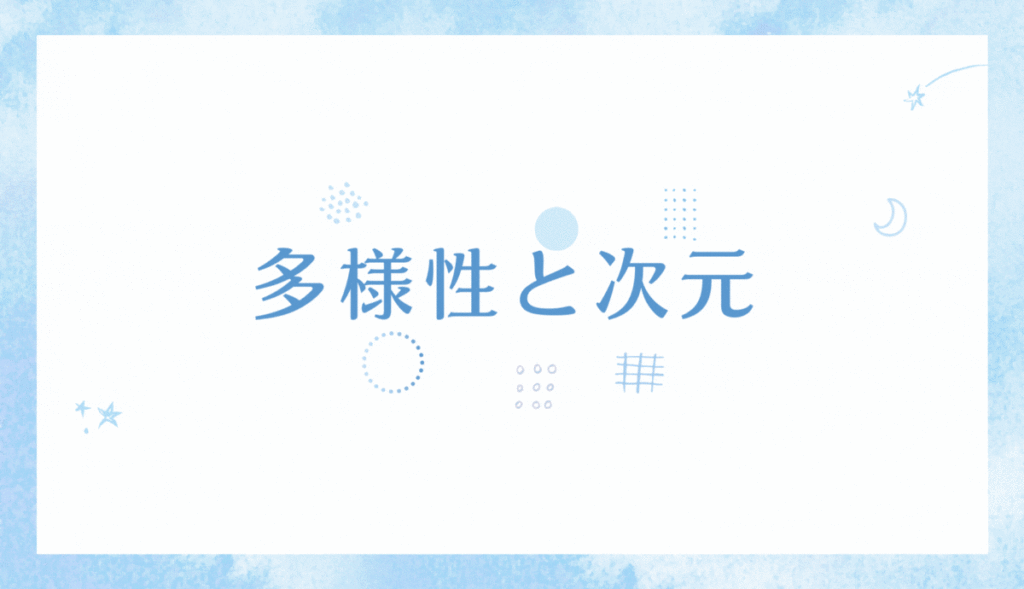
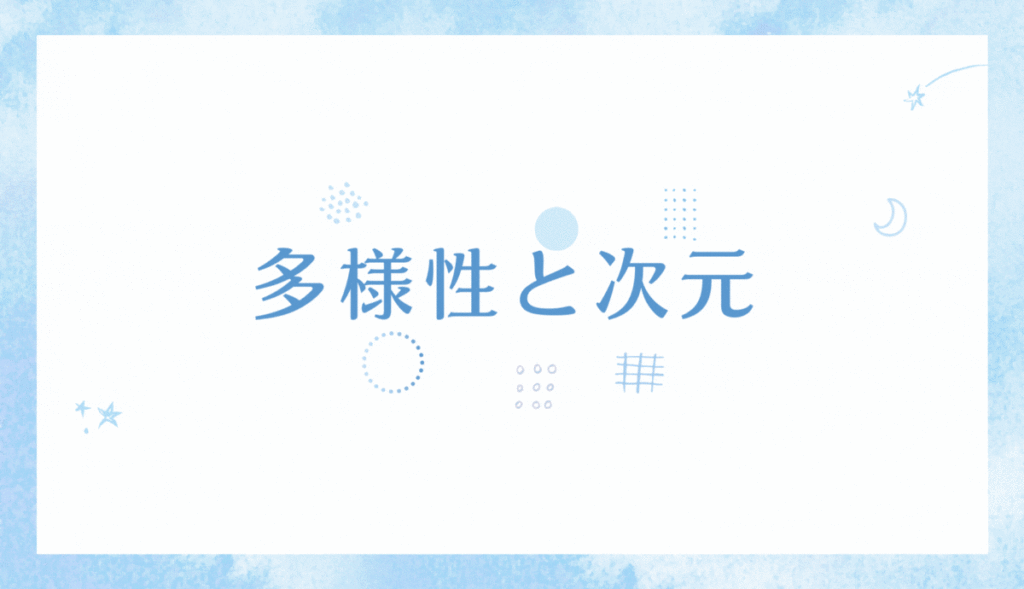
風の時代は『多様性』がキーワードになると言われる。
けれど、多様性は単なる『いろんな意見があっていいよね』で終わるわけがない。
本質は“次元の違い”にあると思う。
人はそれぞれ、理解できる構造や視点の次元が違う。
だからこそ、投影に気づかないまま相手を批判すれば、次元の違う相手の引力に引っ張られ、気づけば同じ土俵で壁にぶつかっている、なんてことが起こりやすくなる。
流されるとは、情報や感情だけじゃない。
自分の投影にすら流される、ということ。
だから、風の時代に生き残るには『自分のハンドル』を握り続ける必要がある。
誰かの引力に無自覚に引っ張られるのではなく、自分の軸で舵を切ること。
多様性とは、好き勝手に叫ぶことではなく、違う次元にいる他者の存在を認め、自分は自分の次元でハンドルを持つということだと思う。
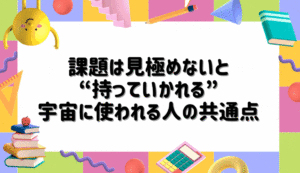
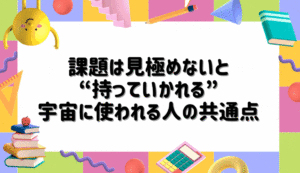
まとめ
私は普段ほとんどテレビを観ない、先日ふと2時間だけバラエティ番組を目にした。
気になったのは、その番組の構成。テンポや展開の作り方が、視聴者の脳にどう影響を与えるのか――そこまで想像したとき、



あぁ、これは思考回路に影響するやつ。
これを毎日観るの?ちょっと怖い。
とひとり納得。
構成は風の時代の構成だったと思うんだけど、演者が土なんだよね。違和感がえげつないのよ。



なんだこれ….違和感MAX。興味な…
けど、あれが面白いんだろうね。
よく分かんない。
この体験から改めて思ったのは、『情報をどう精査するか』がいかに重要かということ。
土の時代には、序列や権威という“外枠”があった分、ある程度は守られていたのかもしれない。
けれど、それでも私は生きづらさを感じてた。
なぜなら、自分と同じ層を見つけられず、孤独に苦労することが多かったから。
構造を解いても、問を立てても淘汰された時代だよね。
小さな社会の枠組みで。
- 枠組みに合わない問いを立てても『そんなのいらない』で弾かれる
- 構造を読んでも『出る杭は打たれる』で淘汰される
- 違和感を持っても声にできないまま、個人の中で抑圧される
風の時代は、翻弄されずに生き抜く力が必要になる。
感情や雰囲気に流されず、自分で問いを立て、構造を読み解く力。
それを持つことこそが、風の時代を進むための条件だと、私は強く思う。
外枠に守られることはほぼないに等しいけれど、その分足かせもなくなるから、大きく飛び立てる。
それが風の時代だ。
そして、その手段のひとつがこのブログだ。
感情に流されず、構造を読めばいい。
わたしには容易だ。
そしてこれは、誰にでも鍛えられる力でもある。



持論だよ。

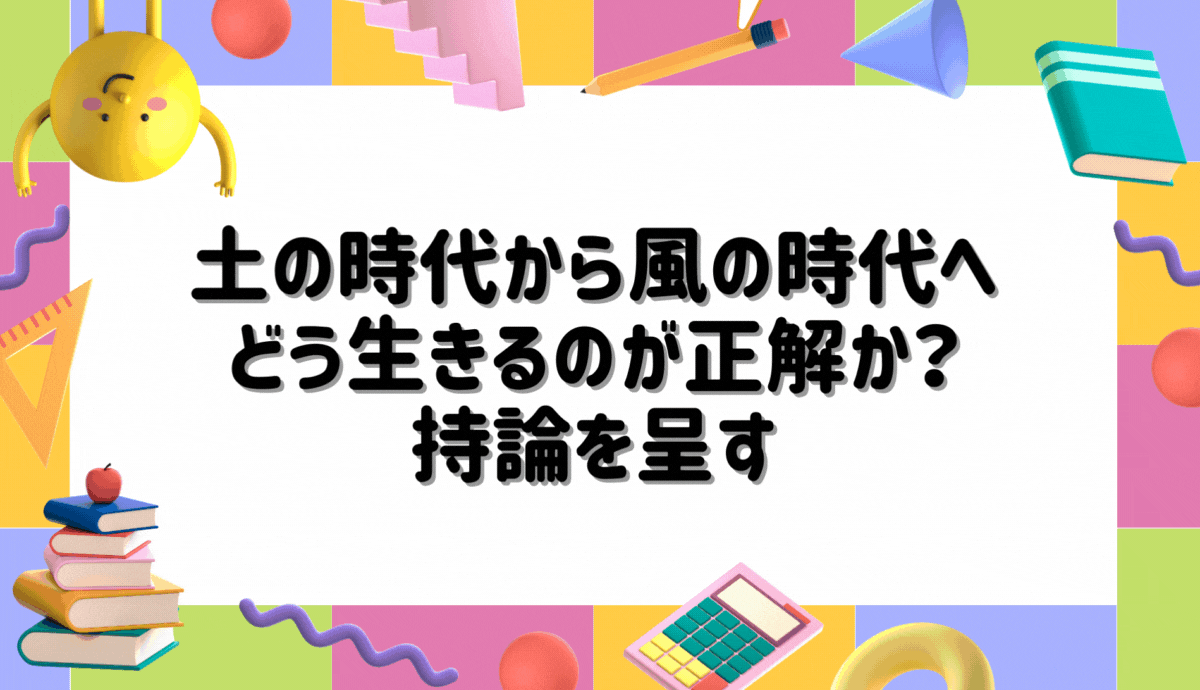
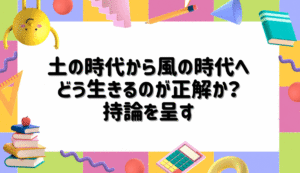
コメント