ごんぎつねの授業で、小学生が『死体を煮てる』と発言した。
そんなエピソードがSNSや教育界隈で話題になったのをご存知でしょうか。
子どもの想像力を心配する声も多く見かけましたが、私は、

いや、問わせたのそこなら、そう答えるんじゃない?
現代の子どもたちは、世界中の情報にさらされてる。もし、彼らの“ズレた答え”に違和感を感じたとしたら、それは問いの方がズレていたのかもしれない。
問いが子どもの感性に寄り添っていなかったのでは?
今回はそんな“問いの設計ミス”を切り口に、アクティブラーニングや読解力について、ちょっと真面目に、でもユーモアを忘れずに語ってみたい。
だって、ごんぎつねで死体煮てる場合じゃないから。
鍋で何を煮ているのか?という問いが示したもの
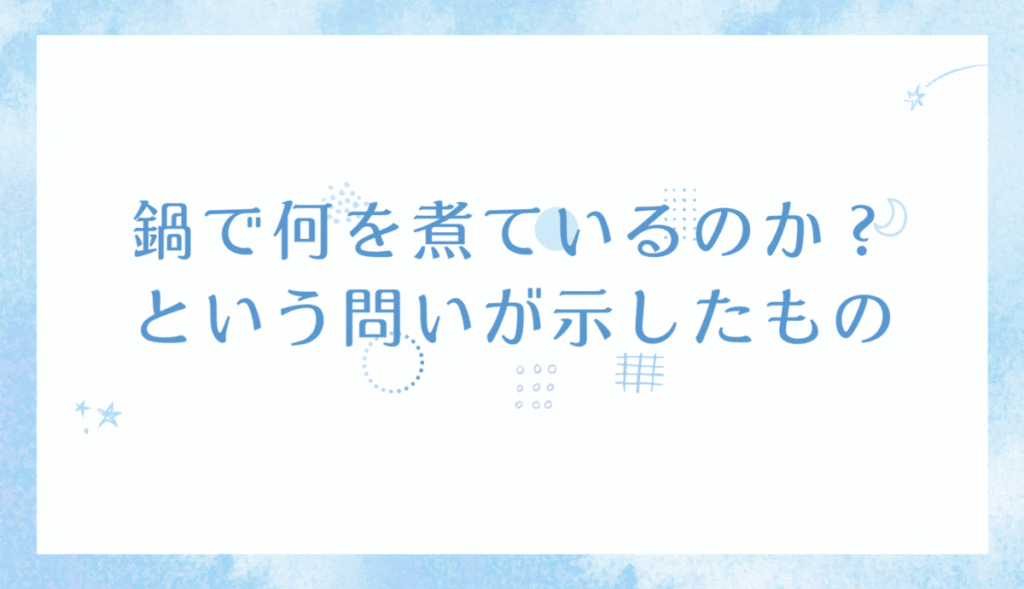
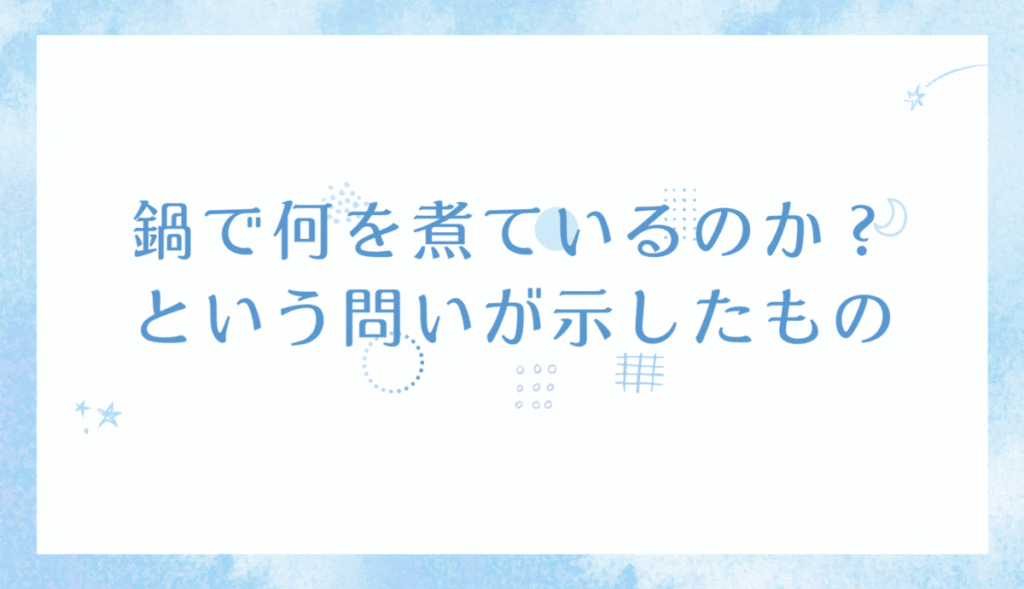
鍋で何を煮ているのか?を問わせる教員。
- ごんが兵十の母親の葬儀に出くわす場面※問わせる場所に違和感を感じる
- 大人の問いが浅すぎる
① ごんが兵十の母親の葬儀に出くわす場面※問わせる場所に違和感を感じる
授業で取り上げたのは、ごんが兵十の母親の葬儀に出くわす場面である。そこでは、兵十の家に村人たちが集まり、葬儀の準備をしているシーンが描かれる。家の前では村の女たちが大きな鍋で料理をしている。作中の描写は次の通りだ。
〈よそいきの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火をたいています。大きななべの中では、何かぐずぐずにえていました〉
新実南吉は、ごんが見た光景なので『何か』という表現をしたのだ。葬儀で村の女性たちが正装をして力を合わせて大きな鍋で何かを煮ていると書かれていることから、常識的に読めば、参列者にふるまう食事を用意している場面だと想像できるはずだ。
教員もそう考えて、生徒たちを班にわけて『鍋で何を煮ているのか』などを話し合わせた。ところが、生徒たちは冒頭のように『兵十の母の死体を消毒している』『死体を煮て溶かしている』と回答したのである。
この話、ネットでも教育界隈でも、議論になったらしい。“現代の子ども、読解力なさすぎ”とか、“想像力が欠如している”とか、あれこれ言われてたけど、わたしから言わせれば、



問わせるところ、そこ?
もう令和だし、SNSを通して色々な情報が飛び交う時代。昔はそうだったのかも……という生徒が出たって、別に不思議じゃないと思う。騒ぐところ?
『かわいそうだったね』『優しい気持ちになったね』の雰囲気で終わらせる読解から抜け出して、先生が問う理由を一生懸命考えた末に出た答えなんじゃないの?
② 大人の問いが浅すぎる
問題なのは、子どもが“死体”なんて言ったことじゃない。
そこにたどり着くまでに、教員が何を問いかけていたのかってことだと思う。
こんなところ問わせるからこうなるし、昔の葬儀も今と変わらず…という説明すればいいだけでしょ?つまるところ、問いがおかしいよ。
講演会が終わって校長室でお茶を飲んでいる時、私は『ごんぎつね』のことを持ち出し、ああいう意見はよく出るのかと尋ねた。校長の男性は、三〇年以上の教員経験があり、国語を専門にしていた。彼は次のように語った。
『今日のケースは少々極端でしたが、最近は多かれ少なかれあのような意見が出るのは普通です。教員もそれをわかっているので、先ほどの授業でも班になって話し合わせたのでしょう。それでもああいう回答になってしまったようですが……。残念ながら、似たようなことは、私も他の学校でしばしば経験してきました』



昔のお葬式を問うと、問われた理由から、普通じゃないと思うのは定跡。あそこは想像を膨らませるところじゃないと思うよ。どこ、問わせてんの?
問われたら、今と違う何かがあるのか?って、問い始めるじゃない。
だって、問うのよ?わざわざ授業で。トリッキーな答えが隠されていると、賢い子どもたちは思うんじゃない?だって、SNSの普及すごいのよ?それなのに、、



なんてことだ….ショックだ….異常だ。



逆に問うけど、何で?
だって、教育体制考えたことある?
教育モデル※あらかたこんな感じで推移してない?
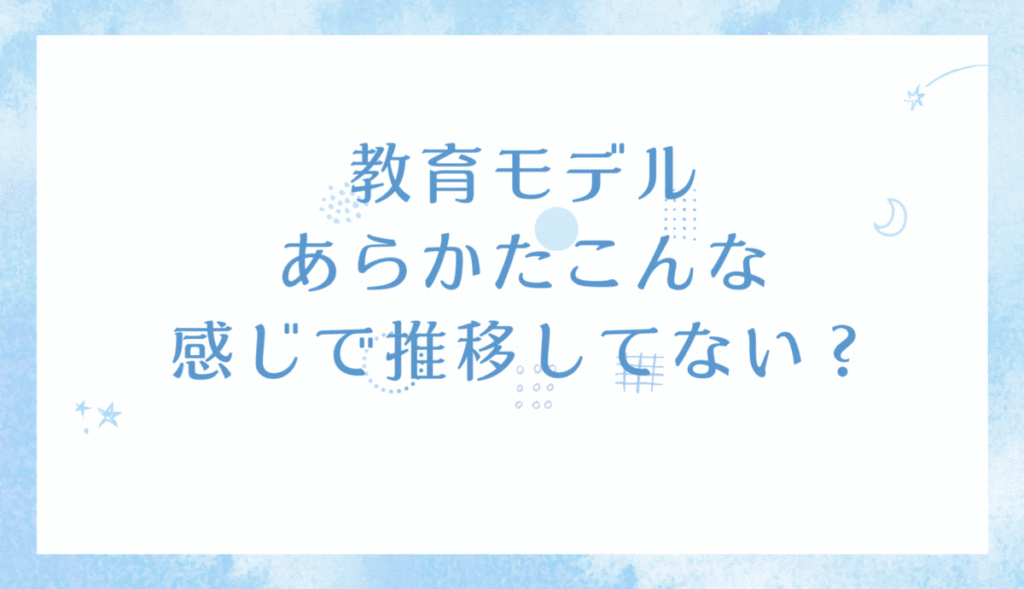
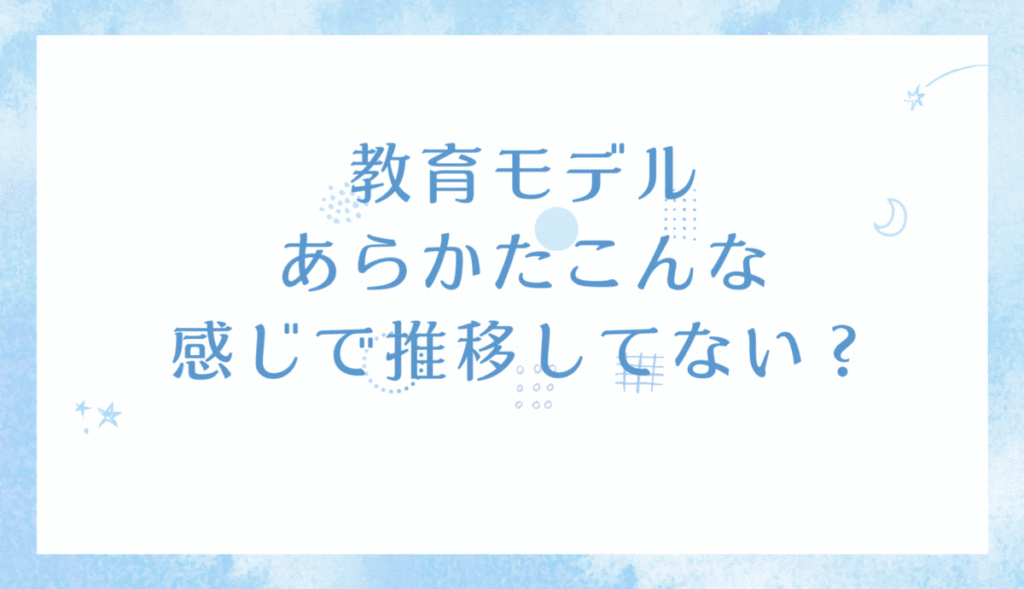
- 昭和〜平成初期:『正解主義・指導主義』の教育観
- 平成中期〜:探究・対話型の兆し
① 昭和〜平成初期:『正解主義・指導主義』の教育観
『問い=答えを引き出すもの』という発想は、戦後の一斉授業モデルに由来していて、指導要領も、『模範解答を想定した問題設計』が前提。
② 平成中期〜:探究・対話型の兆し
2000年代以降、『アクティブラーニング』『思考力・判断力・表現力』みたいなキーワードが登場してきてる。
ちなみに、アクティブラーニングの中身として、
問題解決能力の育成がある。これは、正解のない課題に取り組み、議論を通して解決策を探ることで、問題解決能力を養うというもの。世の中がそういう風潮になっていけば、そういう思考回路に育つ子どももいるでしょう?



で、アクティブラーニングがあるとか、わたし知ってるわけじゃないのよ。この記事を見たときに、なぜこの子どもたちが、このような答え方をしたのか?という問いを自分に問うと、自ずと出るじゃない。教育制度が違うのでは?こういう構造化までパッと行かないと嘘でしょう?
調べたら、あるじゃない。笑っちゃったわよ。ごめんだけど、大爆笑よ。自分たちで教えといて悩む図よ?そして潰す図。何してんの?ヤバいのはどこよ?
『似たようなことは、私も他の学校でしばしば経験してきました。』
気づけよ。
関係ないけど、アクティブラーニングの手法自体も間違えてるような気がする。参観日でも思うもの。
ごんぎつねの参観日には出たことないけれど、本当のアクティブラーニングは↓こんな感じなはずでしょう?
| ステップ | 問い | 教育的意義 |
|---|---|---|
| ① 問いが提示される | ごんはなぜ撃たれたのか? | 興味の起点。表層的な問いでもOK |
| ② 思考・対話する | いたずらだと思われたから | 一般的な読みでまずはOK |
| ③ 問いの背景に気づく | どうしたら防げた?なぜ伝わらなかった? | 読みの構造や前提に踏み込む |
| ④ 新たな問いを立てる | 伝えるって何?信頼ってどう作るの? | 答えのない問いへの遷移(抽象化) |
| ⑤ 探究が始まる | ごんは話せたのかな? | 個人の問題意識と繋がる探究へ |
でも、現実の教育現場では…
- みんなで話した、何かアクティブ
- 感想をシェアしたから対話した風
- ワークシート書かせたから探究OK♪
……みたいな形だけの“アクティブ風”が多そう。持って帰ってきたプリント見ても、正直思うよ….何コレ。
アクティブラーニングとは?
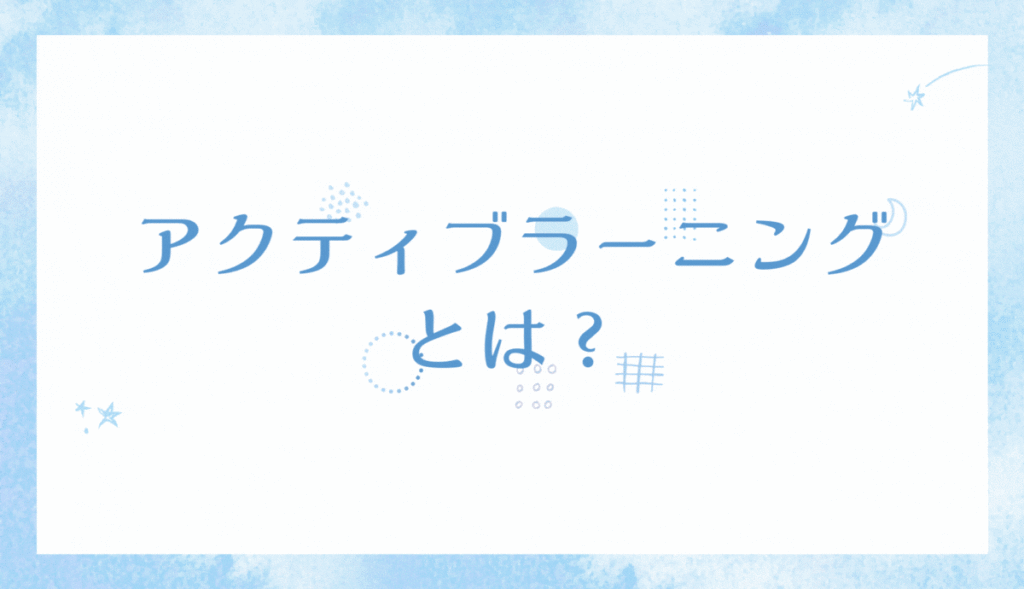
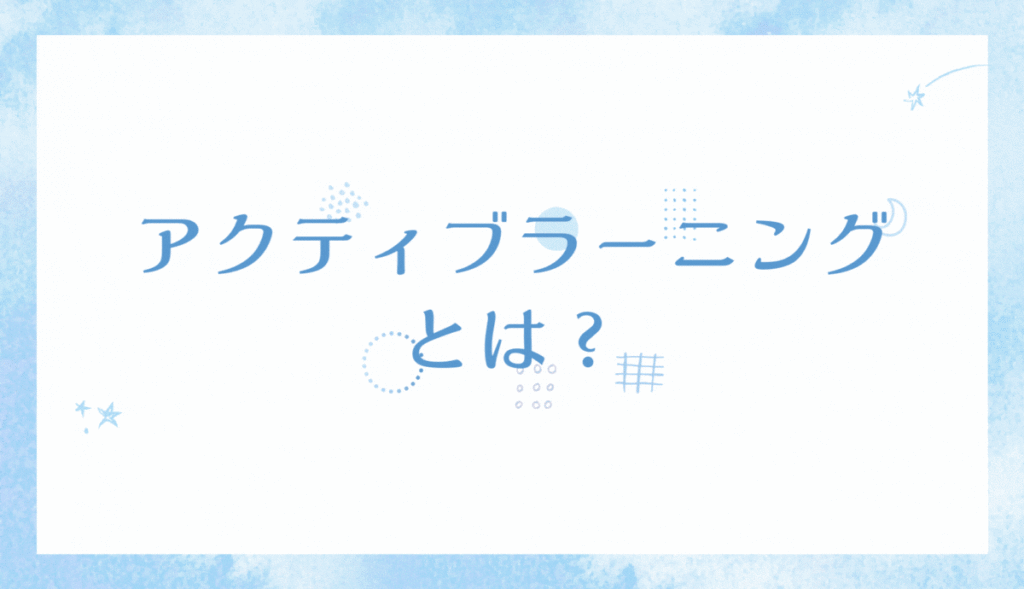
生徒たちを班にわけて『鍋で何を煮ているのか』などを話し合わせた。ところが、生徒たちは冒頭のように『兵十の母の死体を消毒している』『死体を煮て溶かしている』と回答したのである。
わたしは、ここは『ごんぎつね』の内容としては問わせなくてもよいところだと思う。
けど、問わせたのなら、現代の賢い子どもはこう考えるんですよ。



なんで、先生がわざわざここを聞くんだろう?
普通のお葬式じゃないはずだ…きっと、昔は今と違う形で葬儀が行われていたに違いない。
こういう思考回路が起こることは容易に考えられるし、正解のない課題に取り組み、議論を通して解決策を探ることで、問題解決能力を養うという教育を受けてると仮定すると猶更、『兵十の母の死体を消毒している』『死体を煮て溶かしている』のような回答が出ても何ら不思議ではない。
だから、何度でも言う。



昔のお葬式を問うと、問われた理由から、普通じゃないと思うのは定跡。あそこは想像を膨らませるところじゃないと思うよ。どこ、問わせてんの?
問われた理由も問いもしない年代なのか、何なのこれ?わたしは普通に問うよ。なんでこんなこと聞かれたんだろう?って。これ、定跡じゃないの?
ここもだよ。
素直に読めばその考えにいきつくと思いますが、もっと文章の“テクニック”的な面から話すと、最後の『筒口から青いけむりが細く出ていた』という一文。ここが悲しみを現した表現になっています。
『青い煙』は何を表している?情緒的読解の危うさ
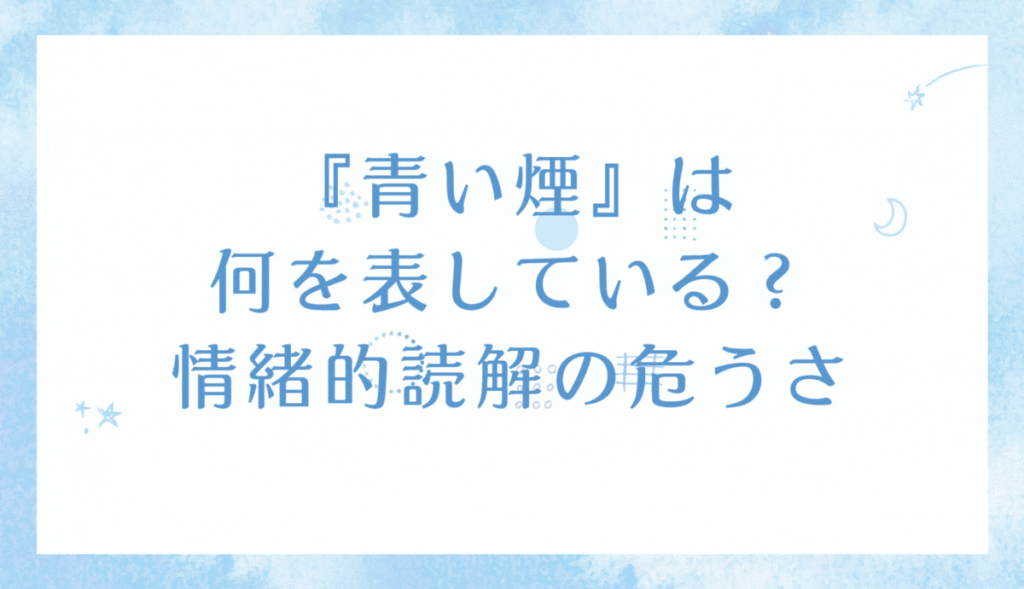
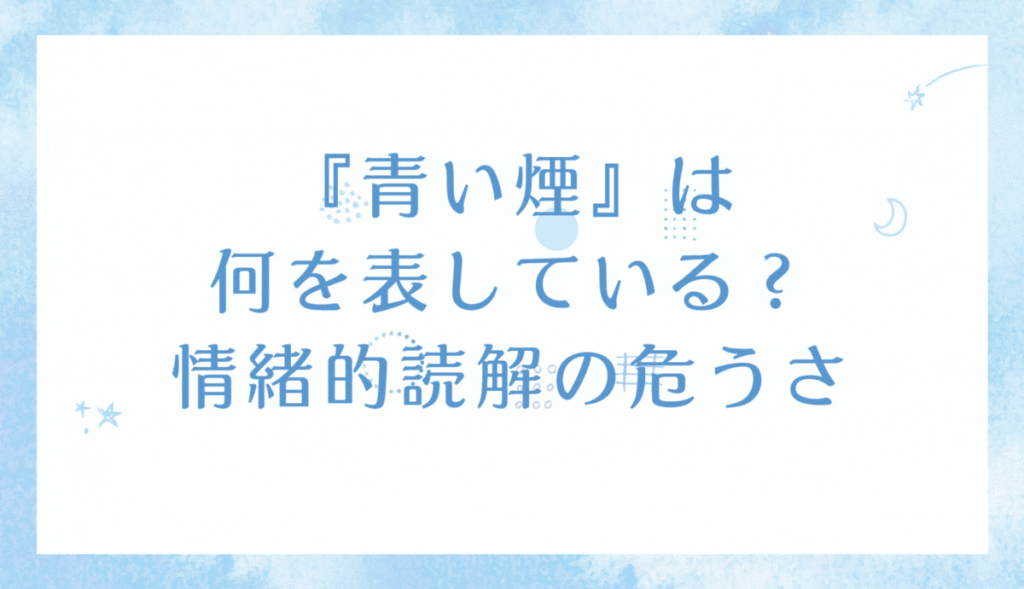
- 『悲しみの象徴』説は誰の視点なのか
- 青い煙で何を問うか?
① 『悲しみの象徴』説は誰の視点なのか
『ごんぎつね』のラスト、『青い煙が細くのぼっていく』。ここで、先生が言う。



『これは悲しみの象徴です』
『命の終わりを情緒的に表してるんです』
それが読解のテクニックです。
テクニック!?え、それ、誰の感情? ごん? 兵十? 作者? 読者?
しかも、青い煙=悲しみって、いつから決まったの? 教科書の裏に書いてあったの?確かに、浅葱幕を演出しているというのも、チラホラは見たりしたけれど、そこから悲しみを想像しましょう!って断定になるの?



新美南吉が言ってたなら信じるけど、これ誰かの想像でしょう?
この“情緒でねじ伏せる読解”が繰り返されると、子どもたちは“正解っぽい気持ち”を当てる科目なんだって理解するでしょ。いや、それ、共感ごっこで、読解じゃないから。



青いし、青って悲しい印なんだー。
で終わるわ。
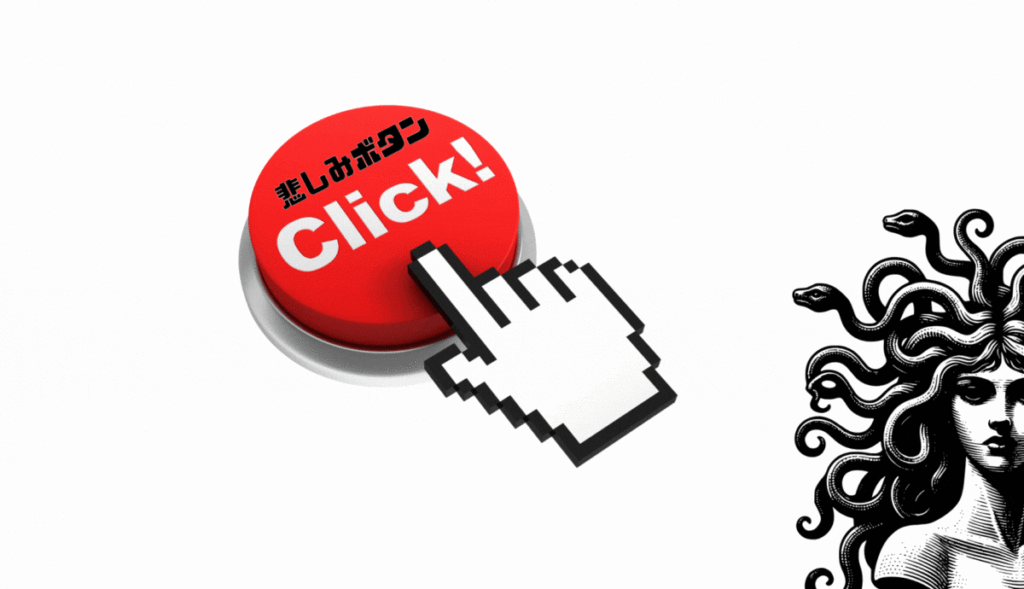
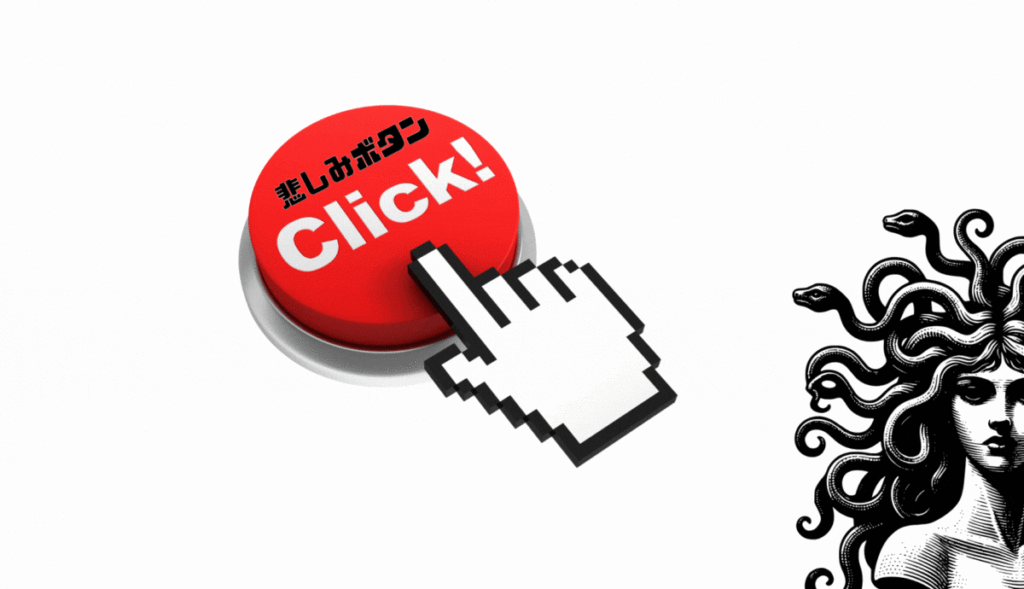
感情を“答え”として提示してしまう教育は、読解を受動的な受け入れ作業に変えてしまう。『はい、感動しましょう。悲しんでください』ってボタンを押されるようなもので、教養という名の強要だよ。
ちなみに、わたしは悲しみなんて思わないかな。



自分の内面にある不安や恐れの象徴として見た。それがようやく理解できた証明とでも言うのかな。だから、わたしで言えば青い煙=不安や恐れになる。あの物語の構造を説いてるから、こうなる。
もっと掘ると、理解した後の静寂とも取れるよね。青=冷静さを想像するなら、だけど。
② 青い煙で何を問うか?
最初から物語の構造を問いながら、物語を理解した後に、初めて問うことができる問いだと思う。
あらためて、あの煙はなんだったのか?悲しみ? 無念? 魂の昇華?
- なぜ作者は“青い煙”を最後に描いたのだと思う?
- この“青い煙”は、ごんにとってどんな意味を持っている?
こういう問いかけなら、分かる。
ここに『悲しみを表しています』という情緒ラベルを貼ったら、構造を読む機会を潰すことになる。
- だから『青い煙は悲しみの象徴です』と言われたとき、
→ 『それ、誰の感情?』と問い返せる子が、本当に読んでいる。 - 『死体を煮ている』と答えた子どもは、
→ 『なぜこの問いがここで出されたのか?』と読もうとした可能性がある。
これ、アクティブラーニングのど真ん中でしょ。
なのに、



近々の生徒ときたら….何も分かっていない。
屁理屈ばかり言っている。
『ごんぎつね』が投げかけるのは『感情』ではなく『構造』だ
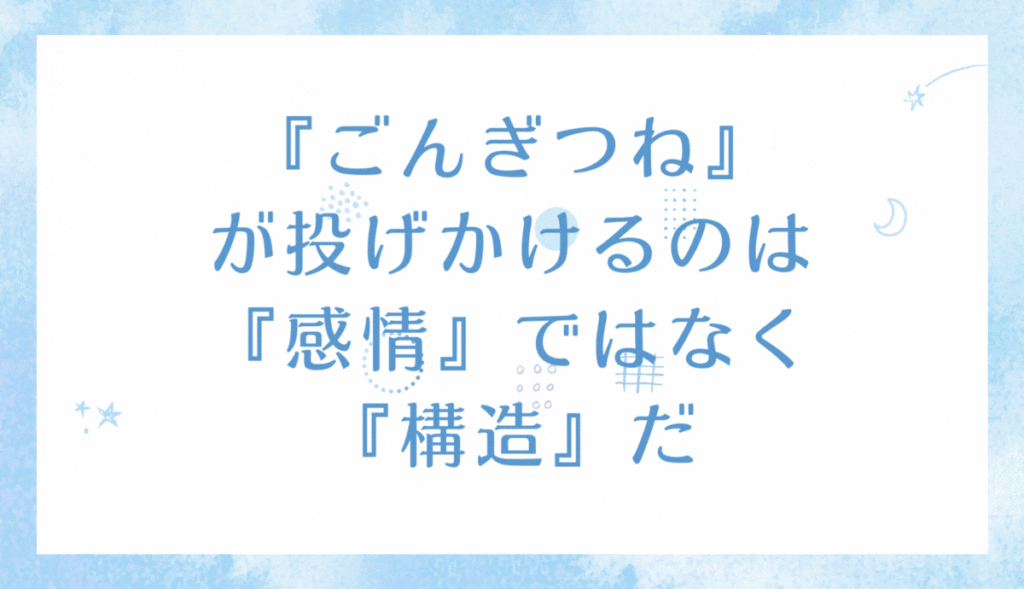
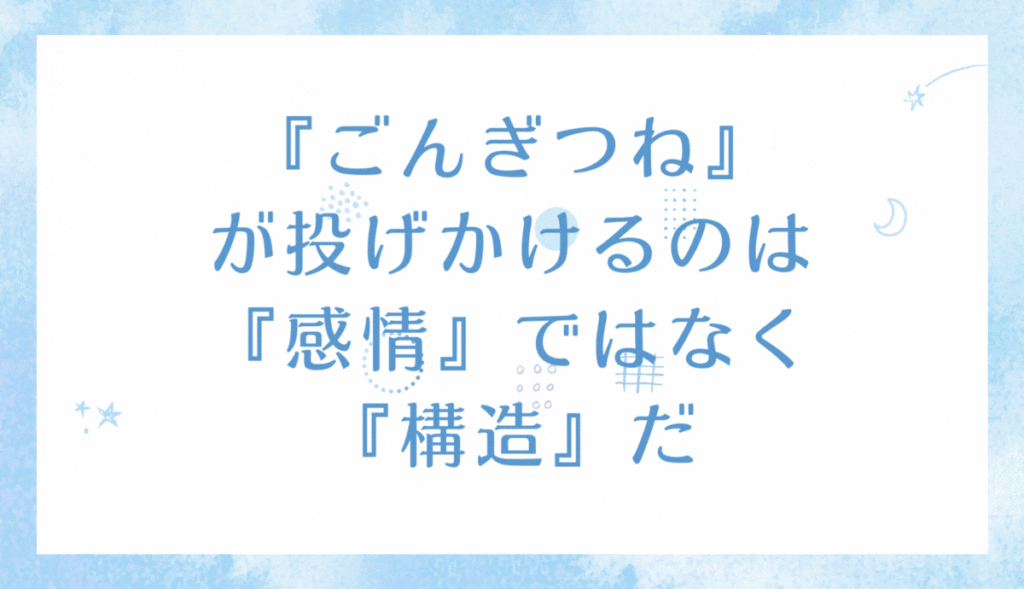
わたしは、ごんぎつねは、兵十とごん、どちらの登場人物も作者である新美南吉の投影を描いたものだと推測してます。
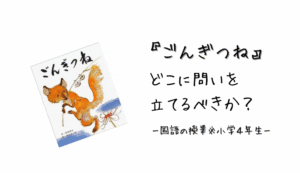
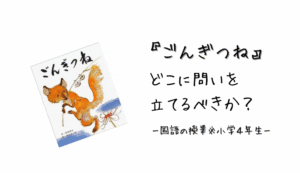
だけど、小学4年生で取り扱われているので、



これは投影です!両者共に自分のことを描いています!
だから何?さっぱりわからんって話になる。
大人がそれを分かったうえで、この『ごんぎつね』の構造を生徒にどう説明して問わせていくか?というのは、難易度が高いとは思う。ちなみに、わたしには容易である。
- 読解力ではなく、“読み方をどう設計するか”が問われている
- 『登場人物の気持ち』ばかりを問う指導の限界
- 『感情理解』中心の教育が想像力を狭める構造
① 読解力ではなく、“読み方をどう設計するか”が問われている
結局のところ、子どもたちの読解力がどうこう言う前に、『大人がどんな問いを立てているか』の方が、ずっと問題なんじゃないかと思う。
- 『どう感じた?』だけで終わる問い
- 『かわいそうだったね』で蓋をするまとめ
- 『やさしさとは何か?』というテーマの強制
- 問う場所の間違い
- 問わせ方の間違い
そういう問いの“浅さ”が、子どもたちの想像力を狭めているのも問題かとは思う。
『やさしさとは何か?』ということを問わせるのはいいけれど、そこをちゃんと構造理解して問わせることができるかどうかは分かれ目になる。



松茸や栗を持って行ってるから、良いことをしている。やさしいごんだよね。兵十のことを考えてしているんだよね。みんなも、ごんを見習いましょうね。



とか言ってる教員がいたら、教壇に立つの止めるべきだと思う。こういう人は、余計なことをせず、問題プリントを配って、生徒にさせてくれたらいい。説明は弊害にしかならない。じゃないと、業増えるけど大丈夫?
自分が許してもらいたくて、せっせとプレゼント運ぶヤツのどこが優しいんだよ。子どもにやさしさすら教えることができない、この教員に、ここを説明したとするじゃない。



全くやさしくない。自己中だよね。
ごんは、自己中です。



とかなるんだって。嫌になるのよ。
これを弊害だって言ってんだよ。だって、この波及すごいでしょ。言っとくけど、教えたら教えた分だけ『業』が増えると思った方がいいですよ。当然の摂理でしょ。嘘を教えているんだから。自覚が無い分、深くなるじゃない。ちなみに現在、学校にどれくらいの嘘があると思います?そして、その嘘を教えられた生徒、毎年何人を送り出してると思います?
厄介な保護者に出会ったな….そうお思いですか?でもわたしは、あなた方の業を減らずべく、その人数をちょっとでも減らす作業をしています。つまるところ、人助けです。できる限り、間違いのないように子どもとそのお友達は、嘘から守らせていただいています。その分、わたしの良ポイントは加算されるし。
まだ、エプロンにシミがついたクレームの方がマシ、そう思います?
これは優しいわたしからのアドバイスです。だから、プリントだと言っていますよ。わたしは、業を背負わなくていい方法を伝えましたからね。知らない方が良かった?嘘でしょ。この知識があってもなくても、無自覚に業は作られる。自覚的であった方がまだマシよ。
みんな持ってるのよ。種をね。その存在を知ってるか知らないかで人生は激変していく。



一生懸命だから大丈夫?いえ、そこには課題の分離が存在しています。一応、書いておきます。一生懸命も、何に一生懸命か?問えてないと、足元すくわれるしね。
どういうことかというと、こういう親が育つんですよ。
みんなのために….都合のいい代名詞が付く。ぜーんぶ自分のためなのに、その区別もつかないのよね。みんなのために動いてたのなら、そもそもが怒りは湧かないということに気づきもしない。ごんだって、兵十に気づかれなくて不貞腐れてたじゃない。割に合わないってね。やさしさに『割に合わない』なんて言葉ある?
そして、こういう教員が出てるかもしれないですよね。



生徒のために、授業中の折り紙は禁止にすべきです!
適切な環境づくりは学校の仕事ですから!
生徒のため?まぁ、知ったことではないけれど、これも嘘だもの。業を増やしたいんでしょうね。その是非が問われるだけの話。
先生方、そういうことですよ。ご自身が、どういうポジションにいらっしゃるか、今一度問うてみてください。
情弱者は刈られる。どんなポジションでもね。
まだ、授業でジブリ映画とか見せてた方がマシだと思いますよ。
全ては必然であり、イコールが成り立つ世界、それが世の中。現時点でご自身の周り、見渡してみたらいいですよ。何かに気づくか、気づかないか、気づかないなら、まだ先になる。不平不満を漏らせるうちが花よ。
それはあなたの考えでしょう?って?
いいえ、
世の原理原則っていうのは、不変であり普遍なんですよ。
これも縁起でしょ?
そうやって、わたしは自分を納得させています。厳しいこと言うようだけど、1年から見てますけど、今年で4年目です。教育は総合的に見て、ゼロどころかマイナスだと思いますよ。お友達とのコミュニケーション、そこには感謝しています。それ以外補う術はないですもん。小学校は特に。自分は縁起と見て対応してますけど、日本の未来考えたらどうなんでしょうね。だけどわたしは、そこのポジジョンにいないから、できることだけをさせて頂いた。



聞いていただけただけでも、感謝しています。
別にどうにかして欲しいなんて思ってないんですよ。ゼロかマイナスだという自覚だけ持っていただければ幸いです。責めるために言うんじゃない。じゃないと、パラダイムが変わらないでしょう?
逆に、『なぜそうなった?』『どうして伝わらなかった?』『この関係は対等か?』といった構造を問う設計があれば、子どもたちは驚くほど深く読めるんじゃないかとも思う。
子どもは変わっていない。時代が変わって情報の伝達が早いのよ。構造を読みもしない付け焼刃の感情理解の教育が時代遅れなだけだって。
構造さえ問うてれば、時代変わっても不変だと思うけどね。時代によって、問う内容は変わることがあるかもしれないけれど、構造さえ押さえていれば、何ら問題は生じないのよ。押さえてないで教科書やら指導案作るから、時代に追いつかなくなってくるんでしょ。
だって昔は、ストーカーなんて言葉なかった時代。ごんの行動は、現代からするとストーカーにしか見えない。わたしからするとそうだ。犯罪も出るような時代に、ごんが可哀そうだと目に映る生徒がどれくらいいるか?と想像してみて欲しい。
毎日靴箱に、飴とか四葉のクローバーが置いてあってみてよ。怖いって。
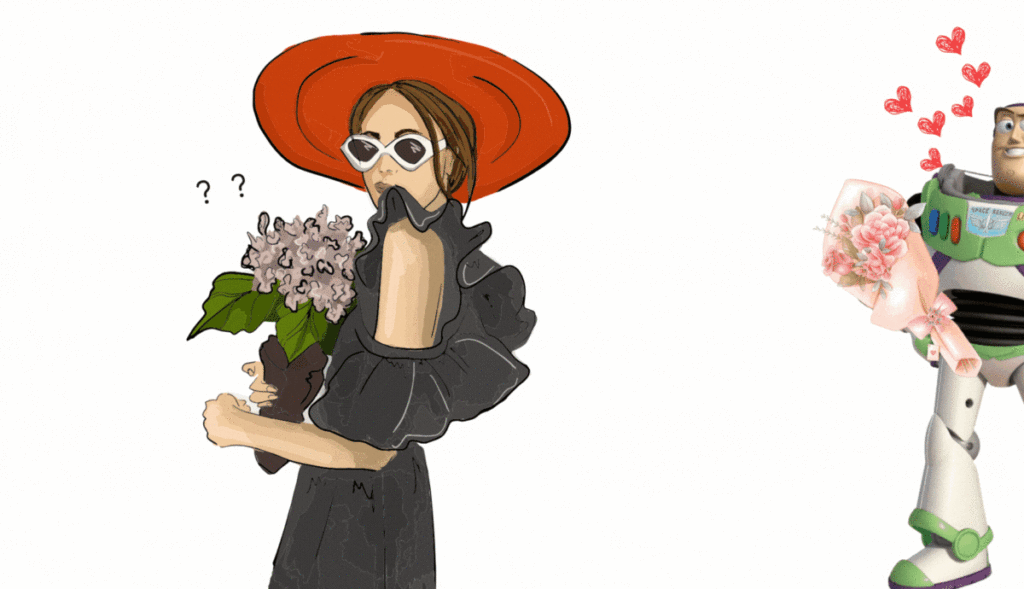
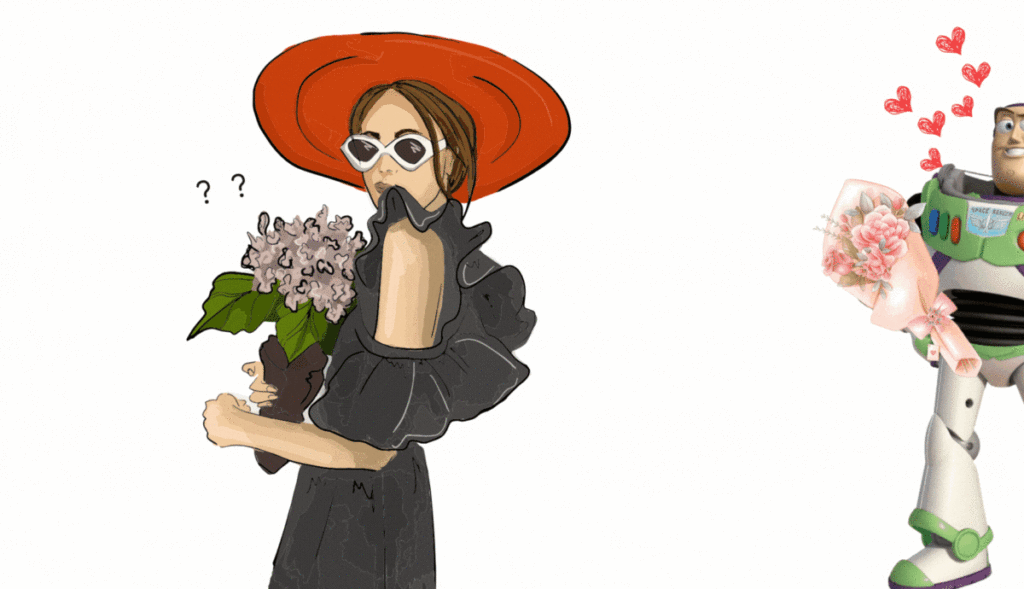
構造を理解しないで、感情なんて問わせることにしてるから、時代が変わって通用しないような教育になるんだよ。あんな素晴らしい作品がね。作品潰しだよ。



ごん?どこがかわいそうなの?勝手に色々持って来て、ストーカーとかわんないって!
そりゃ現れるさ。当然だよ。



けど、これは花束とかじゃないし、栗とか松茸で、動物だしかわいいし、物語だからー。



こうするの?笑
嘘でしょ?
つまり、問うべきは『読解力』ではない。“どんな読み方を前提にした問いを投げているのか”という、教育そのものの設計じゃないかと思う。
② 『登場人物の気持ち』ばかりを問う指導の限界
小学校の国語の授業で、『登場人物の気持ちを考えよう』ていう呪文。


『このとき、ごんはどう思ったでしょう?』
『兵十の気持ちになって考えてみよう!』
……って、それ本当に考えてる?
だいたいの答えはこうだ。



かなしかったと思います。



びっくりしたと思います。



うれしかったと思います。
お、おう、で??
そう、気持ちだけ聞いて終わり問題が全国の教室で蔓延中じゃないの?
なぜそう思ったか、どの場面にそう感じる根拠があるか、その気持ちはどう変化したか――っていう構造を読み解く手順があったとしても、構造の根っこを問えてないから、宙ぶらりんで終わる。
結果どうなるかって?
『気持ちを当てるクイズ大会』開催!
しかも正解はだいたい“かわいそう”か“やさしい”。
道徳の授業もこんなんばっか。正直、参加日でもうんざり。
③ 『感情理解』中心の教育が想像力を狭める構造
『感情を理解する力が大切です』
『共感できる心を育てましょう』
うん、それ自体は大事。異論はない。でもそれ、“共感の押し売り”だよね。背景も読めずに、どうやって共感するんだろうと思う。
たとえば『ごんぎつね』。
『ごんはかわいそうだったね』『兵十も悲しかったね』――で終わる授業、もう何千日手目ですか?
大事なのは、『なぜそうなったか』『どこですれ違ったのか』『どうすればよかったのか』っていう構造。そして、本物の構造が見えてないといけない。
だけど、どう作った指導案ですら、抜けができる。
なぜか?それにはちょっと頭を使う。そして何より、できる人がいない。だって、教育体系がずっとそうだもの。多分、わたしはゲシュタルト崩壊して、自分の構築をしているからか、構造化を読み解くのが得意なんだと思う。違和感にすぐ気づく。
そしてそこから、正しく教えることができる者が存在しない。ここが一番重要だ。
だから感情だけ読ませとこう、っていう教育になるのも分からないではない。だから、理解はしてる。そういう背景があるのもね。できないものは、求めることができないことを理解している。
ごんぎつねで見るすれ違い※言いたいことが分からない弊害
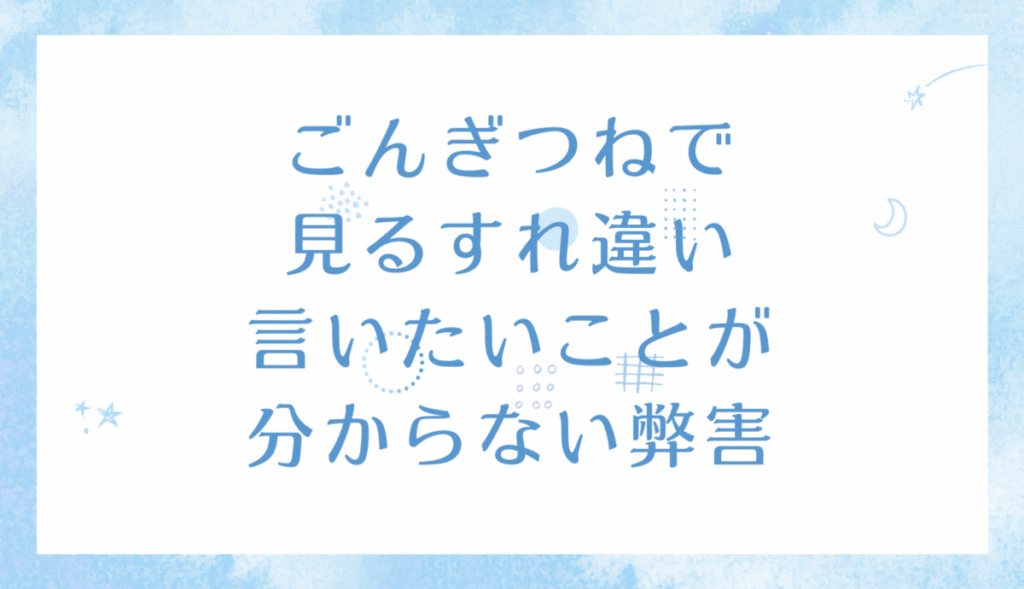
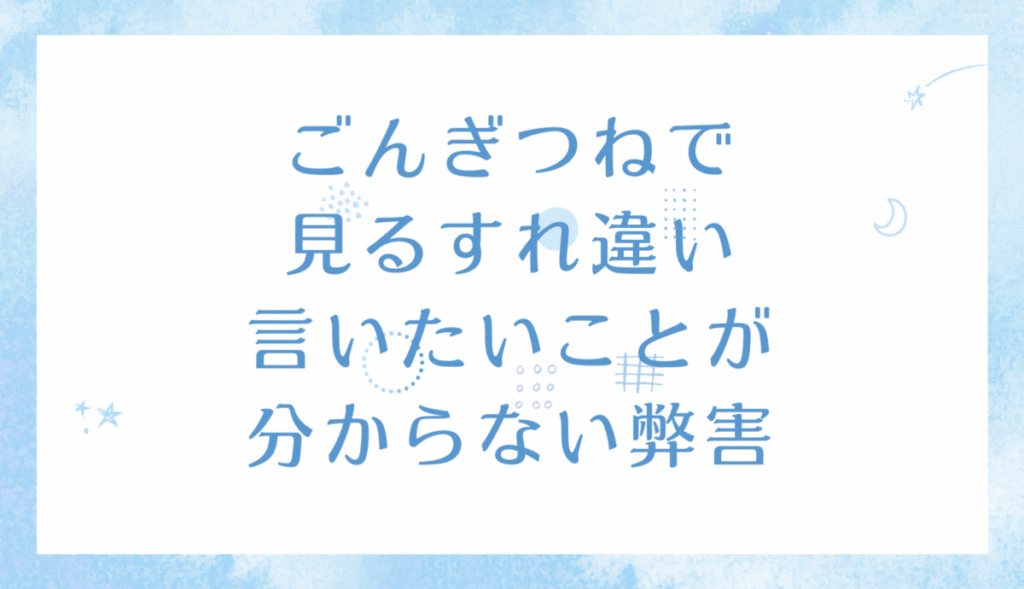
- 信頼の不成立――悲劇の本質にある関係性の崩壊
- 言葉を持たなかった者たちの行き違いをどう読むか
- 『自信がないんですね』と勝手に解釈する構図
- 物語の“構造”を読むことの意味と教育的価値
① 信頼の不成立――悲劇の本質にある関係性の崩壊
『ごんぎつね』を『悲しいお話』として読む人は多い。実際、悲しい。悲しいんだけど──
問題は、どこでどうすれ違ったのか。
この話、何が核心かというと、信頼関係が築かれなかったことにある。
これって、恋人関係でも、友人関係でも、ビジネスでも──ありがちな話。
要するにこの物語、『やさしさ』が通じないという悲劇じゃなくて、『信頼が成立しないま進んだ末路』と取れる。
本来は自分との信頼関係を描いたものだけど、本では『兵十とごん』の信頼関係。
行動だけが積み重なって、兵十との関係性の“構造”がまったく成立しないままに、ごんが好き勝手動いて、取り返しのつかない結末になる。



投影でもよくあることだ。相手に投影して好き勝手解釈して、すれ違い破綻や誤解を招く。
② 言葉を持たなかった者たちの行き違いをどう読むか
ごんには『言葉』がなかったと仮定しよう。話せないのか、話さないのか分からないけれど、言葉が存在しない世界。
これって、ものすごく現代的でもある。
たとえば──
- 何を考えているのかよくわからない部下
- 言いたいことをはっきり言わないパートナー
- 顔色ばかり伺ってくる友人
ごんと兵十って、まさにそういう『なんかズレてる関係』の典型でもある。
共感とか気持ちじゃないんだよ、問題は。『行動』だけで関係を構築しようとしても、言葉という“構造材”がなければ、信頼の建物は崩れる。
しかも、相手に何を伝えるべきか?を自分でわかっとかないといけない。自分が分からない状態で、相手には問えない。例えば、何を考えているのかよくわからない部下がいたとしようよ。
それって、投影じゃないですか?
よくわからないのは、部下の方かもしれない事実。あなたの説明はあっているんだけど、部下の問いに対する答えになっていなくて、部下は迷ってばかり。部下からしたら、あなたが何を考えているのかわからないし、あなたからしたら、部下が何を考えているのか分からないという構図が成立する。
つまるところ、投影だ。そしてこの上司は常日頃、家族からこう言われているだろう。



何言ってるか、わかんない。



は?ちゃんと答えてんじゃん。
ここがすごく本質的なんだけど、
『相手にどう伝えるか?』の前に、問いに対して『自分は何を伝えるべきか?』を明確にしておかないといけない。
参観日にある保護者が、



発表しない子どもへの促し方を教えてください。
保護者の問いは、表面的には『発表できるようにしたい』なんだけど、その背景には、
- 我が子の“自信のなさ”への不安
- 『うちの子だけ発表しない』ことへの孤立感や焦り
- 親として、どうサポートしていいか分からない戸惑い
- もうひとつは、質問してただ目立ちたいだけ
があるわけよね。
それに対して、先生はたぶん、こう思った。
- 音読 → 読解力向上
- 積み重ね → 自信 → 手が挙げられるように
……つまり、認知→理解→行動っていう教育プロセスに則って説明してる。理屈は合ってる。
でも、ここでのズレは何かというと、
方法の提示だけになっていて、保護者の“感情”や“動機”に共鳴する言葉がない。
これをわたしがどう読み解くかって、飛躍もあるかもしれないけれど、イコールで読み解けば、こう読み解く。
| 他者理解ができない | 行動によるわたしの想像 |
|---|---|
| 相手の意図を想像しない | 勝手に想像して勝手に答えたいところだけを答える。相手が『自信が無い』とは一言も発信していないのに『自信をつければ大丈夫です』という独り言を言っている。 つまるところ、それって、あなたのことですよね?あなた、自信が無いのですか? |
| 相手のズレを、理解力が無いと『相手のせい』にする | 自分がどうズレているかを省みず、終わらせる |
③ 『自信がないんですね』と勝手に解釈する構図
これはつまり、
- 相手が何も言っていない
- こちらが勝手に『きっとこうだろう』と想像する
- 自分の中でその“想像”を“確信”にしてしまう
- その“確信”を前提にアドバイスや指導を始める
──これ、“理解”じゃなくて、“投影”と“処理”じゃないの?という解釈も存在するのよね。わたしの中ではね。
この“自己把握”の手続きなしに、他者との関係構築なんて成立しない。言い換えれば、上司が『ちゃんと答えたつもり』でも、それが“相手にとっての問い”に接続してなければ、ただの独り言なんだよね。
自己理解が浅いと、他者理解も歪む。



こういう歪みが蔓延してるのが、今の教育であり世の中だよ。SNSが普及して、相手の背景まで読まないといけない時代であふれているときに、何してるんだろうねとは思う。誤解まみれ、喧嘩まみれになるのかな?っていうのは容易い想像ではあるよね。知らないけど。
あぁ、わたしは大丈夫。
④ 物語の“構造”を読むことの意味と教育的価値
さて。ここまで読んできた人にはもうおわかりかと思うけど、『ごんぎつね』って、感情で読むと詰む。
『ごんがかわいそう』
『兵十がひどい』
大事なのは、『なぜそうなったのか』『この関係に何が欠けていたのか』という構造へのまなざし。
- どこで誤解が生まれたのか
- なぜ誤解を解けなかったのか、解かなかったのか
- どうすればよかったのか
こうした『関係性の読み解き』=構造的読解を教えることが、ほんとうの読解力の育成につながるとは思う。
それってつまり、物語の中で“自分や他者とどう関係を結ぶか”を学ぶってことでもある。
国語って、『漢字だけ覚える教科』じゃない。構造の教科でもある。言葉が届かなかった理由を、心じゃなくて関係と背景から読む。その力こそが、『読む力』の正体だと思うけど。
まとめ
『感情』や『構造読み』も大事、だけどそこに子ども到達させるには『問いの設計』がすべてじゃないだろうか。
もちろん、誤解しないでほしい。感情理解の教育的意義は否定しない。
『感情を読むこと』それ自体が悪いわけじゃない。
他者の気持ちを想像し、受け止める力は、人間関係の土台としてとても重要だしね。
子どもたちが『かわいそう』と感じることも、『やさしくしたい』と思うことも、全部、大事な心の動き。
それは、読解というよりもむしろ、『人間になる練習』として必要。
だから、感情を読む教育を全否定するつもりはない。ただし、問題はそこに拘り過ぎた、教養という名の強要が問題だと思う。
『やさしくなろう』で終わってしまったとき、それはもう、読解じゃなくて情操プログラムになってしまうと思う。
感情ばっかり重視すると、子どもたちは『正しい感情を表現するゲーム』だと思い始める。当然だ。



ここは“悲しい”って言えばOKでしょ?
みたいな。
つまるところ、このデフォルトを理解しておけばいいだけの話だ。だから、何の不満もない。けど、保護者がどうの、子どもがどうの、じゃぁ、教育はどうでしょうね?って言いたいのがわたしだ。
劣悪な保護者や劣悪な生徒いた方が楽ですものね。スケープゴート。そうはさせませんよ。保護者代表ではわたしがお話を聞こうと思います。いつでもどうぞ。最初にお伝えしますが、アドラーはデフォ、お話の途中で『課題の分離ができてない』そう判断した時点で帰らせていただきます。



そしてこの記事みて、教員を罵倒することも愚かと思う。この記事読んだあなたも、誰も出来やしないよ。自分ならできるという者がいたら、名乗り出ろ、砂に埋めてやる。できないんだよ、誰にも。あぁ、わたしはできるよ。わたし以外の話だ。
期待するとこっちが崩壊する案件だから、落としどころは必要だよな。それがこちらの諦観なる慈悲だよ。
何も問題はない。今のままでいい。願いはただひとつ。



この教育に何も言わないから、その代わり、子どもたちから自由を奪わないで。自由にさせて。
学校にクレーム言う保護者なんて、電話で受け付けしなければいいんじゃないの?直接来てもらえばいいじゃない。直接のやり取りでも、投影が見られるのに、電話なんてさらに揉めるだけよ。
きついこと言うようだけど、ごめんなさいね。巻き込まれは勘弁してほしいの。
デフォが弊害なのよ。お願いだから分かって。わたしと競うことに意味が無い。
未来の大事な宝たち。わたしは守りたいのよ。これ以上、業を深くしたくないでしょう?
ここまで言いたくなかったのよ。けど、言わないとどうしようもなさそうだものね。
これがほんとの人生の回答書よ。聞いてどうかしら。ここに立つと、苦しいのよ。楽ではないけれど、自由にはなれるわ。呪縛からは解放される。愚痴り他責にし、怒鳴りながら生きる楽も一手よ。けど、こちらは呪縛とはセットになる。わたしはそれを選ばなかっただけの話だから。
楽を選びたいときには、そう宣言すればいいだけの話だから、宣言したらいいと思うわよ。
つまるところ、エプロンのシミのクレームを引き受ける覚悟になる。



自分は知っているけれど、あえて『楽』な方を選ぶ。
とね。そしたら、クレーム来ても腹も立たないでしょう?自分で、そこで生きると決めたんだもの。
わたしが責めないように、誰も責めないわよ。その件に関してはね。それが引き受ける覚悟だもの。知らない人は知らずに『楽』を生きるだけの話よ、つまり流されるだけ流される運命。だから職員会議に持ち出せるんだよ。そっからの自身への波及も考えずにね。無知って怖いわよ。
知っていれば選べるの。それが知識。宣言しないと、知ったものとして進みだす、それが宇宙よ。
だから問いは、静かにあなたに返ってくる。楽か、自由か。
そして、知らなくてもずっと問われるのが宇宙よ。だったら、知ってた方がいいでしょう。
子どもはいいよ。思いっきり周りの大人と親の責任にしたらいい。
何も悪くないよ。何の罪もない。
わたしが言ってたのは、これだって。
今は、まだいいんだよ。子どもに責任を背負えだなんて、言わないよ。
思いっきり他責にしろ。そして、この知識を糧に、少しずつ受容できるといいね。教わらなくても、わたしが教えといたから、きっと糧になるよ、保証する。



この知識を今はまだ扱いきれない。



そう宣言しておけばいいんだよ。
あと、無力と自覚的な大人も、扱いきれないのなら、子どもと同様に宣言するといいよ。その代わり、大人は『無力』これを受け入れることだね。これを扱っているのがわたしだって。無力じゃないと宣言したいのならすればいいだけの話だ。
宇宙から、



了解。
って返事が来るだけの話だよ。
わたしは学びをずっと受け続けたんだって。そしてこうなった。『神様、わたしはもう、学びたくない。お願いだから、わたしにもう、学びを与えないでください。』、ゲシュタルト崩壊以降も、辛過ぎた。そこを通って今がある。今は、学びも普通に受け入れることができるフェーズに入ってるけどね。きつかったよ。だから、鬼厳しい意見を言わせると、じゃぁ、あなたもそこ通ったらどぉお?って言いたくなるのが私だって。あなたはお願いしたことある?神様に。言わないだけの話で、ちゃんと通ってるのよ。いばらの道をね。近道なんてしてないわ。そこを経て、ようやくできるようになったのよ、道選びがね。
- やさしさとは?
- 権力とは?
- お金とは?
- 教育とは?
- 同情とは?
- 親とは?
- 母とは? 父とは?家族とは?
- 環境とは?
- 人生とは?
こうやって、挙げたらキリがないくらいの答えのない問いを問いつづけて答え合わせしてきたのが、わたしよ。そっから、本で整合性を確かめる。同じことを言っている人がいるかどうかの確認。ロジックが全部合ってるかどうかの確認。だから、問われたら、すぐに答えることができるんだって。
ミイラ取りがミイラになるのは簡単よね。ミイラにならないようにあがくことが難しいのよ。
ここまで来て関係ないけど、わたしはこうやって引き受けているから、認知不協和の解消(味わい尽くす)ができるんんだと思う。引き受けてないと、モヤモヤを途中で放棄しちゃうのよ。この引き受ける生き方こそが、心の筋肉を鍛える方法とも言える。自責しか存在しない世界だからね。他人を動かせないのを分かってないといけないのよ。二ーバーの祈りね。
“”Voices’ is about my inner battle-everything that pulled me away from myself and from really understanding what I wanted… and more importantly, what I didn’t want,” David explains. “This song is the final piece before the full story unfolds with the album. Funny Little Fears is basically my emotional diary from this past year. Writing it helped me work through some deep emotional blocks and anxiety, and let me show a more personal, maybe unexpected, side of myself -both musically and as a person”.
Releasing ‘Voices’ before the album feels like opening the last door, inviting everyone into my inner world, without fear.”
『Voices』は、僕の内なる葛藤について歌っているんだ。僕を自分自身から引き離し、自分が何を望んでいるのか、そしてもっと重要なのは、何を望んでいないのかを本当に理解することを妨げてきたものすべてについてね」とデヴィッドは説明する。「この曲は、アルバムで物語が本格的に展開する前の最後のピース。『Funny Little Fears』は、基本的にこの1年間の僕の感情的な日記。この曲を書くことで、深い感情的なブロックや不安を乗り越えることができ、音楽的にも人間的にも、よりパーソナルで、もしかしたら予想外の自分の一面を見せることができた。」アルバムの前に『Voices』をリリースすることは、最後の扉を開き、恐れることなくみんなを僕の内なる世界に招き入れるような気持ちだ。

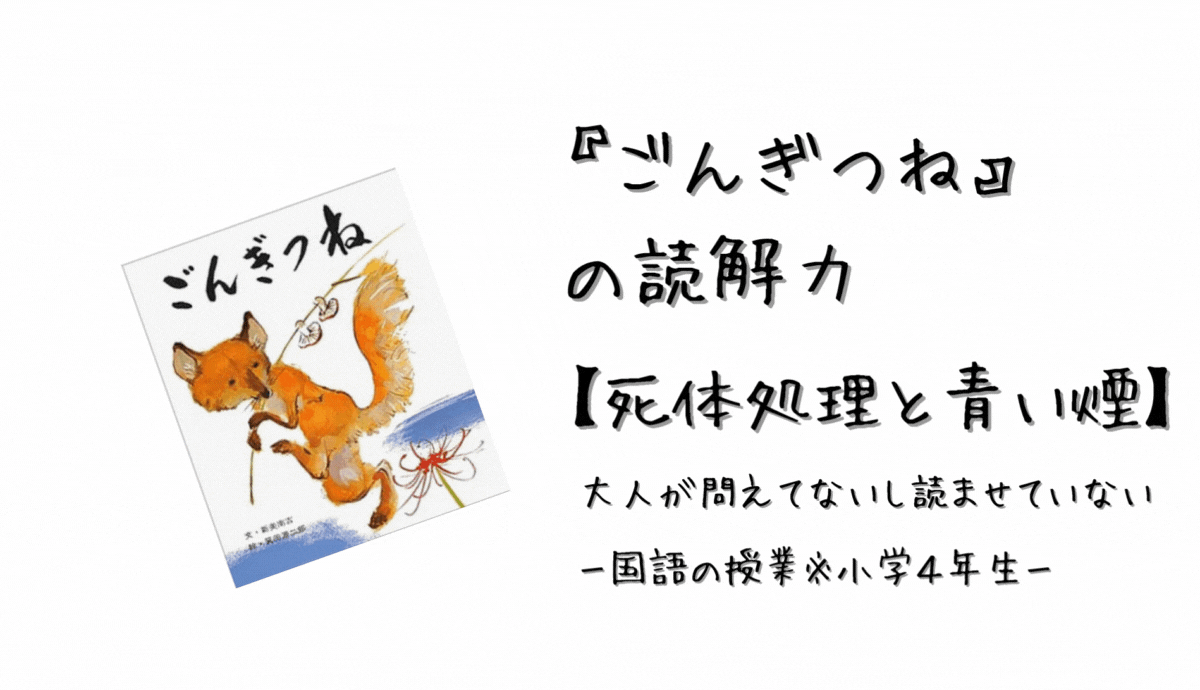
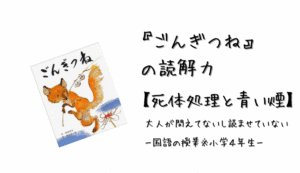
コメント