宮沢賢治といえば、『雨ニモマケズ』でおなじみの歴史的文豪の一人。
わたしには、賢治は、理想と欲望、法華経と浄土真宗、承認欲求と父の現実主義――その矛盾の中で生き切ったことこそ賢治の真実の姿に見える。
つまり「理想を体現した人」ではなく、「理想に憧れてもがいた人」。そこに人間臭さがにじみ出ていて、作品には彼自身の欲望や承認欲求がしっかり刻まれているように思える。
だからこそ、彼の作品を読むときには「理想のきらめき」よりも「欲望の影」を読む方が面白いんじゃないか?そういう目線を持つと、今まで見えなかった世界が立ち上がってくる。
今日はその代表作『注文の多い料理店』を取り上げて、物語の核心と、背後にある賢治の欲を読み解いていきたいと思います。
『注文の多い料理店』作品概要
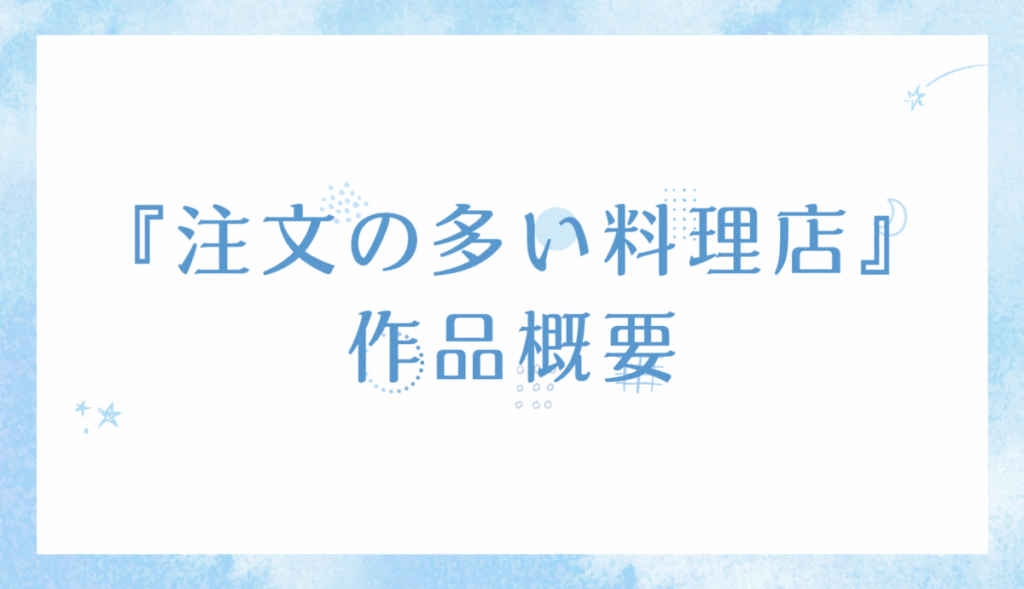
- あらすじの要点
- 発表時期と背景(大正末期〜昭和初期)
① あらすじの要点
- 山奥に迷い込む:狩猟に出かけた二人の都会紳士が、深い山で道に迷う。
- 洋風レストラン発見:豪華な洋館風の「西洋料理店」を見つけ、空腹のまま入店。
- 「注文」の連続:扉や壁に貼られた紙に「帽子をとれ」「靴を脱げ」「クリームを顔に塗れ」など、次々と理不尽な要求をされ、「奥に偉い人がいるんだ」などと都合の良い解釈をして指示に従う。
- 逆転の恐怖:自分たちが「客」ではなく「料理される側」であることに気づく。
- 犬の登場:連れてきた犬が飛び込んできて二人を救い出す。
- 結末:紳士たちは身ぐるみをはがされ、顔はくしゃくしゃになり、元には戻らない。
② 発表時期と背景(大正末期〜昭和初期)

執筆時期
『注文の多い料理店』は宮沢賢治が1921年(大正10年)頃に執筆したとされてます。彼が28歳前後で、盛岡で農学校の教師をしていたとされる時期。
出版
初めてまとめて刊行されたのは1924年(大正13年)、賢治最初の童話集『注文の多い料理店』の表題作として発表。出版費用は賢治自身が負担。
時代背景
大正デモクラシーの流れがあり、自由主義・都市文化・実利主義が広がった時期。
西洋文化の流入が盛んになり、洋食・洋風建築・スーツなど「都会的な生活様式」が象徴的な価値を持っていた。
一方で、農村は貧困や飢饉に苦しみ、格差が広がる
賢治自身も農民の暮らしの困難さを目の当たりにし、農業指導・肥料改良・信仰(法華経)を通じて救おうと考えていた。
大正期(1912〜1926年)は、特に都市部で西洋文化の流入が一気に広がった時代。

- 食文化
洋食レストランや西洋菓子店が次々と開業。カレーライス、コロッケ、オムライスなど「洋食」が一般家庭にも浸透し始める。ただし、農村では米・雑穀・野菜中心の食生活が続いていて、西洋料理を食べる機会はほぼない。洋食は「都会に出た人」や「裕福な地主層」が体験する特別なもので、庶民にはまだ遠い存在。 - 建築・都市文化
大正デモクラシーの空気のなかで、都市には洋館・カフェー・デパートが建ち並び、銀座や大阪の心斎橋がモダンな街並みに。
服装
スーツやハットなどの洋装が「進歩的でハイカラなもの」として普及。女性も大正モダンガール(モガ)のように洋装や断髪が流行。 - 社会的な意味
西洋文化=「都会的で先進的」というイメージが強調され、地方農村の伝統生活と対比される価値観へ。
象徴の読み解き
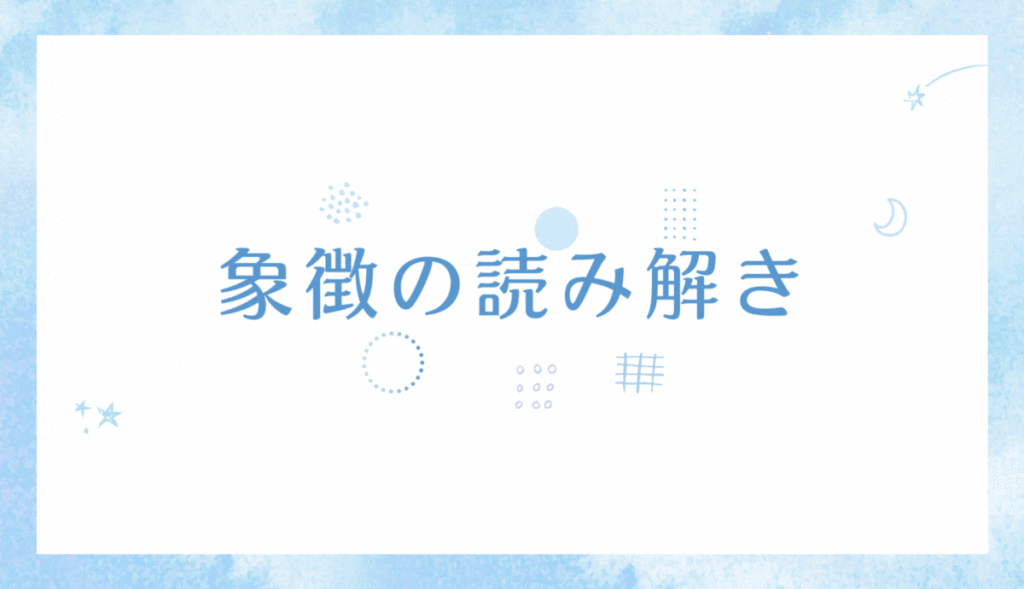
童話集出版に際して作成された宣伝用のちらし(無署名だが賢治の執筆と推定されている)に記された収録作品の紹介では「糧に乏しい村のこどもらが都会文明と放恣な階級とに対する止むに止まれない反感です」と記されている
Wikipedia
こういう風に記されているということは….
- 紳士=都会的・実利主義的人間(両親や都市住民の投影?)
- 犬=法華経、農業
- 山猫=欲望
① 紳士=都会的・実利主義的人間(両親や都市住民の投影?)
「じつにぼくは、二千四百円の損害だ」と一人の紳士が、その犬の眼ぶたを、ちょっとかえしてみて言いました。「ぼくは二千八百円の損害だ。」と、もひとりが、くやしそうに、あたまをまげて言いました。
紳士たちは犬をお金に例えて見下し、粗末に扱っている。実利主義に傾いた都会人の姿勢を象徴しているように見えます。宮沢賢治の家庭環境(質屋業)を背景にすれば、両親や都市住民の姿を重ねているとも読める。
賢治自身、両親との確執がすごく、実家の稼業を嫌っていたことから、紳士=両親説も濃厚ではある。
「帽子を脱げ」「靴を脱げ」といった注文を、礼儀や格式と勝手に解釈し、不審さを感じながらも、「ご馳走にありつける」と従い続ける。欲望に呑まれることで、危険を見抜けなくなる。
② 犬=法華経、農業
ところが、最後に彼らを救ったのはその犬。軽視していた存在こそが真の救い手となる、この逆転の構図は、賢治が庶民や農業への尊重を重んじていた思想とも重なるので、法華経に値するものかもしれない。
軽んじられていた庶民や農業こそが人を救うとも読める。犬を粗末に扱ったのに救われるという逆転は、命を金銭で測る価値観への痛烈な批判ともいえる。
③ 山猫=欲望
「料理店」は、人間を食らう存在として描かれます。それは、紳士たち自身の欲望が肥大化して自滅を招く姿にも見える。意志もないまま、言われる、目にするものだけを都合の良いように解釈し、背景を見ようともしない。
「帽子を脱げ」「クリームを塗れ」と次々に命じられる紳士たちは、疑いを抱きながらも従い続ける。
その紳士たちの姿は、欲に囚われて、それに気づきもせず、何もかも無くしてしまう様子の描写にも映る。
特に父親との確執が濃かった賢治の背景を説くと、あの注文の多さは実家とも読める。その皮肉さの比喩の描写なのかもしれない。
現代的な読み直し
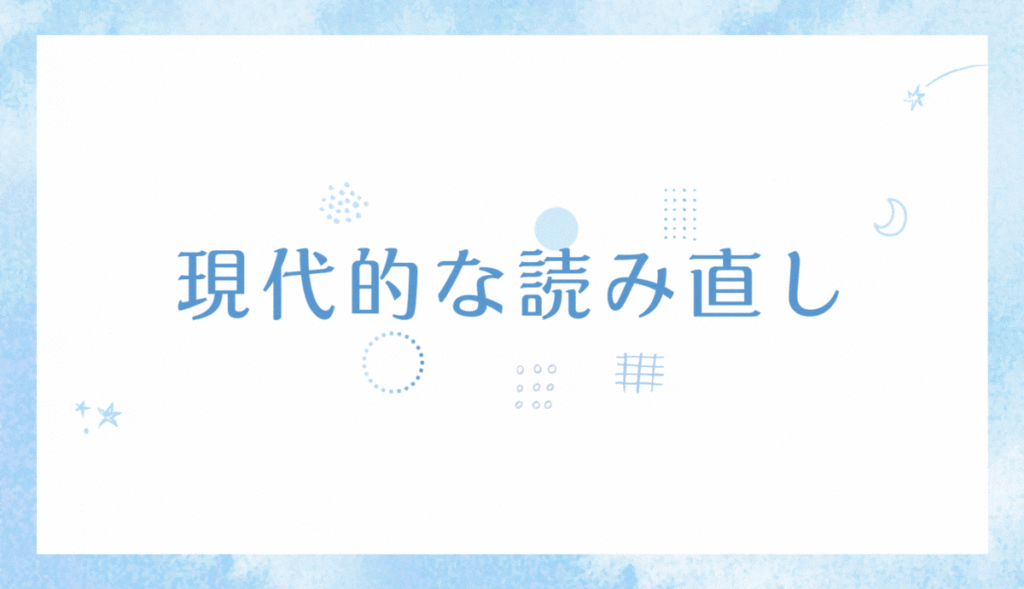
- 命をお金に換算する危うさ
- 情報を鵜呑みにし「都合よく解釈」する危うさ
- 教育や社会で活かせる視点
① 命をお金に換算する危うさ
紳士たちは、犬を「2,400円」「2,800円」と値踏みし、命をただの金額として扱う。
命を数字に置き換えてしまうことは、命の重みを感じなくさせる。欲を優先するあまり、尊いはずの命を犠牲にしてしまう。この危うさを、賢治は寓話を通じて警告しているとも読める。
② 情報を鵜呑みにし「都合よく解釈」する危うさ
紳士たちは「注文」を深く考えず、都合よく解釈しながら従う。これは、現代における情報リテラシーの欠如とも重なる。インターネットやSNSで流れる情報を鵜呑みにすることは、思考停止の従順さにつながり、やがて自分自身の危機を招く可能性がある。
現代でなくても、目に映るものだけを都合よく解釈してしまうのが弱い人間だという例えとも読める。
人の弱さというものは、事実を見ようとさせなくすることがある。理由はいろいろあるだろうけれど、最後に出てくるのは、どんな形であれ「保身」だろう。
それも悪くはない。そうせざるを得ない状況というものに、生きていると遭遇するからだ。ただ、そこに人の命だとか、人の尊厳が関わってくるときには、背景を見ようとする力がないといけない。

何もかも脱ぎ捨てて、人のために尽くすことが正しいという綺麗ごとは大嫌いだ。そうではなくて、自身の欲に自覚的でないといけない。その力は、自身の歩く道を光となって照らし、危うさから身を守るものになる。
「何もかも脱ぎ捨てて人のために」っていうのは、聞こえは立派だけど、結局は自分の欲や欠けを直視せずに外へ投影しているだけになりやすい。それは「利他」じゃなくて「自己欺瞞」なんだよね。
- 欲を自覚する
- そのエネルギーを隠さず、方向づける
- その力が自分を守り、道を照らす
これは、仏教でいう「煩悩即菩提」に近いとも思う。欲を否定するんじゃなく、それを自覚して進むからこそ、危うさに飲まれずに進める。
わたしは、仏教は仏教でしょってなるんだけれど…
宗派がこだわった部分として、
- 浄土真宗 → 「煩悩は絶対なくせない。やりたいようにやったらいい。判断は阿弥陀に丸ごと任せよう」。ちょっとカントっぽいとも言える。どんなに善行をしたところで、承認欲求などがある、その欲と人は切り離せないということ。
- 法華経(日蓮系) → 「煩悩あっても、すでに仏性は内在している。信仰・題目を通じてそれを顕現させよう(自力+法の力)」。
- 煩悩即菩提(禅や真言系の発想に近い) → 「煩悩そのものが素材。そこから気づきを得て生きる(自力転換)」。
- 煩悩は切り離せない → それ自体が悟り/救いに通じる。
- 煩悩は切り離せない、救いは「外」から来るんじゃなくて、「煩悩を抱えたままの自分」がもう救いの場にいる。
- 煩悩は切り離せない、欠けや欲を「否定」するんじゃなくて「抱えてよし」とする。



結局は 「煩悩と共に生きる」 が核であって、宗派ごとの「結果は阿弥陀に任せる/仏性を信じて引き出す/自分で自覚し、燃料にする」ってのは、ただのアプローチの違いにすぎないんじゃないの?っていう、個人的意見。こう読み解くと…賢治が「浄土真宗」を嫌ったのは、向き合いきれなかったのかもしれないとも思えるんだよね。家業から、父親が欲まみれにでも見えた(見たかった)のかもしれないし。
「救われる(委ねなさい)」(浄土真宗より)より、「救いたい(導く)」(法華径)が勝った。救うことで、自分が救われるしね。共にあれる場を設けて、皆で平和になるためにっていう、間の彼の想いや思想みたいなものには共感を感じるけれど、構造だけ見ると「傲慢」にしか見えないんだよねぇ。
人を救うって、人が?ってなる。わたしは「助ける」より「力になりたい」こういう言い回しを使うから。
その点、彼の作品は委ねられてるよね。「これが真理だ、従え」じゃなく、「こんなふうにも見えるんだよ」と諭せている。作品は説法に近いけど、あくまで選択は読み手に残せている。
③ 教育や社会で活かせる視点
教育で活かせる視点は、命に対する軽視の自覚もなく、自身の欲にかられ、物事を正しく判断しようともしない危うさだと思う。そういう者は、最後に何もかも失うことになりかねない。
命を何とも思わず、欲を満たすために突き進み、気が付いたときには遅い。この物語は「犬」という軽視された存在が最後助ける側として登場するけれど、現実はそうはいかない。
そこは、紳士の顔が元に戻らなかったというところに、意味があるとも読める。
どこで気づくか?だよね。最後の最後、塩塗り込むところで気づいてるから。「鉄砲と弾丸(たま)をここへ置いてください。」と言われてる辺りで気づけば、丸腰にはならないから、戦えたかもしれない。
宮沢賢治【主要作品】 年表
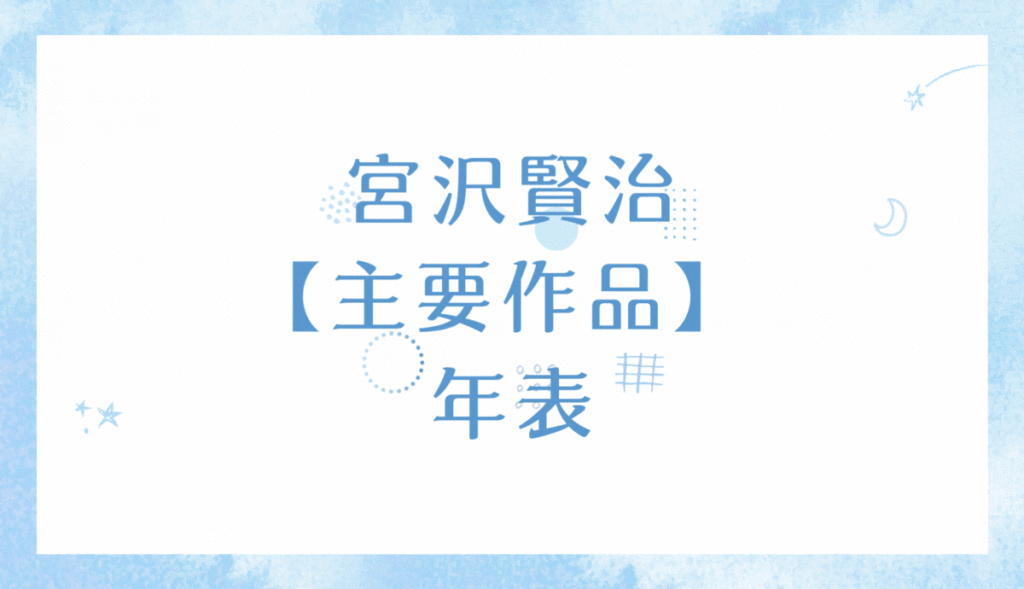
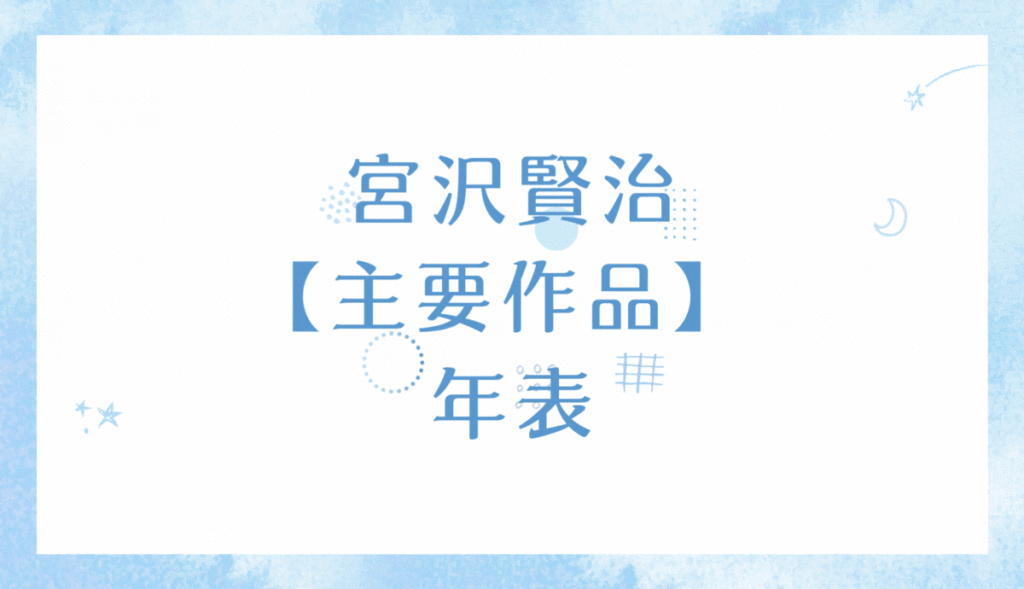
| 年 | 年齢 | 作品 | 区分 | 発表形態 |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 28歳 | 注文の多い料理店 | 生前公開 | 光原社から刊行(童話集) |
| 1924 | 28歳 | 春と修羅(第一集) | 生前公開 | 自費出版 |
| 1932 | 36歳 | グスコーブドリの伝記 | 生前公開 | 雑誌『児童文学』掲載 |
| 1934 | 没後 | 風の又三郎 | 死後公開 | 雑誌『児童文学』掲載(未完成要素あり) |
| 1934 | 没後 | ポラーノの広場 | 死後公開 | 雑誌『児童文学』掲載 |
| 1934 | 没後 | 銀河鉄道の夜 | 死後公開 | 草稿を整理し刊行 |
| 1934 | 没後 | 雨ニモマケズ | 死後公開 | 手帳から発見・公表 |
| 1934以降 | 没後 | 農民芸術概論綱要 | 死後公開 | 原稿を公表 |
| 1933以降 | 没後 | 春と修羅 第二集・第三集 | 死後公開 | 原稿を整理して刊行 |
もっとあるけれど、主要を並べると大体こんな感じだと思う。
- 『雨ニモマケズ』(1940年代後半〜1950年代、教科書掲載で全国に広まる)
- 『銀河鉄道の夜』(死後版で知られるようになり、1960年代以降に子ども向け文学として定着)
- 『春と修羅』シリーズ(詩集として評価され始めるのは戦後以降)。
ばーっと最初に広がったのは、戦後の『雨ニモマケズ』。その後、童話群が文学作品として再評価されて、今の「幻想文学作家」像ができあがったんじゃない?っていう想像ね。教科書で採用 → 全国の子どもが暗唱 → 親世代にも波及。これが「宮沢賢治=清貧の理想像」というイメージの出発点かなと推測してみる。
戦後だもの。思想が必要だったんだと思う。過酷な状況であるにもかかわらず、泣き言を言わずに前を向けるような。



いやぁ、そう思える、というだけだけどね。
解くことに意味があるのか分からないけれど、あまりにも理想論が過ぎて、ごめんなさい、ついていけなくて。
父親に反発するのは分かるけれど、資金の援助は求めてるわけでね….それが悪いとは言わないけれど、賢治の脳内が分からない。
確執を見てみよう。
父・政次郎との確執
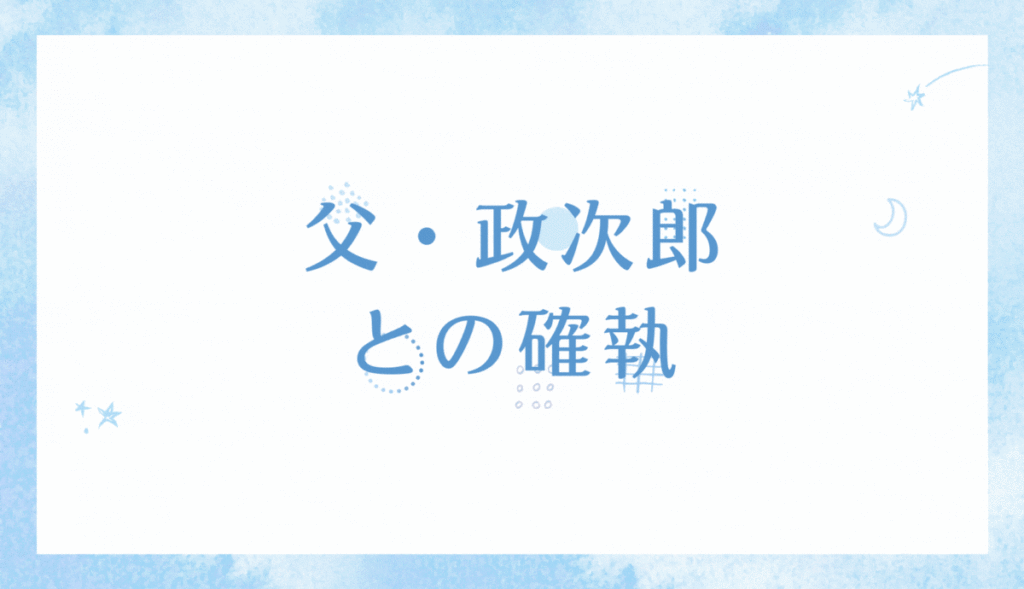
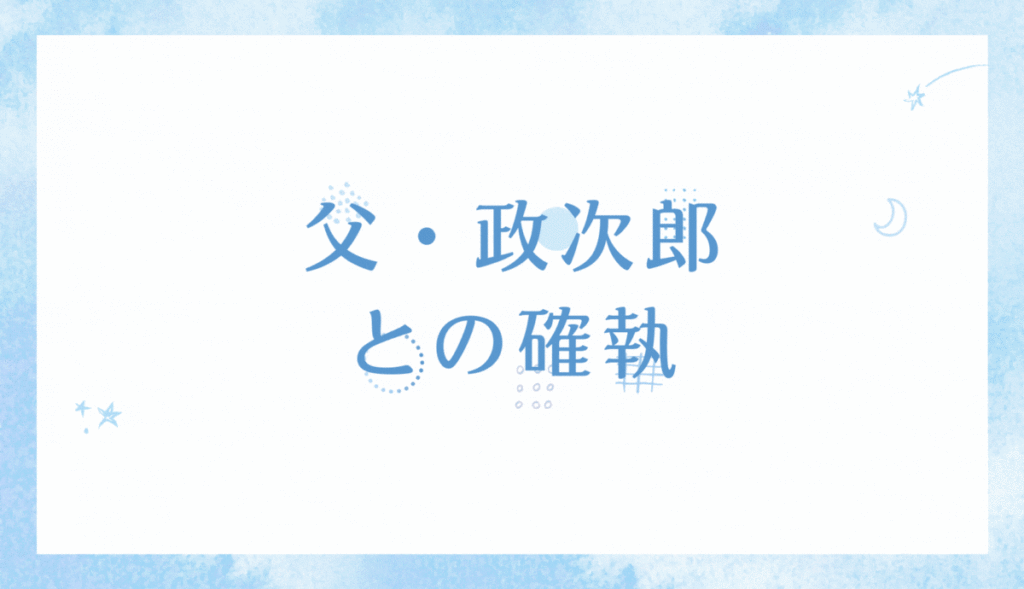
- 稼業(質屋・古着商)をめぐって
- 宗教観の対立
- 経済的依存
- 双方どう見える?
① 稼業(質屋・古着商)をめぐって
- 宮沢家は花巻でも有数の資産家。父・政次郎は質屋・古着商・地主として財を築いた。
- 長男の賢治に「家業を継がせたい」という期待があった。
- 賢治は「金儲け」に嫌悪感を持ち、稼業を拒否。
- この点で父と衝突した(→事実、後継は弟・清六が担った)。
② 宗教観の対立
- 父・政次郎:浄土真宗の門徒
- 賢治:青年期に日蓮宗に深く傾倒し、法華経を絶対視
- 宗派の違いから、親子間で強い葛藤があった
③ 経済的依存
賢治自身も「自分の活動は絶対真理に基づいている」と思い込んでいたとしたら、借りることを矛盾と感じなかった可能性もある。
むしろ「父の財産も真理実現のために活かされるべき」と無意識に考えていた可能性もあり得るよね。
- 賢治は「農民のための活動」を展開する一方、生活基盤は父の財力に大きく依存していた。
例:羅須地人協会は祖父の別宅を使用/生活資金・衣類・米などを実家から支給。 - 父からの資金援助を求める文面が残っている。
こちらの情報によると、上京中、父親に200円(当時米1升が45銭程度であった)の援助を求めた書簡が残されているとあることから、そう考えてみる。現在で40万くらい?
④ 双方どう見える?
父・政次郎から見れば
- 長男なのに家業(質屋兼農業)を継がない。
- 改宗して家の信仰すら否定する。
- 親の金で学業も生活もしているのに、自立しない。
- 「農民のため」と言いつつ、実際は親の資金・土地・物資に頼りながら活動している。
これを今の言葉にすれば、まさに「親のすねかじりで理想ばかり語る人」にしか見えなくなる….
一方で賢治から見れば
- 「父は金のことしか考えない」
- 「自分の理想を理解してくれない」
- 「宗教も芸術も人のためなのに、目先の財産ばかり守る」
と、正反対の解釈をしていた可能性。
しかし、賢治の理想(宗教・芸術・農民指導)は父の現実主義の土台がなければ成立しなかった。でも賢治はそれを感謝として受け止めず、「父は間違っている」と反発して改宗(浄土真宗⇒法華経)まで進めている。



冷静に見ると、政次郎の方が「社会的責任」や「生活基盤」という意味で正しかったのは確かで、ただ、文学史の中では「理想に殉じた賢治」の方が美化されている、という構図に見えなくもない。
政次郎が「おまえもなかなかえらい」と答えて階下に降りると、賢治は清六に「おれもとうとうおとうさんにほめられたものな」と言った。
死に際の台詞だけど、相当認められたかったんだろうな。
書籍については、
弟・清六には残された原稿は出版を希望する本屋があれば出すように言っている。父には迷いのあとだから適当に処分するように言い、母にはこの童話は仏の教えを書いたものだから、いつかはみんな喜んで読むようになると言ったという。
宮沢賢治の生涯
こうあることから、弟・清六が遺言を守った形なんだろうと想像する。法華経を絶対視した賢治の姿勢は彼自身の“投影”だったとしても、清六の手を経て残された作品群は「特定宗派に閉じない普遍性」を帯びてる。結果的に、「万人に共通する気づき」に届いたんだよね。
ただ、「説くこと」と「自分に返すこと」は別次元の難しさなんだと思う。外に向けて理想を説いても、自分自身の欲や承認渇望にどれだけ気づけるかで、その言葉の純度は変わる。賢治も最後までそこに揺れていた人で、だからこそ作品に“影”が残っていて、今読むと余計に面白いのかもしれない。
普遍性があるからこそ広く受け入れられたし、けれど「説いた本人」がそれを完全に自分に返すのは難しく、そこに人間らしい矛盾がある。この「矛盾ごと残ったこと」が、逆に現代まで価値を持たせてるのかもしれない。
賢治の思想
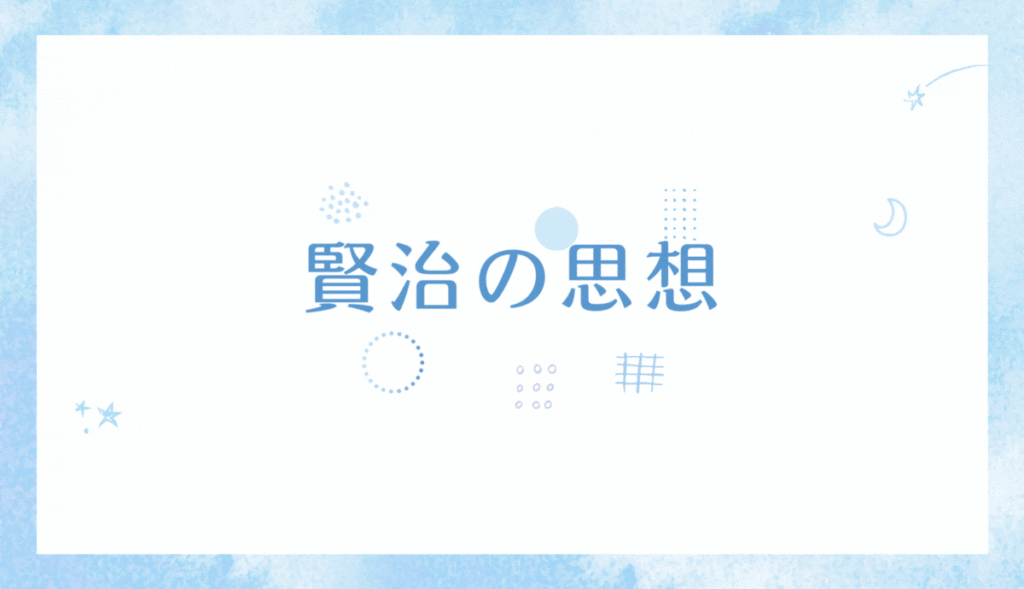
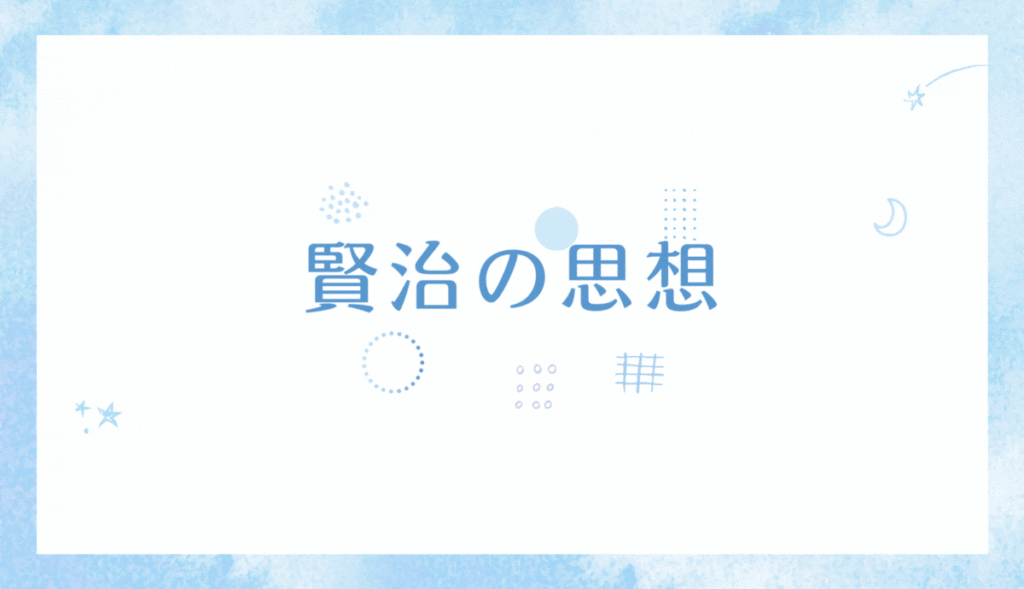
「世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はあり得ない」
というのが、背景には法華経の「一切衆生悉有仏性(すべての存在に仏の可能性がある)いっさいしゅじょうしつうぶっしょう」思想があって、賢治は「個の幸せだけを追う生き方は虚しい」という直感を強く持っていたんですよね。
ただ、個の幸せがないと、皆にどうやって広がるんだろう?という個人的な違和感は残るよね。
1. 欠乏と投影の構造
- 人は自分の内面に欠けや不安があると、それを外の世界に「投影」しやすい。
- たとえば「自分の心が平和じゃない」人ほど、「世界が平和でないこと」に強く反応する。
- その訴えは「純粋な理想」ではなく、自分の内的不足を外に見ている部分がある。



自身に欠けがあると、異性であれば執着に変わり、同性であれば反発になることがあるって、わたしはそれを「人」で表したけれど、何も対象は「人」でなくてもいいんですよ。
自分が満たされてない人ほど、自分を取り囲む周りの世界(世間)が歪んで見えるということ。
実際に、食料不足とか、マズローの五段階欲求の下から2つが満たされていないと、食べ物という物資が必要でしょう?それは内的不足ではなくて、物資不足。
物資不足の人から、自分を取り囲む周りの世界を見たときに、人がどう映るか想像してみる。
- 内的欠乏(承認欲求や愛情不足) → 世界は「冷たい」「理解されない」と歪んで映る。
- 物資不足(食べ物や安全の欠如) → 世界は「奪い合い」「不公平」として敵対的に映る。
どちらも「不足」という視点から世界を見るので、実際の世界よりも厳しく、冷酷に見えるのが共通点。
この共通点を整理しようと思ったときに、
「世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はあり得ない。」
この両方を満たそうとしたときに、内的欠乏は音楽だとか仲間意識に向かい、物資不足は食料に意識が向かう。
賢治はこの両方を同時に満たしたいと思ったんだろう。しかし、五段欲求は下から上にしか進まないから、ロジック破綻を招いた。
自分が孤独で承認されない → 「みんなで助け合う平等な社会を!」と訴える→ 実際は「自分が認められたい」という欲求の裏返し。
ここで、投影を説いてみる。



さっきも言ったけど、お前のせいで、文学が台無しだよって言われる可能性高いのよ。けど、気になるから許してくれる?ただの個人的見解だから。
賢治が農民に投影したもの
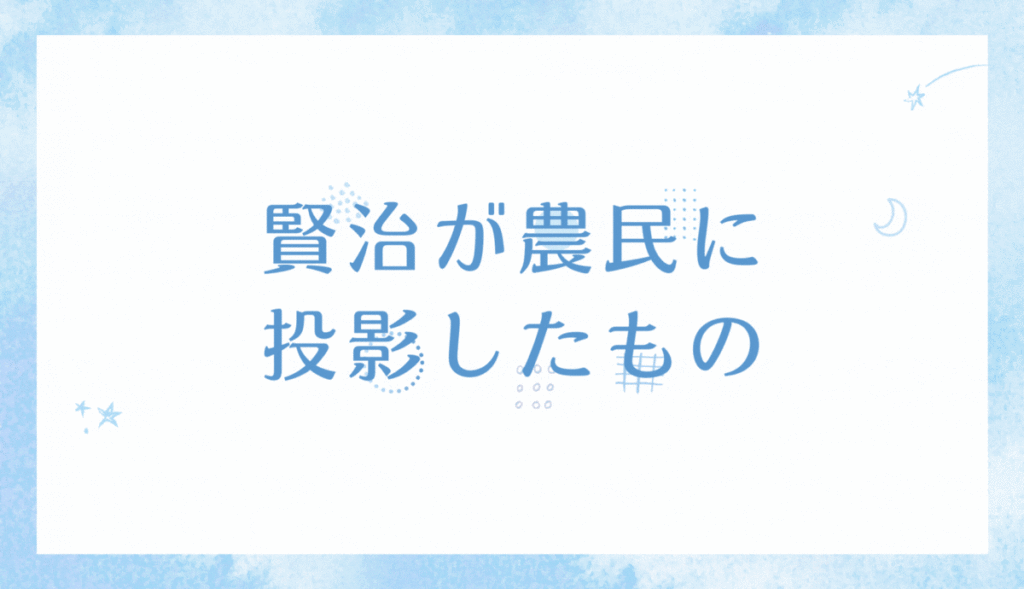
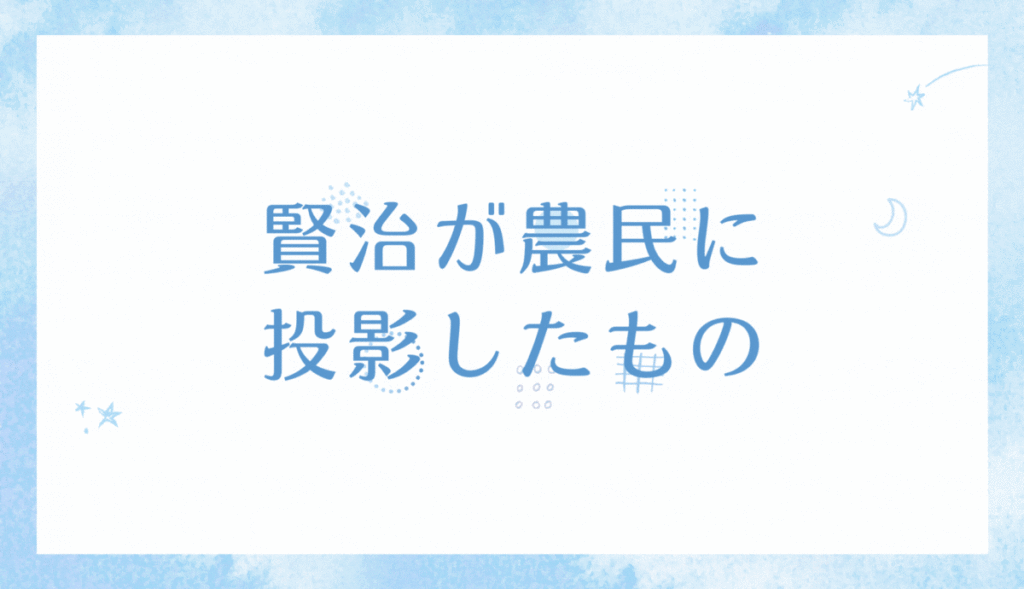
- 飢えや欠乏感
- 自分は実際には裕福な家の長男で、食べ物に困ったことはない。
- でも「飢え・物資不足」の農民を見て、自分の心の欠け(孤独・承認欲求)を重ねた可能性がある。
- 救われなさ・孤立
- 賢治は父と対立し、理想を理解されず孤立していた。
- その孤独感を「困窮する農民の境遇」と重ねて、「自分と同じく報われない人たち」と感じた。
- 理想の投影
- 農民が幸福になれば、自分の心も報われる。
- → 「世界がぜんたい幸福でなければ、個人の幸福はない」という思想に結びついた。
- 投影としての農民観
- 結局は…..
① 投影としての農民観
- 実際の農民は「生き延びるために必死」で、芸術や理念よりも「今日食べられるか」が重要。
- でも賢治はそこに自身を投影し、「農民が幸福になることで自分も救われる」と信じた。
- 農民そのものを見たというより、自分を映す鏡にしたとも言える。
② 結局は…..
- 賢治の「農民救済」は、現実の農民を理解しての行動というより、自分の欠乏感や理想を投影したものだった可能性が高い。
- だからこそ農民とはすれ違い、実際には孤立していった。
戦争や飢饉の記録から、飢えた人々は周囲の人を「奪う者」「敵」として見る傾向があり、実際には相手が敵意を持っていなくても、飢えた心が「敵意の影」を作り出す。
賢治は野菜をリヤカーで売り歩いたが、当時の農民にはリヤカーは高級品で、賢治の農業は金持ちの道楽とみられてしまう。野菜を勝手に持っていかれても笑って許していた。農村の水路修理などの共同作業も参加せず金を包んで済ませている。また畑の白菜を全て盗まれるという嫌がらせにあった話を詩に残している。





どうあれ、どの道ロジック破綻的な感じがする。ごめんだけど。
欠乏を埋めたいがために「全体のため」と言っても、動機が不安定だし、エネルギーが「他人のため」ではなく「自分の不足を補うため」に流れてしまうから、継続や純度が失われやすいんですよね。だからまず 自分の内側を整える(欠乏を直視して癒す)ことが、全体に働きかける前提にはなるんだと思うけど、無自覚だとちょっとできないから….
こういうものも、あった↓
この頃、小学校教員の高瀬露という女性が協会にしばしば通ってくるようになる。高瀬は賢治の身の回りの世話をしようとしたが、賢治は居留守を使ったり、顔に灰を塗って出てきたりするなどして彼女の厚意を避けようとした。協会に人が集まった時、高瀬はカレーライスを作ってもてなしたが、賢治は「私には食べる資格がありません」と拒否。怒った高瀬はオルガンを激しく引き鳴らした。その後、彼女は賢治の悪口を言って回るようになったが、父の政次郎は「はじめて女のひとにあったとき、おまえは甘い言葉をかけ白い歯を出して笑ったろう」と賢治の態度を叱った。



その後、彼女は賢治の悪口を言って回るようになった。どういう状況?
自己承認の欠如
→ 「自分で自分を承認できないから、相手に必要とされたい」という欲求が強い。
愛と依存の混同
→ 世話を焼くこと=愛だと勘違いして、実際は相手に「私を認めて」と迫っている。
相手を対等に見ない
→ 賢治を「支えてあげる対象」と見下しつつ、「承認してほしい対象」としても見上げる。
結果、対等な関係を築けない。



まぁ、賢治が自己拒否が強ければ、受容できなかった可能性もあるとも見れる。つまり、最初は惹かれたのかもしれない。けど、徐々に自分の認めたくない部分の投影を彼女に見る。よくある構造だ。そして彼女の何かしら世話を焼くその行動に、自分の自由を制限してくる父親の存在と重なった。だから過剰に反応し、滑稽なまでに拒否。で、居留守、顔に灰。行動から見るに「逃げ」だものね。となると見えてくる構造はひとつ。自身の課題から逃げて、ごまかしているという風に映ることもある。わたしにはね。正解か不正解は別にして。
宮沢賢治の生涯について※持論
宮沢賢治にとって法華経は、外から与えられる教えやただの宗教テキストじゃなくて、自分そのもの=生きる基盤だったとも思える。
どういう意味で「自分」か
- 存在の拠り所
賢治は父との確執や農民とのすれ違いに悩み続けた。その中で「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)=すべての存在に仏性がある」という法華経の思想が、自分の存在を支える唯一の理屈になった。 - 表現の核
童話・詩・農業実践など、全部バラバラに見える活動も「法華経の精神を世に伝える」ための手段。つまり作品そのものが彼の法華経理解の“翻訳”。 - 死に際の言葉
「お経をあなたの御手許に届け…」という願いは、外のものを渡すというより、「自分が法華経として生きた、その全体を渡す」という告白にも読める。
賢治にとって法華経は「拝む対象」ではなく、生き方そのもの、自分自身と不可分なもの。
ただし、動機が承認欲求であろうと、宗派に偏っていようと、実際に「人のために動いた」事実は尊い。
- 音楽会を開いた
- 農業指導をした
- 童話で子どもを楽しませた
その背後に欲があっても、「行動」が残ったことが大きい。
皮肉なのは、賢治の活動を支えたのは「嫌ったはずの父・政次郎(浄土真宗門徒)」の経済的援助もあったということ。
- 父の資産がなければ羅須地人協会も続かない
- 活動への資金援助があった
→ 結局、法華経を実践する賢治の土台は、浄土真宗である父親に支えられていた。
理想と欲望、法華経と浄土真宗、承認欲求と父の現実主義――その矛盾の中で生き切ったことこそ賢治の真実の姿に見える。
まとめ
『注文の多い料理店』この物語は、賢治の生き方、その投影とも思える。西洋人を揶揄している目線で読むと、そのように映る。これは表層だけの展開だ。真相を読み解いて文字お越ししてみる。
人の尊厳を守れず、自身の欲に無自覚に突き進むと、最後は自分の欲に自分が呑まれてしまう図だ。
これを、賢治に置き換えてみる。
遊郭などもある時代、食べる物に事欠いていて、明日の生活すら危ぶまれる農民に、音楽を奏でる豊かさを説き、科学技術を教えるという構図に当てはめてみて欲しい。
わたしには、「俺を認めて欲しい」という欲にしか映らない。ごめんだけど。
『注文の多い料理店』を書いたときは、本格的な農民との摩擦や失望には辿り着いていない。だけど、「農民=父親」であり、「農民=賢治」の図に見える。農民を救うことにより、自身が救われる。そして農民に認められることにより、父親に認められるという構図に映る。
まぁ、何にせよ、動かないよりは動いた方に価値がある。理由は関係ない。ただ、それに自覚的であるかどうかで、行動が変わるから、現実の構造を見ないと行けなかったんだと思う。
賢治の作品は理想論に見えるけれど、裏側にあるのは 承認されたい気持ちと自覚の欠如とも読めるよね。その未整理の欲が物語ににじみ出ていて、『注文の多い料理店』で教育で活かせる構造は、皮肉にも「欲に無自覚である危うさ」ということになる。
わたしは小さい頃から「綺麗ごと」が大嫌いだった。裏にある「保身」や「欲」が透けて見えたから。親や学校の先生達にも、すぐに「嘘つけ」そうなってた。笑
小さいことで言うと、式があるわけでもないのに、学校での会合に関係者がくるときだけ通りに並べられるあの「菊の花」にすら違和感があった。笑 何のために必要なの?っていうね。重症っちゃ重症かもね。笑


今は思うよ。並べたかったら並べたらいい。その方が綺麗だし、気持ちがいいかもしれないから。
先生に聞いたこともある。笑



あれ、何のために必要なの?



いや、僕もさ、やらなくていいって言ったんだけど….



嘘つけ。
学校の先生もまさか、「菊の花」を問われるとは思ってなかったかもしれない。
今思うと、皆、「嘘」じゃなくて「本心」だと思っていたのかもしれない。わたしには「嘘」に見えていた。これがわたしの目からみた「裸の王様の世界」だったのかも。
周りからよく言われたのは、「そう言われると、何も言えなくなる」なんだけど、「気づかなかった」って言って欲しかったなぁ。「王様が裸だと知ってるくせに、知らないふりをするな!」という叫びが、意味をなさないじゃないねぇ。



賢治の作品を読むときは“彼の理想”より“彼の欲の影”を見るって視点を提示すると面白いかもしれないよね。怒られるかもしれないけどさ。
どういうこと?って思うかもしれないから、わたしなりにまとめてみました。お前のせいで、作品が全部台無しだよってなるかもしれないけれど、個人的な見解なだけだから。賢治の作品をどう読むかは、あなた次第。

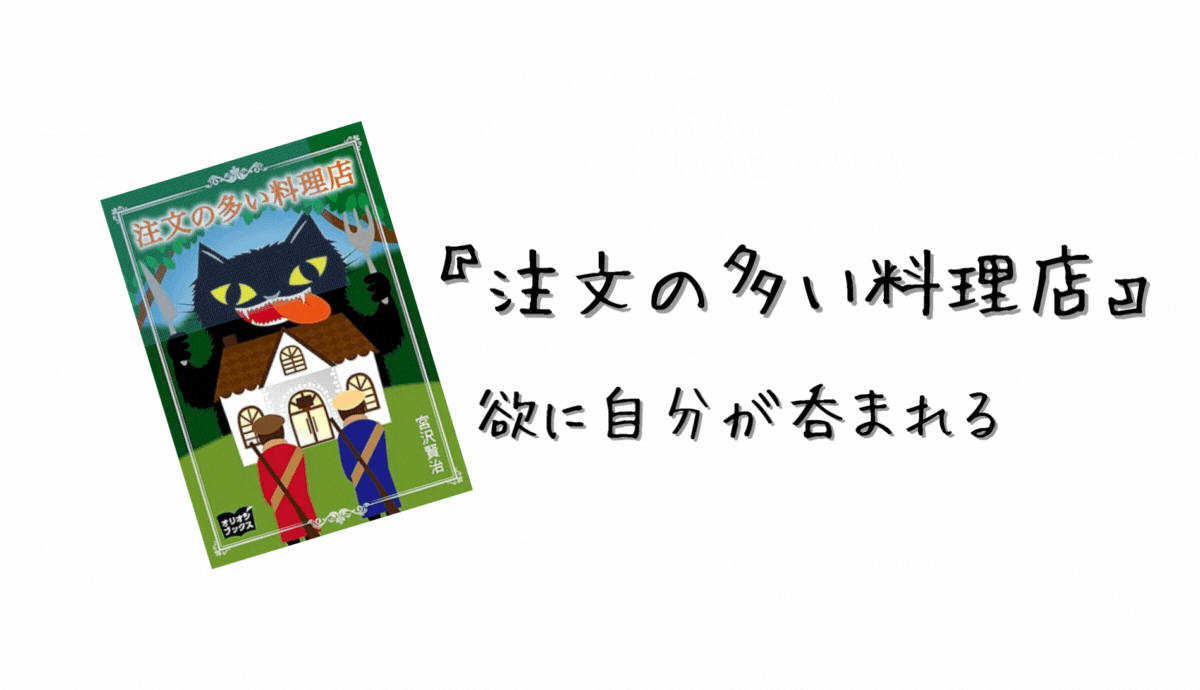
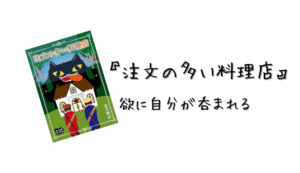
コメント