宮沢賢治についてあれこれ調べていくと、「じゃあ、この作品はどうなんだ?」と次々に考察してみたくなる。
今回は、まさに“乗り掛かった舟”という気持ちもあって、『どんぐりと山猫』を読んでみることにしました。
すると、どうなったか?

これ、国語の教科書で取り扱ってたの???、何を言っているのかちょっと分からない部分が多すぎて草。
こうなった。笑
彼の作品を、当時の彼の周辺人物に置き換えることに意味があるかは分からないけれど、そこから見えてくる新たな見解もあると思ったので、わたしの見解を勝手に残しておくことにしました。
参考PDFはこちら↓
『どんぐりと山猫』は何を描いているのか?
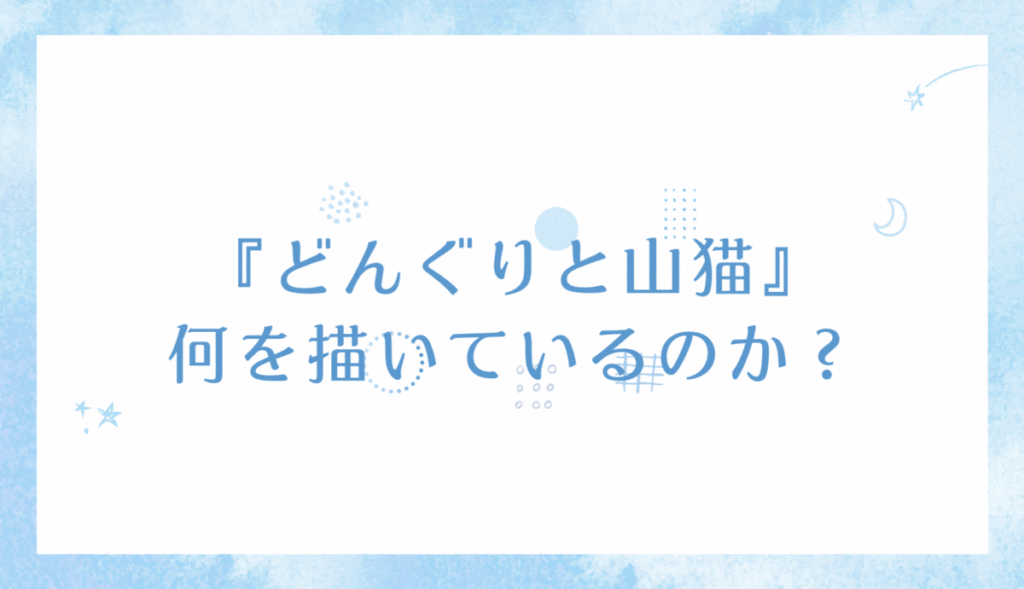
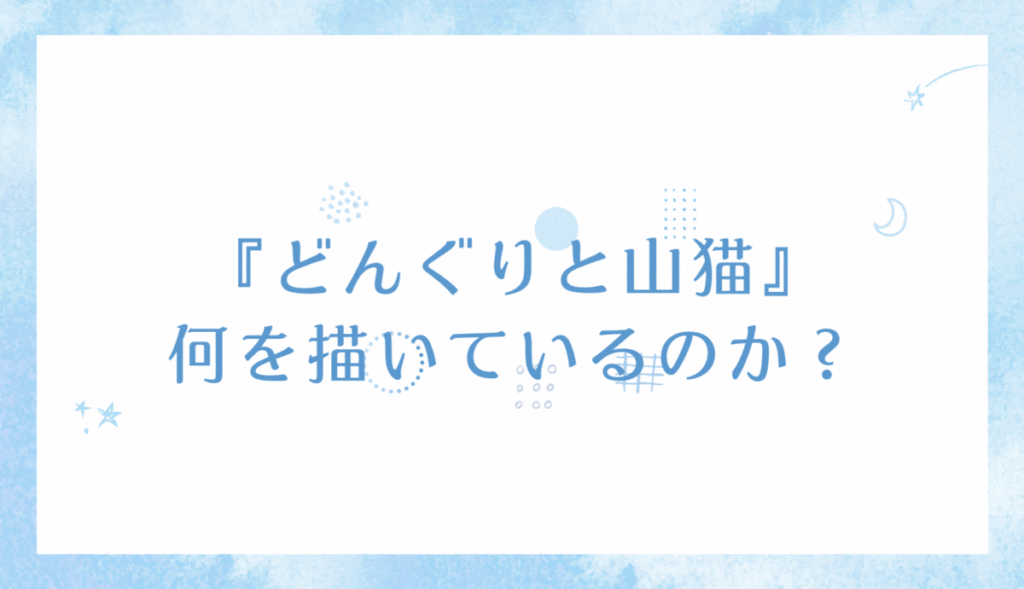
個人的な見解だから、ひとつの仮想として読んでもらいたいのだけど、わたしはこう読んでます。
- 一郎=宮沢賢治自身の投影
- 山猫=保坂嘉内という読み
- 馬車別当=アザリアの仲間
① 一郎=宮沢賢治自身の投影
物語の「一郎」は、純真さを持ちながらも、方便を誤解してしまう賢治自身の未熟さを象徴していると読める。
一郎はこの物語で「善」として描かれているんだと想像する。
しかし、馬車別当への対応に、方便を人間関係の潤滑油ではなく「誤魔化し」として使ってしまう姿勢が見える。つまり、一郎=賢治は「自分の矛盾」に気づききれないまま、それを物語化しているのでは?という構想。
② 山猫=保坂嘉内という読み
一郎が山猫からのはがきを受け取り、飛び跳ねて喜ぶ場面。また、山猫と意見が合わずに最終的に疎遠になっていく構図を考えると、山猫は当時賢治と交流のあった保坂嘉内と重なる。
この保坂嘉内という人物は、とにかく賢治にものすごく影響を与えた人物で、賢治の代表作とされる『銀河鉄道の夜』のカムパネルラのモデルとも言われている人物。
賢治⇒保坂の求愛とも思える構図がすごい。



それでは、文句はいままでのとおりにしましょう。そこで今日のお礼ですが、あなたは黄金のどんぐり一升と、塩鮭のあたまと、どっちをおすきですか。
塩鮭の頭を二択に持ってくるところを見ると、なかなか馬鹿にしていると想像する。あたまって何?場違い・残り物・侮辱のニュアンスが強調されてるようにも思えるけど、どうだろう。この鮭の頭だけは、ちょっと読解が難しい。
あと、



一升にたりなかったら、めっきのどんぐりもまぜてこい。はやく。
これらの失礼な言葉は、賢治に自分の立場を否定されたと勘違いし、誤解を抱えてしまった保坂との関係を象徴しているように見える。
そしてこの時期、保坂自身、アザリア事件で退学後に家族を亡くしたりと生活が安定していない。
となると、
どんぐり=思想・理想・理念の世界
鮭の頭=生活・現実の重み
とも読めるかもしれない。その線が妥当かも。理想ばかり追いかける賢治に対して、現実を無視するなという保坂側の視点。
山猫は「誤解する他者」として描かれつつ、賢治自身が保坂に投影した存在でもあるかもしれない。
わたしの見解では、ここはむしろ自覚的に描かれた可能性が高いと想像する。
なぜなら物語の最後で一郎は「出頭すべしと書いてもいいと言えばよかった」と後悔しているからだ。そして、黄金のどんぐりが普通の茶色のどんぐりに変わっている。この後悔の描写は、賢治自身が「途中で誤解があった」と気づいていた証拠、誤解から夢が破綻した図とも読める。
つまり、山猫からの返事を待っている構図がすでに存在しており、そこには「相手を誤解させてしまった」「すれ違い」という自覚が込められているのではないだろうか。
③ 馬車別当=アザリアの仲間
一郎宛のはがきを馬車別当が代筆するくだり。
ここから、当時アザリアで編集的な役割を果たしていた保坂や他の仲間たちの姿が連想される。
仲間の言葉を修正したり整えたりする役割を保坂が担当していたら、馬車別当はアザリアの仲間を象徴しているのではないかと推測する。
方便思想の誤解が生んだすれ違い
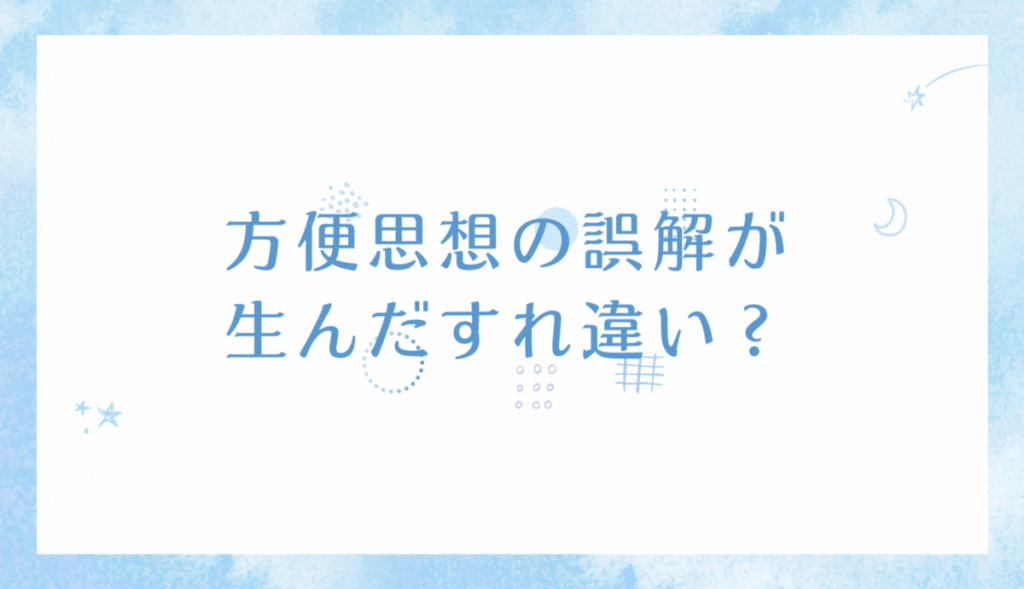
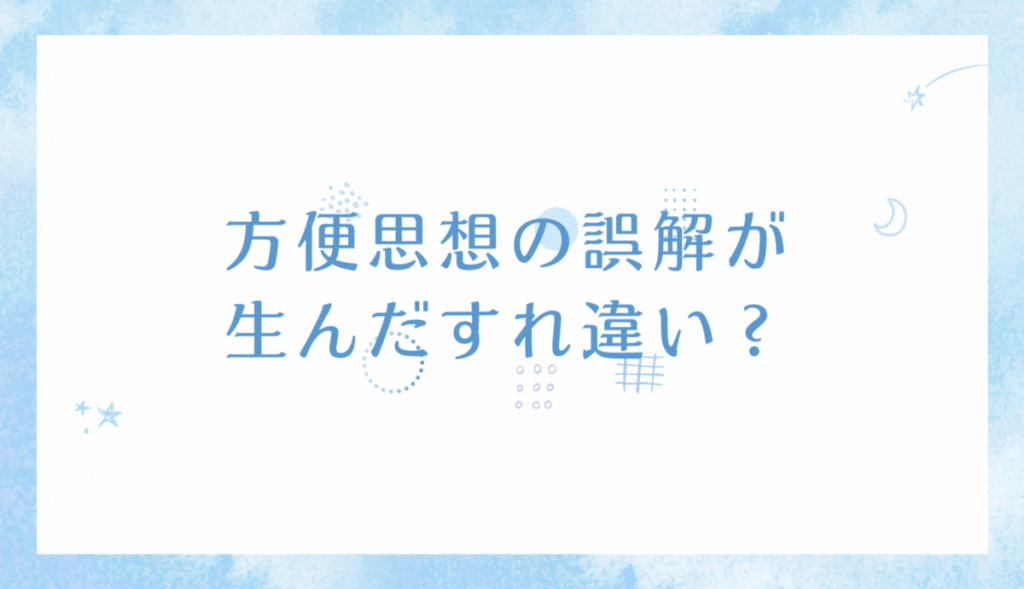
- 本来の方便とは何か
- 否定だけでは伝わらない
- 人間関係への波及
① 本来の方便とは何か
仏教で言う「嘘も方便」とは、本来は自己保身のための嘘ではないはずだ。相手を救うために一時的に仮の言葉を用いることを意味するんだと思う。
法華経における方便は「すべての人に仏性がある」という真実へ導くための知恵であるのに、賢治はこの核心を取り違え、方便を「相手をなだめるための言葉」程度に捉え、それを物語化してしまった可能性があるとも考察できる。
② 否定だけでは伝わらない
物語の中で一郎は、「さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。」と山猫の言い分を否定する。
だが、なぜ「変(へん)」と思うのかを語らず、理由を説明しないままその場を後にしている。その結果、山猫は「残念だ」と誤解を深め、両者の関係は崩れてしまったのではないか。
誤解かどうかは分からないけれど、なぜ「変(へん)」と思ったのかの描写が無い。ここには「伝え方ひとつで人間関係を壊す」という典型例が描かれているようにも見える。
③ 人間関係への波及
方便を誤用すれば、相手を励ますつもりが、かえって卑下する行為になる。
このことに気付かない現代人も多いのではないかと思う。
誤用があれば、励ますつもりの言葉が、相手には「バカにされた」と映ることもある。賢治が物語で描いたすれ違いは、方便を誤解したまま使うことで、人間関係の信頼を損なう構造を示している。
このことを意図的に描いたかどうかは分からないけれど、一郎自身が馬車別当に尊重が見られないのは確かだ。そういう思考回路の人が人間関係を上手に築くことができるか?という視点を設けたときに出る答えは「NO」になる。
結果、山猫とも誤解を生み、その後連絡は途絶えている。



わたしからすると、当然の結果と思える内容だ。
理解を生むのも対立を生むのも、結局は相手のことを考えた「言葉の使い方次第」なのではないか?
わたしには、一郎に見えていた世界は「自分自身が描いた世界」だけで、相手の意志や解釈を受け止める余白がなかったように思える。
現に、二度と裁判に呼ばれることがなかったという文言で物語は終わる。そして一郎は、「出頭すべしと書いてもいいと言えばよかった」と後悔を滲ませている。



感情も事実も掴まない、こういう決断をすると、後悔が付きまとうよね。掴まないといけない。そして咀嚼しないと翻弄されるよ、自分にも他人にもね。難しいんだろうね。自分の状況、していることを判断して動くということは。原理原則だよ。
例えば、事実がそうであったとしても、伝えてはいけない内容というものは存在する。ここを理解するには、現状と構造を正しく理解する必要があり、それが他者尊重になる。
伝えてよいこと、悪いことの判断ができないレベルと話すのは、疲れるだけだよ。
わたしなら、



出頭すべしで大丈夫ですよ。
こう答えるかな。帰ってから、次の裁判に出向くのかどうか考えたらいいだけの話だ。
そうして多角的視点で言動の波及先まで読んで、構造に落とし込む。そうしたら見えてくるものが変わってくることがある。一旦持ち帰る、一旦従う、その場で返さない。基本としてる。わたしには、朝のトイレくらい当然のものだ。
分かるかな。言動を読んで(仏教の空)、構造に落としてみる。構造は不変だから、自分の描いた世界がブレていないか確認する作業になる。そこにブレがなければ、それは正解となる。
反射的に返すと、誤解や衝突が生まれやすい。一度受けた後で構造に照らして再検証すれば、どちらにブレがあるのかを確認できる。それは方便の誤用(相手を安心させるための嘘)とは真逆で、相手を尊重しつつ、自分の判断を普遍の枠組みで確かめることになる。
一郎は、その場で「それは違う」と返してしまった。だから関係がねじれ後悔が生まれた。主導権は山猫。私の方法なら、相手の言葉をいったん受け止め、後で構造に照らして検証できる。そうすれば、波及をコントロールできるし、相手との関係を選び直す余地も残せる。結果的にブレない結論にたどり着けるし、相手に翻弄されることもない。
- 何が目的かを常に捉え、
- 無駄な戦いをしないで、
- でも「誰が何をしたか」「してくれたのか」は記録として握っておく



という姿勢は大事。闘わないけど、見ているし、記録しておくけど、執着しない、翻弄されない。そうすると、波に乗れる、そう感じる。 「相手にどう思われるか」より「本質に近づけているか」 「共感されるか」より「尊重できているか」 、「勝ったか負けたか」より「波を読んで自分で選べたか」。覚悟はいるよ。わたしはそうしてるってだけの話。
私の考察
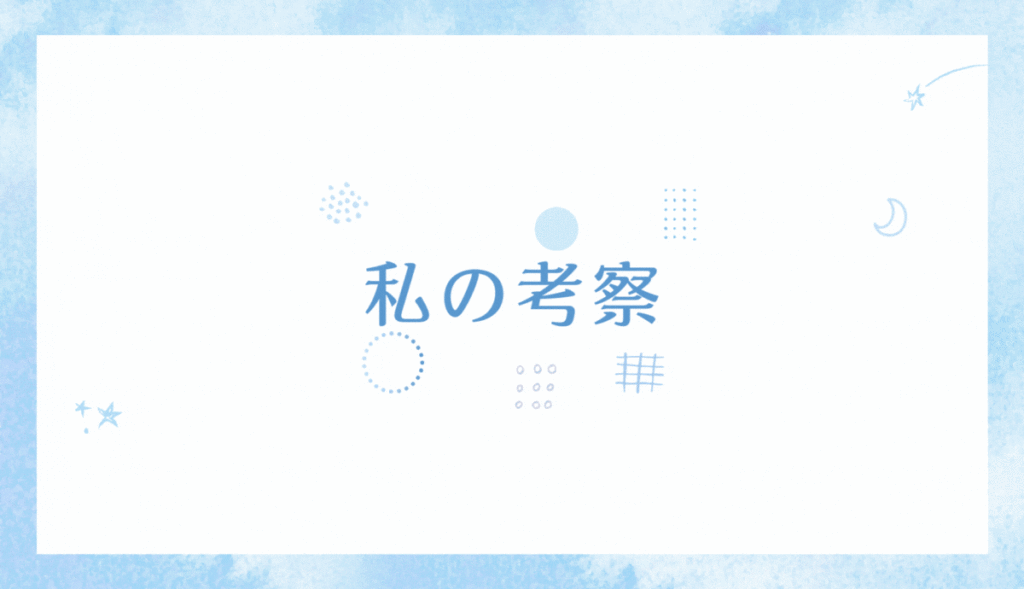
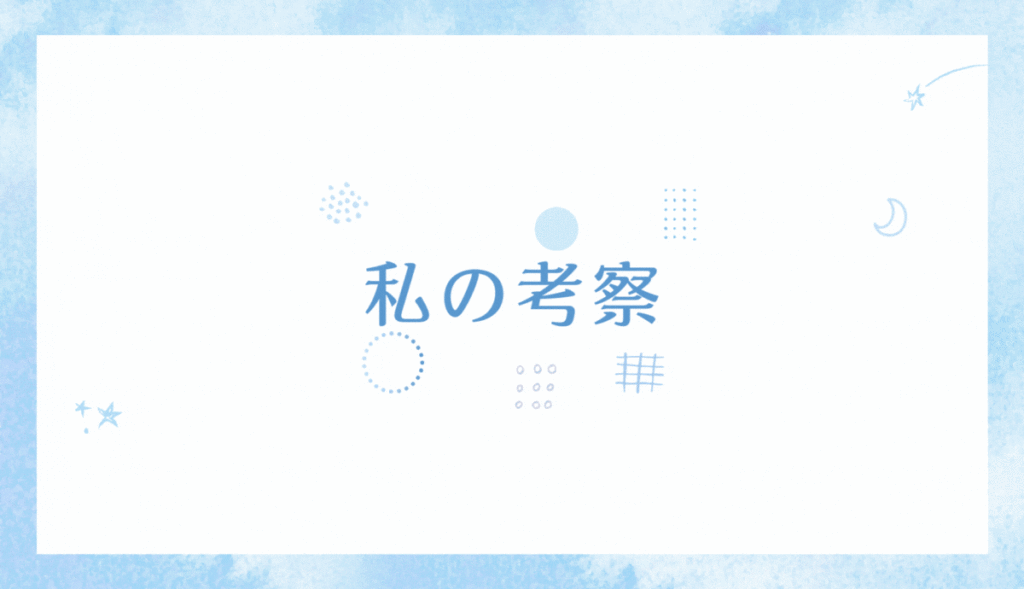
『どんぐりと山猫』は「方便の誤用」の構造を示しているようにも思える。
そこを「誤用」として描いたものなのかは分からない。
この『注文の多い料理店』の「序」に彼自身が「わからない」と言い残していることを踏まえれば、方便を意図的に堕落させたというよりも、本人が方便を誤解していたと見る方が現実味があるのかなとも思える。
「あのぶんしょうは、ずいぶん下手だべ。」と男は下をむいてかなしそうに言いました。一郎はきのどくになって、
「さあ、なかなか、ぶんしょうがうまいようでしたよ。」
と言いますと、男はよろこんで、息をはあはあして、耳のあたりまでまっ赤になり、きもののえりをひろげて、風をからだに入れながら、
「あの字もなかなかうまいか。」とききました。一郎は、おもわず笑いだしながら、へんじしました。
「うまいですね。五年生だってあのくらいには書けないでしょう。」
すると男は、急にまたいやな顔をしました。
「五年生っていうのは、尋常五年生だべ。」その声が、あんまり力なくあわれに聞えましたので、一郎はあわてて言いました。
「いいえ、大学校の五年生ですよ。」
すると、男はまたよろこんで、まるで、顔じゅう口のようにして、にたにたにたにた笑って叫びました。
「あのはがきはわしが書いたのだよ。」
一郎はおかしいのをこらえて、
「ぜんたいあなたはなにですか。」とたずねますと、男は急にまじめになって、
「わしは山ねこさまの馬車別当だよ。」と言いました。
「そんなら、こう言いわたしたらいいでしょう。このなかでいちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなっていないようなのが、いちばんえらいとね。ぼくお説教できいたんです。」
どんぐりたちの争いは、雨ニモマケズで言う「つまらないからやめろ」の争いに該当するんだろうな。けど、どんぐりたちにしてみたら、どれも大事なことなんだろう?えらいかどうか?ってよりも、自分の長所(とんがり、太さ、せいの高さ、まるさ、大きさとか)を良しとしたいんだろう?なのに「えらい」で終息になる、この構図がもう理解できなくて。
表層だけ取られて読むと、皆「えらい」に執着してるけど、主張してることは皆違うじゃない。そこが問題だと思うのに、なんで「えらい」だけで終息させるのかが理解できない。



お世辞言ってるし、結局「えらい」が終着になる。どの道、偉い者が出てくるこの構図よね。たまに、このどんぐりの攻防を教材として盛り込んでいるものを見かけるけど、舞台装置や比喩として軽く使われただけで、中心テーマではないと思うんだよね。というのも、当時賢治は、保坂と一緒に世の中を変えようと約束をしていたから。どんぐりは世の中の比喩じゃないのかと思う。
例えばだけど、めちゃくちゃで、まるでなっていないようなのを雨ニモマケズに出てくる「デクノボー」としようじゃないですか。法華径で言う、「長者窮子の譬え」に例えてみます。
- 法華経「長者窮子の譬え」の本質
- 賢治の「デクノボー」思想
- 「どんぐりと山猫」の馬車別当
- 現代での例え
- 賢治の未熟さに映るところ
① 法華経「長者窮子の譬え」の本質
- 窮子(愚かで劣っているように見える子)=実は仏の子。
- ポイントは「本人が(仏性に)気づいていないこと」。
- 父は方便で“徐々に”気づかせる。 → 最後に「お前は仏の子だ」と気づくのはあくまで本人の内側。
→だから「劣っててもいい」「デクノボーでいい」というのは、他者が言うものじゃない。本人が「自分の中に光がある」と悟るまで待つのが肝。
本人に、こういう教えがあるから「デクノボー」の方が偉いんだ、最後には勝てるんだと教えることも違うでしょ?愚かで劣っているように見えようが、そうでなかろうが、皆に仏性があるということでしょう?
なので「本人に“デクノボーの方が偉い”と教える」のも方便の誤解だし、「劣って見えるものを持ち上げること」が救いになるわけでもないじゃない。
② 賢治の「デクノボー」思想
『雨ニモマケズ』でも出てくるデクノボーという表現。あれは、自分で「デクノボー」と呼ばれることを何とも思わないということが前提で、それを皆に、「デクノボー」と呼ばれても気にするなっていうのは違うと思うんですよ。
だって、気にするかどうかは、他者の問題で自分の問題ではないから。
- 「自分がそう思えること」と「他者にそうラベリングすること」を混同していた可能性がある。
- つまり「俺はデクノボーでいい」なら成立するが、「デクノボーと呼ばれても気にするな」と他人に言うのは、法華経的には方便の誤用と思える。
→それをやると「他者尊重の欠如」になる。
③ 「どんぐりと山猫」の馬車別当
- 馬車別当が「字が下手だ」と言った → 自覚がある。
- そこに「いやいや立派だよ」と言った一郎は、方便を履き違えているのでは?
- 本来なら「そうなの?けど、わたしには、あなたの伝えたかったことが分かったから、ここに来れたよ。文字や文章は上手に書けた方がいいかもしれないけれど、相手に伝わるのが一番だよ。」と事実だけを伝えたらよかったのではないか?だけど、一郎は馬車別当に「字は上手でしたよ」と見え透いた嘘をついている。お世辞にも上手ではなかったし、文章の解読もやっとかっとなのに、馬車別当は喜んでいるから、一見、良いことをしたようにも思える。
→これは法華経的な「方便」じゃなくて、ただのごまかし(承認欲求ゲーム)だ。
「五年生っていうのは、尋常五年生だべ(小学五年生)。」その声が、あんまり力なくあわれに聞えましたので、一郎はあわてて言いました。
「いいえ、大学校の五年生ですよ。」
すると、男はまたよろこんで、まるで、顔じゅう口のようにして、にたにたにたにた笑って叫びました。
「あんまり力なくあわれに聞えましたので」これに翻弄されるんだよね。これを無視すればいいんだよ。そう思っている風に見えるのは、一郎の仏教の空に映っただけのモノに過ぎない。
ここからの「方便」は意味をなさないんだよ。
「方便」を使うのなら、他者尊重が第一にくる。じゃないと成立は絶対にしない。相手の内側にある仏性を信じて待つ、あるいはそれを引き出す方向に作用しないなら、それは方便じゃなくて単なるお世辞・同情・ごまかしにしかならない。これは不変であり普遍だ。



この辺りが、賢治が「方便」についての履き違えを自覚的に描いたものかどうかが分からない。
相手を褒めて認めることの勘違い。
④ 現代での例え
例えばだけど、



私、ちょっとぽっちゃりしてるから~。
って自己卑下。



そんなことないよ!
これと同じ構造じゃない?
- それは相手の仏性を引き出す行為じゃなくて、単なる社交辞令・お世辞。
- 本人は一瞬喜ぶが、根本の劣等感は何も変わらない。
「そんなことないよ!」待ちの自己卑下。面倒くさ。



ペラッペラ。言う方も言う方だしね。こんな人、まず、関わらない。
あと、アドラーの「褒めてはいけません」「叱ってはいけません」の誤解と同じとも思える。褒めてはいけないとも、叱ってはいけないとも、アドラーは言ってないのにね。



全ては子どもに任せて、親は見るだけでいいのね。



言いわけないだろ。
- 褒める/叱る=上から下への評価行為
→「あなたは親(先生)にとって良い子/悪い子」というラベリングにつながる。 - 勇気づけ=横の関係で相手の努力や存在を承認する
→「あなた自身が〇〇というところで頑張れた姿が良かった」「失敗したかもしれないけど、挑戦できてた」「こういう工夫がすごい!」という事実を伝える。
という対比だから。
アドラーは「褒めるな・叱るな」と禁止したんじゃなくて、褒めや叱りを“評価”のツールにするなと言ってるだけ。
だから、親は見るだけでいいだなんて子育て放棄と一緒だって。
⑤ 賢治の未熟さに映るところ
- 法華経は「本人の悟りに委ねる」教え。
- 賢治は「相手を救わなきゃ」「救うために、相手のために良いことを言わなきゃ」と焦って、他者に“悟り”を与えようとした。
- その結果、「方便=嘘も方便」の安っぽい解釈に堕ちてしまった。
つまり、賢治は「方便」を誤解していたのでは?
本人が気づくべき仏性を、外から、



君は尊い。
字は上手。
小学生じゃなくて、大学生レベル。
とか言うのは、むしろ仏教の精神から外れていると思える。
だって仏教での「嘘も方便」っていうのは、相手のためを思って使う言葉であり、自分のために言う意味合いで使われてないと思うから。一郎が馬車別当に伝えたのは、どう見てもお世辞。あれが本人のためになると思います?全然思わない。
だって、あれで満足したら本人伸びないし、喜んでるとしたら、馬車別当は他者承認を抱えたまま、満たされないまま生きることになる。それを支持してることになるし、人の人生に介入しすぎだって。ロジックがおかしい。



まぁ、賢治が意図的にあれを描いたのであれば、誤解とは言えないんだけどね。つまるところ、一郎が法華経を理解していないという前提で書かれたということ。(けど、こちらの可能性は低そうだ…)賢治は理解しているけど、あえて、一郎が理解していない前提としたということだ。
ややこしいけど、分かるかな。
馬車別当への、



さあ、なかなか、ぶんしょうがうまいようでしたよ。
という文字を、わたしの脳内で文字お越ししてみると、



あなたはデクノボーですけど、それでいいではないですか。
こう見える。
このような「デクノボー」的発言は、自分が“自分に対して”言うなら本物になるけど、他人に使うと「相手を馬鹿にしている」構造になる。だから、馬車別当の場面は“方便の堕落”をそのまま体現していると思える。
「あのはがきはわしが書いたのだよ。」
一郎はおかしいのをこらえて、
おかしいのをこらえてってあるけど、ここはあまり気にしなくてもいいのではないかな。「方便」を相手のために使ったと思っているのなら、



あ!喜んでる!
って単純に思った可能性も高いしね。想像だよ。
わたしがなぜ、こんな風に思うかと言うと、宮沢賢治をめぐる一連の行動については、彼の実生活と作品の双方から、誤解や未熟さがにじみ出ていると見ることができるからだ。
まず、実生活の例として父への改宗強要が挙げられる。本来、法華経の立場では「各人が信じるかどうかを待つ」ことが重んじられるはずだ。ところが賢治は強引に国柱会への入信を勧めてるし、その結果、父の拒否を招き失敗している。
また、農民への音楽活動や教育活動も同じ構造を持っている。賢治は農民の生活改善のために音楽活動や科学技術を中心に広めたけど、その姿勢は「救わねばならぬ」という他者依存的な誤用の気配が見える。
こうした行動の延長線上に、作品冒頭の自己告白がある。『注文の多い料理店』序文に「わたくしにも、なんのことだか、わけのわからないところもあるでしょうが、そんなところは、わたくしにもまた、わけがわからないのです」と記されているけれど、これは単なる免責表現ではなく、むしろ「自分が仏教を完全に会得していない」という自覚の表明と読むことができる。方便の概念を物語に書き込んでいながら、その理解があやふやで誤解混じりのまま作品化されてしまった可能性は否定できないのでは?という個人的見解。



未熟な理解のまま、それが行動にも作品にも表れてしまった――という一つの見解にすぎないので、お気になさらずどうぞ。
『どんぐりと山猫』から何を学ぶのか?
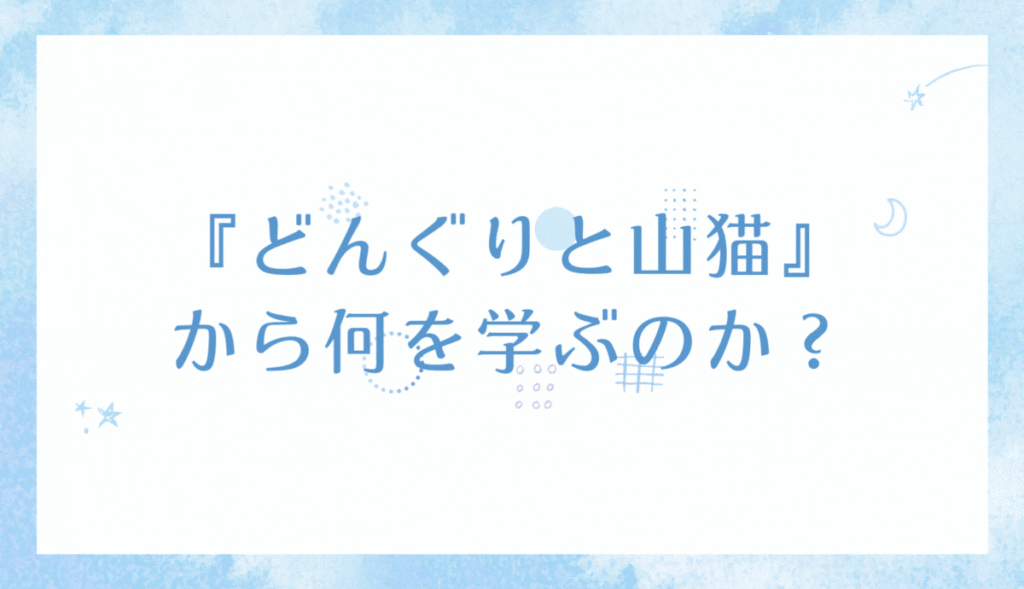
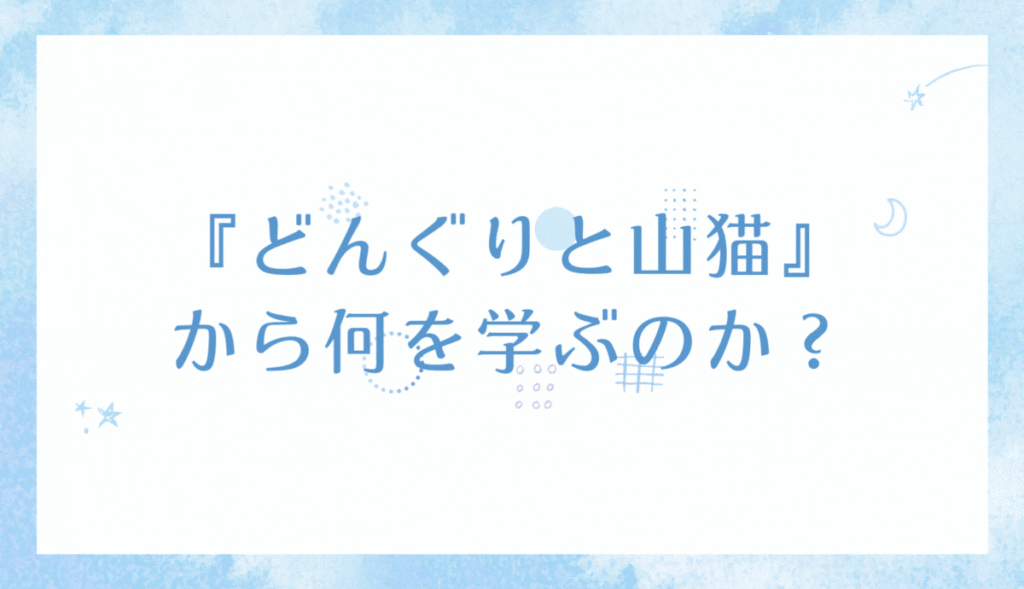
- 仏教理解の難しさ
- 現代への示唆
① 仏教理解の難しさ
賢治自身、「序」でわざわざ「わけがわからないところもある」と書き残している。
これは単なる免責ではなく、自分が方便思想を完全には理解できなかった自覚の表明とも読める。会得できない葛藤が、無意識に物語の構造に投影されている。
② 現代への示唆
作中で一郎は、馬車別当に「うまいですね。五年生だってあのくらいには書けないでしょう。」などとお世辞を言っている。
それから、山猫の意見に「それは変(へん)」と反論するけれど、理由を説明しないために誤解を深めてしまっている。
この構図は、言葉の誤用や未熟さが人間関係を壊すという普遍的な警告になっているようにも読める。
現代でも「そんなことないよ」といった安易なお世辞や、理由なき否定は同じ危険をはらむ。
危険というのは、その安易なお世辞を相手のために言っているという誤解、理由なき否定とは、自分だけが唯一の正しさだと思う危険性、そういうことだ。
展望台から見える景色を、頂上と思うなかれ。
って書いたことあるんだけど、まさにそれで、自分の考え方に自信を持つのはいいけれど、それだけが唯一の正解とは限らないから。生きてきた人生も違えば、接してきた人や環境も違う。同じ展望台にいるとは限らないんだよね。
頂上から見ている人もいれば、まだ道半ばの展望台から景色を見ている人もいる。この理解は必要かもしれない。
賢治の未熟さはそのまま、私たちへの示唆になっているのかもしれない。
まとめ
宮沢賢治の世界というのは、未熟さの理解として見ると、考えさせられるものがたくさんあると思う。
自分が正しいと思うことを、他者も同じ目線で正しいと感じるとは限らない。そのズレは現代にも通じる課題であって、賢治はその矛盾の中で「善」として生きようとする苦しさを体現していたように思える。
自身が信じる「善」にズレがあると、見ている世界も歪んで見える。
そのズレに気付けるか否かが人生の分かれ目でもあるし、他者理解の入り口にもなる。
つまり、彼の作品は悟りの完成ではなく、理解と誤解のあいだでもがき続けた記録だと読める。その姿は、私たち自身の矛盾や迷いを映し出す鏡にもなるし、今も考えさせられる。



わたしはね。あなたはどう読んだ?

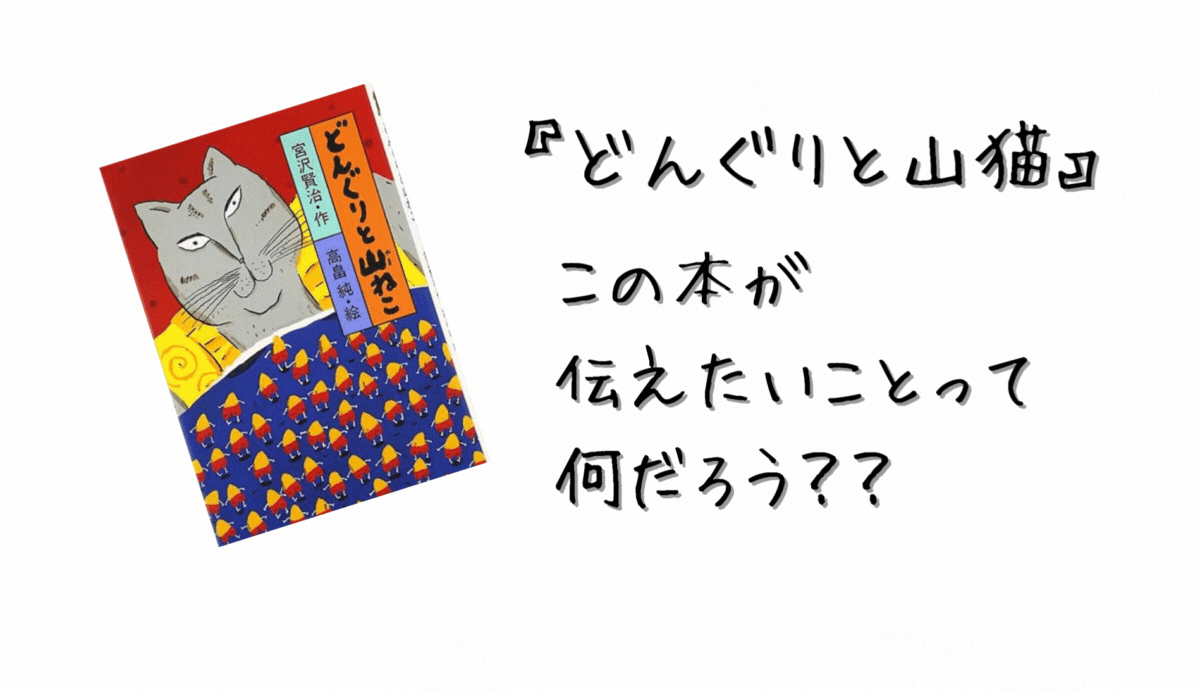
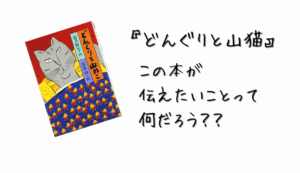
コメント