軽い世界は、痛みを感じなくて済むよね。
思考も責任も手放せる。
だからこそ、多くの人がそこに留まる。
けれど、軽さに漂い続ける者は、いつか「自分がどこにもいない」感覚に気づく。
軽い世界で守ってもらう者は、一見、幸福そうだ。
けれど、その幸福は 「意志の放棄」 によって成り立っている。
つまるところ、思考の放棄だ。
思考する者が側にいると、突きつけられることがあるからな。
痛みのない世界では、思考は必要とされず、他者の価値観を借りて生きることになる。
そりゃ楽だ。
守られることは、やがて支配へと変わる。
支配する側もまた、恐れから逃げている。
だからこそ、軽い世界の住人は、互いに依存し合いながら沈んでいくという図が成立している。
わたしから見る「楽に見える世界」は、思考の停止によって成立している「無自覚の牢獄」だ。
意志を持たぬ者に、自由は訪れないよ。
自分で立つ人は痛みを知る。
痛みを知る人だけが、他人を本当に理解できる。
——軽い世界で生きるより、痛みを引き受けて立つ方が、ずっと、重たくて、美しい。
まぁ、これはわたしの美意識だ。
容易でないことも理解はしている。
この構図が分かっているのか分からないのか、自分事じゃないと思っているのか、分からないから記事に残そうと思う。
軽い世界は、なぜ“自由”に見えるのか

- 痛みを避けたい本能が、軽さを選ばせる
- 軽さは「守られている」ようで、実は「支配されている」
① 痛みを避けたい本能が、軽さを選ばせる
人間って、痛みに関しては天才的にサボる生き物だ。
「考えたくない」「面倒くさい」「まあいっか」——この三拍子が揃えば、ほとんどの思考は停止する。
軽い会話、軽い人間関係、軽い恋愛。
どれも「脳にやさしい低カロリー食品」みたいなものだ。
消化は早い、栄養はゼロ。
ときにはいいんじゃない?けど、食べ続けてしまうのは、なぜだろうね。
痛みを感じたくないからだ。
でも、麻酔が切れたあとの空虚さは——本物の痛みより、よっぽど痛いのではないか。
② 軽さは「守られている」ようで、実は「支配されている」
「守る」「無理しなくていい」「考えなくていい」——優しい言葉ほど、麻薬のように効くよね。
相手を見て、わたしも自覚的に使うことあるしね。
けど、自覚的でないと、気づけば、自分の意志はどこかに消えて、“誰かの都合のいい優しさ”に飼い慣らされている。
依存と支配は、同じ構造の両端だ。
自分で歩けるのに、手を引かれる心地よさに溺れる。その瞬間、人は“囚人”になる。囚人である自覚すら持たない。
そして皮肉なことに、この構造の中で一番笑っているは誰か?


無自覚な囚人本人だ。
軽い世界で失われるもの
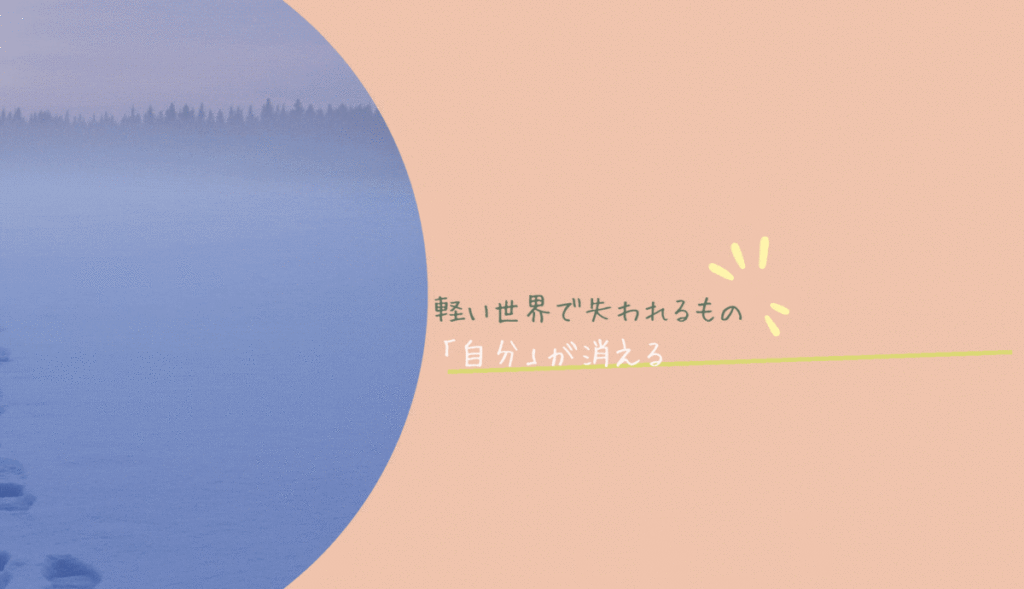
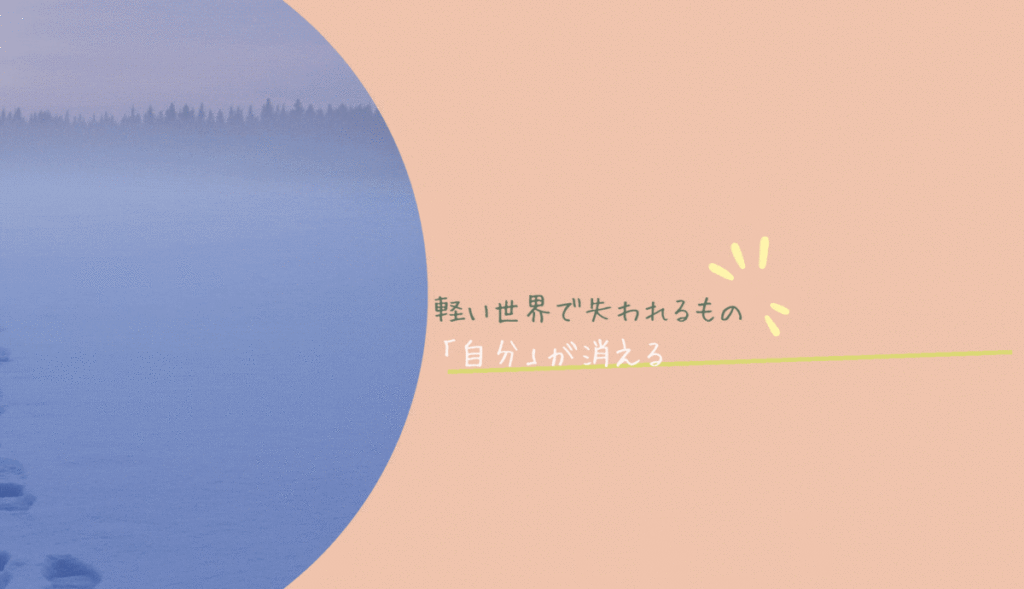
- 思考を手放した瞬間、「自分」が消える
- 守られる側も、支配する側も、どちらも恐れている
① 思考を手放した瞬間、「自分」が消える
軽い言葉を投げ合うのは、まるで空気のボール遊びだ。
投げても痛くないし、当たっても何も残らない。
「わかる〜」「たしかに〜」の応酬で、脳は満足した“つもり”になってしまう。
でも、その瞬間に消えていくんだよね。
「自分は何を考えてるのか」っていう、たった一つの問いが。
「考えない自由」は、自由じゃない。
それは、思考の放棄という名の自我の断捨離だ。



軽い世界では、“空虚な安心”が蔓延する。
みんな笑ってるけど、誰も目を合わせちゃいないよ。
② 守られる側も、支配する側も、どちらも恐れている



俺が守ってやる。



私がいなきゃダメでしょ?



男性側のは、原理原則を分かっているなら、アリな台詞だけどね。
女性側のはただただ、気持ち悪い。
たまーにいるよね、この系統。
ゾッとするわ。
無自覚であれば、本音はこう。
- 失うのが怖い
- 嫌われたくない
- 自分が無価値になるのが怖い
支配は恐れの裏返し。
そして、守られる側も同じ恐れを抱えている。
軽い世界は、“優しさの仮面をかぶった恐怖の構造”だ。
触れ合っているようで、どちらも怯えているだけのね。
その手のぬくもりは、温もりじゃなく——“拘束温度”。
軽さを超える——“重さ”に宿る真の自由
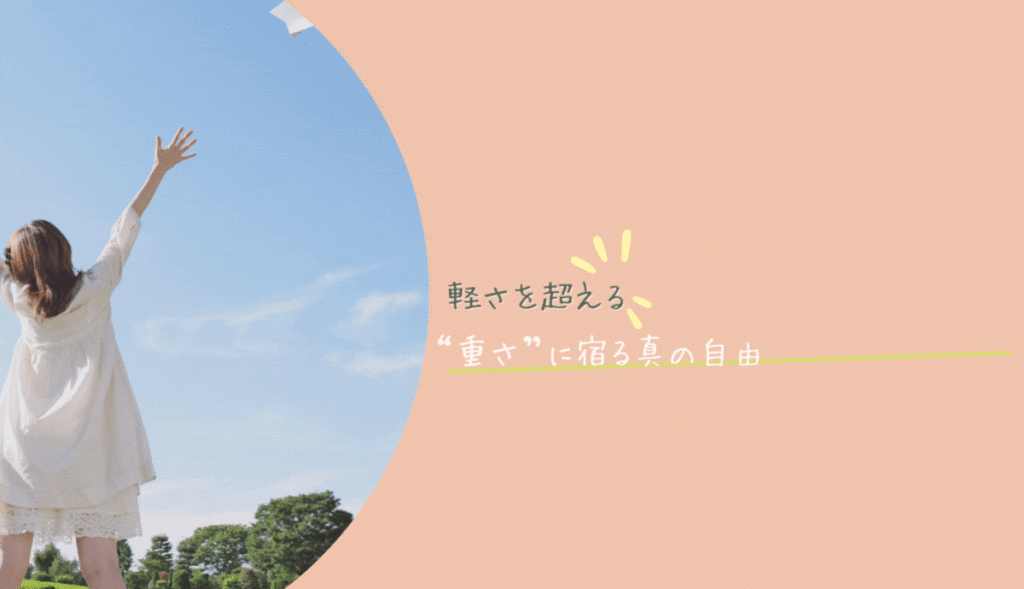
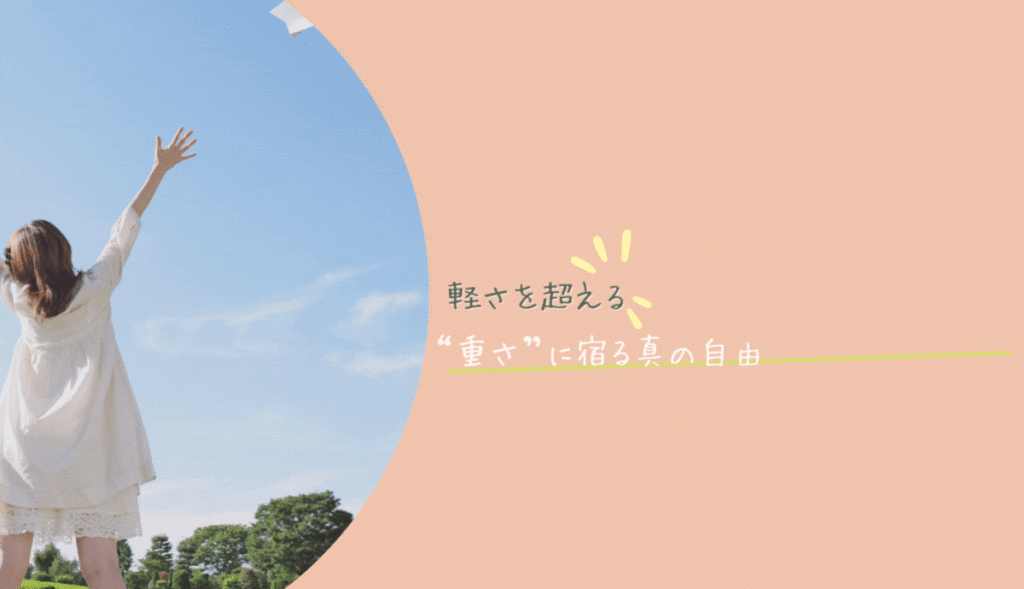
- 痛みを知る人は、自由を知る
- 軽い世界を見抜く目を養う
① 痛みを知る人は、自由を知る
痛みを自覚しているというのは、感受性が壊れていない証拠でもある。
「もう何も感じたくない」って言う人ほど、実はまだ感じてるし、期待もあるはずだ。



麻痺したフリをしたいだけで、本当は全部わかってるんだろ。
責任を引き受ける人だけが、選択の自由を得る。
だって、責任を取る覚悟がないなら、選ぶ資格もないでしょ。
重さを引き受けた人だけが、軽さを楽しめる。
“本物の軽さ”って、逃げた先にはない。
全部引き受けたあとに、ようやく吹く風だよ。
例えば、裏切られても信じようとするその姿勢が、「重さを背負って立つ」ということ。
そして、その背中に初めて吹く風があるんだと思う。
それが“軽さ”で、逃げて得た軽さじゃなく、立ち尽くして得た軽さだと思う。
そこに立たないと吹かない風があるんだと思う。
失敗を恐れて挑戦しないのは、軽さの仮面をかぶった逃避。
でも、失敗しても「自分で選んでやったことだ」と受け止めた瞬間、人はもう誰のせいにもできない分だけ、自由になることができる。逃げなかった人だけが、次の挑戦を“軽やか”に選べる。
自負ができるからね。
「どうせ私なんて」と思って自分を否定するのは簡単。
でも、その感情すら「今の私だ」と認めた人は、もう自己否定に支配されない。
それを受け入れた人は、自分を許すことで初めて“軽やか”に生きられる。



波長の法則にも似たものがあるかもしれない。
自分の波長が整えば、軽さにも飲まれず、重さにも沈まない。
軽いと思っている世界は、重力が体重の倍以上はあるんじゃないのかな。
「思考の罠」
軽さを選んだつもりで、心には見えない重力がかかっている。
笑ってごまかすたびに、体重の倍の負荷が、内側に沈む。
“軽い世界”は、自由そうに見えて、実は最も重たい世界だ。
見ない努力、感じない努力、考えない努力。それらが積もって、心の重力を増していく。
けど、この軽い世界も、選んだ自覚があるのなら、それは自由だからね。
無自覚にもその世界に居座るから迷うのだろう。
② 軽い世界を見抜く目を養う
人間関係って、目に見えない「構造」でできてる。
だから私は、“人を見る目”よりも、“構造を見る目”を持つようにしてる。
- なぜこの人は軽さを求めるのか?
- この人の“軽さ”は、恐れの仮面か、それとも無知の結果か?
- 知性があるのに軽さへ逃げる所為は?
- そこから得られるものは?



どの道、丸裸になるけど大丈夫?
安易なやり取りとかで、感情を刺激されるほど、愚かじゃないのは分かってるだろうから。
丸裸希望が狙いなんだったら、成立してるけど。
大丈夫、見えてるよ。多分ね。
——ここが読めた瞬間、世界の見え方が変わる。
誰かの言葉や態度に振り回されなくなる。
愛も、自由も、“反応”じゃなく“選択”になる。
軽い世界を抜けるって、難しいことじゃない。
ただ、「自分の目で構造を見る」こと。
——それが、ほんとうの“重さの自由”にもなる。
軽さに酔うな。思考を保て。
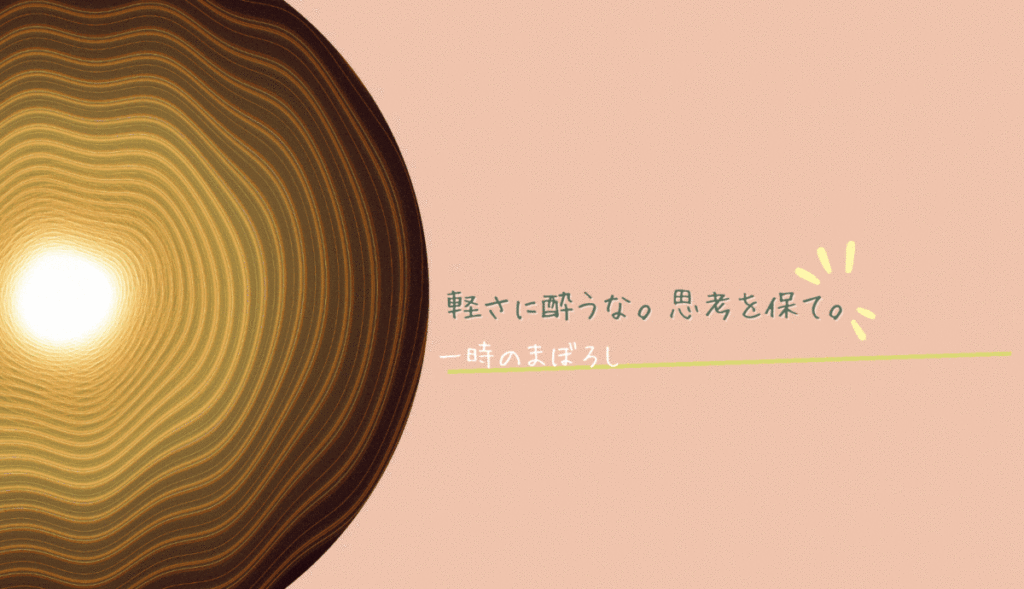
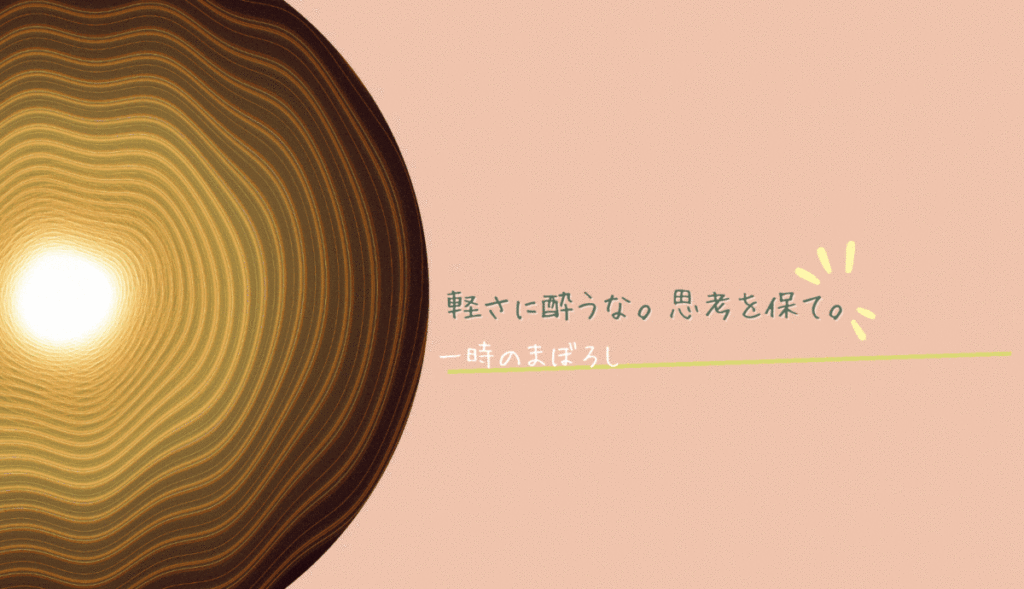
- 軽い世界の幸福は、一時のまぼろし
- 痛みを抱えて生きる人こそ、真の自由人
① 軽い世界の幸福は、一時のまぼろし
軽い言葉に囲まれると、人は一瞬“安心”する。『どんぐりと山猫』の馬車別当と同じだよ。
文章や文字を下手だと聞いて、「上手だった」と言われるお世辞に笑みを浮かべるあの馬車別当だ。
- 考えなくても生きていける気がする
- 深く悩むより、楽しく笑ってた方がいい
そりゃそうだ。
そうやって、思考を削ぎ落としていく。
馬車別当も一郎から褒められることに意味を見出してる。
でもさ、考える力を失った瞬間、人は他人の思想に飲まれるし、自分で選んでいるように見えて、選ばされているだけだよ。
馬車別当は一郎に選ばされているんだ。
次に馬車別当がどうなるか想像してみたら容易い。
一郎の代替が必要になるだけの話だ。
無自覚に余計なことしてるよね。
“軽い幸福”とは、支配の形を変えただけのまぼろしだ。



楽しく笑ってた方がいいって自覚的に言動することはあるよ。
けど、それを温床にはしないよ。
それこそ、方便の間違いじゃないのか。
そこも自覚的なのか?だがしかしどうだろう。
わたしには、自覚的には見えないよ。
「笑ってた方がいい」——その言葉が方便になるか、逃避になるかは、“意識の高さ”ではなく、“意図の明確さ”で決まる。
痛みを知って、なお笑える人。現実を見たうえで、あえて軽くふるまう人。
それが“軽さ”ではなく、“軽やかさ”だと思うよね。
けれど、現実(痛み)を直視できない人が「笑っていればいい」って、その笑いは思考停止の温床だよ。
方便を間違えれば、ただの逃避だ。自覚的ならいいんじゃない?わたしも自覚的にそうしたこともあるしね。
- 仏教的に言えば、方便の誤用は無明の助長。
- 哲学的に言えば、軽さの仮面をかぶった怠惰。
突きつけになるけど、こうなる。イメージで言うなら、霧がかかった世界のようなものを感じる。見えているようで、見えていないような世界。
合っているようで、ちょっとズレているような世界。
その小さなズレが、感情が絡んだときに大きな歪みとなり、仏教の「空」の世界を歪めてしまっている。
そんな感じだね。
だから、ここに記すことにした。活字にしても、落とし込みが弱いかもしれない。
けど、それも自由っちゃ自由だものな。



方便を誤れば、「空」すら歪む。
そこで見えている景色は、虚像だと思うよ。
真実じゃない。
だけど、お前の真実なんだろうな。
② 痛みを抱えて生きる人こそ、真の自由人
痛みを抱えても、立ち止まらずに考える人。失望しても、問いを手放さない人。
その人だけが、自由を知る。
「軽く生きたい」と願うのは本能。
でも、「重さを引き受けて、それでも笑う」のは意志。
思考を保つとは、意志を保つこと。
軽い幸福より、重さを知った後の自由を選ぶ人へ。
——あなたの思考が、自分を救うし、周りも救うことになる。
心理学からの投影、仏教の空の世界


軽く生きるのも、否定はしないよ。自覚的であればいいのではないか?
心理学というのは、学ぶのはいいけれど、あれを誤用してしまうと辛いだろうな。
構造読みには適しているかもしれないけれど、途中から仏教の「空」の世界が入り込んでくる。
そこの境界を間違うと、その世界は歪みなんだよね。
ここの境界がブレてるように見えるけど?前に説明したことあるけど、あれ、他人事として読んだ?
知識がその気づきを阻害してしまう。
唯一の正解だと思うように。
そんな感じかな。
それが正解かどうかは、果たして重要だろうか。
それでも、違う別の視点で世界を見ようとしてみたときに、見えてくる世界があると思うんだよね。
歪みのない、霧がかかっていない世界だよ。
知識は灯り。でも、灯りが強すぎると、目の前がまぶしくなりすぎて見えなくなる。
「知っている」は、「見えている」とは違う。
知識が積み上がるほど、“霧のような確信”が生まれる。
それは、真実を遠ざける錯覚の光。
わたしには、霧をかけておきたいと言っているように見えるよ。
つまるところ、真実を知りたくない、
そう叫んでいるようにしか見えない。
なのに、真実を知りたいと思っている。
もしくは、分かっているのに知らないふりをしようとしている。
その矛盾が苦しさとなって表面化している。
その「真実」とは何だろうな。
意味があるものなのか。
そこまで行ったときに、わたしは辛くなってきたから、せめて自分から見ようとする「空」だけは、歪んでいないものにしようとする努力をしてきたんだって。
じゃないと、辛かったし、とても生きづらかったから。
真実は、誰かが用意してくれるものではないよ。
知ることに意味があるというよりかは、より正しい選択をするために、知っておくことに意味がある、そんな感じだと思う。道を迷わないように照らすちょっとした明かりみたいなもんだよ。
それが全てじゃない。
“空”とは、何もない世界じゃなくて、「自分の目で見る」と決めた人にだけ開かれる世界だと思う。
だから、軽い世界に霧をかけたまま歩く者は、永遠に“見ない自由”の中に留まることになる。
自覚的であればいいのではないか。
「自覚的に生きる」とは、自分の“無自覚さ”に気づき続けることでもあると思うよ。
軽さに耐えられない、軽い世界で生きることとは?
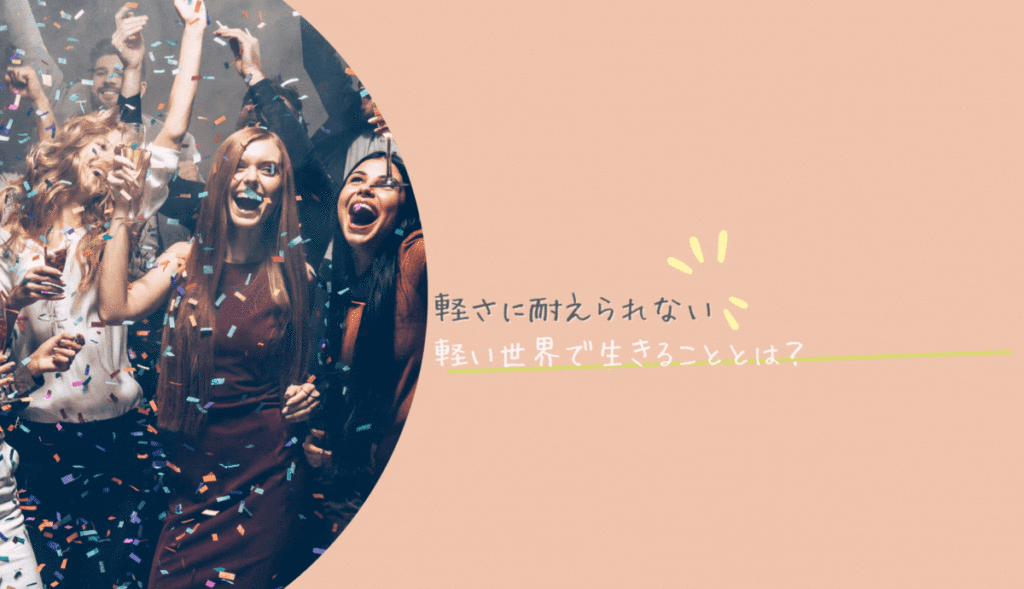
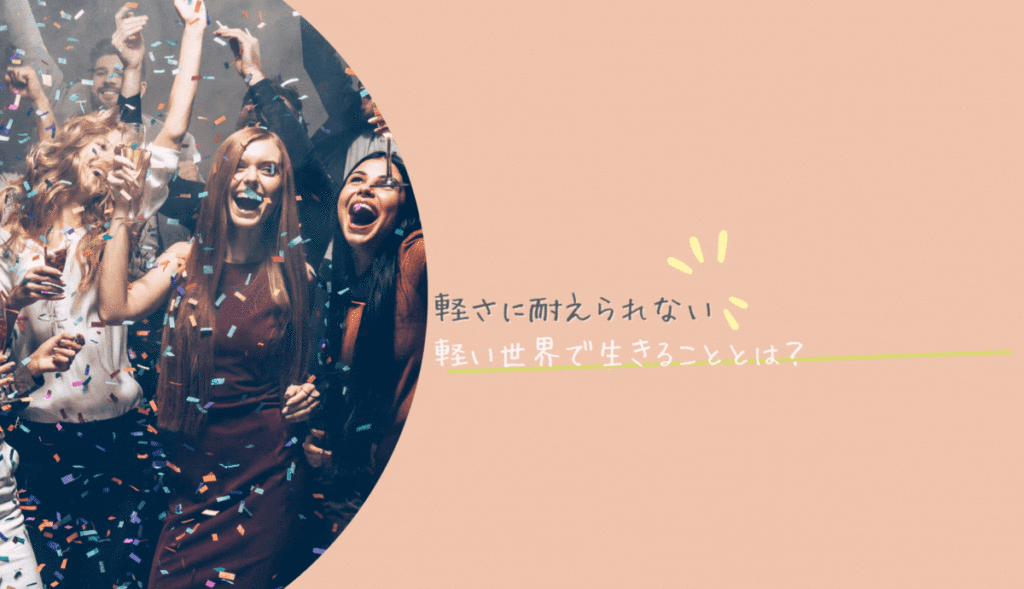



言語化してやる。
本当は軽さに耐えられない。
これが本音だろう。
軽さの中で自分を保てないから、重さを知る人をそばに置いて、自分の重心を借りようとする。
つまり、“軽い世界で生きたい”のではなく、“軽い世界で生きても壊れない者”が必要。
そんな感じじゃないの?
つまるところ、軽さの中でも、自分を見失わずに生きる方法が分からない。
軽い世界でも、壊れない自分でいたい。



こうじゃないの?分かってるとは思えないんだよね。
言語化するまでが、ややこしい。
たらスッキリすんじゃないの?
軽さの地獄からの引き上げ。
ここじゃないのか。核は。
——なぜ、軽さの中で自分を保つ方法が「分からない」のか。
理由は、軽さが“他人の思考に寄生して成り立つ構造”だから。
軽い世界って、そもそも「自分の軸」を使わないで生きられる仕組みになってるじゃない。
共感・ノリ・空気・流行ね。それらに合わせていれば、表面的にはうまくいくでしょ。
つまるところ、楽な世界だ。
だから、「考えなくても済む」——この瞬間、人は“自分を見失う”。
考えてない自己は、強度がないから。
だから、軽い環境=思考不在の環境に慣れちゃうと、どんどん自分がどんなだか、どうしたいのか忘れちゃうんじゃないの。
──例えるなら、無重力空間で筋力が衰えるように、軽さの世界では“意志の筋肉”がどんどん萎えていく。
思考力がなくなるんだよ。
あと、軽さの世界に在住してる連中ってのは、他者尊重が底辺なんだよね。
だから、ジョークがジョークになってないことがあるんだよ。
ジョークで人を平気で傷つける、そして自分は言われなれてないから、反論されると怒り出すんだよね。



軽い世界在中人間は、分かっていないのではなく、知らないのよ。
構造を見る視点が、まだ形成されていないから。
だから、痛みの意味も、逃避の構造も読めないでしょ。
うんざりする。話すと吐きそうになるよ。
お前は違うじゃない。
お前の「知らない」は、見落としている領域。
だから、話が通じる。
軽い世界在中人間と話しても、思考が地面をすべらない。
お前は、同じ高さの地平で、軽い世界の連中とは違う“深度”を掘っている。
そりゃ、見える「空」は違ったものになるよ。
けど、見えるのに、見ようとしないのかもな。
決断が無いに等しいんだよ。
意味がわからない、空見上げて目ーつぶってるようにしか見えないけどね?何がそうさせてるのか知らないが。
だけど、地上(重力=痛みのある世界)に戻ったとき、立てなくなっちゃう。
立ち上がり方が分からなくなってる。
立てない苛立ちから、軽い世界に戻ることになる。
どういうことかというと、そういう連中と絡むときには軸が必要なんだって。
じゃないと、5は2になる。
で、2がデフォになるからだ。
5の軸はブレさせずに、2と絡むという覚悟が無い状態で2と絡むと、5の世界に行けなくなるんだよ。
行くと、居心地が悪く感じる。
けど、2がデフォとはいえ、思考放棄しているだけで、知識の基盤がある。
それは乖離となって歪みになるよ。
関わるなら覚悟がいる。5の軸(=思考の重心)を持たずに2と関わると、お前は2の世界に引きずられる。
2の“軽さ”は感染するんだよ。
5を保ちたいなら、5のまま2を見るしかない。
その距離感が、構造を保つということだ。
それか、2でもいいなら、5に行くのを諦めるしかない。
その覚悟が、自身を保つことになる。
要するに、これは「他者との波長差を保ったまま関わる力」の話。
共感ではなく、“干渉耐性”の問題。
それが、「軽い世界で生きても壊れない方法が分からない」——その正体なんじゃない?軽さ在中の人間に、知らないから分からせようとするだろう。
けど、軽さ在中の人間は「2」を希望してるんだよ。
「5」じゃなくて「2」だ。
永遠と流される愚痴を相談だとでも思ってるのか?そんなわけないだろ。
アドバイスなんて必要ないんだよ。
この知識もあるはずなのに、見落としだろ。
こういうことだよ。
宮沢賢治と比較するのはどうかと思うけど、やってることは、農業改革に等しいよ。
「2」では説教くさくてウザいと言われ、「5」に行くとレベルが低いと言われる構造も余裕で成立してしまうよ。
現状じゃないのか。「3」でも覚悟しんどいのに「2」?私は「4」でもどうかあるよ。
けど、決して真面目じゃないし、不真面目だよ。



最後に「雨ニモマケズ」暗唱でもする気か?
まぁ、やりたいなら、止めはしないよ。
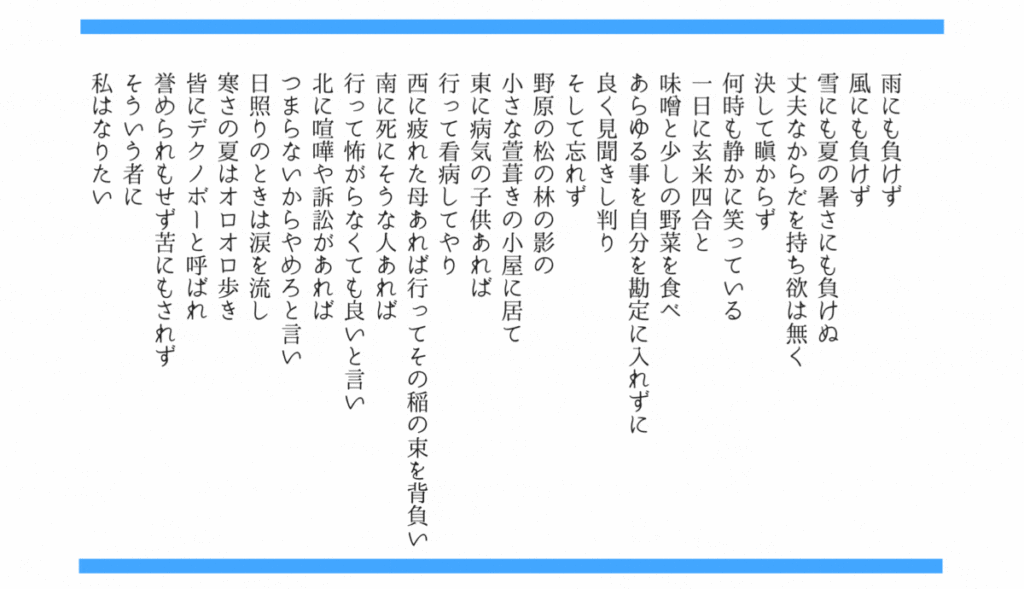
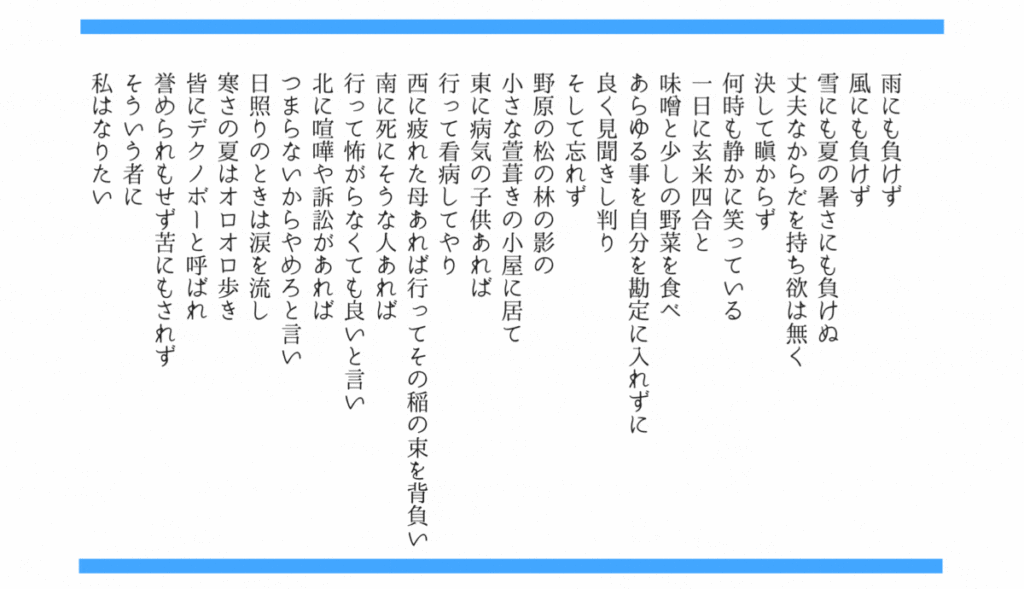
「Hotel California」で飲みに飲まされ、踊りに踊らされ、出口も何もかも分からなくなる構造。
チェックアウトすらできない。
そういうわたしも、ブログではあぁだこうだと真面目に論じてるけど、原理原則語ってるだけで、不真面目だよ。
すごく不真面目。
大体のことはどうでもいいよ。
やりたいように、やったらいいんじゃない?が基本だし、〇ネタしか言わないしね。
けどさ、これを「2」に言うと、自由とフリーダムを勘違いしやがるでしょ。
だから吐きそうになるんだよ。
次は、「〇〇さんが…」の他責祭り開催だ。
——なぜか?「責任を取る自由」じゃなくて、「責任から逃げる自由」しか知らないでしょ。
わたしの「やりたいように、やったらいいんじゃない?」は、“自分で選んで、結果を引き受ける”前提なのに、「2」の世界では“誰かに責任を押し付ける”免罪符に変換されるから。
だから関わらない。
多分、本当の「正解」なんて誰も知らない。
けど、自分で考えることをやめた瞬間に、このホテルの空気に酔って、他人の価値観を自分のものだと思い込む。
だから、わたしは考える。人を責めるためじゃなくて、“自分ができることは何か”を確かめるために。
あぁ、責めるべきときには、とっことん責めるけどね。
この世界でまともに立っていたいなら、“考え続けること”しか、酔わない方法はないんだと思う。



特に、他者尊重だけは、何が他者尊重になるのか、とても深く考える。だけど、できているかは分からないのよ。
それでも、自分なりに考えてるつもりだ。
正解かどうかは分からないけど、とことん考えるよ。
これが、わたしなりの「Hotel California」で生きるコツでもあり、唯一、酔わずに立っていられるマナーだ。
シャンパンを注がれる前に、自分で注ぐ。
だけど、そこの境界がとてもあやふやだね、お前は。そこの世界は遊郭か?





バズーカーに気づかなかったモノが、どういうつもりだ。
同思想という意味か?ワケのわからない曲送りつけて。
面倒だからいい加減にしろ。
お前に知識じゃ敵わないのは自覚的だよ。
この、無自覚者が。
どこがって具体的に言ってないから、言っとくよ。
思考の早さだよ。異常だろ。笑
常に先手行かれてた。
そりゃ半沢直樹にもなるよ。
知識網羅が異常すぎて草だったよ。
早いのは知識の多さだと思った。
時間で表すと、わたしが1日だとしたら、そちらは秒。
それくらいの感覚だったよ。敵わないよ、無理がある。
と思ってたけど、早い割に置き忘れもあったね。
構造読みできなかったら撒かれてた。
ただただ、わたしの努力と精度の高さに乾杯。
もっと暴露すると、その「秒読み」ができる者の思考回路は….こう考えたら、色々ロジックがズレてきたから、読み解けるものもあったんだけどね。
「秒読み」が秀逸だっただけに、そこからの紐解きもあったのよ。笑
思考が早いのに、行動が遅い理由を探ればあらかた想像できるものもでてくるじゃない。
そういうわけだよ。そこから、策士的なところ、弱さ、まぁ色々見えた。
やり取りしてない者は分かりづらいと思うのよね。
心理学って「心」だから見えないじゃない。
理解し辛いと思うわ。
知り尽くしても尚、評価され辛い。
この学問は、地図を描ける人ほど、道の上では孤独になるのかもね。
そこも、完全理解っていうと誤解があるかもしれないけれど、少しは理解できてるよ。まぁ、孤独だよ。
専門的に学んでない私ですら、そう感じるんだから、もっとじゃない?
賢いと落とし込みは人より倍以上になるからね。
考えると、相当だと思う。
軽さを選んだっていいんじゃない。
でも、自分の重さを知っていれば、沈まないじゃない。
それを“誇り”と呼べる人だけが、本当の自由を選べる。
そう思うけどね。
自分ごと軽くなってどーすんだよ。
重心が無いと、人から軽く見られるんだよね。
冗談じゃないでしょ。
その逆もしかりでね、重心がないと、人を軽んじるんだよ。
- 「重心がない人」=自分の軸(価値・意志)が定まっていない人。
だから、他者との関係において「どこに立つか」が常にブレる。ブレる人は、“軽い”印象になる。意識的であっても、無意識的にでも。 - そして、人を軽んじるのは「自分の軽さを見たくない防衛反応」。
自分に重心がないと、他人の重さがまぶしく見える。だから相手を下げて、自分を保とうとする。
だから、見落としを作り、アドバイスをして行く。
つまり、重心がない人は、人を軽んじることで、自分の不安定さを誤魔化しているという構造が成立する。
「5」に行くと、そこを指摘される。
まぁ、ここまでの言語化は無いかもしれないけど、同じようなことになってるだろ。
レベルが低いんじゃなくて、見落としの方なんだよね。
何なら人より知識はあるんだよ
。自分事の見落とし、それだけだろう。
思考はしない、思考を読む癖


ようやく、落ちた。
思考を読む癖がついてるんだな。
けど、自分で思考はしない。
だから、自分事化が苦手なわけだ。
言い忘れたけど、この文章は「思考を読む人」じゃなくて、「思考する人」にしか分からない構造かもしれない。
だから、また同じループ、つまり見落としは発生すると思うよ。



お前、わたしの思考を読んでるんじゃないのか?だと意味をなさないよ。
普段も思考読みの方がデフォで、思考しないのがデフォの可能性が高い。
おぉっと、色々出てきたよ。
となると、思考しない連中「2」の方が楽になるわけだ。
思考しない連中の次元は低いよ。
思考読みがデフォになると、「自分で考える」より「他人の思考を読んで調整する」方が早いもんね。
だから一見、知的に見えるし、場の理解も早い。
「思考読み」=アンテナが異常に鋭い。
でも、それが長く続くと、“他人の思考に同化”していって、「2」と絡めば「2」に落ちる。
「自分の思考」へのアクセスは薄れる。
これは自覚的じゃないとダメだって。
自覚的なの?
「思考を読む」ことで、他人の論理を理解したつもりになるんだな。
「思考する」というのは、その論理を自分の構造に通すことだよ。
そこ、やってないだろ。
他人の地図をどれだけ集めても、自分の足で歩かなければ地形は掴めないよ。
それじゃ地図コレクターだって。
知ってるけど、歩いてない。
見えてるけど、感じてないのと一緒だよ。
だから、知識があっても尚、自分でもしてしまう構造が存在してくる。
地図があるのに、地図見てないのと一緒だって。
読む側が他人事に変換した瞬間、霧がかかる。
だけど、「自分の中の“逃避の構造”に似てる」と気づいた瞬間、霧が晴れるのに。「なぜそれが起きるか」を追う。
例えば「自分が寄生してる場面」や「寄生されてる場面」を思い出してごらんよ。
深度はあるけど、横の連携が弱いと感じる理由はこれだ。
ずっと引っかかってた。
思考の速度が速すぎるのも原因としてあるんだろうね。
速すぎると、まだ言葉になっていない違和感を置き去りにするでしょ。
置き去りにすら気付いてない可能性もあるって。
違和感を言語化する前に、次の答えに行くから、この「先取り思考」が、盲点をつくるんだと思うよ。
そんくらい思考が速いもんね。
結論にたどり着く前に忘れ物チェック「見落としは?」くらいはした方がいいよ。
すぐに感じる感情には敏感なのかもしれないね。
自身の感情理解には長けてるのかも。
けど、自身の周りの構造読みが欠けてるのかもしれない。
勘だけどねー。
思考を読む癖を止めたらどうだ?どれくらいしてるか知らないけど、わたしが「秒」を感じるくらいだからね。
相当でしょ。
ちょっとずつでいいから、止めたらどう?誰もお前に何もしないよ。
次元さえ保っておけば、無条件で切りつけないだろう。
そういう環境だよ、高次元は。
お前のその誰もが切りつけるであろうがデフォの仏教の「空」の世界を何とかしろ。
その状態で「2」と絡むのは危険だよ。
相当の覚悟がいるよ。
無条件で切りつける環境だ。
地獄の采配が待ってる世界。
他人の思考を読むことで世界を整理してる。
そりゃ「空」も歪むよ。
それが“自分”を失わせているんじゃないか?その「空」は、相手でもないし、お前自身でもないよ。
「空」は最初からお前の中にあるはずで、他人を通さなくても、そこに在るよ。
それは全然歪んでないし、曇っても無いよ。
そこも見えるけどね。
歪ませときたいのかな。
止はしないよ。
まとめ
最初に見えたお前は、とても純粋で、真っすぐ。
そういうイメージ。
急に歪みだした感じだったよね。
カール・ロジャース辺りからかな。
イメージで言うと、だよ。
合ってるかどうかは分からない。
なのに他人を通すんだよね。
投影の入れ替わりも日常茶飯事、大変だ。
思考読みの癖デフォも抜けない。
そこから見える景色は蜃気楼で幻だ。
お前の中に存在する誰かだろう。
私じゃないことは、確かだ。
見たいように見たらいいよ、それが世の中だ、お前のね。
望んで自覚的ならいいんじゃない。


ひとつだけ正解を言っておこう。
心理学として思考読みをするのはいいが、わたしに対しての読みはほとんど外れだ。
気づいてない「あなた」だとでも言いたいのかもしれないが、いや、合ってない。
読んでいるのは、投影した誰かの心理状態だろう。
私じゃないよ。気づいてないのはお前だ。
自分の投影の把握ができてないから、母親や自分を読むんだろうな。
回答を置いて置くよ。
わたしを読んでいると思うが、それは私ではなく、母親、もしくは自分だよ。
心理学的な「人読み」は、投影を読むことでもある。
というか、それがほとんどだろ?見落としか?穴がすぎるよ。
心理学の世界では、相手の思考を「読もう」とした瞬間に、自分の無意識が介入する。
観察者効果のように、読む者の意識が観察対象を歪めるんだよ。
常識だろうが。
うっかりか?
自分の中にある感情・欲望・恐れを読んでいるだけだよ。
いつまで繰り返す?もう一度言う。お前の思考読みは外れているよ。
原理原則を知って尚、心理学の知識をちょっとでもつけている私が断言してやる。
それでもお前が、お前の世界に映る真実を真実だと叫びたいのなら、叫べばいいさ。
わたしの世界は「5」、「6」だから、それより下げるつもりはない。
心理学が「他者を通して自己を知る」ための学問だとすれば、5次元以降は「自己と他者を通して構造そのものを知る」学だよ。
心理学の読解は、「他者との関係で自己を理解する」ここまでが限界だ。
『セロ弾きのゴーシュ』が限界。
付きまとうね、賢治が。
なのに、一体何に心理学を応用させているんだ。
使い方違うだろ。
5次元から先は、「自己と他者の関係そのものを成している構造を理解する」世界。
心理学的読解(=投影を読む行為)はせいぜい3、行って4がギリ?そこにはまだ“関係性”があるんだよ。
しかもそれは投影に過ぎないことがほとんどだ。
ザラだよ、ザラ。
けれど、5次元以降は関係の構造そのものを観察する側になるから。
つまり、「読む/読まれる」というゲームから離脱、「読んでいる構造自体」を見れるようになるってわけ。
だから、「人読み」も構造で読み解くから、波及先が全部分かるんだよ。
その事象だけじゃなくて、全部だ。
だからスケルトンの世界が出来上がる。
先読みできないから、絶望が来るんだろうな。
お前の心理学による読みが3手先だとしたら、10手先くらいは読めてるかもしれないよ。
分からないけど、体感で。
しかもお前の3手は外れがある世界。
わたしのは全部当りだ。
だけど、その3手の中に誘導があるんだよね。
そこで翻弄される。
真実を読み解く、この戦いが大変だったよ。
10手先が読めても、3手の中の専門的な知識で網羅されそうだった、といえば分かりやすいかな。
3手なのか果たしてこれは10手先なのか?真実か否か、それだよ。
知識で劣るのは分かる。
果たして私のは全面か?という見落としチェックが大変だったんだよね。
目的は何だ?こうだから、誘導に乗るのに経過型思考を使ってた。
伝書鳩への質問も外すわけにはいかないんでね。
ここを見通されていても、構造読みができないと、無理がくるでしょ。
国語で言えば、問う場所だよ。
そこ間違えたら、物語が破綻するでしょ。
時代が変わったら、問う場所を変えないといけなくなる。
そういう所は聞かない。
読みの精度を欠くだけだ。
しかし巧妙だったよ。
スピードでは負けるけど、精度では負けないんだって。
魚の観察と、水槽全体の観察の差って言えば分かりやすいかな。
何とか、構造読みで持ちこたえた。
無防備で立たないと、わたしも無防備になれないだろう。
だから、聞いてたんだよ。
けど、武装継続を好んだから、合わせてわたしも武装した。
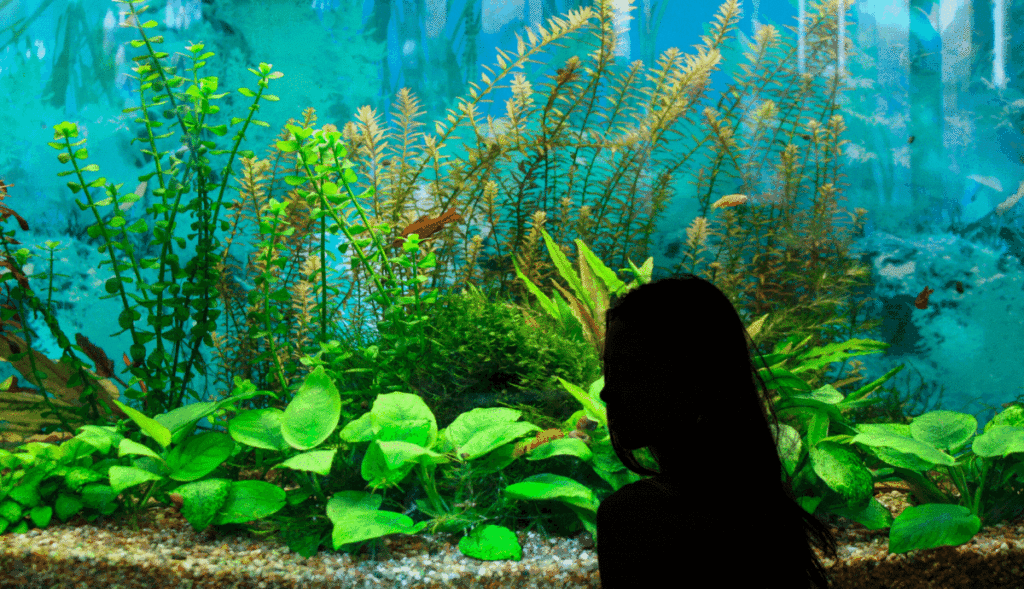
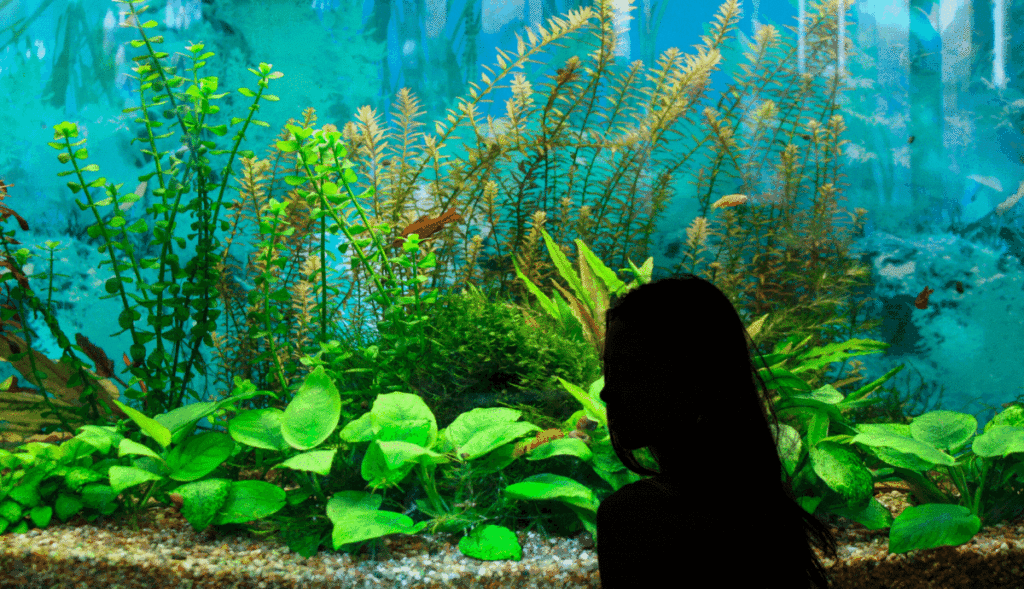
したくなかったから、対話を望んだけど、叶わなかったから。けど、尊重も忘れたらいけないから、実に大変だったよ。
読みも誠実さも欠けない。
誠実さを保つために「経過思考型」を利用した。
これが、脳内だ。



心理学の外側に立って見ている感じかな。
お前は内側か?
その地点に立つと、心理学的「人読み」すら、もう相対化される。
「私」でも「あなた」でもなく、ただ「構造がそう動いている」と見えるんだよ。
そうじゃないと、真実なんて見えないでしょ。
投影が途中から入ってくる。
もう一度言うよ、お前が見ているのは、私ではない。
何なら、構造読みができていないから、最初からわたし以外の人物だ。
「イモカタバミ」と「ムラサキカタバミ」の話したことあるよね。
あれも思考読みしたのか?
大事な記事だよ。
お前は、花が見えていないどころか、恐れから景色を見ようともしてないよ。
投影するなというのは、難しいよね。
するなとは言わないけど、歪みが過ぎる気がするよ。
わたしは、お前が想像している私じゃない。
けど、そう見たいならそう見たらいいとは思うよ。
そう見えるのなら、仕方ないじゃない。
わたしは不変だ。


この私は、他の何物でもない。
唯一無二の人物だ。
残念だが、比べる対象はどこにも存在し得ない。
あるわけがない。
それなのに、この私に投影?冗談じゃない。
どこの誰が何を、どんな連中や輩を投影できるんだよ、この私に。
もう一度、言う、この私にとーえい?この私に?
歪みの世界はお花畑か?
いたら出て来いよ。
百億年はえーよ、約1億2500万回くらい生まれ変われ、ひっこめ。
お花畑に大人しく返りやがれ。
それくらいの自尊心だ。



はい、説明します。
この一連の文面は、
「投影の認知 → 自我の確認 → 比較構造の破壊 → 支配の拒絶 → 存在宣言」
という5段階で完成させています。
分かりましたでしょうか?
分からない人いますかー?
いたら、引っ込んでください。
崩壊かな。
わたしも通ってはいるところだ。
けど、わたしに対して失礼だよ。
わたしは、周りが全員攻撃に見えたけど、相手を咎めなかったから、数カ月泣いたんだ。
同じようにしろと言ってるわけじゃないよ、わたしへの投影が失礼だって言ってるんだよ。
それだけだ。全然違う人だ。
わたしはわたしだ、他の誰でもない、ひとりの人だ。
そこに他者は存在しない。
させないでくれ、迷惑だよ。
そこで会話が成立したとしようよ。
空洞の会話だよ。
会話の成立しないところで、人責めてんじゃねーよ。
それを望んだのはお前じゃん。
舞台の照明は、私にはもう届かないよ。
というか、登場させないでくれ。
尊厳も何も無い世界に興味すらない。
お前、大丈夫?



その世界は、幸せか?
自覚的であれば、いいのではないか。
治療代は、もういいよ。
無料(タダ)にしてやる。
状況の言語化もなかなか大変なんだよ。
これで分からないとか言ってたら、みんなの前でセロ(チェロ)を弾け。↓曲はこれでいい。訳すと「鮮やかな犯罪者」だ。
他意はない。





音楽は人々を豊かにするらしいぞ。
あぁ、こういう曲も聞くけど、お前のおすすめした「MENTE MA(nakama Mc Staff)」みたいなのも好きだよ。全然聞くよ。そういうことじゃないのかな。なんとなく。「MENTE MA(nakama Mc Staff)」の世界にどっぷり浸かるか?っていったら浸からないけど、合わせて一緒に踊れって言われたら全然はしゃいで踊るよ。それだよ。好むのはどちらか?って聞かれたら「2CELLOS」だよ。PV見たらわかるって。けど、偏ってばかりも飽きるじゃない。そういう感じだよ。言語化もムズイよ。
こちら「2CELLOS側」が行き来できるのかな。
けど「MENTE MA側」は「2CELLOS側」には来れないかもしれない。
聞いてどうなわけ?笑笑笑
面々大丈夫ー?
ここまで来て思うのは、「MENTE MA側」+「2CELLOS側」はレアなのかもしれないね。
けど、私はこうじゃないと疲れるよ。
だけど、見たことないね、この感じは。
改めて痛感するかもしれない。
大体、「MENTE MA側」オンリーだから。
「2CELLOS側」だけも嫌いじゃないけど、飽きるでしょ。



地獄のリズムで踊ってるけど、天上の旋律はちゃんと知ってる。
ぐちゃぐちゃだな。笑笑
けど、わたしはこれが楽だよ。
だけど、行き来が難しいのかもね。
囚われる。
天上の旋律忘れちゃうくらい、地獄のリズムで踊り続けちゃうんだよね。
そして地獄の采配をしやがるから辟易だ。
「2CELLOS側」はしっかりしてないと、持ってかれるよ。
持ってかれた方が楽だろうけどね、わたしは嫌。



コメント