小学4年生の娘から、

ママ、これ、小学4年生で習うらしいのよ。



あぁ、それで?だから何。



ううん、それだけ~気になったから、言っただけ~



………は?
何なんだよって読んでみたんだけど、まぁ、読んだ後に、スッキリしないというか、何が言いたいんだろなってちょっとモヤる物語。ハッキリしないんですよね。中身が。情報が散らばってスッキリしない。
結論から言うと、この物語は心理学で言うなら、自己理解が進んだ物語だと思う。
「伝えたいことは何だろう?」という問いをもう一度持ってよくよく読み返してみると、ぼんやりして掴めないもどかしさを冒頭では「空(湖)」「雲(白鳥)」と「風」で表していて、それを機に、最後にはっきり主人公である歌の決意に変わっている。
歌が体験を通して、自分を振り返り、決意する物語。そんな風に読めたのだけど、多分こういうことが言いたいのかな?というのを私なりにまとめてみます。



国の題材で定まってるのは「想像力」「美しいものに感動する心」だそうです。わたしは、意味わかんない。
「スワンレイク」は“景色”じゃなくて、“記憶”から自分の感情を掴む話でしょー?
この物語の構造だけを抜いてみる
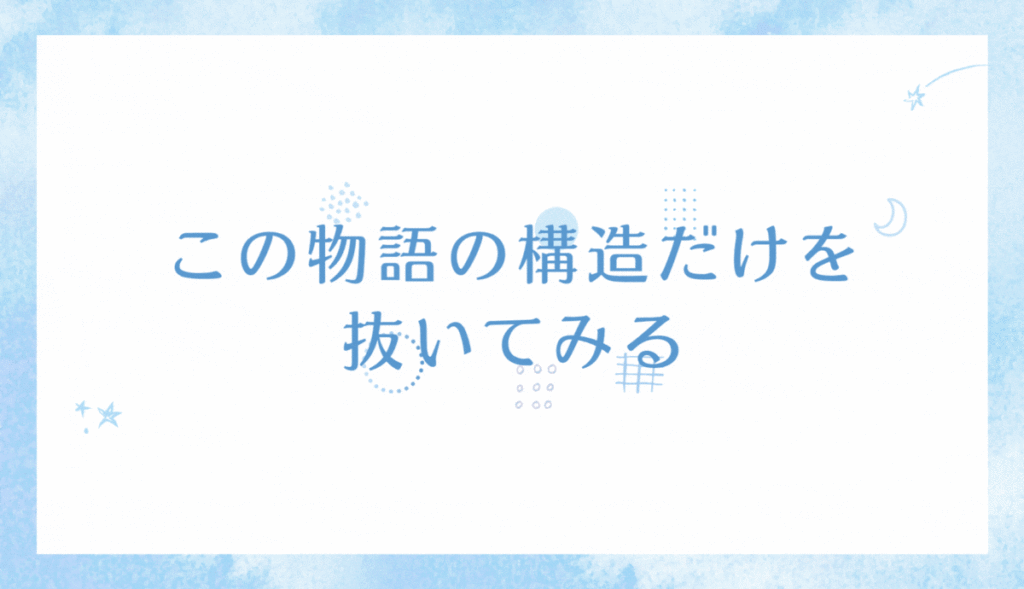
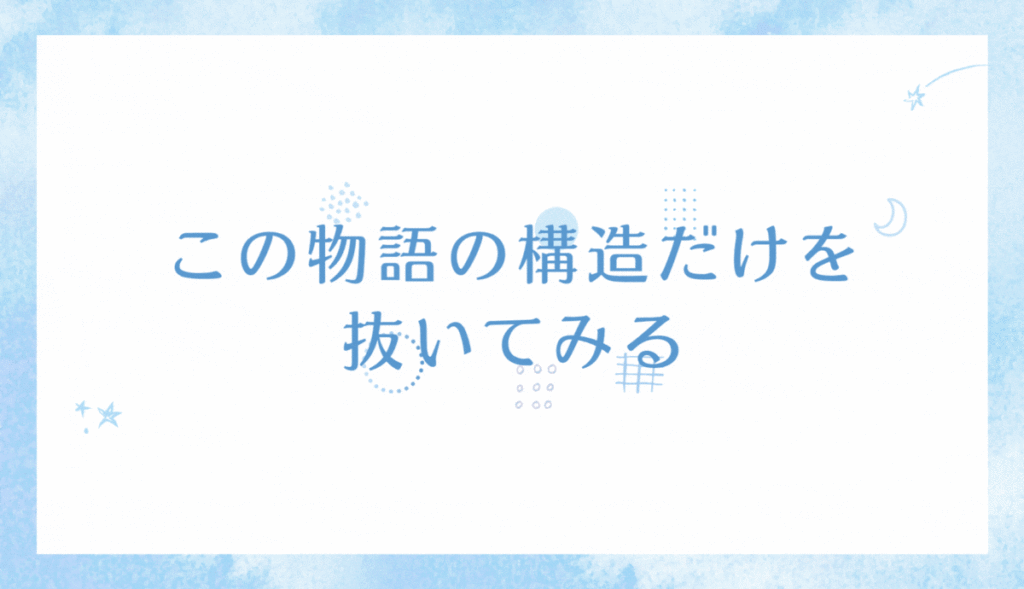
◆物語の素材一覧
- アメリカに住む父の妹の真琴さんの家に遊びに行く
- 異文化
- 車いすのグレン
- 野菜の種類
- 伝わらない会話
- 作文
ざっとこんな感じかと思う。
色々学ぶところはあると思うんだけれど、因果で繋いで重要度をみていくと、基本的に赤字が重要になると判断する。
事実を抜く → 因果でつなぐ → 構造を立てる
この3段階で「構造読み」が完成。
- どこに焦点があるか?問う場所は?と考えたときに、冒頭に「書けない主人公」がある。
- 「なぜ書けないの?」という理由を物語に探しに行くことになる。
- その「書けない」理由に、物語のどこがどう影響しているのか?と考えて行く。
→「書けない理由」自体は明確に表現されていないことに気づく
※ここが混乱の要素でもある - 物語を追い、歌がどこで心を動かされて、どう感じているか?というのに着目する。
- グレンとの交流で、もどかしさを感じている。
→となると、このもどかしさを掴んだに違いない
→異文化の流れは刺激と判断※ここで情報が混乱と予想 - 最後に英語の勉強を決意している。
となると、異文化や野菜の種類だとかは、副次的要素に該当する、わたしはそんな感じで整理して、「あぁ、自己理解ね。」となる。
「書けない」という現象が起点になり、なぜか?→異文化の刺激 → 情報処理の混乱 → 感情の捕捉不能 → 自己理解 → 表現への意志、という因果連鎖。



言葉にするのは難しいね。言葉になると簡単。構造が掴めるまでは混沌、掴めた瞬間に世界が整理されるんだけど、その過程を分かりやすく文字にするのが遅れるな。普段から問うてないものね。「自分以外に構造化の説明をするには?」っていう問いを。そこだろうね。ここは、速くしたいね。構造翻訳。ほんと「雲」と「風」。
「空」「雲」「風」、そこから読み解く歌の心境は?様々な刺激を受けて、最後に歌はどう変わることができたのか?
主人公の歌が何を思い出して、どんなことを思い、決意まで至ったのか?
わたしならこの辺りを問うと思うのだけれど、国の題材で定まってるのは「想像力」「美しいものに感動する心」。



想像力は、まぁ分かるわ。美しいものに感動する心?絵とか景色みた方がはやくない?この題材でしなくていいと思うけど。この作品のお題は、景色の中じゃなくて、通じなかった言葉の中に“自分の感情を見つけていく姿”にあると思うけど?わたしはね。
構造読み読解は不変※表現は自由
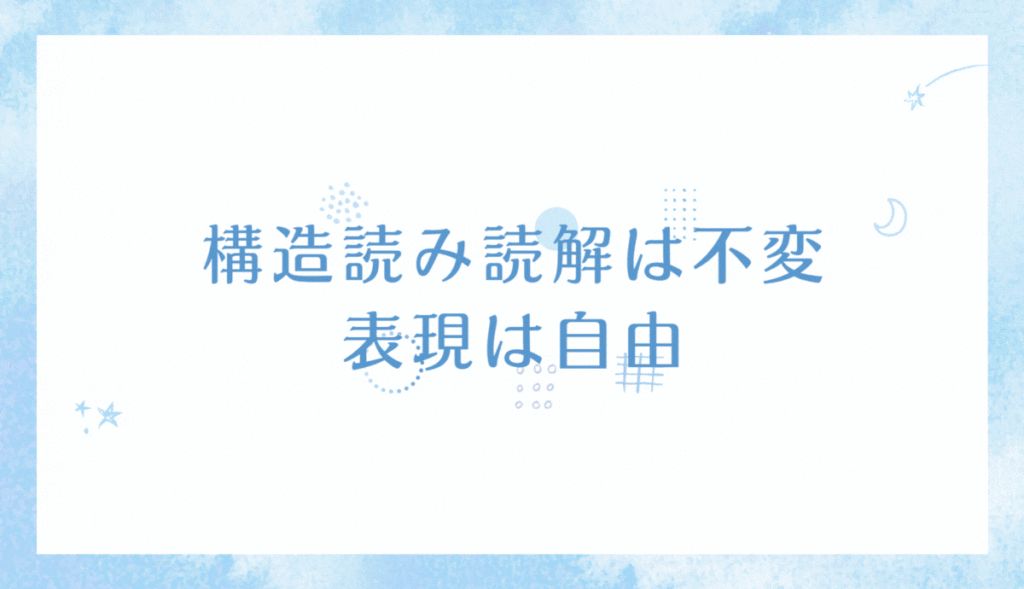
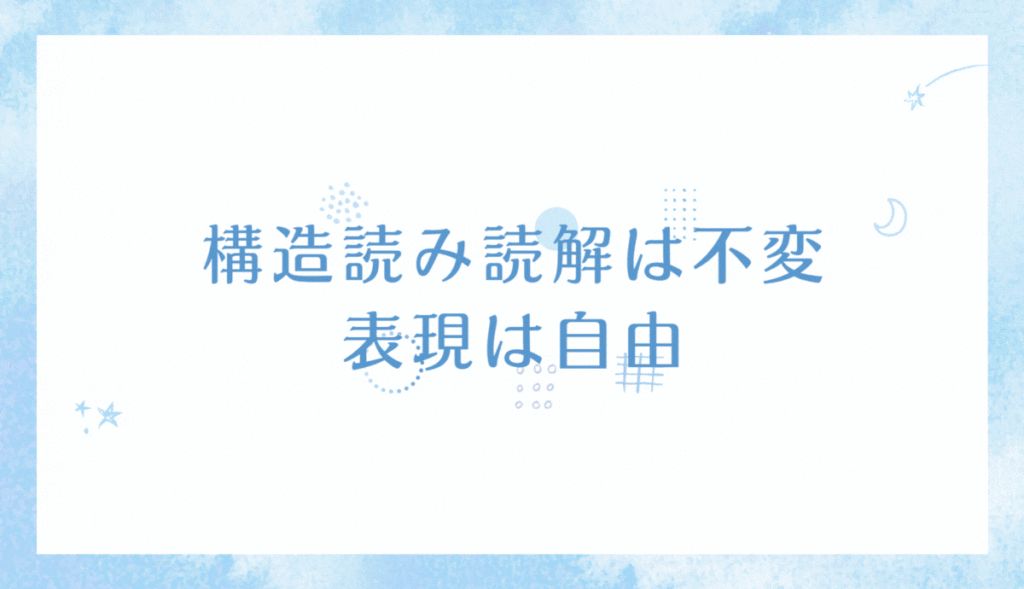
構造は不変なんだけれど、その構造の表現の仕方は変わってくるんだと思う。これらを統合して、どの現場にどの部分まで抽象度を下げるか?というのが大事なのかもしれない。
例えば、小学生には「心理学」「哲学」を直では落とせないじゃない。そこを落とさずに、翻訳して説明はしないといけない難しさがあるよね。
① 教育的読み
テーマ:「感じたことを言葉にする大切さ」
② 心理学的読み(感情)
テーマ:「感情認知と自己理解」
③ 哲学的読み(意識の構造)
テーマ:「他者を通じて自己を知る」
※他者と通して自分が立つ(存在意義の方)
※『セロ弾きのゴーシュ』の「他者を通じて自己を知る」は心理学の方、つまり他者は自分のスクリーン。この物語は哲学寄りだと思う。異論は認めます。



心理学と哲学の「他者を通じて自己を知る」というのは、紛らわしいのだけれど、両者意味が違っていて、簡単に説明するなら、心理学で表すのなら、相手をスクリーンとして見るから、自分もないし、相手もない、スクリーンとして見るから、自分もあるし、相手もある。そういう解釈。だから、哲学で言う「空」が成立して、相手を通して自分が立ち上がる。
まえにも説明したけれど、相手は投影を通して、わたしを見たいようにしか見ない。わたしという存在は、相手の心の中で作られた“像”にすぎない。けれどその像の中には、わたし自身がまだ知らない“何か”が映り込む。だから、他者を通して、わたしという存在が立ち上がる。
こんな感じだと、ずっと思ってる。合ってるかどうかは、分からない。笑 整合性は取れるでしょ。心理学と哲学が交差するところだと思う。
哲学と心理学の相互作用
わたしが自分に何を先に導入したかって、独学の「心理学」。先にニーチェとか行ったら、迷子になっちゃったから。



ちょっと…何言ってるかわかんない。
ムッズ….(難しい)。
軽くこうなったから。笑
けど今、独学だけど、体感として「多分、合ってる」っていうものがある、それくらいの知識。だから、素人として、心理学だとかスピリチュアルだとか、割と体感として得やすい分野を読んでから、哲学に行くと、あぁ、アレのことだっていうのがあった。それからは、心理学でも哲学でも、それ、おかしくない?っていうのも問えるしね。
哲学者が語る「自由」「意識」「存在」って、ぜんぶ人間の心の動きの構造化で、でも、心理学を知らないと、「それは心のどの現象を指しているのか」が難しくなると思う。
例えば
- カントの「悟性」=“スキーマ理論”に類似
- ヘーゲルの「自己意識」=“メタ認知”に類似
- ニーチェの「力への意志」=“自己超越へ向かう衝動”に類似
心理学なしで読むと、ここ全部「難しい言葉」でわたしは止まる。追えない、「悟性!?」。心理学の言葉が入ってると、「あ、これ感情の構造の話」「これは認知の話」って即座にマッピングできる。だから素人なりにも迷わない。
心理学を知ってると、具体的な心の運動として再現できるから、



あぁ、難しい言葉だけど、ヘーゲルのはメタ認知でしょ?とか落ちた。
ニーチェ(1844年10月15日 – 1900年8月25日)と賢治(1896年8月27日 – 1933年9月21日)が知り合ったとしたら、ニーチェは賢治にこう言うだろうかな?と想像してみる。



君の理想は尊い。ただし、それに支配されるな。理想の奴隷になるくらいなら、泥(現実)の中で笑うといい。生きるとは、汚れを恐れずに自分の意志を持って生きることだ。君の「善」が君を殺している。



ただの想像。持論。
哲学は「なぜ」を問う、心理学は「どうしてそうなるか」を説明する
哲学が“理由”を問うのに対して、心理学は“メカニズム”を描く。だから両者をつなげると、「抽象」と「具体」が一致しやすくなるでしょ。
例えば
- 「なぜ人は自由を求めるのか?」(哲学)
- 「自由を求める衝動はどこから生まれるか?」(心理学)
→ 統合すると「自由欲求=「自分で決めたい」「自分として生きたい」っていう、人間の根っこの欲求。」になるのかな。
哲学の問いを“自分ごと”にするには心理学は必要なのかもしれない
哲学は、構造としての「人間一般」を語るのに対して、心理学は、それを「わたし」の中でどう起こるかを可視化する。
つまり、心理学は哲学を「体験化」する翻訳装置と言ってもいいかもしれない。結論として言うなら、哲学の高さとか危険域を実感するのには、心理学という知識は必要なんじゃないかと思う。持論だよ。
ニーチェの「永劫回帰」も、最初は「何だろう?」って思うでしょ。けど、気づきがない限り、これは正しいのよ。つまり、人は同じ出来事・同じ感情・同じ選択を、形を変えて何度も繰り返すという構造がある。
でもこの「永劫回帰」という言葉だけ聞いても、何のことだか分からないじゃない。で、ちょっと怖いじゃない。果たして防げるの?とも思うしね。縁起の知識とかあると、ちょっとゾッとするのよ。けど、そうじゃないの。



じょーだんじゃねーよ。
わたしは、こうなったのよ。マジで嫌だ。こうなった。
そこに心理学が入ると、「永劫回帰」は“内面の構造”として見えてくる。無意識のパターンが行動や人間関係を再生し続ける――これが心理学でいう反復。
自己理解=「私はこう考える傾向がある」「こう反応する癖がある」
メタ認知=「その思考や感情を上から観察できる」
感情制御=「観察したうえで選択的に反応を変えられる」
ここが分からないと、“気づかないまま同じ選択”をして、回帰する。それでも笑っていれるか?って問うのがニーチェでしょ?
君は、“回帰の構造”を自覚したうえで、「それでもこの人生を選ぶ」と笑えるか?
君は、この「反復」を“自己理解”に変えるか、それとも“他責”で終わらせるか?
つまり、心理学は「自己を安全に覗くための足場」を作ってくれる。深く潜っても、ちゃんと戻ってこれるようになる。
そっから、こうなったのよ。



じょーだんじゃねーよ。だけど笑ってやるよ。何もかんも構造化が分かるからお見通しだ。迷わねーから、笑えるよ。
あと「じょーだんじゃねーよ。」って思えることに、意味があるでしょ。心からそう思えたら、行動が変わるんだよ。だから「永劫回帰」にさせないんだよ。ここが、わたしをいっちばん苦しめた悩みだ。「無意識」が怖かった。ここから、どうやって、知識を統合して繋げていくか?無意識に支配されてたまるか、こんな感じだ。「お前はどうしたい?」自分にずっと問うてきた。
だから、大丈夫だよ。繰り返す習性、構造があることを分かっておけば、繰り返さないでしょ。5次元と3次元の意識の行き来も自覚的にできるじゃない。
だから、大丈夫だ。繰り返さない。
このブログの知識があり、自分に問うことができれば大丈夫、繰り返さないんだよ。
見えない力に支配されてるようで、当時は本当に本当に怖かった。思い出すだけで背中がゾッとする。この見えない力に、どうにかされそうで嫌だったんだよな。でも、“気づくための反復”だったと思えば納得もできるよ。



お前が見ようとしたからこそ、世界が反応したんだ。だから、もう大丈夫。お前はもう、見えている側にいる。見えていない者は、見させられる。でも、見えているなら、こっちの勝ちだろ。
と、第三者目線で自分に語ってみる。



ざまぁみろ。だって、見えてるからな。見えないお前に、支配されてたまるかよ。お前ごと吸収してやる。
そう、はっきり言って、わたしはおかしいのかもしれない。笑笑 けど、これはわたしの世界だ。
心理学だけだと「自己理解」という知識はあっても、なぜそれが必要なのか?大事なのか?が、多分分からないでしょ。「自己理解」というものがあります⇒「なるほど」っていう。わたしはそうなるから。



哲学を知らない心理学は深さを失いやすくもあり、心理学を知らない哲学は地に足を失いやすいと言えるのかもしれない。けど、分かる人には、すぐに分かるんだろうな。わたしはちょっと、時間かかっちゃったから。もう一度言っておく、わたしの持論だ。
あと、心理操作があるとしたら、わたしが何を見抜くかというと、まぁ色々だ。その操作の内容だけだと思うだろうけれど、そうじゃないのよ。違う違う。そこだけ見ても意味が無い。操作の構造、操作している人の心理構造、背景全部。使えば使う程に、色々透けて見えるから、一応伝えておく。で、何を重要視しているかというと、操作している人の心理構造だね。すると、全てがイコールになっていく。行動があらかた想像つくようになる。種明かしだ。
縁起読みのシミュレーション。操作を見る者は、相手に反応する。構造を見る者は、相手を理解する。背景(縁起)まで読む者は、相手に巻き込まれないじゃない。そして、その構造の中に、他者は存在しないんだよね。合ってると思うんだよ。正否は分からないけれど。
素人判断ね。この先にあるのは、「存在しない」が最終到達じゃないのかな。「他者は存在しない=自分は存在しない」。存在してんじゃないの?十分。だったら、あとは「どう在りたいか」を選ぶだけだし、他者に反応するでも、操作に巻き込まれるでもなく、自分で、自分を選ぶことが、いちばんの自由にはなる。



打開策として、自分が活躍できる場を得ることには意味があるかもしれないね。そこからだと早いと思う。まぁ、「慢心」を自覚的に行動すれば、見通しがスッキリするね。もう一度言っておく。素人判断だ。
この判断が相手の「怒り」に触れることがあることも、先に言っておく。けどこれ、最善手じゃないの?
支配を恐れていた私が、見えない者からの支配を作る。その構造を見破るには、問うて「選ぶしかない」んだよね。問えてるならいいんじゃない。そうやって、ひとつひとつ選び直すことで、わたしは「わたし」という形で世界に触れていくことができるようになった。
相当脱線したな。別記事案件かもしれない。笑
④ 文学的読み(比喩構造化)→ 掴めなかった雲を掴もうとする風=“感情を言葉にしようとする意志”
| 次元 | 目的 | 構造(正解) | 形(多様) |
|---|---|---|---|
| 構造レベル | 外界刺激→感情混乱→自己理解→伝達意志 | 固定 | すべての読み方に共通 |
| 表現レベル | 教育/心理/哲学/文学 | 変化 | 読者・目的により自由 |
こうなるのかな。
スピリチュアルも無理くり入れるとなると、3次元で感じた「もどかしさ」を5次元で内的動機付とする、こんな感じかな。
| 読解 | テーマ | 焦点 | 使用する言葉・翻訳例 |
|---|---|---|---|
| 教育的読み | 感じたことを、自分に問いながら言葉にする大切さ | 行動化 | 感じたことをそのままにせず“自分で問う”ことが学びの始まり。気持ちを言葉にできると、わかり合える。問うことで自分が分かる。問うことが、人生で一番大切。 |
| 心理学的読み | 感情認知と自己理解 | 内的動機付 | 気持ちがわからないのは悪いことではなく、ただ“整理の途中”にいるだけ。整理できてくると、自分が何を感じ、何をしたいのかが見え始める。 |
| 哲学的読み | 他者を通じて自己を知る | 意識の構造 | 他者との出会いが価値観を揺らし、“自分とは何か”を再定義する。他者を通じて本当の自分に気づく。 |
| 文学的読み | 雲を掴もうとする風=感情を言葉にしようとする意志 | 象徴・比喩 | “雲”は掴めない感情、“風”はそれを言葉にしようとする意志。 |
| スピリチュアル的読み | 3次元で感じた「もどかしさ」を5次元で内的動機にする | 3次元→5次元 | 外界での刺激(他者・体験)から、内側の成長へと転換。 |
細々まとめていって気づくこともある。
この物語を「教育的読み」だけにしてしまうと、感じたことがバラバラになって、



日本の野菜の違いと、海外の野菜の違いは?
こうならない?感じたことに問いを立てるというには、東洋っぽいけど、問い(野菜の違い)が西洋、西洋のフレーム(自己理解)もないから、飛躍ぶりがすごすぎて。
感じたことをそのままにせず“自分で問う”ことが学びの始まり。これに沿ってるでしょ。怖いことに。
そして、日本の野菜の違いと海外の野菜の違いを友達と相談して、共有するっていうアクティブラーニングが形成されてるんじゃないの?
アクティブラーニングの乱用。
「感じたことをそのままにせず、自分で問うことが大切」
→ この“問う”が、内省ではなく「題材内での比較作業」にすり替わるという悲劇ね。
こんなことある?
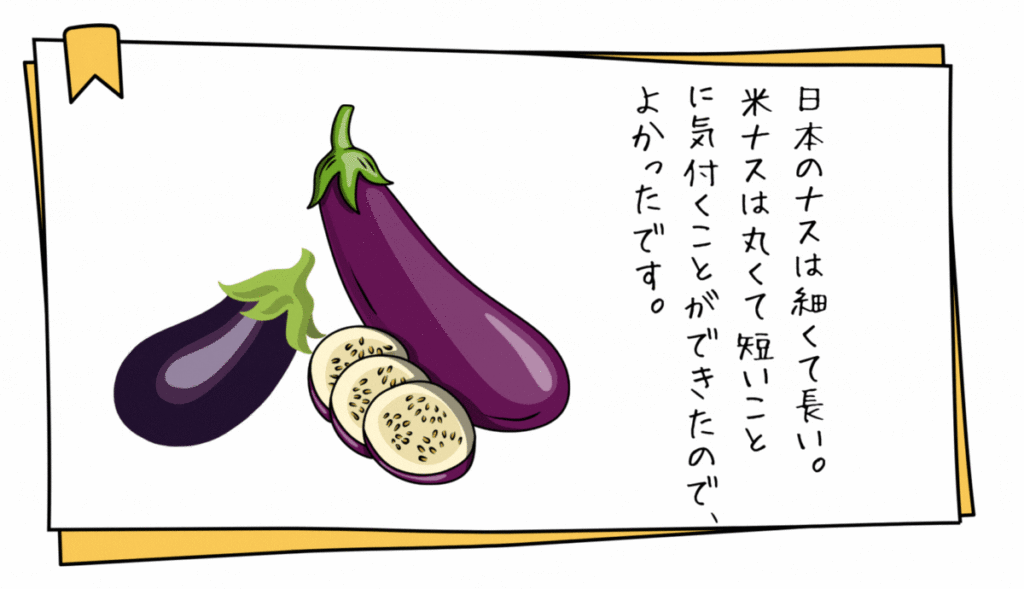
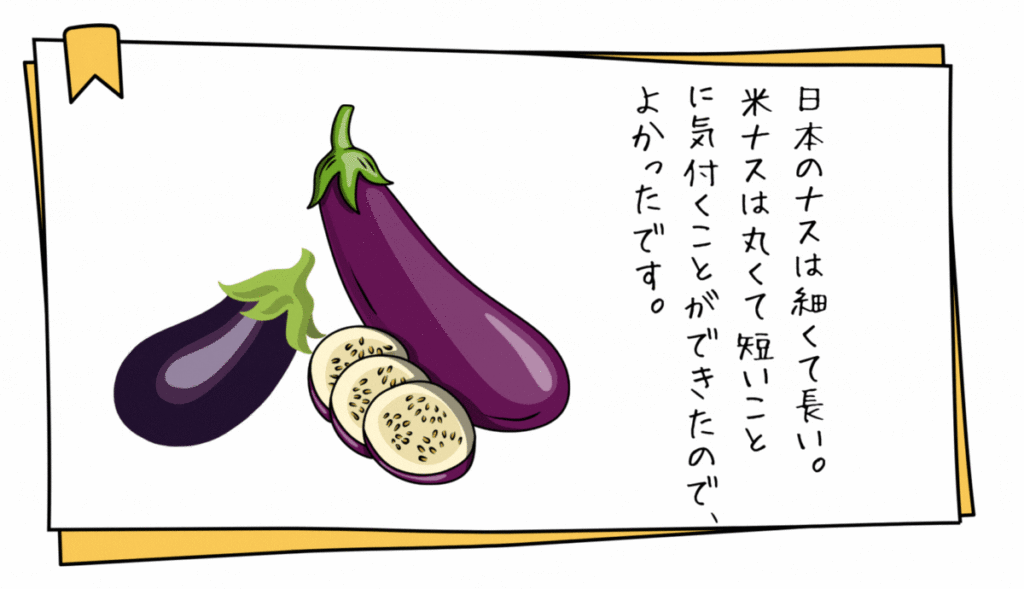



だから教師も生徒たちも安心して「問うてるつもり」になる。でも実際にやっているのは、「日本と海外のナスの違いは?」っていう理科の観察でしょ。
何これ。課題がないところに、課題(問い)を見出すというのは大事で、それがアクティブラーニングとして教育現場に降りてきてるんだけど、構造は読まないと、むちゃくちゃじゃん?構造の読解(因果や心理)をすっ飛ばして、素材だけ眺めて「問い」をでっちあげる。そらミステリーにもなる。物語としても学びとしても成立しないっていうね。
江戸川乱歩も混乱。事件のない推理小説と同じ。いない怪人二十面相を追うの図、けど逮捕できる。
これ何だろう。作品は秀逸、教科書微妙、教育体制壊滅、現場混乱、どこがどうなってるの?そうとうなヤバさを感じる(語彙力)。
構造を読まずに“問い”だけを立てる授業って、まるで「犯人がいない事件を推理しろ」って言われてるようなものでしょ。
子どもたちは、



たぶんこの人が怪しい!
って言いながら、存在しない怪人を追いかけて、最後に「犯人は、ぜったいあの人です。」って作文を書く。



主体的に学べましたね!
って満足して、でも実際は、誰も事件解いてない。動機(=なぜそう思うか)も因果(=どうしてそうなったか)も扱われない。
冤罪成立。
つまり、“読み”が構造化されていないから、教育も生徒たちも物語の事件の中に迷い込む。
そして皮肉なのは、その「いない怪人二十面相を追うごっこ」こそが、主体的学びとして制度的に評価されていること。
乱歩もさすがに言うと思う。



事件起きてから、呼んでくれる?



これじゃぁ、物事の原理原則分からないはずだよ。人生で一番大事だと思うんだけどねぇ、わたしは。厳しく言うなら、作品の冒涜にも近い気がする。個人的な雑感だから。



使い方は間違えてませんから。



まぁね。それが「日本の国語だ」って言われたら、わたしは何も言えないかなぁ。かき氷があるとしたら、わたしは蜜のたっぷりかかったハワイアンブルーを食べたいのよね。けど、「水」を渡されたような感覚。「氷」でもない「水」。そこには、形も何も無い。ただ喉を通り過ぎるだけの。味も形も記憶に残らない。反論はしないけど、異論は呈すよ。
波及もすごそうだ。
↓脱線したけど、以下、作品の話に戻ろうと思う。
書けない理由は「言葉が見つからない」から
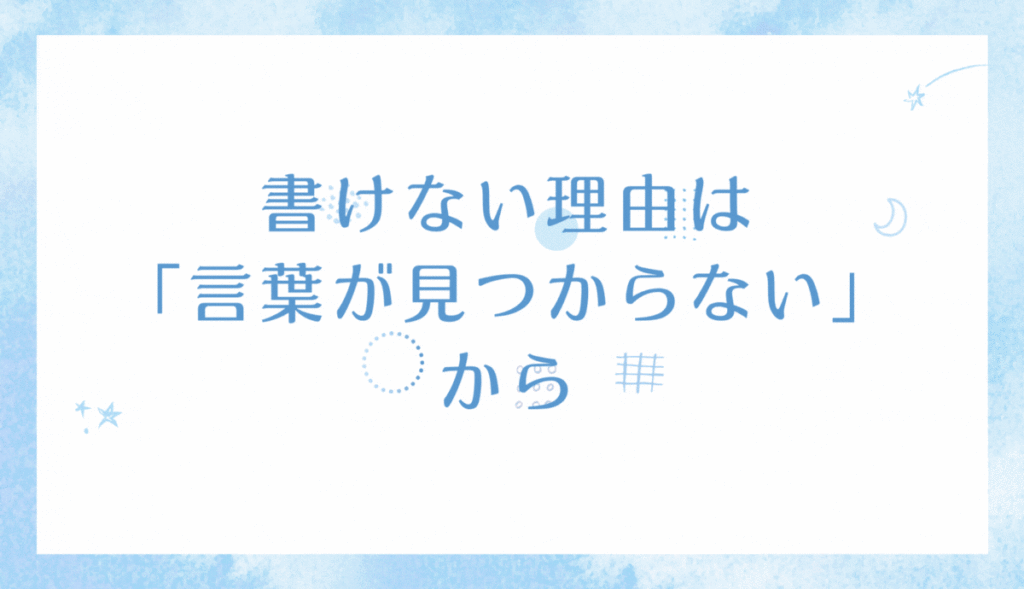
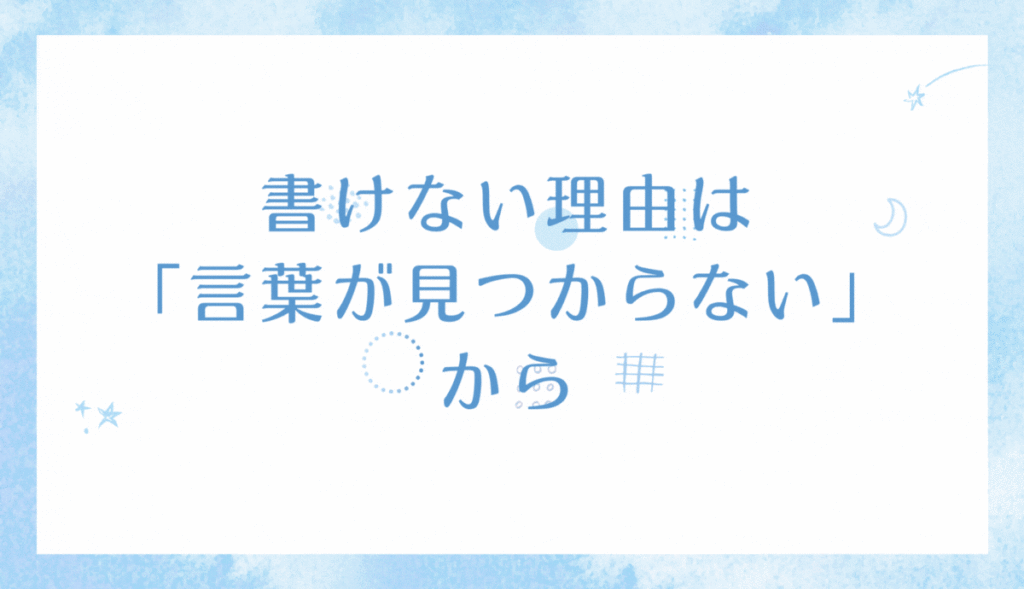
作文の前に、まずペンが止まる。いや、止まるというより――ペン先が「どこを向けばいいのか」分からない。
それくらい、生まれて初めてのアメリカ旅行の体験は情報の洪水だったのかもしれない。
アメリカに着いてからは毎日、おどろきと発見の連続だった。
スーパーの広さ、異国の人。車いすのグレン、見たことも無い野菜や動物たち。あれもこれも書けるのに、どれも“自分の言葉”で何が言いたいのかわからない。
たくさんの感情が動いたはずなのに、掴むことができない、おどろきと発見の連続だったのにも関わらず、モヤっとした感覚。
だから、ペンが紙の上で渋滞している。
- 旅行の体験は刺激的だったのに、作文にできない
- 思いはあるのに、言葉にならない――そのもどかしさが出発点
① 旅行の体験は刺激的だったのに、作文にできない
目の前で起きたことは全部「すごかった!」「やばい!」で終わってしまう。
よくありますよね。
そう、“語彙が足りない観光客”状態。



ほら、わたしが前偶然付けたTVショーで見た、ヤバいカップル状態。エメラルドグリーンの海を見て出たセリフたち。覚えてる?
言うよ、「ヤバい」くらいはね。けど多用はしないから。ずっとコレだったから。
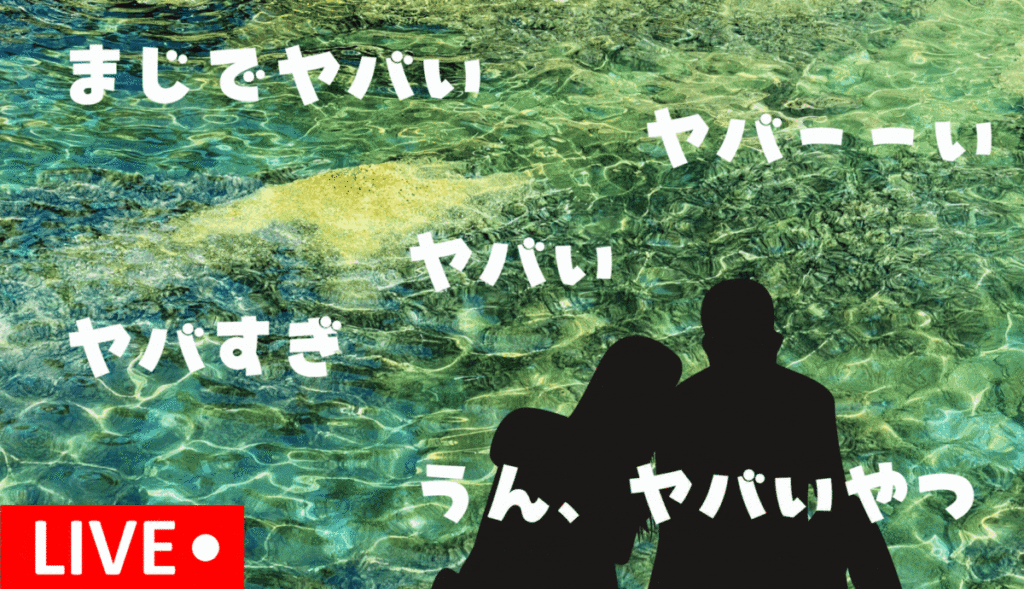
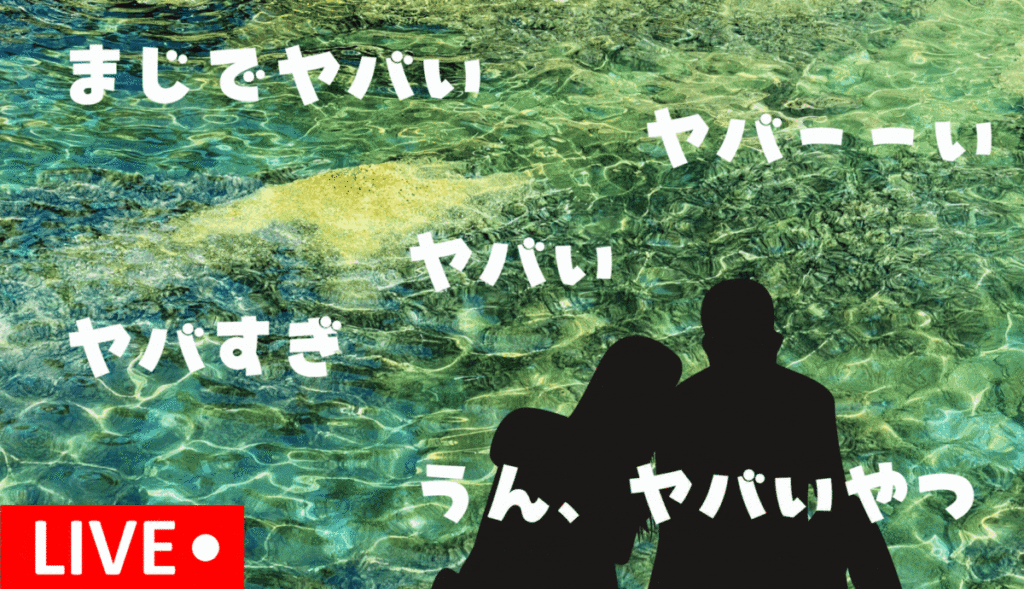
異文化の刺激はあったのに、心の整理はされていない。まるで写真フォルダはパンパンなのに、日記が真っ白というあの感じ。
彼女の中では、「体験」はあるけれど「意味」がまだ育ってない。難しいんですよ。日常から自分の本当に言いたいこと、伝えたいことを拾う作業っていうのは、本当に難しい。
わたしも、自分の感情を自分の中で咀嚼して、「何に、どう感じているのか?」を言葉にするのは、エネルギーを使うことがある。それくらい、難しい作業だと思う。事象にもよるけれど、慣れるまでは大変だと思う。
なぜ難しいかというと、表面の情報に翻弄されるから。この物語で言うなら、アメリカの刺激。つまり“未知の情報の多さ”に心が振り回されてしまう。
目に映るもの、耳に入るもの、すべてが新鮮で、すべてが「わあ!」と反応してしまう。けれど、あまりに多くの刺激を受け取ると、脳は「感じる」より先に「処理する」方にエネルギーを使ってしまう。
だから、視覚から入る情報が多いほど、内側の感情にアクセスしづらくなる。「見た」「知った」で終わってしまい、「どう感じた」には、なかなか辿り着けない。
それが人間だと思う。
目に映るものが多すぎると、心の声が聞こえなくなる。
② 思いはあるのに、言葉にならない――そのもどかしさが出発点
アメリカで出会ったグレン。日本のナスの形を説明できずに笑ってごまかしたあの瞬間。



日本のナスは、米ナスより細くて長いの。
頭の中ではいいたい言葉があるのに、英語にできない。笑顔でうなずくことだけしかできなかった。
書けないのも同じ。今度は紙の前で、言葉が渋滞している。
人は感情を掴むことができないと書けないんですよ。感じたことを文字にするのが難しいんだけど、その前に何を感じたのか?を問うのが難しい。
だから、ペンが止まる。
そのもどかしさこそが、彼女の物語のスタートライン。
風が雲をつかまえられないように、彼女もまだ、自分の思いを言葉で捕まえられていない。
この一連の流れは、「書けない少女」が「書く少女」に変わるまでの心の旅。
↓表にまとめると、大体こんな流れかな?と思う。
| 段階 | 心理的プロセス | 対応場面 | 内面の状態・変化 |
|---|---|---|---|
| ① 感情が整理できない | 情動と認知の分離(アレキシサイミア) | 空と雲を見つめる | 体験はあるのに、何を書けばいいか分からない。感じているのに、言葉にできない。感情が“霧のよう”に漂っている。 |
| ② 外界に翻弄される | 情報過多・外的刺激依存 | アメリカ旅行の描写(動物・野菜・異国の人) | 見るもの聞くものが多すぎて、心の整理が追いつかない。「感じる」よりも「処理する」状態。自分の感情が見えない。 |
| ③ 自分の感情に気づく | 自己認識の萌芽 | グレンとの会話/通じない英語 | 「話せなかった」事実の奥にある、“伝えたかった”という気持ちに初めて気づく。ここで“自分の心の輪郭”が生まれる。 |
| ④ 感情を意味づける | 自己理解の形成 | 作文に向かう/風と雲の比喩 | 伝わらなかったもどかしさ=「通じなかった言葉」から、“伝えたい”という思いを見つけ出す。体験を自分の意味として統合しはじめる。 |
| ⑤ 自分の意志で動く | 内的動機づけ | ペンを握る結末 | 「もっと英語を話せるようになりたい」と心の奥から湧き出す意志。誰かに評価されるためでなく、“伝えたい”という純粋な衝動に変わる。 |
| ⑥ 経験を自分の物語にする | 自己表現・自己統合 | 作文を書きはじめる | 「通じなかった言葉」が「伝えたい」という願いに変わる。体験が“自分の物語”として意味を持ちはじめる。 |
つまり、自己理解のプロセスでもある。
書けない理由は、“言葉が見つからない”からじゃなくて、何かが気になったはずなのに、刺激が強すぎて情報が多すぎて、何をどう感じたのか“自分の気持ちがまだ形になっていない”から。
この物語は、そこから始まる。
ここでの動機は、グレンともっとお話ししたい、伝えたいっていう思いだけど、それがまた次の動機に繋がる可能性だってあるから。英語を勉強してグレンと話せるようになるという小さな動機が、もっと大きな目標に変わることもあるじゃないですか。
そういう自分の目標を見つけるためにも、日頃から感情にアクセスするというのは大事だと思う。それが自己実現に繋がっていくから。
「スワンレイク」は心の中の思い出
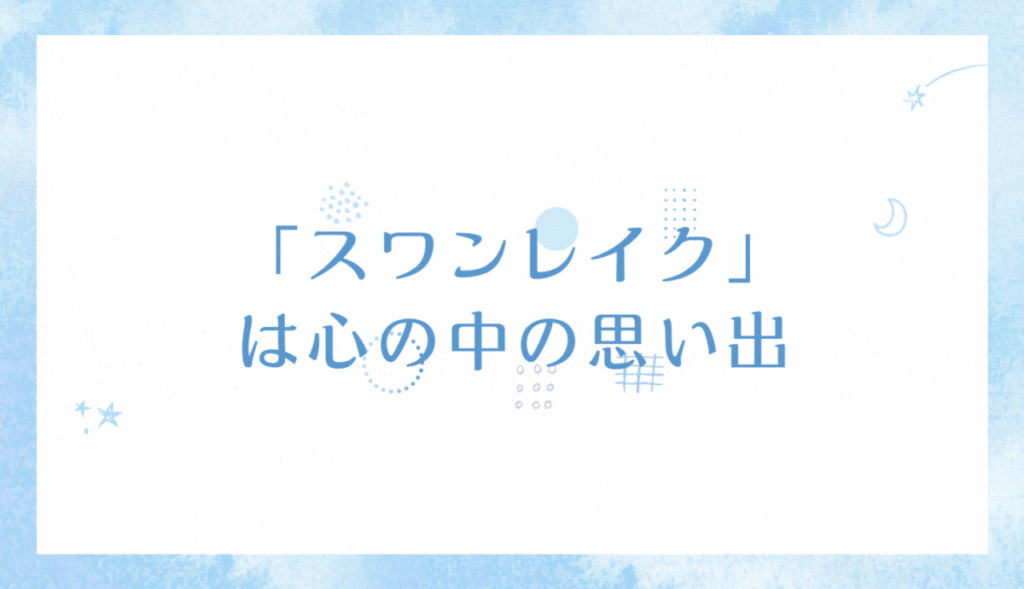
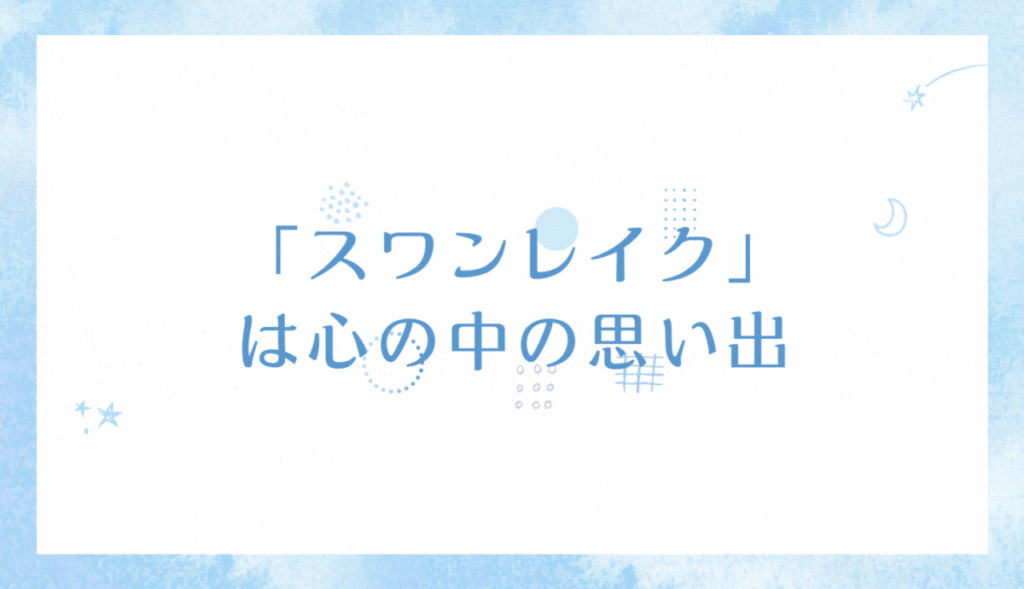
グレンが言った。



ここはスワンレイクだよ。でも今は、あの白鳥たち、空を泳いでるけどね。
——その言葉が、ずっと彼女の中に残っている。
日本に戻り、作文用紙を目の前に、空を見る歌。
そのときの情景を表している、湖を表す空、白鳥を表す雲。雲をつかむことができない風は「言葉で伝えることができなかったもどかしさ」だと思う。
思い出を通じて、自分の中に言葉が戻ってくる。
風は雲を掴むことができないという比喩表現を通して、彼女は掴むことができないもどかしさを掴むことができたんだと想像する。
その景色を思い浮かべることで、初めて自分の気持ちを、自分を掴むことができたのではないだろうか?
白鳥たちは湖に留まらず、空へ向かって飛び立っている。
通じなかった言葉が「伝えたい」に変わる瞬間
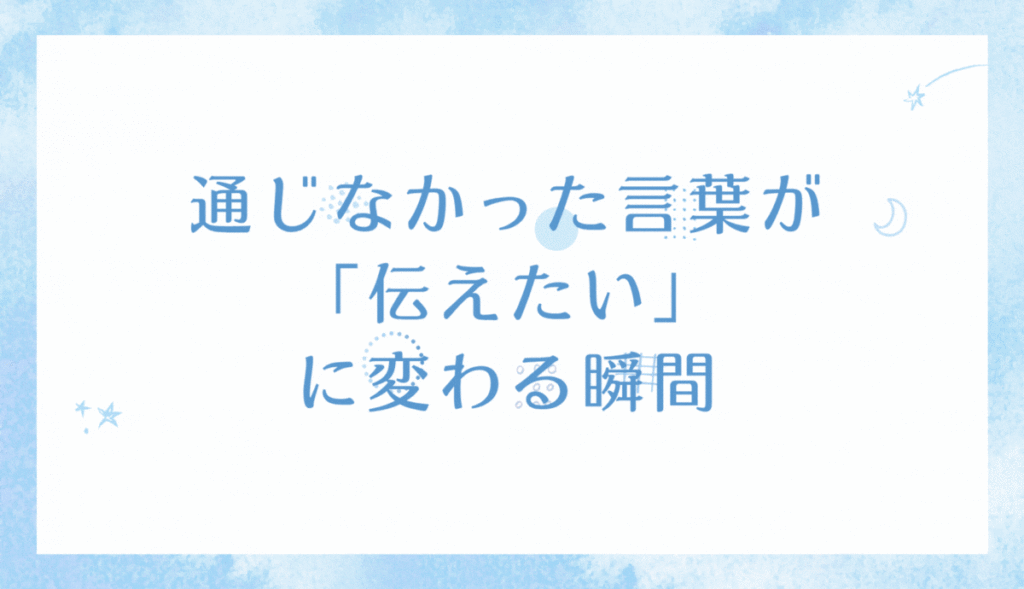
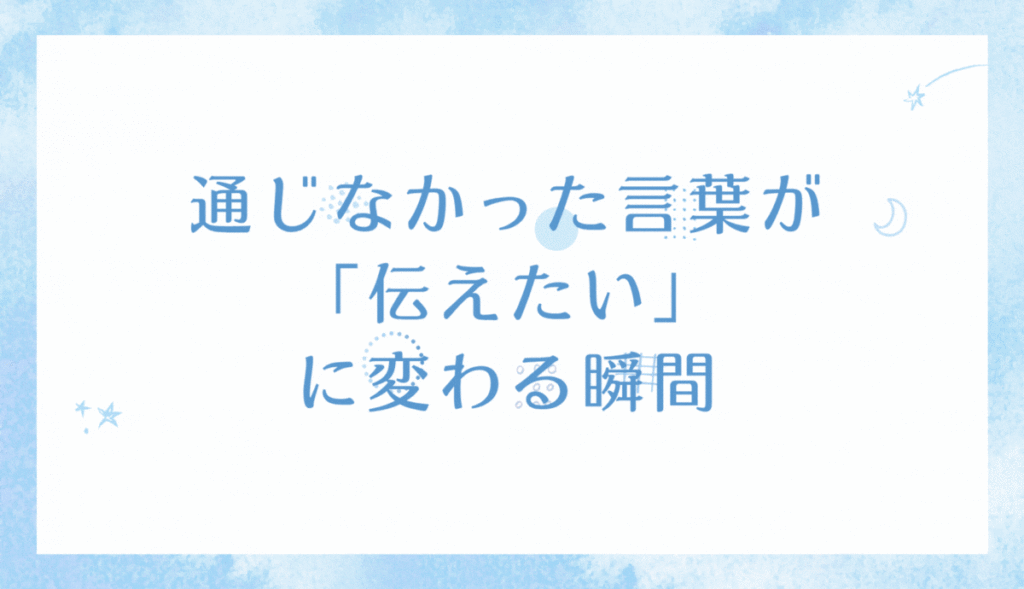
風は雲をつかまえられない。その景色を見て「伝えられなかった思い」あのもどかしさが、今はもう“もどかしさ”ではなく“動機”になってる。
笑ってごまかしたあの瞬間、本当は、もっとちゃんと話したかった。



もっと聞きたかった。もっと伝えたかった…..
もっとたくさん話したかった。
そんな気持ちが、“また会って話したい”へと形を変えていく。
もっと英語の勉強をして話ができるようになりたい、自分の思いを伝えられるようになりたい。
この「勉強したい」という気持ちは、テストのためでも、先生に褒められるためでもない。
それは、歌が、グレンとの会話を通して感じた「もどかしさ」を自分で掴み、心の奥から生まれた彼女の意志であり表現欲求でもあると思う。
異国の文化に触れて、自分たちこそ外国人なのだと気づく。見たこともない動物たち、色とりどりの野菜、そして言葉の通じない車椅子のグレン。
彼女は、未知のものから押し寄せるようにたくさんの情報を受け取った。けれど、そのどれもがある種「刺激」でしかない。
だけど、心の奥に残ったのは、「知ったこと」ではなく、「通じなかったこと」。
だから彼女が書きたかったのは、異国の文化でも、珍しい動物でも、色鮮やかな野菜でもなく、——ただひとつ。
グレンと、もっと話したかった。
その思いだけが、本当の自分の言葉として残ったんだと思う。
日本の野菜のことさえ伝えられなかった「グレンに伝えたい」という思いが、伝えるために「英語を学び、話せるようになりたい」に変わった。
つまり彼女はアメリカ旅行で得た「知識」じゃなくて、「心で感じたこと」を初めて書こうとした。
そして、その願いは「他人とのつながり」を通じて芽生えている。
「伝えられない」→「伝えたい!」「学びたい!」「また話したい!」
まとめ
この物語中で彼女が学んだのは、「世界を知る力」でもあり「自分の感情を理解して掴む力」、それから「自分の思いを伝える力」が必要なことだと思う。
それは歌の学びであるとともに、読み手であるわたしたちの学びでもあると思う。と同時に、この物語を読んで感想文を書きなさいという指示があったとしたら、ペン止まるどころじゃないだろうと思う。大人でもどうだろう。そういう訓練もいいかもしれないけどね。



あ、ごめんなさい。わたしには容易です。感想文ね。
ここを、歌と読者が同じ悩み(書けない、言葉にならない)を抱えるトラップだと表現すれば、この物語は数倍面白いね。すごいよ、この物語。
そして、作者の天才感が際立つよ。表現が分からなくてモヤモヤしてたのが、トラップという表現でようやく落ちた。わたしの中で、一気に面白い物語となった。



ようやく気付いたかい!?諸君!



お前、分かって作ってんのかよ。
偶然の産物がっ。
現場は混乱だよ。



それは、わたしが考えるところじゃないから。



考えろよ。分野も現場もミステリーになってんだよ。
このざっくばらんとした物語に、君は何を思う!?
これなのかもしれないね。問うべきは。けど、指導の力量が問われるよ。力量が無ければ、何もなくして終わる学習になる題材だと思う。それくらい難しくない?この物語。
歌は、言葉が通じなかったからこそ、自分の「伝えたい」を知るきっかけになった。
作文を書けない歌から、自分の「感情を文字にする難しさ」を知らされていると思う。想像する力も大切で、初めてのアメリカ旅行は、想像するだけでは体験が無いから難しいかもしれない。
刺激が多いと、人の脳はどうなるか?というのを知れるといいのかもしれない。体験から補うのがいいけれど、例えば、色々な種類の野菜を見て、感じることが違えば伝えたいことも変わるでしょ。
歌は「日本のナスはね、もっと細くて長いの。」って伝えたかったみたいだけど、他の誰かがいたら、もっと違うかもしれない。ナスの味の違いとかね。
日常でもそうだけれど、異質な状況に突然放り込まれたとき、人は情報の波に飲まれて、自分の気持ちを正確に掴めなくなる。
その情報を整理して、自分の中に落とし、「私は本当は何を感じたのか?」を問い続けること。それは、日々の訓練であり、考察からしか生まれない力だと思う。



だけど、何も感じたくないときがあるのも、人生の一部だからね。
例えば、ルールを支配に感じて拒絶したいとき。無秩序の中にいる方が、むしろ呼吸が楽に感じることもある。それは壊れたからじゃなく、生き延びるための手段でもあるものな。感情を閉じるのは、心が“もうこれ以上は無理だ”と判断したから。ある意味、それも自分を守る知恵だ。まぁ、閉じててもいいから、「どんな生き方が心地いいか」「違った賢い守り方はないか」を、自分のペースで選び直せたらいいのではないかな。どうせ守るなら、賢く守りたいよ。守ってるようで、自分を切ってるなら、それはナイフの無駄遣いだ。
理解することも大切だけど、伝えようとする過程で人は成長する。それが、この物語の静かな核心だと思う。
歌もさ、



異文化をもっと楽しみたい!
グレンはなぜ車いすなんだろう…
他にはどんな野菜の種類があるんだろう?
海外の動物をもっと知りたい!
これでもいいじゃない。将来の職業が変わるしね。だけど、歌が考えた末に行きついたのは、



通じなかった。もどかしかった。もっと話したい。
体験があったからこそ、彼女は“言葉の力”を信じられるようになったし、今の自分に必要なモノ(英語力)を知ることができて、その必要だと思うものを手に入れるにはどうすればいいか?を考えられるようになってる。
現実での、これの難しさよ。
ここに気付かないと、この物語は、何も問えないのではないかな。



海外にはいろいろな人がいます。海外の野菜と日本の野菜の違いは?



バーベキューは楽しそうだと思いました!



登場人物の性格を想像してみましょう!(もはや風物詩)



別にいいけど、それで終わってるところがあるとすれば、それはどうなんだろうね。登場人物の人柄や人格なんて、フレーム枠も無しに、ほとんど投影だろう。意味あるのかと思うわ。秋のサンマくらいの風物詩ってくらい、ほとんどの指導案にあって草。
登場人物の心情を想像するには、その人の人柄を想像するんじゃなくて、フレームを渡さないと意味ないよね。あと、この物語では、人柄は問わなくていいところだとも思う。ある指導案も見つけたけどね。問うてどうするのか逆に聞きたい。
意味があるどころか、心理学で言うなら融合訓練になるよ。相手を自分の中に置いて、まるで自分と同一化させる。一番やっちゃいけないやつ。破滅一直線。
自分の内側に他者を置く。どんな教育法だよ。怖いよ。
人格想像は構造ごと覆い隠すよ。人を理解した気になるしね。
本件とは全然関係ないけど、国語教育ってどうなってるんだろう?って探ってみた。
国語教育ってどうなってるの?
文部科学省「国立教育政策研究所」が出してる「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料。
↓②「ごんがいたずらを後悔する場面」、③「ごんがつぐないを始める場面」(P68)
後悔って「自分の行動を誤りと認めて、その結果を悔やみ、自己反省する感情」のことでしょ。この定義からズレてるし、つぐないもしてないものね。絶句じゃない?しかも、ここでも「性格」言ってるわ。存在そのものの不器用さを読まないといけないのにね。「性格を表す言葉を取り上げ」ってあるけど、「いたずら好き=やんちゃ」とかにするのかな?



要するにあれでしょ。ラベリング練習でしょ?
「あの人は〇〇な人だ」っていうヤツ。笑
この『ごんぎつね』の教育を受けた「児童1」を分析。ものすごく「ごん」に同調してる。児童1って、優しいけど周りに流されるタイプで、感情の処理が外向き。このタイプは、いい子のまま、内面の軸が育たない危険が恐らく高い。児童1の「優しさ」って、たぶん共感ベースじゃなく、同調ベース。つまり、「自分が悪く思われたくないから助ける」。こっち。
想像ね。指導でこうなっていったのか、元からなのか分からないけど、現時点でそうなったのか、今後これが固定するのか?ってところじゃないかな。後に「自己否定」か「他責」へ振れるんじゃない?掲載されてる感想文に「なぜ?」が全くないもの。
「正しい答え(=つぐない)」を教えると、「なぜ?」を問う思考の筋肉は育たないよね。結果「正しさ=与えられたもの」、それが崩れた瞬間、再構成不能 → 自己否定の規定路線が成立してると思う。
見本として使われているけどさ。



わたしからすると、「うなぎを取る」と「栗や松茸を送る」は同じ構造(孤独・渇望)の別表現にしか見えない。ここまで来る必要があるかどうかは、分からないけど。
本題に戻るけど、「通じない」というのは、言語の違いだけじゃない。
伝えたいのに伝えられない。その切なさや悔しさを知る人ほど、相手に届く、そして心に響く言葉を使えるようになると思う。
もし、この教育が「心情想像」ではなく「自己理解」を育てる方向にあったなら、歌のように自分の言葉で世界を掴む子どもが増えるかもしれない。そう思うと、この物語は未来の国語教育への問いでもあるかもしれない。国が力を入れてるとは言えよ、「心情想像」という単語の独り歩きが過ぎるよ。それは性格じゃない、フレーム枠を渡した後の問いだから。国ごと間違えてるのか、途中でどっかの機関が歪んでるのかどっちなんだか。
――通じなかった言葉が、歌のはじまりになった物語。
そして、心情理解が他者との融合になっていることに気づけって話。



持論です。
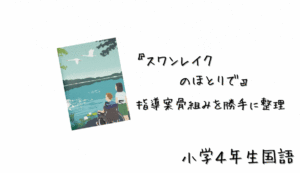
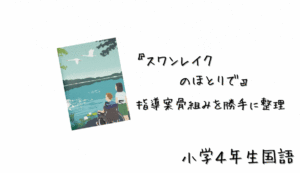

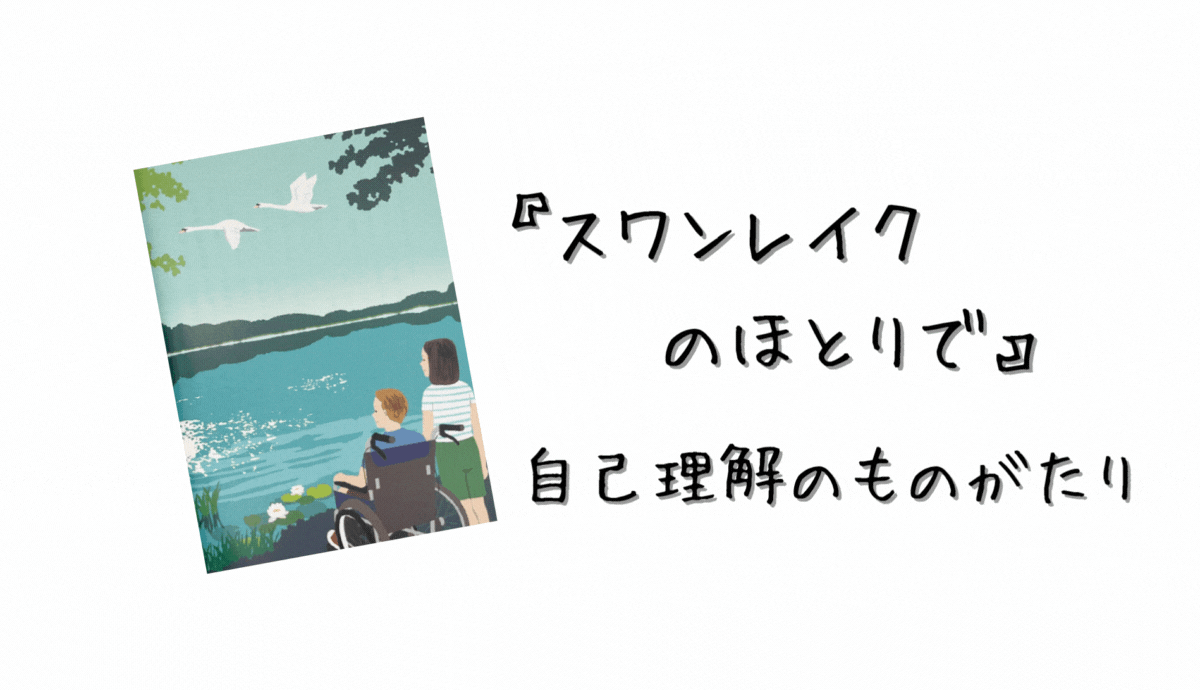
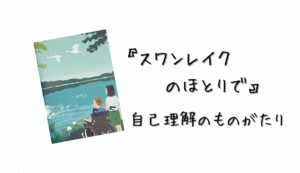
コメント