私たちの文化や社会の基盤を形成している西洋思想は、古代ギリシャの哲学者たちが人間の存在や知識、倫理などについて問いを立て、理性的に探求したことに起源を持ちます。

西洋思想の歴史的な流れが、確実に現代に根付いていて、私たちがそれを受け継いでます。すっごく受け継いでる。
本ブログでは、この西洋思想の歴史的な流れと、各時代の代表的な思想家や思想の特徴を、個人が勝手に解説しています。
古代ギリシャからはじまり、中世、近世、近代へと続く哲学の発展の軌跡を辿り、私たちの価値観や考え方の根源を把握しておくと、西洋・東洋両思想の重要性を知りやすいのではと思います。ちなみにわたしは、子育てに役立ててます。
西洋思想とは?基本の基本をわかりやすく
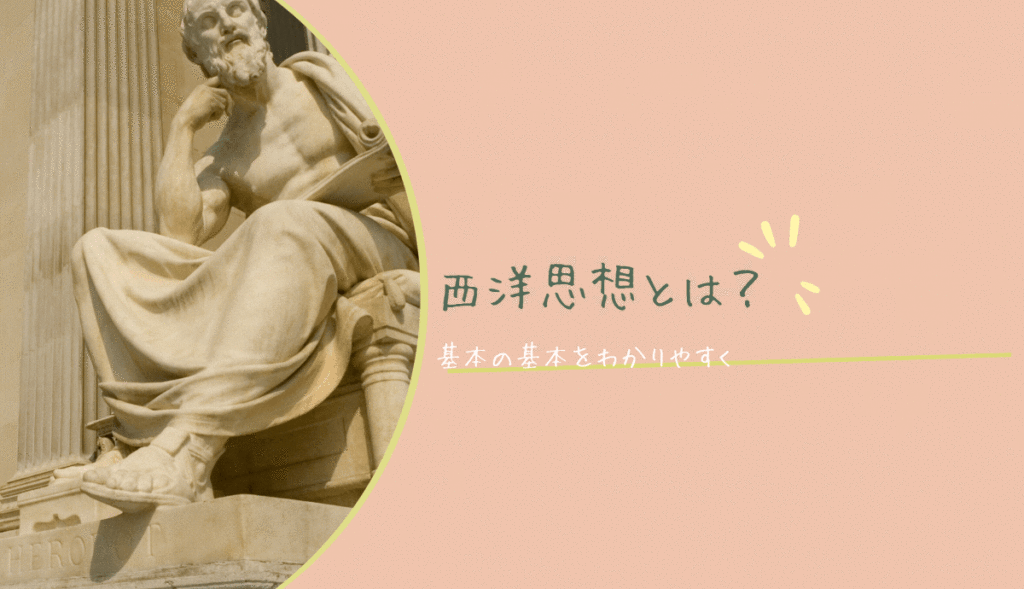
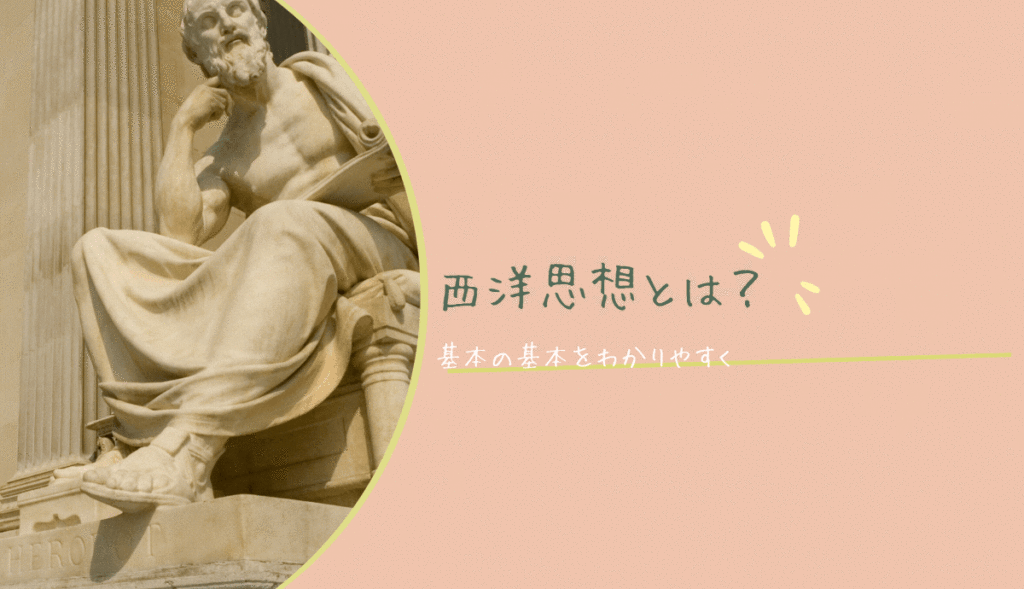
西洋思想(せいようしそう)とは、主に古代ギリシャから始まり、中世、近世、近代にかけて発展してきた哲学的思考の体系を指します。
この思想は、現代の文化や社会の基盤を形成しているため、無視することができない重要な分野。
- 西洋思想の起源
- 主な流れと特徴
- 西洋思想の重要性
①西洋思想の起源
西洋思想は、紀元前6世紀ごろの古代ギリシャ哲学がその出発点とされてます。
哲学者たちは、人間の存在や知識、倫理、政治などについて問いを投げかけ、それに対する理性的な答えを探求。ソクラテス、プラトン、アリストテレスといった哲学者たちによって、論理や倫理、形而上学といった基本的な概念が形成されて行きました。
②主な流れと特徴



西洋思想は、主に以下の四つの時代に大別されて進化してきました。
- 古代ギリシャ哲学 – 知恵を追求し、理性的な思考が育まれた時代。
- 中世哲学 – キリスト教の影響を受け、宗教と哲学が融合し、信仰のもとに倫理が論じられる。
- 近世哲学 – 理性の重要性が高まり、神学(キリスト教)からの独立が模索される時代。科学革命が進行し、経験と論理に基づく知識の探求が行われる。
- 近代哲学 – 近代的な思索が生まれ、特にカントの登場により神と哲学の関係が大きく転換。
③西洋思想の重要性
西洋思想の特徴は、その論理的な思考の方法にあり、以下の点が特に注目されています。
- 論理性:古代ギリシャから続く厳密な論理構築により、知識を体系的に整理する能力が育まれる。
- 対話の重要性:ソクラテスの対話法に象徴されるように、他者との対話を通じて真理を探究するスタイルが根付いてます。
- 倫理的視点:人間の行動や社会の仕組みに対して倫理的に考える姿勢が強調。
これらの特徴は、法律、政治、倫理学、科学、文学など、さまざまな分野に影響を与え続けています。さらに、西洋思想の探求は、単なる学問にとどまらず、私たちの日常生活や価値観にも深く根付いてます。すごく根付いてる。
これが西洋思想の基本的な大体の概要。



それと、ソクラテスの問答法はこんな感じ。対話式で矛盾を追求していく感じ。論破系ですよね。
A:可哀そうな人を見た
B:何で可哀想と思ったの?
A:いじめられて、泣いてた
B:泣いてたら可哀想なの?
A:いや、誰も助けてなかったから
B:誰かに助けられてたら、可愛そうではなかったんだね
A:うん、いじめてた奴らが許せない
B:あなたは何をしていたの?
A:…………………遠くから見てた
B:あなたが言っていることは矛盾しているよ。誰も助けてなかったというあなたもまた、助けていないじゃない
A:…………………



はい、論破。
あと、ソクラテスと言えば『無知の知』、これは『気づき』と同意なのではと思います。
文字通りの意味は『無知であることを知っていること』が重要であるということ。 要するに『自分がいかにわかってないかを自覚しなさい』ということで、 言い換えると『知らない』状態よりも『知らないことすら知らない』状態の方が危ういということです。ほーんと、危うい。


ギリシャ哲学からはじまった西洋思想の歴史
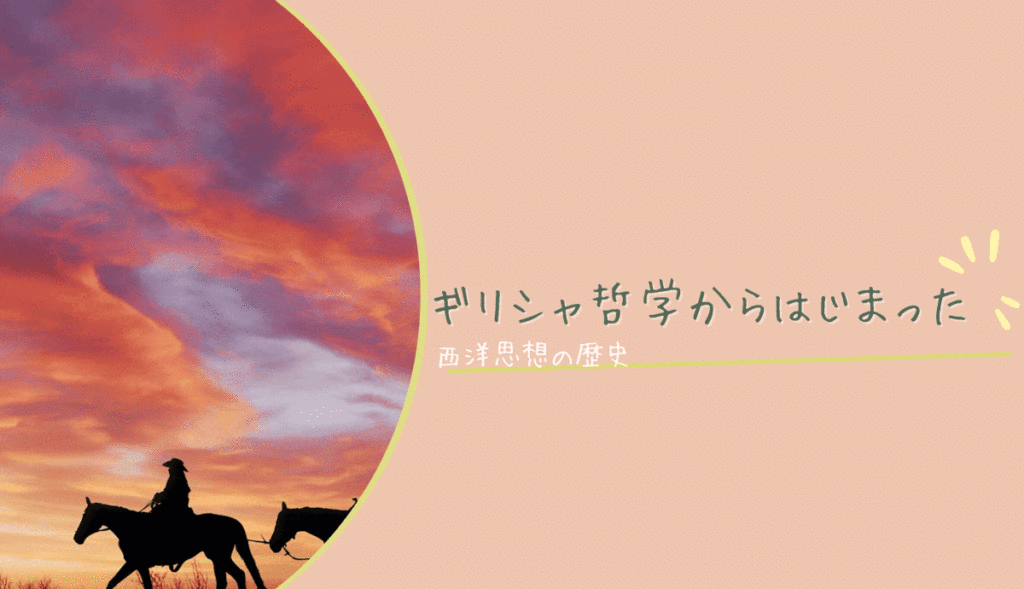
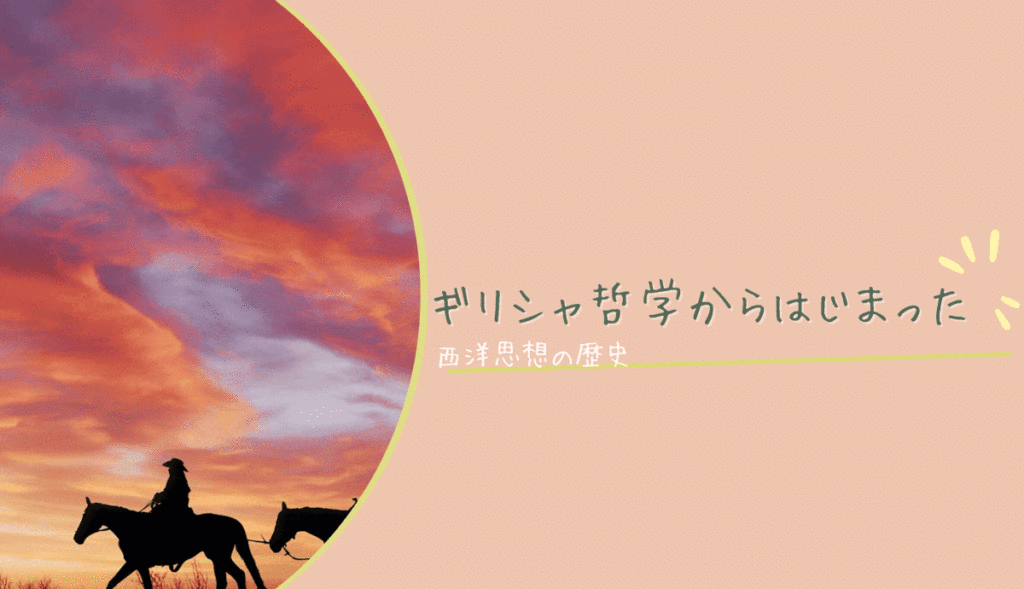
西洋思想の歴史は、古代ギリシャに遡ります。哲学の始まりとされるギリシャは、知識を追求する姿勢が芽生え、多くの偉大な思想家たちが登場した場所です。



ここでは、ギリシャ哲学がどのように形成され、発展してきたのかを整理してみることにします。
- ギリシャ哲学の起源
- 哲学の発展と時代背景
①ギリシャ哲学の起源
古代ギリシャにおいて、哲学は神話や宗教の枠組みを超えて、自然や人間の存在についての理論的考察が行われるようになりました。
最初の哲学者であるタレスは、『万物の根源は水である』と提唱し、物事の本質を探ることの重要性を示した人物。
これまでの神話に依存するのではなく、自然現象を科学的に理解しようとする態度は、哲学の新たな道を切り開くことになり、西洋哲学の祖とも呼ばれています。
その後、ギリシャ哲学は以下のような流れで発展していきました:
- ミレトス学派:タレスの後に続くアナクシマンドロスやアナクシメネスは、万物の根源についてさらなる議論を展開。彼らの考えは、後の哲学者たちに影響を与えました。
- ソクラテス:古代アテネの黄金期に登場したソクラテスは、倫理的な問いを立て、真実を探求。彼は『知を愛する』姿勢を強調し、弟子のプラトンに多大な影響を与えました。
- プラトンとアリストテレス:プラトンは『イデア論』を提唱し、理念の世界を強調。一方、アリストテレスは現実的な観点から哲学を探求し、倫理や政治学の形成に寄与しました。
②哲学の発展と時代背景
古代ギリシャでは、ポリス(都市国家)が形成され、市民たちが集まり、自由な議論や論争が行われました。このような環境は、哲学が育まれる土壌になります。また、競技会や芸術活動が盛んであったことも、思想の発展に関係しています。
- 競技会:オリンピア競技会などの催しは、都市間の交流や文化的な発展を促進。
- 文化的背景:ギリシャ神話から影響を受けた哲学者たちは、神話を背景にしつつも、より論理的に物事を探求しようとしました。これにより、文化や価値観が哲学に反映されることとなります。
ギリシャ哲学は、単なる学問の体系にとどまらず、西洋の文化の基礎を形成。
その後の中世哲学や近世哲学、そして近代哲学へとつながる道筋を作ることになります。このように、西洋思想の大きな流れは、古代ギリシャから始まった哲学的探求の基盤です。
中世哲学の特徴:キリスト教と哲学の出会い
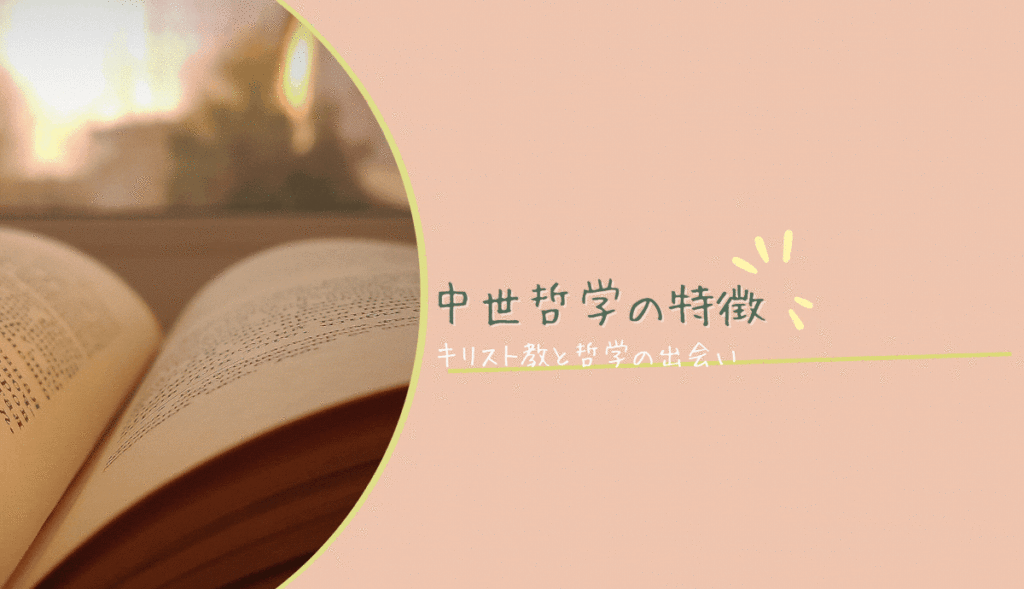
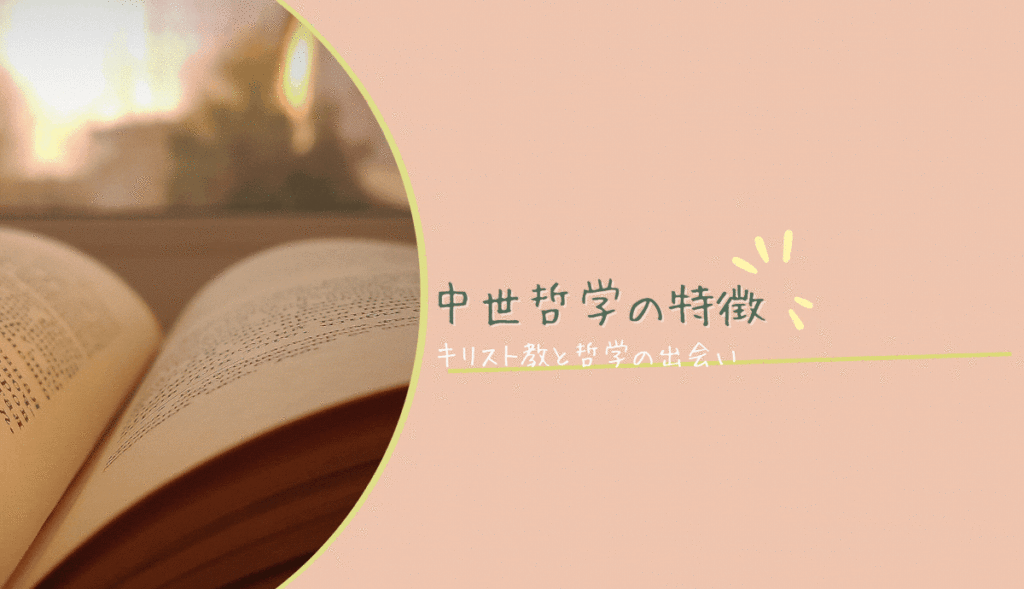
中世哲学は、キリスト教の影響を色濃く受けながら進化した思想。
その中でも特に、理性と信仰の調和を模索することが主要な特徴として挙げられます。
アウグスティヌスなどの教父たちは、この時代に信仰と哲学の接点を探り続け、重要な役割を担いました。



ココでは、中世哲学の特徴について詳しく解説し、その背後にある文化的背景を考察してみます。
- キリスト教と哲学の融合
- 教父哲学の誕生
- スコラ哲学の発展
①キリスト教と哲学の融合
中世の思想家たちは、古代ギリシャの豊かな哲学的理論を基に、キリスト教の信仰と融合させることを考案。この過程では、以下の重要な試みが見られました。
- 信仰の理論化:理性を用いてキリスト教の教義を支える理論の構築が行われる。
- 論理性の重視:アリストテレスの論理学を取り入れ、神や宇宙の存在に関する深い考察が展開される。
アウグスティヌスは特に注目すべき哲学者であり、彼の名著『告白』や『神の国』は信仰と理性の調和に向けた試行錯誤を描いています。彼はプラトンの思想を基にし続けながら、万物の真実を探究し、神の存在を常に意識。
②教父哲学の誕生
中世哲学における『教父哲学』は、キリスト教の信仰を広めるために古代ギリシャ哲学を巧みに利用し、アプローチする手段として用いられました。
③スコラ哲学の発展
中世の後期には、スコラ哲学が大きな影響を持つようになります。この哲学は、教育機関で広く学ばれ、特にトマス・アクィナスによって完成。彼は哲学と神学の統一を目指し、以下の特徴が大きな役割を果たしています。
- 神の存在証明:アクィナスは神の存在を理論的に証明するための『五つの道』を提唱し、神に関するの立証、論証を行いました。
- 自然と超自然の調和:宗教と哲学の間の縺れを解消するため、キリスト教とアリストテレス哲学を総合。
このように中世哲学は、信仰と理性の間の対話を通じて多くの発展を遂げ、その考え方は後世の思想にも大きな影響を与えることになります。これらの背景を理解することで、近世哲学や近代哲学との関連性を探ることができ、より深く理解することができます。
近世哲学:理性の時代への大きな転換点
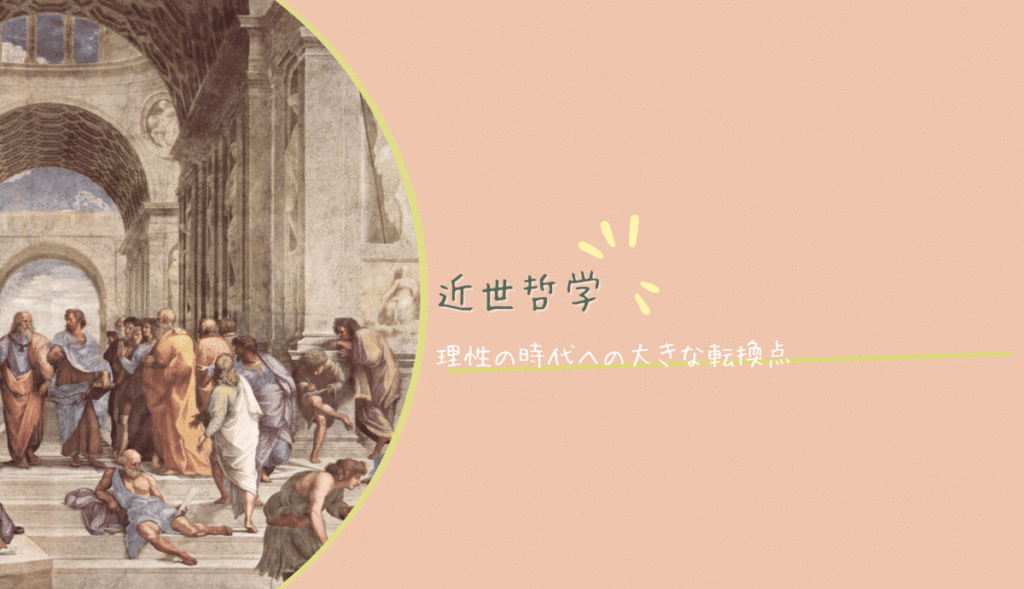
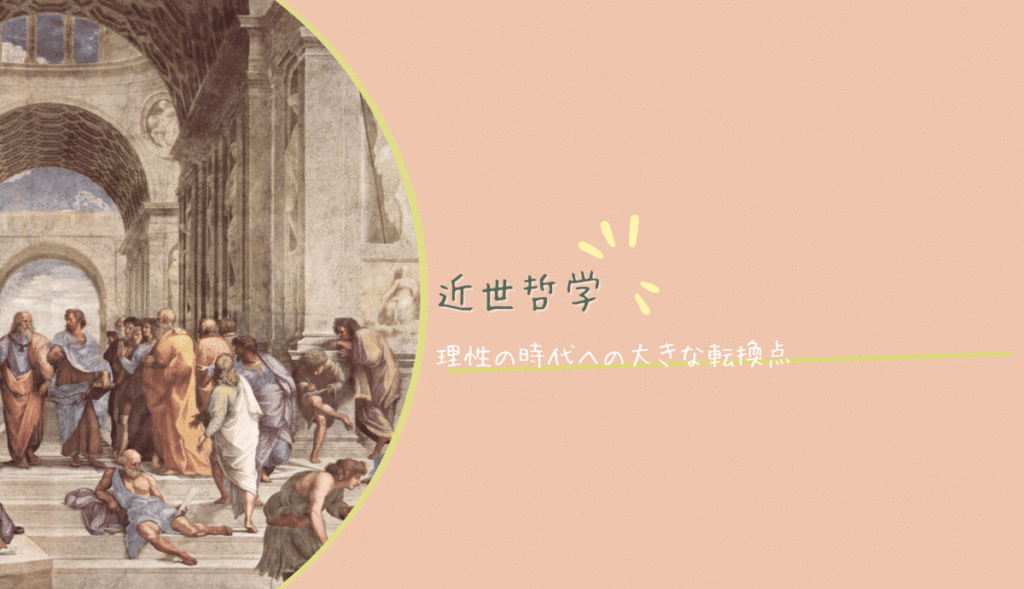
近世哲学は、17世紀から18世紀のヨーロッパにおいて、理性が中心的な役割を果たす新しい思想の時代を特徴づけています。



この時期、宗教的な権威の失墜と自然科学の急速な発展が相まって、哲学の方向性が大きく変化しました。ココでは、近世哲学の背景とその重要な特徴について詳しく見て行きます。
- 近世哲学の背景
- 合理主義と経験主義の対立
- 理性の役割
①近世哲学の背景
近世哲学の誕生は、宗教改革や科学革命と密接に関連しています。
カトリックとプロテスタントの対立が深まる中、伝統的なキリスト教の教えに対する疑念が高まることに。
特にコペルニクスやガリレイ、ニュートンといった科学者たちの研究が、自然界の理解を根本から変え、『神』とも言える存在を合理的に考察する基盤を作ります。キリスト教による圧倒的支配が終わり、『理性教』(合理主義)に主導権を明け渡すことになったキッカケの哲学者たちです。
このような状況下で、哲学者たちは理性を基盤にした新しい思想を展開。
②合理主義と経験主義の対立
近世哲学の中心には、大陸合理主義とイギリス経験主義という二つの主要な潮流があります。
合理主義の根幹には、『人間は賢い、論理的にしっかり考えれば知識を得られるはずだよ』という価値観があります。一方、経験主義の根幹にある価値観は、『人間はそこまで賢くないし、経験や実験によって新しい知識を獲得して行こうよ』というもの。
◎大陸合理主義(デカルト、スピノザ、ライプニッツなど)
理性を唯一の真理探求の手段として位置づけ、神の存在を前提にした哲学を展開。『我思う、ゆえに我あり』のように、自己の存在を出発点とする考え方を強調。
『自分はなぜここにあるのか』と考える事自体が自分が存在する証明であるという意味。
◎イギリス経験主義(ロック、バークリー、ヒュームなど)
経験と観察を重視し、神の存在を否定する立場から始まる。人間の認識や知識は経験から得られるという考え方を主張するもの。経験を通じて得られる知識が真理に近づく鍵であるとし、『人間は万物の尺度である』という考えを展開。
『個々の人間の知覚こそ真理の基準であり、絶対的な真理は存在しない』という意味。
- 経験や観察を通じて、実態があるから理屈はこうなんじゃないか、と考えていく方法
- 思い込みや偏見を捨て、実際に見聞きしたことを根拠に思考することを主張
- 実験や観察からデータを集め、それをもとに一般的な理論を導き出す方法を帰納法と言う
③理性の役割
近世哲学では、理性の役割が非常に重要視されました。この時期の哲学者たちは、理性を通じて世界を理解し、真理を追求していました。
ドイツ観念論:カントが変えた西洋思想の新しい形
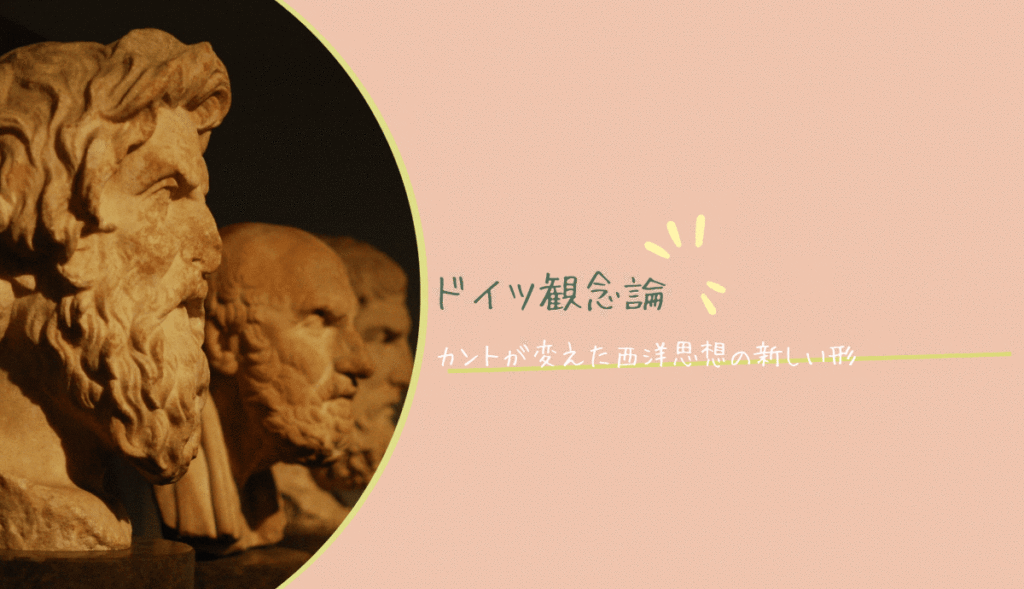
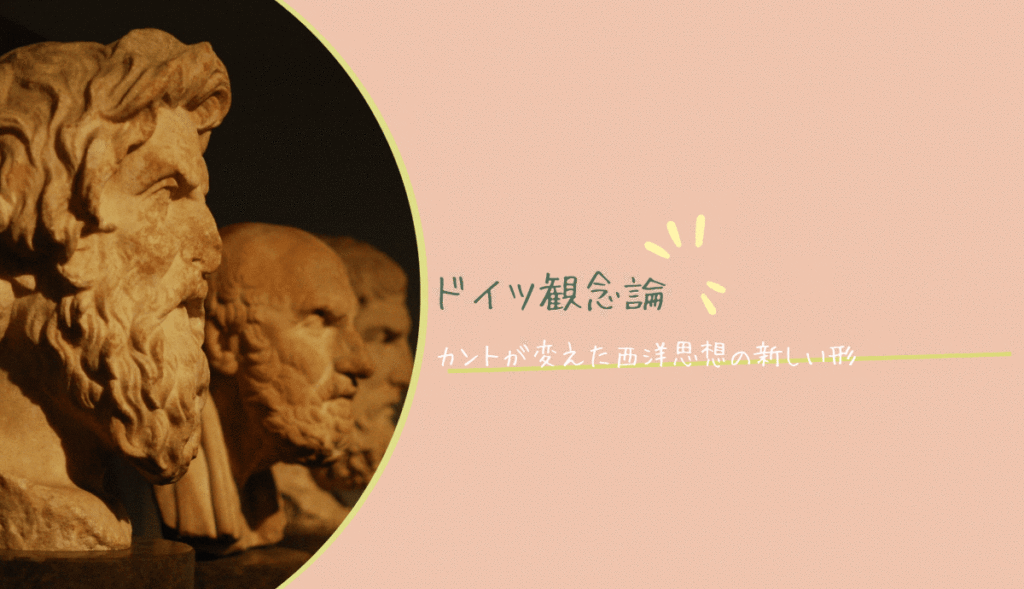
ドイツ観念論は、18世紀末から19世紀初頭(1781~1831年)にかけて、ドイツの哲学界で誕生した重要な思想潮流。
上で紹介した『合理主義』と『経験主義』は、イマニュエル・カントの登場によって『統合』されたと考えられています。
この時期、カントは革新的な理論を展開し、西洋哲学に劇的な変化をもたらしました。カントの思想を理解することは、ドイツ観念論の全体像をつかむうえで不可欠です。
- カントの認識論とその影響
- ヘーゲルと絶対精神の概念
- ドイツ観念論がもたらす新たな視点
①カントの認識論とその影響、定言命法
カントの哲学の中でも特に注目すべきは、彼の認識論。
※ちなみに、認知の概念の起源をさかのぼると、古代ギリシャの哲学者ソクラテスにたどり着きます。
カントは、学問や知識がどのように構築されるかを深く考察。カントの代表作『純粋理性批判』では、以下のような重要な概念が提起されています。
- コペルニクス的転回:従来の『われわれの認識が対象に従う(主観)』という考え方を覆し、『対象がわれわれの認識に従わなければならない(客観)』と主張しました。これにより、認識の主体が主体的であることを強調。
- 認識の限界:カントは、人間の認識には限界があることを説き、経験に基づく知識が必然的には普遍性を持たないことを指摘。この点は、後の哲学者たちに大きな影響を与えました。
わたしは『話すのが苦手』、『マイナス思考だ』(主観的)
わたしは『話すのは苦手だが、人の話を聞くのが得意だ』、『間違えると、マイナス思考になってしまう』(客観的)
認識の限界というのは、人間の認識は、経験できるこの世(現象界)のことに限られ、神や魂の不死など、この世を超えたこと や、事物そのもの(物自体)を認識することはできないということ。
多分、幽霊を見ても、あちらが『わたし、幽霊です、出ちゃいました。』って言わない限り、分からないってことだと思う。



・・・・・・・・・!!!!(怖)
人は得体の知れないものは認識できないってことでしょう。
そして、カントと言えば、人は誰でも『守らなければならない、自ら立てた道徳的な法則に従って、命令を受けたわけでもなく、見返りを求めることでもなく、ただそれが義務だから、という理由で行えることこそ人としてあるべき姿、意志の自立を自由』とした哲学者。
例えば、困っている人は助けるべきだ。とか。
では、どんな動機で行動すべきか?カントは『助けるのが当然』という義務として行動することこそが、道徳的だとしました。これは『仮言命法』と反対の『定言命法』という考え方です。
仮言命法:『友達が探し物をしている、ここで助けたら自分をよく思ってくれるだろうから、助けよう』
定言命法:『友達が探し物をしている、一緒に探そう』
仮言命法は『困っている友達を助けてよく思われたい』という欲求を伴っているのに対して、定言命法は『友達を助けることに理由はいらない』と当然の行動としています。



『他の誰からの命令を受けたわけでもなく、また見返りを求めることでもなく、ただそうあるべきだと自ら行うことこそが道徳的であり、人としてあるべき姿だ』というのが、カントの導き出した『道徳』の結論。それが人格にもなる。
さらに、黄金律のような倫理観『他人にしてほしいことを(正義的に正しいと考えられるなら)、まず自分が他人にするべき』とも共鳴する部分がある。
他人に優しくすることは道徳的行為かもしれませんが、自分が優しくされたいからそうしているともいえる。『仮言命法』にもとづく行為は、つまるところ自分の利益を優先する行為であり真の道徳的行為とはなり得ないというのがカントの考え方。
超絶善人だからこその教え。



わかるけど、あなたにしかできないかも。
教え方ひとつだと思うんですよね。
話は逸れますが、『他人に優しくされたいのなら、まずは自分に優しくありなさい』がわたしの思想です。この辺りからアドラーを取り入れて行った。人間の尊厳や自律性を重視するところ、人間観など、両者の思想には共通するものがあるように思われますが、少し違いますね。ちなみにアドラーは仏教に影響を受けていた言われています。
『他人に優しくされたいのなら、まずは自分に優しくありなさい』
補足すると、自分に優しくもできない人が他人を大事にする術を知るはずはないから。他人に優しくなんて、できっこないんですよ、知らないんだから。どうやったら嬉しいか、喜ぶかを。
こう教えています。
いません?そっとしておいて欲しいときに、『元気だせよ!あんなことくらいで!人生で見ると大したことないって!』とか。



あんなことって何だよ。
善意のつもりが、悪意にしかなってないっていう。『あんなことくらい』と決めるのはそもそも本人にしかできないことだし。それすらも分からないヤツが何の様だよっていう。
あと、ガリガリに痩せて倒れそうな人から、これどうぞってリンゴ出されて快く受け取って食べることができますか?負の連鎖しか生まないでしょう。
それをできるってことは、そういう人(ガリガリに痩せた倒れそうな人からもらったリンゴをひとりで頬張るような人)が周りにたくさんいると思ってるってことでしょう?そんな人、いないって思えるその思考が他人への優しさに繋がって行くと私は思うんですよね。



話題が逸れた・・・(ゴメンナサイ)
戻ります。真の道徳も大事でしょうが、『友達によく思われたい』というその承認欲求はなぜ生まれるのでしょうね。よく思われないとどうなるんでしょうか。



お金もらえたりするの?
そういうところから道徳論を論じればいいのかなと思います。
人格ベースで語るのであればわかる。けど、ギバー・テイカー・マッチャーの思考は必要かとも思う。



欲があっても、人が助かるなら良くない?っていうのが私で。けどその事象だけで見ると、カントの考え方が正しいんでしょうね。もっと俯瞰的に見るなら、自分のための行動で人が助かるんだったら、それで良くない?結果を言うなら、そんな下心、どうせすぐバレるって、、、ていう。論点はズレてるかもしれないけど。もっと言うと、友達に『自分をよく見せたいから、助けるわ』って言えばいいと思う。やっぱ論点ズレまくり。『そういうこと言ってんじゃねーんだよ』ってカントに殴られそう。



・・・・・・。
気になる記事も見つけたので飯塚毅博士と私や啓蒙期ヨーロッパにおける儒教情報の流入をどうぞ。
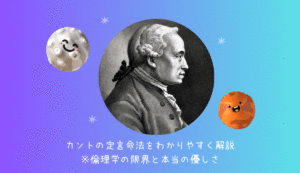
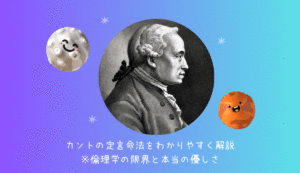


②ヘーゲルと絶対精神の概念
カントの理論を受け継ぎ、発展させたのがヘーゲルです。



ヘーゲルは『絶対精神』という概念を導入し、精神がどのように自己実現に至るかを論じました。彼の弁証法的論理は重要です。ポイントは以下の通り。
- 弁証法的統合:対立する要素が融合することで新しい真理が生まれる過程を示しました。これによって、個人の精神と共同体の精神がどのように相互に影響し合うかを考察。
- 絶対精神の達成:ヘーゲルは、個人と社会の関係性を通じて、最終的には絶対精神(人間の精神活動の最高段階に達した状態)に至る状態を目指しました。この考え方は、後の歴史的発展や社会的動向に大きな影響を与えました。
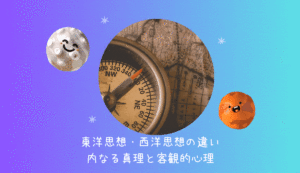
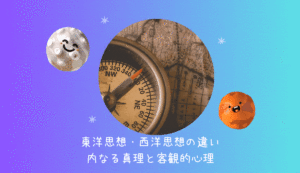
この弁証法的思考を繰り返して、絶対精神にたどり着くことができる。としたのがヘーゲル。



絶対精神とは、それはカントが考えていた人間が認識している現象(主観)と、存在の実像である対象(客観)を一致させたもので、人間の知識や意識が最終的に到達する完全で包括的な真理のことを指します。
例えば、経験し、学んできた知識が一つの巨大な意識や知識として統合されていくようなイメージ。
先ほどの、話すのが苦手で、マイナス思考なわたしの概念で説明するなら、
わたしは、話すのは苦手だけど、人の話を聞くのは得意、間違えるとマイナス思考になってしまうところがあるが、その間違いを慎重に吟味し、次の成長の糧にできる力を持っている。自分で把握して知識として理解できている。つまり、自分自身を分析して得た知識。
ここまで理解できて十分。(メタ認知)
さらにここから一歩踏み込み、得た知識を生かし、不得意とする分野への対処法までを把握できてはじめて自分を生かすことができる。自分を認識できているので、どのような職場でも力を発揮できる人となり、社会で必要とされるようになる。
多分、こういうこと。自分のマイナス面とプラス面を融合させて、たどり着く境地。(弁証法)
これが個人ベース、この考え方を身につけて行く手段として、これを繰り返すだけではなくて、世の中の色々な事象や人を対象にも応用させてみる。『弁証法的思考』を身につけたとき、洞察力と予見力が身につく感覚、物事を点で見る感覚ではなくて、線で見る感覚です。
- バレー部で全国優勝を目指している
- 部員全員が威圧的な監督を嫌っている
このことを単体で見て、保護者からクレームが出たとしましょう。そこから、安易な選択をするとすれば、監督を変えてもらう方針に動く可能性もある。
違った目線で見てみると、その監督のお陰で、チームの団結力が増してたらどうでしょうね。そういう洞察は大事だと思います。
ひとりの人を皆で嫌うって、ある種団結力が増すんですよ。部活という短時間なら、相手は指導者だし悪くない選択です。
あとは優勝へ導くだけの指導力があるかどうかの確認が必要になる。
監督のお陰で団結力が増し、指導力があることが分かる。チームが大会で優勝に向かって突き進むことを目標として掲げているのなら、必要不可欠な存在ということになります。
威圧的な監督に目線・意識を奪われるということは、女子特有のいがみ合いだとか、小さな事件を気にすることなく済んでいる可能性もある。大きな問題があると、小さな問題は浮き彫りにならずに気にならないんですよ。



皆、大きな問題を排除しようとするけれど、その監督に対して威圧的だと感じて愚痴を言うレベルということは、排除したところで、今度は小さな問題への愚痴が始まりループを生むだけなんですよね。そこには、人が気が付きにくい罠がある。
すると答えはこうなる。
という結論に達する。西洋的弁証法の指導だと、こういった感じになるでしょうね。監督を変えることに意味が無い。
テーゼ(命題)は監督が厳しすぎる。アンチテーゼ(反対命題)は監督を変えるべき。統合したジンテーゼ(統合命題)は監督を維持しつつ、指導に寛容性を持たせる。
こういう見方を容易にできるようになると、世の中の出来事も同じように見えてくるということだと思います。
視野が広がり出して、人生を読みだす。
人生で言うなら、過去の出来事があり、今がある、そして未来に繋がる。それを繰り返して行くと、絶対精神にたどり着く。
これが五次元思想のことだと思う。多分、これで合ってる。
歴史は、①ある安定した段階で、②矛盾が生じ、③次の時代に入る(例:絶対王政・革命・民主国家など)という三段階で展開されます。
ヘーゲルによると歴史の発展段階をになっている代表的な偉人も、歴史の目標を実現するための手段(道具)として登場します。ナポレオンのような英雄は、いわばあやつり人形にすぎず、一定の役割がすめば没落するとされました。今では、歴史の法則性という考え方は古いように思われていますが、もしかしたらそれもアリかもしれません。
DIAMOND ON LINE
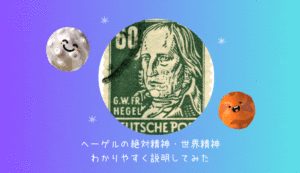
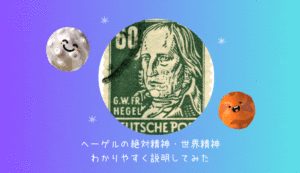
わたしも、『歴史の目標を実現するための手段(道具)として登場します。ナポレオンのような英雄は、いわばあやつり人形にすぎず、一定の役割がすめば没落する』こう考えています。
ただ、歴史の法則性という考え方が古いかどうか、ナポレオンがどうか知りませんが、そう見る方が自然である、そういう感じです。そして、運命は変えられなくても、岐路の行動がどうか?で没落の仕方は変えられたかもしれないとも思う。私は、そういう考え方でいます。没落の仕方にも色々あると思うんですよ。
もっと言うなら、岐路の行動が変われば、運命も動かせる可能性があると思ってます。
変えなくても、彼は彼でこれで良しとしていたかもしれないんですよ。例です、たとえ話。



要するに、一定の役割がすめば没落するところで、没落の仕方は彼の行動次第で選べたのではないか?歴史の一部と見るのか、彼の人生と見るのか、そういう目線。歴史の一部と見るならば、そういう選択をさせられたのか、したのか、どの道終わり(運命)だった。彼の人生と見れば、単なる自業自得とも感じられるし、目的は果たせたと見るのか、どうだろう、見方は色々。その都度、最良の選択ができていたのだろうか。個人的にはですよ、できててアレってある?感はあります。
今度はナポレオンに殴られそう。



・・・・。
もっともっと俯瞰的に見た場合は、世界的歴史的なパラダイムで言うなら『最良の選択』だったんでしょうね。没落の仕方はどうだっていい。没落に意味があるから。
ナポレオンと並ぶとか、そういう大それた意識は到底ありませんけど、そういった俯瞰的視野で自分を見たときに、所詮あやつり人形に過ぎないよなと、ふと思うこともあります。ありませんか?



あやつり人形だとしても、世の中のためになっている『あやつり人形』であれば、他者貢献になってるし。見えない力に使われてる感あるな、白羽の矢か。ここでの白羽の矢のための今ままでか?とか。これからのための白羽の矢か?ともあれ、自分が納得して、色々なパラダイムを見ておく必要があるし、あやつり人形だとするなら、あやつり人形としての役割を果たせているのかどうか。とかね。引かないでね。
世界で色々なことが起こるけれど、そのときそのときに応じた主要人物が現れて、良い方向へ進むように流れているのでは?という見方が自然かなと思うことがあります。
小さく言うと、自分の周りをそう見る、世の中もそう見る、つまり、③に至るまでの時間をあらかたの概念でたたき出す。私はこういうことを普段からしていますね。
あのときこうしていれば、、、そう考えるのか、どの道この結果はこうなっていたと考えるのか。大事なのは、どの道こうなっていたと思えることじゃないでしょうかね。あのときこうしていれば、、、という考えが生じるということは、後悔がある。どの道こうなっていたと思えるということは、後悔が無いんですよ。
あらゆる方向から流れを読み、どの道こうなっていたとするならば、そこからどうするのか。また流れの読み直し。すると岐路が分かる、その岐路の修正が効くかどうか。そういう読み方ですね。岐路を見抜かないといけない。
わたしで言うなら、②の段階で生じる矛盾の大きさによる、そういう見方もします。矛盾が大きければ大きいほど、③での出来事が大きくなったり、早まったりする。世界で言えば、②が戦争なら、③は更地、そんな感じかも。
こういうことだと思う。これができるようになると、世の中の流れが分かりだすから。多分。



成長し続けた結果、何事にも動じない、自分に向かってくる異質な力が何ひとつなくなったときに、絶対精神を獲得できる、こんな感じかと思います。多分こうでしょ?という感じ。
ただの個人の見解です。ヘーゲルを全体的に支持しているとか、ナポレオン批判とか、そういうものではなくて、ヘーゲルのこの見解は合ってると思う、と、柄にもなく真面目に語りました。
ヘーゲル哲学の特徴は、存在論、論理学、認識論が重なり合い融合していることです。
③ドイツ観念論がもたらす新たな視点
ドイツ観念論は、個人の自己意識や精神の発達に焦点を当てることで、従来の哲学から大きく転換。その結果、以下のような新たな視点が生まれました。
- 主体性の重視:人間の認知や経験を通じて知識が形成されることを強調。
- 社会と個人の相互関係:個人の自由と共同体の構造の関係性を探究。
- 批判的思考の促進:既存の価値観や知識に対する批判を通じて、新たな理論の展開を促しました。
ドイツ観念論は、19世紀以降の思想に多大な影響を与え、社会科学や人文学の発展に寄与。
『現実的であるものは理性的であり、理性的であるものは現実的である』(意味)現実的なものはすべて合理的であり、合理的なものはすべて現実的であるという意味。
『真実なものは全体である』(意味)個々の部分ではなく、すべてを包括した全体こそが真理であるという、ヘーゲル哲学の核心を表現。
合理主義:物事の処理を理性的に割り切って考え、合理的に生活しようとする態度のこと。哲学においては、感覚を介した経験に由来する認識に信をおかず、生得的・明証的な原理から導き出された理性的認識だけを真の認識とする立場を指します。
コトバンク
後の産業革命などは、ヘーゲルの哲学的基礎づけと共に進行して行ってます。
まとめ
西洋思想は、古代ギリシャから始まり中世、近世、近代と発展してきた長い歴史を持ち、現代社会の基盤を成しているのを、なんとなーく分かっていただけたでしょうか?
やっぱり、自分の考え方の基礎になる部分が多く、改めて、東洋思想だけではなく、西洋思想の重要性を認識させられる。
論理性や対話の重要性、倫理的視点といった特徴が様々な分野に影響を与え続けていて、中世哲学では信仰と理性の調和が探られ、近世哲学では理性が中心的役割を果たしました。
さらに、ドイツ観念論では個人の主体性や社会との関係性が重視されるなど、西洋思想の発展が凄まじく、西洋らしい批判から始まる発展の仕方も面白い。
これらの知見を踏まえた上で、私たちは現代の課題に対して、東洋思想と西洋思想を見直し、融合させることに大きな意味があると思っています。

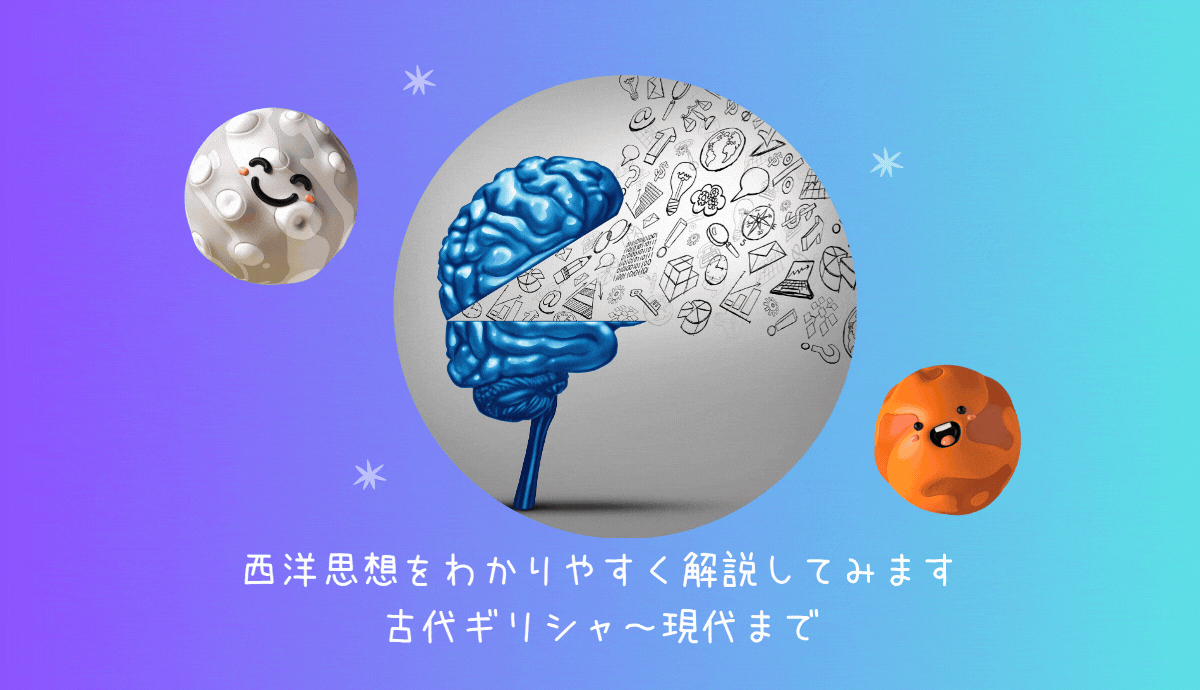
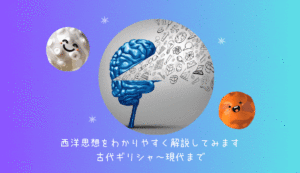
コメント