成功するギバーが、一体どういうギバーなのか気になっていますか?
ここでは、、
- ギバーの特徴
- 成功するギバーとそうでないギバーの違い
- ギバーとして上手に行動するためのコツ

などをまとめてみました。是非参考にされてみてください。
成功するギバーとは? ギバー、テイカー、マッチャーの違い
世の中には、主にギバー、テイカー、そしてマッチャーという3タイプの人間が存在しています。
その中で、他人への思いやりの心を持った人々が『ギバー』と言われている。



この3タイプは、それぞれの成功の在り方や人間関係の築き方が大きく違ってるんです。
↑『与える人』こそ成功する時代ってなってるけど、世の中、おそらくずっとこうなってる。
ギバー※与えることを重視する人
ギバーは本質的に『与える人』。
他者の利益を優先し、喜んでもらうことに喜びを見出す傾向があります。
ギバーは自身の成功を、他者との関係や信頼の構築によって測ることが多く、そのために時間とエネルギーを投資する。
その与える行動は、単なる親切だけに終わらず、長期的で良好な関係を築くことで社会的な影響をもたらすことができます。
テイカー:受け取ることを重視する人
一方、テイカーは『受け取る人』。
他者からの恩恵やリソースを最大限に引き出そうとする傾向があります。
テイカーは一見、効果的に見えるかもしれませんが、周囲との信頼関係を築くことができず、結果的には孤立することが多いです。要するに恨み、妬みを買いやすくなる。



GIVE&TAKE 『与える人』こそ成功する時代で紹介されている、テイカー代表の建築家『フランク・ロイド・ライト』の人生を見てみたら、分かりやすいかもしれません。
このため、長い目で見ると成功を収めにくいタイプとも言えます。
だって、最後は『人』、『人間関係』だから。運だって、人が運ぶでしょう?
何をもって『成功』とするのかは、個人個人違うと思いますけど、長期的視座で見たときには、収めにくいということです。逆を言えば、短期的には成功しやすいとも言える。
マッチャー:バランスをとる人
最後に、マッチャーは与えることと受け取ることのバランスを取ろうとする人です。
他者から恩恵を受けると同時に、自分も相手に何かを与えることを重視する。
マッチャーの特徴は、公平性や互恵的な関係を維持しようとする点で、一定の成功を得やすい性質を持っています。
ギバー、テイカー、マッチャーの成功の違い
これら3タイプの中で、成功する可能性が高いのはどのタイプでしょうか。



直感的にはギバーが成功すると思われがちですけど、ギバーは『他者志向型ギバー(他者思考型ギバー)』と『自己犠牲型ギバー』の2タイプに分かれていて、自己犠牲型ギバーが成功を収めるためには工夫が必要。
自己利益と他者利益の両方を考えられる他者思考型ギバー(他者志向型ギバー)こそが、世の中で一番成功しやすいと言われています。
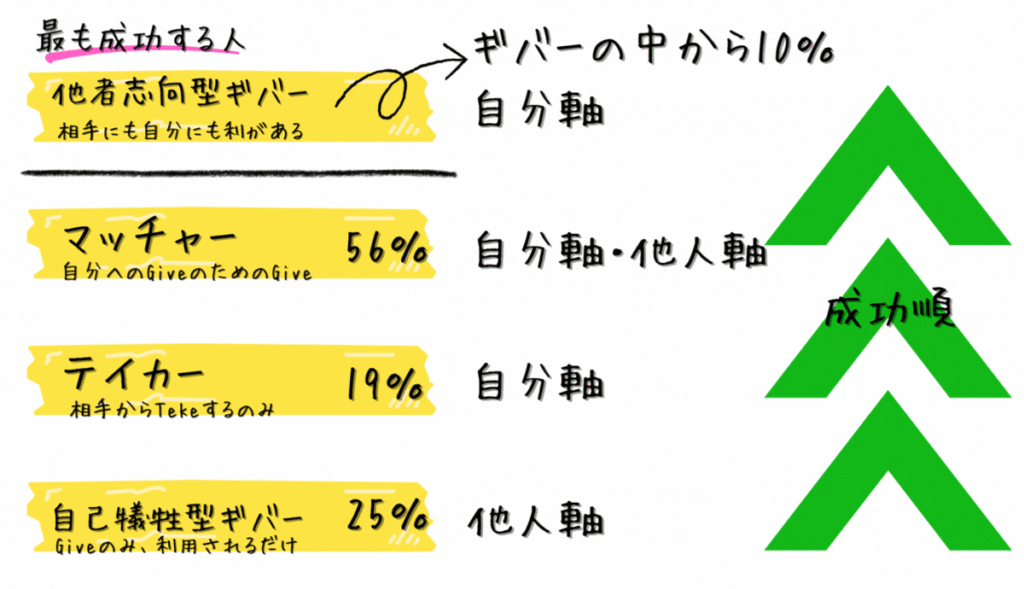
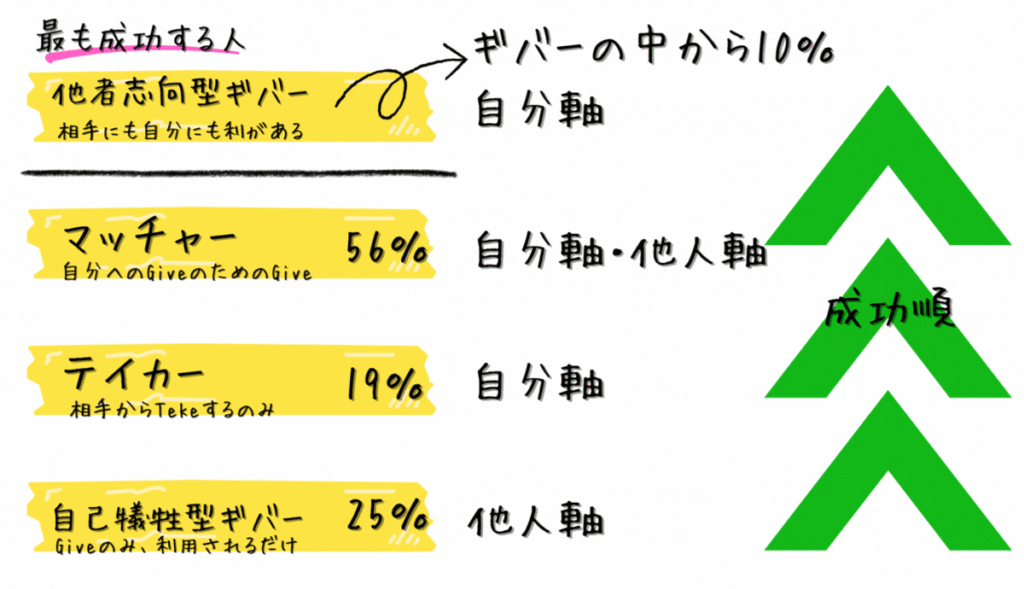
アドラーで言う、主体的ギバーのことです。



ギバーとテイカー、マッチャーの違い、それぞれの成功の道筋を理解することで、人付き合いで楽することができるうえ、成功を収めるコツを掴むことができますよ。
成功するギバーの秘訣※4つの考え方と行動
成功するギバーは、単に与えるだけではなく、全体の利益を考えて行動することができます。
『WINWIN』の関係性を築くことを意識できる。



ここでは、成功するギバーが持つ4つの大切な考え方と具体的な行動を見てみます。
- 失敗を恐れないギブの精神
- 自発的な広がりを促すギブ
- ギブした内容を発信する力
- 自己認識と他者の価値を理解する
①失敗を恐れないギブの精神
健全なギバーは、『失敗しても後悔がない、失敗を失敗と思わないギブ』を大切にしてます。



目の前の人を信用し『自分に何ができるか』を考えらえるといいのかなと。一生懸命考えることができたら、自負ができる。なので、失敗も何もないんです。単なる結果が出ただけ。
これは、見返りを期待せず、純粋に他者を支援できるという意味です。こういう心構えで、与えること自体を楽しむことができるので、ストレスにならない。
ギバーにとって重要なのは『行動を通じて、他者に喜びをもたらすこと』になってるので、結果に囚われない姿勢が、結果成功へと繋がりやすくなるんだと思います。



この行動を天が応援してくれる、それに近いと思います。色々なことが作用しやすくなってくるので、成功に早く近づくことができる。多分、こんな感じです。巻き込む力に勢いがつきやすくなる。
②広がりを促すギブ
ギバーは、与えるときに『広がれーー!』って気合を入れていないのに、なぜか広がる。
たとえば、自分が誰かのためにやったことが、相手の中で『うれしかった体験』として残って、その人がまた別の人に『実は…』って話し出す。
するとそこからまた、新しいご縁がポン、と生まれる。
これ、ギバー本人は何も営業してないのに、口コミが勝手に回ってる状態。
つまり、健全なギバーって、『人に喜ばれる行動』をきっかけに、ご縁やチャンスが自然と育つ環境をつくれる人。
別に“戦略的に広めよう!”とか考えてはいないけど、人のために動いてることが勝手に伝わり、巻き込まれてくれる人も出てくる。
結果、その人のポジションができてたりする。
ここまで来ると、もう“ギブがギブを呼ぶループ”に突入してる感じです。
③ギブした内容を発信する力
健全なギバーって、ただ与えて終わりじゃないんです。



これ、もっと誰かの役に立つかも?
って思ったら、ちゃんと発信するんです。
SNS、ブログ、動画――やり方はなんでもOK。



オレの武勇伝聞いてくれ!
じゃなくて、『こういうことやったら、誰かのヒントになるかも』っていう“未来の誰か”へのギブ。
ギバーにとって、発信は自己アピールじゃない。むしろ、“ギブを広げるための回覧板”みたいなもん。
だから、『目立ちたい』とか『フォロワー増やしたい』とかよりも、『伝えた方が、役に立てるかも』が先に来る。
結果的にその発信が波紋のように広がって、『助かった』って人が現れて、次に繋がる。
で、ギバー本人はというと、



楽しいし。
って顔してまた次の誰かにギブしてる。そういう“巻き込み力”、自然と持ってるんです。
④自己認識と他者の価値を理解する
健全なギバーは、ただ優しいだけじゃないんです。観察力と分析力もエグい。
まず、自分が何をギブできるか?をちゃんと分かってる。スキルなのか、知識なのか、時間なのか――“なんでも与えるマン”にはなりません。
何でも与えてたら、依存になる。ギバーはそれも知ってる。
そして、それが今ここで、本当に相手の役に立つのか?ってところまで考えて動く。押しつけがましさは無い。



それは、『周りをよく見てる』からできることで、空気を読んで迎合するんじゃなくて、ちゃんと自分の意思と視点を持って見てるんです。
つまり、ギバーって『観察力 × 主体性』のハイブリッド型。
そのうえで『これが今ベストの行動か?』を自分に問いながら動くから、結果的に信頼されやすいし、“ちゃんと分かってくれてる人”ポジションに収まりやすい。
そうなると自然と、いい人間関係がまわりに育っていく。これもまた、ギブの連鎖のひとつです。
他者思考型ギバーと自己犠牲型ギバーの違い
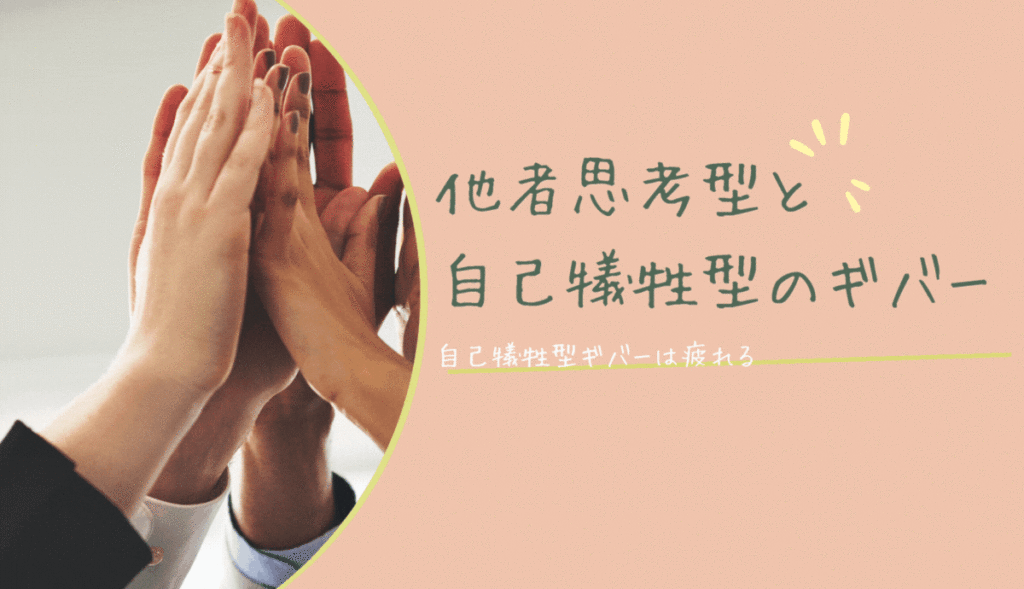
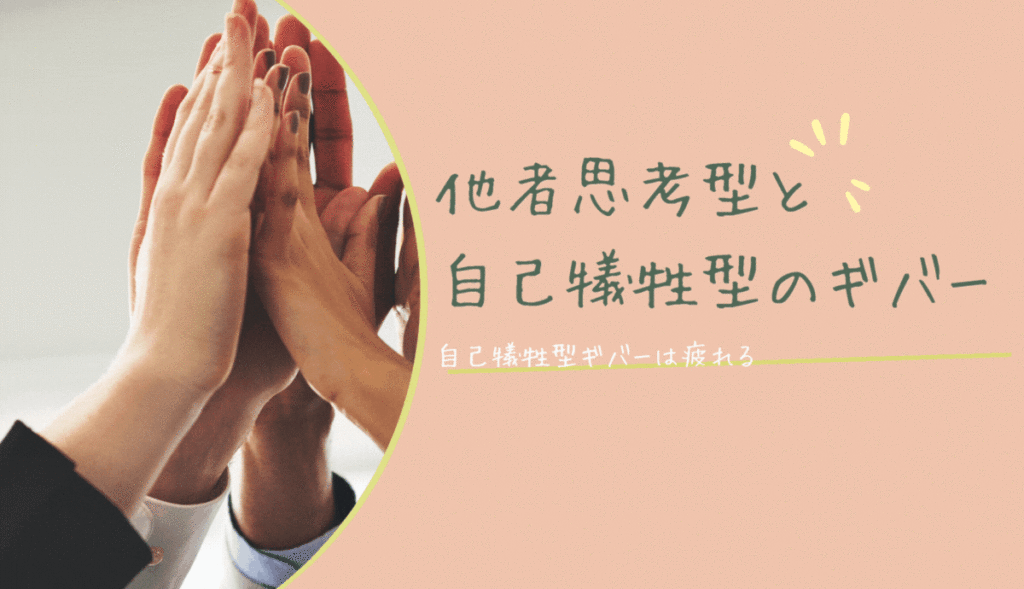
他者思考型ギバー(他者志向型ギバー)と自己犠牲型ギバー。
自身がギバーであると認識できている人は、自己犠牲型ギバーにならないように注意が必要。
自己犠牲型ギバーは疲れる。
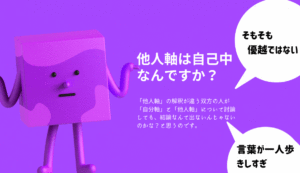
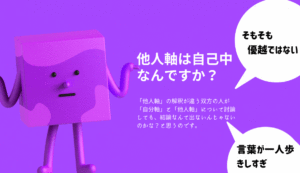
これらの違いを理解しておくことで、自分自身を守ることができます。
- エネルギーの配分
- 感情のバランス
- 成功の結果
①エネルギーの配分
他者思考型ギバーを目指すなら、まずこれだけは覚えておいてほしい。
ギブは体力制です。無限じゃない。
どれだけ『誰かの役に立ちたい!』と思っても、自分のエネルギーや時間が底をついたら、“優しさゾンビ”になってしまいます。
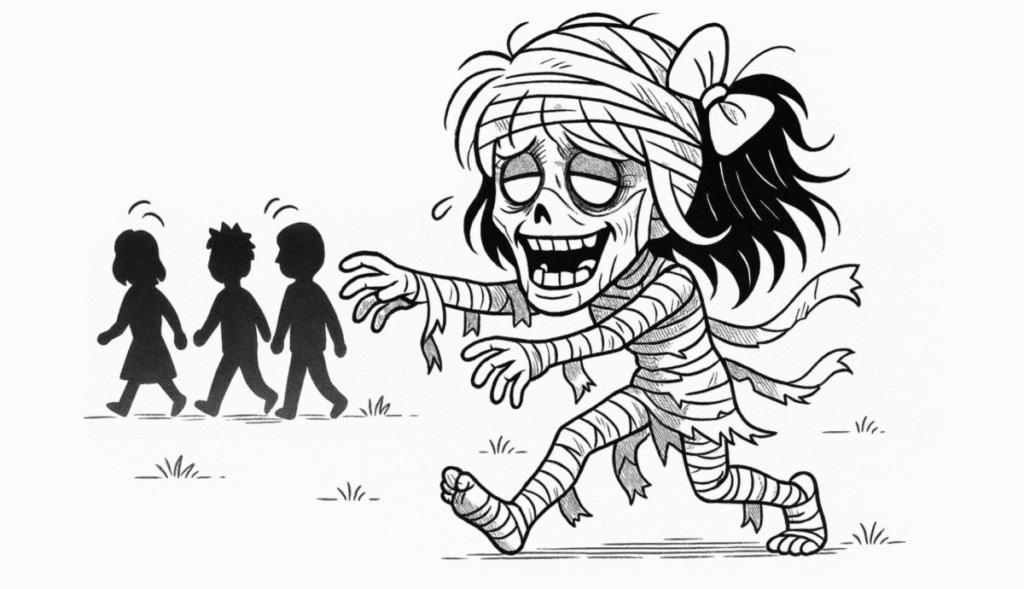
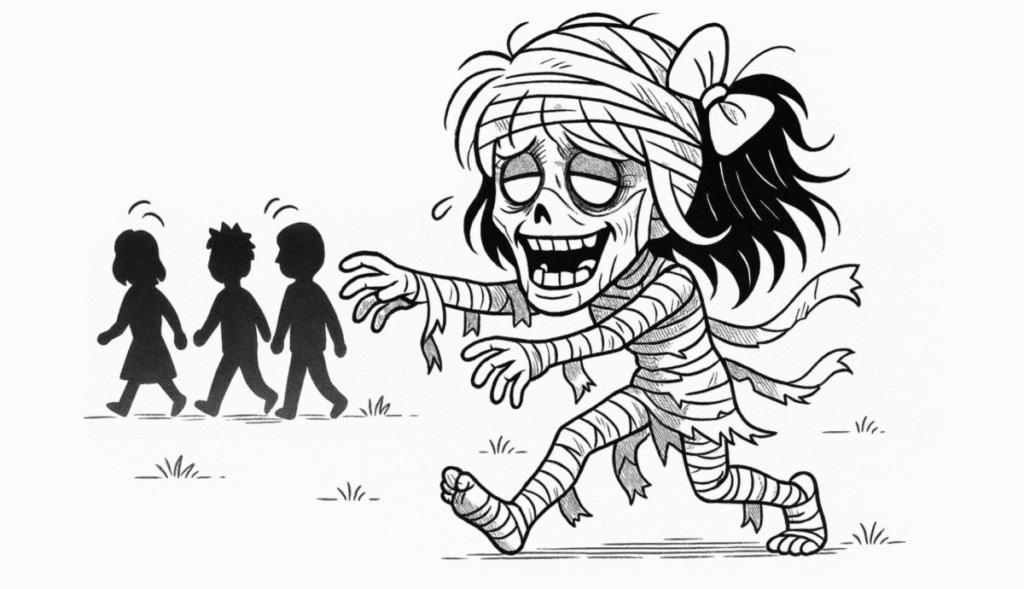
動いてるけど、魂が抜けてるやつ。
だからこそ大事なのが、ギブの使いどころを見極めること。
相手が明らかな“テイカー気質”だった場合は、ギブストップ!一旦様子を見る、もしくは“お試しサイズ”のギブにとどめておくのが安全です。
対して、自己犠牲型ギバーは……まるで“ギブの自販機”。
お金(感謝)を入れられなくても、永遠に商品を出し続けてしまうタイプ。
『見返りは期待してないから……』って言いながら、内心モヤモヤして、でも与え続けて、最終的に燃え尽きる。



それじゃ、人生回せません。
だって、自分を大事にできない人が、他人を本当に大切にできるわけがない。
与えることは素晴らしいけど、“自分を削って差し出す”のはギバーじゃなくて、もはや自己解体ショー。
だからまずは、自分のエネルギーを守ることから。それができてこそ、ほんとの意味で人を助けるギブができるようになる。


②感情のバランス
他人のために何かをすることに喜びを感じつつも、自分の感情や健康維持の大切さも理解しておくといいです。
自己管理が大切。
とにかく感情を乱さない。
一方、自己犠牲型ギバーは、他者のために自己を犠牲にすることが美徳だと考えがち。
美徳だと考えているのに、愚痴る。
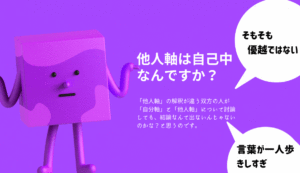
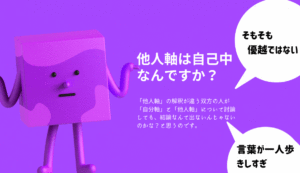
そのため、周囲からの評価や期待に応えようとしてしまい、結果的に自分の幸福感を削ってしまうんです。



心が沿わないことは、とにかくしない。
③成功の結果
ギバーって、なんとなく『いい人が報われる』みたいなイメージありますよね。でも、実は健全なギバーって、感情より設計図で動いてます。
長期的に見ると、他者思考型ギバーの方が明らかに成果を出しやすい。
なぜなら、ちゃんと“自分も含めたWin-Win”を考えて動いてるから。
自分がすり減らずに、相手にも価値を届けて、結果的に信頼も育つ。この流れ、完全にポジティブなフィードバックループ。しかも、持続可能。SDGsなギバーです(多分違う)。
一方で、自己犠牲型ギバーは…というと、『与えること=正義』になっちゃって、気づいたら全力で空振りしてるパターン。
頑張って尽くす → 自分のパフォーマンス下がる → 相手にも悪影響→ なんか空気ギスギス → 最後に『なんで私だけ…』ってなりがち。



いやほんと、良かれと思って動いた結果、相手も自分も疲れてるってどういう構図?
共に成長するどころか、片方が萎れて片方が依存してくるという、完全に“詰みルート”。
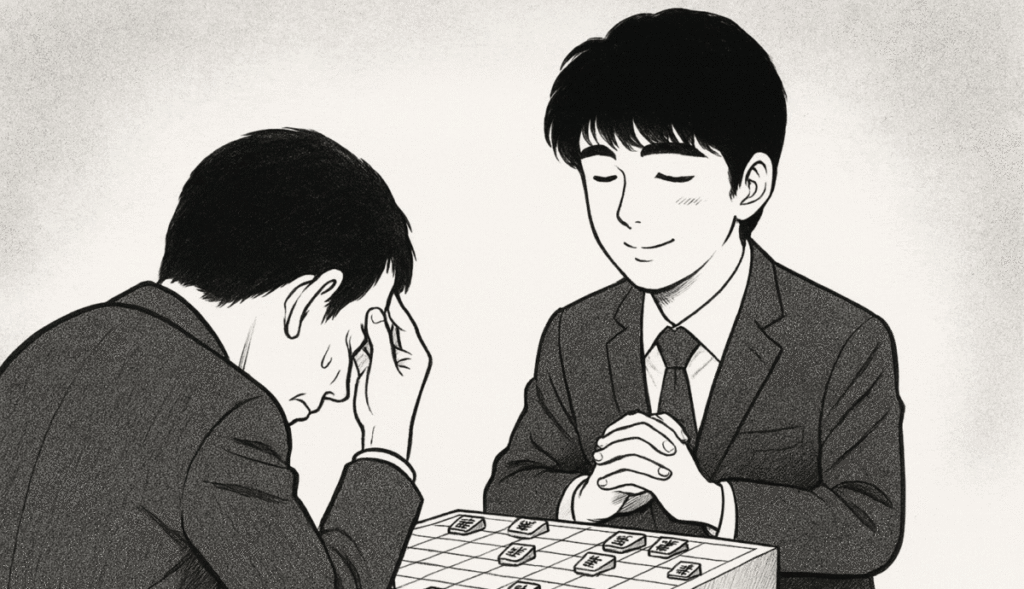
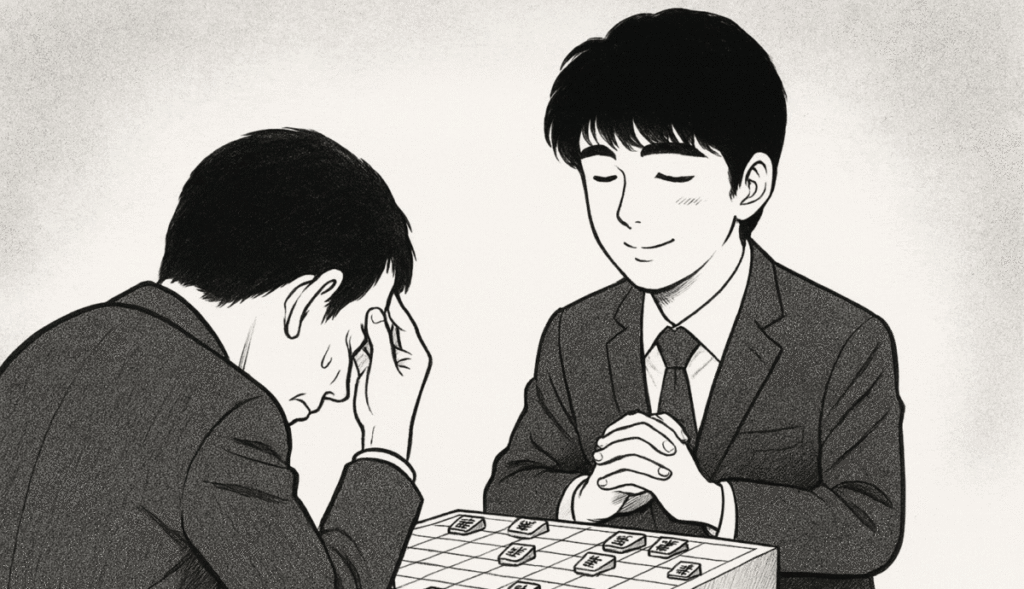
与えるって、『自分が壊れるまで差し出すこと』じゃないんです。
成果を出したいなら、自分の土台をしっかり保ちながら、相手にも役立つ形でギブする。これができるから、他者思考型ギバーは長く結果を出し続けられるんです。
④パートナーシップの形成
健全なギバーって、『自分が得するかどうか』じゃなくて、



この行動、相手にとって意味あるかな?
っていう視点で動いてるんです。
つまり、頭の中がいつも“WIN-WINシミュレーター”。しかも、自分側のWINより、相手側のWINを最初にチェックするという高性能っぷり。
で、相手の喜びが自分のモチベーションになって、その喜びがまた新しい原動力になって……という、“喜び連鎖型エンジン”で動いてるような人。
もちろん、ちゃんと『ここは無理、手伝って』って他人に頼ることもできるので、長くいい関係が築けるし、自分だけ空回りして燃え尽きることもない。
対して、自己犠牲型ギバーはというと……
相手のために頑張りすぎて、気づいたら依存されてる&されてる側も割と疲れてるという残念スパイラルに。
『なんかうまく回ってるっぽい』と思ってたのに、気づいたら関係が“重い・しんどい・続かない”の三重苦。
要するに、ギブは“やりすぎ”ても“報われない”ことがあるってこと。
だから、健全なギバーは“相手と自分、両方がちゃんと立ってる状態”を大事にしてるんです。
幸運なギバーになる方法※五次元思想


コレ、五次元的思想のことです。
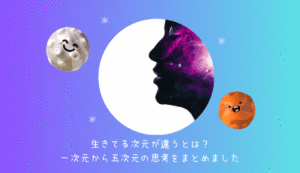
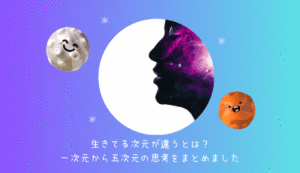
例えとして、全体を蜘蛛の巣のように見れるようになると、とも生きやすいと思う。
- 鳥の目の重要性
- ギブする意味を深く考える
- 経験による視野の拡大
- 期待を超えたギブ
- フィードバックを活かす
- 周囲の人を育てる視点
- 自己反省の時間を持つ
①鳥の目の重要性とは?
『鳥の目』って、“視野が広いからこそ、焦点を絞れる力”のこと。
たとえば――
部下がミスした。
→ 怒る?叱る?教育する?いやいや、まずは『なんでそうなったのか?』を見に行く。
『本人の注意不足』じゃなくて、『業務フローがややこしい』とか『マニュアルの順番が変』ってところかもしれない。
つまり、目の前の“症状”じゃなくて、“構造”を見る。これが鳥の目。
けど実際、多くの人はその“表面だけ”に全力でアプローチしちゃう。
『体調悪い?栄養ドリンク飲んで寝ろ!』じゃなくて、『そもそも寝不足の原因って…仕事抱えすぎじゃね?』ってとこを見るのが鳥の目です。
健全なギバーって、この“本質を見に行く姿勢”を持ってる。
相手が何に困ってるのか、その奥には何があるのか。そこまで見に行けるから、アドバイスや行動にズレがない。
その結果、『なんでそんなにタイミング良いの?』って言われたりする。



鳥の目、持ってるんで。
ギブの質を高めたいなら、“一歩引いて全体を見てから動く”。
②ギブする意味を深く考える
多くの人は、ギブすることの重要性を認識していますが、単に与えるだけでは深い成長にはつながりません。
健全なギバーは、相手のニーズに寄り添いながら、そのニーズに最も効果的に応えられる方法でギブすることができます。
例えば、今じゃない、コレじゃない、と思ったら引っ込める。
全体の流れを主体性を持って必ず読む、見る。
脳内でパラダイムシフトを何度も繰り返します。見え方を何度も変えてみる。自分目線と相手目線の両方で見る。両方が見えてないとダメなんです。そこから原理原則に沿って結論を出す。


見るのは置かれている立場と状況。思考は見ません。



みんな思考を読もうとするんですよ。これが違う。主観的になってしまう。あくまでも立場、状況。
相手の求めるもの、自分が与えることができるもの、そこから生じるであろう感情や出来事の分岐、いろいろ見みた後に、課題の分離。こんな感じです。そこに必ず正解がある。


\パラダイムシフトは、これに書いてます/
相手が必要としている情報をただ渡すのではなく、その情報がどのように活用されるのかを考えることも大切。



さらに活用された先の影響まで見ることもあります。そこまで考える必要があるか?どうか?の見極めも重要ですが、それが容易にできるようになる。
③経験による視野の拡大
鳥の目を育てるためには、経験が必要。
とくに必要だと感じるのは、、
- 思考の整理、遮断※とくに感情に気を付ける
- 周りの、あなたが気になる色々な人(家族含む)の観察(できたら数年単位で10年くらいまで追ってみる)
- 自分で正解を探す癖をつける※安易に愚痴と言う名の相談をしない
感情に疎くなると、人生迷子になるので、とにかく自分の感情は大切にした方がいい。アドラーで言うなら、課題の分離はできた方がいい。



考える問題と感情の切り離しが難しいけど、分離ができないと苦労する。分離ができたら、簡単だし楽。
比較がないと分からないから、自分の周りに気になる人いません?あの行動って、行いってどうなんだろう?こういう人のその後を追ってみるといいかもしれない。どんな人生を歩むのか。
するとその人の人生での学びの内容が分かるようになる。
体感で、早くて3年、次は5年、遅くても10年以内には結果がでるから。もちろん、3年の方が取返しはつきますよね。それより長くなると、学びが長くなる。



あぁ、慢心だな。となると、次はあぁなる、次はこうなる。
とにかく、分かるようになる。学びが長くなっている人は、学びを学びとも思っていないので、大体、翻弄されてますよ。
思考を鍛えた方がいいので、自分で考え抜く癖はつけた方がいいと思います。けど、その考えに固執してしまう可能性もあるので、柔軟に周りの人に聞いてみるといい。
お友達でもいいけれど、できればあなたが信頼を置ける第三者の方がいいでしょうね。違った目線の回答をくれるから。



けど、基本的には考え抜いたその答えを信じる力を鍛えた方がいいと思う。自負になるから。それと、心の筋肉が鍛えられる。
ほかの人を助けるために、利己的な衝動を常に抑えているので、精神的な筋肉が強化され、つらい作業で気力を使い果たしても疲労困憊することがないのである。この考えを裏づけるように、他の研究でも、ギバーは自分の思考、感情、振る舞いをコントロールするのが得意なことが明らかになっている。筋力トレーニングを積んでいるうちに、だんだんと筋力が鍛えられるように、気力も鍛えられていくのかもしれない。これがギバーに起こることなのだ。
P281『GIVE&TAKE 『与える人』こそ成功する時代』
そうすると、↑こういう感じになれる。利己的な衝動を抑えた結果、助かる人が現れるでしょう?それでトントンになるんですよ。トントンというより、仕組み化して言えることは、後のチャンスとして“利息付き”で戻ってくる。
自己受容も大事。
分岐から、結果まで、そうならないように身動きが取れるようになるようになり、最良の選択ができるようになると思う。それが大事。それが蜘蛛の巣思考。
\感情を切り離すことが、最良の選択の第1歩/
経験を通じて、自分の視野が広がり、より本質的なギブが可能になります。
④期待を超えたギブ
健全なギバーって、『Aさんのためにやったこと』を“そこだけで終わらせない”。
- Aさんに渡した資料 →『他の人にも使えるかも』と思って社内共有にする
- Aさんへのアドバイス → 後でブログに書いて、もっと多くの人が読めるようにする
- Aさんとのやりとり → そこから学んだことを仕組みに落とし込んで、組織全体に還元する
つまり、1回のギブを“再利用可能な価値”に変えていく。
その行動が回り回って、まだ出会ってもいない誰かの助けになる。
⑤フィードバックを活かす
ギブした結果がどのように受け止められるかを観察することで、自分のアプローチを改善することができます。
ただ、人対人だと、思ったような結果に至らないこともある。けど、それもまた流れのひとつ。
自分さえ信用していれば、改善というより、ハンドルを違う方向に切り直すだけのこと。
どの道、それが最善になって行く。
フィードバックは重要な資源でもあるので、知識として次に生かすようにします。



どのように相手に影響を与えたのかを分析して、それを次の行動に結びつけることで、共に、常に、成長し続けることができるからです。
⑥周囲の人を育てる視点
健全なギバーって、誰かを助けて『はい、おしまい』じゃないんです。むしろその先――『この人が、次に誰かを助けられる人になるにはどうしたらいいか?』まで考えてる。
例えば
- 仕事を手伝うときも、やってあげるだけじゃなく『こう考えるとやりやすいよ』ってコツも渡す
- アドバイスするときも、『自分で考えられるように』問いかける
- ちょっとずつ任せてみて、成長のタイミングを見守る
要するに、“自分がいなくても回る”仕組みを育てようとしてるんですよね。
このスタンスが、周囲の信頼を自然に集めて、『あの人がいると人が育つ』『なんか場がよくなる』って存在になっていく。
つまりギバーは、ただの“親切な人”じゃなくて、“仕掛ける人”でもある。
それが、信頼→協力→チャンスにつながる“影響力の連鎖”を生んでいくんです。
⑦自己反省の時間を持つ
物事がうまく進んでいるのかどうか、途中で見返すことは大事。
自分を整える”視点。



自分の選択、あのとき最善だった?相手のためになっていた?
……を、ちょっと鳥の目で、引いて見てみる。
で、もしうまくいかなかったとしても、それって“天からの進路変更のお知らせ”かもしれない。



あー、こっちは道じゃなかったかな?じゃ、次はこっちかな?
くらいのノリで、ハンドルを切り直す勇気が持てると、ギバーはどこまでも成長していける。
自分さえちゃんと信じていれば、自分を信じてくれる人と一緒に、また仕切り直せばいいだけの話。
まとめ
健全なギバーには、他者への思いやりと、冷静な自己管理の両方が求められる。
ただ優しいだけでも、ただ戦略的なだけでも、うまくいかない。
“与える”という行動の中に、その場の空気を読む力も、相手の成長を想像する視点も、自分の限界を知る感覚も――
ぜんぶ含まれているから。
そのバランスが取れてくると、自然と信頼が集まり、結果として、ビジネスにも、人生にも、少しずつ『いい流れ』がやってくる。



でも、最初から完璧なギバーなんて、いないんですよ。誰だって最初は、受け取る側=テイカーからスタートしてる。
わたしもそうです。
テイカーが羨ましかった。いつも与えられていて、羨ましかった。先回りをしてしまう自分、気づいてしまう自分、してしまう自分、あの時代が嫌だった。だけど、こうやって伝えられる経験ができているということは、ギバーは嫌だと思っていたあの頃のわたしは、テイカーだったということになる。
振り返れば、あの頃テイクさせてもらった時間と、読書で得た知識が、今こうして、ギブとして誰かに届けられる形になってる。
もしあなたが今、まだ『もらう側』にいるとしても、大丈夫。その経験が、きっと未来の“誰かを支える種”になります。
ゆっくりでいい。返したくなる日が、ちゃんと来るから。
そして、元々は自己犠牲型ギバーだったわたしも、少しずつ『他者思考型ギバー』を目指して、どうにかここまで来ました。
…だけど今でも、テイカーの立場になることはある。基本ギバー、時々テイカー。誰かに助けられてる瞬間が、実はたくさんある。
だからこそ、与えられていることにも、ちゃんと気づいていきたい。そう思っています。

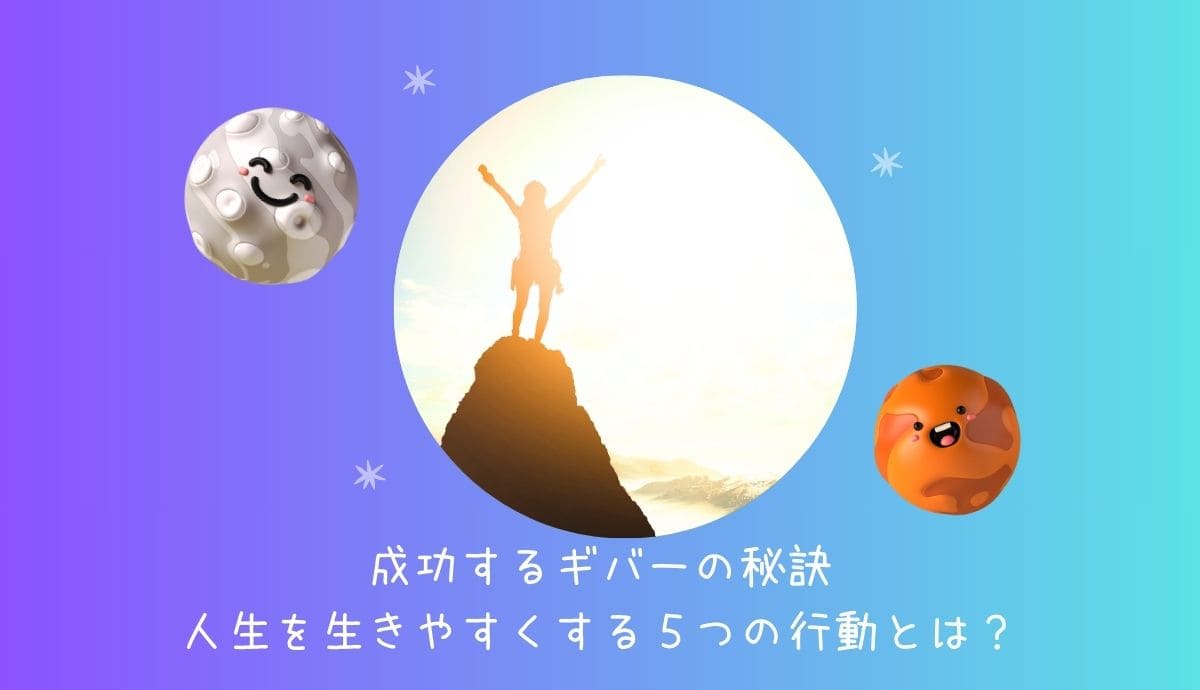

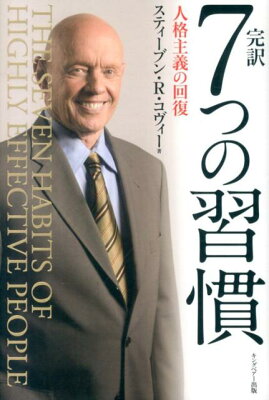


コメント