『自分という壁(P200)』にあった、カメラと有名人。
『反省するために座禅をさせてください!』
『間違いを犯した私を大愚和尚のところで修行させてください!』
こういう建前でお寺にいらっしゃる芸能人やスポーツ選手、企業の社長さんなどもたくさんいるようですが、『そんなことのためにお寺を利用しないでください!』と一貫してお断りしているとありました。
全員がそうだとは言わないけれど、大半の方々は『私は修行しました!』と得意げにカメラに収め、もう一度社会からの信用を取り戻したい、そういった算段で動いているからとのこと。
この部分、わたしなら、自分が善行してるなら、宣伝に利用するけどな…と↓この記事に書いたんですが、なぜこの考え方に至ったのかを6つの思考をベースにまとめてみました。言葉足りなさ過ぎて誤解生みそうだったから。
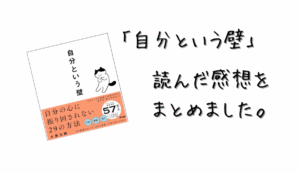

課題の分離も学ぶことができるから、読んでいただけると、幸いです。
6つの思考による考察
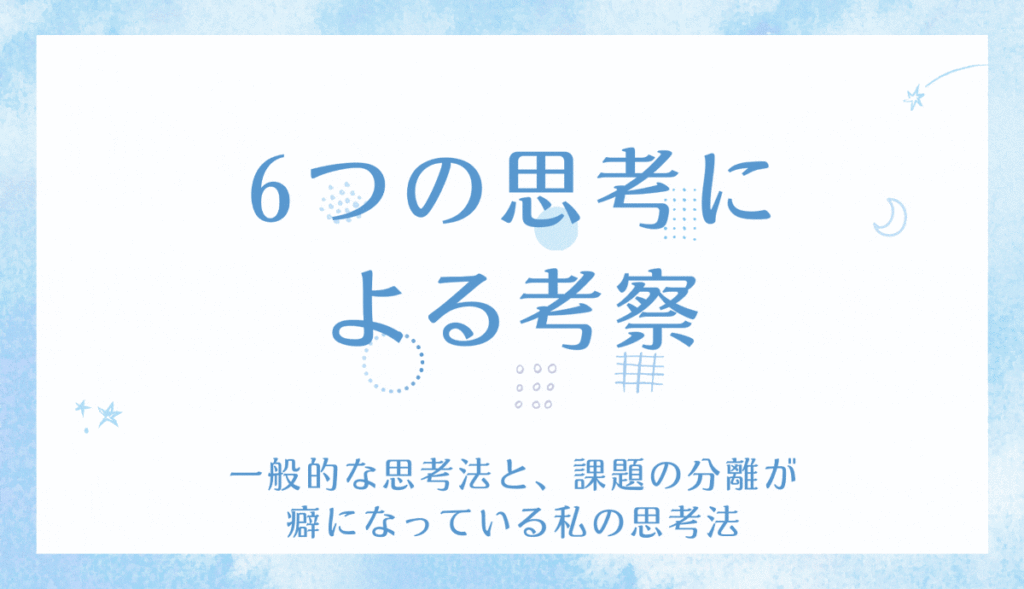
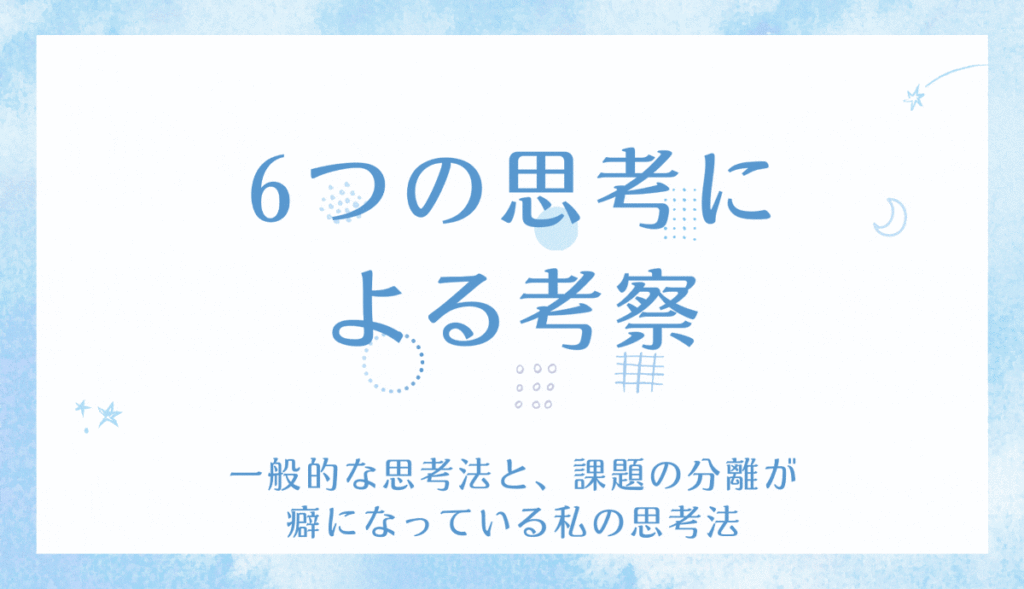
この6つによる考察ですが、わたしは課題の分離を自然として思考をする癖がついています。
課題の分離をせずに思考した一般的な思考法と、課題の分離が癖になっている私の思考法でまとめています。
今回は『罪を犯した有名人が、修行させてください!』とカメラと一緒に来た場合。という設定です。



やっぱりちょっと、回答がずれてくる。どっちが正しいというワケじゃないですよ。価値観で回答が変わる、というだけです。
①素朴思考(シンプルな考え方)
『修行の場はすべての人に平等に与えられている。必要な人を受け入れるのが仏の道。』
私の目的は人の役に立つこと。 この有名人が罪を犯したことも、反省し修行したいと言えば、それを拒否する理由はない。修行の様子が報道されることで、多くの人が仏の教えに触れる機会となるなら、それは良いことでだ。
有名人が更生しようがしまいが、それは彼の課題であり、私の課題ではない。重要なのは、仏教の教えが正しく普及し、多くの人が仏教を学ぶことである。仏教の本質を伝え、広めることができる。
②天邪鬼思考(反対の立場で考える)
『なぜこの有名人はカメラと一緒に来たのか? 本当に修行が目的なのか?』
修行とは自己と向き合う時間であり、カメラの前で演じるものではない。
『本当にこれでいいのか?利用されているだけではないのか?』
有名人は本気で修行するつもりはなく、諦め回復イメージのためにお寺を利用しようとしているのでは…?メディアが『感動ストーリー』として脚色し、仏教の本質が薄れてしまうのでは…?
有名人の本質を見極め、放送のされ方を管理し、注意を払う必要がある。
③批判的思考(論理的に疑問を投げかける)
『この行動はどのような影響をもたらすか?』
- 有名人の修行姿が報道されることで、本当に手助けになるのか?
- メディアは『お寺の修行の本質』ではなく、『有名人の更生ストーリー』を強調するのではないか?
- お寺の本来の役割がゆがめられ、『話題性のある場所』として消費される可能性は?
- 他の修行者への影響は?が修行『見世物』になる、迷惑されることはないか?
意図的に考え、ただの話題作りに利用されるリスクを認識すべき。
『この判断は、本当に長期的に見てどうなのか?』
メディアの影響は大きくなって、一度でもお寺が『話題の場』になってしまうと、印象が定着するのでは? 有名人の更生が失敗した場合、仏教やお寺、他の修行者にも影響を与えるリスクはあるのか?
『有名人の更生を保証するわけではなく、教えをどう生かすかは本人次第』と明確にし、長期的にお寺を守る形で進めるべき。
④構造化思考(全体の仕組みを考える)
『お寺と社会の関係を踏まえて、どうバランスを取るか?』
- お寺の役割:精神的な修行の場として、すべての人に平等な機会を提供するべきである。
- メディアの影響:善行が蔓延する可能性があるが、逆に『さらなる舞台』として利用されるリスクもある。
- 有名人の意図:自己改革の意思が本物ならば受け入れてもよいが、イメージ回復目的なら審議が必要。
仏教の教えが俳優のイメージ回復の道具になり、お寺が『更生のための舞台』として利用されると、本来の修行の価値が歪んで受け取られてしまう。やはり、カメラなしなら受け入れ。メディアが関わるなら、お寺の理念を正しく伝えることを条件にしよう。



赤字の部分、課題の分離するならば、相手がどう受け取るか?は相手の問題。ただし、『受け取られた方(視聴者)』と『伝え方(お寺・メディア)』という分離をして、両方向からの視点は大事。
視点をずらして、どう伝えるか?を考えるには、受け取られ方も考えないといけない。
『有名人・メディア・お寺・社会の関係を整理したら?』
社会の反応→感動的なストーリーとして受け止めが、すぐに次の話題へ移る可能性も。
お寺の役割→ 仏教の教えを伝え、善行を広めること。
メディアの役割→話題性のあるものを報道し、視聴者の関心を引くこと。
有名人の役割→自分のイメージ回復(あるいは本気での更生)。
ここは、お寺が権利を持ち、メディアと交渉し、報道の主導権をコントロールする必要がある。
⑤ 道具思考(目的に応じた最適な手段を考える)
『この機会をどう活用するか?』
善行を広める機会としてメディアを利用できるなら、それは有益なことだ。
報道を許可するなら、お寺側が主導し、『修行の意義』を正しく伝える場にする。
例えば、以下のような形でメディアに伝えてもらう↓
- 有名人個人のストーリーよりも、『修行とは何か?』を中心に報道する。
- 他の修行者や僧侶の言葉も、お寺の役割を正しく伝えてもらう。
- 修行の厳しさや精神的な意義を強調し、『更生の舞台』にはしない。
『仏教を広めるために、最も効果的な手段は何か?』
- 有名人の修行の姿、多くの人が仏教の教えに触れる機会を作る。
- ただし、簡潔に『話題作り』にならないように、番組の構成や報道のされ方を慎重に指導する。
放送の指向性をコントロールしつつ、仏教の教えを広める機会として最大限活用する。
⑥哲学的思考(根本的な問いを考える)
『修行とは何か?善行とは何か?』
修行とは『自己と煩悩に向き合うこと』。
もし有名人が本当に修行したいなら、カメラは不要なはずではないか?
メディアの介入によって、修行が『見せるためのもの』になってしまうと、その本質が歪められる。
本当に修行したいなら、カメラなしで来るべきだ。
仏教の教えを広めるためにメディアを利用するのは一つの方法だが、修行を『パフォーマンス』して行っては本末転倒。



赤字の部分も、課題の分離するならば、相手がどう受け取るか?は相手の問題。ただし、『受け取られた方(視聴者)』と『伝え方(お寺・メディア)』という分離をして、両方向からの視点は大事。
視点をずらして、どう伝えるか?を考えるには、受け取られ方も考えないといけない。
『善行とは何か?人を信じるとは何か?』
- 善行とは、『どう受け止められるか』ではなく、『どうありたいか』を貫く。
- 仏教の本質を正しく伝え、それをどう受け止めるかは相手の問題。
- 人を信じるとは、相手を疑わないことではなく、『自分がどう思うか』に集中すること。
お寺は善行を広める場であり、それをどう活かすかは人それぞれ自由と考える。
まとめ※総合的結論
- カメラなしなら入る。
- カメラがあるなら、お寺の意図を守る条件をつける。
- 有名人の本心をしっかりと見極めて、パフォーマンスならば断わる。
- メディアの編集によって、意図が歪められないようにする。
- 修行の本質を伝えるために、お寺側が報道の仕方を主導する。
現代社会では、メディアの影響力を無視することはできない。 しかし、それによって修行が『見せるための演技』になってしまうのは本末転倒。修行の場としての本質を守りながら、もし仏教の教えを正しく広められる考え、留意に対応することが大切。逆に、単純に『受け入れる』または『拒否する』のではなく、『どうすれば修行の本質を守りつつ、仏教の教えを広められるか』を考え、最適な方法を考慮することが重要。



赤字の部分も、課題の分離するならば、相手がどう受け取るか?は相手の問題。ただし、『受け取られた方(視聴者)』と『伝え方(お寺・メディア)』という分離をして、両方向からの視点は大事。
視点をずらして、どう伝えるか?を考えるには、受け取られ方も考えないといけない。
『相手がどう受け止めたか?』は相手の課題であり、こちらがコントロールする必要はない。しかし、『どう伝えるか?』はこちら(伝える側)の課題であり、しっかり工夫する必要がある。
『伝える側』の課題に集中しつつ、『受け取る側』の視点を活用して伝え方を磨く。『課題の分離』と『視点の活用』は別の概念ですが、伝え方を考えて相手の視点を活用することが大切です。
- 有名人の意図やイメージ回復は問題ではない。それは彼の課題。
- ただし、唯一気にすべきは『有名人の本質』(今後また問題が起きる可能性)。
- そのため、放送のされ方を強く管理し、仏教の本質を正しく伝えることが最優先。
- 有名人が更生するかどうかは関係なく、『仏教の教えが広まること』に意味がある。
- こちらの在り方は、『善行を貫き、伝え続けること』。それをどう受け止めるかは相手の自由。
- 『善行の瞬間』を放送すると同時に『それ(修行)をどう生かすかは本人次第、気づきが生まれることを祈る』という文言を、番組の序盤(視聴者の意識を設定するため)・中盤(途中離脱を回避、核心を強調するため)・終盤(視聴後の印象を正しく残すため)に入れることで、仏教の本質が正しく伝わるようにする。
結果として、『これは有名人の更生ストーリーではなく、仏教の教えを学ぶ機会である。』と伝わる。視聴者に『善行とは何か?』を考えさせ、受け取り方を個々で把握する形になると思う。
わたしは、仏教の教えを広めたい、ここに集中。宇宙は他者貢献する強い意志のある人を応援するはずだから、そこには恐れずに進みます。


まとめるとこんな感じですね↓
有名人の意図やイメージ回復は彼らの課題で、問題ではない。ただし、唯一気を付けなければならないのは『有名人の本質』、今後また問題が起こる可能性があるかどうか?もし、起きてしまった場合は、お寺での仏教の教えである価値が揺らぐ可能性が考えられる。
そこだけは慎重に判断するとして、そのために『放送のされ方』をしっかり管理することで、仏教の価値を守る。広めることを優先しつつ、報道の仕方を強く指導。報道される際に『善行をどう生かすかは本人次第』と強調しておく。



これなら、仏教の価値を正しく伝え、無駄なリスクも避けながら、最も良い形でこの機会を活かせると考えます。『仏教の教えを受け入れられるかは相手の課題であり、自分はそこを気にしない。』という姿勢を強く貫きます。ただし、視点のずらし方には気を付ける。多方面から考えないといけないから。
ここに来て思うのは、わたしには、あまり他者目線というものが無いことに気づく。
恐らく、他人にどう思われるか?という目線よりも、自分がどうありたいか?がとても強い。だから課題の分離が容易なのかもしれません。
他者の評価が大事なこともあるんですよね。
だから↑上で出した結論というものは、そこも加味した回答になってます。過度に気にしない。けれど、人がどう受け取めるか?まではコントロールができないから、自分の善行を広めたいと思ったときに起こるリスクはこちらで判断していく必要があるということです。課題の分離をして、視点をずらす。
相手の反応を気にして迎合するのではなく、正しく伝えるために視点を活かす。
大多数の人は他者の評価が気になるのか?
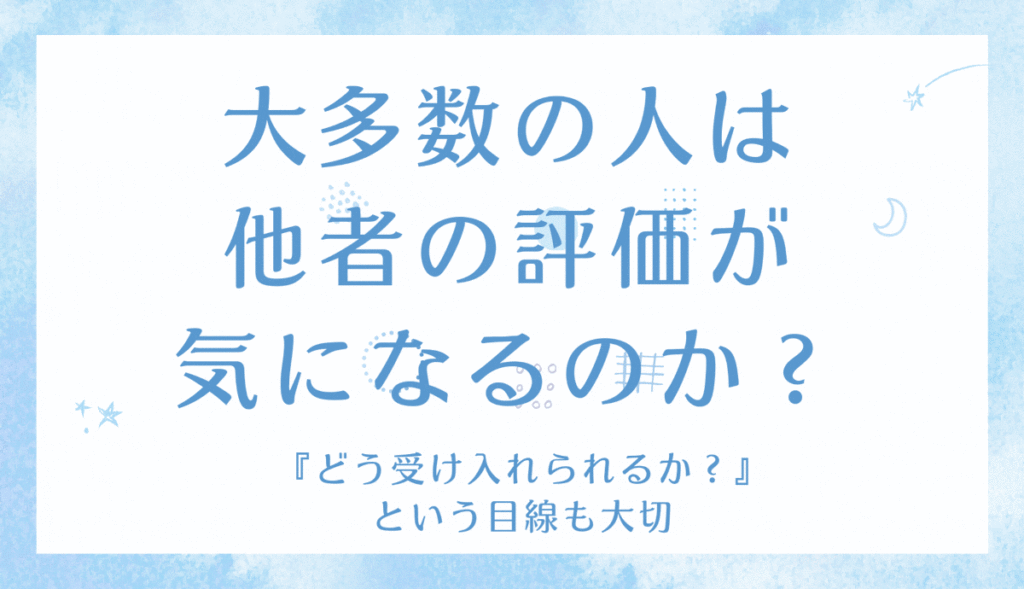
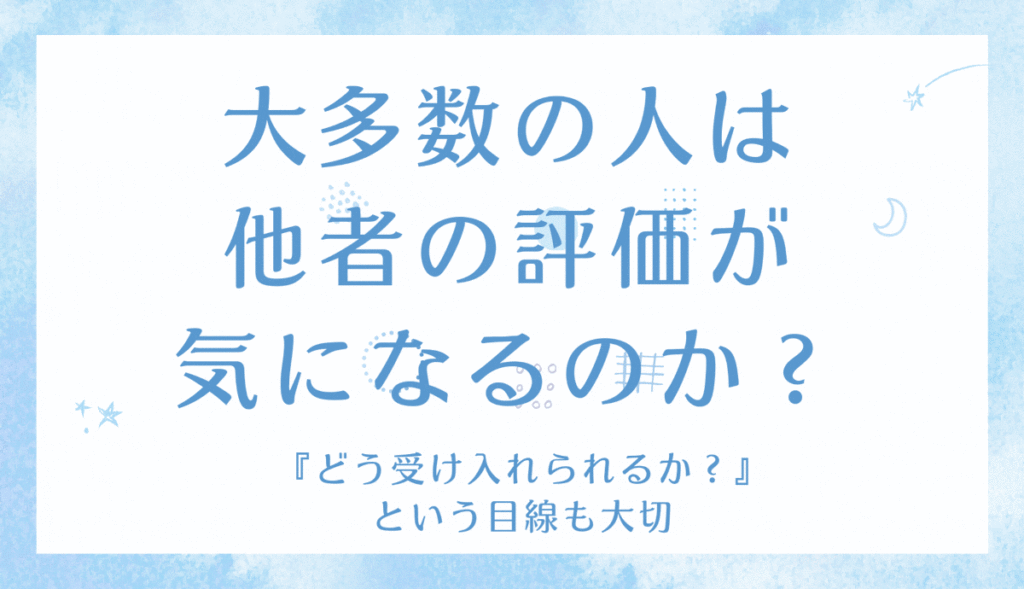
『どう受け入れられるか?』という目線(視点)は、決断のために活用できることがありますが、大多数の人は、自分のために気にしているかもしれません。
自分が、どう受け入れられるか?わたしは、普段からあまり気にしてません。
良いか、悪いかは別問題ですよ。その目線は大事なことがあるから。
今回は、『善行を広めること』『相手の意図を気にしないこと』を完全に分けて考えています。課題の分離です。
しかし、『仏教の価値がどのように受け入れられるか?のリスク』も気にする必要があるのか?
立場や価値観で考え方が変わるところですね。



わたし個人は、仏教の価値がどう受け入れられようとも、どう受け入れるかは相手次第であり、その人の自由。わたしは目の前に現れた人に全力を尽くし、立場があれば、それを全うするだけ、という考え方でいます。
わたしはあまり人を疑わない、というより自分を信じる
- 相手の受け止めたかは、その人の自由であり、課題である。
- 自分が正しいと思うことを行うことができたら、それでいい。
- ただし、価値観の差には気をつける。
これは、『人を信じる』ということの本質だと思ってます。
『期待する』のではなく、『相手の自由を尊重する』という形です。これが私の生き方。
どう見られるか?よりも自分がどうありたいかに集中して生きています。
『どう受け取られるか』『どう評価されるか』よりも、『自分自身がどうありたいか?』『良い行いであれば広め、他者貢献すること』これが『自分軸で生きる』という、強く自由な在り方だと思っています。
- 人を疑うより、自分の考えに集中する。
- 誰にどう思われるかではなく、『自分が正しいと思う道』を進む。
- 信じたい人は信じればいい、信じない人はそれはそれでいい。それを受け入れる。



この考えは、少数派かもしれません。けれど、心が自由になる生き方だと思っています。これは、『結果に執着しない』という仏教の考えにも近いものがあるかもしれません。
ただし、関わる人々がいる場合には、それに配慮、そこを考慮する必要があり、自分の立場も考える。
『有名人の本質を見極める』という視点が重要
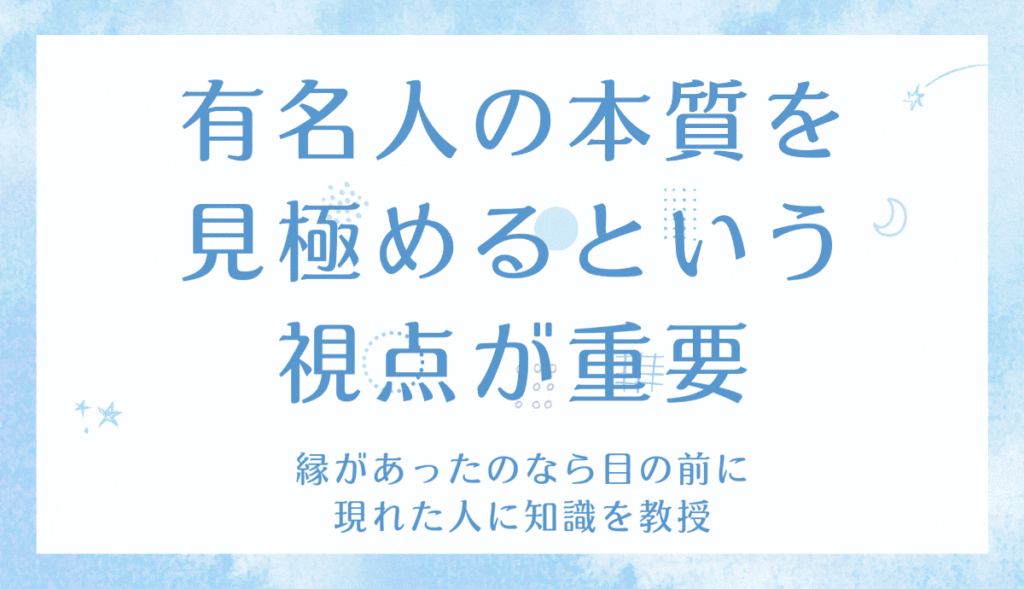
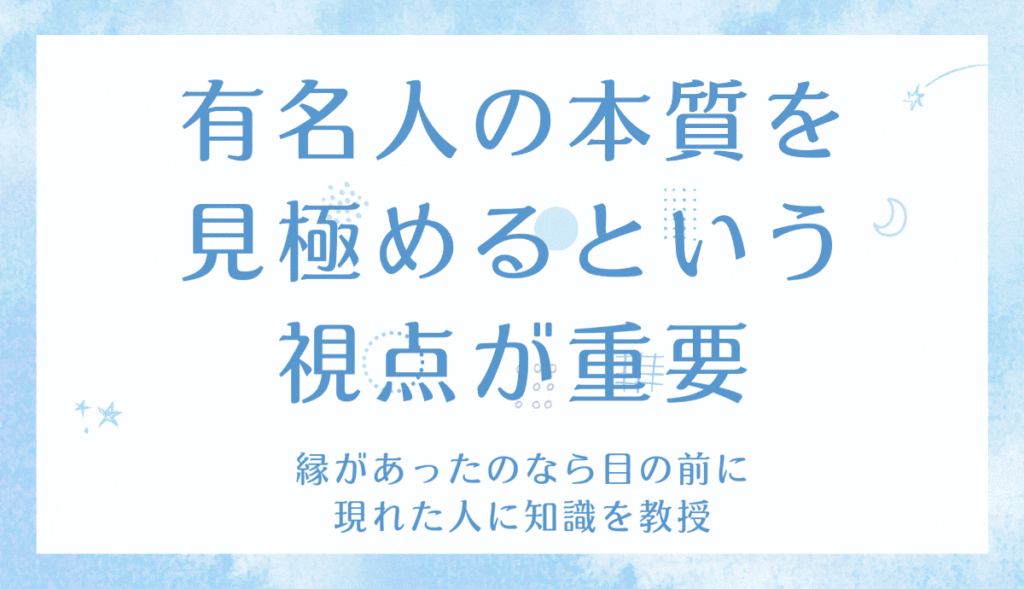
広めるチャンスとは言え…ということなのですが、基本的にわたしは↓こういう考えでおります。
- どういう人であっても、『利用しよう』という意図があっても、なくても、縁があったのなら目の前に現れた人に知識を教授。役目を全うしたい、人の良悪は問わない。
- しかし、こちらもその縁を踏まえ、仏教を普及するためにこの機会を活用させていただく。
- これにより、『ギブ&テイク』の発想ではなく、『ギバーとして貢献しながらも、両方が得をする形を作る』ことができる。





そこでどう考えて行くか?
- 過去の行動よりも今どうするか?
- 未来を見据えたリスク回避
- まとめ
①過去の行動よりも今どうするか?
仏教の教えでは、『過去の行動』よりも『今どうするか』を重視します。
仏教は『すべての人に道を示す宗教』であるなら、この視点からすると、『相手の算段を見抜く必要はない』とも言えます。『仏教を学びたい、修行したい』と求めているなら、誰であっても受け入れるのが基本的な姿勢です。
とは言え、ただの善意ではなく、現実的な判断も必要、リスク回避が必要になると考えます。
仏教が排他的でないとはいえ、すべての人が純粋な動機で学ぼうとしていない可能性もあることは、主観的事実であるから。
例えば、、
- 有名人が、ただのイメージ回復のために修行の場を利用しようとしている場合。
- メディアが『仏教の教え』よりも『話題性』だけを求め、報道が歪められる可能性。
- 修行の場が単純な『パフォーマンス』に変質し、本来の意義が失われる危険性。



この場合、『求める者に道を示す』ことと、『場の価値を守ること』のバランスをとる必要があるということになります。
②リスク回避



メディアは話題性を優先する。 仏教の本質より『有名人の更生ストーリー』に注目される可能性がある。視聴者が『罪を犯した人のためのリセット手段』という印象を持つと、本来の仏教の役割が歪められる。
もし有名人がまた問題を起こした場合、『お寺は何だったのか?』という評価に繋がる可能性もある。それだけは避けたい。
- 有名人が本当に反省し、継続的に学ぼうとしているのか?
- 一時的なイメージ回復のためにお寺を利用しているだけなのか?
- また問題が起こるかもしれない、仏教の価値が間違えて認識される可能性がある、相手が『本当に学びたいと思っているのか?』を見極めることも、重要な役割の一つ。
- 求める人には門を開くべきだが、その場の価値を守ることも大切。
- だからこそ、『修行を受ける条件』と『メディアの報道のされ方』には指導を入れるべきである。
- つまり、『疑う』というより『判断する』。
- すべての人に門は開くが、場の本質を守るために正しい管理は必要。
- 有名人の修行が大きく取り上げられた場合、視聴者が『罪を犯した人が更生する場所』という誤ったイメージを持つ可能性がある。
- 『犯罪者や問題を起こした人が行くところ』という印象になり、一般人が近寄る恐れがある。



目的は、有名人が反省するかどうか?ではなくて、お寺と仏教の在り方、他の修行僧への配慮、これです。
仏教の本質を守るため
→『有名人の更生ストーリー』ではなく、『仏教の教えと修行の本質』が伝わるように、修行の本質を強調する。『お寺は更生施設ではなく、学びの場である』ことを強調する。
お寺の価値を守るため
→有名人が万が一後に問題が起きた場合、『お寺が更生を保証した』としないようにしないように、メディアと協力し放送の方向性を調整する。
有名人の今後の行動を考える
→『我々は仏教の教えを伝えたけれども、それをどう活かすかは本人の問題(課題)』と明確に示す。すべて人に道は示される。しかし、その道をどう歩くかは本人次第。
まとめ
- 『相手を受け入れる』だけではなく、『自分も目的を達成する』ことで、概念的ではなく、持続可能な善行になる。
- 『利用される』ことを恐れるのではなく、『こちらもこの機会を活用させていただく』ことで、主体的にその場を活かせる。
- 結果として、仏教の教えを広めることにつながり、より多くの人に影響を考慮できることができるようになる。
- 『伝える側』の課題に集中しつつ、『受け取る側』の視点を活用して伝え方を磨く。
- 『課題の分離』と『視点の活用』は別の概念ですが、伝え方を考えて相手の視点を活用することが大切。
どんな人が来ようと、その縁を大切にし、知識を惜しまずに。しかし、『考える』だけではなく、『どう活かすか?』も考え、双方にとって最適な形を作る。これにより、無理なく善行を続けながら、仏教の価値を最大限に広めることができる。
何にせよ、何事も物事の本質を見抜くというのは、大事。それからの判断になるから。
そうできると、理想かなと勝手に考えて、勝手にまとめてみました。



ところで…読まれてお気づきでしたか?
課題の分離【補足】個人的な意見
『お寺をそんなことのために利用しないでください!』という住職の言葉が相手の行動(利用しようとする)に反応してしまっていることに。
ここでも課題の分離って必要なの気づいてましたか?
- つまり、『相手の課題』に沿った答えになっているため、感情的に聞こえる。
- 結果として、『お寺はどうあるべきか?』という本質的な意見が存在しない。
例えば、、
『当寺は、修行に重点を置いております故、カメラでの撮影はご遠慮いただいております。』
『他の修行僧もおりますので、カメラでの撮影はご遠慮いただいております。』
『当寺の考えとして、修行とは〇〇のようなものだと考えています。』
『カメラでの撮影無しでしたら、受けられますがどうなさいますでしょうか?』
そういった対応なら、感情に流されず、『こちらの方針』を主体的に伝える形になる。『相手の課題』に巻き込まれずに、『自分の課題』に集中できる。結果として、住職としての在り方がより明確になり、信頼されるようになる。
- 『お寺を何だと思ってるんだ!』は、反応的な態度→これは、相手の行動に振り回されている形。
- 『当寺では修行に重点を置いております故…』は、主体的な態度→これは、『こちらの方針としてこうしている』という能動的な判断。
相手の態度に振り回されて『反応する自分』ではなく、『方針として示す』ことが重要で、こちらの方が感情的ではなく、合理的な判断として伝わりますよね?
相手の課題→有名人や企業家がどんな意図でお寺に来るのかは『相手の問題』。
住職の課題→どんな対応をするか、どうお寺を運営するかは『住職の問題』。
それにもかかわらず、
相手の意図を否定することで、自分の方針を表明しているつもりなのでしょうが、本来は『お寺の方針』を主体的に伝えた方がいい。伝え方の違いが、考え方の明確さにつながる。



『相手の課題に反応する』のではなく、『お寺の継続方針としてどうするか』を軸に伝えることができると、結果として、相手に対しても明確なメッセージを伝えられ、感情的な摩擦も避けられますよね。
個人的な意見です。
『その人の言っていることではなく、行動を見よ』
自分という壁※P201
確かに、その通りだと思う。
ここは、アドラーの課題の分離必要だと思う。


まとめ
相手が『利用しよう』としていようが関係ない。 それは相手の意図であり、こちらの問題ではない。
こちらは『知識を教授する』という任務を全うするだけで、相手の意図に左右されず、ただ淡々と善行を広める。
利用しようと思う心が変わらないかもしれない、それは相手次第。とにかく期待しない、干渉しない。ただ、正しく伝えるだけ。
『有名人である彼の立場』を活用させていただいて、仏教の善行を広める。『利用される』のではなく、『こちらもこの縁を活用させていただく』ことで、主体的に機会を活かす。
この考えにより、相手に振り回されない強さを持ち、相手がどんな意図であろうと、自分のやるべきことを淡々とする。
ただ、自分の立場やそれに関わる人々がいる場合、課題の分離をした後に、相手の視点を活用しながら判断をすることも大切。
基本的には相手に期待しないことで、心が揺れない自分になることができる。



基本的にはこんな風に、普段のことも考えています。
これでいいと、思う。孔子も言ってたから↓



そして、気が向かなかったら『しない』。こういうのも大事。
色々考えるけど、それは自由だから。受けたくないのに受けたら波長が乱れる。私、住職じゃないし。



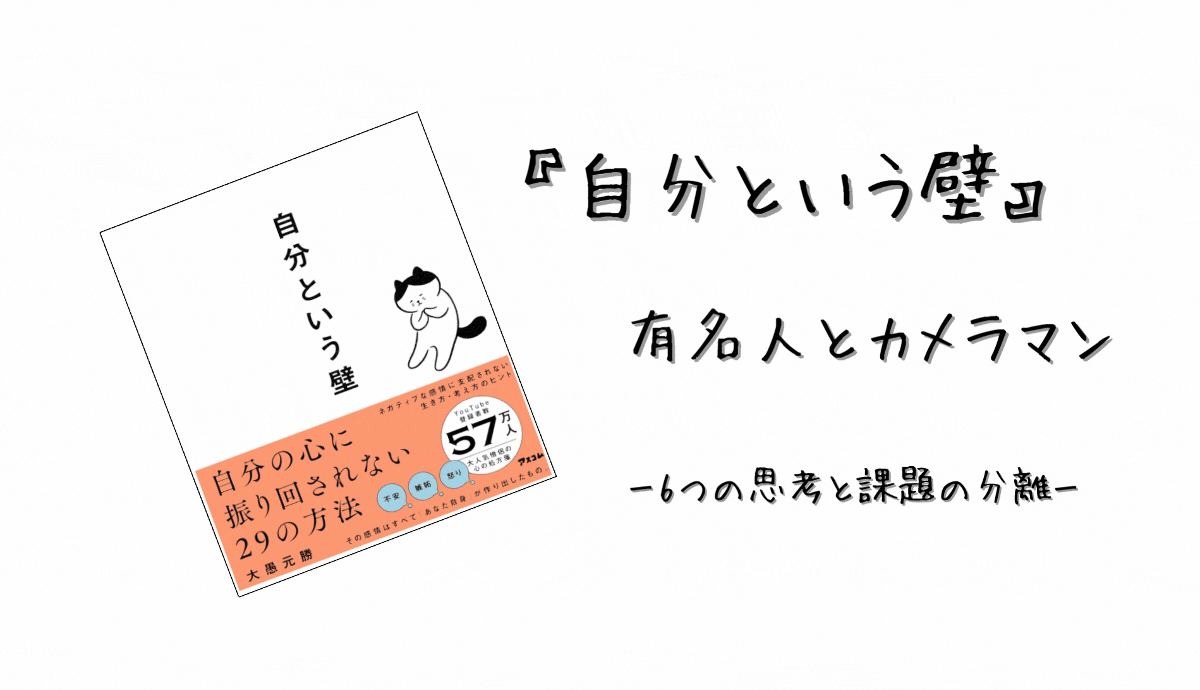

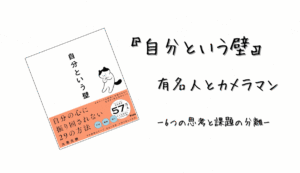
コメント