わたしは日常生活で『課題の分離』をよくしているんですが、慣れてしまうと悩みが減るのでとても便利。
ただ、人によっては冷たく受け取られてしまうこともあるようで、でもそれは誤解です。
ストレスも多く、人間関係でも様々な問題に直面してしまうという人は、課題の分離ができていないかもしれません。

皆、意外にできてないんですよ。話をすると、アレアレ、、、ってよくありますよ。
アドラー心理学の『課題の分離』という考え方は、人生においてかなり役に立ちます。
課題を自分のものと他人のもの、もしくは出来事と感情に分離することで、ストレスは軽減、複雑に感じる人間関係を分かりやすくすることができる。
このブログでは、アドラー心理学で有名な『課題の分離』のコツをまとめてみました。課題の分離の基本的な考え方から、冷たく感じ取られてしまう原因と対処法、具体的な実践方法までをまとめています。
課題の分離とは?初心者にもわかる基本の考え方
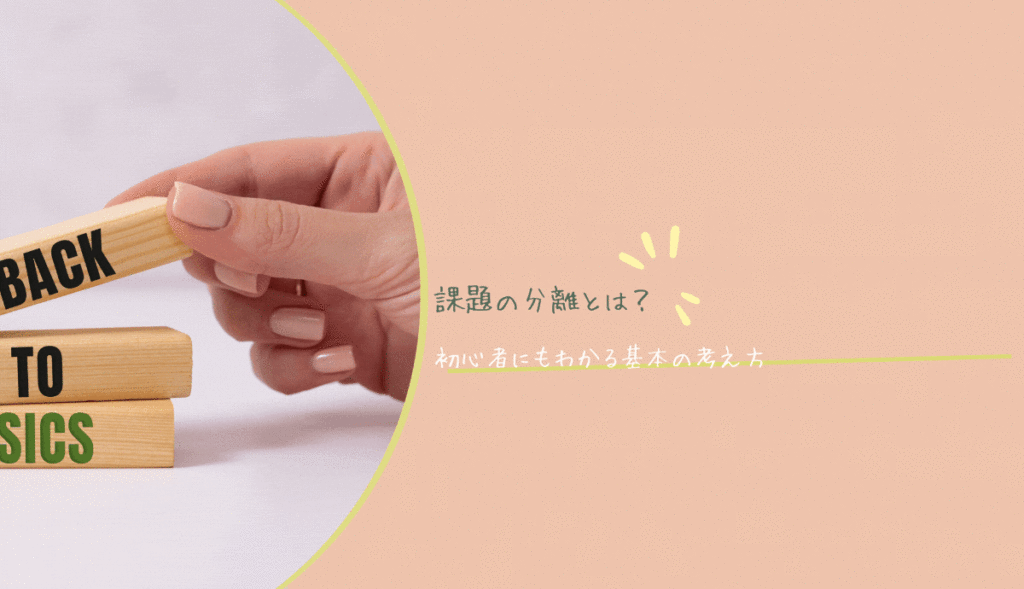
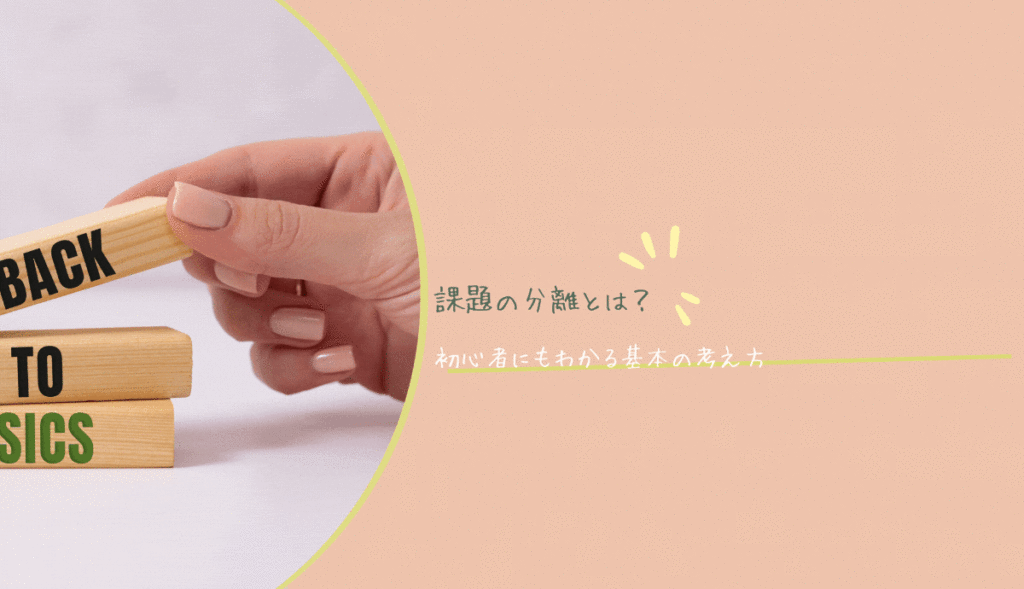
課題の分離は、アドラー心理学の中心的な考え方で、日々の生活の中で活かせる実用的な手法のひとつ。



このテクニックは、『この問題は誰の課題なのか?』という問いを自らに問いかけることで、自分が抱える悩みや問題を整理しやすくしてくれます。
- 課題の分離の基本的な考え方
- 課題の分離の具体的なアプローチ
- 日常生活での応用例
①課題の分離の基本的な考え方
課題の分離とは、自分自身の課題と他者の課題、感情をはっきりと区別するプロセスです。この方法により、以下のような効果を得ることができます。
- ストレスの軽減: 他人の問題に不必要に関わらなくなることで、自分自身の心の重荷を減少させることができます。
- 人間関係の向上: お互いの課題を理解し尊重することで、より良好なコミュニケーションと関係性が築けます。
- 自己成長の促進: 自分に関わる課題にフォーカスすることで、自己成長をより促進できます。
特に自己成長の促進ですが、自分の課題が分かりだすので、自己理解が進みます。ということは、人生を謳歌できるようになる、と言っても過言ではないと思います。



自己成長の鍵、自己理解の鍵は課題の分離です。
②課題の分離の具体的なアプローチ
- 自己分析: 現在の悩みや問題の中で、どの課題が自分のものであり、どの課題が他者に関連するものであるかを確認しましょう。
- 困る人を考慮する: 問題の真の本質を見極めるために、『この問題を放置した場合、誰が困るのか?』という観点から考えることが有効です。これで、本当に自分の課題であるかが明確になります。
- 選択を尊重する姿勢: 他人の選択や行動に対して過度に干渉しないように心掛けましょう。この態度を持つことで、他者との関係が円滑に保たれます。
他人(親や兄弟、友だち)の問題を自分のことのように捉え考えることは、一見、素晴らしい行動にも思えますが、あまり意味はなさないのかなと個人的に思うので、わたしはしません。
他者の立場に立ち、置かれている状況を想像することには意味があるんじゃないですかね。気持ちが理解できるから。
そこで生じる問題と言うものは、あなたが作り出した問題ではないので、解決しようがない。
アドバイスできるじゃん!と思えるかもしれませんが、アドバイスなんて必要ないですよね。



相談に乗り、話を聞くことはできるかもしれませんが、その問題を解決するのは相手であることを忘れてはいけないんです。そこを忘れてしまうと、過干渉ということになる。
基本的には、見守るという選択肢意外ないんです。そこに介入してしまうと、問題解決力を奪うことになってしまう。それは相手のためにならないですよね。
そこから生まれる関係性は『依存』です。共依存。
共依存も悪いだけではありませんが、互いに無知である状態の共依存は弊害にしかならない。基本的には相手の問題解決力を奪ってはいけないんです。



そして、アドバイスしたところで相手は変わらない。これは世の法則です。ここが皆さん理解できていないようです。人は変わらない。なぜか?自分で考えさせてないからですよ。
思考が変わらないでしょう?ということは?行動が変わらない。
こういう答えが容易にでる。
つまりは『1+1=2』こうとしか、ならないということ。
問題はものすごく単純なのに、複雑にしているのはあなた自身なんです。
アドバイスしたところで、同じ問題でまた悩むのが相手、そして何で分からないんだよ!と怒るのがあなた。という世の法則ができあがるだけ。課題の分離って大事なんです。
参考になるのは、こちらの記事かと思います↓


③日常生活での応用例
- 家庭内の例: 子供が部屋を散らかしているとき、親が『これは子供の課題』と理解することで、過度の介入を避けることができます。
- 職場における実践: 同僚の行動に対する不要な心配を減らし、自身の仕事に専念することで、業務の生産性を向上させることが可能です。
人には目や耳があるので、色々な情報を頭に入れていきますよね。
そして思考を巡らせる。その中には、他人の課題であっても『許せない!!』というものもあったりするじゃないですか。



聞いてるこっちがイライラしてくるんだけど!?
こういうときに、課題の分離をして、冷静になるといいんです。



ひと言言ってやらないと気が済まない!!
も、あるかもしれないけれど、基本的には課題の分離をして行った方が人生上手に進むことができます。
他人の問題ほど、介入して拗れるものはないと断言します。
例えば、子どもが部屋を散らかしていてイライラしたとします。
片付けしなさい!!!と言いたいところですが、わたしはこうです↓
部屋や机の中というものは、頭の思考回路と同じで、頭を整理したければ部屋を片付ける方がいいし、部屋を片付ければ頭も整理される。視界から入る情報を遮断するか、頭を整理していくか、どちらかしかない。そして、整理整頓できない人の人生がどうなるかを教えます。
論理的に物事を考えることができなくなる余波まで説明してから、



あなたがそれでいいなら、いいんじゃない?
そして、基本的に私はこう思って自分を落ち着けています。



わたしは困らない。
子どもは、整理整頓をする理由を知らないから。
そこへ知識の穴埋めをします。なぜ整理整頓が人生において重要になってくるかの説明を。
そこから考えるのは子どもの課題ですから。
よく、アドラーの課題の分離の子育て論で、宿題をしないのは子どもの課題だという文言も見たりしますよね。だから親のわたしには関係がないと割り切ることが重要だと。けど、子どもには知識がないから、宿題をしない弊害、勉強をしない弊害を教えるのは親の役目です。
そこまでを放置して、子どもの課題だから親には関係がない、は愚かです。
知識を授けて、そこからは子どもの課題。それが子どもの知恵になるから。
まずは、自分自身の課題と他人の課題をしっかりと分けることから始めてみてください。
課題の分離を実践して得られる5つのメリット
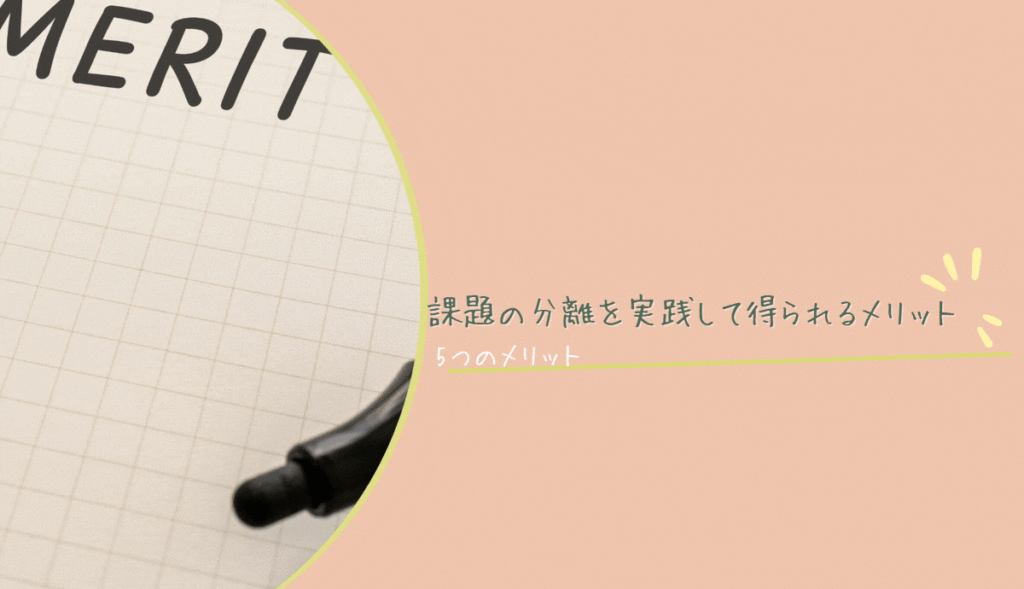
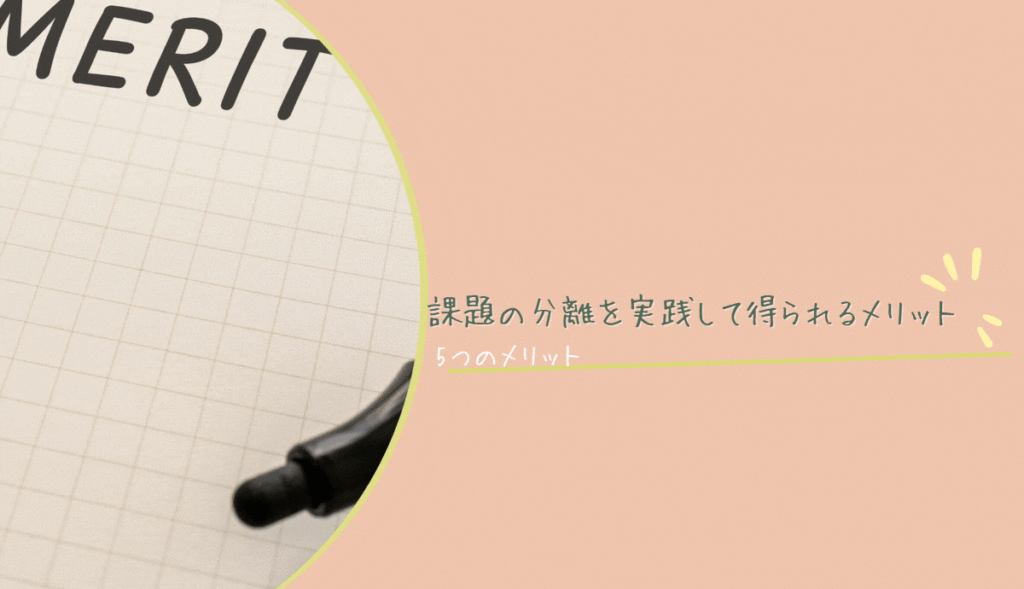
- ストレスの軽減
- 人間関係の改善
- 自己成長の促進
- 自分軸の確立
- 冷静さの維持
①ストレスの軽減
課題の分離を実践することで、最も顕著なメリットの一つはストレスの軽減。
日常生活において、他人の行動や感情に振り回されることが少なくなり、自分の課題に集中できるようになります。
このように、自分にとって重要な事柄にフォーカスすることで、余計な心配や負担を減らすことができるようになる。
②人間関係の改善
次に考えられるのは、人間関係の改善。
課題の分離を通じて、自分と他人の役割を明確にすることができ、嫌悪感や摩擦を減らせます。
例えば、職場でのトラブルや家庭内の対立が減り、お互いの境界を尊重することで、より健全な関係を築くことができるようになります。
③自己成長の促進
課題の分離を実践することは、自分の自己成長にとても役立ちます。
自分の課題に真摯に向き合うことで、主体的な行動が増え、自己理解を深めることができます。
このプロセスを通じて得た選択により、あらゆる面でミスが減り、人間関係も円滑になるので、勝手に自己評価が高まり、自信を持って行動できるようになります。
④自分軸の確立
また、課題の分離は自分軸を持つことにもつながります。
他者に左右されず、自分が本当に大切にしたいことは何かを見つめ直すことができるからです。この自分軸が確立されると、外部からの影響に振り回されることも減り、確固たる意志を持って行動できるようになります。
⑤冷静さの維持
最後に、課題の分離を実践することで冷静さを保つことが可能になります。
ここが冷たいと思われる故でもありますが、感情的になりやすい状況でも、自分と他者の課題を客観的に見極める力が育まれるため、緊張感のあるシーンでも冷静に判断できるようになります。



これは、特に感情的な対立が予想される状況において大きな利点となります。失敗や後悔がなくなります。
以上のように、課題の分離を実践することで得られるメリットは多岐にわたり、人生をより豊かで自由に感じさせてくれる重要な手法であることがわかります。
これらの利点を活用しながら、実生活で課題の分離を取り入れてみることで、ストレスのない生活を送ることができるようになります。
ただ、上述したように、課題の分離は時に『冷たい』印象を与えることもあります。
課題の分離を冷たいと感じてしまうのはなぜ?考え方と対処法


わたしは常日頃から課題の分離が癖になっているんですが、相手によっては『冷たい』と感じてしまう人もいるようです。
理由は、他人のことに対して無関心だと思われがちだということ。しかし、実際は逆で、この考え方は、他人を尊重する行動に基づいています。



むしろ尊重しかしていない。
- 冷たさの源は誤解から
- 感情の境界線を引く
- 信頼の構築
①冷たさの源は誤解から
- 自分勝手な行動の誤解:課題の分離が進むと、『他人に干渉しない=自分勝手、無関心』と捉えられることが多いです。そんなことはなくて、むしろ相手を尊重しかしていません。他人の人生や課題を尊重する行為は、冷たさとは無縁です。
- 干渉と協力の違い:他人の課題に干渉するのではなく、協力する姿勢は温かみを持ちます。たとえば、友人の悩みを理解しながらも、その解決は友人自身に任せるというスタンスが求められます。このスタンスが時折冷たさを感じさせるようです。



課題の分離って、自分だけが諭していると誤解を生みやすいのは確かです。双方に理解が必要な考え方であることは間違いありません。
例えば、こちらは他人の問題に干渉してはいけない前提で話を聞いていても、相手によっては『アドバイスは!?』とか、『わたしに任せないで、どうしたらいいか教えてよ!!』というようなね、考え方の人に遭遇することもあるから。
そこに乖離が生まれると、無機質で冷たく感じられてしまうでしょうね。
②感情の境界線を引く
感情の境界線を明確にすることは、課題の分離において重要です。自分がどう感じるかだけでなく、他人の感情にも配慮する必要があります。以下のポイントを考慮すると良いですよ。
- 自分の感情は自分のものである:他人の感情に影響されず、自分の感情を優先して考えること。
- 他人の感情を受け入れる:他人の感情に対して理解を示しつつ、それに振り回されない。これは、冷たさではなく、理解の表れと言えます。



ここもね、例えば、他人が思いっきり怒ってたとして、こちらが冷静に聞いていると、その態度に更に怒るみたいな現象が生じることもある。
他人の行動に対して冷静に対応していると、感情的でないこちらに無関心さを感じられることがある。けど、違うんですよね。
課題の分離をしている人は知ってるんですよ。むやみやたらと感情に支配されることの無意味さを。
だから、課題の分離にたどり着いてるんです。
③信頼の構築
課題の分離は、相手を信じることで成り立ちます。自分が過度に関与しなくても、相手が自分で解決できる能力を持っていることを理解することが大切で、課題の分離をしている人は↓以下がよく理解できています。
- 信頼をもって見守る:相手が課題に取り組む姿を見守り、その成長を信じる。これが、冷たさではなく、温かい支えとなることを知っています。
- 適切な距離感:相手と良好な関係を築くためには、適度な距離を置くことも重要なことを知っています。この距離感が、真の信頼関係を生む土台となることを理解しています。
互いに信頼がないと『課題の分離』は誤解しか生みません。
こちらが相手を信じていても、相手からそれが無ければ成り立たないですからね。
過度に関与しなくても、相手は自分で解決できる能力があることを理解していても、その理解する行動そのものが冷たい!と感じられてしまうことがある。



ここでですが、こうなってくると、ジレンマが生じてしまうので、わたしは次元というものを参考にするようにしています。
課題の分離は難易度が高い人には高い。依存度が高いと理解ができない部分なんです。
生きていると色々な出来事に遭遇し、人には感情があるから、そこに意識を取られる。そのときに必要になってくるのが課題の分離。これが上手にできないと、他人の問題や感情に支配されることになる。
だから、5次元を保つのって難しかったりするんですよ。
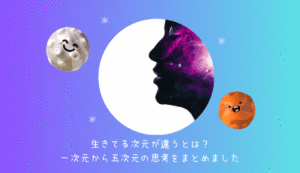
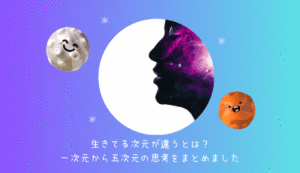
そこからどうなるか?というと、3次元→2次元→1次元に落ちることがある。3以下は磁石のように引きが強いので、落ちるのは容易いですし、感情に支配されるという特徴があります。妬み・嫉みの世界だから。よって、揉めやすい。次元が一度落ちると、なかなか上がるのが難しい。そして、5次元と思っているのに、1、2次元であるという次元の勘違い現象もよく起こることです。
大体次元説明で言うなら、こんな感じかな?と思います↓
| 5次元(一番生きやすい) | 全体を把握するときに視点が追加されて、異なるパラレルワールドも見えるので、リスク回避が容易 |
| 4次元 | 全体を把握することで本質を見極められる、ある程度リスク回避もできる |
| 3次元 | 考えることはできる、全体把握は無理、妬み・嫉みがある |
| 2次元 | 自分の意志はあるけど、言われたことしかできない、妬み・嫉みがある |
| 1次元 | 自分の意志がない、何も決めることができない、言われたことしかできない、妬み・嫉みがある |
自分の意志がない状態にも気づいてないという状態の人もいます。そして、妬み・嫉みのレベルは下に行くほど強くなると思ってください。つまりは悩みが増えるうえに、自身で解決もできないという世の法則が成り立ちます。



難しいのは、この把握ができているか?できていないか?の把握、でしょうね。自分の意志と思っているものが他者の意志である、こういうことは、よくありますよ。自分で決めている(つもり)、つもり人もいますね。決定基準は自分じゃなくて、自分の周りの反応オンリー。
上手に課題の分離をして、感情に支配されず、まっすぐに道を進む。これが5次元以外の人には難しく感じられることがある。
次元が違うと、言っていることがわからなくなるんですよ。素直に聞き入れることができなくなる。
これは宇宙の法則(スピリチュアル)。もちろん異議は認めますが、合ってると思う。
しかし、課題の分離を意識することで、不用意に悩むことがなくなるので、人生を楽しむことができるようになります。



基本的には、次元が違うと思ったら、和解をしようとせずに、そっと見守る方針、もしくは離れる選択をした方が人生上手く行きやすいと思います。相容れることがないから。
できることと言えば、自分が感じた感情、課題の分離をして得た自分の感情を相手に伝える選択くらいじゃないですかね。それをするかどうかは、もちろん自分次第。
他人の課題に振り回されないコツと実践方法
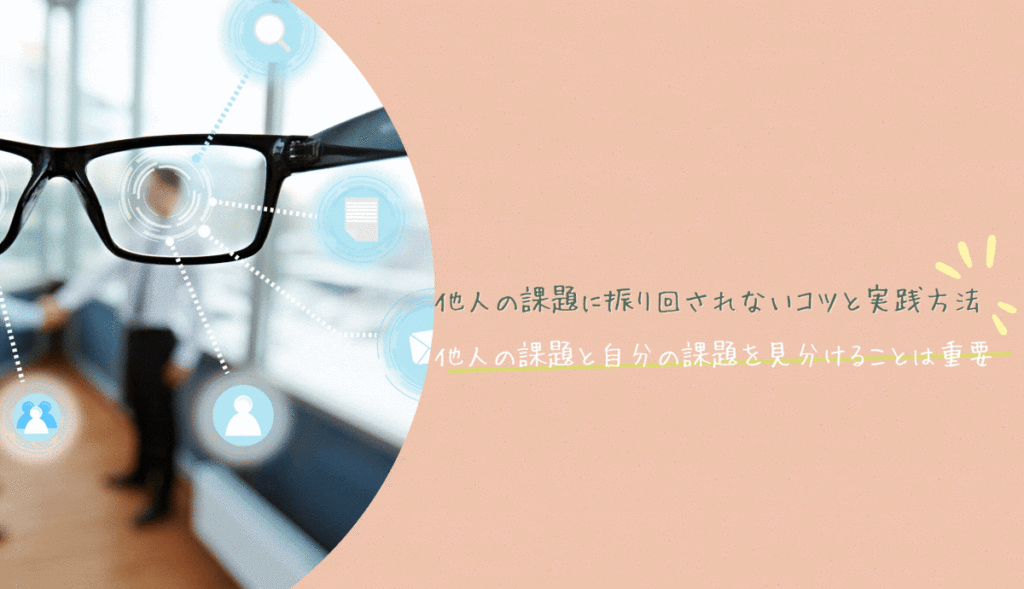
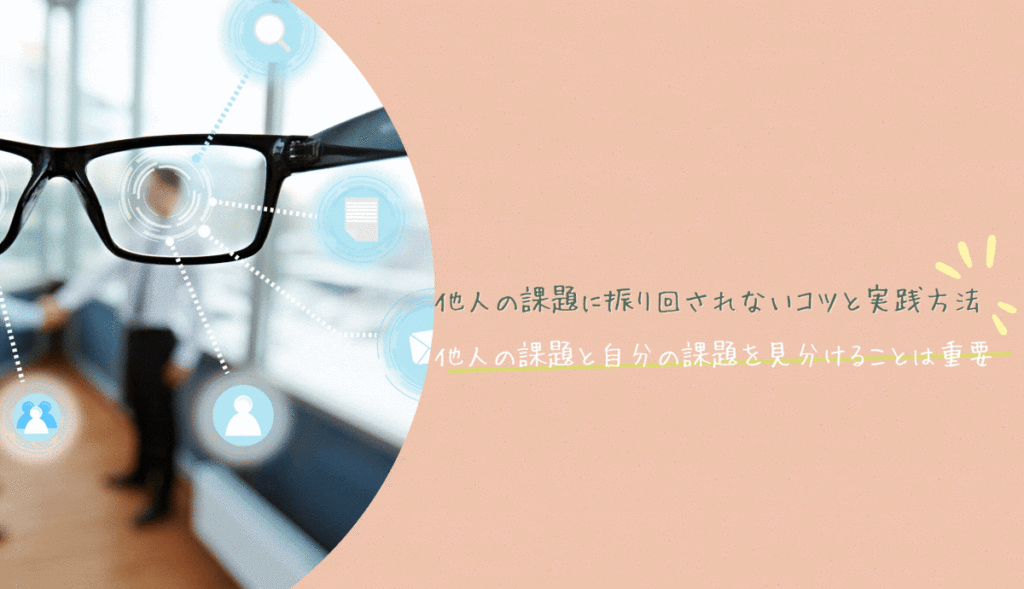
他人の課題に左右されることは、ストレスや不安の元にしかなりません。課題の分離を実践する上で、他人の課題と自分の課題を見分けることは非常に重要です。混乱しやすいこのプロセスを明確にするためのシンプルな方法をいくつかご紹介します。
- 自分の役割を明確にする
- 『NO』を言う勇気を持つ
- 感情を一歩引いて観察する
- 日常生活での実践方法
①自分の役割を明確にする
まず最初に、自己の役割をしっかり理解することが大切。それぞれの状況や立場において、自分が果たすべき役割を意識することがカギ。
職場や家庭、友人関係において自分が担うべきことを意識することで、他人の問題に不用意に巻き込まれるリスクが軽減されます。
例えば、自分の母親が誰かの愚痴を言っていたとして、それを解決するために奮闘するのは愚かですよね。
それは母親の問題であり、自分の問題ではない。介入すべき問題ではないので、聞くだけで良いという結論になります。あと、前述したように、不要なアドバイスも必要ないですね。
②『NO』を言う勇気を持つ
他人の期待に応えるのも重要ですが、自分の時間やエネルギーも大切にすること。
時には、『NO』と伝えることが重要。
相手からすると、この行動を咎められることがあるんですよ。『冷たい!』とか。けど、これは冷たい行動とは異なり、自分自身の限界を認識し、尊重する行為です。
当然です。
マズローで言う『尊重の欲求』は無視できないでしょう?自分の人生ですから。そう、ここから逸れるわけにはいきませんよね。自分にも自己実現の道があるとするなら、それを実現したいから。つまりは自己犠牲ギバーにはならないという選択が必要になる。
課題の分離ができる人は知ってるんですよ、どうしたら最良の選択ができるのか。



逆を言うなら、『冷たい!』と言い放っている人の方が冷たいでしょう?だって、相手に自身の時間すら与えられないんだから。
冷たい?どっちがだよ、そっちがなって話です。
わたしからしたら、そういう人の方がとても冷たく感じる。実際そうでしょう。




③感情を一歩引いて観察する
感情は、他人の課題に影響されやすくなる大きな要因。
特に、怒りや不安が高まると、自分の判断が鈍ります。そのため、冷静に状況を観察する習慣を持つことが不可欠です。
会話中に強い感情を感じた際には、一度深呼吸をし、その感情が自分のものであるか他人に起因するものであるかを識別する努力をしましょう。
要するにここでも、『問題』と『感情』の課題の分離が必要ってことです。
なぜ感情が乱されたのかという、自己理解をすることに意味がある。自尊心を刺激されたのか?それとも相手の皆に対する対応に怒りが湧いたのか?色々あると思うんですよね。
感情を発見できたのなら、課題と感情の切り離しをして、課題の解決だけを先にしてしまいます。
その後に、抱いた感情を相手に伝えるのか、伝えないのかはあなたの自由です。
④日常生活での実践方法
これらのポイントを日常生活に取り入れるための具体的な方法として、以下の方策を試してみてください。
紙に書きだす: 日々の中で自分と他人の課題を振り返り、誰に責任があるのかを書いて明確にしてみることで、自身の責任範囲が見えてきます。どのような状況で課題が発生しているかを把握して、 自分が考える問題を書き出し、それが『自分の課題』か『他人の課題』かを明確に分けます。誰がその課題を対処する責任を持っているのかを自問してみましょう。たとえば、『これは私が解決すべきことか?それとも他人の問題なのか?』
考える時間を持つ: 他人からの依頼について即答するのではなく、自分の意思を示すために思考する時間を設けましょう。『少し考えます』と言うことで、立ち止まる習慣ができます。実はこれは重要で、自分で考えて答えを出すという行動が思考の筋肉を鍛えます。
環境を整える: 他人の影響を軽減するために、生活環境や人間関係を見直すことも大切です。自分に合った環境を維持することで、不要なストレスを減らすことが可能です。次元の話を覚えていますか?次元の違い過ぎる人と一緒にいないことです。
伝え方を考える: 人とのコミュニケーションにおいて、使う言葉がどのような影響を与えるかを考えましょう。伝え方によって、相手に課題を強く意識させることができます。
自分の感情を伝える:『わたしはこう感じる』と、わたしはをつけて相手に伝えることで強要を防ぐことができます。
相手の立場を尊重する:相手に対し、『あなたはどうしたい?』とやんわり聞くことで、相手への課題の干渉を避けられる上、相手の意志を尊重することができます。『わからない』と言われたら、『少し、考えてみたら?』でも十分。
これらのシンプルな方法を用いることで、他人の課題と自分の課題を適切に見分ける力を養えます。日常生活で意識的に実行することで、ストレスの軽減や人間関係の改善が期待できます。



自らの課題に焦点を当てることで、他人の課題に振り回されることがないようになります。忍耐強く少しずつ自己改善に取り組むことで、より豊かなライフスタイルを実現できるはずです。課題の分離も容易にできるようになります。
課題の分離で人間関係がラクになる4つの理由
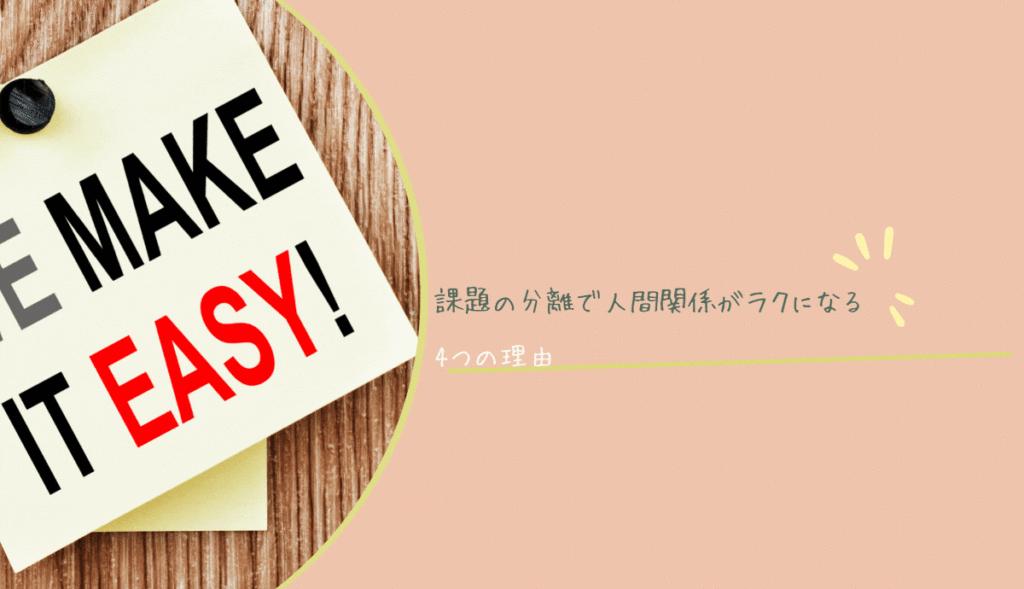
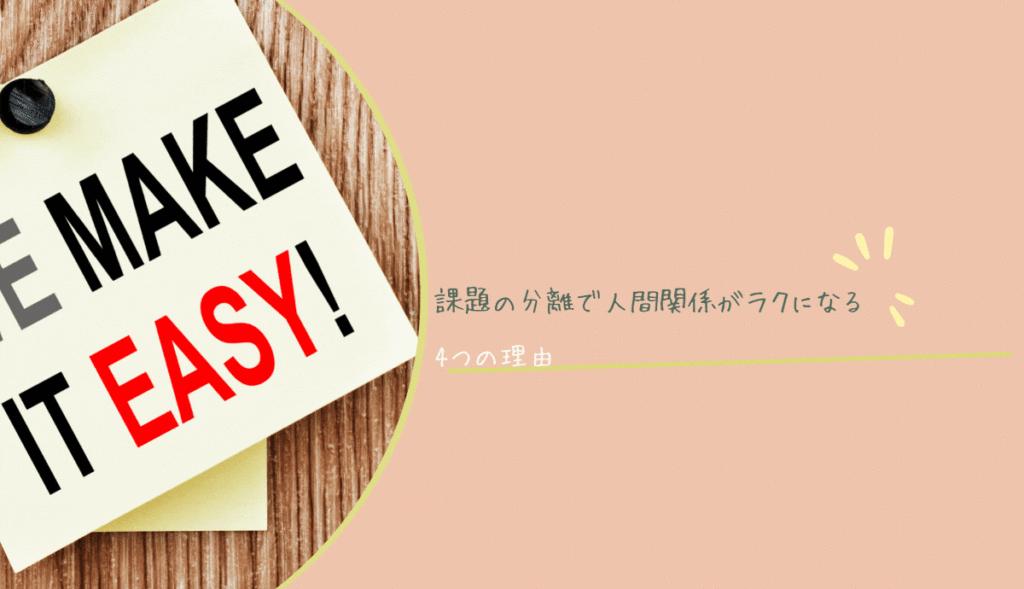
- 自分の限界を理解する
- 健全な人間関係を築く
- ストレスを減らす
- 自己成長を支援する
①自分の限界を理解する
『課題の分離』とは、他の人の問題に引きずられるのではなく、自身の課題にきちんと目を向ける考え方です。
このアプローチにより、自分のコントロールできる範囲がはっきりとして、他人の行動や感情に心を乱されにくくなります。特に、周囲からの期待によって自信を失うことが続く場合、無理に応えようとしてしまうことがあるため、課題を分けることが重要です。
これに意識的になることで、不要なストレスを回避することができるようになります。
②健全な人間関係を築く
課題の分離を取り入れることで、自分と他者の役割が明確になり、適切な距離感を保てるようになります。
例えば、親子間や同僚との関係において、互いに課題を尊重し合うことで、摩擦が軽減され、より協力的で信頼に満ちた関係が構築される。
その結果、コミュニケーションが円滑になるので、以下のような利点があります。
- 互いの責任を尊重:自分自身の役割を理解し、他者の課題に無理に関与しないことで関係が安定します。
- 対話の質が向上:課題を分けることで、理解を深めるための話し合いが進めやすくなり、誤解やストレスが減少します。
③ストレスを減らす
他人の問題に必要以上に反応すると、ストレス値がすごくなる。



当然ですよね、解決できない相手の課題に介入して、変わらない相手に悩み、怒り、変わろうとしない、変わらない相手を変えようとしているんですから。人を変える、神様じゃないと無理ですよ。自分を過信しすぎです。
しかし、課題を明確に分けることによって、『自分は何をすべきか』を意識でき、自己の課題に集中しやすくなります。これにより、次のようなメリットが得られます。
- 感情の制御が可能:他者の影響を受けにくくなり、自分の感情を落ち着いて扱えるようになります。
- 安心感を得やすい:他人の課題に過度に責任を感じることが減り、心に余裕が生まれます。
④自己成長を支援する
課題の分離を実践することで、自己成長を促進できます。
自分の課題に焦点を当てることで、多様な挑戦をする機会が増え、それが自信や自己効力感の向上に繋がります。
また、他者に対してもサポートを提供しつつ、自分自身を失わないことで、建設的なフィードバックを受け入れる余裕ができるのです。こうしたポジティブな影響により、次のような成果が期待できます。
- 主体的な行動の促進:自分ができることに注力することで、新たな挑戦へと進む道が開かれます。
- 他者との信頼関係の構築:自分の役割が明確になることで、相手も安心して関われるようになり、信頼関係が強化されます。
課題の分離は、単に他者から距離を取るための方法ではなく、豊かな人間関係を築くための有効な手段であることを理解できるといいと思います。
まとめ
課題の分離は、アドラー心理学における重要な概念で、自己と他者の課題を明確に区別することで、ストレスの軽減や人間関係の改善、自己成長の促進などさまざまな恩恵を得ることができると思っています。
一見冷たいと感じられがちですが、正しく理解し実践することで、むしろ相手を尊重しつつ、自分の人生を主体的に歩んでいく力を身につけることができます。
さらに、自己の優先順位を確認しながら、他者に対して適切な距離感を保つことで、建設的な対話と信頼関係の構築に役立ちます。
課題の分離は、自己成長を促進し、豊かな人生を送るための重要なスキルです。



日常生活に入れ込んでみると、余計なことで悩まなくて済みますよ。



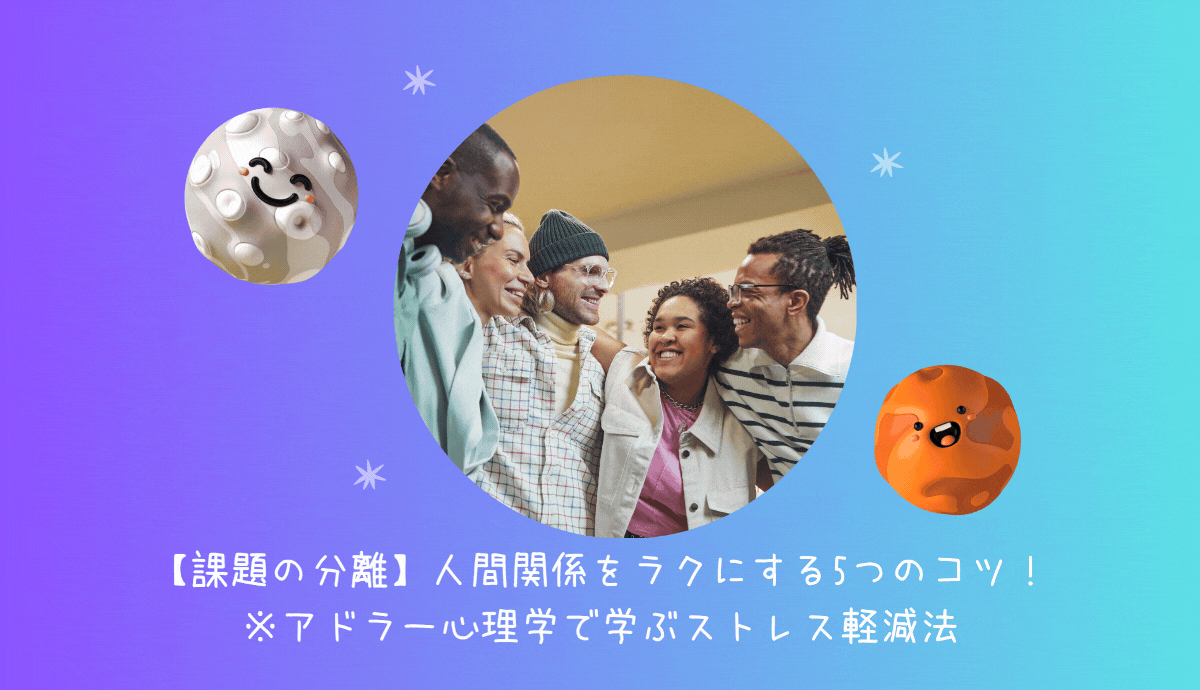


コメント