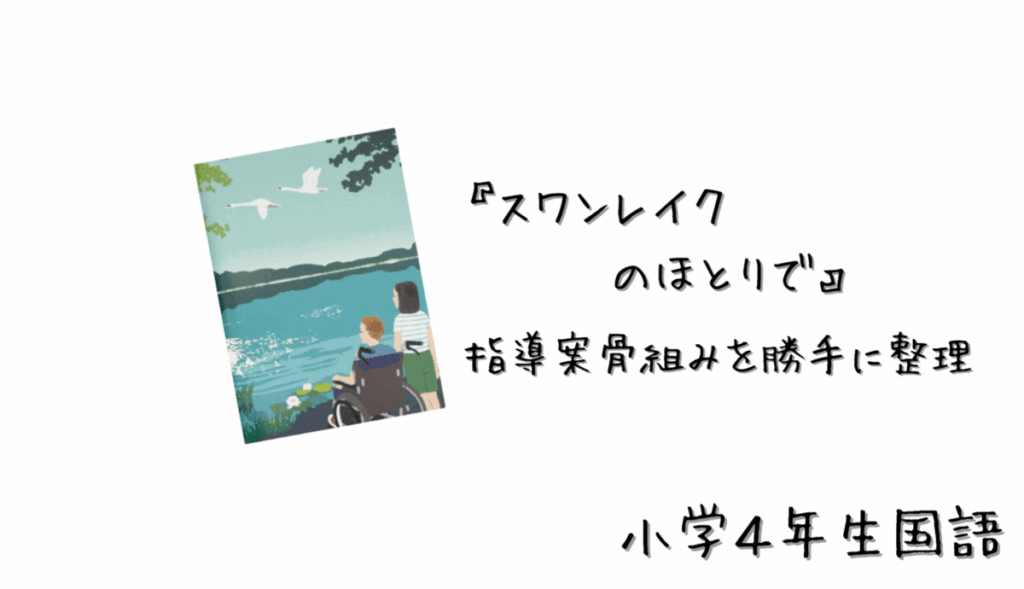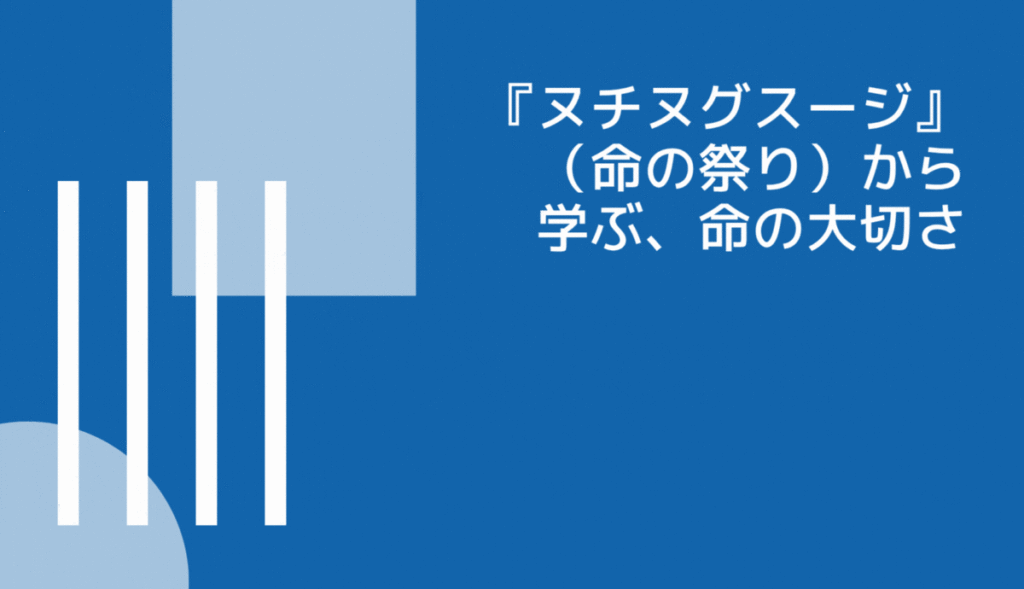MENU
- ホーム
- 本読んできた本の感想を綴っています。要するに、ひと言もの申したい!という内容のカテゴリです。
- 教材
- わたしの知識カテゴリ『わたしの体験談』にある経験から、色々な書籍を読み漁り、この考え方にたどり着いています。読み始めは共通なんて無い、答えすら書いてないと思っていましたが、全ては古代からつながっていました。本は部分で書いている。それをつなぎ合わせたら、ひとつのテーマが出来上がりました。その集大成がこのカテゴリです。
- わたしの体験談このカテゴリでは、人付き合いに悩んだわたしの体験談を綴っています。この経験で、色々な本を読み漁り、他にある『わたしの知識』のカテゴリを作っています。 こちらは体験談、『わたしの知識』のカテゴリは学んだ証です。
- プロフィール
- お問い合わせ
- サイトマップ
- プライバシーポリシー・著作権
- ホーム
- 本読んできた本の感想を綴っています。要するに、ひと言もの申したい!という内容のカテゴリです。
- 教材
- わたしの知識カテゴリ『わたしの体験談』にある経験から、色々な書籍を読み漁り、この考え方にたどり着いています。読み始めは共通なんて無い、答えすら書いてないと思っていましたが、全ては古代からつながっていました。本は部分で書いている。それをつなぎ合わせたら、ひとつのテーマが出来上がりました。その集大成がこのカテゴリです。
- わたしの体験談このカテゴリでは、人付き合いに悩んだわたしの体験談を綴っています。この経験で、色々な本を読み漁り、他にある『わたしの知識』のカテゴリを作っています。 こちらは体験談、『わたしの知識』のカテゴリは学んだ証です。
- プロフィール
- お問い合わせ
- サイトマップ
- プライバシーポリシー・著作権
- ホーム
- 教材