前回の記事では、『誰も見てないのに、なぜか全力で走ってる人』の話をしました。
走らなければ価値がない。止まったら置いていかれる。──そんな強迫観念に追われて、今日も人生を全力ダッシュしてる人、いませんか?
で、今回のテーマは──まさかの『給食』です。
え?いきなり何の話?って思うかもしれませんが、この“食べる”という日常にも、東洋と西洋の思想のズレがバッチリ詰まってるんです。
というのも、わたしの娘が通っていた保育園。
とても良い先生たちばかりだったんですが──ひとり、『善意と信念で全力疾走してる教育タイプ』の先生がいまして。
その先生の給食指導をきっかけに、『東洋思想の“在り方”と、西洋思想の“考え方”がどう教育現場でズレてるのか?』を、今回は深掘りしてみようと思います。
保育園での給食※先生からのアドバイス
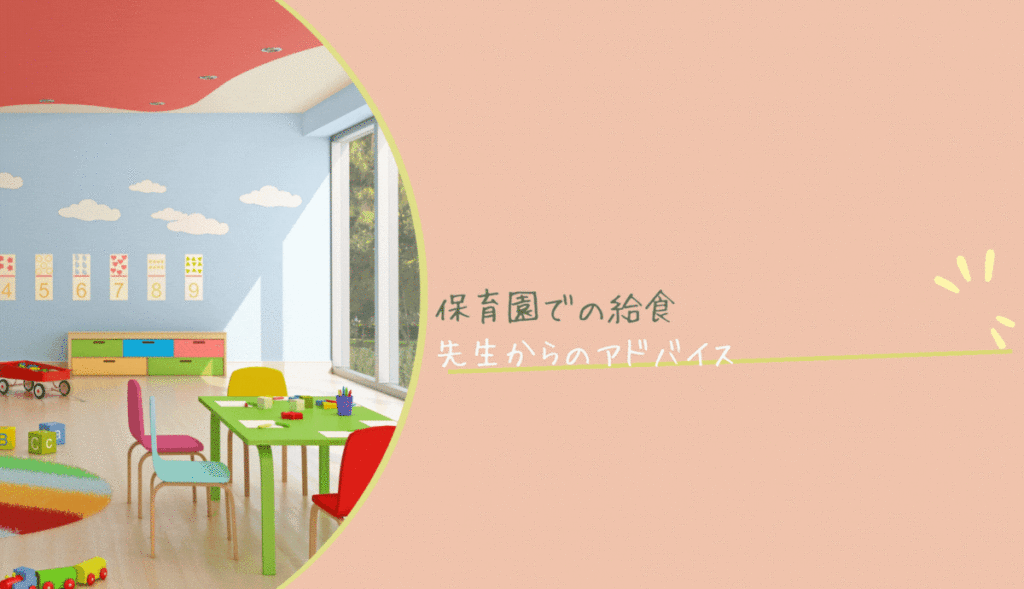
我が子、今は普通に食べることができますが、保育園のころは特に小食で、食べるのがとても遅かったんですよ。
それなのに…担任の先生から、

小学校では、給食の準備の時間があるから、食べる時間は10分くらいしかないと思うんです。
その時間内に全部食べ終わらないといけないから、今のうちに訓練をしておいた方がいいと思います。
食べるのがとても遅いので、明日から持ってくるごはんの量を増やしてください。
※ご飯だけは家から持参



何言ってんだ?
こう思ったんですが、とりあえず提案に乗るのがわたし流。
大体そうしています。
こういう持論タイプは、言ったって効かないから、賛同しておく。



わかりました。明日から増やします。
そして翌日、食べるの劇遅になった娘(当然だろ、想定の範囲内)。
先生から、お帳面に、



頭おかしいだろ。
こう思ったんですが、言い争いしても仕方がないので、
と返答しました。結局、ご飯を大量に持って行かせたのは1日で終わりました。
当然だよね。
何の意味もないでしょ。
給食の時間を苦痛に感じる方が問題だと思ったから。
先生からは
『一時的に少なくするのは、良いと思います。わかりました。』
と帳面に書かれていました。
まぁ、結果オーライです。
私自身、量は少なくても、娘的には足りている。
小学校でどうなるか分からないけれど、その訓練の仕方は間違っている、と判断したので、取り合いませんでした。
今を無理に矯正する必要がないと思ったから。
『食べる量を増やすことで、早く食べる訓練になる』はロジックとして破綻してるし、普通に考えて『量を増やす→時間かかる』なので、目的にも逆行。
『小学校の準備』という建前があるけど、その“準備”の仕方が乱暴すぎる。
本来の準備は『環境に慣れるサポート』であって、『今の個性を否定する訓練』じゃないですよね。
善意かもしれないんですが、わたしからしたら、余計なお世話にしか思えなかった。
善意と肯定したとしても、まずここは保育園、そして年中。
小学校の給食は小学校で考えればよい話だから。
先々のことを考えて手を打つことは有効かもしれないけれど、そういう先手は要らないと思うんですよ。
個人個人成長のペースもあることだから。
現に、給食後に『お腹すいたー』と先生に訴えたことなんて、一度もなかったですしね。
娘的に、量は足りている。野菜や苦手なものも、少し減らしてもらいながらも、食べることはできていたし、残しているワケではなかったので、その後、その問題はスルー。
無事に年長に上がり、小学校へ入学しました。
小学校での給食※まさかの連帯責任
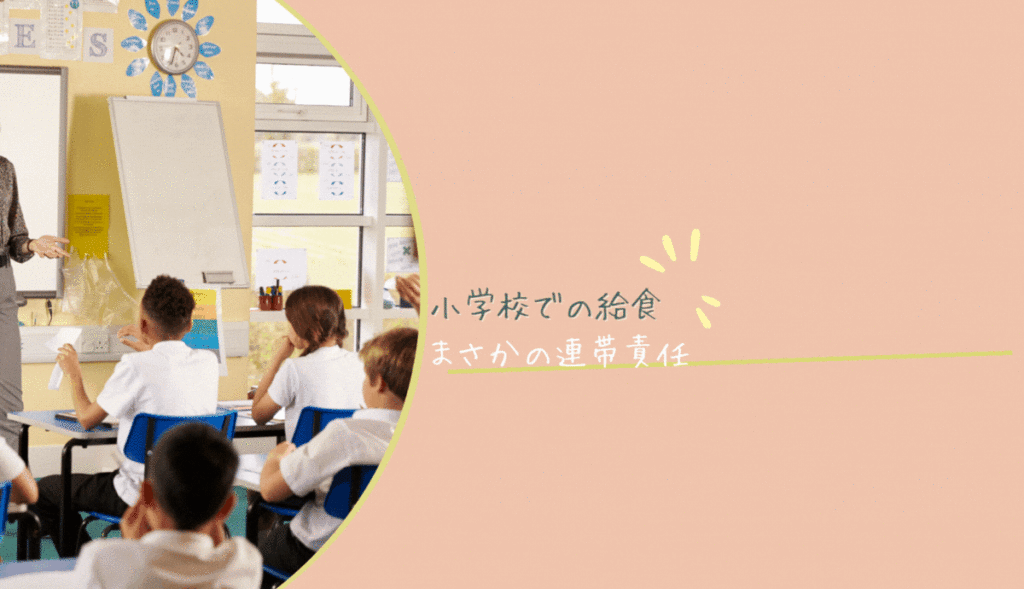
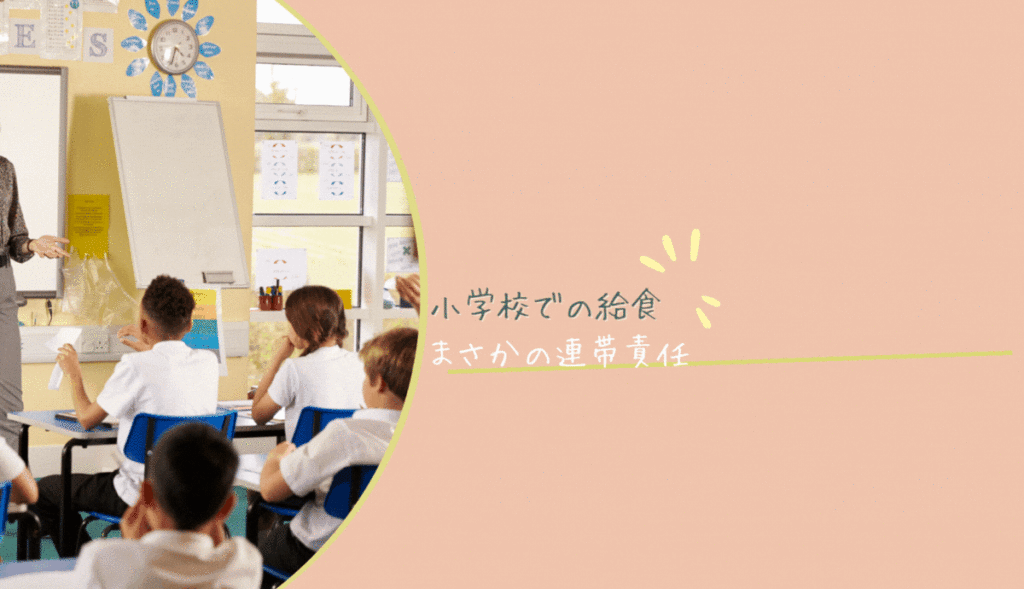
小学校では、普通に食べ切ることができるようになっていました。
先生は、別な記事で紹介した『くるリンパ先生』です。
そこでは別の問題が浮上。
娘から聞いた話ですよ。
先生が、



給食を食べ終わった子は、お片付け、歯磨きをせずに、食べ終わらない子が食べ終わるまで、椅子の後ろに手を組んで、そのまま待ちましょう!!!
早く食べ終わってください!
早く食べないと、休み時間がどんどん少なくなりますよ~!!!!
ほらほら~!



食べ終わった子は、食べ終わった子の応援をしましょう!!
はい!皆でガーンバレ!ガーンバレ!ガーンバレ!


〇鹿でしょ。



くるリンパの次は、ガーンバレ。
娘から聞いたときに、ぶっ飛ばしてやろうかと思った。
まさかの連帯責任。
記事でも書いたように、この内容も先生に手紙で伝えたんですよ。
連帯責任は小学校低学年には早すぎると。
食べるのが遅い子は、プレッシャーを感じるし、食べ終わった子は、あいつのせいでお昼休みがなくなる。
こう思ってきますよね。
小学生ですもん。普通でしょ。



それを、そういう状況を作っておきながら、そういう風に思うことは悪です!止めましょう!も違うし。むしろ、それが正解と思っていたら、そこでまた私は洞察・分析に入る。こういう思考回路ね、了解、です。そして次の体制(こちらの行動)を考える。
こういう小さな所に、その人の世界観があるから。
何のために、待たせるのか?
食べ終わった子から先に促せばいいじゃないですか。
集団生活だし、時間が決められている。
その中で、どう行動(食べる)するのがいいのか?は、本人が考えたらいいことだし、もし、考えが及ばなけば、そこのフォローは大事だと思う。
本来、食育って『栄養の大切さ』や『命の尊さ』を伝える機会でもありますよね。
でも、ここではいつの間にか、
時間内に食べ終わらなきゃダメ
残すのは悪
食べないと休み時間なし
というルール至上主義になっていた。



命の尊さより、昼休みの尊さの方が体感的に勝つでしょ。



栄養?命????
あ!!お昼休みなくなる!!どうしよ!
またあいつのせいかよ!!!!!
こうなりますよね。普通。



野菜を残さず食べなさい!!
早く食べないと皆が迷惑します!!はい!
皆で応援しましょう!!!ガーンバレ!!!



…..公開処刑?
まじで、どこに向かってると思います?
応援されながら食べる給食って、精神的デスマッチでしょ。
──まさに見えないゴールに向かって全力で走らされてる”状態。
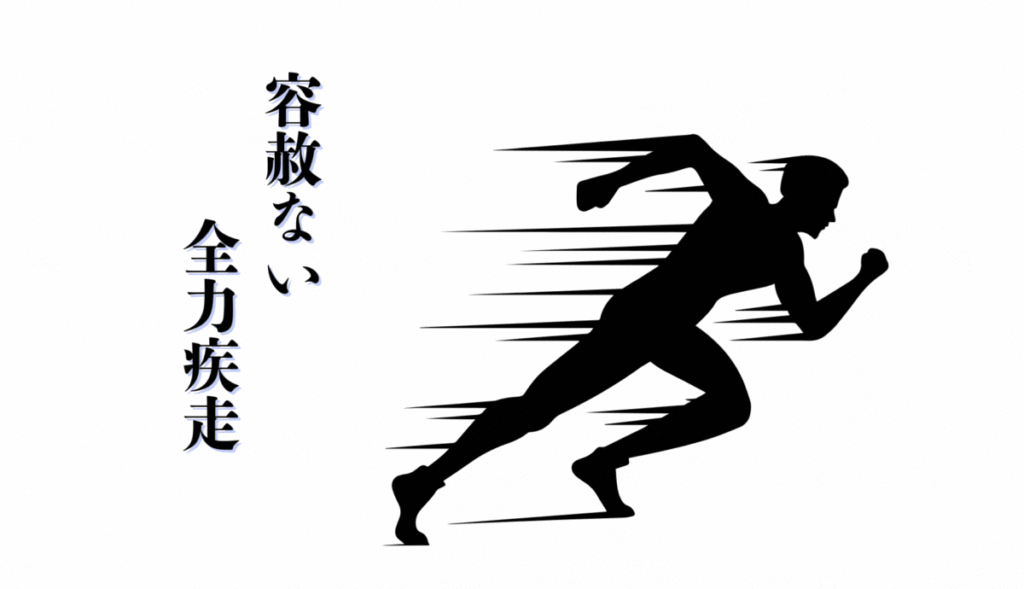
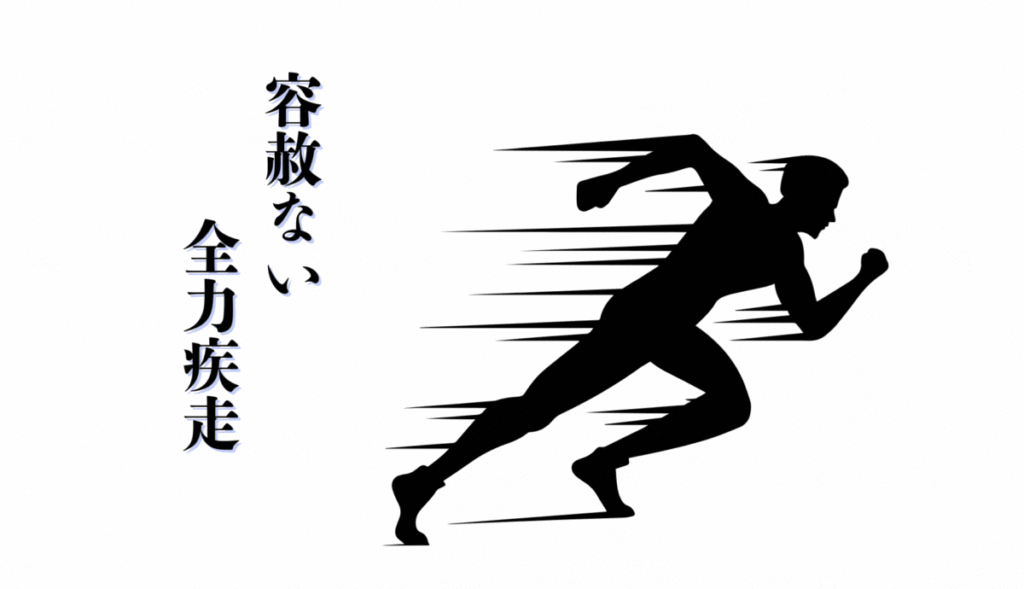
でもそれ、子どもにとってはこう聞こえてる可能性もある。
- 残さず食べられる子が“いい子”
- 食べる速度が遅い自分はダメ
- みんなに迷惑をかけてる自分=悪
- 食べられない=努力不足
- 食べる時間なのに、息抜きじゃなくて試練
- “完食”が評価対象になる
これは、給食だけの話だけど、この思考が人生に影響しないとも言い切れませんよね。
根っこにこういう考えがあるということは、余波がある。
全てにおいて、恐らくそうでしょう。
そういう思考回路での対応が、学校、親といった周りの大人から種植えされれば、全力疾走で走らなければ価値が無い!!と思う少年や少女が現れても、まぁ、そうなるかもね。とも思える。



いいから残せ。
無理に食べるな。
それで何か言われたら、わたしが学校と話す。
そう娘に伝えていました。わたしも、学校給食が苦手で、食べるのが苦手だったから。
完食!完食!って言われて育った世代です。
今でもトラウマ。
多すぎて食べられないんですよ。
トラウマだけど、時間内に食べ終わろうとする思考回路、栄養は、とても大事だと思っています。
結局、学校には言うことなく、1年過ぎましたけどね。
『走らされる給食』を東洋・西洋で読み解くと…
東洋思想のズレ
東洋的な在り方、東洋思想(特に儒教・仏教・道教)に共通する価値観のひとつは、『それぞれ違うけど、ちゃんと場に調和している』ことですよね。
個々が自分の道(タオ/中道/徳)を歩みながら、全体としての調和を壊さない。つまり『同じになること』じゃなくて、『違っていても、流れを乱さないこと』。
でも現場では、『同じスピードで食べる』が“調和”になっていて、ほんとは『無理のない量を、気持ちよく食べる』が自然だったはずなのに、それすら空気で潰されていた。
→ 本来の“自然な在り方”が、表面的な“足並み”にすり替わっている。
西洋思想のズレ
『ちゃんと食べるのが正しい』『残すのは悪』といった正解の押し付けだけが残り、『なぜそうするのか?』『どんな食べ方が本人にとってベストか?』という思考が育たない。
→ ロジカルさの“型”だけが残り、“考える力”は置き去り。
まとめ
このくるリンパ先生は、論外で、東洋でも西洋でもなく、『全員を同じ箱に詰めて並ばせたい“管理思考”』の発露なんですよ。
この先生の教育法は、『考えなくていいから黙って従って』が、教育の場に“しれっと”入り込んでしまっている。
だから、難しいんですけど、そこを除けば、走る人も、給食で苦しむ子どもも、どちらも『型と空気』にがんじがらめになっている。
東洋的な“自然な在り方”は、『空気を読め』にすり替えられ
西洋的な“ロジカルな考え方”は、『正解に従え』に矮小化された
結果、子どもたちは『なぜ?』も『どうしたい?』も言えないまま、誰も見ていないゴールに向かって、今日も黙ってスプーンと箸を握る。
この先生の『教え方の偏り』は、その場限りの問題ではなくて、当然ながらその先生の教育全体に連鎖し、さらに子どもたちの人生観や行動パターンにも波及していきます。
もっと言うなら、実は先生個人の人生にも影響を与える(本記事とは関係がないけど)。
教育というのは、そういう意味で、先生自身の思考回路と人生を映し出す鏡でもある。
つまり、教育とは、『子どもの未来を育てる』と同時に、『先生自身の在り方を露呈させる鏡』。
という視点も必要で、私は、そういうものを含めて、全体を見渡して行ってます。
だから、色々『想定の範囲内』になるということはある。
つまり、たとえば『給食の食べ方』ひとつ取っても、
- ペースを自分で選べない(選び方は教育が必要)
- “正解”から外れると指導が入る(何が正解か?を考える)
- なぜ?と問い返す余地がない(例えば、時間内に食べ終わることの重要性は何か?)
こういう『教育→人格形成→人生観』までの因果の流れを、構造的に見るという視点、危機意識。
そういった“教育の在り方”が積み重なることで、『自分で考えて選ぶ力』や『違っていても大丈夫』という感覚が育ちにくく、結果として、人生でも『誰かが決めた正解を探し続ける人』になってしまう。



例えば、みんなが早く食べ終わるから、自分も急がなくちゃ!!!
とかね。
みんなが早く食べ終わるから、自分も急がないといけないんじゃない。
そうじゃない。
『みんなに合わせる』ために急ぐんじゃなくて、それもある意味必要ではあるけれど、『時間内に食べ終える』という目的の意味を理解して、工夫する。
ただ焦るんじゃなくて、『どうすれば、自分のペースを守りつつ時間内に食べられるか?』を考える。
量を減らすとか。“空気”に飲まれるんじゃなくて、“目的”と向き合って動く。
まとめ
給食の時間に込められているのは、
『命をいただくことへの感謝』
『栄養をバランスよく取ることの大切さ』……
つまり、本来“教養”であるはず。
もちろん、学校が悪いわけじゃなくて、先生たちも必死だし、決まった時間内で全員の配膳・食事・片付けを成立させるのは、本当に大変なことだと思うんです。
あと、野菜、苦手な子はほんと苦手だし。
けど、ちょっと思うんですよ。
保育園でも、時間内に野菜含め完食することを目標にさせられていて、学校では応援という公開処刑。
どうなってるんだろうって。
まぁ、あのくるリンパは論外なんでしょうけれど。
本来、東洋思想は『それぞれ違っても、場に調和する在り方』を大切にすることで、西洋思想は『なぜそうするのか』を考える力を育てるもの。でも今は、東洋も西洋もズレて、『空気を読め』と『正解に従え』だけが残ってる気もする。
問いも違いも許されない中で、ただ“完食が正解”とされる世界。
もちろん、食事は大事ですけどね、それはそうとして、つまり──
本来の西洋思想(ロジカル思考)からもズレている。
本来の東洋思想(多様性の容認)からもズレている。
と感じた。
教育現場が完璧である必要はないし、先生にすべてを背負わせる必要もない。
わたしも、とてもじゃないけど、完璧な子育てはできていません。
だけど、『なぜ?』を封じる構造に、無自覚なまま乗っていくのではなく、子どもと一緒に、“問いながら生きる余白”を持っていたい。
そして、子どもにも『なぜ?』と問い続けてほしい──そう願っています。
わたしは、小さい頃の『なぜ?』に、



世の中そういうものなの。
そのうち分かってくるから。
と言われたことを、今でも覚えています。
小学生のころの出来事です……
でも、全っ然分からなかった。
だから、知識を埋めるしかなかった。



世の中そういうもの?どういうものだよ。
諦めないでほしいんです。
馴染んでいるようで、馴染まないでいてほしいんです。
だから私は、子どもにはこう伝えています。



何でも聞いてこい。全部答えてやる。
『世の中そういうものだ』なんて、絶対に言いたくないから。
もし言うことがあったとしても、説明できるし、それでも納得できなければ、どうしてそうなってるのか、一緒に考えようと思う。





コメント