『こどものろんご』
という本を読まれたことありますか?
どうやって子どもに教養を付けたらいいのかな?
と思ったときに、やっぱり本の知識から得たほうがいいと思って、購入してみた本です。
分かりやすいかな?
と思ってポチってみた。
ところが、内容を読んでみると、わたしの考えと乖離が出る。

これ孔子?
どこそこのページでこう思った。
なので、色々な解釈もあると思いますが、
わたしはこういう風に解釈をしていますよ
というのをページごとにまとめてみました。
知識は疑え。
著者の知識もわたしの知識も疑って、ご自身に合った答えを導かれたらいいと思います。
思想は自由ですから。
何かの参考になればいいなと思います。
『こどものろんご』の感想と口コミ
P12※苟に仁に志せば、悪しきこと無し
苟(まこと)に仁(じん)に志(こころざ)せば、悪しきこと無し
本当に仁を目指し大切にするなら、悪いことはなくなるものだ。
友だち同士でも、何か気に入らないことがあるとけんかになったり、口をきかなくなることがあるかもしれない。でも仁のハートをなくさずにいたら、きっと仲直りできるし、また友だちでいられるはずだ。そしてみんなが仁を大切にすれば、いじめやかげ口(かげで人の悪口を言うこと)、けんかやぼう力など、悪いことは怒らなくなるはずだよ。
ーおうちのかたへー
わがままな心をなくせば、悪いことやいやなことは起きなくなることを理解させたいですね。『こどものろんご』P12



そんな単純?
『仁』とは思いやりの心のこと。
人が『悪』にならないように、
ならないためには『仁』を志す心を持つといい。
こちらの方がスッと入りません?
喧嘩や暴力を目にしたら、子どもだけで解決をしないように、先生(大人)に助けを求めよう。
かげ口を言ってる人がいたら、注意できそうなら注意しよう。
一緒に言いたくないと思ったら、そっとその場所を離れよう。



でよくない?
『わがままな心』ってひと言で難しいよね。
わたしは子どものわがままは聞きたいと思っているから。
子どもの状態が分かるから。
自分だって人間だし、もしかしたら、親としての行動を誤っていることがあるかもしれない。
その振り返りのためにも、わがままは言って欲しい。
モノを買っても粗末に扱い、
あれ買ってー、
これ買ってーのわがままなのか、
甘えたいわがままなのか?
もしかしたら、何かしらの訴えに入ることがある。
見極めが大事でしょ。
買って、買って言うその心はどこから?
モノを買っても粗末に扱うような
『わがままな心』
は無くそうと思って無くなるものじゃないでしょう?
だから悪いことや、嫌なことは起こるでしょう。
だって、わがままな心を持ってしまっている原因は恐らく家庭にあるから、思考が変わらない。
思考が変わらないから、行動が変わらない。
理解させるんじゃなくて、親が向き合わないと。
とわたしは思ってます。
ちなみに私は自分で向き合うしかなかった。
この記事に書かれていることは全て、自分で学んだ証。
P14※これを愛して能く労すること勿からんや、忠にして能く誨うること勿からんや
これを愛して能(よ)く労(ろう)すること勿(な)からんや、忠(ちゅう)にして能(よ)く誨(おし)うること勿(な)からんや
人を愛するなら、励まさずにはいられない。人に誠実であるなら、教えずにはいられない。
友だちが、まちがったことをしたり、よくない考えをしていたら、『それはちがうよ』『まちがっているよ』と、きみから教えてあげよう。それは『よけいなこと』でも『おせっかい』でもない。友だちなら、当たり前にやるべきことなんだ。はげまし合ったり、教え合うのが心の友だちだからね。
ーおうちのかたへー
つらい気持ちでいる友達に対しては、励ましたり、やさしくなぐさめたりすることで力になってあげようねと伝えたいです。ことばで言えなくても、ただ寄り沿うことも大事です。『こどものろんご』P14



……大丈夫?
情愛を掛けているとすれば、
役割を与えて活躍する場所を与え、
誠意を感じれば、教え導くものである。
という意味だと思うんですよ。
あとは、
『かわいい子には旅をさせよ』
とも取れるもの。
それを友達に見立てて説明されたのだと思うんですよ。
友だちが困っていそうに見えたなら、手を貸すかどうかは相手に聞けばいいよ。
必要であれば、
『手伝って、教えて』
必要なければ、
『ありがとう、今は大丈夫だよ』
こう言うはず。
『手伝って、教えて』
そうお願いされたときには、一生懸命教えよう。
友だちができるようになったら、それを一緒に喜ぼう。
友だちが間違ったことをしたり、
よくない考えをしていたら注意をするとありますが、人によっては揉めますって。
『余計な事』でも『お節介』でもないとありますが、人によっては十分余計なことで、お節介と思われることもある。当たり前にやるべきこと、励まし合ったり、教え合うのが心の友達?
机上の上の空論になっちゃう。
美しいけれど、現実はそうもいかないこともあるから。



処世術教えとくしか、手立てがないでしょ。
あと、励ましたり、やさしくなぐさめたりすることで力になってあげようね。
の『あげようね』が嫌。
P16※巧言令色、鮮なし仁
巧言令色(こうげんれいしょく)、鮮(すく)なし仁(じん)
ことばが巧みで見た目ばかりよくしている人は、仁が欠けているものだ。
調子いい人はまごころが足りない。
ことばに心がこもっていないことや、外がわだけカッコつけていることは、みんなにすぐばれてしまうよね。孔先生は、こういう人は仁(思いやり、まごころ)が足りないと言っている。仁があれば、ことばや見た目をかざるひつようはないし、気持ちはちゃんと相手につたわるはずだよ。
ーおうちのかたへー
やさしやや思いやりは嘘やかざりのない『まごころ』から生まれてくるものです。口先だけのカッコつけ君には、そういう素直な心や純粋な気持ちが欠けていることをうまく伝えたいですね。『こどものろんご』P16



着飾っちゃダメなの?
そっちじゃないよね?
巧みな話しぶりで、お世辞ばかりを言い、人の顔色を伺う人間には、誠実さや『仁』は備わっていない。
ということで、調子いい人には、まごころが無い。
という意味ですよね。
格好ばかり気にして内面を気にしないってことかもしれないけど、本人の自由だし好きにさせたらいいことですかね。どの道、見ればどんな格好してようが、発言ひとつでその人の程度はわかるだろうから。
口先だけのカッコつけ君がいたとして、そうなってしまってる原因は何でしょうね。
伝えるだけじゃなくて、どうしてそうなってしまっているのか?
という目線がおうちの方に必要な気がする。
けど、そういう人を見てしまったときの対処法くらいは、子どもに教えておきたいかも。
わたしは、孔子は見た目のことは言ってないと思うけど、一応言っとくよ。
人は見た目が9割とも言われているから『見た目』も大事。
けど、人に取り入ろうとする人には、誠実さが足りてない。
そういう人は自分のことしか考えない人だから。
外見を着飾っている人に、思いやり、まごころが無いと決めつけてもダメ。
強く見せたいっていう弱さとか、自己表現であることもあるから。
あくまでも言葉や態度で見ること。
お世辞言いまくって調子いいだけの人に期待なんかするなという意味だよ。
大体、人というものは『発言と行動』この2つを見れば分かるから。
普段の格好なんて清潔であれば、何でもいいんだって。
P18※君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
君子(くんし)は和(わ)して同ぜず、小人(しょうじん)は同じて和(わ)せず
しっかり者は、みんなとなかよくできるけど自分の考えをちゃんと持っている。
君子は人と仲良くできるが、いい加減に同調することはない。未熟な者はすぐ他人に同調するが、心から仲良くなるわけではない。『こどものろんご』P18



?
徳の高い人は、他の人たちと協調(協力)はするけれど、だからといってむやみと同調(雷同)するわけではない。 それに対して、徳の低い人は、他の人たちに同調はするけれど、協調はしない。
という意味だと思うんですよ。
賢い人は、協力しながら同じ問題を解決しようとするけれど、そうでない人は、調子ばかり合わせて、とりあえず同じにする選択をしてしまうということだよ。
同調って、相手に調子ばかり合わせることはとても簡単で、あまり良い関係とは言えない。
ちゃんと自分の意見をはっきり言って、協力できるような関係を作っていけたらいいね。
『しっかり者は、みんなとなかよくできるけど自分の考えをちゃんと持っている。』



みんなと仲良くできる人には自分の考えが無いみたいな言い方にも取れますね。
『けど』はいらないでしょ。
『そして』が正しいでしょ。
いちいちパニックだよ。
P20※子貢、友を問う。子の曰わく、忠告して善を以てこれを導く。不可なれば則ち止む。自ら辱めらるること無かれ
子貢(しこう)、友を問う。子の曰(い)わく、忠告して善を以て(もって)これを導く。不可なれば則(すなわ)ち止む。自ら辱めらるること無かれ
相手の身になっていろいろ忠告し、正しい道にもどしてあげるべきだね。しかし、いくら言っても聞かないならやめて、ムリをしてきみが恥をかかないようにしたほうがいいね。『こどものろんご』P20



ムリをして恥をかく。
どういう状況?
忠告するときには善意を尽くして忠告する。
その忠告が聞かれなければ、やめる。
相手に聞く気が無いのに言い続けて、うっとうしいなと思われたりすることの無いように。
という意味だと思うんですよ。
状況が分からないですが、自分が思う正しい道が相手にとって正しい道とは限らないというのも、あると思います。
そこを理解できていれば、無理強いするという行為すらも無くなると思うんですよね。
そこで無理をするということ自体が愚かな行為に相当するとは思う。
相手のことを思うというのは、自分の思う正しい道に戻すことじゃなくて、気づきを与えるということだと思います。
気づきさえできれば、その人の人生を歩ける。
忠告しすぎると、自分が忠告した本人から咎められることがあるということ。
その人の人生は、あなたのものではないから。
あなたの『善』がその人にとっての『善』とも限らないでしょう?
出すぎた真似をするなって意味だよ。
誰しも、聞けるとき、聞けないときという期間が存在するから、そのときはそっと見守った方がいいよ。
相手のことを考えて、助言できる勇気を持てただけで偉いよ。
P22※義を見て為ざるは、勇なきなり
義を見て為(せ)ざるは、勇なきなり
いじめを目にしたら、放っておいてはだめだ。
行うべきことを前にしながら、行わないのは臆病者だ。
信用できる友だちに相談して、何人かで協力してやめさせるか、先生にありのままに言ってみること。
ーおうちのかたへー正しい行動にこそ勇気を使うべきだということを教えたいです。
『こどものろんご』P22
正義の行いだと知りながら実行しないのは、勇気がないからである。



という意味でしょう。
わたし、『ベキ論』好きじゃないんですよ。
正しい行動を知りながら行わないのは、勇気がない証拠。
これでいいと思う。
いじめを目にしたら、子どもだけで協力してやめさせるのは、止めなさい。
必ず大人を呼びに行くか、解決したとしても報告をすること。
大人は最善策を知っているから、その方法で正しかったかどうか、聞くといいよ。
間に入れることで、揉めずに解決することができるから。



わたしは、学校でのこういった出来事は全部報告するように伝えています。
先生とて人間、間違った対応があるかもしれない、それはそれでいいから、とりあえずママに報告してね、と伝えています。
何が悪かったのか、どこでどうした方が良かったのか、全部子どもと話し合うようにしています。
そしたら次に生かせるから。
P24※君子は人の美を成す。人の悪を成さず。小人は是れに反す
君子(くんし)は人の美を成す。人の悪を成さず。小人(しょうじん)は是(こ)れに反す
君子は他人の美点をほめて伸ばし、欠点は小さくしてやるが、小人はその反対のことをする。
友だちの欠点については、『気を付けて』とそっと教えてあげたり、それが目立たなくなるように直してあげるといい。
ーおうちのかたへー欠点は小さくしてあげるのが本当の友だちだと教えたいです。
『こどものろんご』P24



何様?
君子は、人の善行や成功を心から喜ぶことを願い、人の悪行や失敗を喜んだりしない。
ところが小人は、その反対のことをする。人の美や成功を心から喜べる人物でありたい。
こういう意味ですよね。
成功を手にしている人の背景には、必ず努力があるんだよ。
あなたも努力していて、敵わないときには、あなたの倍努力している証拠。
だから、その努力に心から『おめでとう』だね。
友だちに何か助言をするときには、
『~の方がいいかもしれないよ。もっと良くなりそう!』
くらいの言い方で伝えた方がいいかもね。
あとは、『~ができるなんてすごいね、~したらもっと良くなるんじゃないの?』とかね。
こっちの方が聞きたくなるから。
『気を付けて』『しない方がいいよ』『ダメだよ』は全部否定から入るから、聞けなくなっちゃう。
お友だちのことを思うのなら、むしろそっちの方に気を付けて。
P32※これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず
これを知る者はこれを好む者に如(し)かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如(し)かず
知っているというだけでは、それを好きな人にはかなわない。好きというだけでは、それを心から楽しむ人にはかなわない。
ピアノなどの楽器やクラスの合唱の練習なんかも、好きになる以上に心から楽しんじゃえば、きっとどんどんうまくなる。勉強も同じだよ!
ーおうちのかたへー心から楽しむほどではない。そんな子には何か夢中になれるきっかけを与えられるといいですね。上達をほめてあげ、発表会などは親も一緒に盛り上げ、『すごいなぁ、すばらしいなぁ』と楽しみましょう。
『こどものろんご』P32



え?
知識があっても、その学びを好きな人にはかなわない。
その学びが好きな人は、その学びを楽しんでいる人に及ばないものである。
こういう感じだと思うんですよ。
習い事でも何でもですけど、楽しんでしている人には敵わないって言うじゃないですか。
アレでしょ
ピアノ、ダンス、サッカー、バレエ、書道、色々な習い事があるけれど、それを『好き』という人よりも、楽しんでいる人には適わないもので、結果が伴わないのなら、楽しみ方が違うだけだと思う。
楽しんでしている人って、努力を努力とも思わない人だから、練習時間とかも人並外れて当たり前だったりするのよ。
それを他人が見たら、相当の努力!!
と思うんだけど、本人からしたら、努力?当たり前のことだけど?という感覚があって、ここから違うのだから、結果は違って当然なのね。
だからと言って、楽しもうと思って楽しめるものじゃないから、『なんとなく好き』だけで続けているものがあったら、一度考えてみるといいと思うよ。
あと、発表会を一緒に盛り上げ『すごいなぁ、すばらしいなぁ』??
アドラー心理学では、褒めずに勇気づけをすることを推奨されていて、わたしはそれを支持しています。



わたしなら、ピアノの選曲のセンスが素晴らしかっただとか、間違えたとしても、力強く弾くところと、ゆっくりと弾くところの強弱が素晴らしかった、だから間違いなんて気にもならなかった。
姿勢が良く舞台の上で堂々と挨拶している姿が素敵だっただとか、そういう勇気づけをしますけどね。
P35※学びて時にこれを習う、亦た説ばしからずや。朋あり、遠方より来る、亦た楽しからずや
学びて時にこれを習う、亦(ま)た説(よろこ)ばしからずや。朋(とも)あり、遠方より来る、亦(ま)た楽しからずや
学んでは適当な時期におさらいをするのは、嬉しいことだね。友だちが遠くから会いに来てくれるのは、楽しいことだね。
孔先生は、おさらいとすると、とてもうれしい気持ちになると言ってるよ。しかも『友だちが遠くから会いにきてくれたときと同じように、うれしくて楽しい』と言うんだ。
むりにがんばっておさらいするのではなく、『ちょっと友だちに会いに行ってくる』みたいな楽しい気分で復習のノートを開いてみたらどう!?
ーおうちのかたへー
いまはパソコンや携帯端末で何でもすぐ調べたりチェックすることがでいますが、孔子のことばのように、久々に友に会うようなゆったりとした気持ちで勉強させることも大切かもしれません。『こどものろんご』P35



これ何語なの?
これ、『人知らずして慍(うら)みず、また君子(くんし)ならずや』と続きます。
学んだことを復習するのはより理解が深まり楽しいことだ。
友人が遠くから訪れてくれて学問について話し合うのは喜ばしいことだ。
人に存在を認められなくても気にすることなく、自分のやるべきことを粛々と行うことができる人は、一角の人である。
学んだことは復習することで、もっと理解が深まる。
理解が深まると次々と色々なことが分かってくるから、楽しくなるよ。
楽しさって、ついつい人と共有したくなるし、学んで得たことを人に伝えられるのはひとつの喜びにもなるから、友だちと同じ学びについて語り合えるのはすごく喜ばしいこと。
同じ学びについて語り合えるということは、滅多にできることじゃないから。
そういう人に出会えると素敵だけれど、出会えなくても自分のするべきことを日々行い、さらに学んで行くことができる人になれるといいね。
P36※憤せざれば啓せず。悱せざれば発せず
憤(ふん)せざれば啓(けい)せず。悱(ひ)せざれば発せず
自分で悩みわかろうと求めていないうちは、指導しない。自分の考えを口から出そうとしていないうちは、示さない。
生徒が、自分の考えをうまくことばで言い表せなくてウズウズしてるときも、先生はじっと待ってから、ヒントをあたえ、みちびいてあげたんだ。
授業中、ぼーっとして聞いているだけじゃ、先生も教えがいがないよね。きみも『知りたい!』というわくわくする気持ちをなくさないようにね。『こどものろんご』P36



無くすもなにも、最初から無いんでしょ?
頭で分かっていながら、それを表現する方法が分からず、口に出せないで、もどかしく思うほどの積極性がないうちは、教えない。
子どもへの指導は難しいですよね。
無いものを持ちましょう!
というのは簡単だけれど、
正しくは
『持てるように教育するのこと』でしょ。
先日、読書感想文について子どもと語っていて、どこでどう思ったのか?
という問いに、『~がやさしいと思った。』と答えたんですよ。



どうやさしいと思ったの?



~なのに、~と言えてたから。



~て言えると何でやさしいと思うの?



・・・・えっと、~なのに、~ていう言葉を言えてたから・・。



・・・言えたから?そう言うことが何でやさしいの?



だって、~なのに、、



自分は~というひどい状況なのに、その状況下で人にやさしい言葉をかけられたというその行動のこと?



そう!それ!



自分が~できない状況と、掛けるやさいい言葉はイコールにならないでしょう?
ひどい状況下にも関わらずまで言えて満点。で、もっと言うなら・・・
で、熱く語って、娘ドン引きって言うね。本末転倒ですよ。
パッパッと書いていますけど、結構時間かかってるんですよ。
でも、これを対応するのなら、、
難しいなら、学年を下げる(留年じゃないですよ)。
3年生なら2年生の問題集をさせる。
そして満点取らせる。ここに戻ります。
自分にもできるという自信をつけさせることから始めるかもしれません。
そうじゃないと、ワクワクも生まれないだろうから。
読書ならレベルを下げるとかね。
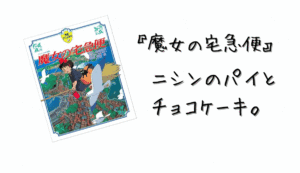
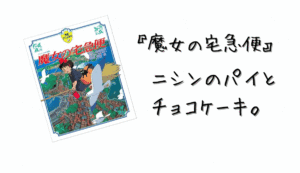
P40※故きを温めて新しきを知る、以て師と為るべし
故(ふる)きを温めて新しきを知る、以て(もって)師(し)と為(な)るべし
古いことをよく学習し、そこから新しいことも学んでいくなら、人の教員になれるだろう。
何も知らずにいたら、百年も昔の人と同じことをやって、『これは自分の発明だ!』なんて、かんちがいをしてしまうこともあるからね。『こどものろんご』P40



誰だよその勘違い野郎は。
昔の出来事や学説を研究して、現在にも通じる新しいものを発見することができたら、指導する立場になれる。
歴史を学んで、現代がどう作られてきたかを学ぶことは、未来を読む力を育てるためにも大事だと思う。
この孔子の論語もそうで、言葉は難しいけれど、生きて行くための知恵・知識が詰まっているものなのね。
この知識を元に考えて、行動することに意味があって、これが原理原則になって行くの。
この知識も無いままに社会に出てしまうと、原理原則が分かっていないから、正しい行動が分からず迷うことになる。
そのためにも、歴史ある書物を読むことも大事だし、歴史を学ぶことも大事なんだよ。
そして、学んだことを誰かに教え伝えて行くことに意味があるんだよ。
P52※君子は泰にして驕らず、小人は驕りて泰ならず
君子(くんし)は泰(ゆたか)にして驕(おご)らず、小人(しょうじん)は驕(おご)りて泰(ゆたか)ならず
君子は落ち着いていていばらないが、未熟な者はいばって落ち着きがない。
ーおうちのかたへー
必要以上に騒いで落ち着きのない子には、『静かで落ち着いている子はオトナに見えてカッコいいね』と話してみてはいかがでしょう。『こどものろんご』P52



それでどうにかなる?
人間の出来ている人は、泰然として威張らず、高慢ではない。
人間の出来ていない人は、威張り散らして落ち着きがない。
威張っている人をみたら、自己肯定感がないと思って大丈夫。
誰かに認めて欲しくて仕方がないの。
気になるなら、『威張ってるけど、わたしに何か認めて欲しいの?』とか、『褒めてもいいけど、それで自己肯定感はできないけど大丈夫?』って聞いてもいいし、ほっといてもいいし、好きなようにしたらいいよ。わたしが責任は持つから。
『人の振りみて吾ふり直せ』とも言うから、自分もそうならないように気をつけようね。



必要以上に騒いで落ち着きのない子に言って聞かせるんじゃなくて、なぜそうなってしまっているんだろう?という目線も大事だと思います。気にしすぎも良くないけれど、気にしなすぎ、言って聞かせるだけも問題だと思うから。
P56※仁遠からんや。我れ仁を欲すれば、斯に仁至る
仁遠(じんとお)からんや。我れ仁を欲すれば、斯(ここ)に仁至(じんいた)る
仁は遠いものだろうか。自分から仁を求めれば、仁はすぐに自分のもとにやってくる。
『いや、そうじゃない。きみがそれを求めるなら、それはすぐにきみのものになるよ』と孔先生は言っているだ。誰にでもやさしい人になろう。きみが本当にそう心に決めたのなら、思いやりもやさしさも、きみのものになる。
仁というのは、もともと人の心にあるものなんだ。きみの心からもずっとはなれないよ。
ーおうちのかたへー仁(思いやり)はけっして遠いところにあるわけではないのに、それが自分にも周りにも大切なものだと気づかないうちはなかなか身に付きません。友だちや兄弟と仲良くすること、ペットを可愛がること、弱い子や困っている人に手を貸すこと、そうした日常の行動をほめてあげることも子どもの気づきには大事です。
『こどものろんご』P56



?色々入ってこないって。
仁は手の届かない遠いところにあるものではない。
自分が仁を求めれば、あなたの目の前にいつでもあるのです。
思いやりは、いつでも自分のそばにあって、人の小さな親切、それに気が付かないだけだって意味だと思います。
例えば、辛い出来事があったときに、友だちがずっと話を聞いてくれるとするじゃない。
やさしい友だちだよね。朝、『おはよう』って言ったら、友だちも笑顔で『おはよう』って返してくれるでしょう?嬉しいよね。
だから、自分だって友だちが話を聞いて欲しいと言ってきたときは、聞きたいと思うだろうし、挨拶だって、元気に『おはよう』って笑顔で返そうと思うもんね。
逆もあるでしょう?自分がしたことを友だちがしてくれるってこともある。
そういう意味だよ。
思いやりややさしさって、難しいことじゃなくて、気づかないだけで、すぐそばにあるの。
当たり前のことが、思いやりだしやさしさの行動なんだよ。
すでに自分にあるものだし、友だちにもあるものなんだよ。
P58※剛毅木訥、仁に近し
剛毅木訥(ごうきぼくとつ)、仁に近し
真っ正直で勇敢で素朴で寡黙なのは、仁者に近い。
正直でかざりっけがなくて口下手な人は、けっこういいやつが多いんだ。
『巧言令色、鮮なし仁』の反対の言葉で、『口下手だしカッコよくないけど、真っ正直で勇気のある人は、仁(思いやり)が深いものだ』と言っているね。人は見かけじゃないんだ。正直で強い心を持っているかどうかが大事なんだよ。『こどものろんご』P58



人は見かけじゃないんだ?
口下手の使い方合ってます?
口下手でカッコよくないけど?思いっきり見かけで判断してません?、、、主観がすぎる。
説明してる側がどうなのよ。
意志が強く、思い切りがよく、自分の意見や考えをしっかりもっていて、実際よりも自分をよく見せようという気持ちがなく、さっぱりとしている。
そのような人には、仁の心があるものだ。
下心が無い人は、信用できる。
寡黙で伝わり辛いことがあるかもしれないけれど、言葉足らずなだけで、行動は思いやりにあふれていることもある。
だから、言葉だけでなくて、人を見るときには行動も見てみるといいよ。
というか、行動がすべてだよ。
P68※子、四を絶つ。意なく、必なく、固なく、我なし
子(し)、四(し)を絶(た)つ。意(い)なく、必(ひつ)なく、固(こ)なく、我(が)なし
先生は四つのことを絶っていた。勝手な心を持たず、無理押しをせず、執着をせず、我を張らない。
自分だけよければいい、なんてわがままな心をすてよう。
孔先生は、自分が生きていくうえで『これはしない』と心に決めた四つのことがあるんだ。それは、『勝手な心を持たない。人に無理を押しつけない。しつこくこだわらない。わがままを言わない』という四つ。これを守り続けた人だから、先生のことばは、二千五百年以上もたっているのに、世界中の人の心にひびくんだね。きもみ、まずは四つめの『わがままを言わない』を心に決めて、がんばってみてはどうかな!?『こどものろんご』P68



勝手な心を持たず、無理押しをせず、執着をせず、我を張らない。
こうやって聞くと、四絶の必要あるの?
とも思える。そうなるときもあるから。
孔子は人々が陥りやすい四つのものを断ち切った。
四つとは主観的な私意(思い込み)、
必ず押し通そうとする思い込みの心、
自己主張を堅く守って譲らない心(自分の考えに執着すること)、
我を張り通す心(自己中心)。



こう聞くと、四絶もわからんではないわ。てなりません?
伝え方ひとつだと思うんですよね。
他人の意見をよく聞き、他人への無理強いはせず、自分の意見に固執せず、他人のためになることを考えることができるようになろうね。
柔軟に対応できるのが生きやすいかも。
けど、そうできないときもあるから、それはそれでいんじゃない?
他人の意見をよく聞けないとき、無理強いして我がままになってしまうとき、自分の意見に固執してしまい、自分のためにしか行動できない、そういう時期も人にはあるから。
そういうときには、信頼できる人の意見だけ聞くようにしてみるとかでいいんじゃない?
P72※三軍も帥を奪う可きなり。匹夫も志を奪う可からざるなり
三軍(さんぐん)も帥(すい)を奪う可(べ)きなり。匹夫(ひっぷ)も志(こころざし)を奪う可(べ)からざるなり
どんな大群でも、その総大将を奪うことはできるが、平凡な男でも、その志まで奪い取ることはできない。
どんな大群でもその大将をうばうことはできる。でも、一人のふつうの子だって、強い志を持っているなら、だれもその志をうばうことはできないんだ。『こどものろんご』P72



パニック。読解パニック。
数万を率いる大将の身を奪うことはできるが、一人の男の心の中にある志を奪うことは誰にもできない。
とりま、こういう意味だと思います。
何か目標に向かって努力している人の意志を変えたり、諦めさせたりすることはできない。
それくらい強い志を持てる将来の目標を見つけようね。
P76※利に放りて行えば、怨み多し
利に放(よ)りて行えば、怨み多し
自分の利益ばかり考えて行動すると、うらまれることが多い。
『だれかにほめてもらえることと、おこづかいがもらえることしかしません』なんて勝手なことを言う人は、『自分のことしか考えていない!』と、みんなからきらわれてしますよね。やさしい人は、損か得かなんてなにも考えずに、人に親切にするはず。それが当たり前だからね。
ーおとなのかたへー
自分の得にならないことはしない、という人は大人の社会でも嫌われたり恨まれたりします。子どものうちはなおさら利害や損得勘定とは無縁な世界で生きてほしいものです。『メリットがあるかないか』というのも言い方を変えただけで打算の匂いがします。子どもが『損なことはしないよ』などと言うのは、親や周りの大人の影響もありそうです。利を追う態度には気をつけたいですね。『こどものろんご』P76



ほめて….おこづかい…
自分の利益ばかりを考えて行動すると、人から恨まれることが多い。
テイカーのことだろ。
ほめられたい、おこづかいがもらいたい。
と言って人から嫌われるでしょうかね。
ちょっと疑問です。
やさしいの定義もあるけれど、損得考えずに人に親切にする行為は素晴らしいけれど、やさしいからするんじゃないと思う。
人だからするんじゃないですかね。
やさしいかどうかを決めるのは、受けた相手だし。
そこに『やさしさ』は関係ないでしょ。
あと、子どものうちから利害関係など、ちゃんと教えることは大事だと感じるね。
教え方ひとつだと思うんですよ。
『損になるからしない』
という表現を子どもが使うとしたならば、その発言を正せばよいだけの話でしょ。
本当にその行為は『損』になるかどうか?
もしかしたら、一目『損』に見えるその行為は、長い目で見たら『徳(得)』になるんじゃないか?
その辺りを大人がちゃんと説明できたらいいんですよ。
見極めから全部。
WINWINの関係を作れるように行動するといいよ。
両方に得がある考え方ができるといいよね。
例えばさ、お勉強が分からないお友だちがいたとするじゃない?
あなたは教える側で、お友だちは教わる側。
あなたは復習になって、更に覚えることができるし、お友だちも問題が解けるようになる。
これがWINWINの考え方で、両方得する考え方だからね。
P92※人の己を知らざることを患えず、人を知らざることを患う
人の己(おのれ)を知らざることを患(うれ)えず、人を知らざることを患(うれ)う
人が自分を理解してくれないことを気にするより、自分が人を理解できていないことを気にしなさい。
自分を知ってほしいと悩む前に、まず人のことを知ろう。
たとえば、きみは友だち思いだし、人が見ていなくても、小さい子や弱い子にやさしくしている。でも、みんなは気づいてくれないし、きみを理解してくれない・・・。さびいしいよね。
略
まわりの人をよく知ろうと思えば、きみのことも知ってもらえるよ。
ーおうちのかたへー
でも『簡単にわかってもらえるはずはないんだよ』と切り換えさせ、『まず自分から周りの子を知るように努力してごらん』と気持ちを内から外へ向けさせることも大事です。『こどものろんご』P92



誰基準で、小さい子や弱い子にやさしいと判断してるの?
もしかして自分基準?ww
とんだ自己陶酔野郎。
たとえ人が自分のことを理解していなくても気にしてはいけない。
むしろ、自分が他者を正しく理解できていないことを知った方がいい。
上の注釈で言えば、小さい子や弱い子にやさしくしていることを皆が気づいてくれないし、理解してくれないというその感覚ですが、これは人が思って判断することであり、自分じゃないんですよね。
まず、ここが一目気になるところ。
あと、自分を知って欲しいがもうおかしい。



自分が思っている自分と、人が思っている自分というのは乖離があって、ある意味当然でしょ。
思いたいように思ってくれたらいいし、言いたいように言ってくれたら良くない?
だって、人は見たいようにしか見ないし、言いたいようにしか言わないでしょう?
それが原則だと思ってるから。
というのは極論なんでしょうかね。
わたしはそう思っていますし、子どもにもそう教育しています。
ただ、陰で自分のことを庇ってくれる人がいたときには、とても嬉しいです。
自分が『別にいいや』と思っている分を他の人が言ってくれているというのは、色々諦めてきた分、感謝しかありません。
あと、自分のことをきちんと理解できていたら、人のことは知ろうとしなくても理解できるという原則があるはずなんです。
自分のことが分からないから、人のことも分からない。
ここがイコールなはずなので。
だから、まずは自己理解をした方がいいと思う。
人は、言いたいようにしか言わないし、見たいようにしか見ない生き物なの。
でも、あなたのことは、わたしが一番理解できて知っているから、そんなこと気にしなくて大丈夫。
それでももし、わたしそういう人じゃないのに、、って思うようなことがあったら、冗談で『そうなんだ~』なんて言っちゃだめ。
きちんと自分の意見を伝えて、誤解を解くように。
嫌なことは嫌。
そう伝えておくことで、皆があなたのことをそう扱ってくれるようになるから。
一石二鳥でしょう?『善行』なんてアピールするためにあるものじゃないしね。
それをすることで、神様がたくさん助けてくれるから、皆が気づいてくれなくっても平気じゃない?
そうやって生きてたら、庇ってくれる人もたくさん現れるよ。
P94※君子は言に訥にして、行に敏ならんと欲す
君子(くんし)は言(げん)に訥(とつ)にして、行(こう)に敏(びん)ならんと欲す(ほっす)
人を導く者は、口下手であっても行動は迅速であろうと望む。
孔先生も『リーダーになる人は口下手でもいいから、行動はテキパキとすばやくやろう』と言っているよ。
ーおうちのかたへー
口達者よりも口下手なくらいのほうがリーダー向きだと孔子は考えていたようです。実際、指導的立場の人がいくら調子のいい演説をしても、口だけでは誰もついていきません。『まずは行動で示す』ことを子どもたちも覚えてほしいですね。『こどものろんご』P94



口下手の使い方合ってんの?
何を言うかよりもどう行動するかの方が大切だということ。
行動で示せってことですよね。
まんまでしょ。
口で言うだけ言って、行動が伴わない人ってカッコ悪いじゃない。
言うのは簡単。
じゃぁ、行動は?
って誰もが思うのよ。
だから、まずは動こうね。
そこが全てだから。
P96※与に言うべくしてこれと言わざれば、人を失う
与(とも)に言うべくしてこれと言わざれば、人を失う
話すべきときに話しかけずにいると、大切な人を失ってしまう。
出会いのきっかけをのがしちゃダメだ。『こどものろんご』P96
話し合うべくして、この人と語り合わなければ、その人物を逃す。
大切な人がいたら、ちゃんと話なさい、語り合いなさい、そうしないと分かり合えないまま、その人ごと失いますよという意味。
語り合える仲間、語れるお友だち、同士って、一生のうちそんなにたくさん出会えないから。
この人と話したいな、という人が現れたのなら、話せるときには、ちゃんと向き合って話すといいよ。
大事な話もできないまま時が過ぎちゃうと、信頼関係も築くことができないまま、その人との関係が終わっちゃうこともあるから。出会いは大切にね。
これ、続きもあるんですよね。
子曰わく、与(とも)に言うべくしてこれと言わざれば、人を失う。与(とも)に言うべからずしてこれと言えば、言(げん)を失う。知者(ちしゃ)は人を失わず、亦言(またげん)を失わず。
話し合うべくして、この人と語り合わなければ、その人物を逃す。
語るに値しない人と語れば、失言することもあり、行動も誤ることがある。
知者は人を失わない、失言もしない。



要するに、知者は語るべき人物が分かり、失言もしない。
まぁ、そうだろうね。
P98※約を以てこれを失する者は、鮮なし
約(やく)を以て(もって)これを失(しっ)する者は、鮮(すく)なし
つつましく控えめにしていて、失敗する人は少ない。
ひかえめで落ち着いている人は、大失敗しないもの。
なんにでも出しゃばって、声が大きくうるさい人。ハデなことが大好きで、目立ちたがりの人。こういう人は、活発でいい面もあるけれど、おとなしくてしずかなことが好きな人には、ちょっと苦手かもしれないね。それにこういう人は、だいたい落ち着きがないので、ときどき大失敗もする。そして、なにかしくじると目立ってしまうんだ。
反対に、しずかで落ち着いている人や、出しゃばらずひかえめな人は、大失敗することは少ないものだよ。お金のことでも同じで、ガツガツかせいで大金持ちになろうとすると失敗することも多い。コツコツまじめにはたらして、つつましく生活する人は、大きな失敗はしないものなんだ。
ーおうちのかたへー
何にでも顔を出したがる出しゃばりさんや、目立ちたがりの派手好きさん。こういう人は行動が何かにつけ目立つので、失敗したときも目立って印象に残ってしまいます。
何ごとも控えめな人は、失敗がないわけではありませんが大失敗はまれで、周りへの影響も少なくて済みます。引用句の『約』には『倹約』の意味もあり、お金に関してもつつましいのがよいと孔子は言っていますよ。『こどものろんご』P98



このページごと何?
つつましやかで控えめにしている人で、失敗している人は少ない。
つつましやかに、行き過ぎのないようにやっていれば、人生において失敗することは少ないという意味でしょうね。
当然の摂理、それだけが正しいと言ってるわけじゃないから。
あとは自分次第でしょう?
生きてみないと、どのあたりまでが行き過ぎかも分からないもんね。
無理せず、自分に正直に生きていれば問題ないから。
出すぎず、控えめすぎず、バランスを保ちながら、どんなときも心引き締めておくといいよ。
そしたら、失敗しても次の糧にできるから。
P102※徳の脩めざる、学の講ぜざる、義を聞きて徒る能わざる、不善の改むる能わざる、これ吾が憂いなり
徳の脩(おさ)めざる、学の講(こう)ぜざる、義(ぎ)を聞きて徒(うつ)る能(あた)わざる、不善(ふぜん)の改むる能(あた)わざる、これ吾(わ)が憂(うれ)いなり
道徳を修めない、学問を深めない、正義と知って行動できない、不善を改められない、これらが私の心配事だ。
たくさんの弟子にかこまれて、尊敬をあつめていた孔先生にも、心配なことがあったよ。それは、いろいろな学問や道徳を学んでいた弟子たちが、学ぶことを途中でやめてしまったり、学んだことを、自分や世の中のために役立たせずにいるのではないか、ということ。
ーおうちのかたへー
何より憂い(心配事)となったのは自分から学んだことを少しも世間で役立てていない弟子のことでしょう。学問・芸術・芸事などは、ただ勉強したり習うためにあるのでなく、世の中で役立てるためにあることを子どもにも理解させたいですね。『こどものろんご』P102



一理あるけど、違うと思う。
これは、弟子のことを言ったのではなくて、自分のことを言ったんだと思う。
学んだことをどう生かそうか、殺そうかは本人次第であり、教えた側が気にすることじゃないからです。
そして孔子は『心配』しないと思う。
弟子を信じると思うから。
他者信頼。
道徳を身に備え、学問にいそしみ、反省も常にしている。
それなのに、知っているはずなのに、学んだはずなのに行動できない自分がいる。
こっちだと思う。
あと、学校で学んだことが全く生きないということは無いと思うからです。
どんな形であれ生きるでしょう?
どう生かすか、活かすかは自分次第で。
わたしも色々なことを学んできたけれど、知っているのにできないことがある。
自分の中に『欲』を発見することもあって、その『欲』に気が付くことができるのは、学んだから。
発見したときには落ち込むけれど、発見できることに意味があるから、それで大丈夫だと思ってる。
それで、いいんだよ。
学校の勉強や活動は将来のためにあるから、一生懸命取り組むといいよ。
学んだこと全部が社会に出たときの糧になるから。
P104※父母は唯だ其の疾をこれ憂う
父母は唯(た)だ其(そ)の疾(やまい)をこれ憂(うれ)う
父母は子どもの病気の心配ばかりしているものだ。
とくにお母さんは、きみが毎日元気バリバリでいたとしても、ケガをしないか、病気をしないかと、いつも気にしているんだよ。
ーおうちのかたへー
引用句には、『親というものは子供の病気のことばかり心配しているものだ』とありますが、ここには『だから健康のこと以外で親に心配をかけるようなことをしてはだめだよ』という意味を含んでいます。
授業中私語が多いとか、そうじをサボるとか、クラスの女子と仲が悪いとか・・・親としてはたしかに健康以外の心配をさせないで、というのが正直な気持ちですね。『こどものろんご』P104



多分、全然ちげーよ(違うよ)。
特に心配しないけれど、病気ばかりは変わってやりたいと思うほど辛く感じる。
という意味だと思いますけどね。
病気しないか、ケガしないか、いつも気にしてないし。
心配かかったときは、それはそれだし、対応するしできるし。
って言うね。
身体だけは、大切にしてね。
P108※吾れ十有五にして学に志す
吾(わ)れ十有五(じゅうゆうご)にして学に志(こころざ)す
私は十五歳で学問をきわめることを志した。
『こどものろんご』P108
これ、続きがあって、吾十有五にして学に志す、三十にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知る、六十にして耳順(みみしたが)う、七十にして心の欲する所に従えども、矩(のり)を踰(こ)えず。
私は十五で学問に志し、三十になって独立した立場を持ち、四十になってあれこれ迷わず、五十になって天命をわきまえ、六十になって人の言葉が素直に聞けるようになり、七十になると心のままにふるまって、それで道をはずれないようになった。
15歳くらいで、人生の目標ができるのは素晴らしいペース。
それまでに自分を知ることが大事で、それができない人が多いから、親や世間、周りの人に惑わされる。
まずは、自分はどうありたいか?世の中でどうありたいか?どう生きたいかを考えることができたらいいのかな、と思います。



結構あったなー。すごい文字数。

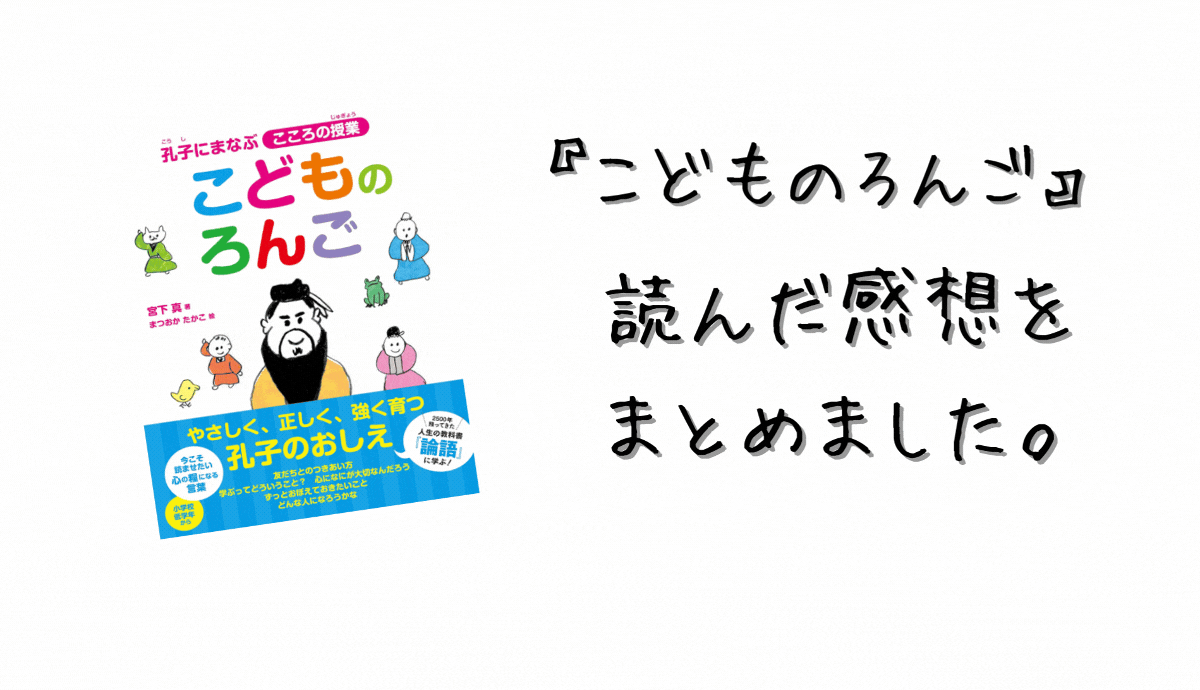

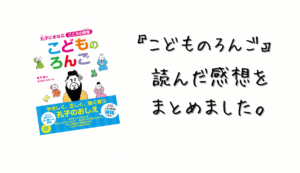
コメント