例えば——
『これ、やってみたいんだよね!』
ってワクワクしながら言ったのに、3秒後に
『……でも、失敗したらヤバくない?』
って、脳内の“やさしい風警察”がサイレン鳴らしてくる。
別に誰にも迷惑かける予定なんてない。
それでも、“挑戦”という文字を思い浮かべただけで、全力でブレーキを踏む。
そして出てくるセリフがこれ。
自分が失敗して、誰かに迷惑かけたらどうするの?(お前はどうしたいの?)
ちゃんと結果出せなかったら、期待を裏切るんじゃない?(お前はどうしたいの?)
こんなにしたのに……(それ、頼まれたの?決めたのは誰?)
……いや、思ったより“やさしい”。
いいえ、とても自分に“不誠実”じゃない?
全部、軸が相手だもの。

誰の人生、生きてんの?
しかもこれ、誰かのためっぽく見えて、実は自分の評価も守ってる。
『いい人でいたい』
『迷惑かけたくない』
『見放されたくない』
——ああ、これ、ギバー特有の呪いだったりする。
アダム・グラントの『GIVE & TAKE』では、
人はギバー/テイカー/マッチャーに分かれると言われる。
で、ギバーは優しい。
優しいけど、優しさの向きがズレると——行動が死ぬ。
今日はそんな「やりたいのに動けない」をほどく、心の筋トレの話。
動けない“やさしさ”の正体
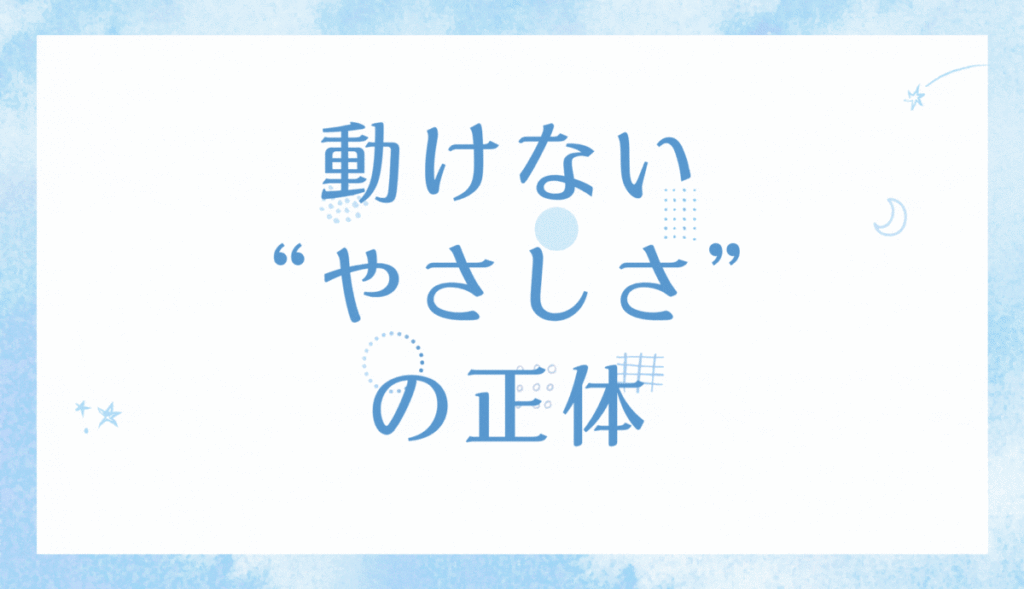
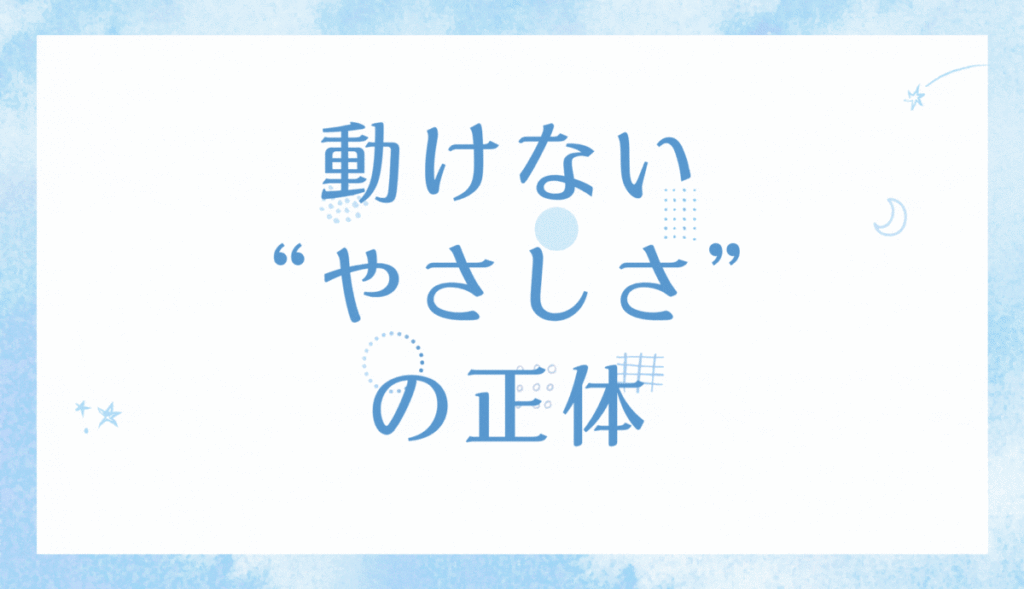
- そのブレーキ、相手じゃなく“評価”
- 違和感は筋肉痛
① そのブレーキ、相手じゃなく“評価”
『やりたいけど、やっぱやめとこうかな』って立ち止まるとき。
理由を一回、ちゃんと観察してほしい。
多くの場合、表面にあるのはこれ。
- 迷惑かけたらどうしよう
- 失敗してガッカリさせたくない
いかにも「やさしさ」だよね。
でも、もう一段掘ると、大体こっちが出てくるじゃん。
- 迷惑かけて、色々言われたくない
- いい人だと思われたい
- 見放されたくない
……それ、相手のためじゃない。
自分の評価を守るためのブレーキ。
アダム・グラントの言う“ギバー”は親切で優しい。
でも優しさの向きがズレると、こうなる。
他者への優しさという名の、自分への不誠実。
自己犠牲型ギバーの典型。
やりたいことまで
『迷惑かも』『嫌がるかも』で止めてるなら、もうそれは優しさじゃない。
行動を奪う呪いになる。
② 違和感は筋肉痛
『自分はこうしたい。
でも、やめておいた方がいいかもしれない。』
この瞬間に起きているのは、他人への気遣いじゃない。
自分の本音とのズレ。
つまり、自己不一致。
このズレを繰り返すと、どうなるか。
だんだん、自分の人生を生きていない感覚になる。
だから、ここで一度問い直してほしい。
その“やさしさ”、本当に誠実?
誰かを思って動けないとき、
その感情の根っこに
『評価されたい』
『嫌われたくない』
そんな恐れは混ざっていないか。
やさしさは本来、行動を促す力のはず。
それが足を止めているなら——
そのやさしさ(仮)は、
自分に対して誠実じゃない。
本当に大切なのは、
まず自分に誠実でいること。
それが結果として、
他人にも誠実であれる、唯一の土台になる。
認知不協和と“心の筋肉”
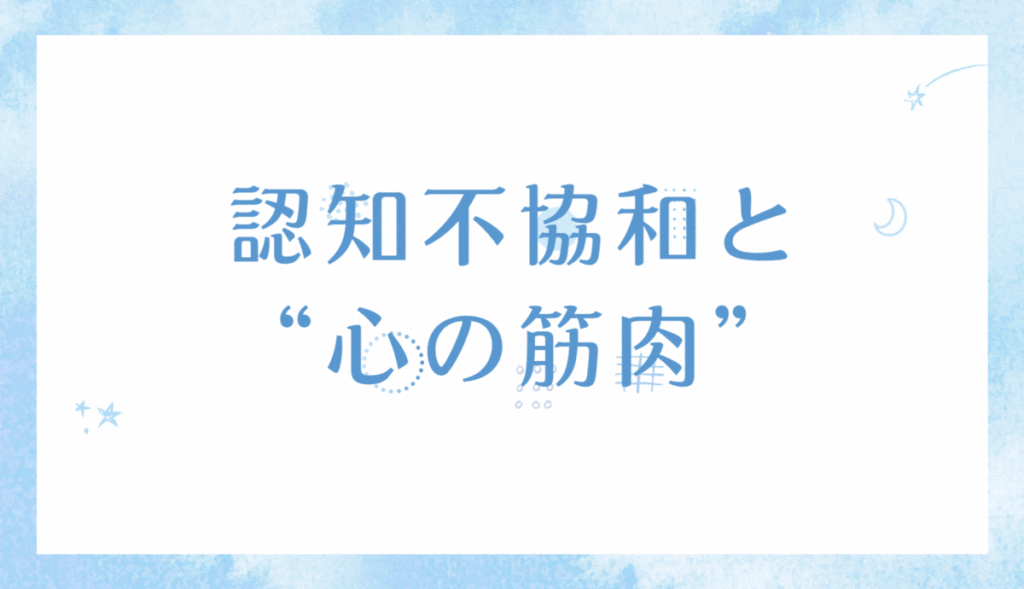
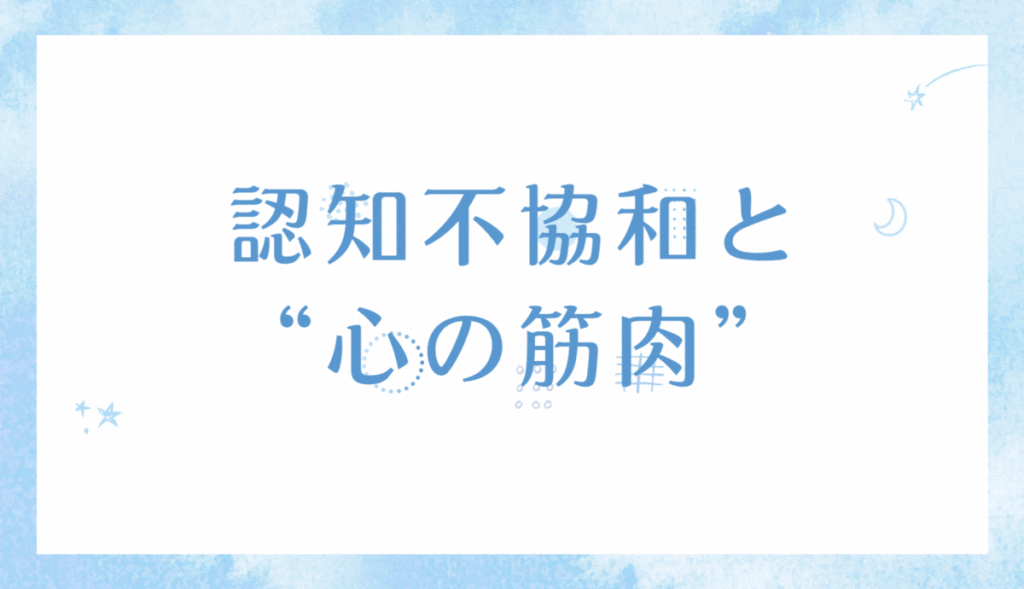
- 違和感=成長のサイン?
- 『手放す』ことは自分を信じる力
- どの部分が心の筋肉を鍛えるのか?
① 違和感=成長のサイン?
『やりたいのに、動けない』
『やらないと決めたのに、気になってしまう』
──こんなふうに、内側にズレやモヤモヤが生まれるとき。
それはたいてい、認知不協和が起きているサイン。
でも実は、その違和感こそが、
今、心が筋トレ中だという証拠。
アダム・グラントが語る
「レジリエンス(回復力)」の考え方を、
わたしなりに実践の流れに落とすと、大体こんな順になると思うんだよね。
アダム・グラント“を起点に”、私の実践はこういう形になった。
ここから先は、完全に私の運用。
- 自分の感情に気づく(自己一致)
- 思考パターンを疑う(スキーマの更新)
- 新しい視点で捉え直す(認知不協和の解消)
- より柔軟で誠実な選択に戻る(アタッチメント)
これが、心の筋肉。
だから、
『ああ、今ちょっとツラいな』
『なんでこんなに疲れるんだろう』
そう気づけること自体に、意味がある。



筋肉痛があるから、筋肉は育つ。
同じように、違和感があるからこそ、感情と行動は一致していく。
逆に言えば、
違和感にすら気づけないなら——
もう、そこ、どこ?
地図で言えば、歩いてるのは砂漠。
たまに都合のいい蜃気楼が見えて、「あっちだ!」って走る。
でも、それ、消えるやつ。
わたしで言うところの、ポジティブ(蜃気楼)探し。
正直、意味ないと思う。
② 『手放す』ことは自分を信じる力
状況が悪くても、
「このままでは終わらない」と思える力。
ネガティブな現実を否定せず、
その中に、未来へつながる何かがあると信じられる力。
ここで言う「信じる」は、
希望を握りしめることじゃなくて、状況の意味を、自分で引き受けること。
たとえ現実が望ましくなくても、
「今ここにある経験を、どう受け取るかは自分で決める」
そう構えられるかどうか。
これが、
アダム・グラントが語る
「レジリエンス(回復力)」の核心だと、わたしは思うんだよね。
そしてそれは、わたしが実践している心の筋トレの正体でもある。
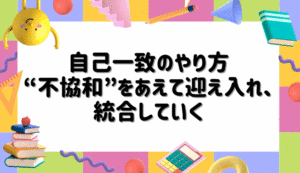
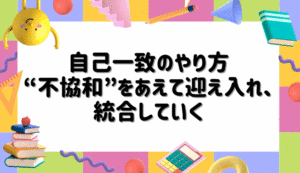
ネガティブ想像で『感情の未来予測』をする
例えば、何かに挑戦しようとしたとき。
不安が一気に押し寄せて、体が止まる。
そんなとき、わたしはあえてこうする。
「最悪の結果になったら、自分はどう感じるか?」
を、徹底的に想像する。
仏教でいうところの
貪・瞋・痴——
欲、怒り、愚かさ。
フルセット。笑
無くそうとしない。
整えようともしない。
ただ、見る。
ただ、感じる。
Aを選んで失敗したら?
Bなら後悔しない?
でもCもあるよね。
……いや、やっぱCは違うか。
この地獄ループを、ちゃんと回しきる。
すると、ふっと来る瞬間がある。
「どの結果でも、多分、大丈夫」
そう思える、静かな感覚がくるんですよ。
諦めじゃない。
投げやりでもない。
委ねられた状態。
凪。
体感した人じゃないと、たぶん分からないと思う。



けど、翌日また再発することもあるから、まぁ、感情という生き物を飼いならすのって大変ではある。
あぁ….また戻ってる…!よくあるよ。
やり直し。これを内省とも言う。
ジャッジせずに“ただ感じる”という筋トレ
ここのプロセスで大事なのは、答えを出すことじゃないんですよ。
自分の感情が、
どれだけ揺れて、
どう変わっていくか。
それを、ただ観察する。
もう、それだけ。
「あれはダメ」
「これは間違い」
そういうジャッジはいらない。
——あぁ、こういう感情が出てきたな。
——あぁ、今はこんな感じか。
それで終わり。



苦痛?
そう。
それで正解。 笑
それ以外、やることはない。
これを繰り返していくと、
不思議と育ってくる感覚がある。
結果がどうなっても、自分でいられる。
結果を引き受けられないときは、対話になるでしょ。
慣れてくると、
重い案件でも、半日から一日で凪に戻れるようになる。
わたしの場合は、だけど。
感じている間は、正直しんどい。
でも、凪のまま結果を待てる。
結果が出たら、
「あぁ、なるほど」
そう思える。
それでも残る答えがあるなら、
たとえば「Aだな」と思えたなら、
それはきっと、本当の答え。
だから、そこは拘る。
祈る。
対話する。
でも、これしてると、よく誤解されるんです。



何言っても大丈夫な人でしょ?
って。
傷つかない人はいない



そんなワケあるか。
わたしは自分に欠陥がたくさんあって、ポンコツで、人を介して自分をすごく傷つけてしまうタイプだから、自分の感情に付き合って、ちゃんと扱うためにこの方法を使ってるんですよ。
だって、安全基地が自分なんだもん。
基地は守らないと帰る場所がなくなるでしょう?
彷徨うわけにはいかないから。
となると、



自分だけ安全基地の確保なんてズルくない?
と思う人もいるかもしれないけど、それでいいんですよ。
だって、わたしは相手の安全基地でもあれたらという考えの持ち主だから。
当然、誰彼かまわずの安全基地にはならないけど。
でも、いかんせんポンコツの安全基地だし。
色々知識はあるけれど、全然完璧じゃない。
ガタがすごい。
わたしにとって、言葉は『表現』でもあり、『道』でもある。
“思考を扱う言葉”と“感情をつなぐ言葉”がない場所では息が苦しい。
だからこそ、わたしにとっての『誠実にあれる場所』には、“言葉の往復が生きていること”が条件になる。
そして、それがないと、わたしは“誠実に関われない”。
もともと、見たもの、本人から聞いたものしか信じないから。
息をしたい。
アタッチメント理論↓
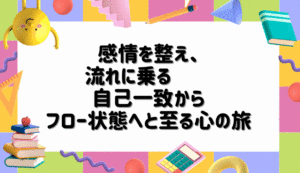
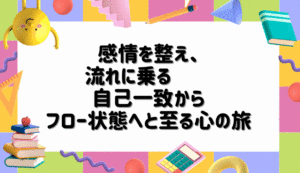
これを数値で例えるなら、10傷つくとして、結果を得たときに、ゼロ、もしくは1とか2くらいの傷で済ませられるから。
何も考えずに結果を聞いて10傷つくとして、感情が乱れてそこから内省?遅くない?とわたしは思うから。
とりあえず、常に先手思考。
けど、安全基地を引き受けるなら、相手の数値に気を付けたいんですよ。
自分が4だと思っていても、相手は10の可能性がある。
だったら、残りの6を聞く。
逆なら聞いてもらいたいやろ。
わたしはそうだけど、人がどうかは知らない。
感情が乱れてから内省しようとすると、その時点ですでに『反応』の渦中でしょ?
冷静さを保つのが難しいでしょ。
結果として、自己防衛的な思考とか、極端な結論に走りやすくなって、結果的に『自分らしい選択』や『望む未来』から逸れる。
だから、感情という生き物が暴走する前に一度立ち止まって、認知のズレやモヤモヤに意識を向けておくことを大切にしてる。
『道から逸れないための内省』は、いわば“軌道修正の筋肉”とも言えるかもしれない。
軌道修正力。
だから、わたしは躊躇なくすぐ動けるだけの話で、そこに至るまでの内省はすごいんだよ。
お分かりかなぁ。
心の筋肉とは、“戻れる力”
このプロセスは、ポジティブ思考じゃない。
だって、ネガティブがあるから迷うワケでしょ?
なのに、そのネガティブを無視して、他のポジティブを探そうなんて、何に意味もなくない?
そう、蜃気楼探しの旅。
それって逃避になるでしょ。
けど、逃避もたまにはいいじゃない。
だから、常時フェスティンガーを利用するのではなくて、一時的な不協和の解消法として利用するのはいいんじゃないかと思う。
だけど、常時それだと感覚が鈍るから。



持論でしょって?
持論ですよ。
でも、何度も繰り返すうちに、『感情がブレたとき、自分に戻るスピード』が早くなる。
確実に早くなります、これは事実。
これが、レジリエンスじゃないかと思う。
『未来の、もっと自由な自分』を作る筋肉になる。
| 項目 | 一般的理解 | わたしの理解 |
|---|---|---|
| ネガティブ | 消すもの | 情報 |
| 感情 | 抑える | 感じる |
| 強さ | 折れない | 戻れる |
| レジリエンス | 前向きさ | 軌道修正力 |
成功者文脈で、レジリエンスがさ、
- メンタル強者
- 打たれ強い人
- ネガティブにならない人
こんな感じで、浅く浸透したんじゃないの?
中身を見ないというね。
成功してる人の過程を見なすぎなんじゃないかな。
“ネガティブが消える=強い”は、強さじゃなくて麻痺のこともある。
強さは、ネガティブを通過して戻れることだと思うよね。
③ どの部分が心の筋肉を鍛えるのか?
どこの部分が筋肉を鍛えるかというと、相手に委ねる部分まで浸食しないという決断でしょうね。
相手が決断する部分を自分が決めちゃいけないんですよ。
それは依存を呼ぶから。
『手放す』ことは、“相手に委ねるライン”を守ることでもある
心の筋肉を鍛えるうえで最も大事なのは、『自分の領域』と『相手の領域』をきちんと分けて考えること。
つまり——相手が決断するべき部分に、自分が踏み込まないという選択。
だって、無理に操作しようとして拗れるでしょう?
感情ぶちまけてスッキリ。
その感情に揺さぶられて優越?傷心?これが判断を不正解にしていく気がする。
つまり、人生の流れに乗れなくなってしまう。
わたしは、乗っていたいから。
相手の部分に侵入しないって、簡単そうで難しいかもしれないですね。
だって、不安だし、結果が気になるから。
でも、そこにまで浸食してしまうと、それは“信頼”ではなく“コントロール”になるんですよ。
相手の領域に侵入しないことは、
見捨てることでも、冷たくなることでもない。
不安に任せて操作しない。
その一線を守ることが、
信頼であり、レジリエンス。
わかります?



あなたのために….



お前のためだろ。
黙れこの偽善者が。寝言は寝て言え。
もっと酷いと、『偽善』にすら気づいてない人もいますからね。
ずっと蜃気楼見てんの。



あなたのために言ってるのが分からないの?



それはお前が見た蜃気楼だってのが分からないの?



蜃気楼?



そう、奇冷(きれい)な蜃気楼。





綺麗?なんかうれしい。綺麗な蜃気楼って、よく見られるの?



いえいえ。場所や時期によって見え方は違うだろうけど、たまに、みかけますよね。
でも、見えにくいみたいで。
わたしには、奇冷(きれい)に見えます。



わたしも見てみたい。



見ようと思ったら見えるんですけど、基本、探さないと、見えないです。
だからこそ、手放すには“自分の意思の責任を引き受ける力”と同時に、“相手に判断を委ねる勇気”が必要。
まぁ、偽善であっても、人のための行動に繋がってるなら、いいと思う。
明らかな自利のためだけの行動で、周りを見ないのであれば、どうでしょう?というのが私の持論。
自覚的な依存なら、別にいい
依存を否定しない。人はみんな、何かに頼って生きてる。
問題は、自覚があるかどうか。
自覚がある依存は、扱える。
「今、依存してる」と分かっていれば、線が引ける。
相談もできる。
必要なら自立に戻れる。
逆に、自覚のない依存は——
- 決断を相手に丸投げする
- 自分で選べない
- 相手の一言でブレる
これが続くと、相手が先に壊れる。
なぜなら、そこには最終的に他責しか残らないから。
「あなたが悪い」以外の結論が消える。
だから、心の筋肉の要はこれ。
「どこまで自分が決めて、どこから手放すか」
この境界を、自分で見極める力。



持論? うん、持論。
でも私は、これが一番効く筋トレだと思ってる。
相手ありきで揺れるたびに、境界を引き直す。
そのとき貪・瞋・痴が見えたら、話せる相手には話せばいい。
信頼があるなら、そこから関係は育つでしょ。
ここまで読んで「で、どうすりゃいいの?」って思った人へ。
今日の筋トレはこれだけ。
① 今止めてる理由を“やさしさ”と“評価”に分ける
② 最悪の結果を想像して、感情をジャッジせず通過させる
③ 「どこまで自分が決めて、どこから相手に委ねるか」を決める
レジリエンスって、折れないことじゃなくて、戻れることだと思うから。
ギバーとして、自分も満たす方法
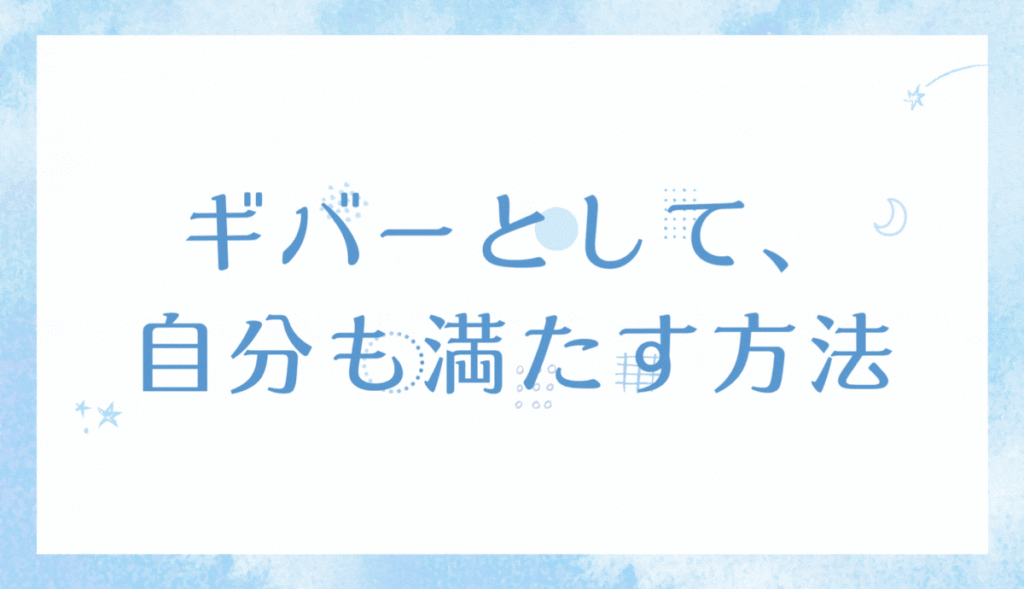
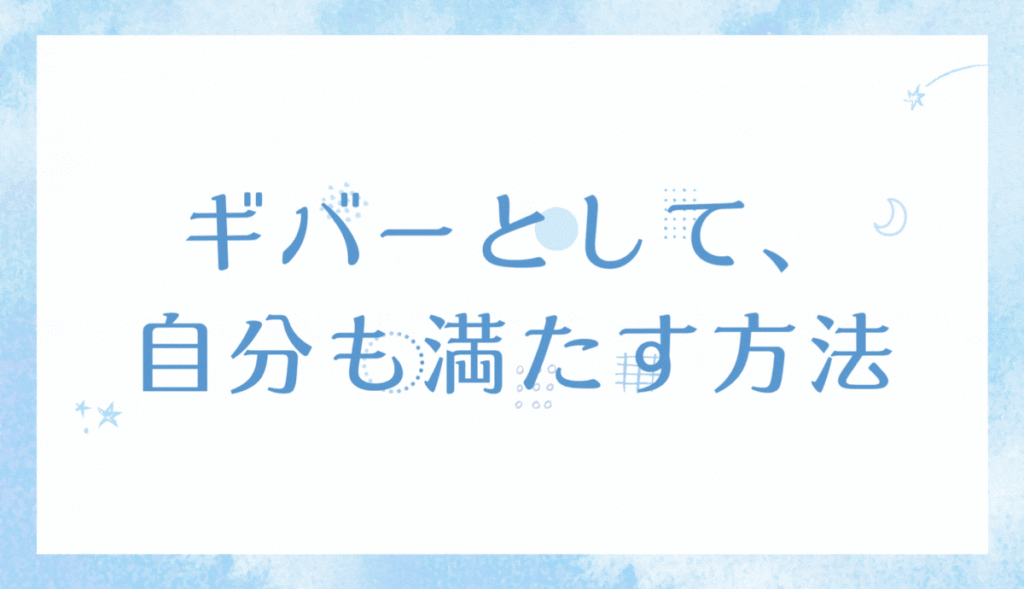
- 自分に誠実でいること
- 挑戦は“祈り”から始まる
① 自分に誠実でいること
「人に優しくしたい」
「誰かの役に立ちたい」
——それ自体は否定しない。
でも、ギバー気質の人ほど見落とすのが、自分の声。
誰かに手を差し伸べる前に、
自分の感情と願い、見てます?
- わたしは、何を望んでいるのか
- どう在りたいのか
この問いを避けたまま“やさしさ”をやると、起きることは一つ。
自分の輪郭が薄くなる。
そして、気づいたら「優しさ」が、自己犠牲の別名になってる。
ギバーだからこそ必要なのは、まず自分に誠実でいること。
誠実さは、「誰かの期待に応えること」じゃない。
自分の本音に気づいて、扱うこと。
それだけ。
カール・ロジャースの言う自己一致って、ギバーの最初の筋トレ種目。
ここがズレたまま誰かに優しくしても、結局どこかで歪む。
自分に誠実でいられる人だけが、他人にも誠実でいられる。
先に自分。
これは倫理じゃなく、構造。
② 挑戦は“祈り”から始まる
挑戦って、戦略的に動くことだけじゃない。
どちらかというと、『こう生きたい』という、“祈り”のような願いから始まる。
『こうしてみたい』
『こんな風になれたら』
——その声に、自分に誠実に行動していく。
これは、誰かを出し抜くためじゃない。
得するためでもない。
誠実な自分で在りたいっていう、切実さの延長。
もちろん、そこには覚悟がいるんだよね。
失敗するかもしれないし、誰にも理解されないかもしれない。
どれだけの道を歩くだろう。
南に向かって歩いていたら、こっちは北だと言われた。
惨敗。
信じていた道が違うと言われる絶望。
見ていたものは蜃気楼。
歩く道のりは?
でも、それでも歩くしかないじゃない。
これで、『違う、西だ東だ』と言われたら、もう壊れるとも思った。
だけど、色々試して、それ以外の選択肢がなくなる。
色々言って伝えて惨敗。
たくさん読んで学んで、合わせて聞いて惨敗。
ただ、いるだけでも惨敗。
どの道、自分を生きるしかなくなって。
まだ、覚悟がいるでしょ。
読むのも疲れたし。
その瞬間、『他人を優先する姿勢』ではなく、
『本音に正直に生きる強さ』に変えてみる。
心の筋トレ。
これが、『ただいる』、じゃなくて、『ただある』?
間違えていたらどうしよう、ふと過る。
けど、心の筋トレ。
信じて歩くしかない、術が無い。
与えることを大切にしてきて、
与え方を間違えて、
挑戦はまた“自分を差し出す行為”になる。
分からない中、思いを行動に変えていくことしか、できない。
それは不器用にしか見えないだろうけど、それが自分なら仕方がない。
どの道、自分を生きるしかなくなる。
それは、本当に不器用だけど、
嘘のない生き方だと思える。
何が正解かは、自分次第。
それを自分が望むのなら、仕方がない。
周りとは乖離があるかもしれないけれど、自分とは乖離がないと思う。
これが正解とも言い切れない。
それでもこれを、選べるかどうか。
自分にとっての正解は何か?
自分にとっての誠実とは何か?
でも、それがたとえ不器用でも、誠実に選んだ道なら、きっとどこかにつながっている。
自分に嘘をつかない選択が、未来のどこかで自分を助けてくれると、信じるしかない。
まとめ
このブログに書いていることって、容易じゃない。
容易なわけがない。
でも、他者にこれを求めてるわけでもなくて。
ただ、わたしの見解は合ってると思うんですよね。
世間一般で流通してる方法論が全部合わなかったのよ。
だったら、自分で検証するしかないじゃない。
それだけの話。
たまに思う。
知識は知識。
わたしはわたし。
——なのに、その線がぐちゃぐちゃにされる。
「知っているわたし」
「話せるわたし」
「書けるわたし」
それがそのまま、
「難しい人」
「圧をかける人」
に変換される。
違う。
それは“知識”の話であって、“人格”の話じゃない。
それでも、ふと考える。
わたしを「わたし」として見てくれる人は、いるんだろうかともね。
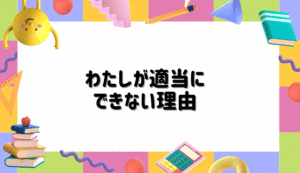
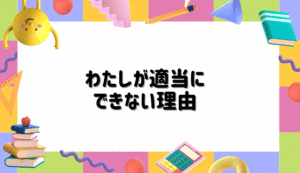
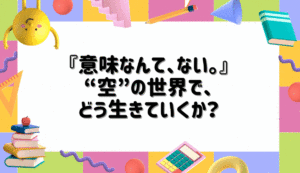
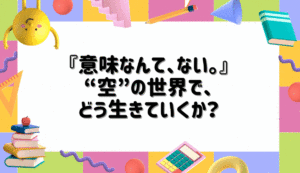

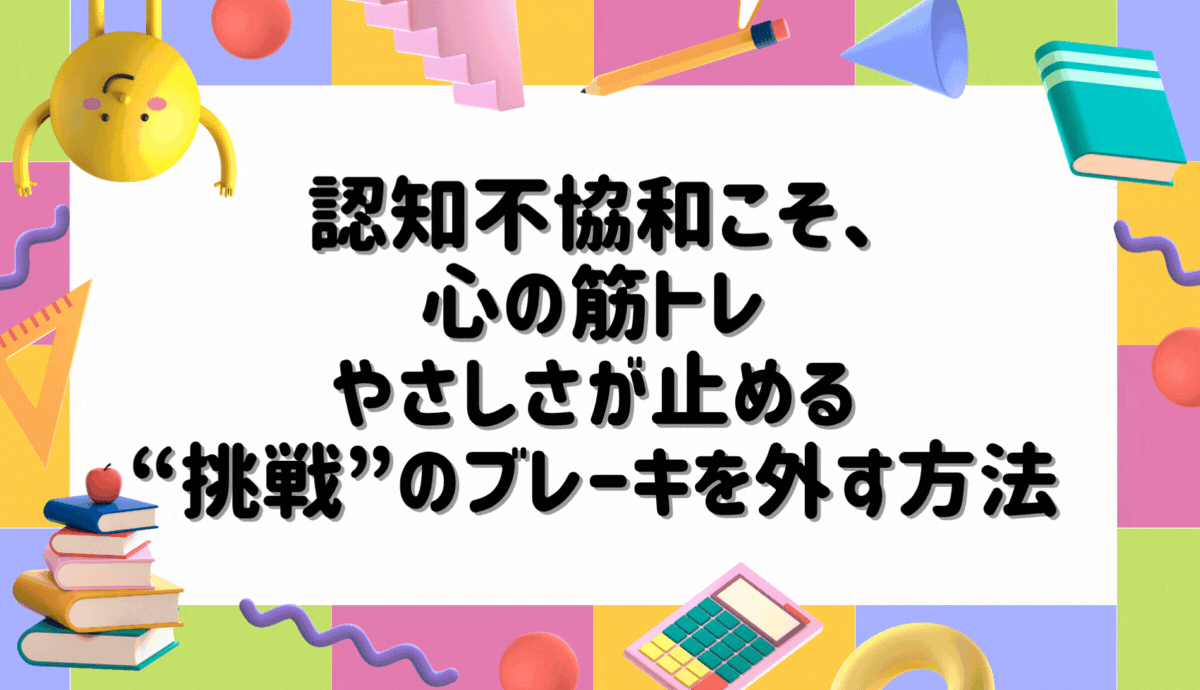
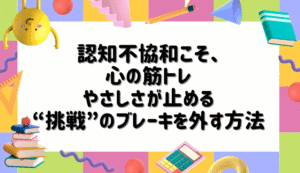
コメント