
うちの親はPTA会長だから偉いんだぞ!
…と、まさかの自信満々マウントを決めた小学生。
どうなったかって、周りのお友達から、



うちのお父さん、PTA会長なんだからねー!
と揶揄されるようになっちゃって、マウント小学生保護者への注意で、無事に解決することはできたんです。
実はこういう場面こそ、問題の本質を見極める目が問われる瞬間で、言葉の奥にある感情や背景をスルーしちゃうと、注意の仕方間違っちゃって、労力が増えるんですよ。
『言い方が悪いよ』とか『調子に乗っちゃダメだよ』と注意したくなった方いますか?



ちょっと待ってください。
それ、“火”は消せても、“火種”は残っているパターン。
この記事では、つい“表面の対処”に走りがちな私たちに向けて、本質を見抜くための6つの思考レンズをユーモア交えてお届けします。
なぜ『本質』にたどり着けないのか?


- 問題の『表面』と『本質』を混同していないか問題
- 感情が思考を曇らせる瞬間
- 思い込み・バイアス・過去の成功体験が邪魔をする
- 視点不足が“的外れ”の原因に
① 問題の『表面』と『本質』を混同していないか問題
たとえば、ある子が、



うちの親PTA会長だから偉いんだぞ!
と学校でドヤ顔キメて炎上したとします。
そこで、



言い方が悪いよ。
調子に乗っちゃダメだよ。
って注意するのは、“表面”への対応。
まあ、火は消えます。
でも燃料タンクはそのまま。
問題の本質はそこじゃない。
言った子は小学4年生なったばかり。



どこでこの思考が?
子どもが“親がPTA会長=家も偉い”と信じ込む空気を、家の中で誰かがフワッと撒いていた。
という可能性が高い。
つまり、“謎の自己肯定感”が家庭内でぬか漬けのように育てられていたわけです。
知らぬ間に『会長菌』が家庭に繁殖してたと。


この状態で表面だけ対処すると、今度は『じゃあ静かに偉そうにしますね』みたいな、“ステルス会長マウント”が始まるだけ。
だからこそ、行動の奥にある『思考の育てられ方』こそ見なきゃダメで。
原因は発言じゃなく、発酵。
② 感情が思考を曇らせる瞬間
問題が起きたときって、大体まず感情が“フライングスタート”するんですよ。



うちの子がいじめられた!?
あの子、なんなのよ!?
学校どうなってんの!?



お前もどうなってんだ。
——気がついたら、完全に“瞬間湯沸かし器モード”に突入。
もうフタも吹っ飛んでます。爆発。
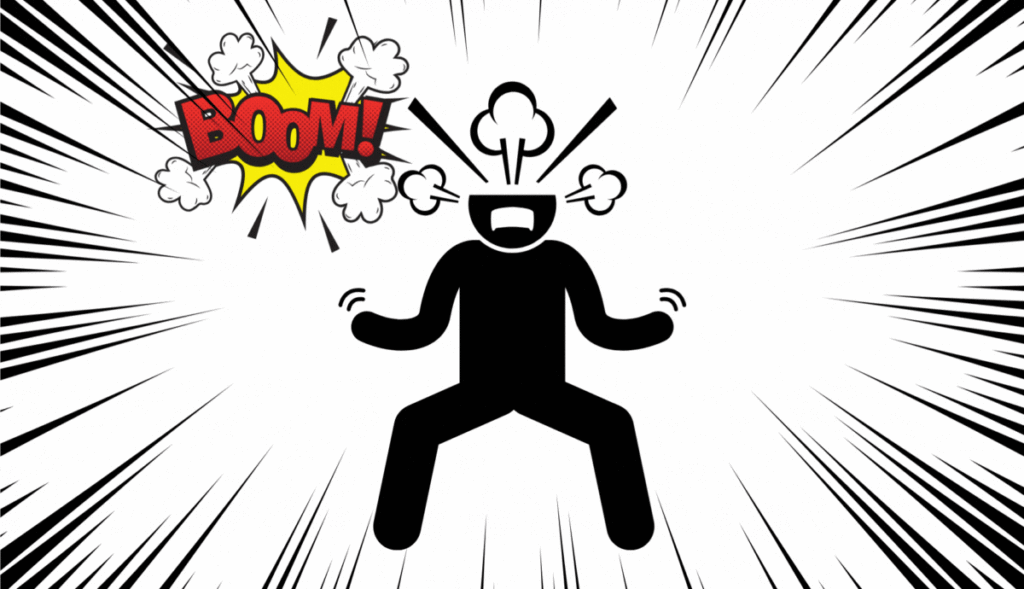
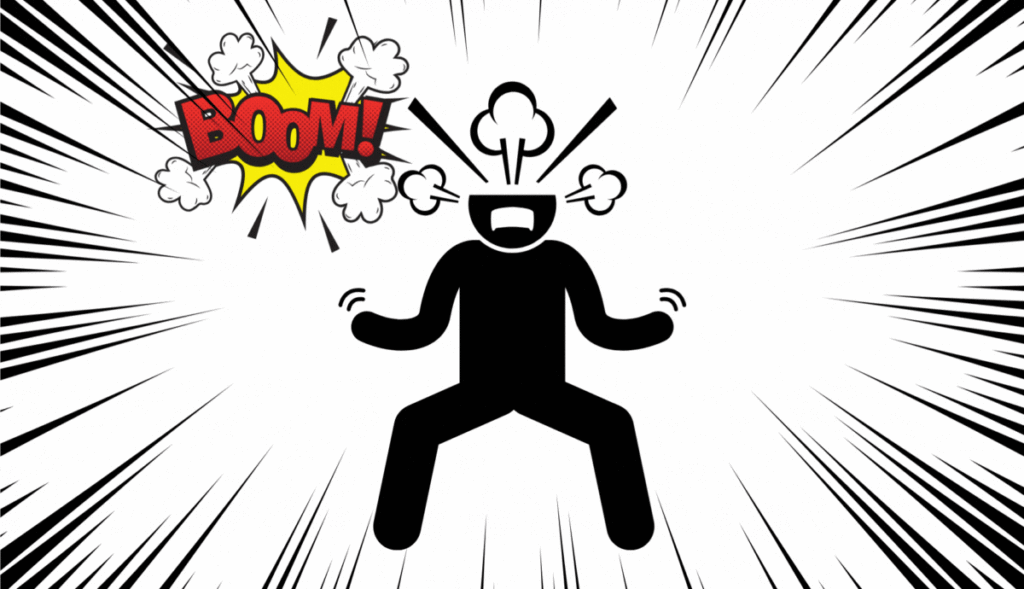
この状態になると、冷静な思考とか、分析とか、全部脳の隅に押し込められて、代わりに感情が全画面表示されます。
でも、これはもう人間あるある。
一理、正常でもある。
怒り、焦り、悲しみ、不安……こういった感情は、思考の『レンズ』を曇らせるんですよ。
まるでマスクしてラーメン食べた後のメガネみたいに。
で、曇ったまま考えるから、感情に支配されたまんま『火を消す!!!』みたいな対応になる。
例えるなら、コンロの火を手でパタパタあおいで『はい、解決』ってやってる感じ。
火元は見てない。
だから大事なのは、自分の感情に気づいた瞬間、『はい、曇ってるな』と認めて、思考のメガネをハンカチでサッと拭くこと。
深呼吸一回。
そして、こう自分に問い直せるといいんです。



で、結局この問題の“本体”ってどこよ?
この一手間が、表面じゃなく『本質』にアクセスするための鍵。
③ 思い込み・バイアス・過去の成功体験が邪魔をする



前はこれでうまくいったから、今回もこれでいい。
いや、あぁいうタイプってそういうキャラじゃん?
——こういう“過去の成功体験メガネ”や“思い込みゴーグル”をかけたままだと、肝心の本質は完全にスモーク状態です。
見えてるようで見えてない。
というか、見えてない。
むしろ、都合よく見えてるだけ。
多くの大人、経験が豊富な立場ほどハマりやすいのがこの罠。
『過去の経験』が“参考”どころか、“もう決めつけレベルの信仰”になってるケース、けっこうあります。
で、ここに登場するのが最強バイアス親あるある。



うちの子に限ってそんなことは…ない!絶対!



知らんけど。
なんだその思考回路。
……その“限って”が案外、問題の震源地だったりするんですけどね。
しかも、本質を見ようとするたびに、心の中の“過去の自分”がこう囁いてきます。



いやいや、それ前もこうだったじゃん?
そっちの見方、なんか怖くない?
やめとこ?
こうして、“気づきの芽”はベランダで干からびるんです。
気づきの芽があるならまだマシ。
結局のところ、経験って武器にもなるし、盲点にもなる。
頼りになるけど、時に“クセが強すぎる”んですよ。
だから柔らかくするのは、『頭』じゃなくて“思い込みの部分”。
フィルターかかってない?と自分を疑う術も大事。
④ 視点不足が“的外れ”の原因に
問題の本質をつかむには、ある程度の視点と背景理解が必要。
でも、視点が足りないまま話すと、対策が完全にズレる。
ガッツリ外す。
まるでメガネなしでダーツしてるようなもんです。



どこ狙ってんの?
当てる気あんの?状態。
当たらないのに腕パンパン。
たとえば、さっきのPTA問題。
『うちの親はPTA会長なんだぞ!』って言って、クラスで問題が発生していると聞いて、その発言自体を止めさせる、または、その発言を聞いて反応している周りの生徒を注意する。



みたいな対応が、わたし的に、ズレてるという解釈になります。持論ですけどね。
これは“発言”にだけフォーカスしてる。
つまり表面への対処だとも思える。
でも、問題の背景にはこういう事情があるかもしれないんですよ。
- 家で親が、PTA役職のことをやたら誇らしげに話している可能性
- 子どもは素直に“親の価値観”をまっすぐ吸収してしまっている可能性
- 本当は『嫌だな』と思ってるけど、家で言い返せないから、外でマウントの道具にしてしまった可能性
- 偉いかどうか分からないけど、親が家で『校長の次に偉い』と言ってたから偉いと大勘違いさせられている可能性
この視点。
“表面の処理”だけで済ませちゃうとどうなるか。
- 子どもは、もっと巧妙にマウントを取るようになる
- 周囲との軋轢はエスカレートし、いじめに発展する可能性すらある
- 最終的に『うちの子が悪いわけじゃない』『わたしはPTA会長なのだから、皆従うように』とPTA会長自らクレームを入れに来る、モンペなのにモンペじゃないと言い張るモンペ代表、自己認識バズ・ライトイヤー型親が完成
見栄・プライド・承認欲求のミックススープを家庭で煮込んだ結果が、子どもの“勘違い発言”として表に出ているだけの図。


ここからの問題は更に悪化の一途と想像がつきますよね。
相手の親や学校との摩擦、子どもも友達と仲良くできるどころか、総スカン。
ちょっとした火種が大炎上。
つまり、『発言』を見て対処しているつもりが、『関係性』や『空気感』を知らないままズレたジャッジをしている。これが、視点不足が“的外れ”の原因になる典型パターン。
ピントがずれたままでも『見えてる気がする』のが一番ややこしいんですが、視点不足って、労力が無駄になる。
何度も同じ注意や対応をしなくちゃいけなくなるから。
親の方も、何度も学校にクレームを入れる。
だって、現場はもっと荒れるでしょうからね。
でも、逆に言えば——『見ること』で、世界の見え方はガラッと変わります。
“ピントを合わせる眼鏡”なんですよ。
しかもブルーライトカット付きのやつ。
あなたの視点、いまどこに合ってますか?
『思考』で問題の本質に迫る!6つのレンズ


俺のお父さんはPTA会長だから偉いんだ。
こんな発言がきっかけで、クラス内に微妙な空気が流れたとします。
ここで伝えたいのは、“問題の本質が見えているかどうか”で、対応の質が変わる。
つまり、
- 自分ができるアプローチ
- しても意味がないアプローチ
この2つを見極めるために、思考を整理する力がとても大事で、なぜかと言うと、楽できるから。
わたしは、無駄な労力省きたいから、いつもこう。
意味あるか分からないけれど、この記事をまとめてみました。
- 素朴思考 ― 『なぜ?』
- 天邪鬼思考 ― 常識の裏にヒントがある
- 批判的思考 ― 情報をうのみにせず、常に『それ本当?』を挟む
- 道具思考 ― 使えるフレームワークは使い倒す
- 構造化思考 ― 問題を分解して地図にする
- 哲学思考 ― 『そもそもこの問いは正しいか?』
① 素朴思考 ― 『なぜ?』



そんなこと言っちゃダメ。みんなに平等に接するのが大事。
……と、“指導”したくなる。
でも、ここで大事なのが素朴思考の視点。
つまり、『なぜこの子は、こんなことを言ったんだろう?』と、シンプルな問いに立ち返る勇気。
一見、浅く見える“素朴な問い”こそ、誰もが見落としている核心に近づく道だったりします。
② 天邪鬼思考 ― 常識の裏にヒントがある
通常なら、道徳的に『平等が大事』『偉いとか言うのはおかしい』と教えたくなるところ。
でも、ここで“天邪鬼思考”を試してみます。つまり——
『逆に考えてみる』って、こんな感じ
- じゃあ、その子自身は“偉くない”と感じてるのかも?
- “PTA会長”を使わなきゃ、自分の価値を示せないってこと?
- “偉い”っていう思考回路は、どこから吸収?親?
あえて逆に解釈することで、本音が浮かび上がってくる。
『素直に受け取らない』ことが、知恵になる
子どもの発言って、ストレートに受け取ると誤解することが多いですよね。
一見『マウント』っぽく見える言葉の裏には、『親に認められたい』『劣等感を隠したい』、そんな“感情の裏返し”が潜んでいることが、実はほとんどかとも思う。
あと、根深いから、付け焼刃対応じゃ無理がくるし、労力は増える。
言葉の奥にある矛盾に気づいて、そこにそっと光を当てる——そんな対応ができれば理想だけど、正直全部は無理じゃないですか。
そこまでいかなくても『理解しようとする姿勢』があれば、行動はきっと変わると思ってるんですよね。
理解が深まれば、おそらく自分の出すエネルギーも変わるから、そのエネルギーに対する相手の反応も、きっと変わる。



ラベリングされちゃうと、ラベリング通りの行動になっちゃうから。
そのラベルを自分から相手が剥がそうとしてくれたら理想。
こちらは剥がせないから、こちらからラベリングを止めてみる。
わたしは、こんなふうに考えて生きていて、変わらない相手がいたとすれば、それもそれ。
そんな感じですね。
けど、アプローチすべきか否か、もっと言えば、する価値があるかどうか、そこの判断だけは見誤りたくないんですよ。
だって、労力増えるの、嫌だから。
③ 批判的思考 ― 情報をうのみにせず、常に『それ本当?』を挟む
たとえば、『俺んちの親、PTA会長なんだぞ!だから偉いんだ!』って発言。
この時点で、ツッコミどころ満載ですけど、いったん本気で向き合ってみると、こんな問いが浮かびます。
- PTA会長って、そもそも“偉い”ポジションなの?
- それを“偉い”と教えてるのは誰?
- 子どもはそれを“良いもの”として捉えてるのか、それとも内心は違うのか?
- その発言、本当に子どもが言いたかったことなのか?それとも親の価値観の代弁?
- 『偉いんだぞ』は、強さのアピールではなく、弱さの代弁?
つまり、『言ってることは本当か?』『その前提は正しいのか?』と、あえて疑ってみる。
これが批判的思考の基本。
たとえば、こんな大人の対応もありがち。



偉そうに言っちゃダメだよ。
他の子が嫌がるからね。



他の子が嫌がるから?おかしいだろ。
ここで必要なのは、『なぜ子どもはそんなことを言ったのか?』という問い。
“そのまま受け取らずに、問い返す癖”が、ズレた指導を防ぐカギになる。
- 表面的な言葉に振り回されない
- 大人の常識でラベリングしない
- 一度、疑う。もう一度、考える
これができると、『発言を止める』じゃなく、『なぜそれを言うに至ったのか』の構造が見えてきます。
すると、“止める”よりも、“育てる”対応ができるようになる。
うのみ厳禁。情報に“突っ込み”を入れるクセ、育てておくと、とても便利。
④ 道具思考 ― 使えるフレームワークは使い倒す
ロジックツリー/5Whys/フィッシュボーンなど、『道具』は使える。
不思議な言葉に思えるかもしれないけれど、私がよく普段から使っている、ごく普通の思考回路。
ロジックツリー
問題:子どもの『俺んちPTA会長』発言が炎上
→ なぜ?
- 親の態度
- PTA役職を家で威張ってる
- 家庭内でヒエラルキー感覚を強化してる
- 子どもの心理
- 家で言い返せない
- 学校で『マウント取り』で自己肯定しようとしてる
- 周囲の反応
- 同級生が『ダッセー』と笑った
- いじめの引き金に
こうやって原因や構成要素を階層的に分解するのがロジックツリー。
思考の迷子にならない地図みたいなもの。



考えるために分解しているようでいて、実は『行動の質』を変えるために分解しているというのが本質。
『感情』で動くと、行動は雑になる。
『構造』を知ると、行動は的確になる。それが目的。
◆5Whys(なぜ?を5回繰り返す)の実践例
『うちの親はPTA会長だから偉いんだ!』という発言に対して、こんなふうに深掘りしてみると——
- なぜそんなことを言ったの?
→ 勝ちたかったから。 - なぜ“勝ちたい”と思ったの?
→ 少し前に友達との口論で引けを取った。 - なぜ引けを取ったと感じたの?
→ 言い負かされそうだったから。 - なぜ親のすごさを競う必要があったの?
→ 親からもダメだと言われていて、自分に自信がない。(知りませんけど『俺はPTA会長なのにお前は何だ?』とか。想像ですよ。) - なぜ自信がないの?
→ 家でもあまり褒められないし、誰にも認めてもらってない気がする。
結果、全然『PTA会長』関係ないってこともあるかもしれない。
わからないですけどね。
親の行動が問題なのか、そこから波及する子どもの心理状態は?
って読み解いていくと、色々見えるんですよね。



けど、そこのアプロ―チをするのは、もちろん保護者だから。
ここの思考回路は、解決するためじゃなくて、現状を把握するためにある。
わたしの場合は、自分のためにあります。
ここまで来ただけでも、



平等が大事だから。
偉いとか言うのはおかしいでしょ。
他の子も嫌がるし。



の注意が無意味なの分かりますでしょうか?皆無。
だから、わたし、この類の言葉は言わないです。
なぜ他の子は嫌がるのに、言うの?
なら聞くかもしれない。なぜ?が基本でしょ。
フィッシュボーン・ダイアグラムで考えると?
フィッシュボーン(特性要因図)なら、こんな構造が見えてきます。
自然にしてる人多くないですか?わたしもよくしてます。
- 原因カテゴリA:家庭の空気感
→ 親のマウント癖があるのかな?
→ 承認欲求の家庭内伝播かな? - 原因カテゴリB:子どもの性格・経験
→ 自尊心が低めなのかも?
→ 対人関係で劣等感ありかな? - 原因カテゴリC:学校文化
→ 家柄や親の肩書に影響されやすい空気があるのかな?
こんなふうに“見えない因果関係を可視化”してくれるのが道具思考の強みでもある。何なら、
原因カテゴリD:保護者の会社での振る舞い、立場。
こんな想像もすることがある。
そちらが満たされていたら、PTA会長に拘るかな?
というひとつの視点。
そこから派生する環境を想像していくと、あらかた、見えてくるものがあるから。
正解でなくていいんですよ。
ただ、そういうことがあるかもしれない、という目線を情報程度に入れておく、行動が想像しやすいから。
今回、バズ―の恰好をしたPTA会長が、なぜそんなに目立ちたいのか?
総会でこんなこと言ってたんですよ。



保育園のとき、リレーで走ってる私を見て、すごくうれしそうに応援してたから、あぁ、親が前に出て活躍する姿は、子どもにとって、とっても嬉しいことなんだろうなと思って、PTA会長になろうと思いました。



ごめんなさい、ぶっ飛ばしてやろうかと思って。
目的がめちゃくちゃでしょ。
そりゃ、うちの長男も、わたしがリレーで走りまくってるのみて、すごくうれしそうでしたよ。
当時5歳。だからってPTA会長?思わねーよ。
他の人に迷惑だって。
けど、それは置いて置いて、この発言から何が見えてくるかって、
- 子どもは現在小学4年生、現在も同じ価値観だと思っている
- 同じ価値観だと思っているということは、恐らく交流が途切れている
- 普段、あまり会話をしていないのでは?
- となると家族の中の立ち位置はどうだろう?関係性はどうだろう?
- あの膨大な資料、いつ作ったんだろう?
すごい情報提供してくれてるんですよ。ありがとう。
ご本人はね、そんなつもり一切ないんでしょうけれど。
だって、『着ぐるみ着て先生・保護者・生徒の前ではしゃぐ親の図』
を喜ぶ年代かどうか?小4ですよ?
普通の感性してたら、いじめの温床になるかもしれないのくらい、想像つきません?
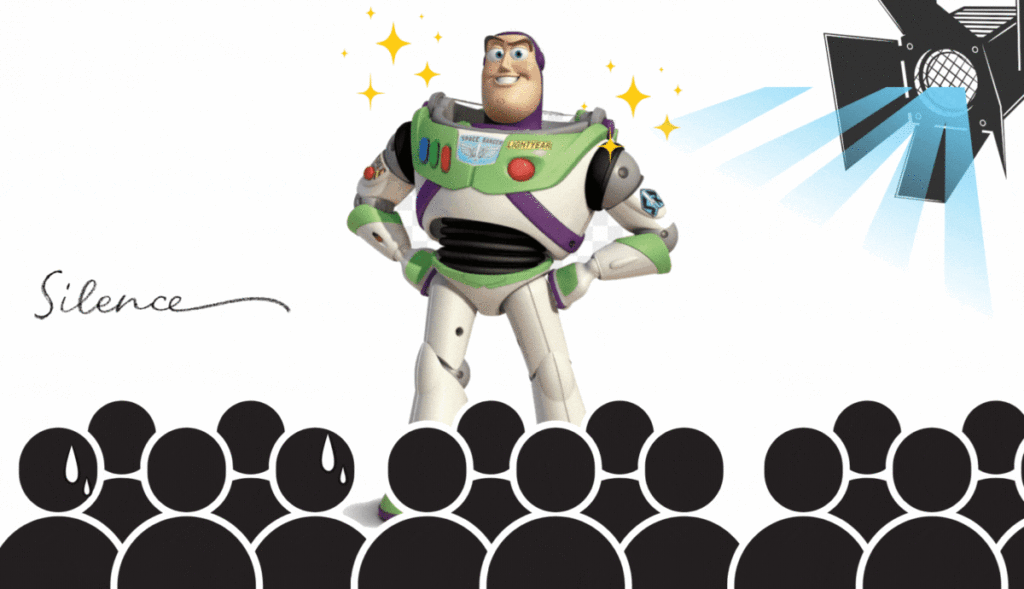
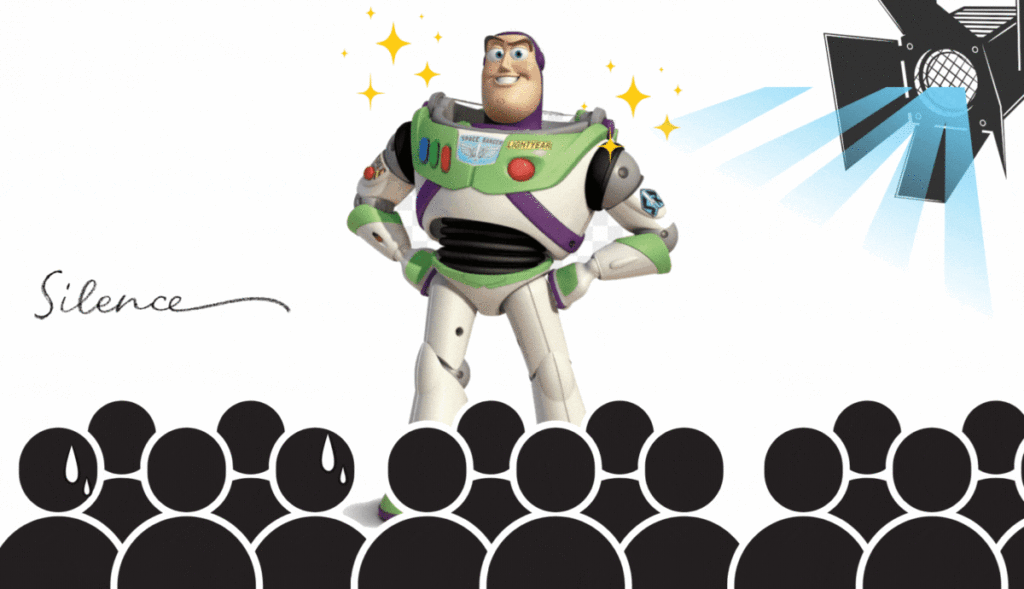
たとえば、マズローの5段階欲求に当てはめてみると、だいぶ整合性が見えてきます。
今回の“会長マウント”で言えば、満たされていないのはおそらく——社会的所属の欲求と承認欲求。
(もしかしたら、家族のなかでの“居場所”への渇望、家族に“すごい人だと示す立場”を得るための渇望も混ざっているかもしれません)
だから、PTA会長という肩書に強くこだわる。
けれど、着ぐるみを着て子どもの前で全力パフォーマンスしてしまうあたり、行動のズレ具合がすごい。
役割行動欲求。
ここまでズレる思考回路ってことは、その背景にはかなり複雑な構造があると考えるのが自然。
つまり、このズレは氷山の一角。
下には“承認されたい過去”や“満たされなかった何か”がごっそり沈んで、人生は樹海の森の確率が高い。
と想像できる。
仕事ぶりまで想像できるでしょ。



こうなると、子どもがあの発言に至った理由にも、徐々に整合性が見えてきます。
もはやギャグ。
けど、本人的には笑ってる場合じゃない案件。
けど、こっちにはどうしようもできないから、とりあえず、バズ―だけ回避。
アプローチできるのはそこくらいでしょ?
闇が深すぎて草。
使い慣れないうちは『これ、本当に意味あるの?』
って思うかもしれません。
モヤモヤの正体が分からないときは、道具を使って“問題の骨組み”を見てみる。
構造が分かると、気持ちに飲まれずに、次の一手を選びやすくなるから。
つまり、道具思考は『気持ちじゃなく、意味で動くためのツール』。
知っておくと便利。
⑤ 構造化思考 ― 問題を分解して地図にする
『この問題、どこがどう繋がってるのか、ぐちゃぐちゃすぎて分からん……』と思ったら、構造化思考の出番。
❶ 親の影響
- 家で『PTA会長として~』と誇らしげに話しているかもしれない
- 子どもに対して『お前の父さんは立派だ』と繰り返し伝えているかもしれない
❷ 子どもの心理
- 親からの承認欲求に応えようとするかもしれない
- 家庭内で発言できず、学校でマウントという形で発散かもしれない
- 劣等感の裏返し、もしくは不安の隠れ蓑として“父親の肩書”を使用かもしれない
❸ 周囲の反応
- 『PTAって偉いの?』という疑問からくる笑いや違和感
- 子ども同士の上下関係が固定されやすい土壌
- 親の権威が学校内の人間関係に影響するという“空気”
❹ 大人側の対応
- 双方『発言の仕方に気をつけて』で済ませると問題の根は残る
- 背景の構造に気づかず、再発の芽を放置する結果になる
分けてみると、
『あ、この道じゃダメだ』
『ここに問題の根があったわ』
と気づけるんですよ。
構造が“地図”になると、感情でぶつかるより、
『どう動くか』に頭を使えるようになる。
構造が見えれば、アプローチも変えられる。
『言い方を注意する』んじゃなくて、
『家での価値観の伝え方を見直すよう、保護者に丁寧に伝えてみる』
『子どもが安心して本音を言える環境を整える』
とか、より根本的な対応が取れるようになるかなと。
このとき、



あなたのその価値観どうなんですか?
とか言っちゃうと、批判になるし、それによって相手が防衛に入るんです。
そうすると、会話が成立しなくなって、わたしの大嫌いな20-80論争が勃発する。
だから、わたしならこんな感じで伝えるかもしれない。



あなたの価値観を否定するつもりはありません。
ただ、その価値観が、息子さんに大きく影響しているように感じます。もしこのまま発展したら……(この先の想像の話)。
その先にあるのは、どんな未来でしょうか?
あなたは今、満たされていますか?だとすれば、なぜ会長という役職に、そこまで拘るのでしょう?
一度、そのあたりを、ぜひ息子さんと話し合ってみてください。
子どもは、想像以上に正直です。
『会長だから偉いんだ』——この一言の背景には、何があるのか。
私はそこが、とても気になります。
と、本人が考えられるように、ボールは“届くように”投げるつもり。
でも、実のところは、ちゃんとブツケるつもりです。
そんな感じ。



そして、わたしは教育者ではないので、もし、この問題で子どもや周りのお友達が被害にあっていた場合(PTA会長だからな!と言われてたり)、先手を打つ行動を取ると思います。
要するに、ちゃんと、咎められるところが咎められるように、子どもたちにアドバイスをするということです。
正解じゃない、わたしなら、の話です。
だって、快適に過ごしたいから。
自分と自分の子ども、周りのお友達、先生、守るべきところは守らないと。
というか、わたしなら、そういうアプローチを試みてみる。
そっちが根っこかな?と思えば。
1度で済む可能性が高いから。
この手の問題、長引いたら半年~もしかしたら1年ずっとでしょ。
クラスの雰囲気考えたらね。



伝えるだけで、どうするかは相手次第ですけどね。
伝わらない相手も数割存在するんですよ。
でも、こちら、わざわざ時間を割いて親切丁寧に伝えてあげたんだから、超偉い。
とりま、任務完了。
それから、次の1手を考えたらいいし。
⑥ 哲学思考 ― 『そもそもこの問いは正しいか?』
たとえば、子どもがこう言いました。



俺んち、親がPTA会長だから偉いんだぞ!
そもそも、『偉い/偉くない』って、なんの話?
この問い自体が、なんかズレてるかもって気づくのが、哲学的思考のはじまり。
問い方がズレてると、答えもおもいっきりズレる。
『PTA会長は偉いかどうか』なんてのは、たぶん議論しても永久に結論出ません。
それより本質はたぶん、こういう問い。
なぜ“偉い”って言葉を子どもが使いたくなったのか?
“偉さ”を主張することで、何を守りたかったのか?
この視点で見ると、『偉いんだぞ』はマウントというより“自尊心の補強材”かもしれない。
たとえば、家で認めてもらえていないとか、自信が揺らいでるとか。
本当は『すごいって言ってほしい』じゃなくて、『寂しい』かもしれない。
哲学思考って、難しい理屈をこねくり回すことじゃなくて、『その問い自体、合ってる?』と疑う勇気のこと。
表面的な言葉を『どう変えさせるか』よりも、その言葉が“なぜ出てきたのか”を問う姿勢のほうが、よっぽど人を理解できる気がします。
子どもの一言に、大人が“問い返し”をできたら。
きっとその場の空気、ちょっと変わるはず。
日常で『問題の本質を見抜く』ためにできること


- 仮説を持つ、でも執着しない柔軟性
- 『なぜ?』を深堀りしてみる
- 議論や対話から“気づき”を盗む
① 仮説を持つ、でも執着しない柔軟性
『多分こうだろうな』っていう仮説、持つのはいい。
でも、そこにしがみつくと逆に見えなくなるものも多いんです。
仮説は“地図アプリ”みたいなもの。
まずは目的地を入れてみる。
でも、事故渋滞って出たらちゃんとルート変えますよね?
それと同じ。



たぶんあの子は怒ってるんじゃなくて、寂しいのかも。
こういう予想を立てることで、行動の背景が見えることもある。
でも実際は『お腹すいて疲れてイライラしてただけ』かもしれない。
仮説は“固定解”じゃなくて、思考のジャンプ台。外れても落ち込まない。
飛び直せばいい。
② 『なぜ?』を深堀りしてみる
日常の中に『なんでだろう?』って思う瞬間、ありますよね。
スルーしない。
それ、金の卵です。
- いつもの発言と違う、何だろう
- なぜ、子どもは『ママがいい』しか言わないのか
- なぜ、自分はその言葉にモヤっとしたのか
“なぜ”の回数を1つでも増やすと、『本質に気づく筋肉』が鍛えられるのかもしれない。
わたしは基本、こんな感じです。
1つ増やすという意識はしていないけれど、基本、あれ?はいつもあります。
考えすぎても仕方ないことなら、手放すこともしますけどね。
仮説立てておくと、すぐに対処できることもあるから。
かもしれない、を増やしておく。
無理して5Whysしなくていい。
『なんでこれ?』を1個、自分の中で聞き返す。
それだけでも、現象の奥がちらっと見えてくるようになります。
③ 議論や対話から“気づき”を盗む
自分一人で考えるのは大事。
でも、たまには他人の思考も“いただきます”しちゃいましょう。
何気ない会話や意見交換の中に、
『あ、それ盲点だった』ってヒント、
けっこう落ちてます。
- 『その視点なかったわ!』をメモする
- 相手の思考回路をまねしてトレースしてみる
- 『なるほど、私はこう思うな』と自分の意見と比較してみる
議論って、戦いじゃないんです。
思考の“食べ歩き”みたいなもの。
消化できそうなら、自分の中に取り入れる。
それだけで、自分の思考の幅がぐっと広がるはずです。
まとめ
『どう対処するか』よりも、
『どこに問いを立てるか』。
それだけで、見える世界も行動も、驚くほど変わる。
問題の本質は、目の前にあるようで、だいたい少し奥にあります。
表面に振り回されないためには、『深く見る』習慣をつけること。
そのために必要なのが視点の切り替え。
本質が見えた瞬間、次にどう動くかは、おどろくほどシンプルになる。
見え方が変われば、生き方が変わる。
背景を理解することができれば、その人の立場を理解できれば、なぜ、その人がそういう行動にでてしまっているのか?
理解できるから。
やむを得ないことなのか、それともエゴか、見えてきたものに対して最善の対処を取るだけ。
やむを得ないことがあれば、そちらの理解も必要だから。
だから、ここでも課題の分離。
立場、エゴ、役割、色々解体ショー。
だから私は、『指導する側の立場の理解』も『指導される側の理解』も、自分なりにしときたいんです。
間違いがあるかもしれないけれど、それでも、誰も傷つかないなら、それでいっかなと。
でも、自分の感情はもちろん大事にしますよ。
いろんな記事でも言及してるけど、色々見えたとしても、あくまでも感情に沿わないことはしない、それが私の流儀です。
ほんと、色々見えたとしても、最悪『調子乗ってんじゃねーよ』で終わることもある。
背景が見えて言うのと、見えないで言うのとではまた、違うと思うから。言葉は変わりませんけどね。
これまでの思考何だったの?っていう。
いいの、それで。



これは『こうするべき!』という正解ではなく、あくまで、わたしがどう思考し、どう動いているかという記録。
私はこのほうが、労力かからないから。
余計なことしなくて済むし、気持ちも疲れにくい。
ていう持論の記録。
長くなっちゃったなぁ….ごめんなさい。
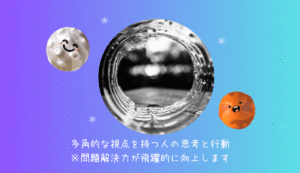
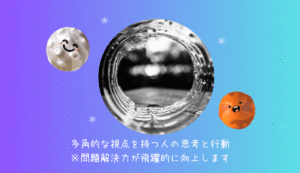

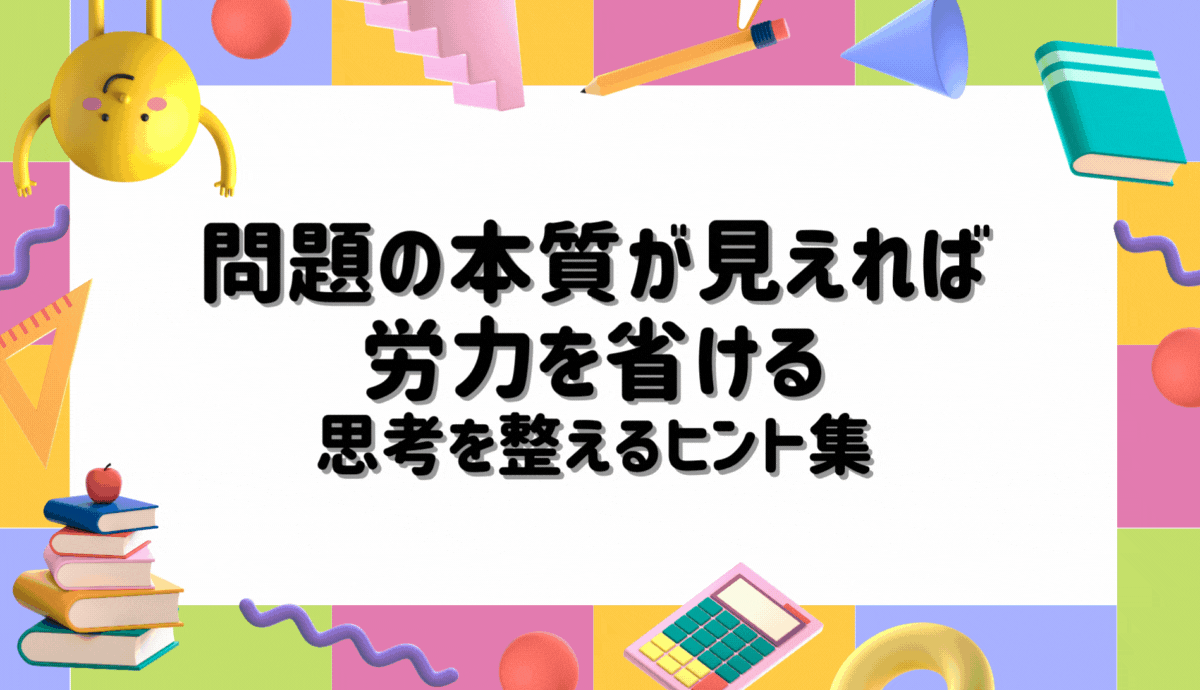
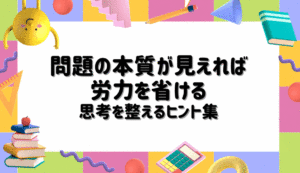
コメント