『なんであの人はあんなに優れているんだろう?』
『私なんてまだまだ、、』
つい他人と比べて落ち込んでしまうこと、ありますよね。でも、比較すること自体が悪いわけではありません。
比較は成長のチャンスでもあります。問題は『比較の仕方』。

『他人と比較すること』は、やり方によっては成長を妨げることも、加速させることもある。
本当は『理想の自分』と『今の自分』、『今の自分』と『過去の自分』との比較が正しいのだろうけれど、大概は他人と自分を比較してしまうものですよね。
この記事では、比較癖を直すというより、うまく付き合い(つまり受容し)、その劣等感を成長のエネルギーに変える方法をまとめてみました。
では、どうすれば『他人と比べる習慣』から抜け出せるのか?
他人との比較から脱却する実践的な方法
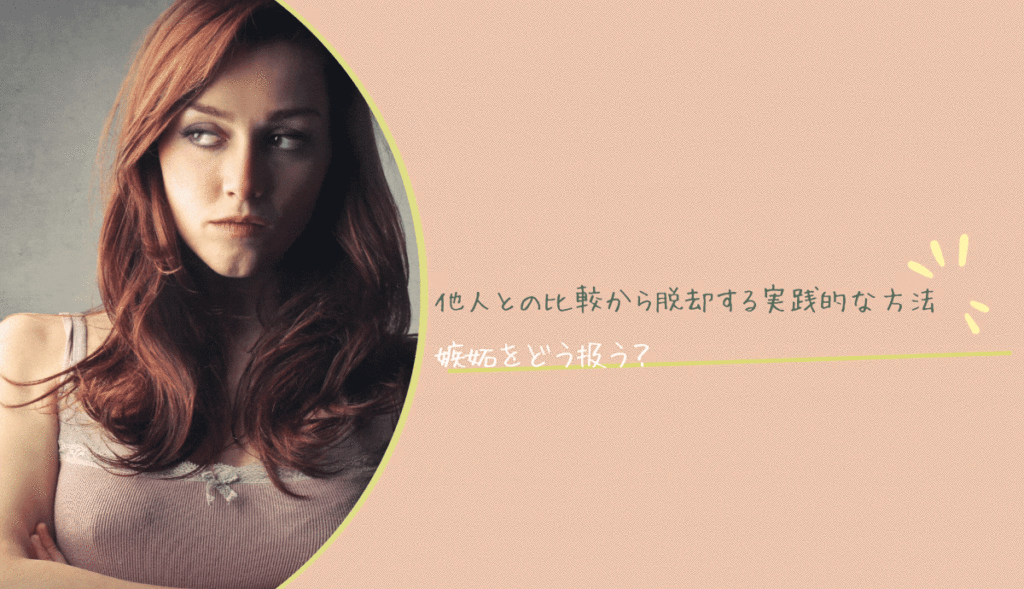
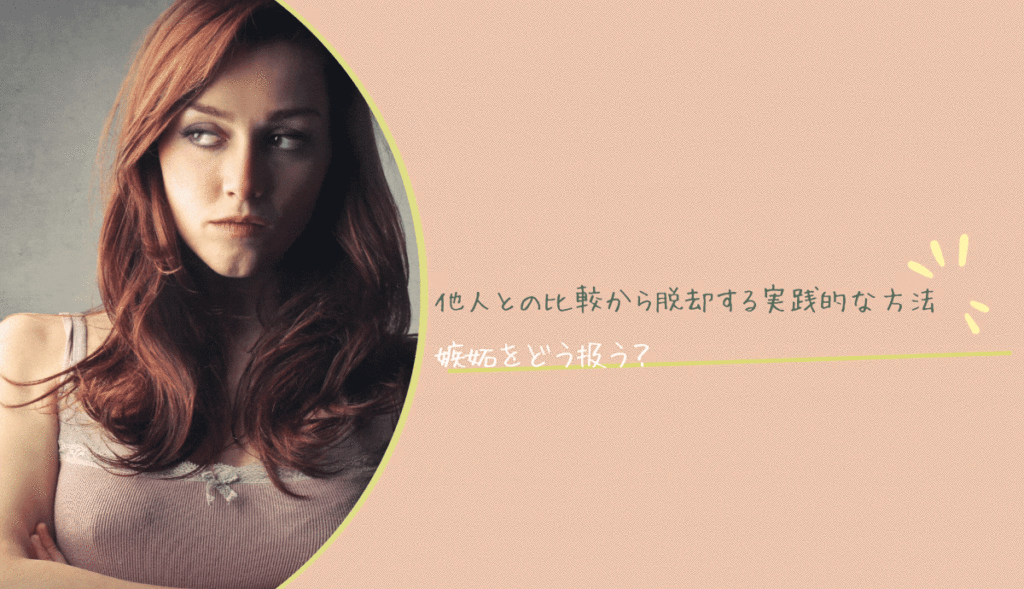
- 嫉妬をどう扱うかが大事
- 建設的に考えられない精神状態とは?
①嫉妬をどう扱うか?
嫉妬が生まれたときの対応には、大きく分けて『破壊的な使い方』と『建設的な使い方』があります。
破壊的な使い方(愚かな方向)
- その人を妬んで悪く言う
- 『どうせ自分には無理』と諦める
- 相手を引きずり下ろしたくなる
- 自分の価値を見失い、自信をなくす
このような反応をすると、エネルギーが無駄に消費されるだけで、自分の成長には一切つながりません。
建設的な使い方(賢い方向)
- 『この人は何をしてここまで来たのか?』と分析する
→ ただ憧れるのではなく、その人の努力や習慣を学び、自分に取り入れる。 - 『自分も同じレベルに行くには何が必要か?』と考える
→ 感情だけでなく、実際の行動に落とし込む。 - 『その人と比較するのではなく、インスピレーションを得る』
→ 嫉妬を『自分の可能性に気づくサイン』として使う。
嫉妬や怒りなどの感情を『建設的に使う』には、まずその感情をコントロールし、賢い方向へ変換できる精神状態になることが重要。
でも、建設的な考え方をして行きましょう!なんて、誰でも言える。



それができないから苦労しますよね。
だからこそ、まずは、『建設的に考えられる精神を育てること』が最優先になります。
建設的に考えられる精神ってどういう状態なのか?
②建設的に考えられない精神状態とは?
人って生きてると、自分にとって良い時期もあったり、悪いと思われる時期もあったり、色々じゃないですか。
そんなとき、感情が揺さぶられますよね。
例えば、
- 感情に流される(怒り・嫉妬に振り回される)
→ 『あの人が羨ましい…でも自分は無理、許せない』と思ってしまう。 - どうしてもネガティブなループから抜け出せない
→ 『どうせ自分にはできない、あの人がすごいのは特別だから』と決めつける。 - 他責思考(環境や他人のせいにする)
→ 『周りが悪い、自分にはチャンスがない、あの人は運がいいだけ』と外部要因ばかりを気にする。
この状態だと、どんなに素晴らしい学びがあっても、結局それを活かせません。
では、どうすれば『建設的に考えられる精神』になれるのか?
建設的に考えられる精神を育てる6つの方法
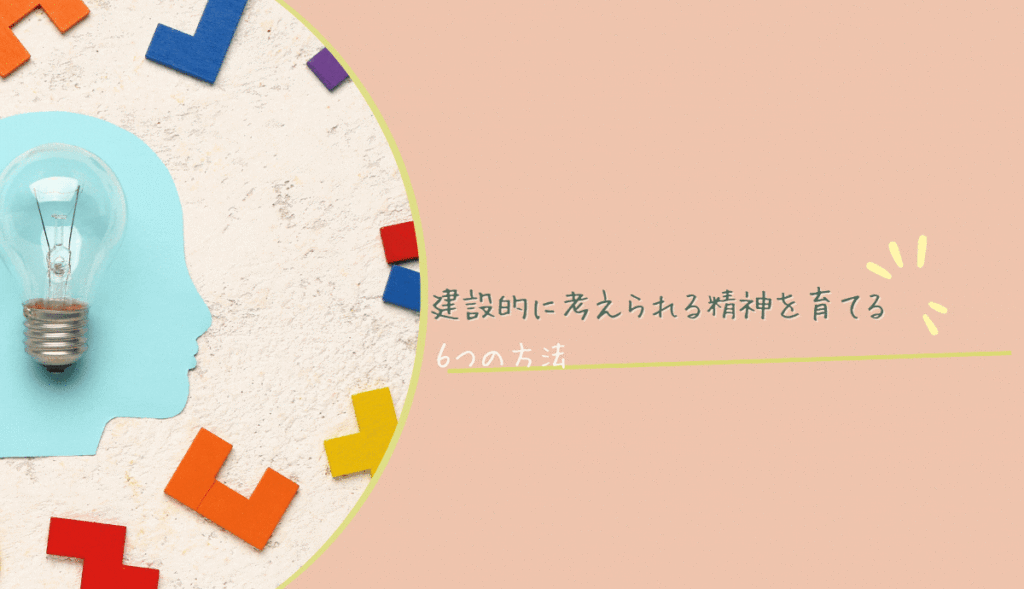
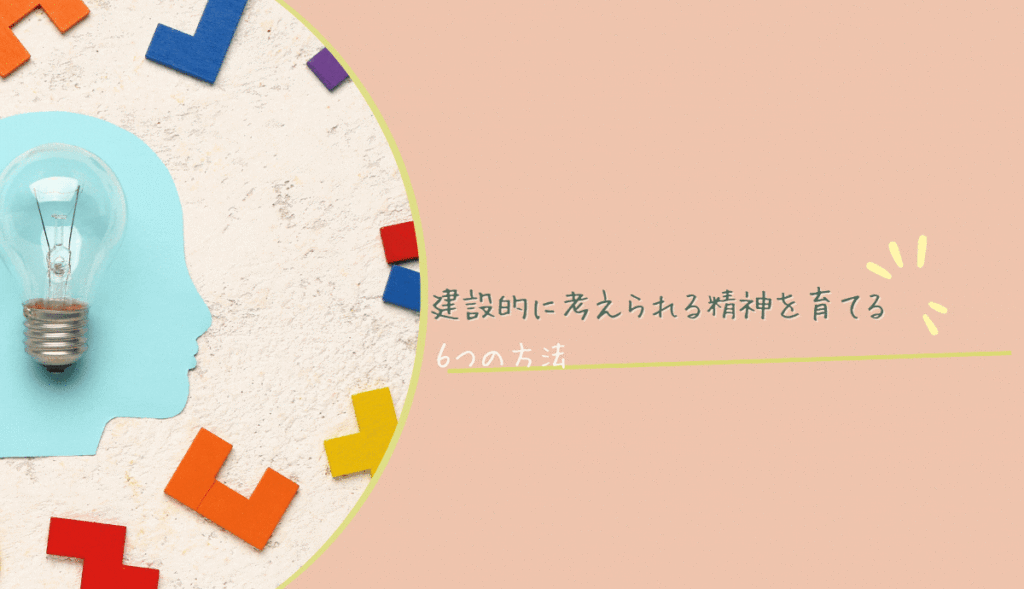
ここで大事なのは、『感情との向き合い方』と『思考のクセを変えること』 です。
- 感情を客観的に見る(自己観察)
- 『比較』を『学び』に変える
- 『できない理由』ではなく、『できる方法』を探す
- 『自分の軸』を持つ※長期視点で成長を捉える
- SNSの使い方を工夫する
- 環境を変える
①感情を客観的に見る(自己観察)
まず『自分は今、嫉妬しているな』『怒りを感じているな』と認識する。
感情を無理に消そうとせず、『なぜこの感情が生まれたんだろう?』と内省する。
ここで初めて、感情がコントロール可能になります。
日本は、同調傾向が強いので、なんとなく合わせてしまって、自分の感情が疎かになることがあるんですよ。
なので、日頃から自分がどういう風に感じているか?を意識する癖をつけたらいいです。
②『比較』を『学び』に変える
例えば誰かに対して、『すごい!』と感じることがあったとします。
その人のどこを凄いと感じたのかを探っておきましょう。
悪い比較:『あの人は〇〇がすごい…自分はダメだ』 → ネガティブになる
良い比較:『あの人の〇〇はすごい!〇〇について自分も学ぼう!』 → 自分の成長に活かすことができる
比較を『学びの材料』にするだけで、エネルギーになります。
内面の充実を優先する。 スキルや知識の向上だけでなく、心の豊かさや精神性の成長を大切にする。
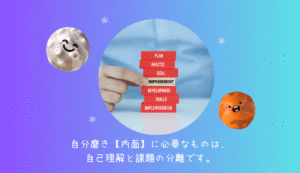
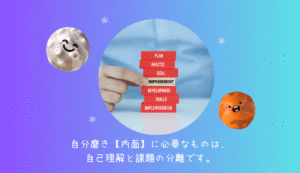
『悔しい』『羨ましい』と思う気持ちは、実は『自分もこうなりたい』という願望の裏返しでもある。
- その人のどんな部分に憧れている?
- 自分もその方向に成長できる?



もし、相手が自分より優れていることを認められない状況なのであれば、理由をいくつか挙げてみます。ここには、きちんと向き合った方がいいと思う。そして考え方に気を付けたら大丈夫。
1. 自尊心やプライドの問題
人は誰でも『自分には価値がある』と思いたいものです。特に、自信を支えている分野で他人が優れていると、それを認めることで自分の価値が下がったように感じてしまうことがあります。
これは、課題の分離ができない状態でもあります。


実際には 『相手が優れていることを認めること』 と『自分の価値が下がること』は別の話です。でも、感情的にはそう感じてしまうことがあるんですよね。
本当は、他人の優れた部分を認めることができる人のほうが、 自分の価値をしっかり理解しているし、むしろ 成長のチャンスをつかみやすいです。ライバルの強さを認めた上で自分を高めようとする人のほうが、結果的に成長しますよね。
例えば、現在の将棋界で注目される藤井聡太七冠は圧倒的な強さを誇ります。彼よりも先輩である永瀬拓矢九段は藤井七冠を尊敬していますが、棋士として対抗するために、独自の研究と弛まぬ努力を続けています。
藤井七冠と永瀬九段は、研究パートナーでもあり、互いに戦型のひとつである『角換わり』での研究が深く、永瀬九段は藤井七冠の強さを認めつつ、そこを乗り越えようと努力しています。彼の『今の棋士は藤井聡太さんという存在に感謝すべきです。(中略)強いだけじゃない。『強い』の上を行っている気がします。』とライバルとなる存在を『感謝すべき』とさえ言う、『努力の上』を行く彼の言葉は、ただの称賛ではなく、己の成長の糧としている証とも感じられます。
テニス界のロジャー・フェデラー & ラファエル・ナダルは、互いの強さを認め合い、フェデラーは芝やハードコートでの試合を得意とすることから『芝の王者』、ナダルはクレーコートでの試合を得意とすることから『土の王者』との異名があります。
ナダルはフェデラーの王者時代に3年間も2位であり続けた。2008年の8月についに順位が入れ替わり、間もなくそこにジョコビッチが割って入ってくる。フェデラーもナダルももう終わりだと囁かれた時期もあった。しかし、沈んでは這い上がる彼らの戦いぶりとその関係はファンを決して飽きさせることなく、月日は流れて2017年の 全豪オープンで劇的なドラマが生まれる。約6年ぶりにグランドスラム決勝での対決を実現させ、膝の怪我から復帰したばかりのフェデラーが4年半ぶりにグランドスラム優勝を遂げた。やはりグランドスラムのタイトルから2年半遠ざかっているナダルに、優勝スピーチでフェデラーはこう語りかけた。
『僕たちがまたこんな舞台で戦えるなんて夢のようだ。たとえ今日僕が負けたとしても君のために喜べただろう。テニスに引き分けがあるなら僕は喜んでこの勝利と君と分け合うよ』



逆に、相手を認められずに『相手を下げよう』としたり『自分をごまかそう』としたりすると、成長が止まってしまうことが多いです。だから、本当は 『相手の優秀さを認めること』こそ、自分の価値を高める行動なんです。
『相手がすごい=自分はダメ』 みたいに感じてしまう。実際には、相手が成果を出したという事実があるだけで、自分の価値は何も変わっていないのに、感情が『負けた』『劣っている』と思わせてしまう。
これは、自分の価値を『他人との比較』で測るクセがついていると起こりやすい。でも、本当の価値は『他人と比べてどうか』ではなく、『自分自身がどうあるか』で決まるもの。
だからこそ、相手の優秀さを認めた上で、『自分は自分で、どう成長していくか?』に目を向けることが大事なんです。
こう考えられるようになると、他人の成功を素直に祝えるし、自分自身も前向きに成長できるようになります。
2. 劣等感や自己防衛本能
自分に自信がない人ほど、他人と比べてしまいがちです。相手を認めることが『自分の劣等感を直視すること』につながるため、それを避ける心理が働きます。



本当は、『相手の実績を認めること』=『自分が負けた』 ではないのに、感情的にはそう錯覚してしまうんですよね。
これは、『勝ち負け』や『優劣』の視点でしか物事を見られなくなっているときに起こりやすいです。実際には、相手が成果を出したことと、自分の価値や可能性とは何の関係もないのに、比較してしまうことで 『自分はダメなのでは?』と感じてしまいやすい。
でも、この思考のクセに気づけば、見方を変えることができます。
相手の成功は、単に相手の成功であって、自分の価値とは関係ない
相手の実績から学べることは何か?
自分も自分なりに成長できる部分はあるはず
3. 競争意識や嫉妬心
特に職場や学業、スポーツなど競争がある場面では、『負けを認める』ことになるのが怖くて、相手を認められないことがあります。嫉妬心があると、相手を認めるよりも、相手の欠点を探して安心しようとすることもあります。
4. 成長の機会を見落としている
相手を認められる人は、他人の成功から学び、自分も成長しようとします。しかし、相手を認められない人は『学ぶ』という視点ではなく、『勝ち負け』や『上下関係』でしか物事を見ていないため、素直に認められなくなります。
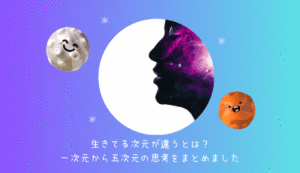
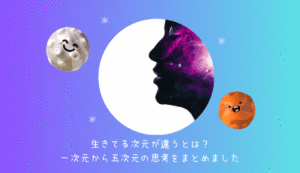
5. 環境や文化の影響
幼少期からの教育や家庭環境、職場の雰囲気などによって、『負けを認めること=恥』と考える価値観が身についている場合もあります。特に、成果主義や厳しい競争環境の中では、『認めたら自分が負けてしまう』と感じやすくなりますが、この発想は逆で『負けを認めないこと=恥』です。
つまりは、自分の否すら認められない方が負けということです。



本当の『負け』は、自分の未熟さや課題から目を背けること。逆に、自分の足りない部分を認め、受け入れることができる人は、そこから成長できるので、結果的に『負けない人』になれる。
成果主義や競争の激しい環境では、『認める=負ける』と錯覚しがちですが、実際はその逆で、認めないことこそが停滞や成長の妨げになる。つまり、『認めない=自分の可能性を狭める行為』 になってしまう。
例えば、スポーツ選手やビジネスの成功者を見ると、自分の弱点を素直に認めて、そこを改善することでどんどん成長している人が多いですよね。『現実を受け止めて、次に進む力にする』ことが、本当の強さにつながるんです。
結局のところ、『相手を認めることができる人』 こそ、自分自身を成長させ、長期的に勝てる人。
劣等感を感じたら、『どうすれば近づけるか?』と前向きに考えられるといいです。


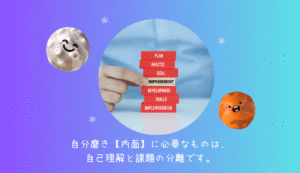
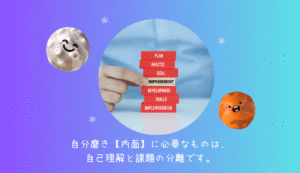
③『できない理由』ではなく、『できる方法』を探す
あの人は特別だから自分には無理。と決めつけるのではなくて、少しでもい近づけるものはないか?小さくでもいいので、『今すぐにできること』を考えるのがポイントです。
全部じゃなくてもいいんです。小さなことからでいい。
④『自分の軸』を持つ※長期視点で成長を捉える
他人の評価に振り回されないために、自分にとっての成功や幸せの基準を明確にしましょう。すぐに結果を求めず、『自分がどこに向かっているのか』を意識する。
- 自分が本当にやりたいことは何?
- どんな人生を送りたい?
『他人より上か下か』ではなく、『自分が納得できる生き方』を大事にすると、比較すること自体が減っていきます。
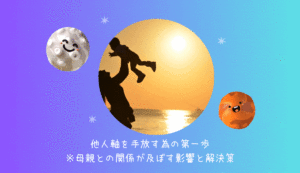
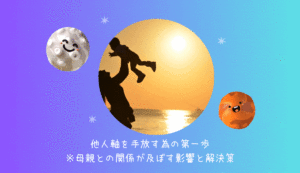


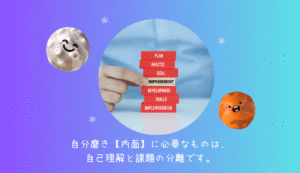
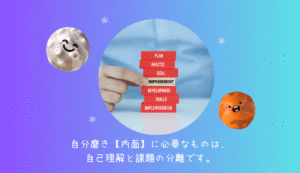
⑤ SNSの使い方を工夫する
SNSを見て『みんなキラキラしてる…』と落ち込むくらいなら見ない、もしくは使い方を変える。
- 自分を比較してしまうアカウントをフォロー解除
- 見る時間を決める(例:1日30分)
- 『学びがあるアカウント』だけ見る



SNSはリアルの全てではありませんよ。むしろ『見せたい部分』だけを切り取っていることを忘れずに…
⑥環境を変える
自分が『レベルが高い』と思う人と関わると、自然と考え方も変わります。これは必然。
本などで成功者の思考に触れるだけでも効果はあります。まず、その人のマインドを学ぶところから始めてみるといいと思います。



建設的に考えられる精神にならないと、せっかくのチャンスや成長の機会を逃してしまいます。だからこそ、まずは 『感情との向き合い方』を変えて、思考のクセを修正していくことが大事です。
ではなぜ、人は他人と自分を比較してしまうのでしょう。
他人と比較してしまう原因とは?本当の理由を解説


他人と比較してしまう気持ちは、多くの人が抱える普遍的なものです。この感情の背後には、様々な複雑な要因が隠れています。
基準が外部にあるため、常に振り回されます。 自分より優れた人を見れば劣等感を抱き、自分より劣っていると感じる人を見れば優越感を持つ。どちらも本質的な成長にはなりません。
他人の成功や価値観に左右されてしまい、自分が本当に大切にしたいものを見失いがちになり、比較によって『自分はダメだ』と思うか、『自分は優れている』と過信するかのどちらかに傾き、本当の成長の道から外れていきます。



ですが『嫉妬』自体は悪いものではなく、そのエネルギーをどう使うかが重要。
まず、『他人と比べること』は人間の本能の一部とも言え、それは、生存本能(進化の過程で備わった性質)や社会的なつながりと深く関係しています。
- 生存本能(進化の過程で備わった性質)
- 自己評価の基準が外部にある※現代にも残る比較する本能
- 成長の尺度として比較してしまう
- 自己肯定感がない
- 環境の影響
- 承認欲求の強さ
- 社会の影響
- 制限する思い込み
①生存本能(進化の過程で備わった性質)
群れの中でどれくらいの影響力を持っているかによって、食べ物を得られるかが決まり、自分が戦うのが得意なのか、道具を作るのが得意なのかを知ることで、群れに貢献できる。
②自己評価の基準が外部にある※現代にも残る比較する本能
SNSでの『いいね!』の数や仕事や収入の違い、外見や才能の違い、これらが自己評価の基準になってしまうと、他人と比べずにはいられなくなります。
③成長の尺度として比較してしまう
『自分が成長しているかどうか』を確認するために、他人と比べる。それが行き過ぎると『焦り・嫉妬・自己嫌悪』につながる。比較が『学び』ではなくて、『自己否定』になり、苦しくなる。
その自己否定が更なる感情を呼び起こし、様々な問題を引き起こすことになります。
④自己肯定感がない
自己肯定感のなさは、他人と比較してしまう一因。
自分に自信が持てず、他者と自分を比べることによって、劣等感を強めてしまうことがあります。例えば、『あの人の方が優秀だ』と考えてしまい、『私は何もできない』と自己否定に陥る、『自分の方が優秀だ』と自己肯定に陥ることがよく見受けられます。このような思考が続くと、他人との比較が日常化し、心理的なストレスを抱えることになります。
⑤環境の影響
幼少期に育った環境や周りの人々の影響も、他人と自分を比較する習慣を形成する要因。
特に、親や教員から相対的な評価を受けて育つと、自分の価値を他の人との比較で測るようになりがちです。
このような環境では、他人と比較することが普通になり、自分を正確に評価することが難しくなります。
ただし、前述したように、正しい比較ならば何ら問題ではありません。競争がダメみたいな極端な発想にならないように、注意してください。
競争や比較が無いと、自分が分からなくなります。他人がいるから、競争や比較により自分という人がわかる。その感情や思考の処理の仕方に気を付けておけばいいんです。
⑥承認欲求の強さ
人は誰しも他者からの承認を求めますが、この欲求が過剰になると、他人と比較することが避けられない状態になります。『自分は価値がない』と感じることで、他者の成功や行動に目が向き、自分との比較を始めてしまいます。
そして、他者に承認を求めるようになってしまう。このような状況では、自分の実力を発揮できず、自己評価は低下します。


⑦社会の影響
現代の情報社会では、SNSやメディアから伝わる成功事例や理想的なライフスタイルが溢れています。
このような情報によって、他人の素晴らしい瞬間が簡単に目に入るようになり、無意識のうちに『私もあんな風になりたい』と思ってしまうことがあります。
良い影響ならば大丈夫。ただ、日常生活の中で無力感を感じやすくなることもあります。
⑧制限する思い込み
偏見や思い込みも、他人と比較してしまう要因の一つ。『成功はお金で測るべき』や『美しさは痩せていることにある』といった固定観念が、自分を狭める要素となります。こうした思い込みが他者との比較基準となり、自分への劣等感をさらに強めることがあります。
このように、他人と比較してしまう原因は、周囲の環境や自分の内面、社会全体の影響など、多様な要素から成り立っています。これを知っておくことが、問題解決に向けた第一歩を踏み出す一助になるかもしれません。



思い当たる原因が分かれば、あとはその感情をどう処理していくか?という視座に変えられたらいいと思う。
比較癖がもたらす心への影響と危険性


『他人と比較してしまう』習慣は、私たちの心に多くの悪影響を及ぼすことがあります。この比較癖は、以下に示すように心にさまざまなリスクや問題を引き起こす要因となります。
- 自尊心の低下
- 不安感の増大
- 人間関係の悪化
- ネガティブな感情の増幅
①自尊心の低下
他者と自分を比べることで、自分の短所や劣等感が炙り出されることになります。
比較で、自尊心が著しく損なわれる危険性がある。特に、他人の成功や魅力に目を奪われることで、自分自身への評価が否定的になることが多く、同じ基準で自分を評価することで、自己の独自性や価値を見失う可能性が高まります。
②不安感の増大
他人と比較する際、比較対象が優れているほど、自分が到底及ばないという強い不安を抱くことになります。
その不安は日常生活におけるストレスや焦りを引き起こし、心に重い負担をかける要因となります。常に『自分には何かが足りない』と感じることで、メンタルヘルスの悪化を招くリスクが増大します。
③人間関係の悪化
『他人と比較してしまう』行為は、競争心を生むことがあります。
これによって、友人や職場での関係がぎくしゃくする恐れがあり、自分を他者と常に比べることで、友情の中に嫉妬心が生まれ、最終的には友情関係が破綻ということもあり得ます。
④ネガティブな感情の増幅
この比較癖が引き起こすネガティブな感情、嫉妬や怒り、劣等感などは、心に深刻な影響をもたらします。
これらの感情が持続することで、ポジティブな経験や感情を享受することが難しくなります。他者との比較によって生じた感情は、自己を否定し、自尊心をさらに低下させる要因。
『他人と比較してしまう』癖は、私たちの心にさまざまな悪影響をもたらします。自分自身に焦点を当て、他者との比較から解放されることが、心の健康を守るためには重要です。
まとめ
他人と比較してしまう行為について、まとめてみましたが、比較して努力した結果、できないことがあっても、それを受け入れることも大事。



その結果、納得ができて『諦めがつく』こともあるから。これは仏教の教えに準じています。
『諦めがつく』とは、納得して手放す、または受け入れること、これも成長。
つまり、『比較の方法』さえ間違えなければ、どこまでも成長できる。
例えば、以下のような場合に『明らかになることで諦めがつく』ことがあります。
現実を知って、方向転換する
→ 『この夢は、今の自分の目指したいものではない』と明確に分かった結果、別の道を選ぶ。
無理だと分かり、執着を手放す
→ ずっと思い続けていた恋愛が『叶わない』と明確に分かり、気持ちを整理する。
他に集中すべきことが見えた場合
→『これを諦めたとしても、別の道がある』と納得する。



ただし、『明らかになった結果、諦めなくてもいい』場合もあります。
『明らかになること』は『諦めること』に直結はしますが、『明らかになることで、次の一歩を踏み出せる』ことでもあります。いずれにしても、『明らかになること、明らかにすること』『諦めること』というのは、次の一歩を踏み出す一助になるということです。
自分に足りないものが明らかになったから、努力の方向を変える
課題が明確になったから、もっと成長しようと思えた



つまり、『明らかになった結果、諦める』のではなく、『諦めるべきものと、努力すべきものを正しく見極められる』というのが本質的な流れです。
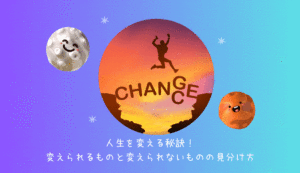
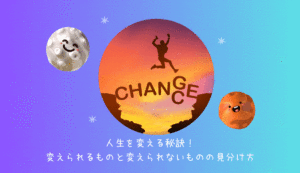
事実を受け入れた結果、諦めがつくこともあるし、新たな挑戦につながることもある、どちらも次の一歩の一助になる。
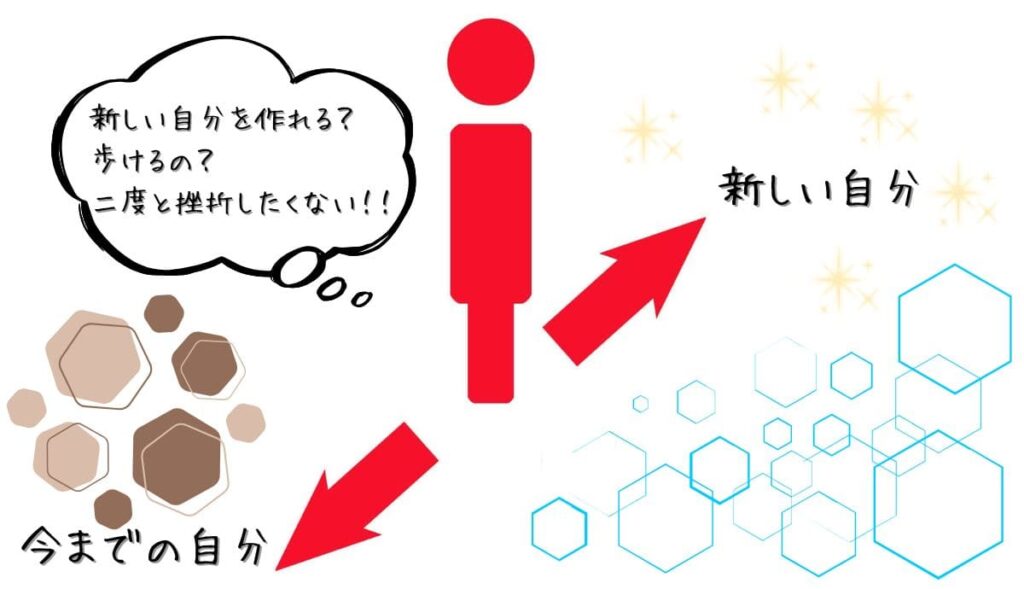
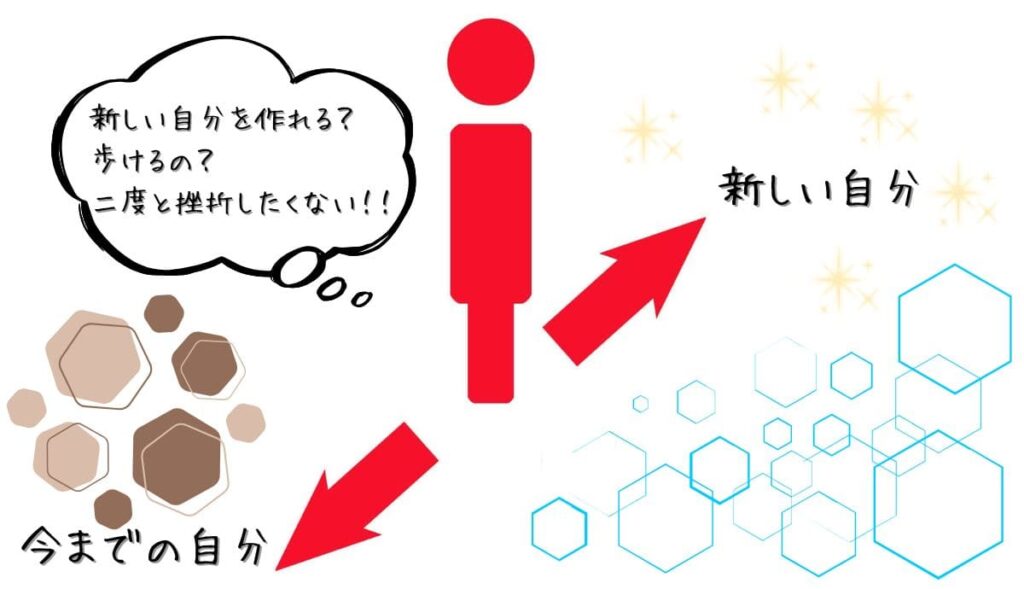
それがヘーゲルの言う弁証法的プロセスであり、絶対精神に近づくための一歩でもある。つまり、事実を受け入れ、諦めや挑戦を繰り返すこと自体が、『自己の成長=絶対精神』への道となる。
過去・現在・未来の流れを繰り返しながら進むことで、人間の精神は成長し『絶対精神』に向かって進む。



合ってると思う。
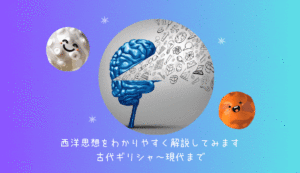
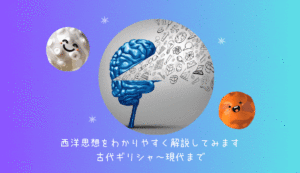
こうした他人との比較は、本能的にやってしまうものですが、現代社会では『不必要なストレス』になることも多いです。
だからこそ、比較の対象を『過去の自分』や『目標に向かうための指標』に変えていくことが大切だと思います。

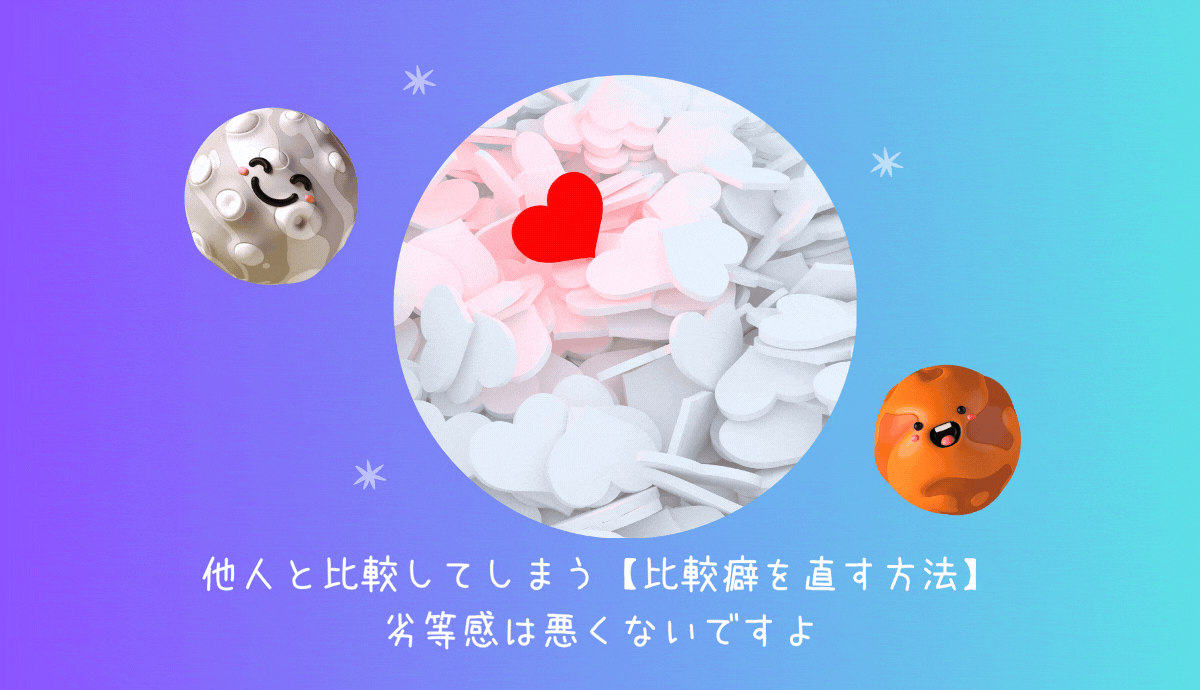

コメント