自分らしく生きれてるんだろうか……そう思ったこと、ありませんか?
わたし、あります。めちゃくちゃありました。
他人と比較して落ち込んで、周囲の評価が気になって、気づいたら『やりたいこと』より『どう見られるか』ばっかり考えてる自分がいて。
で、いつの間にか、呼吸はしてるけど、なんかずっと息苦しい。みたいな状態に突入してたんですよ。
いろんなことを経験して、試行錯誤して、わたしが辿り着いた結論はこれでした。
シンプルだけど、これが意外と難しい。だって“自分を大切にする”って、社会に出るとめちゃくちゃハードモードじゃないですか?

もっと自分らしく生きたい。
それは、かつてのわたしが心から思っていたことです。
このブログでは、自分らしく生きることが難しい理由と、その原因をどうやって乗り越えていくかについて、笑いも交えつつ本気でまとめてみました。
ちょっとでも、『あ、わかる』とか『それな!』って思ってもらえたらうれしいです。自分らしく生きるためのヒント、きっとあります。
自分らしさが見えづらい理由


私たちが『自分らしさ』を感じられなくなる理由は、いろーんな要因がそれはもう、複雑にふくざつーに絡み合っているような気がします。
例えば↓以下の5つ。
- 自己理解の不足
- 周囲の影響に敏感になること
- 過去の経験とその影響
- 学生時代の同調圧力
- 自己肯定感のなさが招く影響
①『自己理解が足りてない』って、よく言われるけど――



わたしって何がしたいの?何のために働いてるんだっけ?
そんな漠然とした不満が、ふわ〜っと湧いてくるんですよね。しかも年齢を重ねるほど、静かに、でも確実に。
で、自分の軸があいまいなまま、他人の意見や期待に流されると、いつの間にか“わたしの人生”が“周囲の評価を満たすための人生”になってるという恐怖。



わたしこれやりたくてやってるわけじゃないんだけどな….
って思いながら、笑顔で働いてる、みたいな。あるあるですよね。
ちなみに、ここでカギになるのがアドラー心理学の“課題の分離”。
『これはわたしの問題?それともあの人の問題?』ってちゃんと線引きできるかどうかで、自分を保てるかどうかが変わってきます。
最初は『なんか冷たい人って思われそう…』って思うかもしれないけど、それ、ただの“自分の心の平穏を守る技術”です。誤解されてもいい、自分を見失うよりマシ。


②周囲の影響に敏感になること
ここで登場するのが、“他人センサー”が超高性能な人たち。『他人にどう思われるか』っていう評価アンテナが、もはやWi-Fiより広範囲に届いてるレベル。
もう、宇宙。
特に日本って、“空気読む能力”が礼儀として神格化されてるじゃないですか。気を遣える=人間力高い、みたいな。
でも、空気ばっか読んでたら、自分の声がどっか行っちゃうんですよね。
本当は『それ違うと思うな』って思ってるのに、『あー…はい…なるほどですね〜』って返してるうちに、個性はフェードアウト。



自己表現?どこ行った?
まじめな人ほど、“期待に応える努力”を重ねて、気がついたら『いい人なんだけど、何考えてるか分からない人』になってたりするんですよ。ほんと、皮肉。
気遣いは美徳だけど、やりすぎるとただの自己消耗。空気を読んでも、自分まで薄まらないようにしたいものです。
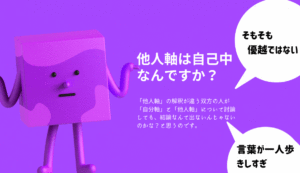
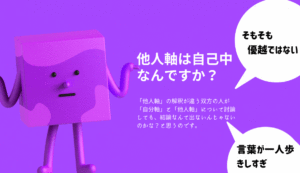
③過去の経験とその影響
ここで登場するのが、“過去のわたしが今のわたしに呪いをかけてくる現象”。
トラウマとか、失敗経験とか、そういうやつです。
たとえば、昔大失敗したプレゼンの記憶が蘇ってきて、



うっ……無理……人前で話すとか一生やりたくない……
ってなるとか。
過去の“イヤな記憶”って、心に重しみたいに居座るんですよね。で、それがじわじわ効いてきて、



わたしには無理!
って思い込みに進化。
気づけば、自己表現どころか自己否定スパイラルに突入。
しかもやっかいなのが、こういうネガティブ感情って、勝手に再生される。頼んでないのに、心の中の思い出シアターが『失敗シーン特集』を上映してくる。ほんと余計なサービス。
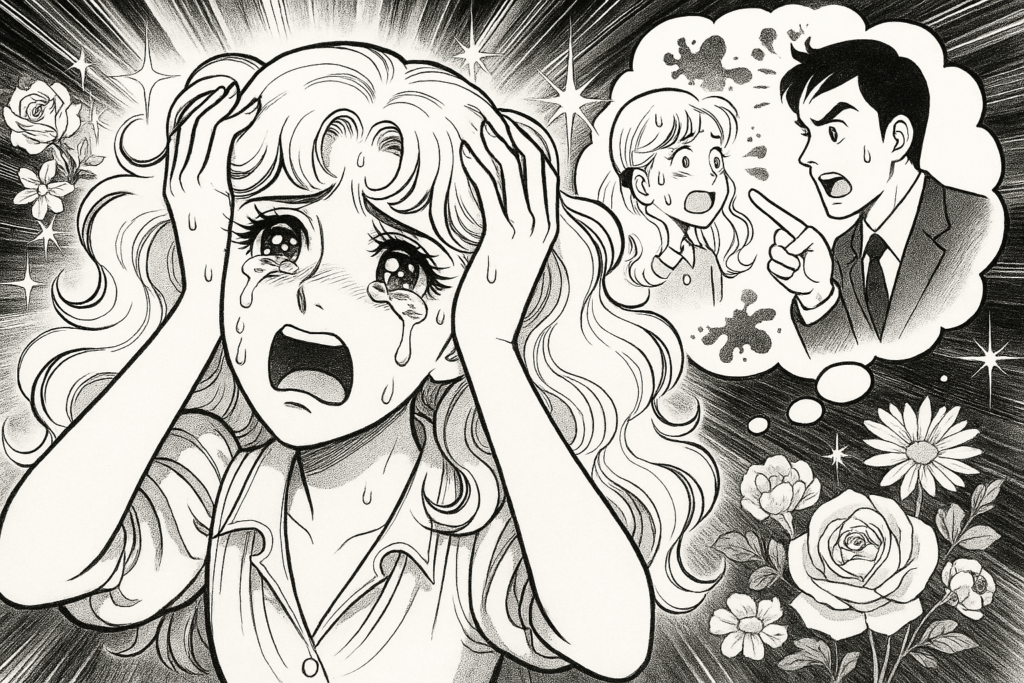
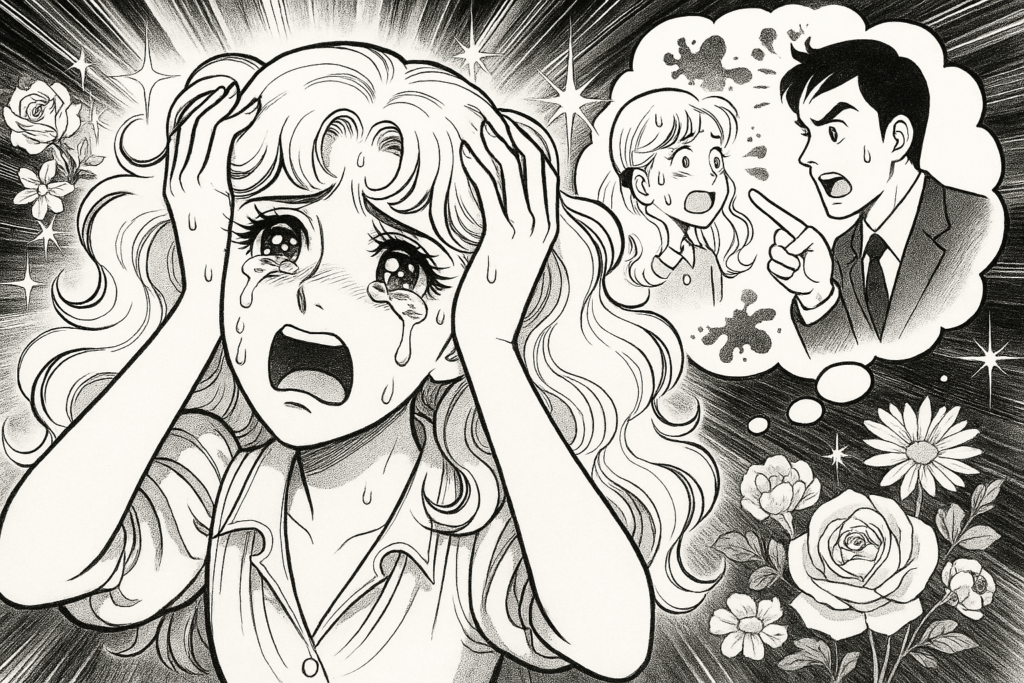
ここで大事なのが、“過去の自分”と“今の自分”は、別人だということ。
子どもの頃なら、周りの大人が外からアプローチかけるのも重要。でも大人になったら、自分で『その重し、もういらんかも』と気づいて、そっと下ろすことも必要。



子どもへの関わり方は、“見守る”であって“制限する”ではありません。そこは間違えないように。行動制限=別の重しです。
④学生時代の同調圧力
学生時代の小中高生って『同調圧力』顕著ですよねー。
友人関係の中で、ちょっと違う意見や行動をしてしまう恐怖から自分を押し殺すこともある。
周囲に合わせることで安心感を得られるという利点もあるけれど、真の自分からは、ますます離れますね。


⑤自己肯定感のなさが招く影響※わたしを認めて!でも無理!の無限ループ
そして最後にして最強の敵、自己肯定感の低さ。
自分に価値があると思えないと、何かにつけて他人と比較してしまうんですよね。



わたしなんてまだまだ。あの人はすごいのに、自分はダメだ。
の三点セット、毎日唱えてる人、いませんか?
この状態になると、もはや自分の“よさ”とか“強み”なんて見えない。自分の評価基準が全部『他人がどう思うか』になるから、やりたいことよりも、“嫌われないこと”を優先しちゃう。
結果、自分の個性はそっと押し入れにしまい込まれて、出番なし。
状態に突入します。
しかもこのループ、抜け出しにくいのが本当に厄介。
『自分を好きになれない→自己表現できない→評価が得られない→もっと嫌いになる』という完全なる負のスパイラル。
自己肯定感って、いきなり100点取らなくてもいいんです。少しずつ『今の自分でいいかも』って思える時間を増やしていくことが、“自分らしさ”を取り戻す第一歩になります。
周囲の目を気にしがち


周囲の目が気になる。
まぁ、普通ですよね?
ただ、この『周囲の目』が自己表現や自分本来の生き方の妨害になること、あるじゃないですか。
ここでは、その理由や影響について3つを考えてみたいと思います。
- 周囲の評価に左右される自分
- ついつい比較してしまう
- 自分に合った環境を選ぶ
①周囲の評価に左右される自分
社会生活してると、他人の目ってどうしても気になりますよね。
特に、友達・同僚・家族――このあたりの“身内ジャッジ陣”の視線って、なぜか刺さる。やたら刺さる。
『こう思われたい』『期待に応えなきゃ』って思って、本音を封印 → 笑顔で対応 → 謎の疲労感。のコンボが完成します。
気づけば、“本当の自分”を出すヒマもなく、気がついたら“他人にウケのいい自分”だけが前に出てるというホラー現象。
で、それを長く続けるとどうなるかっていうと――ストレス溜まる。愚痴出る。自分にモヤる。の三重苦。
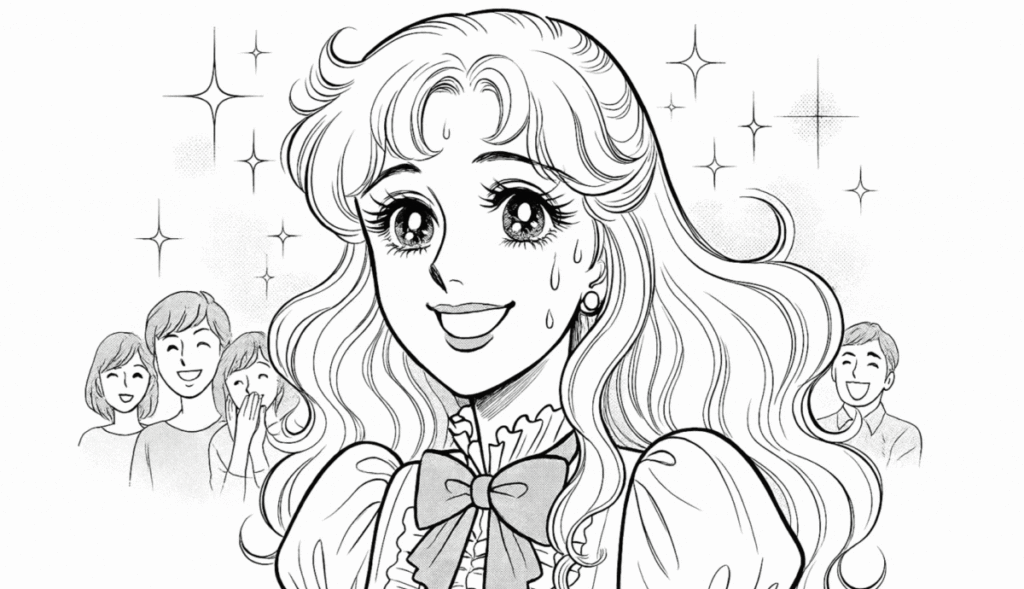
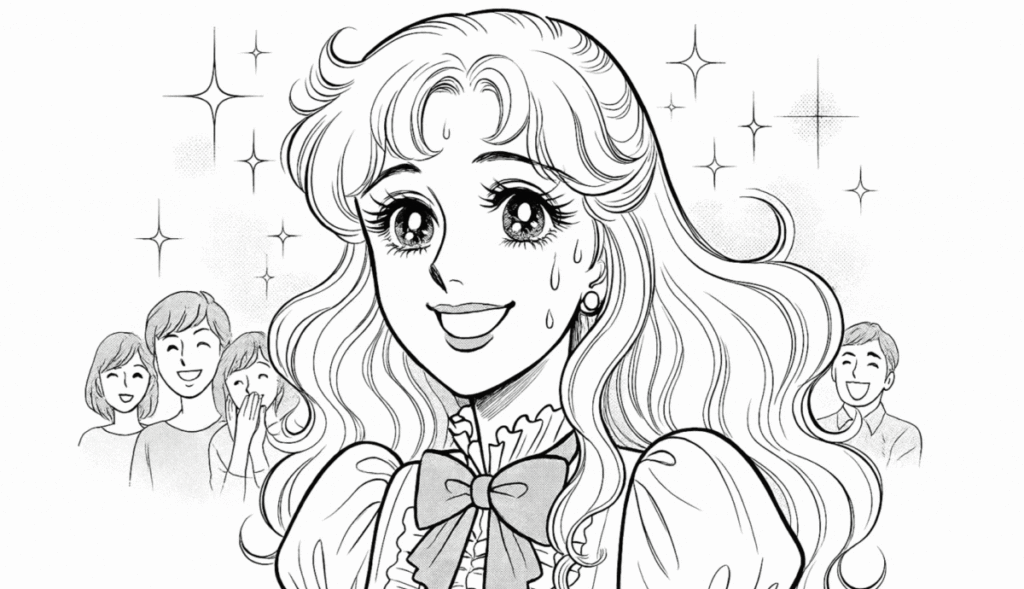
演じ続けるの、疲れるんですよ。舞台じゃないんだから。
他人にどう見られるかばっかり気にしてたら、自分という主役が消えます。
『好かれる』より『自分でいられる』ことの方が、長期的にはコスパも幸福度もいいんです、たぶん。
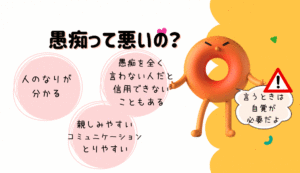
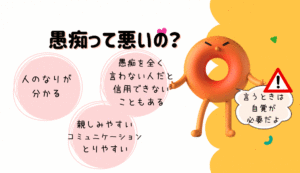
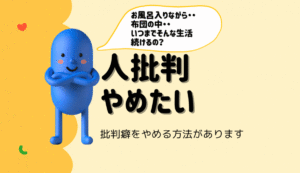
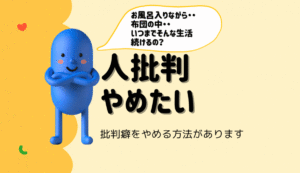
自己を犠牲にするリスク※Yesと言い続けたら、Noが言えなくなった件



うん、行くよ〜!全然大丈夫!わたしがやっておくね!
……え?心の声?



いや、むしろ行きたくないし、大丈夫じゃないし、やりたくない,,,
みたいな。
他人の目を気にしすぎると、本音を押し殺して、“いい人モード”で自分を消費していくんですよね。
例えば、気乗りしない集まりに参加して、笑顔でおしゃべりしながら、心の中では『帰りたい……』とか思ってたり。
で、最初は『まぁ仕方ないよね』って思えるんだけど、何度もそれが続くと、だんだん疲れてくる。気づけば、自己評価がマイナスに突入。
『なんであのとき断れなかったんだろ…』→『わたしってダメなやつかも…』→『あーあ、もう無理』
このループ、怖いです。
周囲に合わせることでその場は丸く収まるかもしれないけど、代わりに自分の気持ちは削られてる。
つまり、“好かれたい”の裏で“自分が自分を嫌いになる”という悲劇が進行中ってこと。
無理な我慢は、相手のためにも、自分のためにもなりません。
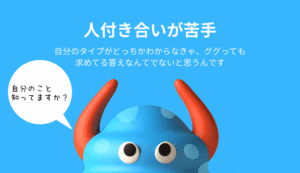
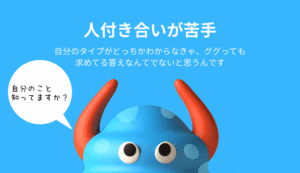
②ついつい比較してしまう※他人のキラキラ投稿に撃沈する日々
他人と比べない、って難しいですよね。
特にSNSの時代、あっちもこっちも『リア充爆発中!』みたいな投稿がゴロゴロ流れてきます。
- オシャレなカフェ
- キラキラの休日
- 順調なキャリアと育児と副業と美肌と腹筋(なぜ全部ある)
で、こっちはというと――『朝から寝ぐせすごい』『冷蔵庫にあるの納豆だけ』『やる気が迷子』みたいな日常。
比較しちゃいますか?落ち込みますか?



あの人みたいになりたい。
でもその“なりたい”って、本当に自分が望んでるものなんでしょうか?
気づけば、“本来の自分”じゃなくて“理想っぽい誰か”を追いかけてしまって、結果、自己評価は地面にめり込み、周囲の期待に沿うことが最優先になっていく。
そして、“わたし、何やってんだろ…”という謎のモードに突入。
他人の人生は他人のステージでやってる別ゲーム。見えてるのは“ハイライト”であって、“編集されてない現実”じゃないってこと、忘れがちです。
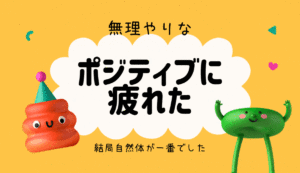
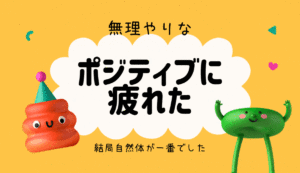
自分の価値に気づくために
周囲の目が気になる。評価が気になる。比べちゃう。
でもそれで“自分らしさ”が見えなくなってるなら、一回ストップ。
誰が何と言おうと、自分の価値ってちゃんとあるんですよ。気づいてないだけ。忘れてるだけ。意識が“他人チャンネル”に合わせっぱなしなだけ。
だからまずは、自分の価値観を再スキャン。
- 何を大切にしてるのか?
- 何を望んでるのか?
この2つを見直すだけでも、他人に振り回される時間がガクッと減ります。
たとえば、みんなが『海外かぶれ最高!』って言ってても、自分は『銭湯と畳が落ち着く』なら、それでOK。それがあなたの軸。
周囲の期待に100%応える人生より、『わたし、この生き方けっこう好きかも』って思える人生のほうが、断然しんどくないし、満足度高いです。
自分を取り戻す第一歩は、自分の“好き”や“こうありたい”をちゃんと尊重してあげること。他人の声より、自分の本音にボリューム上げていきましょ。
③自分に合った環境を選ぶ※合わない靴を履き続けたら、そりゃ足痛める
『周囲の目を気にしないためには、自分に合った環境を選ぶことが大事』
――って、よく言われるけど、これほんと真理です。
- ここで本音言ったらめんどくさくなりそう…
- ちょっとでも失敗したら“期待外れ”って言われそう…
そんな状態じゃ、自分の感情なんてそりゃもう後回しになります。
逆に、ポジティブで応援してくれる人が周りにいると、



あ、ここなら自分の気持ち大事にしてもいいんだな。
って思えて、呼吸も楽になる。
つまり――“環境選び”って、自分を守る最初の防御策であり、最大のライフハック。
合わない靴を無理やり履き続けるより、最初からちょっとゆるめの、でも自分にしっくりくる靴を選んだ方が、歩きやすいに決まってるんです。



環境って、自分らしさの“土台”です。自分を出せる場所、探しましょ。作りましょ。
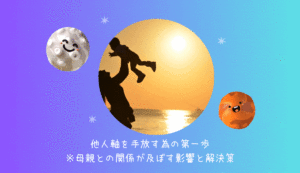
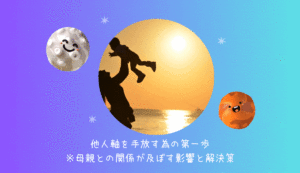
自己肯定感がない
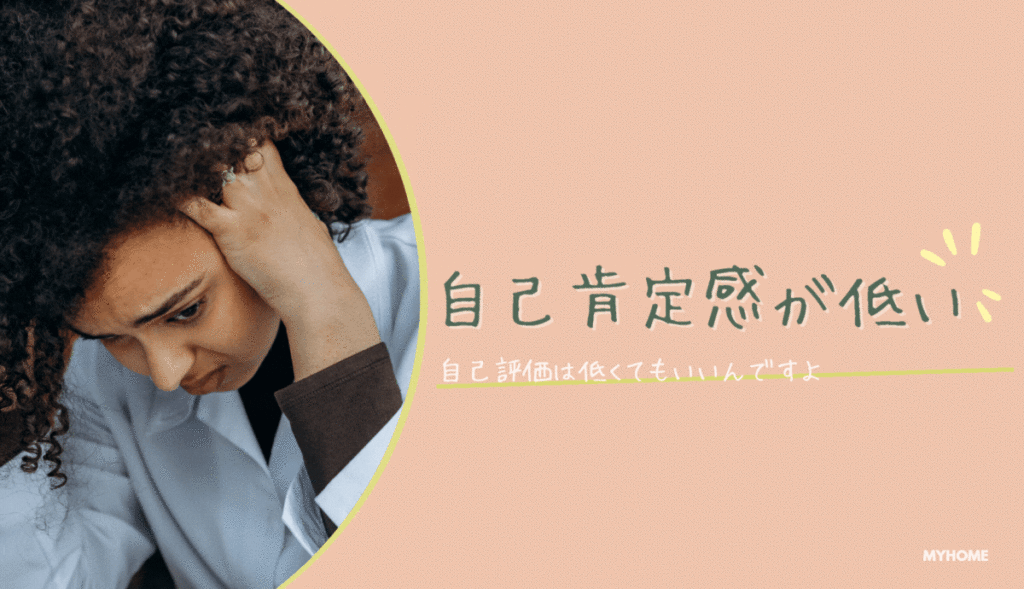
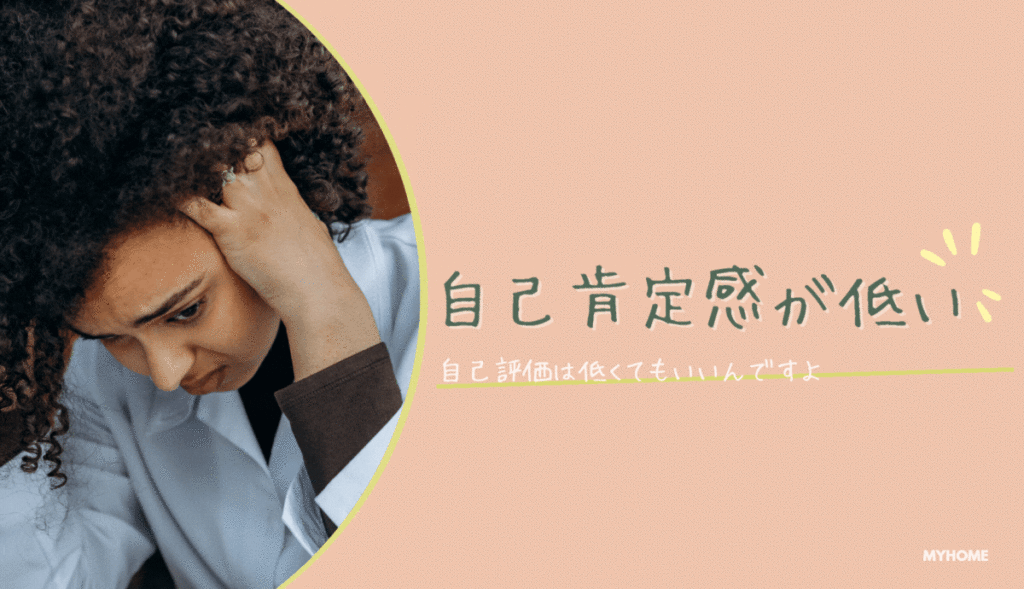
そもそも自己肯定感って何かというと――ざっくり言えば、『自分って存在してていいよね』って思える感覚のことです。
つまり、『こんな自分でもまぁアリかも』と思えるかどうか。
でもこれが、ない人はない。見事にスッカラカン。そしてそれが、思考や行動にじわじわ影響してきます。
- すぐ自分を責める
- 他人と比べてヘコむ
- 意見を言えない
- 人間関係で迷子になる
などなど、『あるある』とうなずく現象が日常に散りばめられていきます。
ということでここからは、自己肯定感がないとどうなるのか?その現れ方と日常生活での影響を、4つに分けて探ってみようと思います。
- 自己肯定感とは何か?
- 低い自己肯定感の特徴
- 親密な人間関係の役割
- 自己肯定感がない状態の改善方法
①自己肯定感とは何か?
自己肯定感とは、自分の存在を受け入れ、自分自身を好きだと感じることができる状態のことです。
良い面だけでなく、弱点や欠点も含めて自分を認めること。
自己肯定感を持つと、自分の意見や感情を素直に堂々と伝えられるようになるので、自分自身を十分に表現できる生き方ができるようになります。つまりは、充実感を味わえる。
②自己肯定感がない人の特徴
自己肯定感がないと、けっこうわかりやすい“あるある症状”が出ます。
以下の症状、いくつ当てはまりますか?
自己批判がすぐ発動する
ちょっとミスしただけで、即・自己ダメ出し。『はぁ〜またやっちゃった……わたしってほんとダメ』って、まだ誰も何も言ってないのに自分で先回りで叱るやつ。もはや心の中に“厳しめの上司”が住んでるレベル。
結果、チャレンジのたびに『いや、無理かも…』が自動で再生されて、どんどん行動にブレーキがかかるという残念スパイラルに。
比較グセが止まらない
他人と自分を比べるのが、ほぼ日課。特にSNSの中にいると、もれなく『他人のハイライト映像』と『自分の未編集映像』を比較して撃沈するという地獄モードに。
- あの人は結婚して子どもいて仕事して海外行って美肌で…
- で、わたしは……えーと、冷凍うどん食べました
みたいな謎の敗北感。
他人の目=人生の指標になってる



これ言ったら嫌われるかも…変に思われないかな…
そんな思考が先に立って、自分の本音がスッと引っ込む。
結果、『いい人なんだけど何考えてるか分からない人』になって、自分も他人もモヤモヤするというコミュニケーション迷子状態へ。
…という感じで、自己肯定感が低いと“自分を生きる難易度”が爆上がりします。でも逆に言えば、『自分を責めすぎてないか?』って気づければ、それがもう一歩目です。
③親密な人間関係の役割
自己肯定感って、ひとりで勝手にムクムク育つもんじゃ……なくはないけど、めっちゃ育てにくい。
やっぱり、



大丈夫だよ。
って受け止めてくれる誰かがそばにいると、ぐんと育ちやすいんです。
たとえば、何か失敗したとき。
『だから言ったじゃん』って言われるのと、『まぁそういうこともあるよね〜』って笑ってくれるのとでは、心の回復スピードが天と地。
こういう『そのままの自分を受け入れてもらえた』っていう体験。それが自己肯定感の栄養になるんですよね。即吸収、しかも無添加で副作用ゼロ。
家族でも、友だちでも、先生でもいい。誰か一人でも、『そのまんまのあなたでOK』って空気を出してくれる人がいると、『そっか、自分ってこれでいいんだ』って信じる力が少しずつ育っていく。
反対に、何言っても『気にしすぎじゃない?』とか『そういうのめんどくさい』って返され続けると、感情出すのがだんだん怖くなって、心に自動ドアじゃなくてシャッターがつきます。防音付きで。
最近は、その“受け止めてもらえる場所”がなかなか見つからなくて、自己肯定感が育つ土壌がちょっと痩せ気味になってるような気もしてます。
でもね、たった一人でもいい。本音を出しても引かれない相手がいると、人生の迷子率がぐっと下がる。
受容って、心のGPSみたいなもんです。
安心して『わたしはここにいる』って言えるようになる。それだけで、もうすでに前進してるんです。
自己肯定感がない状態の改善方法
まずは、、、
- 自分の思考の癖を見つめ直すこと
- 自分を責めるのを止めること
- そのままでいいと思うこと、思い切ること
がカギだと思います。そこからがスタートです。



自己評価は低くてもいいんです。自己評価の低い、自己肯定感のある人間です、でも最初はいいじゃないですか。
そのうち自己評価も高くなります。わたしは、自己評価、上げてもいいかなと思い始めました。
目標がないこと


自分らしく生きるには、目標があるとやっぱり強い。…とはいえ、その『目標』が見つからないのが現実あるある。
なんかこう、『人生の目的』とか言われると重たいし、すぐに答え出せる人のほうが少数派です。
ということで、ここでは『なんで目標が見つからないのか?』その原因と影響を5つに分けて、考えてみようと思います。
- 目標の重要性
- 教育の狭間
- 自己探求の機会不足
- 心理的なハードル
- 目標発見のステップ
①目標の重要性
『目標って、そんなに大事?』って思うかもしれないけど、あるのとないのとでは、人生の“うっかり迷子率”が全然違うんですよ。
目標があると、なんというか――『今日なんとなく頑張ってる理由』が発生する。
たとえば、『英語しゃべれるようになりたい』とか、『副業で稼ぎたい』とか、何かしら“この先こうなりたい自分”があると、日々の努力も『ま、意味あるしな』って思えてくるんです。
目標って、人生というよく霧が出る道に、ちょっとだけ置かれた標識みたいなもの。それがあるだけで、『あ、たぶんこっちで合ってる…はず!』って前に進める。
逆に目標がゼロだと、『なんか今日も忙しかったけど、結局何やってたっけ…?』という“空回り系ループ”に突入しやすい。
なので、大きな目標じゃなくていいから、『ちょっとこれやってみたいかも』くらいのライトなものでOK。
目標=人生のナビアプリです。オンにしておくと、ちょっと安心できます。
②教育の狭間※テストの点が人生の正解じゃなかった件
日本の教育って、基本『テストで点を取ること』がゴール設定されがちですよね。で、それなりに頑張って点を取って、いい学校行って、いい会社入って――



……で、わたし何がしたかったんだっけ?
ってなる人、少なくないはず。
勉強=努力って構図は間違ってないし、否定はしないけど、『将来どう生きたいか』っていう“根っこの部分”にアプローチされないまま、枝葉ばっかり鍛えられるのがこの教育のクセ。
それはそれで有能にはなる。けど、自分が何を大事にしたいかっていう軸が育たないと、社会に出たときにポキッと折れやすい。ステータスはあるのに、なぜか虚しい、みたいな。
これってたぶん、西洋的な教育アプローチの特徴でもあると思うんですよね。『論理的に考える』『答えを出す』はすごく大事だけど、それだけだと“人生の納得”がどっか行っちゃう。
だからこそ、もっと東洋的というか、『自分の内側にある価値観』から出発する教育が今こそ必要なんじゃないかな、と。
東洋的な教育って、物事の“意味”とか“本質”に向き合う力を育ててくれる。いわば、“根っこを育てる教育”。
で、その根っこさえしっかりしてれば、社会に出ても折れにくいし、『なんでこの仕事してんだっけ?』みたいな迷子になりにくい。
だからこそ、『誰かが気づく』ことがすごく大事。
たぶん、この記事をここまで読んでる“あなた”みたいな人が、その誰かかもしれない。
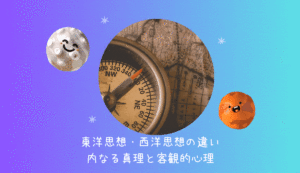
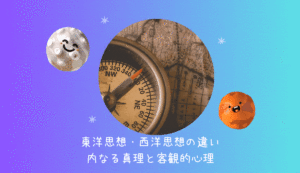
③自己探求の機会不足※自分って何?って思う暇もない現代
自己理解って、じっくり自分を観察したり、考えたりする時間が必要なんですが――
今の時代、そんなヒマある!?
子どもですら、スケジュールびっちり。塾、習い事、宿題、タブレット学習、たまに英検。
気づけば、



自分って何が好きなんだろう?
って立ち止まるタイミングがゼロ。
大人ももちろん忙しい。『今日もバタバタで1日終わったわ〜』って言ってるうちに、1年終わる。そりゃ目標も見失いますよ。というか、最初から“探す時間”すら無かった説。
で、自己探求をスルーしたまま過ごしてると、



これ、なんとなく褒められるからやってるだけかも…
みたいな、他人の期待ベースの人生に突入。
『自分に本当に必要なものは?』という問いかけがどんどん遠ざかっていくわけです。
ここで大事なのは、『勝つため』じゃなくて『納得するため』に行動すること。
競争のための目標って、だいたい疲れるし、途中で『…で、これってわたしの望みだったっけ?』ってなる。
だからこそ、子どもであれ大人であれ、“自分のペースで立ち止まる時間”って、実は超重要。
その時間が、ちゃんと“自分に必要なもの”と向き合うチャンスになるからです。
④心理的なハードルへのアプローチ
目標を立てようとしても、なんかこう…もやもやする。やる前から『無理かも』『失敗しそう』って気持ちがじわじわ湧いてくる――それ、めちゃくちゃ普通です。
だって、失敗ってちょっと怖いし、過去にうまくいかなかった経験があると、



わたし、またやらかすんじゃ…
って思考ループに突入するのが人間というもの。
しかも、これが厄介なのは、『そもそも目標立てるのが億劫になる』ってとこなんですよ。



また途中で折れたら嫌だな…どうせ達成できないし。
って。やる気ごとフェードアウト。
でも実はそれ、目標の立て方や向き合い方をちょっと見直すチャンスだったりします。
- 今の目標、本当に自分に合ってる?
- “無理だと思った”ことって、本当に悪いこと?
- じゃあ、少し軌道修正してみたら?新しく設定してみたら?
こういう対話って、子どもとの間でもめちゃくちゃ大事だし、大人だって、誰かと話すことで『それでよくない?』ってフッと楽になること、ありますよね。
ただ問題は、親や周囲の大人たちも『どうアプローチしたらいいかわからない』ってこと。
特に“成績重視”文化だと、失敗=してはいけないことになりがちで、いつの間にか『間違えるのは恥』みたいな空気が育ってしまう。
それが結局、『挑戦しない方が安全』という思考をつくっていく。
妙な競争社会って、ほんとありますよね。『そこ競うとこ?』って思わず言いたくなるような、微妙にズレた争い。
漢字テストの点数で人格が決まるとか、席順でテンションが上下するとか。でも人生の目標って、そんな一発勝負みたいなもんじゃないですよね。
そもそも目標って、途中で『やっぱ違ったかも』って思ったら変えていいし、『もうちょっと自分に合う形に調整しようかな』って微修正していくことにも、ちゃんと意味があるんです。
“達成すること”だけが偉いわけじゃなくて、そのプロセスで『自分にとっての正解』を探し続けることにこそ、本当の価値があるんじゃないかなと。
⑤目標発見のステップ※いきなり人生のゴール決めようとするから迷うんです
目標を見つけよう!って言われると、



え?人生の…?とかですか?
って肩に力入りがちだけど、そんな壮大なテーマじゃなくて大丈夫。
まずは自分が“なんか気になる”とか“ちょっとワクワクする”ことを拾い集めるところから始めましょ。
- どんなときにテンション上がる?
- 誰かに語りすぎて引かれた話題ある?
- 気づけば調べちゃう分野って何?
こういう“ちょっとした好奇心”が、実は目標のタネです。
あとは、それに関連するスキルや行動を一つ決めてみて、『それ、ちょっとやってみようかな』くらいのノリで始めてOK。
しかも、いきなり大目標とか掲げなくてもいいんです。むしろ“小さな成功”を積み重ねるほうが、達成感も自信も育ちやすい。
たとえば、『毎日10分だけやってみる』とか、『今週1回だけ挑戦してみる』とか、そのくらいのステップで十分。
重要なのは、“自分のペースで進むこと”。
気がついたら『あれ?ちょっと前より自分らしいかも』って思える日が、ちゃんとやってきます。
安定を求めすぎること
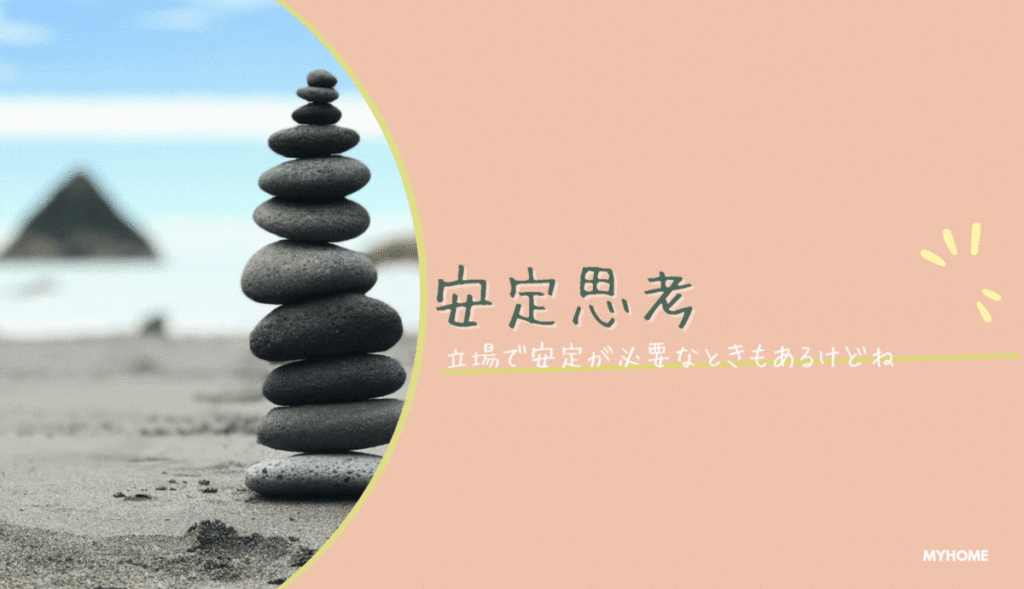
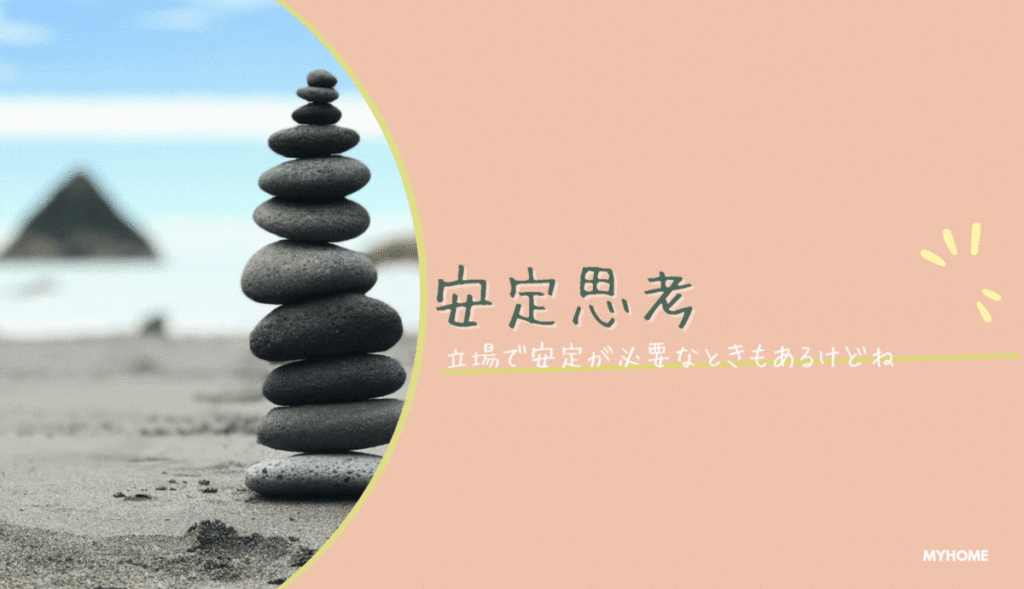
現代って、“安定”を求めるのがめちゃくちゃ自然な世の中なんですよね。正社員、住宅ローン、将来のための貯金、安定収入、保険、年金(←ほんとに出る?)。
で、それ自体は全然悪くない。むしろ大事。『安定志向はダメ!』なんて雑なこと、わたしも言いたくありません。
ただ――安定を求めすぎると、“動かない自分”を正当化し続けてしまうことがある。
『今のままでいいや』っていう快適ゾーンが心地よすぎて、気がついたら10年たってた、みたいなことってありませんか?
特に変化が怖いときって、チャレンジより現状維持を選びたくなる。でも、その“何もしない”が、じわじわと自分らしさを削っていく原因にもなったりします。
例えるなら、ぬるま湯のお風呂。最初は『気持ちい〜』けど、だんだんのぼせてきて、でも外に出るの寒いから出られない、みたいな状態。
本当に大切なのは、『安定=止まること』じゃなくて、『自分が納得して進める場所を選ぶこと』だと思うんです。
『動かないことが安定』と思い込むと、変化する勇気がどんどん削がれていく。でも、小さくてもいいから、自分の意思で選ぶことをやめないほうが、結果的には心が落ち着く気がします。
まとめ
『自分らしく生きたい』って、簡単に言うけど、実際はけっこう難しい世の中です。
- 内面をゆっくり見つめる余裕もない
- 他人の目は気になる
- 自信は揺らぐ
- 目標?なにそれ?状態
- 変化が怖くて足がすくむ
つまり――悩みやすくできてる社会構造なんですよ、これ。
わたし自身も、いろんな本を読んだり、悩んだり、遠回りしたりしながら、ようやく『これが自分の人生かな』って思えるところに辿り着いてきた気がします。
でも、ふと思うんですよ。



これ、小さいころから学べたらもっとラクだったんじゃ…?
- 自分の感情を言葉にすること
- 他人と違うことを怖がらないこと
- “正しさ”よりも“納得できること”を選ぶこと
こういうことを、もっと早い段階で知れていたら――もっと『自分らしい時間』を長く生きられたかもしれない。
もし今、自分がそれに気づけたのなら。
そして誰かに伝えられる立場にいるのなら。
そこからがスタートです。
小さな一歩が、未来の選択肢を増やします。
自分の可能性に早く気づけた人は、そのぶん人生を深く味わえる。それって、社会にも、自分にも、ちゃんとプラスになるはずです。



コメント