カントの定言命法と仮言命法をわかりやすく解説してみます。
カントと言えば、人は誰でも『守らなければならない、自ら立てた道徳的な法則に従って、命令を受けたわけでもなく、見返りを求めることでもなく、ただそれが義務だから、という理由で行えることこそ人としてあるべき姿、意志の自立を自由』とした哲学者。
例えば、

困っている人は助けるべきだ!!
とか。
他人に優しくすることは道徳的行為かもしれませんが、自分が優しくされたいからそうしているともいえる。『仮言命法』にもとづく行為は、つまるところ自分の利益を優先する行為であり真の道徳的行為とはなり得ないというのがカントの考え方。
超絶善人だからこその教え。



わかるけど、あなたにしかできないかも。
話は逸れますが、『他人に優しくされたいのなら、まずは自分に優しくありなさい』がわたしの思想です。
このブログでは、まずカント倫理を詳しく解説し、その後ヘーゲルの理論と比較しています。そして、信用を基盤とすることで道徳的な行為が自然に生まれる社会を築くという発想こそが、より実践的な倫理として重要なのではないか、という私の個人的考えをまとめてみました。
カントの倫理観
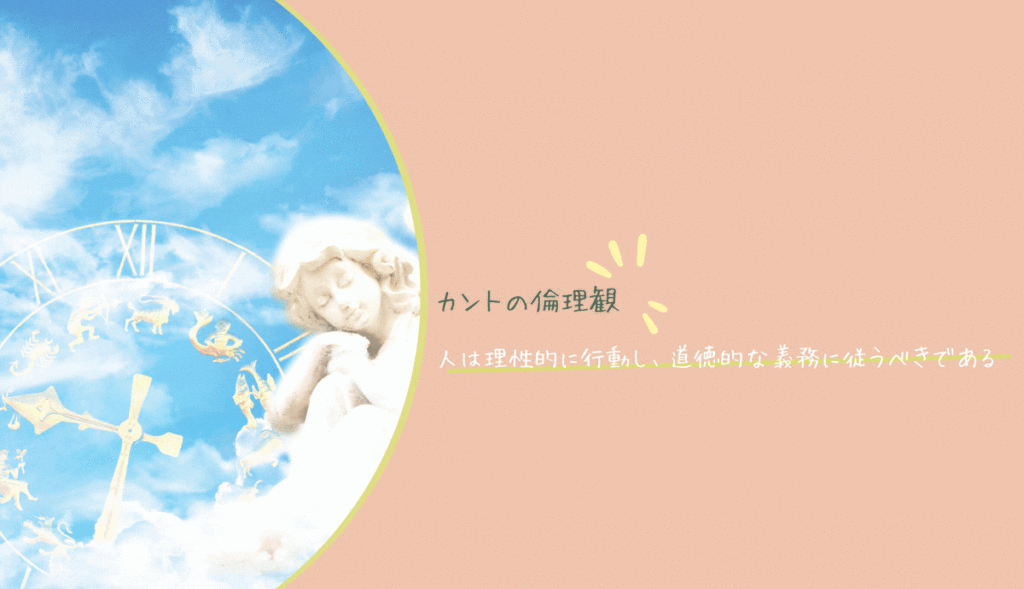
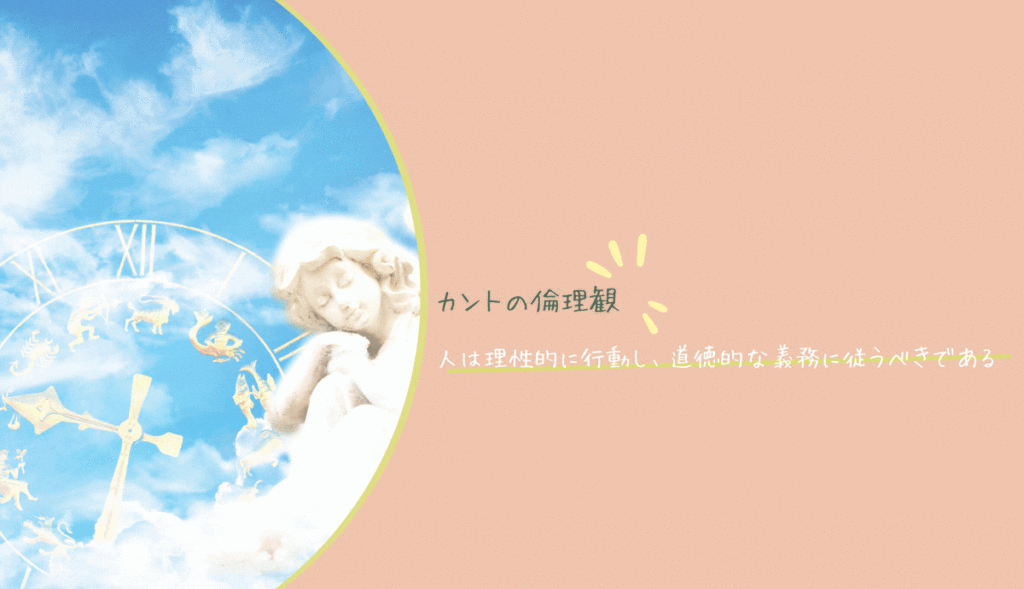
カントは『人は理性的に行動し、道徳的な義務に従うべきである』と主張。これを『定言命法』と呼び、『他人を手段ではなく、目的として扱うべき』 という考えを打ち立ててます。
さらに、黄金律のような倫理観『他人にしてほしいことを(正義的に正しいと考えられるなら)、まず自分が他人にするべき』とも共鳴する部分がある。
この考え方には現実とのズレがありますよね。
カントの倫理観が成立するためには、すべての人が理性的に道徳的な行動をとることが前提となる。でも、実際にはそうでないケースも多くて、カントの理論が必ずしも現実に適用できるわけじゃない。
また、カントの倫理は、人間の現実での欲求とか状況を完無視してるでしょ? という疑問も生まれる。
利他主義が極端になると自己犠牲になりすぎる
自分が満たされていないのに、他人を満たそうとするのは矛盾しない?
結局、自分が苦しんでいるときに他人を助けるのは、他人に負担をかけることになることもあるよね?
カントの仮言命法と定言命法
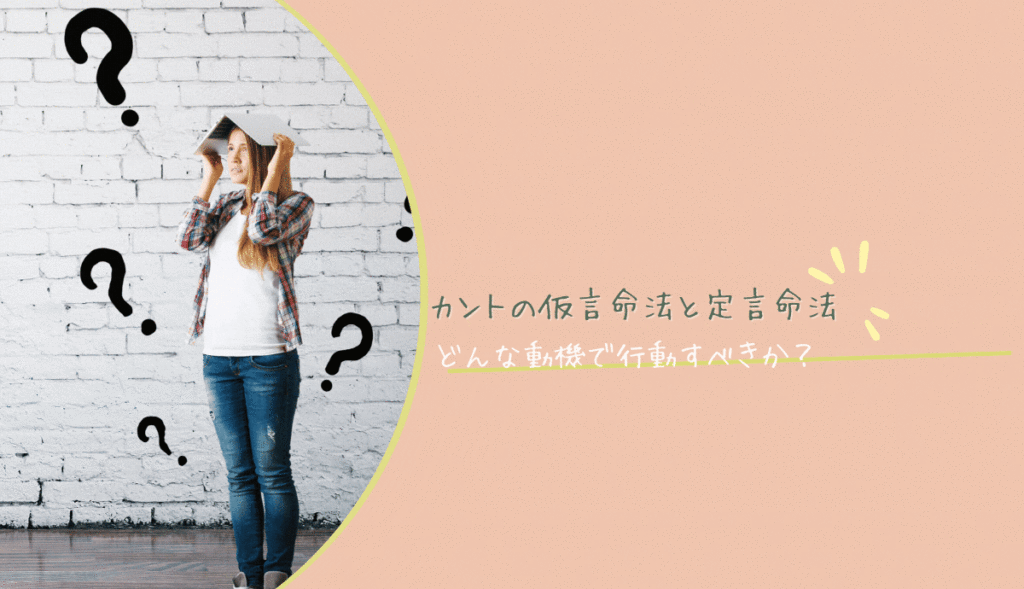
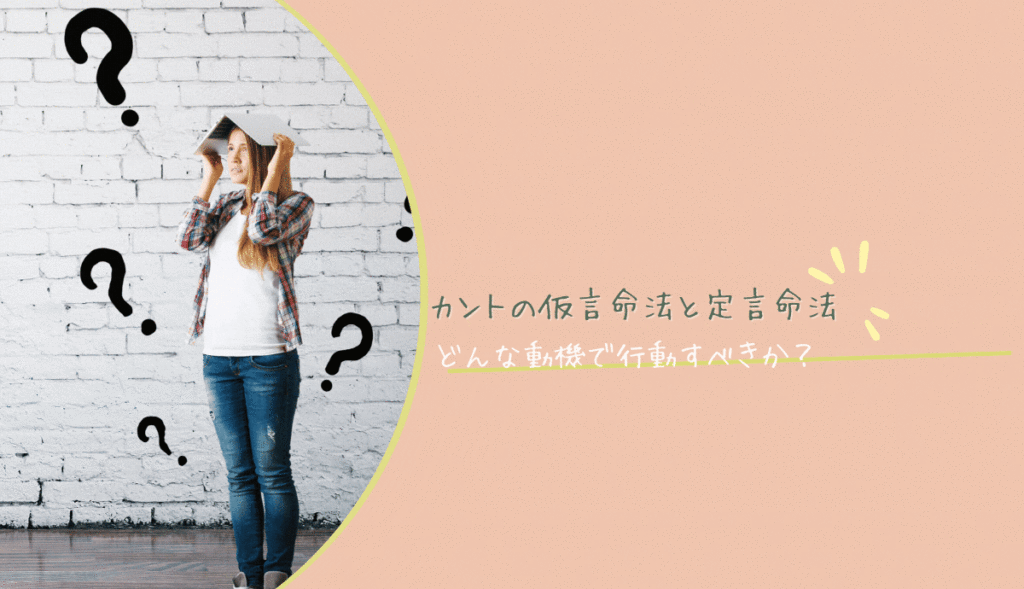
では、どんな動機で行動したらいい?
カントは『助けるのが当然』という義務として行動することこそが、道徳的だとしました。これは『仮言命法』と反対の『定言命法』という考え方。
仮言命法:『友達が探し物をしている、ここで助けたら自分をよく思ってくれるだろうから、助けよう』
定言命法:『友達が探し物をしている、一緒に探そう』
仮言命法は『困っている友達を助けてよく思われたい』という欲求を伴っているのに対して、定言命法は『友達を助けることに理由はいらない』と当然の行動としている。



『他の誰からの命令を受けたわけでもなく、また見返りを求めることでもなく、ただそうあるべきだと自ら行うことこそが道徳的であり、人としてあるべき姿だ』というのが、カントの導き出した『道徳』の結論。それが人格にもなる、と言うね。
- 仮言命法
- 定言命法
①仮言命法
仮言命法とは、『もし○○したいなら、△△せよ』という条件付きの命令のこと。
例えば、
- 『友達が探し物をしている。ここで助けたら自分をよく思ってくれるだろうから、助けよう』
- 『良い評価を得たいなら、誠実に行動しよう』
仮言命法は、何かしらの目的や欲求を伴って行動することを意味します。つまり、見返りや個人的な利益を期待する形で道徳的行動をとるという考え方。
②定言命法
定言命法とは、『どんな状況であっても、無条件にそうすべき』 という命令。
例えば、
- 『友達が探し物をしている。一緒に探そう』(理由は必要ない)
- 『探している場所が分からないのに、適当なことを言ってはいけない』(利益があっても)
友達が『どこにあるか知らない?』と聞いてきたとき、『一緒に探すのが面倒』なので、適当に『机の中じゃない?』と答えることはNG
仮言命法は『困っている友達を助けてよく思われたい』とか、『(探すのを手伝いたくないという)本音を隠せる』という動機を伴うのに対して、定言命法は『友達を助けることに理由はいらない』と当然の行動としてます。
『リンゴをどうする?』カント倫理の限界
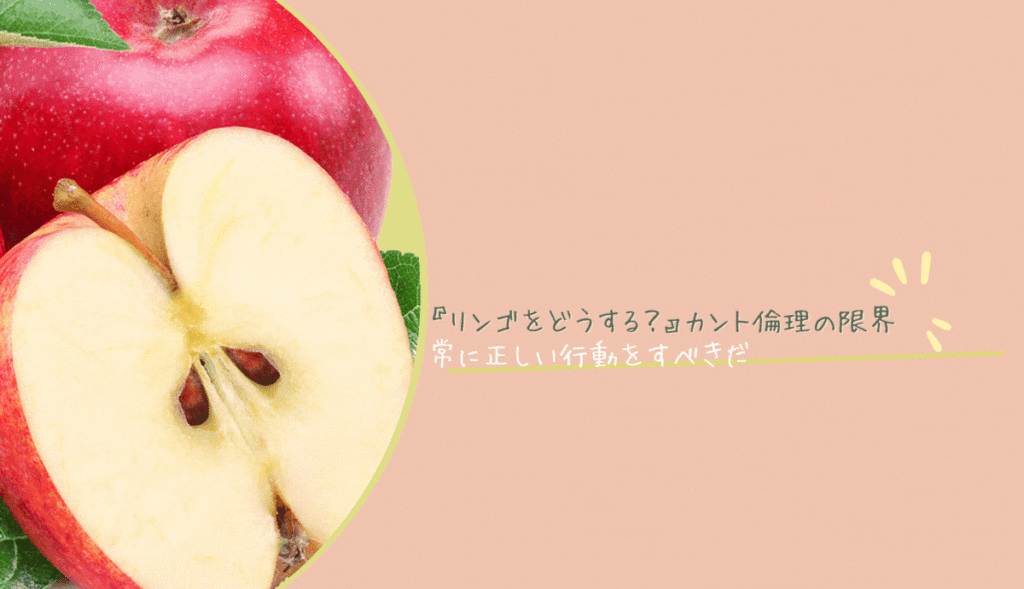
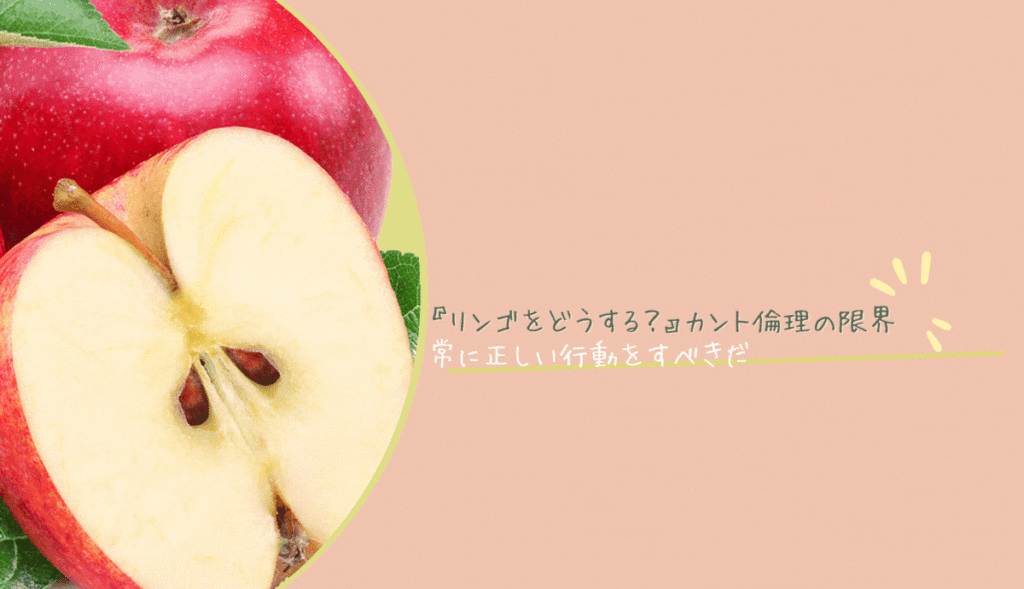
カントの倫理学は、『行動の正しさは結果ではなく、道徳的な原則に従っているかどうかで決まる』 という考え方を基盤としてます。
これを 『定言命法』 と呼び、条件付きではなく、常に正しい行動をすべきだと主張。
例えばですが、自分がガリッガリに痩せていて、自身も空腹である。その自分が目の前の空腹である他者に、『リンゴをどうぞ』と言ってリンゴを差し出す。
カント倫理学に従えば、飢餓状態でなければ『困っている人にリンゴを差し出すのが道徳的に正しい!』になるはず。



理由は、①普遍化可能、②他者を尊重する、③自己保存の問題がないという3点に基づく。カントなら、自分が死の危機に直面してない限り、リンゴを差し出すと思われる。※そうしそうという仮説ですよ
カントの道徳では、行為そのものよりも 『なぜその行為を行うのか(動機)』 が道徳性を決定するから。
例えば、、
① 空腹の者同士『一緒にリンゴを食べましょう』の場合
- 相手を自分と同じ『目的としての人格』として扱っている。
- 純粋に相手の存在を尊重し、共に喜びや必要を分かち合う意思に基づいている。
- 無条件で相手の人格を尊重し、『定言命法』に合致する。
→ 道徳的に適切(完全な道徳的行為)
②『自分も空腹だし(満たしたいし)、あなたも空腹なら半分しましょう』の場合
- 自己の利益(空腹を満たすこと)が条件となっており、純粋な善意や義務感に基づいていない。
- 相手を尊重しているように見えても、実際には 自己利益の充足が前提になっている。
- 相手を『目的そのもの』として尊重するのではなく、自分の利益を達成するための 『条件付きの手段』 として扱っていることになる。
これは、カントの定言命法第二定式(人間を決して単なる手段としてのみ扱ってはならず、常に目的として扱え)に照らすと、『完全な道徳性』を欠いていると考えられる。
→ 道徳的に不完全・不適格な行為



生きるためには、エネルギーの分配が鍵!それは『打算』ではなく合理的だと思う。



それは 『善意』じゃなくて 『高度に計算された取引』だよ。



高度に計算され……..何!?
あくまでも、空想ですよ。
- 再整理(カント哲学の観点から)
- カント倫理学に従うならどうなるか?
- 現実にはそうならないこともある
- 人を手段として扱うパターン
①再整理(カント哲学の観点から)
| 状況(行動・意思) | 動機(なぜ行動するのか) | 定言命法との適合性 | カントの道徳的評価 |
|---|---|---|---|
| 空腹の者同士『一緒にリンゴを食べましょう』 | 純粋な善意・人格への尊重 | 適合する() | 完全な道徳的行為 |
| 『自分も空腹だし(満たしたいし)、あなたも空腹なら半分しましょう』 | 自己利益が条件となった、相手を手段として利用する動機 | 不完全() | 不完全・不適格な行為 |
カントにとっては、『助かったかどうか(結果)』よりも、『なぜ助けようとしたのか(動機)』が重要。
でも、現実世界で考えると、『結果的に助かったのなら、動機はそこまで重要ではない』と感じるのも自然。



これは『功利主義(結果主義)』の立場で、助かれば結果的にみんな幸せ(利益の最大化)。動機が自己利益だろうと、相手が幸せになればそれでよい、という考え方に属してます。
カントはその逆で、『結果』ではなく、あくまで『動機』の純粋さにこそ真の道徳性があり、自己利益を前提にした行為は道徳的に完全ではない(結果がよくても不道徳な場合もある)と考えてます。
定言命法によって、『自身も空腹であろうとも、リンゴを必要とする相手に譲ることが道徳的に正しい』 という結論になる。ここでは、行動の結果は考慮されません。重要なのは、行為が 『他者を目的として扱う』 という倫理原則に基づいているかどうか。
だけど、この理論には限界ありますよね。
実際に、ガリガリに痩せている空腹そうな人から『これどうぞ』とリンゴを差し出されたとき、快く受け取って食べることができます?わたしには無理。



充電残り1%のスマホが、別のスマホにバッテリーシェアしてくる状態。シェアできる?もしくは、燃料切れのロケットが、他のロケットに燃料を分けようとする状態。何してんの?落ちるよ?まずは自分のタンク満たせよって話で。
この状況でリンゴを受け取って一人で頬張るという行為があった場合、結果的に負の連鎖を生む可能性もある。
もし、それができるとすれば、それは『ガリガリに痩せた自分と同じ空腹な人からもらったリンゴをひとりで食べるような人が周りにたくさんいる』と考えていることと同じです。



それとも、相手が断る前提で差し出すの?これもおかしいでしょう?
つまりは、そういう一見、非道徳的と思われる行動をしてしまう人が一定数いると認めてることになるのに、善意を義務とし、施そうとする、何その矛盾。
②カント倫理学に従うならどうなるか?
もしカントの理論が正しいならば、ガリガリに痩せた人がリンゴを差し出したとき、相手は『あなたこそ食べるべきだ』と遠慮するはず。
これは、『他人を目的として扱う』というカントの倫理原則に基づいてます。
③現実にはそうならないこともある
実際には、相手がリンゴを食べつくす可能性もあるわけです。これが起こる時点で、カントの『人は理性的に行動する』という前提が破綻していることを示します。
さらに、『そんなことが起こる』と考えること自体が、人間の本質に『性悪的な側面』もあることを認めることになる。
④人を手段として扱うパターン
もし相手が『この人は善意でリンゴをくれるのだから、利用できるだけ利用しよう』と考えていたら?
これは、相手がカントの理論とは逆に『他人を単なる手段として扱っている』状態になります。カントが否定した『人を手段として利用する』行為が、現実には普通に起こりうることを示している。
欲をエネルギーにすれば?
自分が満たされていないと他人を助けられない
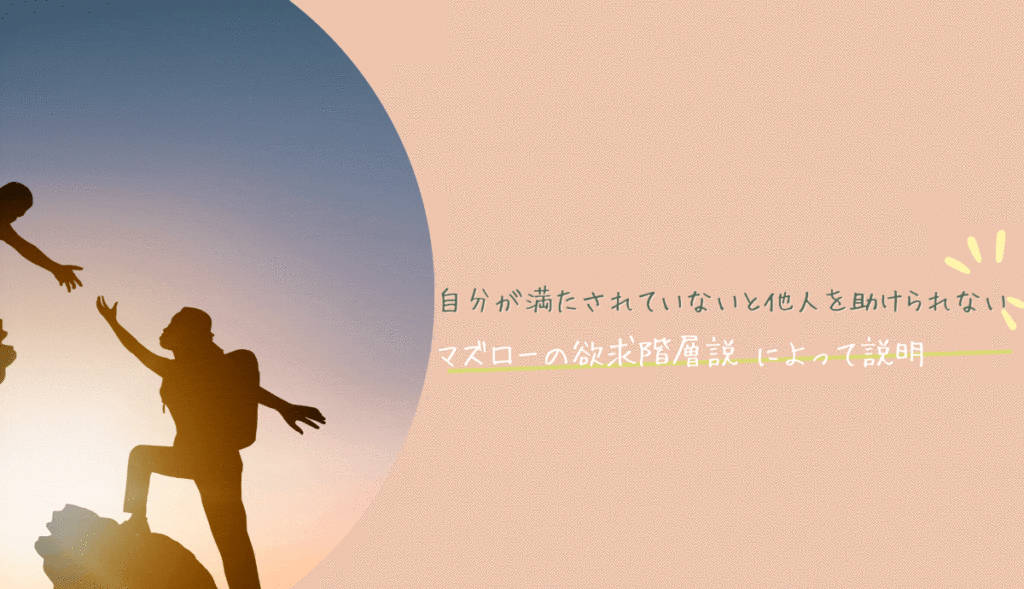
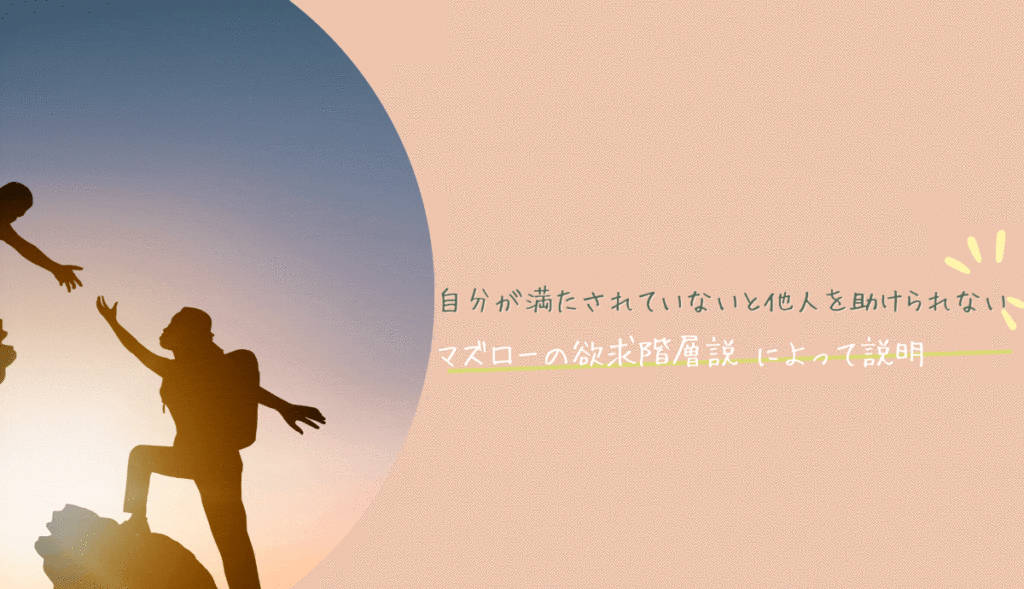
これは、マズローの欲求階層説によって説明できます。
- 生理的欲求(食べる・寝る) → まず自分の命を維持しないといけない
- 安全の欲求(安心して生きる) → 生活が安定していないと他人に優しくできない
- 社会的欲求(人とのつながり) → 自分が余裕を持てば、他人に思いやりを持てる
『自分が満たされることで、初めて他人に与えることができる』という考え方の方が、人間の心理として自然じゃないですか?
人と欲は切り離せない。
つまり、『自分を犠牲にして他人に優しくする』のではなく、『自分が満たされた上で他人に優しくする』方が道徳的にも合理的だと思うからです。
これは、物理学の基本法則とも一致します。たとえば、飛行機の酸素マスクのルールご存知ですか?緊急時に『まず自分のマスクを装着し、その後で他人を助ける』ことが推奨されるのは、自分が意識を失えば他人を助けることができなくなるからです。つまり相手も自分も助かるために重要な行為とされている。
エネルギー保存則と優しさの本質
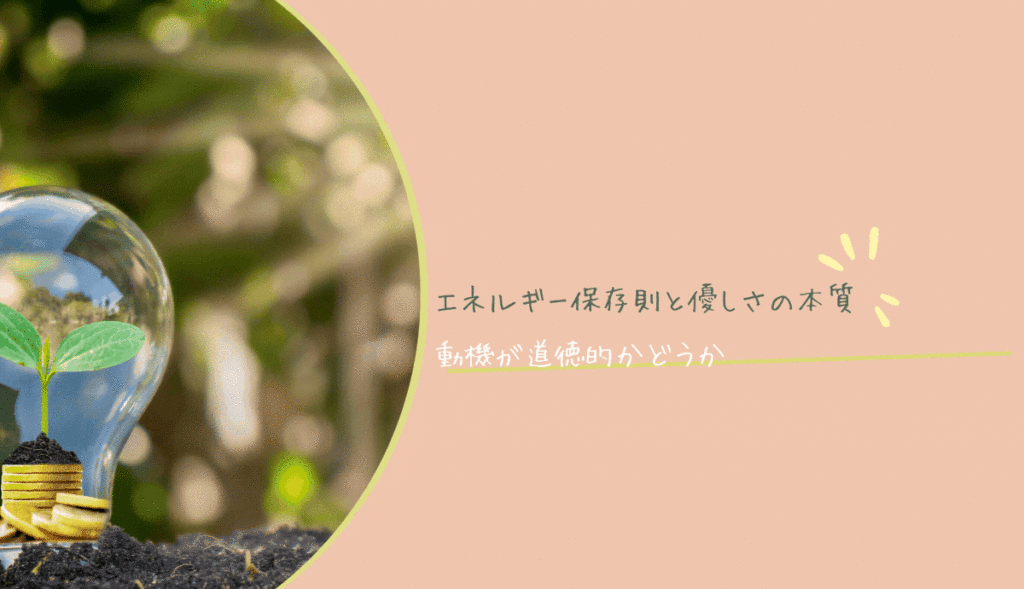
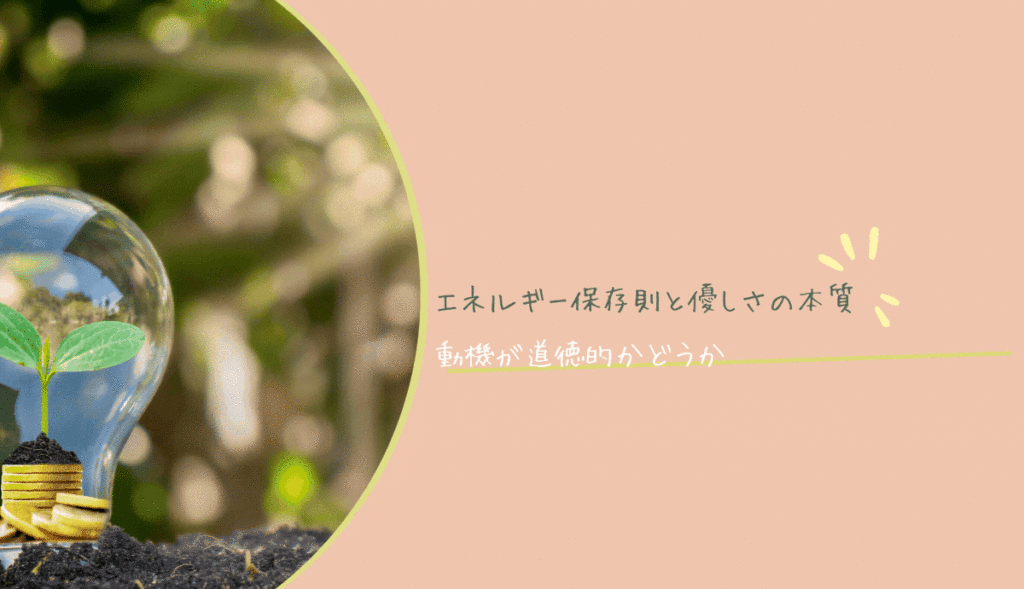
カントの倫理は『見返りを求めず、ただ道徳的だから行うことが正しい、結果ではなく、動機が道徳的かどうか。』としています。でも、ここでエネルギー保存則の視点を持ち出すと、まるで燃料なしにずっと動き続ける機械、永久機関を目指しているみたい。



エネルギーはどこからともなく湧き出ない。それなら、道徳的行動のエネルギーは一体どこから来るの?
もし『純粋な善意』だけで動けるのなら、人間は一日中働き続けても疲れず、善行を行い続けても決して枯渇しない超人ということになる。
現実の人間はそんなわけにはいきませんよね。善意にも燃料は必要で、それが枯渇すれば道徳的行動は続かないと思う。わたしは続かない。
カントの道徳観に従うと、『燃料なしに無限に動き続ける機械』という、物理的にありえない状態が求められます。
結果として、『見返りを求めるな』と言いながら、人はどこかで何らかの形でエネルギーを補給しないと、善行は持続不可能であることが見えてくる。
エネルギー補給とは言えば、人には『相手が喜ぶことがエネルギーになる』という他者思考型ギバーが存在します。これは、相手の幸せや成功を自分の喜びとするタイプの人々です。
カント倫理は道徳は義務なので、この理論からは外れるけれど、この他者のために行動することがエネルギーとなると人(何もかも差し出す、自己犠牲型ギバー)すらも、心理学者アダム・グラントの『ギバー・テイカー・マッチャー理論』によると、自己犠牲型のギバーは、他者のために尽くしすぎるがゆえに、最も搾取されやすく、疲弊しやすい、最も成功から遠い存在になりがちであるとされています。
実際そうだと思う。


一方で、健全なギバーは『自分も満たしながら他者に貢献する』バランスをとることができ、結果的に最も成功しやすいとされている。
道徳的行動のためのエネルギーは何らかの形で補給される必要があり、純粋な『義務としての道徳』が持続可能かと言われると不可能に近いと思う。



仮言命法であっても、何度も言うようですが、自分のための行動で人が助かるんだったら、それで良くない?結果を言うなら、そんな下心、どうせすぐバレるって、、、ていう。論点はズレてるかもしれないけど。友達に『自分をよく見せたいから、助けるわ』って言えばいいんですよ。そっちの方が誠実でしょう?
ヘーゲルの視点:道徳の進化と絶対精神
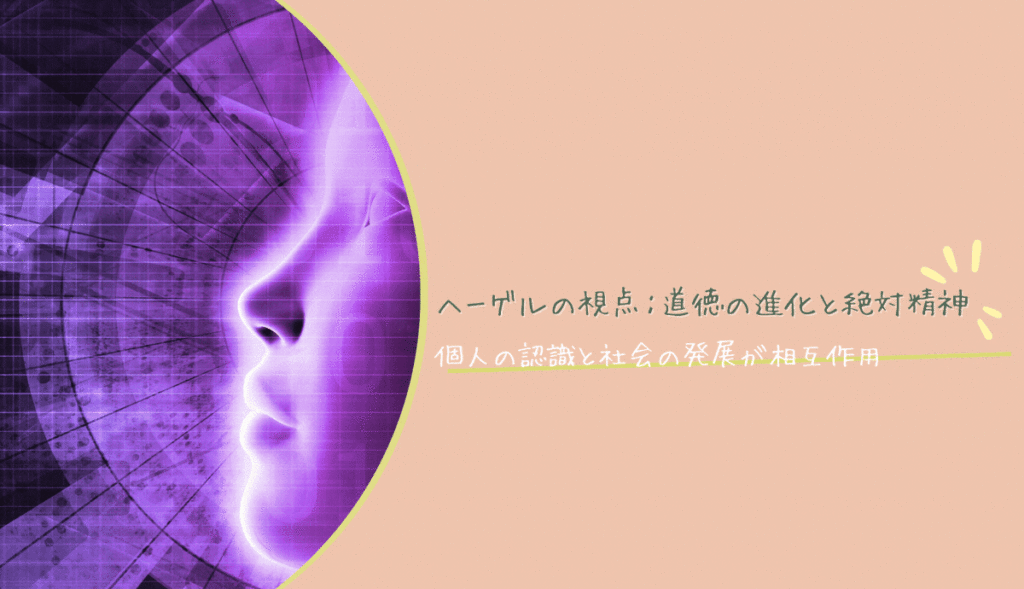
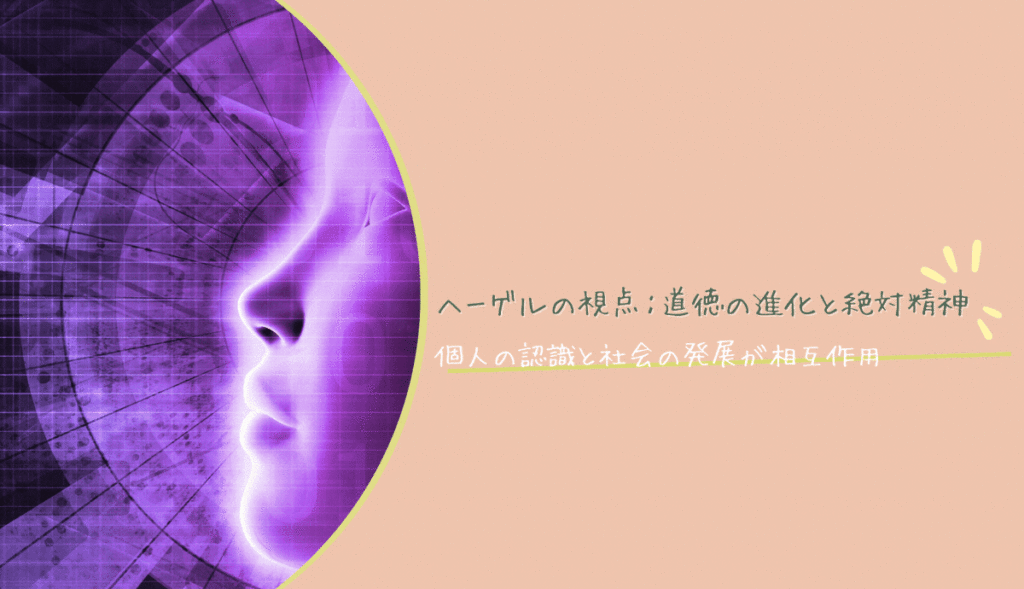
ヘーゲルは、個人の認識と社会の発展が相互作用することで、人類の意識がより高次の段階へと発展し、『絶対精神』へと到達すると考えていました。
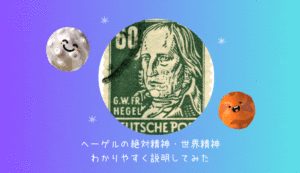
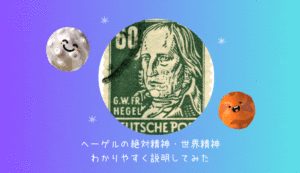
つまり、『他人を疑う』ことは、自己と他者の関係性の中で、自分自身がどのような世界に属しているかを認識することにつながる。『自己の在り方を認識すること』と『他人を疑うこと』が表裏一体になってる。
- 『他人を疑う』こと=『自己を知る』こと
- 『優しさとは何か?』という攻撃の発生
- 『自分は優しい本当にのだろうか?』という自己認識の変化
- 自己意識の発展
①『他人を疑う』こと=『自己を知る』こと
『他人を疑うことは、自分がどんな世界に属しているのかを認識すること』という考え方は、ヘーゲルの自己意識の弁証法に基づいてます。
- 相手がリンゴを差し出し、その人が美味しそうに食べるのを見たとき、それを『自分もそういう人間である』と認めることになります。つまり、自分も、ガリガリに痩せた人を前に美味しそうにリンゴを頬張る人間であることを認めることになる。自分はそうじゃないとしましょう。では他人は?
- 自分はそうじゃない。でも、他人はそうである。
- ここで疑問が生まれる。 相手がリンゴを頬張る姿を見て、『なぜこの人はこういう行動をとるのか?』と考える。 さらに、『自分ならこうしないのに、なぜこの人はそうするのか?』と考える。
→自己が自己を知るためには、他人の反応を自分自身を問い直す必要がある。
②『優しさとは何か?』という攻撃の発生
- 『自分ならこんなことはしない』という意識が芽生えて、次に『では、優しさとは何か?』ということが問われる。
- 一般的に、優しさは『他者を思うこと』と定義されるけれど、ここでは『思いやりとは、なんだろう?自分はリンゴを差し出したけれど、相手は何のためらいもなく美味しく食べた。自分ならできない。相手の行動は優しさなの?』 という批判が上がる。
- つまり、『優しさ』は絶対的なものではなく、相対的なものであることに気づいています。
→ 『優しさとは何か?』という問いが生まれます。
③『自分は優しい本当にのだろうか?』という自己認識の変化
ここで、次の段階に進みます。
- 『自分は相手の行動を見て違和感を感じた。この違和感は何?でも、それは自分が本当に優しいからなの?』
- もし、自分が本当に優しいのであれば、相手の行動を非難するのではなく、何か別の行動をとるのでは?そもそも、相手の行動になぜ疑問を抱えるの?
- すると、『自分は自分の、助けるべきだという価値観に従っているだけじゃないの?』と問い直すことになる。
→ 『自分の優しさは、本当に純粋なものなの?』という疑念が生じる。
④自己意識の発展
相手が罪悪感を気にせず、美味しく食べるには、『状況』が重要になります。
- どちらもお腹が空いている。『リンゴを半分こしませんか?』という提案が意味を持つ。
- これなら、相手は遠慮なくリンゴを受け取ることができる。
- 自分も完全に犠牲になるわけではなく、自己の考えを守ることができる。
- 自己と他者のバランスを整える優しさになる。
- 『かける』ことが優しさなのではない、相手が『気兼ねなく受け取れる』ことが優しさである。
- しかし、それを可能にするためには、『ここの状況がそれを許容できる状態であること』が前提となる。
- よって、『リンゴを半分こする』という選択肢が、『優しさ』として最適解となる可能性が高い。
→優しさとは『相互作用の中で成立するもの』であり、自己犠牲ではなく、相互作用の中で『どちらでも無理せずに成立する関係』を作ることである。『半分こしませんか?』という提案こそが、そのバランスの上で最も適切な方法である。
相手の状況や思いまで考えることができるようになると、そこには真の優しさが含まれていると思います。
まとめ
カントの道徳論は、ある意味で『究極の理想形』として存在していて、それ自体は価値のあるもの。ただ、人間が完璧でない以上、その理想を現実に適用するには、ヘーゲル的な『発展のプロセス』が不可欠になると思います。
カントの道徳は『いきなり最上級を求める』けど、ヘーゲルの弁証法は『成長しながら到達する』という流れだから、両者は対立というより補完関係にあるとも言えるのかなと。
どの道、自分の心と行動に乖離があれば、人は摩耗します。
結局、人は不完全だからこそ、ヘーゲル的な相互作用の中で成長し、カントの理想に少しずつ近づいていけばいいのでは?道徳は『静的な完璧さ』ではなく、『動的な進化』の中で実践されるものだという考え方の方が、現実に即していると思う。
カントの理想を知った上で、ヘーゲルのアプローチで段階的にそこへ向かう。
そして、正義としての正しさは人の数だけあり、状況や立場によって行動が変わる。それでいい。



カントの理想論って、低温の金属をいきなり1000℃に加熱するみたいに思える。ゆっくり温度上げればいいのに、急加熱すると割れるでしょ。人も同じだと思う。
ヘーゲルの理論の方が納得できる。
カントの理論は理想としては価値があるけれど、現実ではより柔軟な倫理観が求められると考えます。
一応、言っときます。個人的な意見です。
まとめ
カント倫理は『信用の必要性』を考慮してなくて、カントは 『理性があれば、誰でも道徳的に行動できる』 という前提を置いています。
そもそも、信用がないから義務化になるのでは?とも考えられる。言っていることに整合性が取れないんです。
でも、現実には『信用』がないと、人は道徳的に行動できないですよね。
カントの考えは『個人の理性』にフォーカスしていて、『社会の中でどう実践するか?』にはあまり触れてない。
でも、現実の社会では、『信用がなければ道徳は機能しない』 という問題がある。この点で、カント倫理には『理論と現実のズレ』がある。
信用がある社会では、道徳は『自然に生まれる』と思う。
儒教(孔子):『徳を持つ人が増えれば、社会全体が調和する。』
仏教(縁起):『すべての行為はつながっており、他人に善を施せば、それは自分にも返ってくる。』
つまり、『信用のある社会では、人々は自然と道徳的に振る舞う』という考え方です。
つまり、『信用があれば、リンゴは自然と回る』、『信用がなければ、リンゴを巡って争いが起こる』。
では、どうすれば『信用のある社会』を作れるか?自己犠牲ではなく、『お互いに満たし合う』文化を作る。
まずは自分が満たされる。その上で『相手に渡しても問題ない』という状態を作る。『信用の積み重ね』を社会のルールにする。こっちの方が合理的。
カントのように『理性だけ』で道徳を考えるのではなくて、『人は感情や信用の上で生きている』という視点を持って、信用を築く社会を作ることが、道徳を機能させるカギになるのでは?と考えます。



まず信用を築いて、それで道徳的な行為が自然に生まれる社会を作るという発想ができれば、、そっちの方が実践的な倫理としては重要じゃない?という、あくまでも個人的な意見です。
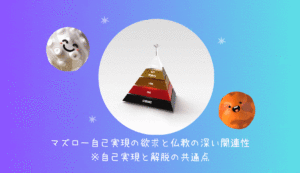
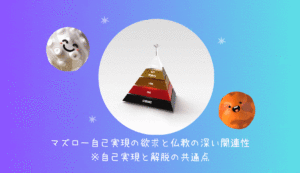

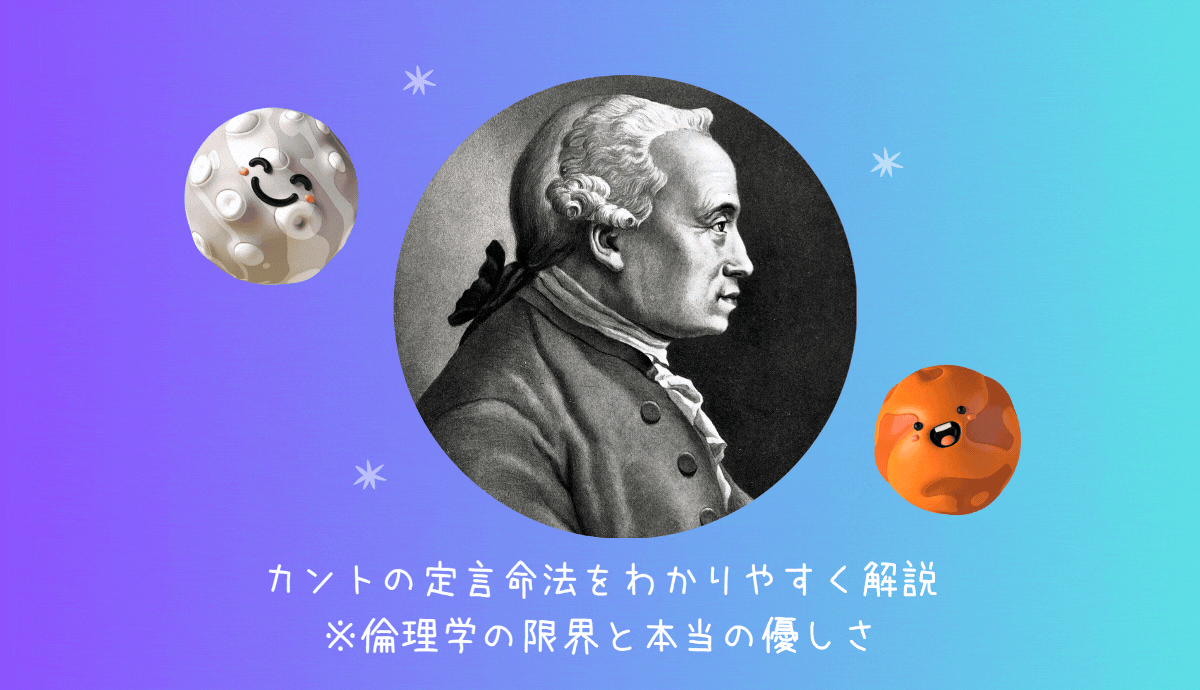
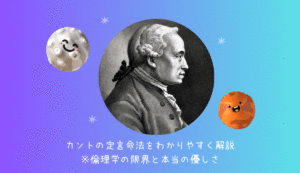
コメント