人生の中には、自分の力で変えられるものと変えられないものがあります。
このブログにたどり着いたあなたはきっと、ニーバーの祈りをご存じですよね。
すると、ふいにこんなことを想像するかもしれない。理解と葛藤↓。
- 変えられるものに集中することで前に進める
- 変えられないものに執着してしまうと、ストレスが溜まり自己成長が阻害される
- 変えられないものを受け入れ、変えられるものに集中することが、心の平穏と成長にはつながりやすい
- 変えられないものと変えられるものの境界は何か
- 変えられないものは、本当に変えられないものなのか

そこで、この記事では、変えられるものと変えられないものの違いを理解し、変えられないものを受け入れる大切さについて解説すると同時に、変えられないものは、本当に変えられないものなのか?ということについてまとめてみました。
自分の人生を切り開くための、ほんのひとつの知恵として、参考にしてみてください。
変えられるものと変えられないものの違いとは
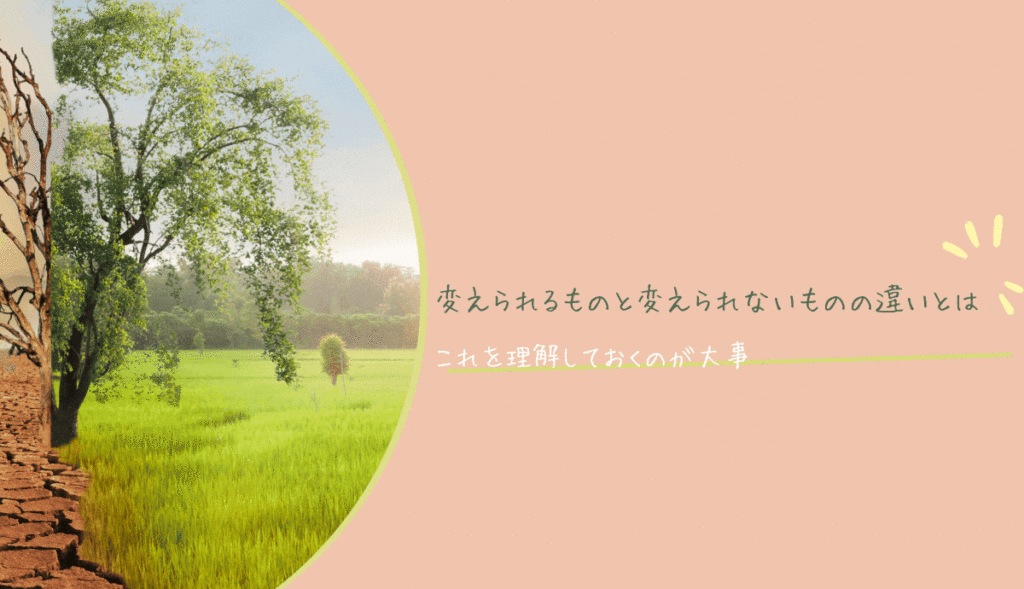
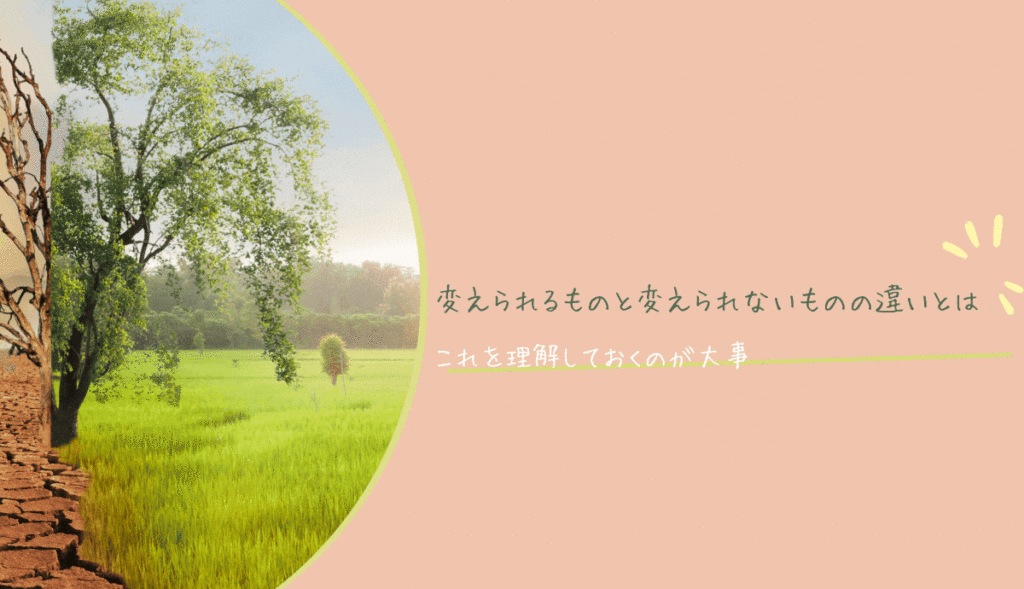
人生の中、生活の中には、『変えられるもの』と『変えられないもの』がありますよね。
アドラーで言う、『課題の分離』です。



これを理解しておくと、ストレスの軽減や自己成長に繋がりますが、大体みんな、『変えられないもの』に注力してめっちゃ悩んでる。では、具体的にどんな違いがあるのかをまとめてみます。
- 変えられるものとは
- 変えられないものとは
- 変えるべきか、受け入れるべきか
①変えられるものとは(自分の課題)
『変えられるもの』とは、私たち自身が意識的に手を加えることができるもの。
主なものは以下の通り。
- 自己の行動: 自分の振る舞いや行動パターンを変えることで、周囲に与える影響も変わります。
- 思考や言葉: 自分の考え方や使う言葉を変えることで、心の持ちようや人生の見え方も変わります。
- 環境: 職場や生活空間など、自分がいる環境を選ぶことで、日々の生活の質が向上します。
- 未来: 将来に関する意識を変えることで、自分自身の未来を築く道筋が見えてきます。
こんな風に、自分自身に関わる部分は意図的に変えることができる。変化することで、多くの成功体験がつまれ、自己肯定感を育むこともできる。
- 自分の考え方(捉え方次第で世界は明るくも暗くもなる)
- 自分の行動(行動できるかどうかはあなた次第)
- 今日食べる晩ご飯のメニュー(ダイエットするかどうかはあなた次第)
- 使う言葉や態度(口が滑るのは不可抗力)
- 勉強や仕事の努力量(結果が伴うかは別)
②変えられないものとは(他人の課題&自然の摂理)
一方で『変えられないもの』は、私たちがどれだけ努力しても変えられないもの。
例えば、以下のようなもの。
- 他人(自分以外の誰か): 人の行動や感情は、自分の力で直接変えることはできません。変わるかどうかは、相手次第。
- 過去: 一度起きた出来事や経験は変えることができず、受け入れる必要があります。
- 自然の法則や運命: 自然環境や社会の動き、世の法則も、個人の力で変えるのは難しい。
- 他人の性格(自分の性格すら変えるのが難しいのに他人はなおさら)
- 他人の行動や価値観(他人の行動を変えようとして人生の半分をムダにする)
- 自分の過去(消したい過去ほど消せないようになっている)
- 世の中の天気(大事な日に限って雨が降るという宇宙のいたずら)
- 自分の寿命(生きる時間は限られているのにSNSの無駄スクロールで寿命を浪費する)
ただし、補足として、過去は変えられませんが、過去の見え方(捉え方)は変えることができます。
例えば、嫌な出来事が起きたときに、その経験は変えることができないでしょうが、その経験を通して感じるものは変わるということ。
あれさえなければ!という感情から、あの経験があったから今がある。あの経験が無ければ、今の自分はない。
こう思うと、過去の見え方が変わりますよね?嫌な思い出も、ひとつの経験として人生の一部になる。その嫌な過去が人生の全てを支配してしまっている状態では、『過去は変えられないもの』として自分の中に残るでしょうが、人生の一部にしてしまえば、『過去の経験は変えられないが、見え方(捉え方)は変えられる』ということになる。
話題は『過去の見え方』に逸れましたが、『変えられないもの』これらの要素に執着しすぎると、思うようにいかないことからストレスが溜まり、自己信頼感が失われる原因となります。重要なのは、『変えられないもの』を受け入れる強さを持ち、それに引きずられない心の持ちようです。
他の人がどのように感じ、どのように行動するかは、私たちのコントロールを超えていて、たとえ親しい人であっても、相手の考えを変えることは難しい。



それぞれが異なる価値観を持っていること、そして、相容れないこともある、ということを理解しておくと、後が楽だと思いますよ。
③変えるべきか、受け入れるべきか
『変えられるもの』と『変えられないもの』を明確に分けることで、ストレスを減らし、どう行動すればいいのかが見えてきます。自分が変えられるものに注力すると、良い変化を促すことができ、逆に、変えられないものに意識を向け続けると、無駄なエネルギーを消耗してしまう。
自然の摂理とも言います。



変えられないものを変えようと努力することは、まるで天気予報に文句を言って雨雲を追い払おうとするくらい滑稽で、無駄なこと。
だけど、人はそんな無駄を繰り返しながら、自分の人生を自分でつまらなくしている。
なぜ変えられないものにこだわってしまうのか


私たちが『変えられないもの』にこだわってしまう理由は、様々で、これが時には私たちの思考を縛り、成長を妨げることがある。その背景には、以下のような要因がある。
- 心理的要因
- 社会的要因
- 変化への抵抗感
①心理的要因
- 不安と恐れ
変えられないものに執着することで、安心を得ようとするから。これは、過去に縛られることで安定した現在を保とうとする心理の表れでもあります。 - 自己肯定感の喪失
過去の失敗や他人との比較によって自己評価が下がると、どうしても変えられないものに対して執着しがちになります。
例えば、前を向かなければ仕方がない状況で、受け入れがたく、逃げ出したくて『変えられないもの』にこだわることで安心を得ようとしてみたり、『自分は何も変えられない』という悲観的な考えが、自分の能力を制限し、そこに留まらせる。



厳しいことを書くならば、そうすることが、本人にとって都合がいい、楽であり居心地がいいから、とも言える。そういう状況にいたいときもあるから、それがダメとは言えない。けど、知っておいた方が楽になることもあるから、一応知識としてだけ綴っておきますね。
例えるなら、ダイエットしようと思った途端に『人間の体質って遺伝だから仕方ないよね~』って言いながらポテチを食べるのと同じくらい都合がいい話。
で、最終的には、『どうせ痩せない』と宣言して、自分を動けない檻に閉じ込め、太ったまま。こんな感じです。
②社会的要因
- 周囲の影響
私たちは周囲の人たち(友人、家族、同僚)の意見や価値観に大きく左右されます。『こうあるべき』という社会的なプレッシャーが、変えられないものに対する執着を強めます。 - 文化的背景
日本の文化は、調和を重視するため、他人に合わせることが美徳とされる同調傾向がありますよね。これで、自分の意見や立場を押し通すよりも、変えられない現実に妥協してしまうことが多くなりがちです。



要するに、周りに翻弄されがちになっちゃうってことです。自分がしっかりしていれば大丈夫。
③変化への抵抗感
- 年齢による固定観念
年齢が上がるにつれて、新しいことに挑戦することへの抵抗感が増すことがあります。『これまでのやり方を変える必要はない』と考え方が固執してしまうことがある。 - 失敗への恐怖
変わることに対する不安や、失敗することへの恐れが心のブレーキとなり、変えられないものにしがみつくことがあります。この恐れは新しいことに挑戦するための壁となり、結果として成長の機会を逃すことに繋がる。
年齢が高くなると、これまでのやり方を変えるのって抵抗があるんですよね。それを今まで信じて生きてきたから。それまでの自分の人生を否定されたかのように思ってしまうことがある。
誰にでもあるんですけどね。これって、驚異だったりする。
年齢に限らず、やっぱり、人生で起こる色々な出来事は、受容に時間がかかることがある。けれど、今までしてきたその自分の行動や実績全てが否定されるわけじゃない。そこがあったから、今がある。
そこがなければ、今は無い。過去否定するための『今』じゃない。
そうじゃなくて、今まではその行動や実績が必要だったんです。ここから変えて行くというよりも、新しい部分を取り入れて行く、そういう感覚じゃないでしょうか。一新されるわけじゃない。
今が正しくて、過去が正しくないわけじゃない。
過去は過去で必要なんです。そこに続いて今があるなら、新しい何かも、自分の一部になって行くと私は思います。
心理的な執着は誰にだってある。
今まで進んで慣れてきた道じゃなくて、急に『次は右です』って言われたら、『何で!?』ともなる。けど、『次は右です』って言われたことに気づくって、すごいことじゃないでしょうか。
言われても、気づかない人は気づかないし、気づかないふりをするんですよ。
右見るの、勇気がいるから。
変えられるものに目を向けることで、より充実した人生を生きることができるようになる。けど、受け入れるのに勇気もいる。けど、きっと『次は右です』と言われたことに気が付いたあなたにはきっと、もっともっと、良い未来が待っていると思います。



これが弁証法で、過去があり、今があり、未来がある。こうやって、どんどん進化して行く。そして絶対精神にたどり着くんじゃないですかね。
ヘーゲル:1770年8月27日~1831年11月14日
ラインホルド・二ーバー:1892年6月21日~1971年6月1日
ヘーゲルの絶対精神論が先にはなりますね。二ーバーが弁証法を意識していたかどうかは知らないけれど、ヘーゲルが言ってる絶対精神論はこういうことだと思う。
変えられないものを受け入れる難しさと大切さ
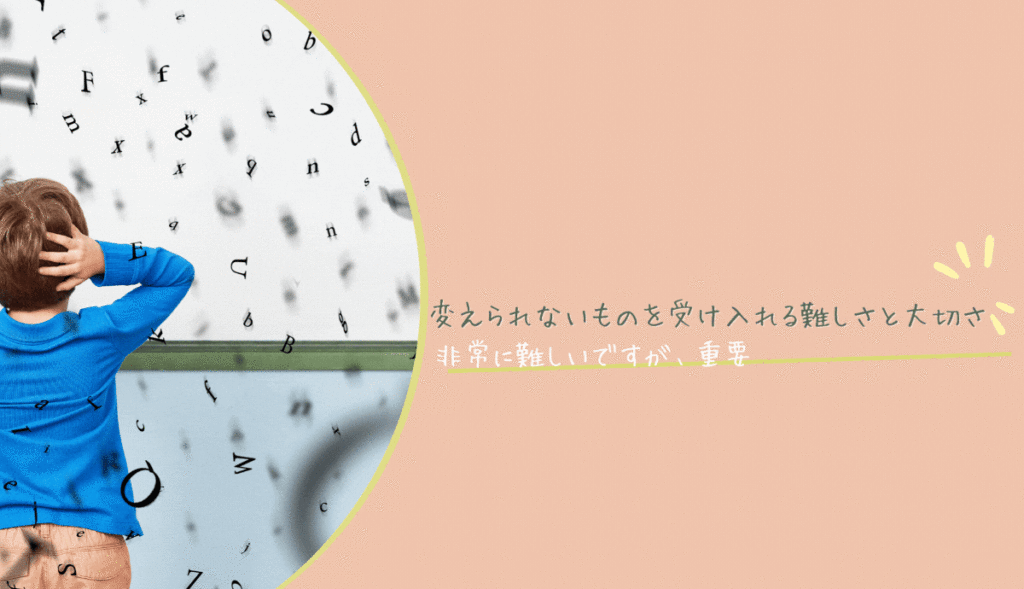
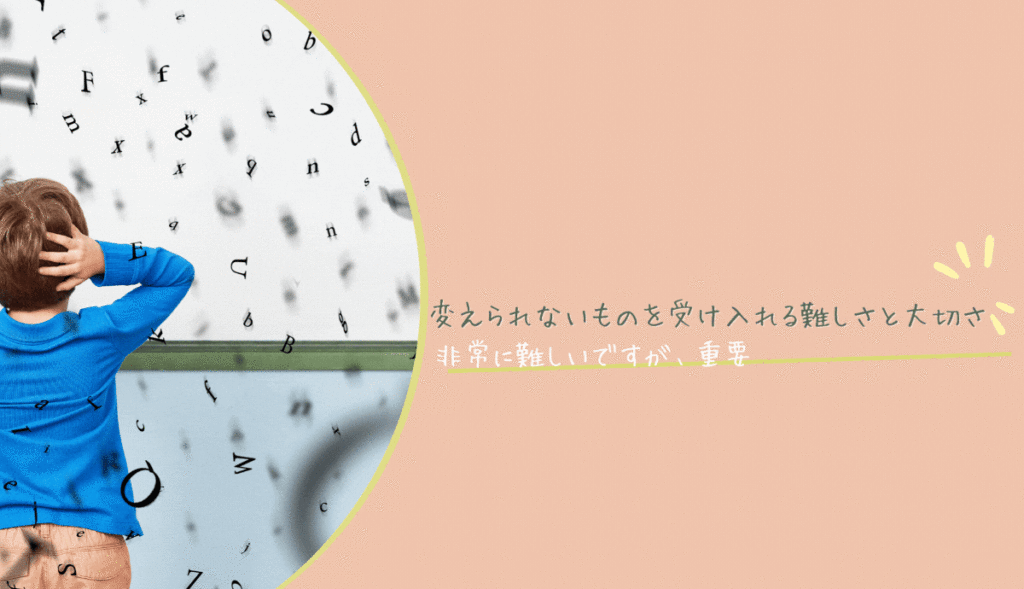
人生、生きて行く中で、『変えられないもの』を受け入れることが大事なのは分かるけど、やっぱり抵抗もあって難しいと感じることもある。
当然ですよね。



人って、『絶対変えられないもの』に向かって全力で文句を言ってストレスをためる天才だったりする。これって、熱々のラーメンを自分で頼んでおいて、『なんで熱いんだよ!』って怒ってるようなもんなんです。
皮肉だけど、人間は『絶対に変えられないこと』を受け入れるより、その現実に全力でキレている方がなぜかラクなんです。だけど、実はその無駄な怒りを手放して、『あぁ、これは無理だな』って笑えた瞬間に、人生って急にラクになっちゃうんです。
…まあ、言うは易し、ですけど、この4つに気を付けてみてください↓
- 自分を解放するために
- 受け入れるためのポイント
- 課題の分離をする
- 心理的なハードルを乗り越える
①自分を解放するために
変えられないものを受け入れることは、自分自身を解放することにもつながります。
例えば、過去の出来事や他人の行動に対する執着を手放すことで、心の負担を軽くすることができる。これには、以下のようなメリットがあります。
- ストレスの軽減: 他人の言動や、どうすることもできない状況に対するプレッシャーが減り、心が穏やかになります。
- 自己肯定感の向上: 自分が変えられる部分にエネルギーを注ぐことで、達成感を感じやすくなります。
- 関係性の改善: 他人を変えようとすることをやめることで、対人関係がスムーズになり、より良いコミュニケーションが生まれます。
とは言え、、、執着を手放すって何?自分を解放って何?てなります?
要するに、到底受け入れることができない過去の出来事、他人の行動があったとき、そこの経験で感じた負の感情を手放すといいということです。



けど、出来ないですよね。
どうやってすんの?
てなる。
そういうときには、一度心の中の箱にしまっておく。
それでいいと思います。
例えば、親からひどい仕打ちを受けた。
その事実だけを受け止める。経験として覚えておく。そこで感じた感情があれば、その感情を受容して行くことができればいいと思います。
ここで、一番効果的なのは、理解者がいることでしょうが、いないときには、その感情、悔しかった、悲しかった、それをいったん感じることです。
『わたしは、〇〇の経験で悔しかった、悲しかった。』という事実を見る、受け止める、理解しておく。ショックだった、だけじゃなくて、どうショックだったのか、そこまで掘ることに意味がある。



そこが、つまりは、どんな経験で、どんな感情を抱いたのか?ここがぼんやりしているから、次に行けない。だって、嫌な経験を自覚しないと、いつまでも引きずられ、引っ張られるでしょう?感情を理解しないと、自分を理解できないでしょう?
ここをハッキリさせておくことに、意味があります。自分の一部、つまりは自分を無視しない。
ハッキリさせた後に、それを伝えるかどうかは、自由です。
②受け入れるためのポイント
変えられないものを受け入れるには、こういう過程が大事です↓。
- 自分の感情を認識する: まずは、自分が感じていることを素直に受け入れることが大切です。どんな感情でも、自分の一部です。
- 状況を客観視する: 『何が本当に変えられないのか?』を冷静に考え、状況を客観的に分析してみましょう。
- 小さなステップを踏む: 変えられないものを無理に受け入れようとするのではなく、少しずつその心構えを育てていくことで、自然に受け入れられるようになります。
状況を客観視できない人の例として、変えられないものに向き合えず、前に進まない、進めなくなるとか。
先ほどの親の例で例えるなら、親に変わってもらおうと必死にアプローチし出すでしょうね。
これだけ報いたのだから、変わってくれる、感謝してくれる。
幻想ですよ。



①変えられないものにアプローチする人は、幻想を見続けます。そして、②その幻想を見続けている人を変えようとする者もいたりする。こちらも幻想が続く。分かります?このループ。
そして、③幻想を一緒に見る人もいたりする。
①にも②にも③にも気づきがない。②から見た①は『変えられないもの』に該当する。
その判別を都度しっかりしていく必要がある。
ここをミスると翻弄されるから。アドラーで言う『課題の分離』が必要。
あなたが携わろうとしているその課題は、誰の課題ですか?
きっと、①・②・③の方の回答はこうなります。



相手の課題です。
そしたら、解決できるのは相手だけですね。全ては必然。
嫌な出来事をすべて受容するには、時間がかかることもある。本人もこれに気が付いている状態が好ましいけれど、そうでないこともある。けれど、それもそれだから。
少しずつその心構えを育てていくことで、自然に受け入れられるようになる。少しずつ心構えを育てていく以外手段がないんです。
③課題の分離をする
この過程で大事なのが、前述した課題の分離です。アドラー心理学の理念を参考に、次の質問を自分に投げかけてみてください。
- これは本当に私の課題?
- この問題の最終的な責任は誰にあるの?
- 他者の行動に対して、私ができることは何?
これらの質問に答えることで、課題が自分に帰属するものであるのか、他者に帰属するものであるのかが明確になります。



ここがバラバラになると、翻弄一直線、『樹海の森ツアー』ー彷徨いの旅編ーが始まります。
課題の分離ができたなら、していいのは『感情を相手に伝える』これだけでしょうね。それをどう受け止めるかは相手次第。
それを伝えるかどうかもあなた次第。


④心理的なハードルを乗り越える
多くの人が『変えるべきだ』『変わるべきだ』と考えてしまうのは、心の中にある『変えられなければならない』『変わらなければならない』という思い込みから来ていることもあります。この思い込みを解消するために、自分自身に対して以下の問いをしてみてください。
- 本当に変えたいのは何ですか?
- それが自分にとってどのような意味を持つんですか?
- 誰のためにしたんですか?
- 今、変えることで何を失うんですか?
例えばですよ。先ほどの親の例で書いてみます。
- 本当に変えたいのは何ですか?
-
親です。
人は変わらないと伝えましたよね?だから、変わりません。これは世の法則です。
例えば、時速300kmの新幹線に、『止まってください!』と伝えたところで、止まらない。
- それが自分にとってどのような意味を持つんですか?
-
親が変わってくれたら、自分が解放されるから。
自分以外の人が変わることによって、自分が解放されるんですか?それこそ幻想です。
自分が解放されるためには、自分が変わる以外ありません。だって、親が変わったとしても、それは相手の課題で、相手が頑張った証拠でしょう?あなたは何を頑張ったのですか?
あなたは、親のことで悩み出す前のあなたと同じあなたです。
よって、あなたの環境を取り巻く環境は、何も変わることはありません。親の人生は変わるでしょうが、あなたの人生はこれまでと同じ、そして同じ悩みにまた出会う。これも必然。
- 誰のためにそれをしたんですか?
-
親のためです。
いいえ、あなたのした行動は親のためではありません。全ては自分のための行動。
そういう行動は相手に伝わることはありません、これは法則です。
あなたはキャッチボールをしているつもりなのでしょう。けど、あなたがしているのは『ドリブル』です。
皆、キャッチボールをしているつもりなんですよ。ドリブルだということに、気づかないといけない。
ヒントを言うなら『自分はドリブルをしている』ということを自覚さえ出来てればいいとは思いますよ。それが覚悟になりますからね。
- 今、(相手を)変えることで何を失うんですか?
-
失いは、、しません。
ですよね。相手が変わっても、相手が変わらなくても、何も失わない。これも必然、当然です。
だって、全ては相手の課題で、あなたとは何の関係もないから。



誰かありきの人生じゃない。自分の人生ですから。
これらの問いを通じて、変えられないものへの執着から少しずつ解放されていくことができるといいなと思って、書いてみました。
変えられないものを受け入れることは、決して諦めではないんですよ。
むしろ、自分ができることに集中するための力強い一歩、内面的な成長を促進する重要なプロセス。心の中の余裕を持つことで、人生の質は必ず向上して行く。
それが『覚悟』にもなる。覚悟関連の記事はこちらにもあります↓


この問いのように、実は私たちが直接影響を与えられるのは『自分』の行動や思考である、ということを覚えておいて欲しいんです。相手じゃない、自分。
実は変えられる※自分の行動で変わるもの
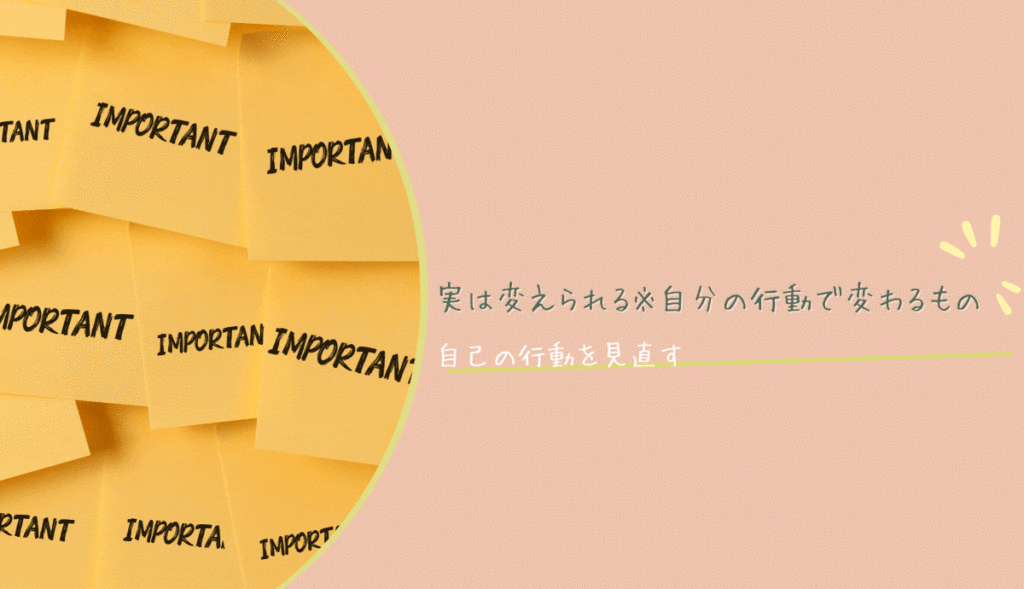
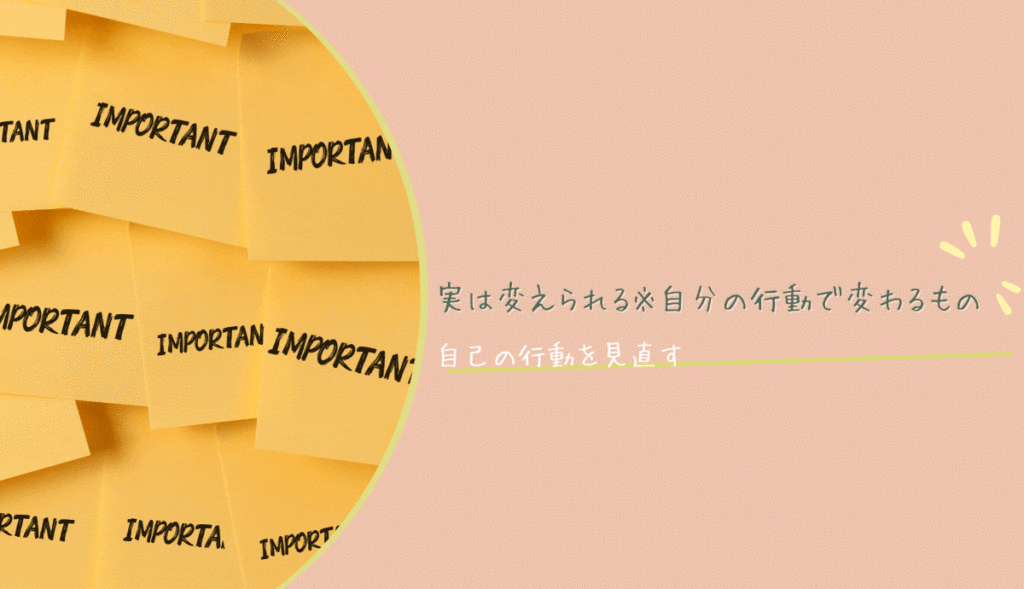
私たちが日常生活の中で感じるストレスや不満は、『他人』や『過去』に起因してることが多いです。
けれど、実は私たちが直接影響を与えられるのは『自分』の行動や思考であることを知っておかないといけないんです。自己の行動を見直すことで、周囲の状況を大きく変えることができるからです。
- 自己変革の重要性
- 環境との相互作用
- 行動の連鎖効果
①自己変革の重要性
自分自身の行動を変えることは、最も身近で効果的なアプローチになる。
以下のような行動は、自己変革に寄与できます。
- 意識を変える: 自分の思考の枠組みを広げることで、新しい視点を持つことができます。前向きな自己対話を実践することで、マインドセットが改善されます。
- 習慣を見直す: 日常生活における小さな習慣を変えるだけで、大きな変化を引き起こすことができます。例えば、朝のルーチンを見直し、運動や読書を取り入れることで、全体的な生産性が向上する。
例えば、否定的なことが頭に浮かんだとしたら、『いや、自分ならできる。きっとできる。』こう思い返すだけで十分です。
もっと言うなら、過去の経験を振り返ってみて、自分の小さな成功でもいいですよ、どんな努力をしてその成功を掴むことができたのか想像してみてください。できれば感情ベースに。
絶対やってやる!と思ったのか、できる、と冷静に思って自分を信じたのか、色々ありますよね。



あのときも、あのときも、ほら、あのときだって・・・
俗にいう引き寄せの法則に値するかも。
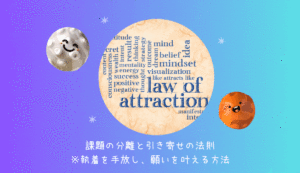
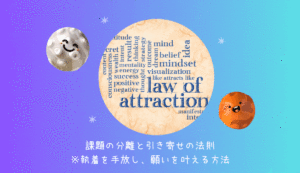
そして、想像できたのなら、『ほら、やっぱりできてる。自分の人生、こうなるようになってる。』こう変換してもいいと思います。こうやって、自分を信じて行きましょう。
想像してないようなことが降りかかることもある。受容には時間がかかるかもしれない。



最終的には、勝つ。
これくらいの意志があるといいなと思います。そういう人は勝つから。
これは、宇宙の理性によって導かれた証拠でしょう。
②環境との相互作用
私たちの行動は、周囲の環境と強く結びついています。環境が変えられるのなら、環境を意識的に変えることで、自分の行動も変わることがあります。以下の点を考慮してみてください。
- 人間関係の見直し: 良い影響を与える人々と過ごすことで、自分自身の行動も変わる傾向があります。より良い環境を求めて人間関係を築こうとすることに意味があります。
- 物理的環境の変化: 仕事場や生活空間を整理整頓し、心地よい環境を作ることで、精神的な余裕が生まれ、生産性が向上します。
人間って、実はすごく単純な生き物で、周りの環境にかなり左右されます。
たとえば、あなたがダイエットしたいとして、周りにいるのが全員『大盛りラーメンが主食』の人たちだったらどうでしょう?
『一緒に痩せようぜ!』なんて言いながら、毎晩のように深夜にラーメン屋へ直行するハメになります。
結果的には『ただのぽっちゃりグループ』のできあがり。
でも、周りが急に『毎朝6時からヨガをやり、オーガニック野菜しか食べません』っていう人ばかりになったらどうでしょう?
最初は『こいつらヤバい』と引きつつも、気がつけば自分もちゃっかりヨガマットを買って、無農薬野菜をかじりながら『デトックス最高』とか言い始めるかもしれません。
また、物理的な環境も同じです。
汚れた机や散らかった部屋で『生産性を上げるぞ!』と意気込むのは、ゴミだらけの道を自転車で爆走して『快適サイクリング!』と叫んでいるようなもの。
いくら本人がやる気を出しても、いつか散らかった荷物で足を滑らせ、やる気も一緒にすっ転んで終わります。
つまり環境っていうのは、あなたを『成功』へも『ぽっちゃり』へも一瞬で変えるほど強力。



『人は環境の動物だ』なんてよく言いますが、正直『環境に踊らされる操り人形』くらいに思ってた方が賢いかもしれません。
③行動の連鎖効果
- 他人に影響を与える: 自分の態度や行動が変わると、その周囲の人々の反応も変わることがあります。例えば、自分が積極的になることで、周りも積極的になるとか、そういうことです。
- 自己肯定感を持つ: 小さな成功体験を重ねることで、自信がつき、好循環が生まれます。
出来るだけ多くの変化を自分の力で引き起こすことができるようになることが理想。どんどん好循環が作られて行くから。
前述した『覚悟』もそのひとつになります。
その覚悟でした体験が、自信になり自負になって行くからです。
自分の行動は、自分自身だけでなく、周囲の環境や人間関係にも強い影響を与えることを理解することが重要で、③が一番重要です。



この相乗効果でしか、人に影響を与えることができない。言葉じゃ無理、変えようとアプローチすることが無理筋だということに、できるだけ早く気づくことができたら、より良い未来作りに早く取り掛かることができる。
変えられるものに集中するためのコツ
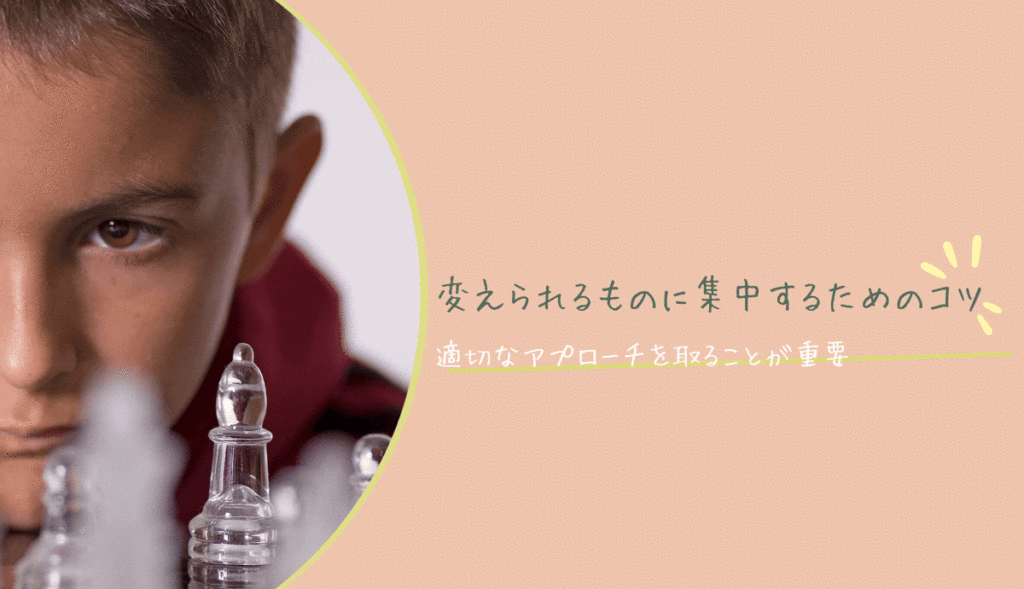
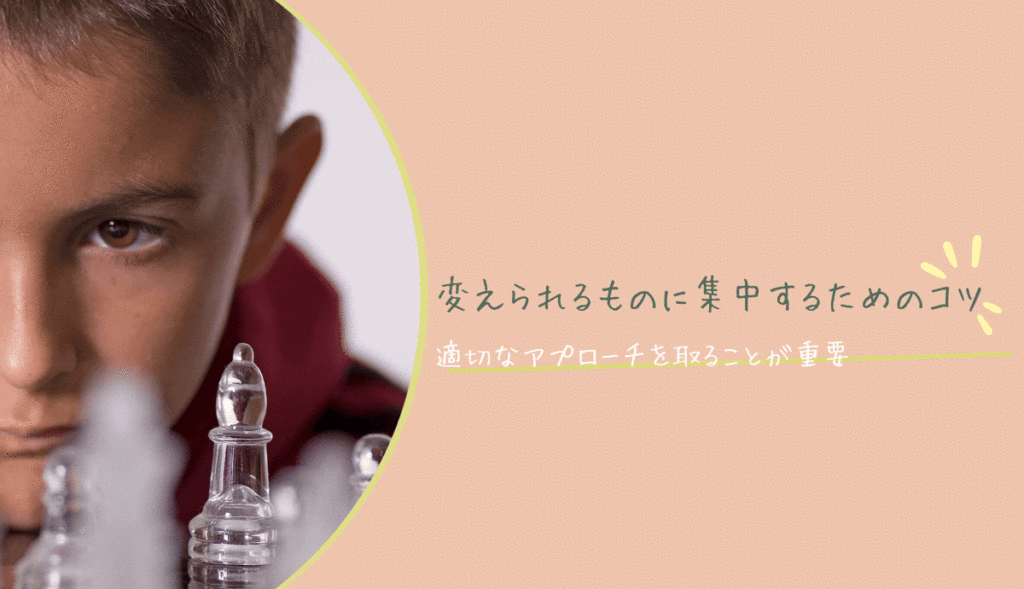
変えられるものに集中するためには、まずその範囲を明確に理解し、適切なアプローチを取ることが重要。
以下のポイントを考慮することで、より効率的に自分の行動や思考を変えることができるかもしれません。
- 自己認識を高める
- 小さな目標を設定する
- 自分の周りの環境を整える
- ポジティブな思考を促す
①自己認識を高める
自分が気にしていることや不満に思っていることについて、冷静に見つめることが大事です。次のような質問を自分に投げかけてみてください。
- これは本当に自分の力で変えられる事柄なの?
- 変えたいと思う理由は何?
- 自分にできる具体的な行動は何?
このように考え直すことで、実際に変えられる部分に焦点を当てやすくなります。
先ほどの親の例で言うならば、親さえ変わってくれたら、自分は報われる。こう思いがちじゃないですか。この3つを改めて考え直すことで、ここからする行動の是非を問える。
その後、こここそが『幻想』だということに、気づけたらいいですね。
自分の周りの人が変わってくれたら、自分は報われる?
この思考回路がどういう弊害を生むか教えます。
他責思考です。



自身の成長はどこにもない。常に周りの責任。必然です。
②小さな目標を設定する
変えられるものに注力するためには、無理のない小さな目標を設定するといいです。一度に大きな変化を求めると、逆に挫折感を感じることがあるから。
以下のようなステップだといいかもです。
- 具体的な行動を考える:日常の中で簡単に実行できること、例えば『読書する』などを設定。
- 進捗を記録する:行動を続ける中で、自分の進展状況を記録し、小さな達成感を得る。
- フィードバックを得る:進捗状況を他人に話してみたり、共有してみることで新たな視点を得られる。
- 将来のビジョンをハッキリ決める:将来の職業など、なりたいものをゴールに決めて邁進する。
読書っておすすめですよ。
自分では思いつかない『こんな考え方アリかよ…』という新発見が待ってます。
日記やブログもいいですよね。誰にも読まれなくても、後で『あれは若気の至り』って笑い飛ばせる黒歴史になります。
もし忙しすぎるなら、あえて『やらないリスト』を作るのもいい方法です。『今月もこんなにサボったぜ!』とドヤ顔すれば、思考に余裕が生まれて新たな発見があるかも。
え?と思うかもしれないけど、脳に余白ができるからアプローチとしてはひとつの正解なんですよ。
ひとりで悩むのもいいけど、ひとりで抱え込みすぎると、『仙人みたいな顔でスマホを眺めるだけの人』になるので要注意です。
信頼できる人に相談すれば、『それ絶対ダメじゃん』ってあっさり切られて新しい視点をもらえるでしょう。



あとは『将来のビジョン』を決めておくこと。
ゴールが分かれば、人生は『壮大なRPG』になります。『よし、勇者の剣を探しに行くか』くらいのノリで、ちょうどいいですよ。それがいい。自分に取っての勇者の剣大事。
③自分の周りの環境を整える
変えられるものは自分自身だけじゃないんですよ。周囲の環境を整えることも大切です。
- 整理整頓した空間を作る:洒落た作業環境やリラックスできる空間を用意することで、集中力が増します。
- サポートを求める:自分の周りの人に理解を得て、取り組んでいる目標について伝えることで、支援や助言が得られます。
④クリアな思考を心がける
変えられるものに集中するためには、自分の思考の質も大事。
- 自分の状態を保つ:気持ちの状態を常に意識する。
- 自己肯定感を育てる:自分が達成したことを意識し、自分を褒める。
自分のコンディションを整えるには、環境を整えるのが一番早いです。『心の平穏』は何より大切。
もし周りがザワついてきたら、無理して耐えずにサッと距離を取りましょう。



これは逃げじゃなくて戦略的撤退だ。
と呟けば、なんだか自分がカッコよく見えてきます。
私の場合は、嫌なことが起きたら『よし、今すぐ良いことしよ!』と切り替えます。コンビニの募金箱に小銭をチャリーン。これだけで心が救われます。



そして、小さくても何か達成したら、『自分、偉すぎる!』と勝手に褒めまくります。周りが褒めてくれない分、自分で盛大に拍手喝采しましょう。
だって、自分で変えられないものを受け入れて、自分に変えられるものを変える努力をし、自分にアプローチをかけながら生きていく覚悟をして行こうとしているあなたって、とても偉いでしょう?
それができない人が何人いると思います?体感で9割ができてないと感じますかね。それ以上かも。変えられるものと、変えられないものの区別すらしようとしないから。
全部変えられる、変わると信じ込んでる。



神かよ。
それができるあなたがいれば、それだけですごいんですよ。
これらのポイントを実践することで、変えられるものに集中し、着実に目標に近づくことができる。自分自身の内面を見つめ直して、行動を少しずつ変えていくことが成功の鍵です。
まとめ
世の中には『自分で変えられるもの』と『どうあがいても変えられないもの』があります。大切なのはその違いに気づき、前者に全集中すること。
自分のことをもっと知って、小さな目標を立てて、それをコツコツ実行してみる。周りの環境もきれいにしてみる。すると、いつのまにか人生が進んでたりします。
そうやって楽しそうにしてると、なぜか周囲まで勝手に変わり始めるんですよ。不思議でしょ?もちろん、中には最後まで『絶対変わんないから!』と抵抗する厄介な何かもいますけど、まあそれはそれ。
そういう時こそ、『もしかしたら変わるかもよ?』という、ゆる~い期待感を持ちながら、『まぁ、ダメでも自分は信じてるし!』くらいの軽いノリで構えるのがちょうどいいと思うんです。
それが、結局のところ『楽しく生きる』ための一番シンプルなコツだったりしますからね。



変わるかもしれないじゃないですか。
この期待をしたいのだったら、変えられないものを受け入れる力が先に必要。
これは、宇宙の法則です。この記事では、これを一番、伝えたいです。
先を変えるために、先に受け入れる。そうなってる。



わかるかな・・・。

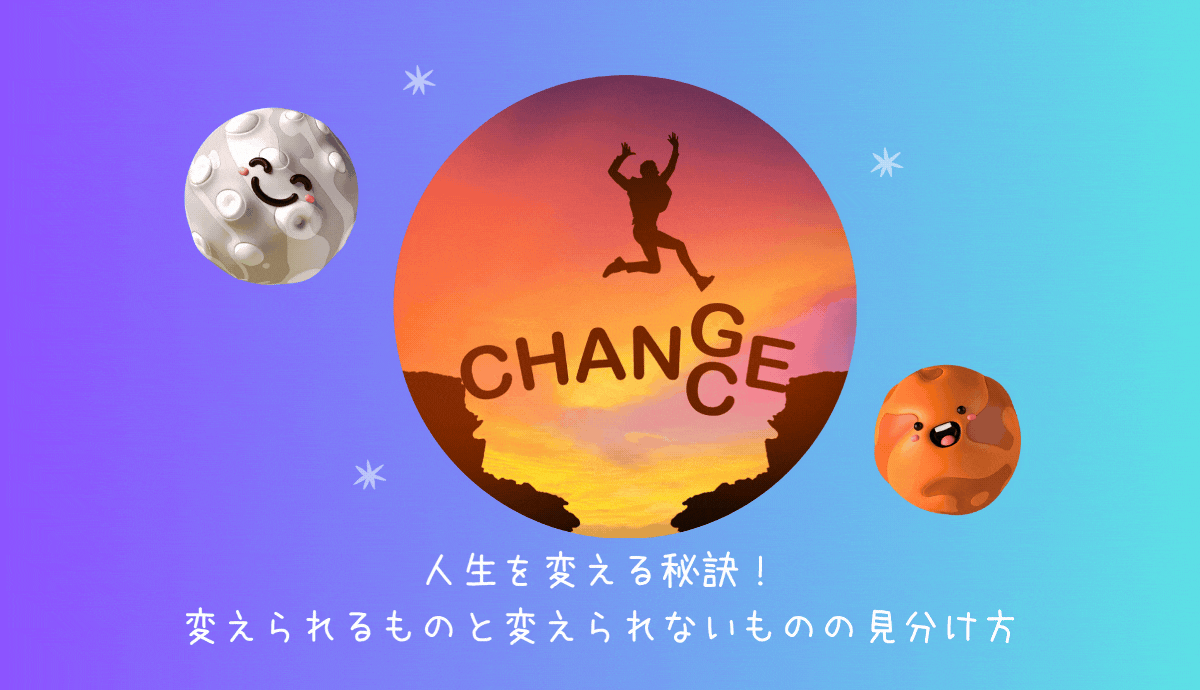
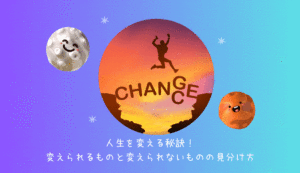
コメント