コミュニケーションって、
人間関係ではめちゃくちゃ大事。
けど、人それぞれ言葉の使い方も解釈も違うもんだから――

え?どういう意味?
ってか、で、何が言いたいの?
……ってなること、ありませんか?
出ました。“含みのある言い方”。
こっちがいちいち読解しなきゃいけない、謎かけスタイルのやつ。
要は、ストレートに言わず、
なんか遠回しに含ませてくる発言。
言葉にダブルミーニングを込めてくるその感じ、正直、わたしはあんまり好きじゃないんです。
いや、けっこう苦手です。
嫌いです。
だって、意図を読むのが面倒だから。
はっきり言ってくれた方が、
100倍ありがたい。
というわけでこの記事では、
わたしが日々『うわ出た、また含み。』
と心の中でつぶやく瞬間に出会った経験をもとに、
その特徴や対処法、
そしてコミュニケーションで気をつけたいことを、笑いとちょっとの毒を交えてまとめてみました。
含みのある言い方の特徴
含みのある言い方って、いくつか共通点があるんですよね。
まず、話し手がストレートに言わない。
本音はある。
でも、なぜか“にじませて”くる。こっちはエスパーじゃないのに。



その言い方、止めろよ……
聞き手は、何が言いたいのか必死で考えるんですよ。
これ、怒ってるの?
頼んでるの?
試されてるの?
クイズかよ!
ってなる。
- 間接的な表現
- 双方向の意味
- 優位に立とうとする発言
① 間接的な表現
含みを持つ人って、どうもストレートに言うのを避けたがるんですよね。
もう直球NG、変化球オンリーみたいなコミュニケーションスタイル。
たとえば――
『この料理は味が薄い』
って言えばいいところを、



昔ながらの家庭の味がするねー
とか言い出したり。
……って、どこの家庭?
聞き手によっては、
『あ、懐かしい味ってことかな♡』
ってほっこりするかもしれない。
でもわたしは、



それ、嫌味だろ?
と疑ってかかるタイプです。
もちろんね、
日本特有の“気を遣う文化”って、
うまく働くときもあるんですよ。
相手を立てたり、場を和ませたり。
でもそれ、使いどころを間違えるとただの“言葉の迷子”。
だから声を大にして言いたい。



含みゃいいってもんじゃないよ。
わたしみたいに、



ん?今のどう受け取ればいいんだ……
って思考停止する人もいるので、
どうか覚えておいていただきたい。
② 双方向の意味
含みのある言葉って、肯定っぽく見せかけて、
実は裏に否定も混ざってたりしますよね?



その服、似合ってるね!
いつもより全然いい感じ!



……それで褒めてるつもりかよ。
〇ケが。



意外と頭いいんだね!



……お前は想像通り、〇カだな。
読まれてるとも知らないで。



意外とちゃんとしてるんだね〜、
見た目からは想像できなかった!



だろうねー。
お前は見た目通り〇カそうだもん。



元カノにちょっと似てる〜!



……誰だよ。
〇〇スぞ。
こういう含み発言、
言ってる本人は
『気を遣ったつもり』かもしれないけど、
受け手としては混乱とモヤモヤしか残らない。
で、気づいたときには地味に傷ついてるという。
いや、地味どころか普通にムカつくときもある。



今は、想像でぶった切って終わりますけどね。
特に、わたしのように“事実はっきり型”の人間にとっては、この曖昧表現、解読不能なんですよ。
嫌いです。
無理です。
何なら、考えること自体が面倒です。
で、今はもう、考えなくなりましたけどね。



ふーん。
で終わるし、その後絡まない。
わたしの脳は、もう含みを解読する余力など残っていない。
③ 優位に立とうとする発言
含みのある言い方って、
実は“マウントのスパイス”が効いてること、多いんですよね。
たとえば上司とか先輩がこう言うんです。



前にも説明しましたよね?



……前にも?
ああ、つまり、
『お前、また忘れたのかよ』
って言いたいんですね?
それ、わざわざ含ませなくても、
十分伝わってますよ。
ありがとうございません。
こういう言い方って、
聞いてるこっちからするともう、
『馬鹿にされてる感・倍増』
『権威押し売り・強め』
『不快指数・メーター振り切れ』。
ていうか、わたしは純粋に不快です。
シンプルにムッとします。
あと、夫婦関係でもありがちですよね
――『〇〇してあげた』ってやつ。
出た、“恩着せがましい大魔王”。
あのですね、人間関係って親切ポイントの獲得ゲームじゃないんですよ。
こういう発言、ほんとに“良心的な関係”をじわじわ蝕む毒。
結果、揉める。だいたい揉める。
含みのある言い方への対処法
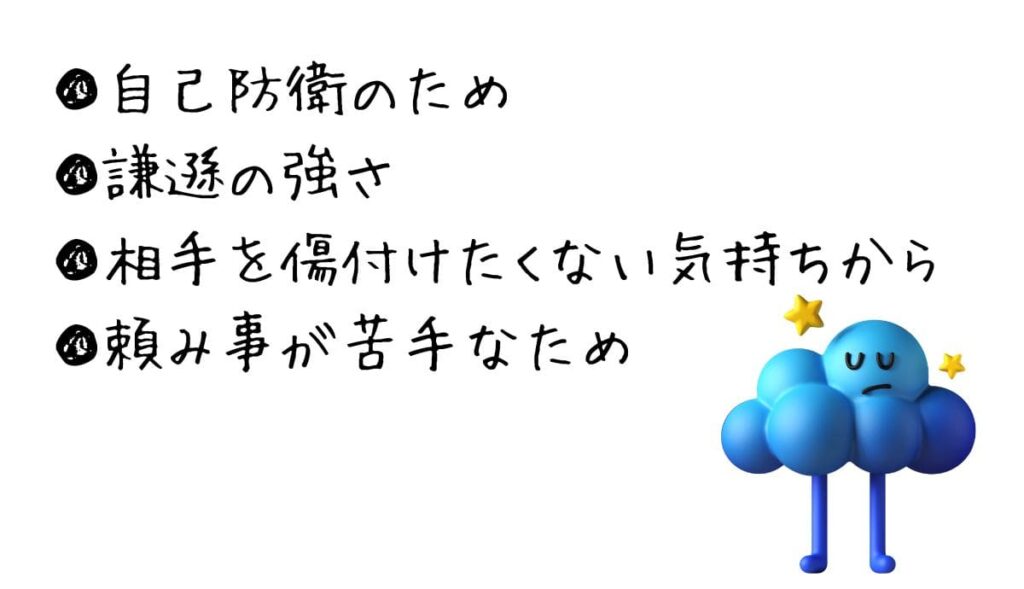
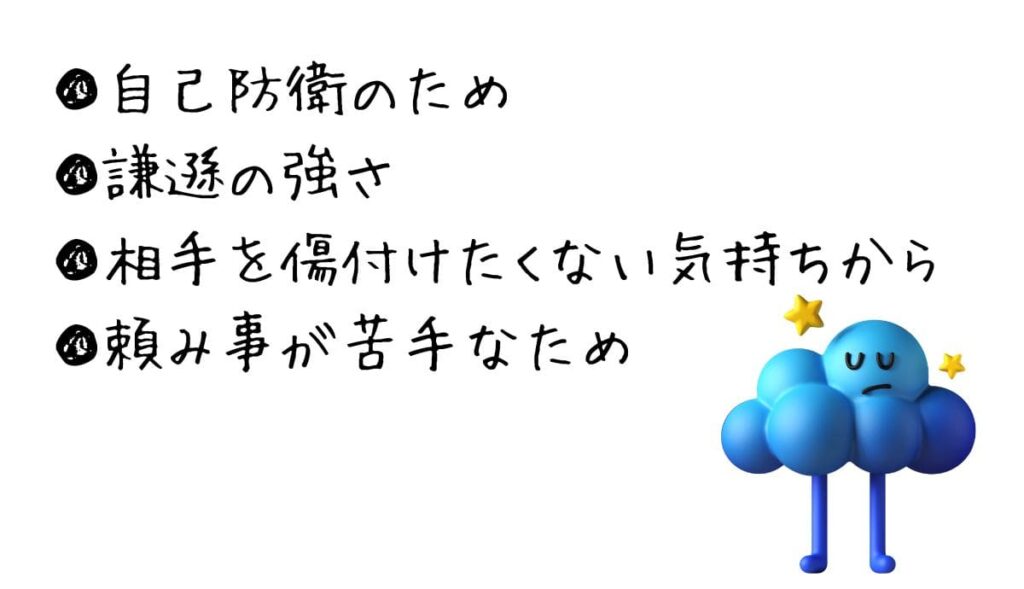
含みのある言い方をされたとき、上手く対処しておきましょう。
そうしないと、人間関係がギクシャクします。



ここでは、いくつかの対処法を紹介します。
- 相手の心理を理解してみる
- 本音で伝える
- 直接聞いてみる
- ポジティブな態度で臨む
① 相手の心理を理解してみる
まず、なぜ相手が含みのある言い方をするのかを一応考えてみます。
その背景には、次のような心理が潜んでいる可能性が考えられる。
- 自己防衛のため
- 謙遜の強さ
- 相手を傷付けたくない気持ちから
- 頼み事が苦手なため
こうした心理を理解することで、
適切な対処法が見えてくるはず、、、はず!!



怠いと思わない限り、一応相手の気持ちに配慮しながら、丁寧な言葉で伝えると敵を作ることはなくなりそうです。
② 本音で伝える
含みのある言い方にモヤっとしたら、
自分の気持ちを正直に伝えるのも一つの手。
いわば、“察して返し”じゃなくて、“言ってみた返し”。
たとえば――



その言い方だと、わたしちょっとモヤるから、できればこういう風に言ってくれたら助かるな〜
みたいに、やんわりお伝えする。
ポイントは、“やんわり”。
こっちがカリカリしてると、



いや、お前の口調の方がこわいわ!っ
てなるので、自分の心の状態が落ち着いてるタイミングでやりましょう。
もう、声のトーンと語尾の柔らかさで印象が全然変わるんですよ。



それ、どういうつもりで言ってます?
って鋭くいくとバトル開始。
でも、



ちょっとだけ気になったんだけど。
って言えば、あらかた平和。
感情って、同じ中身でも
『パッケージ次第で相手の反応が天と地』なの。
マジで理不尽だけど、現実です。
③ 直接聞いてみる
考えるのが面倒なら、もう直接聞いちゃえばいいんです。



それって、どういう意味?
ってね。
わたし、基本的に“察するゲーム”が苦手なので、このシンプル質問法、めっちゃ使ってます。
だって、深読みしてもハズレるし、こっちの脳内ストレージが無駄に圧迫されるだけじゃないですか。
たとえば、『あ、この人たぶん頼みごと苦手なんだな』って察したとき。
たぶん〇〇してほしくて遠回しに言ってるんだろうな…と気づいたとしても、基本スルー。
『知らぬ、存ぜぬ、鈍感力フル装備』で対応します。



というのも、わたし自身は頼みたいことがあるときには、ちゃんと口に出してお願いしたいタイプなんですよ。
だから、同じように『言ってくれる人』が好きなんです。
それだけの話。
でも、たまにいますよね。『お願いしたいけど…気まずい…言えない…』ってタイプの人。
そういうときは空気を読んで、優しさスイッチONにして、



わたしにできることある?
って聞くようにしてます。
気分はもう、鈍感と気配り、両方のスキルを搭載したマルチタスク型人間。
④ ポジティブな態度で臨む
含みのある言い方――
つまり嫌味ボンバーを投下してくる人には、
こっちが先にポジティブでいた方が勝ち。
だいたい『あーはいはい、たぶん〇〇って言いたいんでしょ?』って察しても、スルーが正解。
ガン無視でOK。



知らねー、知らねー、気づかねー、てか聞こえねー。
ぐらいの精神で、笑顔でお付き合いしましょう。
忍耐力っていうより、もはやスキル。
それが難しいときは、
ここまで↑で紹介した対処法がわりと効きます。
わたしは、愚痴には同調せず、やんわり距離を取りつつ警戒モードで接します。
でも、表向きはしっかり目を見て、にこやかにご挨拶。
すると、なぜか嫌味が言いにくくなる。
不思議ですねーー(棒読み)。
あと重要なのが、
『自分の態度が原因かも?』と思ったら
、一応そこはチェックする。
態度に問題がある=嫌味言われて当然、
ではないけど、直せるところは直しとく。
嫌味しか伝え方を知らない人は、
それはもう“器のサイズ”の問題なので、
こっちはこっちの課題だけちゃんとやればOK。分離、分離。


職場でのコミュニケーション
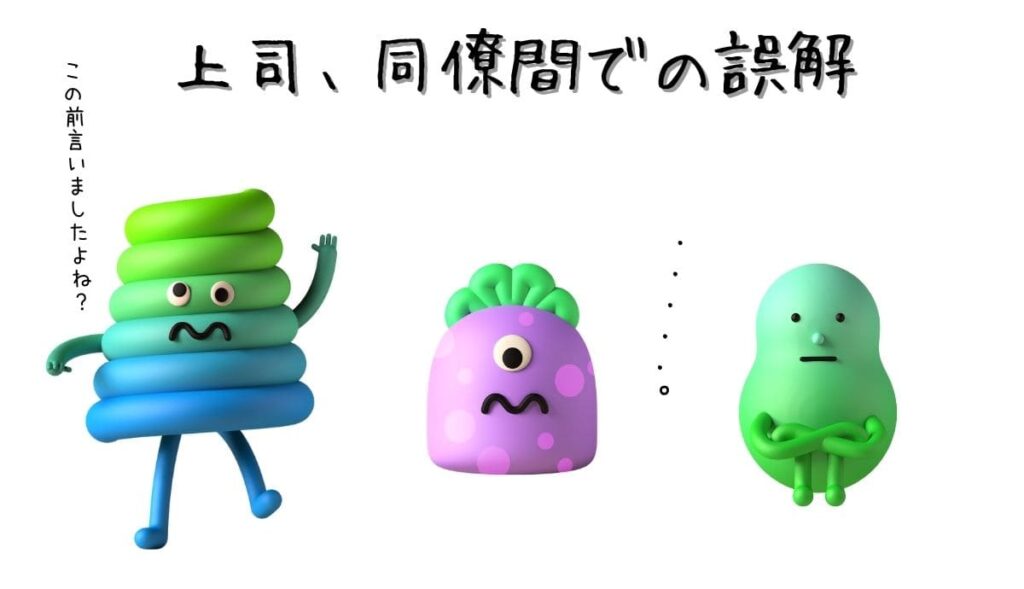
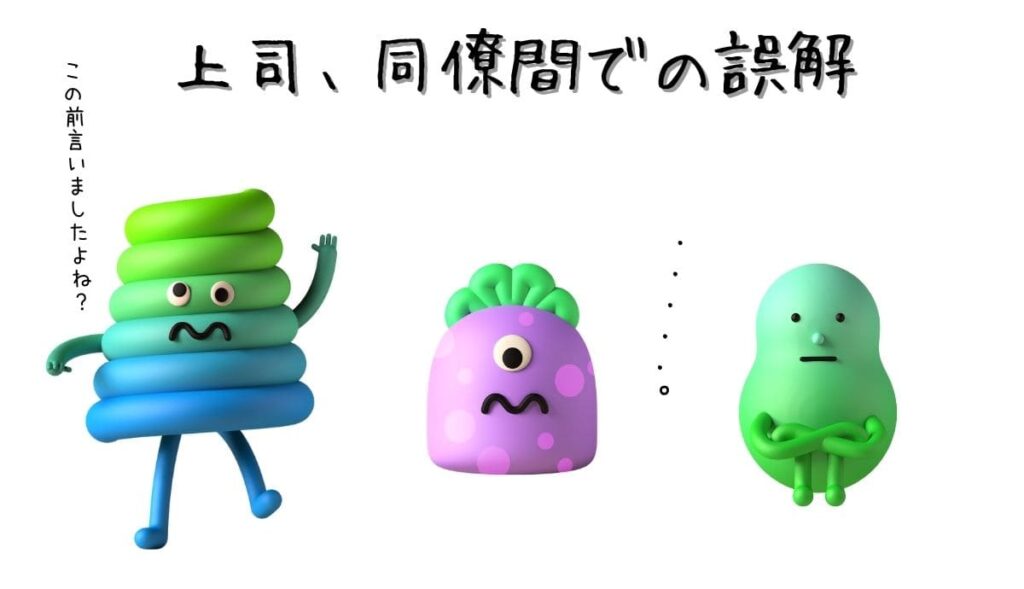
職場のコミュニケーションって、上司とも同僚とも、うまくやらなきゃいけないんですよね。
ほんと、毎日が人間関係マネジメントゲーム。
でもそこに『含み』のひと言が入るだけで、
一気に難易度ハードモード。
だって、自分の意図どおりに伝わるなんて、
もはや奇跡じゃないですか。
期待しすぎ。
『いや、それ、どういう意味で言ってます?』
って心の中で3回ぐらいリプレイして、ようやく、



うーん、たぶん嫌味……認定かな?
って結論に至る。
疲れるんだよ。
- 上司からの含みのある言い方
- 同僚間のコミュニケーション
① 上司からの含みのある言い方
例えば上司から、半笑いで
『そんなことも知らないの?』
『前にも一度言ったけど、、』
といった前置きのある発言をされたりすると、
自分を馬鹿扱いされているような気分になりませんか?
ならない人もいるかもしれません。
そんな人はきっと↓こっち側でしょう。



言い方も知らない程度の低い人間が。
実は、わたしは全然こっち派。
結局、いい気分はしないですよね。
こんな言い方は、嫌みな説教でしかない。
また、
『さすがお局さん(ばかでしょ?デリカシーの欠片も無い)』
『期待してますよ(どこ目線?)』
といった、本音の伝わりにくい言葉も存在しますよね。
こんなもん、確実に嫌味にしかならない。



言い方も知らない程度の低い人間が。
こーんな言葉使っていると、
部下は上司に、基本的に不安感や緊張感、
猜疑心しか持たれません。
② 同僚間のコミュニケーション
同僚との会話でも、
『察して…』みたいな含み言葉が飛び交うと、
だいたい空気がピリつき始めます。



伝わる前提で“ふんわり投下”してるのかもしれないけど、あれ、美徳でも何でもないですからね。
単に伝わりづらい爆弾。
ぶっちゃけ、含みのある言い方なんて、
いらないと思うんですよ。
言いたいことがあるなら、はっきりどうぞ。
だって、遠回しに言って
『察してくれるはず』
って、そんな期待、エスパー業界でもきつい。
経験上、やっぱり大事なのは思いやりと建設的な言葉。
別にきれいごと言ってるんじゃなくて、
『そっちのほうが人間関係ラクだし楽しいよね』っていう、実感。
で、問題はここですよ。



その“含み”って、誰のため?
相手のために含んでるのか、
自分のために含んでるのか。
ね? たいていは、自分のためでしょ。
だから嫌味に聞こえるんですよ。
『含まないと伝わらないこと』は、
そもそも言わないほうがいいか、
もっと考えて言い直すべきじゃない?って話で。
“思いやり”って、別にオブラートを50枚重ねることじゃないと思うんです。
むしろ、『やたらと遠回しじゃないけど、ちゃんと誠意のある言い方』のほうが、よっぽど伝わるし、心に残ると思うんですよね。
まとめ
日本人のコミュニケーションって、『言わなくても察してください』みたいな謎解きゲームが多い。
でもこれ、意図が当たれば『おぉ…エスパーかな?』だし、外れたら『いや、そっちか!』ってなる。
正直、わたしはこの言葉の裏の裏の裏を読め!
文化、ダルイ派です。
『その言い方、もしかして怒ってる?』
『いや、逆に褒めてるの?』
って、毎回“気持ちの読解クイズ”が開催される。
脳内に司会者が常駐してる気分。
ただ、幸いにも、今のところ自前の
『なんとなく察するセンサー』と
『とりあえず笑ってごまかすスキル』で、
生き延びてきました。
でも、やっぱり
『ハッキリ言ってくれたら100点!』
って思うわけです。
とはいえ、『相手の気持ちを思いやる』
ってのは大事にしたい。
だから、できればこう…
含み言葉バトルじゃなくて、
素直に言っても怒らない安心な空気で付き合えたら、もうちょっと世界は平和になるんじゃないかと、密かに願ってます。

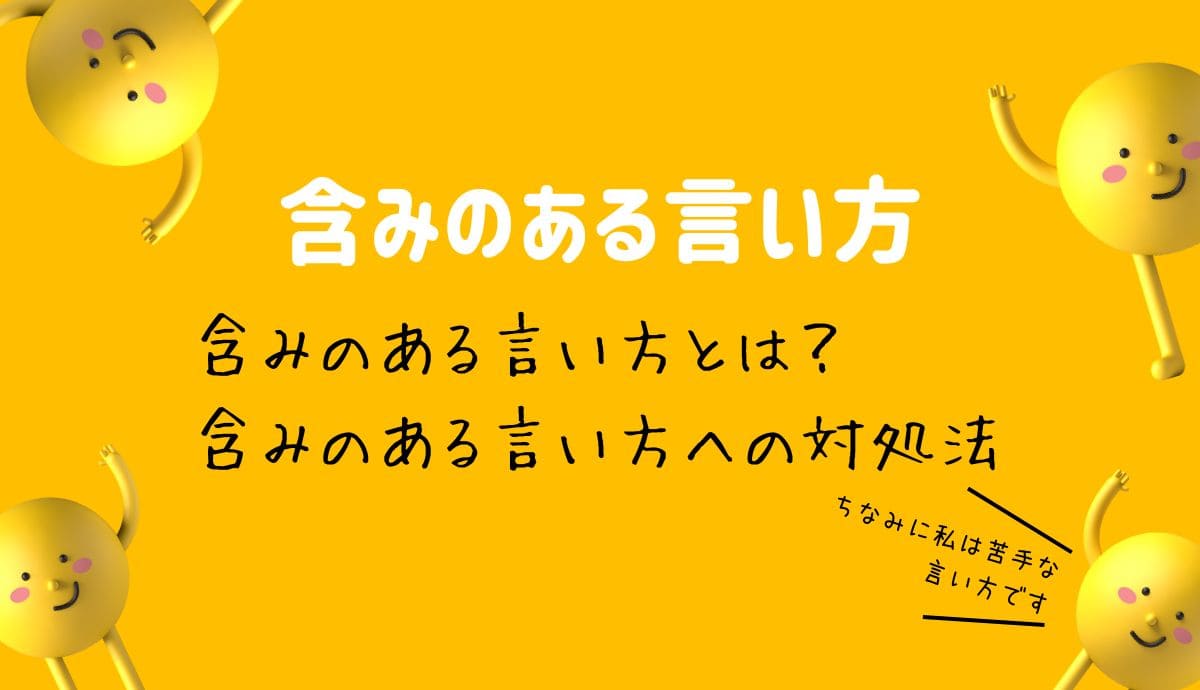
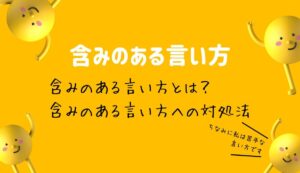
コメント