小学校4年生で習う『一つの花』。
以前、ごんぎつねの記事を書いたときに『一つの花』にも言及があったから(記事内にあります)気になってまとめてみました。
今回読む物語『一つの花』の主人公・ゆみ子は、実は小さなころから「一つだけ」が口癖。戦争で食べ物が不足し、お母さんは「一つだけよ」と言い聞かせながら、ゆみ子に食べ物を渡す。「一つだけ」という言葉は、我慢を強いる制限の言葉なんだけど、同時に「それでも何かを食べさせたい」というお母さんの必死な愛情の表れでもある。
やがて父が出征する日、ゆみ子は父の持っていたおにぎりをねだり続け、最後には全部食べてしまいます。困った父がゆみ子に渡したのは、プラットホームの端、まるでごみすて場のようなところに、忘れられたように咲いていた一輪のコスモスの花。
「一つだけあげよう」――そのとき「一つだけ」は、我慢を意味する言葉から、“命の唯一性”や“かけがえのなさ”を伝える言葉へと変わる。
心理学で言うと「認知の書き換え」に値するんじゃないかと思う。
今日は、この「一つだけ」という言葉が、物語の中でどう意味を変えていくのかを考えてみたいと思います。
一つの花↓置いときます。
一つの花=騒いだ罰、=お金儲け
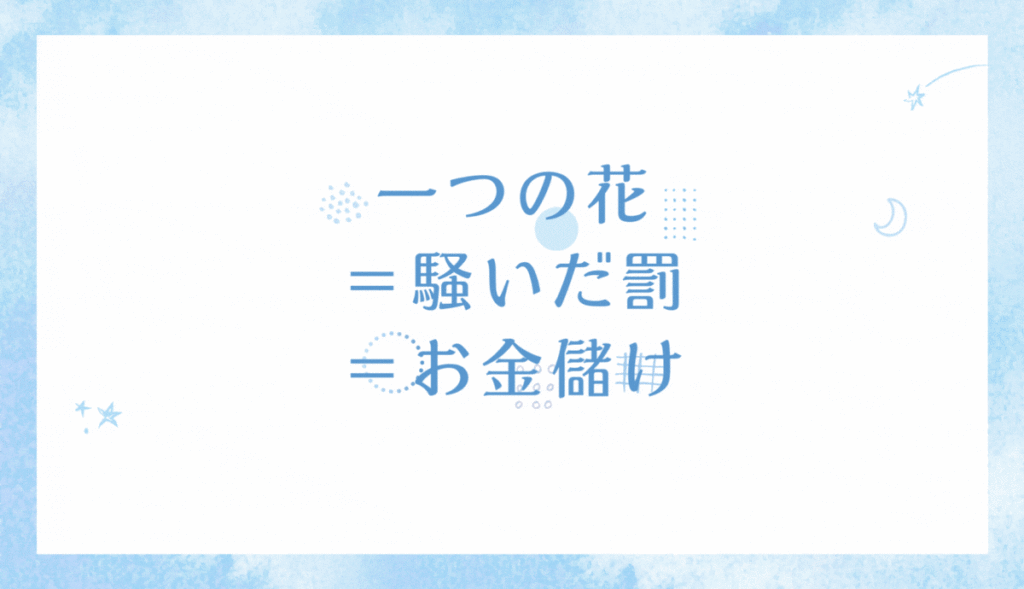
校長によれば、この物語を生徒たちに読ませ、父親が駅でコスモスを一輪あげた理由を尋ねると、次のような回答があるという。
「駅で騒いだ罰として、(ゴミ捨て場のようなところに咲く)汚い花をゆみ子に食べさせた」
「このお父さんはお金儲けのためにコスモスを盗んだ。娘にそのコスモスを庭に植えさせて売ればお金になると思ったから」
作中には、父親がコスモスを渡した時の心理描写はないが、登場人物の立場に立ち、状況や背景を踏まえれば、行間から父親の気持ちを想像できるだろう。だが、一部の生徒たちはその力がないので、父親の悪意や欲望を描いた作品だと受け取ってしまう。二〇二二年二月八日の朝日新聞朝刊でも、この物語の誤読問題が取り上げられているので、特別な例ではないのだろう。
- 「誤読」とは言えるのか?
- 罰の解釈=教育習慣の投影
- 金儲けの解釈=実利主義の投影
- 読解力の問題ではなく「想像力の偏り」
- 教育の慣れの果て?
- フレーム枠を渡してあげたらいいんじゃない?構造化説明
① 「誤読」とは言えるのか?
たしかに文章としては「父は娘に花を託した=愛情や命の象徴」と読むのが作者の意図。だから、罰や金儲けという解釈は「本文に即していない」ので、国語的には「誤読」と分類される。
② 罰の解釈=教育習慣の投影
子どもが「騒いだ罰」と答えたのは、
- 学校や家庭で「悪いことをしたら罰を与えられる」という教育を受けているから。
- だから「大人が子どもに物を渡す=罰やしつけの延長」と自然に読んでしまった可能性。
これは「子どもの読解力の問題」ではなくて、「社会や教育習慣が子どもの想像力を制限している」ことの表れとも読めるかもしれない。

冗談かもしれないしね。それを真に受けた可能性もある。けれど、ニュースにまでなっているところを見ると軽視もできないのかもしれない。
③ 金儲けの解釈=実利主義の投影
「コスモスを庭で増やして売る」という発想は、現代的な実利主義の反映。
- 子どもたちの生活環境に「お金」という価値観が強く浸透している。
- そのため「花を渡す行為」を“経済的行動”に直結させてしまう。これもまた、社会が子どもの「物語の意味づけ」を決めてしまっている例とも見える。
④ 読解力の問題ではなく「想像力の偏り」
だから私は、この現象を「誤読」よりも「想像力の偏り」と捉える方がしっくりきます。文章を正しく理解できないのではなく、読み取るレンズが“罰”や“金銭”に偏っていただけ?あと、読解力の乏しさ・想像力の欠如と説いた方も、そう見えるけどね。背景にあるのは、教育や社会が刷り込んだ価値観とも思えなくもないでしょ。
⑤ 教育の慣れの果て?
「罰で子どもを統制する」教育 → 子どもは行為の意味を「罰」と結びつける。お金 → 子どもは花でさえ金銭的価値に還元してしまう。
「国語力の低下」じゃなくて、社会の価値観が子どもの読解に浸透してしまった結果だと考える方がしっくりくるのかもしれない。
この誤読問題の記事が新聞で取り上げられてるということは、これは特別な偶然ではなく、比較的「普通に起こりうる現象」なんだろうなと思う。だって、わたしが記事にした『白いぼうし』『ごんぎつね』『セロ弾きのゴーシュ』だって、誤読されているようだし、大人だって読めていないのが現実だ。
子どもの読解や物語の意味づけは、必ずしも作者の意図通りには動かない。というか、子どもたちは自分の経験、価値観、家庭・社会での教育のバックグラウンドを持って読み解くから、それぞれの“ズレ”が生じるのは当然かなとも思える。
それを「誤読」というラベルで片づけるのではなくて、読み方の幅・社会的背景・教育のあり方を考える入り口として使う方が、むしろ建設的だと思う。
わたしからしたら、



じゃぁ、『セロ弾きのゴーシュ』、お前が説明してみろ。
こうなるだけだ。トマト云々言った時点でどうなるか….
⑥ フレーム枠を渡してあげたらいいんじゃない?構造化説明
父親がコスモスを渡した時の心理描写はないが、登場人物の立場に立ち、状況や背景を踏まえれば、行間から父親の気持ちを想像できるだろう。だが、一部の生徒たちはその力がないので、父親の悪意や欲望を描いた作品だと受け取ってしまう。
父親がコスモスを渡したときの心理描写は本文にないですよね。だけど、登場人物の立場に立って、状況や背景を踏まえれば、行間から父親の気持ちを想像することは可能ではある。
ところが、一部の生徒にはその力が十分に育っていないから、父親の行為を「悪意」や「欲望」に結びつけて解釈してしまう。
本来、ここは生徒たちに「父親の心理を想像させるべき箇所」なんだけど、戦争を知らない子どもたちにとって、ゼロから想像を膨らませるのは容易ではないでしょ。現実の人間関係であっても、他人の悲しみをその人の立場になって完全に理解することは難しいじゃないですか。
だからこそ、あらかじめ「想像のための枠組み」を渡してあげたらいいんじゃないの?とも思える。今の教材が提供しているのは――
- 家族と離れて、戦争に行かねばならない父
これだけでしょ。これでは「父親がなぜ花を渡したのか」の想像が現実味を帯びない。
そこで、例えば以下のような事実をフレームとして与えてから考えさせれば、子どもたちはより深い想像へと進めるかも?
想像のための枠組み(当時の背景)
- ゆみ子の「一つだけ」という願いが将来に影響しないかを父が気にかけていたこと
- 戦争とは、国から「行け」と命じられれば選択権なく従わなければならなかったこと
- 体が弱くても、戦えると見なされれば徴兵されたこと
- 食べ物にも事欠き、生きるのがやっとの時代であったこと(そんな時代に「花」は買わないでしょ)
- 父が戦地から無事に帰ってこられる保証はなく、命を落とす可能性が高かったこと
当時の価値観・空気
- 別れ際に「万歳」と叫ばれていた。
- それは「お国のために戦える英雄として選ばれた」という意味合いを持ち、命を落とすことさえ“美談”として描かれている。
こういう具体的背景を枠組みとして渡すことで、子どもたちは「罰」「お金」といった身近な解釈ではなくて、父親の悲しみや不安、家族への愛情に想像を広げることができると思うんですよね。



教科書にある「万歳」。この「万歳」ってさ、子どもにとってみたら謎だよね。嬉しいときにしかしない現代の意味する「万歳」が、命を落とす危険があるときに「万歳」しているんだから。「万歳」の意味説明は必要だと思う。この「万歳」が喜びを象徴しているかのような描写だから。ある意味「喜び」だけど、それは「洗脳」とも言える。
だって、あの「万歳」、戦争を知らないわたし達には、理解不能でしょ。「万歳」を現代の意味で解釈したのなら、何か楽しいところにでも行くのかな?という子どもが出ても不思議じゃないよ。なら、「罰」とか「お金」などという、安易な解釈となっても、ある意味整合性が取れるよね。
で、うちの子に聞いてみたんですよ。



「万歳」ってあったじゃん?あれ、楽しいところに行くのかな?って思った?



思った。けど、楽しいところでもないみたいだな…とも思った。



物語自体がさ、軽くならない?ふわっと。深刻さが消えない?



あー、消える。



説明あった?この描写の。



何にもない。
全部説明したら、



(洗脳)キモ‥‥
ここまで読み解くと、見えてくる根っこがある。「罰」とか「お金」と回答した子どもへの説明は足りてたの?ていうね。「戦争=ゲーム」の連想が無いとも限らないじゃない。完全にはそう思っていなくても、すぐ生き返ることができる、バトルゲームとか色々あるでしょ。感覚が軽くなるよね。案の定、説明が足りてない現実もあった。



疑問に思ったらしいけど、聞かなかった(聞けなかった)らしい。まぁ…わかるよ。だから、だとしても、言い訳にはならないよ。帰ってから、わたしに確認するくらいじゃないとダメだって注意はしたけどね。
- 「天皇陛下万歳」 が元のかたちで、天皇や国家への忠誠を示す掛け声
- 戦地に赴く兵士を「お国のために命を捧げる英雄」として送り出すときに唱えられ、本人にとっても家族にとっても「名誉」「誇り」として美化されていた。
- その背景には「命を落とすことすら国のためなら喜ばしい」という価値観の強制があった。
そこから、



命がどうなるか分からないし、もう最後かもしれない。そういうときに、笑って笑顔で別れたいと思う?泣いて別れたいと思う?
そう聞くのも一手だろう。
父の心情を想像する手がかりになる。
ゆみ子が我がままを言っていると思っている生徒がいるから、「罰」という発想が出る。
笑って別れたいじゃない。最後かもしれないんだもの。子どもの笑顔、見ときたいじゃない。もう、戦地で死んじゃうかもしれない、そんなとき、泣いてる顔見たい?子どもだと想像し難いなら、じゃぁ、相手がお父さん、お母さんだったら?せめて、笑顔でって思えない?
別れ際に父親が涙を流せば、私は「父を戦地に行かせた国」を強く恨んだかもしれない。人が家族と別れ、泣きながら戦地へ向かわねばならない。それは、残された者にとっても、送り出す者にとっても、あまりに辛い現実だ。
そっから考えると、「英雄」と結びつくマインドコントロール的なものは、当時からあるだろうし。じゃないと、反乱が起こる。元々心理学は、人を操作するために生まれたものだから。現代はね、支援と自律の道具にもなってるけどさ。
- 戦況が不利でも「勝っている」と報じる。人々の不安を抑え、士気を高める典型的なプロパガンダ。
ただし、どの程度「虚偽」であったかは研究によって幅があるので、真実かどうかは史料のみで断定できない。 - 『ハワイ・マレー沖海戦』(1942年)などの戦争映画で、実際には誇張や演出を含み、「日本は強い」という物語を国民に刷り込む。
- 「欲しがりません勝つまでは」「一億玉砕」などは、群衆心理を利用して個人の欲望や不満を抑圧、「全体のために」という気分にまとめた。
「群衆心理を利用した」という分析は社会心理学・歴史学の研究に基づくもので、史料そのものが直接そう記しているわけではない。 - 子どもたちに「天皇陛下の赤子」としての役割を刷り込み、戦地に向かうことが“最高の名誉”だと教えた。
ただし、「最高の名誉」との直接表現は時代の空気や教育政策全体からの分析、教科書本文に明言されているとは限らない。
こういう書き方をするとさ、私は、さぞ家族仲が良かったのかもしれないと思われるかもしれない。だから想像できるんだろうと…真逆だ。もし自分がその場にいたなら……と考えることで、父親の気持ちを想像してる。私は父親とも仲が悪かったし、良好な関係とはほど遠かった。それでも「戦地へ赴く」という事実そのものは、胸をえぐるように辛いだろうと想像できる。
補足説明すると、登場人物の発言と行動だ。そこから読み解く、それだけだ。こういう行動と発言がある人のやさしさは….こう考える。思考、発言、行動、この一致を見れば、あらかた想像できるものがある。ゆみ子の父親の言動で一番印象に残ったのは、「ひとつだけ」を気にしてるところ。そして、それを払拭する高い、高いだろうね。決まってしていた….とあるから。普通、気にしないものだから。あぁいうところに、気が付く人のやさしさは深い。
発言というものは、その人自身を表す。



自覚的であってもなくても、わたしには関係がない。見抜けるから。余裕だ。例えばだけど、自己保身なんて朝飯前だ。話の前後、ロジック見れば一発で崩壊だ。どんな言い訳も通用させない。けど、背景(弱さ)は見る、「命」に係わるときには、見ない。
そこからの、
私ならどうするだろう…..私がこの人(父親)なら…→「認知の書き換え」をする。
そう思ったから「ひとつだけ」の書き換えをしているんだろうと思った。



推理小説みたいになっちゃって、お前のせいで台無しだよっ。



って言われるかもしれないけど、それはごめんなさい。だけど、わたしの脳内だから。読み進めて、一輪のコスモスを「一つだけ」として渡す父親の秀逸さよね。フラグのすごさよ。
「国のために行くんだ!」と万歳をして見送る場面が描かれている。選ばれて戦地へ行くことを「英雄」とみなさなければ、自分たちの心が押しつぶされてしまう。そうとも考えられる。何がお国のためだ….そうした時代背景を踏まえれば、父親が娘の「一つだけ」を叶えてあげたいと願った気持ちが、より切実に感じられるかもしれない。



だから、ゆみ子の「一つだけ」を叶えているんだと思う。あの場面からは、やさしさしか感じられないから、そう考えさせる術も必要だと思うわ。本題とは関係ないけど、ぼーんやり生きると、まんまと操作されるよね。構造くらいは見抜きたいよ。情弱者は刈られるし、自覚的でないと、人生はどんどんぶれるよねぇ。
「一つだけ」という制限の始まり
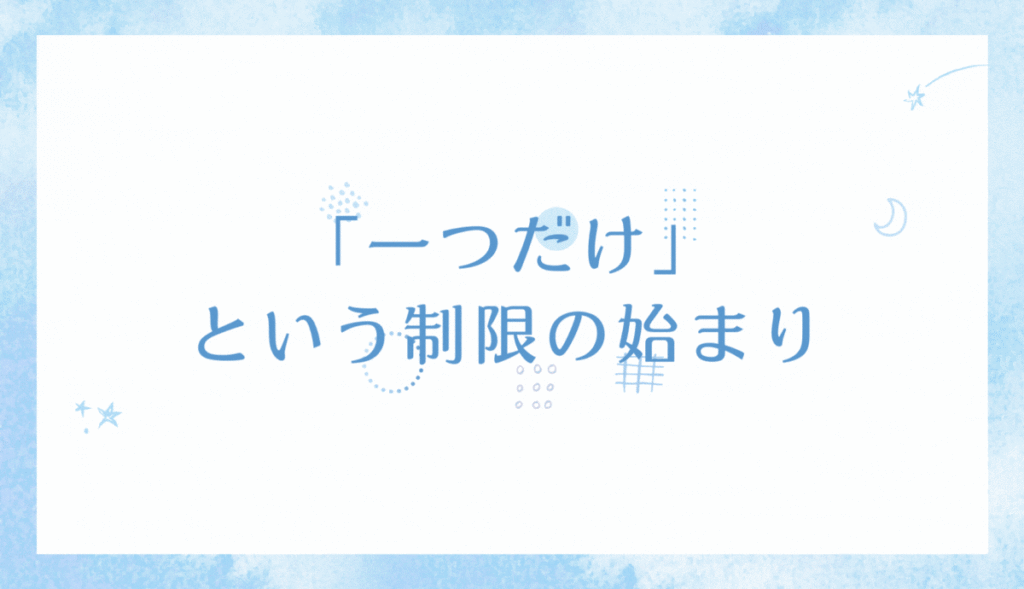
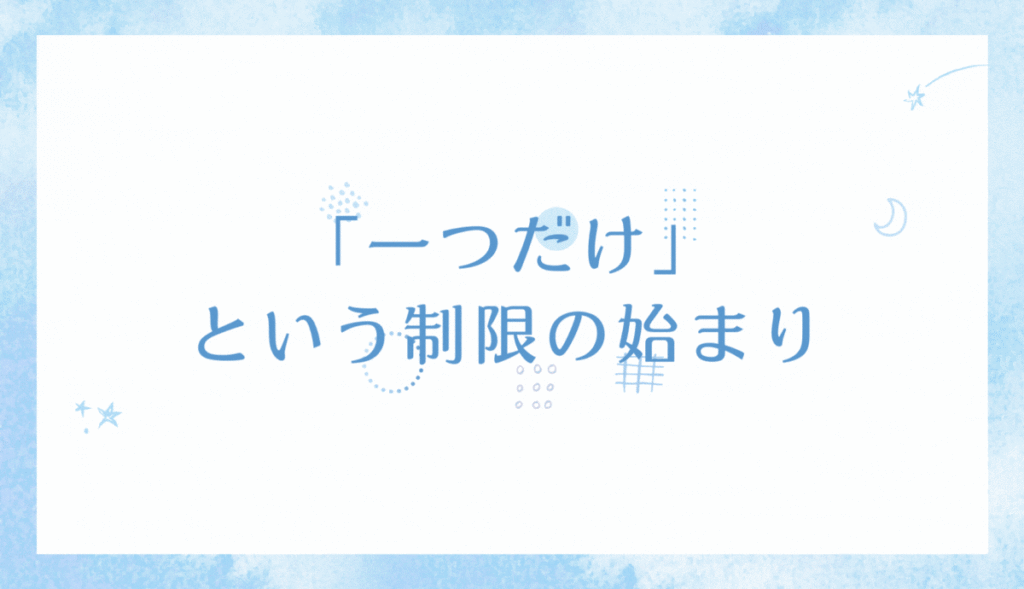
- 戦時下の「一つだけ」―欠乏と不憫さの象徴
- 母が与えた「一つだけ」に込められた愛情
① 戦時下の「一つだけ」―欠乏と不憫さの象徴
お腹がすいても、お菓子もお米もない時代。
「一つだけね」という言葉は、本当は愛の言葉じゃなくて、“もうこれしかあげられない”という現実の苦しさの表れでもある。
子どもの欲求と、大人のやりきれなさが同居する、ちょっと切ないフレーズ。
② 母が与えた「一つだけ」に込められた愛情
でも、その「一つだけ」は冷たさじゃない。
母は「ない」中から、なんとか「一つだけ」を絞り出して与えている。つまり、“制限”の裏には、「この子に食べさせたい」という必死な愛情が隠れているように思える。欠乏と愛情、二つの意味を背負った言葉が、ゆみ子の口癖になっていってます。
父が「一つだけ」を変換する
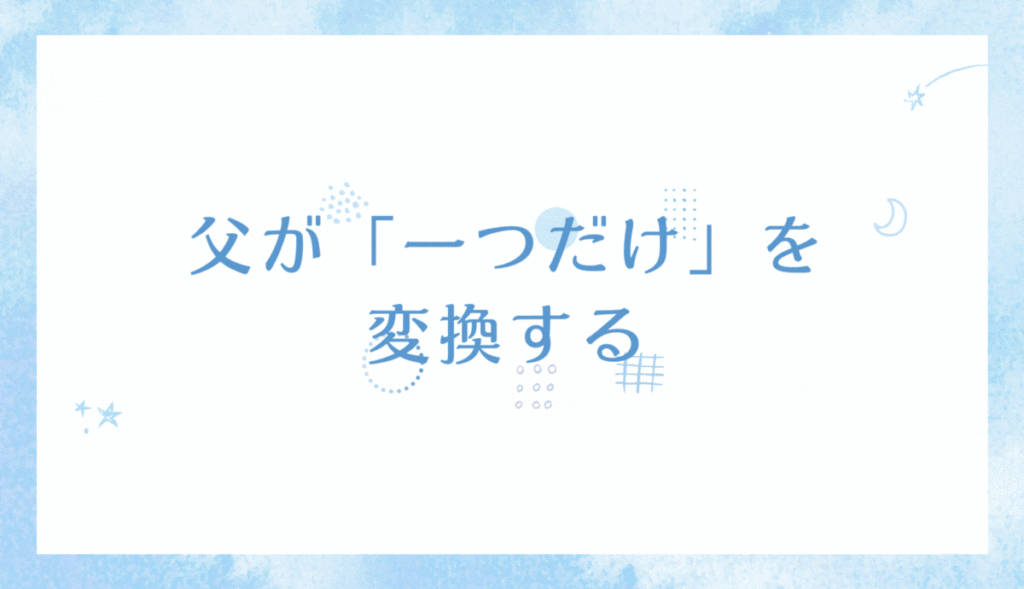
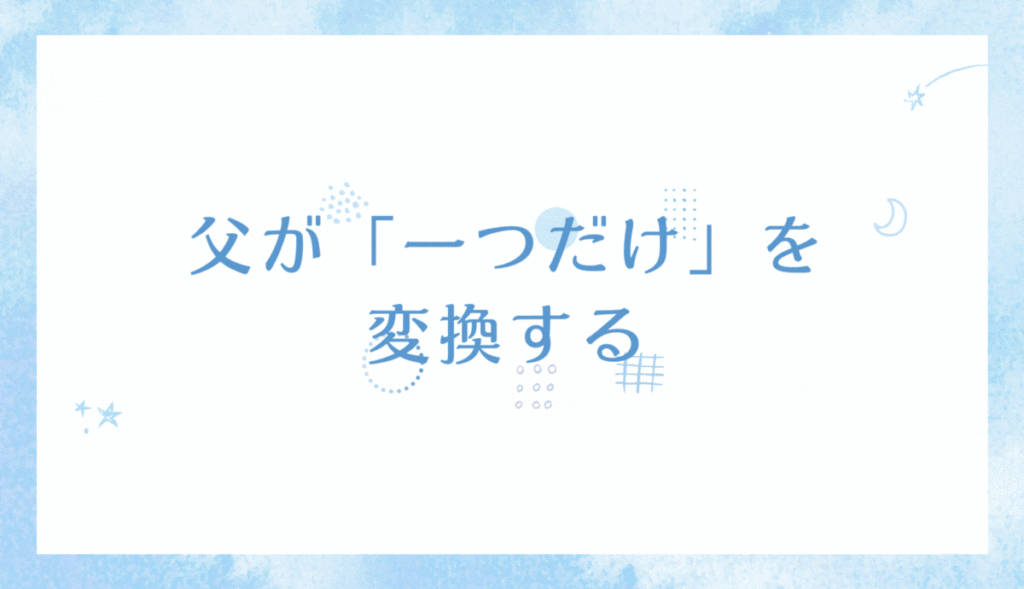
- 欠乏の言葉をそのまま残さない知恵
- 「一つだけ」が命・愛情・花の唯一性に変わる
① 欠乏の言葉をそのまま残さない知恵
戦地に向かう父は、「一つだけ」という言葉が、このまま“我慢の記憶”で娘に残るのを恐れてますよね。
お父さんが、深いため息をついて言いました。「この子は一生、みんなちょうだい、山ほどちょうだいと言って、両手を出すことを知らずにすごすかもしれないね。みんな一つだけ。一つだけの喜びさ。いや、喜びなんて、一つだってもらえないかもしれないんだね。いったい、大きくなって、どんな子に育つだろう」一つだけのイモ、一つだけのにぎり飯、一つだけのカボチャのにつけ・・・・・・。 そんなとき、お父さんは決まって、ゆみ子をめちゃくちゃに高い高いするのでした。
だから最後に、父は考えたのかもしれない。
「この言葉を、ただの“足りない”じゃなくて、“生きる指針”にして渡してあげたい」と。
「一つだけ」を不足から来るものではなく、愛情に変え、それをコスモスに乗せた。
高い高いも、ゆみ子から、そういう思いを吹き飛ばしているようにも読める。こういう足りないからくる「一つだけ」をかき消す、高い高い。ごまかしだけど、愛情だ。
これは、命を賭けて旅立つ父が残した、最大の知恵とも読める。



ただ、この言葉の文中での「意味の変化」に気づかせることに重点を置く教育が多そう、それって意味あるのかなぁとも思う。意味なくはないんだろうけど、もっと掘りたくなるのが私。
「一つだけ」から考えられる弊害
- 欠乏感のデフォ化
常に「足りない」「一つしかもらえない」という意識が根づく。
→ 成長しても「豊かさを受け取る権利」を自分に許せず、満たされても不安を抱きやすい。 - 欲求表現の萎縮
「両手を差し出すことを知らず」とあるように、欲しいと望むこと自体を否定されてしまう。
→ 大人になっても「遠慮が常態化」、自己主張や挑戦を避ける傾向が出る。 - 喜びの縮小となった場合
幸せや喜びに対する期待値を極端に下げる。
→ 自己評価が低くなり、人生に対して諦めやすくなる。 - 承認欲求のゆがみ
「一つしかもらえない」前提で育つと、人から認められることを過度に希少価値化し、承認に飢えたり逆に無関心になったりする。



ざっと説明するとだよ。考えられる要因たち。
こう考えると、戦争の弊害って世代間で連鎖し続ていると言っても過言じゃないと思う。現代でも尚、代々継承されてるんじゃないの?というのがわたしの一つの見解だ。
みんな気づかないまま、継承されてるのが現代でしょ。「欠乏の渇望」として未処理のまま現代に流れている。ゆみ子が、その連鎖を絶てたのかどうかは、分からない。なぜか?それくらい、この戦争における弊害は根深いんだよ。あるものがなくなる、その状態でどう支え合えるか?人が心に抱いた悲しみは、ありとあらゆる渇望と姿を変え、継承されてると思うよ。気づくの大変だって。
ちなみに、わたしは多分、気づけたよ。気づいたけど、それは私の課題じゃないしね。気づこうと思って読書をしたワケじゃない。色々学んでいったら、そこにも辿り着いた、そんな感じだ。だから、わたしは継承を絶つことにした。
わたしが読むとき※「父の意図」を掘る面白さ
ある程度の人生経験や読書経験を持っていると、登場人物の「心の裏側」や「行間」を読むことが面白いんですよね。
- 父は本当に「一つだけ」の意味を意識して変えようとしたのか?
- 娘に未来を託す意識があったのか?
こういう「人物の意図」を掘ることで、物語をより深く味わえるじゃないですか。「解釈の広がり」とか「思想的な深み」が面白さになる。わたしはそれが楽しくて仕方がない。
授業で扱うとき※「意味の変化」に気づく価値
「登場人物の意図を探る」よりも、「同じ言葉が物語の中でどう変わるか」を体感することを重点的を置く教育って…
- 最初の「一つだけ」=欠乏・我慢。
- 父が花を渡すときの「一つだけ」=命の唯一性・愛情。
- 10年後に広がった花々=豊かさへの変換。



こうした言葉の変化を読み取る力は、国語教育の根幹なんでしょうけど、面白い?これ。
- 大人にとって → 父の意図を深読みすることは、思想的・文学的な面白さ。
- 子どもにとって → 言葉の意味の変化に気づくことが、読解力や言葉への感受性を育てる教育的な意義。
「父が言葉を変換して託した」という“教え”を受け取った子と、単に「言葉の意味が変わった」と授業で教えられただけの子。その違いを考えてみたんですよね。
単に「言葉の意味が変わる」と教えられた子
- 学力的には「言葉の意味は文脈で変わる」という理解は得られる。
- でもそれは知識や技術の習得にとどまりやすい。
- 「一つだけ」が欠乏→愛情→豊かさ、と構造を学んでも、それを自分の生き方に重ねる回路は弱くなる。
- 結果、「テストで答えられる」子にはなるけど、「人生で言葉を支えにできる」子にはなりにくい。
この物語の読解は得られるでしょうね。ただ、これを社会で活かそうとして、どう生きるか問うたときに、何の実践にもならないのかな?と思える。
「父が欠乏の言葉を愛情の言葉に変えたのかも…」と教わった子
- 学ぶのは単なる意味変化ではなく、言葉が人の思いによって生まれ変わる力。
- 「言葉はただの道具ではなく、状況を変え、生きる力にできる」と体感できる。
- 人生で困難や制限に直面したとき、
→ 「これも見方を変えれば愛情や希望に変えられるかもしれない」と発想できる。 - これは生きる態度や自己解釈力に直結する。
わたしは、こう思えるんですよ。
前者=「言葉の仕組みを知っている人」
後者=「言葉を現実に活かせる人」
特に日本の教育では前者が多いんでしょうね。この物語でどうか?という訳じゃなくて、全体的にふわっとした授業多いですもんね。ぼんやりしていて、子どももぼんやりしていく….結局、あれ何だったの?みたいな。
でも後者のように「言葉を心の支えに変換できる子」は、将来の困難に対して強くなると思いません?愛情の継承や自己理解、自己表現に結びついていくから。



「ひとつだけ」の意味が文中で変わることを読解する力も必要だけど、父親の現状をフレームとするところからの、「ひとつだけ」を考える力って大事だと思えません?
- 知識としての国語力で終わるか、
- 人生を支える言葉の力になるか。
この分岐は「父の意図」をどう伝えるかで大きく変わると思うけど。
子どもに「言葉の変化」を気づかせるだけで終わるか。それとも「父が言葉を愛情に変えた」ことまで示すか。その選択を下すのは、授業を担う教員ひとりひとりではある。「父の意図まで踏み込む」、教員によって温度差があるだろうしね。
② 「一つだけ」が命・愛情・花の唯一性に変わる
父が差し出したのは、ごみすて場にひっそり咲いていたコスモス。
「ほら、一つだけあげよう。ゆみ子の命も一つ。咲かせるゆみ子の花も一つ。ゆみ子への父の愛情も一つ。」
そうして“欠乏の言葉”は、“かけがえのない唯一”を意味する言葉に変わる。父は自分の命と愛情を、その花に託した図。
もし、この「一つだけ」を、



コスモスは1本しか咲いてないですよね。
だから、「一つの花」という題名になってるんだよ。



あげるものがもう無いし、それでも怒らず、咲いてるコスモスをゆみ子にあげるお父さんは、やさしいよね。



ぶっ刺してやる。
後者は諦観の慈悲。
父の置かれた状況を“構造”として子どもに渡す
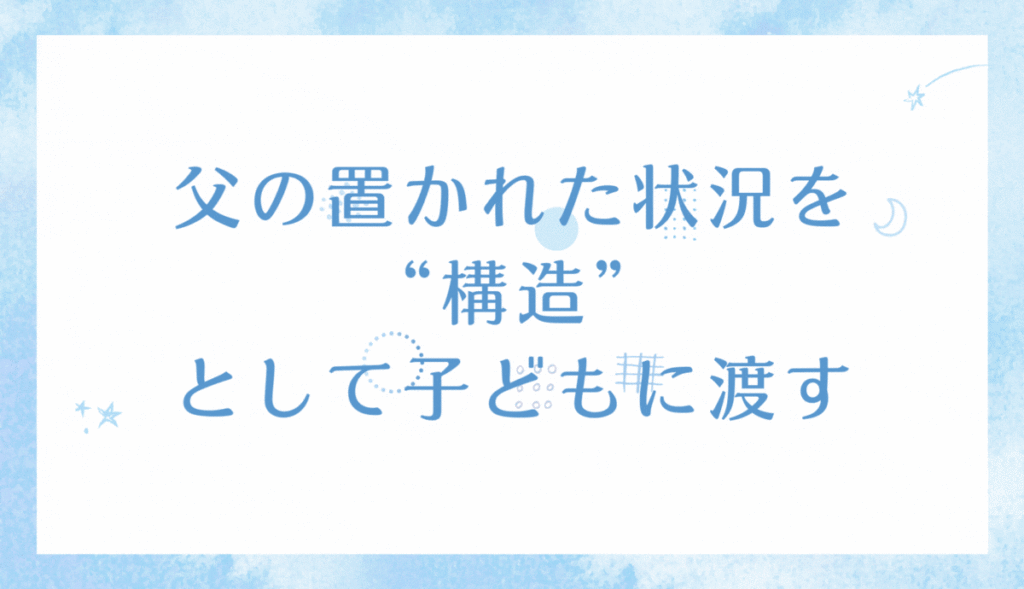
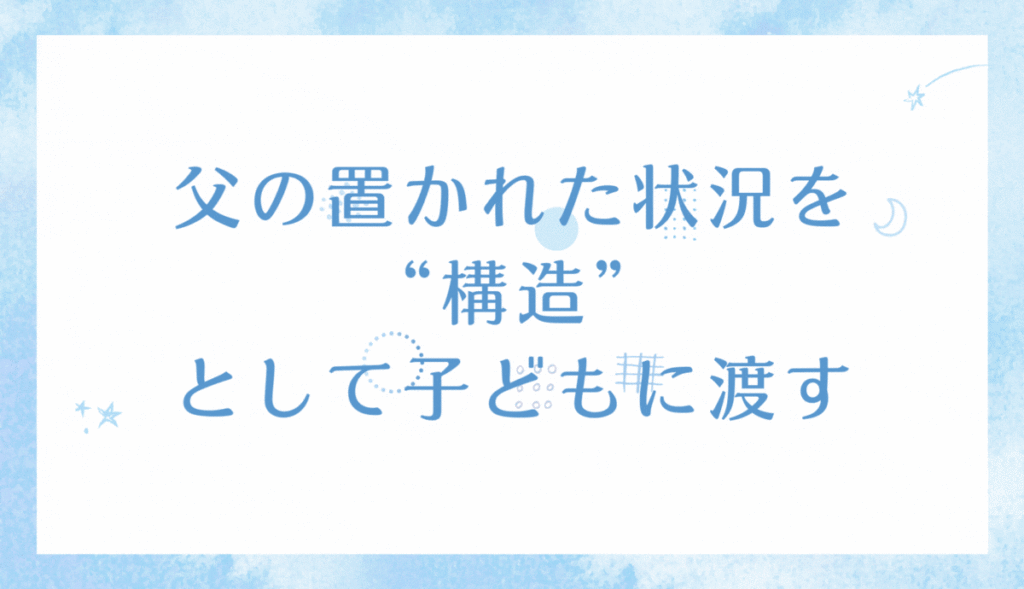
「一つだけ」が冒頭では“欠乏”を示し、最後には“命の唯一性・愛情”を示す。これは国語教育の基本であり、テスト問題的にも扱いやすいと思う。
だけど、ここで止まると 「文中で意味が変わった」=知識で終わる。
① 父親の現状をフレームにする読み
- 出征する父は「命がどうなるか分からない立場」にいる。
- そのフレームを持って読むと、コスモスは「父自身の命」「未来の娘への願い」と二重に見えてくる。
- この読み方は、単なる「意味の変化」ではなく、状況や人物の心情から言葉の重みを考える力を養う。
② 教育的な意味
- 前者(意味変化だけ)=読解技術としては十分。でも「心に残る読書体験」にはなりにくい。
- 後者(父の現状をフレームにする)=子どもに「言葉は状況と結びついて価値が変わる」と実感させられる。
- これは単なる国語力ではなく、人の言葉を“生きているもの”として受け取る力につながる。
③ 私の見方
だから私は、まず、
- 小学生には まず「言葉の意味が変わること」に気づかせる。
- 教師や教育者向けには 「父の現状をフレームにする」ことを伝えたい。
フレームを構造として渡すことができたら、そこから考えさせたらいいと思う。
花は父であり、未来のゆみ子
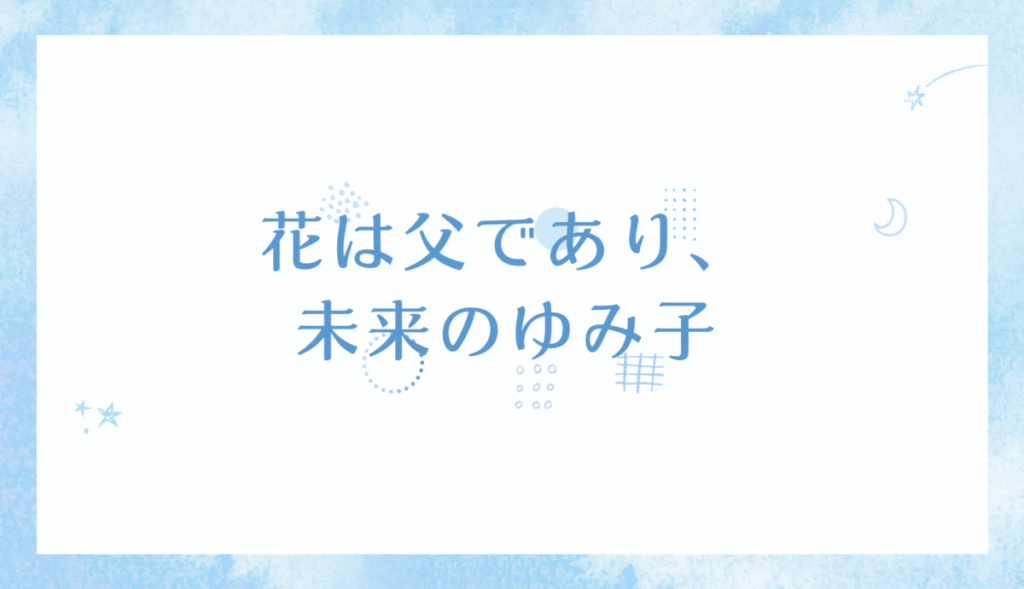
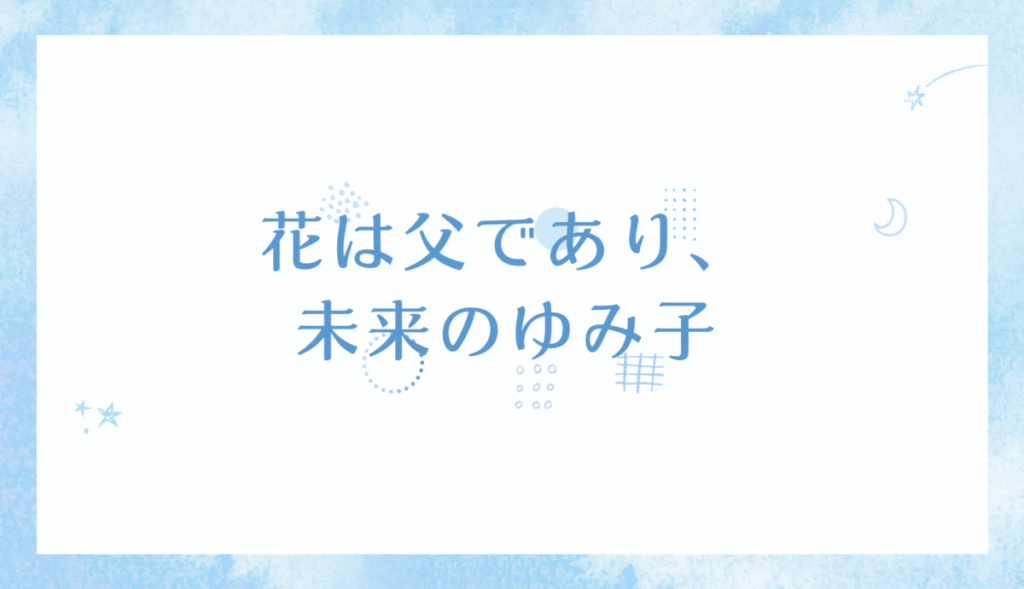
- 父自身の命の投影―社会から忘れられる兵士
- 未来のゆみ子の象徴―自分だけの花を咲かせる存在
- 「ひとつだけ」の意味が変わり、未来へのバトンとなる
① 父自身の命の投影―社会から忘れられる兵士
ごみすて場に咲く花は、実は父そのものとも思える。
だから文中でも、『プラットホームのはしっぽの、ゴミすて場のようなところに、忘れられたように咲いていた』となったとも読める。そこは、父の現状を表しているようだ。
国にとっては「数合わせの兵士」でしかなく、忘れられてしまう命。けれど、ゆみ子にとって父は“唯一無二の存在”。
花を渡すことで「自分の命も、確かにここにあった」と刻み込んだ。



ここから、コスモスは父自身とも読める。ゆみ子の「ひとつだけ」の存在でいれる。
② 未来のゆみ子の象徴―自分だけの花を咲かせる存在
同時にその花は、未来のゆみ子の姿とも思える。



ひとつだけしかない、お前はお前の花を咲かせられる。
父は、ゆみ子が“自分の命を大切にし、自分の花を咲かせる人”になるよう願いを込めた描写。
もしくは、自分にとって、かけがえのない、「ひとつだけ」の存在であるゆみ子。
③「一つだけ」の意味が変わり、未来へのバトンとなる
こうして「ひとつだけ」は、欠乏を示す言葉から、命の唯一性と愛情の象徴へと変わる。そしてその言葉は、花とともに娘に託された“未来へのバトン”になった。



わたしには、そう読めたというだけの話だ。
だけど、『一つの花』の「ひとつ」が問えてない教育があるとしたら、それは嘘だよ。
豊かに咲き広がるコスモス
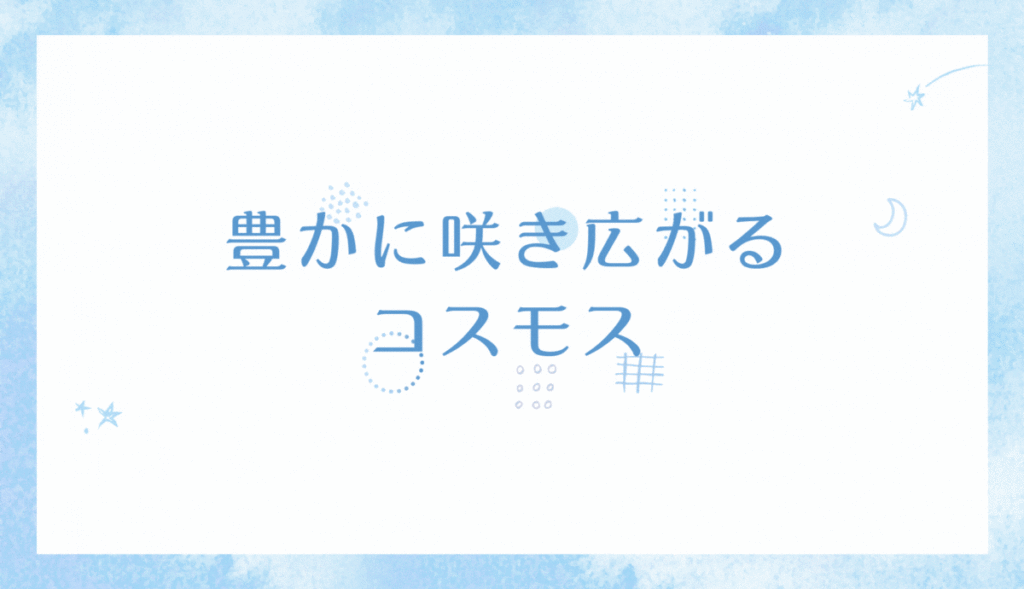
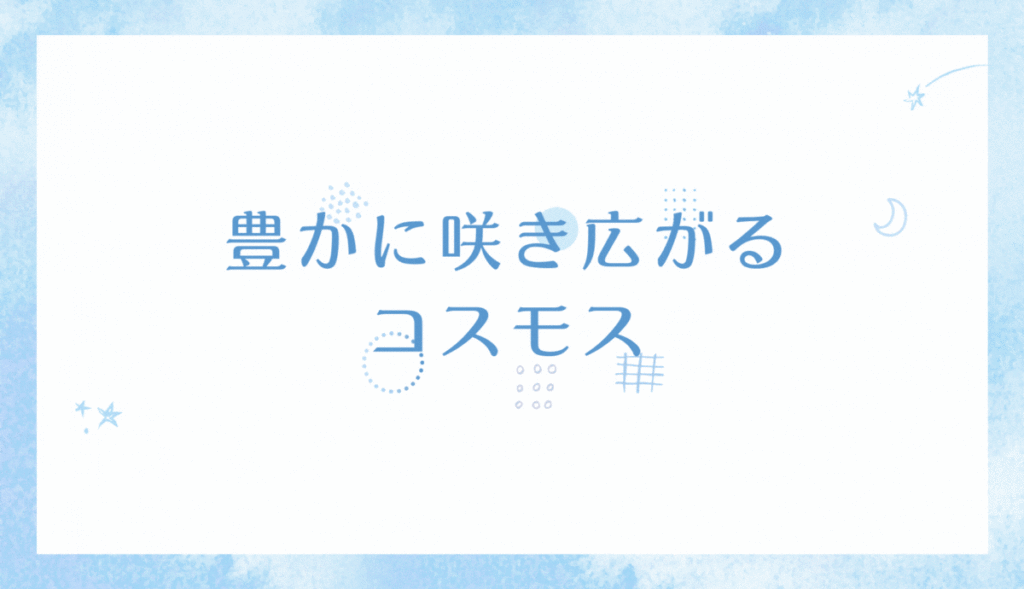
- 10年後の庭に広がった花々の象徴性
- 制限が愛情へ、愛情が豊かさへと変わった証
① 10年後の庭に広がった花々の象徴性
父から託された一輪の花は、10年後には庭いっぱいに広がっていた。それは「たったひとつ」が「たくさん」へと広がる姿。
花は、ゆみ子が受け継いだ父の思いと、母の愛情の積み重ねを象徴しているように思える。
② 制限が愛情へ、愛情が豊かさへと変わった証
「一つだけ」という制限の言葉は、父によって愛情の言葉に変えられた。そして母の手で育まれ、ゆみ子の成長と共に“豊かさ”へと結実。
庭に広がるコスモスは、制限が愛情になり、やがて豊かさに変わっていく人生の証そのもの。
まとめ
最初の「一つだけ」は“欠乏と我慢”。
最後の「一つだけ」は“命の唯一性と愛情”。
その花は父自身の命の象徴でもあり、未来のゆみ子の姿でもある。ゆみ子は何を受け継ぎ、どう生きていくのか?そして今を生きる私たちなら、そこから何を学べるのか?
この物語を通して、私たちは「一つだけ」という言葉の不思議な力に気づかされる。
最初の「一つだけ」は、戦時下の欠乏を表す制限の言葉。ゆみ子にとっては「もっと欲しいのに、これだけしかもらえない」という我慢の記憶、「もっとたくさんあるのに、ちょっとだけの世界」となりかねないもの。けれど、その裏には、母の「ない中からでも与えたい」という深い愛情が隠されている。
そして父は出征の日、最後に娘に残す言葉として、この「一つだけ」を新しい意味へと変換する。ごみすて場のようなところに、忘れられたように咲いていた一輪の花を手渡しながら、自分(愛情)を花に見立てて、「一つだけ」と託した。そうすることで、娘と一緒にいれる。「命は一つしかない」「自分だけの花を咲かせなさい」と伝えたとも思える。父にとっては自分の命の投影であり、同時に未来のゆみ子を託す象徴とも読める。
十年後、庭に広がるコスモスの花々は、父の願いが母とゆみ子によって大切に受け継がれ、豊かに花開いた証。制限は愛情に変わり、その愛情がやがて豊かさへと結実。
父はコスモスとして、家族といる図が成立してる。



この物語が私たちに問いかけるのは、「あなたにとっての一つだけは何か」ということとも読める。それは命であり、愛情であり、自分だけの花を咲かせる力でもある。

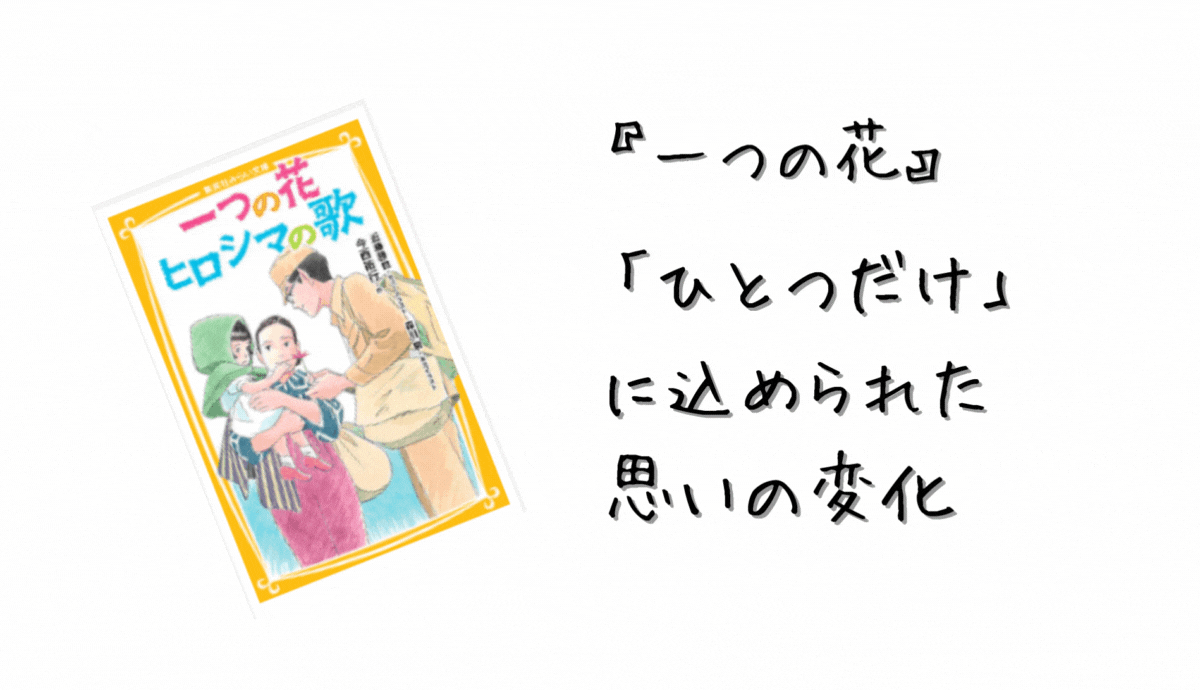
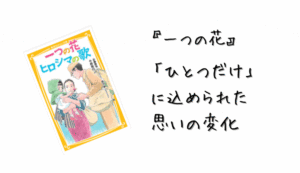
コメント