多角的な視点を持つ人の思考と行動が気になりますか?
私たちが日々遭遇している、仕事、勉強、人間関係など、さまざまな場面での問題、その物事を一つの側面から捉えて解決しようとすると失敗します。
多角的視点を持つ人は、様々なパラダイムから物事を見る癖があるので失敗を最小限に抑えることができる。

多角的な視点を持つことで、高次元の問題解決や意思決定ができるようになるからです。今回のブログでは、多角的な視点の重要性と備え方について詳しくまとめています。
多角的な視点とは?基本的な考え方を理解しよう
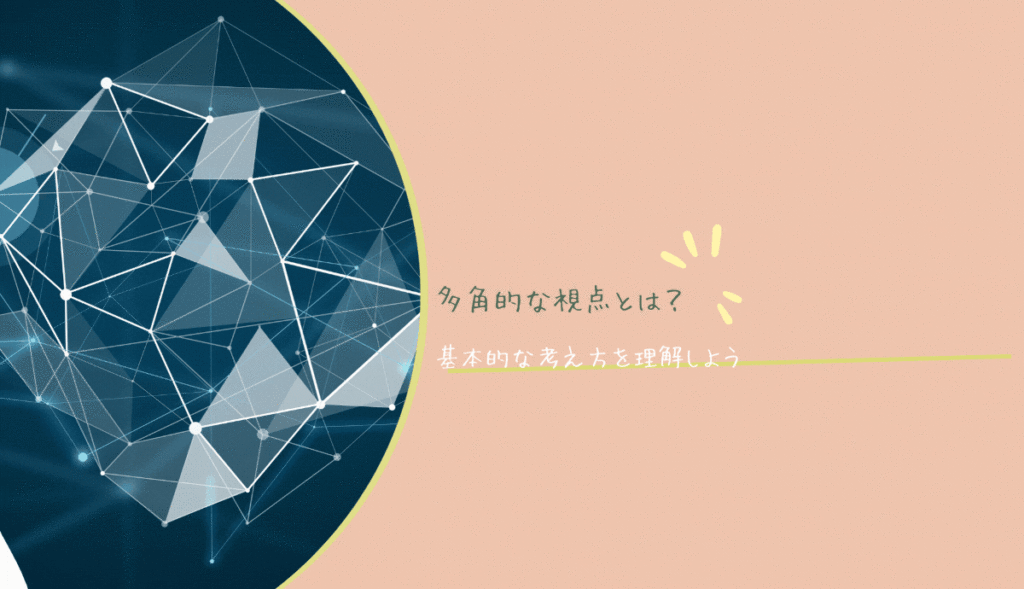
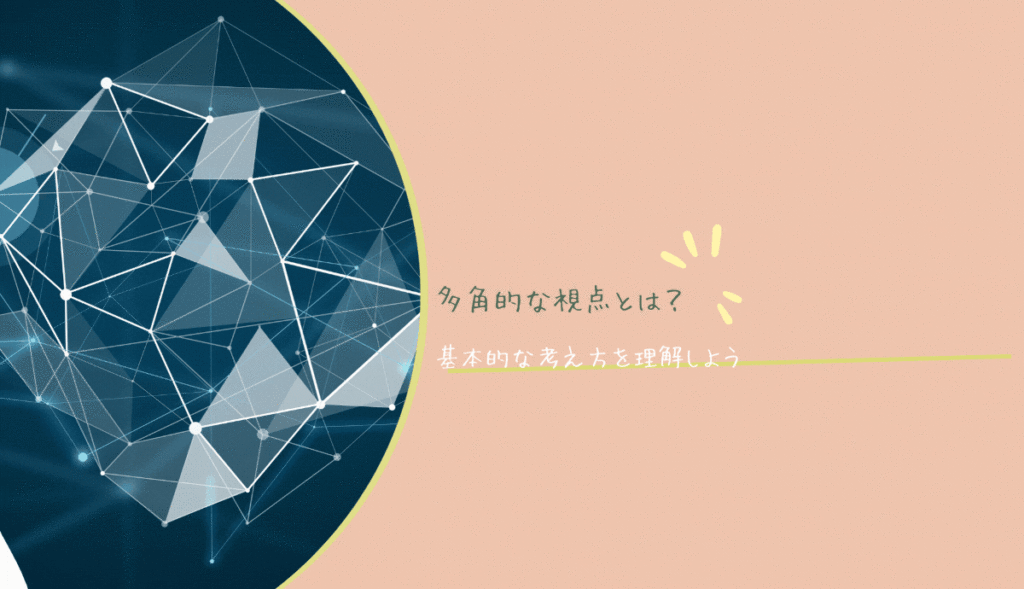
多角的な視点とは、特定の事象や問題について様々な角度から検討し、理解する能力のことです。
この能力を持つことによって、一つの見解にとどまることなく、多面的に物事を捉えることができるようになる。
どういうことかと言うと、主体性を持って問題解決に挑むことができるようになるので、失敗することがなくなります。
現代社会の急速な変化に対処するためには、多角的な視点を育成することが重要なスキルのひとつです。
- 多角的な視点の基本概念
- なぜ多角的な視点が重要なのか
①多角的な視点の基本概念
多角的な視点は、多様な意見や価値観を考慮することによって、より深い理解を得ることができます。
この視点の成り立ちは、以下の要素から成り立っています。
- 多様な視点:異なる経験や背景を持つ人々の意見を取り入れることで、新たな発見や洞察を促進。
- 様々な思考法:単に情報や意見を鵜呑みにすることなく、その信頼性や妥当性を自ら確認する姿勢を大切にすること。ほんとかな?という概念も大事にする。
- 柔軟なアプローチ:固定観念にとらわれず、時々の状況に応じて考え方を変化させる能力。
このようにして多角的な視点を持つことで、複雑な問題に対する効果的な解決策を見出すことができるようになります。
②なぜ多角的な視点が重要なのか
多角的な視点の重要性は、グローバル化や社会の多様性に由来しています。
特にビジネスの分野では、このような視点を培うことが成功につながります。その理由は以下の通りです。
- 問題解決力の向上:異なる観点を取り込みながら、新しい解決策を生みだすことができます。
- コミュニケーションの円滑化:多様な背景を持つ人々との対話を通じて、誤解や摩擦を軽減し、協力関係をより深めることが期待されます。
- クリエイティブな発想の促進:多角的に思考することにより、独自のアイデアや革新を生み出す機会が増えます。



この視点をビジネスシーンで活用することは、競争優位性を高めることになります。
多角的視点を得るためには、視点の変え方を知らなければならない。
視点を変えるとは?その本当の意味と重要性
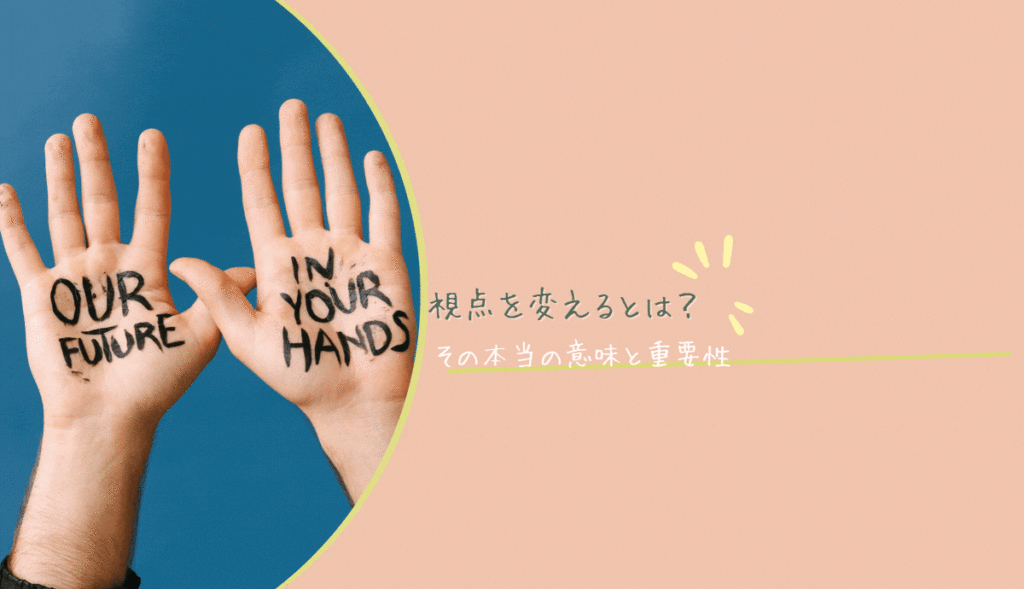
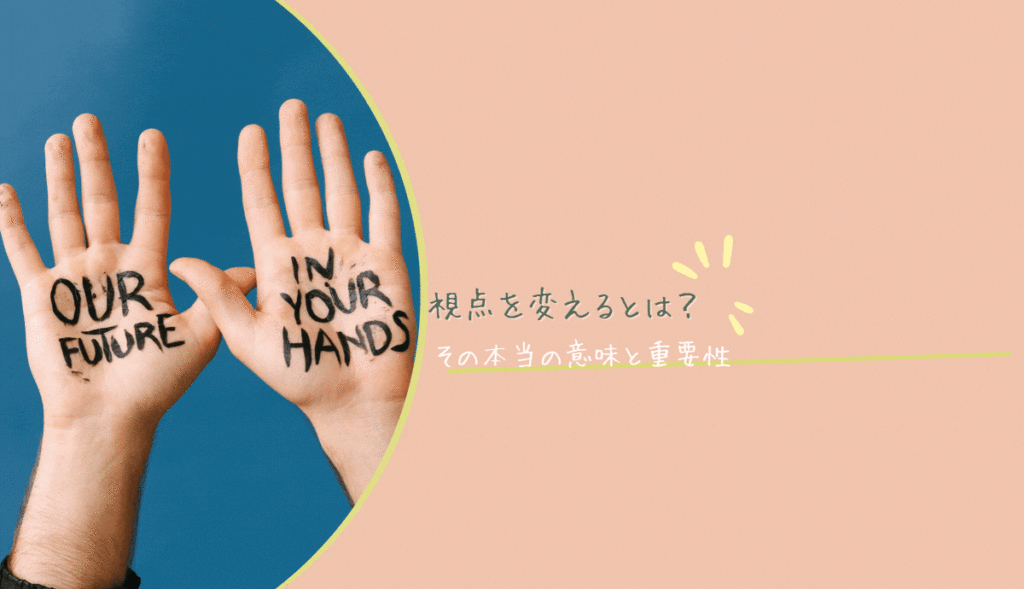
私たちの思考や行動に深く関わる『視点』は、物事の捉え方に大きな影響を及ぼします。
『視点を変える』とは、これまでの見方を手放し、別の視点から再評価を行う過程を指します。
わたしは、視点を変えるのは1度ではありません。起きた事象に対して、2度でも3度でも様々なシーンを想像してパラダイムを作っていく。そしてそのパラダイム数から答えを導き出しています。



それがわたしの主体性です。
この行動によって、柔軟な思考を養い、理解を深め、新たなアイデアや解決策を見つける能力を培うことができます。
視点を変えることの重要性は、さまざまな状況で実感できます。
日常生活や職場、さらには人間関係においても、異なる視点を持つことによって得られるメリットは非常に多岐にわたる。
- 多様性の理解: さまざまな視点を意識することで、他者の考えや感情に対する共感が深まります。この能力は、人間関係を円滑にし、有意義なコミュニケーションを促進する要因となります。
- 創造性の向上: 固定概念を捨て、さまざまな角度から物事にアプローチすることで、新しい発見や独特なアイデアを生み出すことができます。特に、創造的な問題解決においては、この視点の転換が極めて重要です。
- 自己成長: 自身の限界や短所に囚われずに異なる視点から自己を見つめ直すことで、自己理解が深まり成長へとつながります。過去の失敗を新しい視点で考えることで、再出発のチャンスを見出すこともできるようになります。



例えばよく、『過去は変わらない』と言うではないですか。
あれは、過去に囚われている状態。
この見え方を(視点を)ずらしてみます。
例えば、嫌な出来事が起きたときに、その経験は変えることができないでしょうが、その経験を通して得るものはありますよね。
あれさえなければ!という感情から、あの経験があったから今がある。あの経験が無ければ、今の自分(成功)はない。
こう思うと、過去の見え方が変わりますよね?嫌な思い出も、ひとつの経験として人生の一部になる。その嫌な過去が人生の全てを支配してしまっている状態では、『過去は変えられないもの』として自分の中に残るでしょうが、人生の一部にしてしまえば、『過去の経験は変えられないが、見え方(捉え方)は変えられる』ということになる。



それが視点のずらし方です。あれさえなければ!という状態では自己成長はないですから。
視点を変えるための6つの思考法と問題解決の仕方
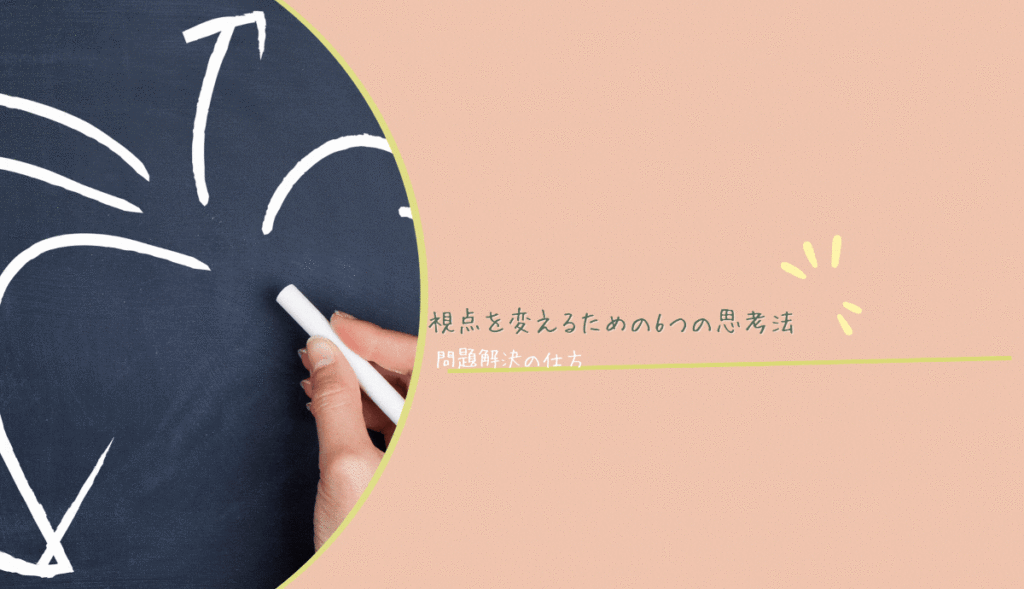
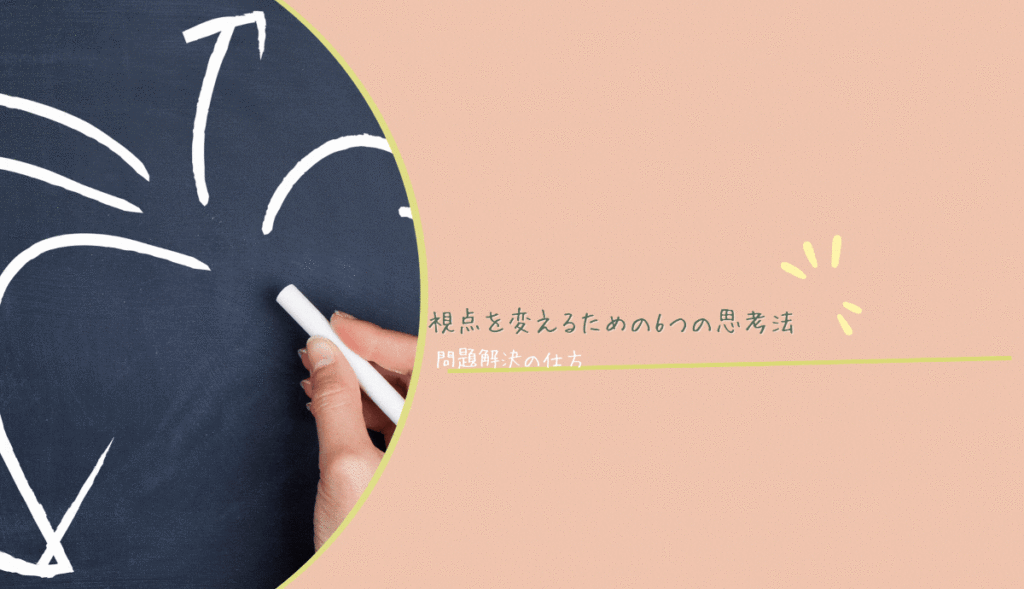
視点を変えることは簡単なことではありませんが、意識的に取り組むことで徐々に自然な習慣として身につけることができます。



以下は、視点を変えるために重要な6つの思考法。どれか1つに偏ると視野が狭くなるため、バランスよく組み合わせることが大切。
- 視点を変えるために重要な6つの思考法
- 問題解決の仕方
①視点を変えるために重要な6つの思考法
6つの思考法の役割と多角的視点でどの部分が重要になっているかを表にまとめるとこんな感じになります↓
| 思考の種類 | 特徴 | 多角的視点での重要個所 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1.素朴思考 | 直感や経験をもとに考える | 日常的な感覚や一般的な価値観を理解する | 感覚に頼りすぎると、誤解や思い込みが生じやすい |
| 2.天邪鬼思考 | 逆の立場を取って考える | 既存の意見や主流の考えを疑い、新たな視点を得る | 逆張りが目的化すると、非論理的な反対意見になりがち |
| 3.批判的思考 | 物事を鵜呑みにせず、論理的に分析 | 単に否定するのではなく、感情や思い込みに流されず、根拠に基づいて考える | 情報を疑いすぎると、何も信じることができなくなる。深く考えすぎて行動が遅くなる。 |
| 4.道具思考 | 知識・ルールを活用する | データや理論を使い、論理的に考える | 知識に依存しすぎると、前提を疑う力が弱まる |
| 5.構造化思考 | 物事を整理し体系的に考える | 複雑な問題を整理し、論理的に分析する | 『整理しすぎて』柔軟な発想を失うことがある |
| 6.哲学的思考 | 物事の本質を深く問い続ける | 前提を疑い、新しい概念を探求する | 抽象的になりすぎて、実践的な結論が出にくい |
6つの思考を組み合わせることで、多角的な視点が得られます。



例えば、『AIが人間の仕事を奪うのか?』というテーマについて考えるとします。
素朴思考:なんとなく、AIが発達すると仕事が減りそう(一般的な感覚)
天邪鬼思考:逆にAIが普及したら、新しい仕事が増えるんじゃない?(主流の意見を疑う)
批判的思考:この議論には感情的な意見が多いので、客観的なデータを基に判断しよう(冷静に分析)
道具思考:過去のデータを見ると、技術革新で失われた仕事もあるけど、新しい職種も生まれてる(データを活用)
構造化思考:労働市場の変化を、①単純労働、②専門職、③クリエイティブ職に分けて分析してみよう (論理的整理)
哲学的思考:そもそも『仕事』って? AIと共存する未来ってどんな未来?(根本的な問いを考える)
このように、1つの問題に対して異なる思考法を組み合わせることで、多角的な視点を持ち、深い議論をすることができるようになります。
直感だけでなく、これまでのデータも活用する。
常識を疑いつつも、論理的な整理も行う。
深く問いながらも、実践的な結論を出す。
これらを意識すれば、より広い視野を持ち、柔軟で深い思考ができるようになります。
1.素朴思考をする(直感的・経験ベース)
専門的な知識や理論に頼らず、自分の直感や日常的な経験をもとに物事を考えることを指します。簡単に言えば、『なんとなくそう思う』、『普通に考えたらこうだよね』というような、素朴で直感的な思考。 直感や経験をもとに考えるという、誰でも自然に考える思考法のことです。
例えば、『太陽が東から昇って西に沈むから、太陽が地球の周りを回っている!』
実際には、地球が自転しているだけ。でも、直感的には『太陽が動いている』と考えやすい。
こういうことで、日常では役立つ場面も多いですが、間違った認識をしやすいため、必要に応じて科学的・論理的な視点を取り入れることが大切になってきます。
2.天邪鬼思考をする(逆張り・反対意見を好む)
一般的な意見や他人の考えに対して、わざと逆の意見を言ったり、反対の立場を取ったりする思考のことです。
これは単なる反抗ではなく、『本当にそうなのか?』と逆張りの視点を持つことで、新しい見方を探ろうとする考え方とも言えます。あえて反対意見を述べることで、より深い議論を促すこともできます。
例えば、『成功=お金持ちって本当?幸せの定義は人それぞれじゃない?』
→こんな風に、一般的な価値観に対して、『それが唯一の正解とは限らない』と考える。
天邪鬼思考が強くなると、『逆のことを言う』ことが目的になり、根拠のない否定や逆張りになりやすいので、批判的思考と組み合わせてバランスよく使うことが大切です。
3.批判的思考(クリティカルシンキング)
物事を鵜呑みにせず、論理的に分析し、自分で正しく判断する思考法。『批判』といっても、単に否定するのではなく、感情や思い込みに流されず、根拠に基づいて考えることを意味します。『これは事実か? それとも単なる個人の意見か?』と見極める、『他の視点や立場から見たらどうなるか?』と考える、『結論に至るまでの根拠は正しいか? 矛盾はないか?』と検証する、『みんながそう言ってるから正しい』という思考を避ける。
例えば、『◯◯を食べると健康に良い』と聞いたとします。
→『その健康効果、本当に科学的根拠があるの?』という疑念から、 『そのデータは信頼できるの? どの研究が言っているの?』を調べる思考法のことです。
情報を疑いすぎると、何も信じることができなくなる危険性はありますが、デマやフェイクニュースに騙されにくくなり、問題の本質を見抜き、適切な判断ができるようになります。思考の幅が広がるので、深く考えすぎて、行動が遅くなることもありますが、創造的なアイデアが生まれやすくなります。
『批判的思考(クリティカルシンキング)』とは、感情や思い込みに流されず、論理的に物事を分析し、正しく判断する力のことで、現代では情報があふれているので、正しい情報を見極めるためにも、批判的思考がますます重要になっています。
4.道具思考をする(知識やルールをツールとして活用)
『概念的な道具』を使って、効率的・合理的に物事を考える思考法。何らかの『道具』を通して別の角度から問題を捉え直してみると、また違った問題の姿が見えてくるかもしれません。知識・記号・ルールを手段として利用しながら、問題を解決したり、新しいアイデアを生み出したりすることができます。
道具の種類と使い方はこうです↓
| 道具の種類 | 具体例 | どのように使うか? |
|---|---|---|
| 知識 | 数学、歴史、物理学、心理学 | 問題解決や意思決定のためのツール |
| 記号 | 言葉、数字、プログラミング言語 | 情報を整理し、伝達する手段 |
| ルール | 法律、倫理、ゲームのルール | 社会や組織の秩序を作る基準 |
| 概念 | 自由、平等、効率、権力 | 物事を理解し、評価する枠組み |
例えば、あなたのエネルギーを詐取するエネルギーバンパイア(依存・支配してくる人)がいたとします。いつも愚痴を言われて疲れることもありますよね。
この場合の道具は『アサーティブコミュニケーション』。
アサーティブコミュニケーションとは、お互いを尊重しながら意見を交わすコミュニケーション方法です。
『攻撃的でも受け身でもなく、適切に主張する技術』を活用。
→NGな対処法は『我慢して全部聞く』、『冷たく突き放す』
→OKな対処法は『今ちょっと忙しいから、また今度。そうなの?検討しとく。』(やんわり距離を取る)
こんな感じです。
知識やルールを活用することで、複雑な問題を解決しやすく、合理的で効率的な思考ができますが、『道具』が絶対正しいと思い込み、新しい視点を持てなったり、感情や直感を軽視しすぎると、人間関係が機械的になるというデメリットも存在するのでバランスが重要です。


5.構造化思考をする(物事を整理し、体系的に考える)
問題状況を構成する要素を俯瞰し、構成要素同士の関係性について分析・整理し、問題を構造的に捉える考え方のことです。『これはなぜ?』『これとこれはなんで繋がってるの?』『本当に要素はこれだけなの?』のように、物事を『構造(仕組み)』として捉え、論理的に整理することで、わかりやすく考え、説明しやすくすることを目的としています。
例えば、『この説明、何が言いたいのか分かりにくい、、』と感じたとします。
構造化思考なしだと、とにかく長々と説明しようとするでしょうが、構造化思考ができると、結論(解決策)、背景、課題、もう一度結論(解決策)の順番で説明することができます。話が整理され、相手に伝わりやすくなります。
『わかりにくいものを、わかりやすくする力』が構造化思考の強みです。
6.哲学的思考(前提を疑い、本質を考える)
物事の根本的な意味や前提を問い直し、より深い理解を得ようとする思考法です。
一般的な問題解決では『どうすれば解決できるの?』と考えますが、哲学的思考では『そもそもこの問題は本当に問題なの?』と、より根本的な視点から問いを立てます。
例えば、『赤信号を渡ったら罰金になるのはなぜ?』という問いに対して、
A:『法律だから守るべき』
B:『安全のために必要だから』
C:『本当にこのルールは絶対なの?』
哲学的思考では、『ルールがあるから守る』ではなく、『ルールはどうあるべきか?』まで考えます。
よくある問いとしては、
『なぜ働くのか?』
『本当に時間は存在するのか?』
『人間はなぜ生きるのか?』
哲学的思考は、結論が出にくく、実践的な問題解決には向かないこともあり、考えること自体が目的になってしまうことがありますが、物事を深く考え、本質を理解することができ、常識や既存の価値観にとらわれず、新しい発想をすることができるようになります。
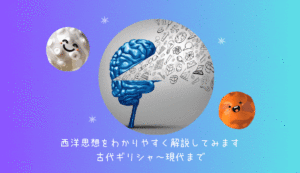
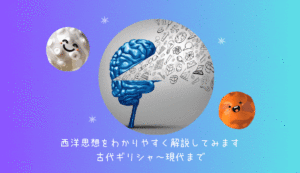
問題解決の仕方※6つの思考法を活用したアプローチ
子どもが反抗する・暴言を吐く・学校をサボる・片付けをしない・ゲームばかりするなど、親が困る『問題行動』を起こすとき、感情的に叱るだけでは根本的な解決にならないと思っていて、わたしは普段から『なぜこの行動をするのか?』を多角的に考え、適切な対処法を見つけることに注力しています。



表にするとこんな感じ。
| 思考の種類 | 問題の捉え方 | 解決策の例 |
|---|---|---|
| 素朴思考 | この子は怠けているだけ | 『ちゃんとしなさい!』と叱る(短期的には効果があるが、根本解決にはならない)。 |
| 天邪鬼思考 | 子どもの視点から考えてみる | 何か伝えたいことがある?親にもっと構ってほしい? |
| 批判的思考 | 感情ではなく、事実を整理し、論理的に考える | 『いつ、どんな状況で問題行動が出るか?』を観察し、パターンを分析する。 |
| 道具思考 | 心理学・教育の知識を活用する | アドラー心理学の『勇気づけ』を使ってみる。ペアレンティングの実践。 |
| 構造化思考 | 問題行動の原因を細かく分析する | ①家庭環境 ②学校でのストレス ③本人の性格 ④親の接し方 などを整理。 |
| 哲学的思考 | そもそも『問題行動』とは何か? | 『この行動は本当に悪いのか?』と考え、柔軟な対応を検討する。 |
子どもの行動の『本当の原因』を特定する(構造化思考・批判的思考)
子どもが問題行動を起こす背景には、必ず何かしらの原因があります。
家庭環境 → 親が忙しくて話す時間が減った?兄弟間の競争?
学校でのストレス → 友達関係・勉強のプレッシャー・先生との相性?
本人の特性 → ADHDやHSP(繊細気質)など、性格の影響?
親の接し方 → 叱りすぎ?放任しすぎ?期待がプレッシャーになっている?



感情的に叱る前に、まず『何が原因なのか?』を冷静に分析して、アプローチの取捨選択をしていきます。
子どもの立場になって考える(天邪鬼思考)
『この子の視点から見たら、世界はどう見えているのか?』
『なぜこの行動をするのか?』と本人の気持ちを探る。
例:『反抗的な態度をとる子ども』
NG:『なんでそんな態度を取るの!』(親の感情をぶつけるだけ)
OK:『最近何か嫌なことあった?』(まず子どもの話を聞く)
例:『ゲームばかりして勉強しない』
NG:『ゲームばっかりやめなさい!』(頭ごなしに禁止)
OK:『ゲームが楽しいのはわかるけど、勉強も大事。どうしたらバランスよくできると思う?』(対話を大切にする)



勉強しろ、と言われても、何をどれくらいすればいいのかわからないし、計画の立て方も分からないんですよね。
解き方も分からないことも多い。問題集1日1ページでもいい、問題を簡単に解くコツでもいい、計画の立て方、解き方の知識を教授して、できるだけ自分で計画する力をつけさせて『自分でも解ける』という自信を持たせることも大事だと思ってます。
心理学の知識を活用する(道具思考)
アドラー心理学の『勇気づけ』
『頑張ったね!』ではなく、『〇〇を工夫したのがよかったね!よく気が付いたね!』と具体的に努力を認める。
→ 自己肯定感が高まり、自ら行動できるようになる。
ペアレンティング(親の接し方の改善)
『命令』ではなく『相談』の形にする。
→ 『どうしたらスムーズにできると思う?』と子どもと一緒に解決策を考える。
親の価値観を見直す(哲学的思考)
『そもそも、この行動は本当に問題なのか?』
例えば…
- 『宿題をしない』→ 宿題をやる意味は? 自分で学ぶ力を育てる方が大切では?
- 『ゲームばかりする』→ ゲームの中で学んでいることもある? ルールを決めればいいのでは?
- 『朝起きない』→ 夜更かしの理由は? 生活リズムの調整が必要?



親の『こうあるべき』という考えが、本当に正しいのか見直してみる。
『問題行動』の原因は多面的に考える必要がある。
『感情的に叱る』より、『なぜこの行動をするのか?』を分析することが大切。
心理学・教育学・環境調整など、多様なアプローチを組み合わせると効果的。
実践の流れ
- まず原因を分析する(構造化思考・批判的思考)
- 子どもの立場になって考える(天邪鬼思考)
- 心理学や教育の知識を活用する(道具思考)
- 親の価値観を見直す(哲学的思考)
『叱る』よりも『子どもと向き合い、子どもに適した環境を整えること』が解決のカギにはなると思います。
基本は↓東洋的思想を大事にしています。※西洋的思想(論理的)も基盤としてはあります
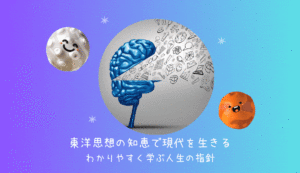
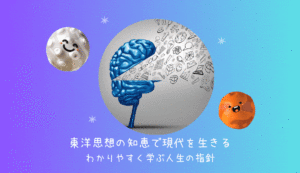



とは言え、万人受けの方法か?と言われると、そう思えばそうだし、そう思えなければ、それはそれ、ですから。あなたが出した結論、それが答えだと思います。
子どもへのアプローチとして考えてみましたが、わたしは基本、起きた事象だけに着目しても何の解決にもならないから、多角的視点が必要だと思っています。視点を変えることに意味がある。
では、様々な視点を学び、視点を変えることで得られるメリットは何でしょうか?
視点を変えることで得られる8つの大きなメリット
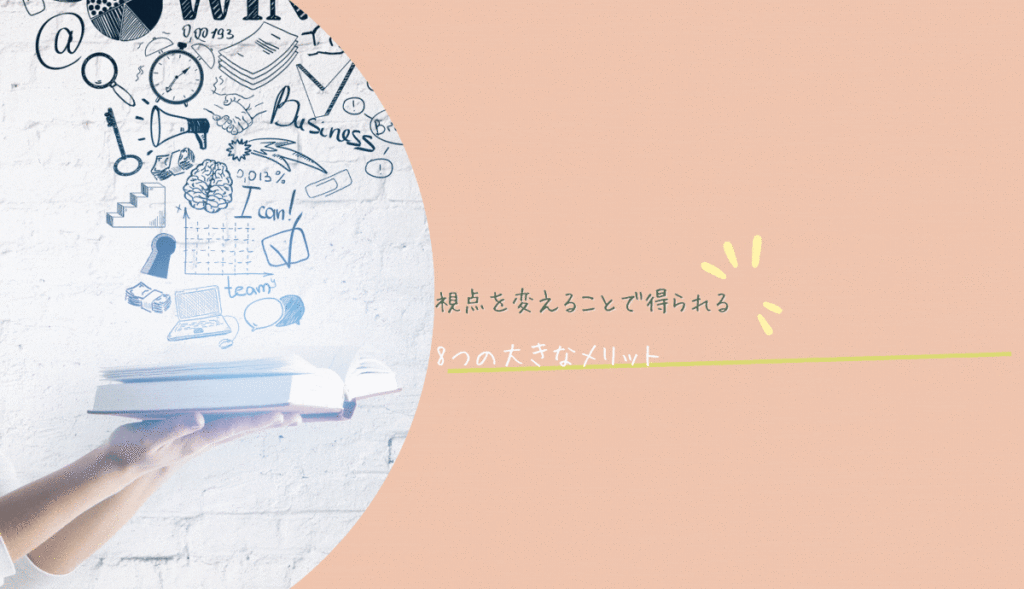
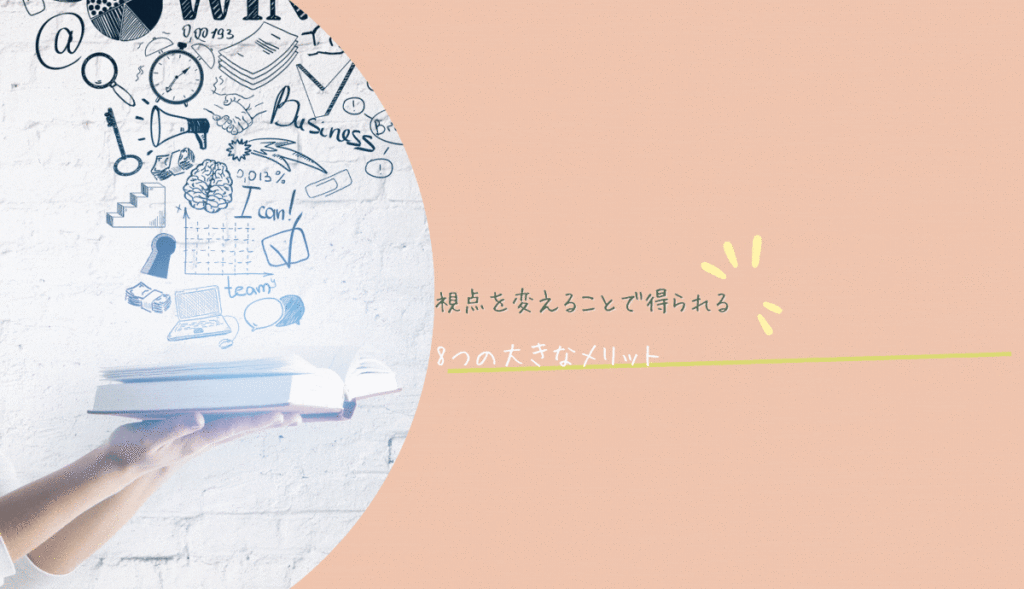
視点を変えることは、私たちの思考や行動に多大な影響を与える重要なスキルです。ここでは、視点を変えることによって得られる8つの大きなメリットについて紹介します。
- 人間関係の改善
- 創造性の向上
- 自己成長と自己受容
- 問題解決能力の向上
- 社会についての理解の深まり
- ポジティブ思考の醸成
- 人生の選択肢の拡大
- 組織やチームへの貢献
①人間関係の改善
視点を変えることで、他者の立場や考え方を理解しやすくなります。これにより、コミュニケーションの質が向上し、信頼関係が築きやすくなります。具体的には以下のような点が挙げられます。
- 共感力の向上: 他者の感情や意見に対して敏感になり、より深い理解が得られる。
- 対立の回避: 異なる意見を認めやすくなり、無用な衝突を避けることができる。
- 協力関係の構築: 共通の目標に向かって協力し合うことで、チームやグループの結束が強まる。
このように、視点を変えることは人間関係を劇的に改善し、より円滑なコミュニケーションを実現します。
②創造性の向上
異なる視点を取り入れることで、問題解決に対しても新たなアプローチが生まれます。視点を変えることで以下のような利点が得られます。
- アイディアの枯渇を防ぐ: 常に新しい視点で物事を考えることで、創造的なアイディアが次々と浮かんでくる。
- 独自の解決策の発見: 従来の方法にとらわれず、新しい視点からのアプローチで独自の解決策を見つけ出せる。
- 多様な選択肢の生成: 一つの問題に対して、複数の視点から考えることで多様な解決策が比較検討できる。
このようにして、視点を変えることは創造性を高めるための大切な手段です。
③自己成長と自己受容
視点を変更することによって、自己理解が進みます。自分自身の短所や弱みを強みに変える一助にもなり、以下のような効果があります。
- 自己評価の向上: 自分の持つ価値や実績に目を向けることで、自己肯定感を持てる。
- 失敗からの学び: 失敗や挫折をネガティブに捉えるのではなく、成長のチャンスと考えることで前向きな姿勢が育まれる。
- 柔軟な思考の促進: 自分の限界を決めず、常に新しい挑戦を受け入れる姿勢が養われる。
④問題解決能力の向上
多角的な視点を持つことで、問題解決のアプローチを多様化できます。一つの角度からだけ考えると、選択肢は限られてしまいます。しかし、異なる視点で物事を分析することで、以下のような効果が得られます。
- 新たな視点の発見: 以前には気づかなかった情報や可能性を見直し、独創的な解決策を提示することができるようになります。
- 創造的なアイデアの生成: チームメンバーとのブレインストーミングを通じて、他者の意見を生かし、多くの新しいアイデアを生み出すことが可能です。
⑤社会についての理解の深まり
多角的な視点を持つことで、多様な社会の側面を深く理解することができます。その結果、以下のような能力が育まれます。
- 枠を超えた視野の拡大: 異なる文化や価値観を認識することで、自身の偏見に気づき、より広い視野を持つことができます。
- 多様性の尊重: 他者の意見や経験を聴取することで、より豊かな人間関係を築くことができるようになります。
⑥ポジティブ思考の醸成
多角的な考え方は、ポジティブな思考を促進する役割を果たします。特にリフレーミングの手法を用いることで、以下のような利点があります。
- ネガティブな状況を好転させる: 不利な状態や困難な感情を新たな視点から見直すことで、逆境に対抗する力が得られます。
- ストレス管理の向上: 視点を変更することで、困難な状況でも前向きに取り組む意欲が高まりやすくなります。
⑦人生の選択肢の拡大
多角的な視点を持つことは、将来的な選択肢の幅を広げるだけでなく、次のような経験をもたらします。
- 柔軟なキャリアプランニング: 様々な視点からキャリアを見つめ直すことで、多岐にわたる可能性を検討することが可能です。
- 自己成長の機会の増加: 多様な知識にアクセスすることにより、自己理解が深まり、成長の機会が広がります。
⑧組織やチームへの貢献
最後に、個人が多角的な視点を持つことは、組織やチームの発展にも寄与する重要な要素です。
- イノベーションの促進: 様々な視点が集まることにより、新しいアイデアの創出が期待できます。
- コミュニケーションの改善: チーム内の意見交換が活発化することで、プロジェクトの円滑な進行が実現します。
多角的な視点を持つことで得られるこれらの利点は、個人の成長だけでなく、社会全体において大きな価値をもたらします。日常生活において意識的に多様な視点を取り入れることで、これらの恩恵を実感しやすくすることができると思います。
このように視点を変えることは、自己成長を促進し、自己受容を高める大きな力となります。
すぐに実践できる!視点の変え方テクニック


視点を変えることは、柔軟な思考を促進し、新たな解決策を見つけるための重要なスキルです。ここでは、すぐに実践できる視点の変え方テクニックをいくつか紹介します。
- 質問を活用する
- マインドマップを作成する
- ロールプレイ
- 制限時間を設ける
- 日記を書く
①質問を活用する
自分自身や周囲に対して異なる質問を投げかけることで、視点を変えることができます。
この方法は、考えていることに新たな角度を与えるのに非常に効果的です。以下のような質問を試してみてください。
- もし、私が〇〇(他の誰か)ならこの問題をどう解決するだろうか?
- 過去の事例はこうだった、今回は当てはまるかどうか?
- この状況を逆の立場から見ると、どのように感じるだろうか?
- 感じ方が違う場合、行動はどう変わるだろうか?
- この問題をそれぞれの立場、それぞれの感情、それぞれの目的という概念から考察してみよう
- 周り(立場や自分との関係性も見ます)から、この問題はどう見えるのか?
- 物事の道理的、倫理的にどうだろうか?
- 感情を抜いて考えてみよう、事象だけで見た場合の考察をしてみよう
- 結論に至るまでに矛盾はないか?
- 矛盾を見つけた場合、その矛盾の原因はどこにあるのか?
- 行動はどうか?思考が変わらないと行動が変わらない原則がある、同じような行動がないか?となると問題の本質はどこか?



とにかく色々な思考法で考えます。考えられるだけ全部。
これをすべて考えた後に、自分の感情と向き合う必要があれば、感情と向き合います。感情を置き去りにしないのは鉄則。
あくまでも自分に沿います。一番良いと思われる結果を目の前に、感情が『無理』となれば、無理。ですが、この思考法で思考していけば、思考中に感情も追いついているので、考えながら向き合っている感じです。出した結論で感情が揺さぶられるということは無いに等しいです。
なぜ感情に着目するかというと、感情に無理が生じると、宇宙に背くことになるんですよ。



そそ、その感情の余波がすごいから。
返ってきちゃう。
『大丈夫』となれば、GO!



だって、いくら合理的とは言え、無理だと思えば無理。
飲めないものは、飲めない。それが最良の選択だと思ってます。
そこは大事、そして、そこに至るまでの思考が大事なんです。淀みが生まれない。
②マインドマップを作成する
視覚的に思考を整理するために、マインドマップを使用することもおすすめです。
中心にテーマを書き、その周りに関連するアイデアや視点を自由に描いていきます。これにより、思考の幅が広がり、視点を変えるきっかけとなります。特に、以下の点に注意しましょう。
- 色を使い分けて、視覚的に特徴づける
- 矢印や線で関連性を強調する
- 新たなアイデアが浮かんだ場合はすぐに加える



頭で整理すると、浮かんだアイデアや質問が消えることがあるんです。それを防ぐために、問題や課題が複雑なときには、紙に書いて思考を整理すると便利です。
③ロールプレイ
他者の立場になって考えるロールプレイは、視点を変える有効な手段です。友人や同僚と一緒に、特定のシナリオを演じることで、それぞれの視点を理解しやすくなります。このテクニックは、グループ内での意見交換やディスカッションにおいても非常に役立ちます。
- シナリオを設定し、それぞれが異なる立場を持って演じる
- 演じた後に感想や気づきをシェアする
④制限時間を設ける
思考を柔軟にするために、制限時間を設けてアイデアを出し合う方法も効果的です。短い時間内に多くのアイデアを出すことで、『正しい答え』を求めるプレッシャーから解放され、自由に発想できる環境が生まれます。例えば、5分間で思いつく限りの解決策を書き出してみるのも一手です。
⑤日記(ブログ)を書く
定期的に日記をつけることも、視点を変える助けになります。自分の感情や出来事、思ったことを書き留めることで、自分自身を客観視できるようになります。こうすることで、新しい並行した考え方や解釈が生まれることがあります。特に、以下のようなことに留意すると良いでしょう。
- 毎日一つの出来事を選び、その出来事を異なる視点から分析する
- 毎日の出来事を良い方向に受け止めるような思考法をしてみる
ただ、視点を変え分析し、成長になるように起こった出来事を良い方向に受け止めることは大切ですが、確証バイアスと言って、都合の良いように受け止めるのとはワケが違います。
良い方向に受け止める思考法を持つときには、自己成長がセットだという認識が必要です。
まとめ
視点を変え、多角的な視点を持つことは、個人の成長や組織の発展に不可欠なスキルです。
この記事では、その基本的な考え方や具体的な効果、実践的な方法論について解説してみました。
今日では複雑化する社会に対応するため、様々な角度から問題を捉え、創造的な解決策を生み出すことが重要となっています。
個人や企業が持続的に成長していくためには、意識的に多角的な視点を育むことが不可欠だと思います。
この能力を身につけることができると、新しい発見や革新的なアイデアが生まれやすくなり、それが自己実現や組織の競争力向上につながって行きます。



すっごい文字多くなっちゃった・・・まとめたら長くなったの・・

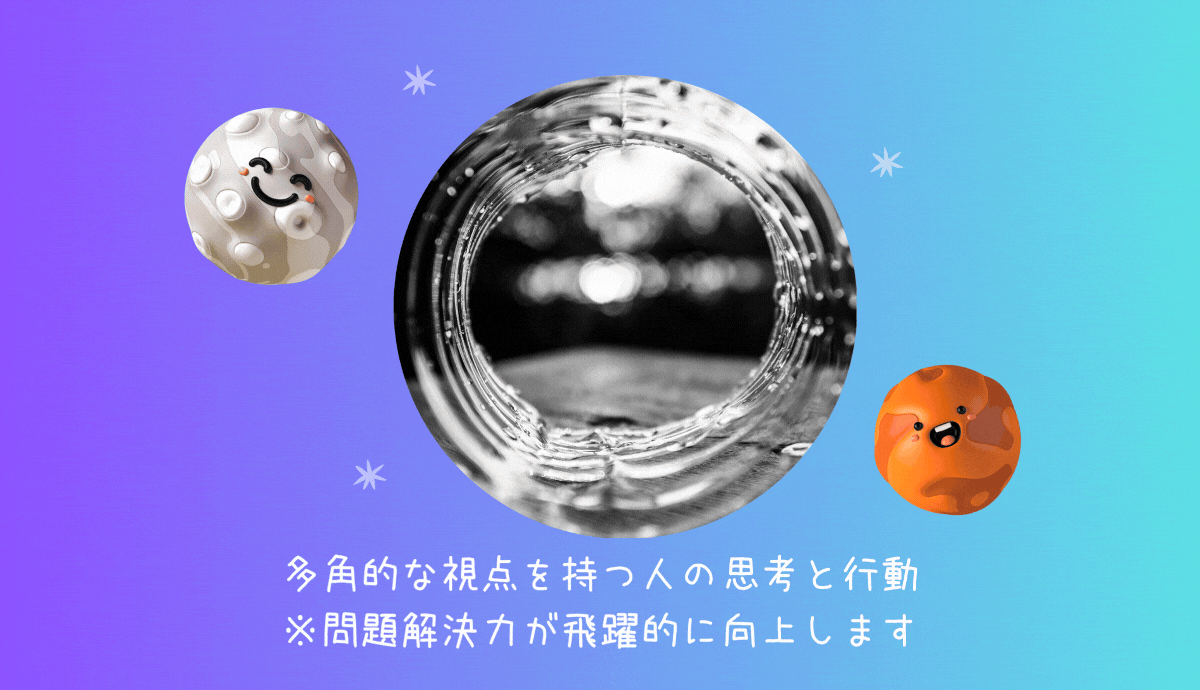
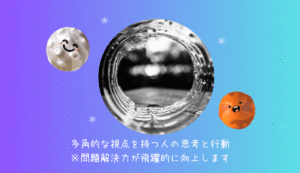
コメント