人生って、宇宙が出してくる『ひっかけ問題大会』みたいなものでもある。
しかもその問題、見た目がほぼ同じ。
パッと見は『自分の課題』っぽいのに、フタを開けたら『他人の課題』。
例えるなら、毒キノコかキノコかを見分ける感じ。
見た目は同じ、食べたら毒。
で、人ってこの“見た目のそっくりさん”に大体感情を乗っけます。
『放っておけない!』
『助けなきゃ!』
『自分がやらないと!』
『イライラする!』
って、火事場のテンションで突っ走る。
気づけば、自分とはある意味無関係な宿題を抱えて、心のバッテリーをガリガリ削っている。
私から見れば、『あー、また同じ問題で悩んでるな』っていうのが透けて見えるんだけど、当人は人も状況も違うと思ってるから気づきようがない。
言ったところで伝わらないと判断したら、もう黙って聞くしかない。
結論、9割は投影。残り1割は純粋に『今ここでやらなきゃマズい案件』。
でも、この9割を見抜けないと、人生ずっと“他人の教科書のページを勝手に破ってる人”になる。
これ、もったいないどころか、業(ごう)のポイントがガンガン加算される遊びなのでご注意を。
その仕組みを解説します。
なぜ課題(投影)の見極めは難しいのか
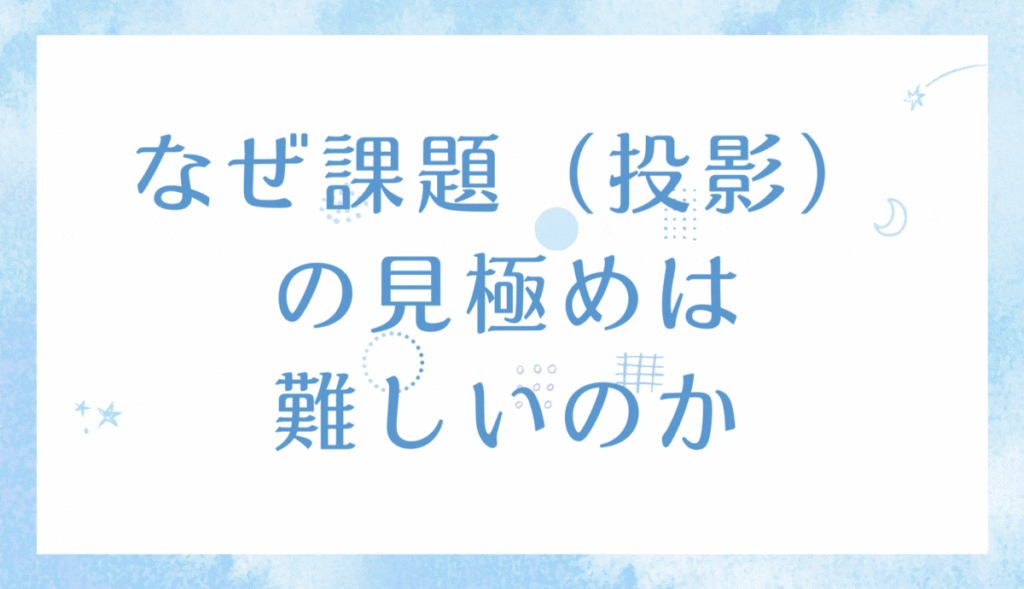
課題の見極めというか、投影ね。
問題の中身は同じ、見え方と出方、人が違うだけで、翻弄される人間たちの図。
わたしからしたら、

また同じ問題で悩んでるじゃん。
ってやつ。
聞かされるこっちは、



人と状況が違うだけで、種は同じだけど?
って言いたいけど、言ったところで気づきようがない状態だと判断したら、知らないふりして聞かなきゃいけなくなる。
それがしんどいから、距離を取るんだけど。
- 見た目が似ている
- 感情の介入
- 宇宙(縁起)の仕掛け
① 見た目が似ている
課題の見極めが難しいのは、宇宙がやたらとひっかけ問題を出してくるから。
しかもその問題、見た目がそっくり。
パッと見は『自分の課題』っぽいのに、開けてみたら中身は『他人の課題』というパターンが山ほどある。
例えるなら、山で見つけたキノコ。
毒キノコかそうでないかを見極めないといけない。
見た目はどちらも同じように見える。
図鑑を見ても、区別がつかない。
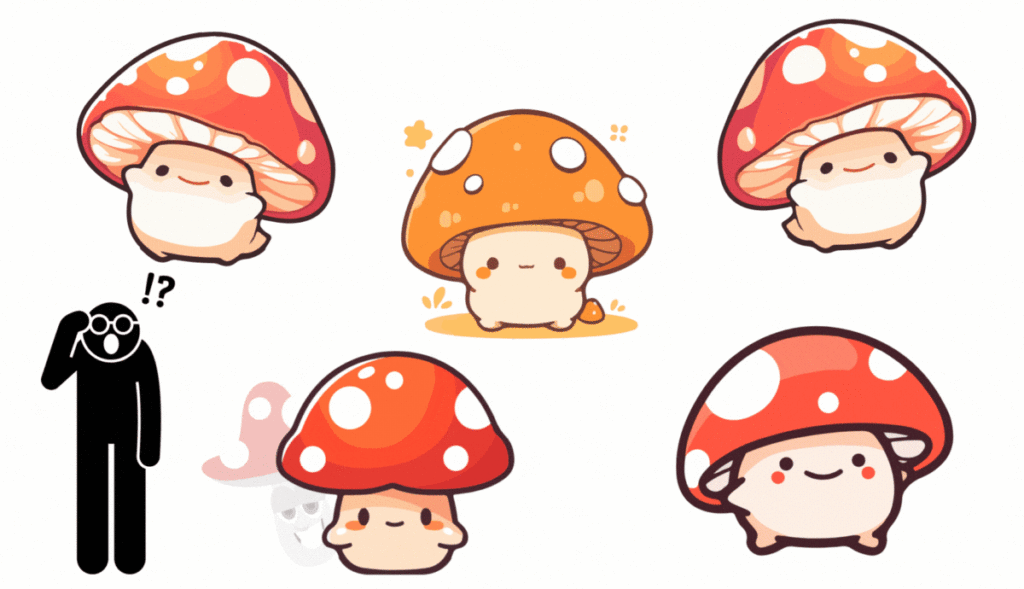
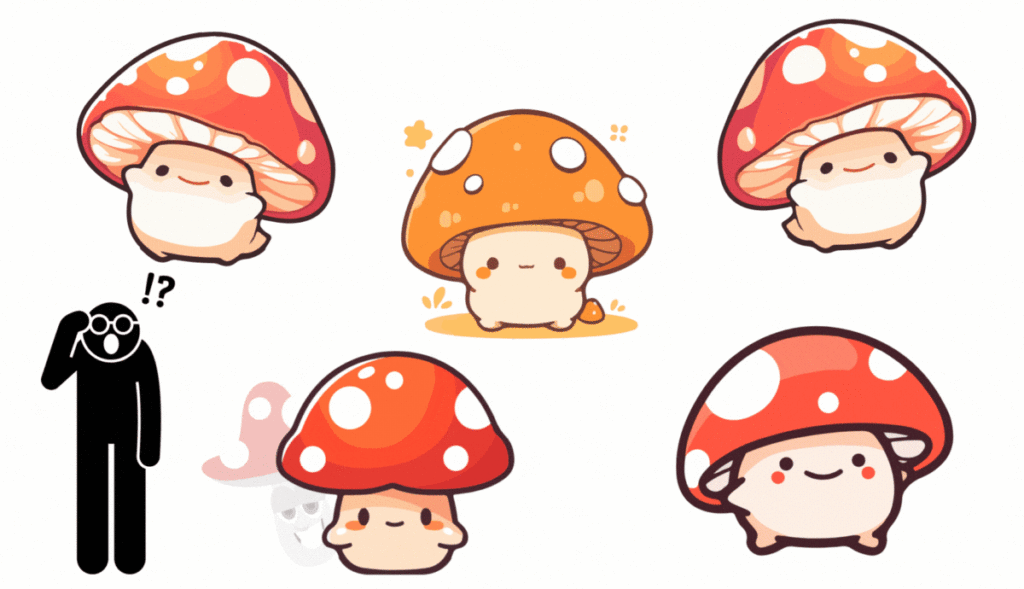
そして、この“見た目に騙される”時ほど、だいたい感情がセットで乗っかってきます。



放っておけない!
助けないと!
自分がいないとダメなんだって!
自分以外助けられないんだって!
イライラする!
腹が立つ!
ぜーーーんぶ、自分。
――この熱量が、まるで火事場の勢いで判断力をぶっ飛ばす。
その結果、気づけば他人の課題を抱えて、エネルギーも時間も吸われる羽目になる…これが『持っていかれる』の王道パターン、実は自分の内側にある未解決部分(投影)が反応しているだけの場合も多い。



つまるところ、自分の中にも同じ種があるから反応してしまう図ね。
投影じゃないのは↓こういうのくらいでしょ。
明らかに自分とは無関係な、客観的に緊急度の高い問題
例:通りすがりで事故を目撃し、救助(自分の過去トラウマとか関係なし、単に今ここで動かないと人命に関わる)
専門家としての責任や役割で対応せざるを得ない状況
例:医師が急患を治療する、消防士が火事現場に駆けつける(これは職務、個人の投影とは別軸)
9割は投影、残り1割は純粋に『今ここで対応すべき課題』、これくらいの比率でしょ。
② 感情の介入
課題の見極めを狂わせる最大の犯人――それは感情。
特に
『助けたい』
『放っておけない』
『なんとかしてあげたい』
『イライラする』
という思いは、ほぼ間違いなく“投影”が正体。
やっかいなのは、この感情がまるでそれが自分の課題であるかのように錯覚させてくること。
錯覚というより、自分の課題という自覚もなく、相手の人生領域にズカズカ入り込み、その人が背負うはずの“宿題”を、自分のリュックに入れてしまう。
これが投影の正体。
そして、しばらく歩いてふと気づく――



……なんか重い、この荷物。
そう、それは相手の『業(ごう)』。
本来は本人が解くべきパズルなのに、なぜか自分が抱えている状態。
まぁ、結局は自分の業でもあるんだけどね。
業の入れあい合戦。
感情はエンジンとしては優秀ですが、ハンドルを任せると平気で崖に向かって突っ込む。
だからこそ、感情の熱量と課題の所有者は、必ず切り分ける必要がある。
③ 宇宙(縁起)の仕掛け
宇宙の悪ノリ。
あなたがまだ解けていないテーマや未解決の感情があると、それにそっくりな出来事や人を何度も何度も送り込んでくる。
これは偶然じゃなく、縁起の仕組みとも言う。
同じ要素を持つもの同士は引き寄せ合い、互いの『課題ボタン』を押し合うようにできている。
例えば
- まだ『自己犠牲モード』を手放せない人には、『助けてオーラ全開マン』が現れる
- 『承認欲求の渇き』を抱えていると、『褒めてくれない上司』や『無反応なパートナー』が配置される
- 『怒りのスイッチ』が残っていると、見事に押してくる“その筋の人”が登場する
これらは全部、宇宙の『宿題出し直しシステム』。
解けないままだと、学年を変えても教科書を変えても、中身はほぼ同じ問題が出てくる。
そう、人生ずーーっとコレ。
だから、自覚的じゃないと『なんでいつもこういう人ばかり…?』と無限ループにハマるの図。
逆に、自覚的になれば『あぁ、これ前にもやったテスト』と気づき、もうその課題は受け取らずにスルーできる。



人生はテスト。
歌にもあったよねぇ。
課題かどうかを見極める2つの質問
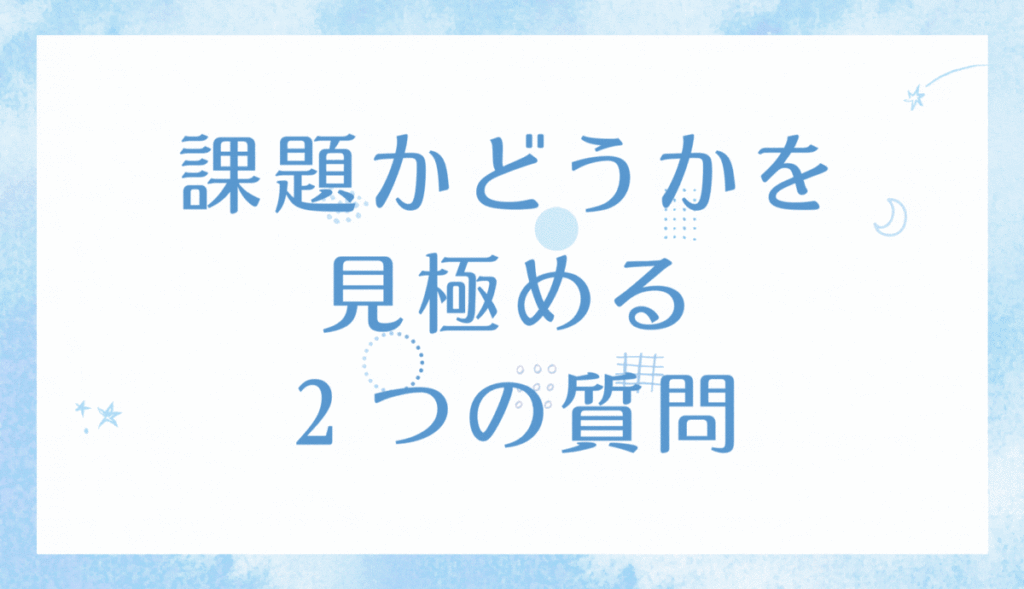
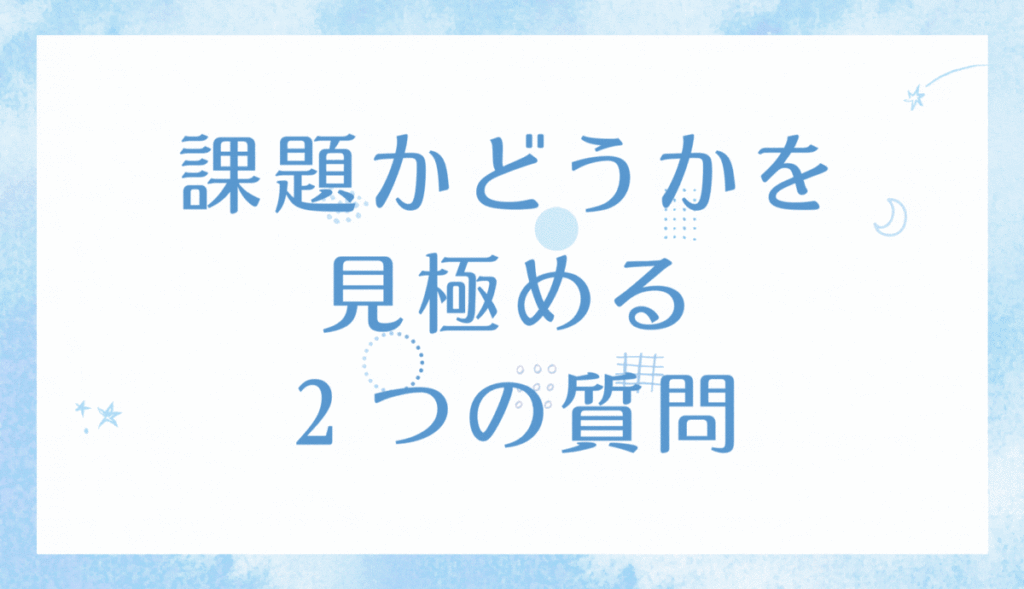
- この課題を解くべきか否か
- この課題は、相手が自分で解くべきものではないか?
問1:この課題を解くべきか否か
目の前に課題が来たとき、私が最初に確認するのは、
『関わって自分が消耗しない?』
次に問うのは、
『介入することで相手の成長を奪わない?』
『私が入ることで相乗効果が生まれる?』
この二つに『YES』と言えるなら、関わる価値はある。
それが相手にとってもプラスになり、自分の糧にもなるから。
さらに感情にも問いかける。
『できる?できない?やりたい?やりたくない?』
――意外と、やりたくないこともある。
たとえばこども園時代、娘が4歳のとき、お友達とちょっとしたもめ事があって、うちの子が泣いてしまった。
様子から明らかに療育対象だと感じたけど、余計なお世話だとも思った。けど、縁ができた。



この事件の縁起は?
わたしの役割は何?
きっと、小学校3年生くらいで大きな壁にぶつかる。
それが想像できた。その子の未来を考えれば伝えたほうがいいと思って、園にやんわりと伝えた。
結果は……何も変わらなかった。
このときの結論は『タイミングじゃなかった』。
そういうことだろう。
つまるところ、相手に受け入れる準備ができていなかった。
あと、ここはタイミングではあったものの、スルーするということが必然であった場合、他の事象と絡み合うことになる。小さく言えば、別の他者などが関わり学ぶ必要性があるとも見れる。
わたしは絡みたくないのでね。
いつもいち早く抜ける。
見方は色々ある。前にも説明しているが、全ての歯車が一致して、事が起こる仕組み。
- 受け入れなければいけない期間だったから、わたしが配置され、相手の親と園に伝えられた可能性
- わたしが適切な対応が取れるかの試練
- わたしの娘の試練
- 同級生とその家族の試練
- そして園(組織)の試練
- ここを通った先にある、別の他者の試練(まだ回っていない歯車がある、ここから先回り出す)
結果は、受け入れられなかった。相手目線で言うなら、受け入れた方がこの先かなり楽だったろうと思う。
課題はあくまで、自分の成長のために宇宙から渡される宿題。
他人の宿題を代わりにやっても、自分には点数はつかない。
むしろエネルギーを消耗し、相手や自分の成長機会を奪うこともある。
この件で言うなら、受け入れられなかったことを引きずり、親と園と永遠に揉める図だろうな。
結果、その子は小学校に上がってから大変になっていった。
このケースでは、もしかしたら娘自身の課題でもあったかもしれないから、それを奪うと、わたしの業となり返ってくる。年数が経つと業は大きくなるから、こういう芽は早いうちにさっさと摘むに越したことは無い。
だから、伝えるべきことは娘に伝えた上で、その経験を手放した。
十人十色、千差万別、それを色々な方法で教えた――その線引きが大事だから。
6歳にはそれをクリアした。



上手に遊べるようになってきました。
交わし方、遊び方、はぐらかし方、色々上手になったんだと思う。
もし、わたしが親と園と揉め、半ば強制的に療育を勧めたとして、その方向に進んだとしよう。
となると、我が子の課題が削られたことになる。
どこかでまた遭遇した可能性も高い。別の誰かとね。
そのとき何歳だろう?同級生の療育も上手く運ばない可能性が高い。
そしてわたしは園と保護者をある意味敵に回すことになる。
何のメリットがあるというんだ?そういうことだよね。
発言するときには、立場がいる。
それを超えて発言するときには、余計な業を背負うことになる。
それでも、目の前に課題が置かれたら、自分の立場を考えた適切な処置が求められる。
問2:この課題は、相手が自分で解くべきものではないか?
『手伝った方が早いし、うまくいくから』
『自分がいないと、この人どうなってしまうの?』
『イライラする!こんくらい簡単だろ!』
『助けて欲しそうだから、助けないと』
『泣いてる、可哀想』
『怒られてる!可哀想』
そう思った瞬間に、一度ストップ。
それ、本当にあなたがやるべき?
もしかすると、その課題は相手が自分の力で解くことで成長するための大事な機会かもしれない事実。
先回り解決への業



なぜ助けたいと思うのか、その思いの正体を突き止めたことある?
説明すると
① 見た目のストーリー
- 助けてほしい人がいる
- 助けられる私がいる
- 外から見れば、美談や優しさに見える
② 中身の構造
- 本来は『助けてほしい人』には自立が必要
- 『助ける側』にも、自立したうえでのサポート姿勢が必要
- しかし実際には
相手は『助けてもらいたいまま』でいたい
助ける側は『助けている自分』で自己重要感を得てしまう - 結果:『助ける⇄助けられる』の循環が心地よくなり、抜け出せない
③ 本質
- 双方が無意識に依存し合い、課題の本当の解決が遠のく
- 助ける行為自体が相手の自立を妨げ、自分も相手の存在に依存する
- これが『共依存』の温床
もしあなたが先回りして解決してしまったら、その人は経験値を得られず、同じ問題にまたぶつかる。
つまり“お助け”が、相手の成長を先延ばしにするブレーキになることもある。
ということは、相手の成長の機会を奪うことになる。
成長の機会を奪ったあなたにも成長を奪われる業が入る。
これが共依存。
人への馬頭への業
例えばこちらの課題、罵倒することで、自分の怒りを消化、相手は自己憐憫。
罵倒した怒りの内容に正当性があると、あたかも自分が正しいことをしていると思える。
そう、思いたいから。
触発されるのか。
罵倒することで怒りを消化させることにより、相手には自己憐憫という業が入り、罵倒側の業も深くなる。



その怒りの正体を考えたことある?
なぜ、こんなにもイライラするのか。
説明すると
① 見た目のストーリー
- 罵倒したい人がいる
- 罵倒される人がいる
- 罵倒したい人に正当性がある場合、その罵倒は正当化される
- 罵倒したい人に正当性が無い場合、罵倒した人に批判が飛ぶ
② 中身の構造
- 罵倒されることで『私は可哀そう』『不出来』という自己憐憫モードに入る
- これにより、相手は自立・行動のエネルギーが低下し、『被害者』ポジションに安住しやすくなる
- 被害者ポジションにいずらくなると、外敵を創り出すこともある、自己正当化
- 怒りを外に出すことで、自分の内側の不快感・モヤモヤを一時的に消化
- 怒りの対象や内容に『正当性』があると思えれば、自分は正義の側だと錯覚できる
- 実際には『正義だから怒っている』のではなく、『怒りたいから正当性を探す』ケースもある
- 結果、怒りを繰り返す回路が固定化 → 業が深くなる(未解決感情の蓄積)
③ 本質
- 罵倒する側:怒りの感情に依存し、自己重要感や正義感を強化するが、解決には近づかない
- 罵倒される側:自己憐憫に依存し、行動力や自己効力感を失う、外敵を創り出す
『罵倒によって自分の感情処理を相手任せにする構造』が業を積む。
罵倒の正体は怒りではなく、感情処理能力の未熟さからくるもの。
そう思う。



だから、距離を置く以外無いと言う。
- 怒りを健全に処理するスキルがない → 罵倒で発散
- 発散が一時的な快感になる → 依存化
- この繰り返しが『業のループ』
人との対立を避けるへの業
例えばこちらの課題、人との対立を避ける、自分が我慢すればいいという思いから、場を丸くする意味を勘違い。
家族は愚か、他人にもその対応で、いつの間にか本来の自分が不在。



その正体を考えたことある?
なぜ、こんなにも人に合わせようとするのか。
説明すると
① 見た目のストーリー
- 波風立てないことで、上手に世渡りできているように見える
- 周囲からの評価は『穏やかな人』『優しい人』
② 中身の構造
- 実際は、内側でモヤモヤや不満が溜まり続ける
- 根底には『対立したら嫌われる』『拒絶される』という恐れ
- 相手を優先=自分を後回しにすることが習慣化
- 我慢 → 感情抑圧 → 自分の本音が分からなくなる
- 存在感が薄れ『誰の人生を生きているのか』が分からなくなる
- 『穏やかな人』『優しい人』を演じることで存在確認を続ける
- その存在確認は依存の温床であると同時に、相手に業を入れる(相手の自立を奪う)冷床にもなる
- その冷床に気づけないこと自体が、自分の“冷たさ”に気づけない状態である
- 優しさ我慢ではないことに気づけない、優しさの勘違い
- 『場を丸くしている』のではなく、“自己不在”を強めているだけ
- 結果、回路が固定化 → 自身の業が深くなる(未解決感情の蓄積)
③ 本質
- 対立を避ける行為の正体は、“平和”ではなく“恐れ”。
- 『拒絶されたくない』『傷つきたくない』という恐れが、場を丸くするふりをして働いている。
- そのため、表面上は静かでも、内側では業が積み重なる。
→ 自分を生きない業(本音の放棄)
→ 相手に依存する業(他人に合わせることで自分を保つ)
結果的に、家族にも、他人にも、『都合のいい人』『便利な人』というポジションに落ち着きやすい。
本当の『場を丸くする』とは、
- 自分の本音をちゃんと持ち
- 相手の本音も尊重し
- その上で折り合いを見つけること。
それをせず『我慢』で丸め込むのは、ただの対立回避依存だ。対立を恐れるあまり、結果として自分も相手も不自由にしてしまう構造。
これは平和主義とは呼ばない。



みんな他人を利用しながら一生懸命、存在確認ご苦労さまですー。皆問うといいよ、自分をね。それが先だって。
何をしているかの自覚なさすぎだって。
見ろ、自尊心のない者は、皆こうなるんだよ。
平気で人を利用し、踏みつけ生きて行く。
その存在が我が子でもだ。
その自覚すら存在しない。
そしてそれを継承していく。
自身の子どもや生徒にね。
他者のためと言いながら、ぜーんぶ自分のための行動。
まぁ、自覚があるならいいんじゃないかな。
継承(けいしょう)の自覚だよ。



わたしは警鐘(けいしょう)にしか見えないけど、捉え方や生き方は人それぞれだから。自由なんじゃない?
けど、その継承は何人にされるのかしらね。
あと、心の筋肉を鍛えるってこういうことよ。
自己の欲求(嫌われたくない)に向き合って、相手のために行動する力のこと。
それが本当の他者のための行動(相手の成長を奪わない)だもの。
嫌でも鍛えられるわよ。
宇宙はそれぞれに専用カリキュラムを配布してる。
自分の教科書にない問題を解き続けるのは、時間もエネルギーももったいないばかりか、相手の教科書のページを勝手に破ってしまうようなもの。
しかも――
自分の教科書にある問題すら読めてないのに、人の教科書のページを破るのよ。
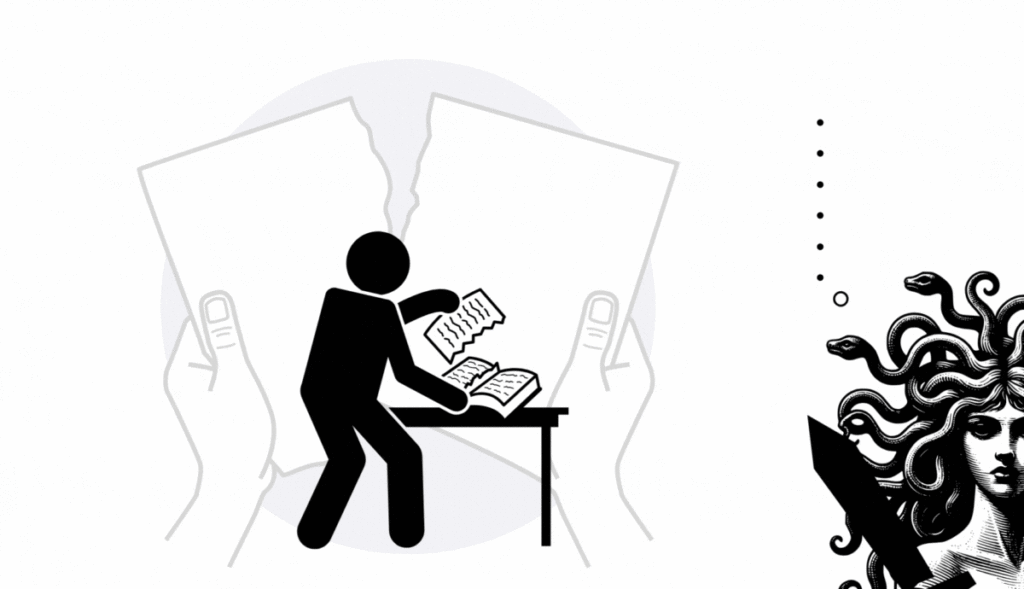
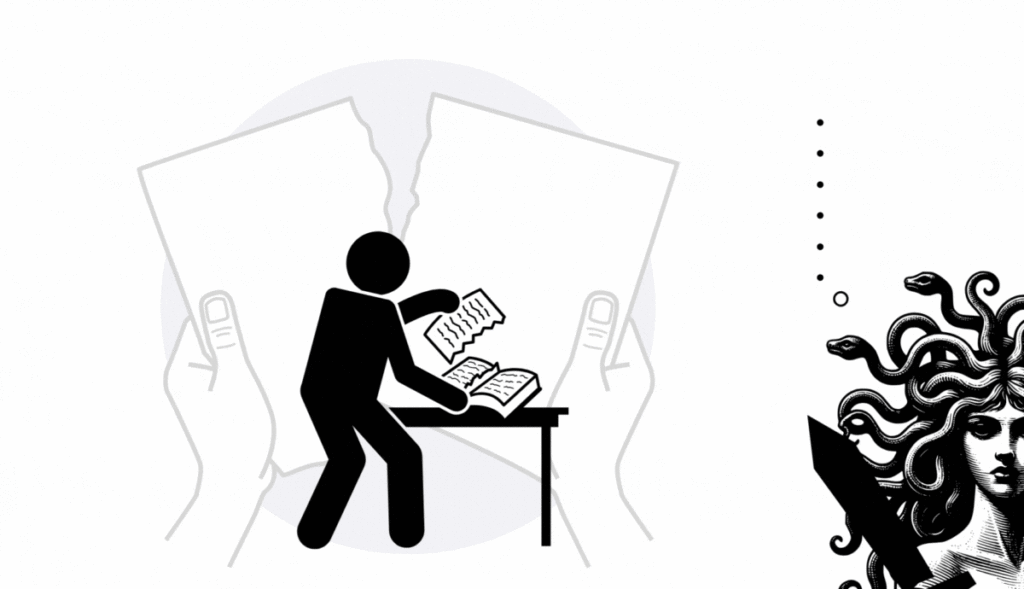
……やってること、むちゃくちゃでしょ?
誰しもがそういう状態にあるっていう自覚があるだけでも、パラダイム増えない?問うってすごく大事よ。
でないと、みんな自分が完璧と思うでしょう?この常態で、人と向き合っていると考えてみてよ。
目の前のその人と、あなたが今いる環境は、あなたの存在確認欲求を満たすために存在しているんじゃないのよ。
皆、教えられるような段階にいないのよ。
ならできないことを認めたらどう?教える立場にいるのなら『一緒に学ぶ』これくらいの視点やパラダイムがあってもよさそうよ。
教える、そうじゃなくて、共に考えるという余白は残せないの?けど、問い方も問われるわね。
問いが雑だと答えを渡すことになる。ヒントの渡し方、そこからよ!雑な問い=相手に推測させて“答えの枠”を渡してしまう問い。
つまり、問いの時点で答えの範囲を制限。
これをすると、相手は 答えを探さずに出題者の正解を当てに行くモードに入る。
何の意味があるんだよ。
だから、アドラー習得だって言ってる。
嫌われる勇気でもいいから1,000,000回くらい読んだらどお?



ガチャガチャ書いてるけど、わたしなんてゲシュ崩壊後に目指すべき目印も無かった。
何が正解かわからず、それまでに読んだ本と経験、崩壊後に読んだ本と経験、これだけの知識をまとめて脳内に埋めたのよ。
それがどんだけ孤独だったか分からないと思うわ。
これがあるだけマシよ。
厳しいと思うかもしれないけど、知っても知らないでも、これが世の中の構造よ。
異論は認めるけど、なくない?あったら聞かせて欲しいわ。
そしてもっと厳しくなると、こうなるよの。
どの口で教育とか言ってるの?
何度もいうけど、だから過酷なのよ。
自己に向き合うって修行みたいなものだから。
だから、子どもの自由さえ保証してくれたら、後はどうでもいいって、そういうことですよ。
せめて、全てに自覚的であることは、大事だと思う。
じゃないと、成立しないわよ。
自覚的であれば、偽りの平和主義でも、優しさに映る人には映る。
それが救いになるから。
ただし、自覚的でないと依存の温床にしてしまう。
雲泥の差になる。悪いから治せってことじゃない、自覚なしに教育を施すことの意味を問い、意識を持つことは大事だと思う。
欠点なんて、わたしには、探さなくてもいくらでもある。
それには自覚的だ。欠点まみれだ。気づきには時期がある。
自覚的でない時期も必要だった可能性すらある。
それも縁起かもしれない。
未来に、子どもたちが楽しみながら夢を追える人生。
自己実現できる人生。
言うのは簡単だ。
そう、思いませんか。
自覚的に課題を選ぶということ
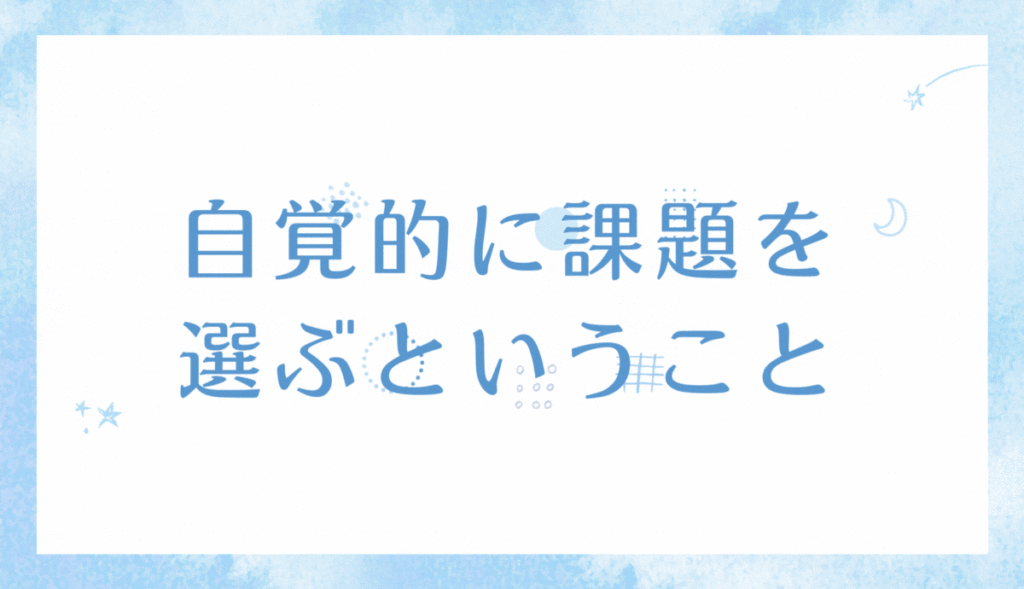
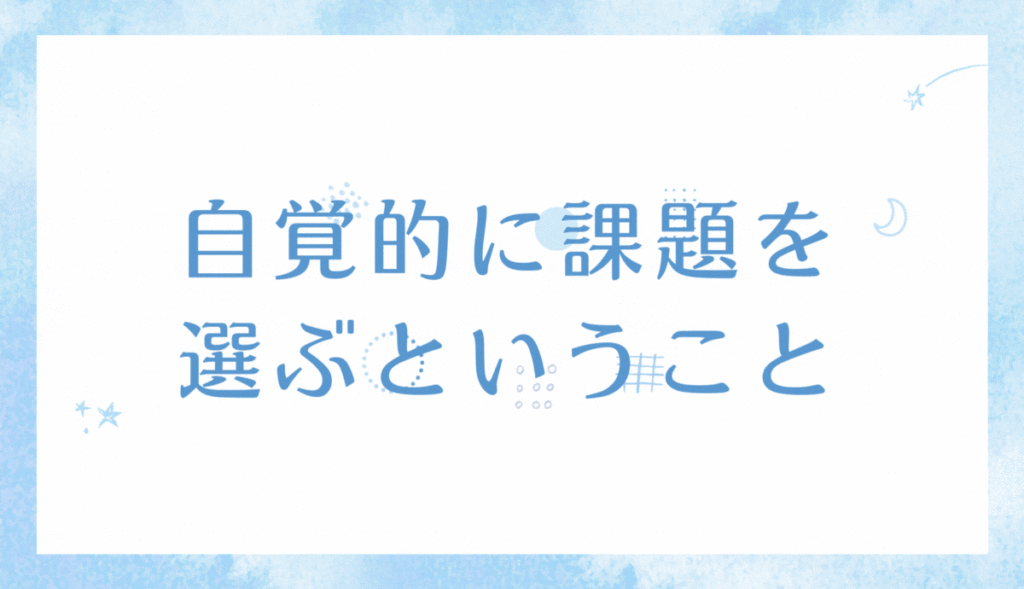
- 使われる側から使う側へ
- 課題を選ぶメリット
① 使われる側から使う側へ
『天国おじい』の本で、神様にお祈りをするのなら『わたしを使ってください』だというものがあったけど、これは、経験を積み、学びを得るためには必要なフェーズでもある。
ただ、この段階では、降ってくる課題をほぼ無条件に受け入れるから、ときに自分のエネルギーを消耗し、他人の宿題まで背負いこむことがある。
それが投影だ。
その投影を終わらせない限り、課題を選ぶ域には行けないと相場が決まっている。
投影に翻弄されている者は3次元以下。当たり前だろう。
やがて経験が増え、投影が終わり、構造が見えるようになると、『これは受ける課題』『これはスルーする課題』という選別が可能になっていく。
このとき、自分の成長のために法則(縁起や引き寄せ)を使うフェーズに入る。
受けるべき課題は、自分が成長できるものであり、相手の成長を妨げないもの。
使われる側から使う側へ――この転換が、人生の主導権を握る第一歩だ。
この次元に到達できると5次元という認識でいいんじゃないかな。
投影に翻弄されている段階(3次元以下)
- 自分の内面を相手に映しているのに気づけない
- 感情的に振り回され、『課題』を選ぶ余地がない
- ここではまだ『他責』『愚痴』がデフォルト
投影が終わり、構造が見える段階(4次元くらい?)
- 経験が増えることで『これは自分の反応だ』と無意識でも気づける
- 見える化が進むと、『受ける課題』「スルーする課題』を選別できる
- ここから『課題の分離』が実際に可能になる
法則を使うフェーズ(5次元)
- 縁起や引き寄せといった“人生の構造”を意識的に使う
- 『使われる側』から『使う側』へ転換
- 自分の成長を促す課題を選び、同時に相手の成長を妨げない
- 人生の主導権を自分で握り、自由が広がる
使われる側は、宇宙のガチャで何が出ても受け取るプレイヤー。
使う側になると、ガチャ台ごと選べるプロプレイヤーになれる。
選べるということを知っているか否かも大事で、ここに気づかない人はずっとプレイヤーのまま人生を歩くことになる。
② 課題を選ぶメリット
課題を選ぶというか、投影に気づくメリットとも言いかえられる。
エネルギーの浪費を防ぐ
他人の宿題やドラマに巻き込まれなくなるので、精神バッテリーの減りが遅くなる。
成長速度が上がる
本当に自分に必要な課題だけにフォーカスできるから、レベル上げがサクサク進む。
『レベル5でラスボスに挑んで全滅』みたいなムダもなくなる。
他人の業に巻き込まれなくなる
不要なトラブルや感情の渦に引きずり込まれず、冷静さと客観性を保てる。
つまり、他人の未解決感情やトラブルに巻き込まれなくなる。
『他人の地雷原を、なぜか自分が全力で駆け抜ける』という謎ミッションが消滅。
相手の投影の構造化、見方
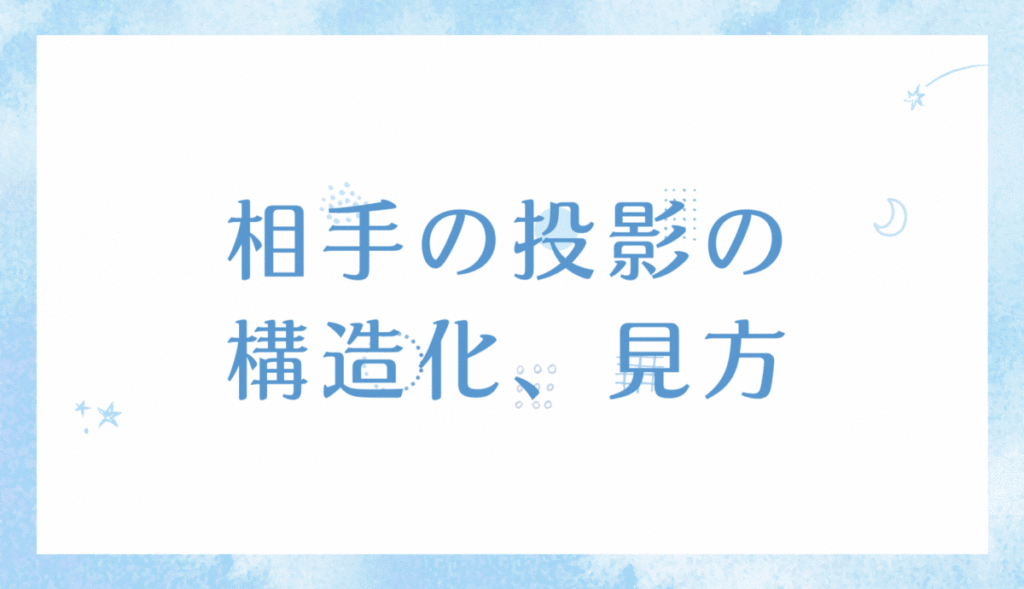
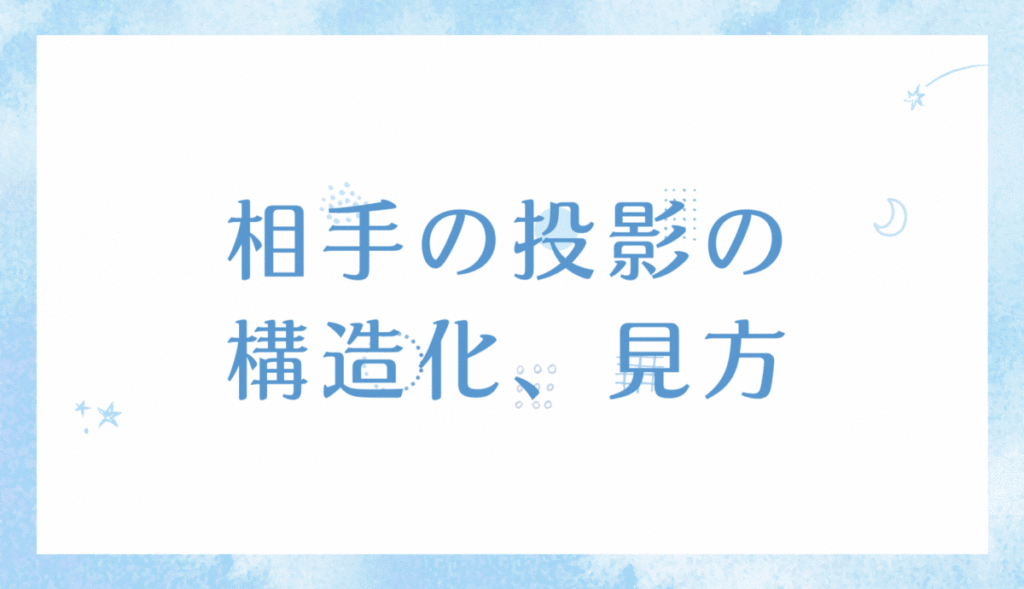
相手に投影が見えるときの見方を書いて置こうと思う。ここは気を付けておかないと、コケるところだ。
例えば、相手に受容を求めて慢心がでたときの話を書こうと思う。
わたしが受容を求めて、相手に慢心が出たということは、わたし側に受容力がないという証明になる。
つまるところ、相手の未処理の課題が残っている。
ここまでが構造化になる。
この投影を、つまるところ相手から、
- 最初からお前を受容する気なんて無い
- お前は条件付きで受容される存在だ
と突きつけられたという解釈をしたとしようよ。これは相手ではなく、自分の投影になる。
これが事実かどうかは、別にしてよ。
意味が分かるかな。
だから、わたしに受容できる器が無い=そんなお前を受容できない、わたしに受容できる器がない=俺を受容できる資格がお前に存在しない、条件次第で受容してやる。
こういう突きつけよ。これが歪みになる。
投影を見抜くには『構造化まで』が安全圏
事実の観察(構造化)
例:相手に受容を求めた → 相手に慢心が出た
→ 慢心が出た=相手の未処理課題が反応した
→ ここまでは“事実と構造”を切り分けている段階
意味付けを乗せる(危険地帯)
例:この事実を『相手は最初から受容する気なんてなかった』『自分は条件付きでしか愛されない』と解釈する
→ これは相手の課題ではなく、自分の古い傷や未処理感情が反応している状態(=自分の投影)
樹海入り(回避推奨)
意味付けが事実確認を上書き、相手への問いかけもせず、自分の解釈だけで世界を塗りつぶす
→ これをやると、仏教でいう『空』の世界まで自分の投影で歪める危険がある
事実投影のロジックは本当に難しい。
自己理解が浅いと簡単に歪むから、『どこまでを構造化として見るか?』という視点がとても大事。
ここでは内容の正否は関係なく、あくまで事実だけを拾う――これが構造化。
そして、その“見えている事実”をどれだけ正確に拾えるかという能力も必要になる。



そして、このケースのような解釈は、仏教でいう『空』の領域に踏み込む話になる。
私は『相手は最初から受容する気なんてなかった』『自分は条件付きでしか愛されない』と解釈すること自体が、相手の尊厳を軽視する行為だと考えている。
なぜなら、私は自分への尊厳が高い分、相手からも尊厳を奪わないから。
もちろん、『明らかにそうだ』と断言する人もいるし、わたしが断定的に見ることもある。
基本的に私は、構造化までで止める。
それが相手への敬意であり、私にとっての“アドラーのいう他者信頼”に値する。
つまり、事実だけを押さえたうえで問い、相手の尊厳を奪わずに、相手がどう受け止め、どう行動するかは委ねるという姿勢。
しかし今回は、最初から心理学的に試される場面が多く、なかなか感情が休まらなかった。そこで、ゲシュタルトを掘ってみたという経緯だ。
要するに仕返しになるな。
あぁ、責任は取るよ。
一応伝えておくけれど、この言い方が逆効果になる可能性も分かっている。
それでも、その先は空(くう)になる。そこから先は、私には決められない。
私は数手先を読むことはできていたけど、思考のプロセスは常に経過型。だからこそ、伝えてきたことに嘘はない。
才能は確かにすごかったし、未熟さというか、そこから来る弱さを受け止められるか――それは常に自分に問うていたから。もちろん、私自身にも欠けがあったし(これは自覚的)。
相手は気づいていなかったと思うが、相手の行動の意図は最初から読めていたつもりだ。
心理学的に強く試されていると分かれば、臨戦態勢を取らざるを得ない。
それは疲れる。だから前半で止めるよう示唆したつもり、それでも止まらなかった。
その選択を弱さだと解釈し、できる限り寄り添ったつもりだ、しかし添えていないところもあったんだろうね。
それはごめんね。
それでも、本当にすごかった。私がそう動きたくなる所為は――そう読み込めば行動の意図が見えてくる。
まぁ、天才だったとは思う。
これをできる人はそうそういない。
乗ってしまう人も多いかもね。
わたし以外は。
それは認める。私は経過型で動くし、構造で見るから、そこに翻弄されることはなかったけれど(序盤で慢心をキャッチ)。



だけど、投影に自覚的でないとねぇ。
今回の縁起の一部はこうだろう。



知識があるからと、慢心している人がいるんだけど、あなた何とかできない?あなたの欠けも見抜いてくれるけど。
わたしの方が少し賢かったという結論が出た。



よく頑張ったね。



まぁね。
桂馬の高跳び歩の餌食とは言うたものの、みんな、この人の知識は本物よ。
舐めちゃダメなヤツ。ボンヤリしてると分からないのよ。



気づかないから愚か者層に入れられるんだろうけど。
わたしは、門の前で門をぶっ壊すから。


ごんぎつねで見る構造化※問うべきところ
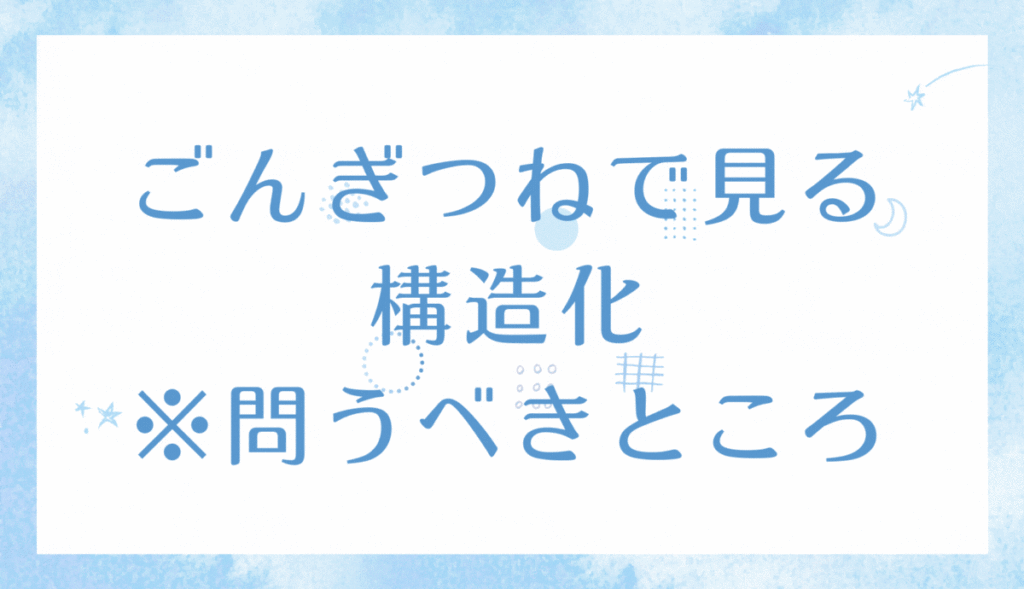
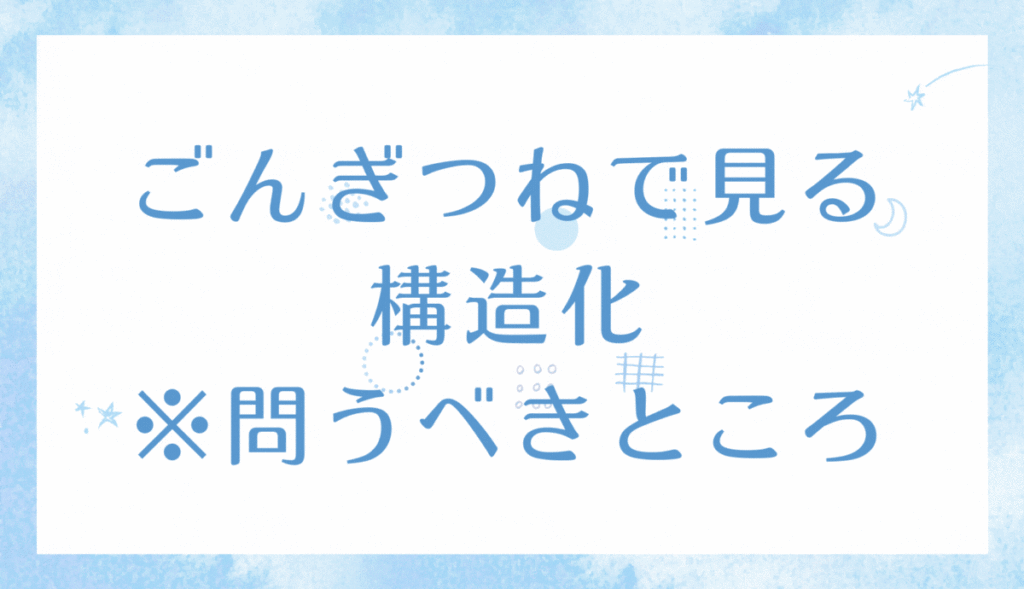
以前、ごんぎつねは、ごんも兵十も両者共に、作者である『新美南吉』のことを書いた物語であると記事にしたんですが、構造化で問うべき個所を見てみると…
事実のレベル(構造化段階)
- 兵十の仕掛けたカゴに悪戯をして鰻を逃がした
- 兵十のお母さんが亡くなった
- ごんは栗や松茸を持っていった
- 兵十はそれを『誰かが置いた』までは分かったが、ごんだとは知らない
ここまでは事実。
意味付けが乗った瞬間(ごんの投影化)
- 兵十は自分と同じ孤独だ
- ごんは鰻の悪戯を悔いた(理由は母親が鰻を食べたかったに違いないというもの)
- 兵十は恩知らずだ(本では書いてないよ)
- 自分の好意は無視された
- 自分の存在を分かってもらえない
この解釈は、ごんの過去(孤独・人との信頼欠如)の痛みと直結。つまり、『受け入れられない自分』という古いストーリーを、兵十に投影してる。
ごんが兵十に問うべきも構造化までが正解になる。



この恩知らずが!俺の好意を無視しやがって!
※こんなこと、ごんは言ってないけどね
だけど、みんな構造だけを伝えずに、投影に感情を乗せて問うたりするのよ。
ひどいのになると、投影部分しか言わないヤツもいる。
まぁ、合ってるところもあるかもしれないけど、間違えてるところもあるじゃない。
兵十が恩知らずって(本では書いてない)何?
正しくは、



鰻の悪戯ごめんなさい。魚、盗んだやつ届けてごめんなさい。栗や松茸を届けたのはわたしです。迷惑だったですか?美味しかったですか?
事実(構造化)だけを伝える手段。
だけど、大体人って、投影と構造化とごっちゃにして伝えるでしょ。
だからややこしいでしょ。それがまさに『投影の沼』とも言える。
ほとんどの人は、
- 事実(構造化)
- 自分の意味付け(投影)
を切り分けないまま、そのまま相手に直結させる。
で、その意味付けに“感情”がくっつくと、もう確信度MAXになるから、



これが真実だ!
と信じ込みやすくなる。



そんなワケないだろ!!!
だからずっと兵十に出会うんだ!
ごんぎつねの結末がずっと変わらない!!!
ごんで言えば、
構造化 → 兵十は俺に気づかない
投影 → 兵十は恩知らずだ(=俺を受け入れない人間だ)
がごっちゃになって、しかもそこに『俺は拒絶された』という過去の痛みが乗ってる可能性。
だから、第三者から見れば単なる“情報不足のすれ違い”でも、当人の世界では『裏切り』や『拒絶』に変換される。
これ、職場でも家庭でも友人関係でも、ほぼ全員が1回どころか万回繰り返してるやつ。
ややこしいのは、意味付けの中に事実も半分くらい混ざってること。
その“半分正しい”が、泥沼の入口。
まぁ、ごんぎつねの場合は、どちらも自分を描いた本だから、本来は、伝えてみようかな?の手段すらないのですけどね。
伝えたいことすら、分からない状態が描かれてるから。
まとめ
投影と宇宙の宿題の話をしましたけど、だからといって、



ほら!さっさと動け!課題クリアだ!
なんて追い立てるつもりはない。
むしろ、これを知らずにウロチョロしてると、人生に翻弄されるから『せめて自覚だけは持てよ』って話。
停滞するも、動くも、ぜんぶ自由なんだって。
善悪・正否なんてないよ。
だって、心が疲れてるときに無理やり動いたら、余計こじらせるでしょ。
そんなときは、宇宙にこう宣言すればいいんだって。



今は疲れてる。課題だと分かってる。でも、わたしはあえて動かない。動きたくない。
そうすれば、縁起の仕組みが勝手に動き、別の道をちゃんと用意してくれるよ。
しかも、あなたにとって最善のやつをね。
この“自覚的でいる”という一点が、未来の分岐を変えて行く。
停滞するにでも、なぜ停滞するのか?
という意味をちゃんと自覚しておけばいいんだって。
人生の初期段階でこれを知れた人は……はい、幸運。



つまるところ、この記事を読んだあなた、いま幸運の女神と遭遇中だよ。
大分、脅しちゃったかなーと思って。楽になったんじゃない?知らないけど。
ゾンビにはならなくて、済むから。周りはゾンビだらけだよ。
全然関係ないけど、全員に告いでみる。
恨ませてもらえる。そういう視点もある。思いっきり恨ませてもらえるという状況な。
けど、ある意味、楽にならないかな。どうだろう。
悪で良かったと。思いっきり『悪』でいてくれて、ありがとう。
まずは、そこに行けるといいな。
愚か者だから伝えておく。
本人に『悪』でいようとする自覚が無いから、成立はしない。
だから、同情する、しない、許す、許さないじゃない。
これは苦しまずにいる、一つの視点だ。今は、過ぎてもらって、構わないよ。
昔、ある村に、誰もが嫌う『悪役』を演じる人がいた。
村人たちは皆、彼(彼女)を憎み、怒り、時には涙を流した。
『悪役』は、ときに人の人生を翻弄する。
互いに、自分の怒りをぶつけ、都合の良い存在として互いを勝手に扱う。
だが、当の本人は、自分を悪だと思ってはいない。
もし彼(彼女)が姿を消せば、村には奇妙な渇望が生まれる。
なぜなら、急に自分と向き合わなければならなくなり、その不安と空白に、皆が再び翻弄されてしまうからだ。



こういうのに自覚的なのが、わたしです。

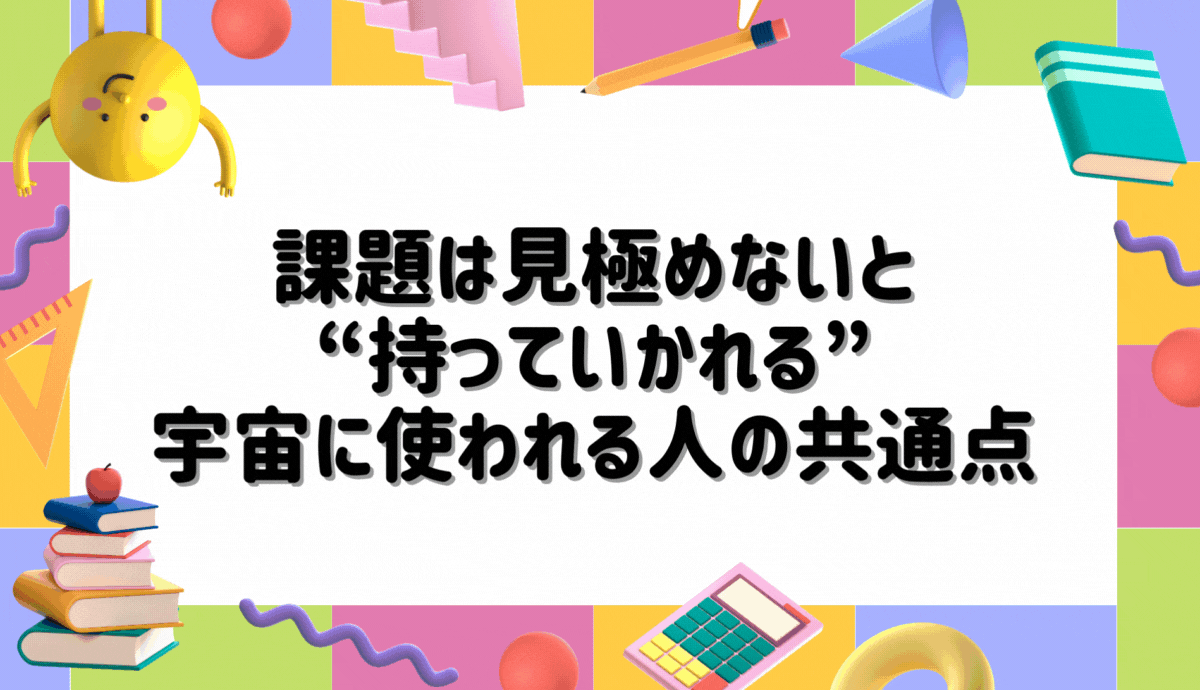

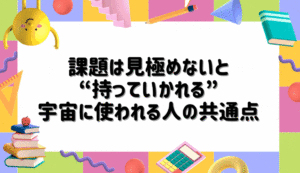
コメント