自分の内面を磨くには、『自己理解』と『課題の分離』が必要ってご存知でしたか?
自己理解がないまま内面を磨こうとしても、それは短編的な『他人の期待に応えるための努力』になりがちで、本当に自分にとって意味のある成長にはならないからです。
自己理解が進むと、人生を生きやすくなります。なぜかと言うと、悩みからの解放があり、笑顔が増えるからです。自然と勝手に自分磨きが進む。

ポジティブな言葉を使い、ネガティブな口癖をやめる 、他人の悪口を言わないようにするなど、小手先の方法はいくらでも溢れてますが、根本的な自分磨きにはなりません。
この記事では、『自分磨き=自己理解=課題の分離ができること』と言っても過言ではない、その理由についてまとめてみました。
なぜ自分磨きに自己理解が必要なのか?4つの理由


ポジティブな言葉を使い、ネガティブな口癖をやめる 、他人の悪口を言わないようにするなど、小手先の方法を試したとしても、人には時期があります。嫌な出来事に遭遇しやすい時期もあったり、ハッピーだと思える出来事が続くこともある。



嫌な出来事に遭遇しやすい時期に、ポジティブな言葉を無理に使うことで自分との乖離が起こることがある。だって、悲しいときに笑えって言われてるから。その乖離が自分の魅力を遠ざけます。ここでは、自己理解が必要な理由を4つ挙げてみました。
- 何を磨くべきかを知るため
- 周囲基準ではなく、自分基準で成長するため
- 自分を受け入れることが、本当の意味での成長につながる
- 『他人との比較』から解放される
①何を磨くべきかを知るため
『自分磨き』とひと言で言っても、何をどう磨くのか分からなくないですか?
何しよう、、、とりあえず、人の悪口言わないでおこう、、とか?
自分のどこをどういう風に磨いたらいいのか、分からない。自分の価値観や大切にしたいこと自体分からない、どの方向に成長しなければならないか考えない。
例えば、『自信をつけたい』と思っても、そもそも『なぜ自信がないのか?』を理解しなければ、正しいアプローチはできません。
ポジティブな言葉を使い、ネガティブな口癖をやめる 、他人の悪口を言わないようにするなど、小手先の方法を試すと言っても、なぜネガティブな口癖が出るのか?他人の悪口を言いたくなるのか?ここに向き合おうとはしない。



『なぜ?』ここに向き合わないといけない。
自己理解があると、自分にとって、本当に必要な成長ポイントが明確になります。
②周囲基準ではなく、自分基準で成長するため
他人の期待や世間の基準に合わせた『なんとなくの努力』は、自分の本質とはズレたものが多くなることがあります。
先ほどの小手先のテクニックもそうですが、例えば、『社会的に成功しなければならない』と思い込み、実際にはキャリアを追い求めているだけ、のことがある。
自己理解があると、『自分にとっての成功は何か?』と明確にできます。ということは、自分にとっての成功を求めるワケですから、人生は生きやすくなり、笑顔が増えることになり、すべては循環し、自分磨きに繋がって行くという法則が成り立ちます。



そう、自己理解することで自分磨きに繋がるというのは、世の法則とも言えます。自分の本当にやりたいことをしているときの自分って、キラキラ輝くから。
③自分を受け入れることが、本当の意味での成長につながる
自己理解が進むと『ありのままの自分を受け入れる力』が育まれます。
例えば、『自分には短所があるけれど、それも個性の一部』と認めることができれば、無理にポジティブになろうとしたり、変えようとするのではなく、その部分を『どう活かすか?』と考えることができるようになる。
ネガティブであれば、それは慎重さの表れでもありますからね。
自分磨きはまず、自己受容から始まります。
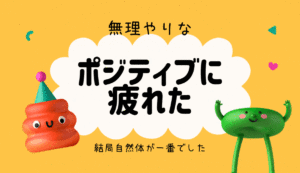
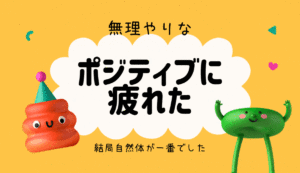
④『他人との比較』から解放される
『他人と比べて劣っている』という思考があると、自分磨きも『誰かに勝つための努力』になってしまう。
劣っている自分という思考がある人は勝ち負けの思想でいるので、第三者から見ても魅力的には見えないものです。当然の摂理。
自分磨きをして内面の成長を思うのなら、自己理解の心構えとして『自分は自分、他人は他人』という視点が大事で、そこを通して不要な比較や競争から自由になることができます。
自分の中の磨くべき基準を知ることに意味があり、その成長に集中することができるようになる。
自分磨きのための自己洞察はどうやってするのか?
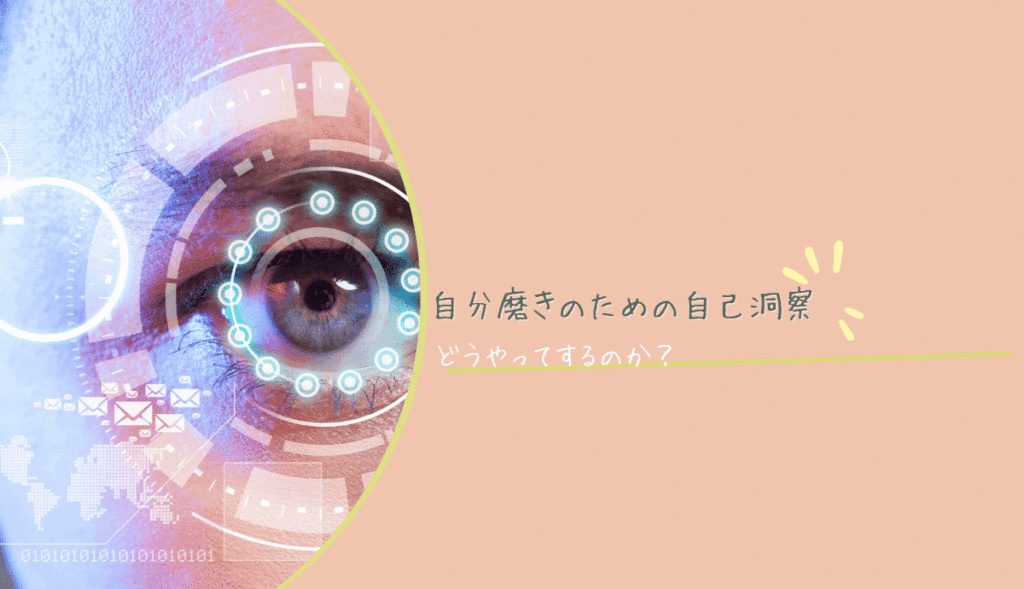
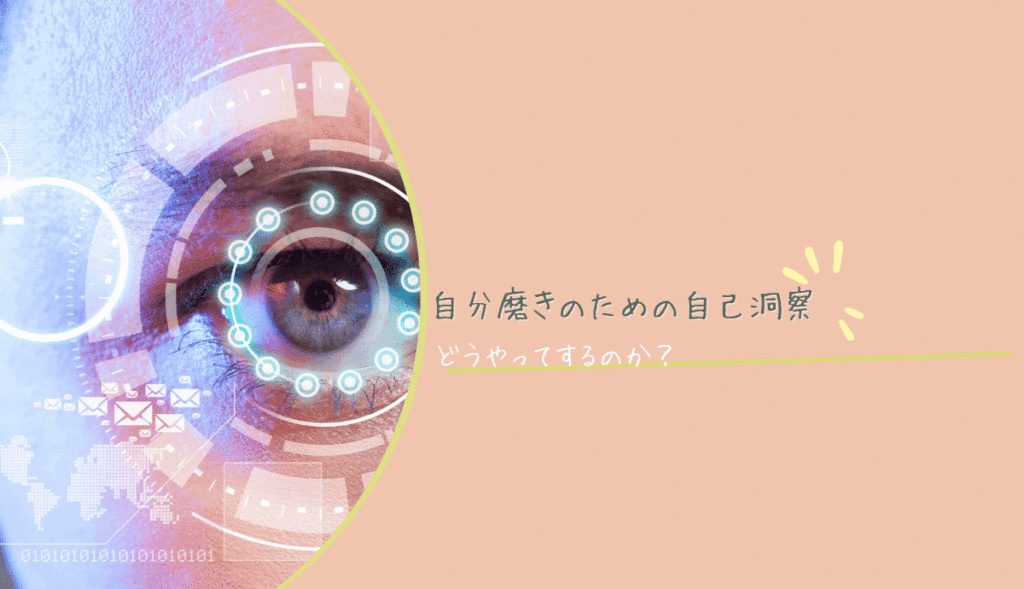
自分磨きをして内面の成長を促すためには、自己洞察が欠かせません。
ここでは、自己洞察の仕方を3つ紹介してみます。
- 『自分の価値観』を明確にする
- 『なぜそう思うのか?』を深掘りする
- 『課題の分離』を意識する
①『自分の価値観』を明確にする
『自分にとって一番大切なことは何か?』を考えます。
例えば、『自由』『安定』『挑戦』『愛』など、自分の核となる価値観を探ります。
②『なぜそう思うのか?』を深掘りする(自問自答)
何かがしたいと思ったら、『なぜそれがしたいのか?』を問い続けます。
例:『お金持ちになりたい』→『なぜ?』→『自由が欲しいから』→『なぜ?』→『自分の好きなことをしたいから』→ここで『本当に求めているのはお金ではなく、自由だ』と気づくことができる。
感情が動いたとき、『なぜ?』と問い続ける。
何かを選択したとき、
①『仕事を変えたい』→なぜ?
→②『今の仕事が嫌だから』→なぜ?
→③『自分のやりたいことができないから』→なぜ?
→④『そもそも、自分のやりたいことが分かっていない』
→ここで『自分は何をしたいのか?』という根本的な問いに気づく。
5回程度『なぜ?』を整えると、本質的な動機や自分の本音が見えてきます。
③『課題の分離』を意識する
他人の期待や評価を自分の価値基準にしない。
『これは本当に自分がやりたいことなのか?、誰かに認められるためにやっていないか?』などを自分に問い続けることも大事。
自分の選択に他者を入れないことです。
例えば、↑上述した『仕事を変えたい』ですが、③の理由が『嫌な上司がいるから』だとしましょう。
そもそもその仕事を選んだ目的は何でしょうか?
仕事の目的が『上司と賑やかな人間関係を築くこと』であれば、仕事変更の理由としては真っ当かもしれません。



システム開発の仕事がしたくて、新たな開発に挑むのが目的で入社したのであれば、『嫌な上司がいる』というこの理由は目的に沿わないことになります。
要するに、仕事を変える理由には値しないということです。
仕事と人間関係を切り離して考える必要が出てきます。
『システム開発を極めたい』、『新しい技術に挑戦したい』という理由でその仕事を選んだなら、本来の判断基準は『その環境が自分の成長に適しているか?』になる。しかし、『嫌な上司がいる』というのは、自分の成長や開発の可能性とは関係のない理由になっている。
要するに、、
『仕事を変えたい』という課題があります。
→その理由が『嫌な上司がいるから』となっている。
→しかし、最初の仕事を選んだ目的は『新たなシステム開発をすること』だった。
→ここで、『嫌な上司がいる』という感情的な理由が、本来の目的と関係があるのかを整理する必要があるのか?
→もし、上司の存在が『新たな開発への挑戦』を阻害するのであれば、それは『自分の課題』として転職を考えた方がいい、逆に、上司が嫌だというだけで目的に影響を与えないのであれば、それは『上司の課題』。
どの職場にも、合わない人や理不尽な上司がいる可能性がある。そのため、仕事を辞める理由が『嫌な上司がいるから』だとしたら、次の職場でも『嫌な上司がいるから、また辞める』という繰り返しになりかねない。
『自分の成長のために必要な環境かどうか』という視点を持つことが大事です。
本来の目的に立ち返ることで、より良い選択ができます。
『新たなシステム開発に挑戦してみたい』という目的に合わない気がするなら、転職の判断は正しいかもしれない。しかし、その目的を達成できる環境が今の職場にあるなら、上司の存在だけで辞めるのは、本来の目的とズレた判断になってしまう。
『自分の成長につながるかどうか?』を判断基準にするのが適切。
そこまで理解する必要がある。
そこをぼんやりしたままでは決断に鈍さが出てしまう。そこまで理解した上で、決断することに意味があります。
それが課題の分離。
課題の分離をしないとどうなるかというと、、
- 上司の態度や性格に振り回され、感情的な判断をしてしまう
- 『本来の目的』がぼんやりしたまま、転職また同じ理由で悩む可能性がある
- 『自分が本当に求めているものは何か?』が不明確なまま、決断の軸がブレる
こういったことが起こります。要するに、辞めるにしても、理由をきちんと自分の中で明確に理解できていることが重要。
外部の領域に土足で入らず(コントロールしようとせず)、逆に自分の課題から逃げることもせず、自分が影響を与えられるところに全力を注ぐ。混ざると決断や行動が鈍ります。
他人に振り回されたりして、結局どのタイミングで決断・行動すべきか迷ってしまい、例えば『上司が嫌だから辞める』という理由だけだと、本来の『なぜこの仕事を選んだのか』という目的や自分の成長につながる視点がおろそかになり、決断に迷いや後悔が起こりやすくなる。
課題の分離ができるということは、
- 『本当に転職すべき理由』が明確になる
- 『嫌な上司』という感情問題ではなく、『成長できる環境か?』という視点で考えられる
- 決断がブレずに、納得のいく選択ができる
ということです。
それでも、



嫌な上司の下で働くことに抵抗がある、システム開発よりも環境を大事にしたい。
こう思えたのなら、仕事を変える選択もありだと思います。



つまり、感情に流されず、本当に自分にとって大切なことを理解した上で決断することが重要ということです。
まとめ
自己理解がなければ、どこに向かって成長すればいいのか知らず、他人の期待に振り回されてしまいます。自己理解があれば、自分にとって本当に意味のある成長ができるようになるので、自分磨きができるということです。
つまり、『自分の内面を磨く = 自己理解すること』と言っても過言ではありません。
自己理解なしに自分磨きで内面の成長を促すことはできない。



自己理解ができ、自分の自分磨きにたどり着いた人は、うまくいかなくても改善しながら続けます。
他人の評価だけ気にしていては続かない、自分が望むことか?を考えることが大切。
『ちょっとやってみたけど、うまくいかないからやめる』、もしくは『いつの間にか止めてた』。自己理解がないから、他人の評価を求めた自分磨きに繋がって行く。そんなもの、続くワケがないんです。そして自分の花を咲かせることができない。
他人の評価を求めるのが悪いというワケではなくて、そこだけが目的になってしまっては本末転倒。
常に、自分がどうありたいか?を意識することが『自分磨き』に繋がり、内面の成長に繋がって行きます。



自分の花を咲かせる=自分磨きになり、内面が輝き出す、すると周りの反応が変わって行くので、全ては循環して行き、他者からも認められるようになっていくんです。
なぜ『課題の分離』が自己理解に必須なのか?
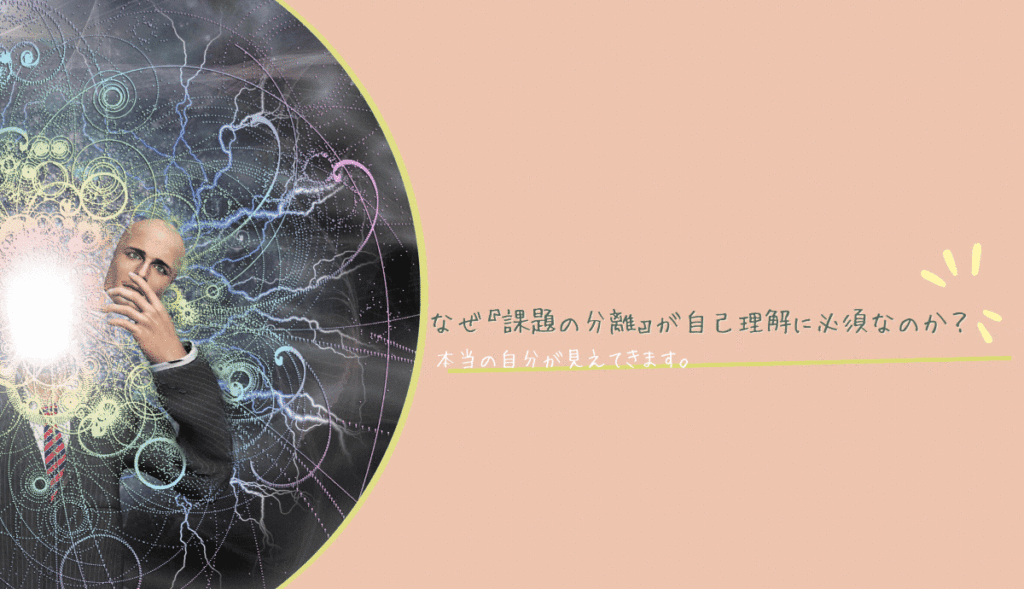
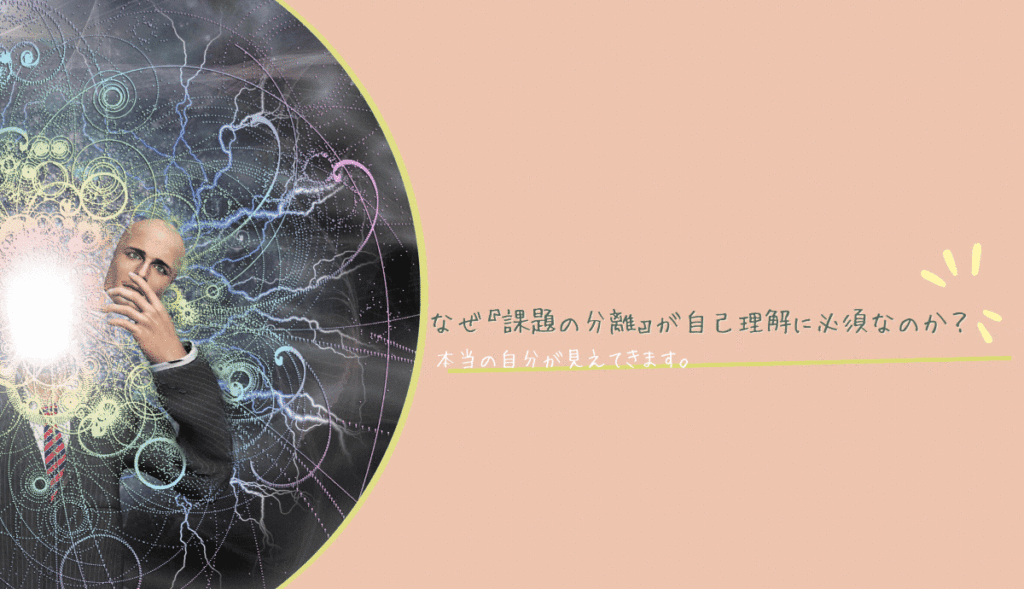
『自分の課題』と『他者の課題』を区別することで、本当の自分が見えてきます。



例えば、『親がこう言ったから』『世間的に正しいから』という理由で生きていると、それは本当の自分ではなく、他人の期待を生きているだけ。それだと不満が出やすいんですよ。そして、その不満がなぜ出ているのか?に気が付きにくい挙句、不満を持っているので、笑顔は減りますから、そんな人がキラキラ輝くわけがない。
自分が本当にやりたいこと、価値を感じることを知るには、まず『それは本当に自分の選択なのか?』自分を見つめる必要がある。
他人の評価や期待に惑わされなくなる。
『あの人にどう思われるか?』『嫌われたくない』など、他人の反応に重点しすぎると、自分の本心に気づかなくなります。
『他人の考えは他人の課題であり、自分にはコントロールできない』と認識することで、自分の価値観を大切にできるようになる。
そして、無駄な罪悪感やストレスから解放される。
例えば、『親がこうしろと言っているのに、自分は違う道を選びたい』という場面で、罪悪感を感じることがある。



しかし、課題の分離を理解すれば、『親の期待に応えるかどうかは親の課題』であり、『自分自身がどう生きるかは自分の課題』だとわかります。
自己理解とは、『自分が何を大切にしているのか?自分とは何者か?』を知ること。
課題の分離をすると、『これは自分が変えられるものか?』『変えられないものものか?』という視点が生まれ、無駄な悩みが見つかる。できるものに集中できる。この利点があるんです。
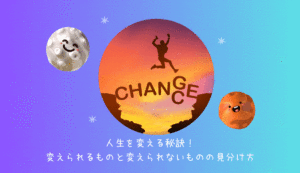
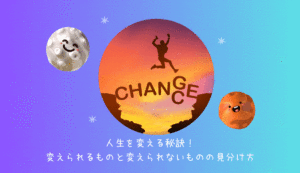
他人の評価や意見ではなく、自分の意思で生きる。
『誰かに認められたいから』ではなく、『自分が本当に望むこと』を選択する。
課題の分離なしに、自己理解は進みません。
しかし、他人の価値観や期待と混ざった状態では、それは不可能。
課題の分離をすることで、本当の自分の考えや価値観が見え、自己理解の加速につながります。
全ての思考・考え方は繋がっています。
アルフレッド・アドラー:1870年2月7日 ~1937年5月28日
ラインホルド・二ーバー:1892年6月21日~1971年6月1日
◆二ーバーの祈り
『神よ、変えられるものについてはそれに立ち向かう勇気を、変えることのできないものについてはそれを受け入れる落ち着きを、そして両者を見極めるための賢さを、私に与えたまえ。』
『父よ、私に変えねばならないものを変える勇気を、どうしようもないものを受け入れる静穏を、そして、それらを見分ける洞察力を与えてください。』
なぜ『課題の分離』が自己理解を加速させるのか?3つの理由


自己理解を加速させる、最善の方法として『課題の分離』があります。
ここでは、その理由を3つ挙げてみます。
- 他人の価値観に振り回されなくなる
- 『本当の自分の願望』が見えてくる
- 自分の責任思考がなくなり、自己理解が生じる
①他人の価値観に振り回されなくなる
自己理解が進まない理由の多くは、『他人の期待や評価に左右されること』にあります。
『親がこう言うから』、『社会的にこうするのが普通だから』のような他者の価値観が、自分の本音を隠してしまう。
いつの間にか、自分でもそう思ってるかのように感じてしまい、自分の意見が消失してしまう。
課題の分離ができれば、『これは本当に自分の考え?』と客観的に判断できるようになります。
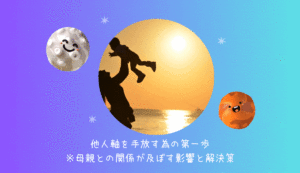
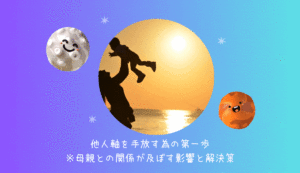
②『本当の自分の願望』が見えてくる
課題の分離をすると、『自分が本当に求めていること』と、『他人に認められたいからやっていること』が明確に区別できるようになります。
例えば、
『成功したい』→なぜ?
『お金が欲しいから』→それって本当に自分の願望?
『お金を得て、自由に好きなことをできる生活がしたい』→『自由』これが本当の願望。
『お金』に着目して目標を設定するのと、自分が『自由に好きなことをできる生活』に着目して目標を設定するのでは、目標の内容がガラリと変わるの分かりますか?
自由にも色々あるでしょうが、今回はそれを『時間の自由』と設定してみます。



例えば、時間に捕らわれることなく働くことができる環境を求めているのに、高い賃金を得ることが出来る企業に就職する、こういうことです。本末転倒。
③自分の責任思考が出てきて、自己理解が生じる
人生に対する責任を持ち、起きた事象を『自分ごと』として考え始めることで、自分の行動や選択の本当の理由を深く理解できるようになります。
『なぜこの仕事をしているのか?』を他人のせいではなく、自分の選択の結果として考えられる人は、自分の価値観や本当にやりたいことに気づきやすくなります。
『あの人のせいで自分はこうなった』、『環境が悪いから仕方ない』という考え方があると、自己理解が進みません。
他人の価値観に流されて生きてゆくのは困難、深い自己理解にはつながりにくい、これは世の法則。
一生、自分探しの旅。



自分磨きができなくなるの分かりますか?自分磨きは、自分にしかない個性を磨くことです。
課題の分離をすれば、『それは自分の問題ではなく、相手の問題だ』と整理でき、余分な思考のノイズが気にならない。『自分はどう生きたいのか?何を一番にしているのか?』という問題の本質にフォーカスできるということです。



つまり、『自己理解=課題の分離ができること』、『責任を持つ覚悟』が、深い自己理解につながるということになります。
課題の分離が自己理解を進めていく最も強力な方法の一つであることは間違いありませんが、それ以外にもいくつか方法があります。
『課題の分離』以外で自己理解を推進!自分磨きする方法
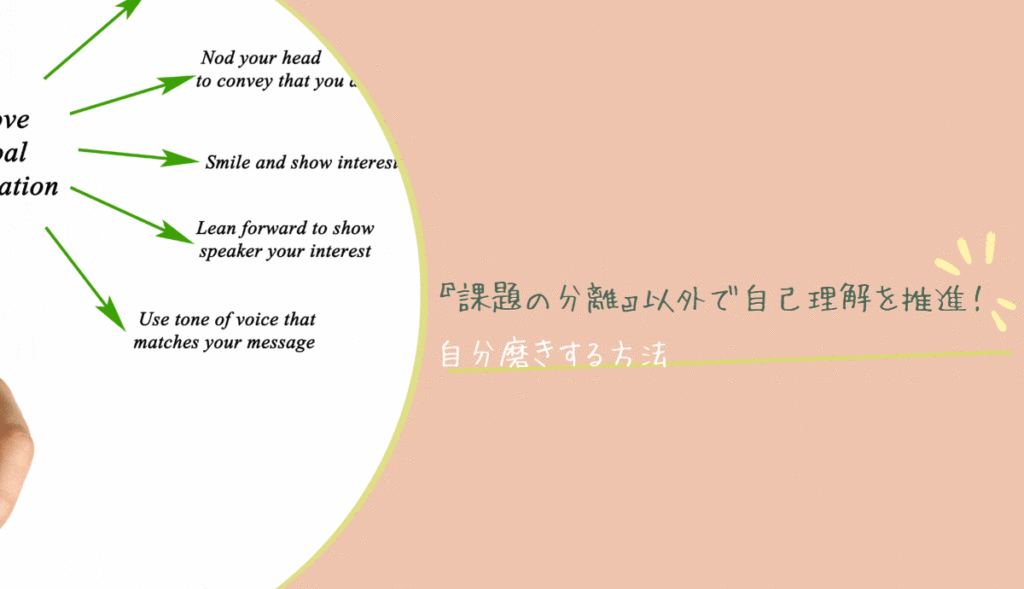
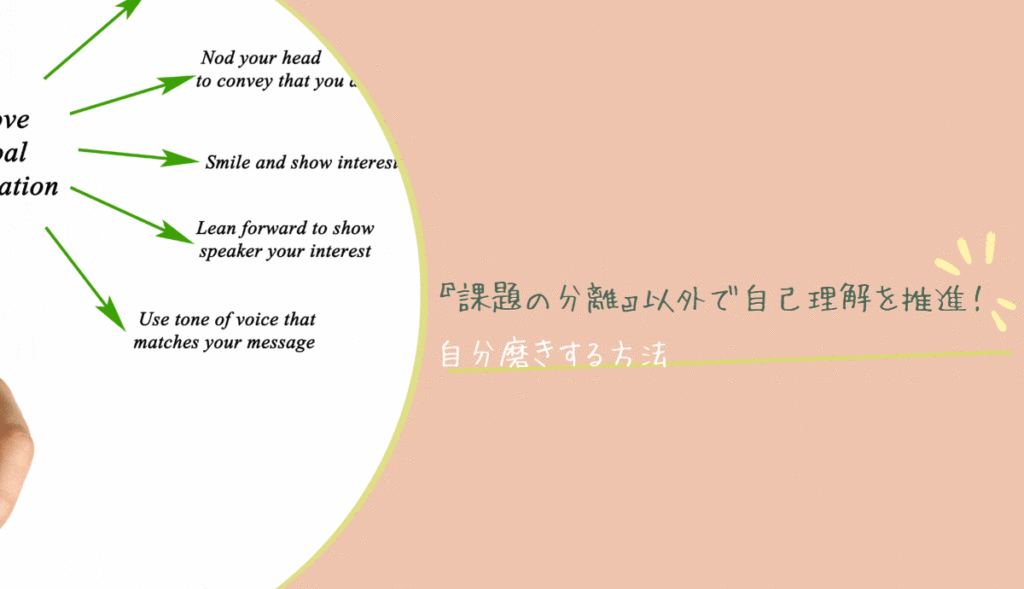



課題の分離が自己理解に向かう最強の方法であることは間違いありませんが、次のような方法を併用するのもおすすめです。
- メタ認知を鍛えて、感情や思考を客観的に見る
- 日記を書くことで、自分の内面を整理する
- 価値観を明確にして、自分の軸を持つ
- 過去の経験から、自分の本質を探る
- 性格診断や心理テストを活用する
- 他者からのフィードバックを活用する
①メタ認知を鍛える(自己観察)
『自分が今、何を考えているのか、何を感じているのか?』を観察する習慣をつける。
他者承認が強いと、自分の感情に疎くなります。なので、常に自分の感情に向き合うようにしてみたらいいです。
例えば、、
- なぜ今、自分はイライラしているのか?
- なぜこの人の言葉にこんなに反応してしまうのか?
- この選択は、本当に自分がしたいことなのか?
ポイントは、第三者の視点で自分を観察することです。自分の思考・感情を客観的に見つめることで、自己理解が進みます。
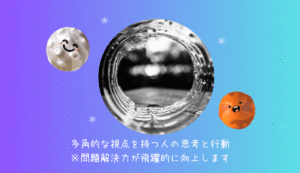
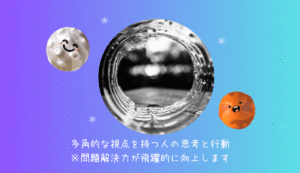
②日記やジャーナリングを書く
『思考を言語化すること』は、自己洞察の方法のひとつ。
1日5分でも、10分でもいいので、自分の気持ちや考えを紙に書きます。
書き方の例は、、
今日感じたことを書きます(今日は〇〇についてモヤモヤ・イライラした)
→その理由を考える(〇〇の発言が自分を馬鹿にしているように聞こえたから)
→そこから分かることを書く(自分は〇〇を大切にしているから、こういう言葉に敏感なんだと思う)
→できたらもっと掘ってみる(〇〇を大切にしていると思っているけど、図星だから馬鹿にされていると自分で思ったんだと思う)
ポイントは、書き出すことで一時的に感じた感情や思考を整理し、本当の自分の思考に気づくことができます。
そこまでできたら、そう思えた経緯をブログに再度清書する形で綴るだけでも、同じ状況の人がいれば参考になります。
愚痴を綴るのではなくて、どのような思考に気づき、どう変化して行けたのか?をまとめることができると、自己成長の鍵になっていきます。ブログでなくても、日記でも何でもいいです。
思考を文字にすることに意味がある。
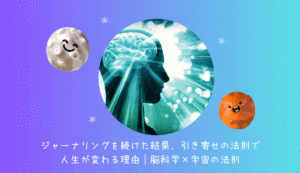
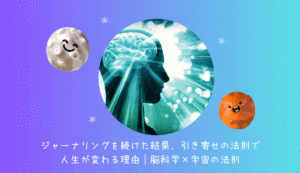
③自分の価値観を明確にする
『自分にとって大切なか?』をリストアップしてみます。
例えば、、
- 仕事:お金よりもやりがい?安定?
- 人間関係:広く浅い?狭く深い?
- ライフスタイル:都会?田舎?ひとりの時間は必要?
価値観を明確にしておくことで、『本当の自分の選択』が分かりやすくなります。
例えば、人とわいわい騒いでいる人を見て『楽しそう』と思うことは大事だけれど、だからって、私もうそうなりたい!は違います。
なぜ『楽しそう』と思うのか?に着目した方がいい。



安直に、楽しそうにしているグループに参加して疲れるという結果を招くこともある。本当の自分は、ひとり好きなのに、、こういうことです。楽しさの求め方が違うという結論が出る。自分を知っておく、自己理解ってやっぱり大事。
④過去の経験を振り返る
『人生で最も楽しかったこと、最も辛かったことは何か?』を振り返ります。
そのときの感情を思い出し、なぜそれが楽しかったのか?なぜ辛かったのか?を考えてみます。
例えば、、
過去に〇〇をしていたときは楽しかった→なぜ?
→自由に働くことができたから、自分で決めることができたから
→つまり、自分は自由を大切にするタイプだと思います。
過去の経験を振り返ることで、自己理解のヒントを得ることができます。
他記事にも書いていますが、わたしの場合を掘ってみます。
わたしの場合は、学生時代が楽しかった。
→特に走ることが楽しかった。
→走ることの何が楽しかったのか?→誰よりも早く走れたから。
→走ることが楽しいというよりも、他者承認が入っているね。
→運動の補充ではなくて、自己承認が必要になる。
→自己承認できるように、どう行動するべきか?
深く考えもしないと、また走る環境を整えるという安直な選択になっちゃって、結局辞めちゃうなんてことになる。
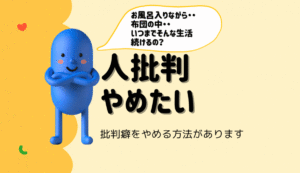
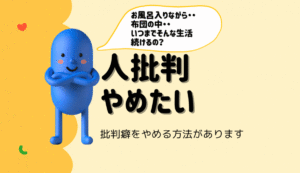
⑤性格診断や心理テストを活用する
エムグラム(mgram)性格診断などのツールを使って、自分の傾向を知る。
面白いですよ。ただし、『参考』としての捉え方、診断結果を盲信しないことは大事です。そういう部分もあるんだな、くらいが一番いい。
確証バイアスで、自分は特別な人間だと思える部分だけをピックアップして頭に入れ込む。これが幸いすればいいけれど、慢心を呼び起こすこともあるから。
あくまでも、判断は自分。
⑥他者からのフィードバックを活用する
自分のことは意外と自分では見えにくかったりします。
信頼できる友人や家族に『私ってどんな人?』と聞いてみるのも一手。その意見を『本当にそうなの?』と考えてみると、新たな自分を発見できることがあるかもしれません。
まとめ
自分磨きをして、内面の向上をする方法をまとめてみました。
自分磨きって、外面と内面両方あると思うんですが、どちらから先にアプローチかけても大丈夫です。
内面を向上するのに一番適した方法は『自己理解』と『課題の分離』。これが最速の方法になります。
自己理解が進むと、自分のやりたいことが明確になるので、それに向かって努力している人って自然と輝きますよね。
自分磨きに没頭するとういよりも、前向きに頑張っている人を見ると、誰だって惹かれますよね?
人の愚痴を言わないようにしようとか、そういうことから始めるのも大事だけれど、やっぱり自己理解をして、それからの自己受容が大事になってくる。
それができるようになると、他者理解が進むから。共感してくれる人って嬉しいじゃないですか。
何もかもが上手く行く。これは世の法則、ここが上手に回り出すと宇宙の理性が作用して行く。
すべては必然。



そうやって生きていると、あなたの周りは勝手に潤うと思いますよ。

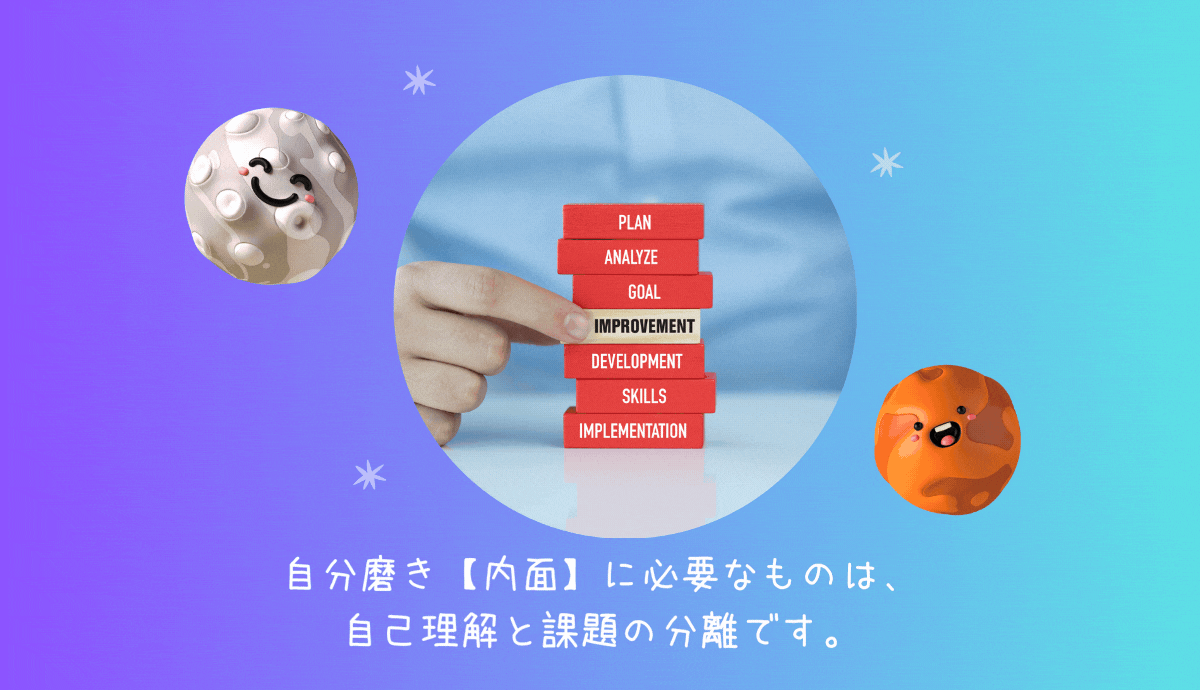
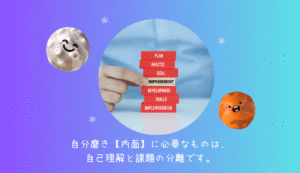
コメント