この物語はフィクションです──課題の分離ができない人ってどんな感じだろう?という仮説で記事を書いてみました。
今回のお題は『スマホ持ち込みは禁止』。

そのルール必要?という哲学思考は無しで記事を作っていますので、先に明記しておきます。
子どもは持ってくる。親は『持たせないと困る』と言う。で、無くなると



学校はどう責任を取るんですか!?
とクレーム。
うん、教育現場って毎日エンタメ。…いや、笑えない。今回は、『課題の分離』ができないと教育の現場でどんな“ズレ”が起きるのか、という妄想シミュレーションをしてみました。
- 『学校の仕事はどこまでか』って線を、明確に引く
- でも、『人として、子どもとして』必要なことはちゃんとやる
- そして『親の不安には共感するけど、代わりに処理はしない』
これをどうやってする?
『その問題、誰の課題ですか?』
でもちゃんと考えさせられる。そんな記事です。
事件の概要と“よくある対応”
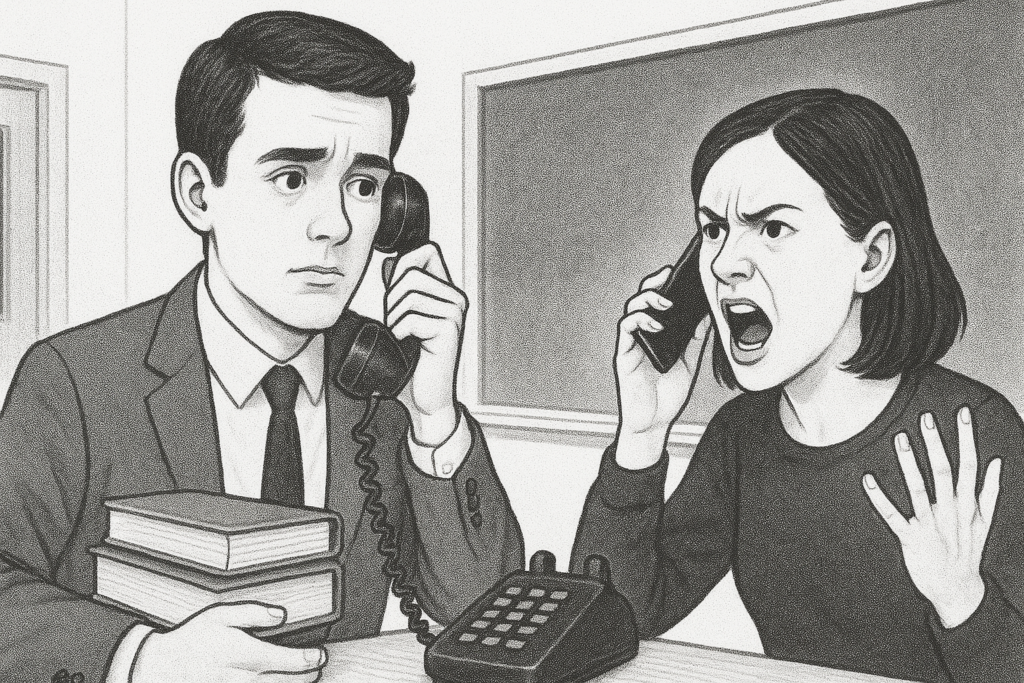
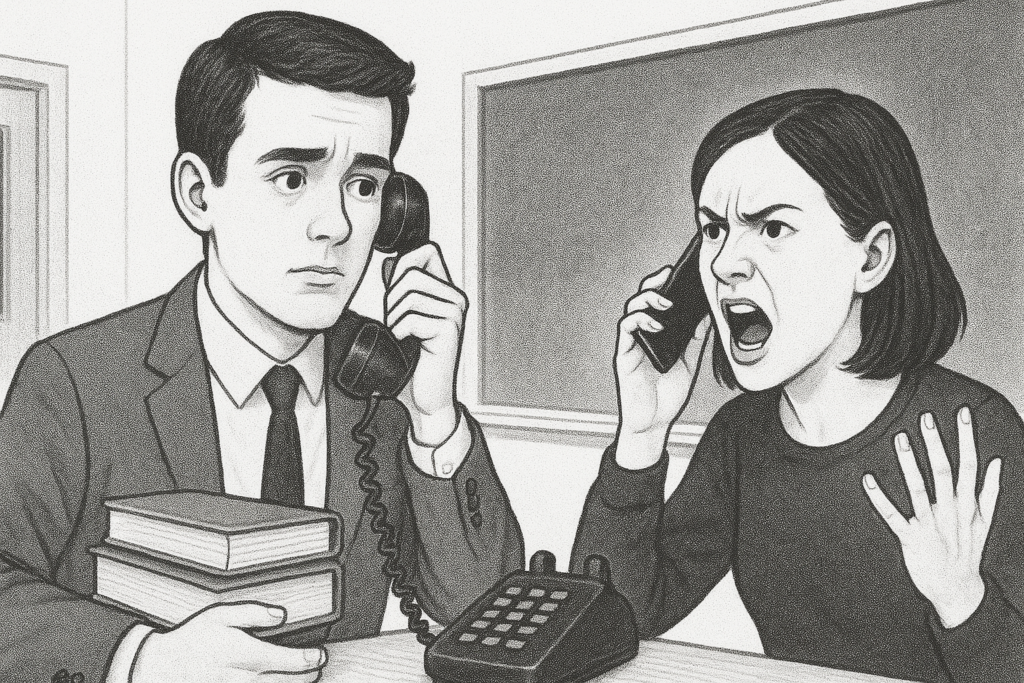
- スマホ持ち込み禁止なのに、なぜ持たせる?
- 先生たちの反応──共感はどこまで必要?
① スマホ持ち込み禁止なのに、なぜ持たせる?
小学校に『スマホ持ち込み禁止』のルールがあるとします。紙にも書いてあるし、口頭でも言ってる。でも、守られるかは別問題。
ある日、ひとりの児童がスマホをこっそり持ち込み、そして見事に失くします。ここから、この“あるある事件”が幕を開けました。
まあ、親としては『連絡とれないと不安』ってのも分かる。共働きとか、塾の送迎とか、事情はいろいろある。気持ちは理解できます。でも、『ルールあるけど今回は例外』ってやると、例外が日常になる。そして、何か起きたら“学校のせい”になる。不思議な構造。
で、案の定こう来ました。
翌日、母親からお怒りの電話。



スマホが学校で無くなったんです!もしかしたらCくんが盗ったかも!それに、人の物を盗っちゃダメって、学校で教えてないんですか!?



……いやいやいや、持ち込んだのお宅の子ですよね?
ツッコミどころ満載ですが、先生たちはプロです。心の中で『ちょっと何言ってるか分からない』とつぶやきつつ、冷静に対応を始めます。
② 先生たちの反応──共感はどこまで必要?
さて、ここで登場するのが、教育現場にいるA先生とB先生。
立場も性格も違うように見えるけど、やってることはほぼ一緒。『言われた通り動く』モード。
A先生は、母親に



それはよくないですね…
と即座に共感し、Cくんを直行取調室(職員室)へご案内。
結果、スマホは裏庭のツツジの木の下から発見。まさかの“植物からの証拠提出”。そして、Cくんには謝罪をさせて事件は一件落着…ということに。
一方のB先生。内心では



いやいや、そもそも持ち込んでるのが違反でしょ…
と思いながらも、やっぱり母親に共感して同じ流れで対応。違うのは、A先生が“表で共感”し、B先生は“心の中でツッコみながら共感”したという、程度の問題。



つまり、共感のかたちが違うだけで、どちらも『誰の課題か』をガン無視して走ってるという点ではお揃い。
ここで大事なのは、『共感』と『責任の引き受け』は別モノってことです。なのに、いつの間にか教育者が『親の感情の後始末係』になってる現場、多くないですか?
共感は『気持ちはわかるよ』であって、『だから私が何とかしますね』じゃない。その境界があやふやになると、先生は教育する余裕を失って、ただの“クレーム対応マシン”と化してしまいます。
あとひとつ。こういうパターンもある。
A先生とB先生は、一応、共感を示して動くタイプの先生。でも、ここにもうひとり、無自覚な爆弾がいます。
それがC先生。
C先生の口グセはこうです。



最近の子どもは甘やかされすぎなんですよ。ちゃんと“けじめ”を教えなきゃ、ダメなんです。
本人、完全に“教育してるつもり”。
で、例のクレームが届いた瞬間、スイッチが入ります。
スマホがなくなった?Cくんが捨てた?……はい、出ました。『正義の鉄槌』タイム。
このときC先生の中には、冷静な判断も課題の分離もありません。
あるのはただひとつ、



人のものを盗るとは何事だ!!!
という反射。
Cくんを呼び出し、強めの口調で言い渡す。



これは立派な窃盗です。どうしてそんなことをしたの!?君は、人の大切なものを奪っていいと思っているのか!?
C先生は本気で『指導している』と思ってる。『私は悪いことを叱っている』→ だからこれは教育だ、というロジック。
でも、周りから見たらどうか?
“問題を丁寧に捉えて指導している”のではなく、“怒りたい相手に怒ってるだけ”にしか見えない。
しかも怖いのは、本人にその自覚が一切ない。
『私はちゃんと向き合ってます。問題にきちんと対応しました。』



──いや、それ、ただの一方的な“処罰”。
でもC先生にとって、それが『ちゃんと指導した証拠』になる。
──これが、『教育』と『咎め』の見分けがつかなくなっている状態だと思う。
そしてもっと怖いのは、C先生は自分の中にある『咎めたい』を認知できていないという行為。
誰を咎めたいんだろう?
子ども?保護者?
それとも…自分自身?
何を咎めたいんだろう?
スマホを持ってきたこと?
盗んだこと?
それとも、クレームがかかってくるこの仕組みそのもの?
指導という皮を被った“怒り”ほど、たちが悪いものはないと思う。その怒りが、どこから来てるのかも分からないまま動き出すから──それはもう『教育』じゃなくて、『発散』になる。
『課題の分離』ができていないと何が起こるか
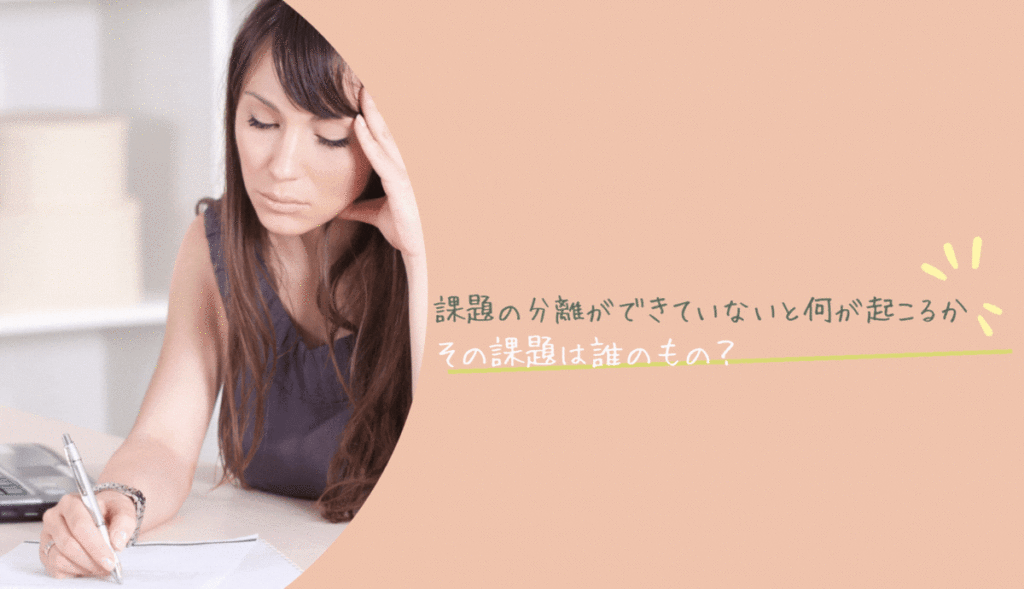
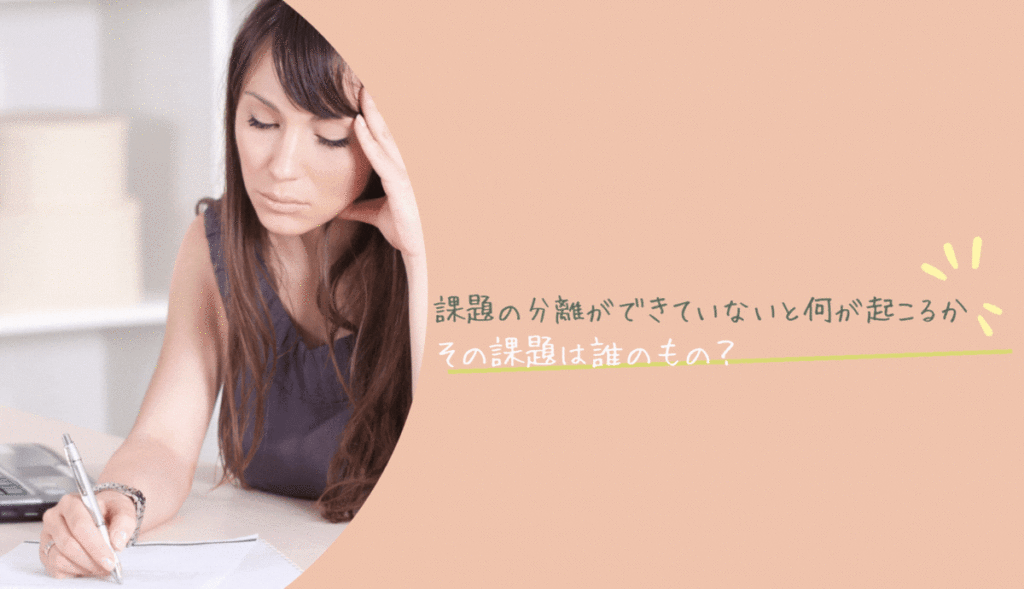
- アドラー心理学で見る『その課題は誰のもの?』
- 親の不安を“代わりに処理”してしまう危うさ
① アドラー心理学で見る『その課題は誰のもの?』
アドラー心理学にはこんな名言があります。
『その課題、誰の?』(※原文じゃないけど、気持ちはこんな感じ)
で、今回の小学校スマホ紛失事件。これ、まさに『課題の分離』が迷子になった人間ドラマのフルコースです。
まず、スマホを学校に持ってきたのは子ども。持たせたのは親。ルールでは『持ち込み禁止』と書かれているのに、『でもうちの子は事情があって…』って、なぜか自分だけ“特別仕様”で参加。そして、案の定スマホが消える。
そこからの展開がすごい。



学校が探してください!誰が盗ったか突き止めて!謝らせて!
って、完全に事件捜査モード。



いやいや、先生探偵じゃないし。学校は交番じゃないんで。名探偵コナンもびっくり案件。
アドラーに聞いてみましょう。



これは誰の課題ですか?



あなた(保護者)です。
自分で持たせたなら、自分で責任取ろうね、って話。
先生の仕事は、親の怒りに“いい感じに寄り添って”処理してあげることじゃない。『この学校にはこういうルールがあるので、それに基づいて対応します』と、ちゃんと“線を引く”こと。
問題を拾うのは優しさじゃなくて、背負わなくていい荷物を自分から肩にかけてるだけ。で、最終的に一番しんどくなるのは、いつも先生自身。
② 親の不安を“代わりに処理”してしまう危うさ



スマホが無くなったんです!Cくんが怪しいんです!そっちの教育、どうなってるんですか!?



それは大変でしたね…。Cくん、ちょっと来なさい。
…ちょっと待って。なにこの即レス対応。親の言い分フル信頼、秒で事情聴取スタート。
もしかしてここ、学校じゃなくてカスタマーサポートセンター?
この時点で、先生の肩書きは『教育者』ではなく、『感情処理担当』。
親の言葉だけを“真実”として受け取り、そのまま対応開始。でも、これ一回やると、次からも絶対にこう言われます。



前はやってくれたじゃないですか!
って。
こう言われたとしても、



そうですか。そんな不手際が。前の担当された先生に、学校の校則を再確認するように、伝言しておきます。わざわざ、ご連絡ありがとうございます。
これでよくないですか?
そう、“なんとかしてくれる学校”は、一度経験するとクセになる。頼れる存在?いや、依存される存在です。それ、全然違うから。
もちろん、共感は大事です。頭ごなしに『それあなたのせいでしょ?』じゃ炎上まっしぐら。
でも、『それは家庭の課題なので、学校としてはここまでしか対応できません』と優しく線を引くことも、大事。
先生が『何でも屋』になった瞬間、教育の軸がねじれる。気づいたら、生徒より先に大人が“甘やかされてる”状態になります。
本当にすべきだった対応とは?
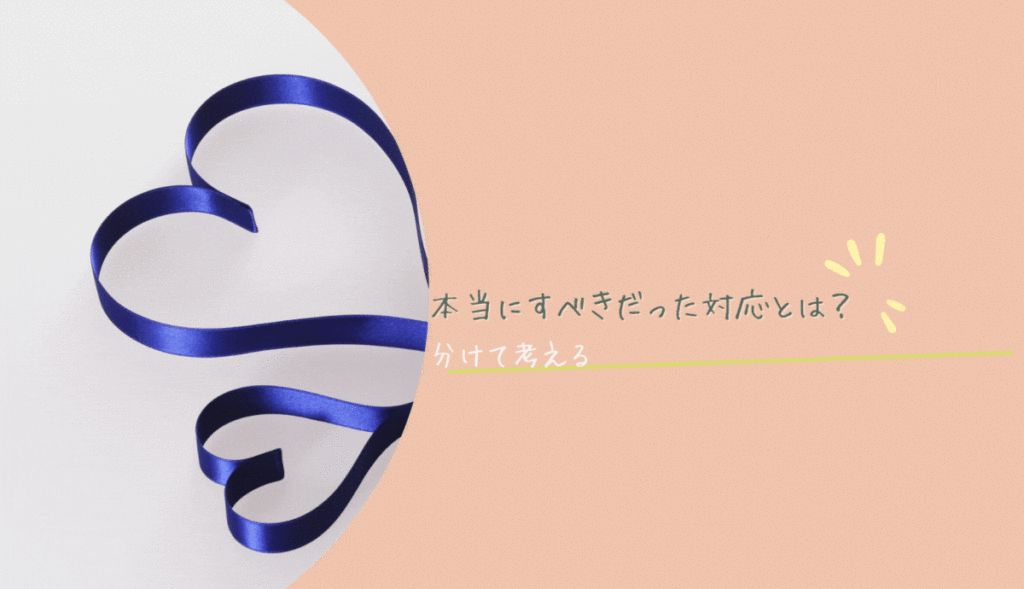
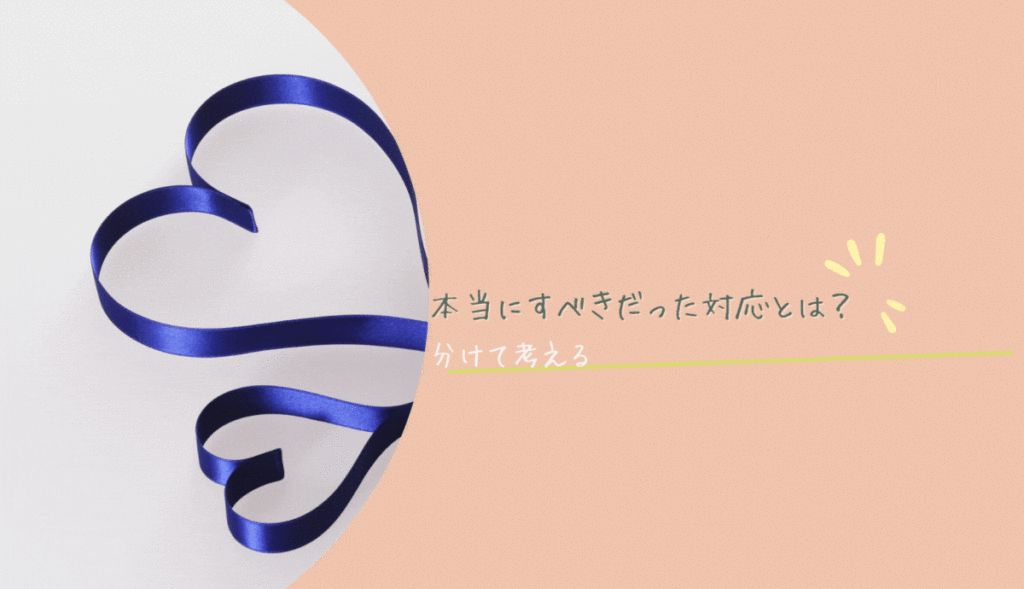
- 『校則として禁止です』の立て方
- 生徒対応と保護者対応は分けて考える
① 『校則として禁止です』の立て方
まず、大前提を確認させてください。
『スマホ持ち込みは禁止です』って、校則にちゃんと書いてあります。
でも、現場ではこのルール、もはや“都市伝説”レベルに扱われてる学校もあるんですよ。



禁止って言っても…みんな黙認してるし…まあ持ってきててもしょうがないよね…
って、空気で運用されるルール。それ、ルールって言います?
で、そんなふんわり校則に守られたある日、事件は起こります。



スマホなくなったんですけど!?Cくんが怪しいって子どもが言ってます!



そ、それは…と、とりあえず探してみますかね…
いや、その“とりあえず”が一番危ない。
だってこれ、冷静に考えてみてください。



スマホを探し始めた時点で、先生も“校則破ってる側”に仲間入りしてるってこと、気づいてます?本来は禁止なのに、『探す』という行為を引き受けた瞬間、黙認どころか、実質公認。つまり、先生自身が“ルール違反を前提に仕事してる”状態なんです。
そしてこれも違う。



そもそも、学校の校則でスマホは持ち込み禁止ってなってますよね!?それなのに、持ってくるそちらが悪いのではないですか!?校則に違反しているんだから!探せませんよ!責任はそちらで取ってください!!



炎上しかしねーよ。誰でも言えるし。
で、どうなるか?
仕事は増えるわ、責任は押し付けられるわ、もうクレームパーティー。とは言え、、と思うかもしれないけれど、相手は人間だから。仕方ないと思う。
叫びたいときに、叫ぶ。言いたいときに、言う。双方が同じことしてるんだから、炎上しかしないでしょう?
それなのに、そのうち先生も保護者もこう言い出すんです。



最近の保護者って、なんでこんなに…!



最近の学校って、何であぁなの!?
ひどくない!?



──いやいや、どっちもどっちだよ。
自分でルール破って怒鳴って対応して、自分で首締めて、で、疲れ果てて『最近の教育現場は…』ってため息つく。
自分でルール破って怒鳴って電話して、自分で首絞めて、で、怒り散らし『最近の学校は!!』ってイライラして、学校への不信感を増していく。こういうタイプの保護者は同調圧力を持っているから、周りの仲間保護者へ愚痴り、学校への敵を増やしていくという最強グループを作って行きます。
どれも“自作自演の地獄”。後者は演者を増やして戦うという術を持っている。
だからこそ、ここで言わなきゃいけない。



本来、スマホは校則で禁止されています。したがって、持ち込みによる紛失やトラブルには学校として責任を負いかねるんですよ。
この一言、言いにくいけど最強の盾です。
装備しないで突っ込むと、自爆確定。
保護者は、自己責任を自覚しとかないといけない。
② 生徒対応と保護者対応は分けて考える
スマホを裏庭にぶん投げたCくん。それはスルーできません。さすがに。
でもここで重要なのは、『Cくんへの指導』と『親への説明』は別ってところ。ルールもルールブックも違うんです。
課題の分離。



Cくんがうちの子のスマホ盗ったんです!



お話を伺ったので、念のためCくんに状況を確認します。ただ、スマホの持ち込み自体が禁止されていますので、その点はご家庭でもご確認いただければと思います。
これ、Cくんの件をどうするのか?というお題は別案件になるので、今回この記事で言及はしませんが、対応するのだとしたら、地雷原を歩くときの最強ムーブ。で、Cくんには静かに話を聞く。聞くかどうかは、決断がいる作業。聞かずに、クラス全体に確認取って、盗まれてないとするのも、聞いたことになるでしょうから。
本当に隠したのかどうか、本当であれば、どうしてそんなことしたのか。何があったのか。
ここはちゃんと向き合う案件だとは思う。これは“教育”の仕事だと思うから。どう向き合うか?も別案件だから、割愛します。
でも、親への説明は“クレーム処理部”の対応とは違うロジックでいくべきで、この二つ、混ぜると本当にろくなことにならないと思います。
境界線を引けないと、いろんな役割を一人で背負い、最終的にきっとこうなる。
気づいたら感情のゴミ屋敷で暮らしてた。
そうなる前に言います。『教育』と『納得させること』は、別ジャンル。
『教育』とは何かを問い直す
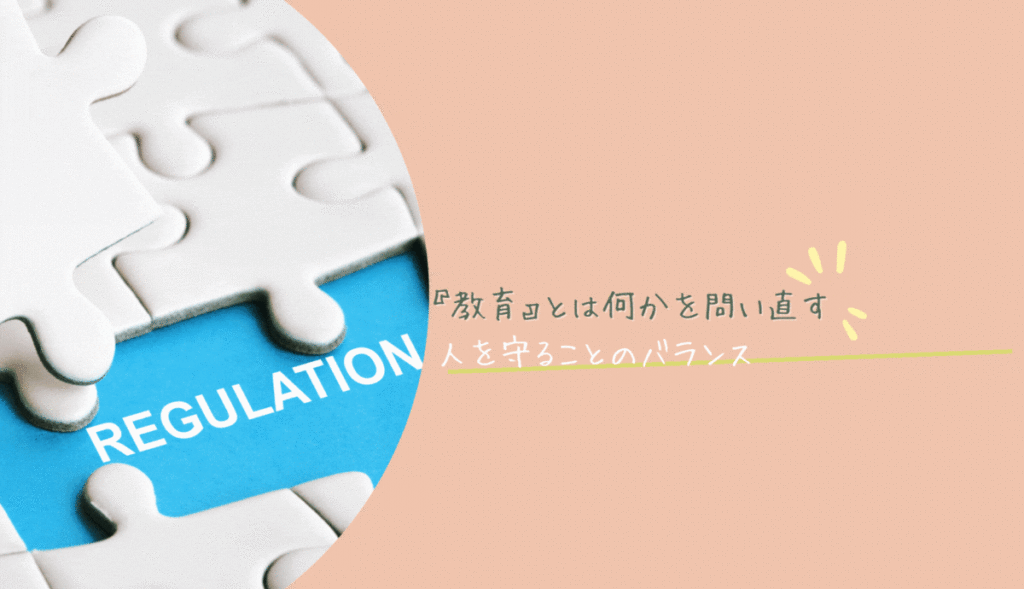
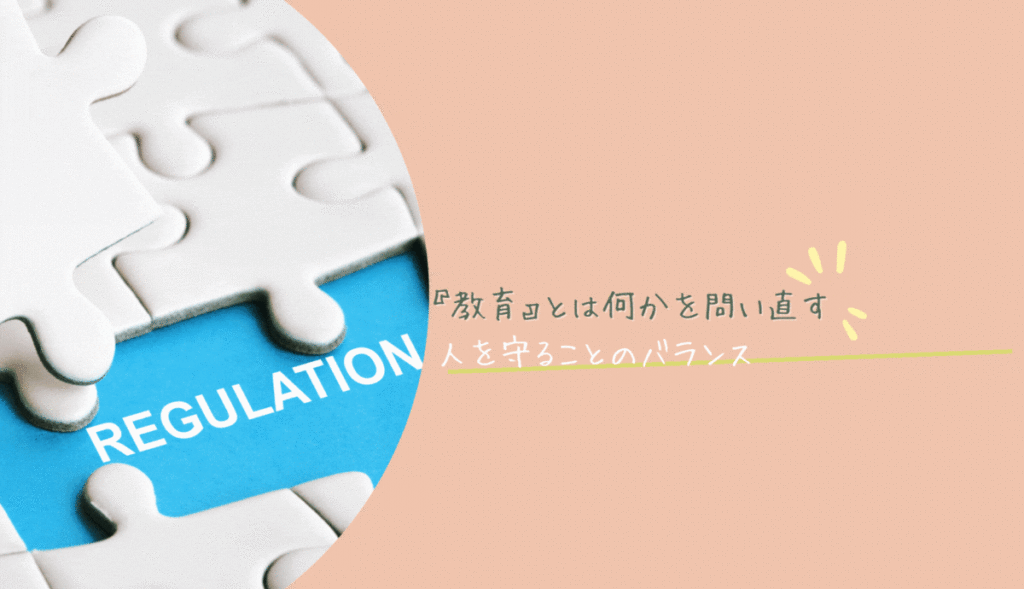
- ルールを教えることと、人を守ることのバランス
- 『教育者のスタンス』が問われる瞬間
① ルールを教えることと、人を守ることのバランス
『校則は絶対です!』とロボみたいに繰り返す先生になれってわけじゃなくて、でも逆に、『今回はまあ、いいかな』って毎回“情”でねじ曲げてたら、それ、もうルールじゃなくてお願いベースの提案書。
教育現場って、『決められたルール』と『子どもそれぞれの事情』の間で、いつもフラフラしてますよね。
じゃあ、どっちを優先すればいいの?って聞かれたら──どっちも大事です。…って、言うと“ズルい”って思われるかもしれませんが、それが現実です。
でも、重要なのは“順番”だと思うんですよ。
まずルールを提示する。で、その上で個別対応を考える。
これが逆になると、『今回はいいけど、次はダメだからね』って、毎回“気分”で運用されるルールになるから。
つまりルールが、“魔法の言葉”から“気分屋の呪文”に格下げされる。
ルールって、人を縛るためにあるものじゃないですよね?『こうしておけば、お互い変な誤解もなく、安全にやってけるよね』っていう、集団行動用の安全装置。
でも、その装置の仕組みを説明しないで『とにかく守って!』って言うと、人はこう思います。
『なんで?』って。
じゃあどうするか?
…でも、それとは別に、人としてできることもあるじゃないですか。“ルール違反は違反として処理しつつ、それでも子どもを見捨てない”という、教育的な対応の形。
たとえば──



スマホ持ち込み禁止なのに、○○がスマホ学校に持ってきて、なくしたって言ってるんだけど、知ってる人いるー?
って、クラス全体に一声かけてみる。
この行動そのものが、“ルールは守るけど、生徒のこともちゃんと見てる”というメッセージになる。そして、その事実を保護者に伝えるだけで、対応の印象はまるで違うと思うんですよ。



スマホの件は、本来対応できるものではないんですが、Cくんに確認入れた後、念のためクラス全員にも確認はしました。
もしくは、



スマホの件は、本来対応できるものではないんですが、クラス全員に確認しました。
とするのか。対応で応答は変わりますよね。ここは枝葉別れ案件。持ってくるから盗られるんだろ!も違うから。持ってきてなくても、スマホじゃない、別の物は盗られるんですよ。



ここでも課題の分離。だって、スマホが目的じゃないからね。ここでスマホだけに注目してる人がいたとしたら、ラーメンで眼鏡が曇った状態で、眼鏡どこ?って探してるような行為ですよ。なんだその思考は。
事情聴取したとして、たとえば、Cくんがスマホを盗ったと認めた場合、その行為には別途しっかりと向き合えばいいし、でも、今回の“スマホ紛失”そのものについては、対応はあくまで『おまけ』。
- 『教育』の軸はブレさせない
- 感情論に引っ張られない
Cくんへの対応はCくんの件として、ルールはルールとして、そして、例外はないという姿勢を静かに貫く。
それだけで、先生の言葉にはちゃんと芯が通ると思う。
──このひと言があるだけで、“ただ突っぱねた学校”から、“ちゃんと配慮してくれた学校”に変わるんですよ。
結局、『なぜこのルールがあるのか』を説明できて、なおかつ“人として”の温度を残せる教員だと、信頼できる。
② 『教育者のスタンス』が問われる瞬間
先生は、便利屋じゃない。教員って『人を育てる』プロ。…のはずが、気づけば現場ではこんな肩書きがどんどん増えていきますよね。
『感情処理係』『謝罪代行』『校則の説明員』『保護者のクッション材』…。
名刺つくったら裏面までパンパン。
その係に無理がきたら、『怒鳴り屋』『当たり屋』『制圧屋』とかに変わっていくでしょ?
でも、大事なのは、そのたびに立ち止まって考えることで、
『これは誰の課題?』
『どこまでが自分の責任?』
『これ、私が動くべきこと?』
この采配を間違うと、的がズレて、どんどん絵はゾンビになっていく。
的がズレると、登場人物全員バグるんです。
アンパンマンの顔がバイキンマンで、チーズが喋りだして、ポッポちゃんがトーマスになるような世界。もう、それ教育じゃなくてカオス。
胴体バイキンマンの顔アンパンマンのゾンビに向かって、『アンパンちょうだい!』で、殴られるんですよ。
この“問い直し”を、面倒くさがらずにできるかどうかが、教育者としての軸になると思う。人生もそうだと思う。問い直しは必要。
今回のスマホ紛失劇も、親も子も先生も、全員“自分は正しい”と思って動いてるからこそ、話がこんがらがる。だからこそ、先生自身が『私はここで何を守る?』って軸を持っていないと、あっという間に流されていきます。
『全部背負う』は、もう令和では化石。『必要なことだけ、ちゃんとやる』。その方がむしろ、ちゃんと伝わるし、信頼される。
教育現場に必要なのは、“全部拾う優しさ”じゃなくて、“拾わなくていいものを見分ける賢さ”。『課題の分離』、できた方がいい。ていうか、できなきゃ潰れる。
まとめ
スマホ紛失をきっかけに見えてきたのは、『教育』の顔をした混乱。親も先生も子どもも、『自分は正しい』と信じてるからこそ話がこじれる。
で、最終的に疲れてこうなる。
『最近の子どもは…』
『最近の親は…』
『最近の学校って…』
──いや、全員ちょっとずつズレてるだけです。
大事なのは、『これは誰の課題?』『それ、ほんとに自分の仕事?』と問い続けることじゃないかと思う。
全部拾ってたら、ゴミ屋敷になるし、拾う前に、“拾わなくていいもの”を見極める。拾うべきものを知る。
『課題の分離』、できた方がいい。というか、できないと、教育者も保護者も、詰む。





コメント