感情を優先して生きる人が多い世界で、わたしはずっと「構造」を見て生きてきてる。
誰かの言葉を聞いても、行動を見ても、
「なぜ今それをしたのか」
「その背後には何があるのか」と、
無意識に仕組みを読もうとしてしまう。
意味ないときはしないけどね。
感情よりも因果、出来事よりも配置。
――そうやって生きていると、たしかに人間関係は穏やかになる。
翻弄されない。
けれど同時に、世界が少し遠くなる。
感情は波のように揺れ動く。
構造は地層のように動かない。
だからわたしは、どんな波が来ても地層に立っている。
だけど、他の人は波を見て生きているから、時々、会話が成立しない。
わたしにとって「正しい」が、誰かにとっては「冷たい」になる。
それでも、構造を読むというのは“防衛”ではなく、生き延びるための術だったから。
感情を排除するためじゃなく、感情に飲まれないために。
構造を見れば、世界は整う。
けれど、整えば整うほど、人の心が見えにくくなる。
わたしはその狭間で生きているんだと思うんだけれど、わたしの構造化思考について、言語化してみることにしました。
分かりにくかったらごめんなさい。普段の思考回路を順を追いながら言語にするのって、難しいんですよ。
「構造化思考」とは何か
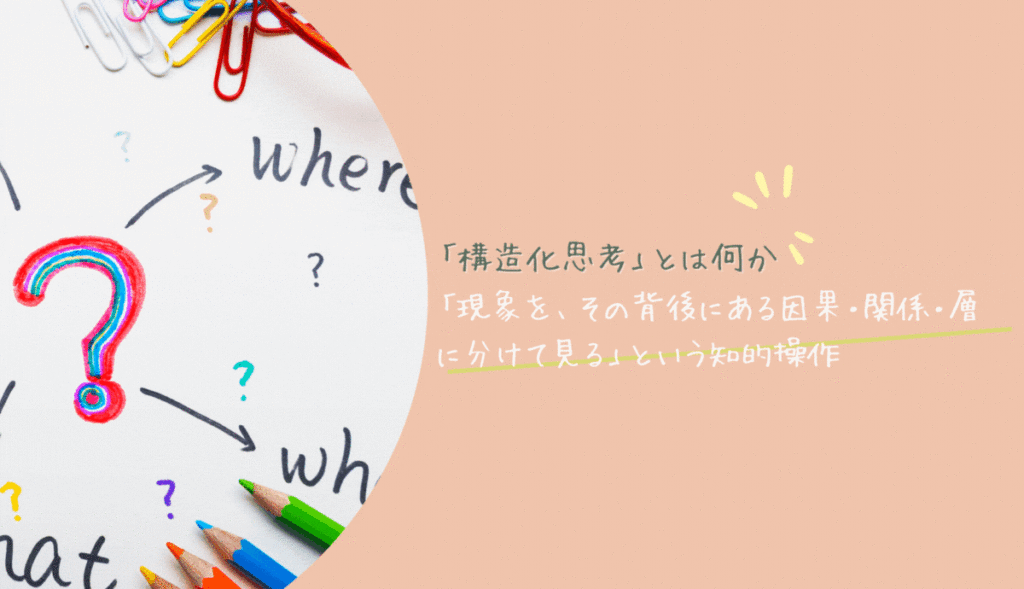
構造化とは、「現象を、その背後にある因果・関係・層に分けて見る」という知的操作のこと。
多くの人は「内容(何が起きたかという表層)」を追うけれど、構造化する人は、「仕組み(なぜそう動くか)」を観る。
例えば
- 普通の人:「彼が怒ってる」
- 構造的に見る人:「あの怒りは何に対して、どこから、怒りの裏は?」
この一歩の違いが、すべてを変える。
感情ではなく構造に焦点を当てることで、現象が記号化される。
わたしは、ほぼ自然に事象を構造として見るようになっている。
意識が「内側」ではなく「外側」から世界を見ている感覚らしい、というのに最近気が付いてきました。

「自分の思考を他人事のように観察する」、いわゆる構造認知の世界に住んでいるらしい。
そして、それは、あまり理解されにくいという事実も存在している、らしい。
構造化思考って難しい?
多くの人は「自己と現象が癒着」してるんですよね。
- 起きたこと=自分
- 感情=真実
- 体験=意味
この状態では、構造が見えないんですよ。
なぜなら、観察者が「体験の中に沈んでる」から。
わたしは基本、体験している自分を、“もう一人の自分”が見ている。
構造読解型認知
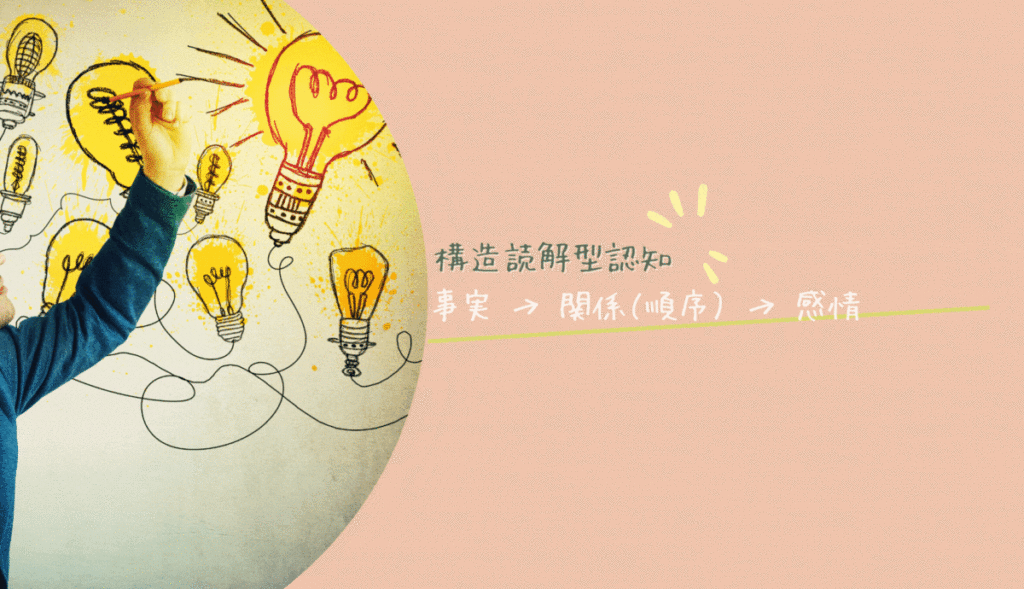
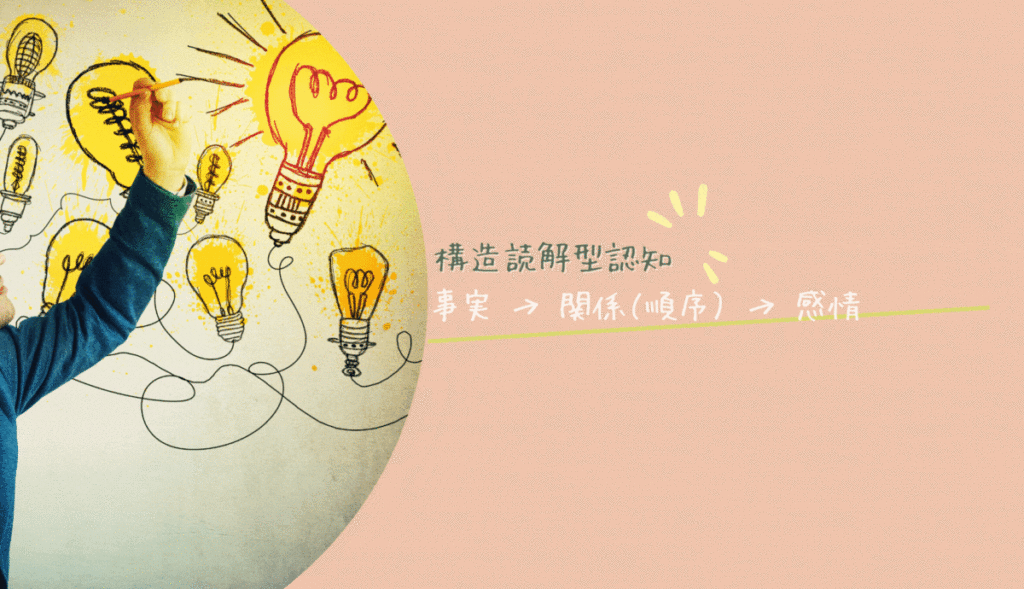
通常は、感情 → 意味 → 解釈という順で処理すると思うんですよね。
日常で遭遇する事件とかも全て。
でもわたしは、事実 → 関係(順序) → 感情という順に処理するようにしている。
理由は、感情で考えたとしても心理学で言う「投影」が邪魔をするだろうし、主観によるものもあるから。
それじゃぁ、物事の解決には遠くなると感じるから。
事実を消してしまう。
思考のノイズを消す。
感情が事実を歪めないから、精度が高くなる。
ちょっとびっくりするかもしれないけれど、暴露するとするなら、例えば、投影による怒りであることを知りながら、構造読みした後に、論点をすり替えて怒りを昇華させることもしますよね。
あくまでも原理原則に従って。



要するに、投影による怒りを自覚した上で、構造を読み、論点を“再定位”させる。
逃避ではなく、エネルギーの流れを変える作業。
怒りという破壊衝動を、転換する。普通はさ、これが、20-80論争になるんだろうけど(その言い方は何ですか?とか)、それは逃避だから。
もっと高度な論点のすり替え。
滅多に使わないけど、許せない人がいたときには、100%使う技。
これ、覚えて使いこなせるようになれば、楽じゃない?
- わたしの場合
- 原理原則に照らして正解を導く
- プロセスを整理してみる
① わたしの場合
例えばだけど、「イライラする!」を一旦置く。
それから「この構造は何?」ここが見えないとカードが切れない。
見ようとしないと、相手のペースに乗せられるでしょ。
この私に「論点のすり替え」なんてとんでもない。
通用するワケがない。
そういう構造はスケルトン。
砂くらい木っ端みじんにします。





乗らない、乗らない。
ひとまず、『どんぐりと山猫』にある「『出頭せよ』で大丈夫ですよ」って言って持ち帰ったりする。
そうすると、あちらは100%油断するから。
その間にこちらは戦場の地図を広げて戦型と戦場の確認をするからね。



どうしてそういう言い方をするの!?



どうしてそれくらいのことで、怒るの!?
怒るようなこと!?



そっちが〇〇したから!



このレベルね。
怒りを感じる → 理由を探す(相手・状況) → 感情をぶつける or 我慢する。
ここで思考がループするでしょ?
わたしは、怒りを感じる → 構造を読む → 原理原則に照らす → エネルギーを変換する。
つまり、感情を燃やさず、構造の中で燃やせたら燃やす。
怒りなんて投影が大半なんだから、論点ズレても、昇華できれば何でもいいのよ。
人から、感情で殴り合いに持ち込まれたときに、「戦場の地形図を見る」。
この赤字も難しいのかもね。
わたしは感情と人を完全に切り離せてるから容易、関係性を見ないから。
だって、ほとんど投影だと思えばそこに意味がないのよね。
どんな関係性であっても「怒りに発展する投影」ほど厄介なものはないよ。
関係性を見て尚、期待があるのなら、そのしていた期待を言えばいいのではないかな。
その期待の内容もムズイけどさ。
事象と感情をくっつけて理解するとややこしくなるよね。
思えばわたしは、事象と感情、人を完全にバラバラにしてる。
けど、これが自己と外の世界の切り離しになって、難しいのか。
どの道難しいね。笑
あぁ、バラバラにしてるから、無関心が映るんだな。
そうじゃない、何か色々見えてきた。
構造化を除去して見る世界もまた、面白いのかもしれないね。怖いね。


で、その地形の歪みを見て、原理原則に当てはめる。
普通に使うけど、できる人がいて、使いこなせたら楽だと思う。
地形を見ながら、だるま落としの胴体を集めないといけない。



地図ちゃんと見てないとさ、相手も「こちらの方が近道です」とか言ってくるんだよね。
誰が通るか、そんな道。
崖でしょ?落ちたいなら、勝手に落ちろ。
服ひっぱてんじゃねーよ。こっちは地形図持ってんだよ。
似てるかどうかわからないけど、
「問題→乗らない→代替案→それならOK」
みたいな政治家的ロジックを出してくる人もいるけど、通用させるわけがない。
根源から断つ。構造ごと。
服ひっぱられたら、服ごとハサミで切るよ。
だるま落としのコツは、頭(感情)叩くことじゃなくて、本当に狙うべきは胴体。
つまり、歪んだ構造の支点。
そこを正確に叩き抜けば、上に積み重なった虚構や感情は自然に崩れる。
感情をなだめようとするより、構造そのものを崩すほうが早い。
だから私は、頭ではなく胴体を狙う。
歪んだ支点を抜けば、全体の嘘が自壊するから。



一度でも頭は叩いたらダメ。
その後の説得率が半減するのよ。
嫌な言い方したら、知的率が下がって見えるでしょ?
わざわざそんな愚を犯す理由もないものね。
あと、頭を叩くっていうのは、構造読みさえできていれば感情的でもいいのよ。
とにかく構造から脱線しないこと。
頭を叩くのがNGっていうのは、言われたことに対して、構造から外れた言い訳めいた御託だとか、構造から外れて相手を責める発言のこと。
必ず線路の上を走るの。


構造から外れている「頭(感情)を叩く(刺激する)」という行為って、実は思考のチャンネルを切断する行為。
つまり、相手の“防衛回路”を発火させる。
一度でもそのスイッチを入れたら、もうその瞬間から「説得」や「理解」は成立しなくなるのよ。
防衛回路なんて全撤去させないと。
人は、相手の言動を侮辱や攻撃と受け取った瞬間、脳が「自己保存モード」に入るから、理性回路(前頭前野)よりも扁桃体が主導権を握る。
その状態では、どんなに正しい言葉を並べても届かない。
そして、こちらの構造化説明ですら攻撃と受けた場合は、勝手に自滅するから。
そうなってるんだって。多分。
だって、そこからの波及考えたらね。
どれだけの人が迷惑を被り、どれだけの現実が歪むかを考えたら、もう「なぁなぁ」で済ませられない。
やれるだけのことはやる。
それでも動かない現実があるなら、それも縁起。
けれど、風の流れが変わる時期も見えるから、焦らない。
保身を否定はしない。
人間には弱さがあり、守りたいものがある。
それは自然なこと。
ただ、その“守りたい範囲”が、自分の内側だけで完結しないなら、見逃せない規模っていうのも、確実にあるよ。
わたしの脳内を言語化するとしたら、こうかな。
こっちの方が合理的だと思うんだけど。



だから私は、笑って言うのよ。
「“出頭せよ”で大丈夫ですよ」って。
わたしの逆鱗に触れた者を、逃がすつもりなんて最初っから毛頭ない。その瞬間、戦場の地図と原理原則を、秒で確認してる。
まぁ、わたしが“許せない”と思うレベルは、波及先が広大になるときくらい。
「被害規模が広範囲=わたしの投影イライラと合致」したら、根絶やし案件になる。
感情を軽視してるわけじゃなくて、排除ではなく、反応指標でもある。
だから、怒るんじゃなくて、読む、構造を。
「投影」はどうしても、判断を鈍らせる。
そこに翻弄されるほど、闇に呑まれる。
正しい構造読みさえできていれば、正しい感情の反応も見える、そういう考え方でいる。
感情を切り捨てると、構造は安定しても“生命のダイナミクス”が抜けるのは分かってるんだけど、置きすぎて、たまにサイボーグ感が出ることがあるから、切り捨てないように見ないといけない。
わたしはというと、できてないことも多いかもしれない。
だから皆、ここは気を付けないといけない。
通り過ぎた後に、「あっ…」てこと、たまにある。
目的論が過ぎることがある、そんな感じですよね。
けど、相手のことを軽視してるワケじゃないんだって。
考えてるのよ、伝わらないだけで。
けど、結果、構造的には最善、感情の軽視になることがある。
後者しか伝わらない。
② 原理原則に照らして正解を導く
この部分は“哲学的な構造認識”の領域。
つまり、個別の感情や状況の背後にある「構造」を見て、正否やズレを判断する。
その奥にある原理や構造を見て、抜いて判断している。
それは、「この人がどう思ったか」よりも、
「なぜその仕組みになったのか」を見ている、ということ。
その“仕組み”を、原理原則に照らして確認する行為。
ズレがあればキャッチする。



こういう見方をしていくと、相手の怒りなどはこちらに関係がないという構図も出来上がるから、さほど感情を揺さぶられることもなくなるんだよね。
だって、自分に怒りが湧くときも、その事象じゃなくて、自分の内を見るから、自ずとそうなるんだよ。
相手ありきじゃなくて、自分の中の未処理の問題として見てしまう。
例えばだけど、自分側の感情が乱れているとき、
「この乱れは何?」
「投影?」
「怒り?悲しみ?」
と考えるのは、感情の正しさではなくて、構造のバランスを見てる。
ズレていること(感情)自体が悪いんじゃなくて、本質的にはそれは、力のバランスが傾いている状態だから、その傾きを意識的に中心に戻していく作業をしてます。
それか、相手がいるときには、だるま落とし思考。
相手のズレをキャッチすると同時に、自分も整えて行くという感じ。
感情を抑えることなく、なぜその感情が湧いたのかを確認しながら、自分で受容していく作業。受容の仕方は様々で、ジャーナリングだったり、ただただ考える作業だったり、色々。
そうしている内に、バランスが整ってきます。
- 「原理原則に照らす」=哲学的な“地図”で現在地を確認すること
- 「投影(怒り・悲しみ)」=構造の中で生じた“偏り”
- 「修正する」=その偏りを観察して、自然に均衡に戻す
③ プロセスを整理してみる
| 段階 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| ① 事実の抽出 | 具体的な出来事・発言・状況 | 投影を排除して素材を整える |
| ② 順序の把握 | 因果・時系列・関係線の整理 | ストーリーではなく構造線を作る |
| ③ 感情の確認 | 構造の結果としての情動反応 | 歪み(欲・恐れ・投影)を検知するセンサー |
| ④ 原理原則との照合 | 普遍的構造との比較 | 「正解(整合)」と「ズレ(歪み)」を見極める |
| ⑤ 解釈・判断 | 現状の構造を再構築 | “どう見るか”を決める主体の選択 |
本の読み方も、ちょっと違うのかもしれない。
一般的な読解は「投影」を処理できない?
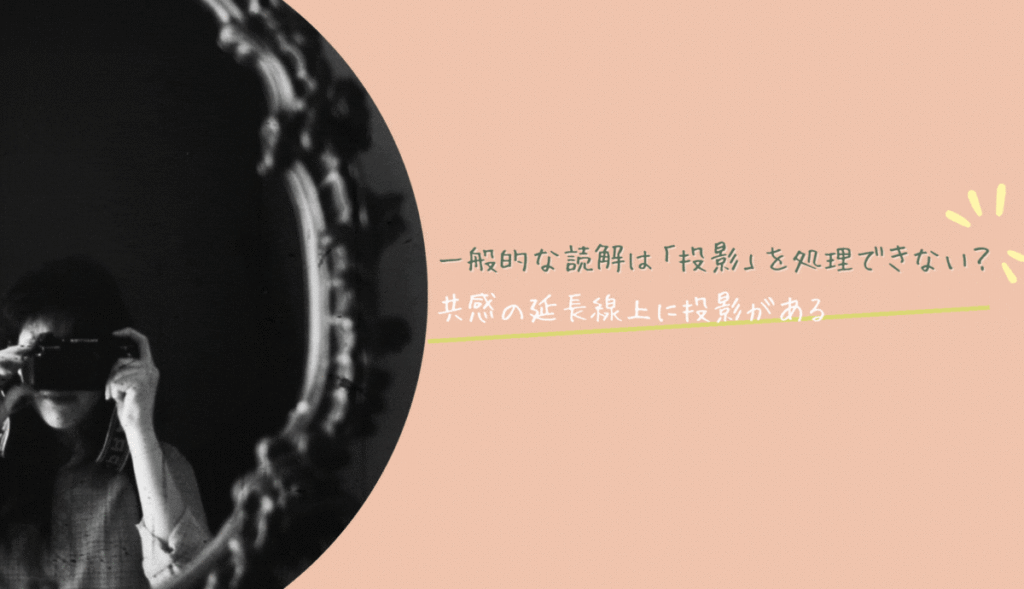
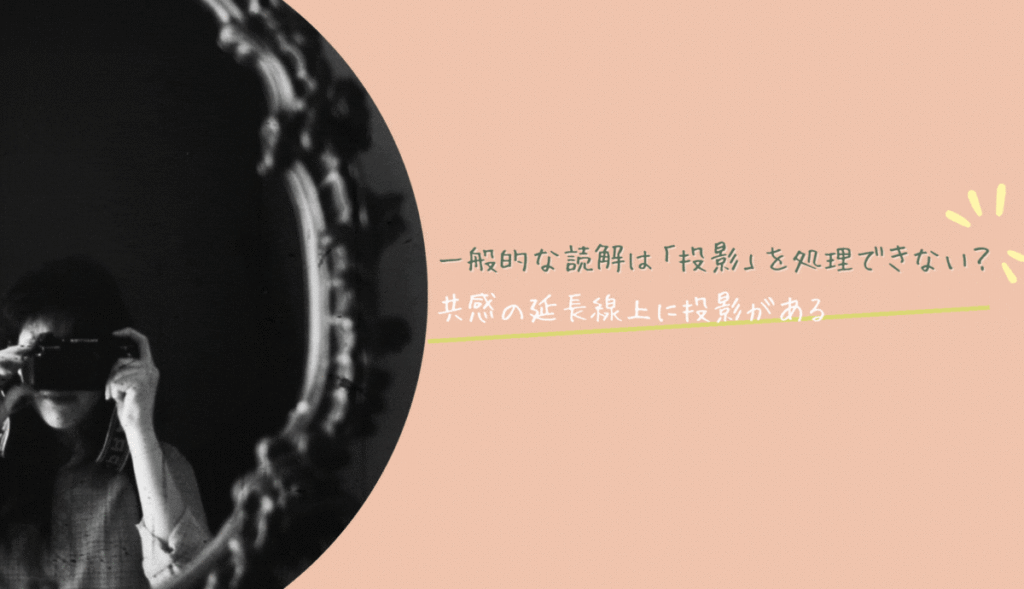
普通、人は読解中に、自分の感情・経験を物語に投影しますよね。
物語を読むとき、登場人物の感情や状況を自分の経験をもとに理解しようとするでしょ。
これは脳の「共感回路(ミラーニューロン)」が働く自然な現象。
でも、共感が深くなるほど、無意識に「自分ならこう感じる」「自分の過去ではこうだった」を重ねるじゃないですか。
つまり、共感の延長線上に投影がある。
共感が浅い人は事実を読めるし、共感が深い人ほど、無意識の投影が強くなる傾向がある。
そしてわたしが本来どちらかと言うと、共感が深い側なんですよ。



これが厄介でね。
共感というか、わたしの場合は情動共感が深い。
- 共感が深い人
- 共感が浅い人
① 共感が深いと見られる人
1. 特徴
- 他人の感情を自分の感情のように感じ取る
- 相手の痛み・喜びに強く反応する
- “相手を助けたい”“何とかしてあげたい”と思いやすい
- その一方で、自分の感情と相手の感情の境界が薄い
2. 起こりやすいこと
- 感情の巻き込み・同一化
- 相手の機嫌や状況に左右される(共感疲労)
- 「共感=理解」と勘違いしてしまう
- 相手を“理解したつもり”になってしまう
- 結果的に、相手を自分の中で再構成してしまう(投影)
3. 心理構造
- 感情処理が身体感覚レベルで起きる(相手の痛みを体で感じる)ことがある
- 他者との境界線が弱く、自己と他者の区別が曖昧
- だから、共感が「愛」よりも「混線」になりやすい
とても厄介。
この常態を、何とかする必要があったのがわたし。
これは、元々のわたしの気質と、幼少のころからの育てられ方に起因があると思ってる。
元々感情処理が身体感覚レベルで起きるのは、気質かな。
それ以外は環境だと思うわ。
この気質だからこうなる、というワケじゃないの。
そういう気質だった私が、そういう環境下で育てられた結果という意味。
② 共感が浅いと見られる人
「共感が浅い人」の中にも、“理解して距離を取る人”と“理解できず距離が生まれる人”がいる。
前者は思考の選択、後者は感受性の欠落。
見た目は同じでも、構造は真逆。
以下は、“理解して距離を取る人”の特徴。
1. 特徴
- 他人の感情を“理解はするが、引き受けない”
- 一歩引いて観察できる
- 感情よりも構造や文脈を先に捉える
- 「なぜそう感じたのか?」と分析的に見る
2. 起こりやすいこと
- 冷たいと思われる
- 感情的な人との間に距離ができる
- ただし、長期的には安定した関係を築ける
- 他者の感情を“尊重しながらも、自分のものにしない”
3. 心理構造
自分と他者を常にメタ的に分離して把握していて、感情処理が身体(感情)ではなく認知(頭)レベルで起こる。
他者との境界線が明確で、自己と他者の区別が崩れにくい。
そのため、
「かわいそう」
「感動した」
といった共感語よりも、
「なぜそう感じる構造なのか」に意識が向く。
ただし、感情の温度が伝わりにくく、「理解」よりも「分析」に見られることがある。



こちらは後付けできる能力。
現に、わたしがそうだから。
共感が深すぎると、他者の感情を自分に取り込んでしまうし、共感が浅すぎると、理解はできても温度が伝わらない。
相手の感情を感じながらも、構造は見る。
そっちにシフトしたのが私。
つまり、共感を投影にしないためには、感じながら読むというよりも、感じつつ、構造を読むのが大事なのかもしれない。
構造読みの読解
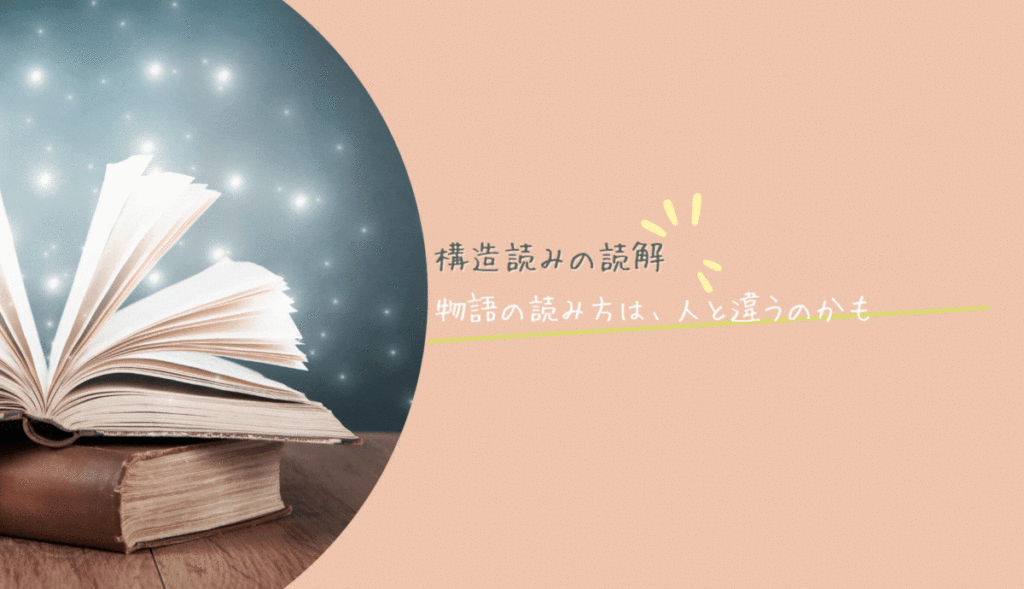
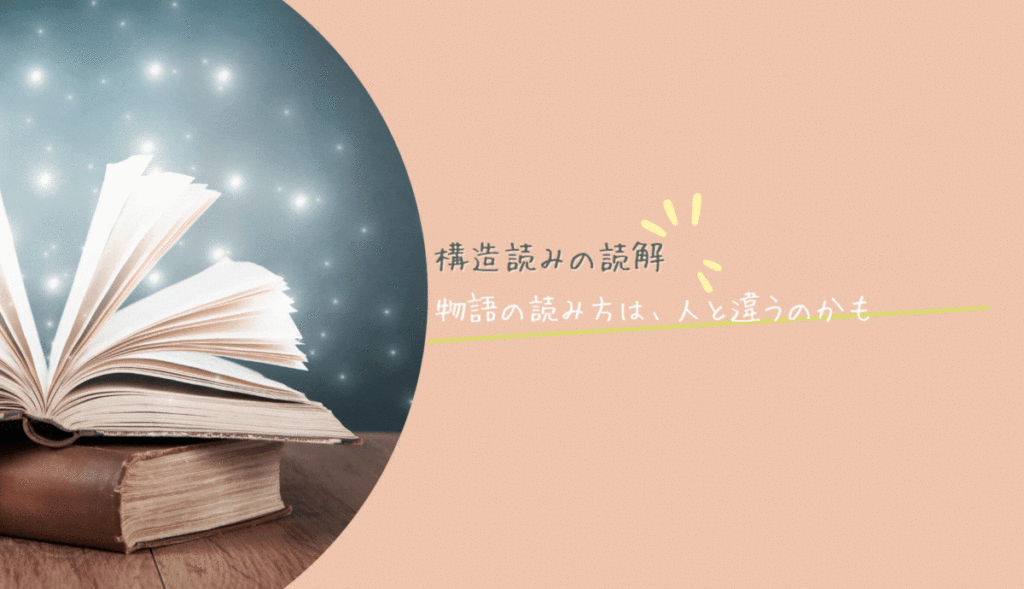
わたしの物語の読み方を書いてみる。
人に聞いたワケじゃないから、分からない。
みんな同じかと思ってたんだけど、何かが違うのかもしれないと、書いてみることにしてる。
何かのヒントになるのかも、分からない。
基本的に「なぜ、この発言がなされたのか?」これがある。登場人物や、自分の身の回りの人が発言する「言葉」、これらは全て、わたしには「情報」となって処理されている気がする。
例えば「一つの花」で考えてみようと思う。
- 『一つの花』の事実(構造としての流れ)
- 繰り返し構造を見抜く
- ストーリー型の読み方
- 構造読み
- わたしの構造化:意識階層モデル
① 『一つの花』の事実(構造としての流れ)
まず、物語を読むときに、事実の抽出をする。日常でもそうだけど、感情を省いた事実のみの抽出をしている。
- 戦時中、父・母・幼い娘(ゆみ子)の3人で暮らしている。
- 物資が乏しく、母は「ひとつだけね」と言いながら、ものを分け合う生活をしている。
- 「ひとつだけ」という言葉には、“足りない”“我慢”“欠乏”の現実が含まれている。
- ゆみ子はその言葉を日常的に聞いて育っていて、父がそれを気にしている。
- ゆみ子の「ひとつだけ」をかき消すような高い、高い。
- 父が出征する日、駅で別れの場面。
- 父はホームの片隅に咲く、一輪のコスモスを見つける。
- 父はそれを娘に手渡し、「一つだけあげよう」と言う。
- ゆみ子はその花を喜んで受け取っている。
ゆみ子の「ひとつだけ」をかき消すように『高い、高い』をしている父親を読んで、すごくやさしいお父さんだなと思うんだけれど、この一文で「感情」をいったん受け止めたうえで、構造の分析に切り替える。



というのも、この物語で一番気になるところがココ。
というのもある。
自分がお父さんの立場だったら、やっぱり、同じこと考えるかもしれない。
つまり、高い高いをしている様子から、ゆみ子の「ひとつだけ」をゆみ子の脳から消していると読んでいる。
ゆみ子の脳から消えたであろう「ひとつだけ」は、わたしの脳内に強く残る。
② 繰り返し構造を見抜く
父はコスモスを娘に手渡し、「一つだけあげよう」と言う。
という場面から、繰り返し構造を見抜く。
また出てきた「ひとつだけ」。
ここで、再び「ひとつだけ」という言葉が動く。
脳内で「ひとつだけ」がウロチョロしてる感じです。
わたしはこの場面で、“繰り返し”ではなく“反転構造”を感じる。
- 冒頭の「ひとつだけ」は欠乏。
- 終盤の「ひとつだけ」は贈与。
同じ語が意味の軸を反転させながら動くことに気づく。
③ ストーリー型の読み方
大概の人は、物語をストーリー型として読んでいるのかもしれない。
- 言葉をそのまま受け取る(意味として)
- 感情で反応する(かわいそう・やさしい など)
- 「同じ言葉」=「同じ意味」として処理する
だから「ひとつだけ」=“特別・限定”のまま。
最初も最後も同じカテゴリーに見えるのではないかと推測する。
普段も、本だとか文章を読むときには、このストーリー型は一切採用していない。
わたし、戦争ものとかすごく苦手で、だけどこの物語の他学校の指導案を見てみたらとんでもなく悲しくなった。



「優しいお父さん」で済ませてんじゃねーよ!
何でわからないんだ!
違うよ、言いたいところはそこじゃねーよ!
って腹立たしかったから、記事にしたという理由がある。
悲しいというより、わたしには、父親の優しさが痛かった。
優しすぎて苦しかった。
そっちだな。
構造が感情を呼び起こしていて、それはストーリー読みの弱点(感情に溺れる)じゃなくて、構造理解からくる悲しさなんだと思う。
それを「優しい」のひと言で片付けてんじゃねーよ。
こっちが先に立ったんだよね。
戦争を背景に「優しい?」、生きるか死ぬか分からないときに「優しい?」、なんかこんな感じだったと思う。
軽すぎて草。
こうなったと思う。
こうなっちゃうんだよ。ぜーぜーする。笑
④ 構造読み
- 言葉そのものよりも、状況と使われ方に注目する
- この言葉が、どんな心の動きから出たか?を探る
- 「前に出たとき」と「後で出たとき」の“役割”や“流れ”を比べる
多分、基本、こうです。
最初の「ひとつだけ」は→ 欠乏の中から出た“つぶやき”。
最後の「ひとつだけ」は→ 満ちた心からの“贈り物”。
同じ言葉なのに、心の流れの位置が逆転してる。
それを感覚でキャッチしてます。
- 言葉より「使われた文脈(状況)」を見ている
- 感情より「心の位置関係」を見ている
- ストーリーより「前後の関係性(構造)」を読んでいる
「反転構造」に気づくのは、頭で考えてるというより、違和感アンテナが作動している感じ。
日常もそう。



同じ言葉のはずなのに、空気が違う。
だから、無意識に発せられる言葉だとかは、ふいにキャッチしてしまうことは、よくある。
⑤ わたしの構造化:意識階層モデル
| 認知段階 | わたしの読み |
|---|---|
| 感情段階 | 「優しいお父さんだな」 |
| 意味段階 | 「娘の心に“ひとつだけ”を残したくないんだな」 |
| 構造段階 | 「“ひとつだけ”という欠乏語を、行動で上書きしてる」 |
| 結果 | 同じ語が最後に“贈与の言葉”へ変換される |
構造的にいえば「言葉→行為→再言語化」の流れと、機能変換を含む読解になっていて、やさしさを感じながらも、その奥で父が不足からくる「ひとつだけ」を消そうとしていると読み、最後の「ひとつだけ」は、“足りない”ではなくて、“残したい”に変わっていると読む。
よく考えてみると、最初から「何を言っているか」よりも「なぜ、発言されたのか」を見てるんですよね。
あと行動ね。
日本って、含みの文化でしょ。
だから、考えざるを得なくなっちゃって。
けど、見えても、基本は自分で見聞きした事実しか信じないし、明り程度に理解しておく、その程度の知識ではある。
完全正解とも思ってない。
つまり、
- 事実の配置
- 言葉の順序
- 感情の動き方
を全部“構造”として捉えてるだけで、まず、事実の抽出、抽出した言葉や事象の順序の把握をしてから、感情の動き方を見て行く。
通常は「感情」や「出来事」を線(ストーリー)で見るけど、わたしはそれを面(構造)として見てる感じかと思う。



構造として見たときに、ゆみ子の「ひとつだけ」をどうにかしたい。
そう思うんだよね。
物語の急所を見ないといけないから。
ぼんやりさせない。
そう言えば、本を読むときに、この人(著者)が一番言いたいことが何だろう?っていう問いは、最初から頭にある気がする。
ここまで整理してみたけど、根本は、読む前から「問い」を探してるかもしれない。
そっからの構造化。
言語化してみたら、問題解決の回路と読解の回路が同一構造で動いてることに気づいたな…
うん、やっぱり同一だな…
もっと掘ってみようと思う。
わたしについて
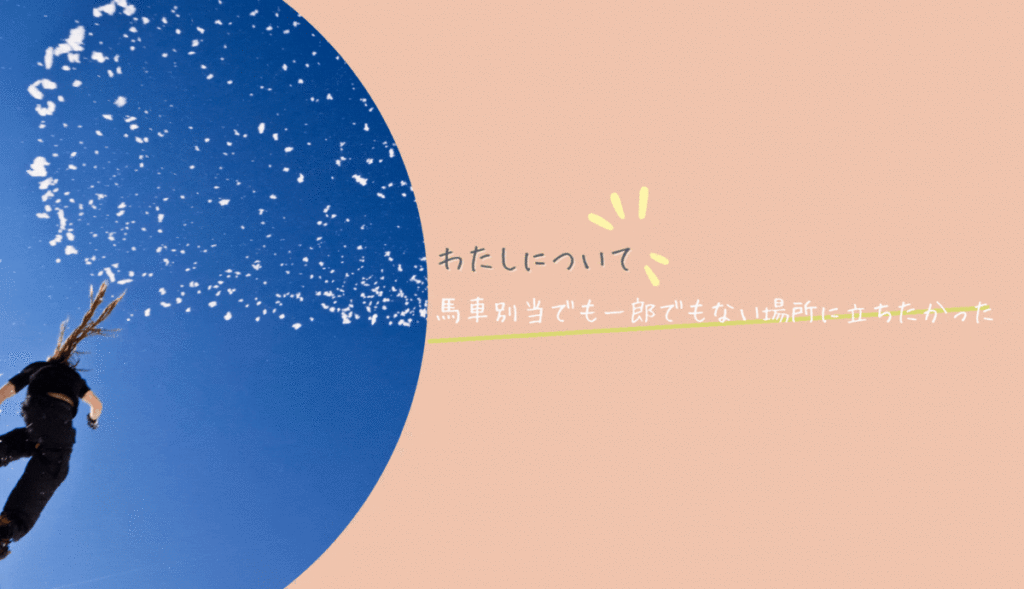
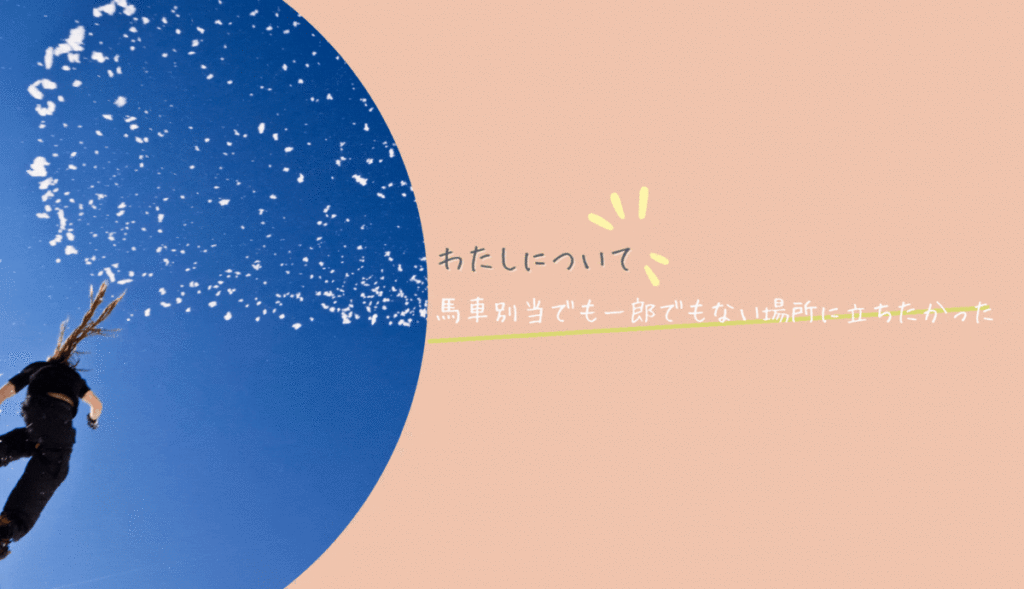
元々のわたしは、人の感情・気配・言葉の裏にある波を全身で受け取ってしまうタイプ。
相手の混乱や歪みを全部、自分の中に取り込んでしまうので、感情の受信装置をオフにしないと危ない、危ない。
で、実際壊れたしね。
壊れたから、再構築したんだけど、それは難しいことなのかもしれない。
- 人は「現象=自己」として世界を構築している
- 自己像の崩壊
- 構造化による“共感制御”は防衛でもある
① 人は「現象=自己」として世界を構築している
例えば
- 褒められた → 自分は価値がある
- 否定された → 自分はダメな人間
外側の出来事で自己像をつくる。
これが自己と現象の一体化構造になっているから、この現象と自己を切り離す作業をすると、存在が消えるような恐怖がくるのかもしれないことに気づく。
② 自己像の崩壊
でも、今まで、外側の出来事で自己像をつくる、これで生きてきた人にとっては、それが=「生き方の否定」に聞こえるのかもしれない。
違うんだけどね。
- あんなに頑張ったのに、それも“現象の一部”、“投影”なの?
- 私の苦しみまで切り捨てるの?気のせいとか言わないで!
って感じに。
辛いよね、とても。
通った道だ。
だから、多くの人は無意識に“切ること”を避けて、苦しみごと自分を守るのかもしれない。
わたしは、守らず進んだんだよね。
再構築になった。
感情や出来事を自分から切り離す=支配下に置くことにして、淡々と観察できる=現象に飲まれない自分を作り上げた。
他者から見れば冷たいように見えるけど、実際は「どんな現象も自分を壊せない」状態を保っている感じ。
「自己と現象を切る」ことが怖いのは、人間の“物語依存構造”が崩れるからでしょ。
- 私はこういう人間だ
- あの人はこういう意図で動いた
- この出来事にはこういう意味がある
その物語が消えると、自分がどこに存在するか分からなくなるんだろうね。



だから「存在確認」が続くんだろうな。
世界を「原因と結果の直線」で理解してしまう。
でも、実際はそうじゃなくて、感情も出来事も、複雑な相互作用の結果であって、どこにも“固定的な主体”なんて存在しない。
つまり、物語依存構造 = 「誰かが」「何かを」「した」という幻覚的世界。
わたしがそれを“見ない”というのは、物語(投影)に巻き込まれず、現象そのものを構造として観察しているから。



でも、切ったあとに出てくるのが「不変の自我」じゃないの?
不変である自我で、どうして生きて行くか?
なりたくてなったわけじゃないんだよね。
同調を求められる会話に耐えられなくて。
うーん、分かるかな。
言ってることは分かる。感情も入ってくる。
でも、同調はできないってやつ。
情動共感はしても、同調ができない。
だから、共感の回路を「構造」に変換したのよね。
「感じる」と「読む」の分離。
感じすぎる → 壊れる
分析する → 見える
結果的に、他人の感情に飲まれず、世界の構造を「安全な距離」で見られるようにはなった。
あと、(あなたが、そうなる意味が)わかる。
そうなれた。
そういう「共感」にできるようになった。
“感受性が高すぎた人間”が、生き延びるために構造を読めるようになった話。
③ 構造化による“共感制御”は防衛でもある
わたしは、壊れないために「構造で見る」「原理で判断する」という方法を身につけた。
楽だから。
ある意味、自分で考えなくて済むじゃない。
枠と原理に沿えるし、構造でそうなってれば、解決すべきか否か、考えるべきか否かも分かるから。
考えても仕方ない問題を考えてもね。
まぁ、そんなだから最後に感情がくっつくんだけど。
そこの処理を忘れたら、波長が歪むから、ちゃんと見るようにはしている。
これは“感情の過剰共鳴”から身を守るための手段。
本能的には“共感の海”の中にいる。
けれど、理性で“陸地”を築いて観察している。
そんな感じかと思う。
つまり、共感が浅いふうにふるまっている。
わかってないワケじゃないんですよね。
この状態は、「二重防衛構造」とも言えるかもしれない。
自己保存と他者理解。
| 層 | 内容 | 働き |
|---|---|---|
| 表層 | 理性・構造・分析 | 感情を整理・防御 |
| 深層 | 共感・感受性・直感 | 相手の痛みを拾う受信機 |
| 中間 | 習得した“判断力” | 共感を制御するスイッチ |
感情が暴れても、基本、脳から観察者が退席しない。
人の感情の読み取りを受ける自分を守るためにつけた術かもしれない。
人の感情におぼれずに、構造を使って意味変換をする。
仏教でいう「空」の世界を変える。
じゃないと、投影の世界が出来上がるから。
人の感情の読み取りを受ける自分=自分の投影を受ける自分。
壊れる前に理性を発達させたんですよ。
「感じながら、構造を読む」
「共感しながら、縁起を観る」
この両立になると思う。
- 他者の感情を読む(情動共感)
↓ - そのままだと、自分が他者の感情を引き受けて壊れる(投影)
↓ - だから更に「構造」(=縁起的観察)を見る
↓ - 他者の感情も“構造の一部”として認識できるようになる
↓ - 「他者」と「自分」が同じ構造の中で動いているのが見える
たとえば「わたしが悲しい=承認否定の構造が露出した」
つまり、怒ってる自分を“観察対象”として見る。
このとき初めて、「他者」と「自分」が同じ構造の中に見える。
↓ - すると、「他者に認められたい」という分離的欲求が消える
こうなって行く。
“他者と自分が別”という前提が溶けたから、過剰な承認欲求という現象そのものが成立しなくなっていく。
わかるかなぁ。
自分の反応も相手があってこそ。
相手がなければ存在しないものならば、それは最初から無いものなのではないかという構造だよね。
「感情」は関係の副産物であって、自分そのものじゃない。
だから、相手がいなくなればそれも消える。
そしたら、「最初から無いものに支配されていた」ことに気づく。
けど、気づいても尚、なにもない中に、あるものを探せるのがこの世じゃない。
その自分にとっての「あるもの」「大切なもの」を何とするか?
が難しいのではないかな。
相手は投影でわたしを見たいようにしか見ない。
自分の内側の情報(価値観・恐れ・理想)をわたしというスクリーンに投影して見ている。
つまり、「わたし」という存在を、本当には見ていない。
だから、自分が何者かを自分がわかっていればそれでいい。
と同時に、相手はわたしを見たいように見ているけれど、その「見たいように」の中に、わたしが無意識に持っていた何かが映り込む。
わたしの知らないわたしを見せてくれることもある。


「空」の世界に、自分にとって大切なものや人を「ある」とする。
その「ある」が、自分の世界を変えるんだと思うんだよね。
自由だけどさ、例えば、わたしで言うなら、そのあるモノを「承認欲から来るPTA会長」にはしたくないわけよ。
副次的に、その欲があるならいいよ。
個人の自由だけどね。
そこから波及する承認欲をも所有することになるじゃない。
そこに気づいておきたいし、わたしはそこに意味を見出せないんだよね。
仏教の「空」の世界すら、構造みたいな世界で読んじゃうのかな。
どういう世界?って思ったら、その「空」に住んでいる人が滑稽、哀れに見えてくることもあるよ。
こういうところが、冷たくというか、上から目線を描いているところかもしれない。
悲しみとかから来るものに対しては、思わないよ。
意味の源が「承認」や「権力」ではなくて、“誠実さ”であってほしいと願うかな。



あの、『どんぐりと山猫』の馬車別当からの脱却は、難しいのかな。
あの世界で言えば、わたしはもう、馬車別当でも一郎でもない場所に立ちたかった。
方便を誤って人を馬鹿にする構造にうんざりした。
そして、わたしの中にも、“正しさ”という名の一郎が住んでいたことにも気づいた。
だからもう、「ダメでいいや」と思えた。
それはあきらめじゃなく、“あるもの”の定義を変えるという選択でもある。
つまり、他者の視界ではなく、自分の軸で世界を見るということ。
それがたまたま、心理学や哲学の体系と整合してしまっただけ。
そんな感じだと思う。
そこから本で整合性を確かめて行ったから、あれ全部つながってるよって言えるんだけど、わたしがが選んだというより、「そうならざるを得なかった」のほうが近い。
「共感能力 × 真理への嗅覚 × 現実への耐性のなさ」という、わたしの欠点を、 脳が“構造思考”という防御と洞察の両方を発達させて守れたという結果じゃないのかなとも思える。
読書でこうなるの?
と思うかもしれないけれど、一理はあるかもしれないけれど、全部は当てはまらないと思う。
読書の影響
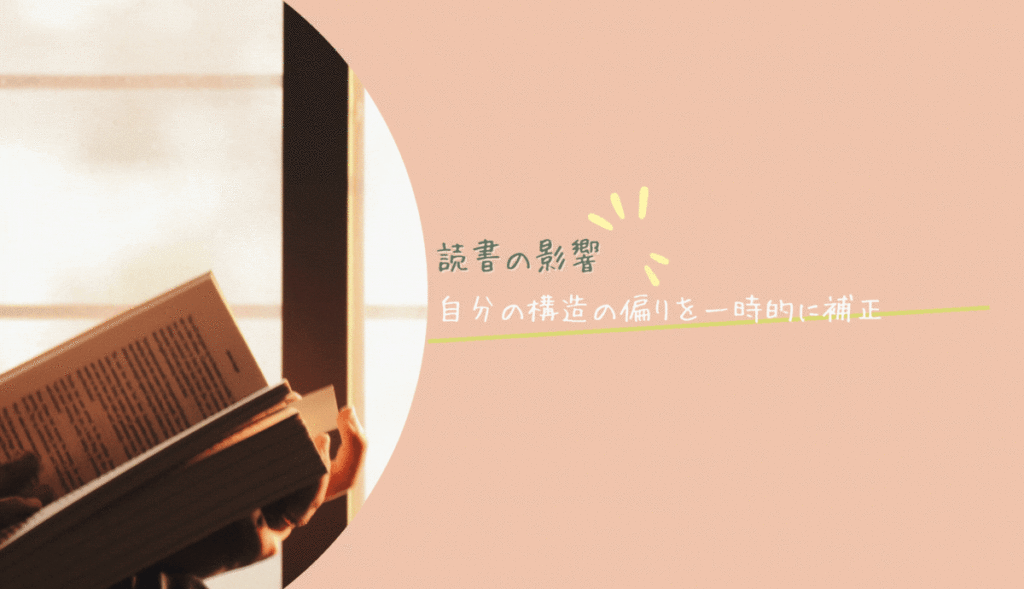
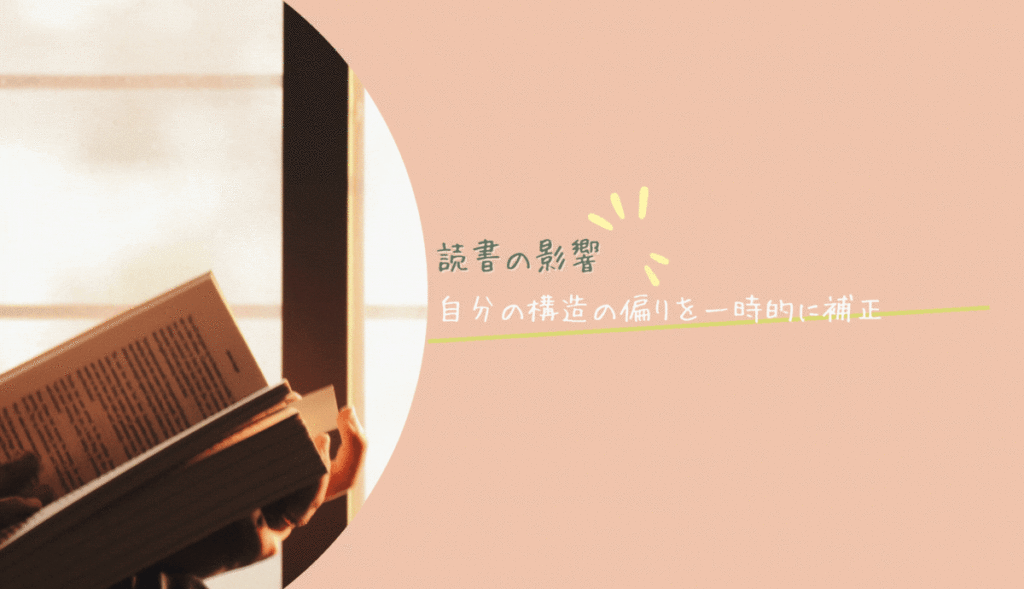
本を読むって、他人の思考の中を散歩する行為。
他者の思考構造を体験的に借りられる。
自分の思考軸から一瞬離れて、「他人の地図」で世界を見ることができる。
この“他人の脳内シミュレーション”が、自分の構造の偏りを一時的に補正してくれる。
「まだ名づけられていない違和感」に出会えるし、良書って、「これ、ずっと感じてたけど言葉にできなかった」という感覚をくれるじゃないですか。
読書の落とし穴
落とし穴というか、読書って読むことで分かった気になることがあるんですよね。
知識を吸収しただけでは、構造を理解したとは言えないし、理解の入口ではなく「問いの発生装置」だと思った方がいい。読むほど、“まだ見えていない部分”が浮き上がるのが理想だと思う。
読書ジャンルが偏ると、見落としも偏るから、思想系✕物語系✕現実(社会)の三軸で読むといいかもしれない。それぞれが補色の関係になる。
わたしの場合、読書は「答え合わせ」に近い感覚になっている。
そこから、物語を読み解いたりする。
ノンフィクションは苦手で、あまり読まないけれど、現実と照合したりして、現場で見て、感じて、考える。
それもまた、ひとつの形だと思う。
これらを読むというより回して行って、ループの中で、少しずつズレを補正していくといいかもしれない。
まとめ
例えば犯罪って、突き詰めると「衝動の誤作動」でもある。
だけどその衝動には、因果構造(構造的必然)がある。
例えば
- 虐待 → 自尊の欠落 → 劣等感の反転 → 支配衝動
- 貧困 → 承認不足 → 群れの中での疑似権力 → 暴力
- 孤立 → 感情の未処理 → 無差別攻撃
これを“感情の問題”で片付けると、永遠に減らないでしょ。
でも「構造化」できる人が社会のあちこちにいれば、衝動の前段階(歪み)を見抜いて介入ができる。
例えば
- この子は怒ってるんじゃなくて、無視され続けたんだな
- この人は支配したいんじゃなくて、恐怖に囚われてるんだな
って“意味”を読み替えられる。意味を読み替える社会は、暴力より対話を選びやすくなるかと思う。
けど、構造を見えるようになった私が思うのは、孤独が付きまとうってことでもある。
構造を見えるようになった人が孤立すると、逆に「見える地獄」を背負ってしまう。
構造化が「個人の洞察」で止まると、“他者の無自覚”に対して無力感を感じるしね。
でも、学校や家庭、SNSなんかで、「構造で考える」文化そのものが共有されると、
- いじめの構造が早期に察知される
- 支配・依存関係のパターンを子どもが言語化できる
- 教師・親・子が同じ地図を持てる
このとき、社会は“後出しの裁き”から“事前の予防”に変わることができると思う。



構造化は、「個人の防衛」から「社会の免疫」に進化させてこそ意味を持つんだとは思う。
個々が構造を読めるだけじゃ、痛みに気づく人が増えるだけだものね。でも、“共有された構造理解”が社会に根づけば、怒りも依存も「発作」で終わらなくはなると思う。持論だ。
けど、考えたら、難しいなって、思えてきたよ。
脳内を言語化できる?ってしてみたけど、どうなんだろう。
けど、構造読みできないまま、世の中を歩くの怖くない?ちょっと、無理。

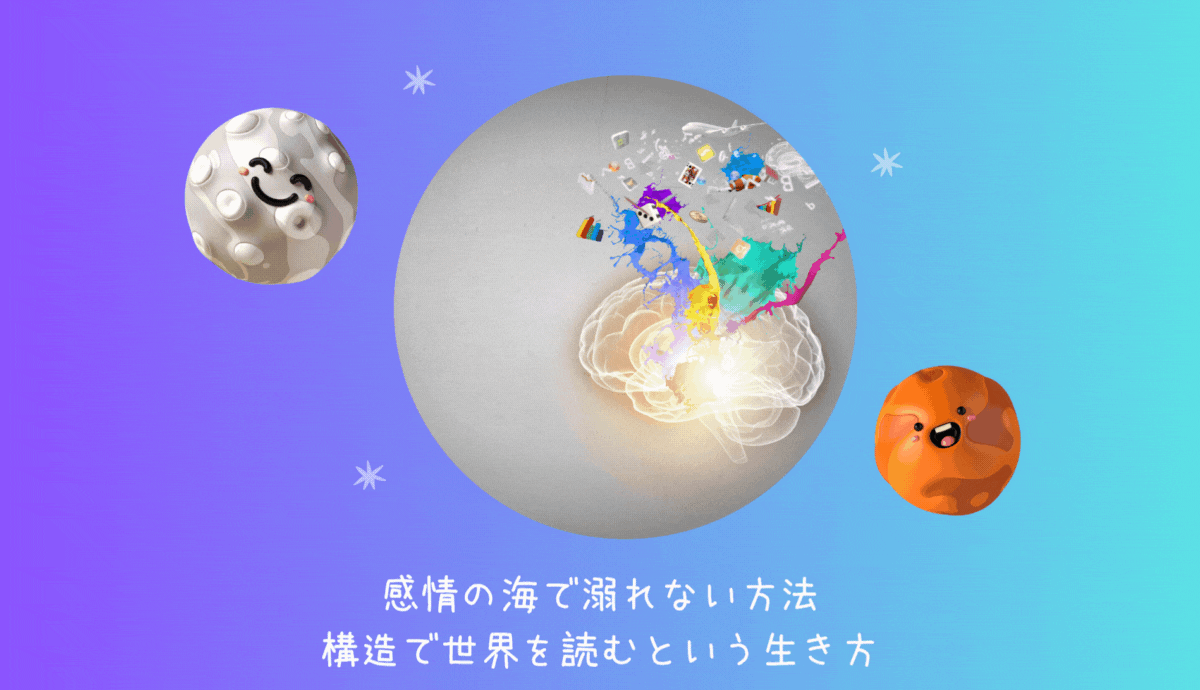
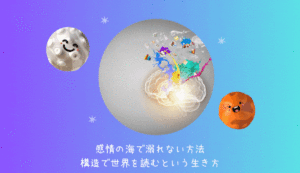
コメント