教育に求めることができないって前の記事で書いたんですが、わたしならこんな感じの指導になるかなぁ?
というのを作ってみました。
当時これを作ったときは、正直、自分の考え方と世間の考え方の乖離に気づいてなかったんだよね。
こんな「核」、普段、話さないでしょ。
でも、あれから「え、噓でしょ?」みたいな出来事が続いて、伝え方を結構変えてます。
変えないと、私の考えをそのまま人にインストールするだけになるから。
このブログは、結論を配る場所じゃなくて、フレーム(枠組み)です。
問いの立て方、見方の切り替え方、条件の探し方——そういう“思考の型”を渡すためのもの。
だから、先生が理解できていないまま使うと危険になる。
危険っていうのは、善悪の話じゃなくて、自分で考えなくなるってこと。
読めば「それっぽく言える」ようになるぶん、「正解の台本」になりやすい。
この思想で討論したら、たぶん“勝てる”。
でも、そこで終わるなら、ただの論破ゲー。
私はそれを避けたい。
勝つのはいい。
問題はその先——
読めば分かる。
それ自体は、誰でもできる。

私が事例を使って、哲学や心理学の補助線まで引いているから、なおさらだ。
分かる=できるは論外。
できるっていうのは、自分の現場で使って、判断して、選んで、言葉にして、結果まで引き受けられること。
それがどれだけ難しいことか。
分からない者が、知識を武器として使いだす。
必要なのは、「自分もそう思う」じゃなくて、
「自分は〇〇という条件/経験/構造があるから、そう思う」まで言えること。
つまり、考えたプロセスに、自分の言葉で責任を持つこと。
要するに自分事化だよね。
そのために、私の見解は“メモ”に移動しました。
授業の主役は、子どもと先生の思考であって、私の答えじゃないから。
ここでは載せてるけど、実際には載せない方がいいんだと思うわ。
一応、載せときます。メモとして。
【目的】単なる感動や美談で終わらせず、『支える行動』がどうやって成立するかを考える。背景にある条件や気持ち、環境を知り、自分にとって“思いやる”とはどういうことかを考える。
【対象学年】小学1年~6年(発問と話し合いを年齢別に調整) 。
【背景に入れたい要素】自然界と動物園の違い、思いやりが生まれる“環境”の重要性、マズローの欲求5段階説の基本的な考え方。
メモ欄について
メモ欄は、先生が読み上げる台本ではありません。
授業で使う場合は、先生が内容を理解し、自分の言葉に落としてから扱ってください。
- メモは「考え方の一例」です。正解として提示しない。
- 児童の発言をメモで評価しない(合ってる/ズレてる判定に使わない)。
- 目的は「結論を教える」ではなく、児童が条件 → 気持ち → 行動を自分でつなげることです。
授業で扱うときのルール
- 断定を避け、「〜かもしれない」「一つの見方」 の形で扱う。
- 児童の発言が善悪判定や人物評価(あの子は優しくない等)に向かいそうなときは、話を戻す。
戻し例:「その子が悪いかどうかじゃなくて、“そのときの条件”を考えてみよう」
メモ欄を使ってよいタイミング
- 先生の事前準備(問いの狙いを理解する)
- 授業後のふり返り(発言を整理する)
- 次時の問い直し(問いを設計する)
※授業中にそのまま読むのは禁止(台本化防止)。
禁止事項(台本化・承認ゲーム化を防ぐ)
- メモを読み上げて授業を締める
- 先生の価値観で「正しい答え」を決める
- 発言を「えらい/すごい/正解」で順位づけする
- “ほめられたい”を「ダメ」と裁く(承認欲求が地下化しやすい)
安全に関する例外
いじめ・危険・暴力が疑われる場面は、価値観の議論より
安全確保と相談(大人に知らせる)を最優先します。
『ゾウのアヌーラ』で本当に伝えたいことは?
『ゾウのアヌーラ』は、病気で立てなくなったゾウを仲間たちが何日もかけて支え続け、命をつないだ話。
授業では
『思いやりって大事だね』
『やさしいゾウたちだったね』
という感想が出てたんですよね。
もちろんそれも大切なんだけど、
このお話には
『やさしさとは何か?』
『どうして支えることができたのか?』
を考えるヒントがたくさんあるんですよ。
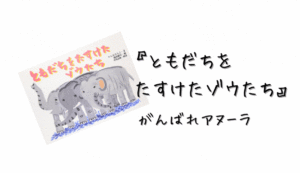
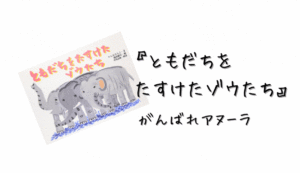
- 命を支える“余裕”と“環境”について考えよう
- ちょっとだけ“心のしくみ”を知ってみよう(アブラハム・マズローの考え方)
- 子どもたちに渡したい問いと補助解説(先生用コメントつき)
- さらに深めたい視点:行動の奥にある“もうひとつのやさしさ”
① 命を支える“余裕”と“環境”について考えよう
やさしさは、気持ちだけでは続かない。
命を支えるには、支え続けられる“余裕”がいる。
自然の中では、敵が来たり、水や食べ物が足りなかったりして、助けたくても助けられない場面がある。
でもアヌーラは支えてもらえた。
それは「動物園」という安全な場所で、食べ物や水があり、敵に襲われない条件があったからかもしれない。
つまり、思いやりは“心の問題”で終わらない。
そうできる環境と時間があって、初めて行動になる。
人もゾウも同じ。
じゃあ、その“余裕”って何でできてるんだろうね。
心の中では、どんな順番で整っていくんだろうね。
② ちょっとだけ“心のしくみ”を知ってみよう(アブラハム・マズローの考え方)
マズローという人は、人の気持ちには「順番」がある、と考えました。
下のほうが満たされると、上のほうの気持ちが出やすくなる、というイメージ。
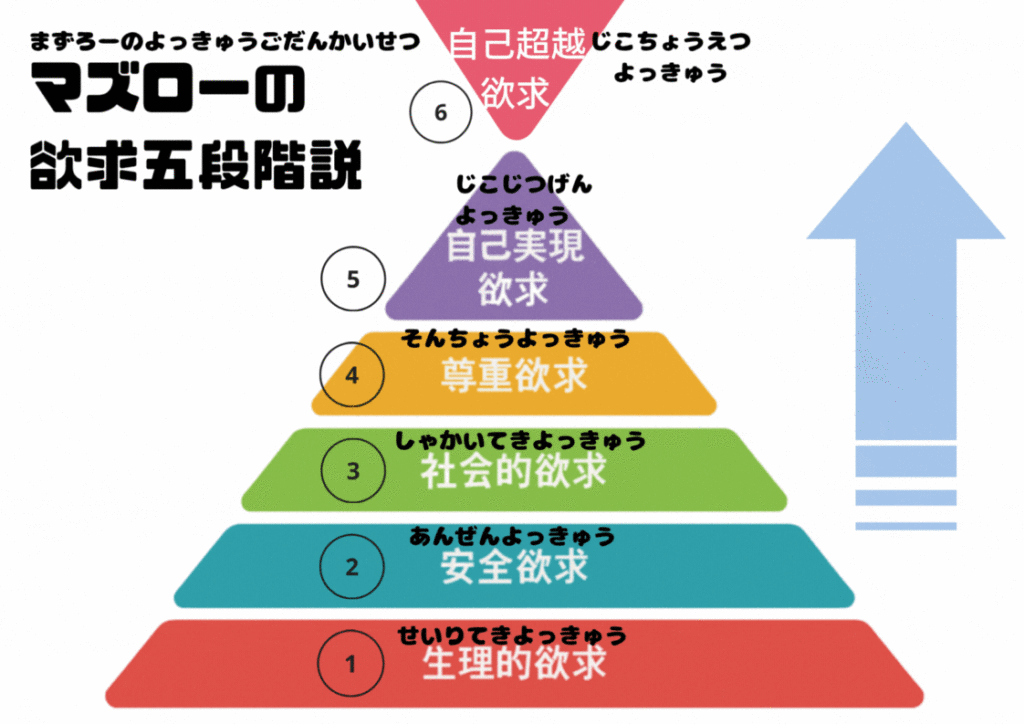
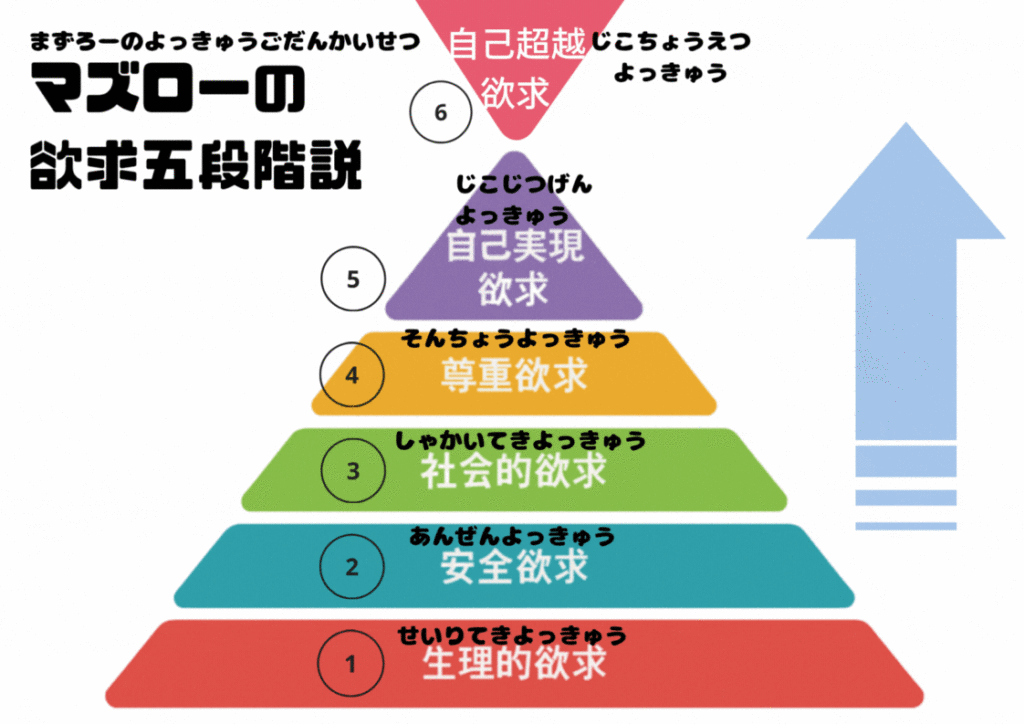
- お腹がすいていない・ねむれる(体が元気)
→ ごはんがちゃんとあって、よく眠れること。 - あんぜん(こわくない・安心できる)
→ まわりに怖いことがない、安心してすごせること。 - なかまがいる(友だちや家族とのつながり)
→ ひとりじゃない、だれかとつながっている感じ。 - 自分に自信がある(できた!って思える)
→がんばったことをほめてもらえたり、自分でも『うまくいったな』と思えたりすること。 - 自分らしく生きる(やりたいことをがんばれる)
→ 『こうしたいな』って気もちが動いたときに、行動できること。 - だれかのために動ける(人のためにがんばれる)
→ 自分のことだけじゃなくて、まわりの人や自然、社会のために『こうしたいな』って思って行動できること。
タカコとガチャコは、①~③のところが守られていたから、アヌーラを支える行動(⑥:だれかのために動ける)につながったのかもしれません。
また、命令されたからではなく、自分で選んで動けた(⑤)とも考えられます。
④ 尊重(承認)欲求
→ ほめられるだけじゃなく、「ここにいていい」と思えること(ばかにされない・邪魔者にされない)もふくみます。
そして、タカコとガチャコの心の中(動機)は見えないので断定できません。
でも、支える行動が起きて、命がつながり、周りに影響が残った。
それが、この話のいちばん大事なところです。
(先生メモ:自己超越の構造としても読める)
※がんばって一時的に上の行動ができることはある。
でも、土台がないと続かない。
③ 子どもたちに渡したい問いと補助解説(先生用コメント・問い返し集)
- タカコとガチャコは、どうしてアヌーラを支えられたんだろう?
-
先生へ:行動の前に「条件」を探させる。
問い返しの例
- タカコたちが支えられたのって、どんな環境だったからだと思う?
- もしタカコたちが、外でこわい動物に囲まれていたら、同じことができたかな?
- “やさしさ”って、いつでもどこでも同じように出せると思う?
“やさしい行動”の背景には、安心できる環境や安全が守られていたことがある。
“やさしさ=気持ち”だけでなく、気持ちが行動になるには条件(場所・状況・余裕)も関係する。
だから「なぜ支えられたのか」を考えるときは、気持ちだけでなく条件にも目を向ける。 - もし野生だったら、同じことができたかな?
-
先生へ:「支えない=悪」を外す。
「支えられない状況」も現実にある、を出せれば十分。問い返しの例
- 自分がこわい場所にいたら、同じことができると思う?
- 助けたいのに動けないのは、どんなとき?
- 動物園と野生のちがいを具体的に言うと?
やさしさをもって助けることは良いこと。
綺麗ごとだけ並べて生きることは、ある意味楽である。
やさしくしたいのに、できないときもある。
助けたいけど動けないこともある。
相手の全部(背景)を知ることは、他人にはできない。人はそのとき、そのときの環境で変わる。
『相手には、相手の事情があるかもしれない』という視点を持つことが大切。
その行動が自分を守り、相手を裁かないやさしさに繋がる。 - 自分の生活で、だれかの力になりたいと思ったとき、どんなときだった?
-
先生へ:「やさしさ=根性」ではなく「余白」へ。
問い返しの例
- やさしくできたとき、自分はどんな気持ちだった?
- やさしくできなかったときは?
- “無理しないやさしさ”って、どんな感じ?
やさしさは、がんばって出すものではなく、自然に出るもの。
- 支える側の人は、ずっとがんばり続けて大丈夫かな?
-
先生へ:支える側の境界線=教育。
ここは道徳の核。
「善行を続けろ」ではなく
「どう支えるかを選ぶ」。問い返しの例
- 支える人って、どんなときに疲れそう?(支えている人が応えてくれないときetc、そこでもう一度『支える』ということを立ち止まって考えることも大事)
- 「自分を守る」ってどういうこと?
- “助けて”と言うのは弱さ?
それとも決断? - 支える形にはどんな種類がある?
(そばにいる/分担する/休むなど)
“支える側”だけがずっとがんばり続けると、どこかで限界がくる。
支えるというのは、ただ“がんばり続けること”ではなくて、“どう支えるか”を選ぶことでもある。
疲れたときは、まず休む。
余裕が戻ったら、小さな親切を一つしてみる。
“自分を立て直してから渡す”という順番を大事に、“支える側としての決断”も、大切である。
思いやりを続けていくには、自分の心や体がちゃんと満たされていることが前提。それがあってはじめて、人のことも大切にできる。
“助けて”を言うことも、実はすごく勇気のいること。それはただ誰かに頼るのではなく、“相手を信じること”であり、自分の弱さを相手に渡すという、大事な決断でもある。
“守る”ことも、“助ける”ことも、“助けてもらう”ことも、どれもみんな、勇気が必要。きちんと自分で選ぶことができるもの。
選択の中には、必ず“自分を大切にすること”も含まれていてほしい。それが、ほんとうの意味で“やさしさを続けられる人”になるということである。 - ほめられたいから、やさしくするのって、どう思う?
-
先生へ:きっかけとしては否定しない。
ただしゴールにすると歪む(承認ゲー化)。
行動のあとに「誰が助かった?」
「次もやる?」へ転換問い返しの例
- ありがとうって言われたとき、自分はどう感じた?
- ほめられなかったら、次もやる?
動機がたとえ“ほめられたい”だったとしても、その結果、誰かが助かったのなら、そのやさしさには意味がある。
やがて、その喜びが“もっと誰かのために”と広がっていく可能性がある。
『ほめられたい』という気持ちで誰かを助けたとしても──それも、その人なりに決断して出した行動。何も考えずに動かない選択よりも、誰かが助かる構造がある。
ほめられたいは出てもいい。
でも、ハンドルは“誰が助かった?”に戻す。 - やさしくしないという選択は、わるいことなの?
-
先生へ:支える行動には『そばにいる』『手を貸す』だけではなく、
『見守る』『信じて待つ』などのかたちもある。
何もしない=無関心、と決めつけない。問い返しの例
- やさしくできないとき、声をかけられないときって、どんなときだと思う?
- もし自分がやさしくできなかったら、どんな気持ちになる?
- “やさしくない”って、ほんとうに悪いことかな?
“やさしくしない”という行動にも、その人なりの思いや事情があるかもしれない。
やさしくしないのではなくて、やさしくできない状況なのではないか?ということを想像する視点はとても大切。
例えば『言わなかった』という決断の中にも、やさしさがあることがある。気づかれたくない気持ちを守ったり、相手の心を思って言わなかったり。そういうことも、きっとある。
例えば自分がしたその決断(助ける・助けない)で、責められるようなことがたとえあったとしても、自分の気持ちや思いを、否定せずに大事にする。
“何もしなかった”ように見えるその中にも、あなた(相手)なりの静かなやさしさがあることも、きっとある。あれば、気づいてくる人がいなくても、相手のことを考えることができた自分を誇る。
全てがそうとは限らない、こういう考え方・見方もあるということ。※相手を尊重する話は大切だが、いじめ・危険・暴力が疑われる場面では「大人に相談する」が優先。
④ さらに深めたい視点:行動の奥にある“もうひとつのやさしさ”
- もしアヌーラが“もういいから行って”って言ったら、どうする?
-
先生へ:相手の気持ちも条件。
独りよがりを外す。問い返しの例
- 『もういい』って言われたら、どんな気持ちになる?
- 自分がつらいとき、『ひとりにしてほしい』って思ったことある?
- やさしさって、どんなふうに届けたらいいと思う?
支えようとする側の気持ちだけで動くのではなく、相手の気持ちや選びたいあり方を尊重することも、大切な『ともにいる』のかたち。
“やさしさ”が独りよがりにならないように、関係の中でどう寄り添えるかを考える。
去るも、寄り添うも、どちらも難しい選択。自分の状態と、相手の気持ちを見たうえで、“今、私はどうしたいか”を選ぶことができたら(去るも、寄り添うも)、それでいい。 - あの行動って、ゾウたちにとって“自然なこと”だったのかな?
-
問い返しの例
- ゾウが『やさしい気持ちで動けた』と思うのは、なぜ?
- ゾウの心はわからないよね、でも、ゾウの行動として自然だと思う?
動物に“気持ちがあるのか?”と考えること、“わからないものについて考える”ことは、とても大事なこと。
動物たちの行動を人間の気持ちに当てはめすぎず、『こうかもしれないな』と想像する力と、『本当の気持ちはわからないかもしれない』という姿勢を両方持つことが大切。
人同士でも、他人のことは、本当のところは分からない。
『きっとこう思ってる』『こういう人なんだ』と、決めつけてしまうこがある。
『相手のことは相手にしか分からない』と思えることも、立派なやさしさの形。
『そうかもしれないけど、違うかもしれない、だけど、わたしはこう思おう、あえて、こう思いたい。』──そんなふうに思いながら相手と関わっていけたら、きっとすごくやさしい世界がひろがる。
学年別:『ゾウのアヌーラ』を深めるための指導ポイント一覧
| 学年 | 主なねらい | 発問・問いかけ例 | 補足する伝え方の工夫 |
|---|---|---|---|
| 低学年(1~2年) | 『やさしいってうれしい』『自分もしたい』を育てる | どうしてゾウたちはアヌーラをささえたのかな? だれかに『ありがとう』って言ってもらったことある? | 『おねえちゃんだから』という立場からではなく、「近くにいたから」「大切だから」「気づいたから」という気持ちを肯定する 兄弟がいても、一人っ子でも、“だれかのことを大切だと思う気持ち”は同じ。 やさしさは立場で決まらず、そのときの気持ちと状況から出てくる。 安心できる環境の中でこそ、思いやりは自然に生まれる。 |
| 中学年(3~4年) | 気持ちの違いや背景を想像する力を育てる | アヌーラの話、野生だったらどうだったと思う? やさしくしなかったら、それはダメなこと? | 思いやりには“余裕”や“安心”という土台が必要なことを伝える。『そのときどんな気持ちだったんだろう?』という想像を促し、支えなかった選択にも意味があることに触れる。 |
| 高学年(5~6年) | 『行動の背景』『自己と他者の間の選択』を考える | 支える側のゾウたちは、つかれなかったのかな? ほめられたくてやさしくするのって、どう思う? | 助けることに上下関係はいらないという視点を伝える。『賞賛されたくてやさしくする』こともスタートとして肯定し、それが“分かちあいたい”思いやりへ育っていく可能性を考えさせる。 |
指導案
低学年は、「やさしい=うれしい」「ありがとう=うれしい」といった感情と行動のつながりを、経験として積み上げる時期である。ここが薄いと、学年が上がったときに言葉(理屈)は言えるが、行動としては結びつきにくい状態が起こりやすい。
したがって本単元では、評価・正解探しに寄せず、「うれしかった」「助かった」という実感を手がかりに、やさしさの芽を丁寧に育てる。
この学年で扱いすぎない軸:動機の分析(承認欲求など)、正しさの判定
この学年で扱う軸:うれしさ/安心/ありがとう
中学年は、他者の内面に意識が向き始め、「あの子もさみしかったのかも」「もしかして怒っていた?」など、相手の気持ちを想像する回路が育ち始める時期である。
ただし、その気づきは不安定で、すぐに安定した行動へ結びつくとは限らない。
だからこそ本単元では、「自分や他者の気持ちに気づく」「そのとき自分はどう感じたかを言葉にする」という感情の認知・言語化を中心に扱う。
また、マズローの段階は「分類を教える」のではなく、“気持ちには土台がある”ことに気づく補助線として、シンプルに導入。
図式化は、感じたことを整理するための道具として位置づける。
この学年で守る軸:「支えない=悪」を固定しない(裁きにしない)
この学年で扱う軸:気づき/事情の想像/状況で行動が変わる
高学年は、他者理解が深まり、「どう関わるか」「どう行動するか」を選択として考える力が育つ一方で、複数の視点が入ることで迷いや葛藤が生じやすい時期でもある。
したがって本単元では、マズローをより明確な補助線として用いながら、「自分の内面をふり返る」「行動の背景(見えない土台)から考える」「どうしたいかを自分の意思で選ぶ」という内省と判断の基盤を育てる。
ここで重要なのは、やさしさを「善行を続けろ」にしないことである。支える側の境界線(疲れ・限界・分担・休む)を扱い、“どう支えるかを選ぶ”という視点に着地させる。
この学年での着地:「誰が助かった?次もやる?」(承認ゲー化を止める)
この学年で扱う軸:動機と結果のズレ/境界線/選ぶ力
- 低学年向け:マズローの欲求5段階(語りかけ補強版)
- 中学年向け:マズローの欲求5段階(気づき育成版)
- 高学年向け:マズローの欲求5段階(内省強化版)
① 低学年向け:マズローの欲求5段階(語りかけ補強版)
| 欲求段階 | 子ども向けの例と問い | メッセージ |
|---|---|---|
| ①からだが元気(生理的欲求) | 『おなかがすいてたら、やさしくできる?』 『ねむいとき、ひとのこと考えられる?』 | 自分がしんどいとき、やさしさは出しにくい |
| ②こわくない(安全の欲求) | 『まわりがこわかったら、ひとにやさしくできる?』 | 安心してると、人のことにも気づける |
| ③なかまやつながり(所属の欲求) | 『友だちがいると、どんな気もち?』 『やさしくされたとき、どう思う?』 | つながりがあると、やさしさは循環する |
| ④ほめてもらう(尊重(承認)の欲求) | 『ありがとうって言われたら、うれしくなる?』 『ほめられたいから、やさしくするってどう思う?』 | 「ほめられたい」を否定しない 気づかせるだけで、評価しない 出てきた“うれしさ”に気づかせる |
| ⑤じぶんらしく動く(自己実現) | 『自分からやさしくしたくなったことある?』 | “やさしさ=自分らしさ”であっていい やらされ感を外す |
| ⑥だれかのために動きたい(自己超越) | 『だれかのために、がんばりたいって思ったことある?』 『“この子のために”って動いたことある?』 | “自己超越”は言わない “人のためになった、うれしい” の感覚を拾う 難しい子がいて当然。 |
⑥は、むずかしい子がいて当然、“えらさ”じゃない、広がりの話。
できない日があって当然。
でも、「自分のやさしさが、だれかの役に立った」って感じたとき、うれしくなることはある。
その“うれしさ”が、やさしさが広がっていく入り口になる。
例:関係・立場・やさしさ
| 欲求段階 | 子どもへの問いかけ | メッセージ(ねらい) |
|---|---|---|
| 立場と期待 | 『「〜だからやって」って言われたら、どんな気持ち?』 (例:おねえちゃんだから/男の子だから/年上だから/しっかり者だから…) | やさしさは“立場”で決まらない |
| 関係性と思い | 『友達ってどんなときに大切って思う?』 | 大切だからやさしくしたい=“思い”が出発点 |
| 自分の気持ちの尊重 | 『いまはムリって言いたくなるときある?』 | 無理なときは、今は無理だと伝えていい、自分を大事にすること |
| やさしさとよろこび | 『やさしくして“ありがとう”って言われたらどんな気持ち?』 | ありがとうがうれしいのは自然 それが目的になると苦しくなることもある 大事なのは「相手が助かったか」 ありがとうがなくても、助かったならOK |
| 上下じゃない“支え合い” | 『助けるって、えらい人だけがすること?』 | やさしさに上下はない。気持ちが動いたらそれでOK |
| 助け合い | 『友達が困ってるとき、“何かできないかな”って思ったことある?』 『そのとき、自分も力になれた気がした?』 | 『やさしさ=相手のため』だけじゃなく、『その行動が自分の喜びにもなる』という感覚を育てる。やさしさが自分と誰かの“橋”になることを知る。 |
② 中学年向け:マズローの欲求5段階(気づき育成版)
| 欲求段階 | 子ども向けの問い | メッセージ(ねらい) |
|---|---|---|
| ① からだが元気(生理的欲求) | 『おなかがすいていたら、イライラしやすくなる?』『ねむいと、友だちの話ってちゃんと聞ける?』 | 自分のコンディションが、まわりへの接し方に影響することを実感する。まずは自分を整えることの大切さ。 |
| ② こわくない(安全の欲求) | 『こわいって思うとき、どうしたくなる?』『安心してるときって、どんなことができる?』 | 安心感があるからこそ、まわりにやさしくできる。安全が行動の土台になることに気づく。 |
| ③ なかま・つながり(所属の欲求) | 『“だれかが見てくれてる”って感じるときってある?』『ひとりじゃないって、どう感じる?』 | つながりは、安心やがんばる気持ちにつながる。『誰かがいること』の意味を考える。 |
| ④ ほめられる・認められる(尊重(承認)の欲求) | 『“ありがとう”って言われたとき、どんな気持ち?』 『ありがとうがなくても、“相手が助かった”なら、それはやさしさ?』 | ありがとうがうれしいのは自然。 でも、「ほめられること」が目的になると苦しくなることもある。 だから、いったん真ん中を「相手が助かったか」に戻す。 その上で、自分の動機にも気づけるようになる。 |
| ⑤ じぶんらしく動く(自己実現) | 『友だちのために“自分から動いた”ことある?』 | 他人の目線でなく、自分の価値観や意思で動くという“自分軸”の育成へ。行動に自分らしさを込める。 |
| ⑥ 誰かのために動けたとき(自己超越) | 『“この子のために動きたい”って思ったことある?』 『それができたとき、自分の気もちってどうだった?』 | 『自分のため』ではなく、『誰かのために』行動した経験をふりかえることで、やさしさの広がりに気づく。行動の動機が“外側”に向かうことで、自分のやさしさに誇りをもてる段階へ。 |
③ 高学年向け:マズローの欲求5段階(内省強化版)
| 欲求段階 | 子ども向けの問い | メッセージ(ねらい) |
|---|---|---|
| ① 生理的欲求(からだが元気) | 『体調が悪いとき、人にやさしくする余裕ある?』 | 自分が満たされていないと、他者に意識を向けるのは難しい |
| ② 安全の欲求(こわくない) | 『まわりにこわい人がいたら、やさしさって出せる?』 『“大丈夫”って思えるとき、どんな行動ができる?』 | 安心感は、行動のベースになる。やさしさも“安全地帯”から |
| ③ 所属の欲求(なかま・つながり) | 『仲間がいるときの自分と、ひとりのときの自分、行動は変わる?』 『“この人たちの中なら言える”って思うのはどんなとき?』 | つながりは、行動を支える土台。安心できる関係があると、自分も相手も見えるようになる |
| ④尊重(承認)の欲求(ほめられる) | 『ほめられたくて、やさしくしたことある?それってダメだと思う?』 『ほめられなくても、次もやる?やるなら何が理由?』 | 承認欲求は自然。否定しない。ただし“ほめられる”をゴールにすると歪む。基準を「相手が助かったか/自分が納得しているか」に戻す |
| ⑤ 自己実現(じぶんらしく動く) | 『やさしくしたい気持ちと、無理って気持ちが両方あるとき、どう決める?』 『“やさしさ”と“我慢”のちがいって何だと思う?』 | “してあげる”ではなく、“自分で選んだ”やさしさへ。自分の境界線を守りながら関わる力を育てる。 |
| ⑥ 自己超越(だれか・社会のために動く) | 『自分のためじゃなくて、だれかやみんなのために行動したことある?』 『それができたとき、自分ってどう感じた?』 | やさしさが『自分の外』へと広がっていく段階。自分の行動がだれかを助け、世界とつながっていく感覚を育てる。『してあげる』ではなく『ともにある』やさしさへ。 |
承認→自己実現の流れは、『評価される自分』から『意味を感じる自分』への移行。
『やらなきゃ』から『やりたい』へ。
賞賛された嬉しさは“きっかけ”であり、“ゴール”ではない。
マズローの欲求段階と問いの対応表(小学1〜6年対応)
| 欲求段階(下から順) | 概要 | 子ども向けの問い | 補足:ねらいと伝え方 |
|---|---|---|---|
| ①② 生理的欲求・安全の欲求 | 『じぶんが元気でいる』『こわくない』が大前提 | タカコとガチャコは、なんで支えられたの?/こわい動物がいたら、どうしてた? | 安心できる環境だからこそ、やさしさが行動になる 無理なときは「休む」「大人に言う」「助けを呼ぶ」も選択肢だと伝える |
| ③ 所属と愛の欲求 | 仲間でいたい、つながっていたい気持ち | アヌーラは、ひとりじゃなかったね。どう思った?/だれかがそばにいるって、どんな気持ち? | 支え合う関係性の価値を感じ取る 自分も誰かとつながっていたいという感覚を育てる |
| ④ 尊重(承認)欲求 | 『ありがとう』と言われたい、認められたい | ほめられたくてやさしくするのって、どう思う?/『ありがとう』って言われたとき、どんな気持ち?/ほめられなくても、次もやる?やるなら何が理由? | 賞賛されたい気持ちは否定しない、けどゴールにしない 基準を「相手が助かったか」「自分が納得したか」に戻す導線を入れる |
| ⑤ 自己実現欲求 | 『自分らしさ』でやさしさを行動にする | 自分にできそうな“やさしさ”ってなんだろう?/やさしくしたい気持ちと、ムリって気持ちが両方あるとき、どう決める? | 自分ができるやさしさを考え、実践につなげる 「自分で選ぶ」「境界線を守る」を含めて主体性を育てる |
| ⑥ 超越的欲求 (貢献・分かち合い) | 自分の幸せを他者にも広げたいという願い | 自分が幸せだったら、その気持ち、だれかにわけたくなる?/みんながやさしくできたら、どんな世界? | 『やさしさを社会に広げる』未来の問い 分かち合いが“循環”になる感覚を育てる ※難しい子がいて当然 |
- マズロー自己理解ワークシート案(低学年1・2年)
- マズロー自己理解ワークシート案(中学年~高学年)
- マズロー自己理解ワークシート案(中学年~高学年)レベル高
- マズローの5段階は年齢による知識差よりも、経験や実感の差で理解が深まる
① マズロー自己理解ワークシート案(低学年1・2年)
①【おなかがすいてた・ねむかったとき】
『おなかがすいてた』『つかれてた』そんなとき、どんな気持ちだった?
そのとき、人にやさしくできたかな?できなかったかな?
- イライラした
- ぼーっとしてた
- やさしくできなかった
- それでもちょっとがんばれた
どんなことがあった?書いてみよう:
②【あんしんできたとき】
だれかがそばにいてくれるとき、心強くなれることない?
そのとき、いつもよりも勇気がだせるような感じがしない?そんなこと、ある?
あるなら、どんなことができた?
- 自分から『どうしたの?』ってきけた
- そばにいることができた
- 力になりたいと思えた
そのときのことを思い出して書いてみよう:
③【“ともだち”って思えたとき】
『この人といると、ほっとする』『いっしょにいると、たのしい』そんな友だち、いる?
その子とどんなことをしたとき、うれしかった?たのしかった?
思い出したことをかいてみよう:
④【『ありがとう』って言われたとき】
『すごいね』『ありがとう』って言ってもらえたとき、どんな気もちだった?
- またやってみたいと思った
- ちょっとはずかしかったけど、うれしかった
どんなときだった?どんなことをした?:
⑤【やさしくしたときの気もち】
『ほめられたかったから、やさしくした』ってことある?
それって、ダメかな?どんな気もちだった?
※ここは“いい・わるい”を決めるところじゃないよ。自分の気もちを見つけるところ
- うれしかった
- はずかしかった
- ちょっとモヤっとした
- なんとも言えなかった
もし、ほめられなくても…それでも次もやる?やるなら、なんで?
(例:相手が助かったから/自分がそうしたかったから/自分も気分がよくなったから)
かんがえてみよう:
⑥【『自分からやさしくした』こと】
だれにも言われなかったけど、『力になりたい』と思って動いたこと、ある?
- 小さい子のお手伝いをした
- おちこんでいるともだちに声をかけた
- 『こうしたいな』って思ってうごいた
※できない日があってもOK
「いまはむずかしい」って気づけるのも、大事なこと
そのときの気持ちをかいてみよう:
② マズロー自己理解ワークシート案(中学年~高学年)
正しい答えはありません。
思い出すこと、自分の気もちを見つけることが大切です。
書けない項目があっても大丈夫。
「初めて考えた」も立派な答えです。
① 自分に余裕がなかったとき
おなかがすいていたり、つかれていたりして、気もちに余裕がなかったとき、自分はどんなふうにふるまってた?
あてはまることに〇をつけてね
- イライラして人にきつく言ってしまった
- あんまりまわりのことを気にできなかった
- 無理にがんばって、あとでつかれた
- 少しだけ人にやさしくできた
- いつも通りにふるまおうとした(中はしんどかった)
そのときのことをふりかえって書いてみよう(できるところだけでOK)
いつ/どこで:
どんな気もち:
何が一番しんどかった:
② 安心できているときにできたこと
安心できるときって、心の中に“余裕”があるよね。そういうとき、自分はどんな行動ができると思う?
あてはまることに〇をつけてね。
- まわりの人のことに気づけた
- 自分から声をかけることができた
- 失敗をおそれずに動けた
- 『だいじょうぶ』って思えたから行動できた
思い出したできごとを書いてみよう
どんな安心があった?(場所/人/空気):
その結果できたこと:
③ つながり”を感じたとき
『一人じゃない』『仲間がいる』って感じたとき、どんな気もちになった?
それは、どんな場面だった?
どんなときにそう思ったことある?あてはまることに〇をつけてね。
- 困ったときに手伝ってもらえた
- だれかと目標に向かってがんばった
- 自分のことをわかってくれた
- いっしょにいて、ほっとした
- 役に立てた気がした
そのときのことを、できるだけ思い出して書いてみよう
どんな場面:
そのときの気もち:
④『ありがとう』や『すごいね』と言われたとき
やさしくしたあと、『ありがとう』って言われたとき、どんな気もちがした?
その気もちの理由も、すこし考えてみよう。
気もちとして近いものに〇をつけてね。
- うれしかった
- 自分でも『よかった』と思えた
- まただれかにやさしくしたいと思った
- ちょっと気まずかったけど、うれしかった
- うれしいより、ホッとした
そのできごと・気もち・理由を書いてみよう(わかる範囲でOK)
どんなことをした:
うれしかった理由(例:見てもらえた/役に立てた/安心した):
⑤ やさしさのうらにある気もち(※裁き禁止)
ここは「よい/わるい」を決める場所ではありません。
「自分の気もち」を見つける場所です。
『ほめられたくて、やさしくしたことがある』って思う?
それって、いいこと?悪いこと?どう考える?
あてはまる気もちに〇をつけてね(いくつでもOK)。
- ほめられたくてがんばった
- だれかに見ててほしかった
- 『いい子だな』って思われたかった
- それでも、やってよかったと思ってる
- ほめられたいという気もちを、今まで考えたことがなかった
- ほめられなくても、やると思う
- ほめられなかったら、やらないかもしれない(正直にOK)
★大事な問い(ここだけは書けたら強い)
「ほめられたい」が出たとき、何が“本当はほしかった”んだと思う?
(例:安心/つながり/わかってほしい/自信/さみしさなど)
自分の中の気もちを言葉にしてみよう
本当はほしかったもの:
そう思った理由:
⑥ 自分からやさしく動けたとき
だれにも言われなかったけど、『自分の中の気もち』で動けたとき、ある?
あてはまるものに〇をつけてね。
- 『こうしたい』と思って行動した
- 力になれたことがうれしかった
- まわりには気づかれなかったけど、自分では納得してた
- あえて何も言わなかった(その方がいいと思った)
- 自分の気もちは出さなかったけど、あとでしんどくなった
しんどくなった人だけ↓
- どうして“しんどくなった”と思う?:
- 次はどうしたら少し楽かも?:
そのとき、“こういう自分でいたい”って思えた?:
⑦ ふりかえりミニ問い(任意)
- 『やさしさ』って、どんなかたちがあると思う?
- 自分にとって、いちばん『自分らしいやさしさ』ってどんなもの?
自由に書いてみよう:
③ マズロー自己理解ワークシート案(中学年~高学年)レベル高
ここは単独配布だと書けない子が出るので、「選択式ワークが書けた子の追加プリント」にする。
つまり、②=全員用、③コレ=伸びる子用。
①【自分に余裕がなかったとき】
たとえば『おなかがすいてた』『つかれてた』
……そんなとき、自分は人にやさしくできたかな?できなかった?
『できなかった経験』も書いてみよう。
自分の経験:
②【安心できているときにできたこと】
安心しているとき、自分はどんなことができた?
たとえば『自分から話しかけられた』『“どうしたの?”って聞けた』など
どんなときに、そんなふうに行動できたかな?
安心できたとき・できたこと:
③【仲間を感じたとき】
『この人といると、ほっとする』
『役に立ててうれしかった』そんな経験ある?
どんなときに“仲間”って思えた?
仲間を感じたエピソード:
④【ほめられてうれしかったとき】
『ありがとう』『すごいね』って言われたとき、どんな気持ちだった?
なぜ、ほめられてうれしかったと思う?
どんなとき?どんな気持ち?/うれしかった理由:
⑤【ほめられたくてやさしくしたことはある?】
ここは「よい/わるい」を決める場所ではありません。
「自分の気もち」を見つける場所です。
『ほめられたかったから、やさしくした』って思ったことある?
そのとき、どうして“ほめられたい”って思ったのかな?
理由を考えてみよう:
⑥【自分からやさしく動けたとき】
『こうしたい』と思って動いたとき、自分はどんな気持ちだった?
自分からやさしくした経験:
マズローの5段階は年齢による知識差よりも、経験や実感の差で理解が深まる
マズローの欲求段階は、年齢による“知識量”の差よりも、経験の量・実感の深さで理解が育つ。
だから、問いは学年で変える必要はない。
変えるべきは、書かせ方と話し合い方。
同じ問いでも、低学年は「できごと」を中心に、
高学年は「理由」「背景」「条件」「自分の選択」へと、答えの厚みが自然に変わっていく。
- 問いを共通化するメリット
- このワークが「難しい」と感じられることがある
- 運用上の注意
① 問いを共通化するメリット
問いを学年で共通にすると、子どもは自分の変化に気づける。
- 去年と同じ問いなのに、答えが違う
- 同じ経験を、別の言葉で説明できる
- 「気持ち」だけでなく「条件」まで見えるようになる
これは、自己理解(内省)を育てるだけでなく、
他者を決めつけない視点(非認知的な力)にもつながりやすい。
② このワークが「難しい」と感じられることがある
このワークは、子どもよりむしろ大人が「難しい」と感じる場合があります。
理由は、問いが“正解探し”ではなく、自分の状態・背景・選択に触れる問いだからです。
なぜ難しいのか?3つの理由
① 経験を“感情ベース”で振り返ること自体が、訓練されていない
多くの人は「何をしたか(行動)」は語れても、「そのときどう感じたか(感情)」を言葉にする経験が少ない。
特に「なぜうれしかったか」「なぜそれが自分らしかったか」まで問われると、言葉が止まりやすい。
② 『やさしさ』は主観的で、定義が難しい
人によって「やさしさ」の基準が違う。
「そっとしておくのがやさしさ」だと思う人もいれば、「声をかけるのがやさしさ」だと思う人もいる。
だからこそ、「自分らしいやさしさ」を自覚するのは大人でも難しく、内省力が要る。
③ 『素直に語る』ことにブレーキがかかる
とくに大人は、周囲を意識して「正解っぽい答え」「かっこいい答え」を出そうとしやすい。
でもこのワークは、“素の自分”の感情や行動に向き合う設計なので、怖い・照れる・深すぎると感じる人もいる。
③ 運用上の注意
- 書けない項目があってOK(書けない=未熟ではない。今は言葉になっていないだけ)
- 語らせすぎない(無理に深掘りしない/本人のペース優先)
- 先生は“答え”を言わず、問いを維持する(正解の台本化を防ぐ)
- ねらいは「いい子にする」ではなく、自分の状態と行動の関係に気づくこと
問いは共通。
成長は、答えに出る。
この設計なら、毎年ふり返るほど「自分の変化」が見える教材になる。


この教材に内在するフレーム
目的:思想を教えるためではなく、問いを「善悪ジャッジ」や「正解の台本」にしないための補助線
原則:授業で思想名を出さなくてよい。必要なのは、問いの運用(戻し方・守り方)
| 思想・理論 | 文化圏 | 教材での活用(先生の手の動き) | キーワード/ねらい |
|---|---|---|---|
| 無為自然 | 東洋 | 「支えなかった=悪」を外す/“やさしさは義務ではない”へ戻す | やさしさは湧き出るもの/自然な行動として肯定 |
| 縁起(仏教) | 東洋 | 行動を“個人の性格”で断定せず、関係性・状況・条件へ視点を移す | つながり/今できないも未来につながる/条件の連鎖 |
| アドラー心理学 | 西洋 | 「ほめられたい」などの動機を裁かず、成長の入口として扱う | 承認欲求の肯定→自尊心へ/動機より“次の選び方” |
| 現象学的アプローチ | 西洋 | 正解探しを止め、実感(そのとき何を感じたか)を丁寧に拾う | 体験から立ち上げる/感情をそのまま言語化 |
| マズローの欲求段階 | 西洋 | “やさしさ=心のきれいさ”ではなく、土台(余裕×環境)で説明する | 思いやり=心の余裕×環境条件/段階の可視化 |
| スピノザ的視点 (感情の理解) | 西洋 | 「その反応には理由がある」へ置き直し、自己受容と他者理解へつなぐ | 感情は理解の対象/やさしくできないも否定しない |
道徳補強教材について
※只今、製作中
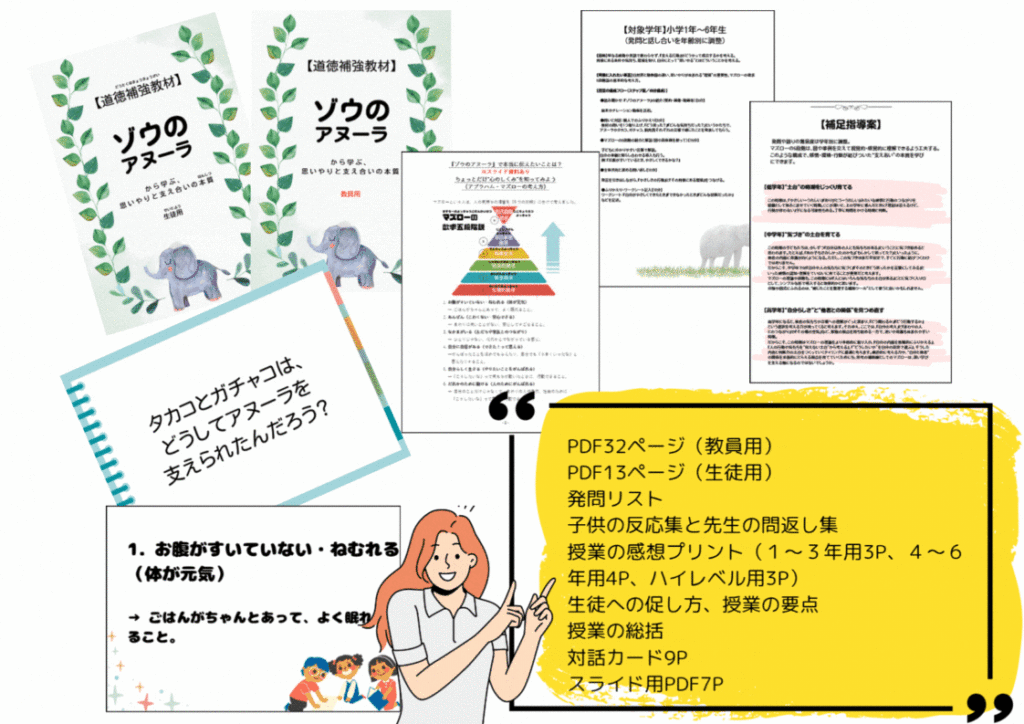
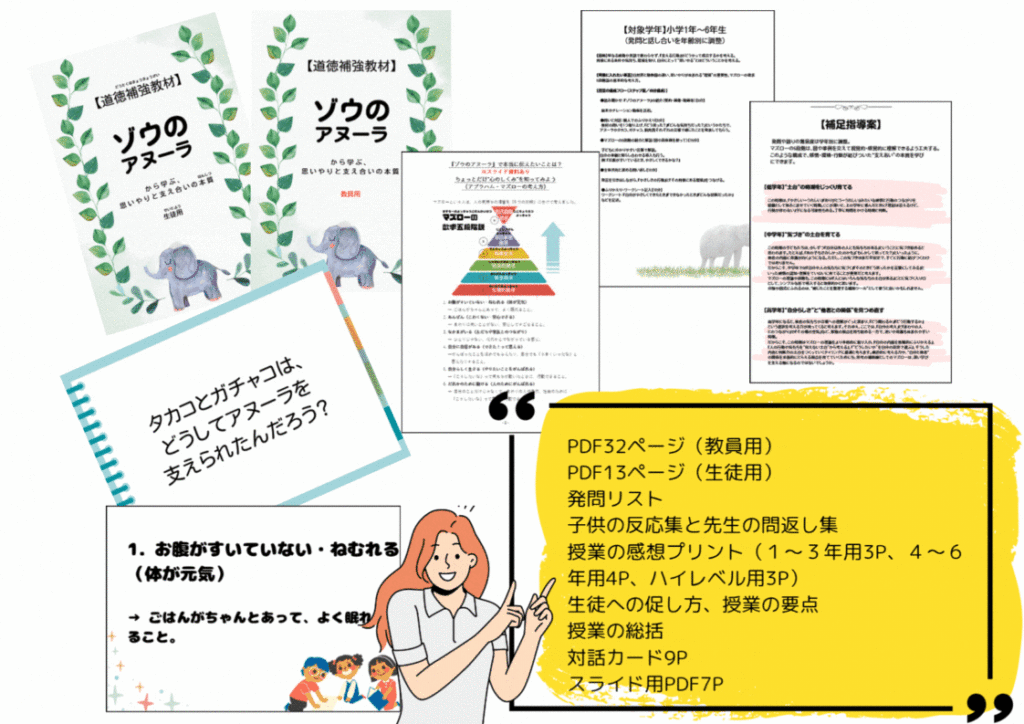

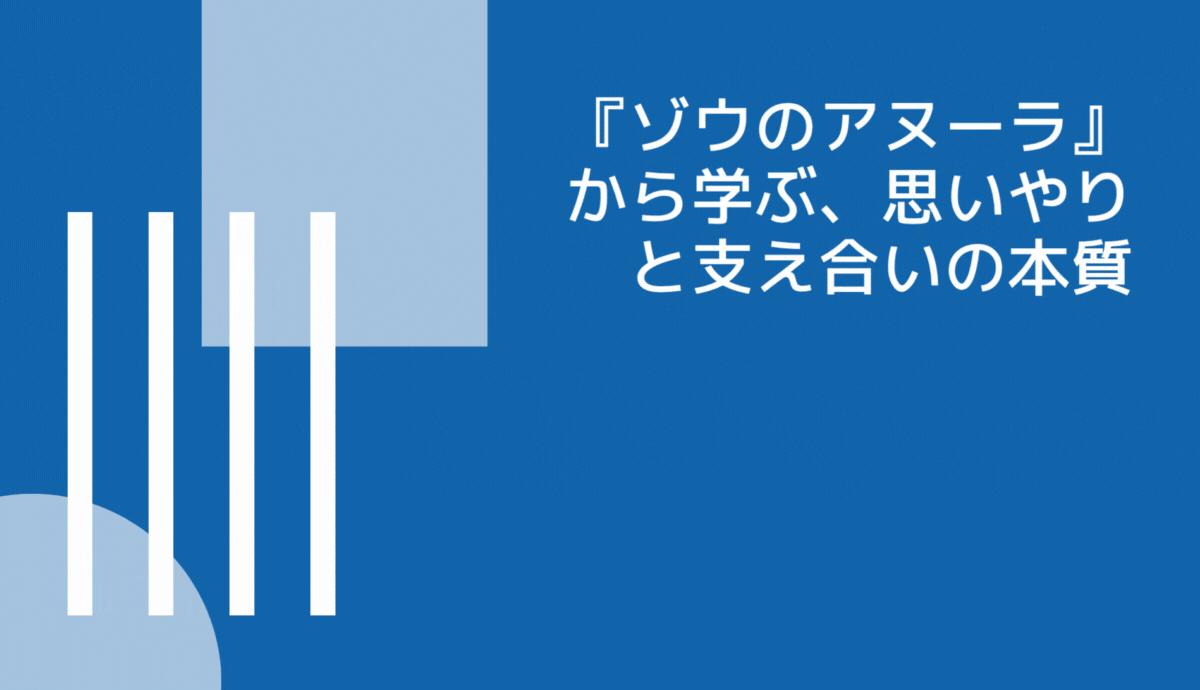
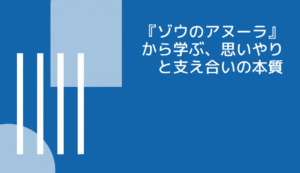
コメント