他者貢献と自己犠牲の違いってわかりますか?
この2つ、境界線があいまいなんですよね。
うっかりすると自己犠牲になっていることがある。
本当の意味での他者貢献は、自身の幸せも追求しながら、周りの人々の幸せにも寄与することができます。
いつもストレスをため込んで愚痴ってしまう、悩んでしまうという方、他者貢献のつもりが、いつの間にか自己犠牲になっていませんか?
そういう方は、感情へのアプローチを考えてみてください。
他者貢献ができるようになれば、世の中で最も成功しやすいタイプである『他者思考型ギバー(他者志向型ギバー)』への転身ができるから。

健全な他者貢献のあり方を知れば、自己を犠牲にすることはなくなり、生きやすく、人生での成功を手にすることができます。
このブログでは、他者貢献と自己犠牲の違い、自己犠牲から他者貢献に変える方法についてまとめてみました。
他者貢献と自己犠牲の違いとは?本当の意味を理解しておく
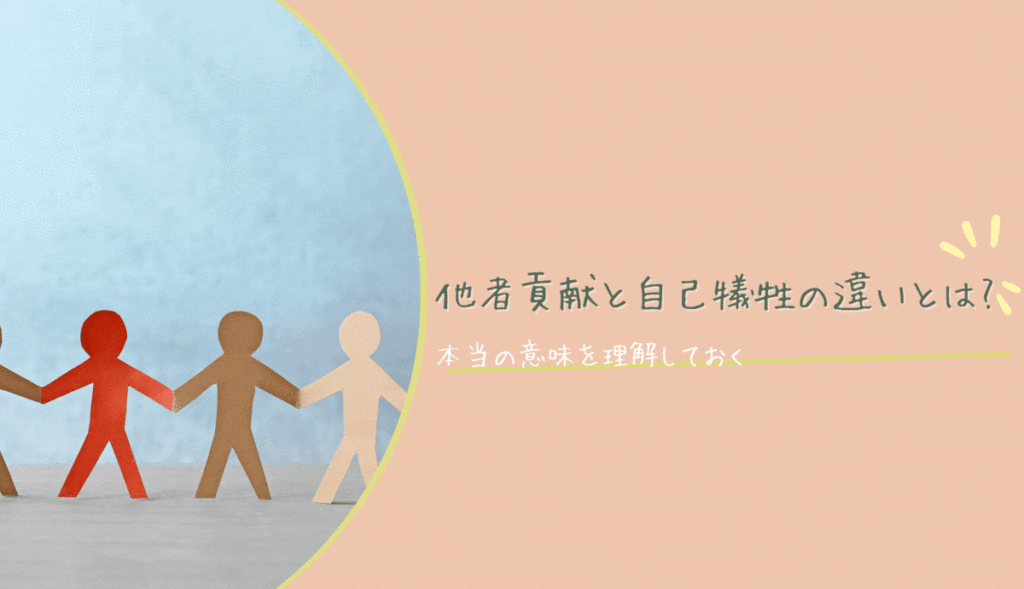
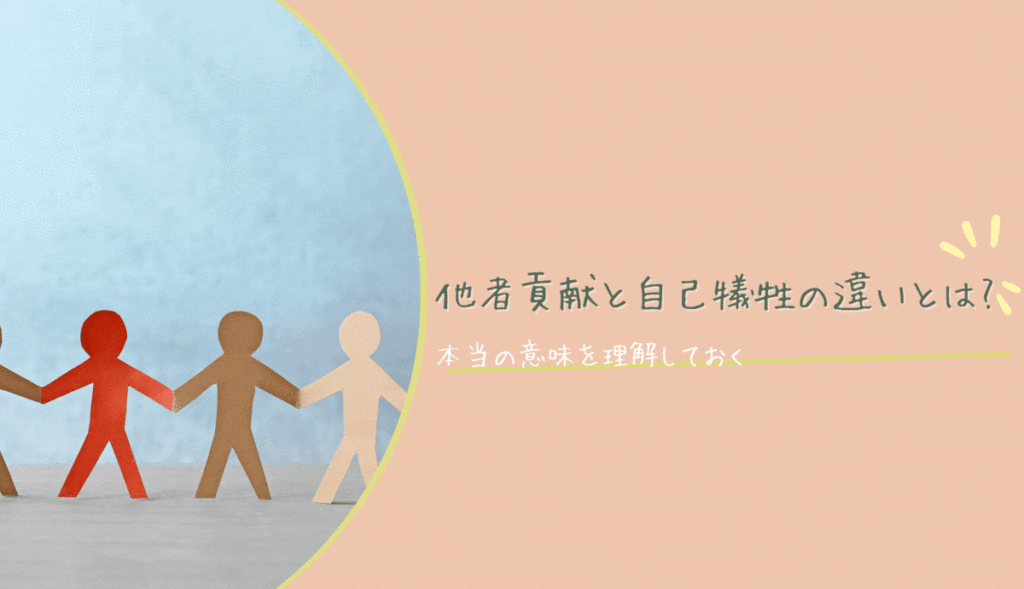
他者のために行動することには、喜びや満足感をもたらす一方で、いつの間にか、そして時には、自己を犠牲にする行動へと変わることがあります。
この2つの概念は非常に似通っていますが、実際には本質的に異なるもの。



この違いを理解することは、私たちのメンタルヘルス、人間関係の質の向上、人生の成功においてとても重要。ここでは、他者貢献と自己犠牲の本質的な違いについて深掘りしてみます。
- 他者貢献とは何か?
- 自己犠牲の定義と影響
- 感情と意図の違い
- 意識のシフトを促す
①他者貢献とは何か?
他者貢献は、他人の幸福を願い、助け合う行動のこと。
この行動は、他者のために行動することが自身の喜びや満足感につながるものであり、自身にも周りにもポジティブなエネルギーを生み出す。
つまり、WINWINの法則が成り立つ。
例えば、友達が困っているときに助けるとか、これは心からの思いやりから生じるもので、助け合うことにより互いに充実感を得ることができる。
②自己犠牲の定義と影響
一方、自己犠牲は自分自身を犠牲にして他者を助ける行動を指します。
この行動は自己を軽視するものであり、義務感やプレッシャーによってされることが多いです。



自己を軽視していることに自分で気が付いていればいいんですが、気が付いてないことがある。これが非常に厄介。どういうことかと言うと、他人の幸福を願うその行為が自己犠牲になっていることがあるからです。
たとえば、他者の要求に応えるために自分の時間やエネルギーを使い果たすことは、自己犠牲の典型。
他人の幸福を願うその行為が自己犠牲になっている場合は、そのことに最初は気が付かないことがあります。それが自分の喜びだと錯覚しているとき、その錯覚には一生気が付かないかもしれないし、生きて行く途中で気づかされることもある。
結果として、自己犠牲的な行為は心の疲労やストレスを引き起こし、持続的な不満につながることがあります。
③感情と意図の違い
他者貢献と自己犠牲を区別する鍵となるのは、それぞれの背後にある感情や意図です。
感情や意図を自分の中で明確にしておく必要がある。
心から『やりたい』と感じている行動は他者貢献であり、他人の期待や評価に押されて行動する際は自己犠牲と考えられます。
この自己犠牲に、人は気が付きにくい。
この他人の期待や評価に押されて行動することに喜びを感じ、自らそれを『やりたい』と感じているときは、自身の持っているパラダイムに気が付いた方がいいかもしれません。



常に自身の行動が他人ありきである事実に。
けど、それが幸せなら、それでいいと思いますけどね。
それがその人の喜びであるなら、否定はできません。
他者のために手助けをして、満足感を得られるならば、それは他者貢献の表れであり、プレッシャーや義務感を強く感じる場合は、自己犠牲でしょう。
④意識のシフトを促す
自己犠牲から他者貢献へと意識を変えるためには、自分の内面の感情にしっかり向き合うことが大事。
自らが選んだ行動が、自分の幸福にもつながると考えられれば、より良い人間関係を育むことができるでしょう。このような意識の変化は、メンタルヘルスを向上させ、良い相互関係を築きやすくなります。



他者貢献と自己犠牲の違いを自分の中で明確に理解することは、心の状態を守り、良好な関係を築くための重要なステップ。自分の感情に敏感になり、意義ある行動を選択することを心掛けることに意味がある。
とは言うけど、自分だってやりたくないって言いたい、けど、やらないといけないんだ。



だから?決めたのは自分でしょう?そこに他責はあり得ない。どんな事情があるにせよ、決断したのは自分なんです。
もっと言うと、やらないといけないと思っている時点で、そうしたいんですよ。なら、それでいいじゃないですか。
自己犠牲から脱却する方法※誰が決めた行動か?すべては自責であること
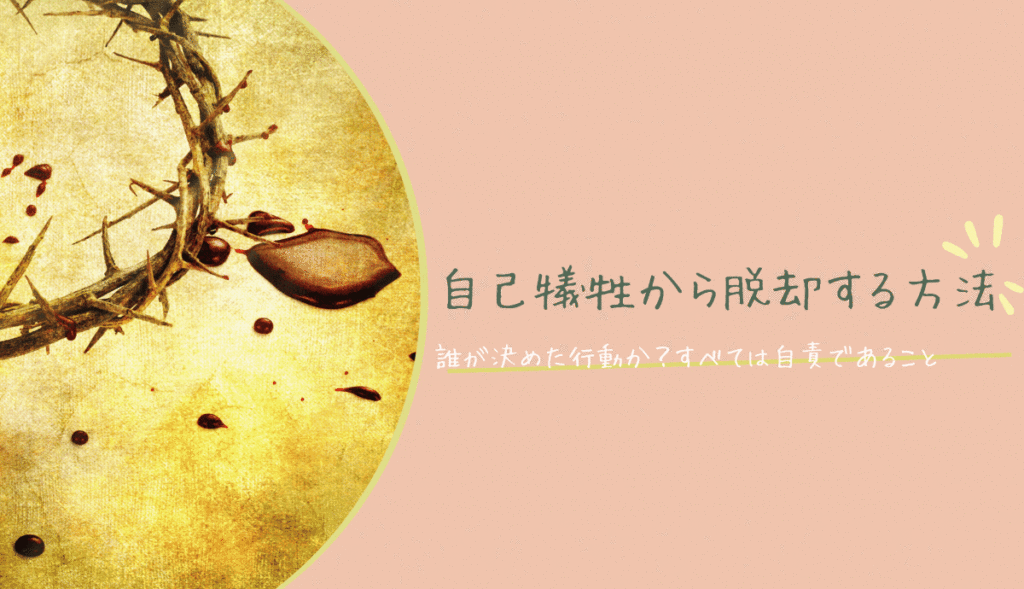
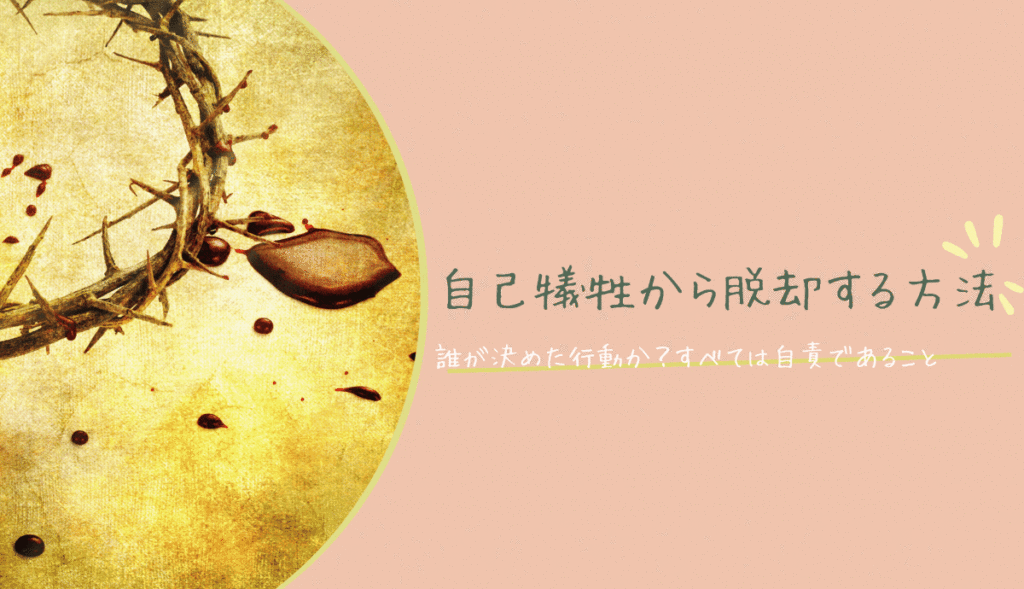
自己犠牲から解放されるための重要なステップは、相手への見返りを求めないという姿勢を持つことです。
相手への期待を求めない記事は『魔女の宅急便』↓に書いています。
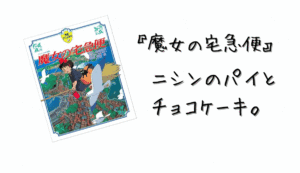
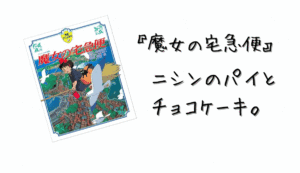
課題の分離についての記事はこちら↓


このマインドセットで、他者への貢献が自身の内面的な充実をもたらし、心の負担が軽減されて行きます。



具体的にどのようにこの考え方を根付かせるか、ちょっと見ていきます。
- 自身の動機を再考する
- 行動の楽しみを見出す
- 期待を手放す
- 自身の感情を理解する
①自身の動機を再考する
実はこれが一番大事で、まず、自らの行動の背景にある動機を見つめ直すことが大切です。
『誰かのために行動する』という発想ではなくて、『自分がしたいから行動する』と意識を変えることがポイント。
この考え方の転換が、自己犠牲からの解放につながって行く。
例えば、友人を助けたくなる場合、『友人が困っているから手を差し伸べる』と考えるのではなくて『わたしが助けたいから助ける』と、こう思えるかが大事。
じゃないと、お礼求めちゃうから。自己犠牲感あって。



助けるって決めたのはだぁれ?



自分でしょ?
お礼を言うかどうかは、相手の課題だから。相手が自分の課題を全うするかどうかは、あなたには関係ないことなんです。
例えば、極端な話、助けて罵倒されるとか、暴力とか理不尽なことがあったとしても、ですよ。無いと思いますけどこうなる。



助けるって決めたのはだぁれ?



自分でしょ?
友人でなくても、家族でも同じ。『わたしが助けたいから助ける』という意識を持てないのなら、助けられませんよ。そう思えないことから生じる結果は『自己犠牲』しかあり得ない。
こんな風に意識を変えることで、行動が純粋なサポートになり、見返りを期待せずに済みますよね?
わたしはこうしてます。覚悟ができるから。
②行動の楽しみを見出す
次に、他者のために何かをする過程を楽しめたら十分。
行動の瞬間に目を向け、それ自体に喜びを感じることができれば、結果についての期待感や見返りを意識せずに済みますしね。
要するに、行動するときの感情は大事。
例えば、何かの活動に参加するとき『その瞬間を楽しむ努力を、、!』なんて言う人もいるじゃないですか。楽しもうとする努力自体がもう違いますからね。そう思えなければ、思わなくてもいいんです。
意識の転換は大事かもしれません。
楽しめない自分がいるなら、考え方を『参加することで得られるメリットは?』こう変えて見る手もある。要するにテイカー思考。


すると、行きたくなかった活動にも、メリットがあれば前向きに参加できるじゃないですか。
こうやって、都度自分に向き合って行くことが大事で、そうすることで自己犠牲感を無くすことができます。
逆に、その動機すらも見出すことができなければ、参加しない選択が大事。
③期待を手放す
他者へ貢献しながらも、どうしても抱いてしまうのが『期待』という感情。
『この行動をすれば感謝されるだろう、変わってくれるだろう』という期待は、不満を引き起こす原因にしかならない。



幻想、そして夢。
期待を手放す姿勢が大事ですが、夢から覚めない選択をするのも否定はしませんけどね。それを決めるのもあなた次第。
世の中には、人に構われたくて、困った行動をわざと取る人もいるんですよ。そういう思考回路。だから、もし、助けたい人の状況が、あなたの目に悲惨に見えたとき、不憫に思えたとしたら、あなたが不憫と思っている人の勝利、つまりはあなたの負け。だって、構ってもらえるでしょう?それでも、あなたの目から不憫に見える人を、助けると決めたのはあなた、になる。だから、期待はしちゃダメなんです。
もっと言うなら、構うほどに、困った行動は増えるという法則も成り立ってくる。だって、もっともっと構ってもらえるから。だから、覚悟が必要。人に与え、助けるということは、こういうことを知っておかないといけない。
『1+1=2』ですよ。
『無知の知』、知らないことすら知らない、不憫に見えるその人も、助ける側の人も。ですよ。なぜそうなっているのかを、知らない。



こんなつもりじゃ、、、、なんて無い。わたしなら、ここまで読み切る。そして決断をするから、決断後は迷わない。選択とはこういうことですよ。
期待なしで行動することで、人間関係も円滑になります。行動の結果に対する反応がなかったとしても、『自分で決めたことだし』と考えることで、無意味なストレスから解放されます。
ようするに『自責』ですよね。



皆、自分で決めたこと。これがすっぽり頭から抜けるんですよ。だから他責になり、期待した分が悲しみや怒りになって自分から解放される。悪循環でしょう?何ごとにも覚悟は必要だと思います。
④自身の感情を理解する
自己犠牲からの自由を手に入れるためには、自らの感情を理解し、確認することも大事。
もし『見返りを求めている』と感じれば、その感情を認識することが自分を見つめ直すキッカケになります。
見返りを期待する自分がいて、その自分にとって何が大切か?を考えることは大事かもしれませんが、見返りを求めてしまっている自分がいることに気づくだけで十分なんですよ。
皆、気が付かないんだから。ずっと見返りを求めて樹海の森を彷徨うんだから。



見返りの対象人物がコロコロ変わるだけ、親、上司、先生、友人、彷徨う、彷徨う、ずっと彷徨う。そういう人生になる。そのことすら知らないの(気づかないの)。
自分自身の感情や思考を大事にしつつ、他者貢献を楽しむことができれば、結果として自分も満たされます。
他者貢献の心得※自分のためにやる重要性


- 自分を満たす行動の意義
- 自己犠牲の落とし穴
- ネガティブな感情を避けるために心掛けること
- 他者貢献は自己成長のチャンス
- 自分軸の重要性
①自分を満たす行動の意義
他者貢献とは相手を喜ばせるための行動である一方で、実は自分自身を満たすための行動でもあります。
自身が心からやりたいと思えることを通じて他者への貢献が生まれたときに、それが真の充実感に変わる。
この感情を大切にすることで、他者を助ける行為が自分にとっての幸福につながっていることが分かるはずです。
②自己犠牲の落とし穴
他の人のために何かをしようとするあまり、義務感や自己犠牲の思いが芽生えてしまう場合もあります。
あと、できないときの罪悪感とか。自己犠牲的な人に見られる思考のひとつですよね。自分が幸せになることに罪の意識が出る。厳しいことを書くなら、幸せにならない覚悟も必要じゃないかと思いますね。
自己犠牲から幸せなんて生まれないのに、求めるのは道理が通らないし、整合性も取れない。覚悟が必要。



そう決めたのはだれ?
自分でしょ。
もっと言うと、酷い状況になっているときに『何で、自分がこんな目に合わないといけないんだ。何で、自分がこんなに言われないといけないんだ。』と思うこともあるかもしれない。何をしたか、しているのか教えましょう。
自己の軽視です。
自分を自分で軽視、大事にしていない人が周りから大切に扱われると思います?これは、世の法則。自分を粗末に扱うと、周りの人からも粗末に扱われるのは当然の摂理です。
『自分は、自分が大事ではありません』と宣言しているようなものですから。宣言された願いは叶えられる。これは宇宙の理性が働いて起きた流れとも言えます。
自分が自分を扱っているように、周りから扱われる。
無価値と思っていれば、無価値になるように自分も周りも動き出す。これが世の法則。イメージしたものが、そのまま目の前に現れる。無価値と思っているのなら、無価値が目の前に現れる。これは宇宙の理性が導いているとも言える。



①無価値が提供できるものは、②無価値。価値あるものが提供できるものが価値。①が無価値なのに②が価値になることは無い、不可能。これは世の法則です。
その結果、満足感を感じられなくなってしまうこともある。実際には、他者貢献は『自分のやりたいことを原動力にして行う』これが正解だから。
義務感から行動するのではなくて、心から楽しみながら行動することが大切です。
自分の人生。わたしなら、自分が幸せになる選択をしますが、罪悪感を感じてしまうのなら、それに向き合うのも手でしょう。
③ネガティブな感情を避けるために心掛けること
自己犠牲的な活動の後に、相手からの期待する反応が得られないと、がっかりしたりネガティブな感情に悩まされることがあります。
『自分はこんなに頑張ったのに、なぜ感謝されないのか』と感じることで、心が疲れますよね。



こんなに頑張るって決めたのは自分でしょう?
自分で決めたことの結果であることを、忘れちゃいけない。
頑張る前に、その先疲れてしまうかどうかの判断が必要で、自身の感情をも封鎖し頑張ると決めたのなら、思いっきりその道を突き進むしかないんです。
あのときあぁすれば、、、これが通用しない。このことを知っておくことは大事だと思います。
その心の余裕のなさが、どれだけの弊害を生むかも知っておいた方がいい。
だって、人は辛い出来事が起こると受け止めることができなくなって、他責にしたくなるから。人と揉めるしかなくなるじゃないですか。そこから派生していく悪循環まで、想像しておいた方がいい。
だから、そこで大切なのは、期待する結果を求めず、自分がしたいと思うから行動する、という強い意志が必要なこと。これが心の余裕になるから。
人に与えるのに、逆にこの意志が無いなんて、嘘でしょう?
④他者貢献は自己成長のチャンス
他者への貢献を通じて得る新しい経験やスキルは、自分の成長にも繋がることがあります。
『自分のやりたいことをしながら、誰かの助けになることができた』という実感は、より大きな自己満足になる。
このようなプロセスこそが他者貢献の喜びで、より良い人生の一助になります。
⑤自分軸の重要性
他者貢献を意識するときには、自分の感情や価値観に基づいた判断を忘れないことが重要です。
自分の感じていることや望んでいることを理解して、それに従って行動する。すると、自身の軸がしっかりしてくるので、他者貢献が自然に自己実現に繋がっていくという好循環が生まれる。
他者貢献は単なる自己犠牲ではなく、自分自身をも満たすための大切な手段。自分の心が満たされながら他者を助けることが、真の他者貢献の意義であることを忘れないでください。
そのための、他者貢献につなげるための自分軸です。
ギブ & テイクの教訓※自己犠牲的なギバーと自己犠牲をしないギバー
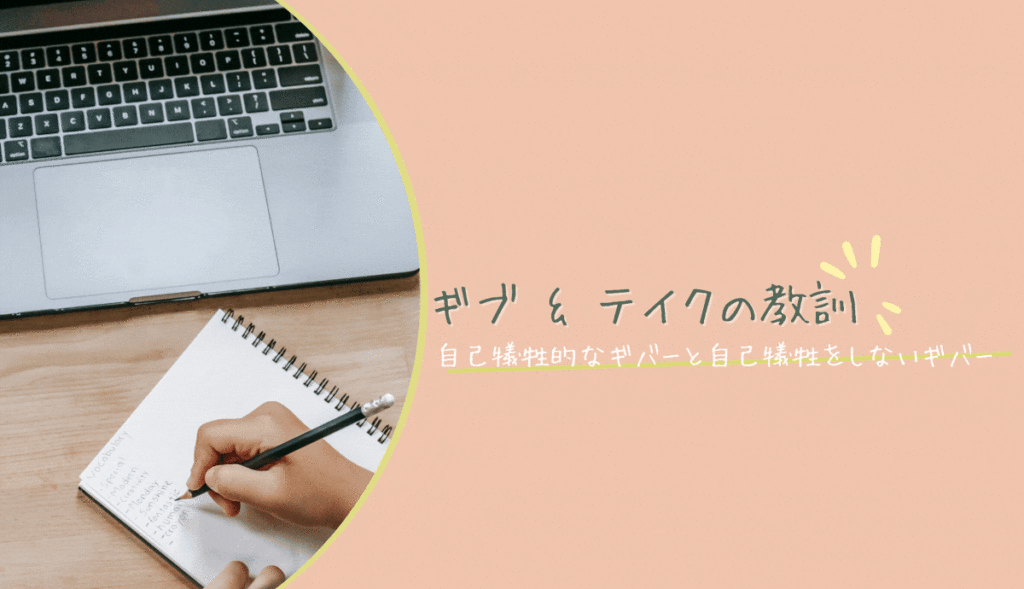
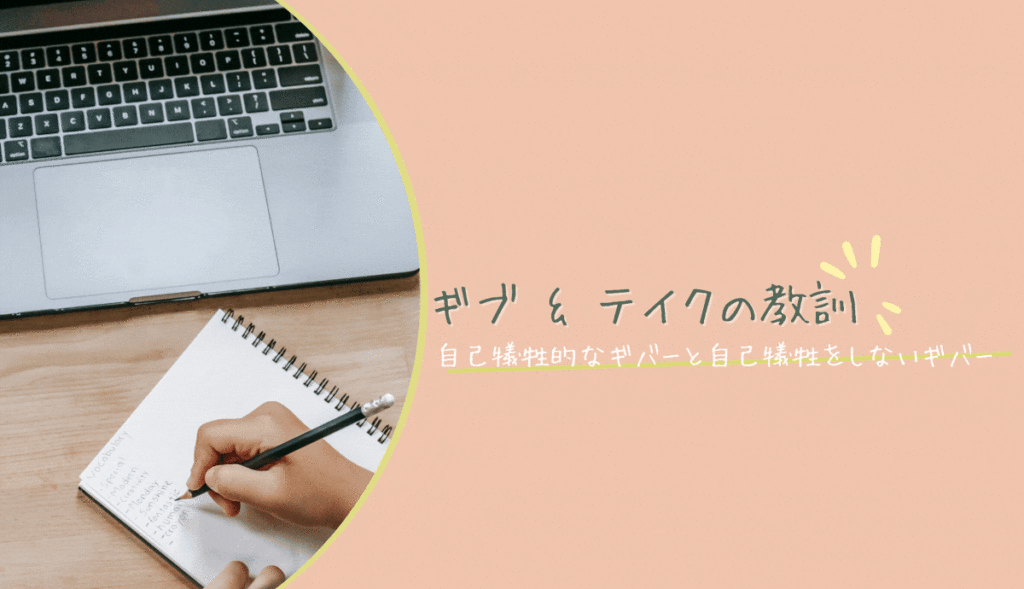
- 自己犠牲的ギバーの特徴
- 自己犠牲をしないギバーの強み
- 高パフォーマンスを生む選択
- より良いギバーになるために


①自己犠牲的ギバーの特徴
自己犠牲的なギバーとは、他者のために自らの時間やエネルギーを惜しむことなく、尽くす人物です。
このタイプのギバーは、他人を助けたり支えたりすることに喜びを感じますが、その代償として自分を犠牲にしがちです。短期的には周囲から感謝されることも多いですが、長期的には自分自身の目標達成を困難にしたり、徹底的に人に利用されることが多くなる。
このような行動パターンは、組織内でも見受けられます。
例えば、プロジェクトのために過度に働き続け、最終的には燃え尽きてしまうことなどが挙げられます。
他者のために尽くすことが美徳とされる社会では、このような自己犠牲的ギバーの存在が力強く支持されることもありますが、果たしてそれが長期的な貢献になるのか、一度立ち止まって考えた方がいいと、わたしは思います。



自分を過信しない。
②自己犠牲をしないギバーの強み
一方で、自己犠牲をしないギバーは、他者貢献を行いながらも自身のリソースの管理ができます。
このタイプのギバーは、自分の良い状態を保持しつつ、持続可能な方法で他者を支えることができるため、結果的により高いパフォーマンスを発揮することが多いです。
例えば、自己犠牲をしないギバーは、タスクを効率的に分担し、他者とも連携を図りながら進めることができます。このアプローチにより、組織内では信頼を獲得できますし、長期的な貢献を続けることが可能となります。
③高パフォーマンスを生む選択
自己犠牲的なギバーと自己犠牲をしないギバーの違いは、単なる行動パターンだけではなく、選択にも大きな差があります。
自己犠牲的ギバーは『与えなければならない』という義務感から行動することが多いのに対し、自己犠牲をしないギバーは『自分がしたいから与える』という姿勢を持っています。



与えると決めたのはだあれ?
この違いが、パフォーマンスや満足感に大きく影響を及ぼして行く。
④より良いギバーになるために
アダム・グラントの研究から示されたように、自己犠牲をしないギバーこそが、終局的には組織や社会のために貢献できることを知っておくことは重要だと思います。
自己犠牲的ギバーは短期的には評価されるかもしれませんが、持続可能な貢献を目指すのであれば、自己犠牲をしないギバーのように行動することが大切です。
これにより、職場環境や人間関係がより良くなり、個々人の充実感も高まります。
リーダーが自己犠牲的な貢献を容認してはいけない理由


- 組織の持続可能な成長を妨げる
- 成果への依存とその危険性
- 自己犠牲的なギバーと真の貢献者の違い
- 自己犠牲の評価が生む副作用
- 自己犠牲的な文化を排除する方法
①組織の持続可能な成長を妨げる
リーダーが自己犠牲的な貢献を容認すると、組織全体のパフォーマンスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。
自己犠牲を美徳とする文化が根付くと、自然と『犠牲になることが求められる』という風潮が生まれ、従業員は自分の気持ちを後回しにして働かなければならないと感じるようになります。
このような環境では、社員の『働きがい』は低下必須、結果として職場の士気や生産性は下がる可能性が高い。
②成果への依存とその危険性
自己犠牲的な行動は、一見すると素晴らしい貢献にも見えますが、その実態は成果への過度な依存につながります。
リーダーがその行動を評価することで、他の社員も『自分も犠牲にならなければならない』と感じ始めるんですよ。
これは、長期的なパフォーマンスを損なうだけでなく、チームのダイナミクス(関わり方、力関係)も悪化させます。成果を上げるためには、持続可能な形で他者に貢献しようとすることが理想だと思います。
③自己犠牲的なギバーと真の貢献者の違い
リーダーに、自己犠牲的なギバーと真の貢献者を見極める能力があるといいですよね。
自己犠牲を強いられる社員は、『自分が我慢している』という被害者意識を抱くことが多く、これが職場の雰囲気に悪影響を及ぼして行くからです。
一方、真の貢献者は、自らの意思で他者を支援し、その行為によって感じる満足感を大切にします。
リーダーとして、自己犠牲を美化するのではなくて、社員たちが自分自身を大切にしながら他者に価値を提供する方法を見つけられるようにサポートすることができたら、最高だと思います。
④自己犠牲の評価が生む副作用
自己犠牲的な貢献を容認し、賛美することで、従業員はその行動に期待される『見返り』を求めるようになることがあります。
成果を上げるために自らを犠牲にすることが常態化すると、周囲の社員もそのスタンダードに従うようになり、見返りが得られない場合には、不満やストレスが蓄積されて行く。
当然の節理です。
このような状況は、組織全体の生産性を低下させ、ひいてはリーダーシップの信頼性を確実に損ないます。
⑤自己犠牲的な文化を排除する方法
リーダーとしては、自己犠牲的な習慣を排除するための施策を講じた方がいいと思う。
具体的には、社員の健康や働きがいを重視した制度や評価基準を設定したり、自己犠牲ではなく他者貢献を促す環境を整えることができたら理想です。
また、自己犠牲を美徳とする言葉や行動を避け、社員が自己を大切にすることの重要性を常に伝える必要があるとも考えます。
こうした取り組みを通じて、持続可能な成長を実現する組織の基盤を築くことができるんじゃないかと思います。
まとめ
他者のために尽くすことはいいことですが、それが自己犠牲につながっては意味がない。
何か決断するときには、常に問うといい。自分の感情がどう思っているのか。
健全な人間関係や組織運営には、自分の幸せを大切にしながら他者に貢献できる『他者貢献』の姿勢が大事だと思います。
他者貢献と自己犠牲の違いを知っておくことが大事で、自分の今の行動がどちらなのかを知っておくことが大切です。
そして、決断した後も常に問うといい。



そうしようと決断したのはだあれ?
自分でしょ。
こうなる。だから、頑張るしかない。



That’s life too.




コメント