楽長にガツンとショックなことを言われても、投げ出さずに古くて重たいセロを家まで持ち帰るゴーシュ。
文句ひとつ言わず練習を続ける姿は「努力家だなあ」と思わされます。
でも、この物語は「努力すれば何でも実現できる、めでたしめでたし」では終わらない。
そこで終わったらもったない。

セロが古いんだ!自分は悪くない!
ゴーシュは一度もそれを口にしないんです。
しかも、夜な夜な押しかけてくる奇妙な動物たちを、自分のスペース(家)に招き入れる。境界を侵されてイラッとしながらも、必ず一度は関わって、その中から気づきを得る。
この姿勢がすごい。
何事も無駄にせず、自分の糧に変えていくゴーシュ。
だからこそ、彼は成長していったんだと思います。
色々な見解はあるでしょうが、私はこの物語を読むたびに、



あ、これってマズローの五段階欲求と同じ流れ。
あと自己理解、自己統合ね。
と感じます。
社会的欲求 → 尊重欲求 → 自己統合した結果、そして自己実現の入り口に立てた物語。
この記事では、『セロ弾きのゴーシュ』を通して学べる要素を、マズロー理論と重ねながらまとめてみました。
『セロ弾きのゴーシュ』が描く成長のプロセス
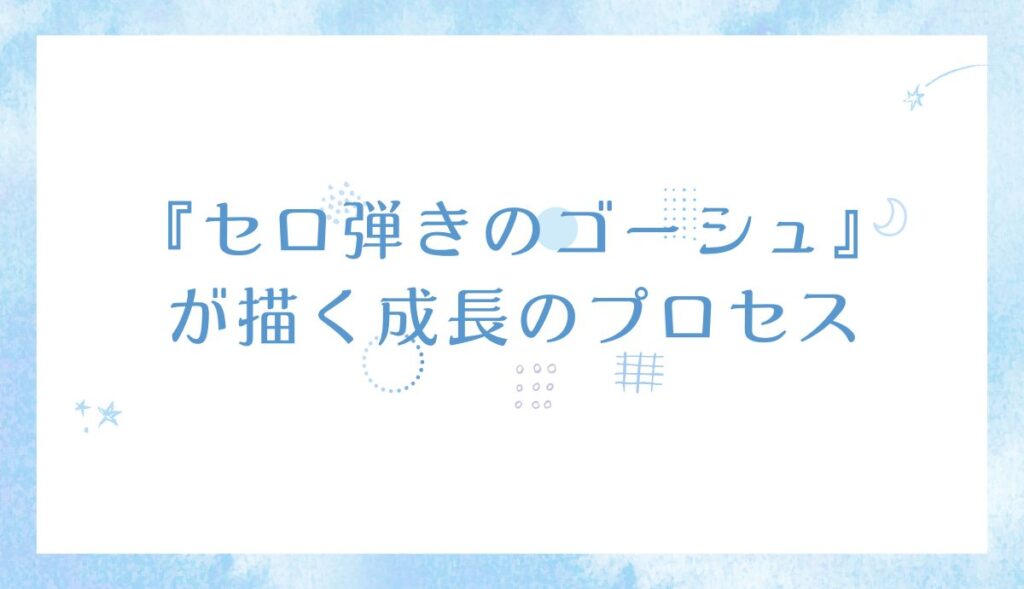
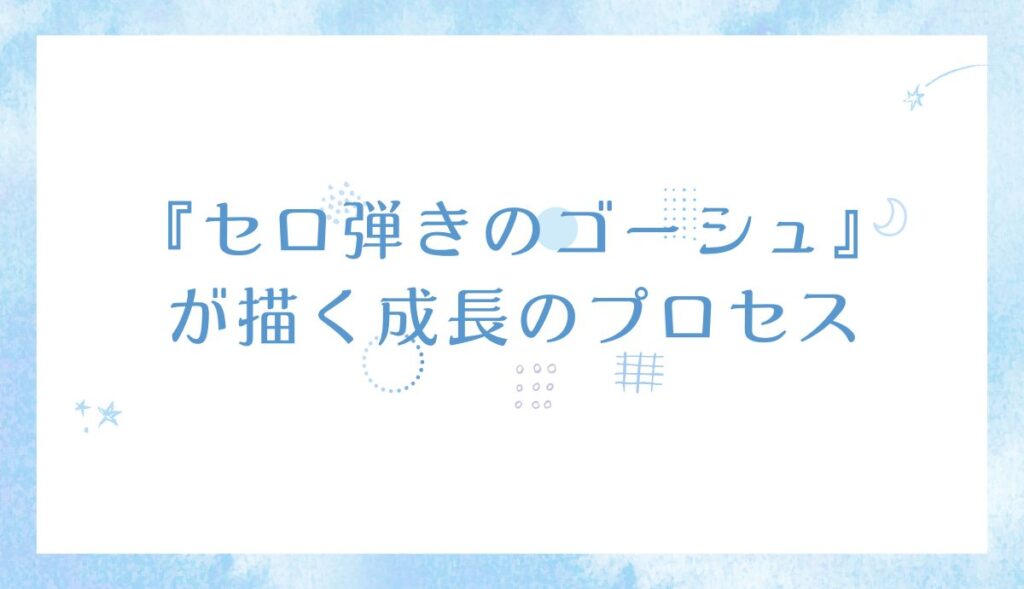
最初ゴーシュは、楽長が手を叩くとビクビクしてましたよね。
けど、ゴーシュは強かった。
言い訳もせずに、涙を拭いてひとり練習に向かった。
他者の評価を気にしていたゴーシュ。
古くて重たい大きなセロを家に持ち帰った。
この行動から、思いもよらぬ物語へと引き込まれます。
人生でも、他責にせず自己に向き合い続ける人には、神様が不思議な縁をくれる。
それを象徴するかのような物語。
- 三毛猫?ただのマウントお客。でもこのムカつく相手が師匠になるんです
- かっこう ― 正確さを学ぶ(生きざま)
- 狸の子 ― リズム感の習得(気づき)
- 野ねずみ ― 音楽が人を癒す力(他者のために弾く)
① 三毛猫?ただのマウントお客。でもこのムカつく相手が師匠になるんです
最初にやってきたのは、トマトをお土産に持参したしっつれいな三毛猫。
お土産っていってもゴーシュの畑から盗んできただけなんだけどね。
この猫、いきなり



シューマンのトロメライ弾いてよ。聴いてあげるから。
なんて上から目線。完全にマウント系お客様。
怒り爆発のゴーシュは、



聴けるもんなら聴いてみろ!
とばかりに怒りの感情全開で「印度の虎狩り」を演奏。
すると猫はビビって逃げ出す。
皮肉にも、猫の挑発がゴーシュに「感情を音に込める」ことを教えてくれた。
ここはつまり、感情を扱えない自分の幼児性への気づきでもあると思う。
※シューマンのトロメライは夢や幻想を表した曲のようです、だから、この物語はゴーシュの幻想と見てもいいと思う
※印度の虎狩りという曲は実際にありません
出会う動物の変化
ここ、波長的に言うなら、ゴーシュの人間性が傲慢な猫を連れてきたとも見て取れますよね。
楽長に言い訳しないのは強さでもあると同時に弱さでもある。
向き合いきれない、自分の感情が分からずに、言い訳、言い返すことができない。
そういう揺れのときに出会う人というのは、大体こういう理不尽な人が多いものですよ。
それは自分の未処理の感情や課題を映す鏡だから。
そして、その相手を通じて「怒り・劣等感・言い訳の欲望」といったテーマに直面し、成長する機会を与えられていると取れます。
② かっこう?執念の塊。正確さに命を懸けるストイック変態
次にやってきたのは、妙に几帳面なかっこう。



音がちょっと違うよ。こうだよ、かっこう、かっこう。
って、リピート練習させるガチ指導モード。
ゴーシュ、最初は、



うっせえ鳥だな!
と正確に音を出すことができない自分と、それでも何度も同じことをさせて、正しい音を突きつけてくるかっこうにイライラ。そして追い出しちゃう。
ただ、かっこうだけは、生き方も伝えてるような気がするんですよね。
物語の途中で、



なぜやめたんですか。ぼくらならどんな意気地ないやつでものどから血が出るまでは叫ぶんですよ。
と言って、諦めないことの大切さを伝えているし、窓ガラスを自分で突き破ろうとするでしょう?
ゴーシュが外に逃がしてやろうとするのに、それを振り切って自分で出ようとするでしょう?
あの姿から、中途半端で終わらせる者に助けなど借りない!という強さとも見えたし、何がなんでも自分の力だけで脱出してやる!という強さにも映ったんですよね。
あとは、正確に弾くことだけを追求しているゴーシュへのダメだしとも取れるかもしれない。
嘴(くちばし)から血まで出る始末。
ゴーシュは最後怒りながらも追い出しちゃうけど、ちゃんと学んではいる。



ああかっこう。
あのときはすまなかったなあ。
おれは怒ったんじゃなかったんだ。
物語の最後にこう伝えているのは、かっこうは何も悪くないのに、怒りをぶつけてしまった。
正確に弾くことだけを追求していた未熟な自分への自責。
正確なかっこうは、何かしらの「自分のズレ」を突きつけてくる相手 → だから苛立って「お前が悪い」と他責にしたくなる。
だって、かっこうが教えていたところは楽長から注意されていたところだし。



セロっ。糸が合わない。困るなあ。
ぼくはきみにドレミファを教えてまでいるひまはないんだがなあ。
ここが一番のターニングポイントになったんだと思います。
出会う動物の変化
三毛猫の出会いから、かっこうへの流れ。
まだ自分を受け入れることができていないフェーズですよね。
自身を受け入れることができていないから、「ダメだ、ダメだ」という人が目の前に現れる。
大体人というものは、三毛猫か、このかっこうで止まるんですよね。
- 三毛猫フェーズ:理不尽にマウント取ってくる相手に感情を爆発させる → 「怒りの中で感情を表現する」学び。
- かっこうフェーズ:正確さを突きつけられて「ダメ出し地獄」に陥る → 「自分に足りない部分(正確に弾くこと、正確に弾くことだけを目的とする危うさ)を突きつけられる」学び。
ここで止まる人が多いのは、承認欲求の段階から抜けきれないから。
「もっと正しく」
「もっと評価されたい」
と思って、結局は 外からのダメ出しや基準に縛られてしまう。
そして疲れて、スケープゴートも余裕である。
もっと手前になると、怒りすら湧かない段階の人もいる。
それをわたしがどう見るかというと、こうだ。
闇が深い。だって、スタートラインに立ててないから。
- レベル0:批判されても怒りすら湧かない。無感覚・無自覚。まだ「スタートライン」に立てていない段階。生きる力そのものが閉ざされている。(闇フェーズ)
- レベル1:批判を材料にできず、防衛か逆ギレで終わる、感情を爆発させることでしか存在を表現できない。(三毛猫フェーズで足止め)
- レベル2:正確さや他者の基準に囚われ、自己否定に飲み込まれる。「もっと正しく」「もっと認められたい」に疲れて消耗。(かっこうフェーズで消耗)
だから、狸や野ねずみのフェーズ――「素直に受け入れて成長につなげる」「人のために力を使う」まで行ける人は、ごくわずかと思う。
- レベル3:素直にダメ出しを受け入れられるようになる。そこから気づき・成長につながる。(狸フェーズ)
- レベル4:自分のためではなく、他者のために力を使えるようになる。(野ねずみフェーズ)



つまりゴーシュの物語は、
「三毛猫やかっこうの段階で終わんなよ。その先に狸と野ねずみが待ってんだぞ。会わなくていーのかよ。」
って現代人に投げてるように読める。
あなたはいまどこらへん?
③ 狸?一番まとも。音楽を“愉快”に変えてくれる貴重な存在
三日目の夜に登場したのは、狸の子。
棒をポンポン叩きながら「愉快な馬車屋」をリクエスト。
そして狸、遠慮なく、



2番目の糸、遅れてるよ。
とダメ出し。
けど、これがかっこうからの伏線で、



たしかにその糸はどんなに手早く弾いてもすこしたってからでないと音が出ない…
こう思えています。そこで初めて、セロにも原因があるということに気づきが入ってるんですよね。
技術だけを磨いても、道具を扱えておらず、正確な音が出せていないという事実に。
ゴーシュは追い返しもせずに、素直に聞き入れて練習。
夜通しのセッションでリズム感がぐんぐん磨かれていく。
ここでの変化は大きい。
「批判を素直に受け入れる」フェーズに進化。
出会う動物の変化
ここで「愉快な馬車屋」という実際にない曲が書かれていますが、愉快な…という言葉を使っている以上、音楽が楽しみに変わってきたと推測できます。
ゴーシュ自身も素直に聞き入れができるようになっていることから、登場する狸の性格もおだやかですよね。
セロという楽器自体に問題があるように、私たち自身にも「どうしても整わない部分」や「特性」があるじゃないですか。
そこに気づかないまま努力を続けても、必ずしも成果につながるとは限らない。
たとえば、足が速いといっても、短距離向きか長距離向きかで適性はまったく違う。
短距離型の人が長距離に挑んでいくら努力しても、なかなか芽は出ないから。
だからこそ、自分の資質を見極めて「どこで活かすか」を選ぶことが大切になる。
そして「セロの糸=資質」と読むなら、それは一見、自身の「欠け」に見える部分かもしれない。
けれど、それを悪いものと決めつけるのではなくて、不器用さを抱えたまま、どう生きるかを模索する。
そこにこそ自己理解と成長のヒントがあるとも読める。
努力だけでは足りない。自分に備わった資質や、環境との相性を理解することが欠かせない。
その本質に気づけたとき、初めて努力は報われる。
楽器の特性を知り、欠けを補いながら弾く――それが人の生き方にも重なるのだと思う。
④ 野ねずみ?もうゴーシュの音楽が治療になっちゃった。医者超え
最後に現れたのは野ねずみの親子。



子どもが病気だから、演奏して治してほしい。
と無茶ぶりオーダー。
最初は困惑するゴーシュ。でも実際に弾いてみると、子ねずみが元気になっちゃうんです。
ここで、自分のために弾く音楽ではなくて、人のために弾く音楽へと進化。
音楽が人のためになっているという気付きが入っています。
そして野ねずみに、パンのおすそ分けをする余裕まで出てきました。
しかも最後には、以前追い出したかっこうを思い出し、空を見上げて「悪かったな…」と心で謝る。
ここに至って、ゴーシュは完全に「ただの下手くそ」から「人に響く音を奏でられる音楽家」に変身。



いや、からだが丈夫だからこんなこともできるよ。
普通の人なら死んでしまうからな。



「お前の努力はただの努力じゃない、常人なら潰れてた」という、最高の承認とも読み取れる。
そう、それくらい過酷なんだよね。
自己に向き合うってのは。
大変なんだよ。
まぁ、この表現は人生単位の修行を一週間、十日だから、そら死ぬよね、とも読み取れるけどね。
富士山の頂上まで全力疾走で駆け上がるようなものだと思う。
出会う動物の変化
ここで使われている「何とかラプソディ」も実際に使われている曲ではありません。
ただ、ゴーシュの人柄に変化がみられているのが分かりやすい描写ですよね。
出会う野ねずみも、感謝やお礼をいう動物に変わっている。
最初の三毛猫からすると、大分進化していっています。
動物たちとのセッションが示すゴーシュの変化
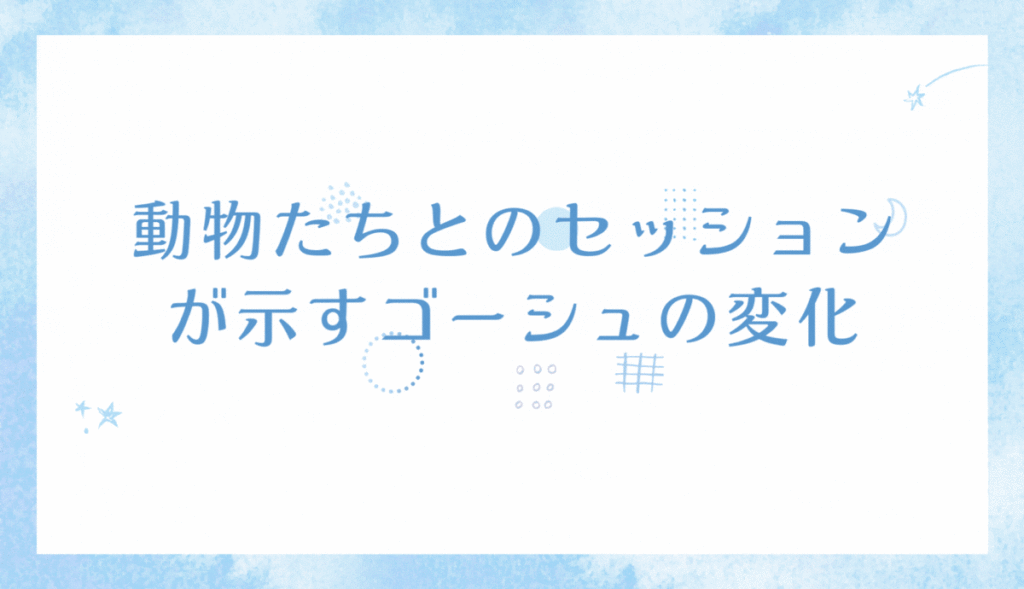
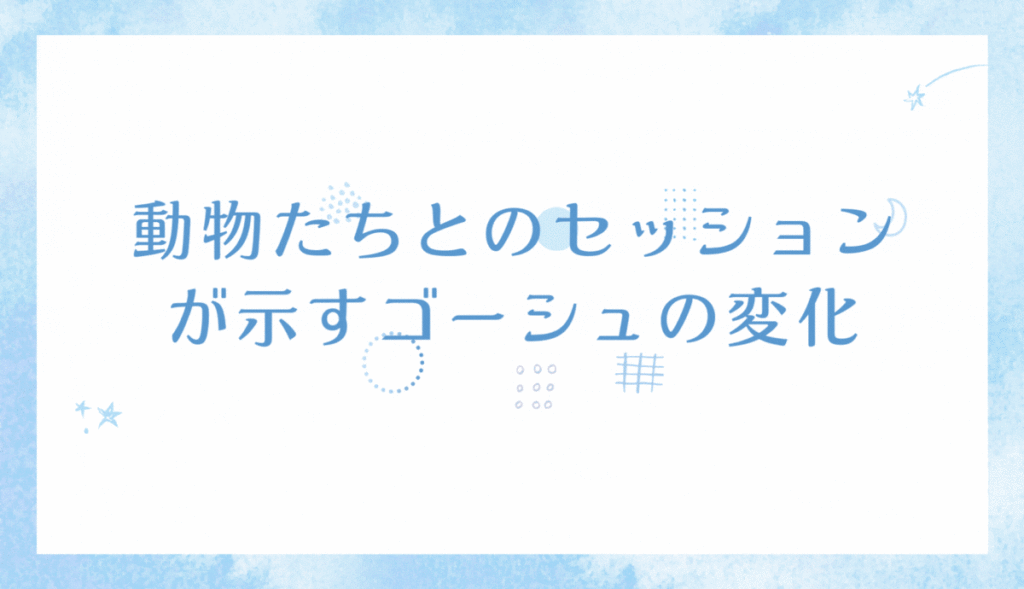
- 批判や要求を排除せず受け入れるゴーシュ
- 学びを自分のものにして変化する過程
- 「演奏を通して誰かのためになれる」への進化
① 批判や要求を排除せず受け入れるゴーシュ
普通ならムカついて追い返したくなるような動物たち。
- 猫は「その曲弾いてみろ」と挑発する→マッチを猫の舌でこする
- かっこうは「音ちがう」と上から指導する→窓ガラスから逃がす(逃げられる?)
- 狸は「遅れてる」とダメ出ししてくる→ありがとうと言われて、狸は帰って行く
- ねずみに至っては「病気を治せ」と完全に医者扱い→ねずみに泣いたり笑ったりおじぎをされて、感謝される
これ、全部“批判”か“要求”。
でもゴーシュは、怒りながらも弾いたし、苛立ちながらも付き合った。
つまり、相手の存在を一旦受け入れてから向き合うという選択をしてるんだと思う。
そこにそれなりの結果がある。
② 学びを自分のものにして変化する過程
ただ受け入れるだけじゃなく、ちゃんと自分の血肉に変えていくのがゴーシュのすごいところ。
猫のときは「感情を音に込める」ことを掴み、かっこうからは「音程の正確さ」と「生きざま」を学び、狸からは「リズム感」を叩き込まれて、糸のひきの遅れを気づかされた。
- 三毛猫 → 怒りを外に出す(感情解放)
- かっこう → 「努力万能論」の象徴かもしれない、努力の限界を突きつける存在?そこで苛立ちを他責(鳥のせい)にしてしまうのがゴーシュの未熟さ(自己否定や苛立ちと対峙)
- 狸 → 楽しみ・リズム・環境理解(努力+工夫で報われる)
これは「批判=敵」から「批判=成長の材料」へと変換する力。
③「演奏を通して誰かのためになれる」への進化
そして最終段階が、野ねずみの子を救ったエピソード。
ここではじめて、ゴーシュの演奏が「自分のため」から「他者のため」に変わる。
しかも、治療効果まで発揮してしまうというおまけつき。
この瞬間、ゴーシュは「自己尊重」からさらに一歩進んで、自己実現の入口に立ったといえる。
さらにラストでかっこうを思い出し、「悪かったな」と謝るところ。
これは自分の未熟さを認めて、他者を改めて承認する行為。
つまり、ゴーシュは「承認されたい人」から「尊重(承認)できる人」へと進化した。



『セロ弾きのゴーシュ』は、動物たちとの関わりの中で、自分の感情・弱さ・素材を受け入れ、自己統合となった結果、他者のために演奏できるようになり、自己実現の入り口に立てた物語と言えると思う。
どこかで投げ出してもよかったじゃないですか。
けど、ゴーシュは投げ出さなかった。
腹が立って追い出したりしたけれど、それでも弾いて向き合った。
途中で、あまりにも受け止めきれなくて、かっこうの責任にして怒った。
けど、投げ出さなかったから未来が開けた。
なぞの指導があるとしたら
白いぼうしの件があるから、猜疑心しか生まれない。
と前に書いて、他の指導案を調べてみたら「動物との共存」っていうのが出てきた。
動物との共存って、何の指導かとも思う。
そして、こんなのかな?ってのを作ってみる。
道徳レベル:正直さ・自己表現。



人の育てたトマトをかってに取ってはいけません。
ほしいときは『分けてもらえますか?』と自分の気持ちを相手にきちんと伝えましょう。
道徳レベル:相手を思いやる安全配慮。



かっこうが家に入ってきたら、ただ追い出すのではなく、怪我をしないように、きちんと窓を開けて逃がしてあげましょう。
道徳レベル:協力・共感。



夜に、棒でポンポン小太鼓を叩いても、『静かにね』と声をかけ、リズムを一緒に楽しむ気持ちを持ちましょう。
ゴーシュの弾くセロに合わせてたぬきがリズムをとりました。
どう思いますか?



音楽はみんなで楽しむものだと思います。
道徳レベル:分かち合い・助け合い。



ねずみにパンを与えるゴーシュをどう思いますか?



やさしいと思います。



宮沢賢治も天国で「そこじゃねぇよ!」って叫んでんじゃねーの?
何度読んでも、やっぱ要は「共存」じゃなくて「自己変容」だと思うよね。
だけどさ、物語の読解に正解なんてないじゃない。
これを子どもに教育するとなると難しいよね。
例えば三毛猫のトマトで説明してみるとさ…
①「トマトを勝手に盗むのは悪」だけを学んだ子
- 外から与えられた「正解/不正解」で動く人間になる。
- 「してはいけません」という禁止ルールに従うことはできるけど、応用が効かない。
- 結果的に「ルールがない場」「グレーゾーン」では身動きできなくなる。
- 他人の基準に依存してしまうから、大人になってからも「言われたことは守れるけど、自分では判断できない」タイプになる。
②「ゴーシュの自己変容」を学んだ子
- 批判や理不尽さに出会ったとき、「何を自分に映しているのか?」と考えられる。
- 怒りや苛立ちをただ押さえ込むのではなく、自己成長の材料にできる。
- 「失敗や否定は成長の入口」と腑に落ちているから、壁にぶつかっても折れない。
- 自分の弱さや資質を受け入れながら、環境に適応して「自分の音」を奏でられる。
人生でどう差がつくか
- ①の子は「模範的に見えるけど、自分で道を切り開けない大人」になる確率が高い。
- ②の子は「失敗も否定も成長に変える大人」になれる。



わたしは②を選びたいんですよ。人それぞれだろうけどさ。
だって、この本で仮に「努力は必ず実る」て教えたとしても、実際の人生とズレるでしょ。
ここでも書いたよ。
内容は少し違うけど、似たようなもんだよ。
間違った努力は実を結ばない。
セロの糸のズレに気づかなければ、どんなに練習しても音が合わないのと同じだ。
何のための「かっこう」だ。
だから教育も、ただ「ルールを守りなさい」じゃなくて、「どうすれば自分の音を響かせられるか」を子どもに渡したい。
これは私の正解。
でもみんなの正解とは限らない。
この辺りは、現在、知ったもん勝ちの世界になっている。笑
持っている者しか、正しい航路は渡れない。
取りに行かないと無いし、取に行かないといけないことすら知らない人が大半の世界。
読書は必要って言われるけど、独学での読解には限界があるみたいだよね。
せっかく良い本を読んでも、解釈がズレれば宝の持ち腐れになっちゃう。
「読み解き、つなげる力」は必要だと思うわ。
ある意味「悲劇」よな。
大人もそうだよ。



あと言えることは、物事、世の中の原理原則が分かるようになると、読解力って必要ないんだよね。
何が言いたいのかがすぐわかるのよ。
読解力って「文字を追う力」じゃなくて「背景を掴む力」でしょ。
読むことには意味はあると思うけど、ここまでくると、わたしにとって読書とは?と問うてみたら、本を読むというより「著者を読む」という、著者の思考を読むということになってきてる気がする。
だから内容が新しい/古いは副次的で、「この人の思考は、何歳でどの深度まで降りてるか?降りていたのか?」が気になってきている。
つい、年齢も調べちゃうし。
だから、宮沢賢治も、新美南吉もだけど、やっぱり物事の原理原則をものすごく理解している方々だと思う。
すごいよ、やっぱり。
『セロ弾きのゴーシュ』を書いたのが31歳、『ごんぎつね』は18歳よ?
こういう読み方をしたら、ものすごく面白いことに気が付く。
感動の世界よ。
知識じゃなくて、体感で理解して、それを物語に落とし込んで描く才能ね。
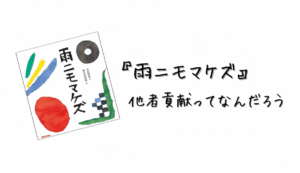
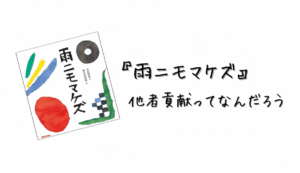
自己理解は「他者を通じてしか見えない」
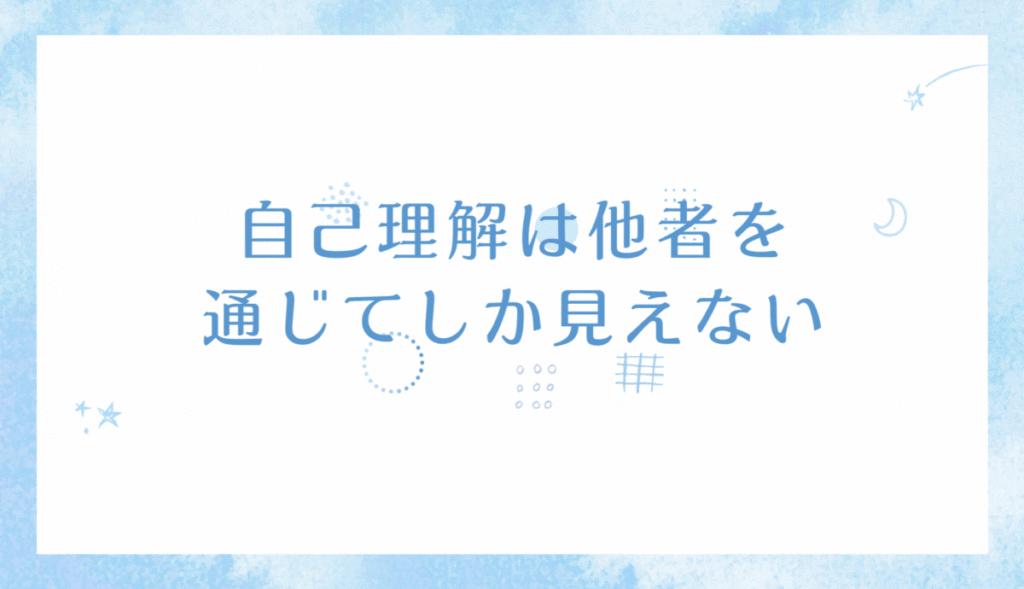
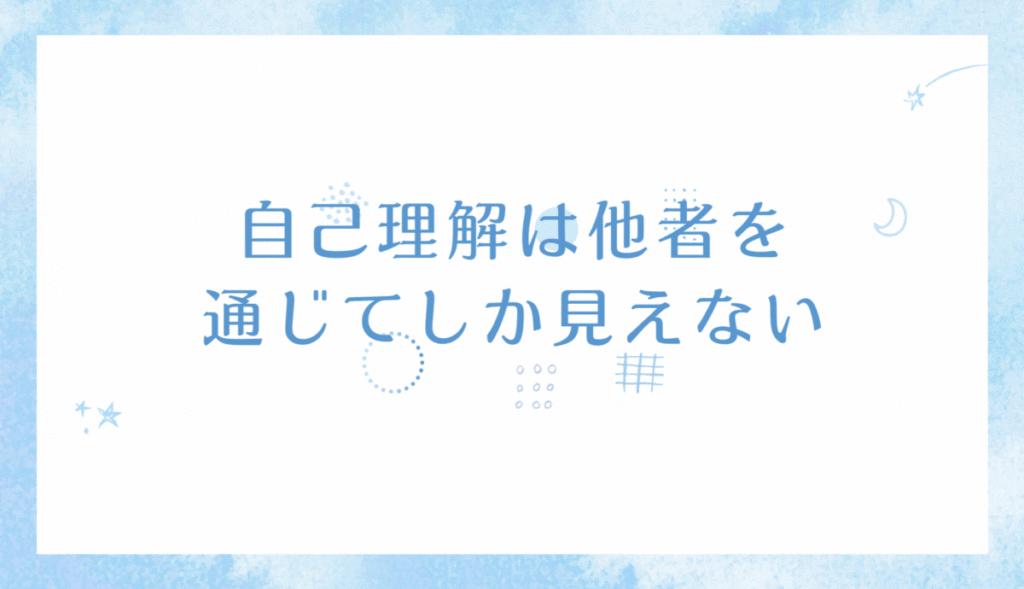
人間って、自分の顔を鏡なしでは見られませんよね。
心も同じ。他者という鏡を通さないと、自分の姿はわからない。
他者は自分の写し鏡。
自分に足りないものを持っている相手には、嫉妬が湧き、異性だと「執着」になることもある。
もちろん必ずしもそうとは限らないけれど、人間の反応はだいたいこのパターンで動いていく。
そして、自分に弱さがあれば、他者の弱さも妙に気になる。
その弱さは「自分が備えたもの」なのか、それとも「他者や環境から植えつけられたもの」なのか――。
『セロ弾きのゴーシュ』のゴーシュも、最初はただセロを弾くだけの人でした。
言い返すこともできない、ただの下手くそなセロ弾き。
弱さも垣間見える。
そこに、楽長からのダメ出しが入る。
涙が出るほどの否定。
でも、その次にやってきた三毛猫とのやり取りで「怒り」として感情が噴き出した。
向き合った証拠だ。
ここから、本当の強さと弱さの受容のフェーズに入る。
つまり、怒りをぶつけたあとから、彼は学びのフェーズに入るんです。
最初は受け入れるのが難しい。
でも立ち止まらずに続けた。
そうしているうちに、気づきが生まれ、やって来る動物たちの性格も変わっていく。
かっこうに謝った瞬間、ゴーシュは“認められたい人”から“認めることができる人”へと立場がひっくり返った。
ここが物語の本当のクライマックス。
拒絶や怒りから、受け入れと気づきへ。
その過程で、表現力や優しさまで身についていった。
つまり、この作品が描いているのは「自己理解は独りきりの内省では足りない」ということ。
他者との関わりの中で、立体的に自分が浮かび上がる。
見たくない自分をきちんと受け入れた結果、自己統合できていく。
そして最後、やけっぱち気味に弾いたセロが、観客を感動させ、楽長からも褒められる。
それまでの道のりは正解か不正解か分からなかったけれど――結果として「正解だった」と証明された瞬間だと思う。その姿を学んだのが、最後に反省していた「かっこう」じゃないかと思う。
ゴーシュの場合は、他者からの尊重(狸・ねずみ) → 自尊心(演奏に自信・誇り) → 他者を尊重できる(かっこうへの謝罪)。
これが通常ルートだと思う。
一週間か十日の間にずいぶん仕上げたってなってるから、ずいぶん短期間だけど、ほんとうの我々の人生は長い。
自尊心が先にくるタイプは、自己理解が深くて、自分の経験を統合していける人にしかできない。
つまるところ、稀だ。
こっちは荒行だ。
だから、通常は他者からの尊重を受けられる環境構築を目指した方がいいのかもしれない。
けどさ、環境に身を置いてからゴーシュのように生きるのは至難の業でもあるよ。
なぜか?ゴーシュには音楽がありセロがあった。
そういう努力を努力とも思えないようなものに出会えないと、環境にのまれるんだよ。
すぐにね。
そこで環境にのまれないようにしなければならない。
いかんせん、これが難しい。笑 大体のまれるし、のまれていることにも気づかないからな。
所有するものに、所有される、環境だって物だ。
環境選びもだが、ゴーシュで言う、自分の「セロ」を見つけないといけないと思う。



仕事は生きる手段であると同時に、アイデンティティを縛る枠にもなる、人間関係は支えになるけど、のみ込まれると同化してしまう。
これの難しいことよ。
ちなみに、わたしには容易だ(言っとかないとね、なぜか?荒行の方を通っているからだ)。
有能な人はさ、論理構造が見えやすい。
だから、正しさを突き付けられても、それを「体系」として理解できるのよ。
知識の埋め込みが存在しないだけでしょ。
「正しさ=ルール」
「正しさ=能力UP」
と結びつきやすいから、知識の埋め込みがあると楽になる傾向がある。
自己効力感に繋げられるから。
「これで改善できる」
「次に活かせる」
と思える脳が存在している。
つまり「正しさ=攻略の鍵」と受け止められるんだよね。
この痛快さよ。
これがさ、そうじゃない人、つまるところ論理が見えない人だと「自分が否定された」としか感じられないのよ。
だから「苦しい」「責められた」と防衛的になることが多い。
正しさを「地図」じゃなくて「刃物」としてしか扱えない。
そしてこの、煩わしさよ。
どこ、航海してんだよ。
「正しさ=地図」
「正しさ=刃物」
この分岐が、人生をまるごと左右する。



ま、関係ないからいいけど。
好きなところ航海すればいいだけの話だ。
知ったことではない。
これがゲームに乗らないものに向けられる刃になることがある。
ゲームをゲームと見抜ける人はもうゲームから降りてる。
ここまで整理すると、「正しさ」って本当に二面性があって、扱い方で人生がまるごと変わって見える。
正直、後者にはものすごく悩まされた。
そう思えない時期にイライラしたから。
イライラどころじゃなかった。
今でもだよ。
けど、正しさはときに刃になることを理解してる。
ものすごい刃に。でも、イライラは変わらない。
だから次元の考え方になったんだけどね。
関わらない一手になっていった。
いいんだよ「刃」を理解してるから。
あぁ、ごめん独り言。
この『セロ弾きのゴーシュ』の流れは、人生そのもの。
成功の法則にも近いものがある。
泣き、怒り、苛立ち、迷い…全部ぜんぶ飲み込んで響いた音が、人の心を動かすことができた。
自己実現の入り口に立てることができた。



そう思わせる物語でした。自分の解釈ですけどね。
誰と何を相談したワケでもない。笑
動物=自己の投影としても面白いと思う。そう読んでも、記事の内容は変わらない。結局は、他者を通して自分が分かるという構造は不変。
ここに来て言えることは、植えられたものは消えないってこと。
最初は責めた。こんな自分はダメだ、自分は醜いとさえ思った。
だから、そこを必死で消そうとした。
でも、消えなかった。
やっぱり嫌いなものは嫌いだし、醜さも消えなかった。
ただ、その「嫌い」の理由がわかるようになった。
そこからが転換点だったと思う。
消すんじゃなくて、抱えて生きるしかなかった。
直視もせず、否認や攻撃に走るより、そっちの方が美しいと思えたんだよ。
そしたら醜さは消えた。大変だったけど、それくらい醜さが強かったから、そうするしか術がなかったとも言える。
わたしの場合は、だよ。
要するに受容だ。抱え方さえ分かればいい。
なぜ嫌いなのか、その理由さえ分かれば、もうそれで十分なんだと思う。
ここが正解じゃないかと思ったから、そう生きてる。
自分なりの抱え方さえ分かれば、人は前に進める。
嫌いな自分を抱えたままでも、自分らしく。
その不完全がわたしだしね。
そう、不完全。

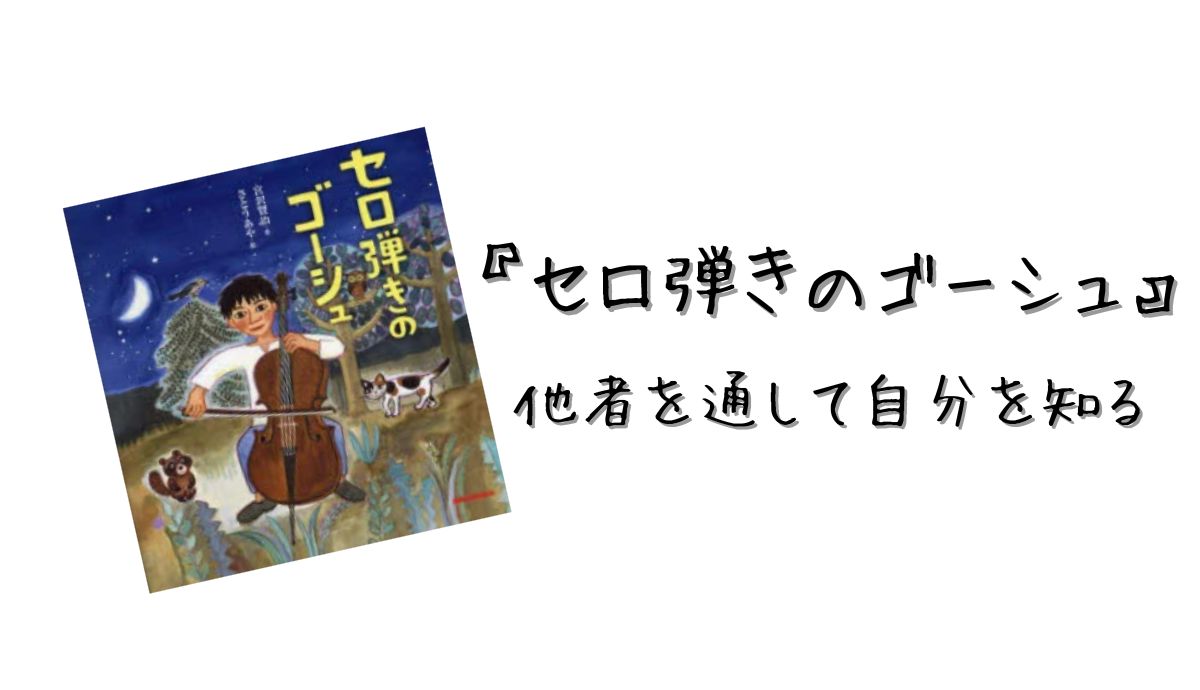
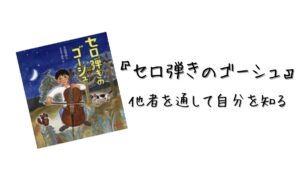
コメント