年長の息子の通う、こども園から配られた“園の準備カード”──
『園で使うものを自分で準備できるようにしてください』
という一言に、あなたはどう対応しますか?
わたしは正直、モヤモヤしました。
なぜなら『自分でできる』ことが“偉い”と評価され、
やらなかった子が“できなかった子”にされる空気を感じたから。
これは本当に『自主性』や『主体性』を育てる教育なのか?

なんなら、自主性とも違う。
100歩譲って、自主性だとして、我が家は主体性を教育方針にしている。こんなことすら、知らないんだってね。
こども園がよ。
今回は、そんな疑問から始まった一つの出来事を通して、『主体性』と『自主性』の違い、そして教育現場での扱われ方について深掘りします。
『一人でできた人〜?』に感じた違和感──わたしの体験から
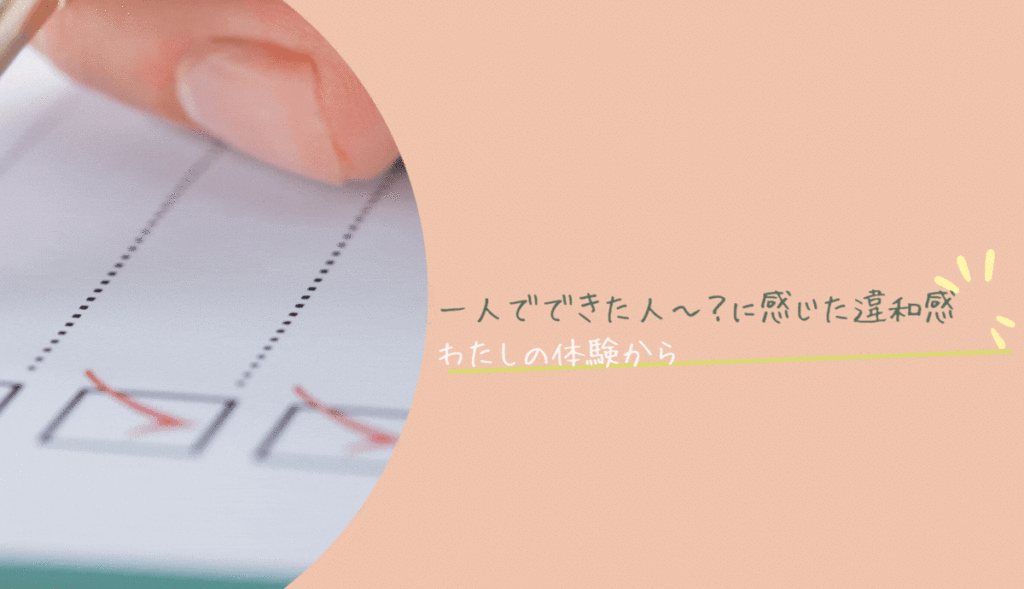
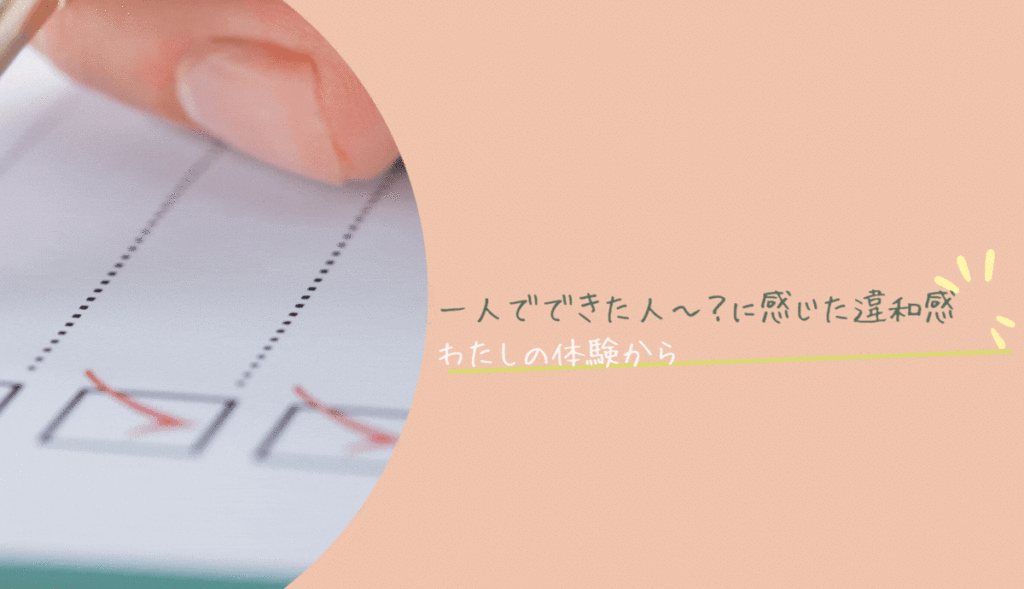
- 年長の息子に配られた『準備カード』がはじまりだった
- できた子が褒められ、やらなかった子に漂う“できなかった”空気
- 園との対話で見えた、教育現場の『一貫性』の欠如
① 年長の息子に配られた『準備カード』がはじまりだった
4月半ば。年長になった息子が持ち帰ってきたのは、こども園からの“準備カード”。
──だそうで。
『自分でやる力を育てましょう』的な…..違和感….まあいい。とりあえず冷静に。



……で、急に?今日から“自分でやれ”と?
うちの教育方針って『自立させたい』じゃなくて
『自分でやりたくなる気持ちを育てたい』なんですよ。
あとこれって、自主性にも主体性にも該当してなくない?
という違和感もあって、ええ、めんどくさいタイプの母です。
けど、譲れない。
『カードを使うかどうかは自由です。
促せるのに使えるなら、使ってください。』
ならまだ分かる。
けど、準備させてくださいには、選択の余地がないでしょう?
自主性も違う気がするし、何が目的なんだろうと不思議でしょうがなかった。
“できるようになった”という外側の成果より、
“やってみようかな”と思える心の芽生えの方が何百倍も価値あると思ってるから。
だから正直、カードを見た瞬間こう思ったんです。



はい、これは放置決定系。
やらせません。
いや、“やりたくなるまで待ちます”って言った方が上品か。
とりあえず、
- 小学校に進級すること
- それまでに、身の回りの準備を自分でできるようになっていた方が良いこと
- 園から準備カードなるものが配られたこと
この3つの説明から入りました。
で、実際に息子に聞いてみたら?



やりたくない。
だそうで。
ですよね。
うん、じゃあそれでオッケーです。



なんでやりたくないの?
理由が言えないなら、やってくれる?
ちゃんと自分がどう思ってるか言える?



…..めんどくさい。



いんじゃない?
それがお前の今の大事な意見なんでしょ?
じゃぁ、いつからならできそう?
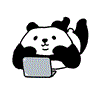
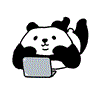
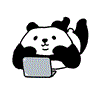
んー小学校になったら、やろっかなー。



ほんとかよ….
って思ったけれど、ま、やりたくないって言えるって時点で、自分の意志はあるわけで。
“主体性”ってそういうとこからじゃないの?
と、カードをそっとしまいました。
② できた子が褒められ、やらなかった子に漂う“できなかった”空気
翌日、こども園の先生から、こんな報告がありました。
……正直、その時、



聞くって何?
それって“任意”だったんじゃないの?
逆に任意じゃないとヤバくない?
と頭の中でツッコミが止まりませんでした。
うちは本人のペースを見たいと思っていたし、実際、やりたくないと言っていたので様子を見るつもりでいました。
でもその報告を聞いたとき、思ったんです。
やってきた子=偉い子
やってこなかった子=スルーされる存在



そんな構図が、無意識のうちに出来上がっていない?
たとえ悪気がなくても、“ほとんどの子がやった”という事実の報告と、“妹の分までやった子が偉い”という言葉がセットになることで、やらなかった子の立場に、静かに“できなかった”というレッテルが貼られてしまうんじゃないか──。
貼られる可能性もあるでしょ?
どんな感性の子がいるか分からないから。危険じゃない?
もちろん、やってきた子を褒めたい気持ちは分かります。
でも、それ以上に私は『やらなかったこと』を“選んだ”子どもたちの心を見てほしいと思ったんですよね。
③ 園との対話で見えた、教育現場の『一貫性』の欠如
次の日、私は園にお帳面で気持ちを伝えました。
と、ながーーーーーーく書いたんですよ。
教育にはうるさいから、わたし。
こうやってお帳面に記してからは、園と揉めずに解決できたんですが、前日のやり取りでは……



これはあくまで“任意”でして…
……なるほど。任意。自由参加。
わかります、建前としては。
でも正直、その瞬間、頭の中でうっすらツッコミが発動したんです。



任意って言ってるのに、“できた人〜?”って聞くの、どこの任意ルール…?
いや、聞かれた子どもたちの気持ち、どうなるんでしょう。
- “やった”と言えた子は、ちゃんと褒められた。
- “やらなかった”子は──黙ってる。それだけ。
それって、実質的には『参加した方が安心』な構造じゃないですか。
それって、本当に“自主性”を育ててるのかな?
なんとなく、『選んでいいけど、空気は読むよね?』
っていう、日本社会の縮図をこども園サイズにしたような違和感。
しかも、やったかやらなかったかだけで判断されて、



〇〇くんは妹の分までやってきたんだって!偉いね〜!
とか言われた日にゃ、



偉い?
誰が?
それで偉いって、何が偉いの?
いやちょっと待って、怖くない?
準備できたら偉いって
──いつからそういうルールできたの?
極論行けばですよ?



やばい!!妹の分までやった子が褒められた!?
じゃあ明日から、パパのお弁当まで詰めて登園してやる!!
闘士メラメラ系が多発したらどうする?ガチの“できる子選手権”スタート。
こういう愚かな保護者が出ないとも限らない。



明日からパパのお弁当詰めて行って、先生に伝えなさい!



はい、ここで質問です。当初の目的は何でしょう?



園の準備をしてから、他の人の分まで用意して、パパのお弁当を詰めたりして、誰よりも早くできるようになり、先生から沢山褒められることが目的です。



What?
って想像しちゃいました。ごめんなさい。
けど、そういう縮図が容易に想像できるでしょう?
こんな教育受けたら、将来社会に羽ばたいたときに誰かに認められるためにだけ、頑張る子ができません?
さらに指示待ち。
園~学校生活は、もしかしたら優等生で通るかもしれない。
でも──その“優等生”であることの弊害って、見逃されがちじゃないですか?
『やれ』と言われたからやる。
『褒められる』からやる。
そうやって、“認められること”に全力で適応する子になる。
昭和じゃない、AIがバンバン仕事こなすであろうこの時代にですよ?
弊害の例えとして、その子が、



わたしは何のために、こんなにがむしゃらに頑張っているんだ….
と思い出さないとも限らない、というかその可能性の方が高いでしょ。
思い出したときに40歳だとしてみてください。
そこから再構築ってかなりの労力がいる。
だから、うちの方針は、『自分でやる』より『自分でやりたくなる』を大事にしたい。
しかし、これはわたしの考えであって、強要はできないから。
園には園の考えがあるのでしょう。
そこにズレがあるなら、それは価値観の違いで、正解不正解じゃないから。
園の先生たちが真剣に子どもと向き合っているのは、日々感じています。
だからこそ、『任意』と言うなら、その“空気の自由さ”も、子どもたちの選択として守ってあげてほしい。
ただ、それだけなんですよ。
主体性と自主性の違いとは?──教育の現場で混同されがちな言葉の正体
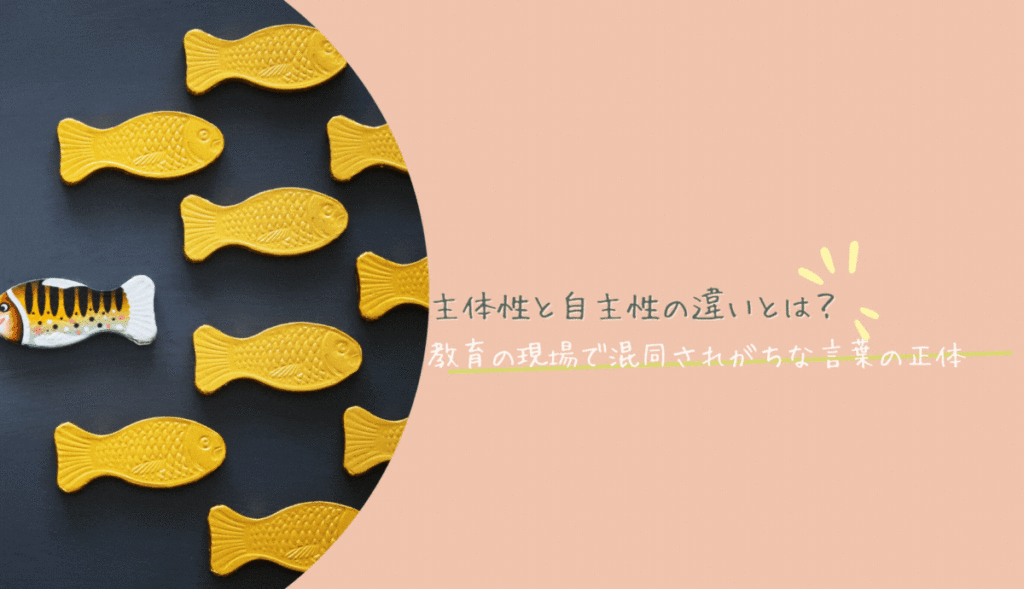
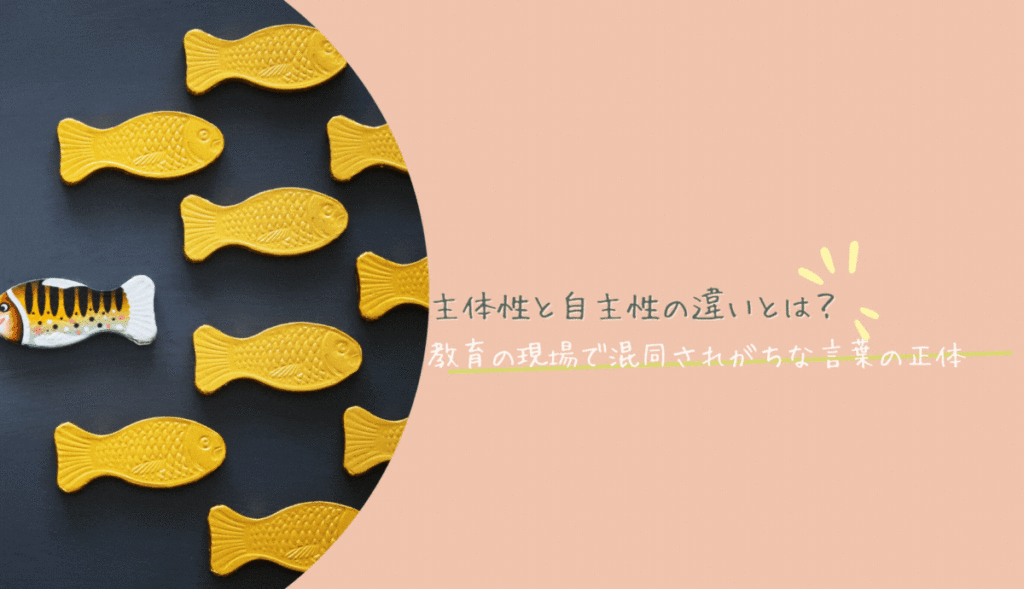
- 主体性とは『自分の意思で考え、行動すること』
- 自主性とは『決められた範囲の中で、自分で進んで行動すること』
- 教育現場で“自主性”を求める指導が、主体性を阻害する理由
① 主体性とは『自分の意思で考え、行動すること』
まず、主体性=“自分軸”の行動です。
誰に言われなくても、自分で『なぜそれをやるのか』を考えて、自分で決めて、自分で動く。
完全に“わたし発信”の世界。
言い換えると、『他人にどう言われるか』よりも、『自分がどうしたいか』で判断できる人。
言葉を選ばずに言えば──



他人の顔色じゃなくて、自分の内側と会話できる人です。
教育現場でこの主体性を育てるって、実はめちゃくちゃ難易度高い。
だって、子どもが『今はやりたくない』と言ったときに、それを認められる余白がいるから。
その余白を、余白とするのかどうか。
本人の意思があって、やらないことも選べる。
それでも周りから『できてなくても変じゃない』と思ってもらえる空気。
ここがないと、主体性って育たないんです。
例えるなら、“自由”と“フリーダム”の線引きみたいなやつ。
やってもいいけど、やらないのも許される空気。
これがあるかどうかで、子どもの判断って大きく変わる。
もっと言うと、やらないという選択が許されるものかどうか?
を大人が知っておかなければならない。
園で使う準備物って、強制ではないじゃないですか。
園内で、自分のことは自分で出来ているなら、家庭での準備は親がしてたって、誰も困らないでしょう?
そういうものは、主体性を付ける道具に活用できるんですよ。
細かく言えば、出来ない本人が困ることが出るかもしれない。けど、それもまた経験でしょう?やりたくないと自分で決めていた結果としての学びがあるから。他責にはできないんですよ。
だからむしろ、教育のチャンスでもある。
例えるなら、園で使うものの準備から、準備カードの説明から入る。
そこから、本人にやるかどうか、確認する。
そうやって、本人の意志を大事にする。
そうやって、気持ちを大事にされた子って、大人になってから強いんですよ。
② 自主性とは『決められた範囲の中で、自分で進んで行動すること』
一方の自主性はというと、『枠の中で自分からやろうとする力』です。
学校や園、つまり“大人”が設定したルールや課題があって、その中で自ら動ける子。
テスト範囲を自分で配分して勉強するとか、宿題を言われる前に出すとか、園で言われた準備カードを『自分でやる!』って張り切る、みたいなやつ。



それ、確かに素晴らしい。便利。
先生も親も大助かり。
……でも、その子、本当に“やりたい”からやってる?
もしかしたら、『怒られたくない』『褒められたい』って理由で動いてるかもしれない。
それって自主性なんでしょうか。
そもそも、準備カードの使い方を親が知らなかったら?
ここで疑問なのは、こども園の方から、
なら分かる。けど、書いてあった内容は、
自分で準備できるようにしてください。
子どもが準備した後は、保護者の方が、全部入っているかどうかのチェックをお願いします。



はい、逮捕。
ここがポイント。
自主性って、そもそも“枠”が存在して初めて成立するものなんですが、でも大事なのは、その枠の中で『自分でやるかどうか』をちゃんと自分に問えるかどうか。
問えない年代なら、親が、準備カードを持って、



自分で準備してみる?どうする?
って聞かなきゃいけない。
つまり──誰かが決めたことが前提にある。
でも、それをやるかどうかは自分で決める。
その『決める権利』があってこそ、初めてそれは“自主性”と呼べるものになる。
単なる“指示の先回り”や“空気を読む”ではないんです。
③ 教育現場で“自主性”を求める指導が、主体性を阻害する理由
で、問題なのはここから。
教育現場で『子どもに自主性を持ってほしい』ってよく聞くんですが、
- 先生『これは任意です(と言いつつチェック表あり)』
- 子ども『やった方が褒められる=やらなきゃ…』
- 親『やらせないと気まずい気がしてきた…』
これ、誰が意思持って動いてるんですか?
子どもが自分で選んでるように見えて、実は“大人の求める行動を察して従っている”だけだったりする。
つまり、自主性の顔をした“空気読み選手権”。
しかも強制エントリー制。
しかも今回はそこに保護者もエントリーさせられる。
その結果何が起きるかって?



『とりあえず正解っぽいことをやっておこう』っていう思考習慣が育つんですよ。
考える前に従う。
やりたいより、怒られたくない。
褒められたい。
問題があったら『指示されただけだから』という他責思考。
責任の所在が指示側にあるからね。
そうやって、主体性はどんどん後回しにされていく。
なのに、教育の現場ではまだ『準備できた人〜?』とか聞いてるわけです。
でも、こういう小さな仕掛けの積み重ねが、子どもの“選ぶ力”や“考えるクセ”を作っていくんです。
その考えるクセがどう影響するかって、その教育を受け馴染んだ子が小学生になると、



ぼく、先生に褒められたんだ~。
一番早くできたんだ~。
こういうことを言い出す。
これ皆普通でしょ?と思われますか?違いますよ。
周りのお友達はどう思うでしょう?
摩擦生みません?
たかだか、準備カードじゃん!
と思うかもしれないけど、ちょっと一度立ち止まって、考えたくなりません?
その“できた人〜?”って、本当に『自分でやりたくてやった人』を褒めてるんですか?
それとも、『やってくれて助かった大人のために動いてくれた子』を褒めてるんですか?
正しくは、
『お母さん、きっと助かったよね!』とか、
『〇〇くんがやってくれて、きっと家族も嬉しかったね。』って伝える方が、本来の意味に近いんじゃないかなと思います。



だから、わたしは娘に、なぜ承認欲求が強い子がいるのか、その理由や対処法も教えています。
すると、あぁ、ママの言ってたタイプね。
で終わるんですよ。
そして、『お母さん、楽できたね!嬉しかったんじゃない?』こう言えるのなら、伝えてあげたらいいんじゃない?って。
ここのロジックには気づいた方がいいと思う。
なぜ“形だけの行動”では足りないのか──子どもの心に寄り添う教育とは
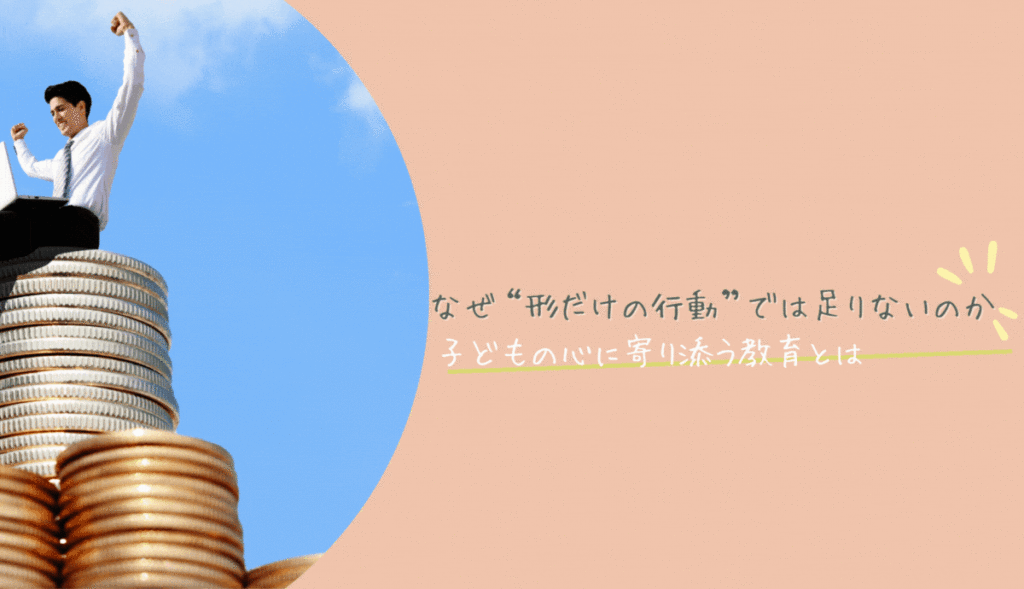
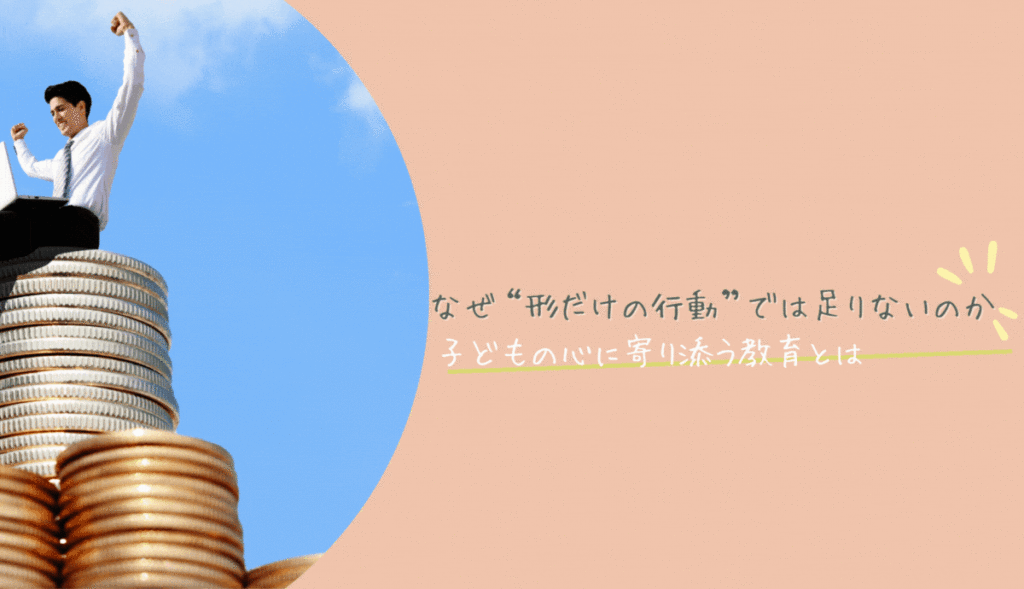
- 子どもが『やりたくない』と言うとき、何が起きているのか?
- 『できること』と『やりたいこと』のズレが生む、教育の歪み
① 子どもが『やりたくない』と言うとき、何が起きているのか?



やりたくない….
子どもがそう言ったとき、大人はつい反応してしまいがちですよね。



どうして?やることになってるよ。
あなただけができないの、わたしが嫌だし。
やったほうがいいよ。
やらないと困るよ?わたしも困るし。
めんどくさいとか理由にならないから。
でも、ちょっと待って。
“やりたくない”って、実は子どもなりの意思表示でしょ。
- 気持ちの準備がまだできてない
- 状況がよくわかっていない
- 体調が微妙かもしれない、新しい環境に慣れるのに必死
- 単純に“初めて”で不安
- そして、シンプルに『めんどくさい』
どれも、立派な“選ばない理由”。
つまり、『今はやらない』という判断を、自分でしてるんです。
なのに、大人の側が“やらない=困る・悪い・頑張ってない”とラベリングしてしまうと、子どもは『自分の気持ち』を無視して“とりあえず従う”ことを覚えるでしょ。



結果として、“できる子”は増えるかもしれないですよ。
でも、“自分の心と相談できる子”は確実に減っていく。
② 『できること』と『やりたいこと』のズレが生む、教育の歪み
ここで改めて考えてみたいのは、“できること”と“やりたいこと”の間には距離があるってこと。
- 準備は“できる”かもしれない。でも、“やりたくない”かもしれない。
- お手伝いは“できる”。でも、“今日の気分じゃない”日もある。
それを全部『できるんだから、やってね』で片付けてしまうと──子どもは“気持ち”より“行動”を優先するクセがついてしまう。
それ、大人になってから『燃え尽き症候群』や『自己否定』『他責思考』につながったりするんですよね。
自分が本当にどうしたいか、わからないまま頑張り続けてしまう。
教育って、『できるようになること』も大事だけど、それ以上に大事なのは、『どうありたいか』に気づけることだと思うんです。
そしてそのためには──“やらない”ことも、選択肢として許される空気が必要だと思う。
やらない選択もまた、選択だということ。
『やることが正義』『できることがすべて』みたいな空気の中で、子どもが“自分の心”に鈍感になってしまったら──それは、教育の本末転倒だと思うんですよ。
主体性を育てるために、大人ができること──家庭と教育現場


- 『任意』であれば、任意である態度を貫いてほしい
- 親と先生で目指す『ゴール』のすり合わせ
- 子どもに“やりたくなる理由”を育てるアプローチ例
① 『任意』であれば、任意である態度を貫いてほしい
まず、大前提として──『任意です』と言うなら、態度も空気も任意であってください。
『やってもやらなくてもいいですよ』と言いながら、『できた人〜?』って聞くの、やっぱり矛盾してますよね。
それはもう、任意じゃなくて“ほぼ指名制”です。
子どもは、言葉だけじゃなく、“空気”を敏感に察知する生き物です。
だから、大人が『任意』と言いながら“事実上の義務感”を作ってしまったら、そこにあるのは選択の自由じゃなくて、静かな圧力。
本当に任意なら、『できたらやってみようね』も、『今回はやらなくても大丈夫だよ』も、同じトーンで扱える空気づくりが必要だと思う。
② 親と先生で目指す『ゴール』のすり合わせ
そして、こども園や学校と家庭とでは、子どもにとっての“ゴール”の捉え方が違うこともありますよね。
我が家とこども園のように、園は『小学校への準備』としての“自立”を重視する。
家庭は『自分の意志で動ける子に育てたい』と思っている。
入園するときに、その園がどんな目的をもっているかを確認しておくといいと思いますが、我が家のように途中から急に方針として入れられることもあるわけですよ。
けど、何が正しくて、どれが正しくないみたいな争いをしても仕方がないじゃないですか。
準備カードという小さなことだけど、その思想と教育には波及がある。
だから、止めないといけない。
今回の件、お帳面で訴えてからは、揉めはしなかったけど、口頭でのやり取りはこうでした↓この先生は多分、主体性の意味が分かってないんだと思いました。



園のカリキュラムがあるんですよ。
今後、〇〇くんはどうされますか?
でましたよ。
じゃぁ、できなくてもいいんですね?っていう確認が。
よくある構造。
従わないなら、知りませんっていう図でしょ。
こんなものに、誰が負けるか。
一緒に戦ってやる。
ここで負けるわけにはいかないんでね。



(カリキュラム!?)わたし、主体性を育てたいんですよ。



しゅ….シュタイセイ?
あと、褒められたい!と思うことにも賛成的だった。



褒められたい!と思いながら行動して欲しくないんですよ。そういう子になって欲しくない。
もっと言うなら、それをゴールにするんじゃなくて、活力にするならいいですよ、けど、そうした考えを伝えても、そこに至るまでの指導法や考え方を知らないと、無理がある。
結局、



え?嫌…..なんですか….?



嫌ですね(このご時世、主体性くらい知っとけよ。)。
流れ的には、夕方先生とちょこっと話す→お帳面に記す→次朝、先生と話す→お帳面読んでくれて解決。
やっぱり教育方針と思いを言えたことは大きかったと思います。
我が家の場合は、結局こうなったんですよ。
特に揉めもせず、幕を閉じました。
自主性とも言い難かったけれど、もう自主性ってことにしたんです。



だってわたしが、カード配って、準備させてください、保護者チェックお願いしますってある時点で自主性でもないでしょ!?なんて言っても何も得しないから。目的は、線引きだから。
そうやって、“対立”ではなく“協働”の視点で話せる関係性ができれば(作れれば)、子どももブレずに安心して動けるようになりますよね。
③ 子どもに“やりたくなる理由”を育てるアプローチ例
主体性を育てるには、『やりなさい』ではなく、『やりたい』が芽生えるきっかけを作る方が大事。
例えば
- 『準備って何のためにあるんだろうね?』と問いかけてみる(うちは説明したけど)
- 一緒に準備してみて、『あれ、自分でできたじゃん!』と気づきをシェアする
- 『今日はやりたくないのか。じゃあどんなときならできる?』と選択肢を一緒に考える
“自分の理由”を持てるような対話や関わりができたらいいのかなと思います。
目的がわかれば、子どもはちゃんと動ける力を持ってるから。
問題は、やらされる構造の中で、その理由を失ってしまうこと。
まとめ※主体性ある子どもを育てるために、大人が育むべき“自分軸”
最後に。
子どもに主体性を育てたいなら、まず大人自身が『自分軸』で関わる』ことが大事だと思う。
- 他の子がやってるから
- 周りの目が気になるから
- 先生の目が気になるから
- できなかったら恥ずかしいから
そんな理由で判断してしまっていたら、それって子どもに『自分で考えてごらん』なんて言えないし、その思考は必ず子どもに伝染する。



うちはこういう育て方をしたいと思ってます。
今は見守りたいと思っています。
そうやって、自分の考えや価値観を言葉にできることが、子どもの“自分で考えていいんだ”という土台になると思うから。
子どもは、大人の姿をよく見てますよね。
どんなに立派な言葉より、『どう行動しているか』を肌で感じてる。
あなたも子どもの頃、そうじゃなかったですか?



だからこそ、まずは大人が自分の信じるやり方を、自分のペースでやってみる。
それが、子どもが『自分で考えていいんだ』と思える一番の近道じゃないかと思う。
わたしは、そうありたいと思ってます。
完璧は無理だけど。





コメント