選択に迷ってる時間、もったいないと思いませんか?
人生は選択の連続。
でも、選ぶのが怖くてつい先延ばしにしてしまうこと、ありますよね?その迷いが、あなたの大切な時間やチャンスを奪っているかもしれません。
本記事では、
選択に迷う本当の理由と解決策
直感を信じることがどれほど大切か?
決断を先延ばしにすることで失うものとは?
…について、分かりやすくまとめてみました。読まれたら、自分の価値観に従い、納得感を持って歩める道を選ぶことができるようになると思います。
選択に迷う本当の理由と解決策、選択を正解にする行動
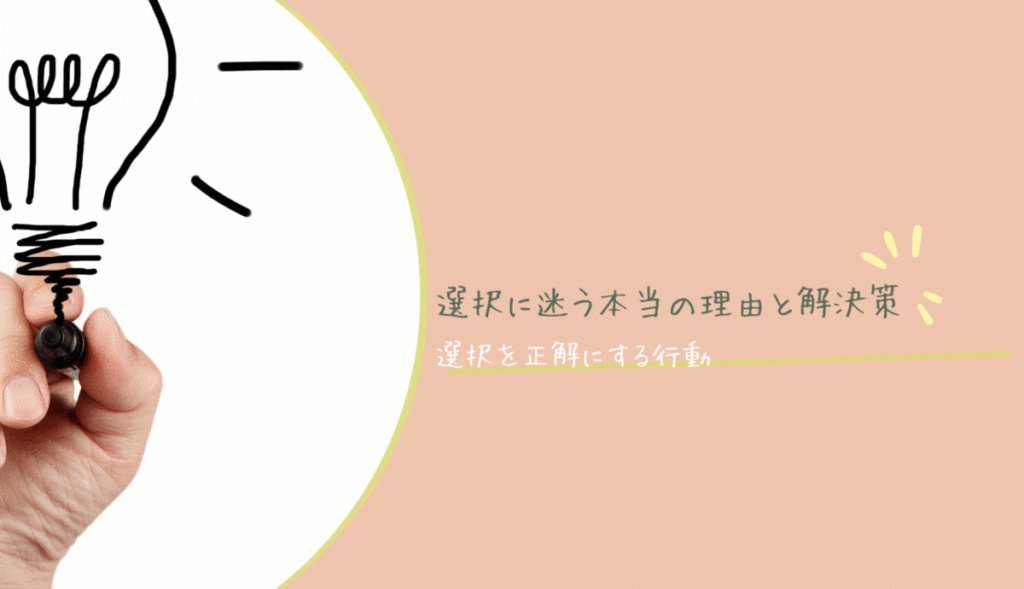
人には感情がありますよね。
感情は一時的なもので、状況によって大きく変化する。その変化が激しい感情を元に、色々なことを選択していくと危険です。

ジェットコースターのレールを外して走るようなもの。 スリルは満点、でも確実にどこかで大惨事。
なので、選択するときに、↓のような考え方を取り入れてみると、感情に流されずに直感を活かしつつ冷静な判断ができるようになると思います。
- 人による選択の基準
- 選択の迷いを生むその他の要素
- 選択の迷い※複数の基準が競合している
- 選択に迷わないための方法
- 選択に迷ったとき※判断のための発言)リストと例
- 選択を『正解』にする行動
①人によって違う選択の基準
人によって、選択する基準が異なってきます。皆同じじゃない。
- 価値観が明確な人 → 『お金よりも自由を大切にする』『安定よりも挑戦したい』など、損得ではなく信念を優先する。
- 損得勘定で動く人 → 『どっちが得か?損か?』という基準で選択をする。
- 直感を重視する人 → 『こっちのほうが楽しそう』『ワクワクする』といった感覚に従う。
- 長期的な視点を持っている人 → 短期的な損を気にせず、将来的な成長や幸福を重視する。
- 精神的に悟った人 → 損得という概念に縛られず、物事を広い視点で捉える。
そして、選択する基準には、環境や自身の性質の要素も関わってくる。
②選択の迷いを生むその他の要素
- 情報不足
判断基準が明確でないと、決断を先延ばししがち。 - 選択肢が多すぎる
『選択のパラドックス』とも呼ばれる現象で、選択肢が増えるほど迷いやすくなる。 - 周囲の影響
『他人にどう思われるか』を気にして、自分の本音よりも『社会的の正しい選択』を求めてしまう。 - 完璧主義
『最適解を選びたい』『失敗したくない』という思いが強すぎると、結果迷い、決断を先延ばす。 - 未来の不確実性
どんな選択も未来の結果は100%確実ではないという思いから、『本当に良かったのか?』と悩むことになる。 - 自分の本音が分かっていない
『本当にやりたいこと』よりも『なんとなく選んだほうがいい気がする』という判断が増える。
③選択の迷い※複数の基準が競合している
『基準がない、もしくは明確でないから迷う』以外に、さらに深い理由として 『基準がブレている』『複数の基準が競合している』ことが原因の場合もあります。
例えば、、
『自由を大切にしたいけど、お金の安定も欲しい。』
『新しいことに挑戦したいけど、失敗したくない。』



こんな風に、価値観や基準が揺れている場合、『どちらの基準を優先するのか?』を明確にすることは大事。
解決策としては、選択の優先順位を決めるといいです。
短期・中期・長期で考えるのであれば、短期的には収入が安定する仕事が必要だけど、長期的には独立を目指す。自分にとって”より重要なもの”を決めて選ぶとして、安定よりも挑戦が大切なら、挑戦を優先する。
④選択に迷わないための考え方
- 自分の価値観を明確にする → 何を大切にするのか決めると、選択が楽になる。
- 何が最優先か?→自分にとって、何が最優先か?を考える。
- 損得だけでなく、成長につながる選択を考える → 『面白いか』『学びがあるか』を重視。
- 完璧を求めない → 『どちらを選んでも最善にできる』と思えば決断しやすくなる。
- 選ばなかった道を悔やまない → どちらを選んでも、結局『選んだ後の行動』が重要。
- 選択肢を3つまでに絞る → 情報を集めすぎると判断が鈍るため、候補を3つ程度に絞る。
- 『最適解』ではなく『納得解』を選ぶ → どんな選択も完璧ではないことを受け入れ、『どちらを選んでも自分が納得できるか?』を基準にする。
- 『損をしてもいい』と考えてみる → 意外と大きな問題ではないと気づくことが多い。
- 直観を大事にしてみる → ただし『経験による直感(磨かれた直感)』と『衝動的な直感(思いつきの直感)』を区別する。
⑤選択に迷ったとき【判断のための発言リストと例】
選択に迷ったときは、以下のような『発言』を使って自己対話をすると、決断がしやすくなります。
迷いがある時に問いかける言葉
- どちらを選ぶ方が、後悔が少ない?(批判的思考)
- もし、時間もお金も無制限にあったら、どっちを選ぶ?(哲学思考)
- 今すぐ決断しなければいけないなら、どっちを選ぶ?(素朴思考)
- もし誰にも批判されないなら、どっちを選ぶ?(天邪鬼思考)
誰かに相談するときの言葉
- 私がどちらを選ぶべきかじゃなくて、あなたならどうする?(批判的思考)
- この選択の利点を第三者の視点で教えてほしい。(構造化思考)
- 私が後悔しないために、大事なポイントは何だと思う?(道具思考)
自分自身の決断を確認するための言葉
- 選んだ後の自分を想像して、心が軽くなる?(素朴思考)
- この決断を10年後の自分自身はどう評価するかな?(哲学思考)
- どちらを選んでも失敗した場合、納得できる?(道具思考)
例えば、Aさんに、勉強を教えて欲しいと言われた。自分は受験勉強中だ。Aさんが教えて欲しいと言っているところは、自分でも復習が必要なところである。
この状況で、どの選択をするか?
- 自分の価値観を明確にする(哲学思考)
『自分の受験勉強を優先するのか?』
『他人を助けることを重視するのか?』
『どの選択が自分にとって納得できるか?』 - 何が最優先なのか?(天邪鬼思考)
社会に出たら、他人を助ける能力の方が大事では?
受験は一度しかない、他人に構っている場合ではない。 - 損得だけでなく、成長につながる選択を考える(道具思考)
Aさんに教えることで、自分の理解も深まる可能性がある。
ただし、自分の勉強時間が短縮され、負担が大きくなるリスクもある。
もし『教えるのが楽しい』と感じたら、『将来的に教育に関わる道が向いている?』という発見につながるかも。 - 完璧を求めない(構造化思考)
どれを選んでも、やり方次第で一緒にできる。
Aさんに考えさせる工夫をするなど、方法はある。 - 選ばなかった道を悔やまない(批判的思考)
教えることを選ばなくても、『今は自分の勉強を優先するのが最善。』と納得できるならOK。 - 選択肢を3つまでに中止(構造化思考)
『教え続ける』『完全に断つ』ではなく、『短時間だけ手伝う』などの選択肢も考える。 - 『最適解』ではなく『納得解』を選ぶ(哲学思考)
『完璧な選択肢はない。どれが自分にとって納得できるか?』
Aさんを助けつつ、自分の勉強もできるバランスを考える。 - 『損をしてもいい』と考えてみる(道具思考、天邪鬼思考)
教えることで少し時間を使っても、それが自分の覚悟ならOKかも。
一見、無駄に見える行動の方が結果的に大きな学びになるのでは? - 直感を大事にしてみる(素朴思考、批判的思考)
もし『教えるのが楽しい』と感じるなら、それを活かす道もある。
逆に『今は自分の勉強に集中すべきだ』と強く感じるなら、それを尊重する。
『Aさんに教えることが、自分の学習にもプラスになるなら、短時間だけ教える。』または『自分の勉強を優先したほうがよいと納得できるなら、申し訳ないが今は断る。』自分の状況と価値観をもとに、納得のいく選択をする。



こんな風に、複数の考え方がありますが、この選択を正解にしていく行動というものがあります。
⑥選択を『正解』にする行動
基本的に、これはめちゃくちゃ大事。
- 第一段階(論理的に決断する)
- 感情を排除し、価値観・長期的な視点・環境の影響などを基準に選択。
- →『この選択は自分にとって合理的?』を問いかける。
- →色々な人の(自分も)立場を考慮する。
- 第二段階(感情と向き合う)
- 『この選択をして、自分はどう感じるか?』を確認する。
- →不安があるなら、具体的に何が不安なのかを分析。
- →ワクワクするなら、その選択は正しい可能性が高い。
- 第三段階(選択を正解にする行動)
- 選んだ後に、『これを最善の選択にするために何ができるか?』を考える。
- →リスクをコントロール可能な範囲と不可避な範囲に分ける。
- →選択の柔軟性を確保し、軌道修正できる仕組みを作る。
- →決断したことに納得し、後悔しないように行動する。
こんな風に、『決断 → 感情と向き合う → 納得して前向きに進む』という流れを意識することで、選択の後悔を減らして、最善の道を歩むことができるようになります。



複数のパラダイムから、自分がした選択による行動範囲を明確にしておくと、後が楽。何がきても動ける。
視点も大事↓
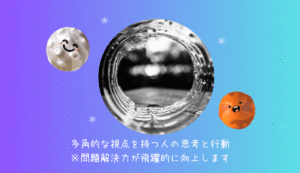
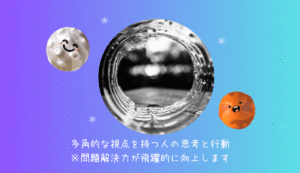
直感を大切にする!選択に迷ったときの決め方※初印象は意外と正しい
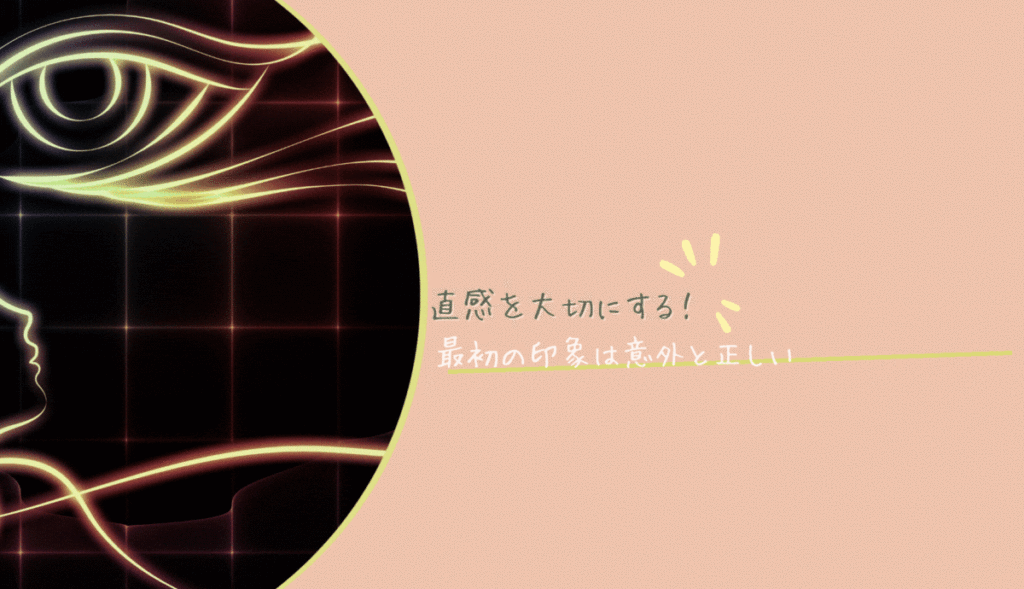
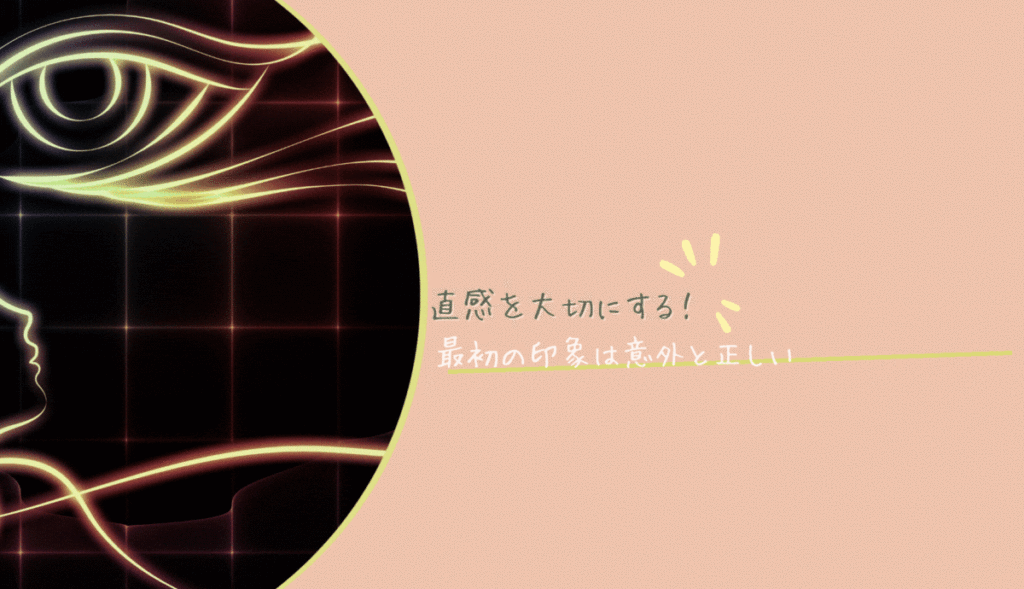
直感は、私たちの心の中で瞬時に生まれる感覚や判断。特に選択に迷ったときと決め方としては、最初の印象を信じることは非常に重要だったりもします。
なぜなら、直感には無意識のうちに蓄積された知識や経験が反映されているから。
- 直感の力
- 直感の使い方
①直感の力
直感にはいくつかの利点があります。まず、↓の点を考えてみてください。
- 迅速性: 複雑な分析をする時間がない場合でも、直感を頼りに結論を出すことができます。特に緊急を要する状況では、心の声に従った方が良い結果を得られることが多い。
- 経験に基づく判断: 過去の経験が直感に影響を与えるため、知らず知らずのうちに正しい選択をすることがあります。たとえば、一度苦い経験をした場合、それに類似した選択肢に対して直感的に抵抗感を抱くことがある。
- 自己理解の向上: 直感を大切にすることで、自分自身の価値観や信念をより深く理解できるようになります。どの選択に対して強い感情を抱くのかを意識することが、自分を知る大きな一助になる。
②直感の使い方
ワクワクや直感はとても大事、だけど、すべてをそれだけで決めるのは危険。



憧れていた人気グループの推しから、SNSにメッセージが。
えっ!?憧れの芸能人からDMが!?ヤバい、これは運命!!
『ちょっと金銭的に厳しくて…』の一言で、20万円振り込むような行為。お前がヤバい。
冷静に考えれば、人気グループなのに20万に困るって何?てなる。
直感には 『経験に基づく直感(磨かれた直感)』 と 『衝動的な直感(思いつきの直感)』 の2種類があり、それを見極める力が必要です。
- 経験に基づく直感(磨かれた直感)
- 例:熟練した投資家が『これは儲かる』と直感的に判断する。
- 衝動的な直感(思いつきの直感)
- 例:『楽そうだからこの仕事にしよう』『ワクワクするからやる』だけで決めると短絡的になりがち。
ワクワクすること自体は悪くないんです。むしろ、ワクワクは『方向性のヒント』になることが多い。だからって、それをそのまま行動に移すんじゃなくて、『なぜワクワクしたのか?』を論理的に分析することが重要。
具体的な考え方としては、、
- 直感がどこから来ているのかをチェック
- これは過去の経験や知識に基づいてる?
- 単なる感情的な興奮や憧れじゃない?
- 論理的に補強する
- この選択のリスクは何?
- 自分の長期的な目標に合ってる?
- この決断をした人で成功した例・失敗した例はある?
- 最終的に『論理+直感』のバランスで決める
- 直感(ワクワク)を大事にしつつ、論理的な判断で確認。
- もし論理的に破綻しているなら、一度立ち止まる。
NG:ワクワクだけ
『楽しくないから会社辞める!』
→ 貯金ゼロ、スキルなし、即詰み
『えっ!?憧れの芸能人からDMが!?ヤバい、これは運命!!』
→ 『ちょっと金銭的に厳しくて…』の一言で、20万円振り込み。翌日、アカウント、推し、20万円消滅。
NG:論理だけ
『安定が大事だから一生この仕事!』
→ 本当はやりたくない仕事、社畜と化す
『芸能人がDMを送ってくるわけがない。すべて詐欺。』
→本物の公式ファンイベントの当選DMすら疑い、推しに会えるチャンスを捨てる。
OK:バランス
『ワクワクする仕事をしたい!でも準備してから辞めよう。』
→副業からて収益が安定してから独立!
『推しからDM!?…いや、普通に考えて怪しい。まず確認しよう。』
→詐欺アカウント?冷静に判断し、振り込まずに回避!
→ 『これ、詐欺です!みんな気をつけて!』とSNSで注意。
→結果、推しの運営も警告を出し、詐欺アカウントがBANされる。推し活、健全に継続。
直感だけでは危ういが、論理だけでは面白みに欠ける。



だからこそ、『ワクワクを感じたら、一度立ち止まって考える癖をつける』ことが、賢い選択につながります。
選択を迷ったときの決め方※先延ばしにすることで失うもの


選択を先延ばしにすることは、多くの人が無意識に行ってしまう行動です。
これには多くのリスクや損失が伴います。ここでは、その具体的な影響についてまとめてみました。
①時間の損失
選択を先延ばしにすることで、最も明確に失うものは『時間』。
考え抜いた上で意図的に選択を延ばすのなら意味があります。
理由もなく決断を避けているだけなら、それが未来に繋がっていく。 新しい仕事を探すかどうか迷っているうちに、貴重なチャンスを逃してしまうかも知れない。
大切なのは、『なぜ今決めないのか?』という理由を明確にすること。
②機会損失
選択を先延ばしにすることで、せっかくの『扉』が閉まってしまうことも。
チャンスというのは、まるで流れ星のようなもので、一瞬の輝きを逃せば二度と手に入らないかもしれない。
『あとで願い事しよう』と思っていたら、すでに星は消えている。そんな後悔をしないためにも、決断のタイミングを逃さないことが大切。
③自信の低下
選択を避け続けると、『自分は何も決められない人間なのでは?』とネガティブな自己認識が生まれます。
しかし、決断を積み重ねることで自負が生まれ、人生の歩みがスムーズになる。
例えるなら、初めは不安定だった自転車のペダルを漕ぎ続けるうちに、バランスが取れ、やがて自由に走り出せるようになる感覚に似てます。
決断は、自分の人生のハンドルを握る力を養うもの。
逆に、決断を避けることで自己不信が強まり、大きな不安を生んでいく。次の選択がさらに難しくなる悪循環に陥ることもあります。小さな決断を積み重ねることが、最終的には大きな選択をスムーズに行う力になります。
④ストレスと不安の増加
先延ばしにするほど、頭の中は『やるべきことリスト』で溢れ、考えることが増えすぎる。
タスクが積み重なることで思考が混乱、冷静な判断が難しくなり、結果としてさらに決断を避ける悪循環に陥ることもあります。
考えることが増えれば増えるほど、行動に移すエネルギーは奪われるし、最終的には選択をすること自体が精神的な負担になっていく。
⑤魅力的な選択肢の消失
『今はまだ決めなくても大丈夫』と思っていたら、気づいたときには選べたはずの選択肢がどんどん少なくなり、いつの間にか後戻りできなくなっている……。時間が経つにつれ、状況は変わり、以前は選べたはずの道が閉ざされてしまうこともある。いざ決断しようとしたときには、もう以前の自分には戻れず、後悔の念だけが残ることも。選択を先延ばしにすることが、実は最大のリスクなのかもしれない。
選択を先延ばしにすることで失うものには、時間や機会、自信、さらにはストレスまで、多くのものがあることがわかります。これを理解することで、より良い選択をするための行動を促していくことが大切。



選択や決断をする際の大きな盲点は、迷っている間も時間が経過し、機会を失ってしまうという事実。結果、現実を受け入れることが困難になり、過去に執着することになる。けど、時間は進んでるから。あれやこれやしてるうちに、状況や環境が変化するでしょう?それを知っとかないといけない。
けど、やっちゃうんですよ、みんな。
そこで大事なのが、『決断の期限を設ける』というシンプルかつ実践的なアプローチ、期限を設けることには、いくつかの明確な利点があります。
- 行動を促進する: 何となく迷っている状態から、計画的に進むための推進力になる。
- 判断基準を明確にする: 期限を設けることで、決断するための基準を設定しやすくなります。たとえば、『今週中に決める』といった明確なタイムフレームがあれば、その時間内に情報収集や分析を行い、より良い選択が可能になる。
- 精神的負担の軽減: 無限に続く迷いや悩みは、精神的な疲労を招きます。期限を決めることで、心の中のさまざまな思考を整理し、スッキリとした気持ちで選択に臨むことができるようになる。



しかし、これもまたすべて(選択を延ばす行為も全て)、宇宙の采配であることもある。全ては必然。
↓ナポレオンの人生で比較検討しています。
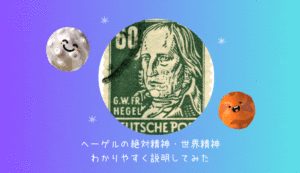
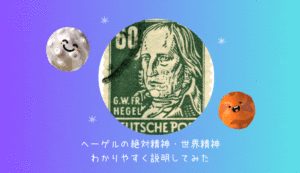
選択に迷ったときは、自分の感覚を信じてみる


- 『委ねる』と考えてみる
- 自分に問いかける
- ちょっとリフレッシュ
- まとめ
①『委ねる』と考えてみる
あまりにも複雑で、色々考えてみたけれど最善が分からない!こうなることもあります。
そういうときは、わたしは『委ねながら進む』という選択をすることにしています。要するに、出たサイの目に対して、受容しながら答えて行く。



ただこれ、圧倒的に自分を信じることが大事。
たまに、合ってるのか…と不安になることだって、そりゃあるんですよ。
人間だもの。
けど、それでも、大丈夫。これで大丈夫。強く思うんです。
例えるなら、旅の途中で寄り道をしてみるようなものに似ていて、予定通りの道を進まなくても、思わぬ景色や出会いが待っているかもしれません。
宇宙の流れ(大きな流れ)に身を委ねることでもあります。この考え方は、道具思考と哲学思考の組み合わせに近いと思います。そして、全体の流れを見る構造化思考が大事になる。
道具思考(全てを学びに変える)
『状況を受け入れ、その中で最適な行動を考える。』
→ 選択する時間を減らし、行動することで得られる学びを最大化する思考。
→ どんな経験も無駄にせず、『これをどう活かすか?』と考え、前に進むためのツールとして利用する。
哲学思考(宇宙の流れを信じる)
『どんな道にも意味がある。流れに身を委ねることで新たな可能性が開く。』
→ あらゆる選択に『最も正しいもの』はなく、そこに学びや必然性があると考える。結果、自身の選んだものが最善になる。
→ 偶然の出来事にも深い意味を見出し、流れに逆らうのではなく、それを活かして次元を上げる視点を持つ。
構造化思考(全体を整理し、最適な形に組み立てる)
『バラバラな情報や経験を整理し、全体像を理解、視点を変えながら、より良い選択を導き出す。』
→ 点で捉えるのではなく、すべての出来事を『大きな流れの一部』として分析し、戦略的に活用。
→ 直感や学びだけに頼らず、論理的に整理し、最もバランスの取れた選択を見つけ出すことで、道具思考・哲学思考をより効果的に活かせる。
こうしていると、気持ちは楽になりますが、自分自身を理解していることが重要です。
あと、五次元思想の理解が大事。
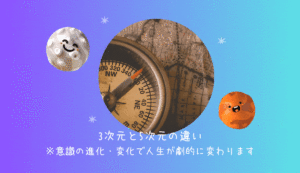
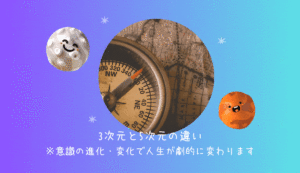
②自分に問いかける
『自分は本当にどうしたい?』『これって心の底からやりたいこと?』と、常に自分に問いかける。
こういう問いかけが、人生のコンパスみたいなもの。
立ち止まって確認するだけで、『あ、こっち行けばいい』と気づけることがある。
どんどん自分に質問して、進むべき道を選ぶといいです。
③ちょっとリフレッシュ
考えすぎると、頭の中がぐちゃぐちゃになって、何が正しいのか分からなくなることってあるんですよ。
そんな時は、一旦リフレッシュ。
散歩したり、好きな音楽を聴いたり、コーヒー片手にボーッとしたり、お風呂入ったり。
気分転換すると、不思議と『あ、こっちの方がいいかも』って答えが見えてくることがあります。
④まとめ
どう選択しても、自分が納得すれば、それが正しい道になります。
自分を見つめて心に従うことは、自分らしい人生を選ぶための大切な指針。直感を大切にしながら、気持ちの変化を観察しつつ、自分が本当に望む道を選んだ方がいい。そのためには自己理解が不可欠です。
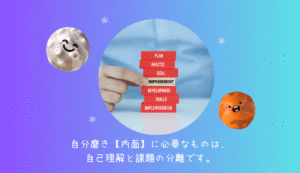
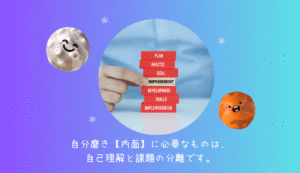
まとめ
人生は、無数の選択の連続。
どの道を選ぶかによって、自分の未来は変わっていきます。ここで、本当に大切なのは『どの選択をするか』ではなく、『選んだ道をどう歩むか』でもある。
完璧な選択かどうかなんて、歩いてみないとわからないから。
求めるのではなくて、どんな選択も自分の手で正解にしていくという覚悟を持つことが、自分の自負になり、強さになって行く。その思考による行動には不思議な力が宿ります。
その覚悟を持って進むことで、思いがけないチャンスや縁が巡ってくることがある。
そうして歩いて行くことが、より充実した人生につながる。
迷いが生じるのは、まだ見ぬ未来に対する不安があるから。しかし、その不安を完全に取り除くことはできません。だからこそ、自分の心の声を信じ、最も納得できる道を選ぶことが重要。
選択は『終わり』ではなく、『始まり』。どんな選択も、それを選んだ自分を正解にするのは、自分自身の行動と信念次第。
自分の人生を切り開いて、運を見方につけるには、決断力が大事なんですよ。自分で決断する力が。最初は1週間とかでもいいから、誰にも何も聞かないで、自分で決めるということを意識して生活してみるのもいいかもしれません。
やってみると分かると思うけれど、結構大変だったりする。



最終的に後悔しない選択とは、自分の価値観に従い、納得感を持って歩める道を選ぶことだと思っています。わたしはいつも『どの道、私が選ぶ道が最善になる。』そう思って選択しています。
こちらの記事では、選択ミスしてしまった後の行動についてまとめています↓





コメント