わたし、子どもが2人いて、教育に興味があります。
知識をパンパンに詰め込んで、このブログに吐露して行ってるんですが、今回は『子どもの主体性』についてまとめています。
学校教育(主に西洋的教育)では『主体的に学ぶことが大切』と言われていますが、その『主体性』が本物であるためには、『深い思考力』が不可欠だと思っています。
主体的に行動できるようになるためには、思考法を知らないといけない。その思考法を元に動くことになるから。
『主体性を持って取り組む』というのは、自分の意志で考え、判断し、行動することを意味します。
しかし、、

思考力が足りていないと、『見せかけの主体性』になってしまわない?
という持論がでたんです。『主体的に学ぶ』『主体的に行動する』と言っても、正しい思考法がなければ、ただの『自己流』になる。つまり、全然主体的に動けない。



多分、そうなる。だって、思考法を知らないのに、どうやって考えて主体的に動けるの?とも思えるから。すごく偏る。
つまり、『主体的に取り組む』と言っても、正しい思考法がなければ、その主体性は間違った方向に行く可能性が高い。だからこそ、主体性を本物にするために、子どもの思考法を鍛えること(根っこにアプローチする、東洋的教育)が最も大切だと思う、というのをこのブログにまとめてみました。
なぜ教育が『思考法』にたどり着かないのか?3つの理由
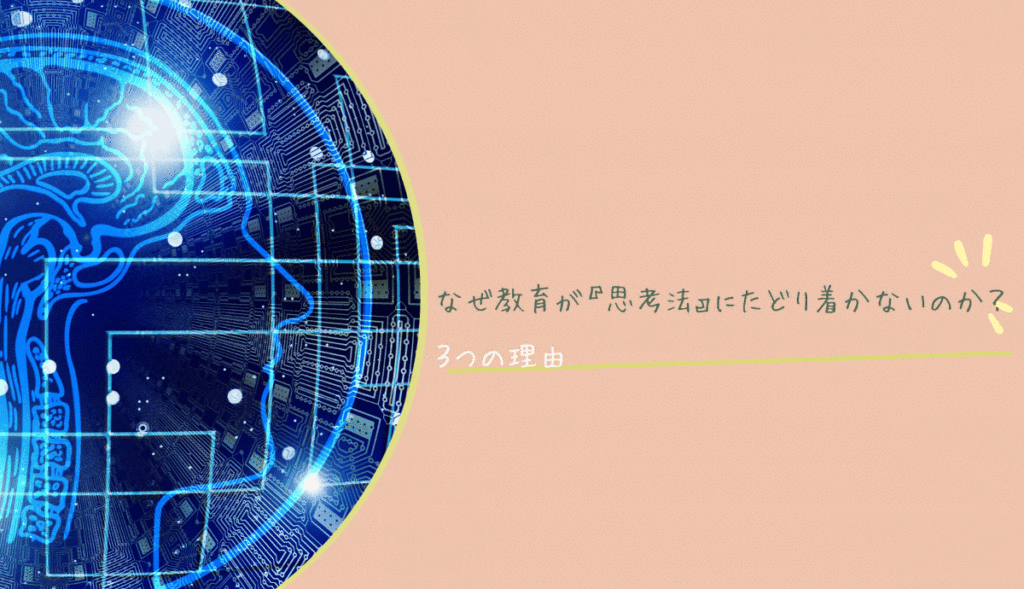
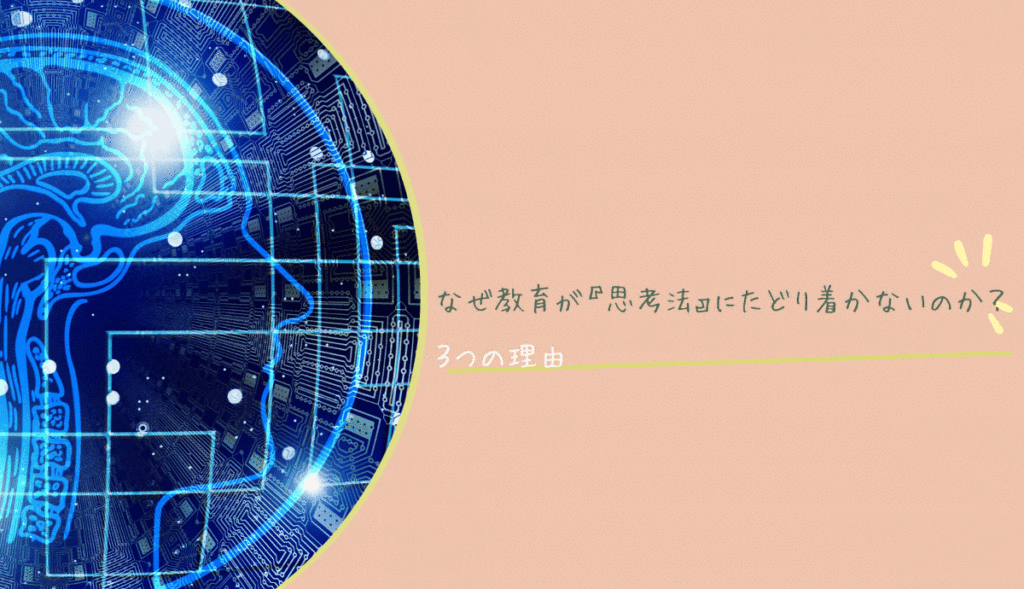
日本の教育は、明治時代に西洋の教育制度を導入して以来、『知識の習得』『論理的思考力』『問題解決能力』の育成を中心とする西洋的教育モデル(枝葉に注力した教育法)を採用してきてます。
- 西洋的な『知識重視』の教育が基盤にあるのでは?と推測
- 『思考法』を育てずに、いきなり『主体性』を指導する
- 枝葉(主体性)ばかりを整え、根本(思考法)が育っていない
① 西洋的な『知識重視』の教育が基盤にあるのでは?と推測
- 日本の近代教育は 西洋の『知識習得モデル』を取り入れ、『正解を覚える』ことに重点を置いてきた
- そのため、『考える力(思考法)』よりも、『答えを正しく導き出すこと』が評価される教育文化 になっている
- 思考法を学ぶ機会が少ないまま、『主体的に学べ』と言われても、何をどう考えればよいのかわからない
日本では、先生が一方的に知識を伝え、児童・生徒がそれを聞くというスタイルが長く続いていて、それを打破すべく昨今、自分で考える力を育てるという教育法にはなってきてはいるものの(グループディスカッションも増えてると思われる)、そもそもその教育スタイルを考える方たちも西洋的教育を受けているため、思考が枝葉に向かいやすいのでは、、、?という持論が出ています。



自分の意志や判断に基づいて行動するにしても、その意志と判断はどこから?思考からですもんね。もっと言うと、主体的って何?とかなる。何なら自主性と何が違うの?とかいう人もいる。全然違うよ。
↑ ね?行動の前に、思考があるでしょう?
② 『思考法』を育てずに、いきなり『主体性』を指導する
- 昨今、『探究学習』『グループワーク』『アクティブラーニング』が推進されていると感じますが、『どう考えればいいのか?』を学ばないまま『自分で考えろ』と言われるため、表面的な学びになりがちじゃないかと感じる
- 考え方のフレームワークがないまま『主体性』を持とうとしても、それは単なる『感覚的な判断』や『場当たり的な行動』になってしまうような気がする



『主体性』は思考法の上に成り立つのに、、
考え方の基礎を作れない。
③ 枝葉(主体性)ばかりを整え、根本(思考法)が育っていない
- 『自分の意見を持とう!』と言われても、そもそも『意見を持つための思考法』がわからない
- 『グループワークで議論しよう!』と言われても、論理的な議論の仕方を学ばずに行うため、深い対話にはならず、形だけの活動になる
- 『探究学習をしよう!』と言われても、『何をどう探究するのか?何のために行くのか?』が分からないまま進められる、とりあえず行く



『主体性を持つこと』自体が目的化し、本来の『思考の基盤づくり』が無い。
考え方が分からないし、何のために〇〇をするのか?という概念がないまま進む。
子どもたちは一見、意見をしっかり持っているように見えても、深い論理や裏付けがないため、根拠のない主張をしやすくなったりする。
『これはダメだと思う!』と言えても、それがなぜダメなのかを論理的に説明できない。目先の問題には対応できても、変化に適応できない。例えば、これまでのやり方でうまくいっていたのに、状況が変わったので対応できなくなる。
教えることができる親がいたらラッキー、けど、いなければほぼ感情論、もしくは素朴思考だけが育ちやすいのではないかと勝手に推測しています。
では、大事な6つの思考法とはどんな思考法でしょうか?
子どもの主体性に大切な教育に大事な6つの思考法
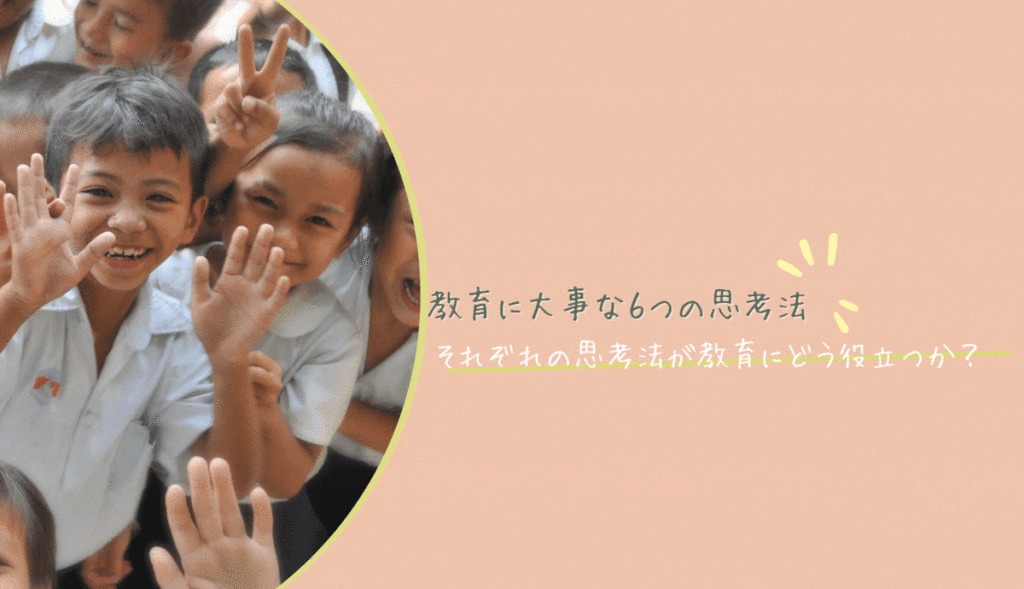
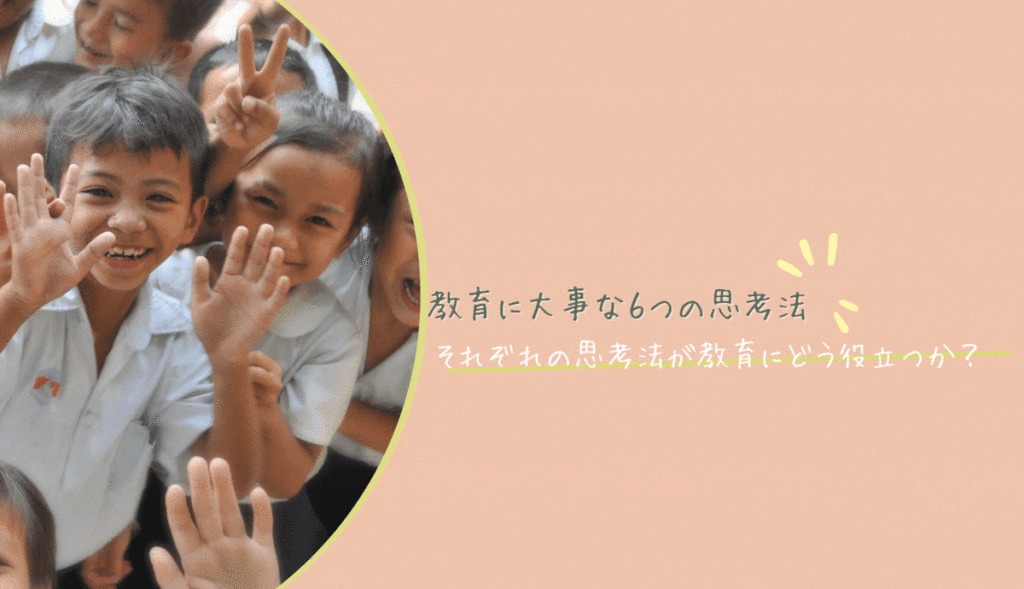
AIの進化などにより、社会の変化が速く、複雑な問題に対応する力が求められる現代では、『多角的な思考法』を身につけることが重要で、『素朴思考・天邪鬼思考・批判的思考・構造化思考・道具思考・哲学的思考』は、これからの時代に必要な『考える力』を育む上で非常に有効だと考えています。



なので、教育にこれらの思考法を意識的に取り入れることは大きな意義があると思ってるんです。えぇ、もちろん勝手に。
これ、個人のブログだから。
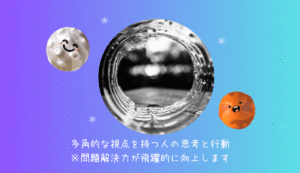
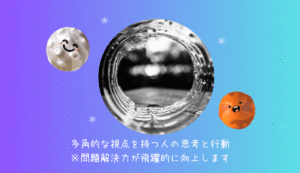
それぞれの思考法が教育にどう役立つか?
教育に取り入れた方がいいと思う理由を、それぞれの思考法ごとに見ていきます。
| 思考法 | 教育における役割 |
|---|---|
| ① 素朴思考(直感的・本能的な発想) | 子どもが持つ『純粋な疑問』を大切にし、自由な発想力を育む。創造的な学びの原点。 |
| ② 天邪鬼思考(逆説的・反対視点からのアプローチ) | 『なぜ逆の考え方もあるのか?』と問い直し、物事を一面的に捉えない力を育てる。 |
| ③批判的思考(多角的な検証) | 情報を鵜呑みにせず、根拠を分析し、フェイクニュースや偏った情報を見抜く力を育てる。 |
| ④ 構造化思考(システム・全体の関連性を整理する) | 物事を部分ではなく全体の仕組みとして理解し、論理的に考える力を養う。 |
| ⑤ 道具思考(実用的な視点) | 『この知識はどう使えるのか?』という視点を持ち、学びを実生活や社会と結びつける。 |
| ⑥ 哲学的思考(根源的な問いを考える) | 『なぜ学ぶのか?』『幸せとは?』といった深い問いを持ち、価値観や人生観を深める。 |
子どもの主体性を育てる6つの思考法を教育に取り入れる具体的な方法
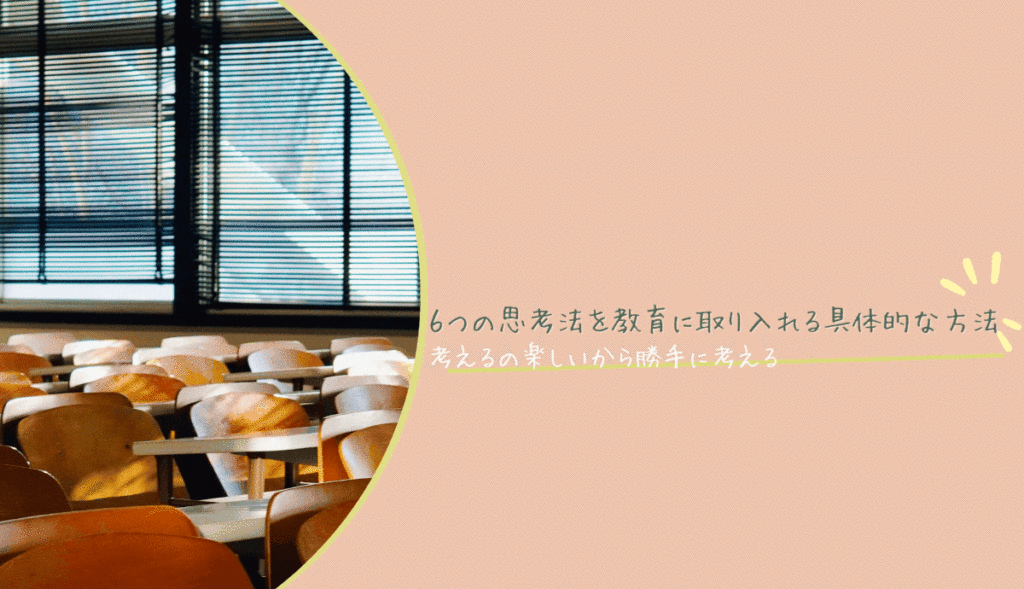
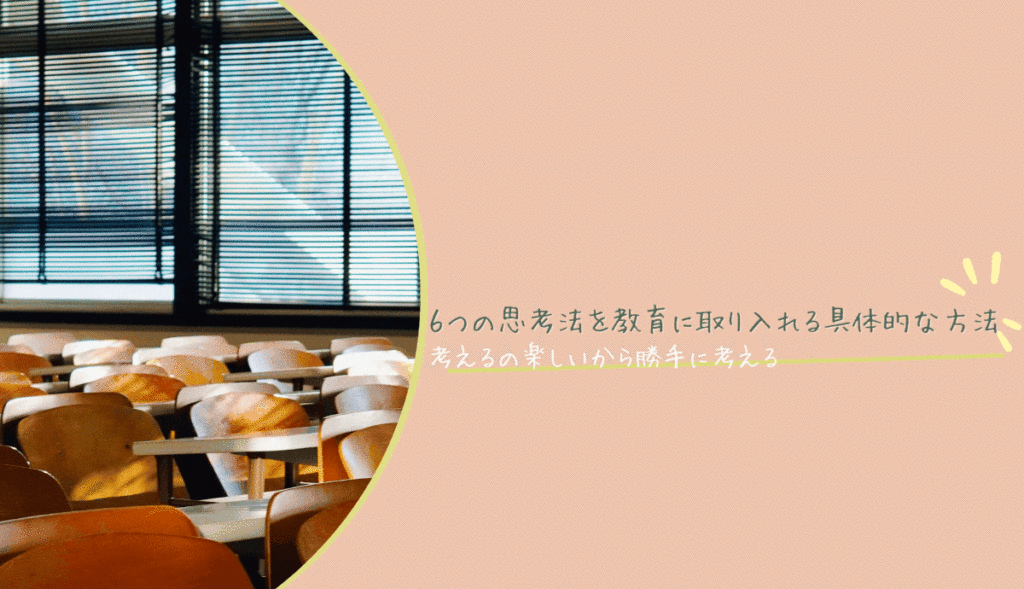
こんな授業あったら、面白い。『考えるの楽しいから勝手に考える』の巻。



どうやってこれらの思考法を教育に盛り込むか? 具体的なアイデアを勝手に考えてみる。
- 素朴思考:子どもの『なぜ?』を大切にする
- 天邪鬼思考:『逆の立場』で考える
- 批判的思考:『情報を疑う力』を養う
- 構造化思考:『全体の仕組み』を理解する
- 『学びを社会でどう使うか?』を考える
- 哲学的思考:『そもそも〇〇とは?』を考える
① 素朴思考:子どもの『なぜ?』を大切にする
自由に疑問を出し合う時間を作る(『問いの授業』)
例:『どうして水は透明なのに、海は青く見えるの?』『どうして学校に行かなくちゃいけないの?』など、直感的な疑問を出し合い、議論する。
目的:自分で疑問を持ち、考える習慣を身につける。
② 天邪鬼思考:『逆の立場』で考える
反対意見を考えるディベート
例:『宿題は必要か?』というテーマで、普段の考えとは逆の立場を取って議論する。
つまり、自分が普段『宿題は必要だ』と思っている人は『宿題は不要だ』という立場で議論し、逆に『宿題はいらない』と思っている人は『宿題は必要だ』という立場で議論する。
目的:一つの考えに固執せず、多様な視点を理解する力を養う。
③ 批判的思考:『情報を疑う力』を養う
フェイクニュースを見抜く授業
例:本物と偽のニュース記事を比べ、どの情報が信頼できるのかを議論する。
食べ物に関するニュースの真偽を比べる
本物のニュース(信頼できる情報)
野菜を食べると、ビタミンが取れて健康に良い(出典:厚生労働省や科学的な研究結果)
偽ニュース(フェイクニュース)
チョコレートを毎日食べると、身長が10cm伸びる!(出典:子ども向けの怪しいウェブサイトやSNSの投稿)
議論のポイント
- チョコレートを食べるだけで本当に背が伸びるの?
- お医者さんや科学者が言っていることなの?
- 試した人が本当にいるの?
目的:『情報を鵜呑みにしない力』を育て、社会での判断力を強化する。
④ 構造化思考:『全体の仕組み』を理解する
マインドマップを使った授業
例:歴史の授業で、『戦国時代の流れ』を単なる出来事の暗記ではなく、因果関係を整理する。
年号だけでなく、流れが分かる図を作ってみる。『なぜ?』『どうなった?』を矢印でつなぐ。
(1) 応仁の乱! → 国がバラバラ → 戦国時代に!
(2) 織田信長が天下統一に向かい、戦い方を変えた! → 力を強くした! → けど裏切られる!
(3) 豊臣秀吉が天下統一! → ルールを作った! → 亡くなった後、権力争いに!
(4) 徳川家康が戦いをなくし、江戸時代に!
目的:『個々の知識』ではなく、『全体のつながり』を理解する力を育てる。
⑤ 道具思考:『学びを社会でどう使うか?』を考える
学んだことを実際に使うプロジェクト
例:算数の授業で『お店を開くシミュレーション』を行い、計算の実践力を養う。
目的:『学んだ知識=役に立つもの』と実感し、学ぶ意欲を高める。
⑥ 哲学的思考:『そもそも〇〇とは?』を考える
哲学対話の授業
例:『正義とは何か?』『幸せとは?』といったテーマで自由に議論する。
目的:答えのない問いについて考え、自分の価値観を深める。
6つの思考法はなぜ必要?大事なのか?3つの理由
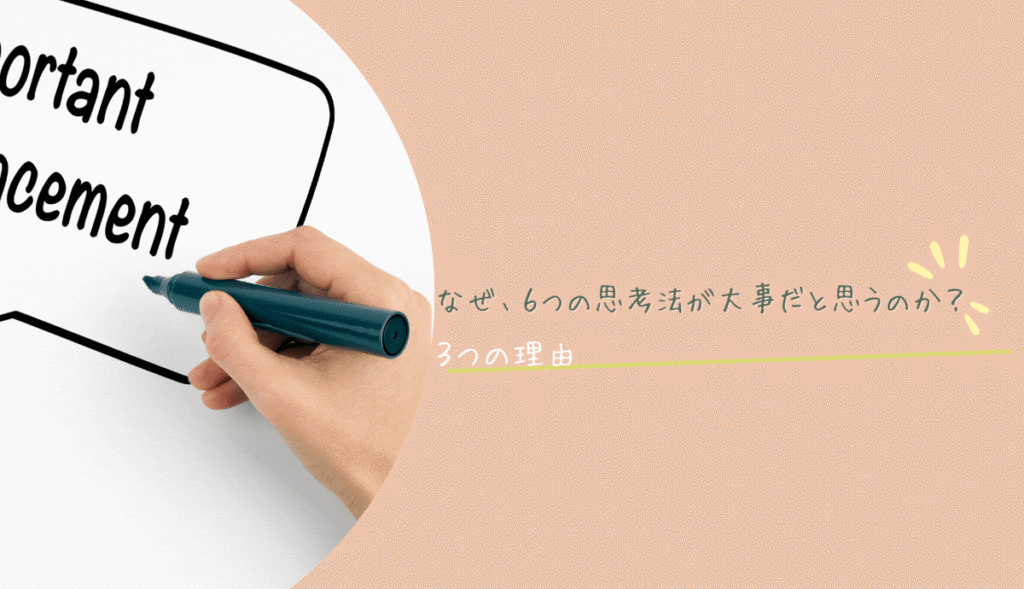
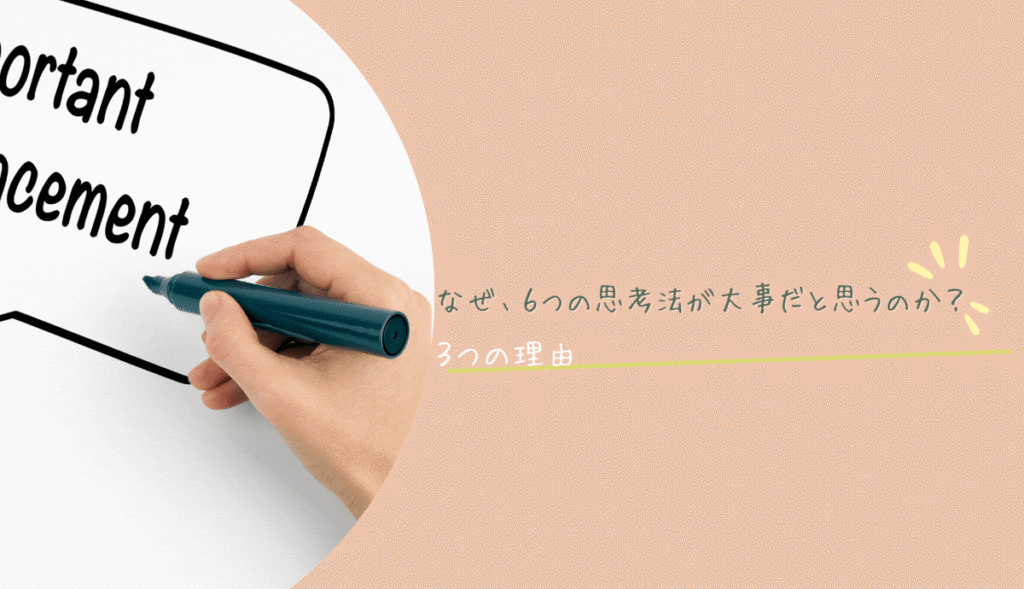
- 知識を覚えるだけでは社会で通用しない
- AI時代には『考える力』が差を生む
- 社会の問題は『単純な答えがない』
①知識を覚えるだけでは社会で通用しない
暗記した知識だけでは、変化の激しい社会で生き抜く力が身につかず、これからの時代に必要なのは、『知識をどう活用するか?』という思考力だと思うから。
学校で習ったことは、実は日常生活や未来の仕事にも役立つものであり、『勉強=使うための道具』と考える。
じゃあ、普段の勉強も 『使える形』にして考えることが大事!
例えば、算数の知識を使う!



ケーキを8人で分けるとき、どうやって切る?



8等分にする!



じゃあ、12人になったら?分数や割り算を使えば、みんなが平等に分けられるよ!



もし、すでに8等分されてるケーキなら、8等分された1切れをさらに3等分すると24等分になるから、2切れずつ配れば12人に均等に分けられるー。
②AI時代には『考える力』が差を生む
AIが知識を処理できる時代では、『単に知識を知っていること』よりも『どう考えるか?』が重要。
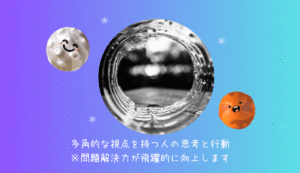
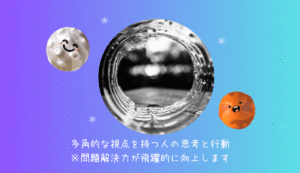
つまり、思考の質。
今はスマホで調べれば何でも分かる時代。
だったら何が大事かと考えたときに、自分で考えてどう使うか?というのが大事になってくる。知らないより、知ってる方がましだけど、使い方が分からないと使えないから。
③社会の問題は『単純な答えがない』
例えば、環境問題や政治の問題は『白黒はっきりしない』。数学みたいな『正しい答え』がない。
みんなの考え方や立場が違うから。人によって、何が大事かが違う。
多角的な視点を持ち、異なる立場を理解し、最適な解決策を考える力が必要だと思います。
戦争はなくすべき → みんなそう思うけど、なぜ戦争はなくならない?
地球温暖化を止めるべき → でも、工場を減らすと仕事がなくなる人もいる…。
動物を守るべき → でも、農作物を荒らす動物をどうする?
まとめ
素朴思考・天邪鬼思考・構造化思考・道具思考・批判的思考・哲学的思考を教育に入れ込むと面白いですよね。
これらを学ぶことで、『知識を覚える』だけでなく、『どう考えるか?』を学ぶ教育にシフトできるから。



AI時代・複雑な社会問題に対応できる力を育てるには、従来の暗記中心の教育ではなくて、思考力を重視する教育も大事かなと思ってます。
ただ、日本の教育は、明治時代に西洋の教育制度を導入して以来、『知識の習得』『論理的思考力』『問題解決能力』の育成を中心とする西洋的教育モデル(枝葉に注力した教育法)を採用してきてますよね。
知識の習得 → 科目ごとに分かれた体系的な学習(数学・科学・英語など)
思考力の強化 → 論理的思考や批判的思考(特に大学受験では重要視)
客観的評価 → テストや偏差値による学力評価
この西洋的な教育システムは、技術革新や科学的思考力の発展には非常に有効であり、日本が高度経済成長を遂げた一因でもある。
だけど、このモデルだけでは 『人間性』『道徳観』『精神的成長』など、教育のもう一つの重要な側面が軽視されがちになるという課題が残ります。



そこで、西洋的・東洋的に、『学ぶこと』がどのように理解されているのか、統合すること(ジンテーゼ)でどんな教育法になるのか、勝手にまとめてみました。
西洋的思考・東洋的思考を統合してジンテーゼとする
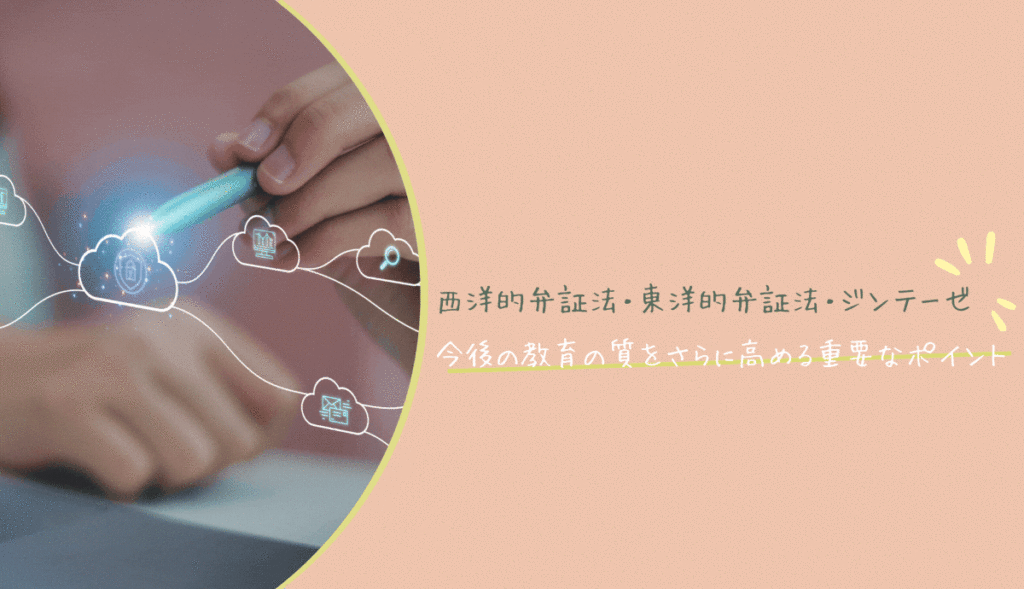
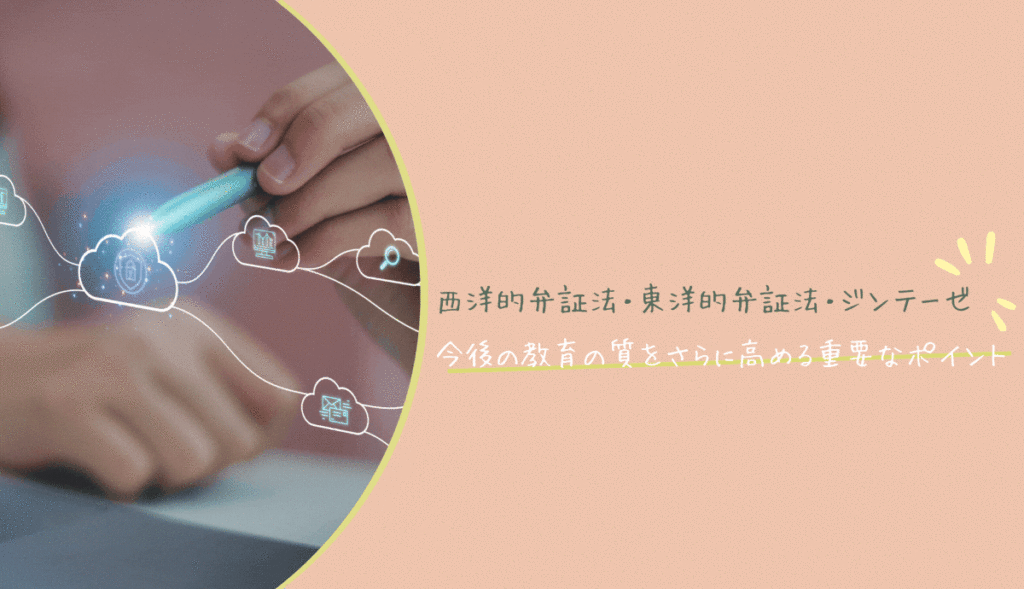
現在の日本の教育は、西洋的な教育システムを基盤としていて、『学力(知識や思考力)の向上』を重視する傾向 が強いですが、東洋的な人格形成の要素も適切に取り入れることが、今後の教育の質をさらに高める重要なポイントになってくると勝手に思っています。
ヘーゲルの弁証法についてはこちらの記事にまとめています↓
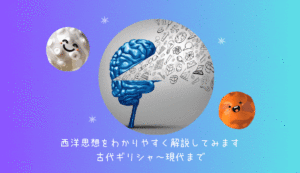
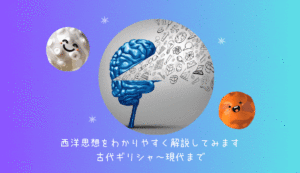
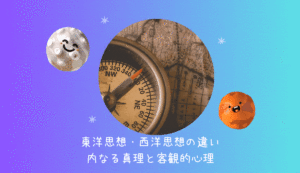
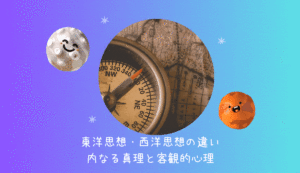
著書の7つの習慣で言うなら、パラダイムシフトで導き出された主体性に該当します。
| 西洋的思考 分析的・発展的アプローチ | 東洋的思考 調和的・包摂的アプローチ | |
|---|---|---|
| 学力と人間性の関係 | 分けて考える(学力の進化が中心) | 一体として考える(学力=人格の成長) |
| 学力の目的 | 知識・論理的思考の発展 | 知識の獲得を通じた人間的成長 |
| 教育の進化 | 学力の最適化(思考力・問題解決能力の強化) | 学力と人格のバランスを取る |
| 人格教育の扱い | 学力とは別の独立した課題として扱う | 学問を通じて人格も同時に育成する |
勝手に弁証法的プロセスを踏んでみる。
- 西洋的思考プロセス(テーゼ)
- 東洋的思考プロセス(アンチテーゼ)
- 西洋思想と東洋思想の統合(ジンテーゼ)
①西洋的思考プロセス
目的:世界を理解し、社会で生き抜く力を身につける
西洋的な弁証法(ヘーゲル的弁証法)では、対立する意見(対立しなくてもいい)を整理・分析し、より高度な理論へと発展させることを重視します。ここでは、西洋的6つの思考法を整理してみます。
- 素朴思考(経験的直感):学力が高いほど成功しやすい
- 天邪鬼思考(逆説的視点):学力だけでは社会で通用しないのでは?
- 批判的思考(多角的検証):そもそも『学力』の定義は正しいのか?
- 構造化思考(システム的視点):学力を体系的に身につけることが重要
- 道具思考(実践的視点):学力は手段であり、社会でどう活かせるかが鍵
- 哲学的思考(根源的問い):教育の目的は何か? 学力だけが最優先なのか?
知識を深め、世界を理解する(西洋的視点)。
学力を体系的に身につける(構造化思考)
→ バラバラの知識を整理し、統合的に活用できるようにする
学力をツールとして使う(道具思考)
→ 知識は『持っているだけ』ではなく、『使う』ことで価値を持つ
批判的思考を鍛え、論理的に考える(批判的思考)
→ 情報を鵜呑みにせず、多角的に分析する力をつける
- 社会で生き抜くための武器を手に入れる
- 問題を解決し、より良い未来を作るための力をつける
②東洋的思考プロセス
目的:学びを通じて、自分自身を成長させ、他者と調和する
東洋的な弁証法(陰陽思想・老荘思想的アプローチ)では、対立を統合するというよりも『対立する要素を共存させ、バランスを取る』ことを重視します。ここでは、東洋的6つの思考法を整理してみます。
- 素朴思考(経験的直感):学力は重要だから、最優先するのは当然
- 天邪鬼思考(逆説的視点):でも、学力だけでは人間としての成長が足りない
- 批判的思考(多角的検証):学力の測り方や教育システム自体に問題があるのでは?
- 構造化思考(システム的視点):学力と人格教育のバランスを考えるべき
- 道具思考(実践的視点):学力は手段であり、人生を豊かにする道具の一つ
- 哲学的思考(根源的問い):そもそも教育の目的とは何か? 幸せとは何か?
人間としての可能性を広げるため、他者と共存し、社会に貢献できる人間になる(東洋的視点)
学力と人格教育のバランスを考える(構造化思考)
→ 知識だけでなく、道徳・共感力・協調性も教育に組み込む
教育の本質を問い直し、幸福と結びつける(哲学的思考)
→ 『学び=成功』ではなく、『学び=人生を豊かにする行為』と再定義する
協調性・共感力・倫理観を重視する(道徳的教育)
→ 社会の中で他者と共に生きるための力を育む
- 自分の可能性を広げ、より良い人間になるため
- 他者と共存し、社会の一員として役割を果たすため
③西洋思想と東洋思想の統合(ジンテーゼ)
目的 :学びは、生きることそのもの
学力は『社会で生きるためのスキル』であり、『人生を豊かにするツール』
→ 知識は仕事や生活のための『道具』であり、『より良い人生を築く手段』
成功の定義は『お金や地位』だけでなく、『充実した人生』
→ 『学ぶこと=競争に勝つこと』ではなく、『人生を楽しむ力をつけること』
知識の詰め込みではなく、『学ぶ楽しさ』『探究心』を育てる教育へ
→ 学び続けること自体が、人生を豊かにする行為である
- 自分の人生を主体的に生きるため
- より良い人生を生きるため
- 学びそのものが、人生を楽しむ要素になるから
- 学力は手段であり、世界を理解し、自分を成長させるためのツール
- 学びとは、社会で生きるスキルを得るだけでなく、『人生をより豊かにする行為』
| 視点 | 目的 | なぜ学ぶのか? |
|---|---|---|
| 知識を深め、世界を理解する(西洋的視点) | 社会で生き抜く力をつける | 世界を理解し、問題を解決する、より良い社会を作るため |
| 自分を深め、人間として成長する(東洋的視点) | 自分を成長させ、他者と共存する | 人間としての可能性を広げるため、他者と共存し、社会に貢献できる人間になる |
| 人生の意味を探究し、豊かに生きる(ジンテーゼ) | 学びを人生と結びつける | 自分の可能性を広げ、人生を楽しむため |
『なぜ学ぶのか?』を問いながら学び、東洋的教育要素を取り入れていけるといいなと思っています。
子どもの主体性を育むために東洋的教育要素を取り入れたい!3つの理由
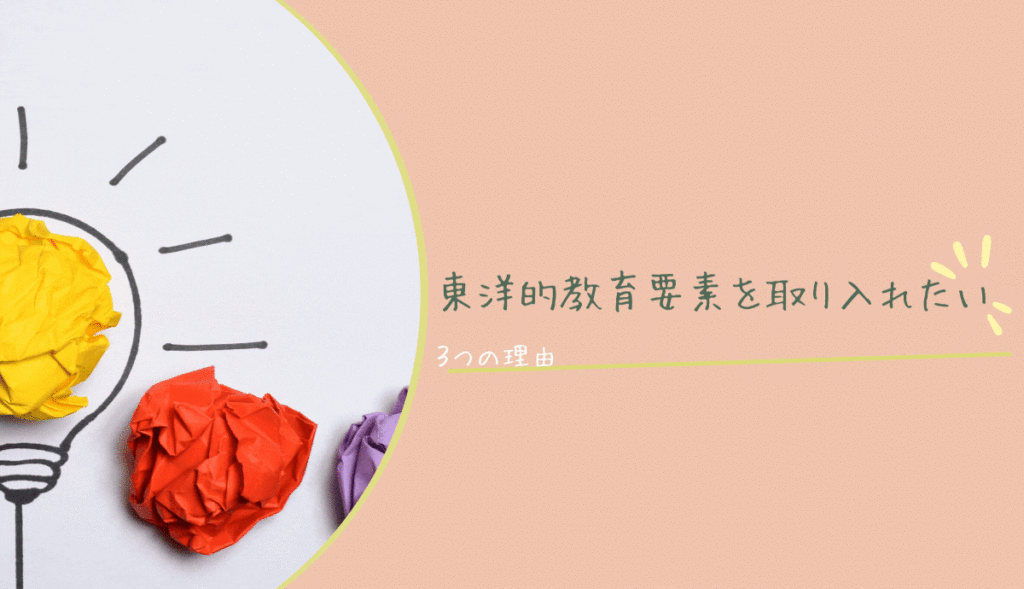
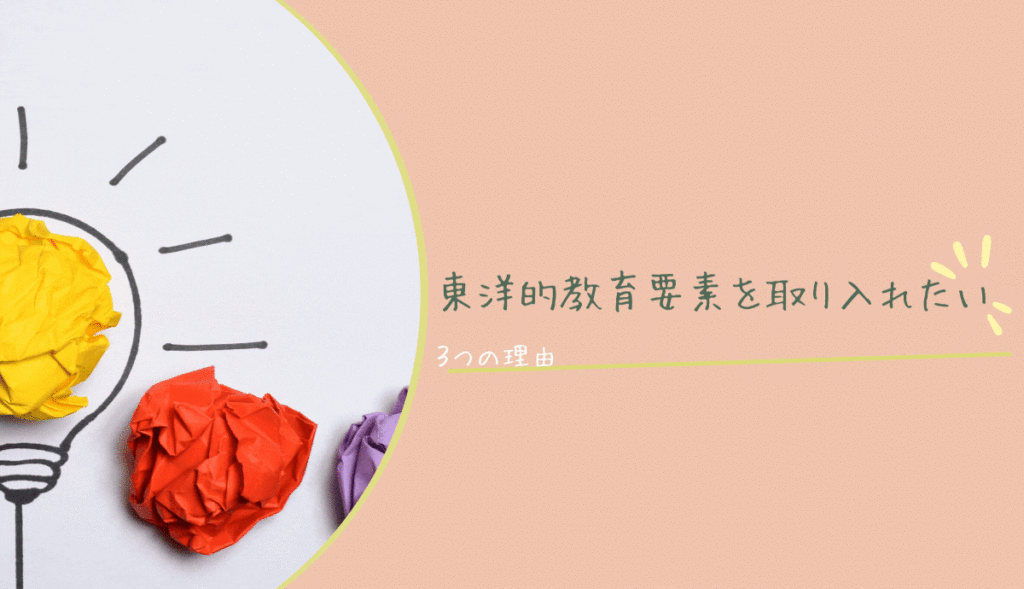
今の日本の教育において、西洋的な『学力重視』のシステムに、東洋的な『人格形成』の要素を加えることが必要だと考えています。
その理由は以下の3点です。
- 知識だけでは社会で活躍できない
- グローバル化における日本人の『自己表現力』の弱さ
- 精神的な豊かさが求められる時代
① 知識だけでは社会で活躍できない
知識や論理的思考があっても、それを『どのように使うか』『どう人と関わるか』といった人格的な要素が不足していると、社会での適応力が低くなります。
→ 学力だけでなく、人間性・協調性・道徳観も教育の中で育む必要がある。
② グローバル化における日本人の『自己表現力』の弱さ
自分の意見を明確に述べたり、多様な価値観を受け入れる力が不足しがちに思える。
→ 東洋的な『調和』や『多様性の尊重』の考え方を活かし、柔軟な思考や自己表現の力を伸ばしたい。
③ 精神的な豊かさが求められる時代
現代は、『どのような価値観を持ち、どう社会と関わるか』が重要視される時代だと思う。
→ 東洋的な『精神の成長』や『道徳的な知恵』を重視することで、心の豊かさを育む教育が必要だと思う。
具体的にどのように東洋的要素を加えられるか?
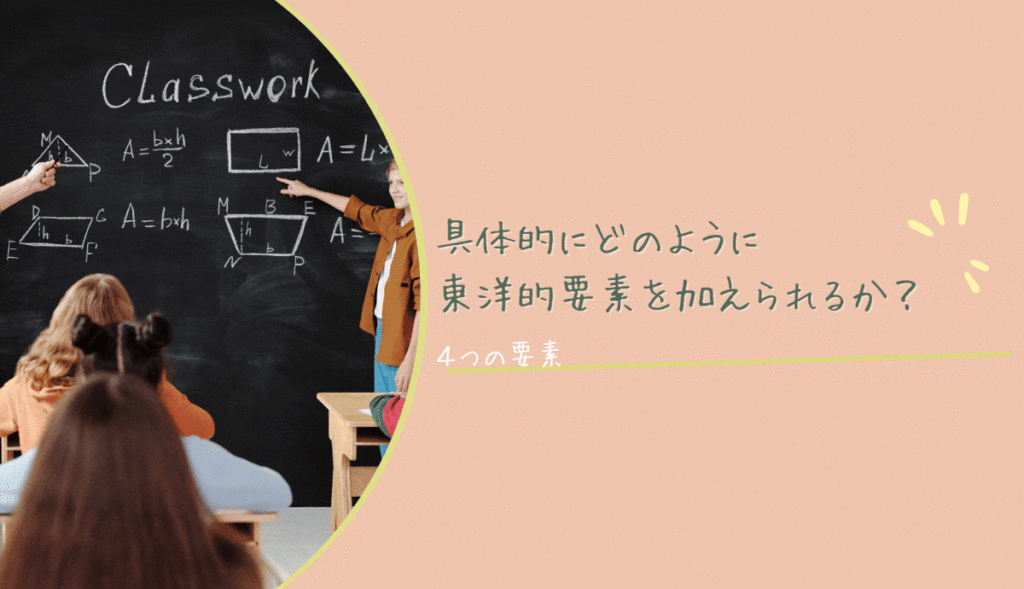
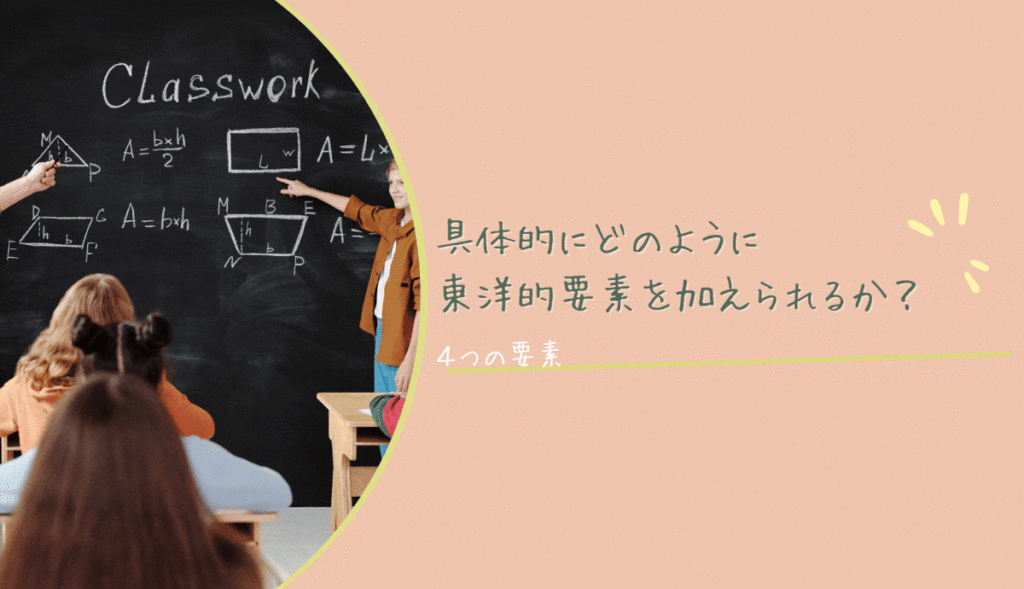
① 道徳・哲学・倫理の授業を強化
- 『考えさせる道徳教育』を導入し、『良い・悪い』の正解を教えるのではなく、自分の価値観を深める授業を増やす。
- 西洋哲学だけでなく、東洋哲学(孔子・老子・仏教思想など)も取り入れ、『知識と人格の両方を磨く学び』を実践。
② 『知識のための知識』ではなく『生きた知識』を学ぶ
- 学力を社会の中でどのように使うかを考えさせる教育。
- 例えば、歴史の授業では単なる暗記ではなく、『歴史から学べる人生の知恵』を考える授業にする。
③ 師弟関係や『学びの姿勢』を重視
- 『先生=知識を教える人』ではなく、『先生=人間性の成長を導く人』という意識を両者とも強化。
- 日本の伝統的な『礼儀』『尊敬の文化』を適度に復活させ、学びの姿勢を重視する教育を行う。
④ 共同体の中での成長を重視
- 個人の能力だけでなく、『集団の中でどう貢献できるか?』を考える機会を増やす。
- 例えば、学校の授業に『地域活動』や『ボランティア体験』を組み込み、社会との関わりを学ばせる機会を設けてみる。
まとめ
日本の教育は西洋的な知識重視の教育を取り入れて発展してきましたが、今後は東洋的な人格形成の要素を取り入れることで、よりバランスの取れた教育へと進化することができるんじゃないかと思っています。
知識を教えるだけでなく、『学びを通じて人間としてどう成長するか』を重視。『学力の向上』と『人間性の成長』を両立する教育システムを構築。『知識をどう活かすか?』という東洋的な視点を取り入れ、実社会と結びついた学びが大切かと思います。
つまり、日本の教育には『西洋的な学力重視のシステム』を維持しつつ、『東洋的な人格形成の要素』を適切に組み込むことが必要だということです。
『主体的に学ぶ』『主体的に行動する』と言っても、正しい思考法がなければ、ただの『受け身の行動』になってしまう。
主体性を持つには、『考える力(思考法)』が土台になっていないと、本質的な主体性にはならない。
素朴思考・天邪鬼思考・構造化思考・道具思考・批判的思考・哲学的思考を身につけることで、はじめて『本物の主体性』が育つ。
つまり、『主体的に取り組む』と言っても、正しい思考法がなければ、その主体性は間違った方向に行く可能性が高い。だからこそ、主体性を本物にするために、思考法を鍛えることが最も重要だと言えます。
西洋的教育法が推奨されている現在では、なかなか『思考法』までは届かないから。
これ、今は(知識を)取りに行かないと、教えてもらえないことだから。



このブログに訪れて、知識を得ることができたあなたは、それを1人でもいいので、誰かに伝えてみてください。その小さな行動がいずれ、大きな力になるから。

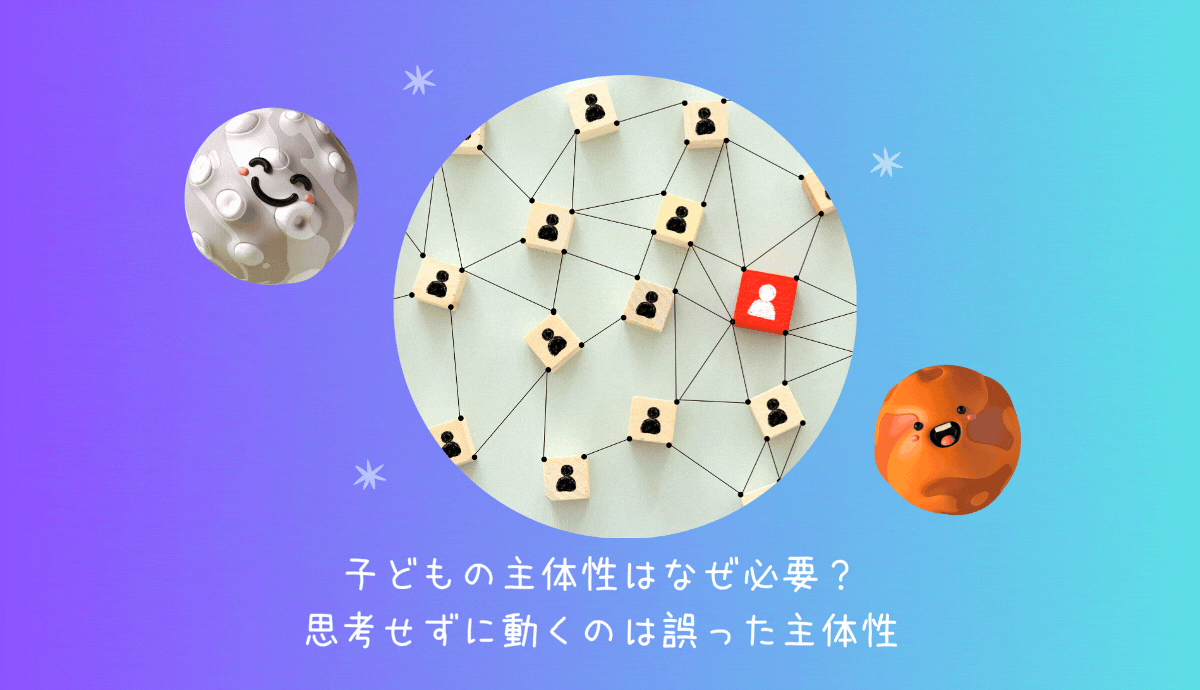

コメント